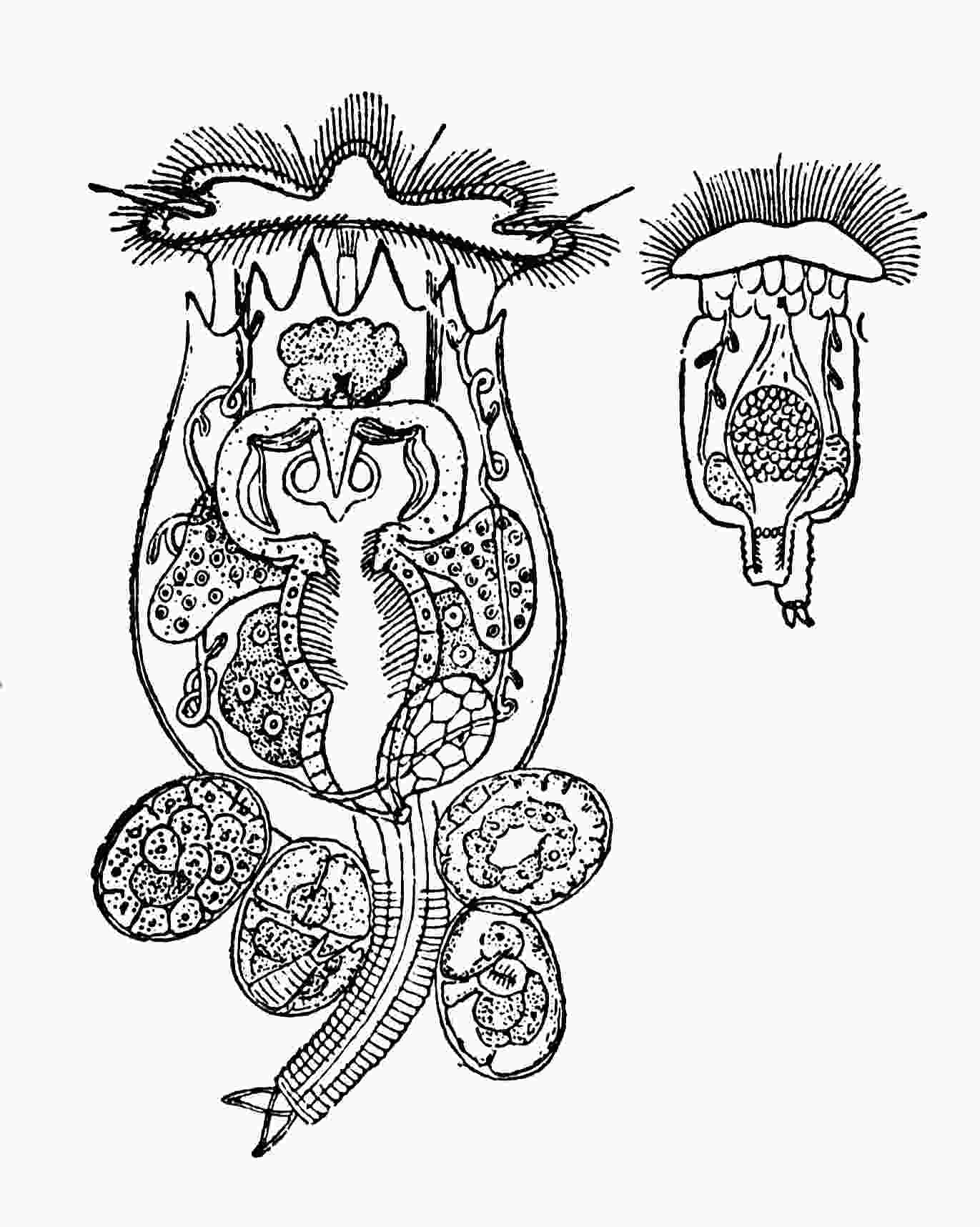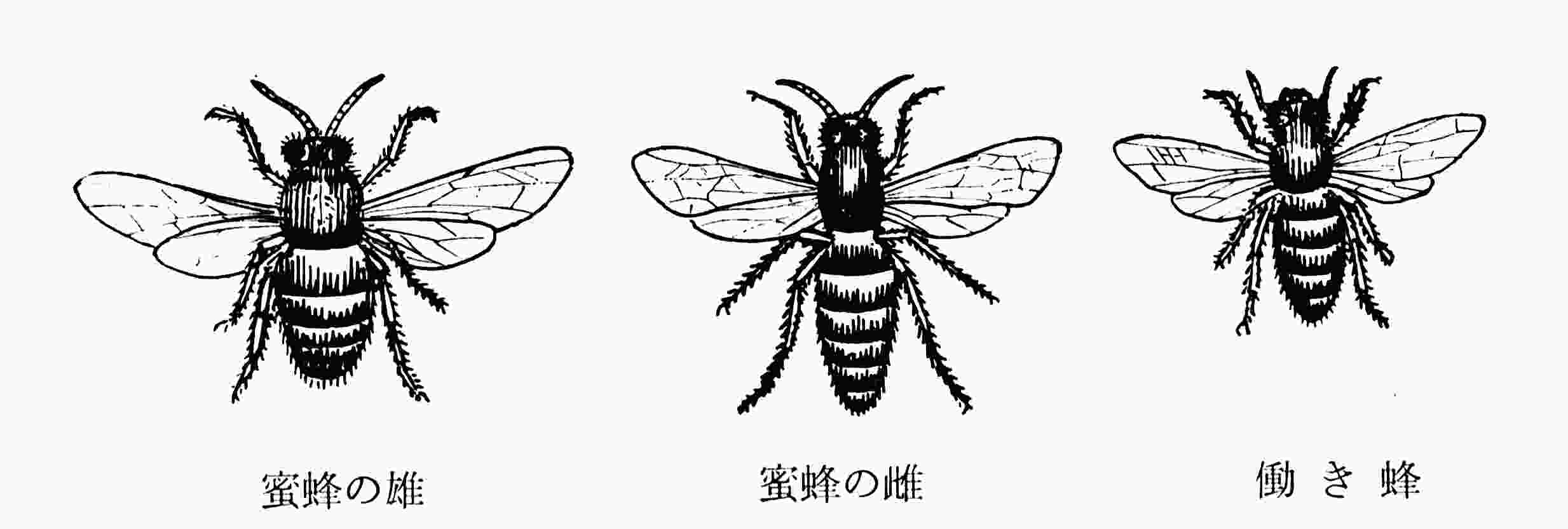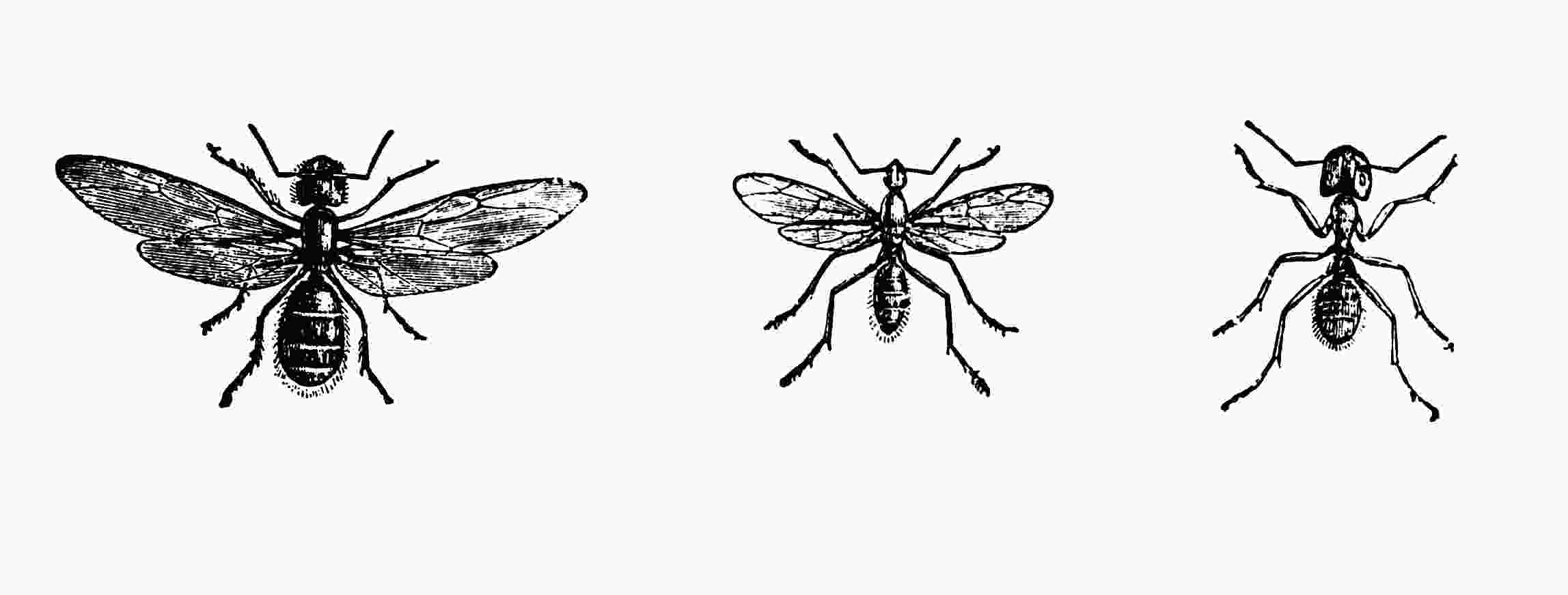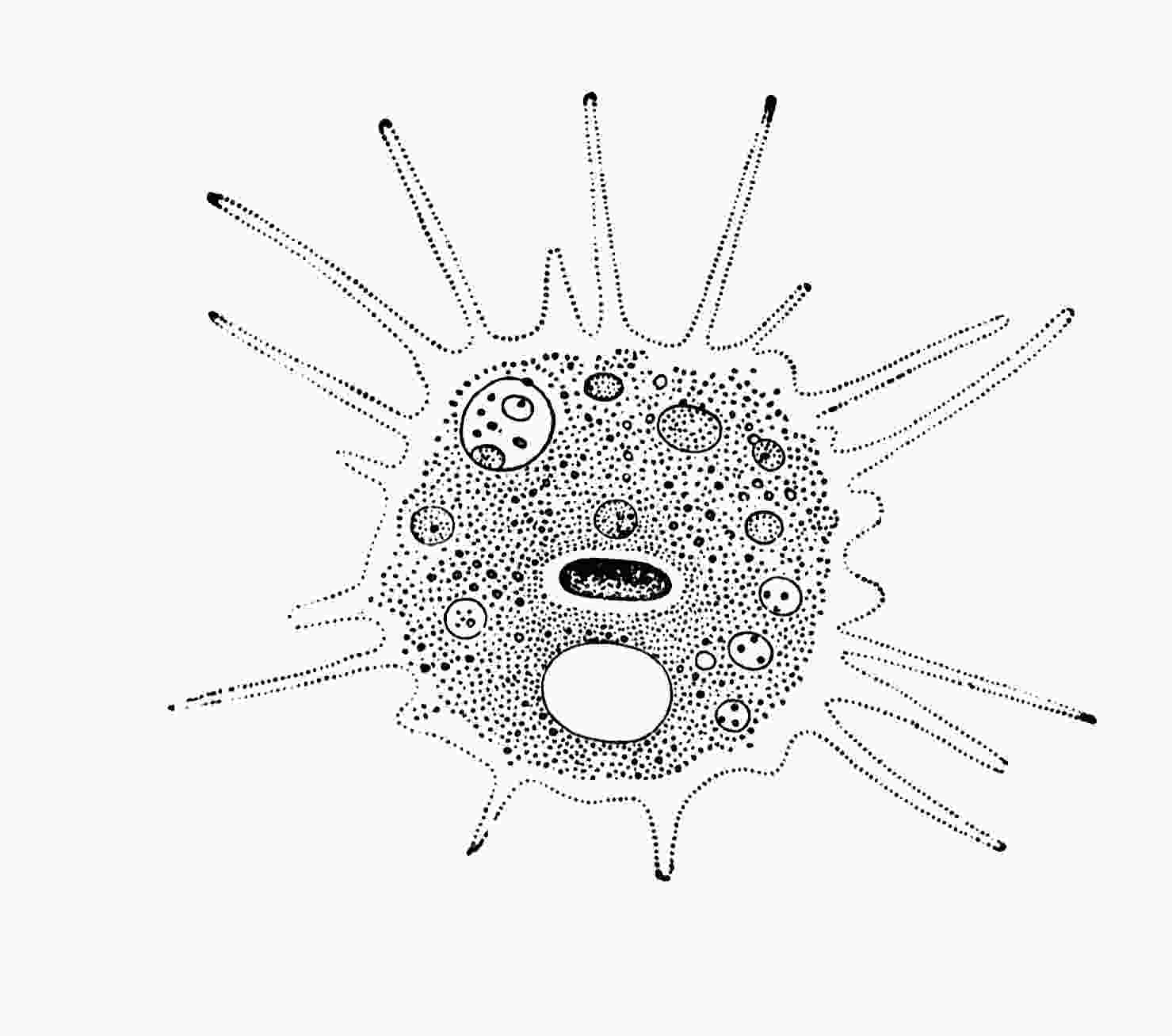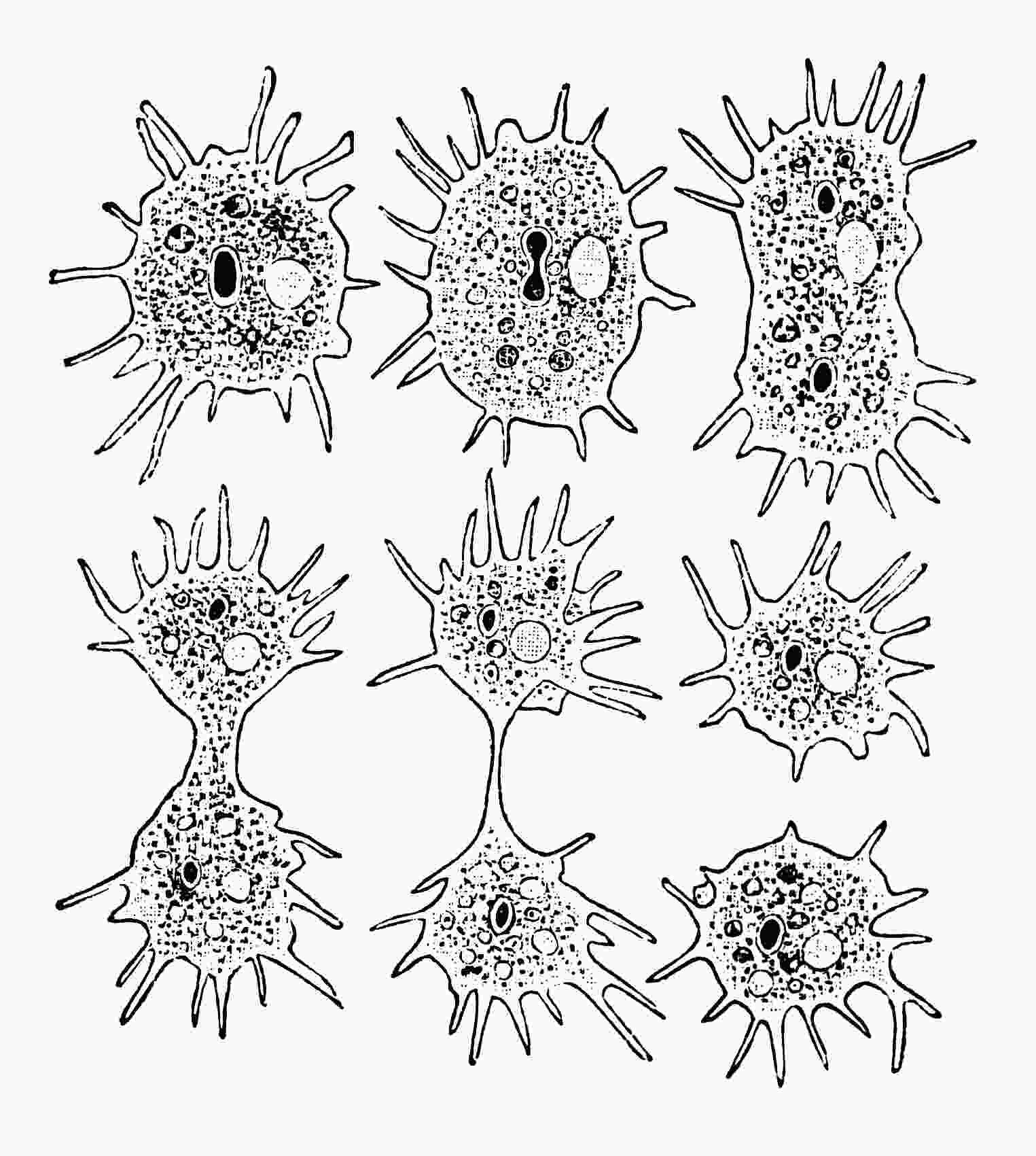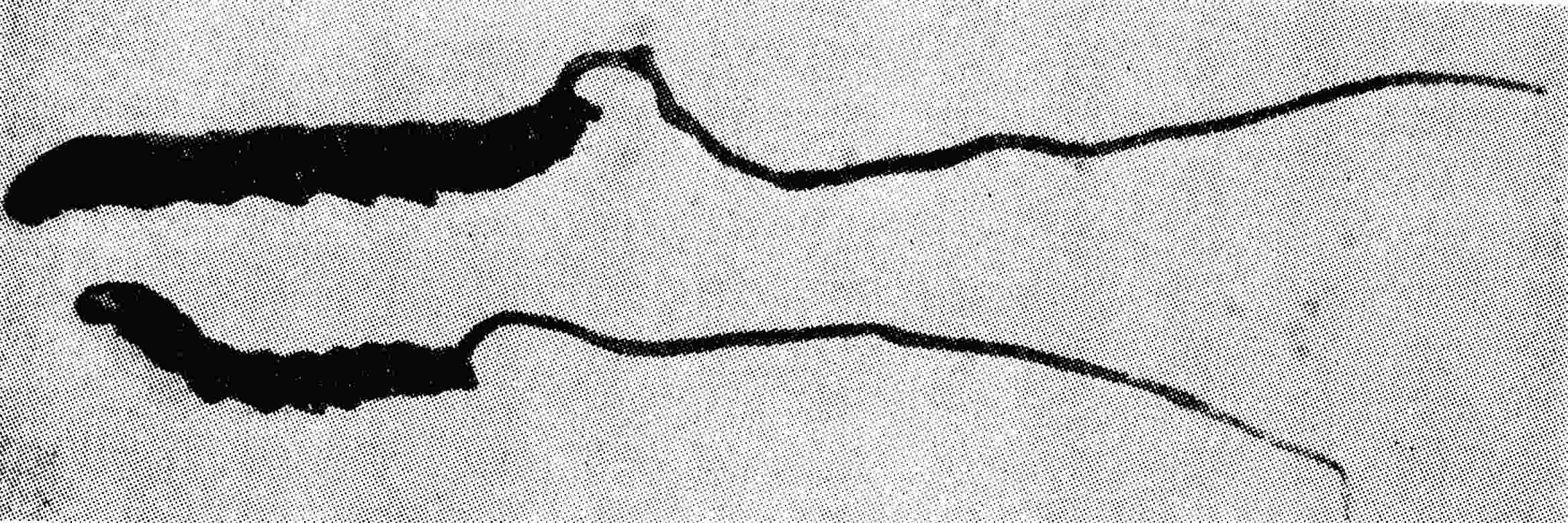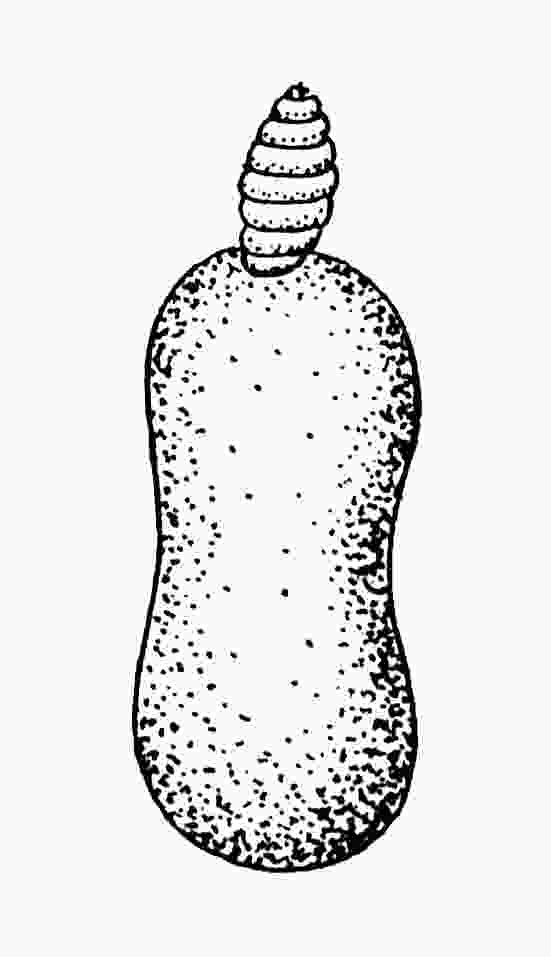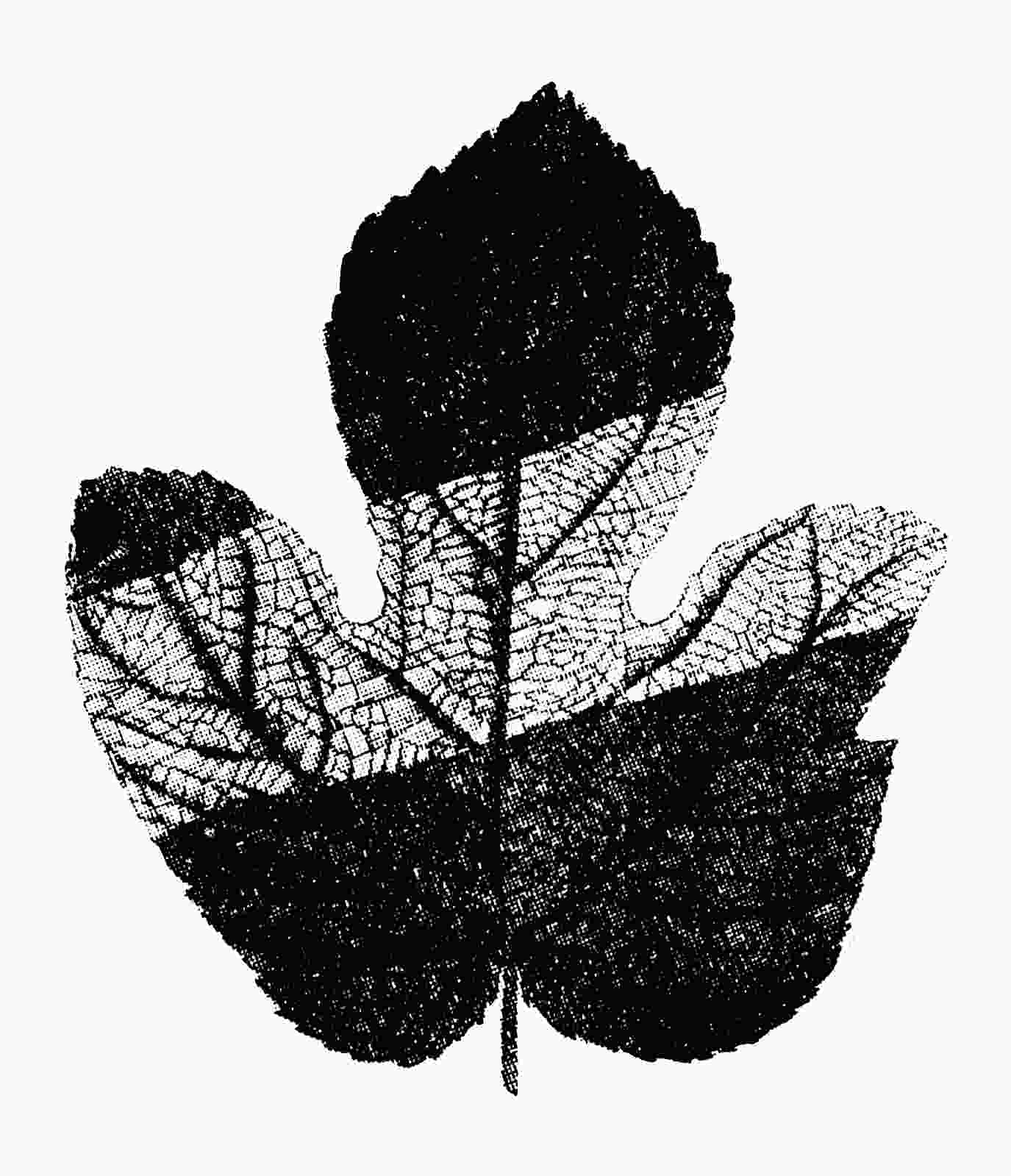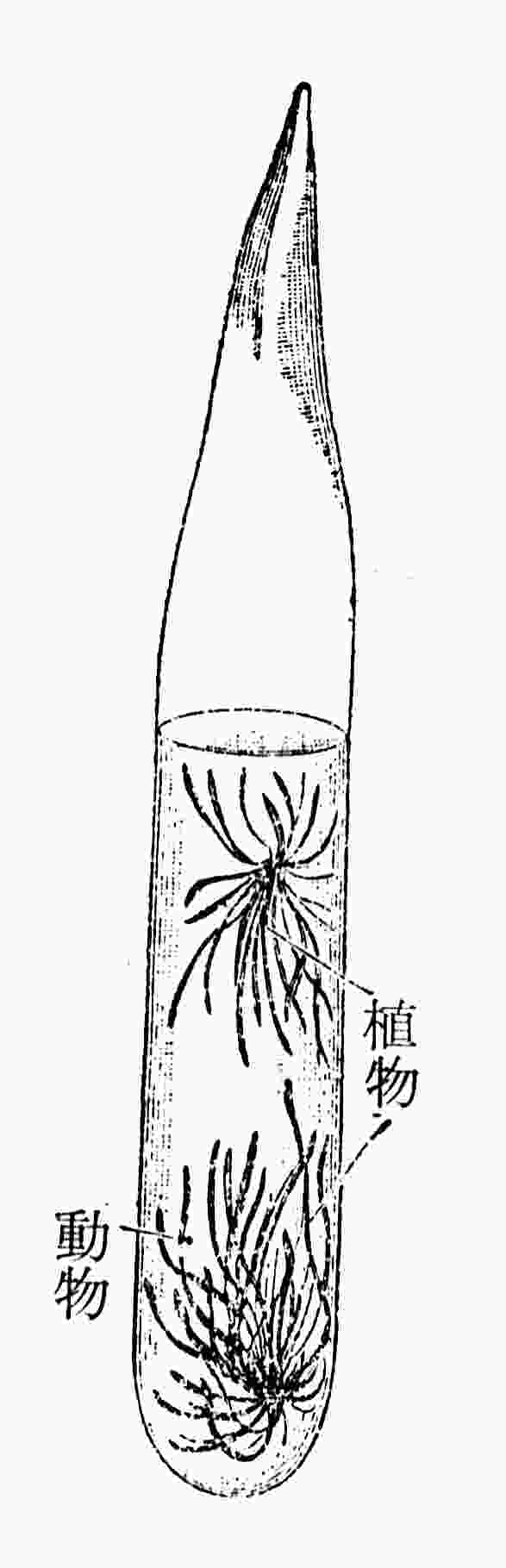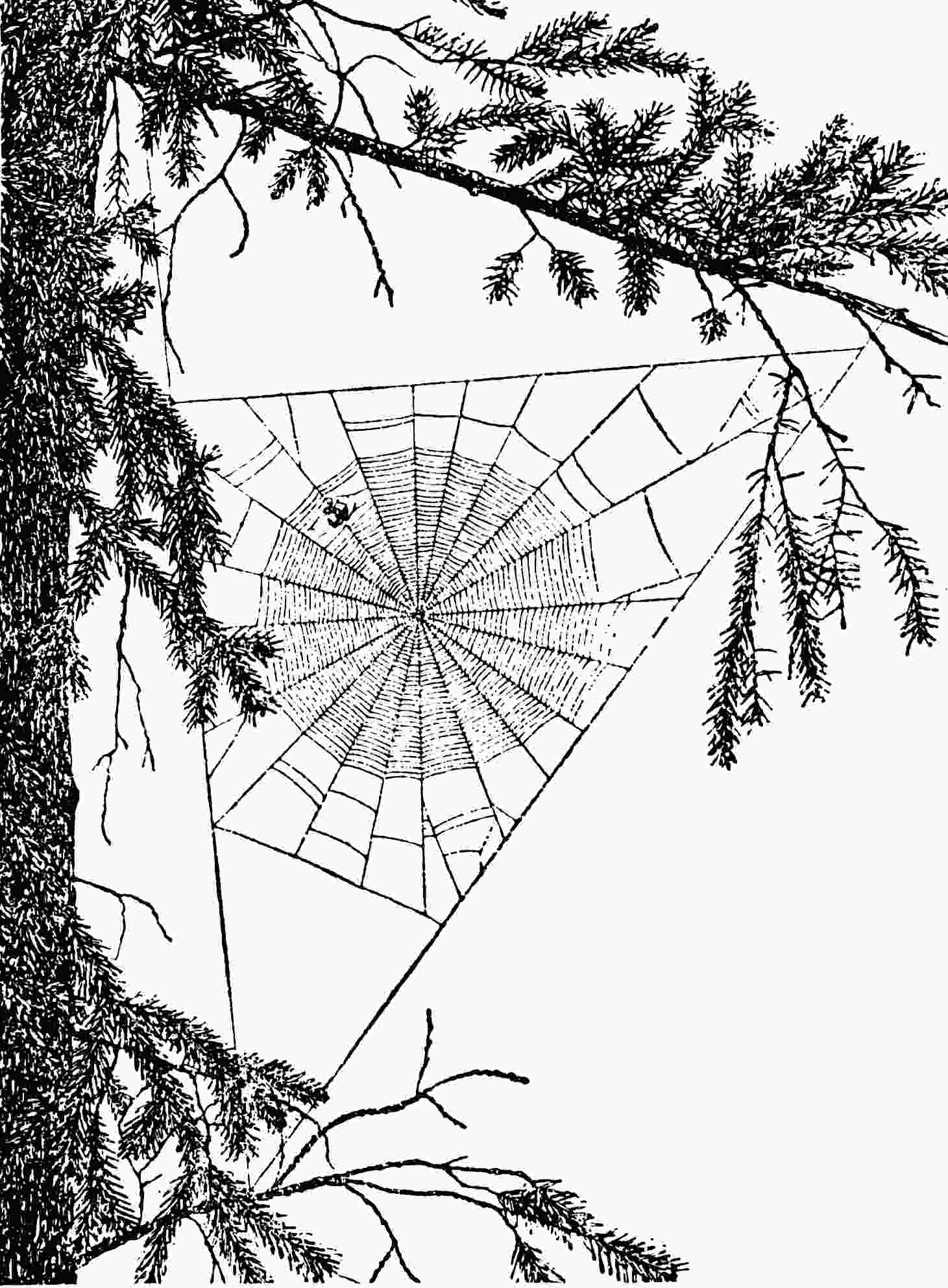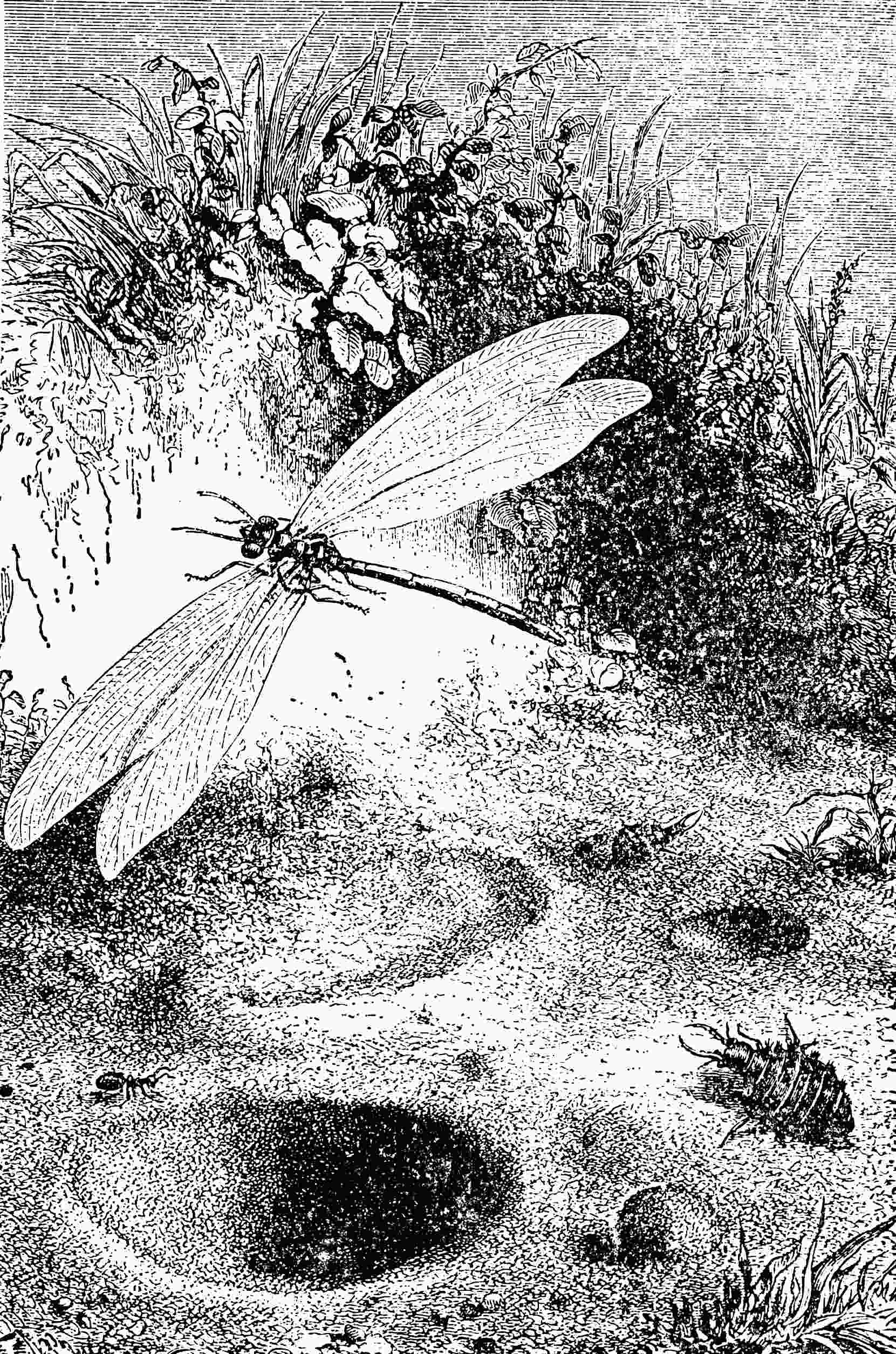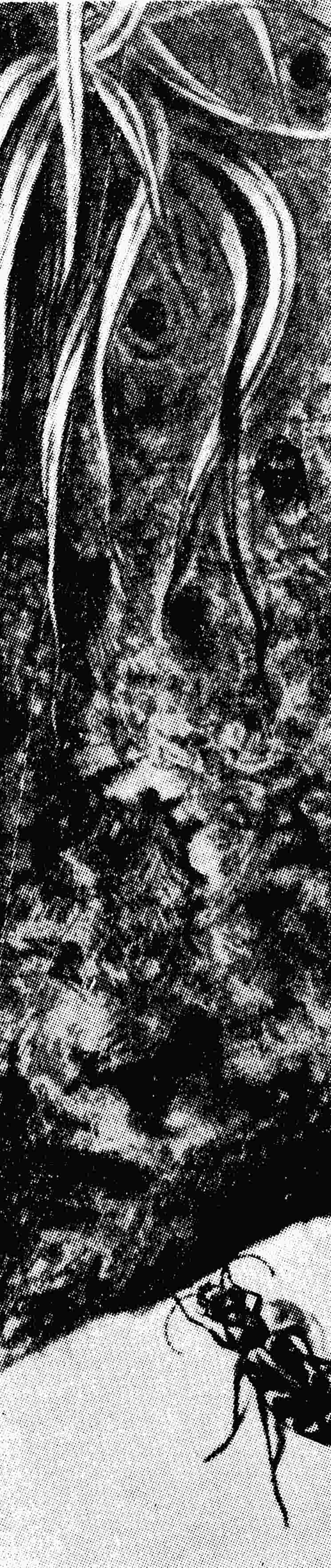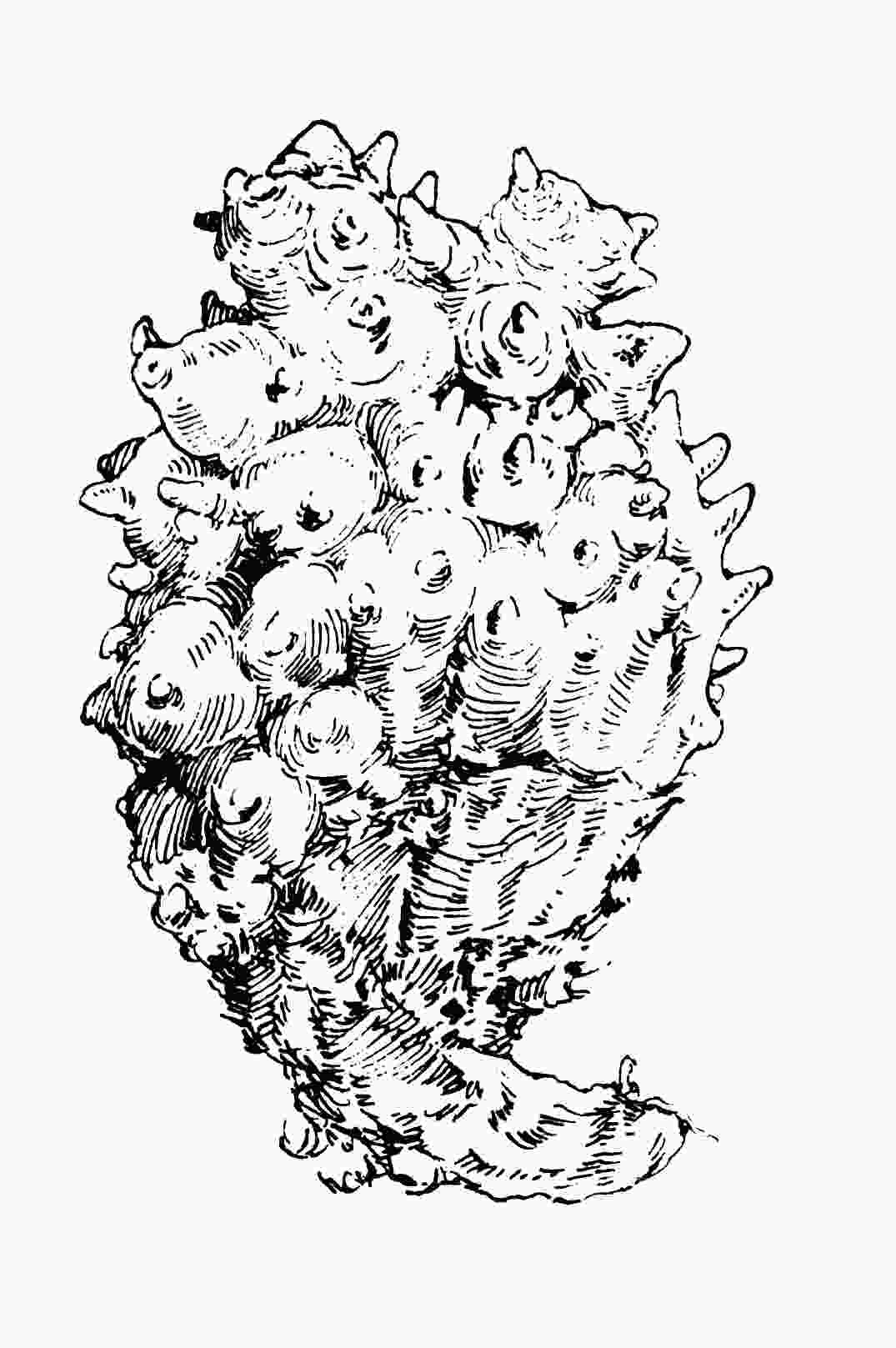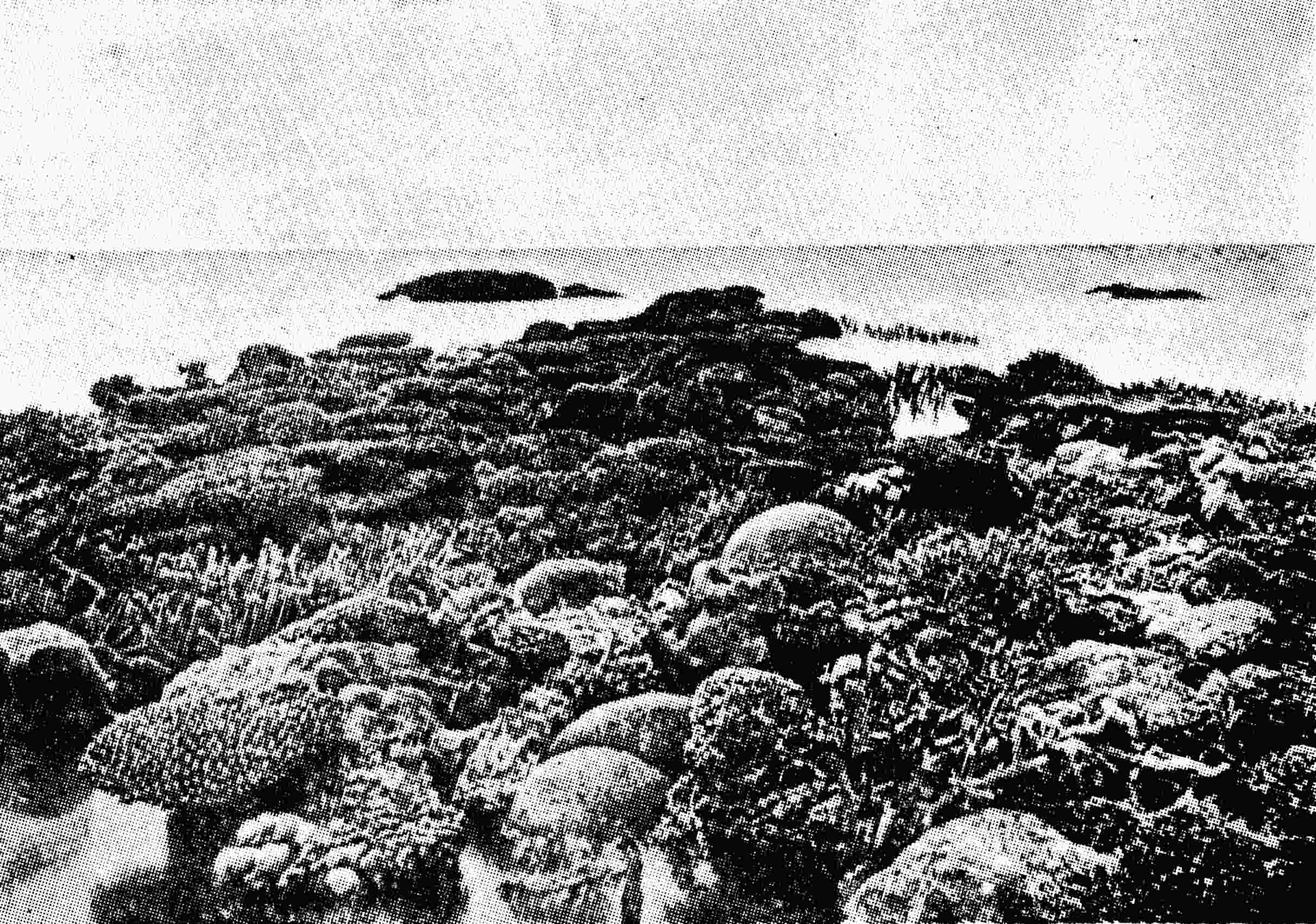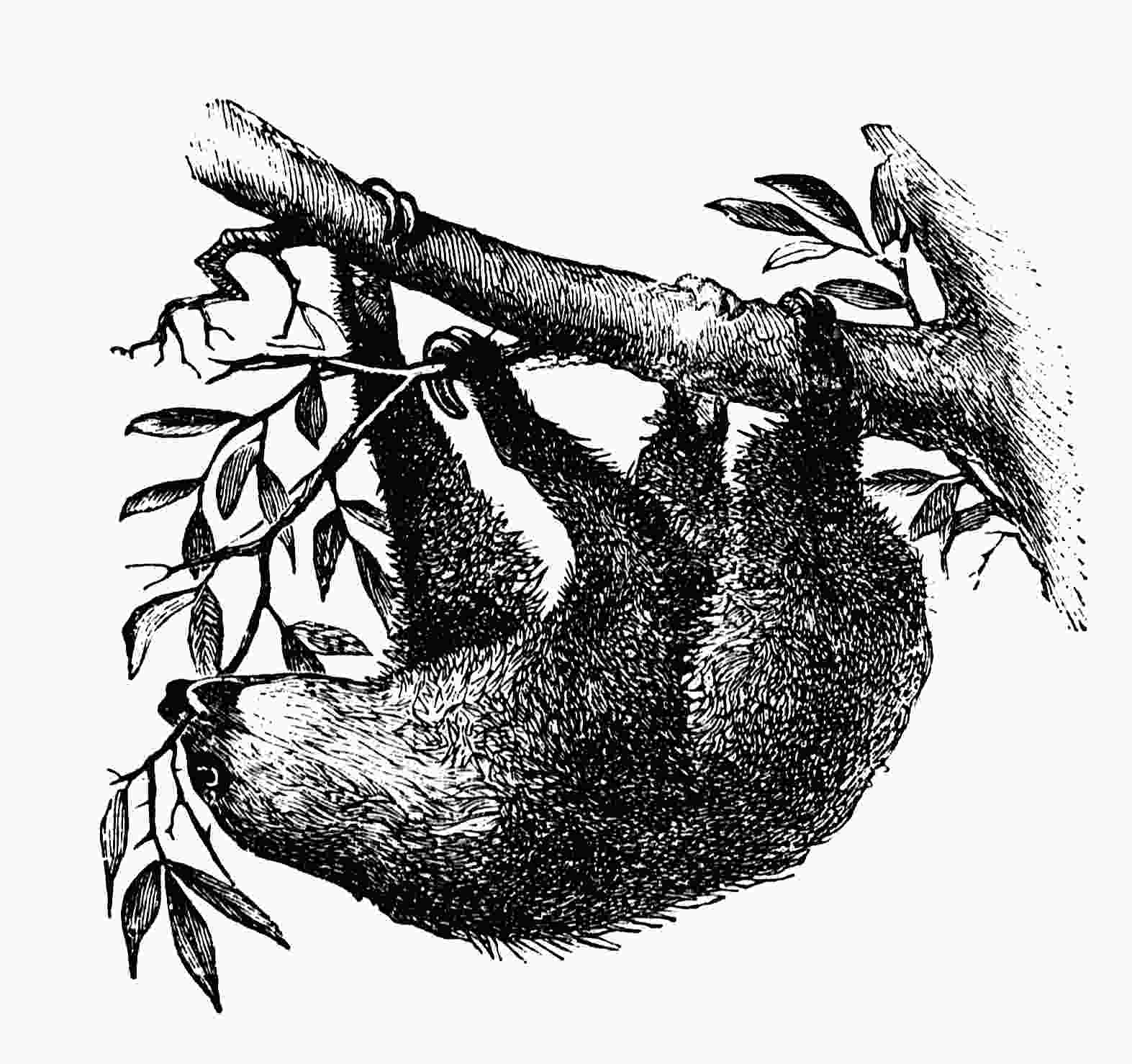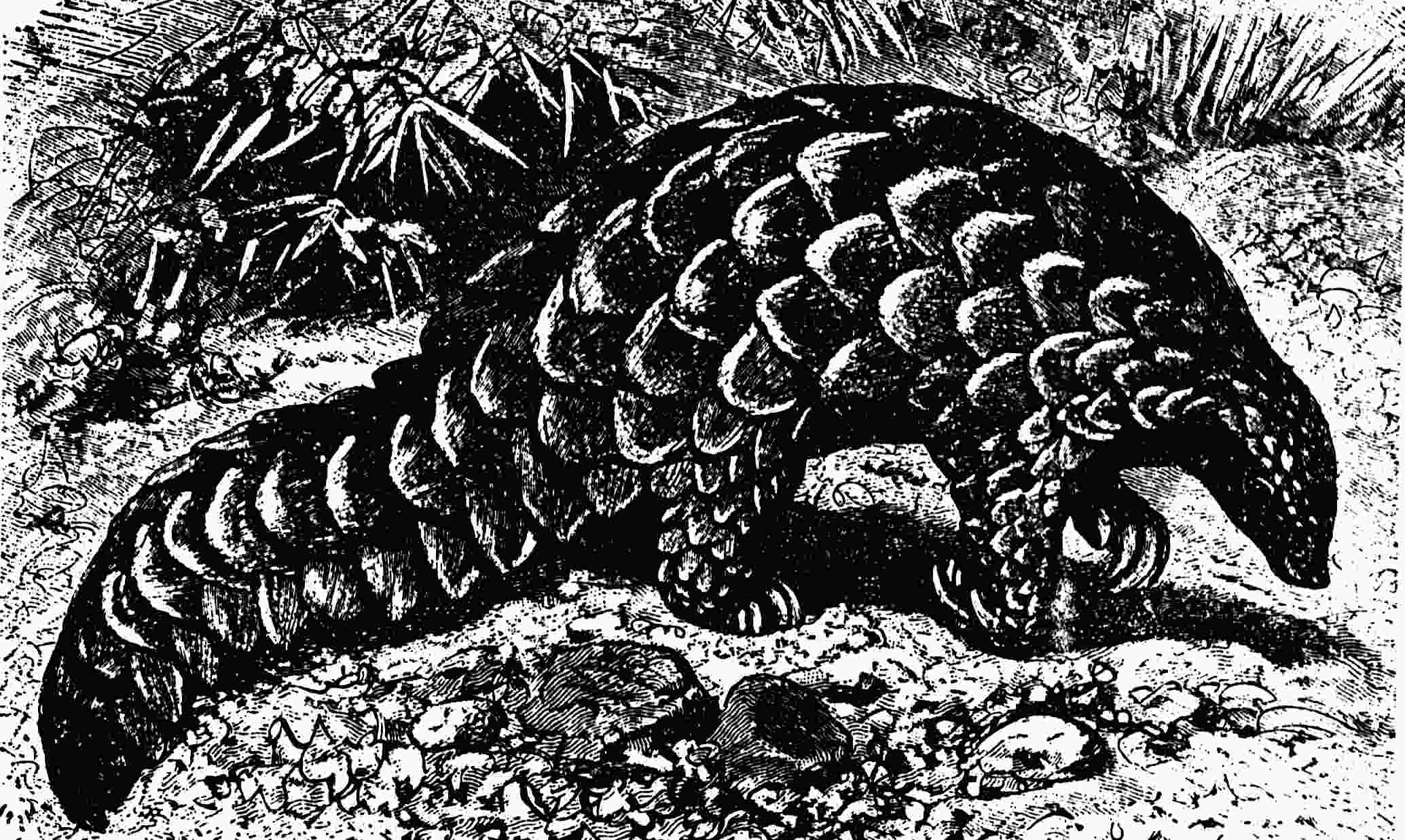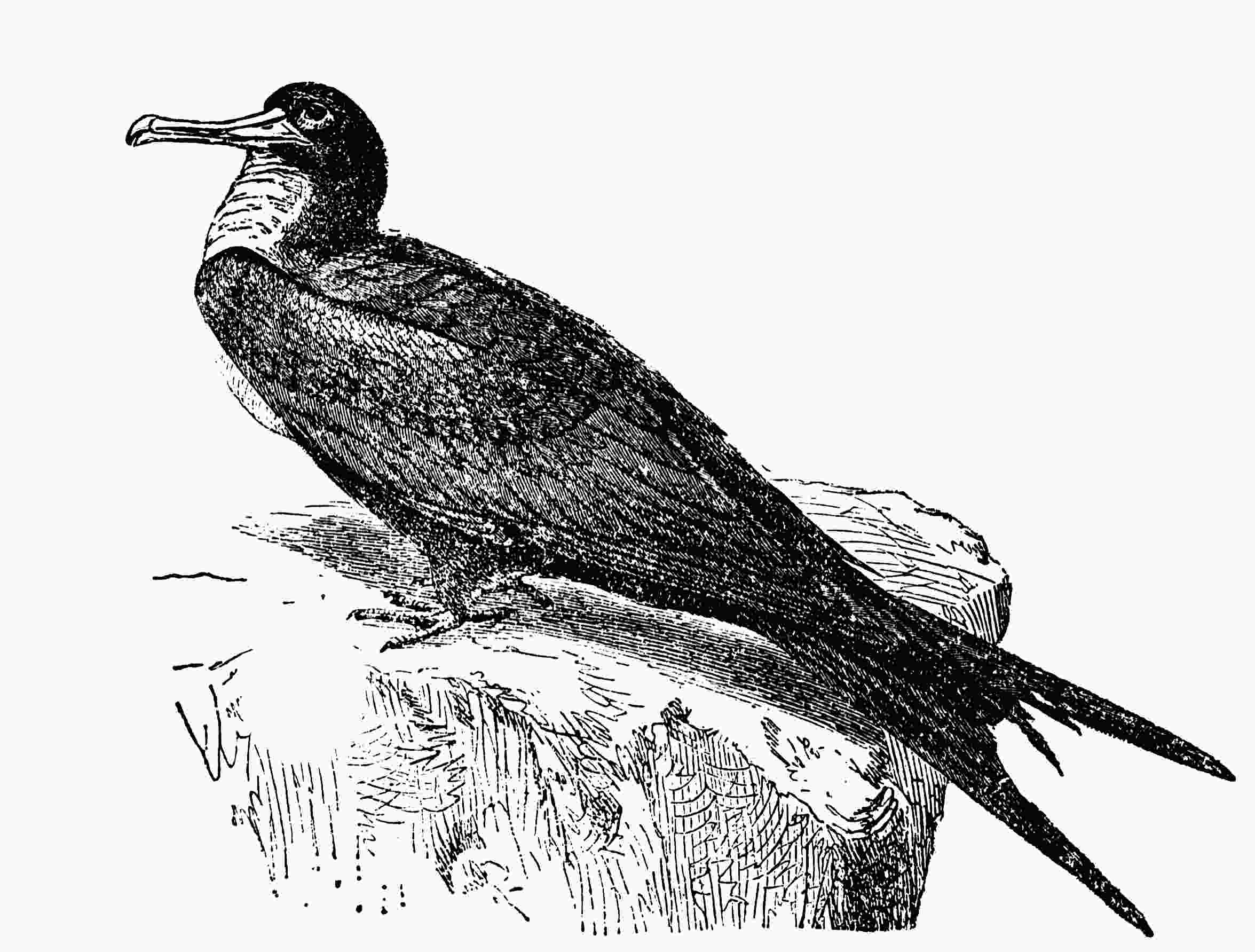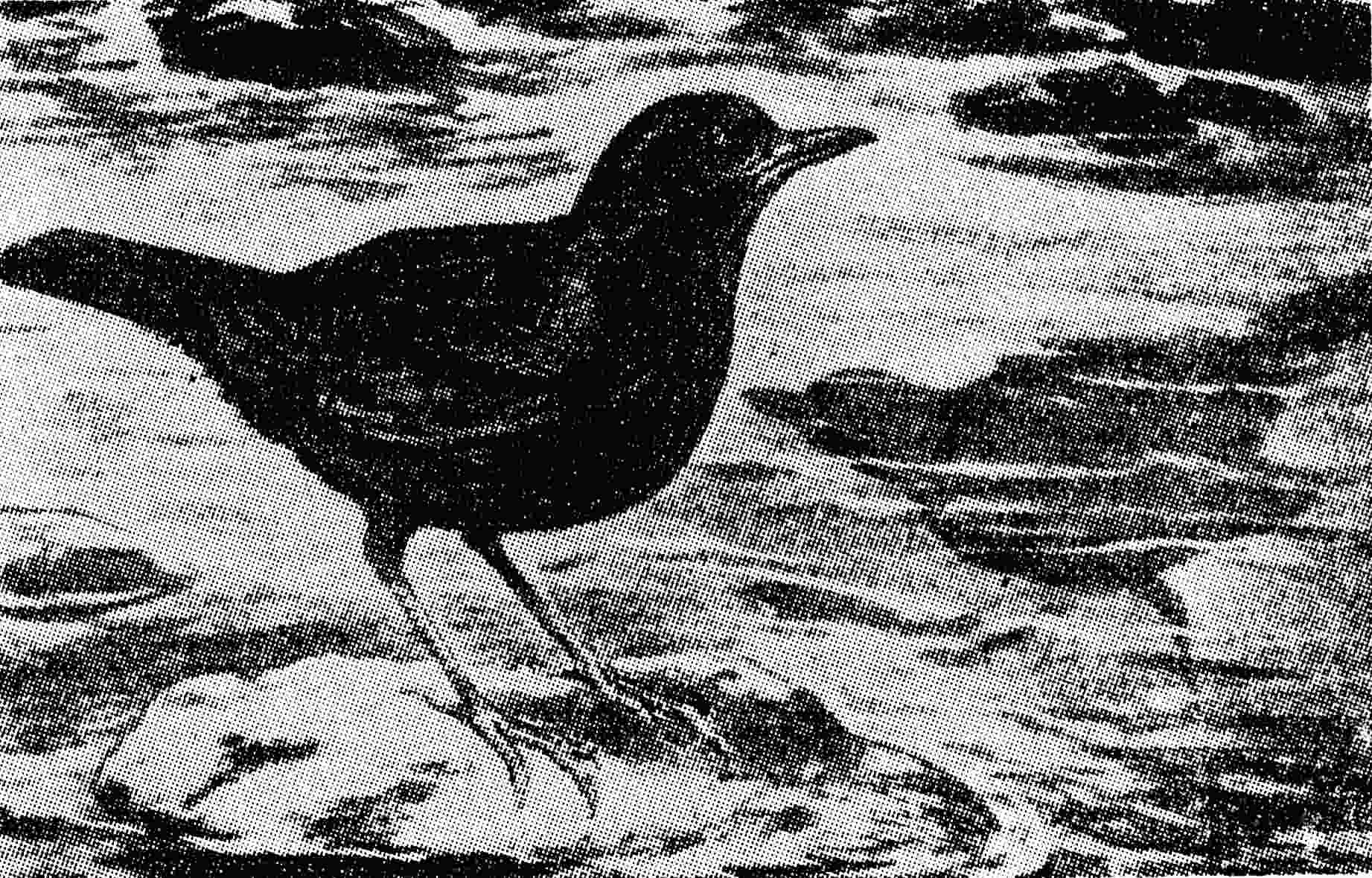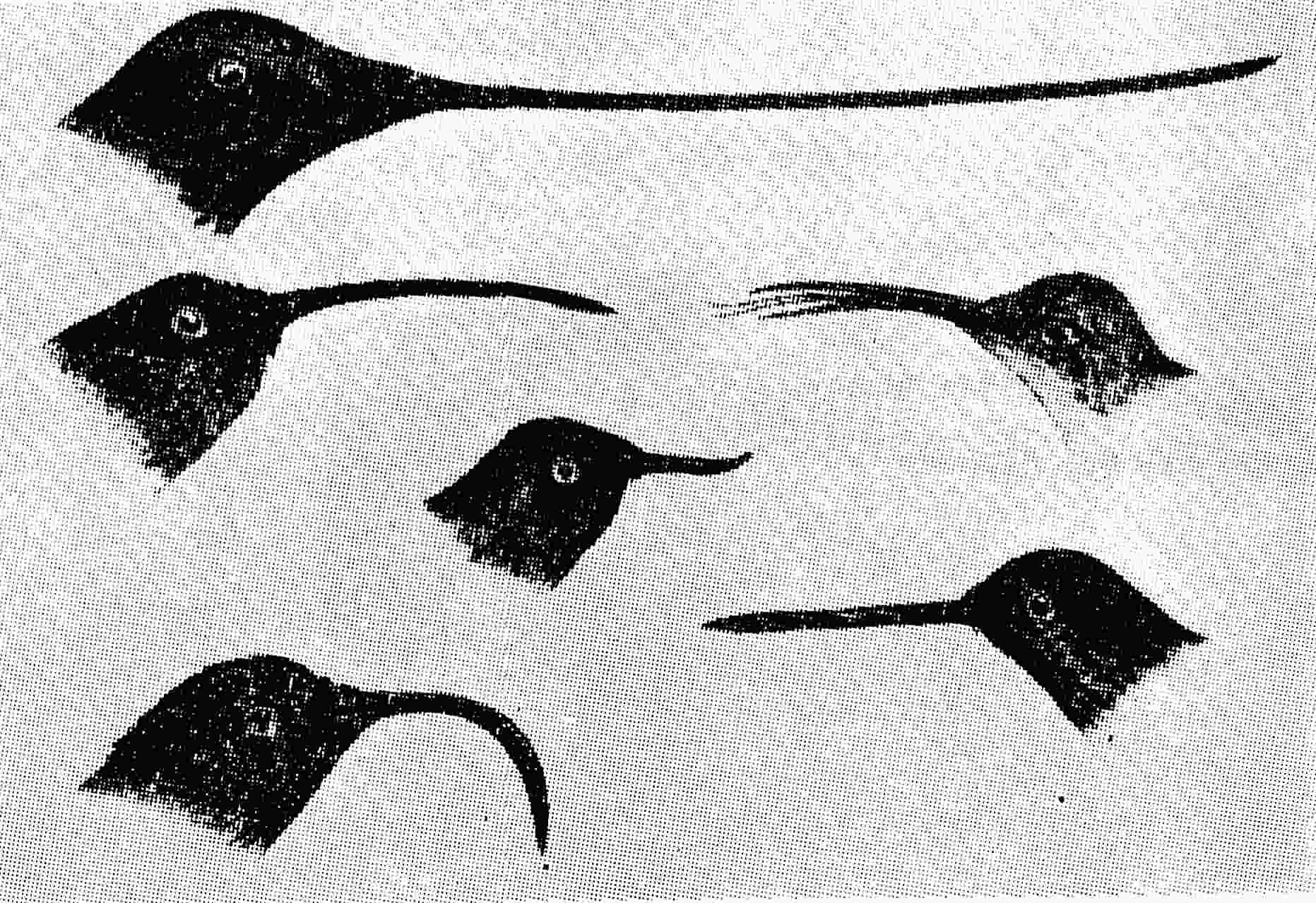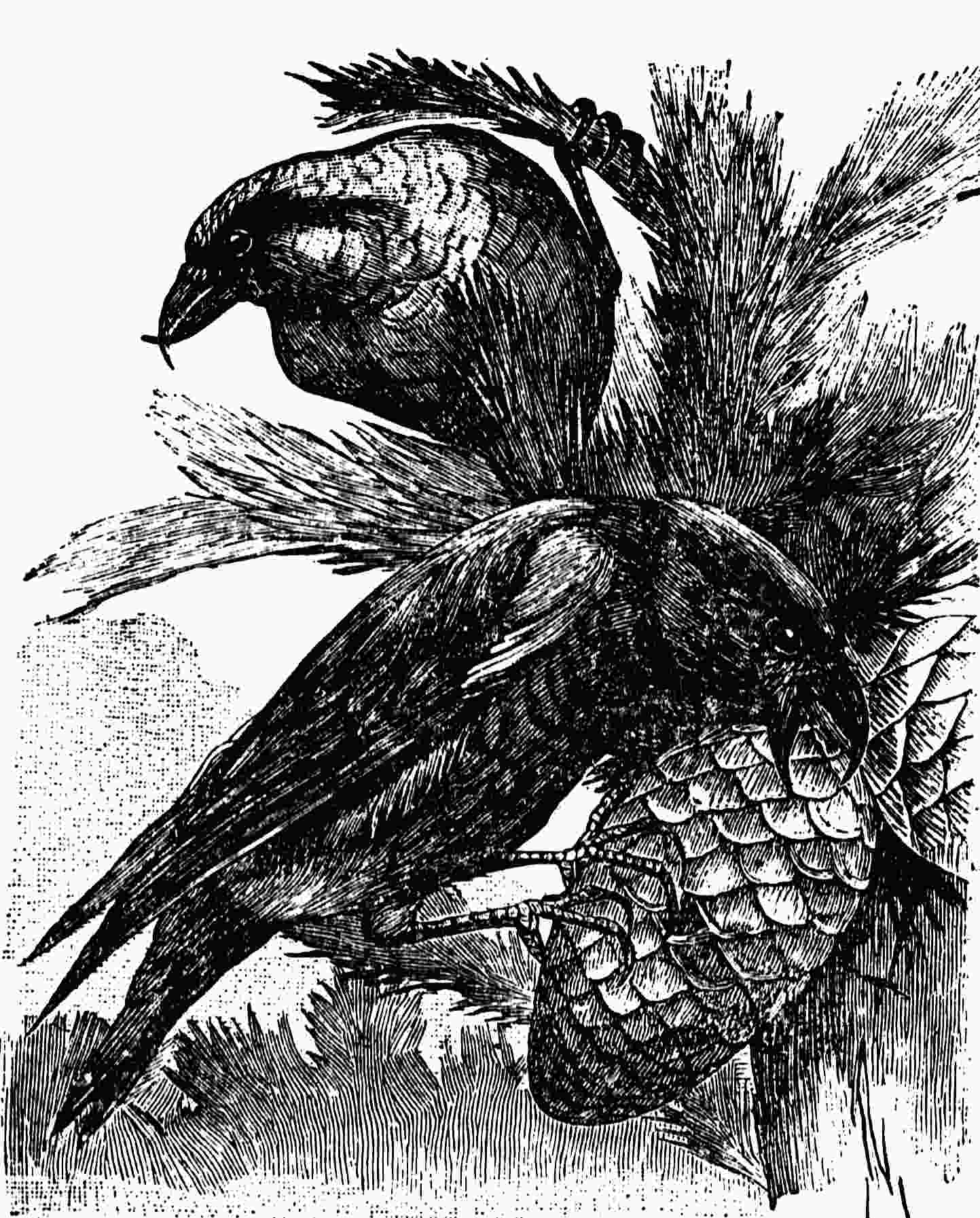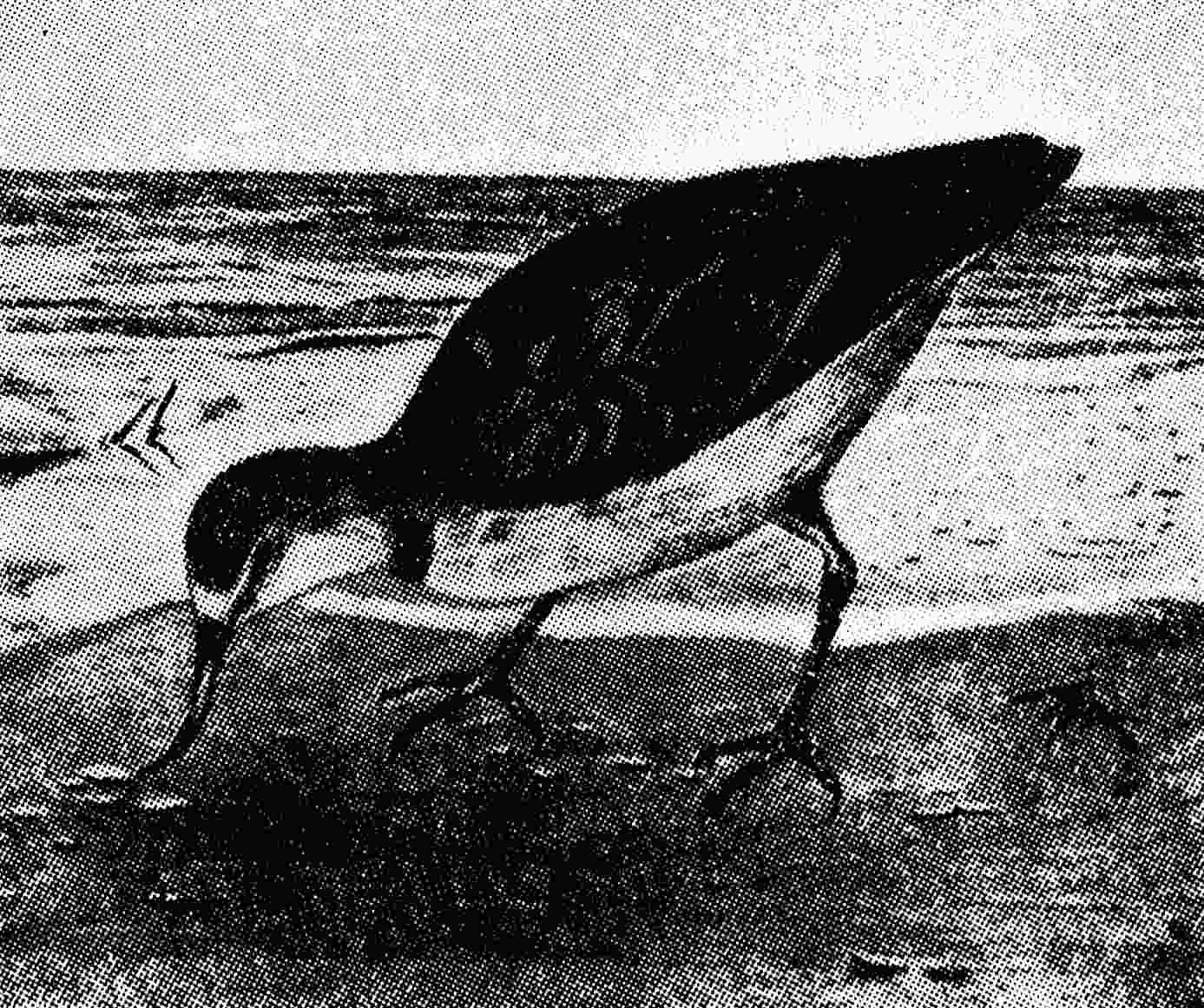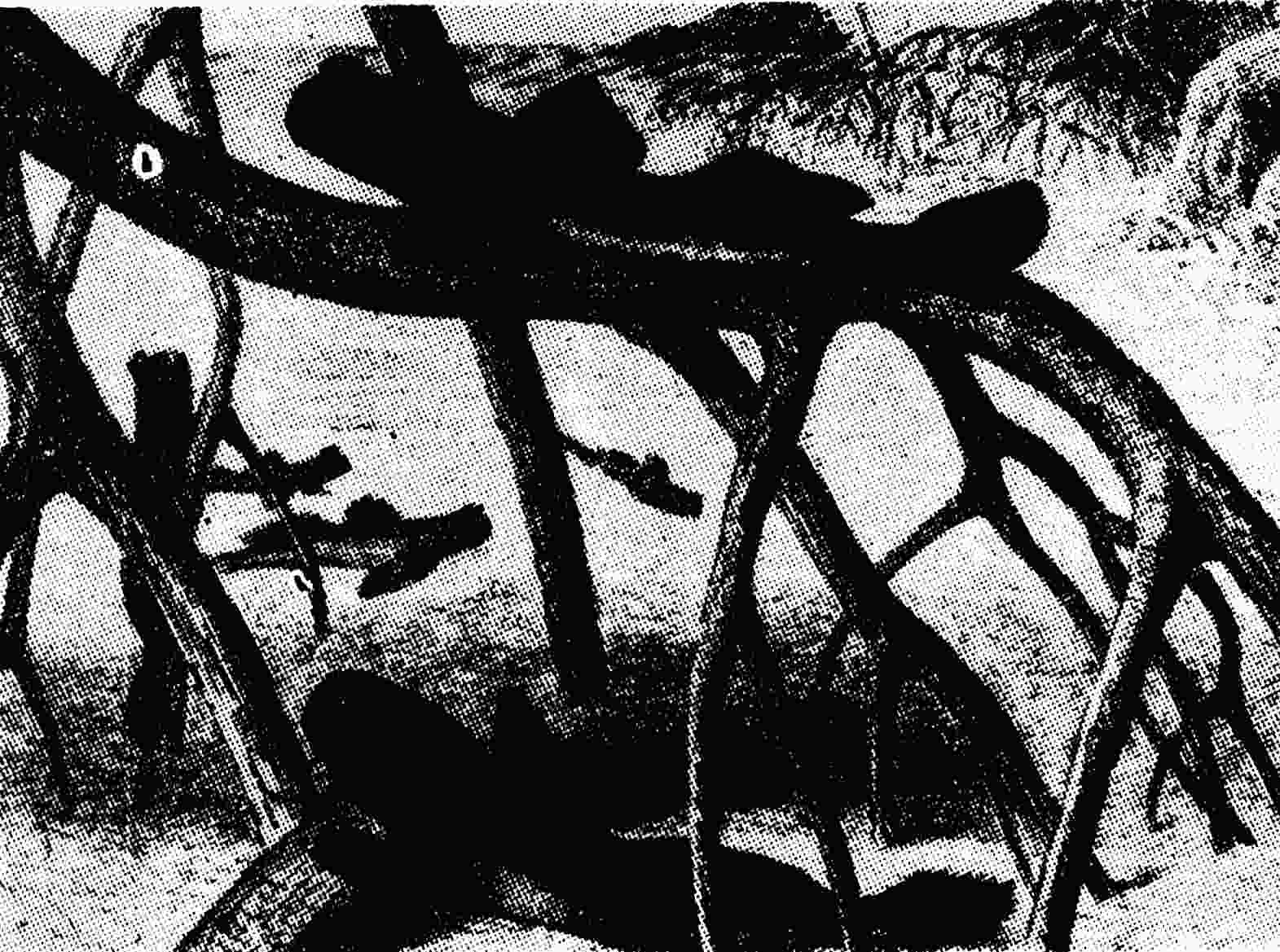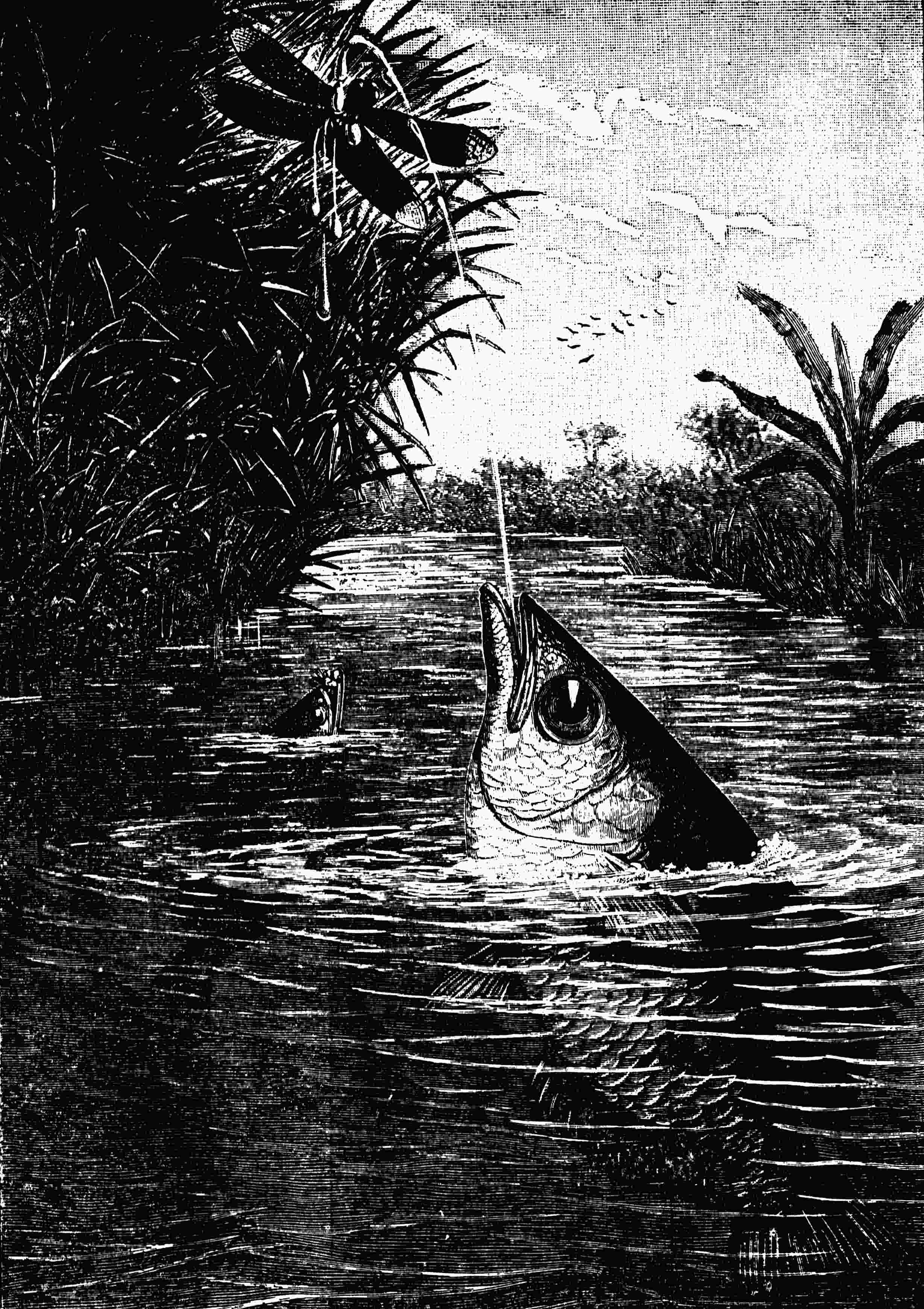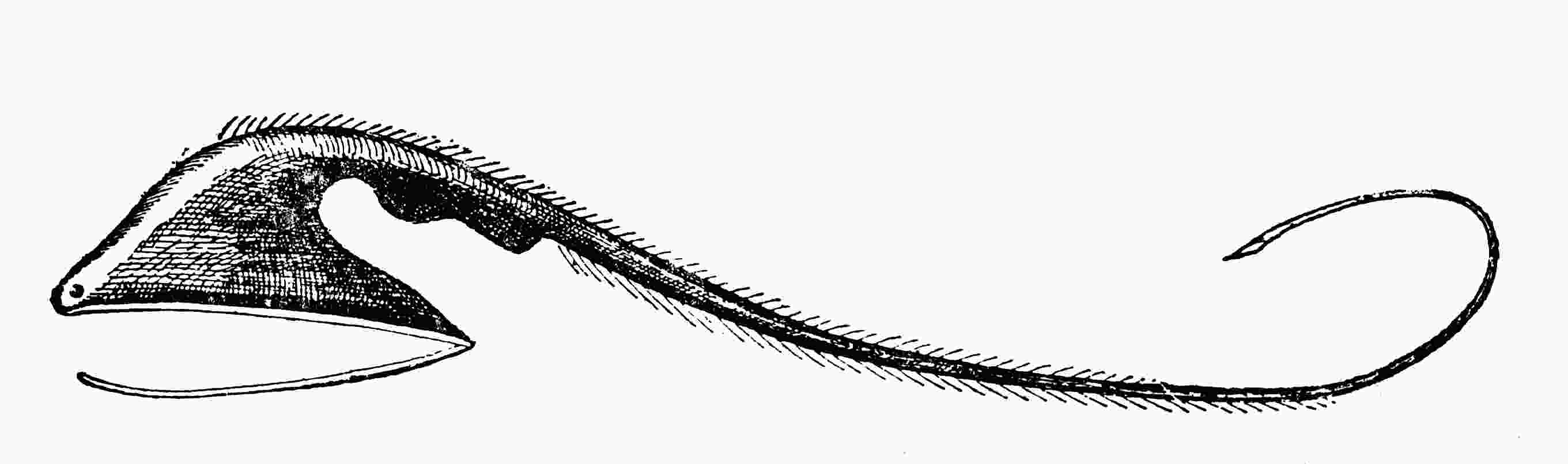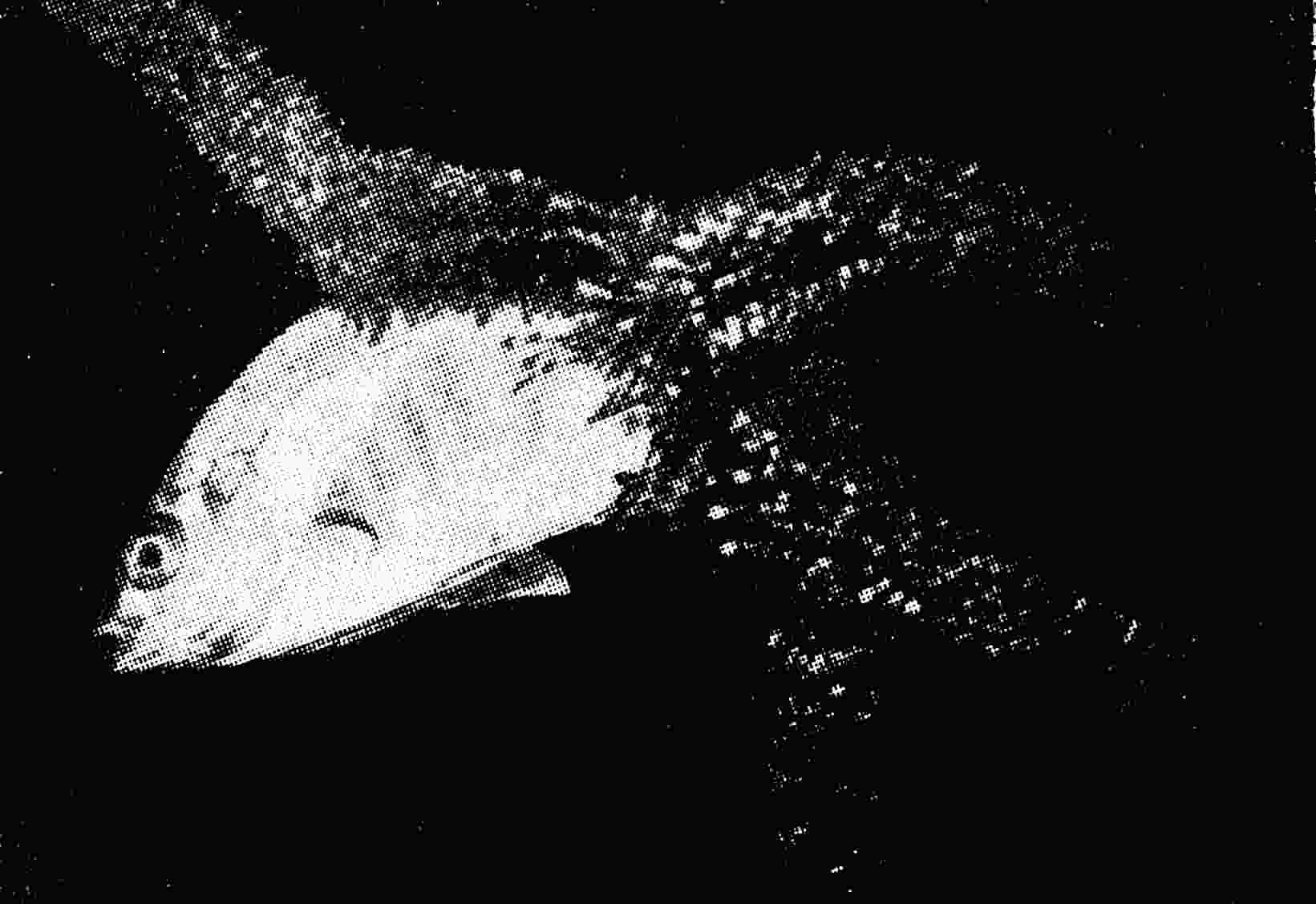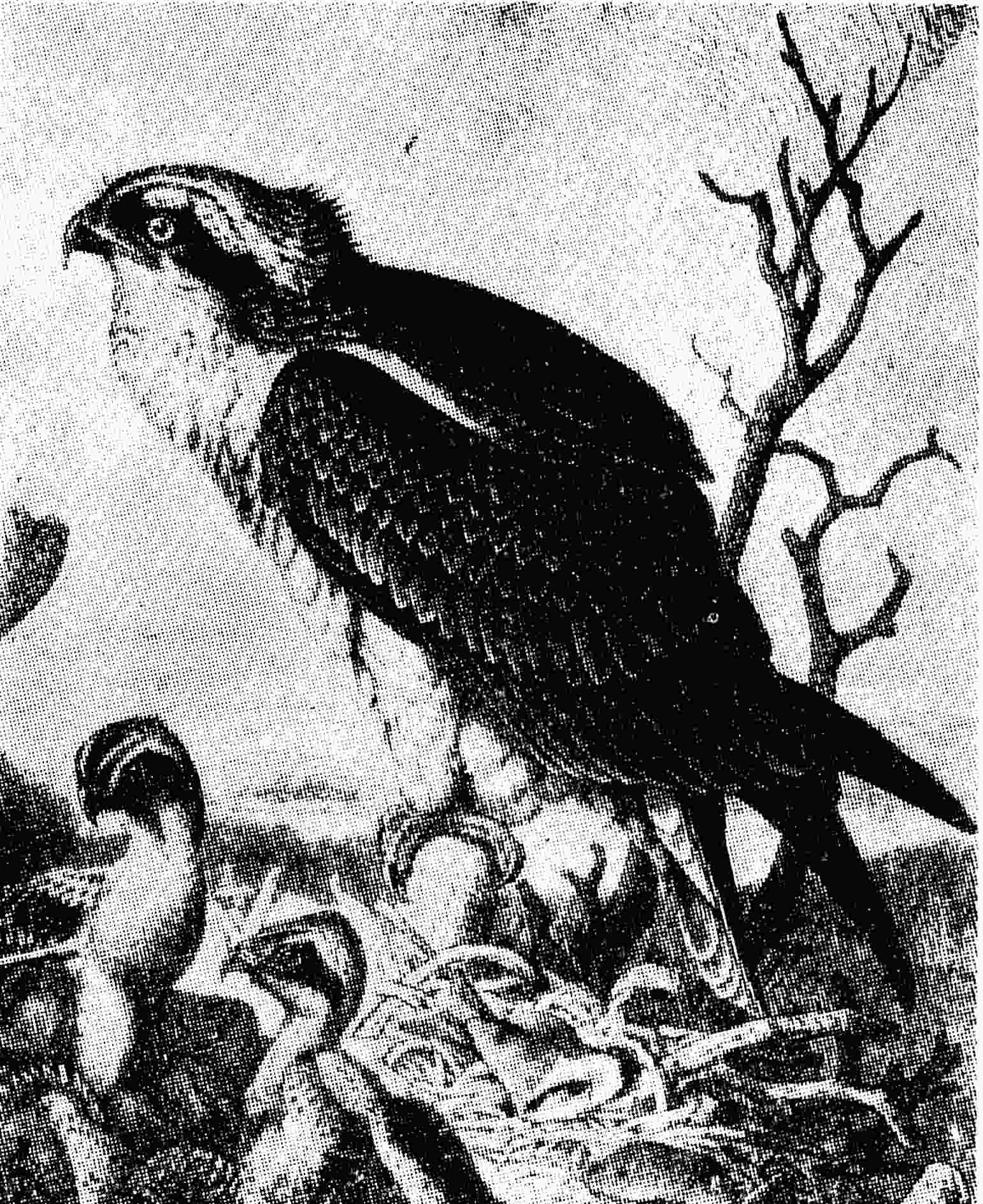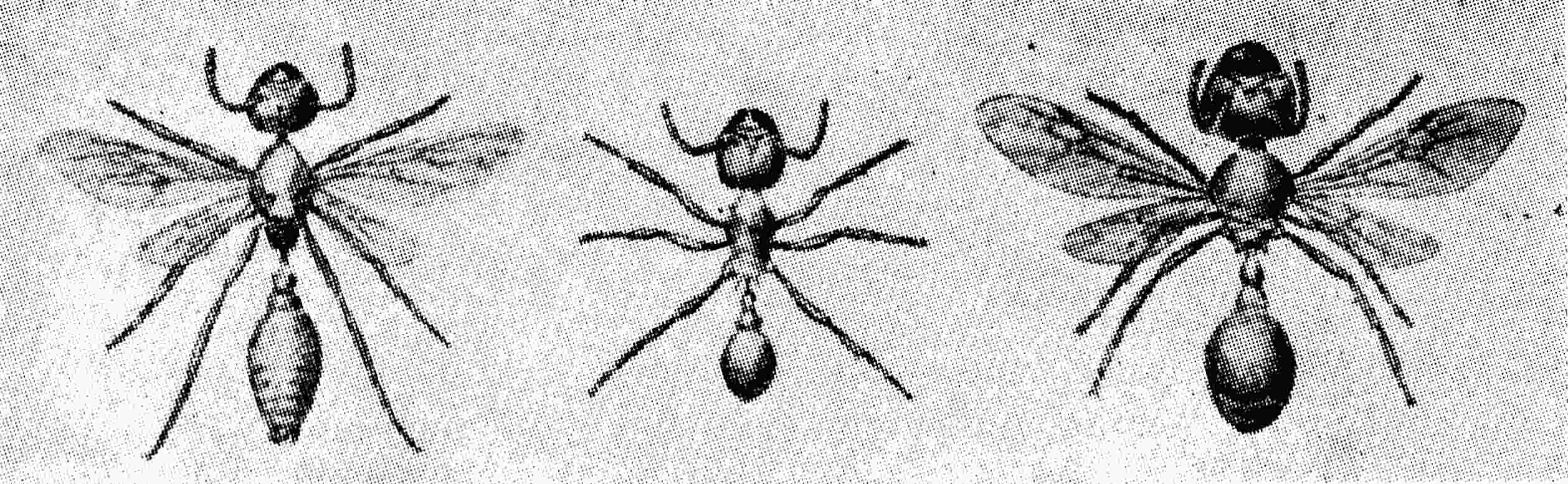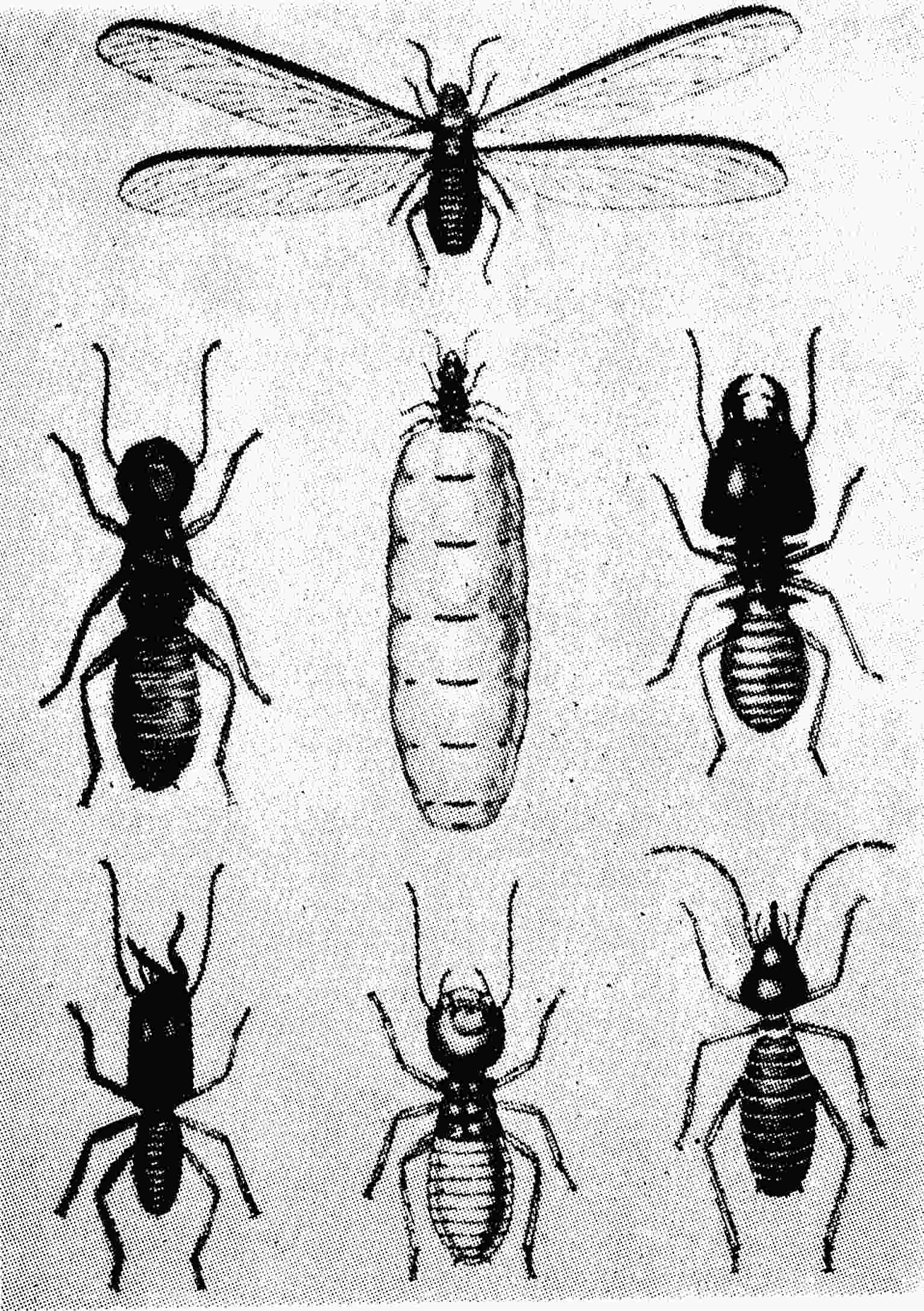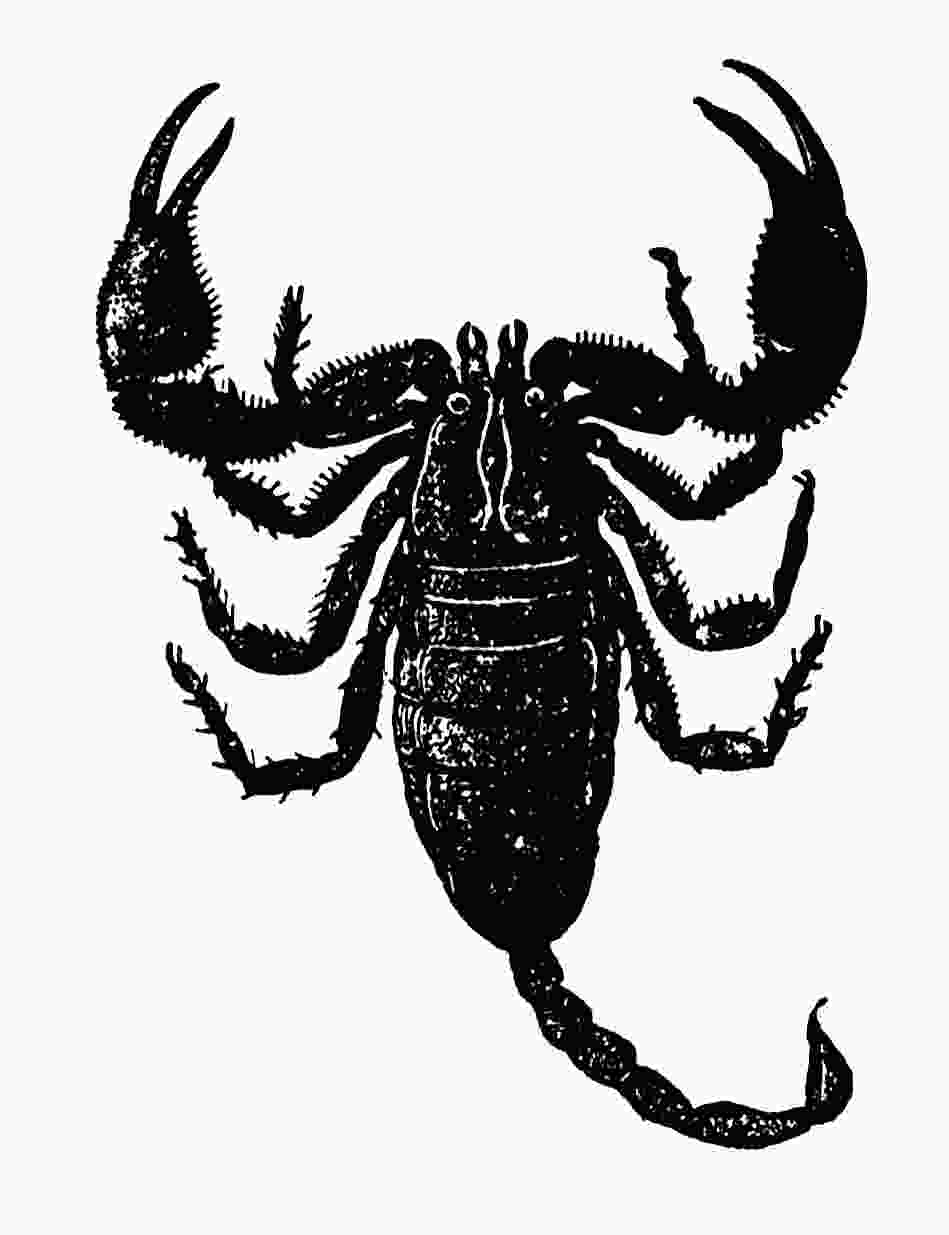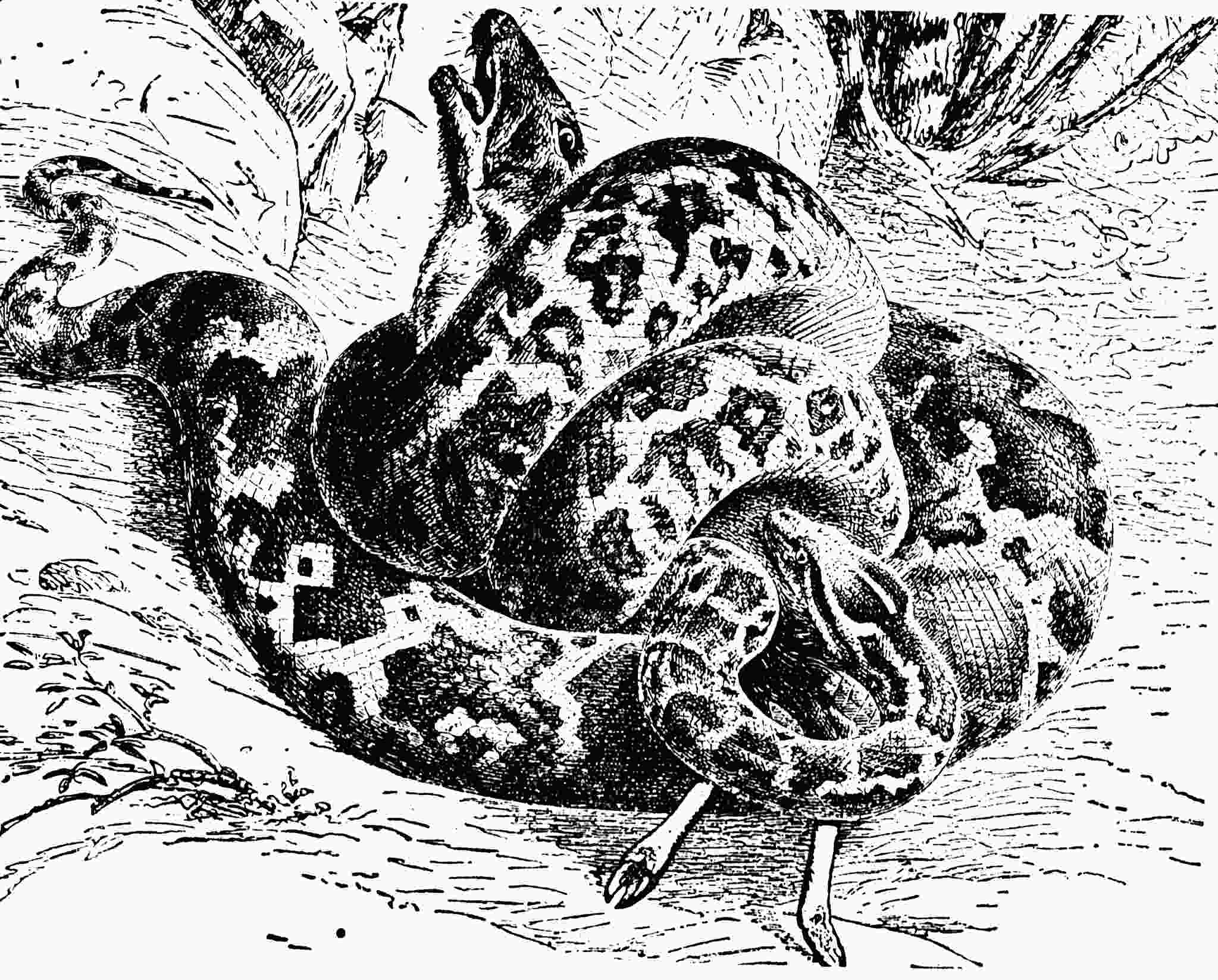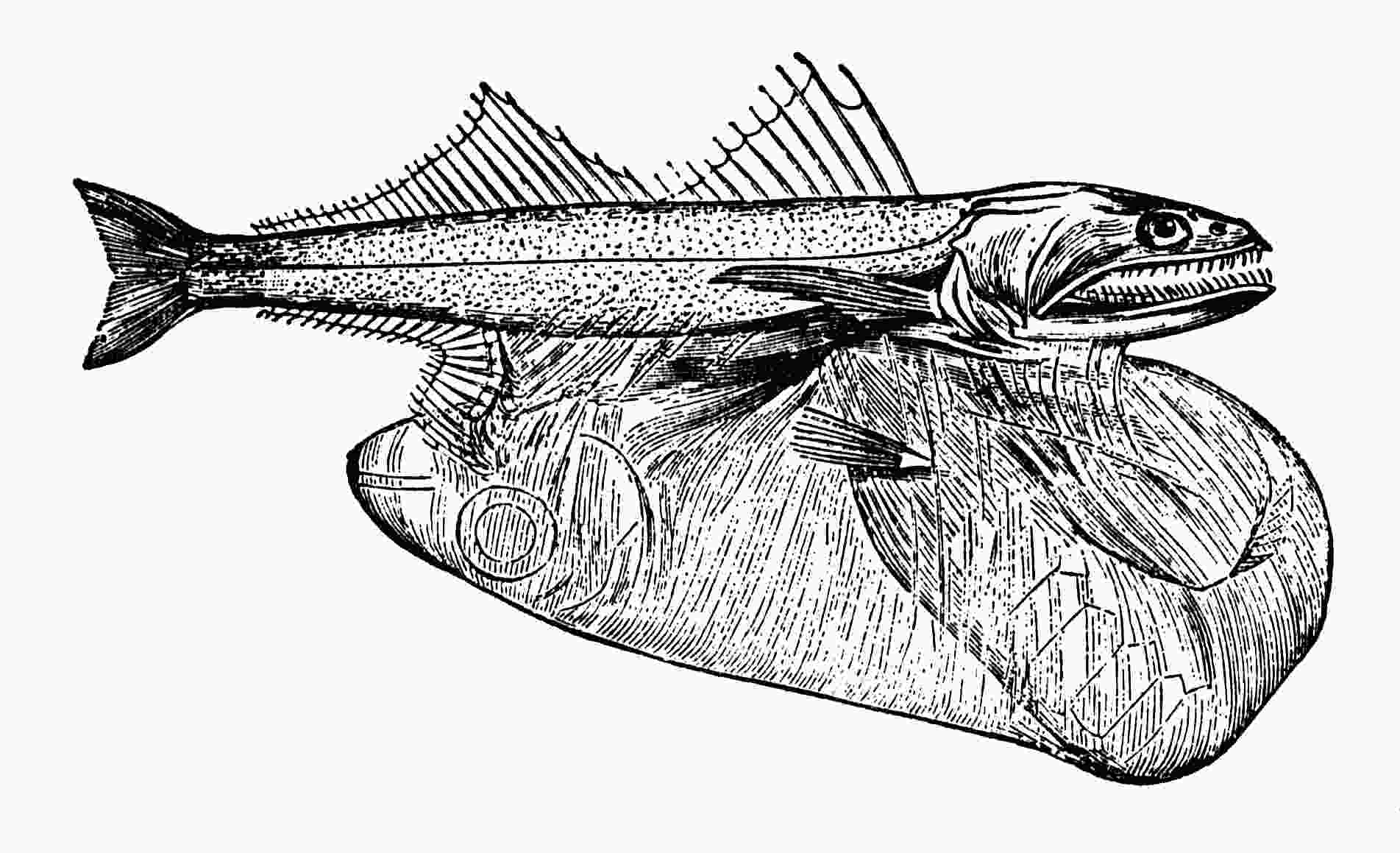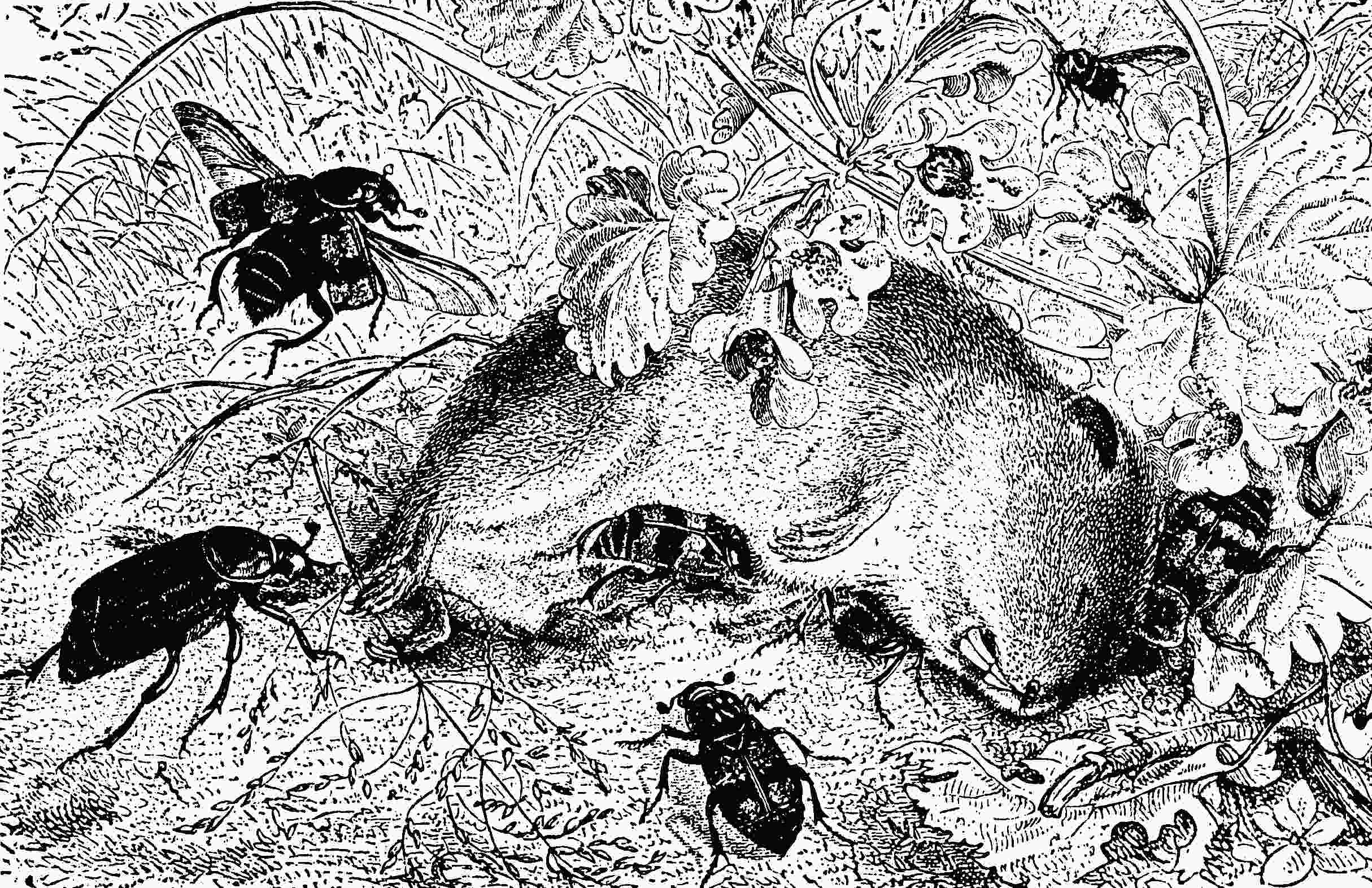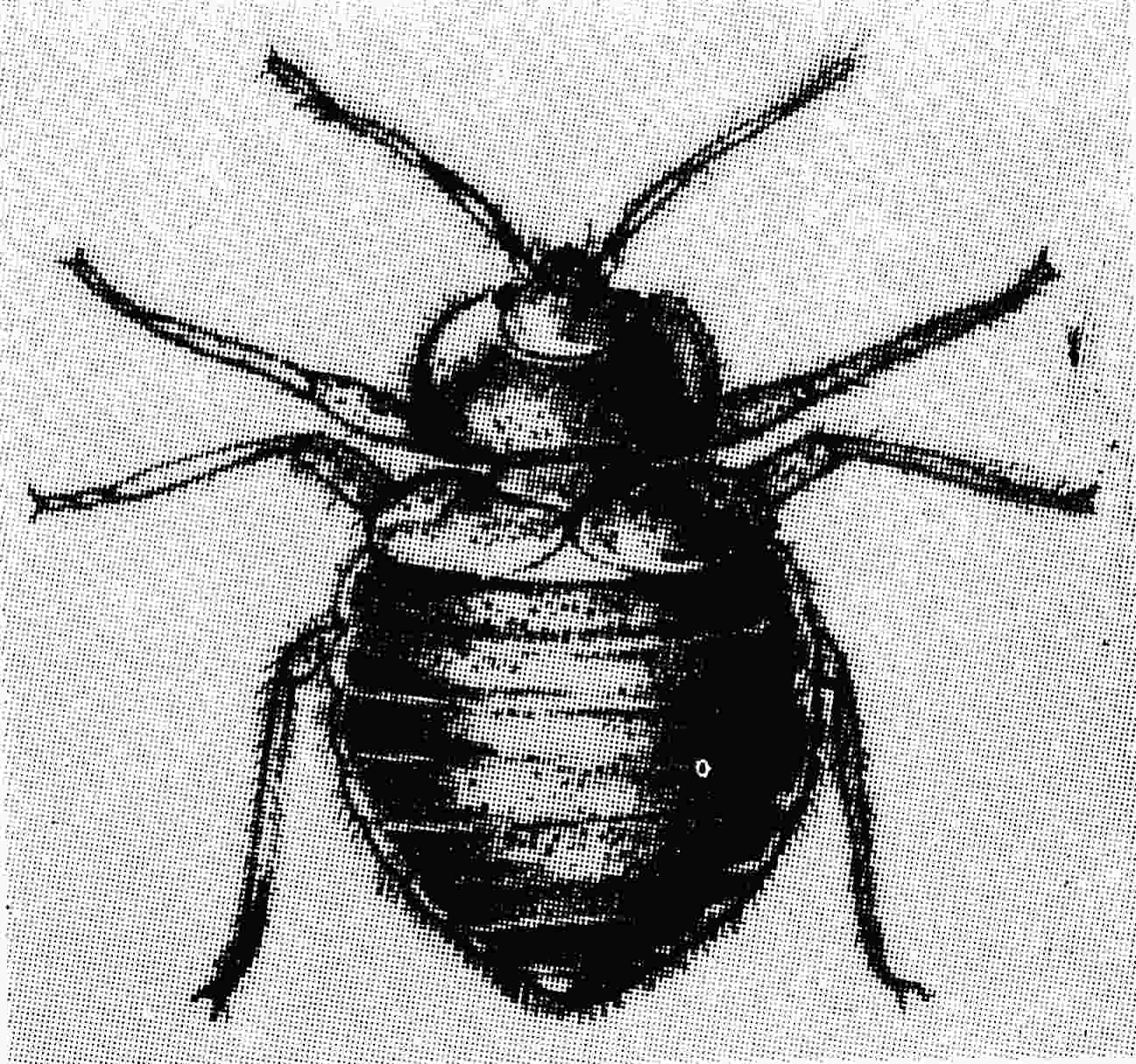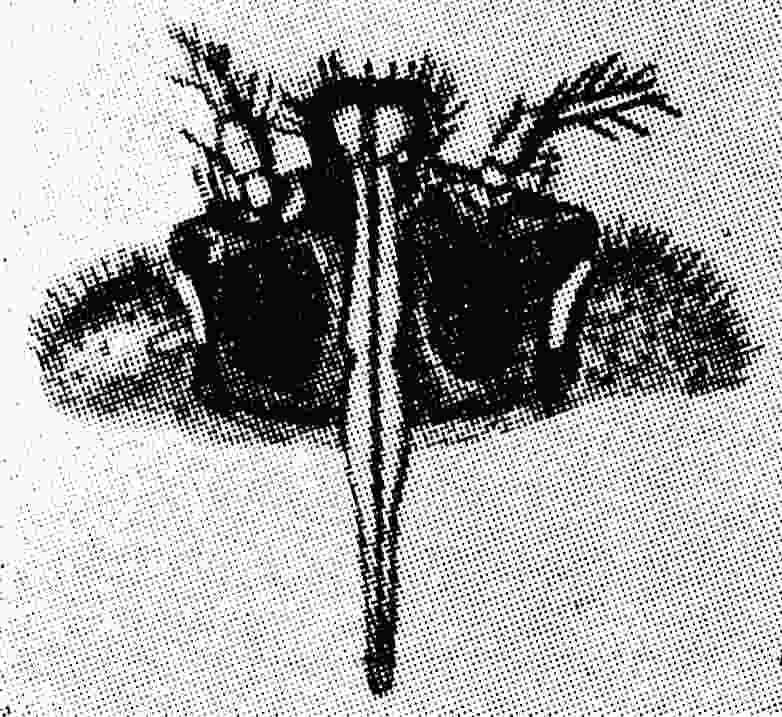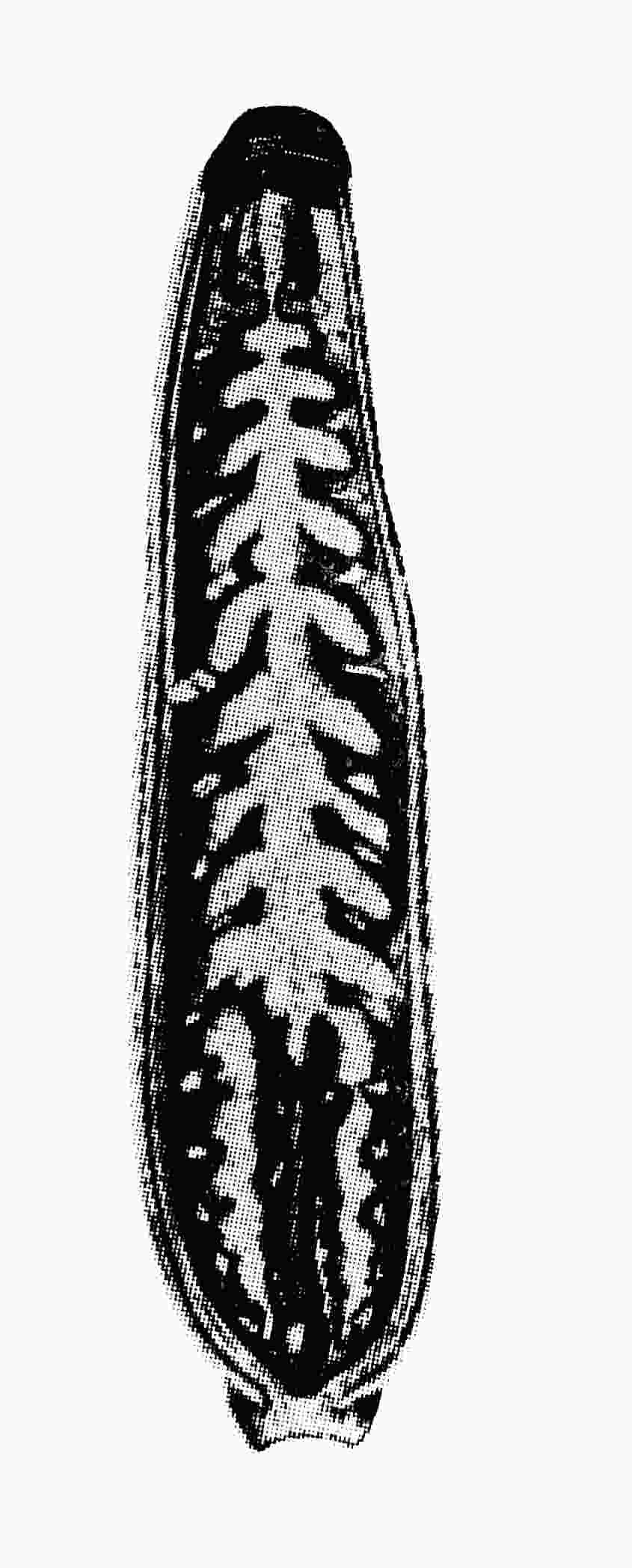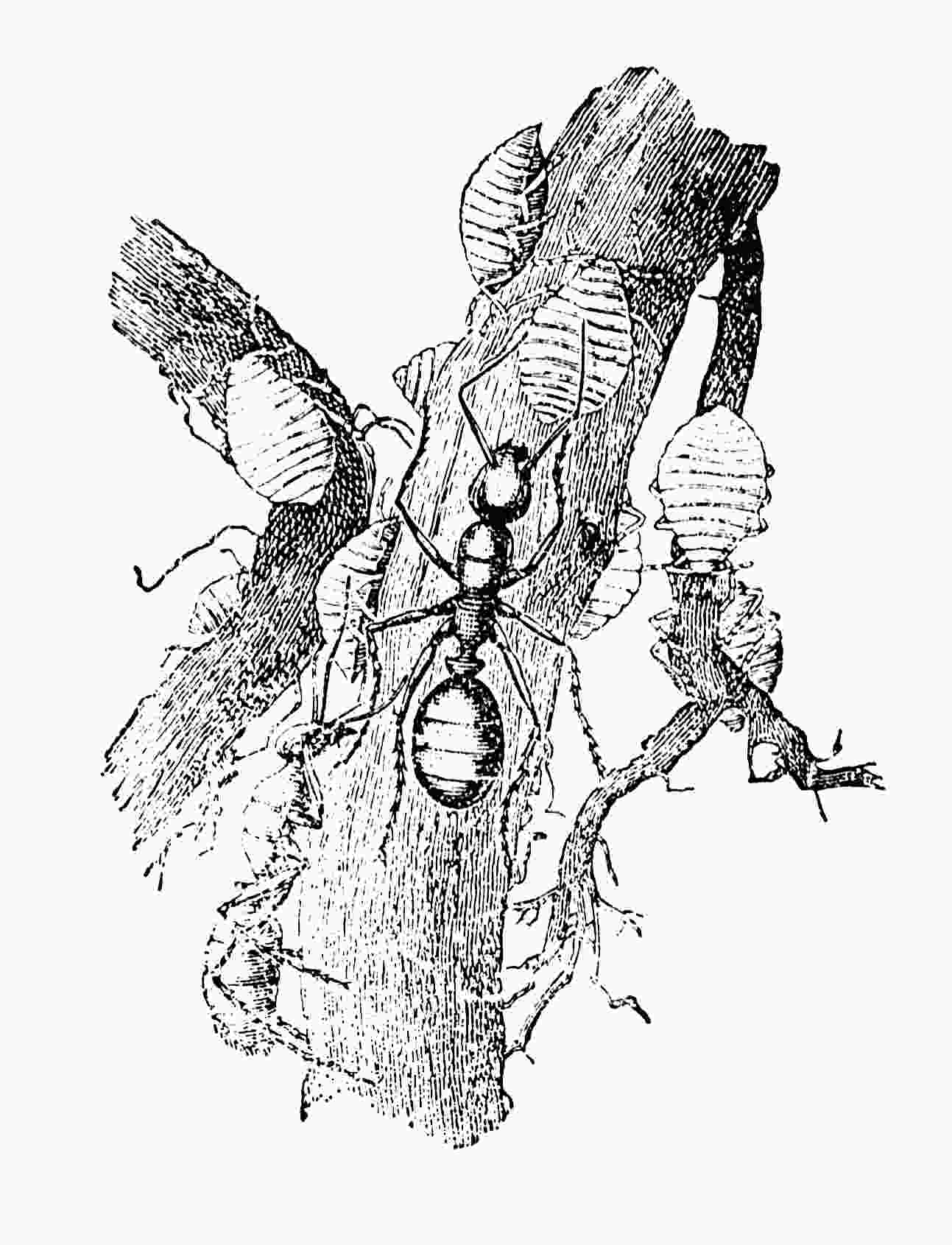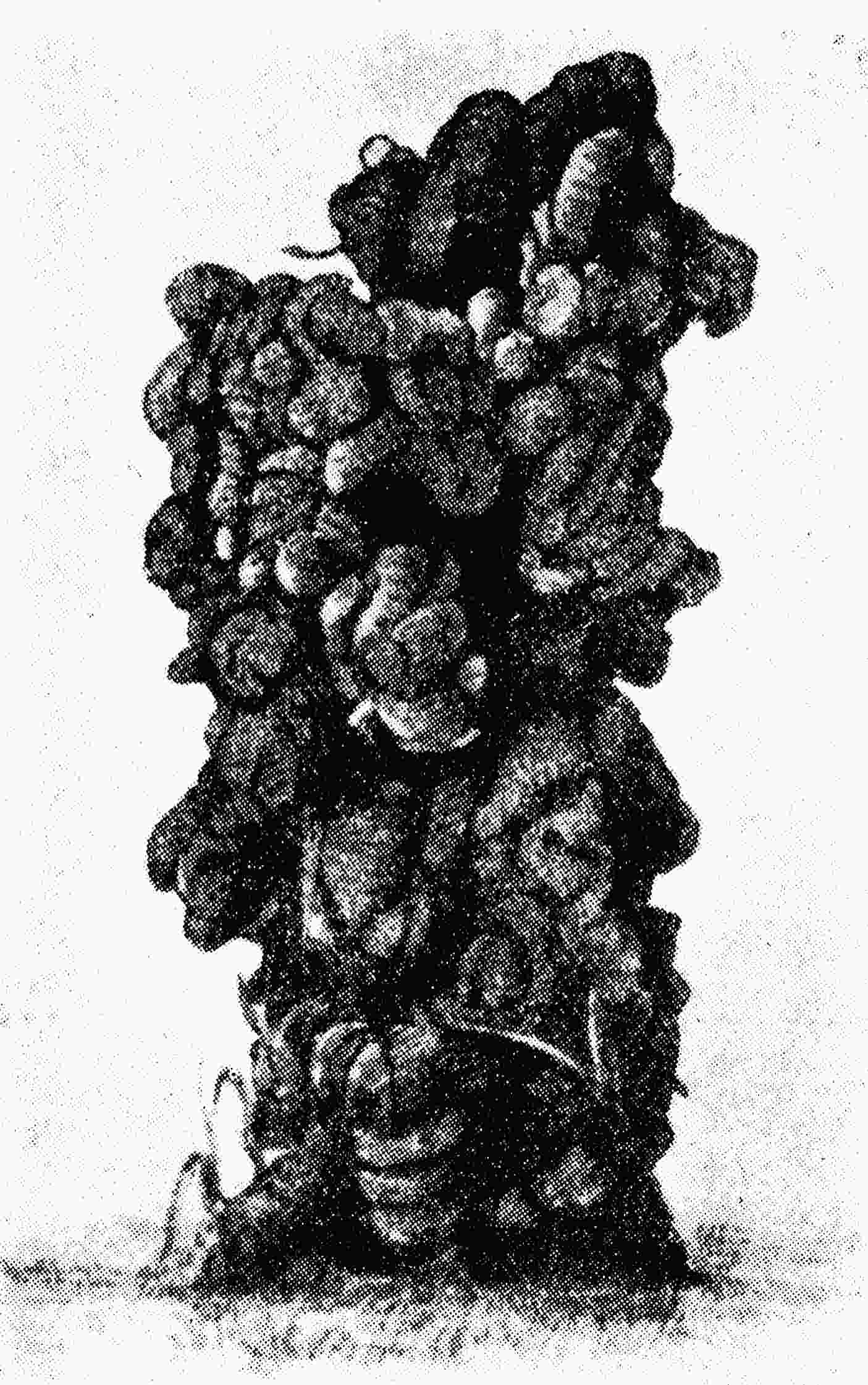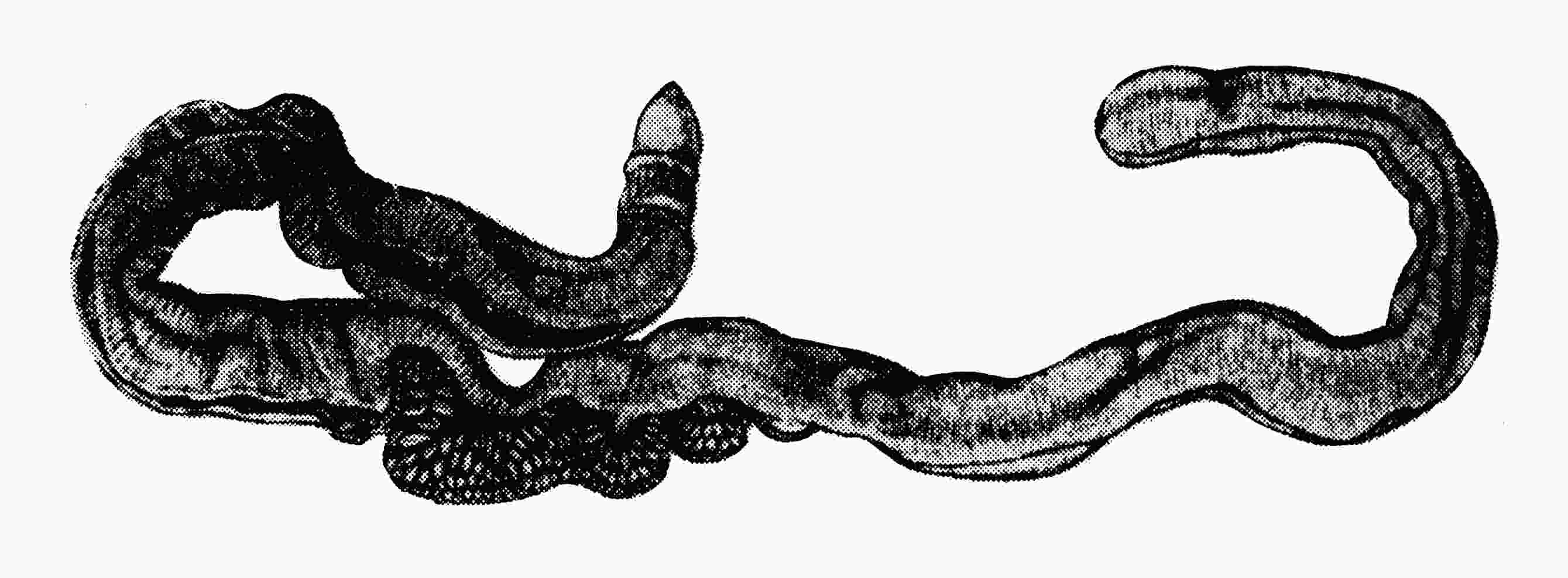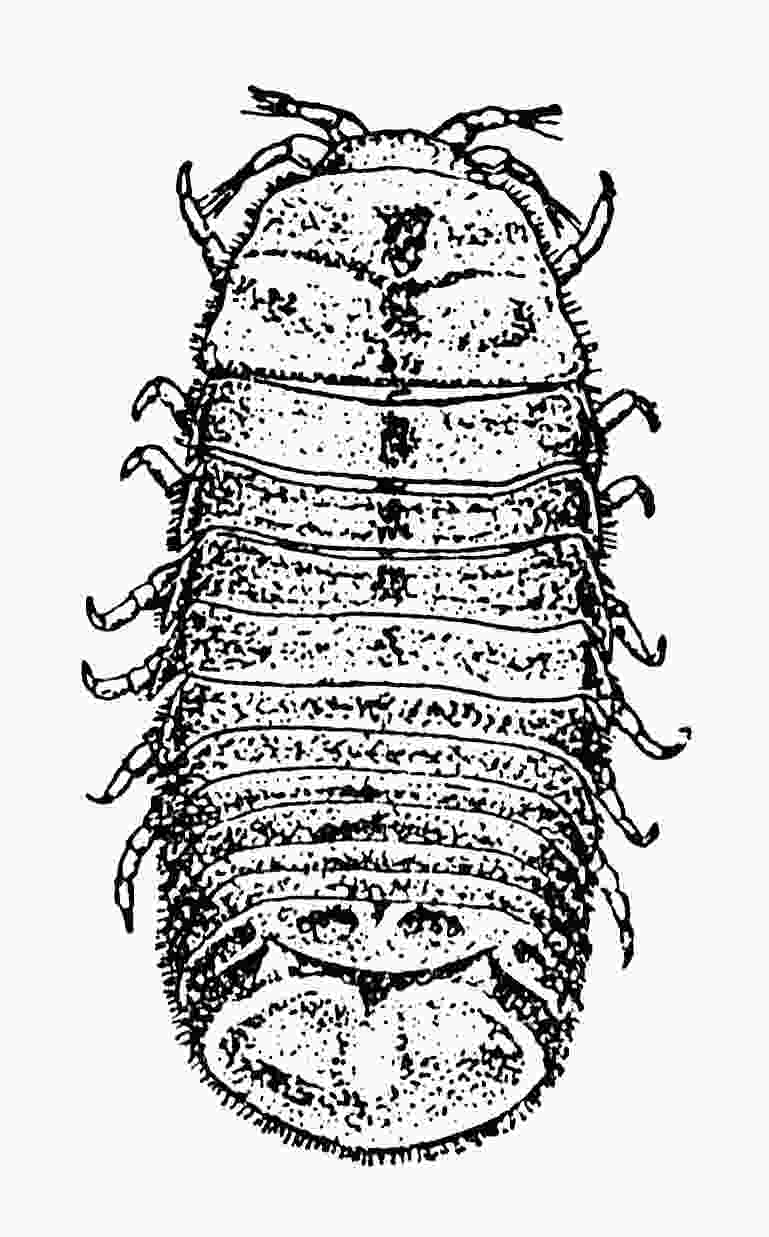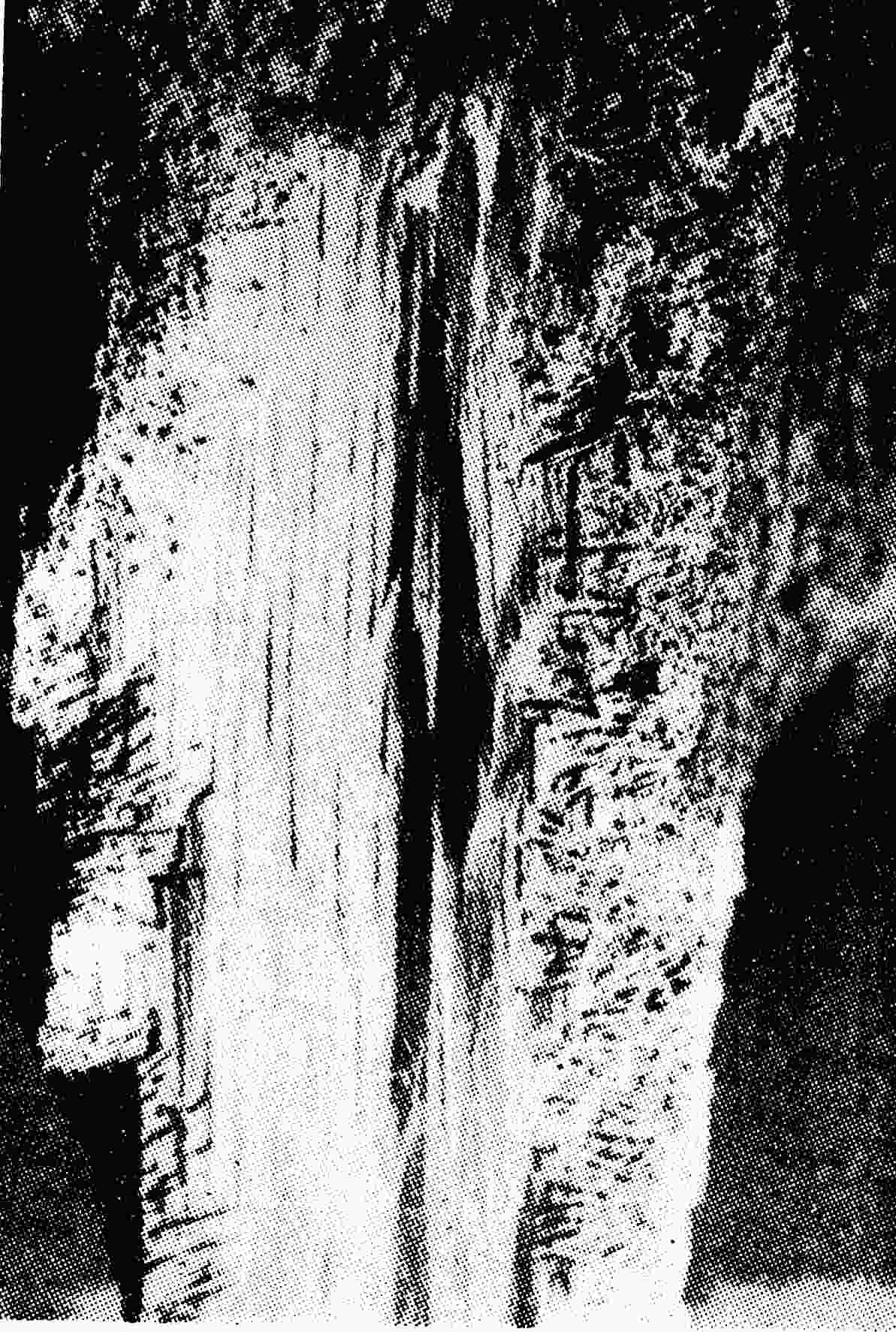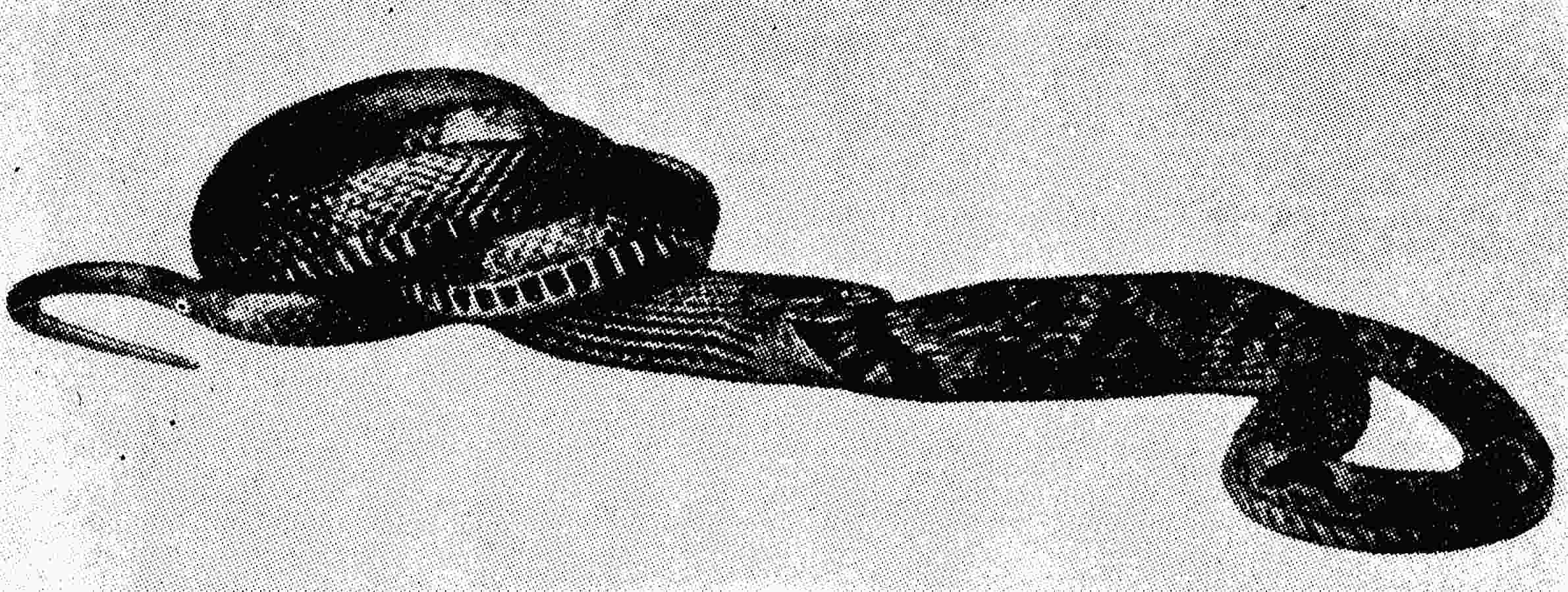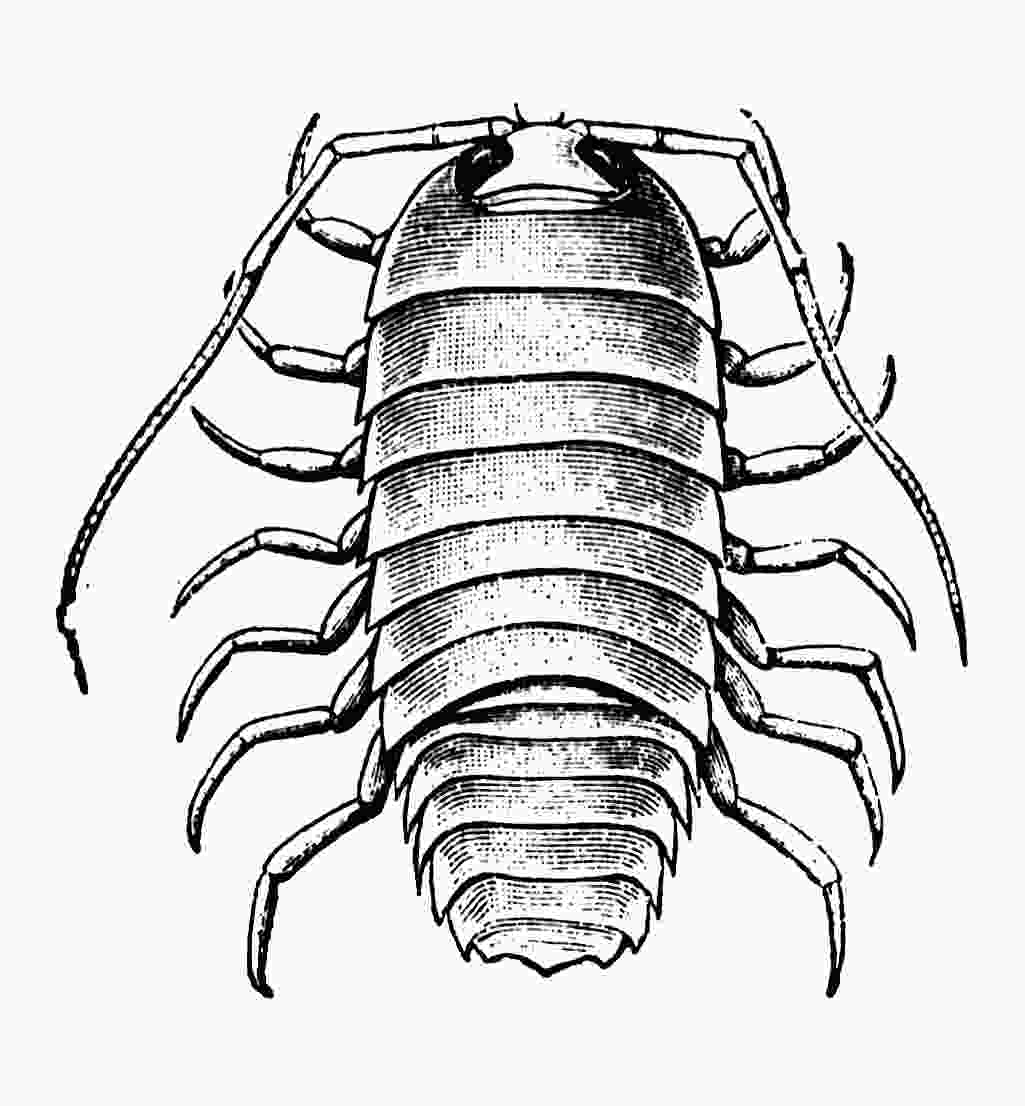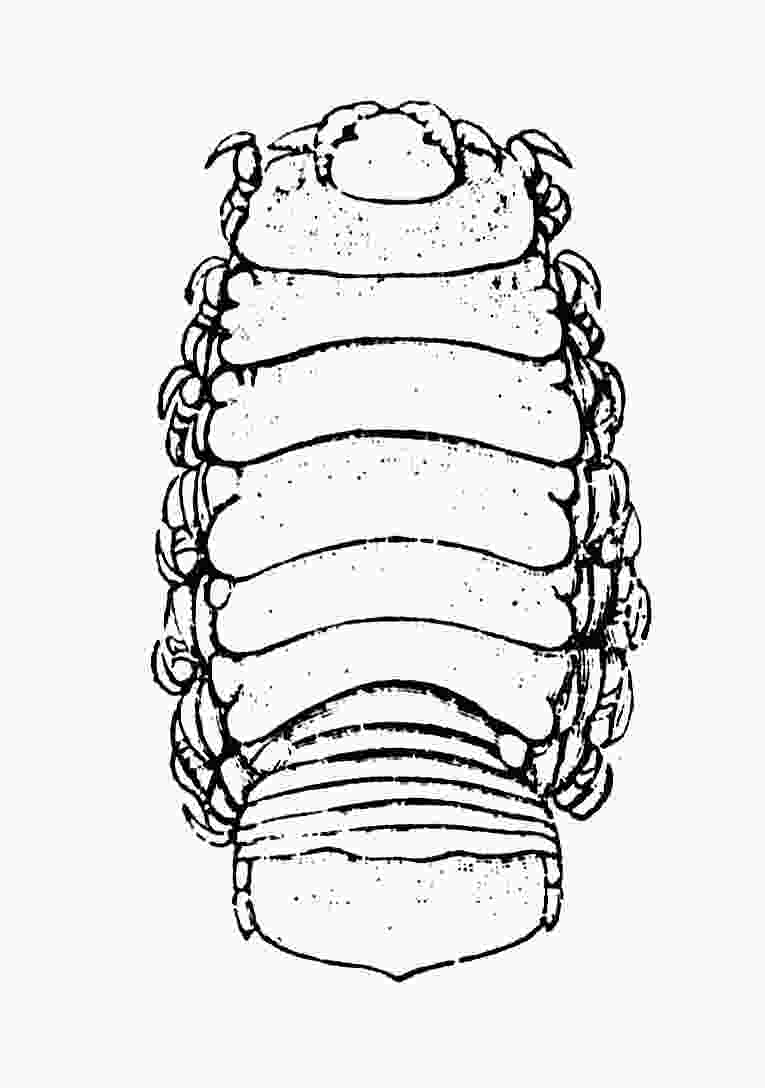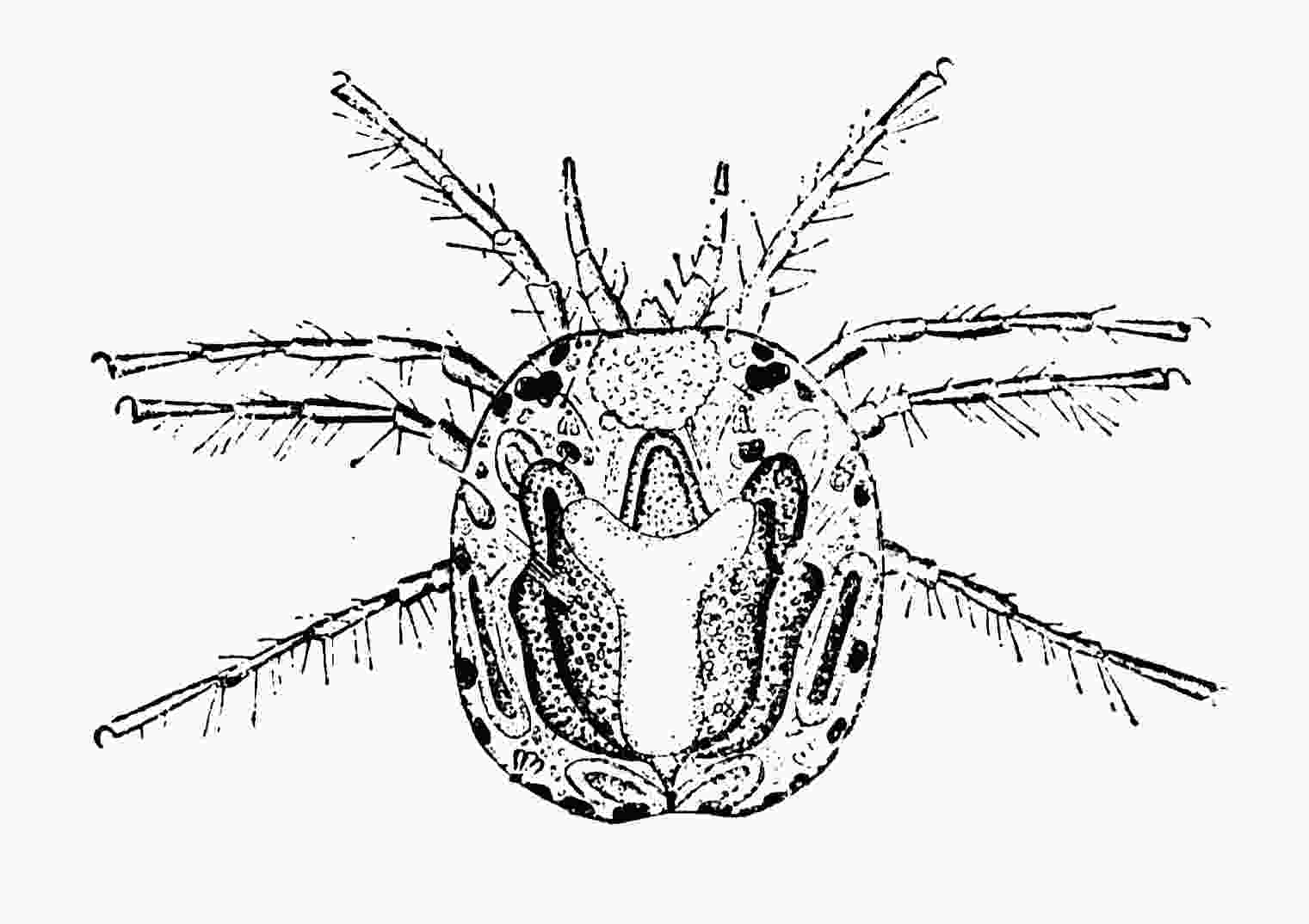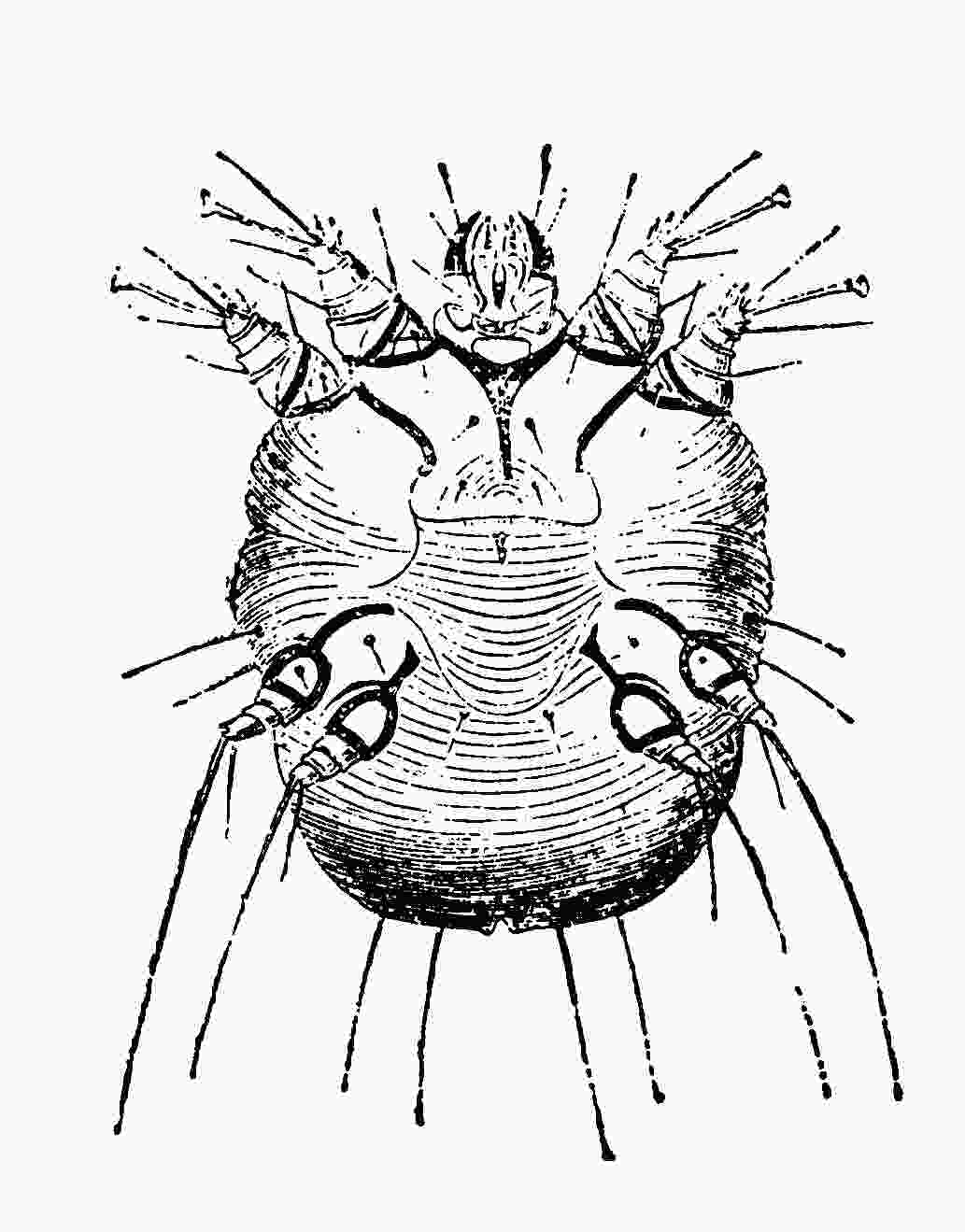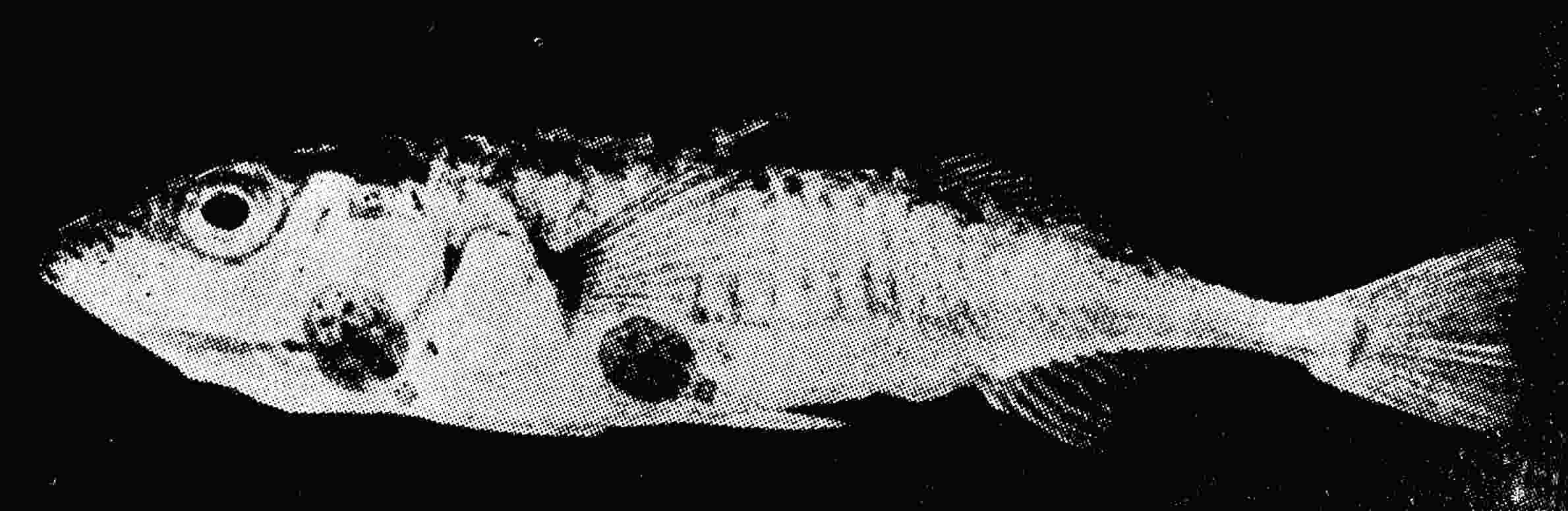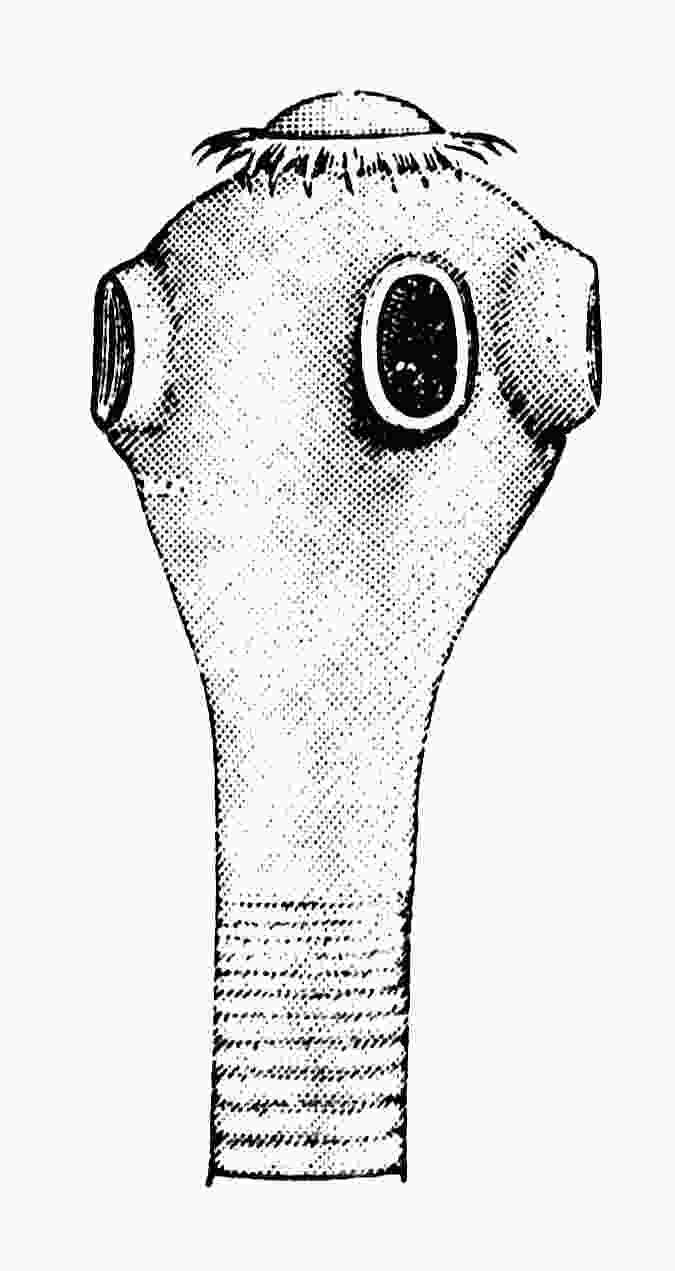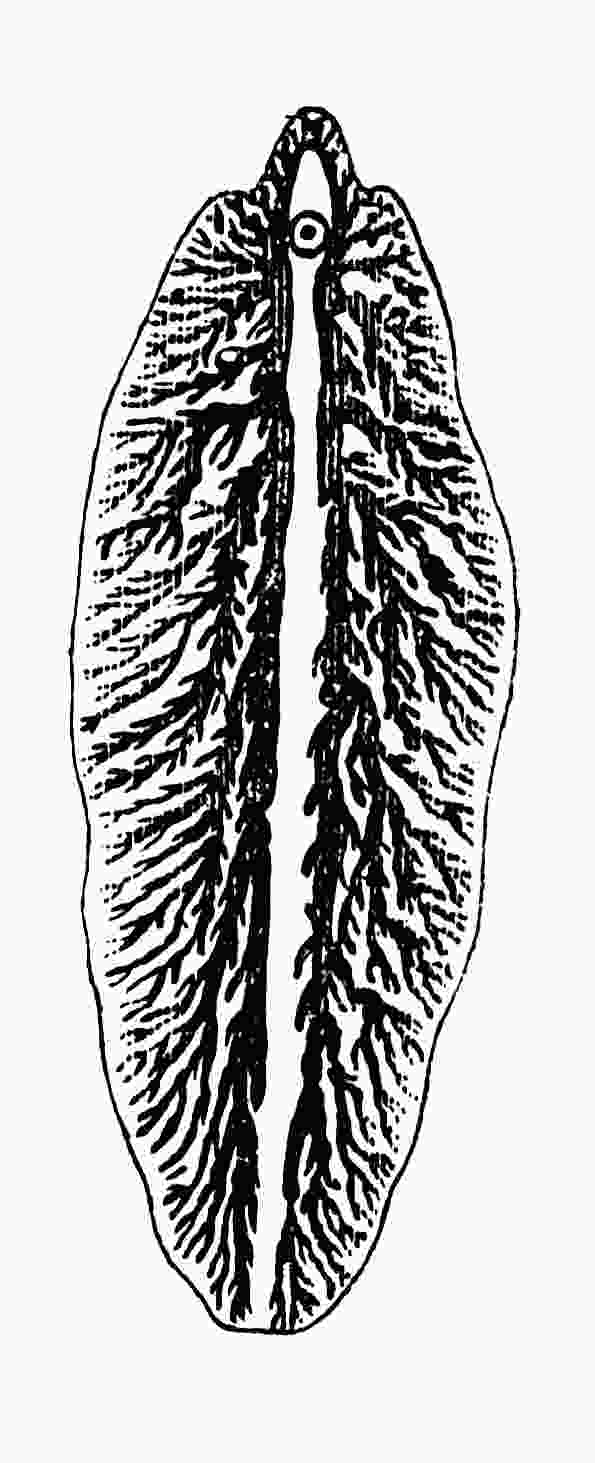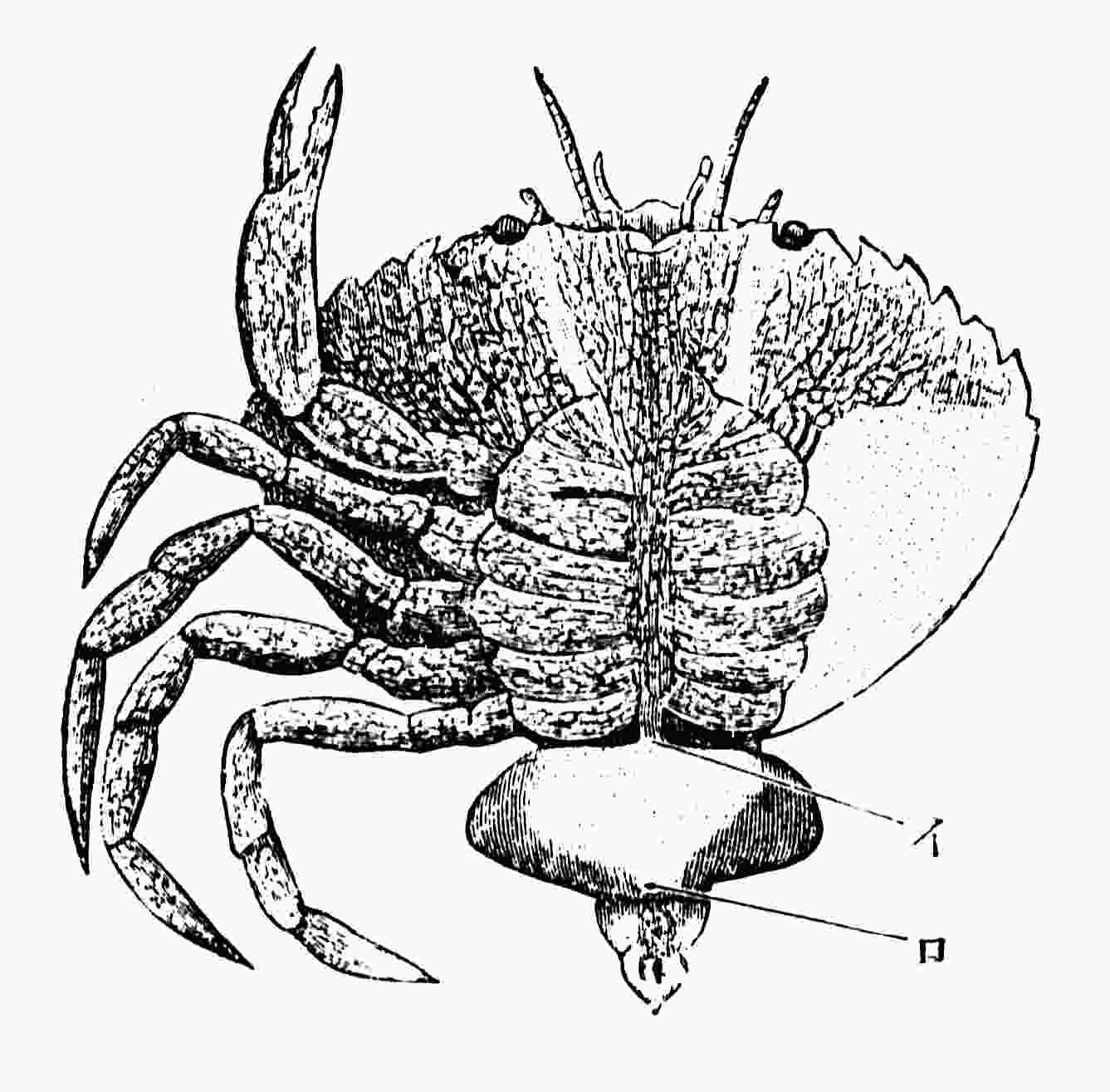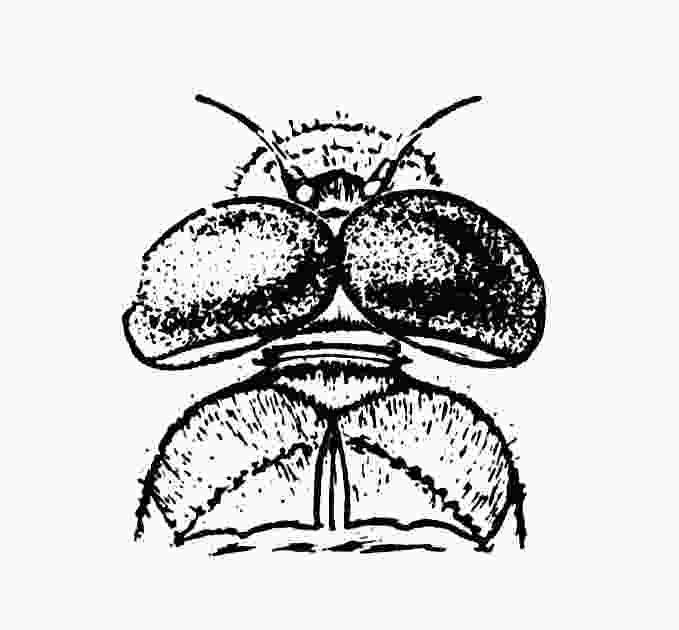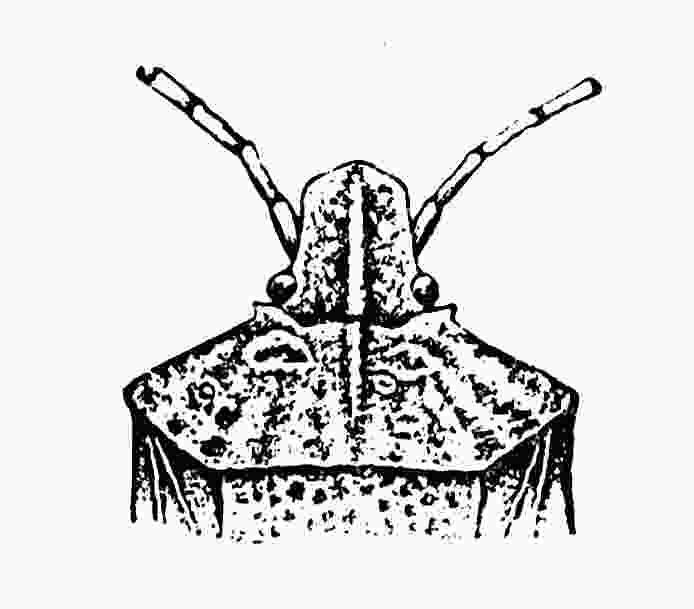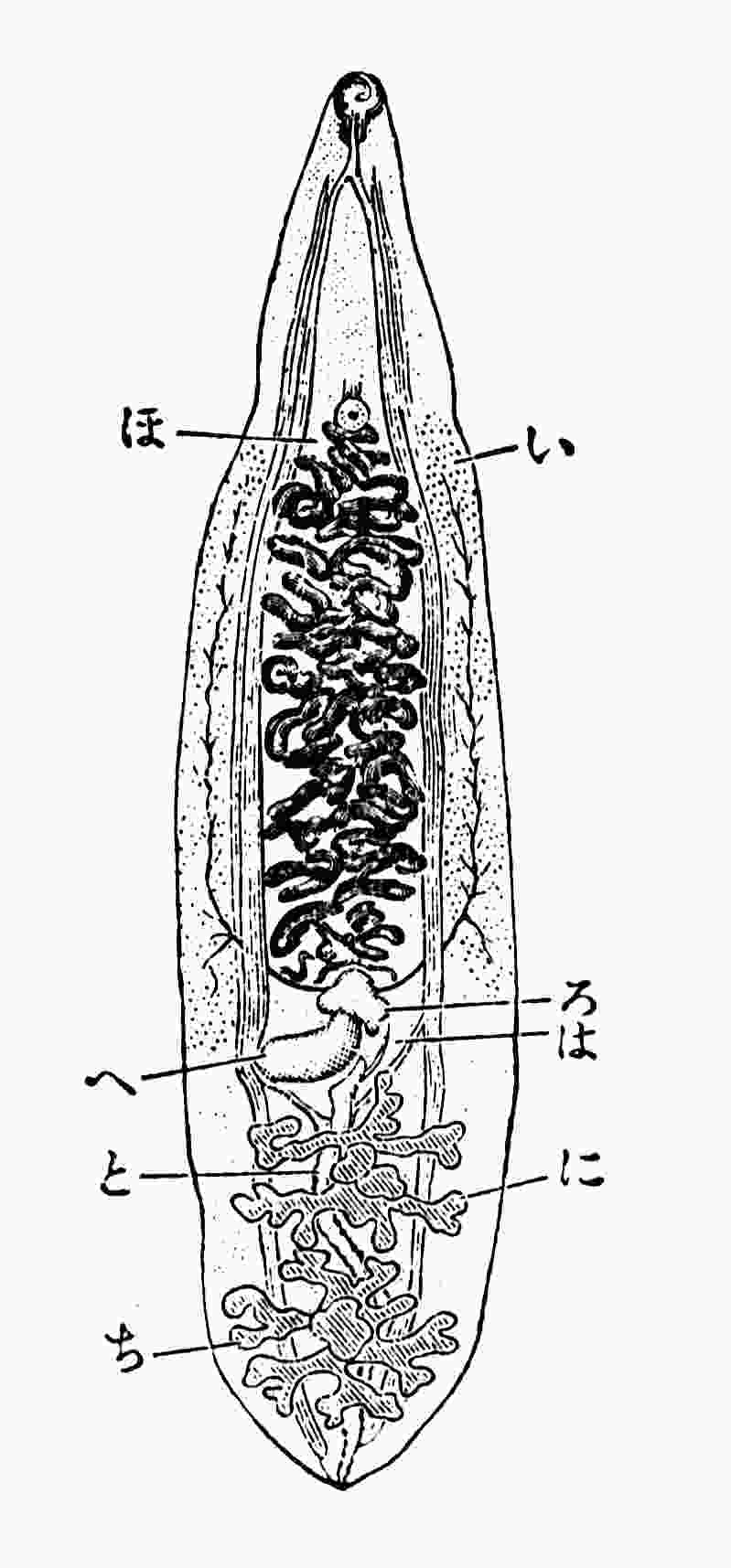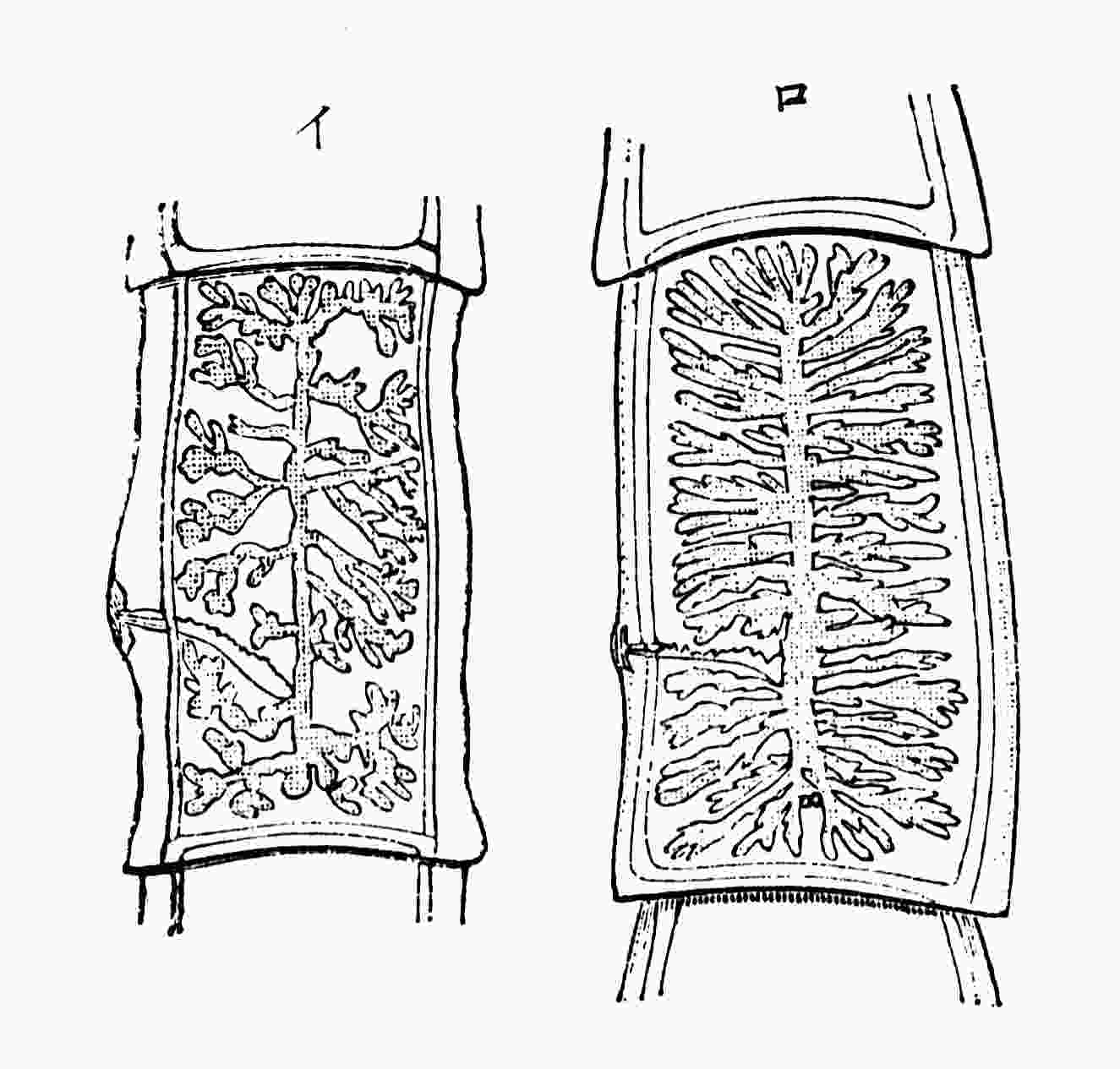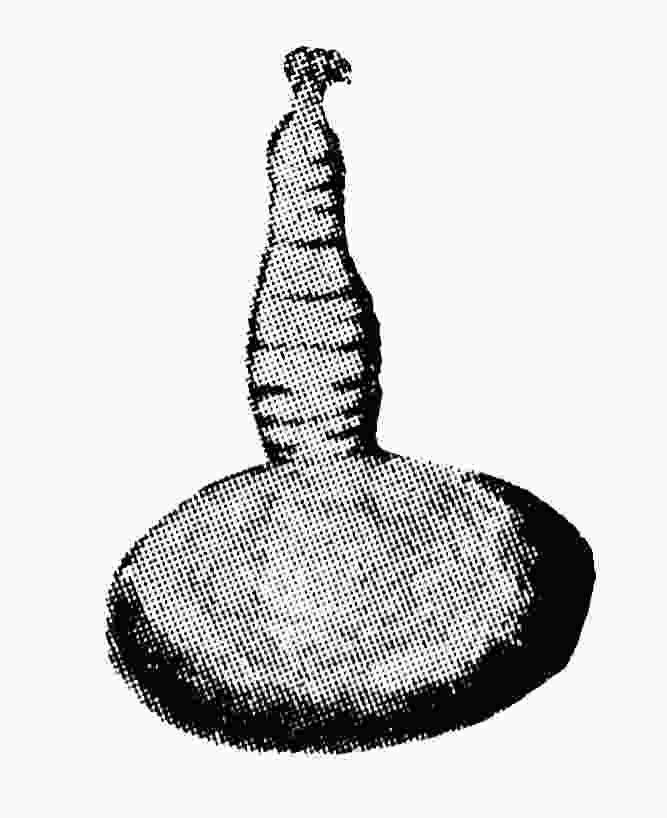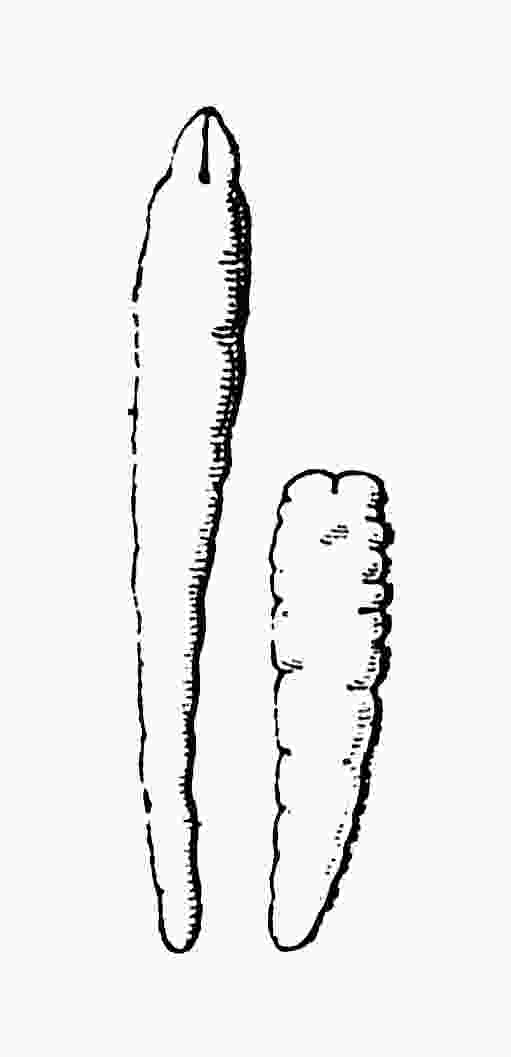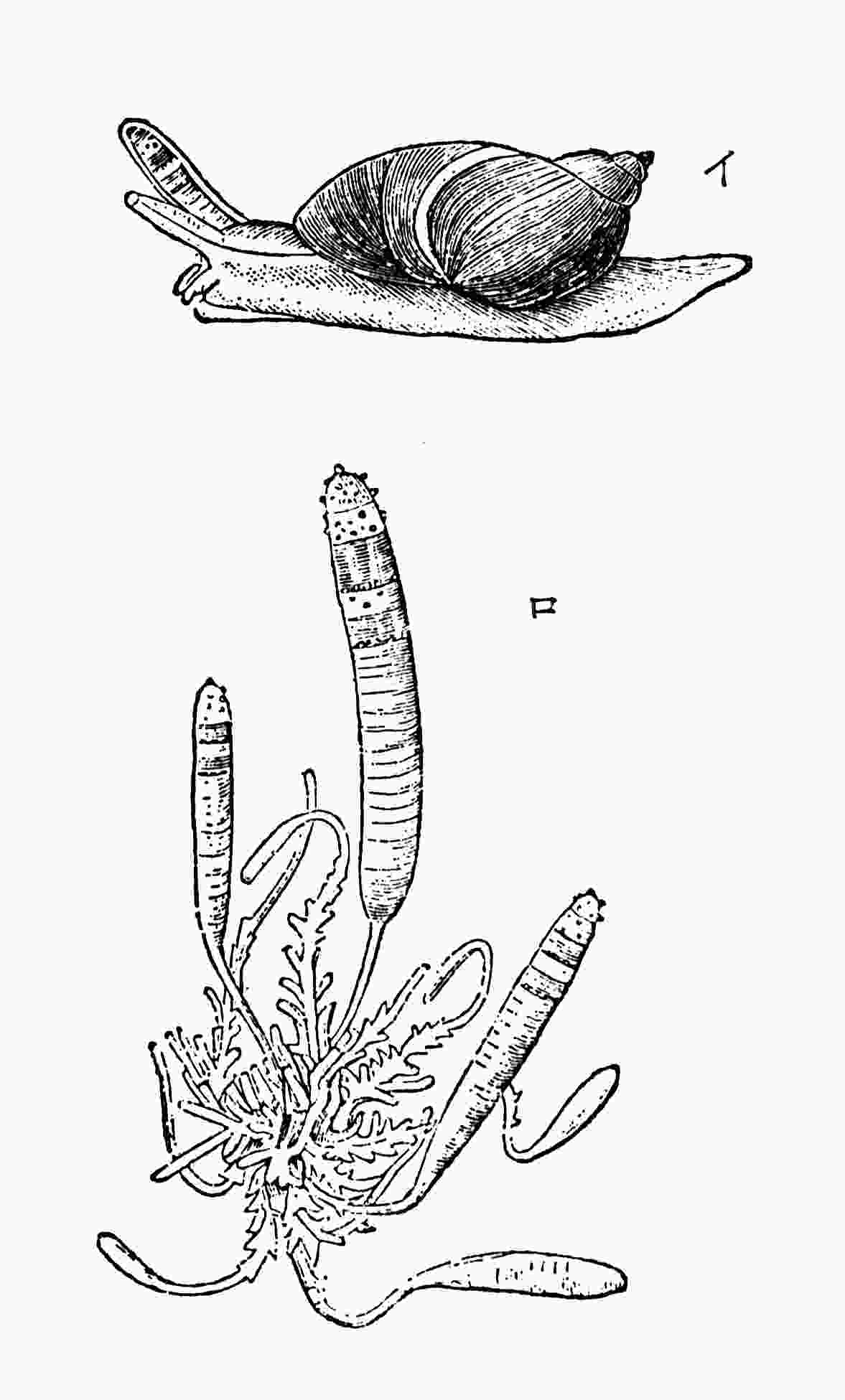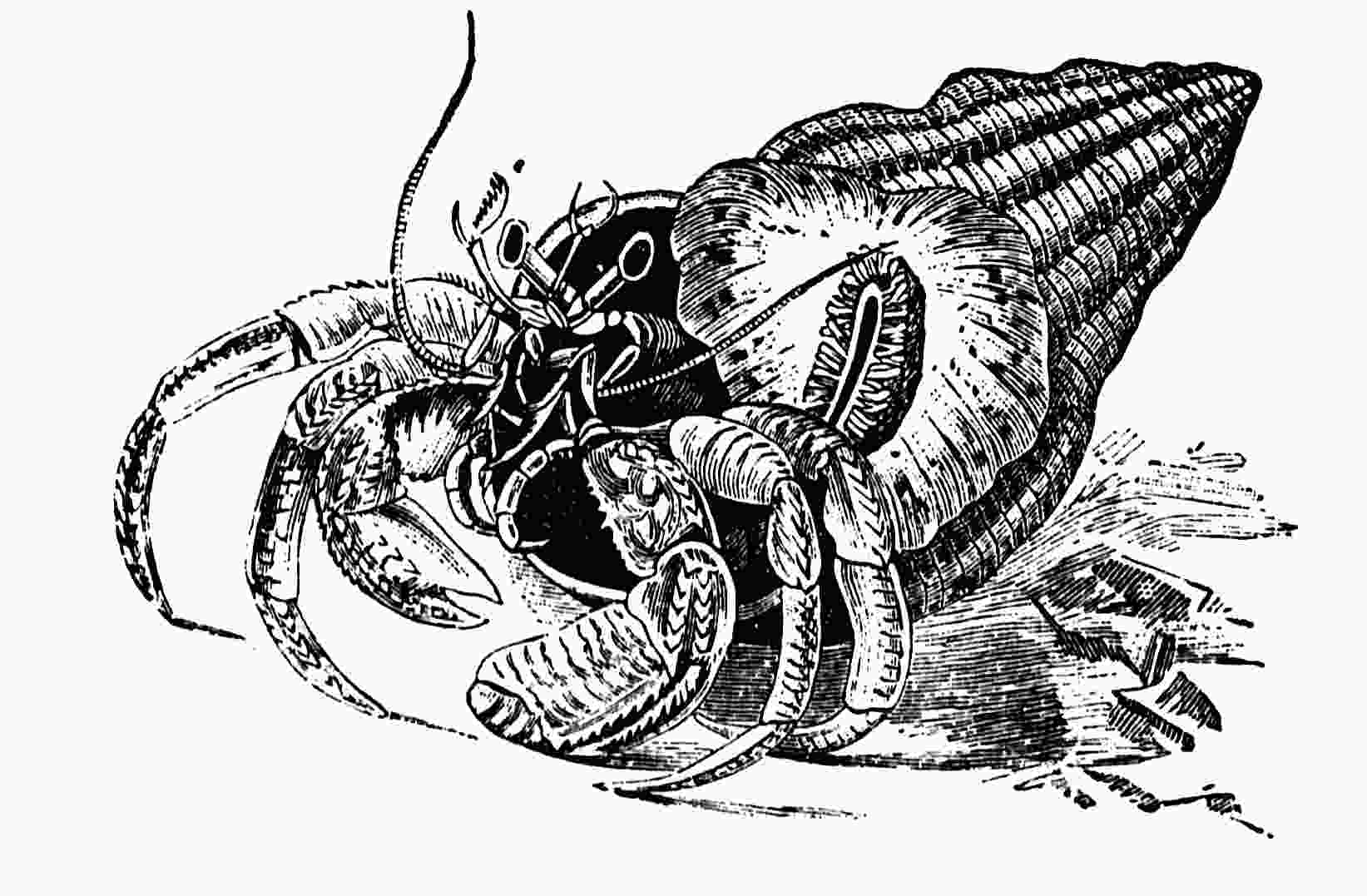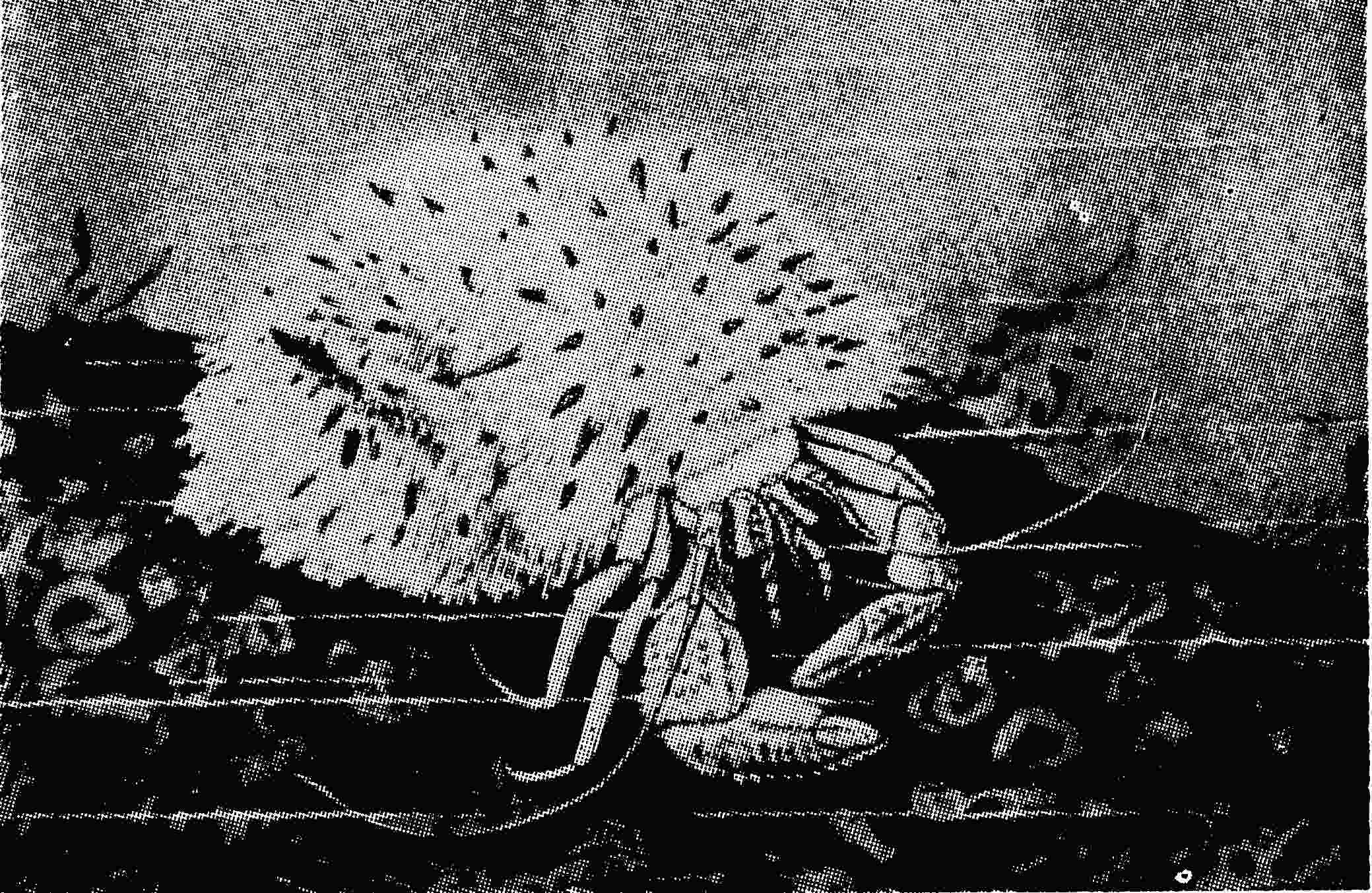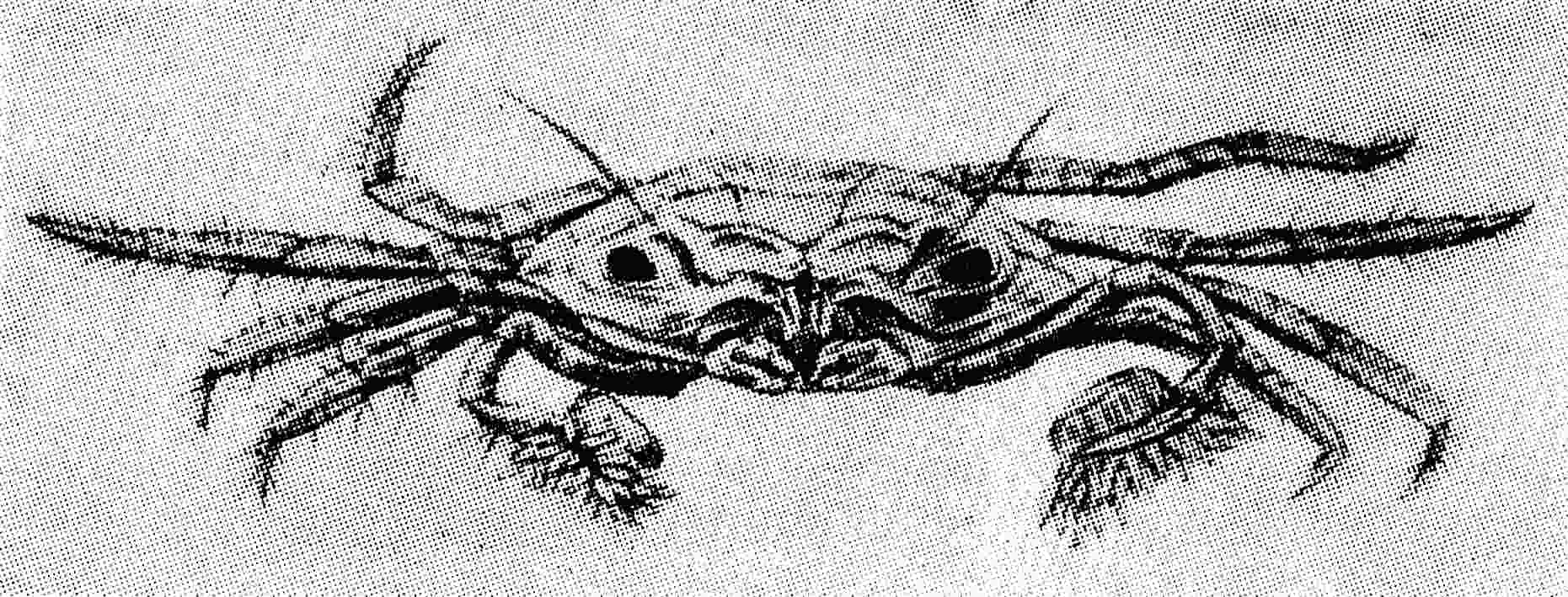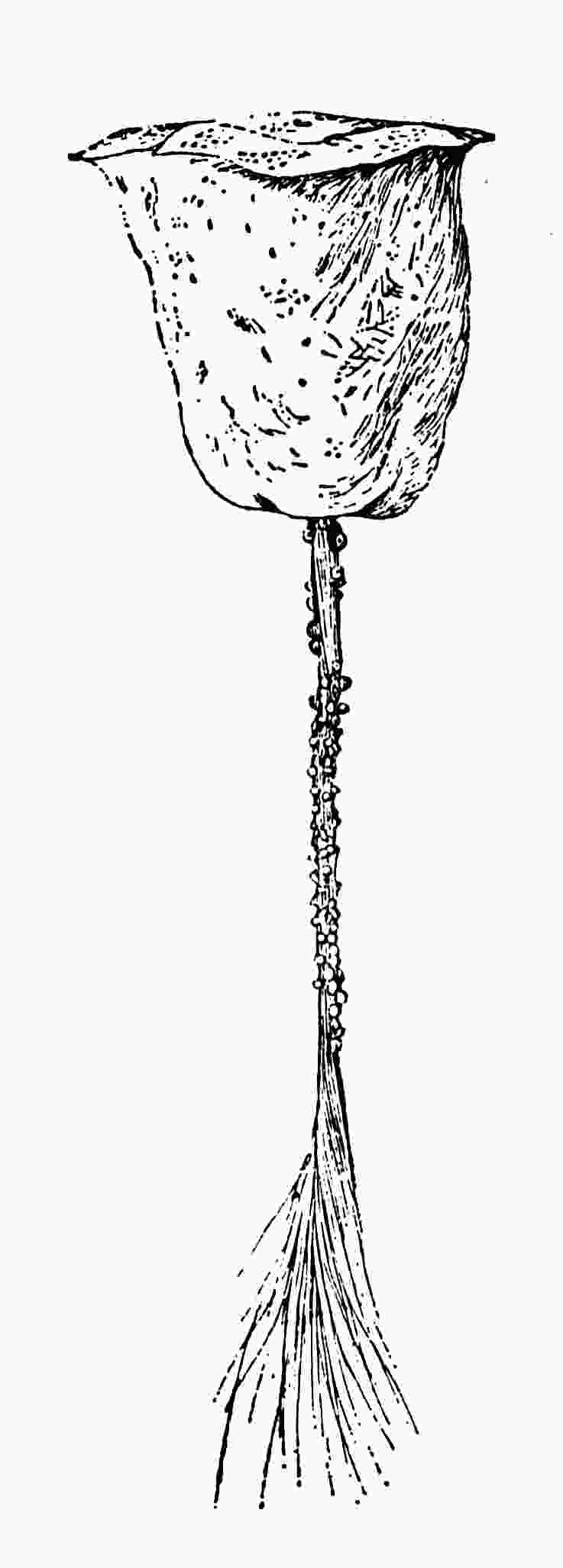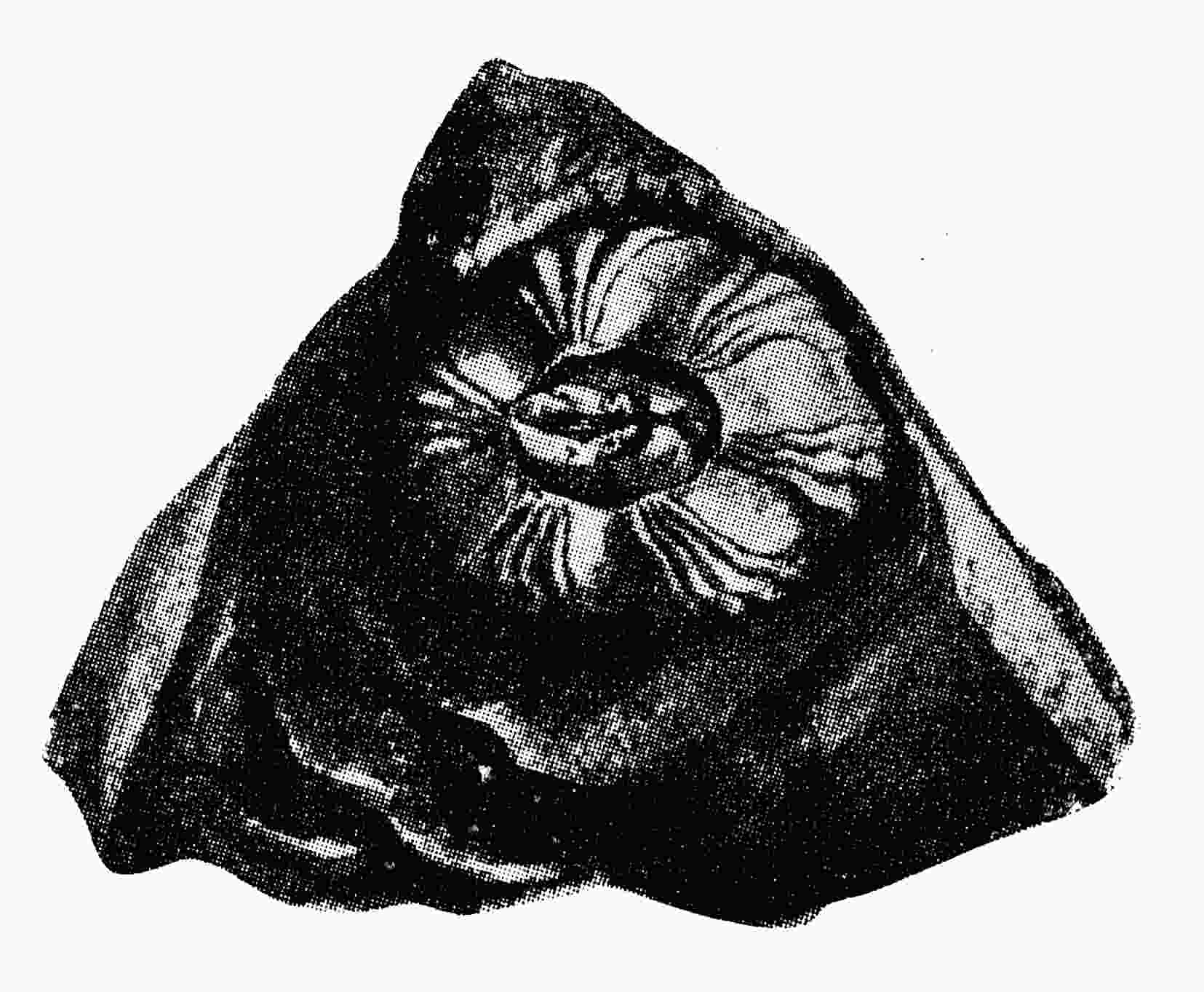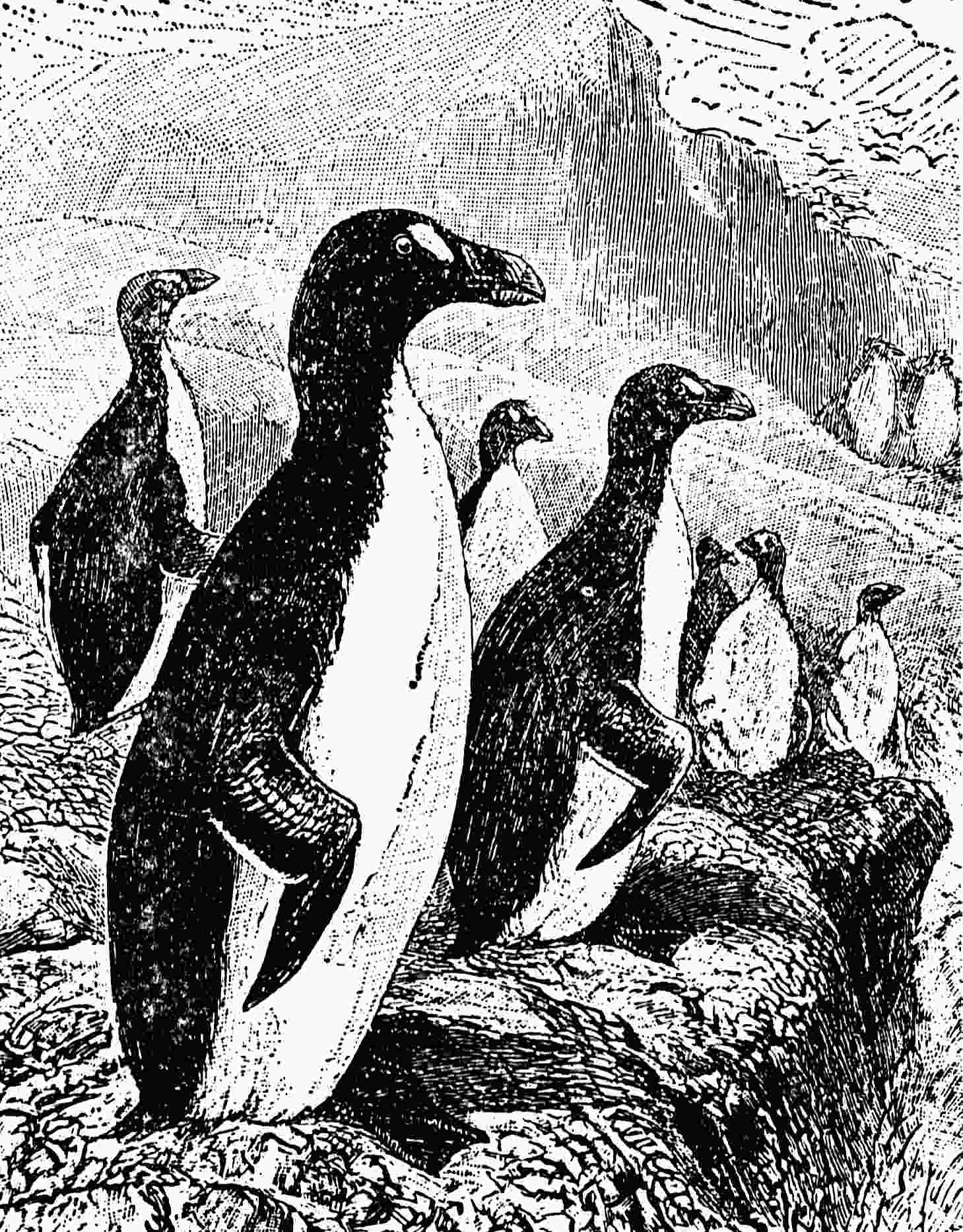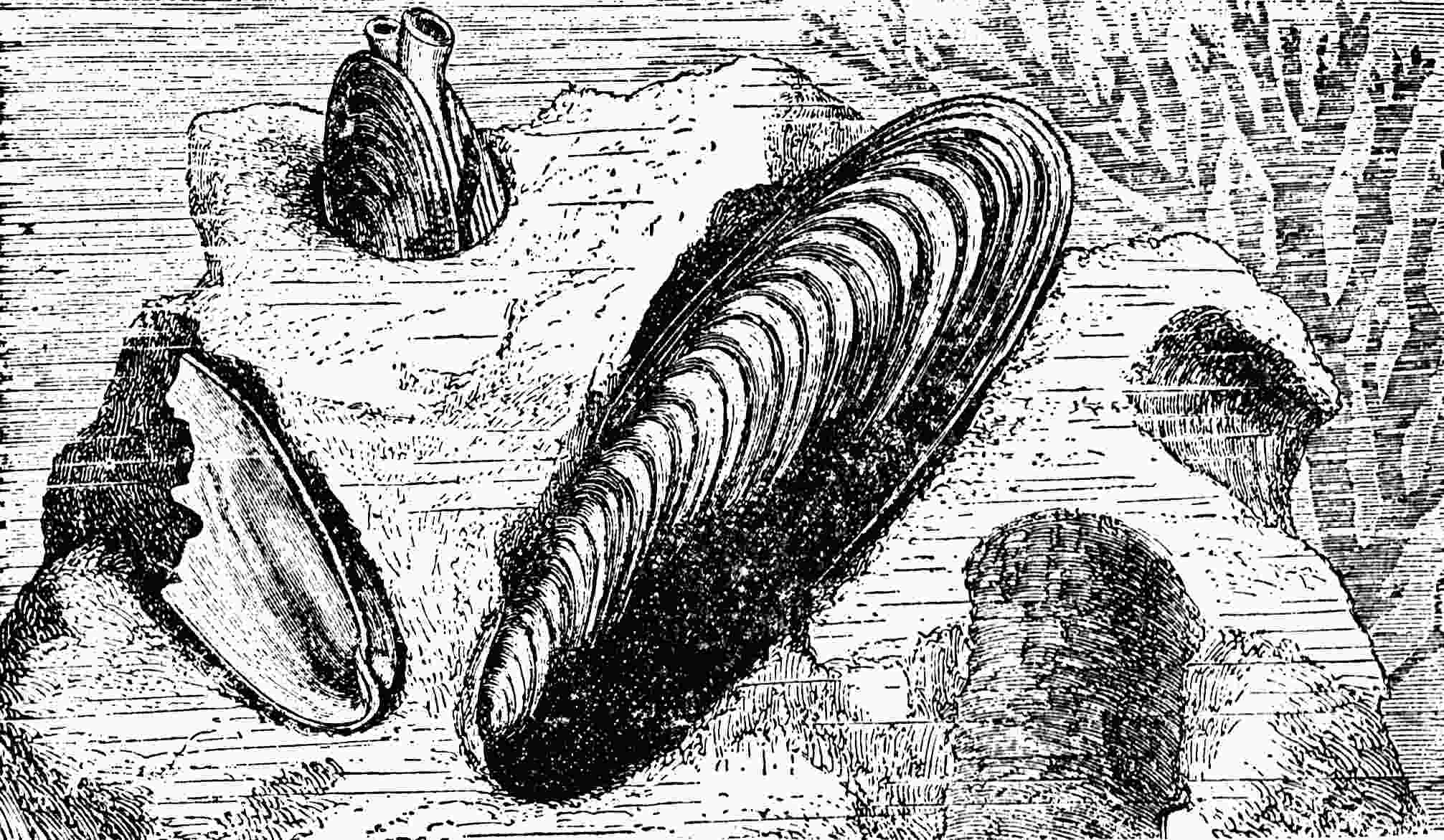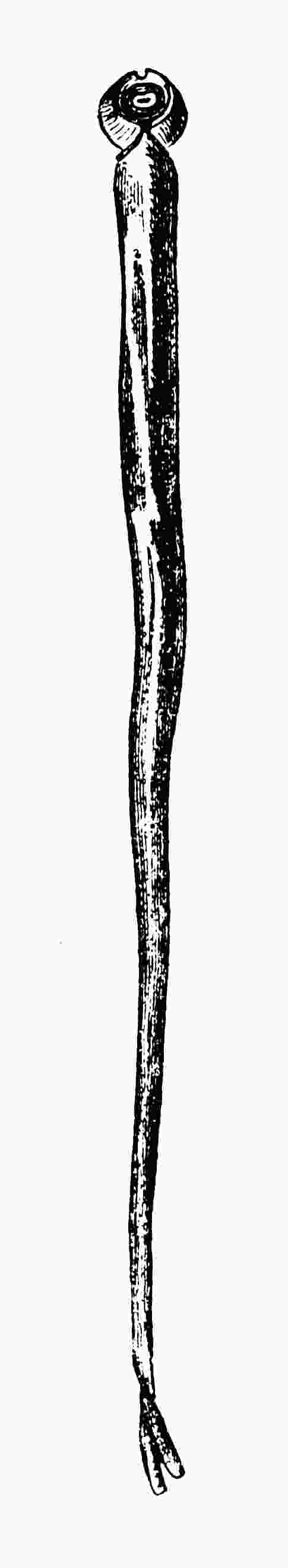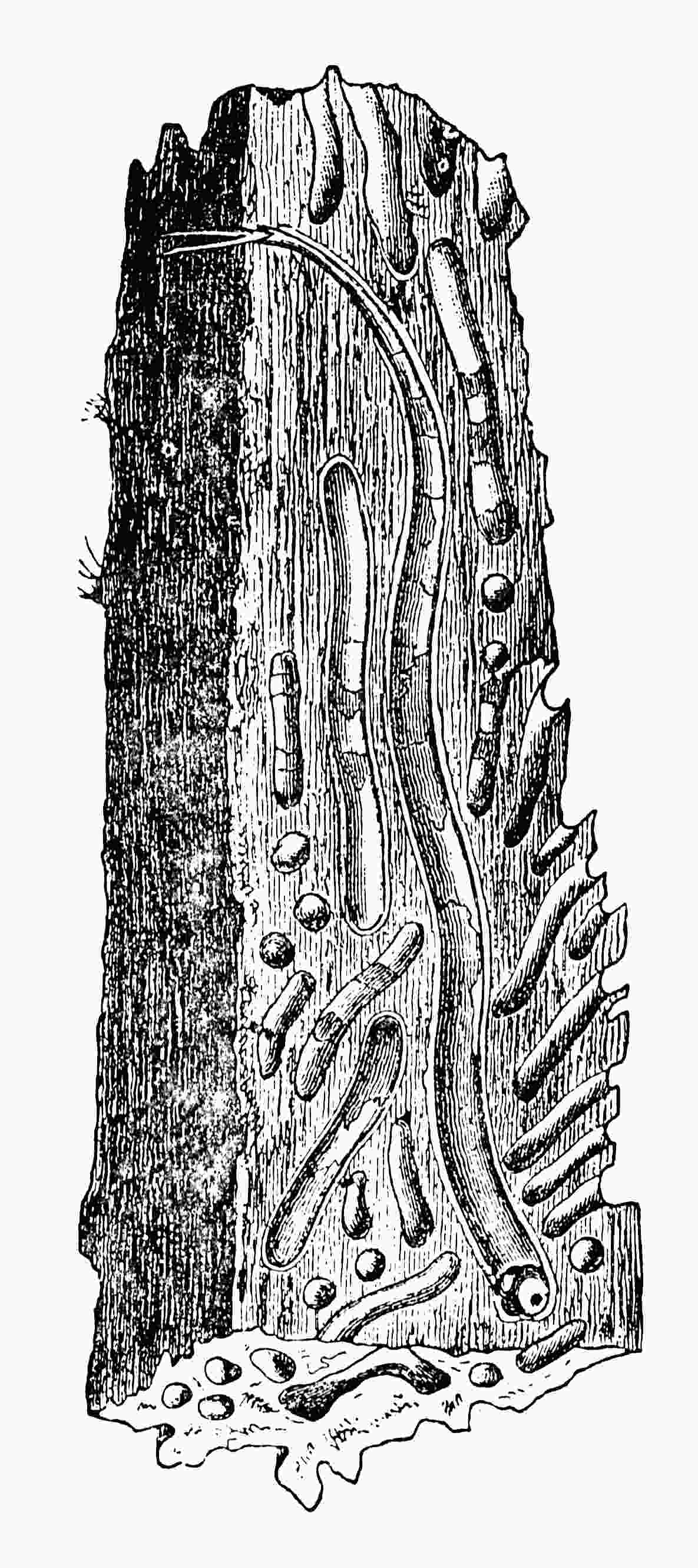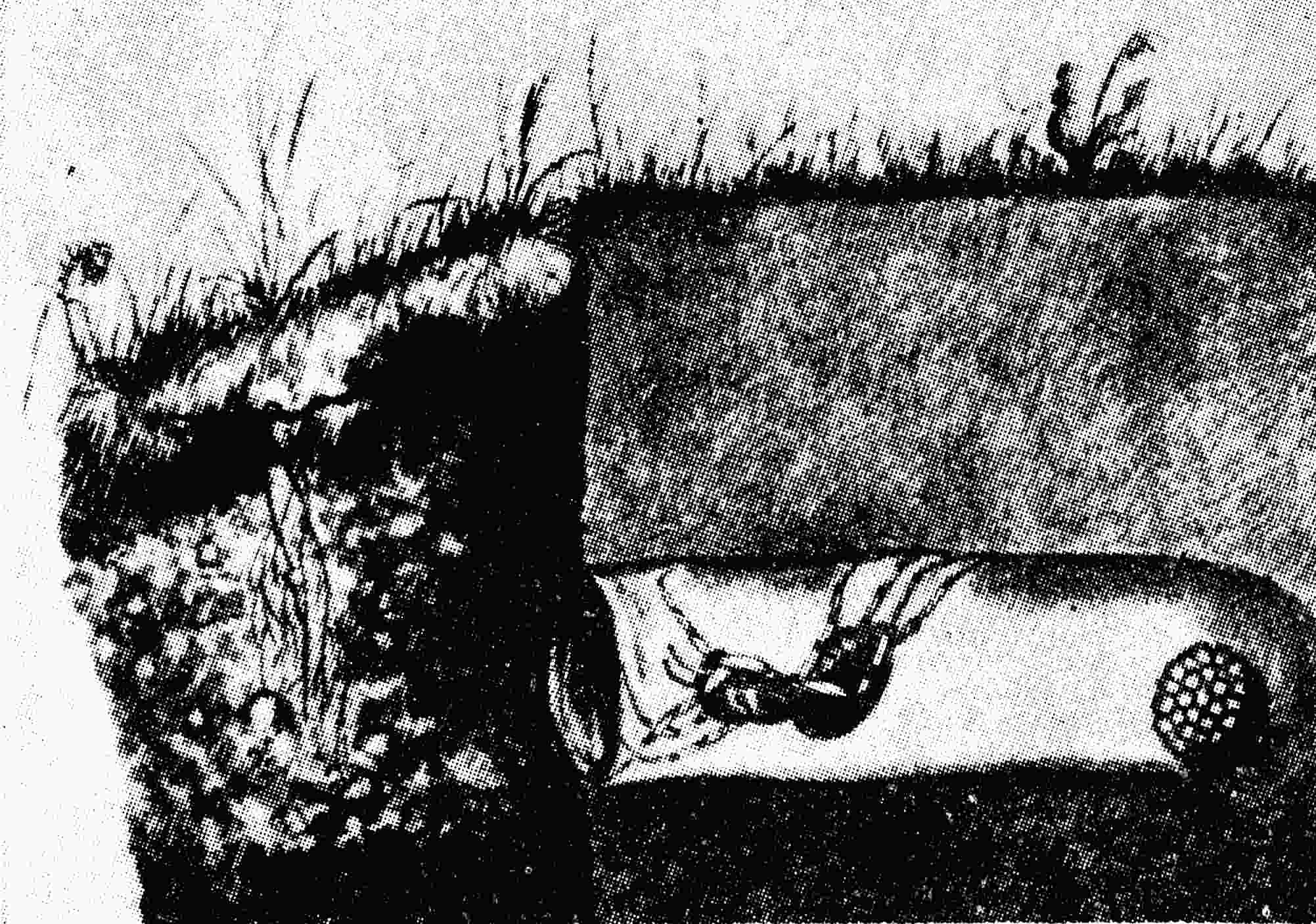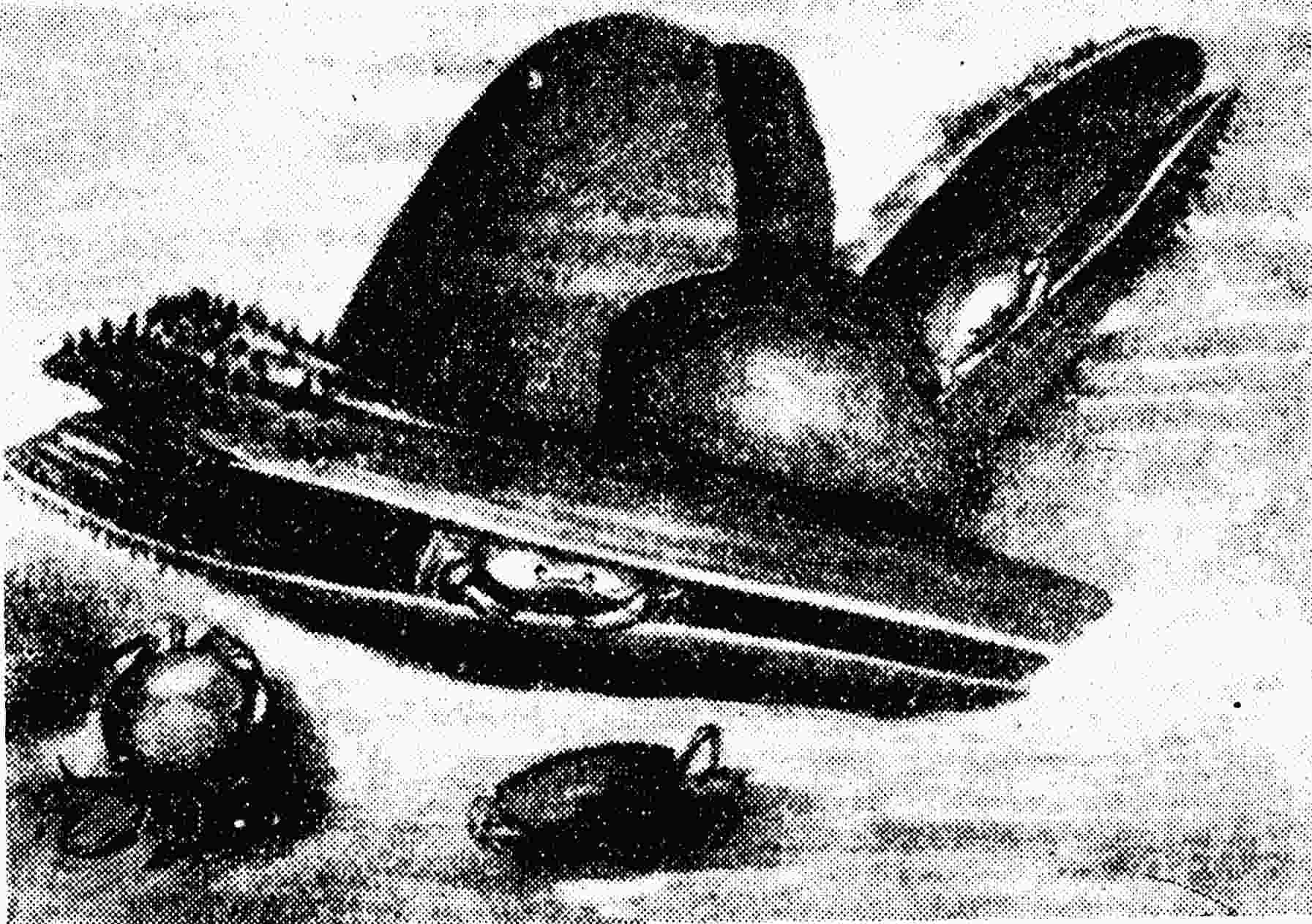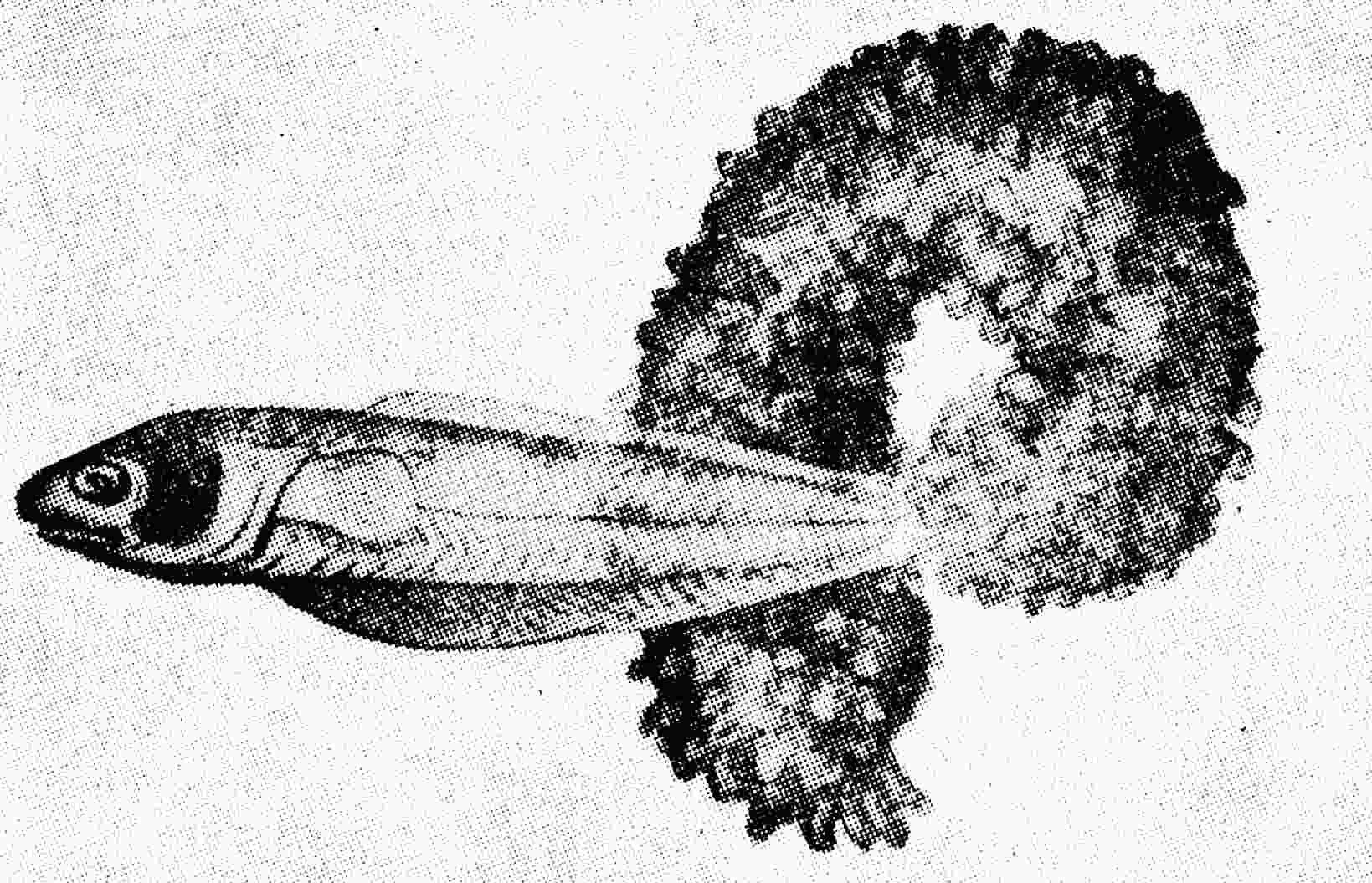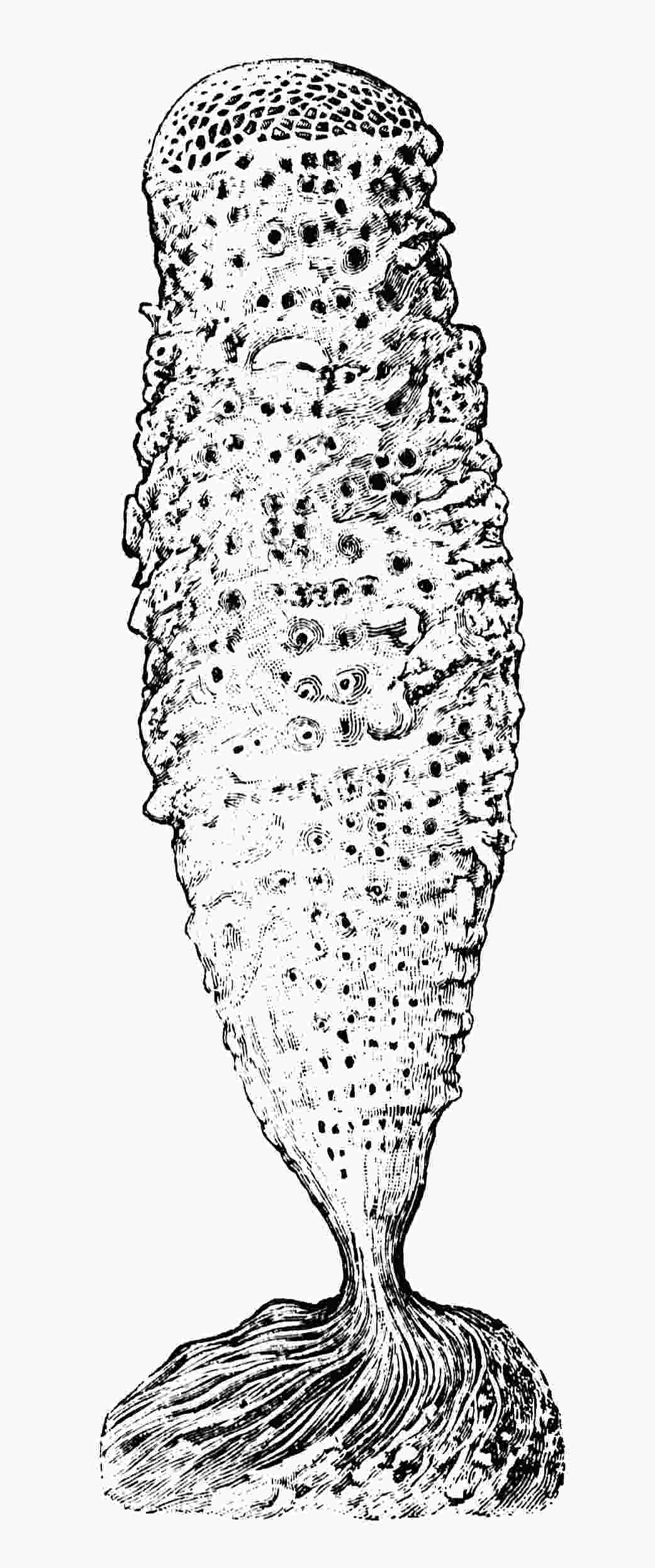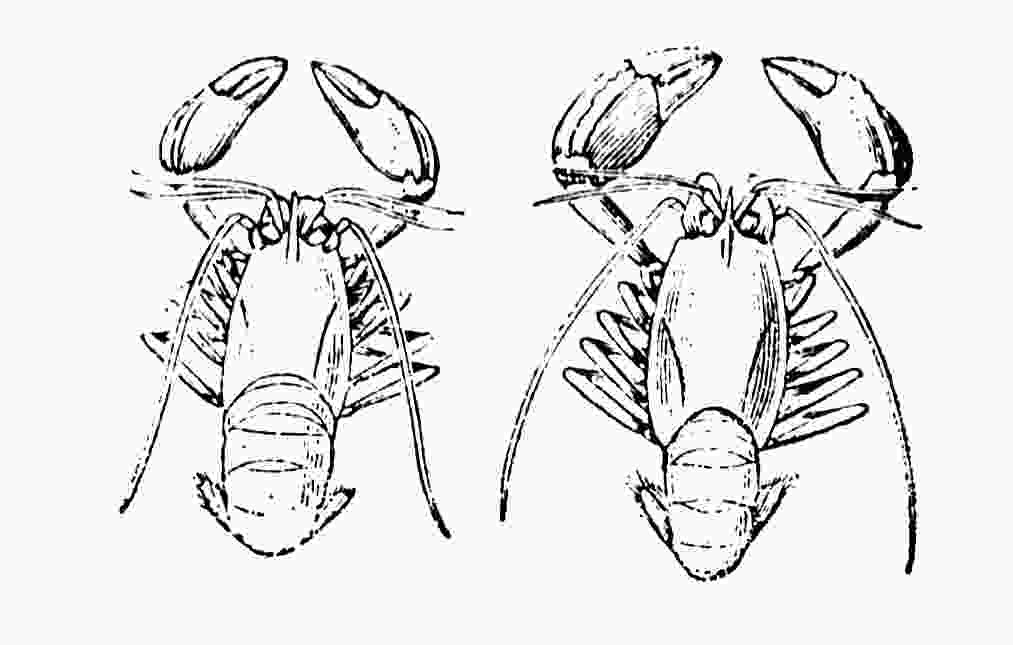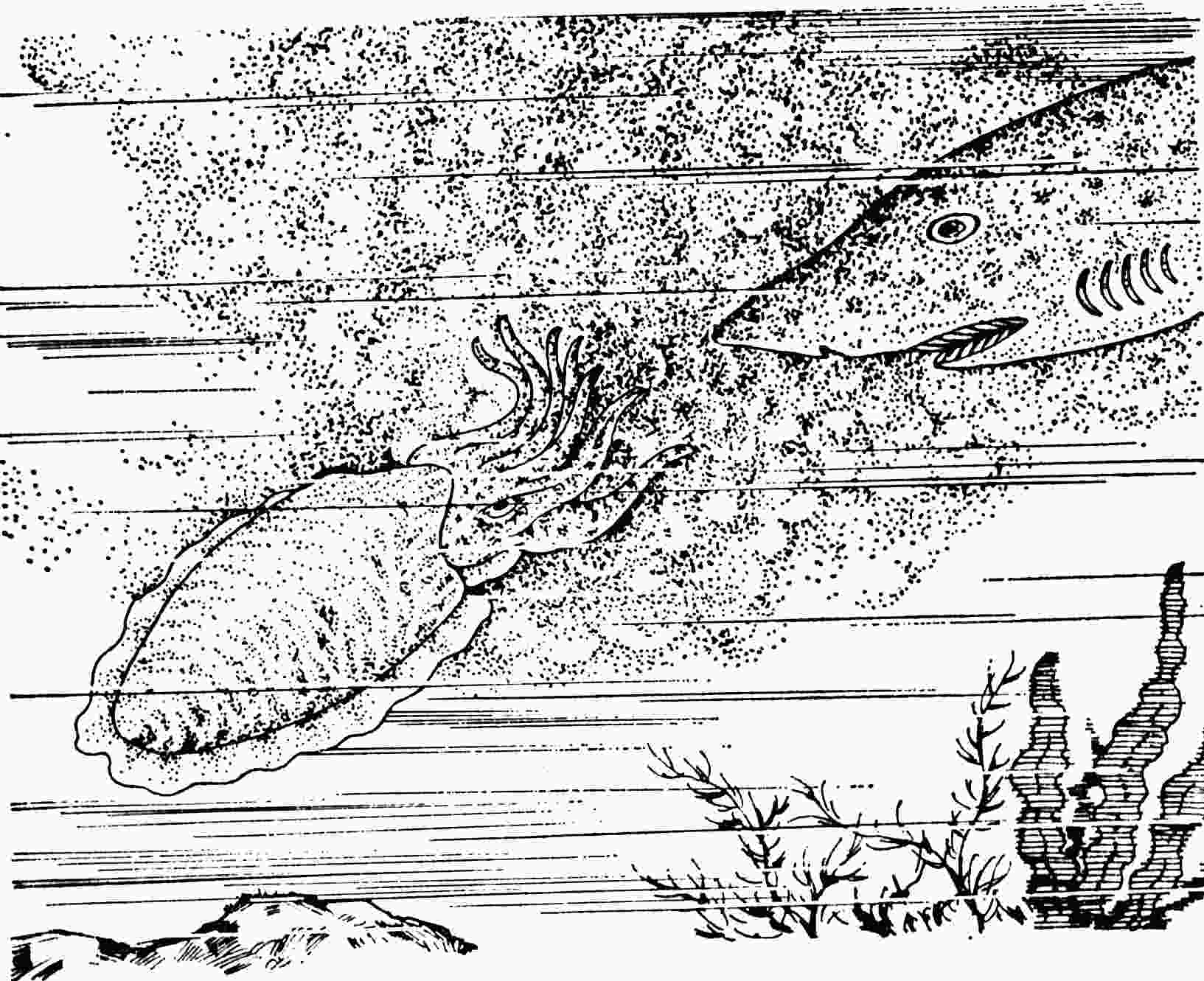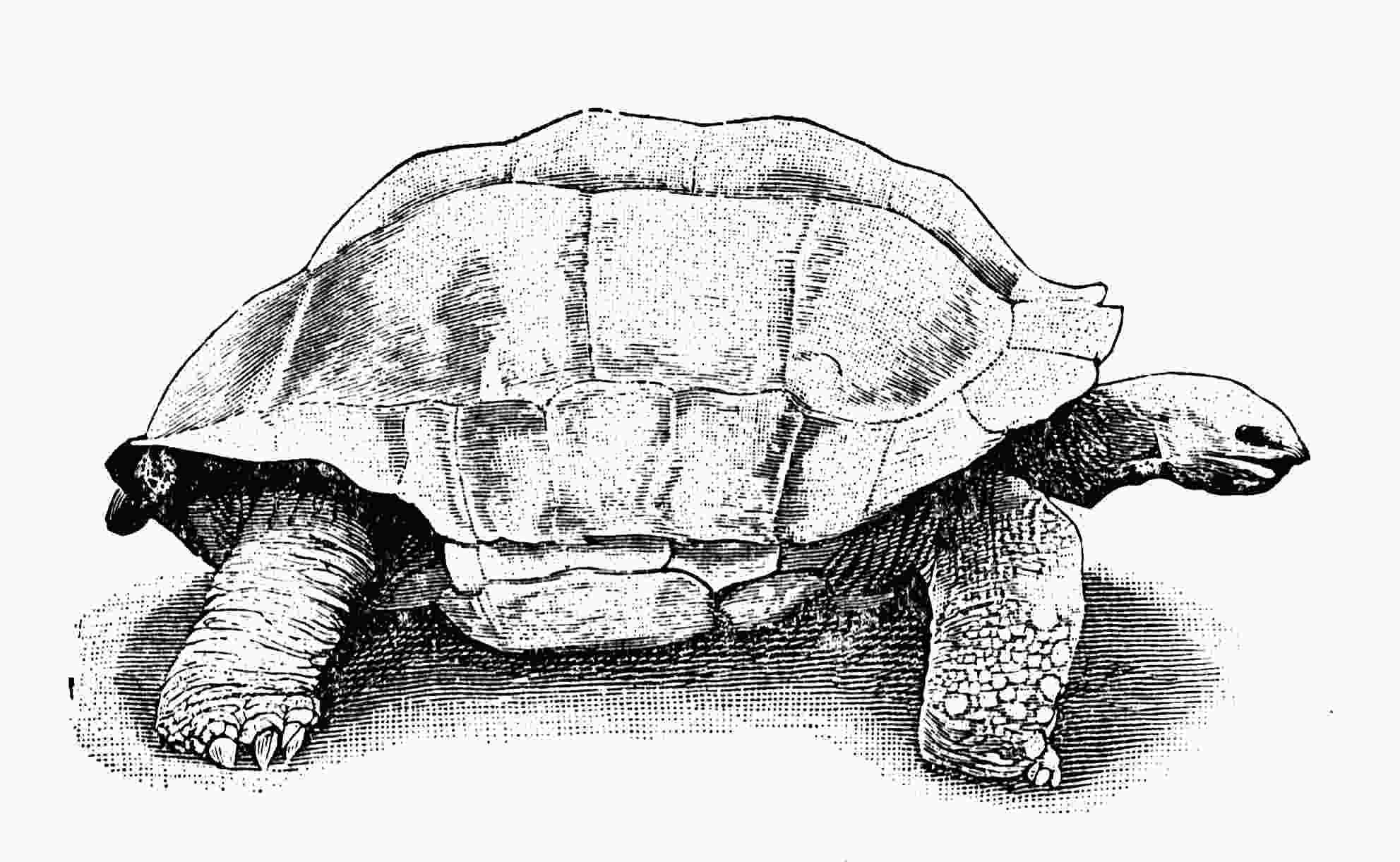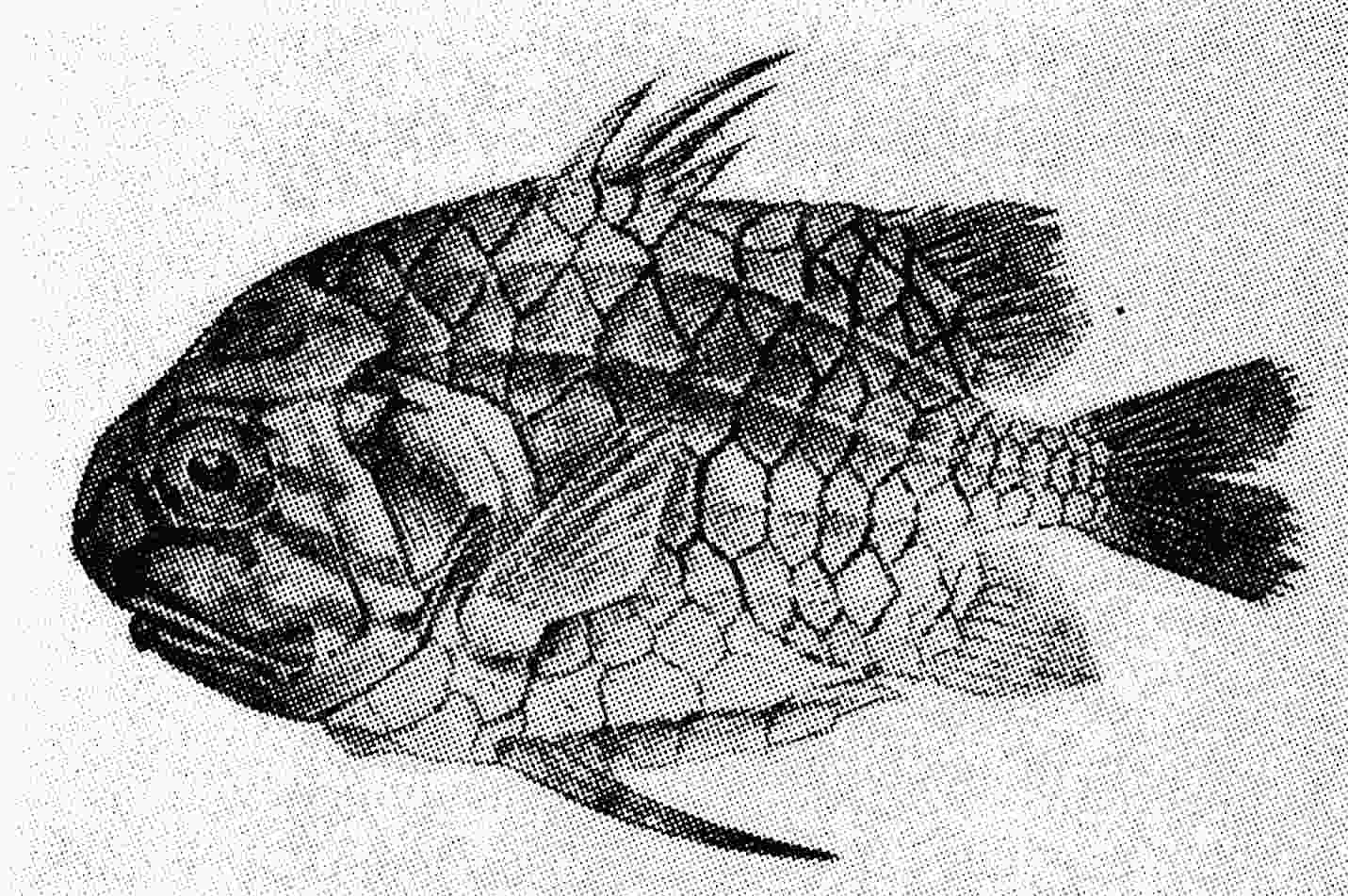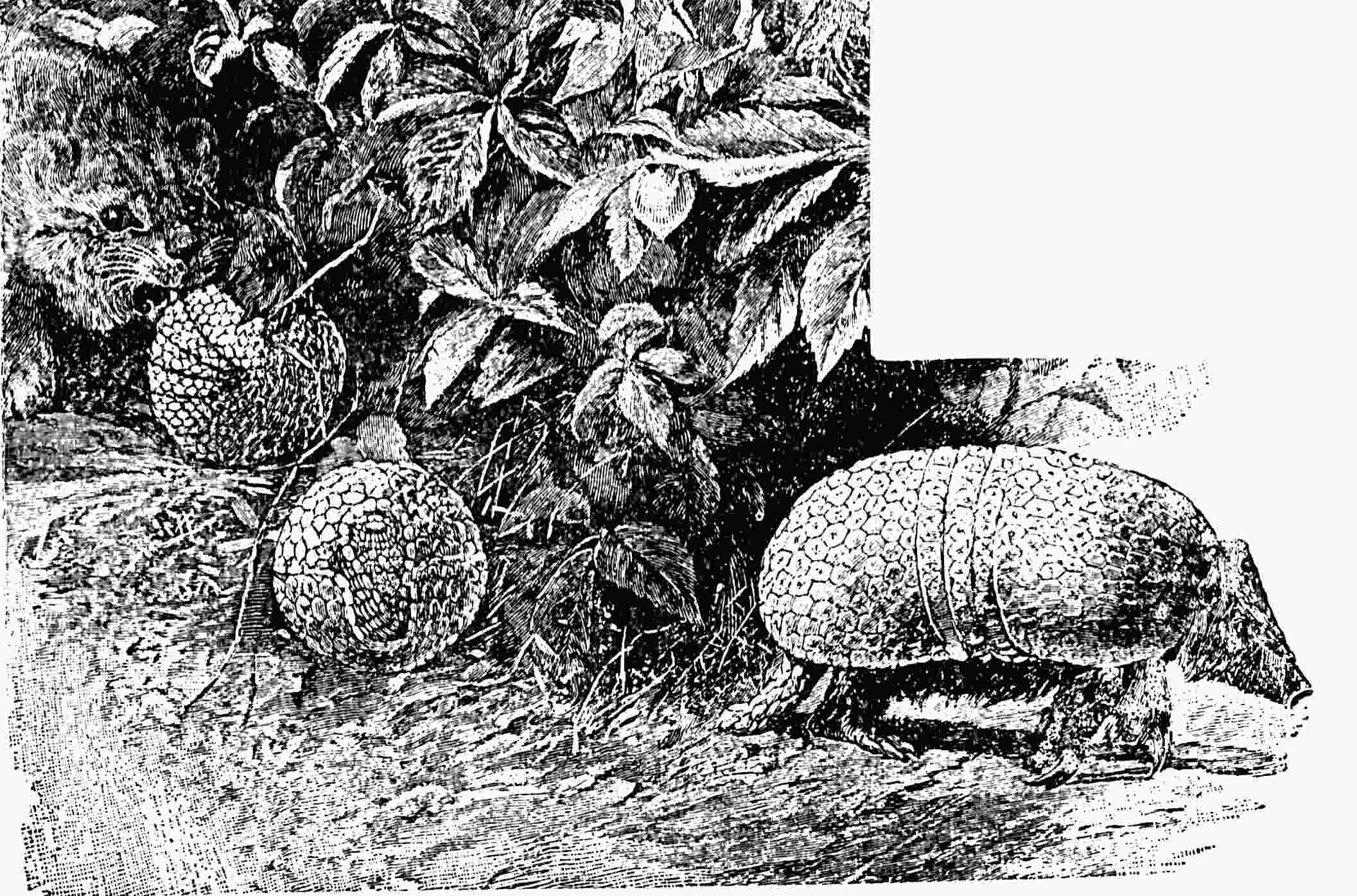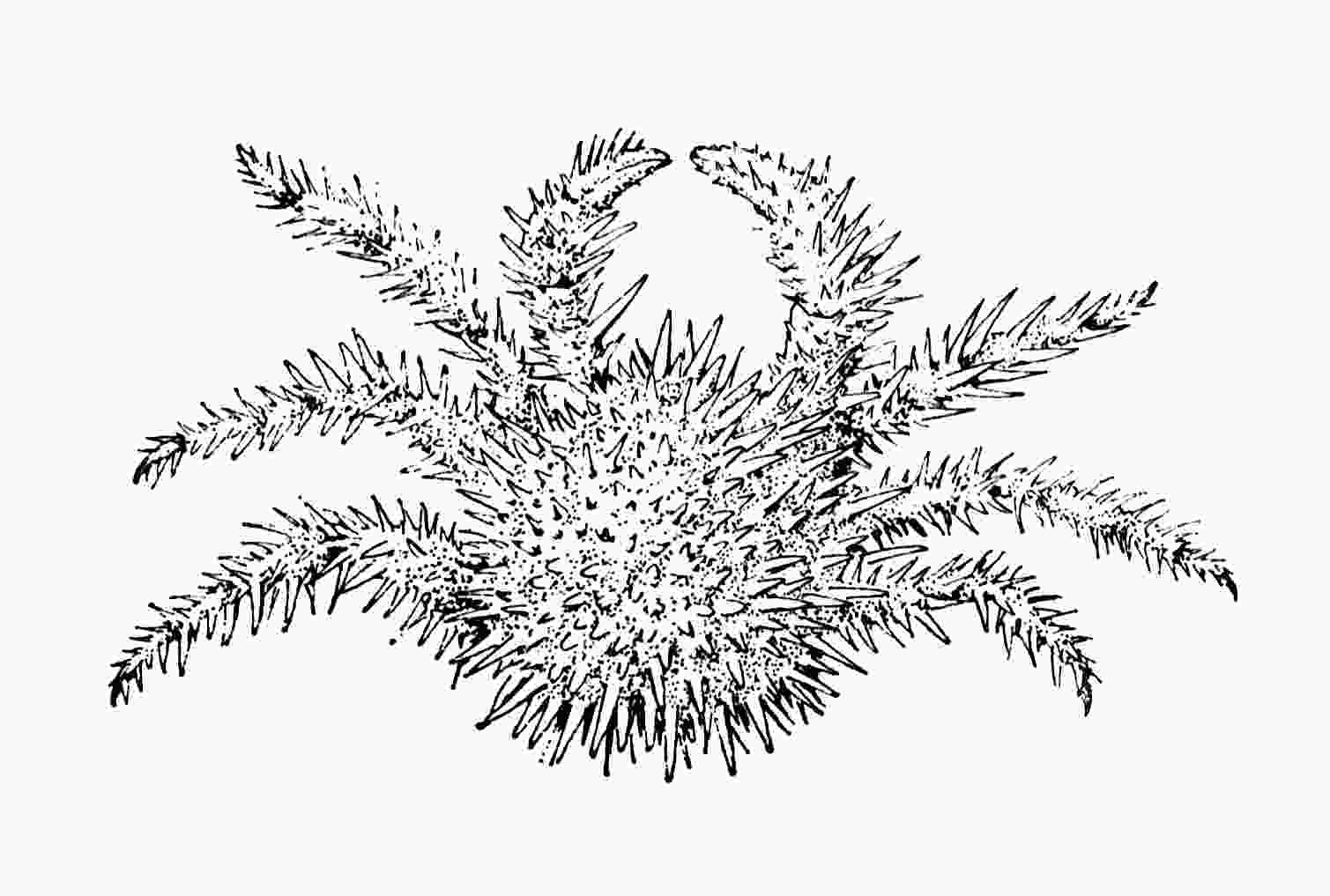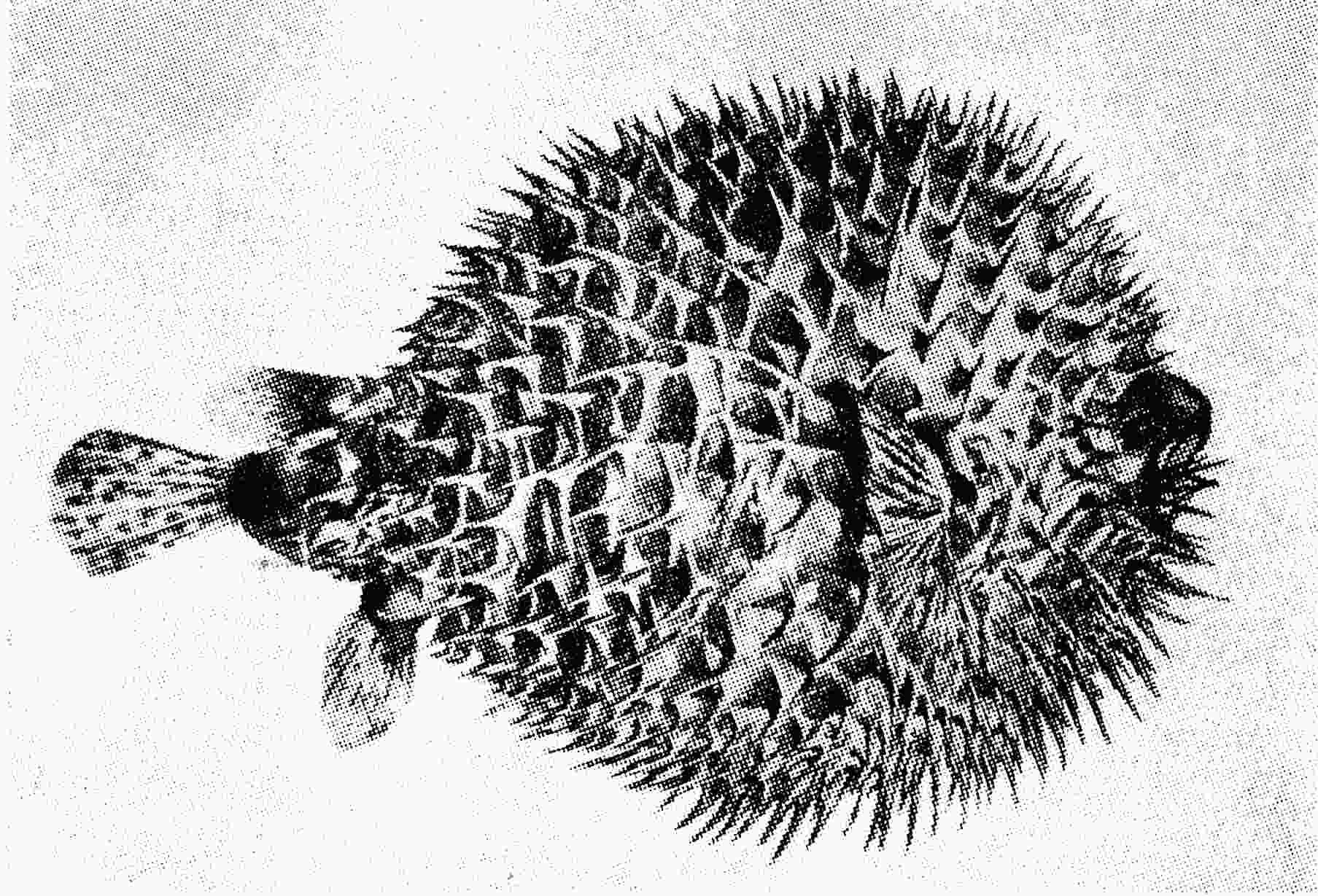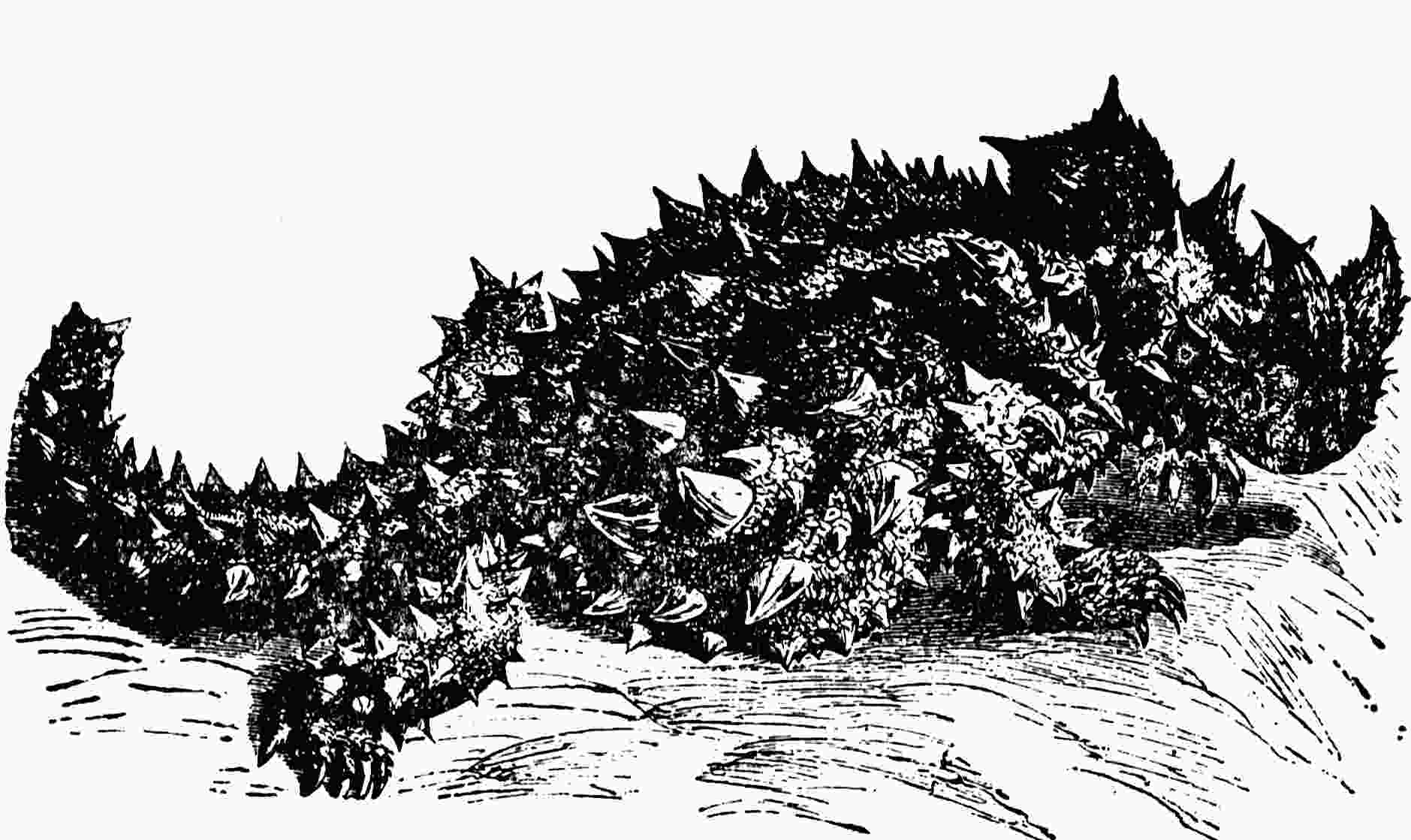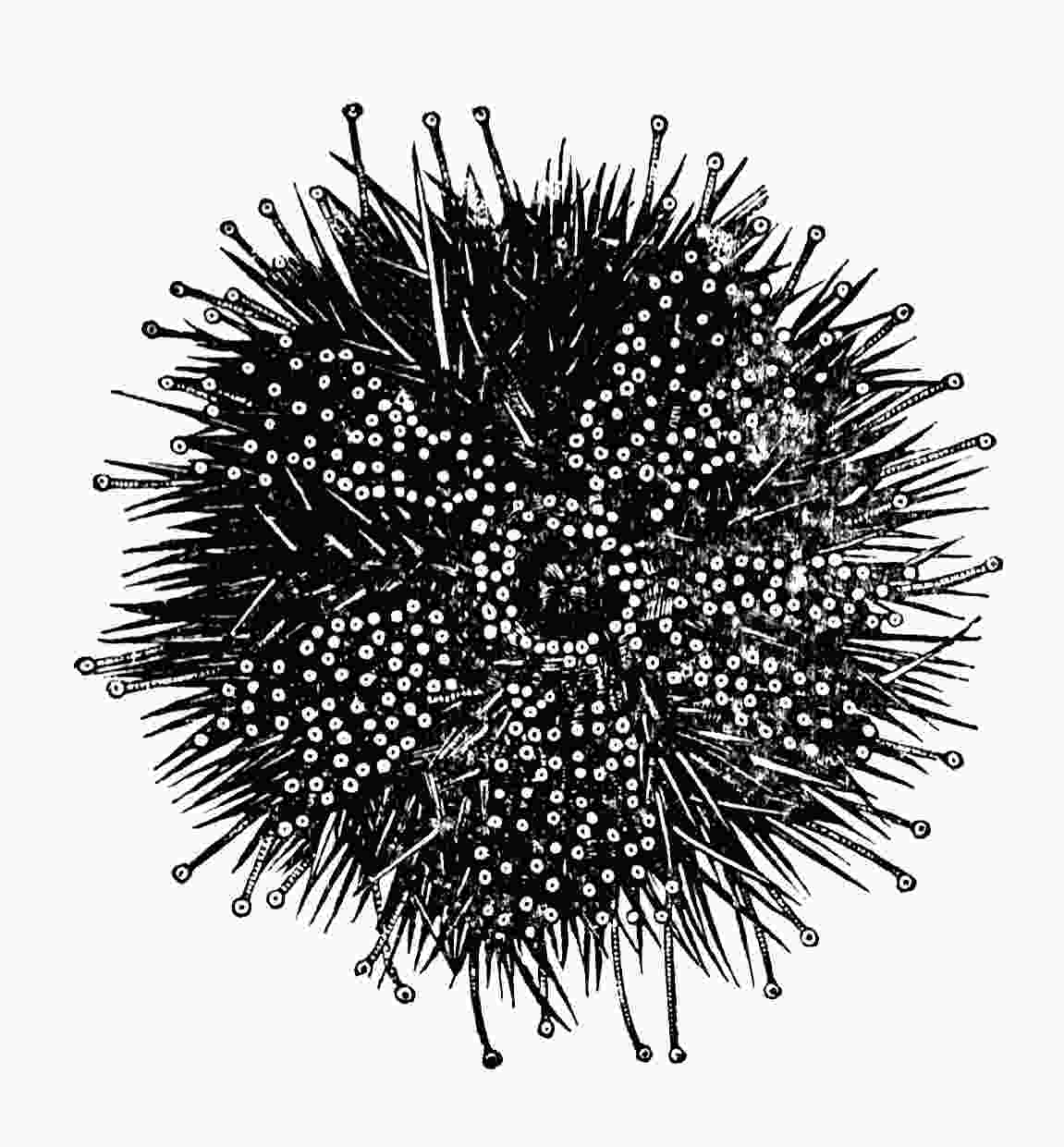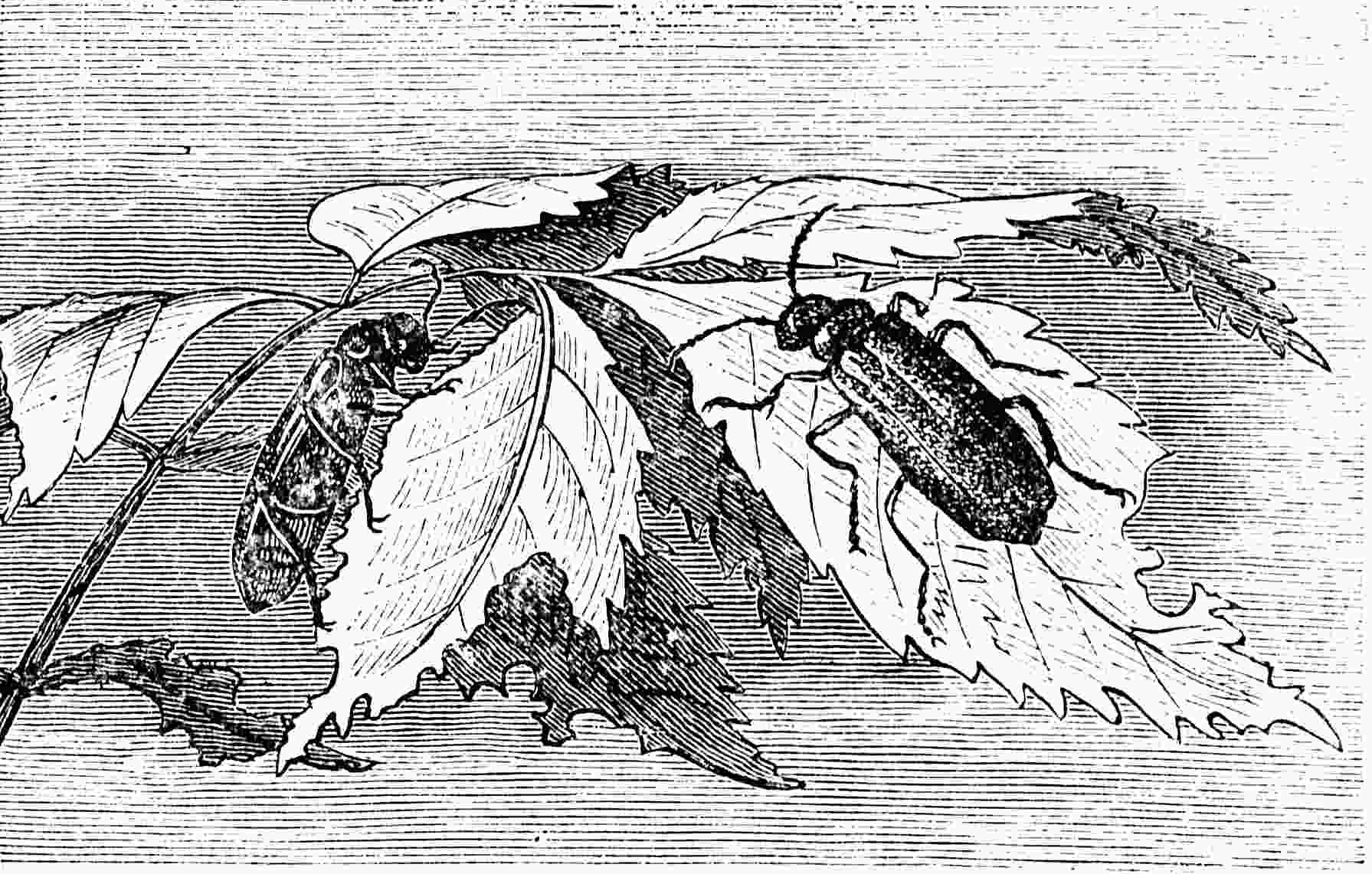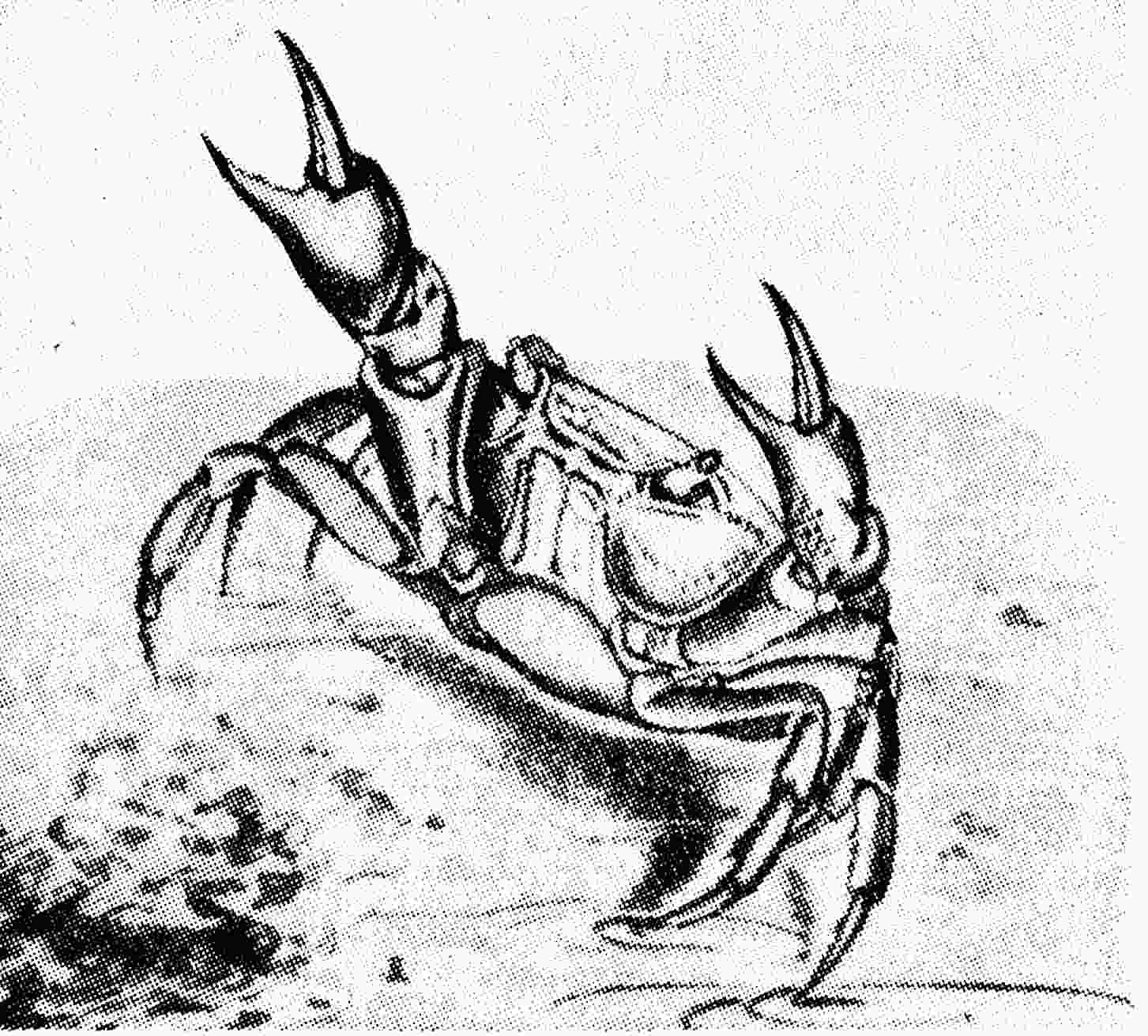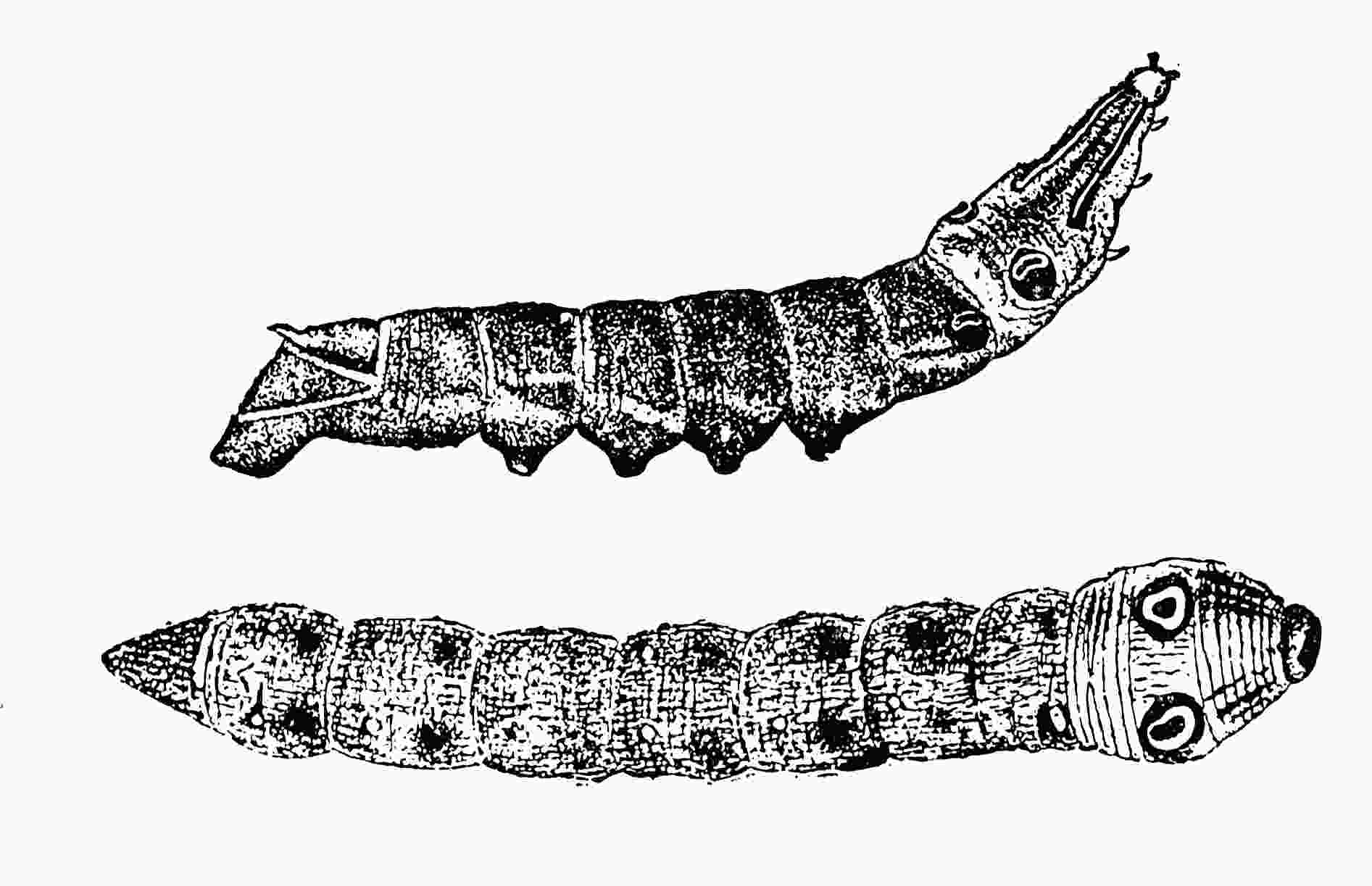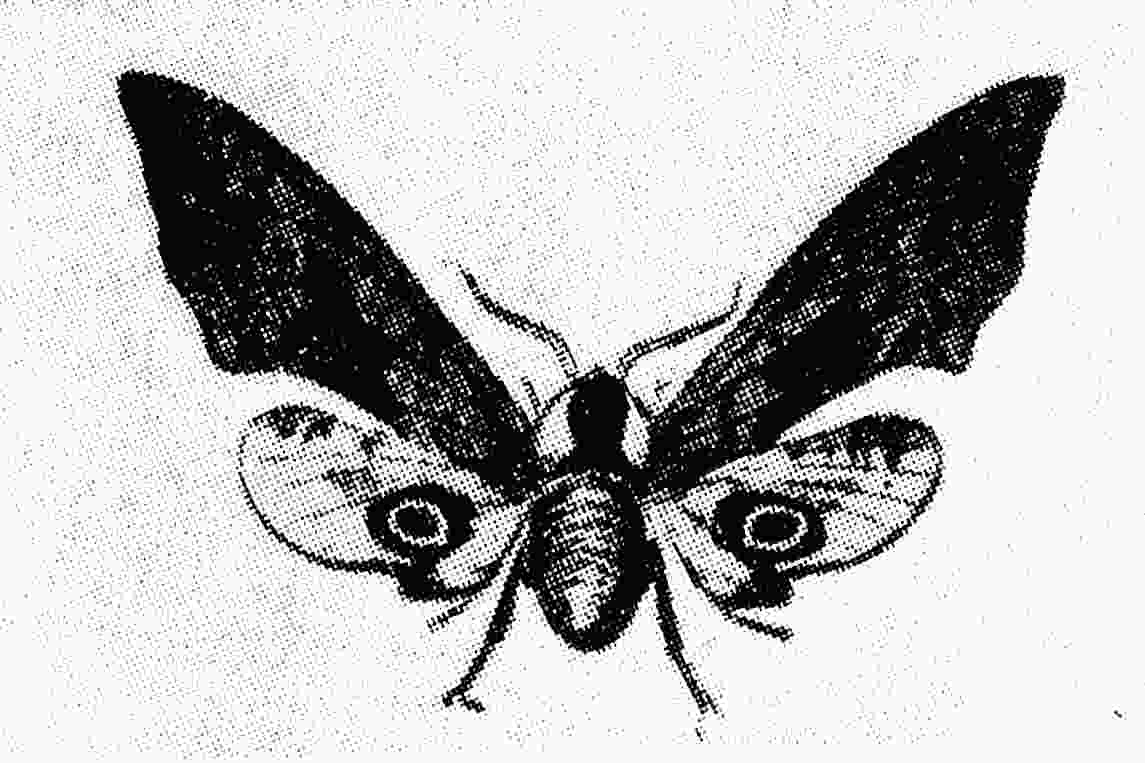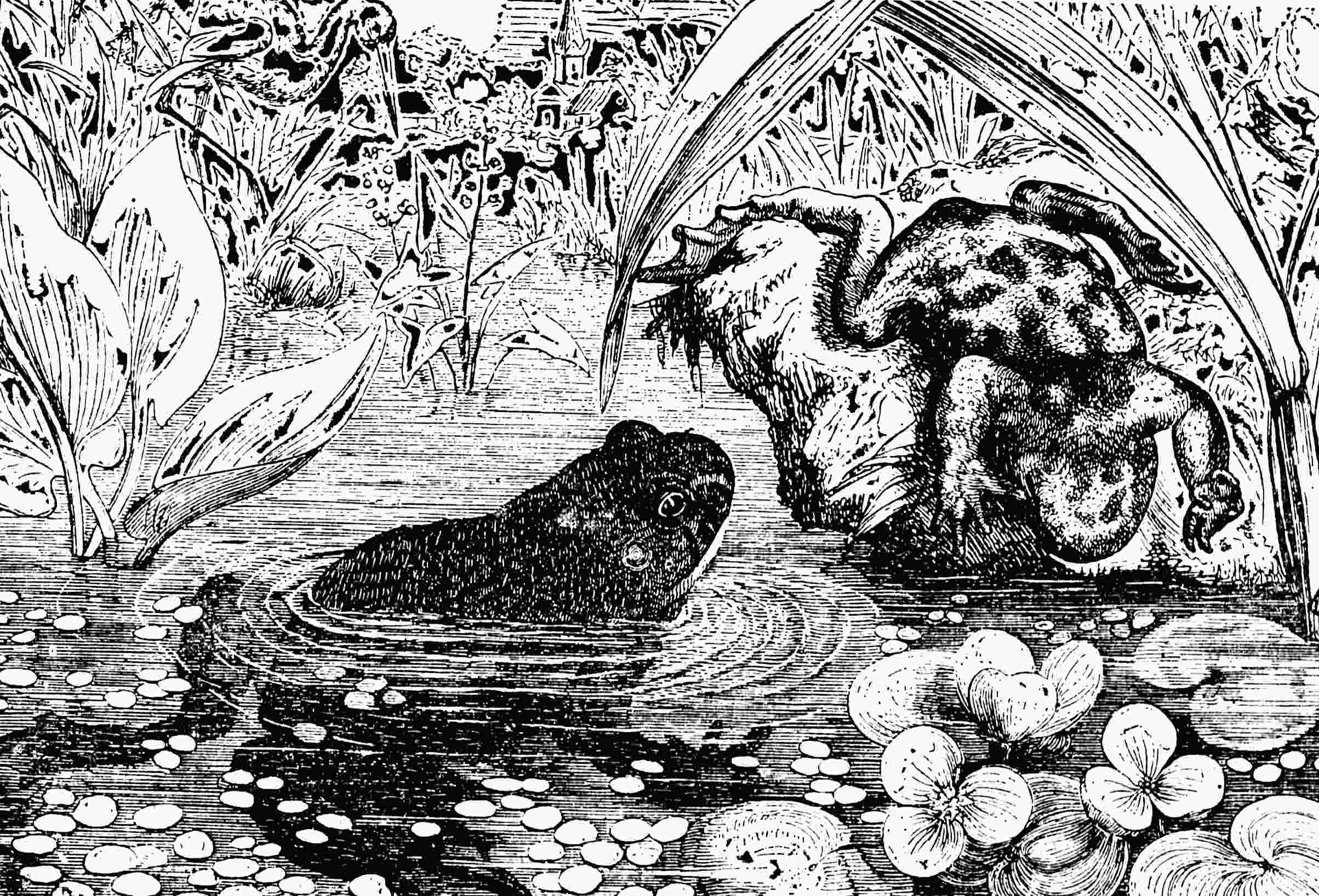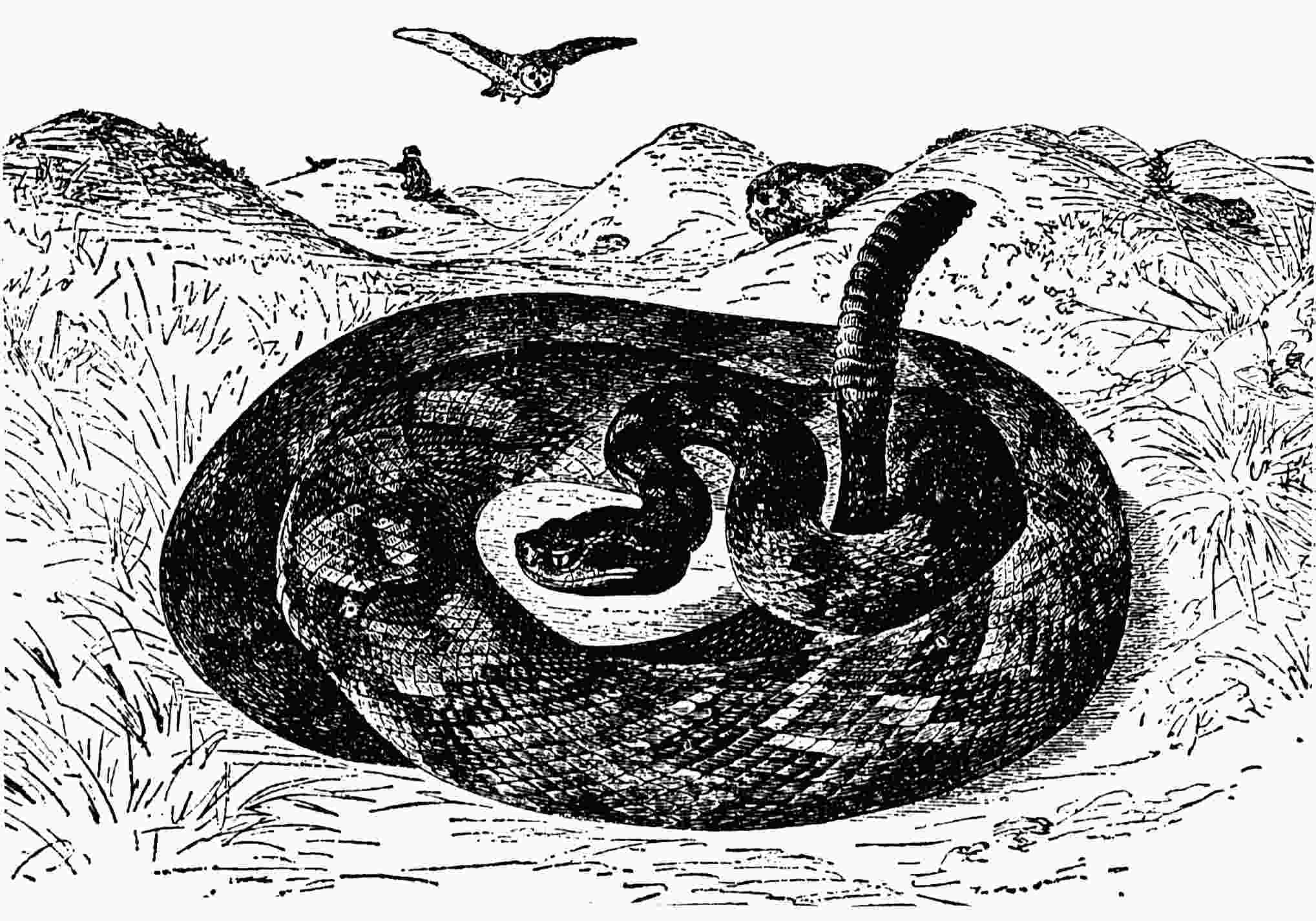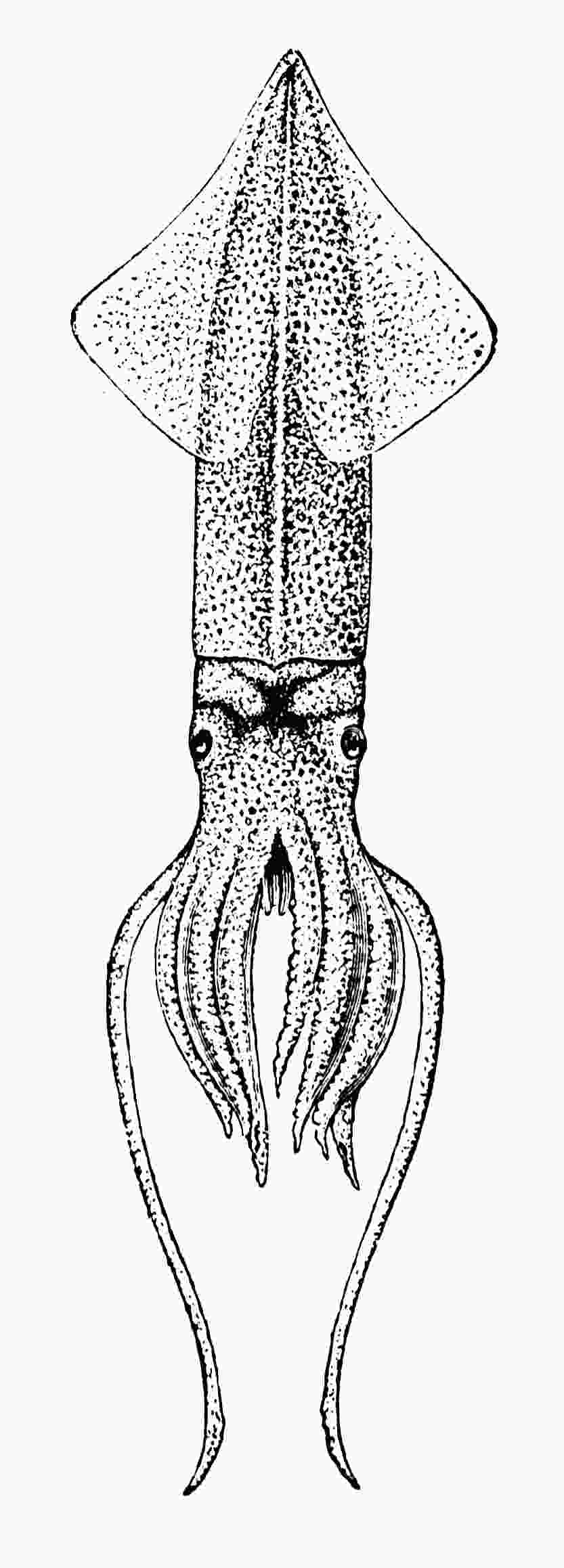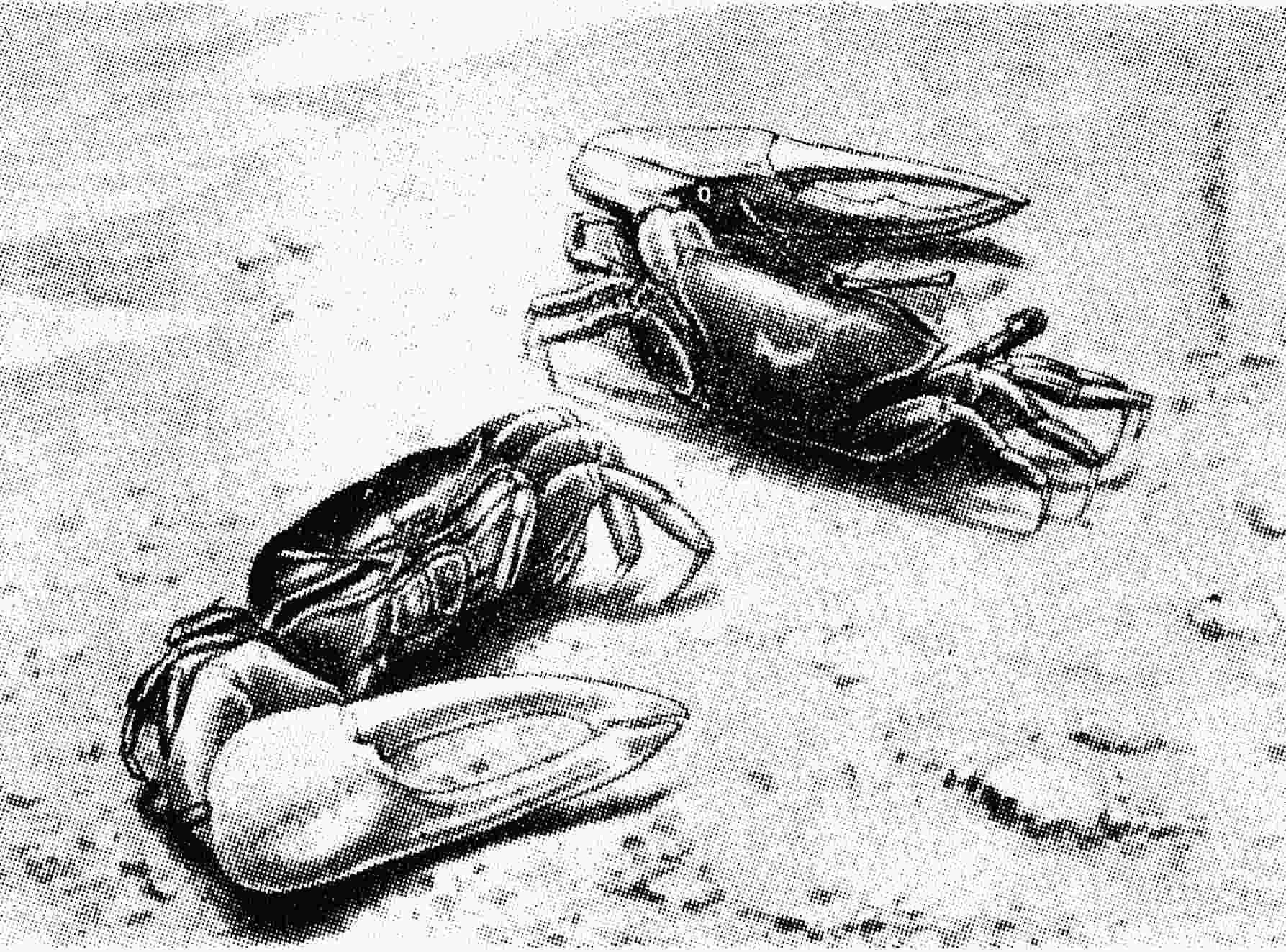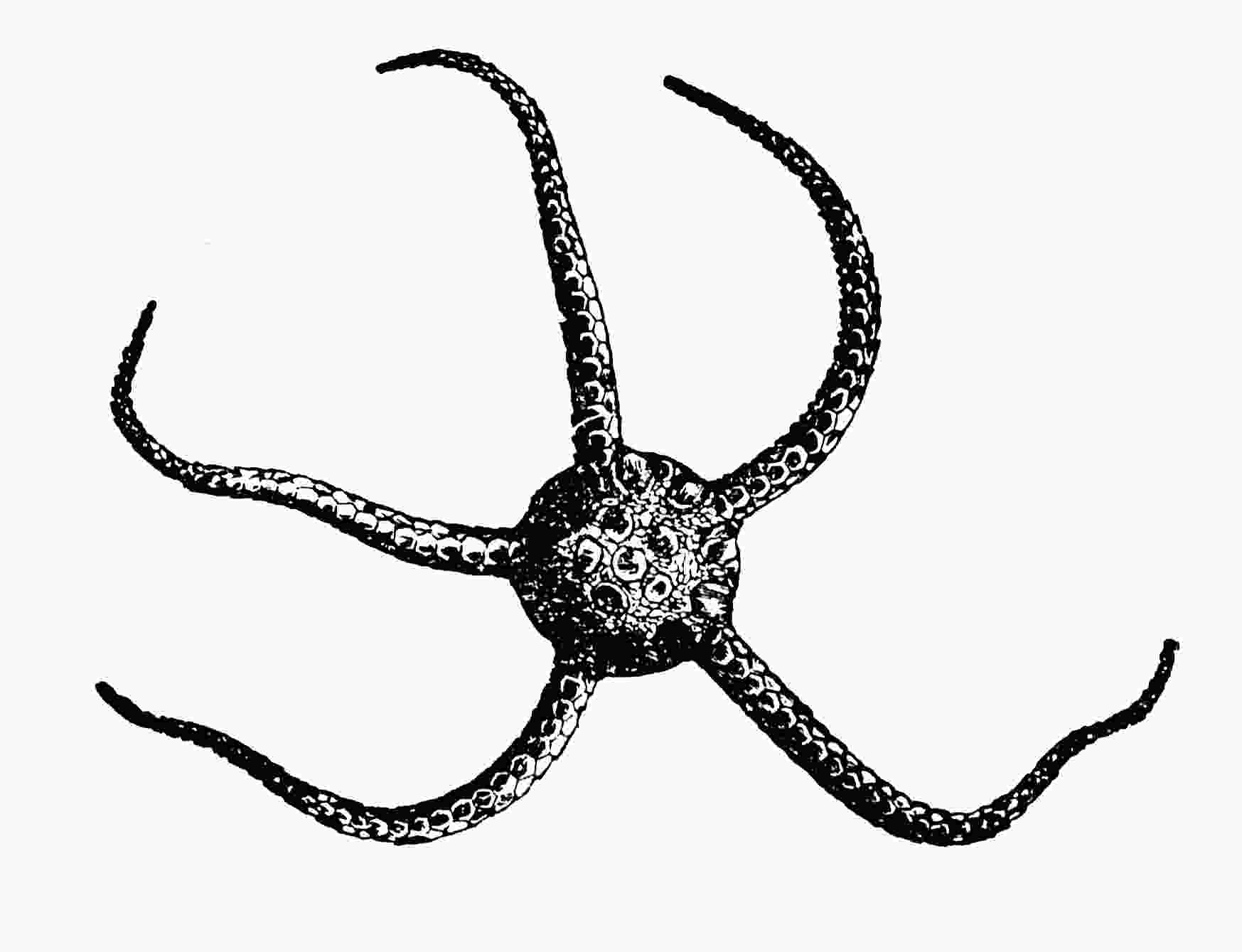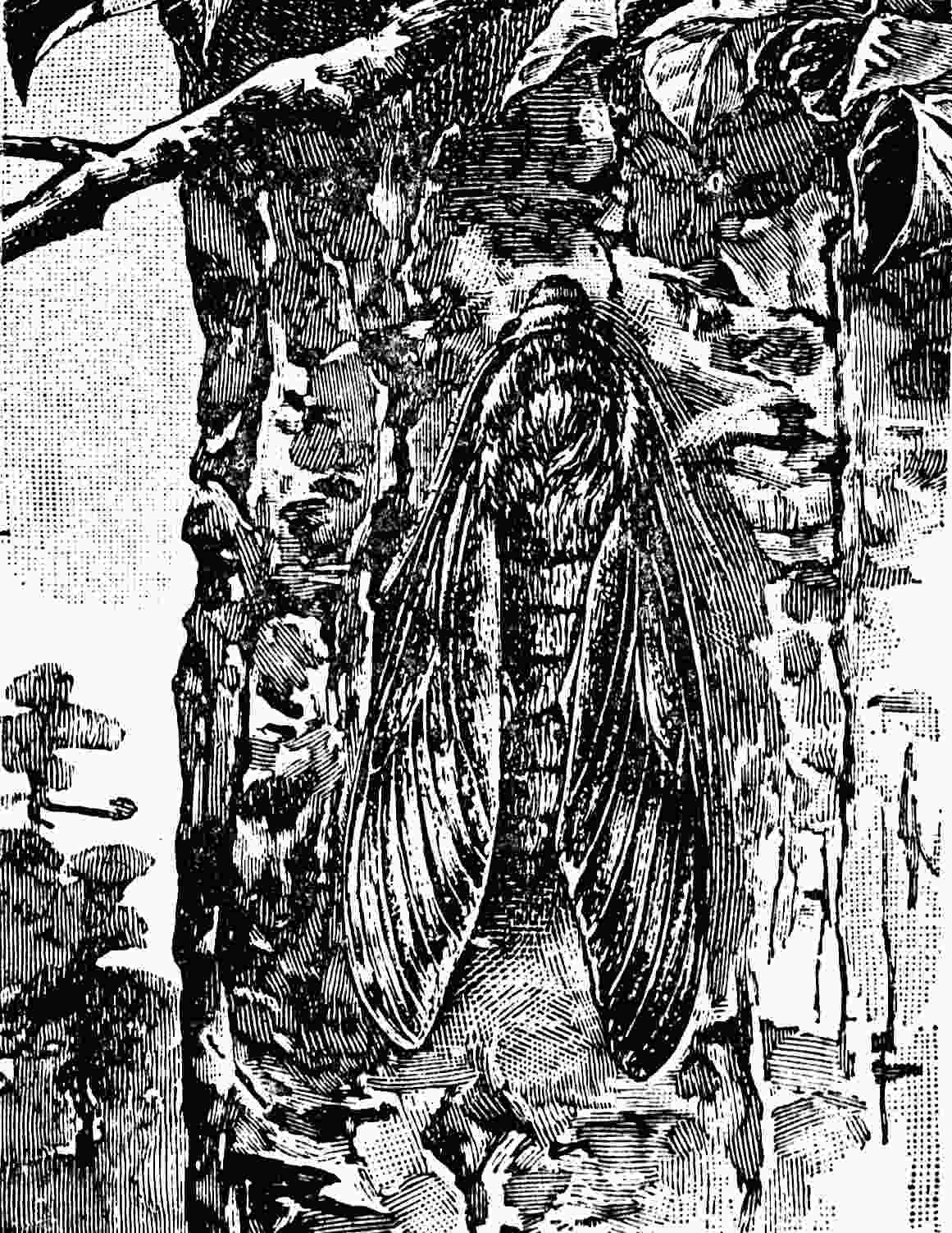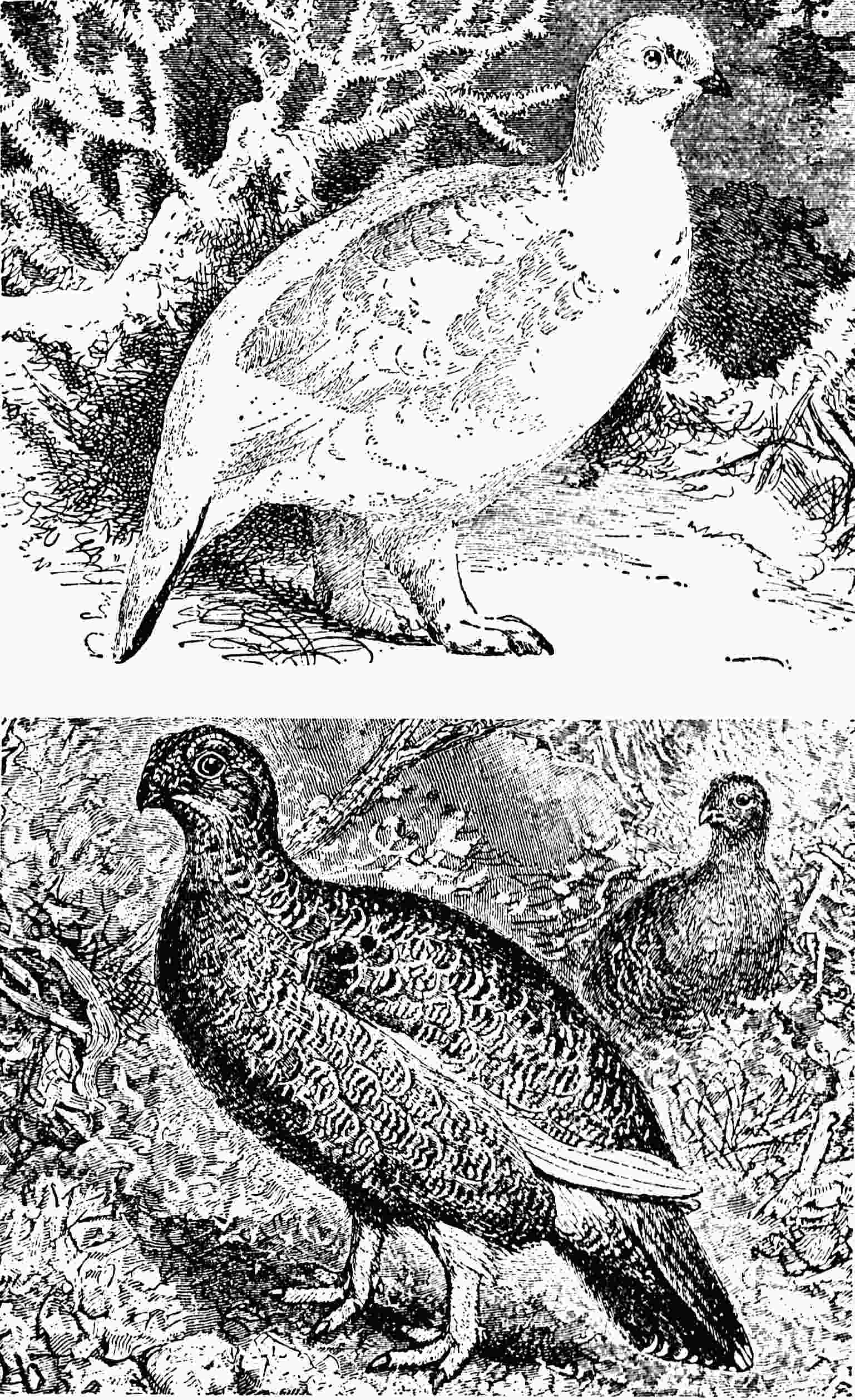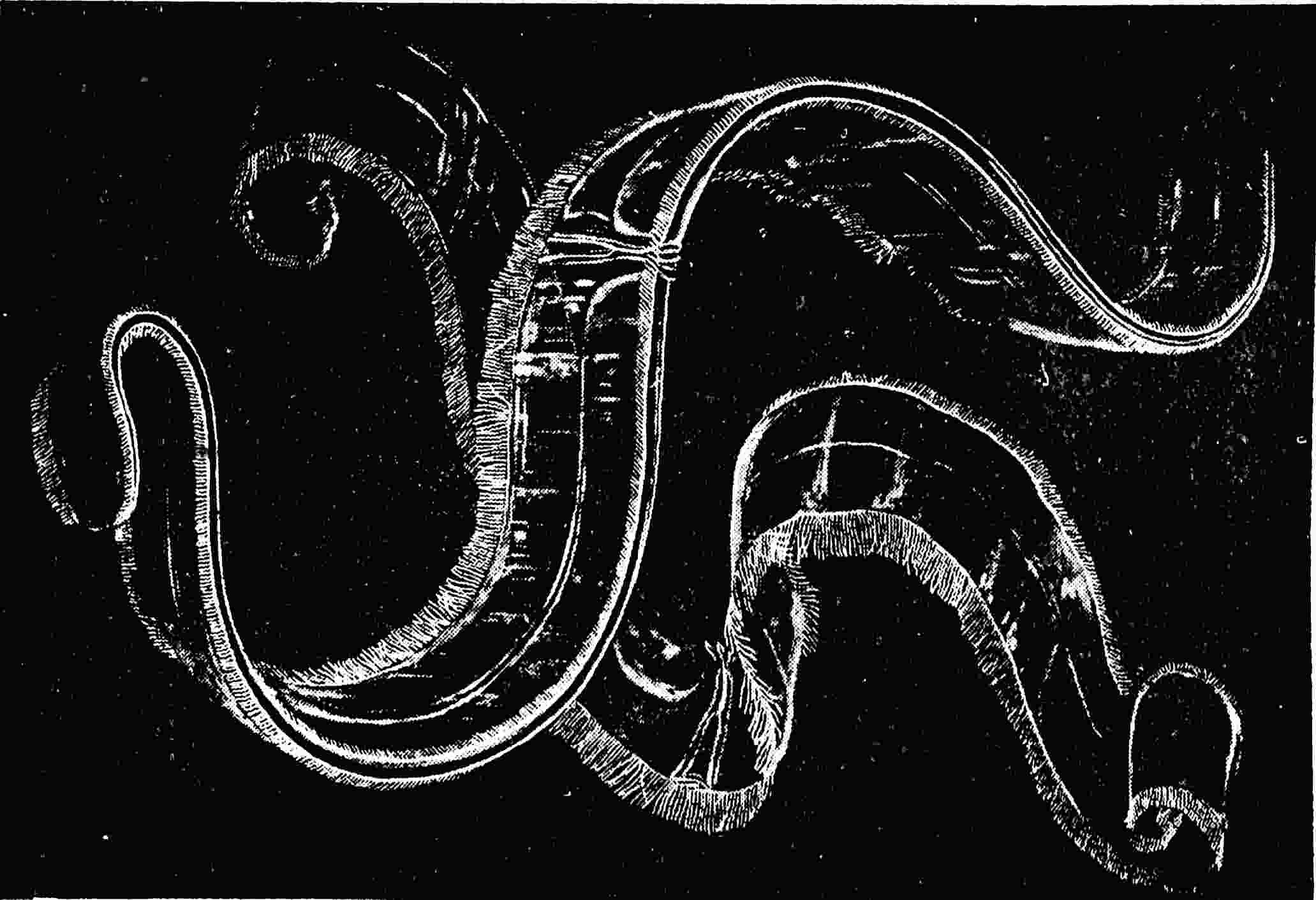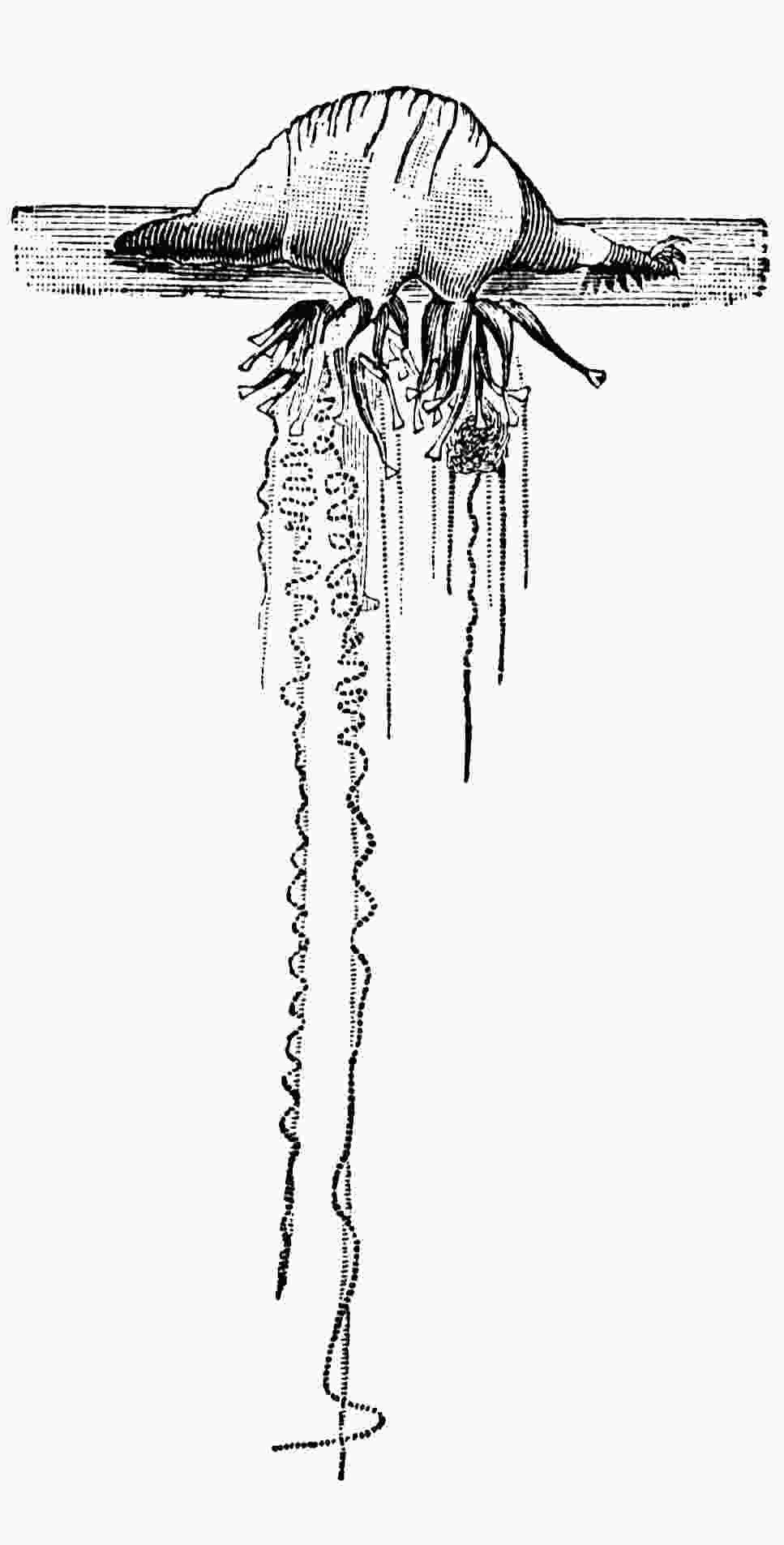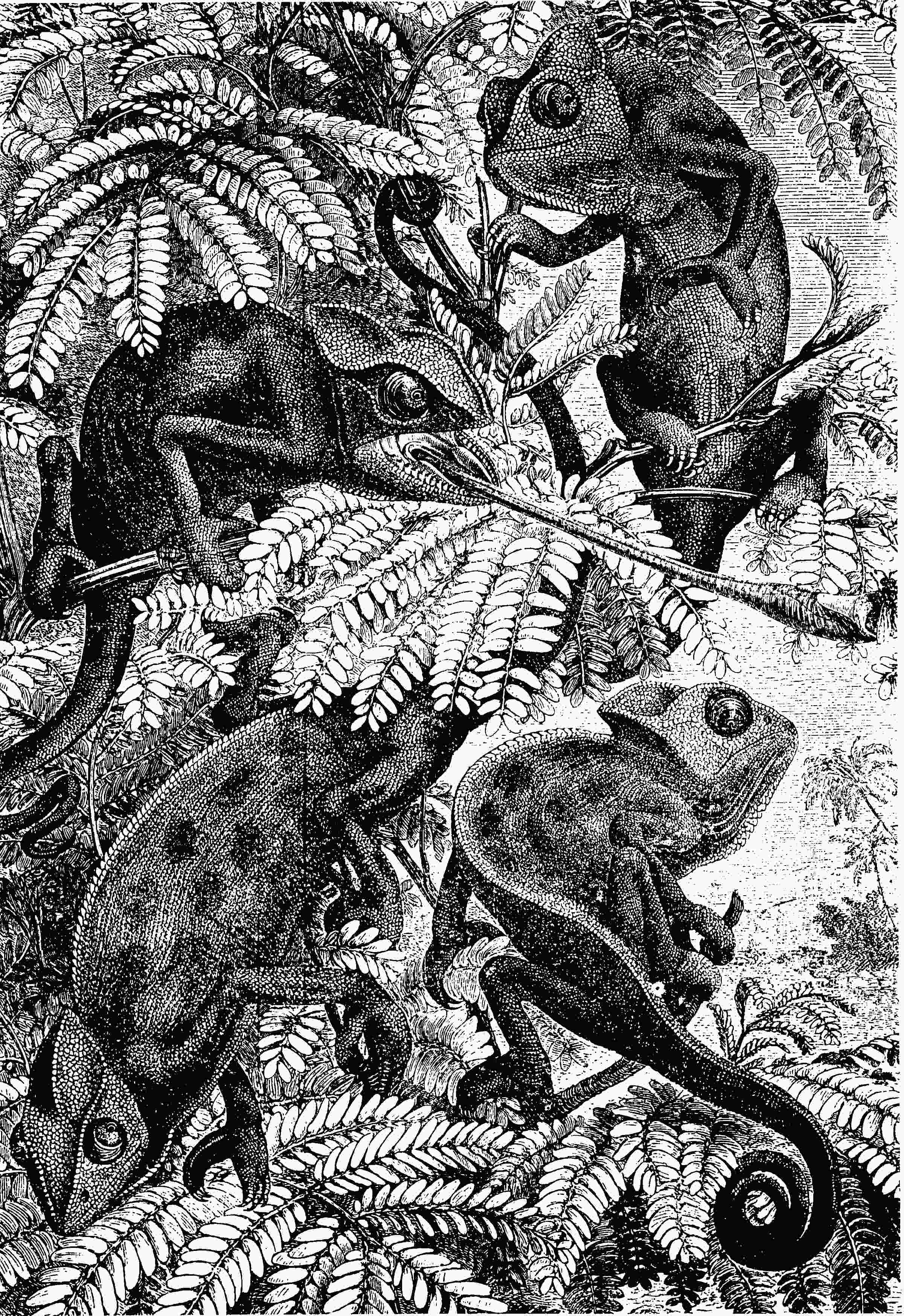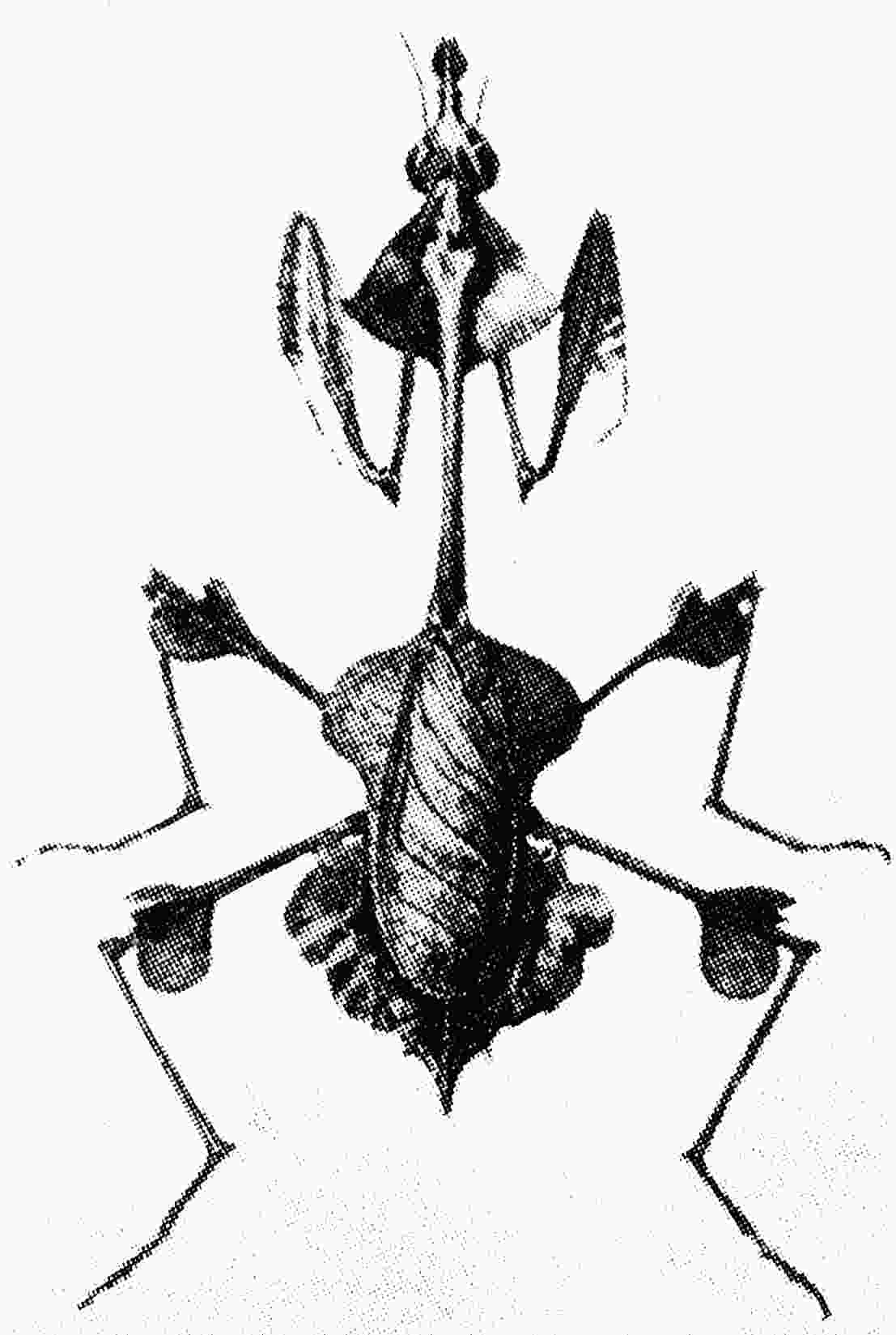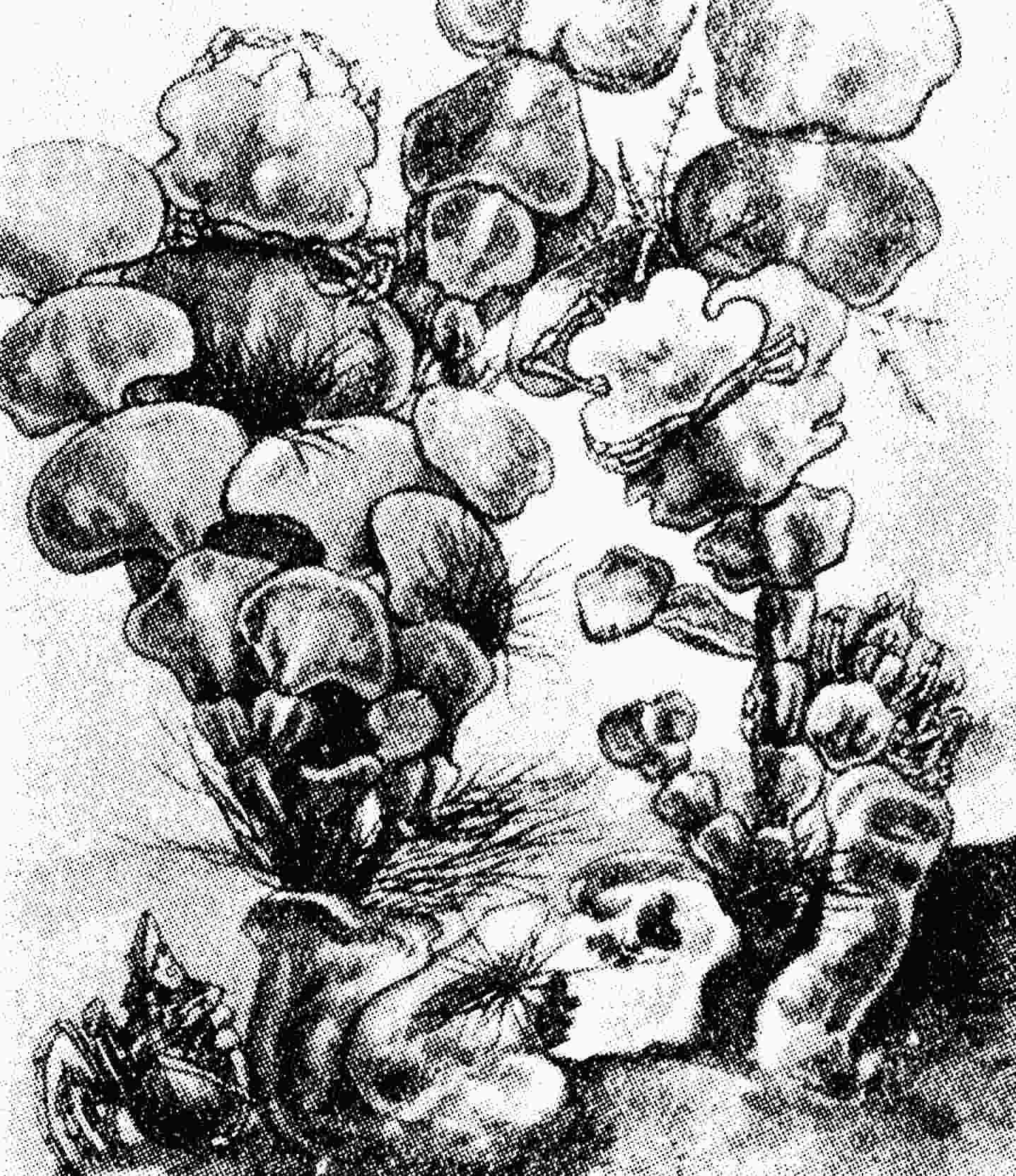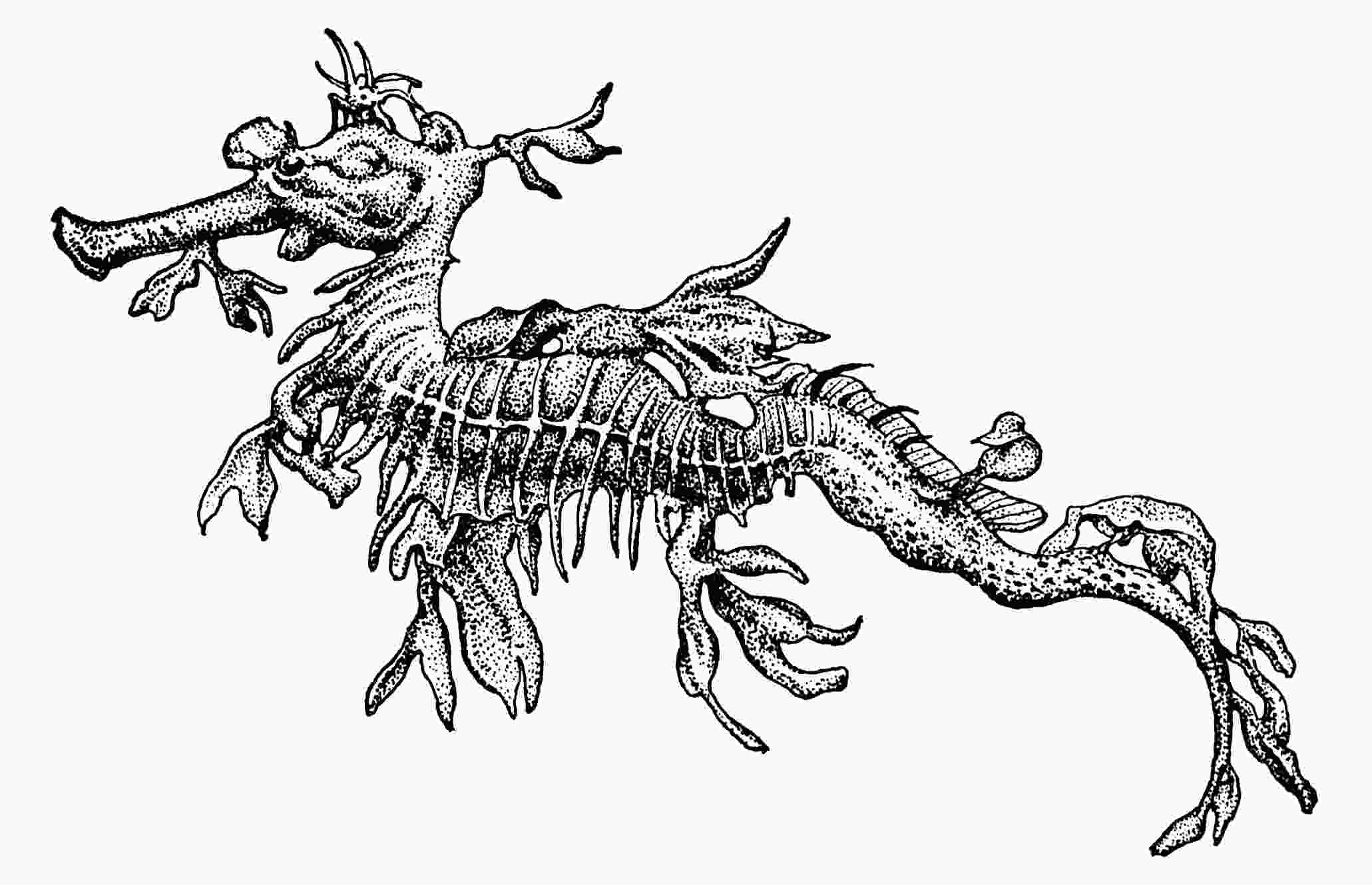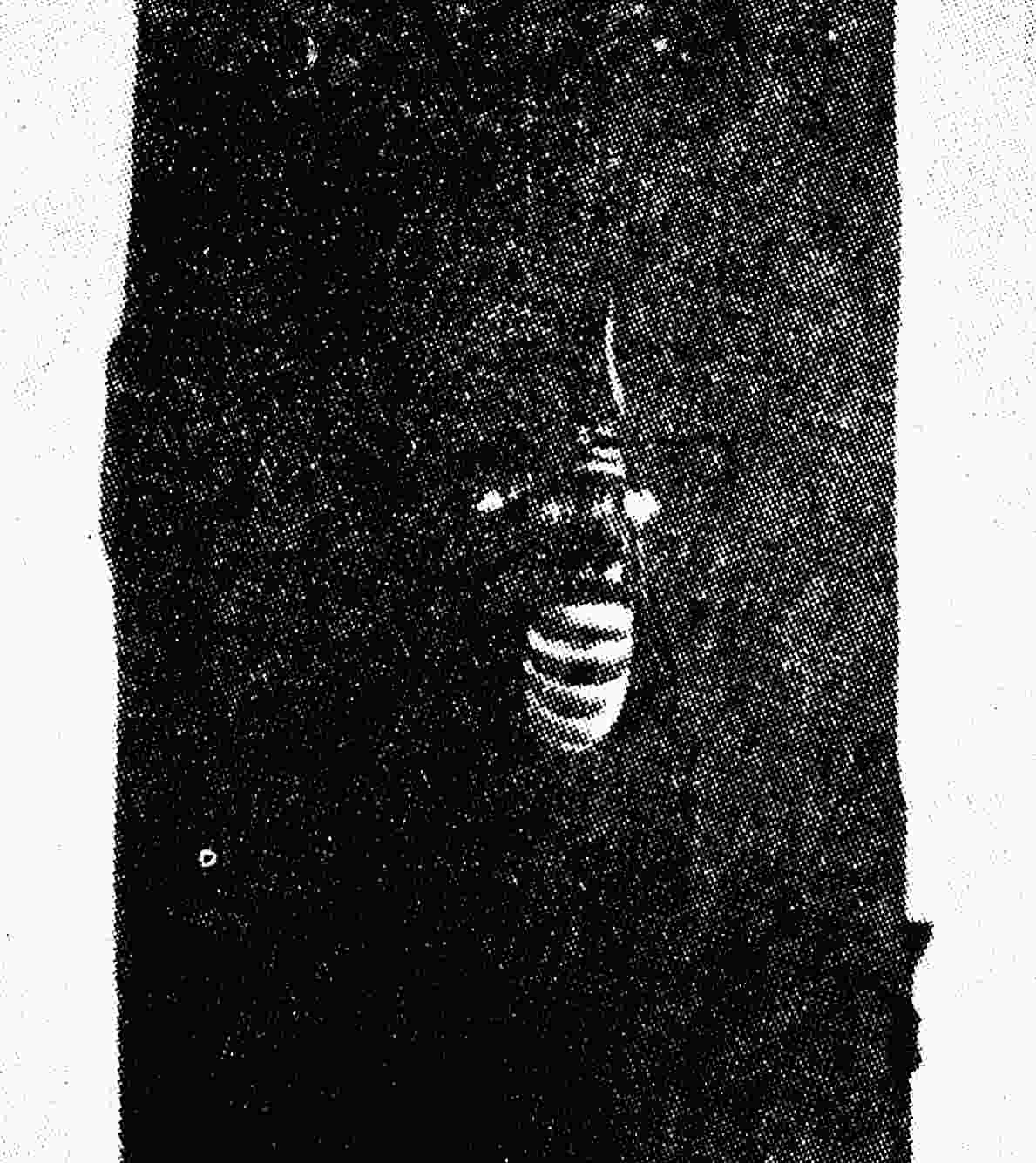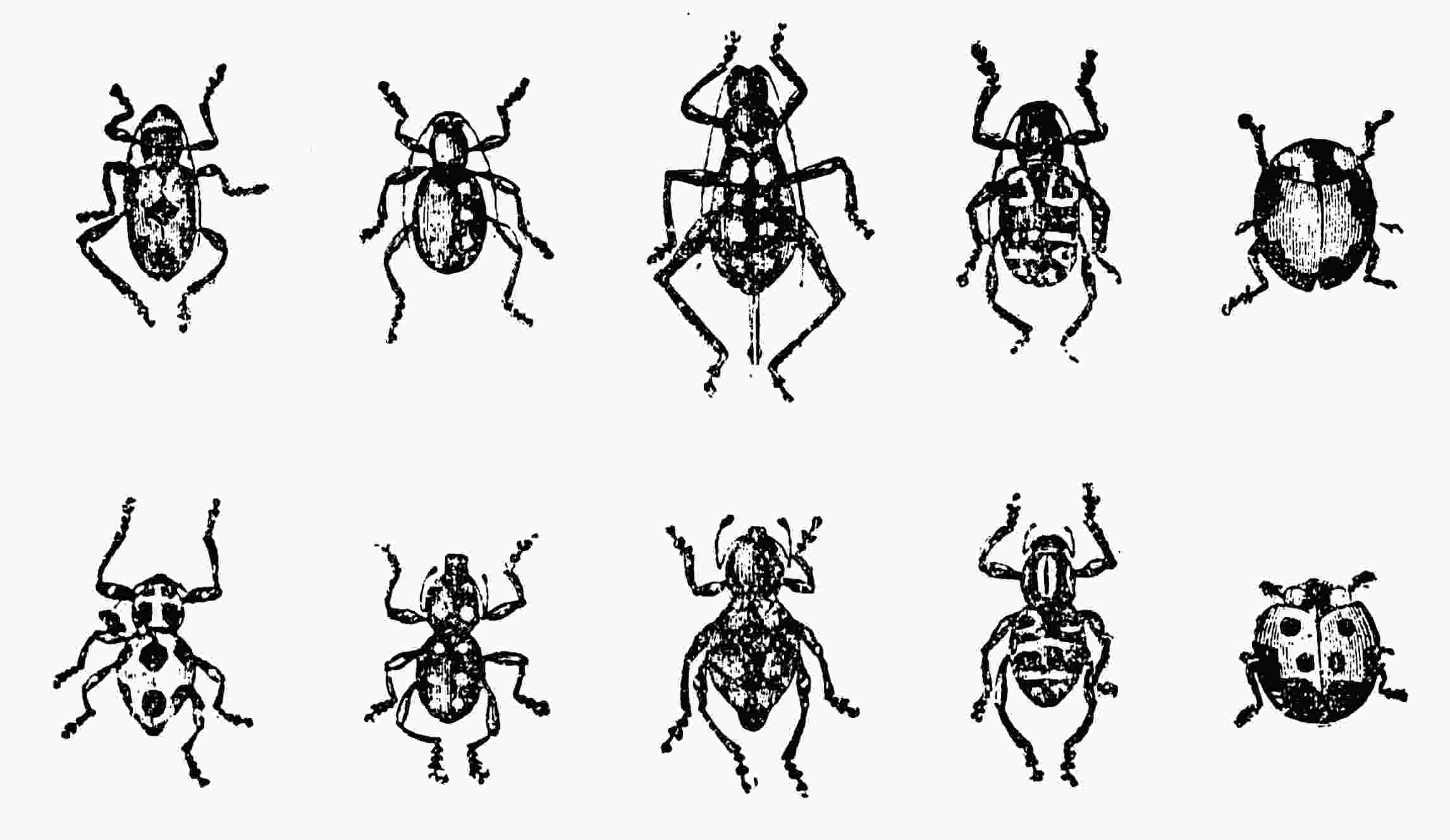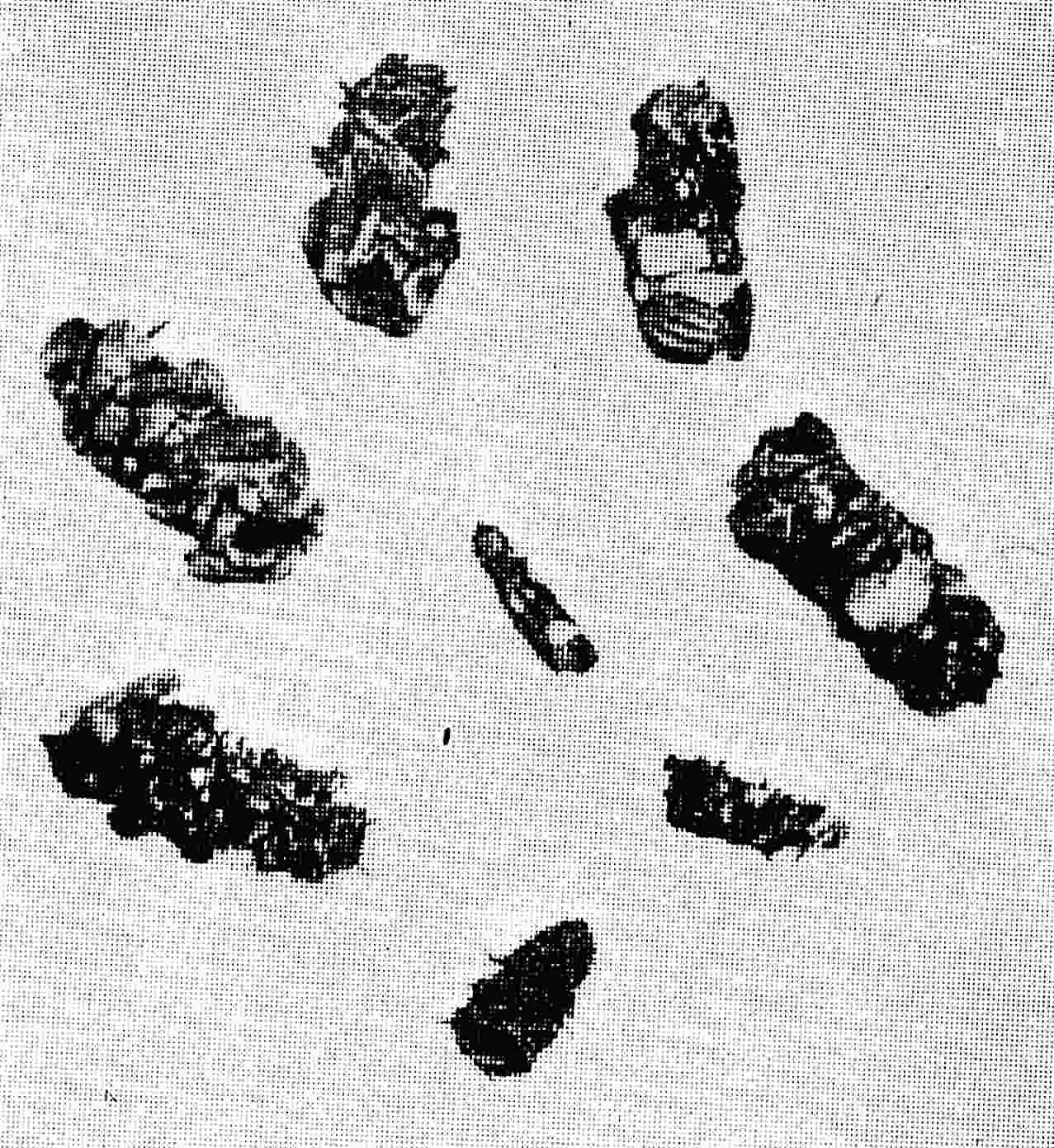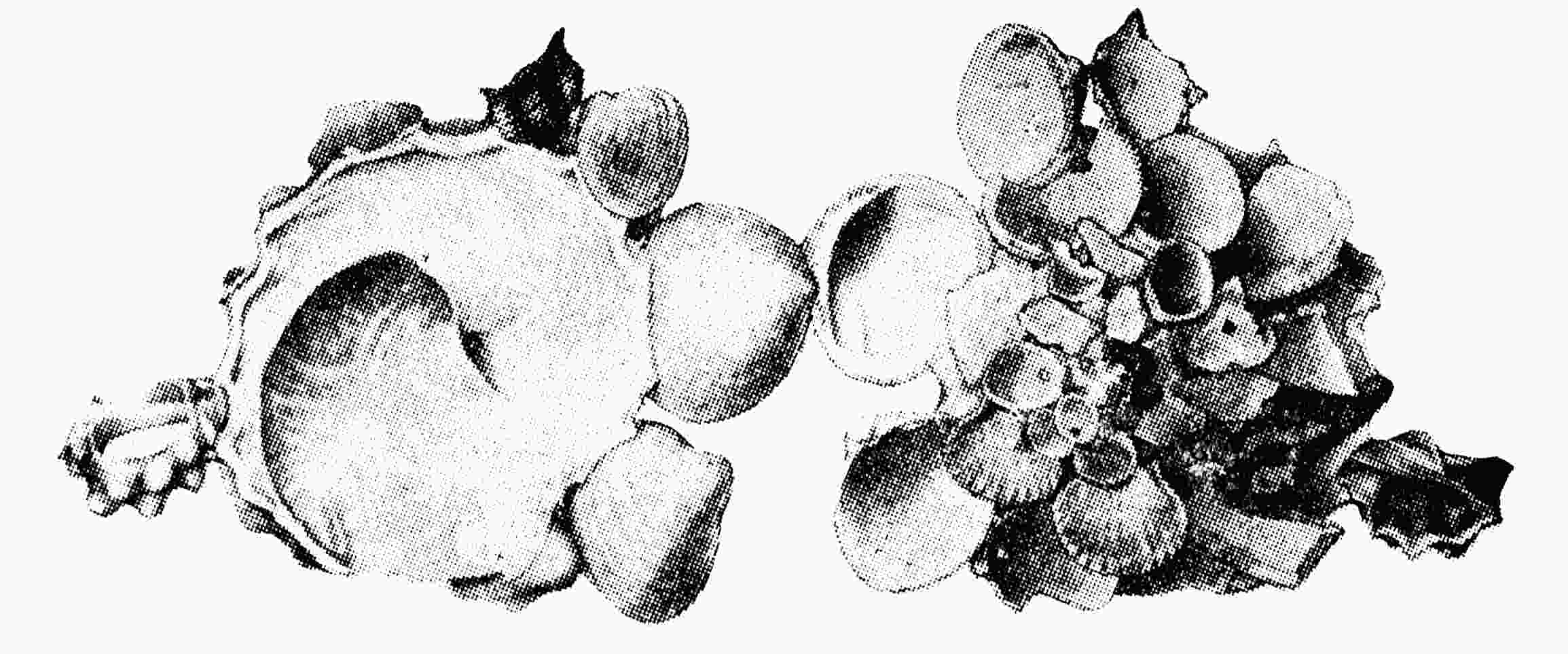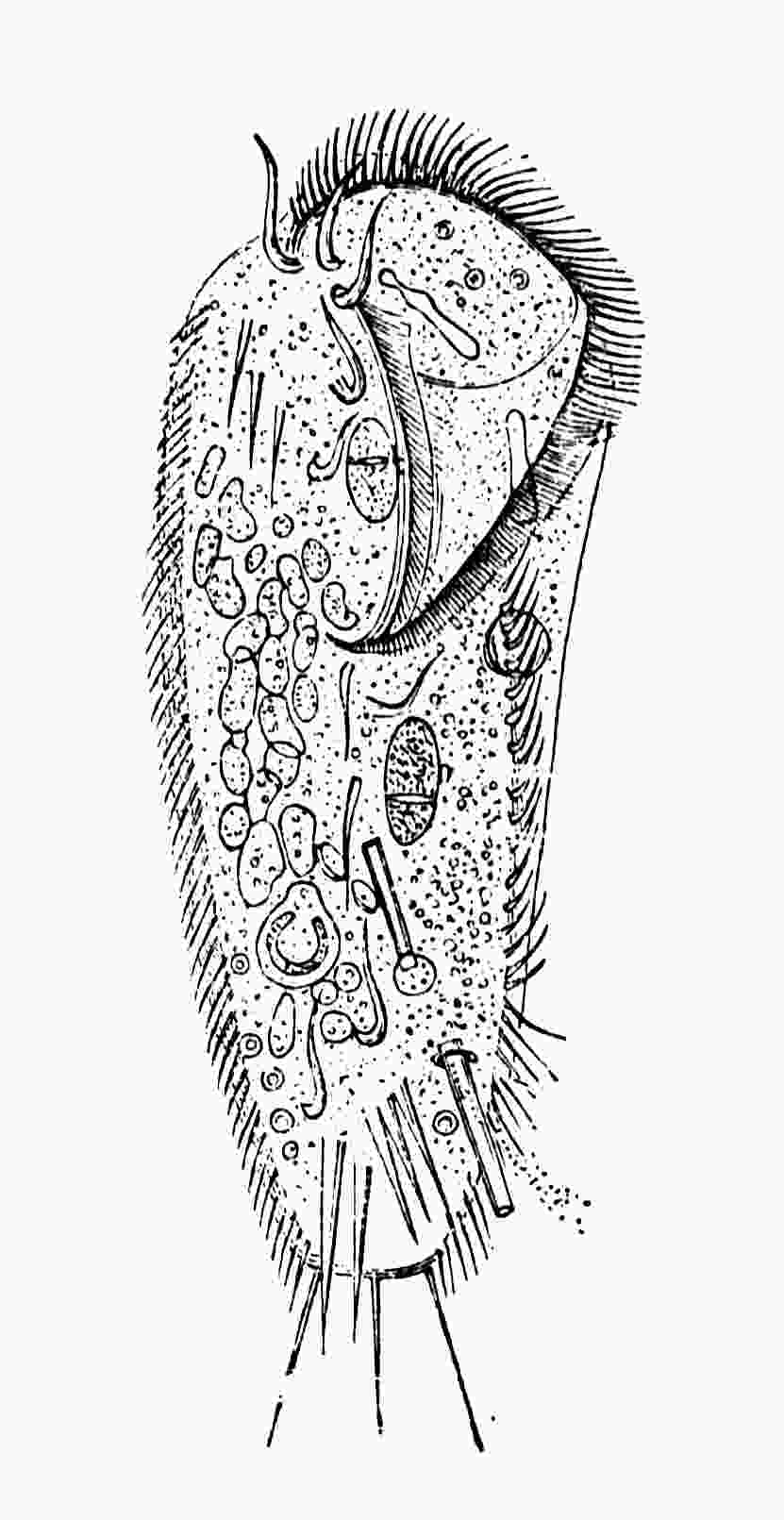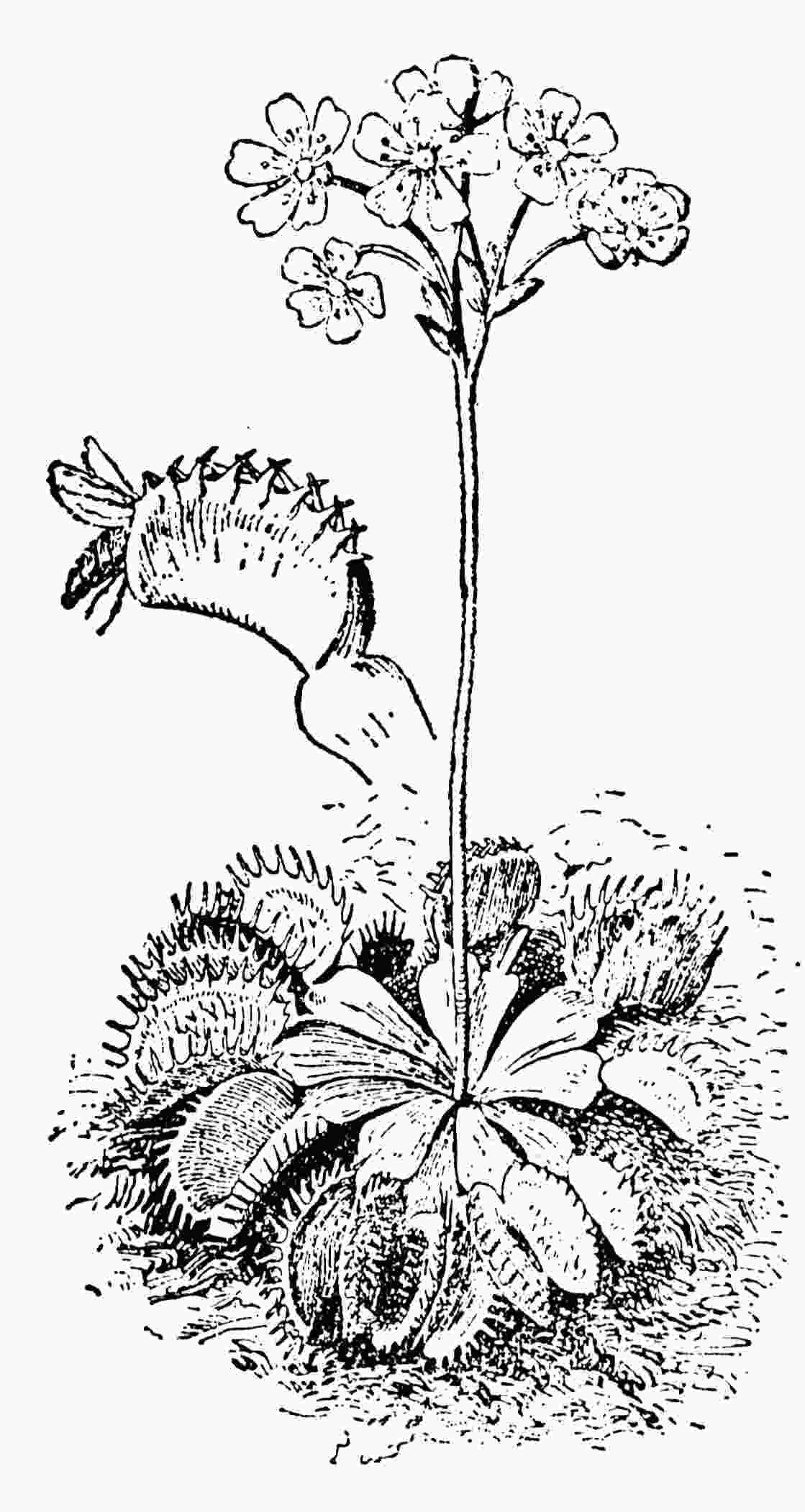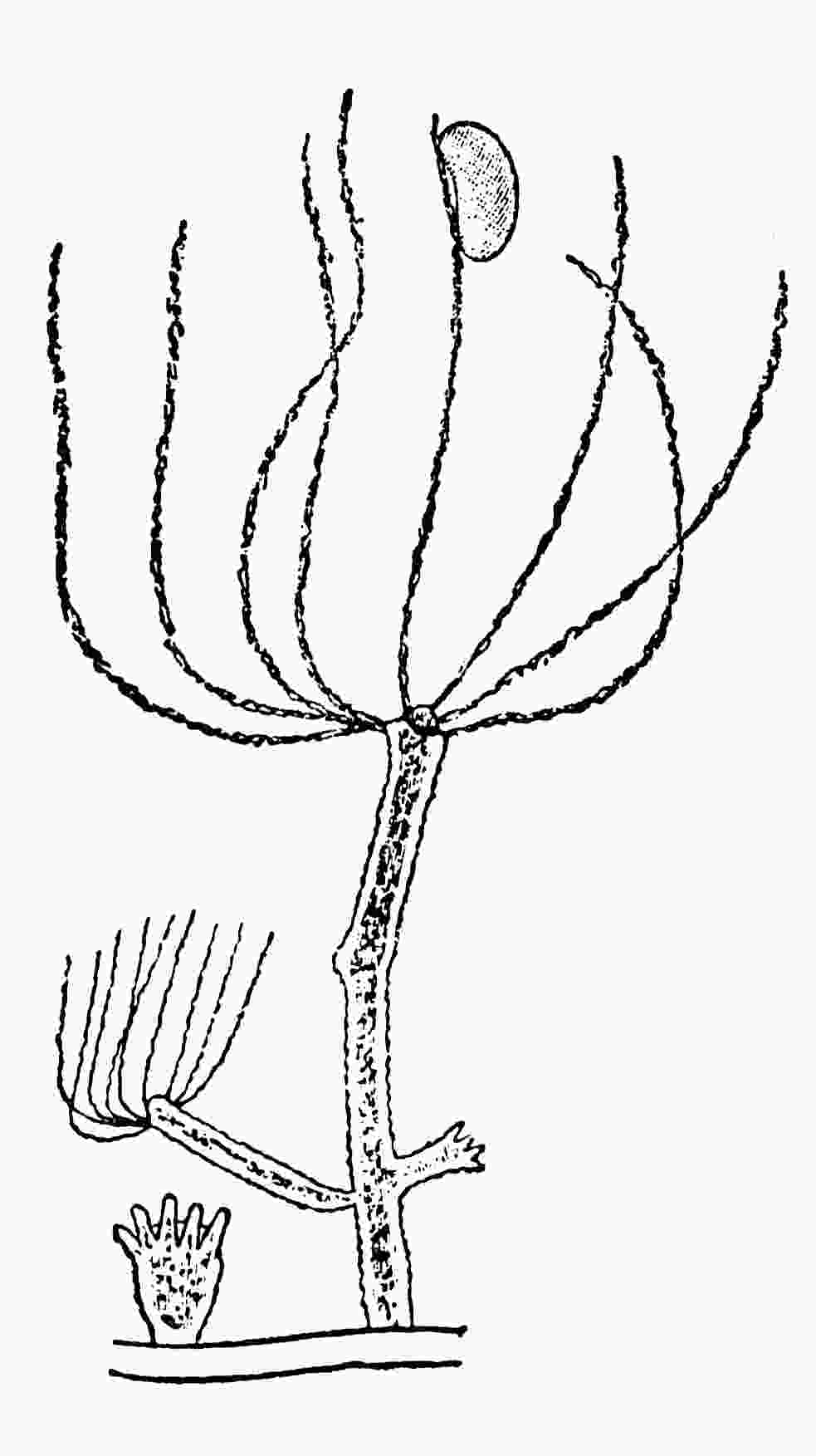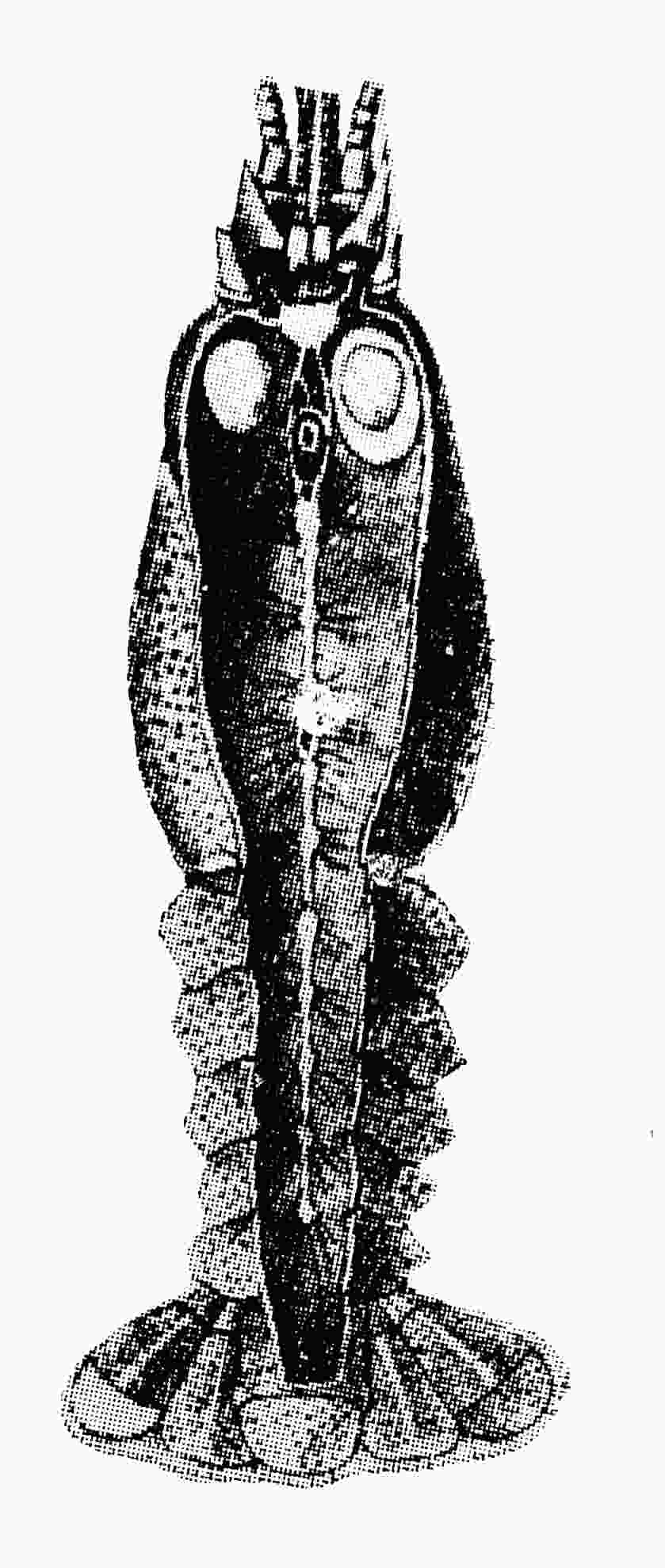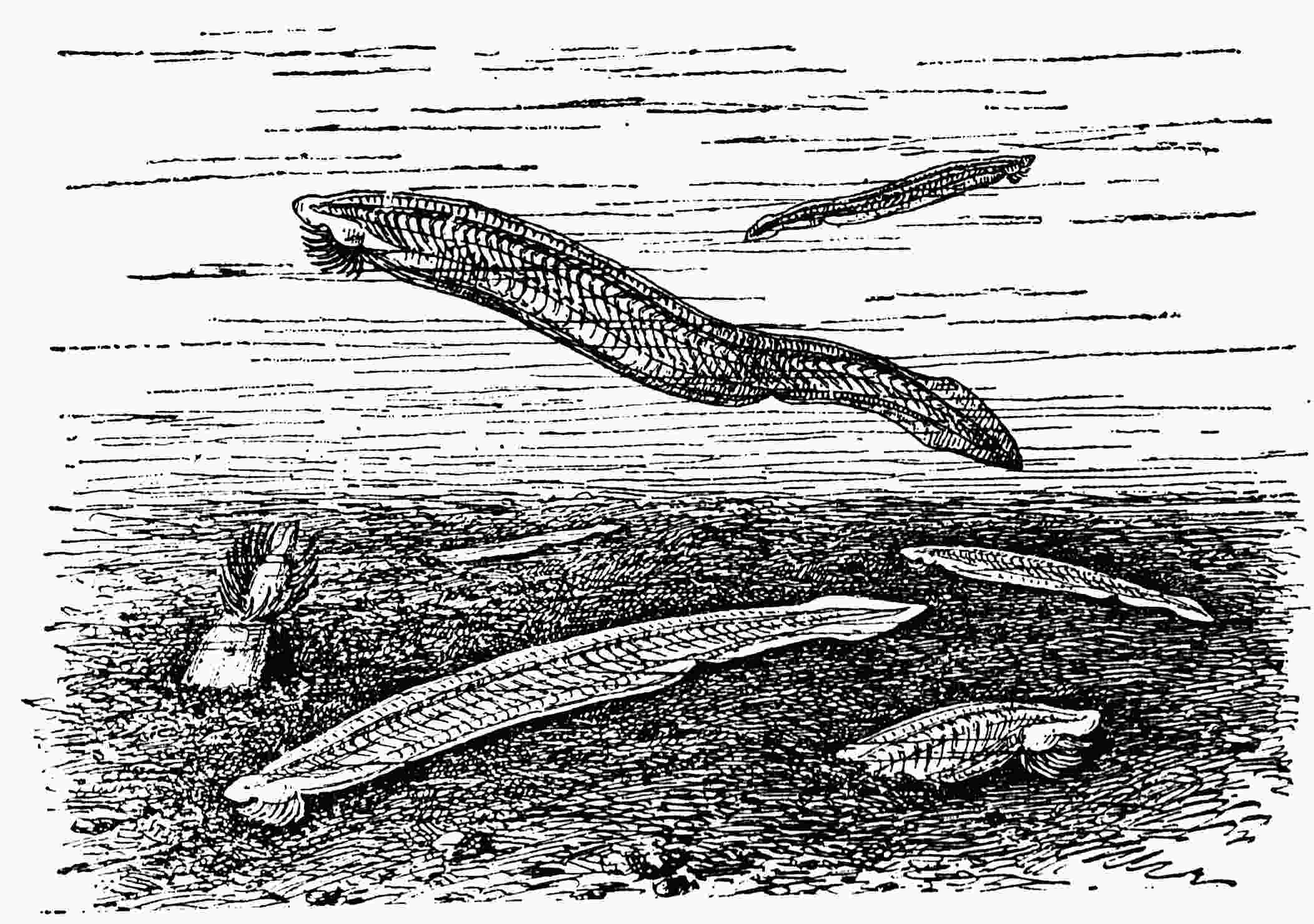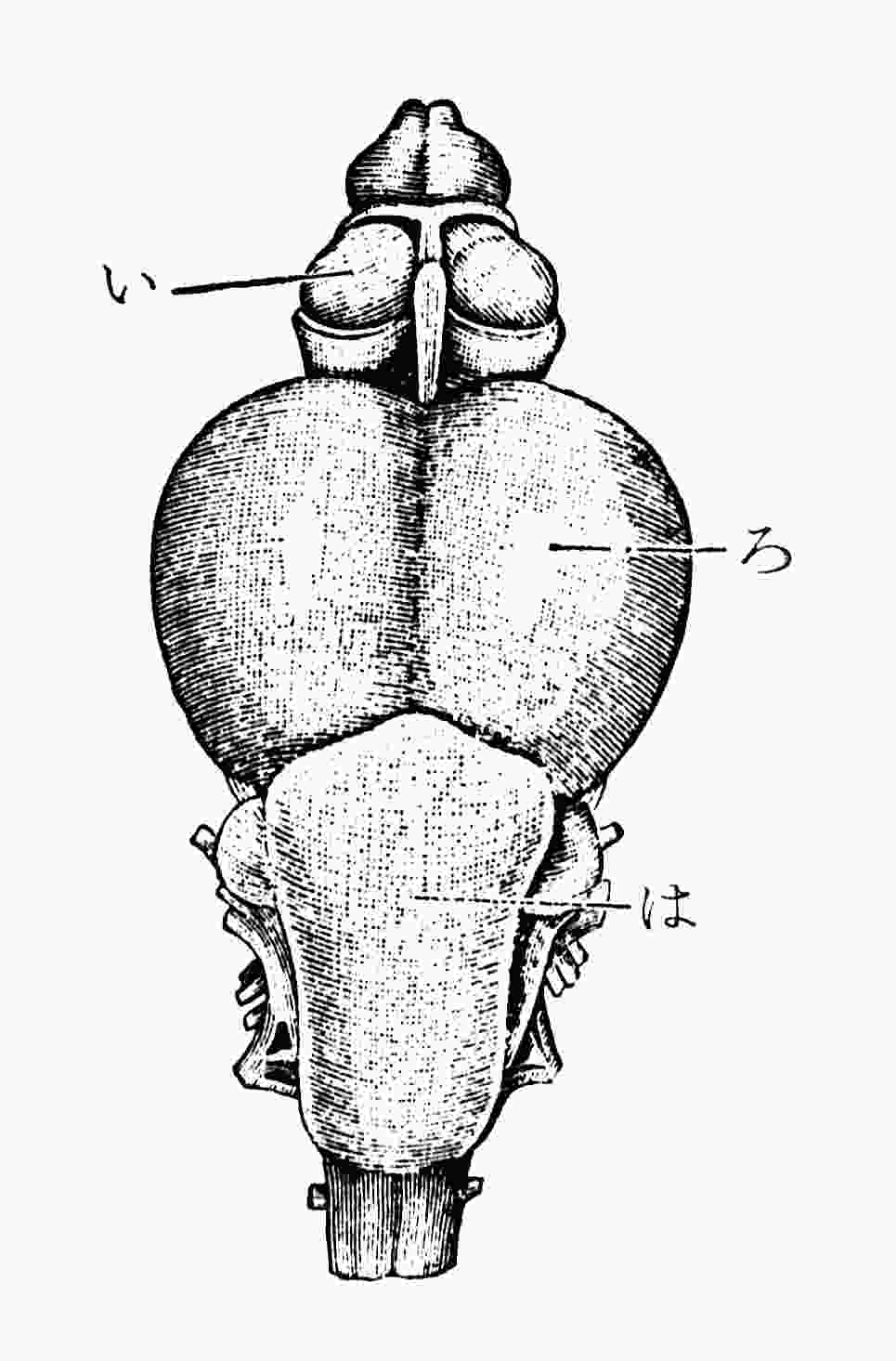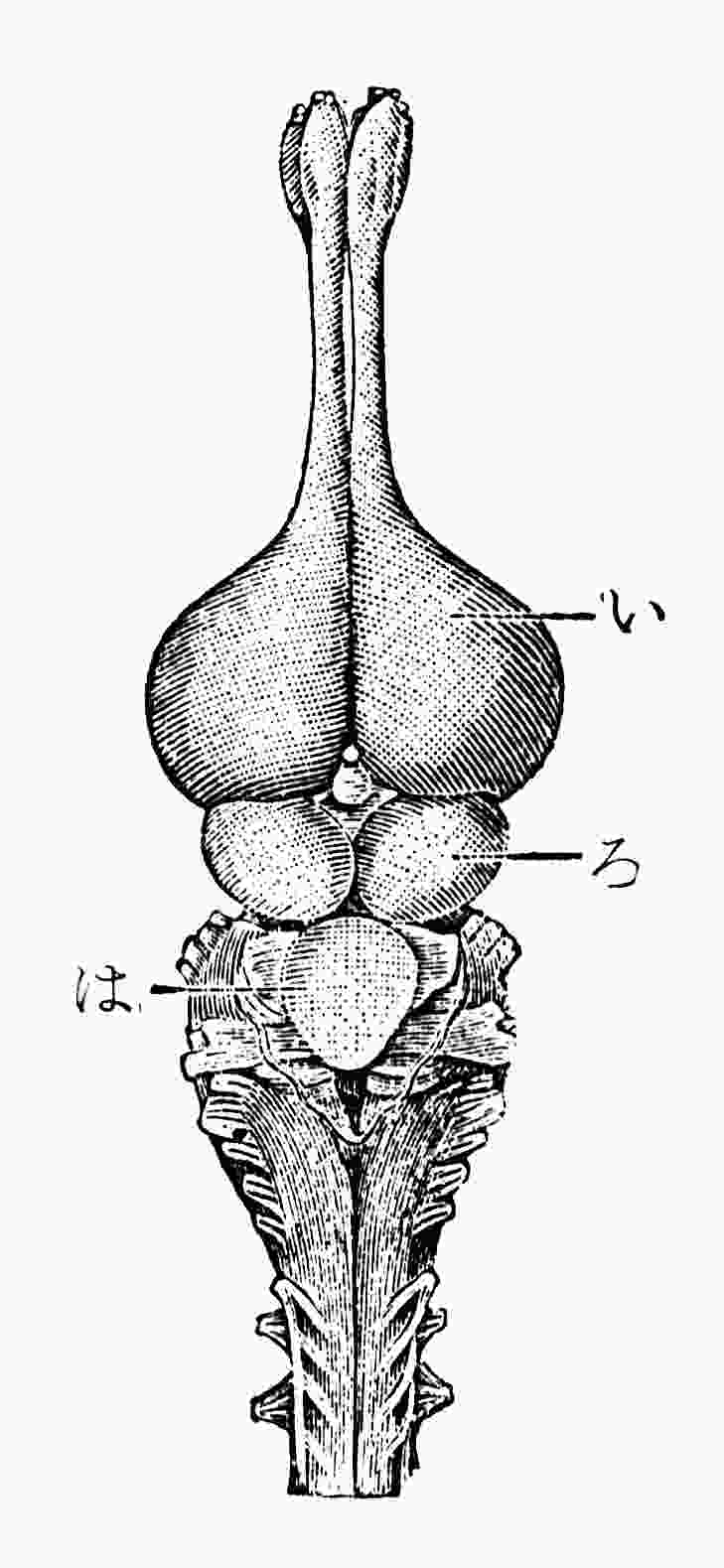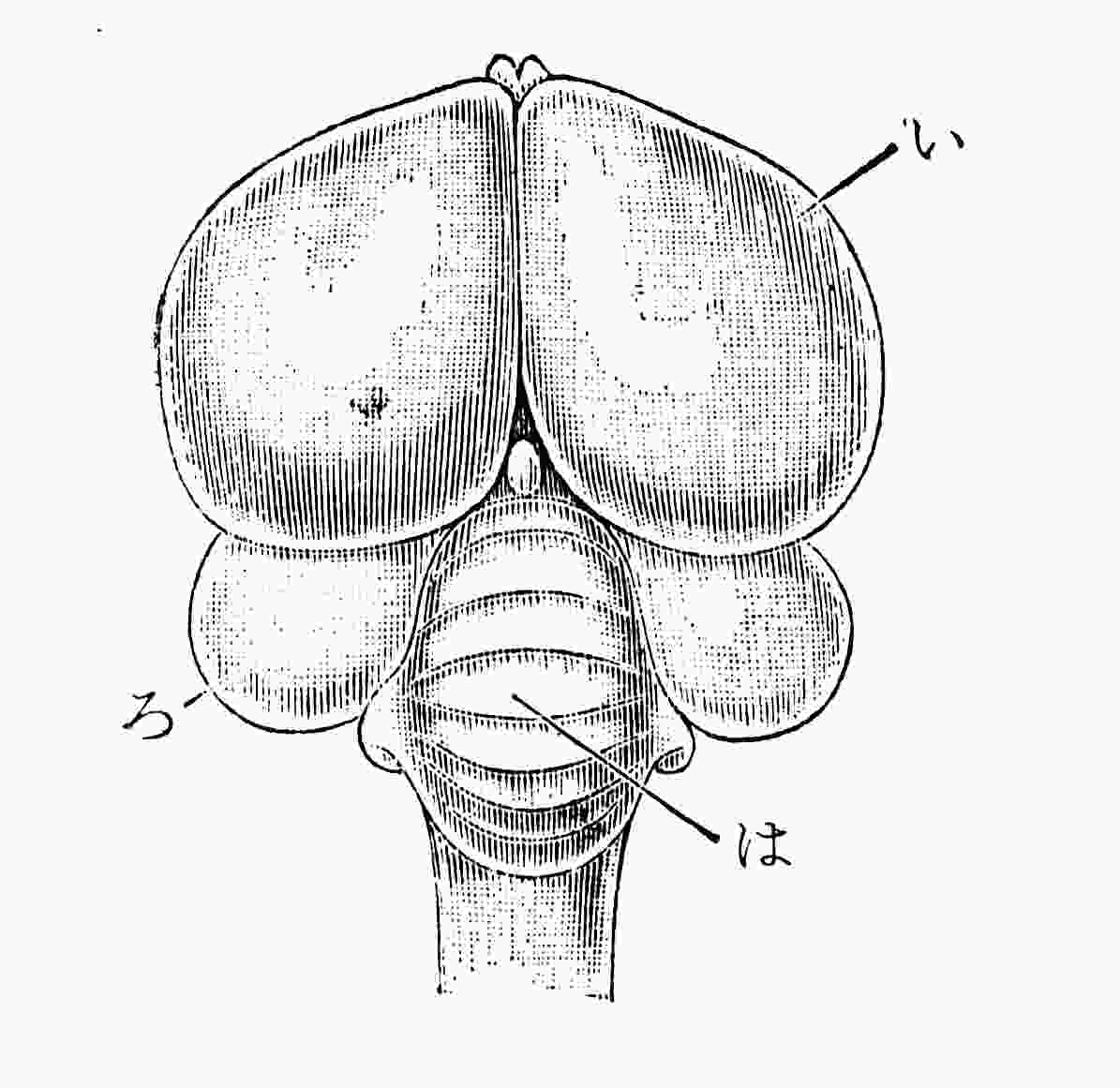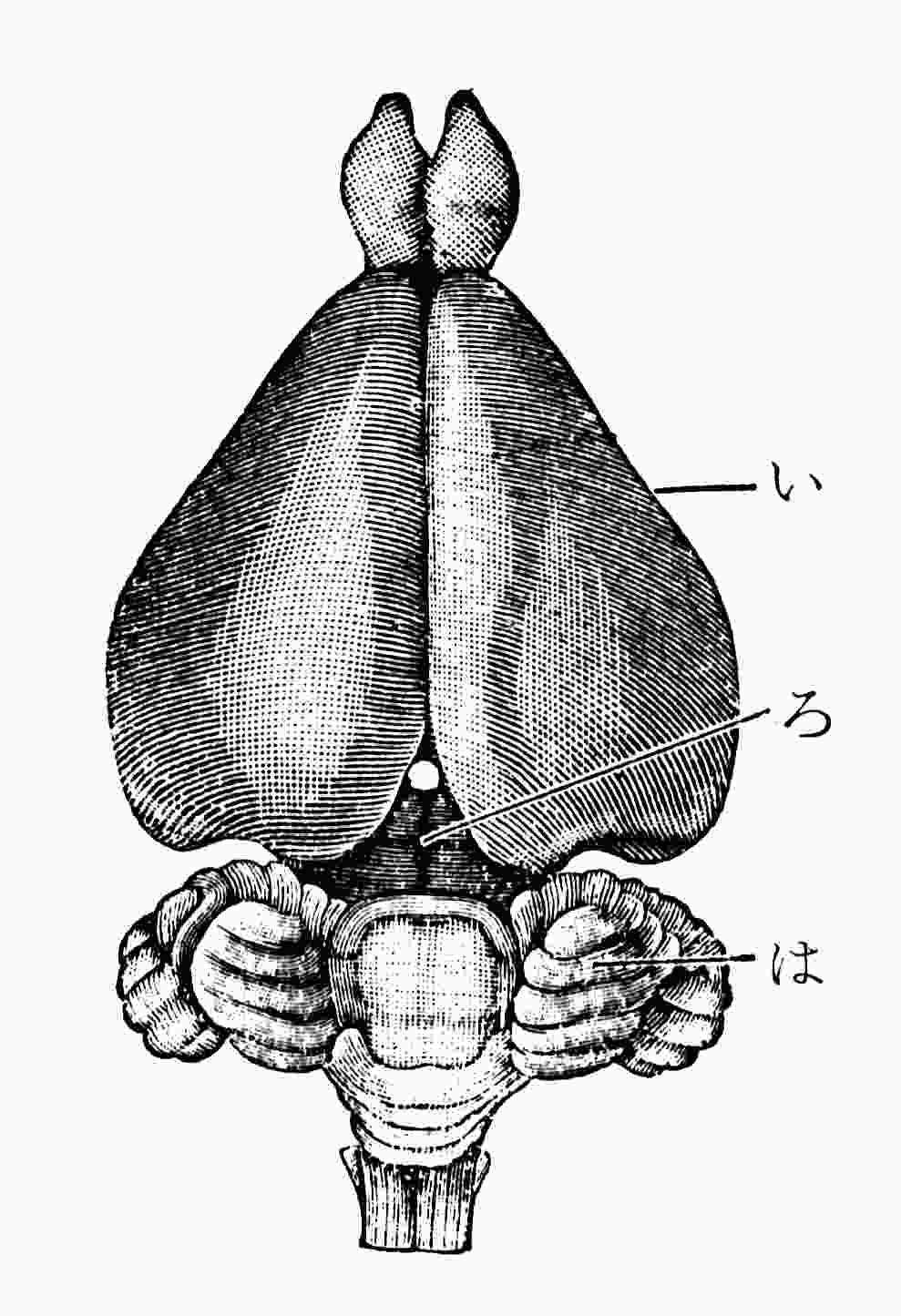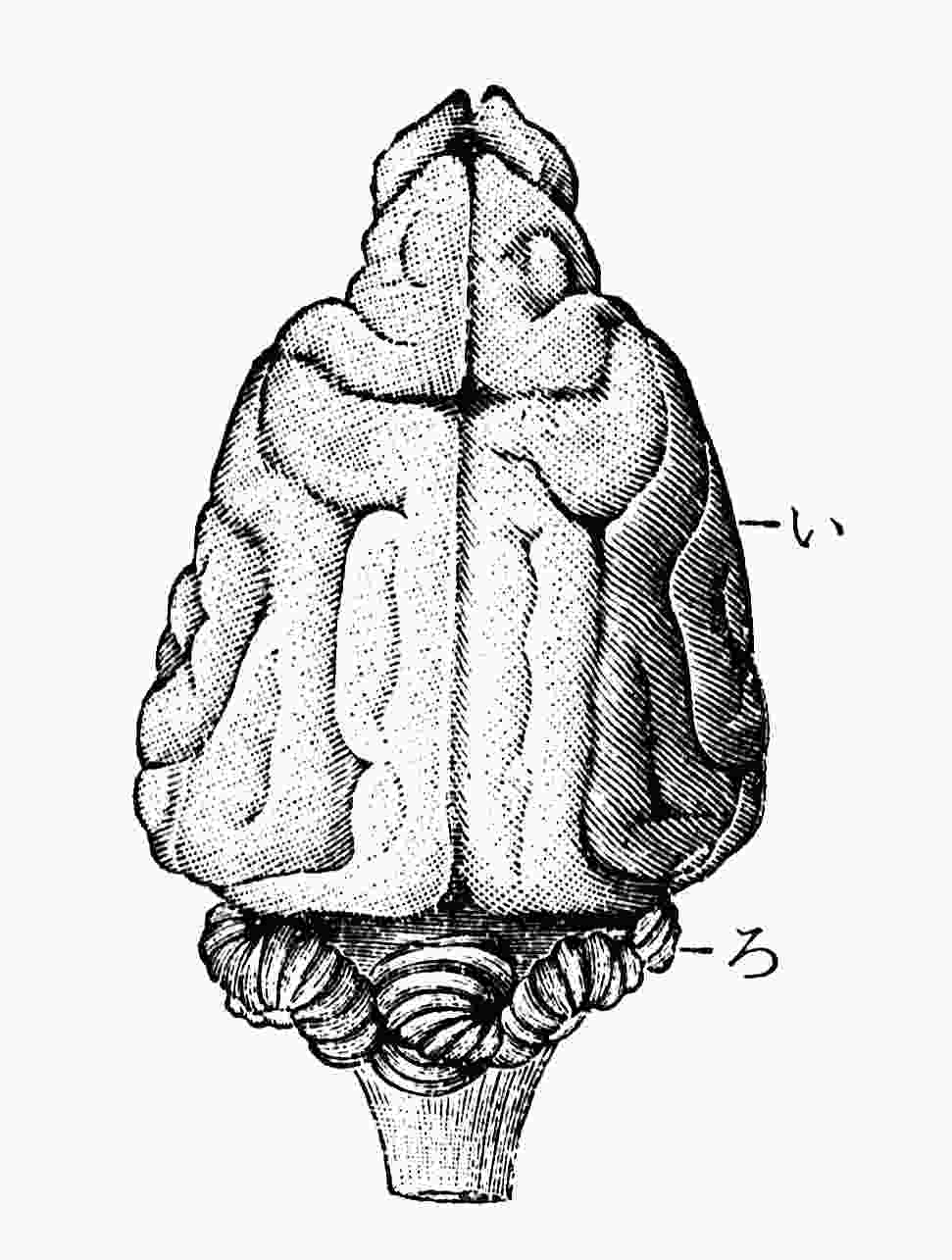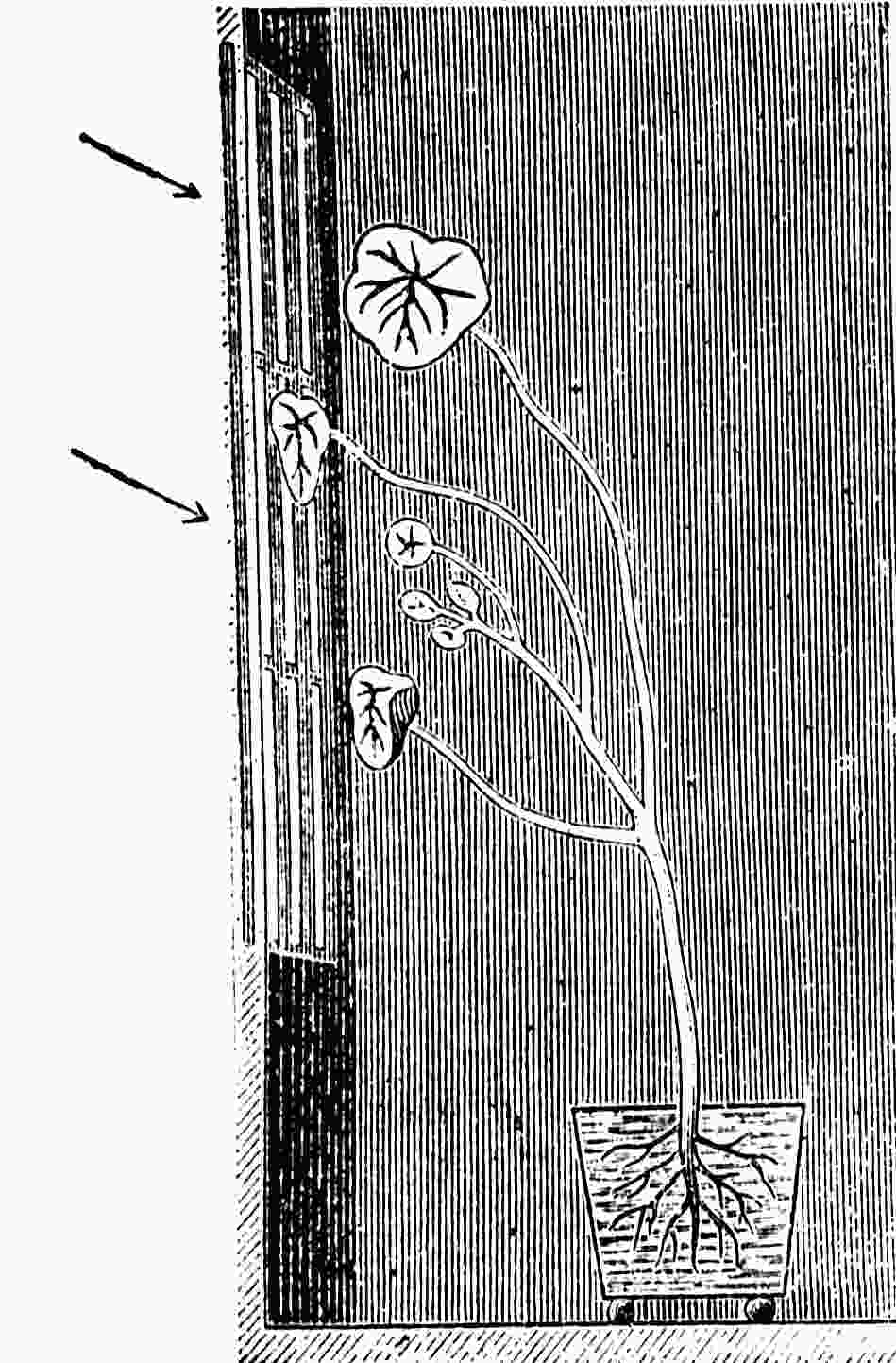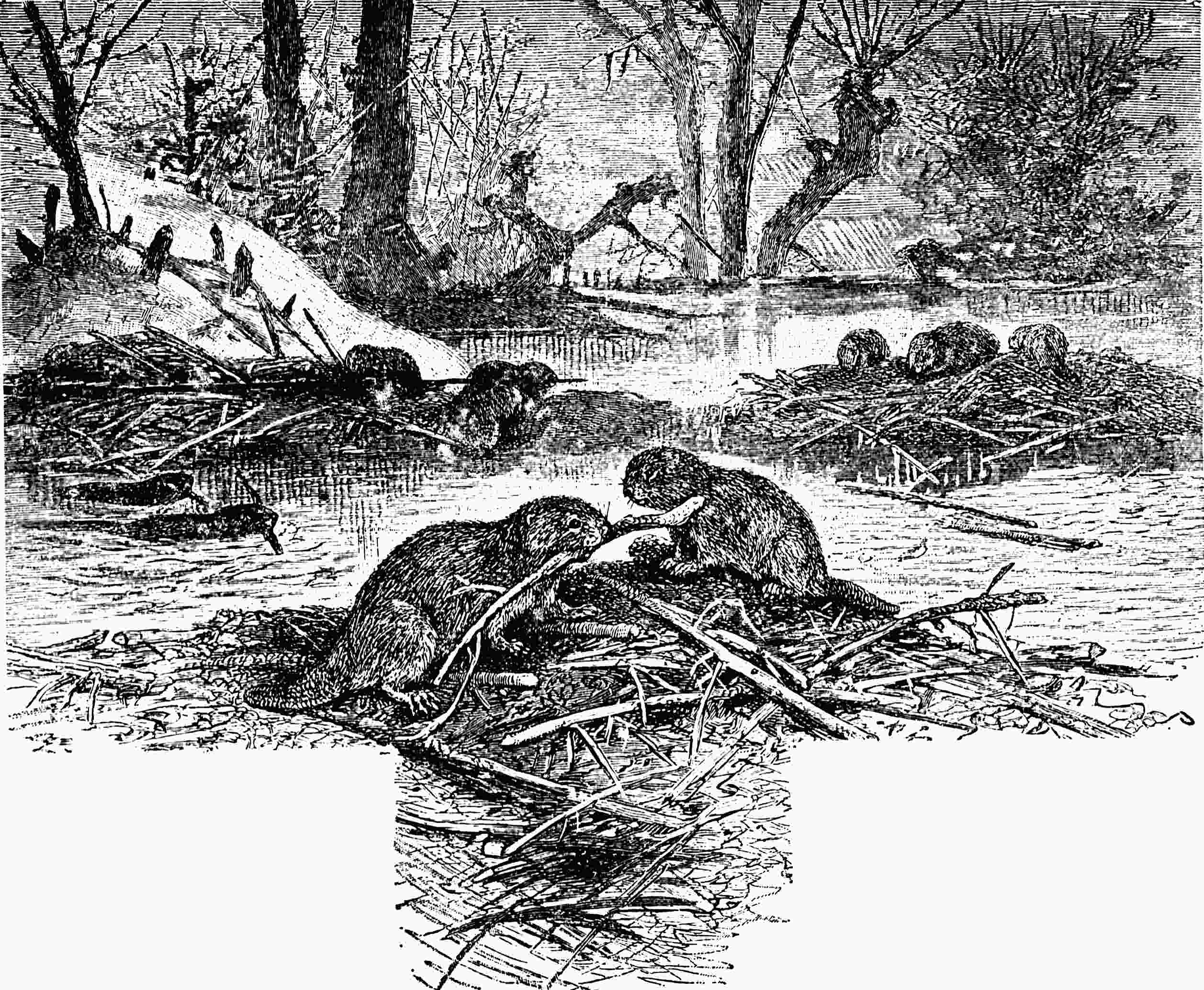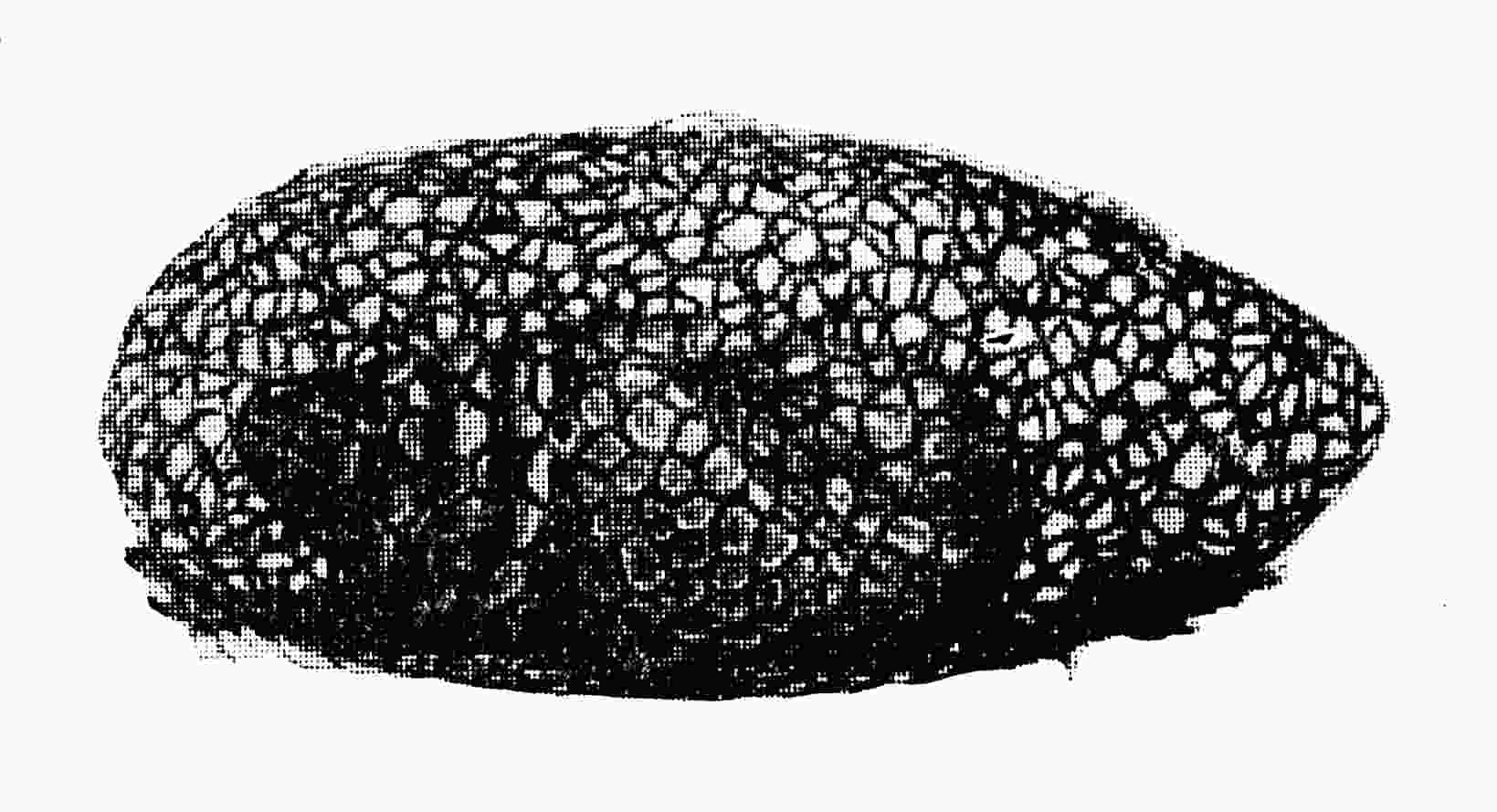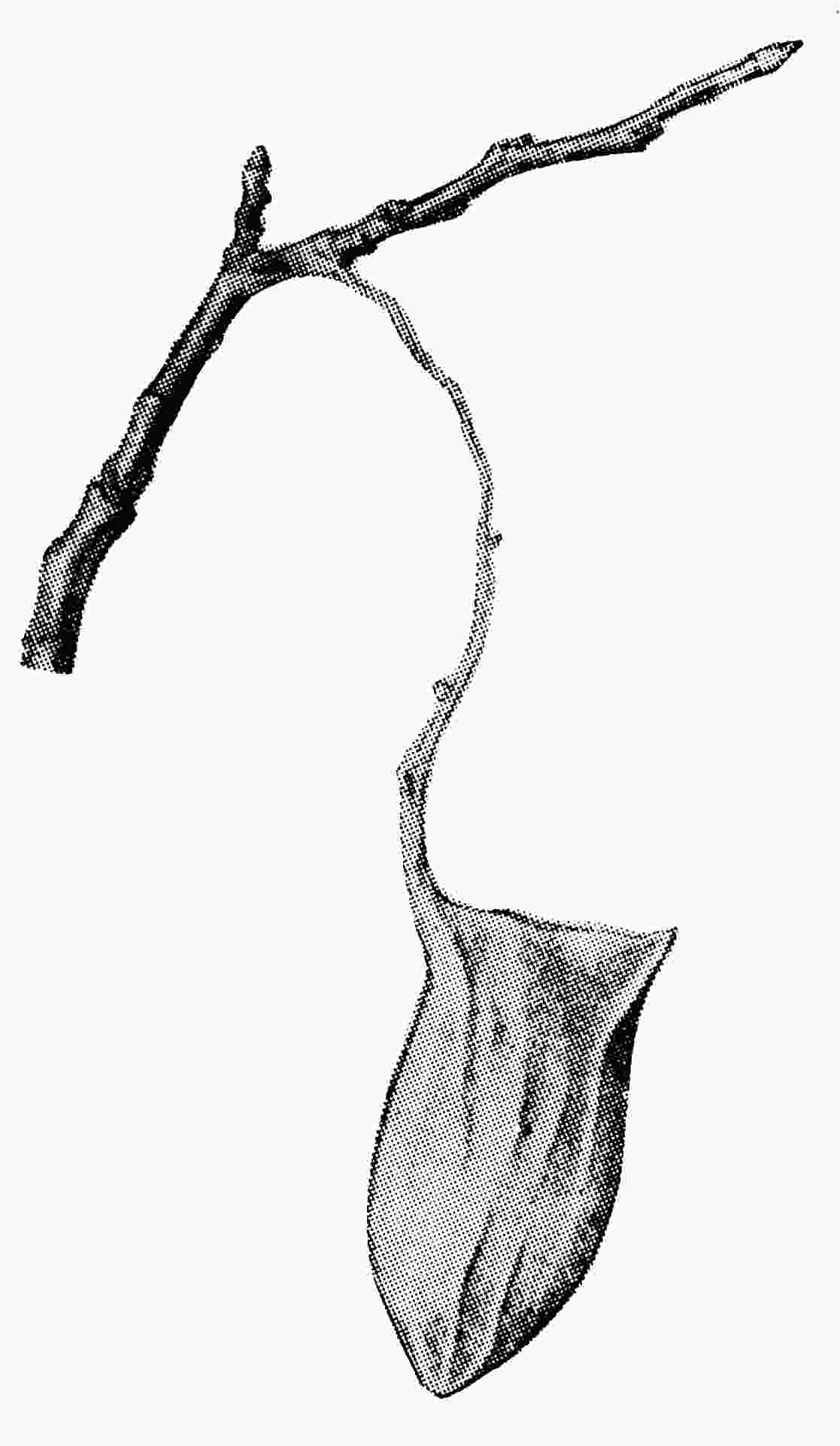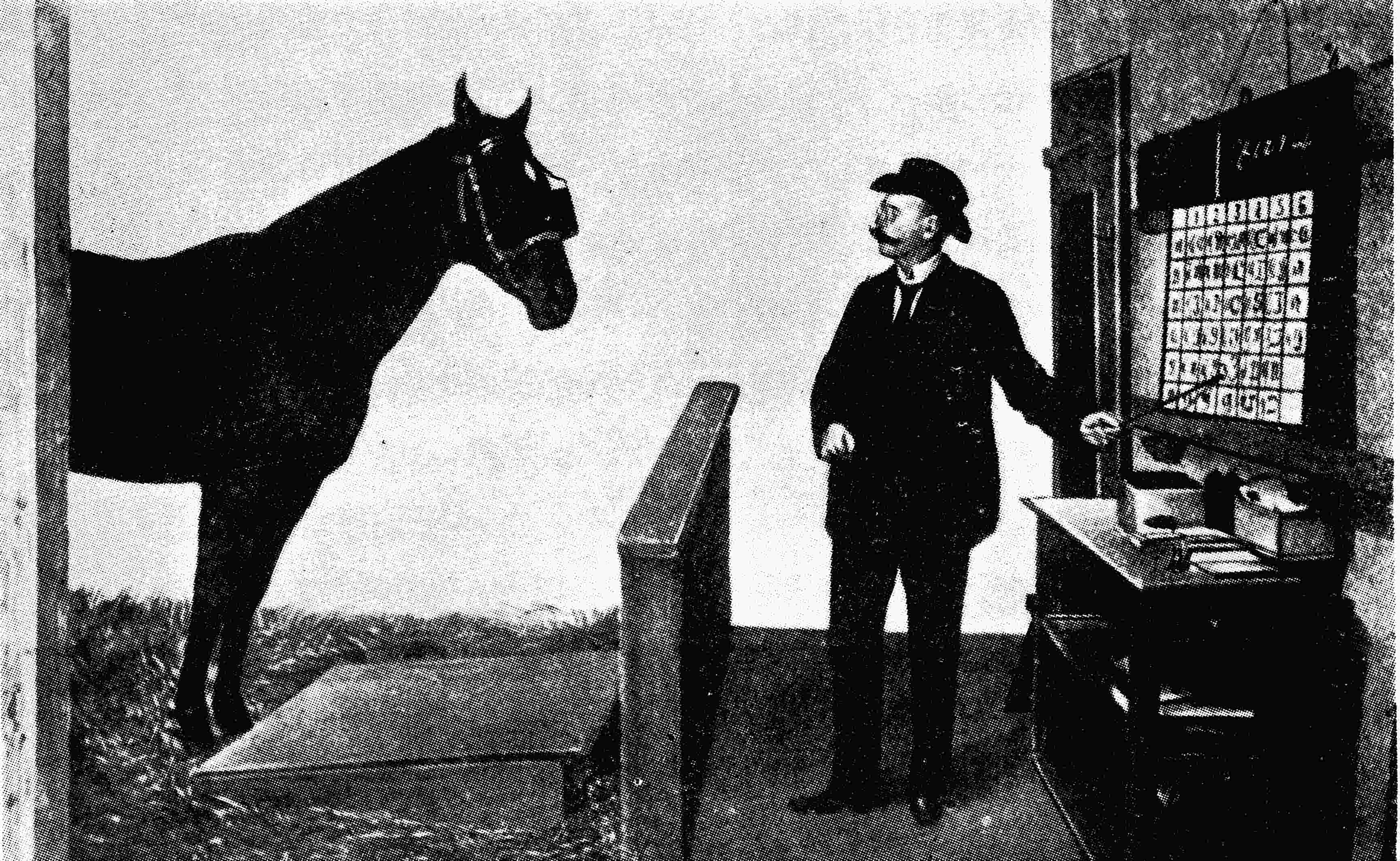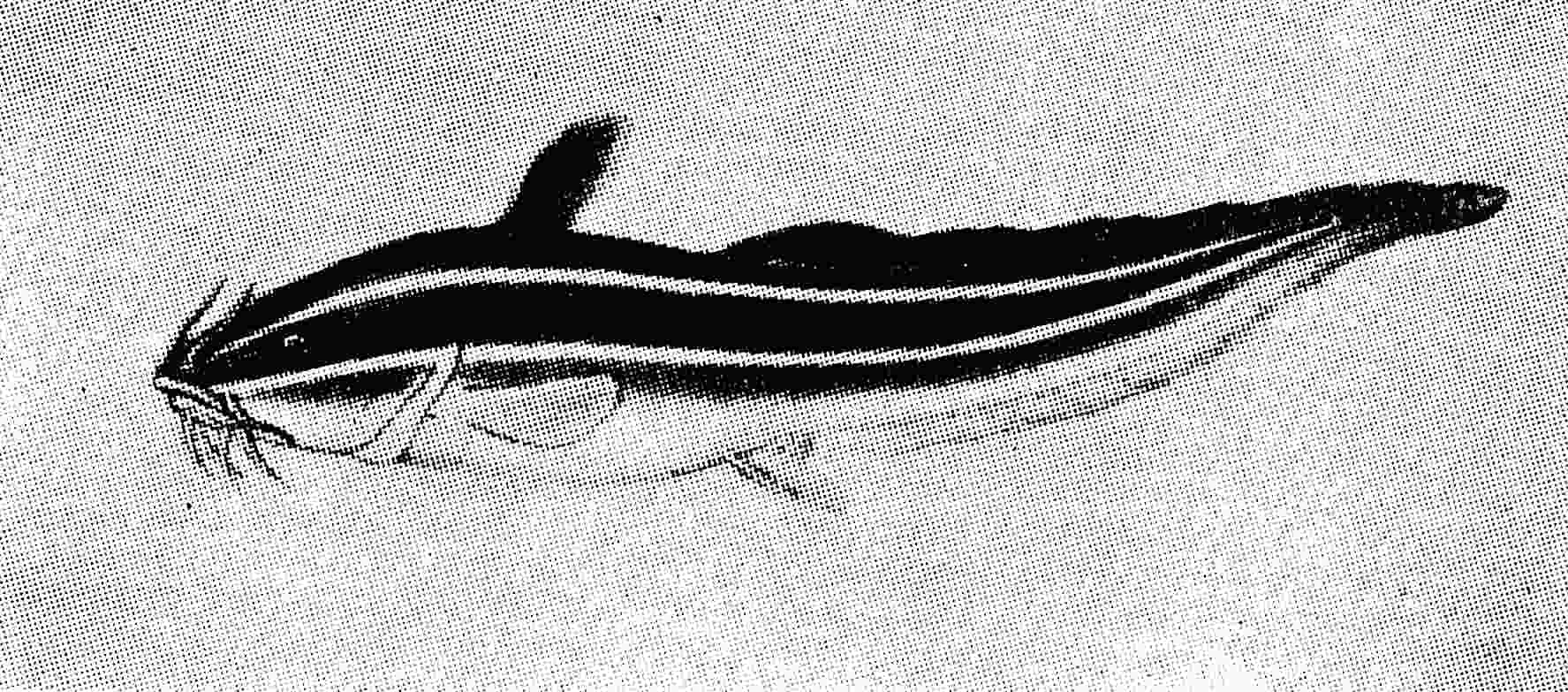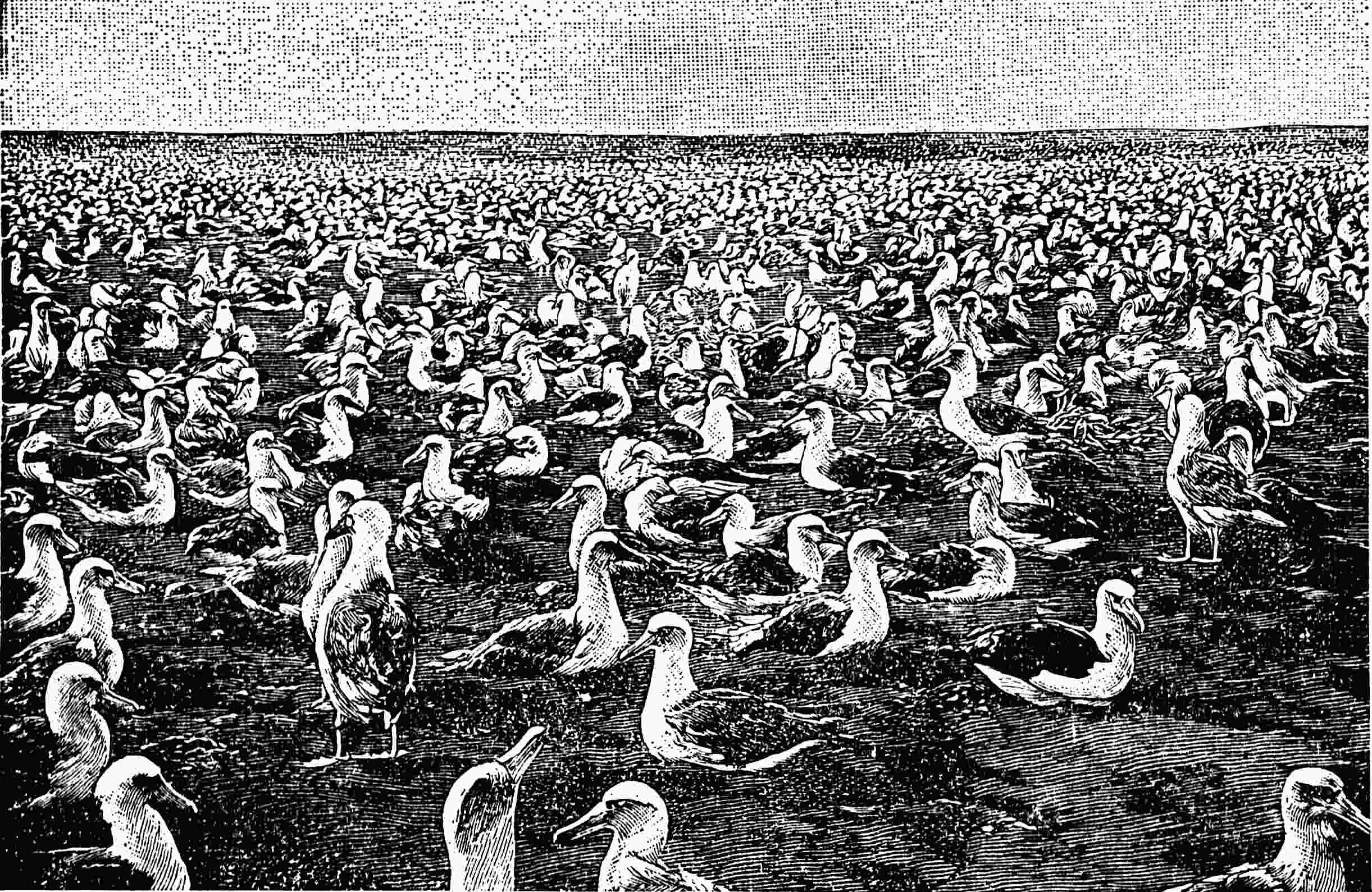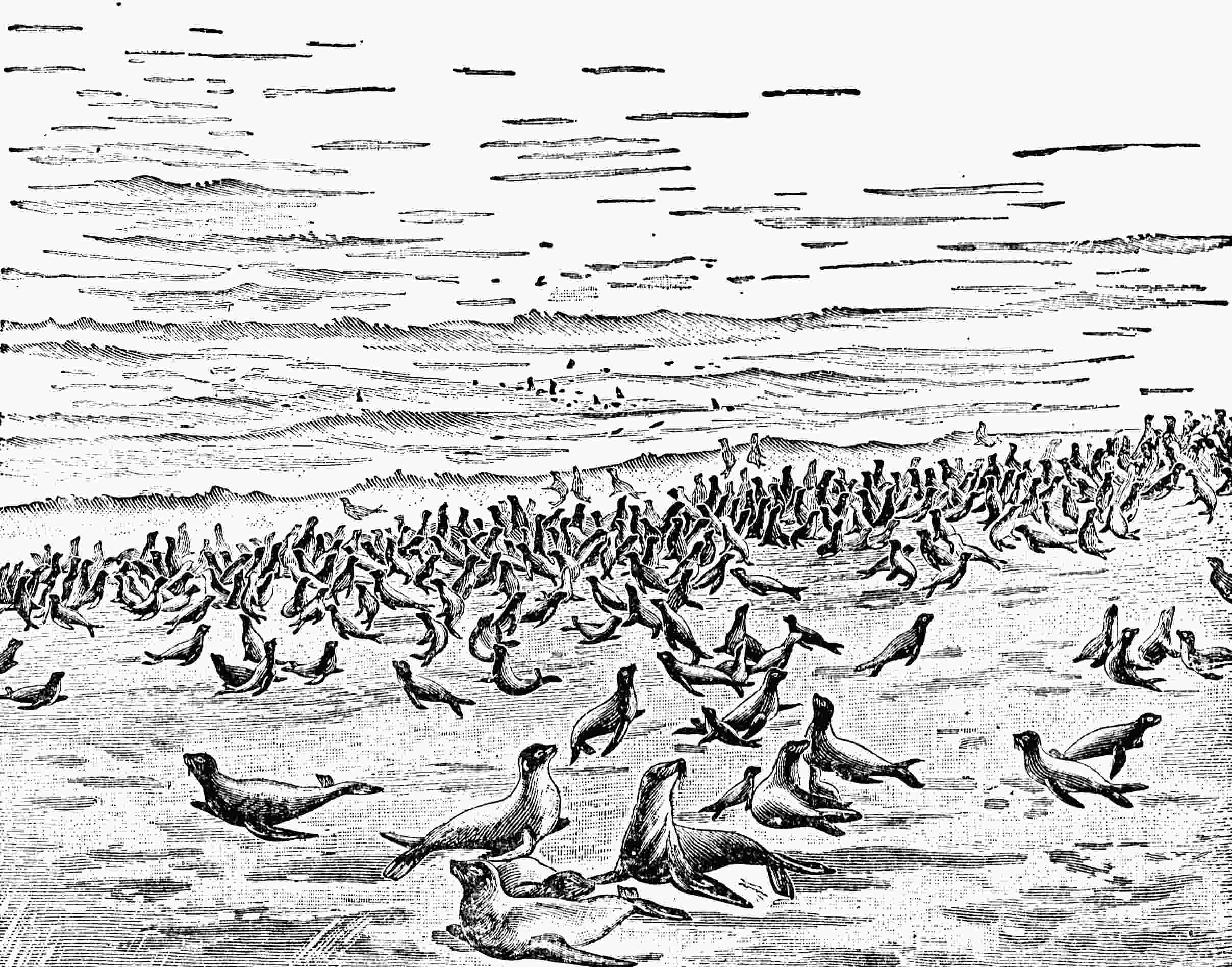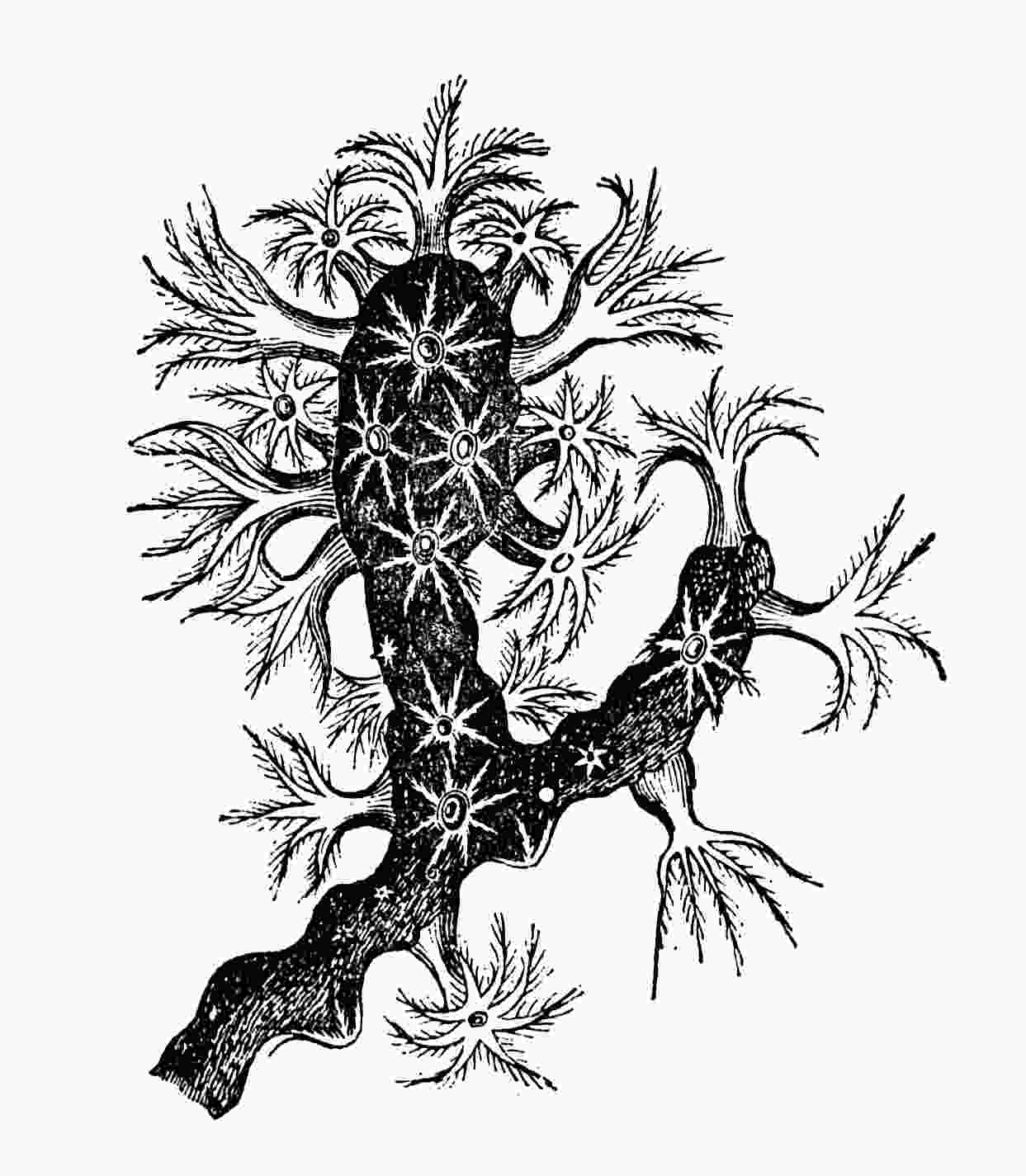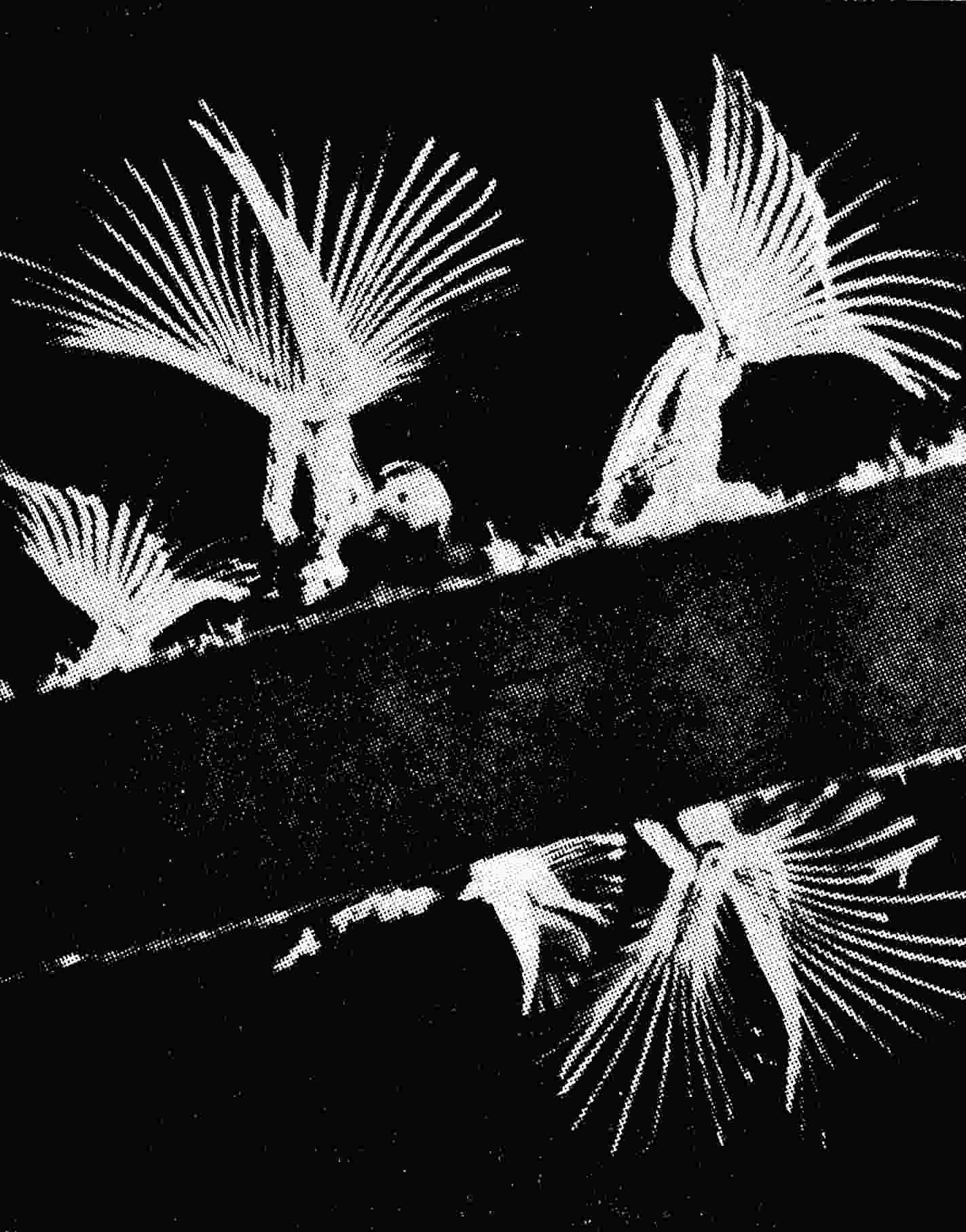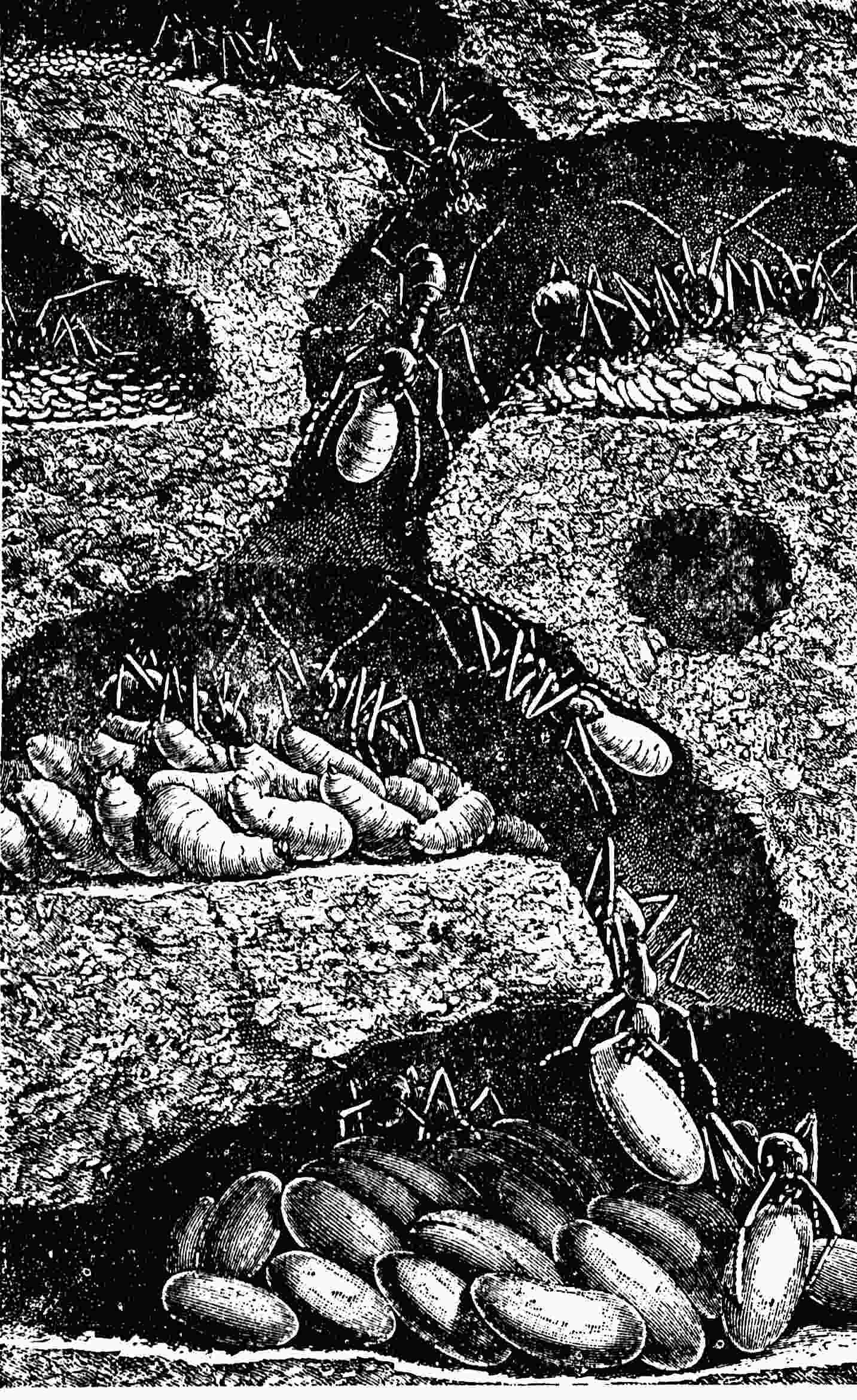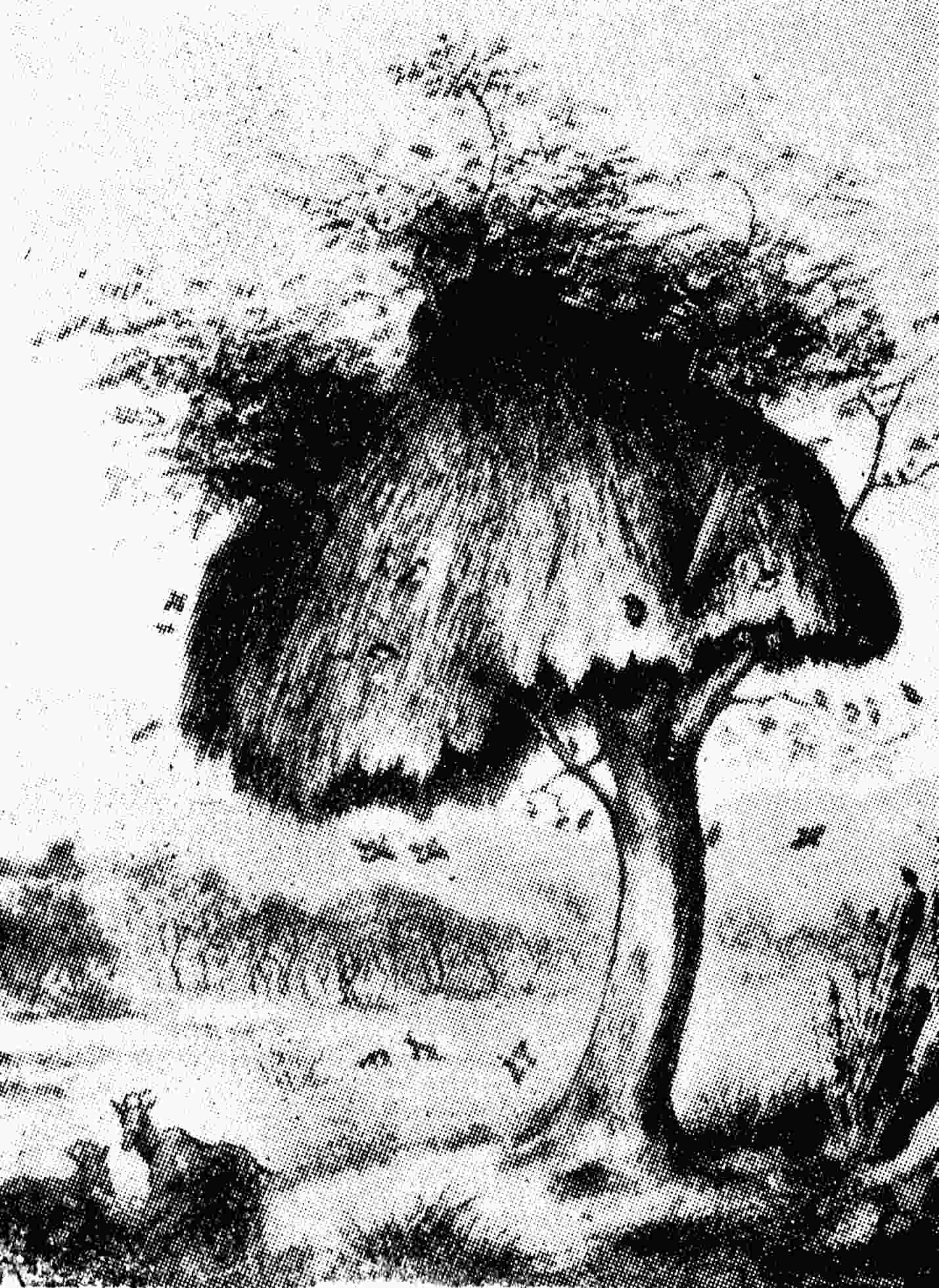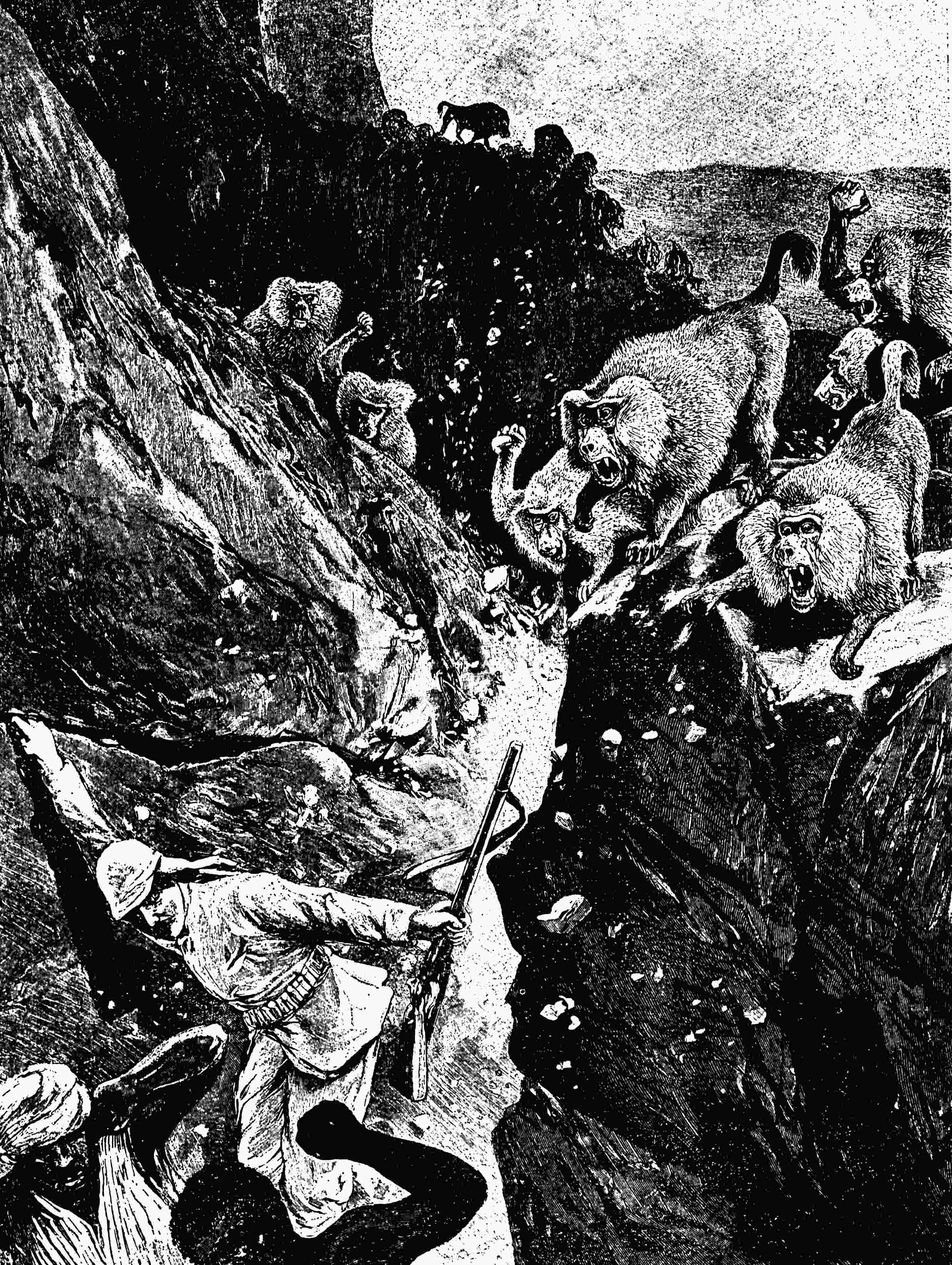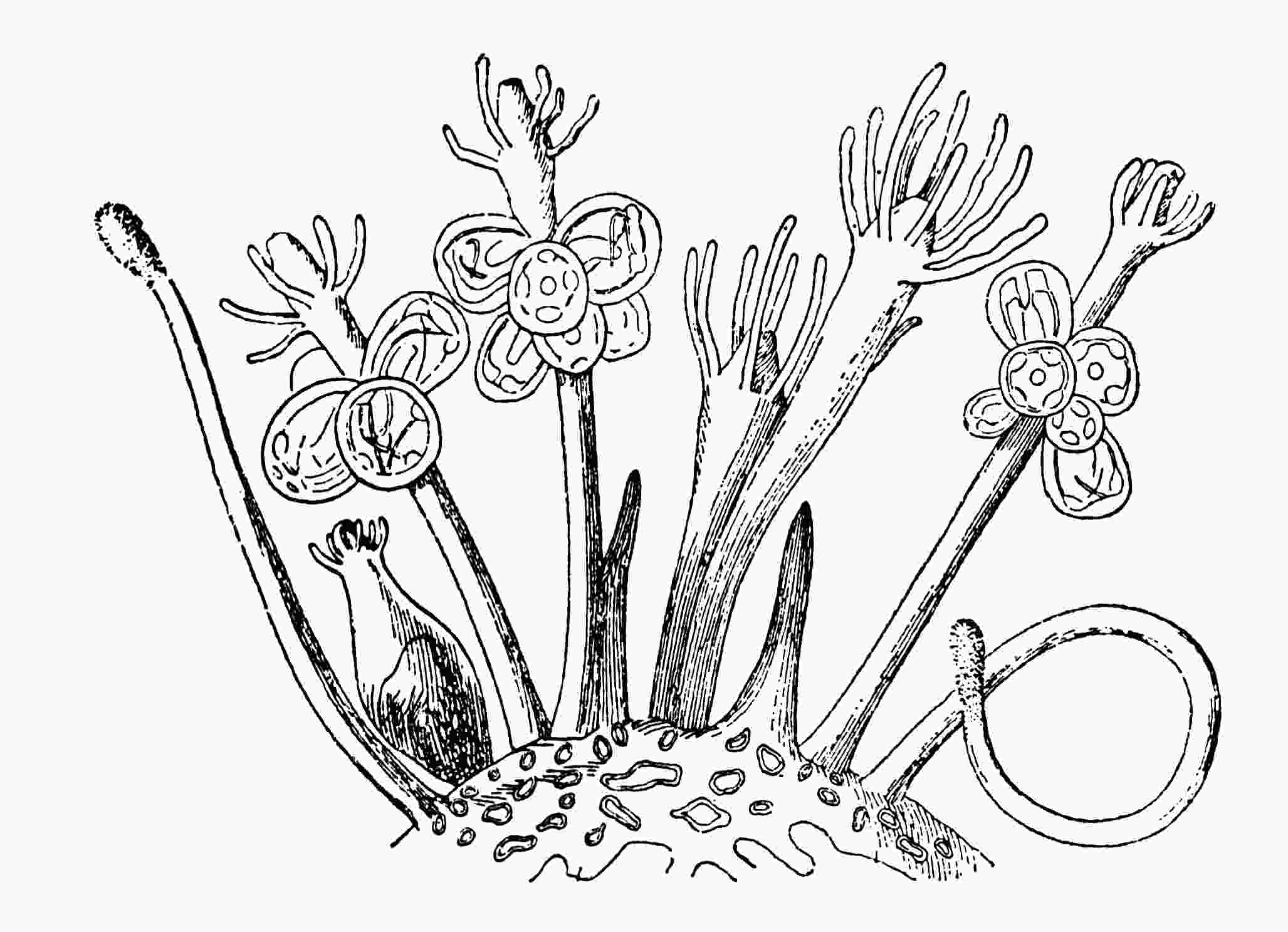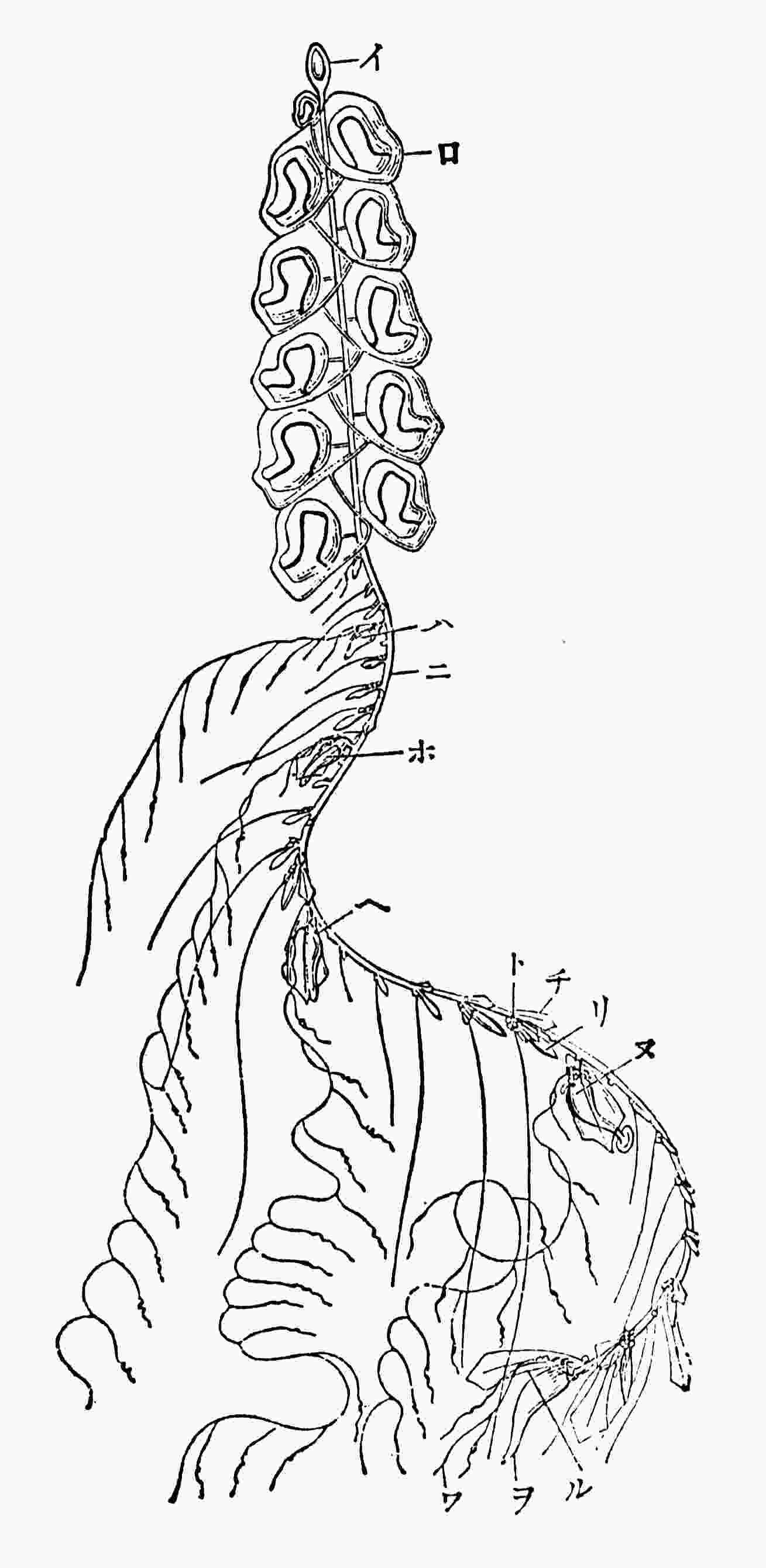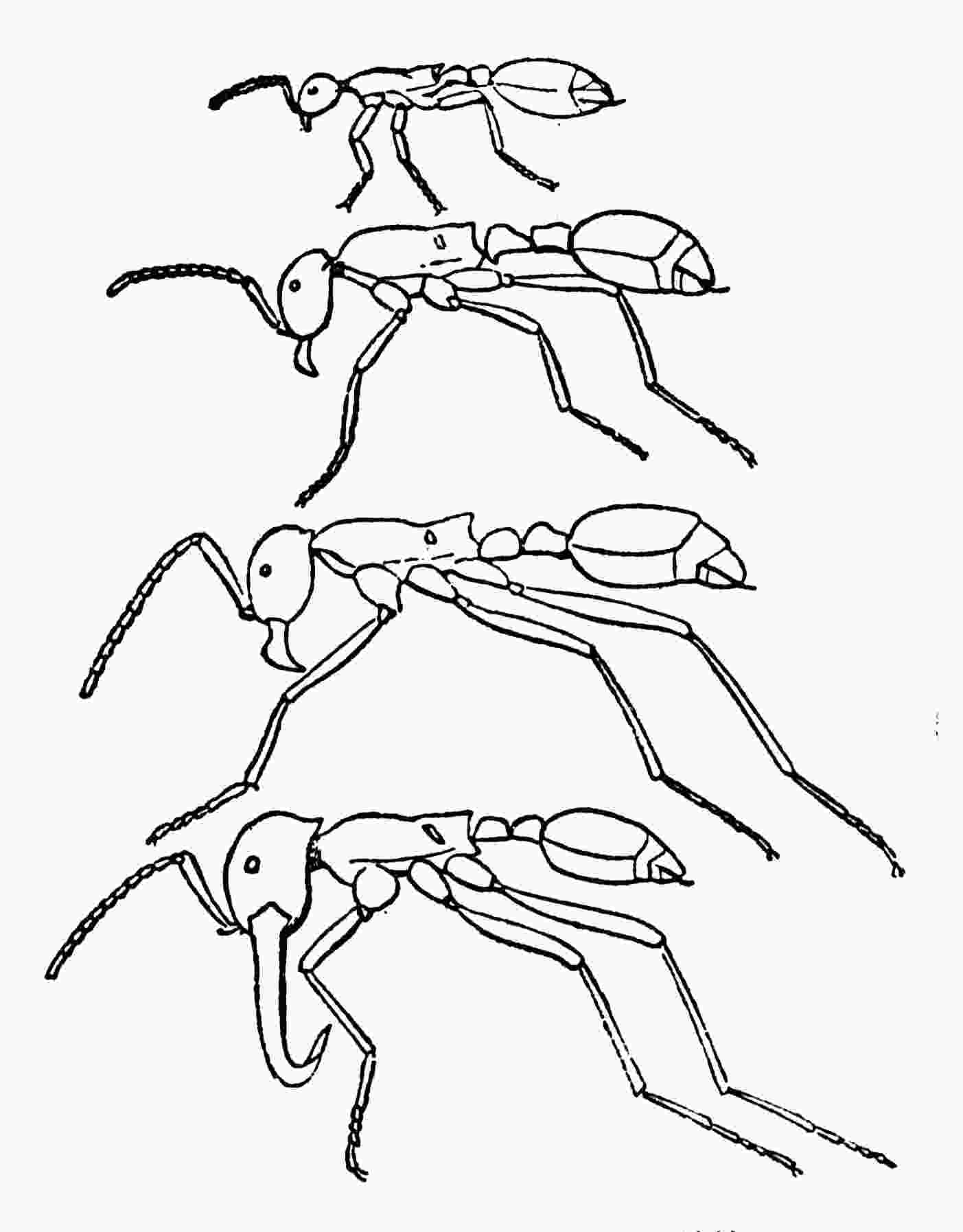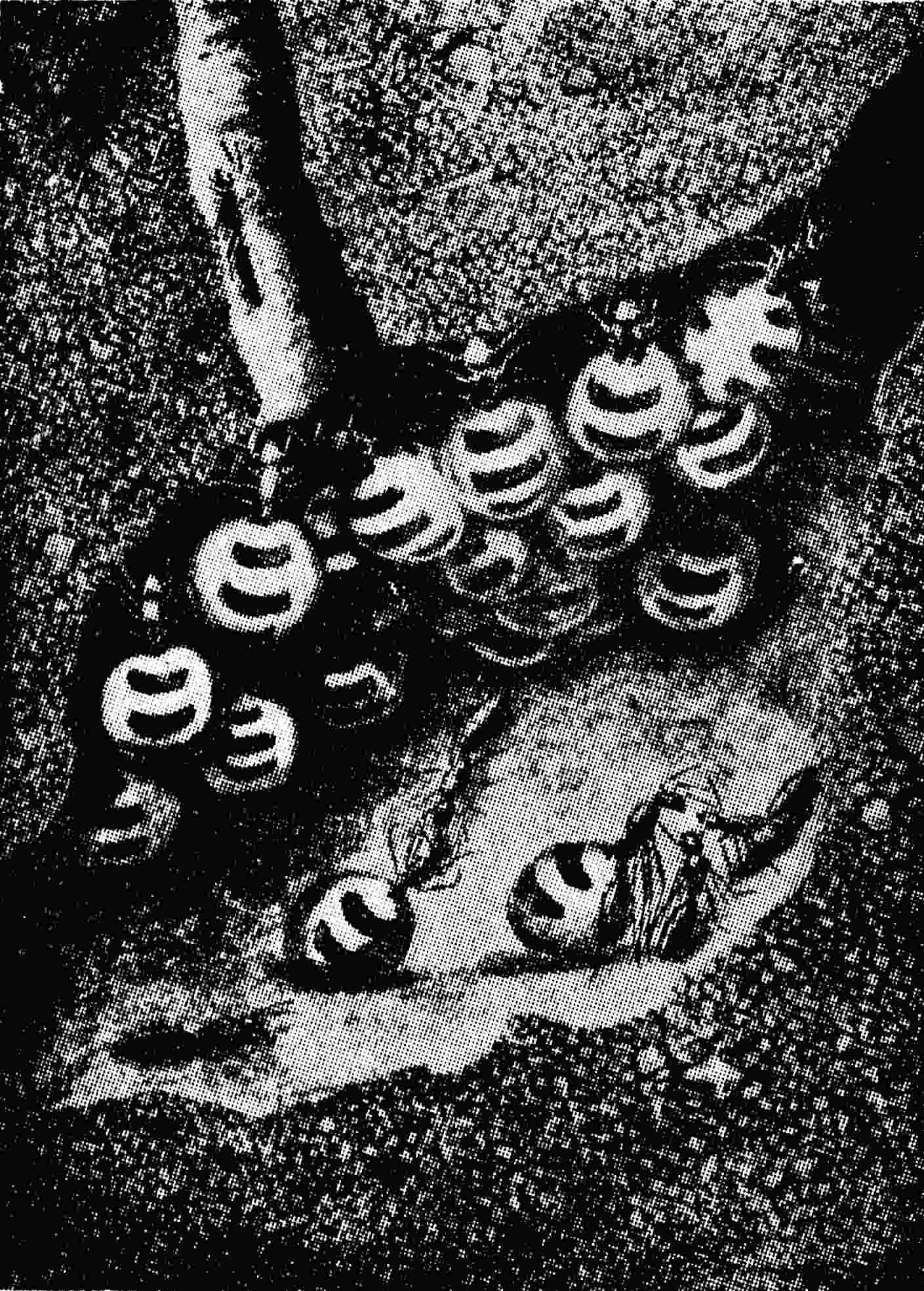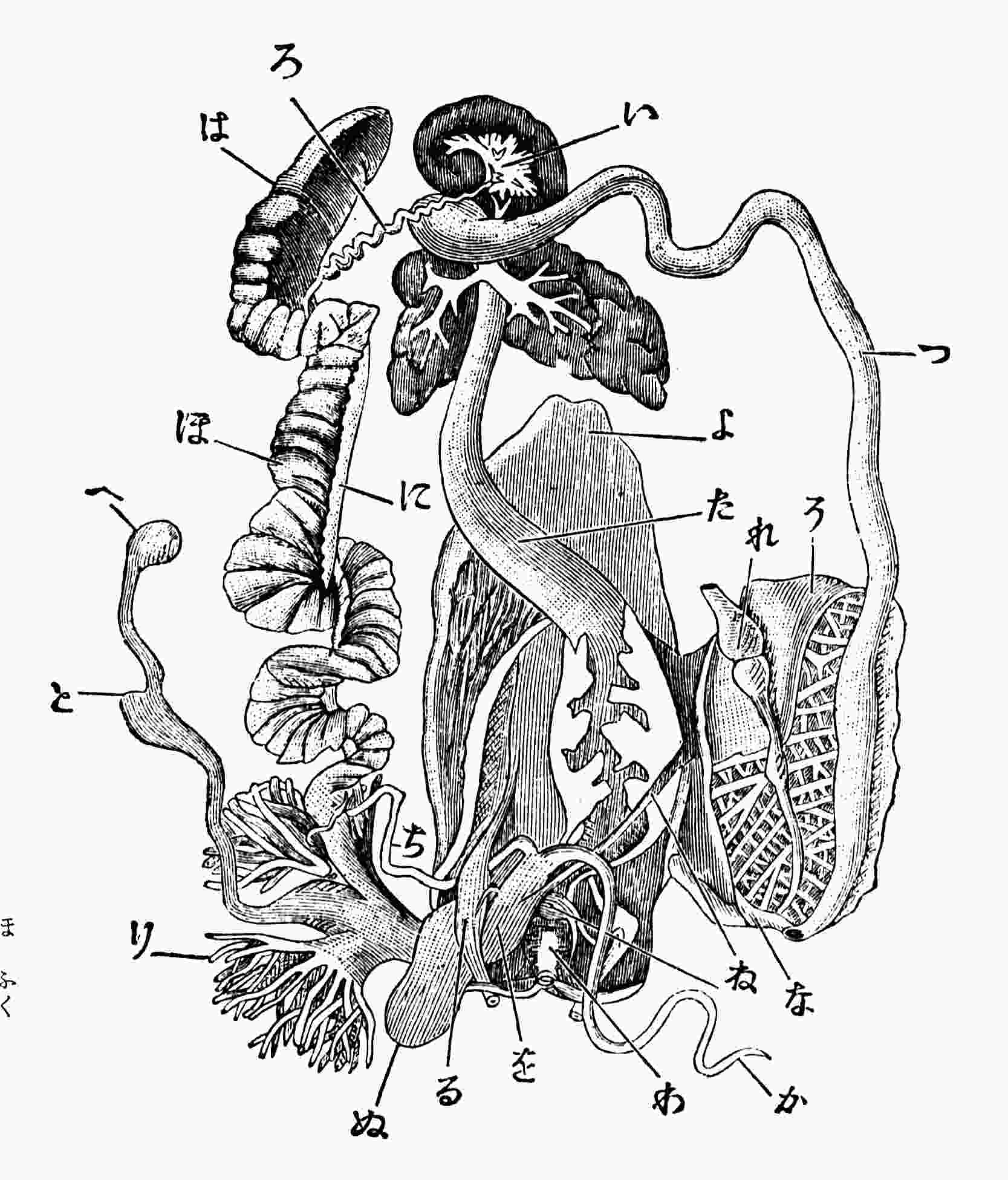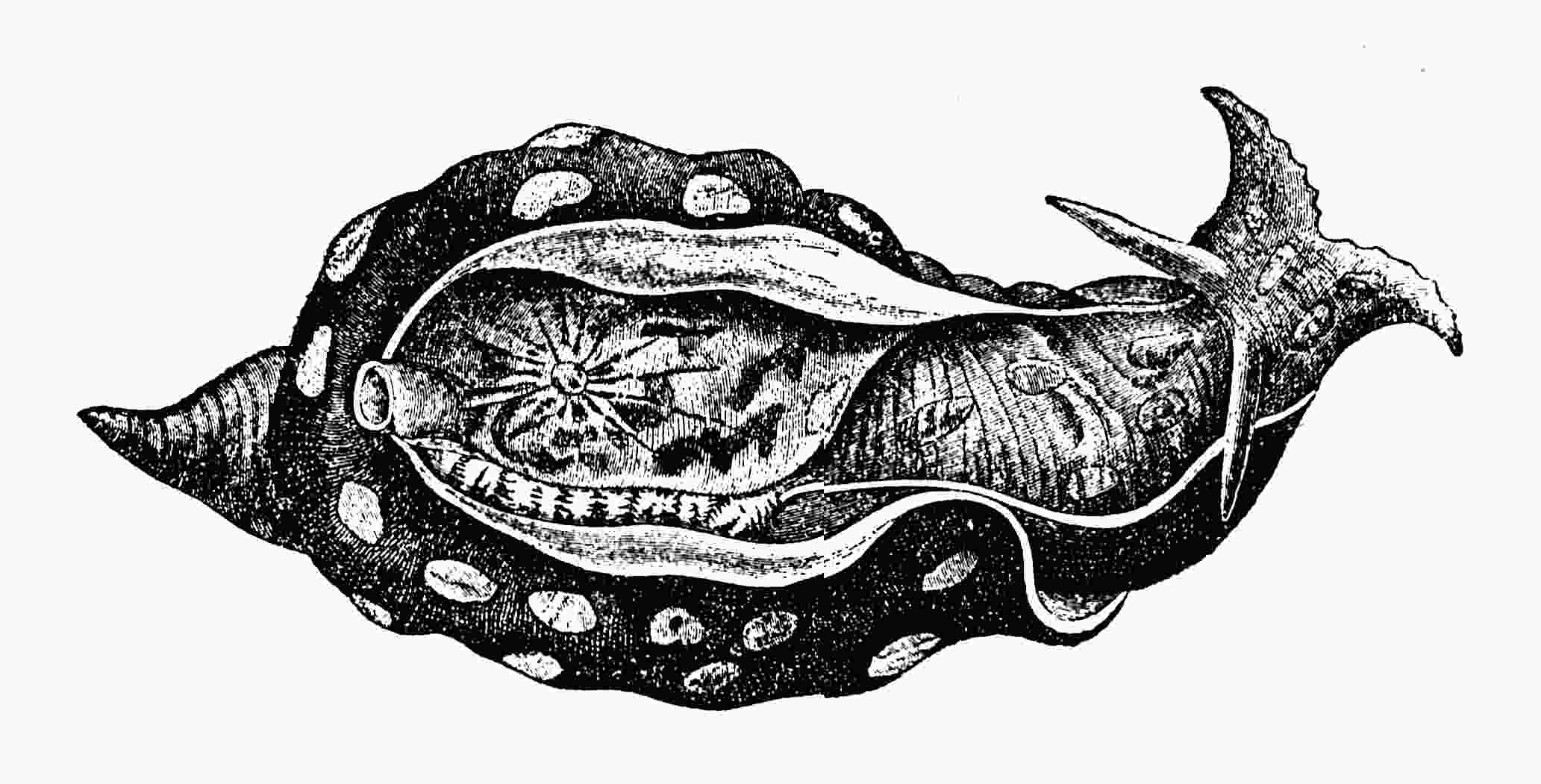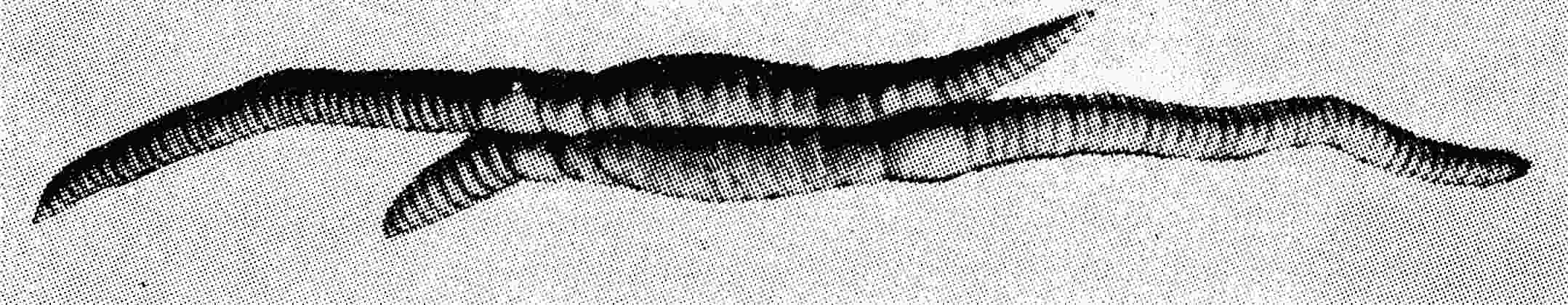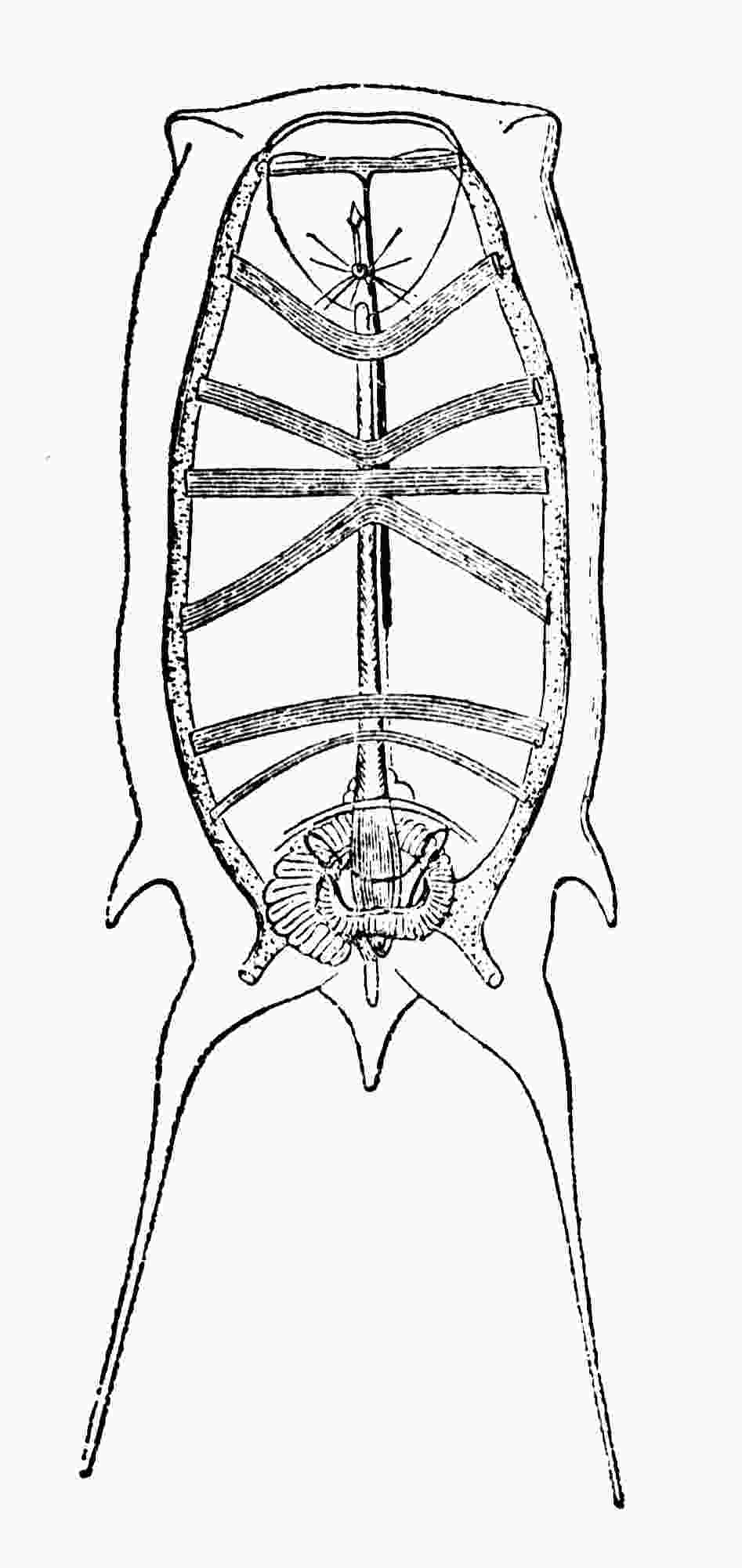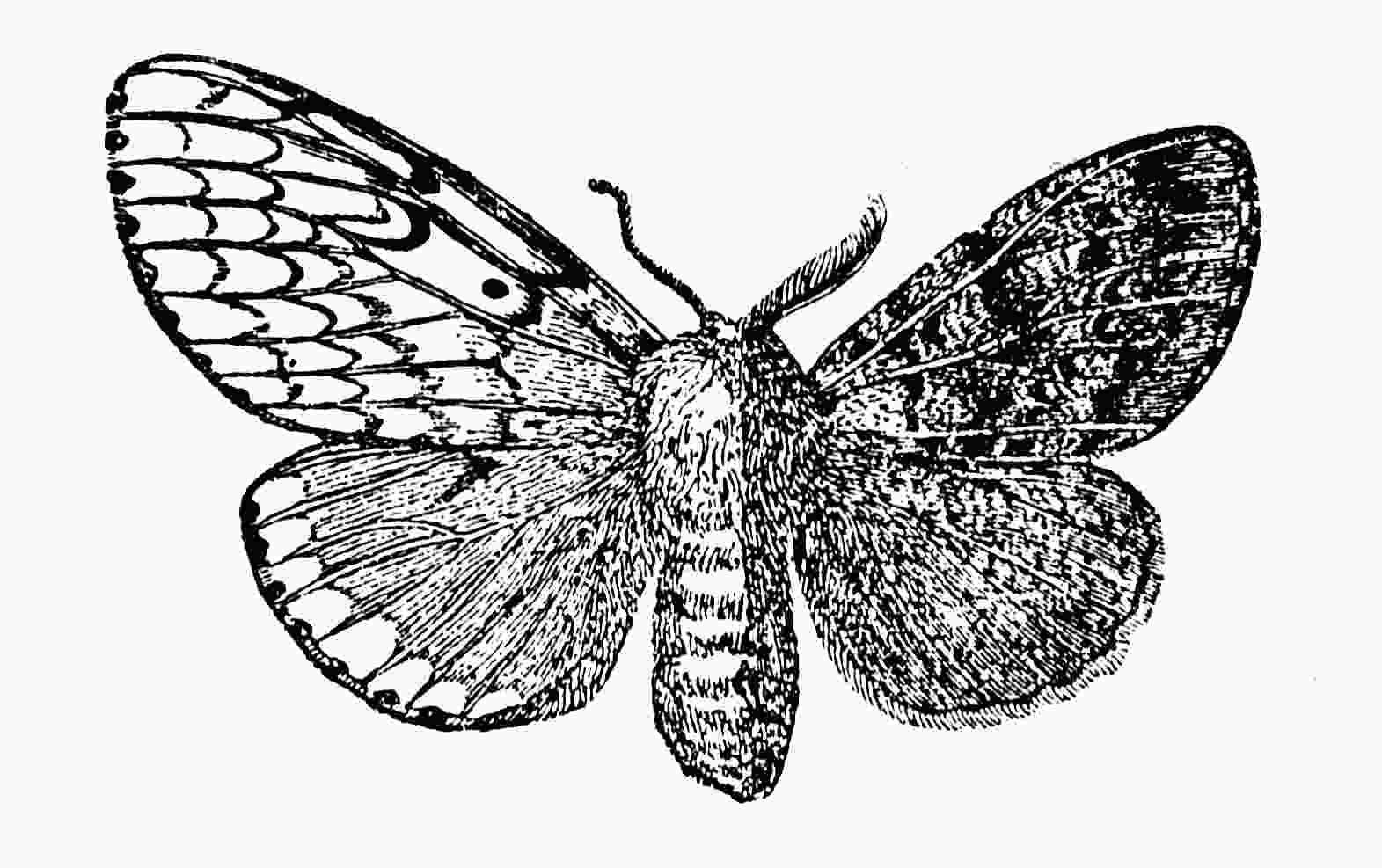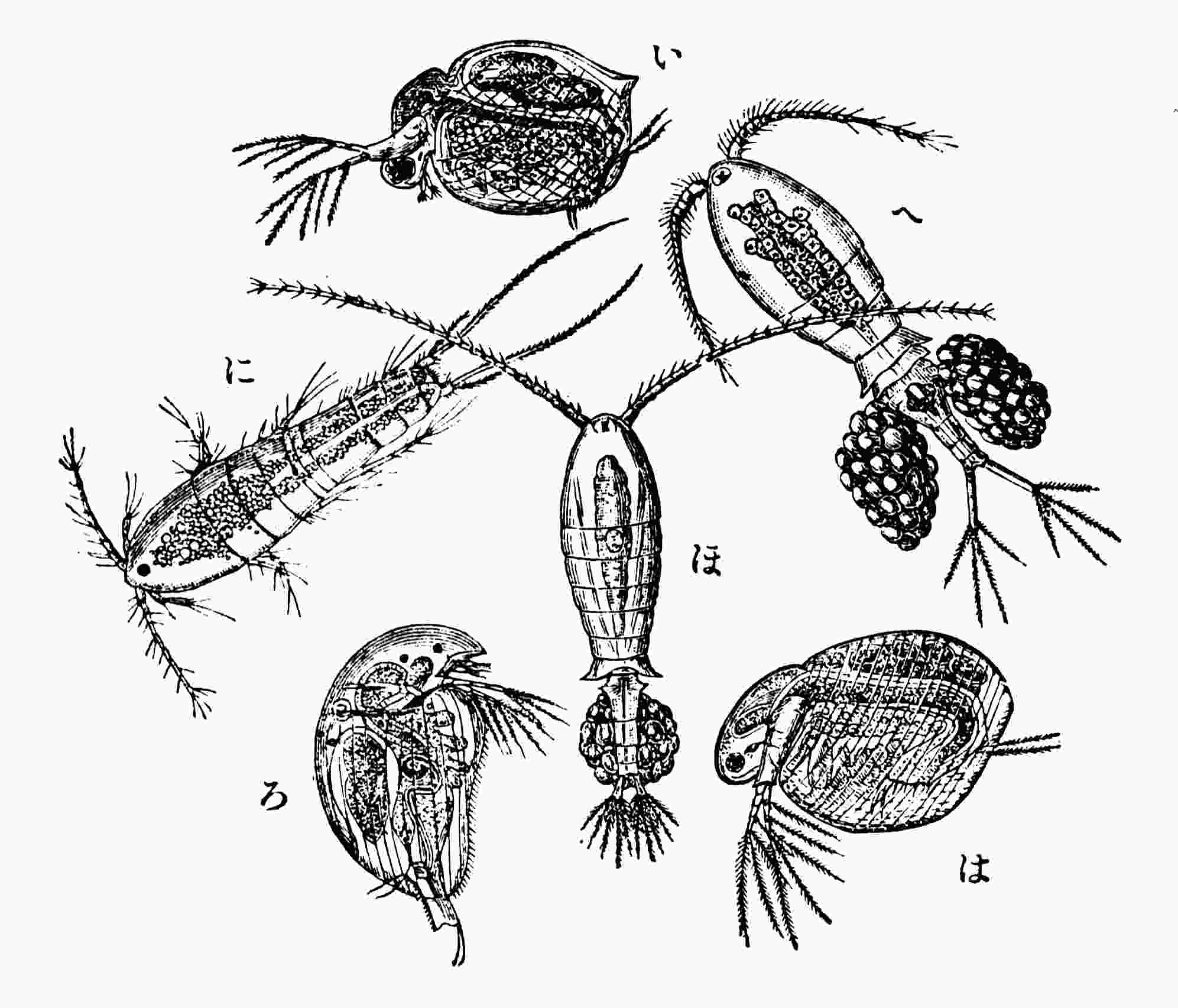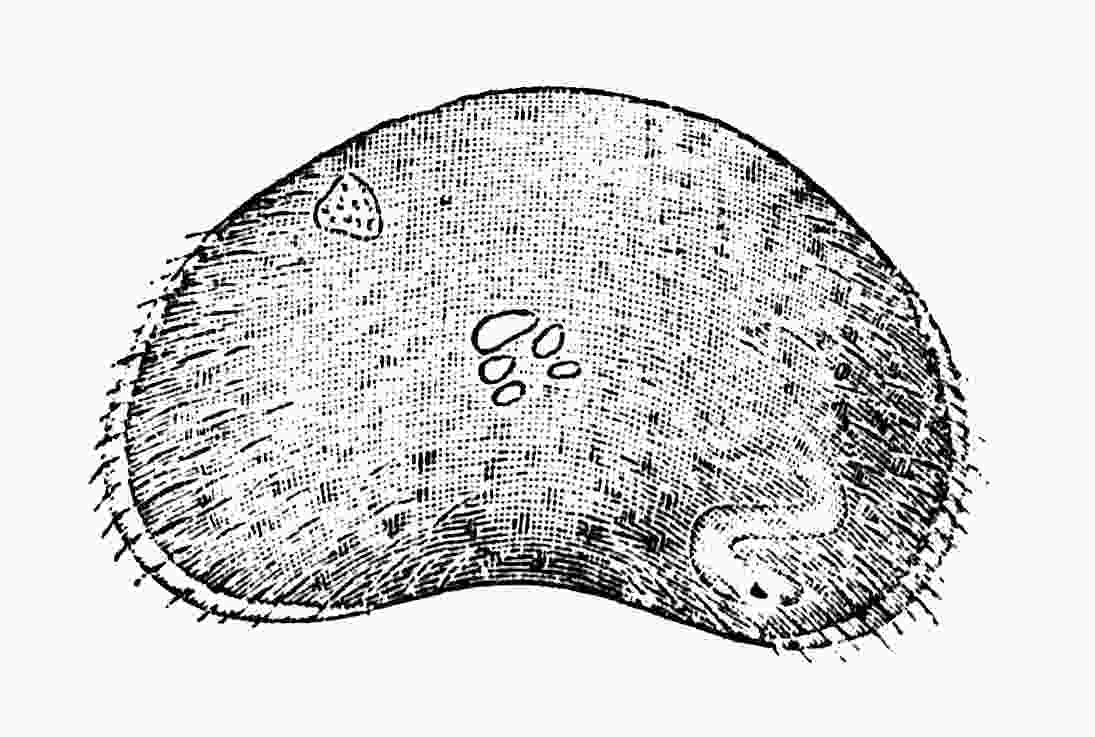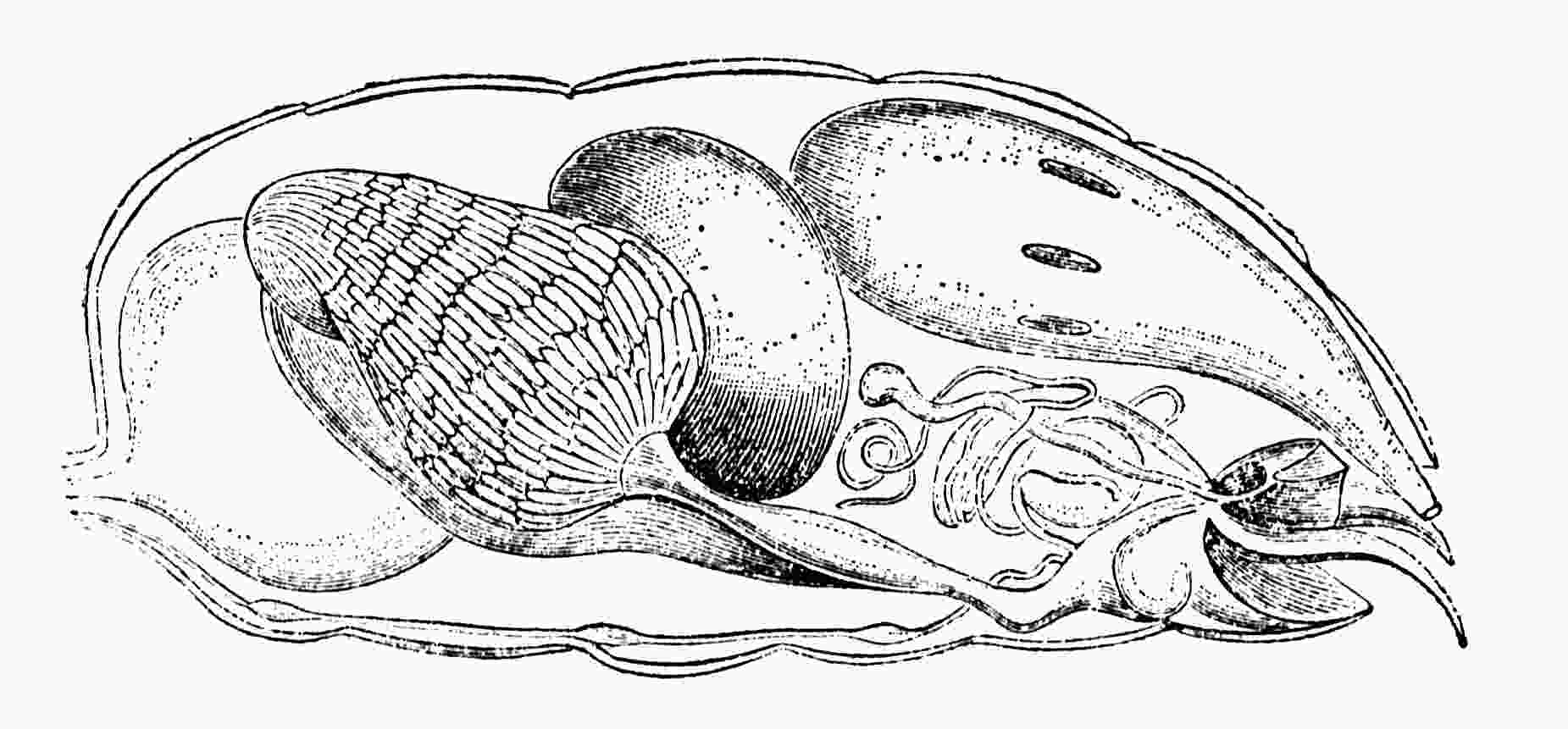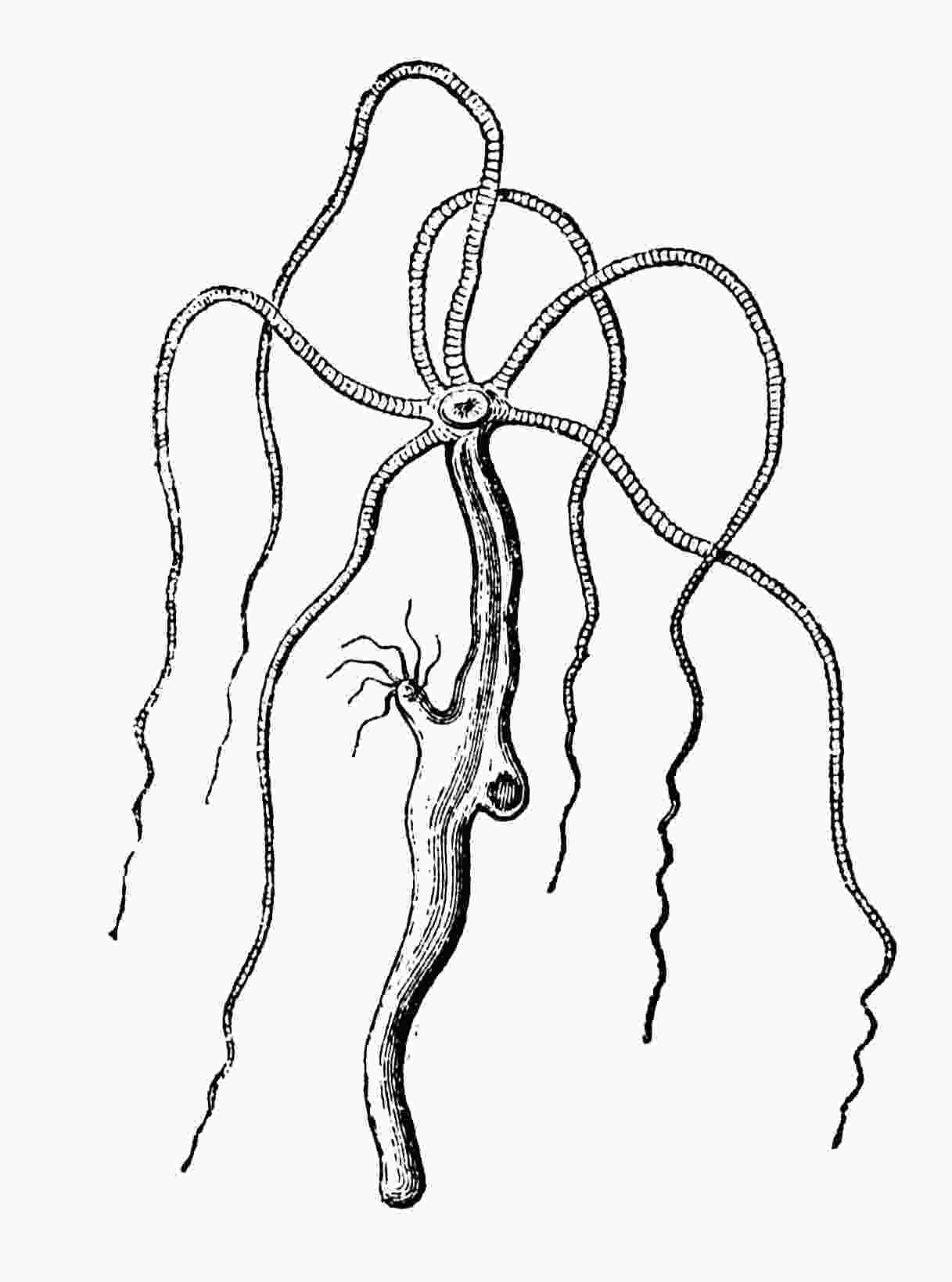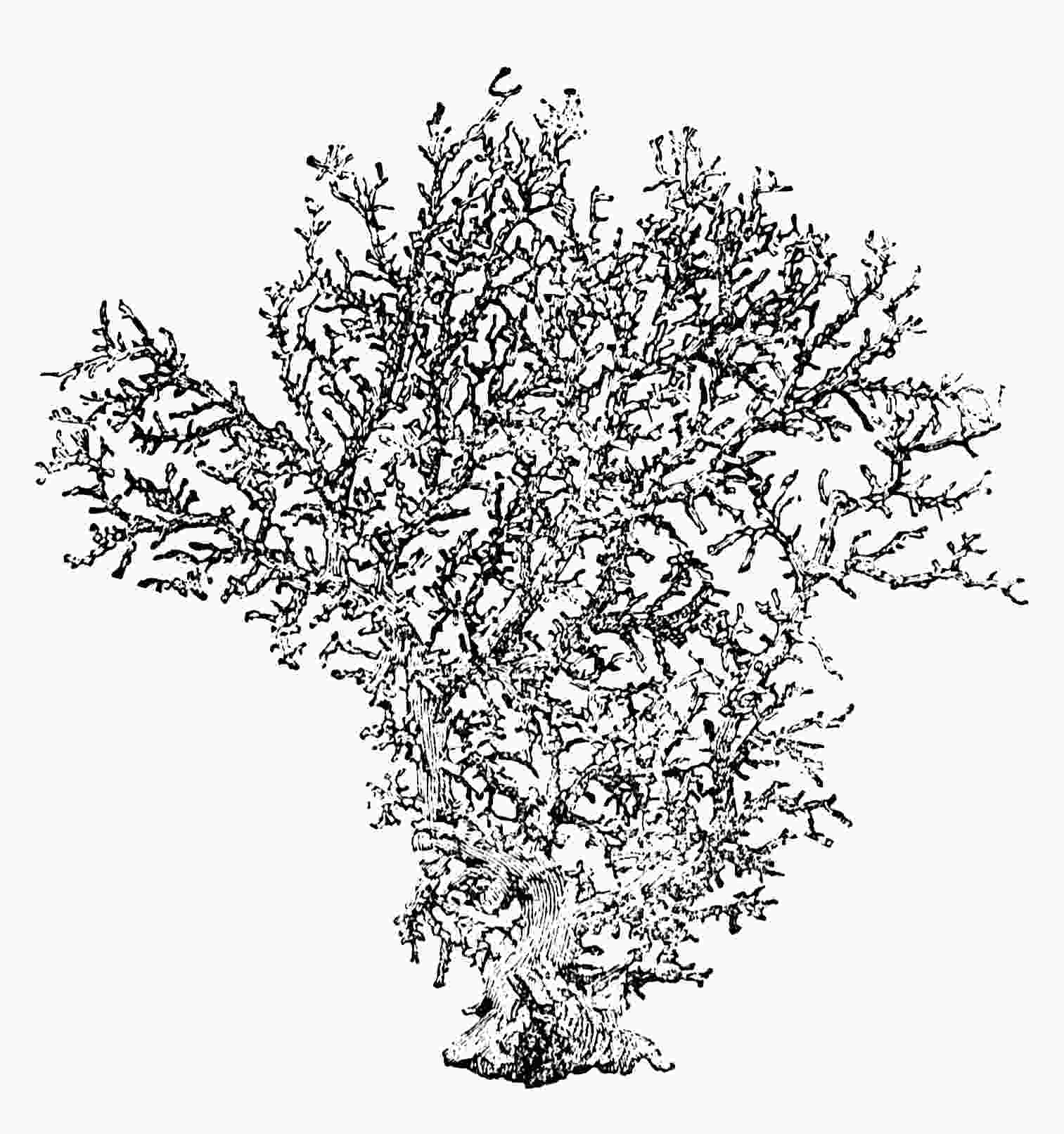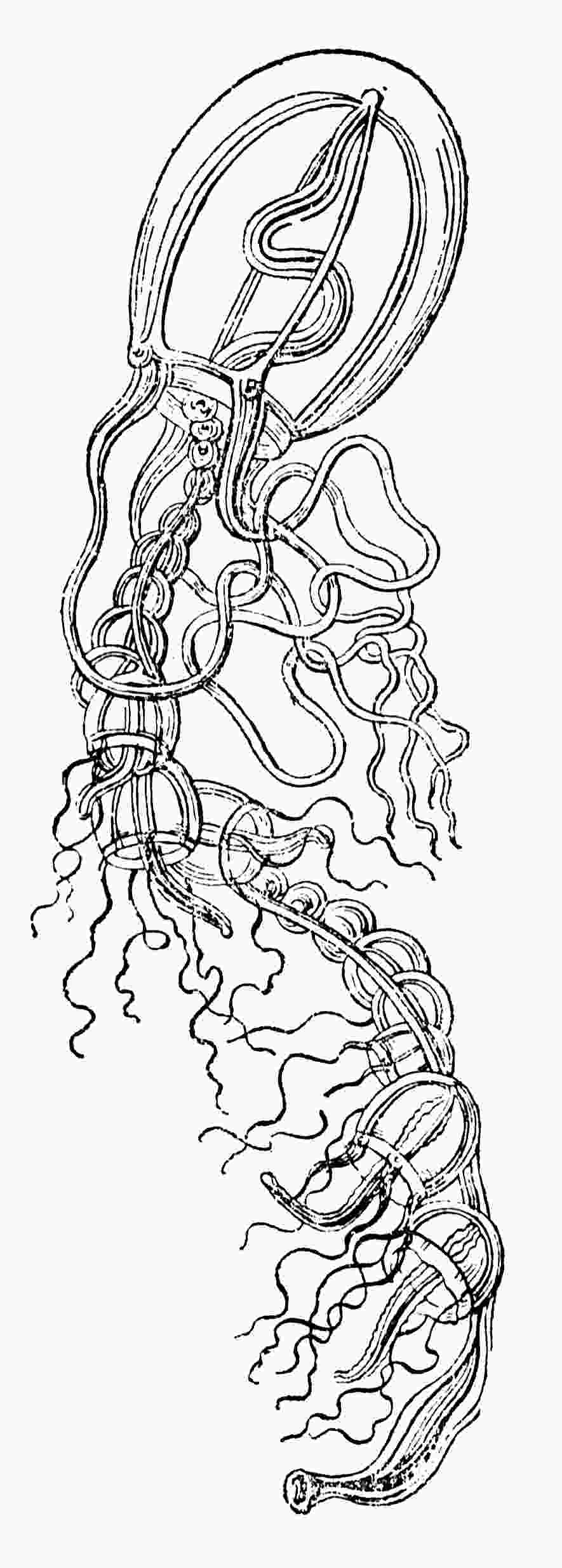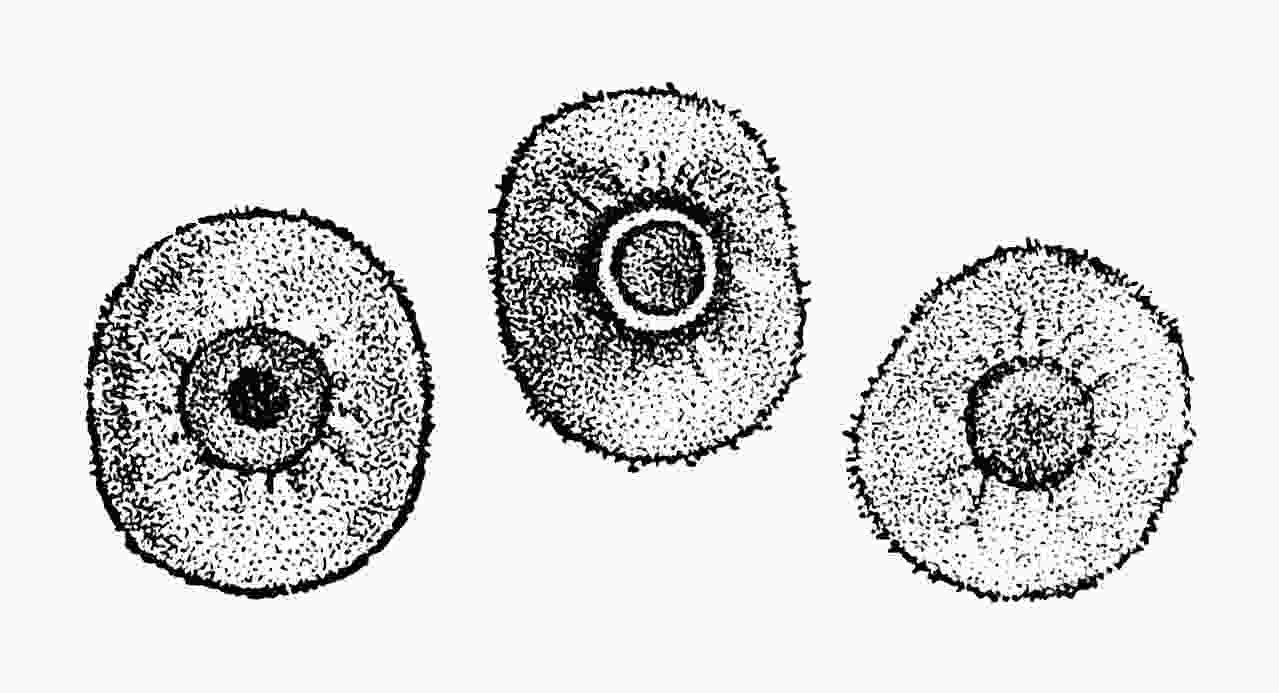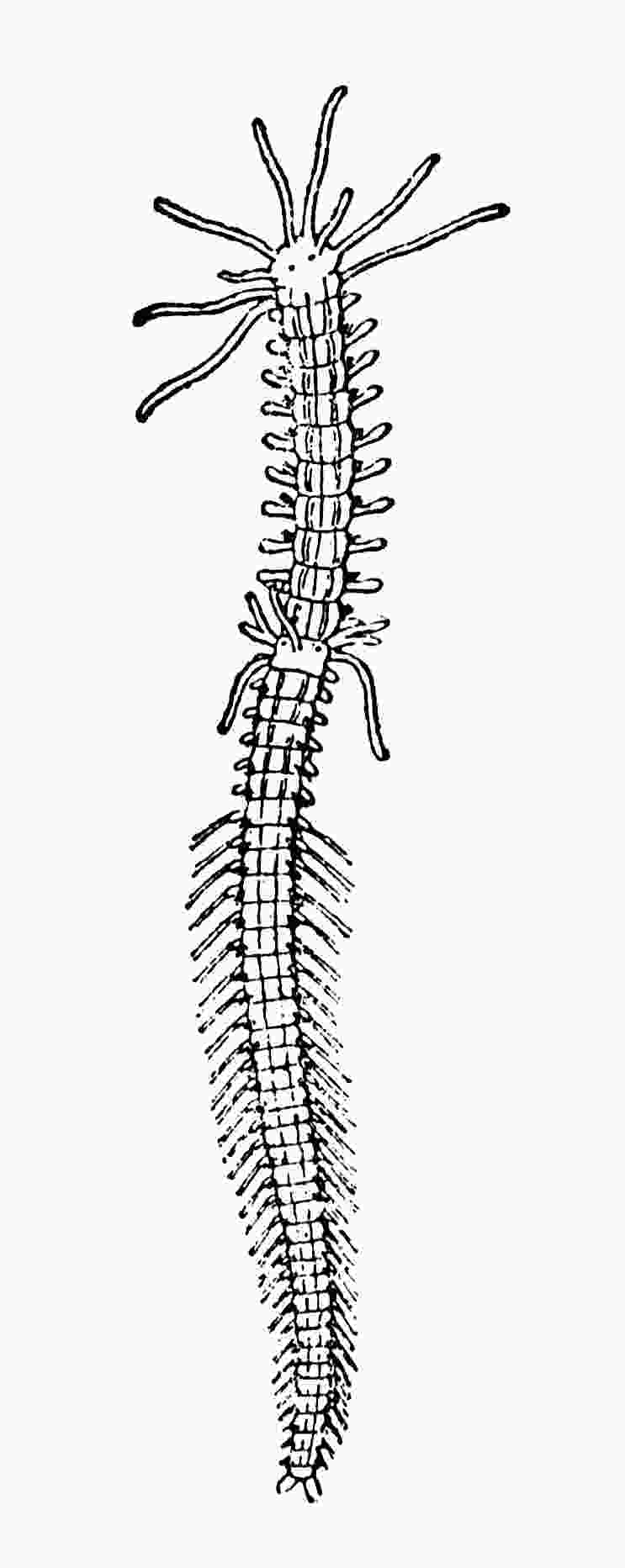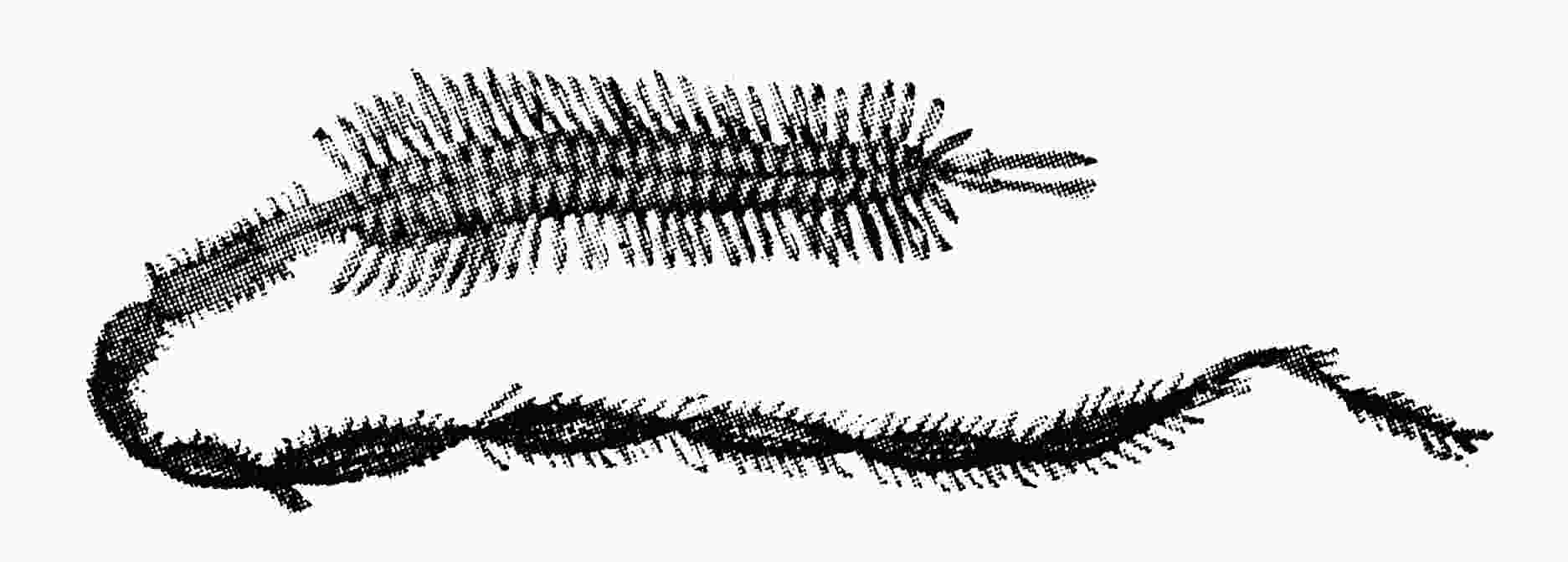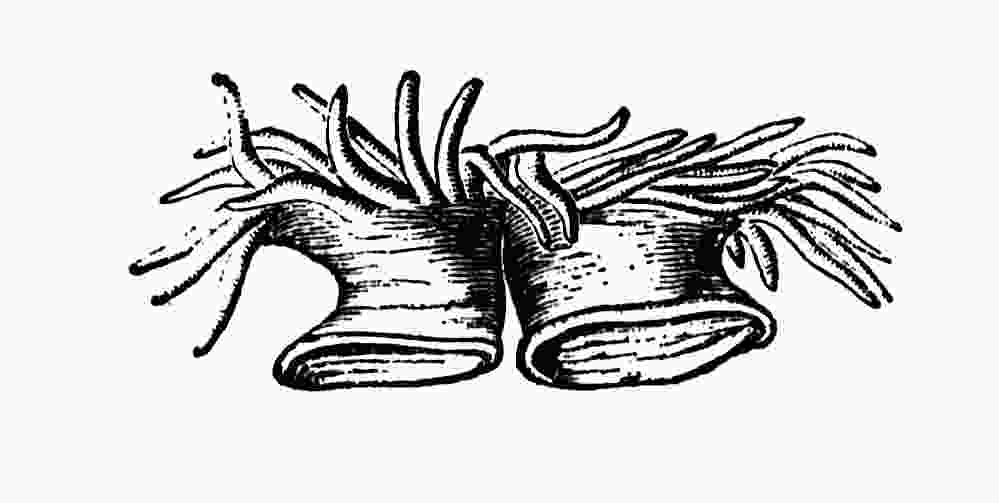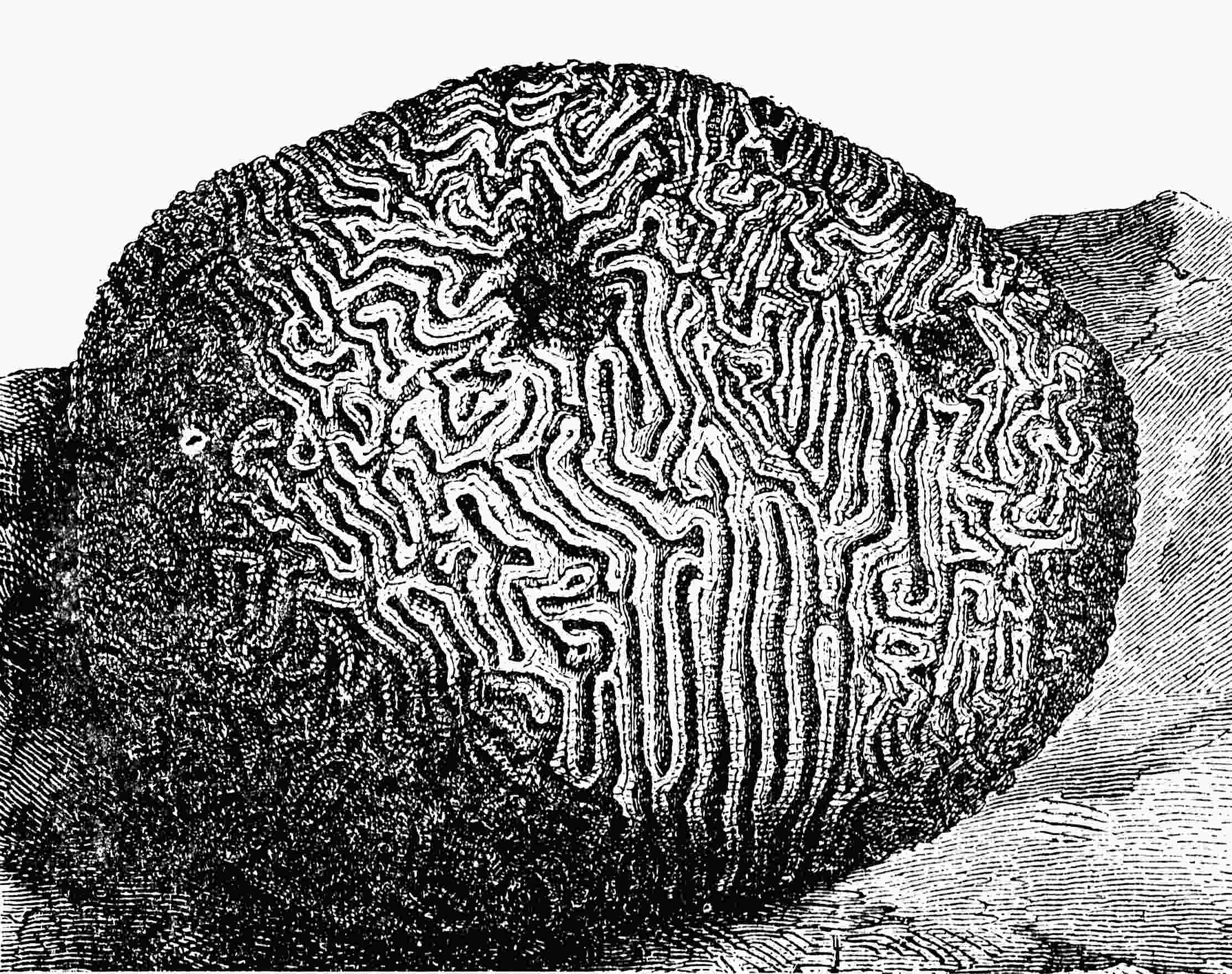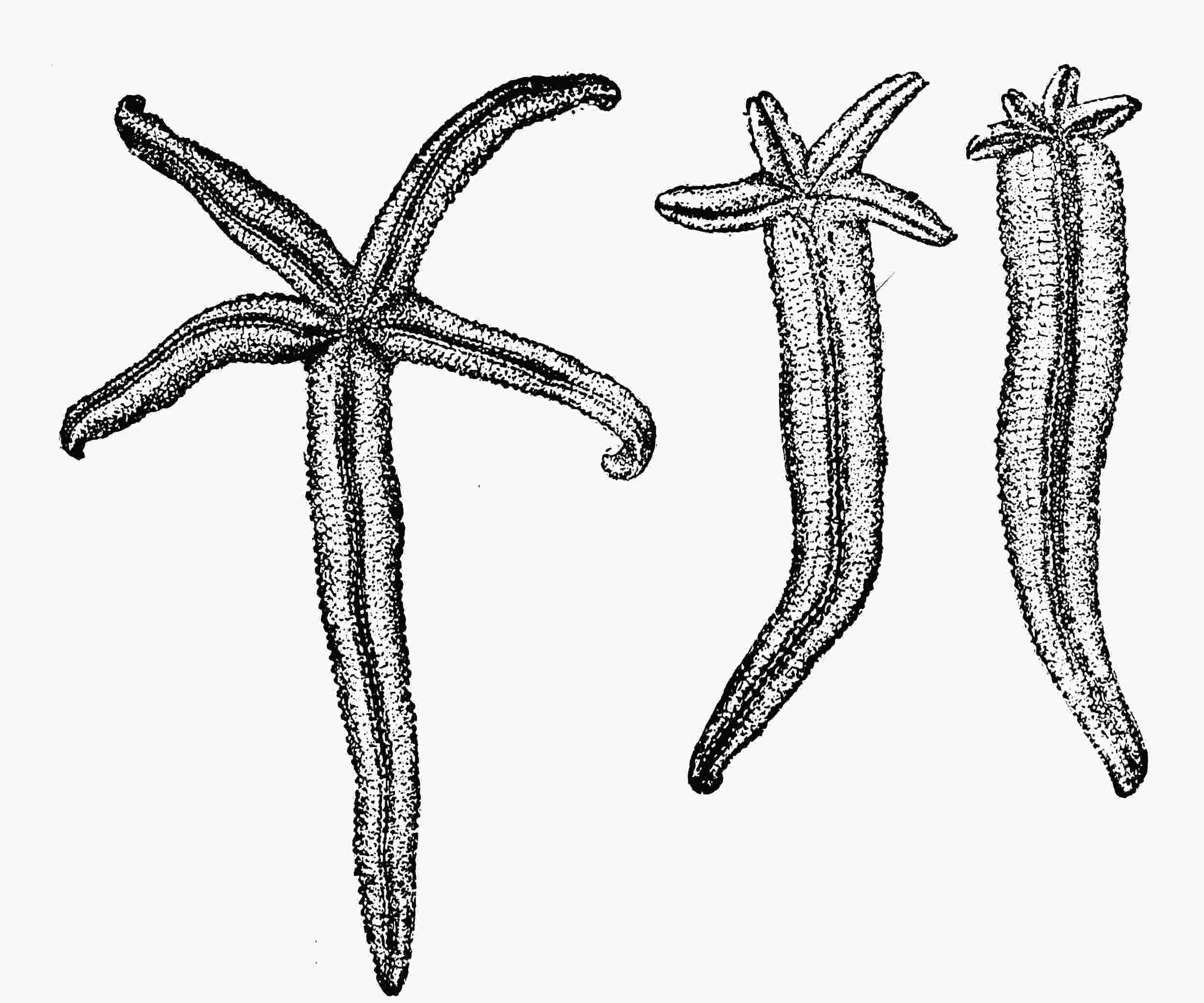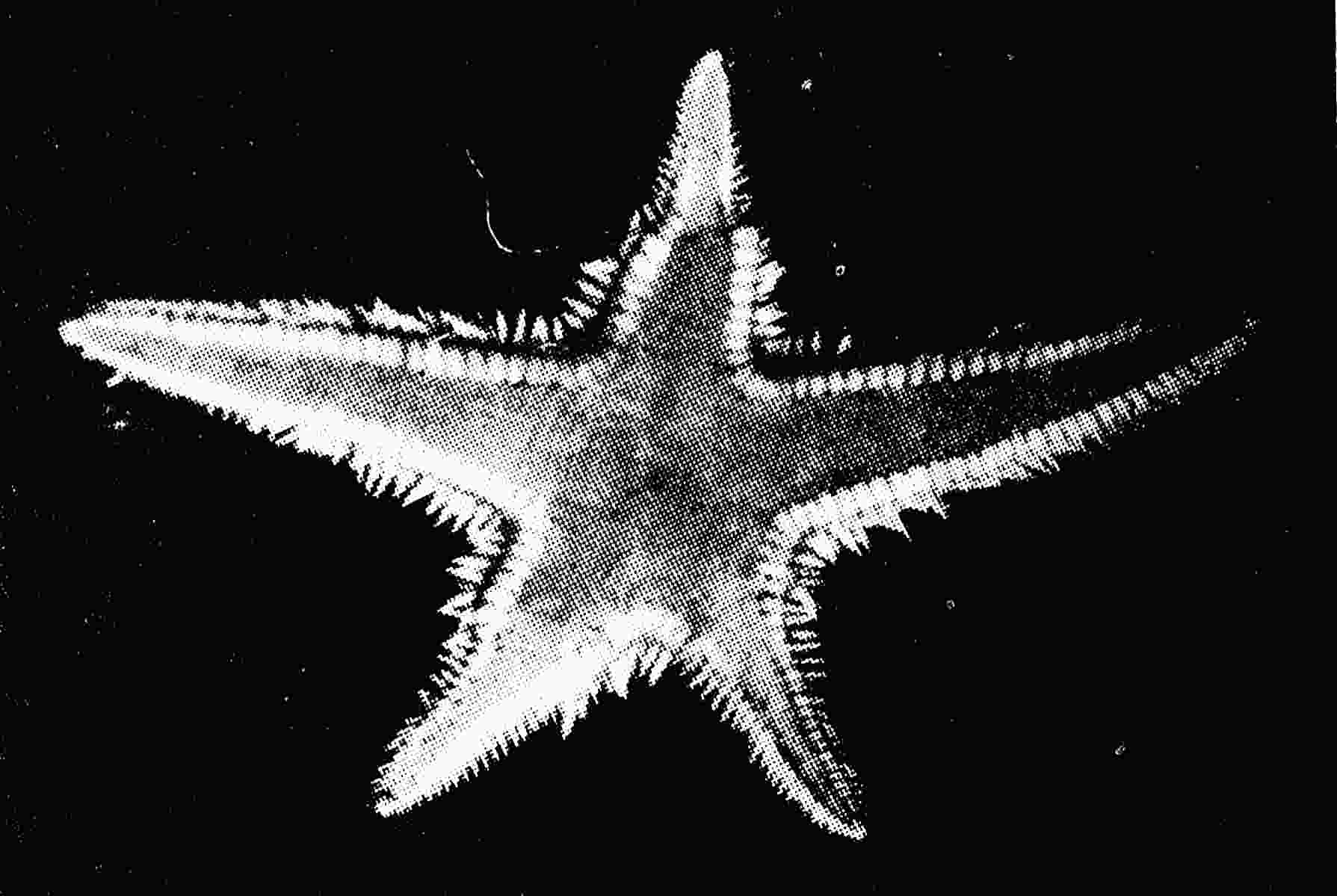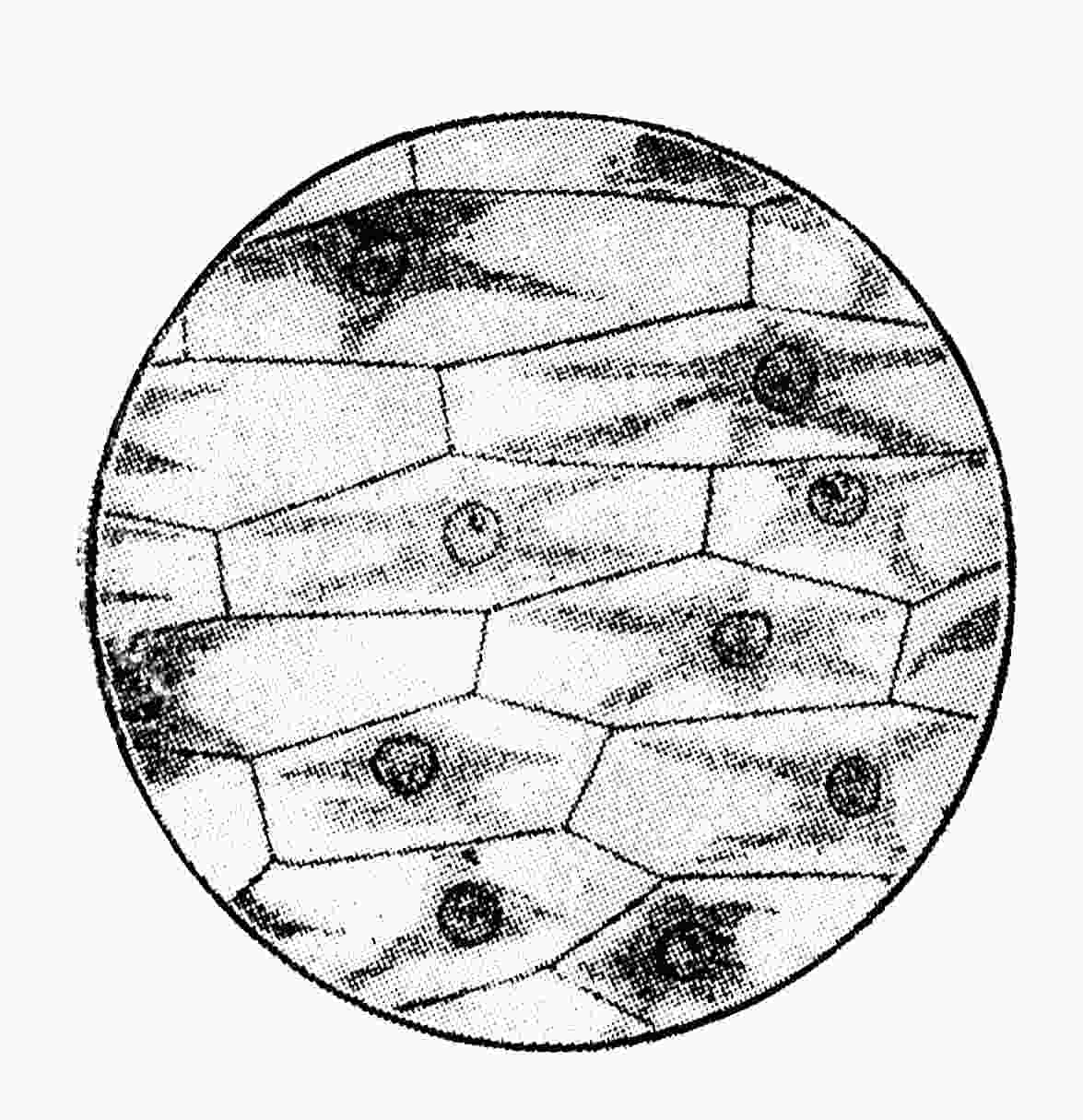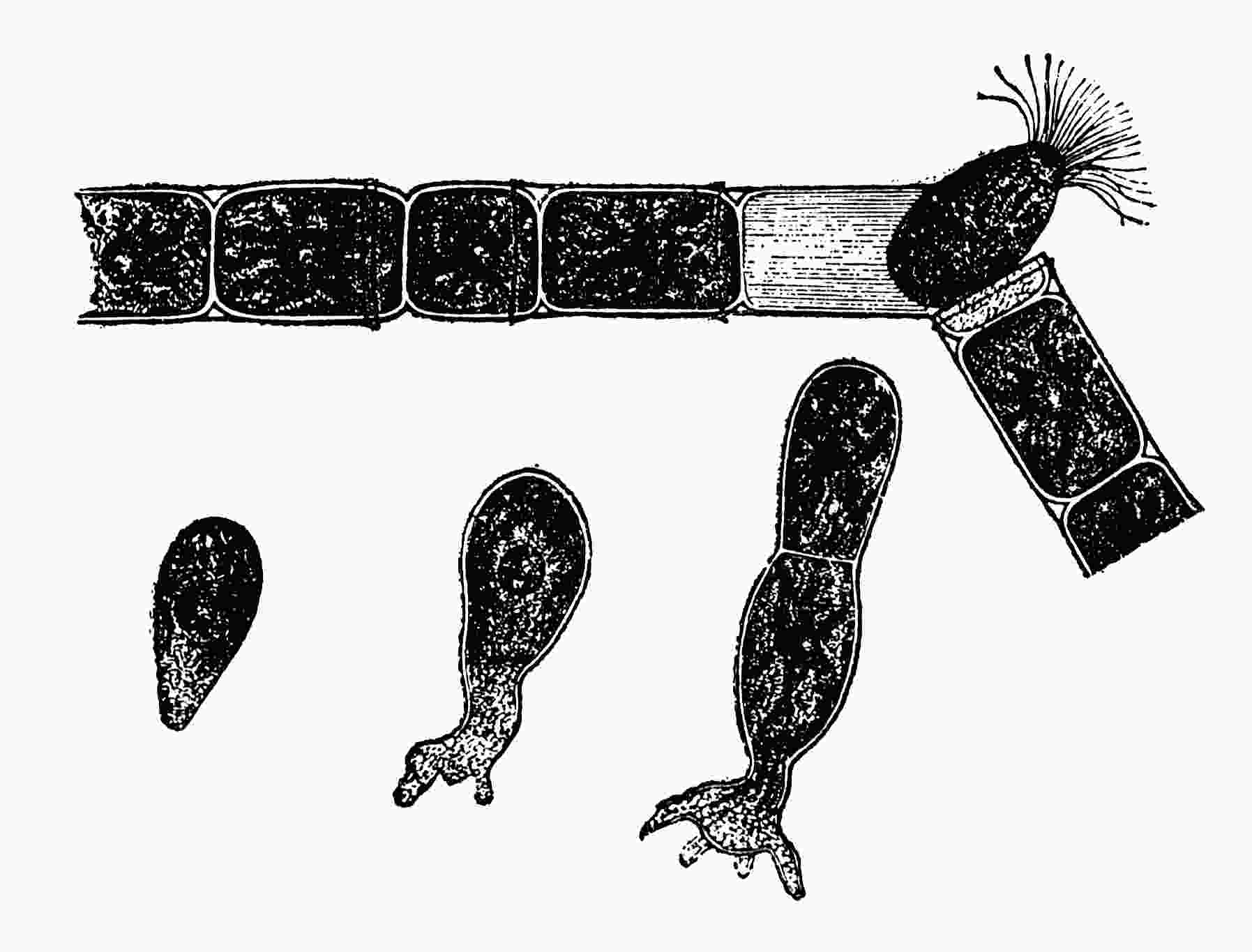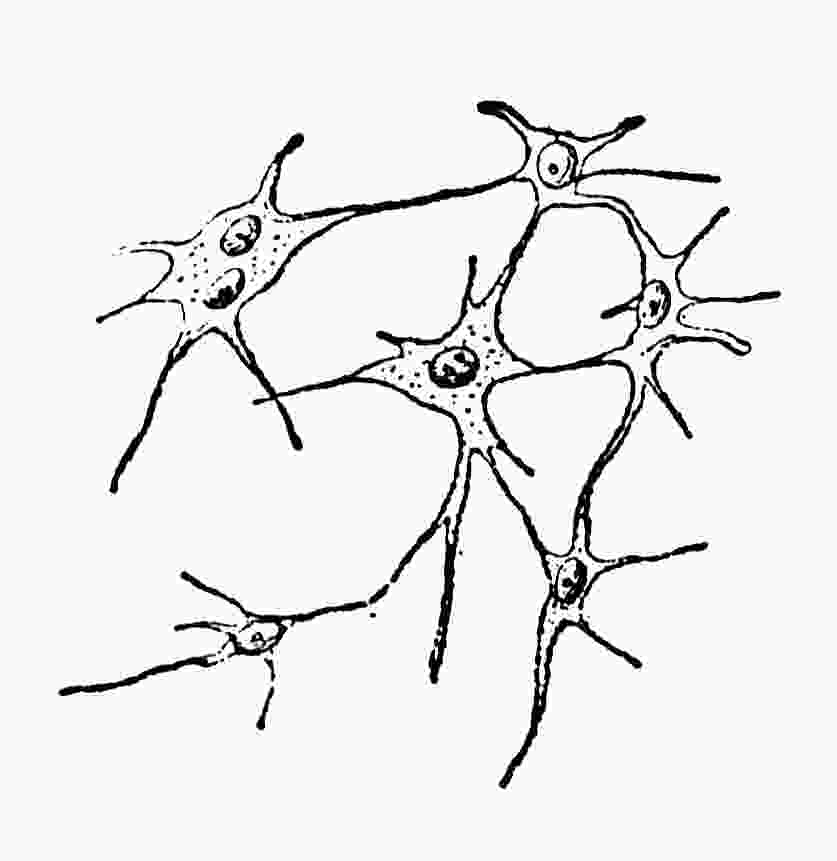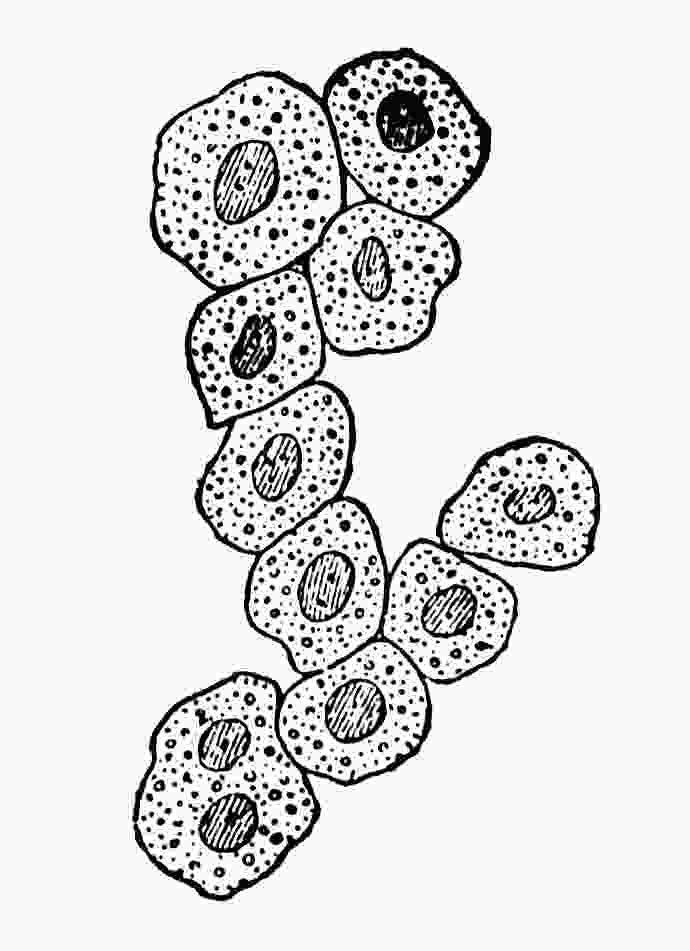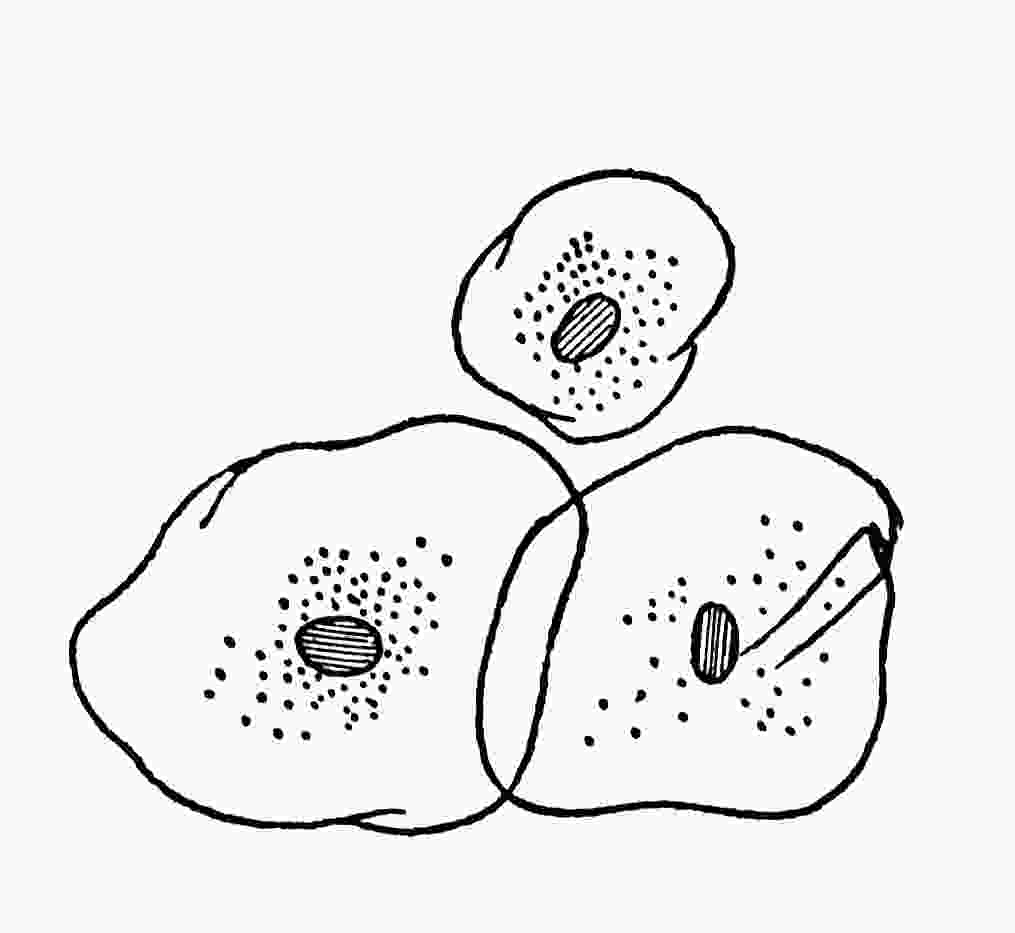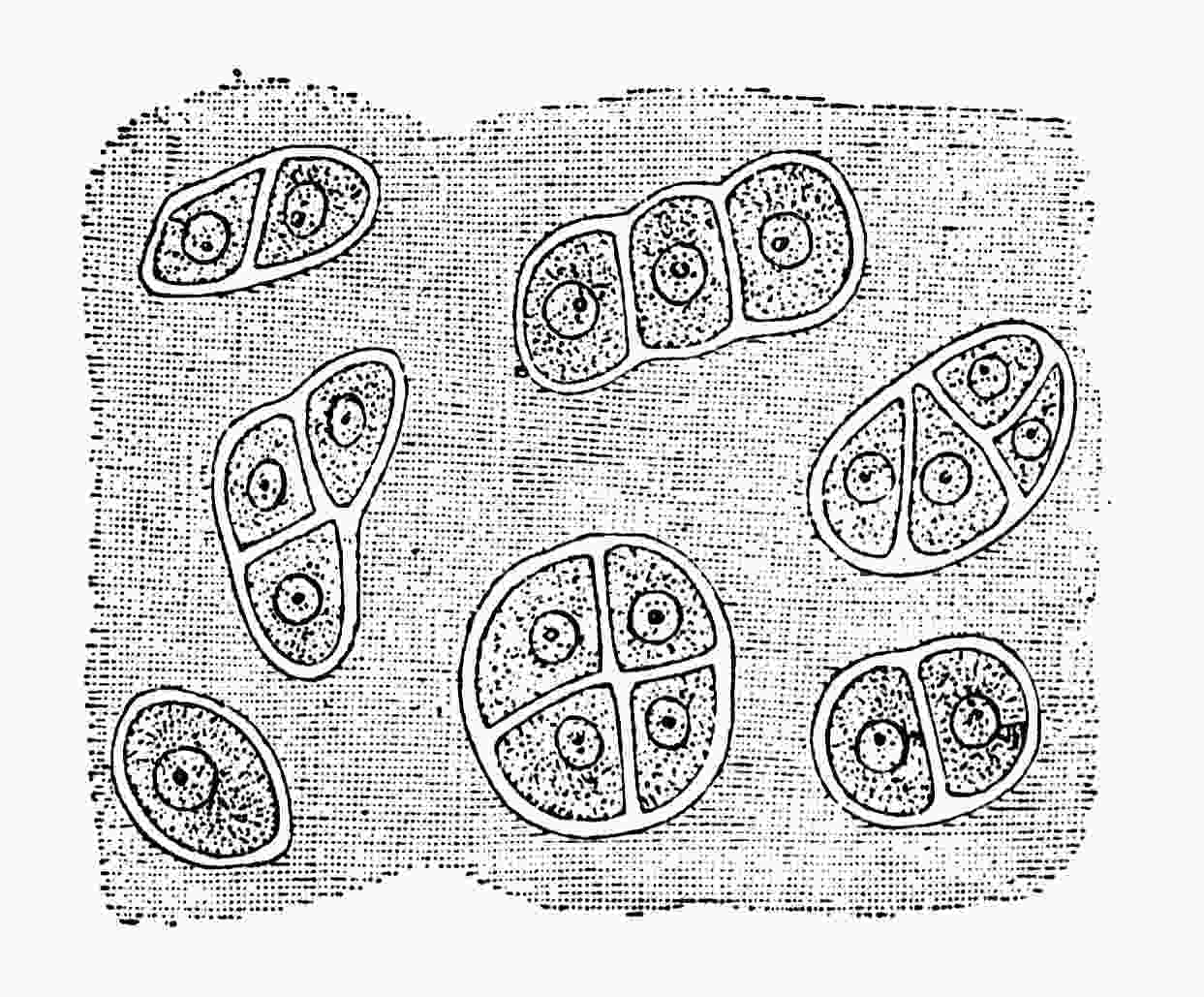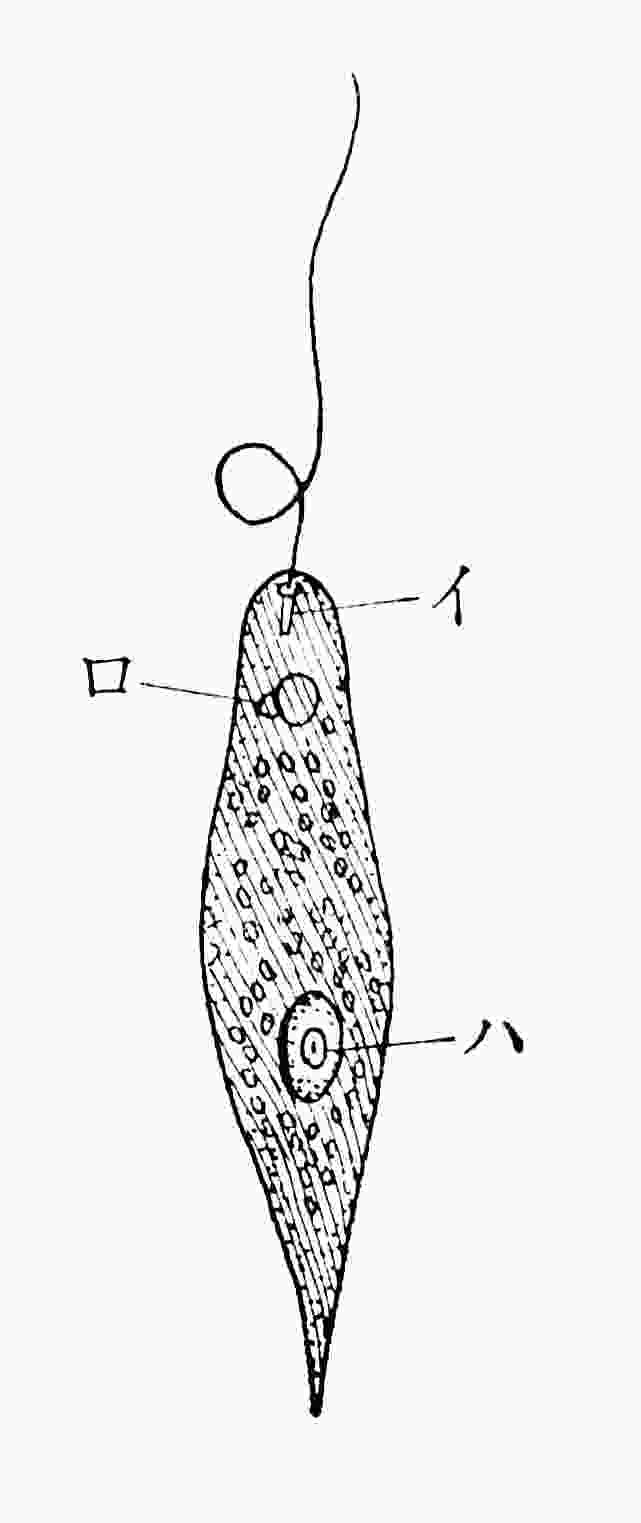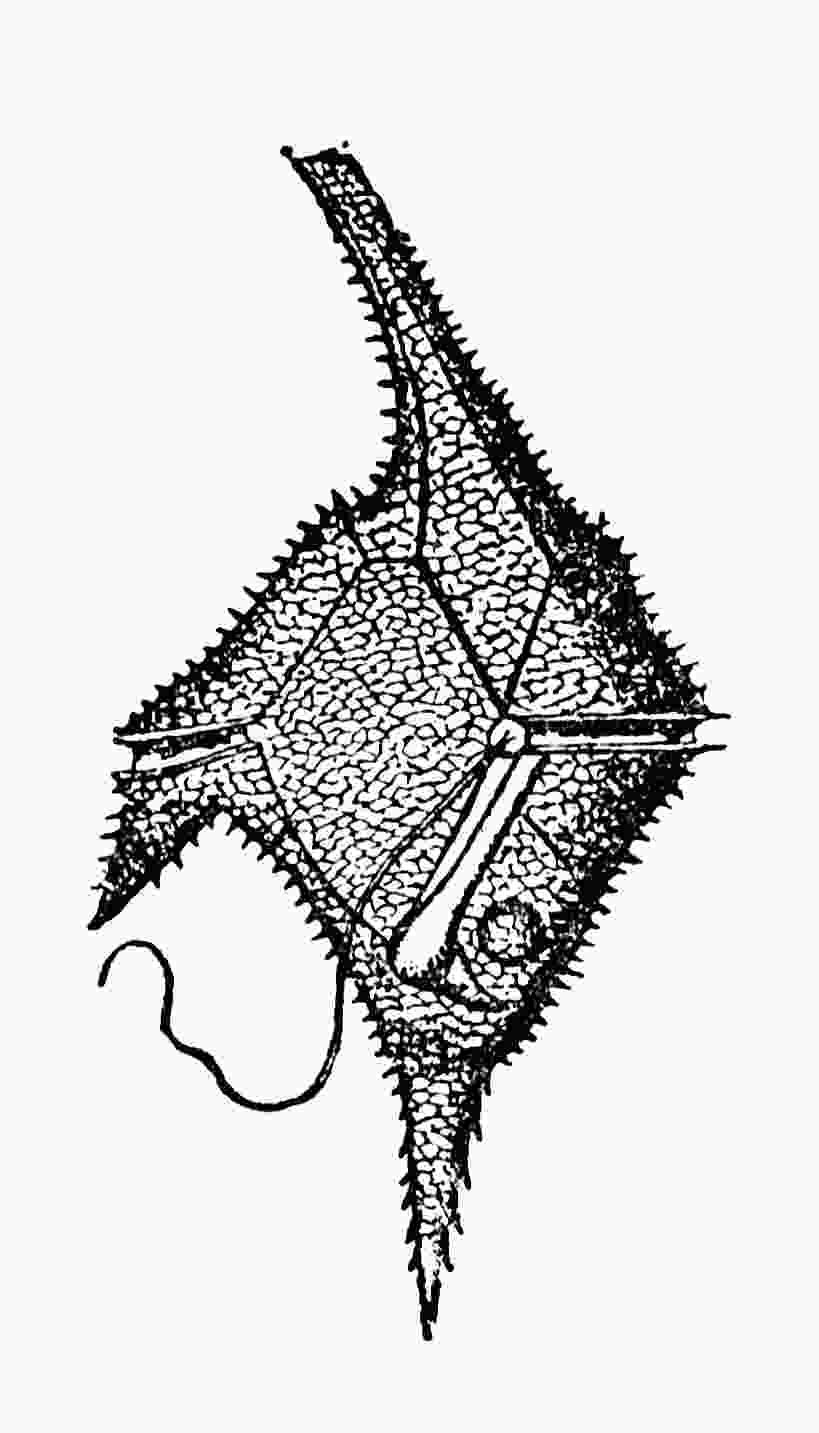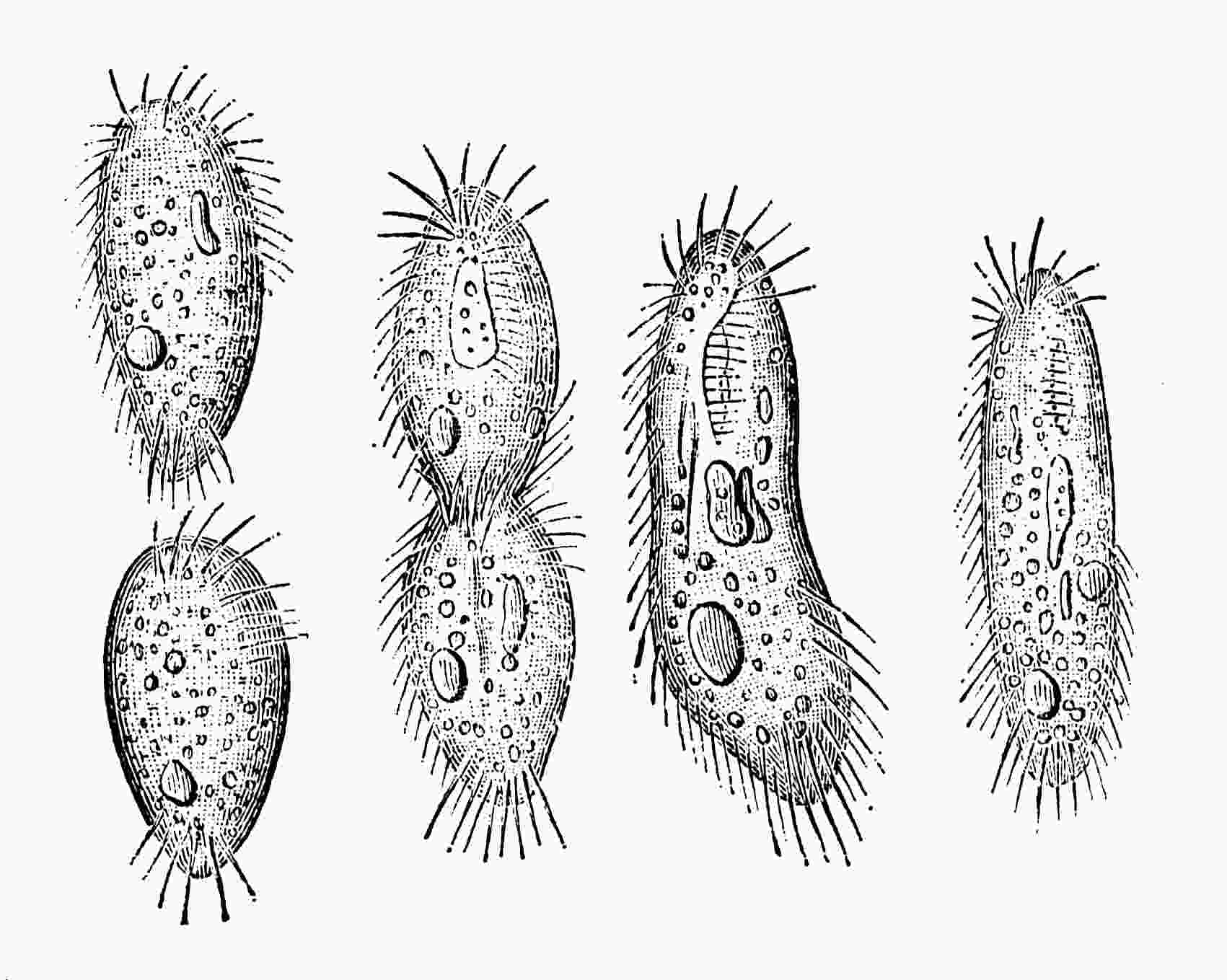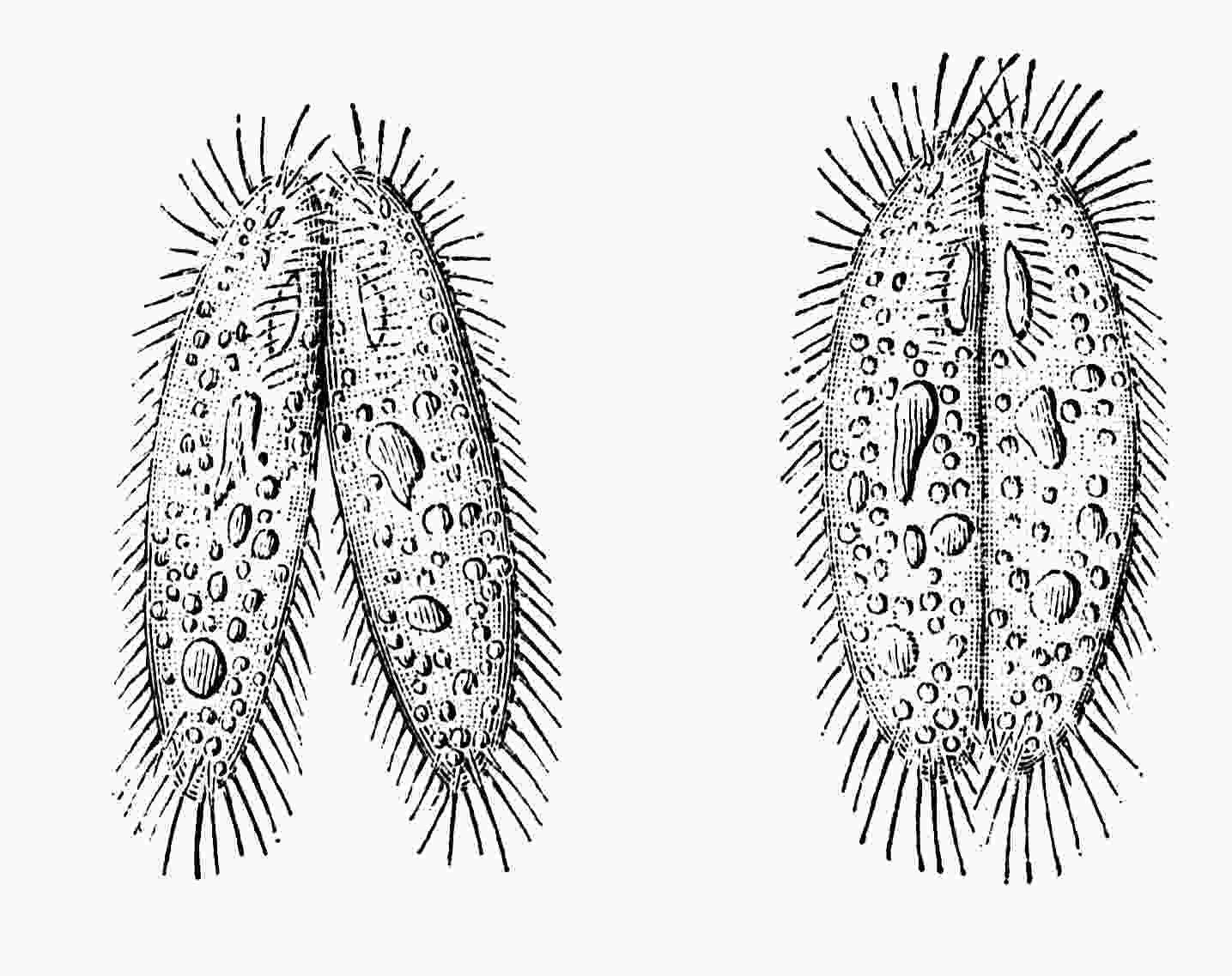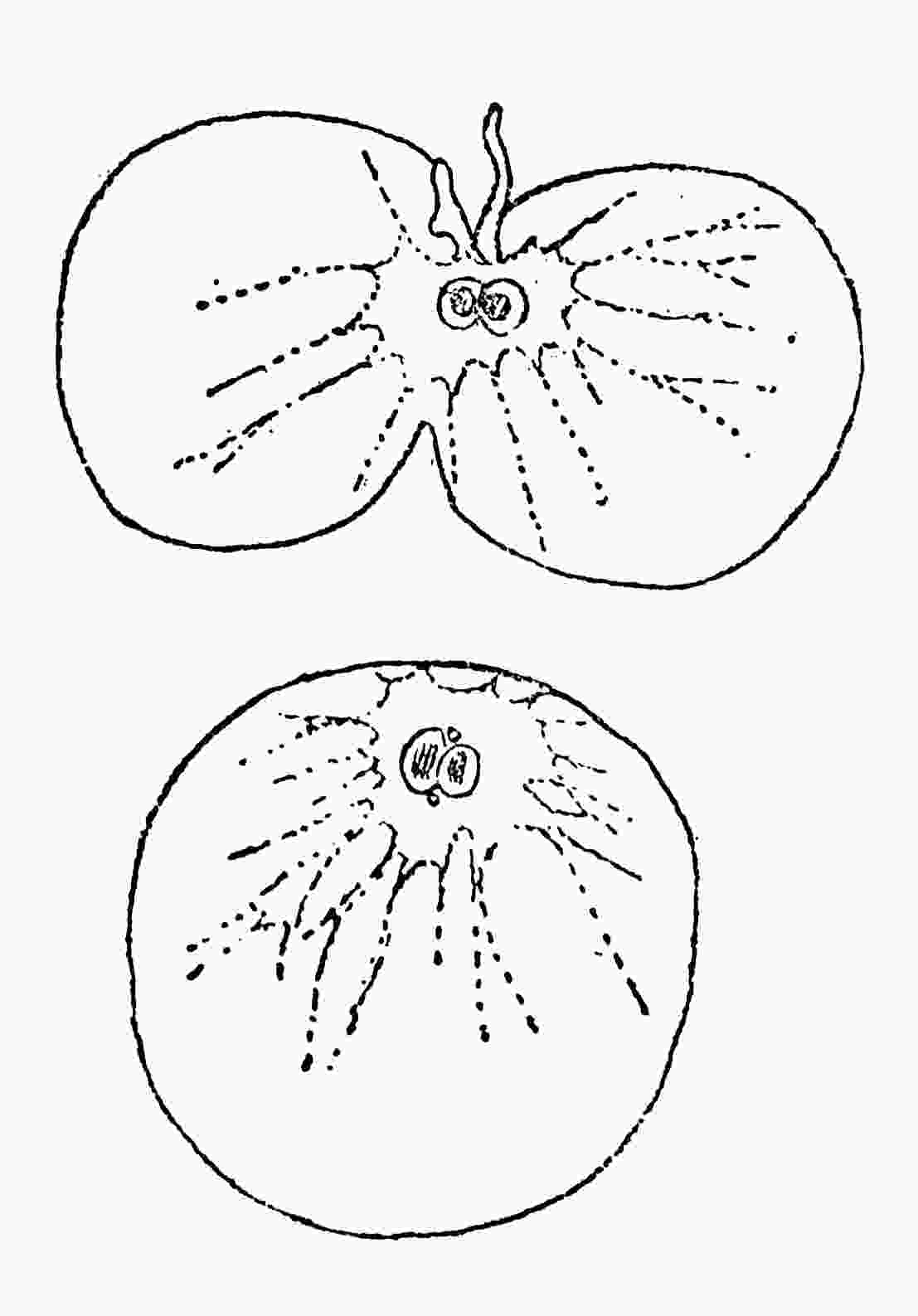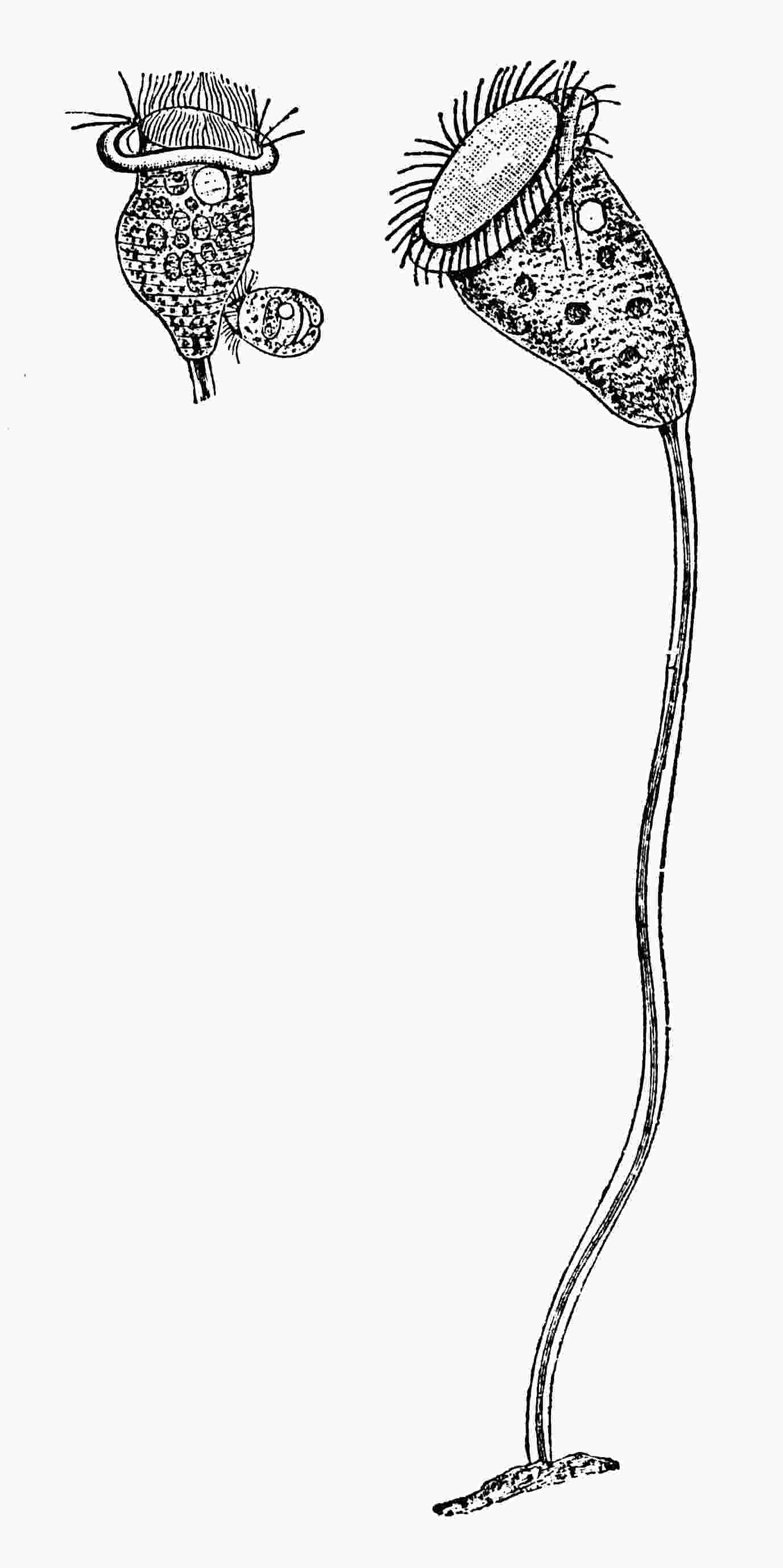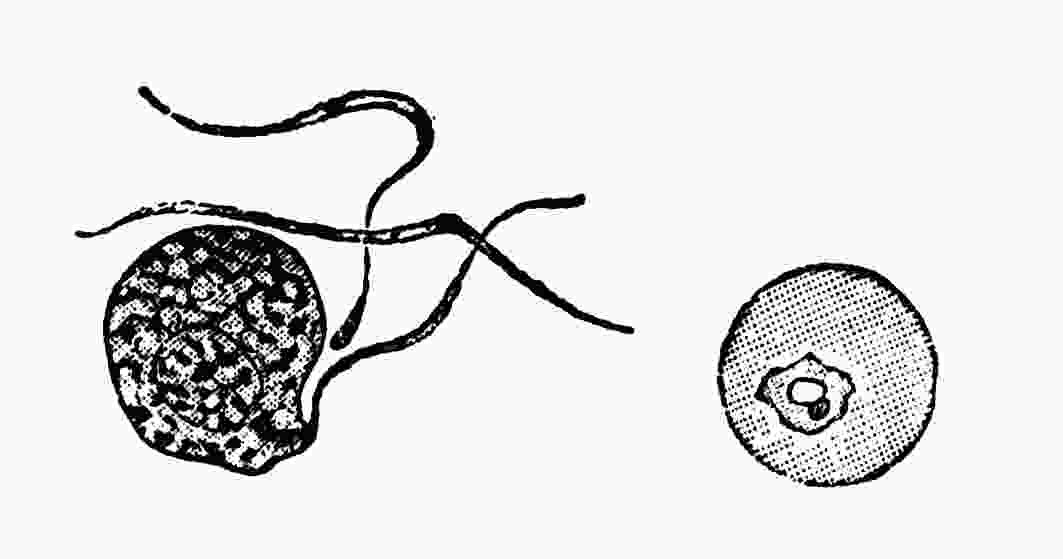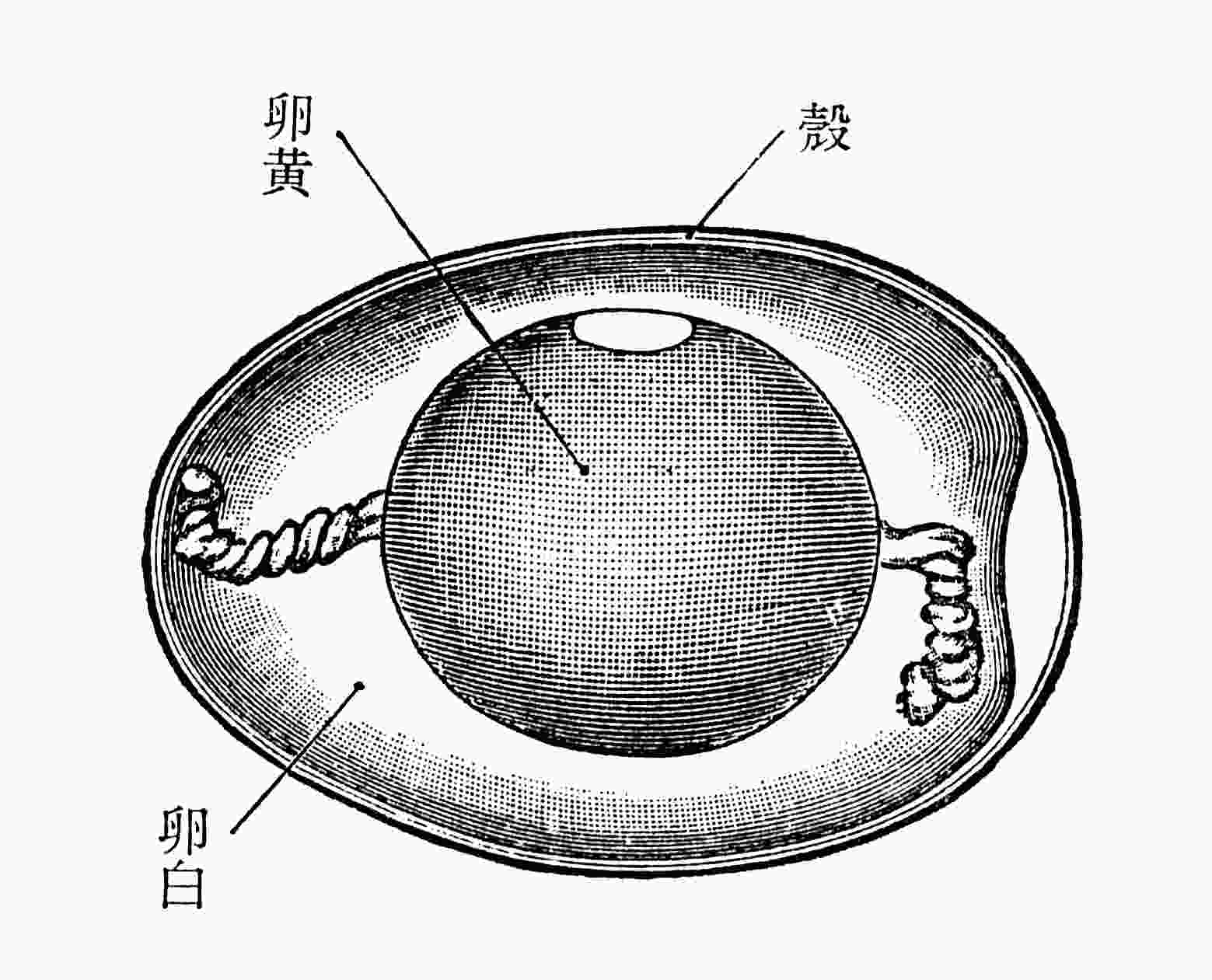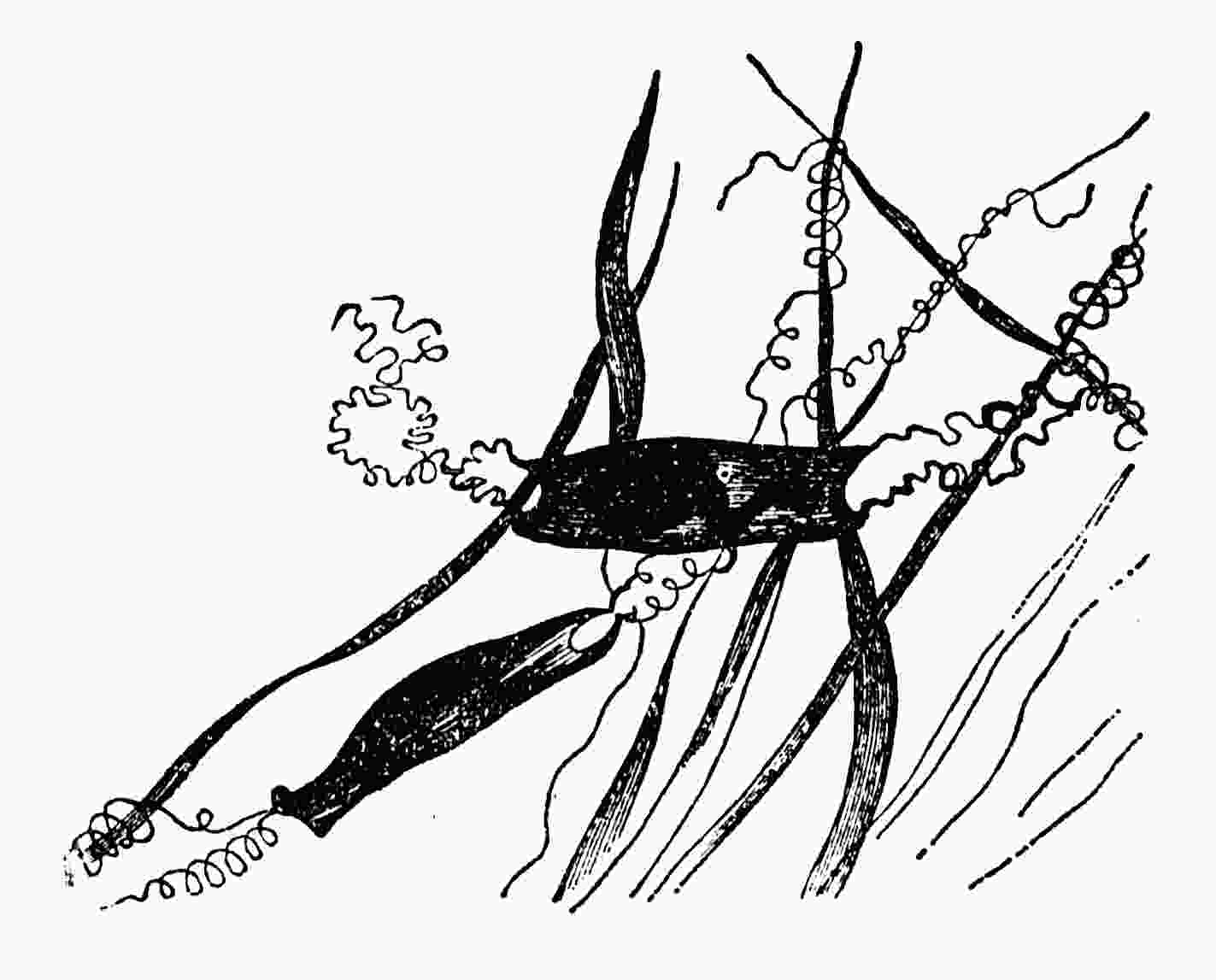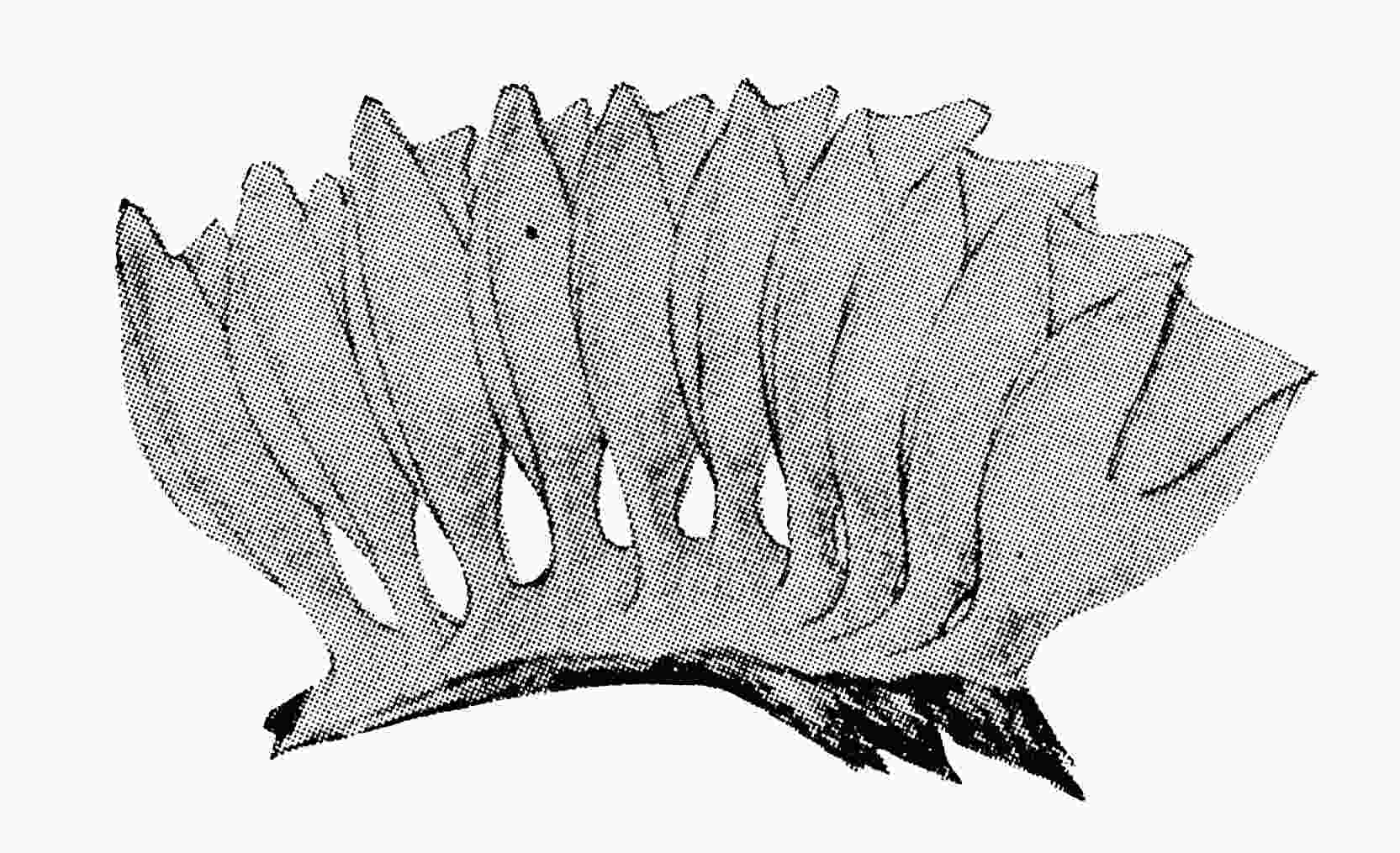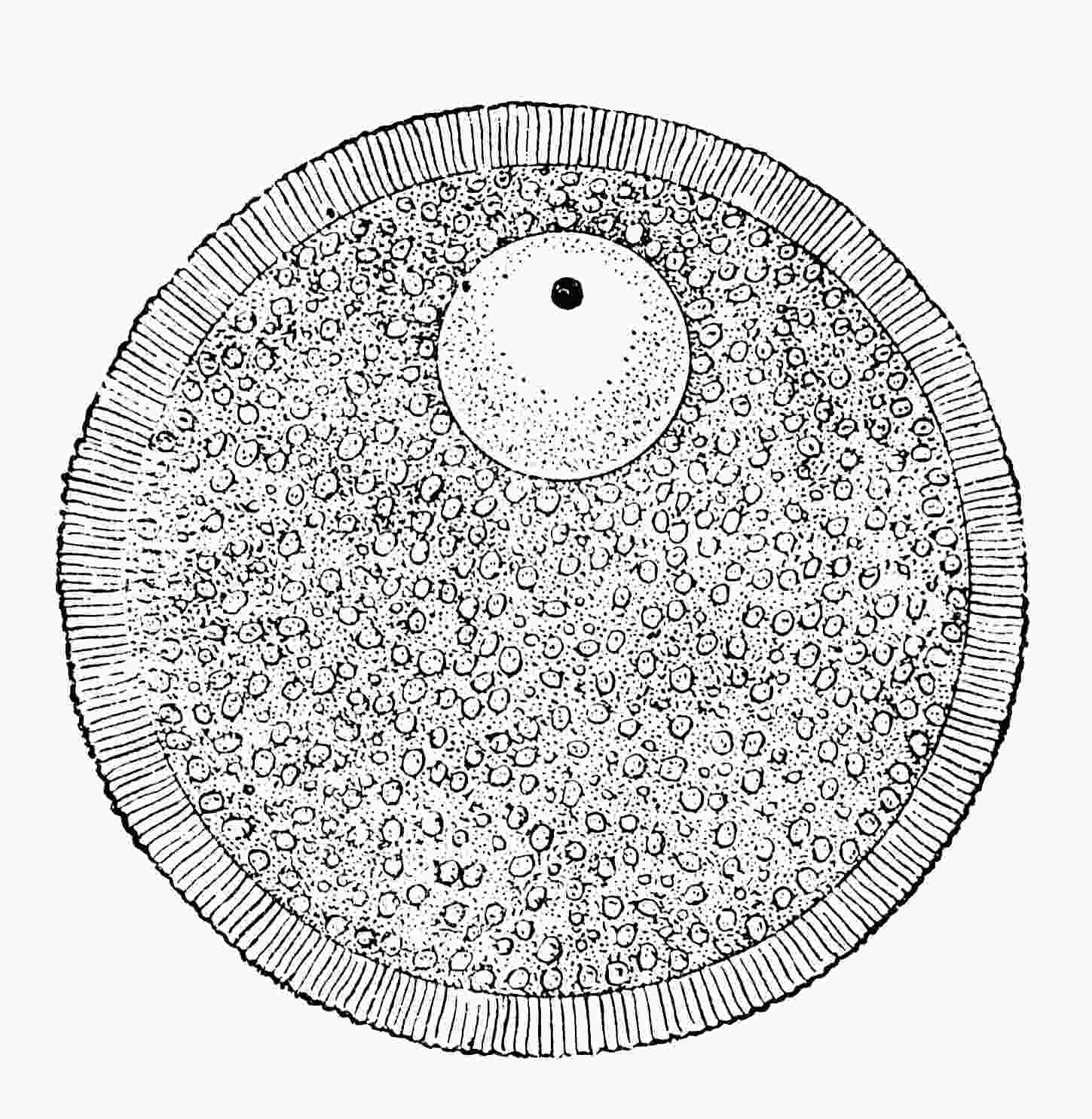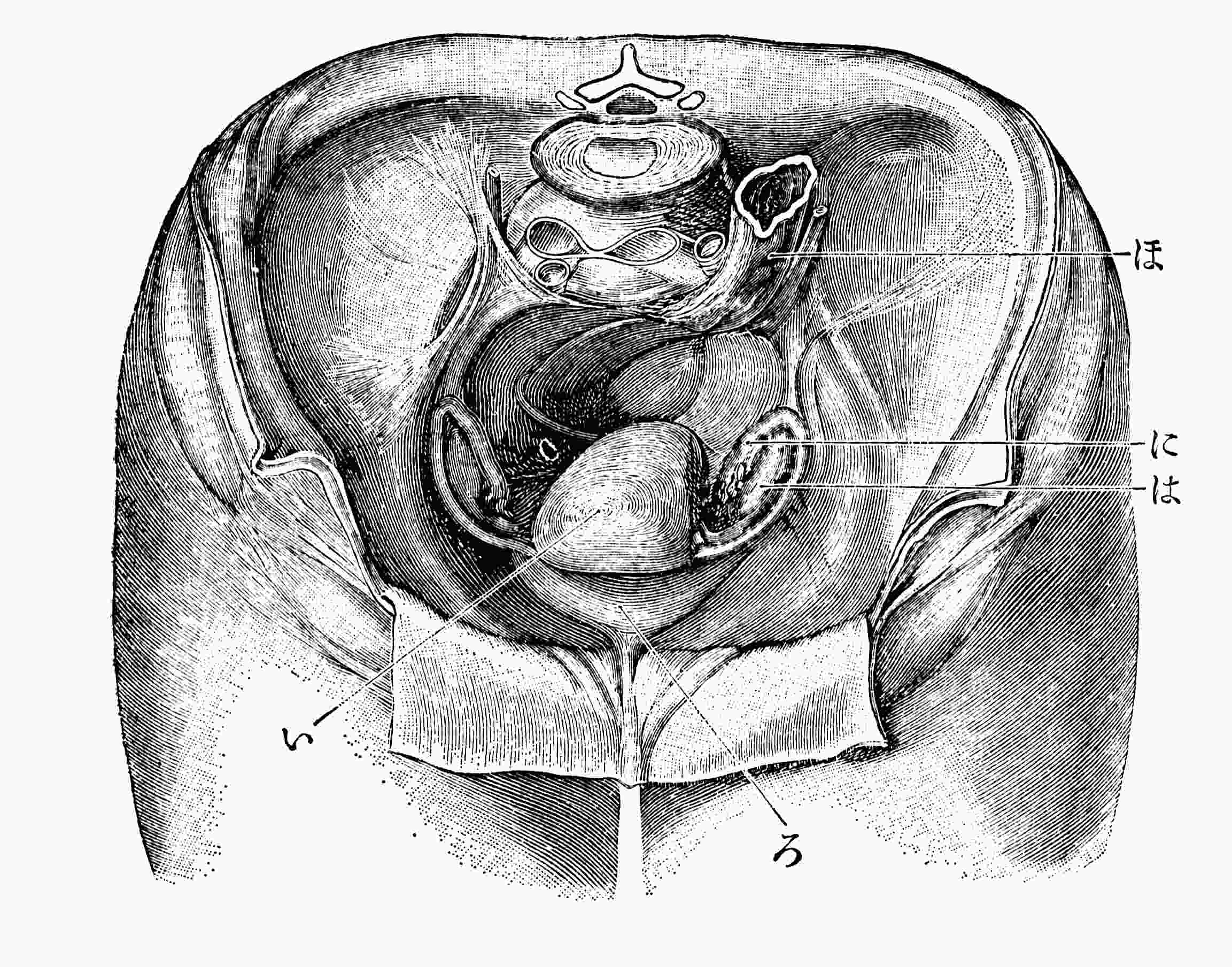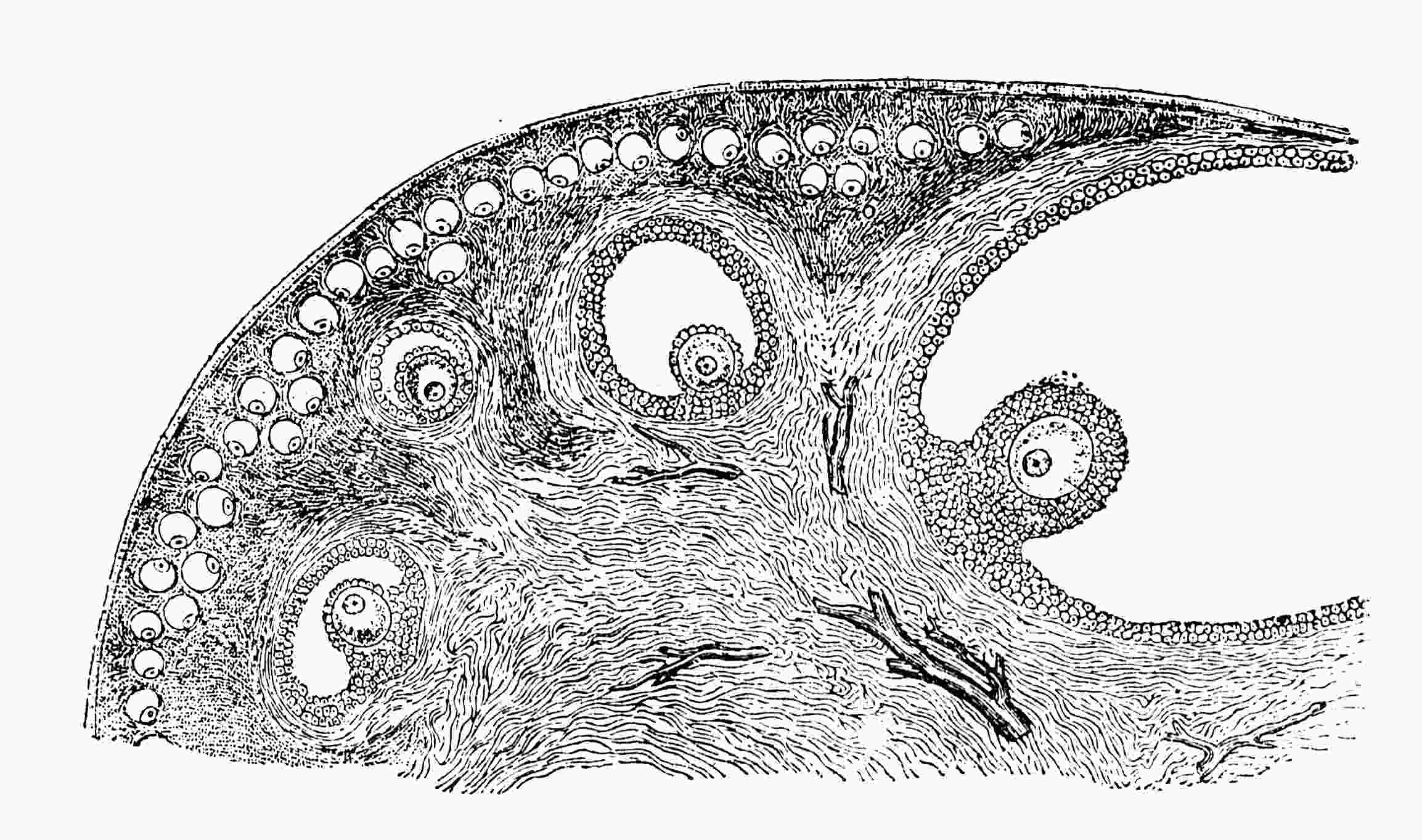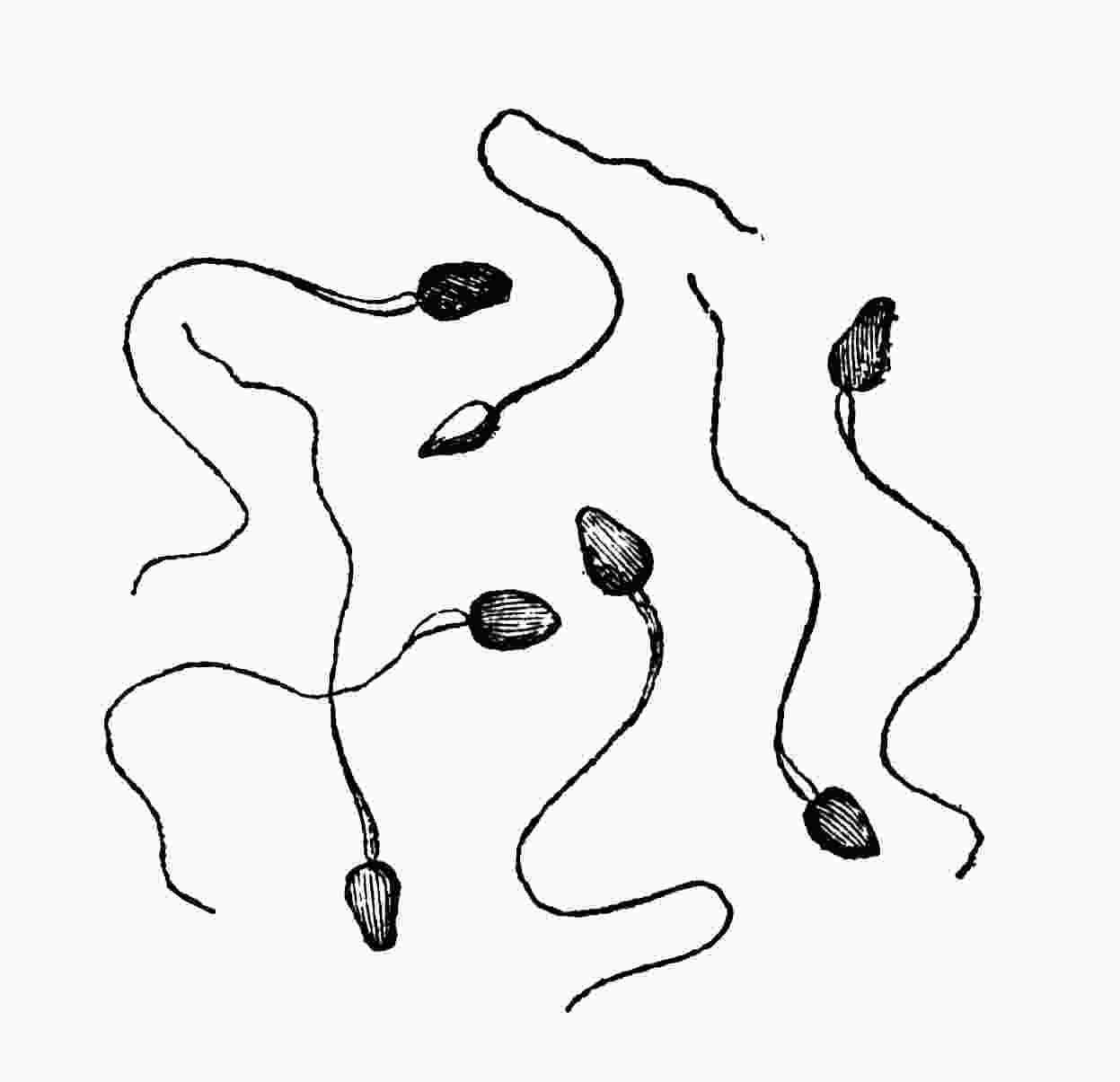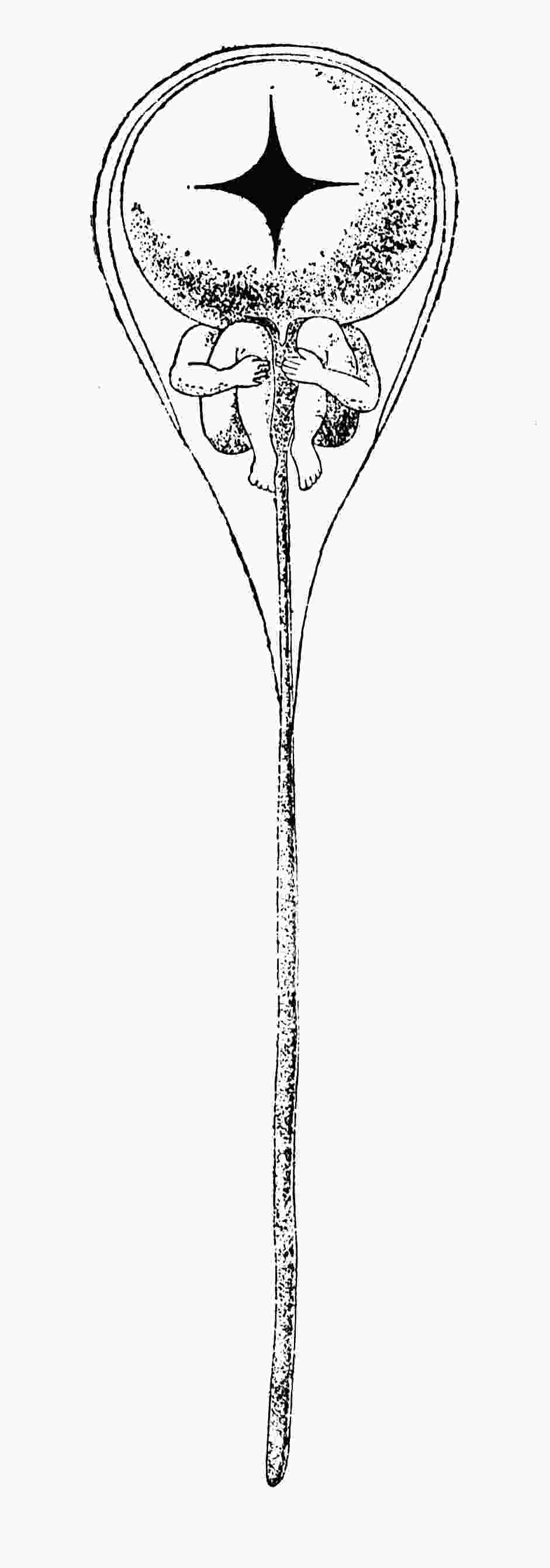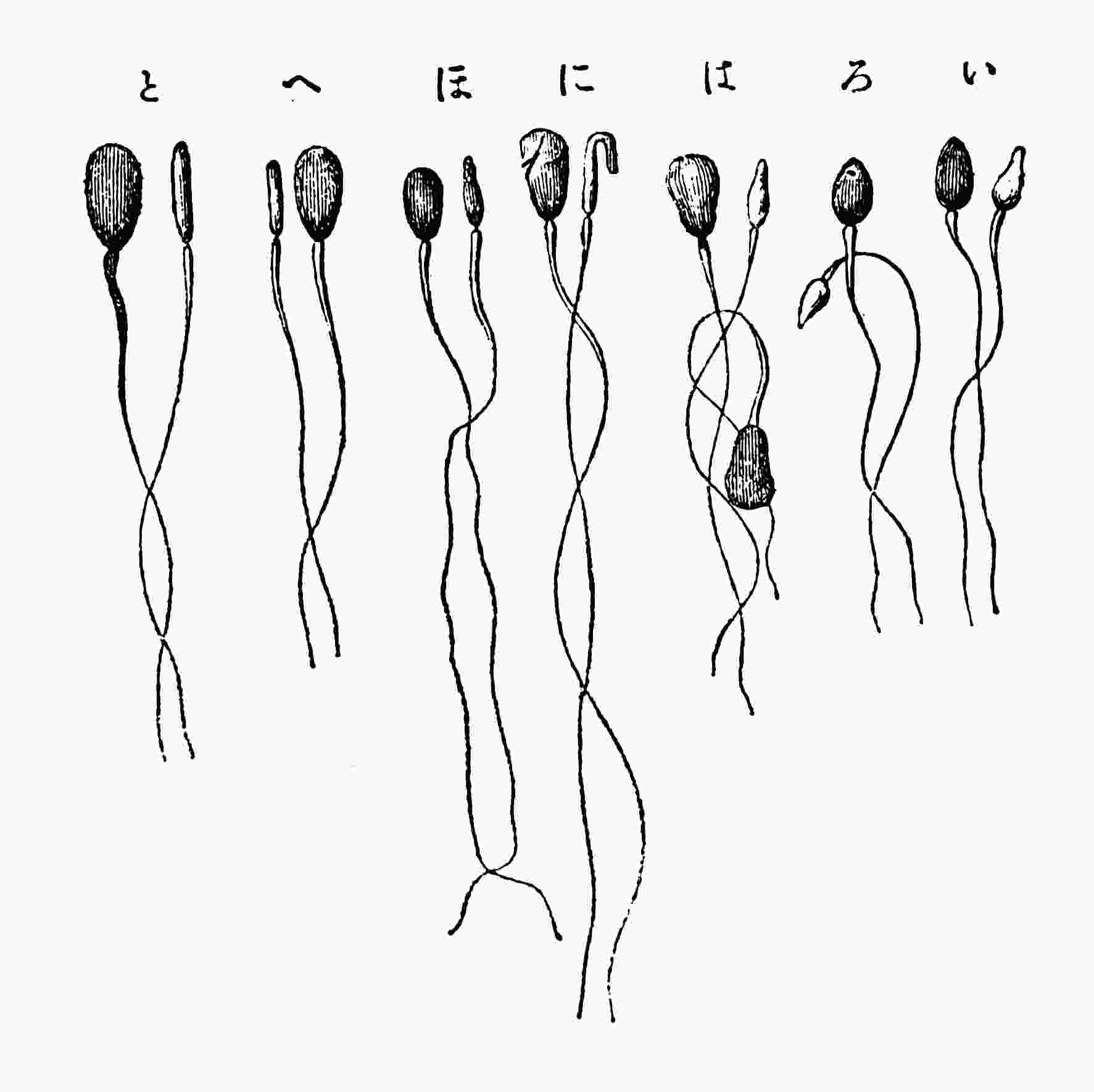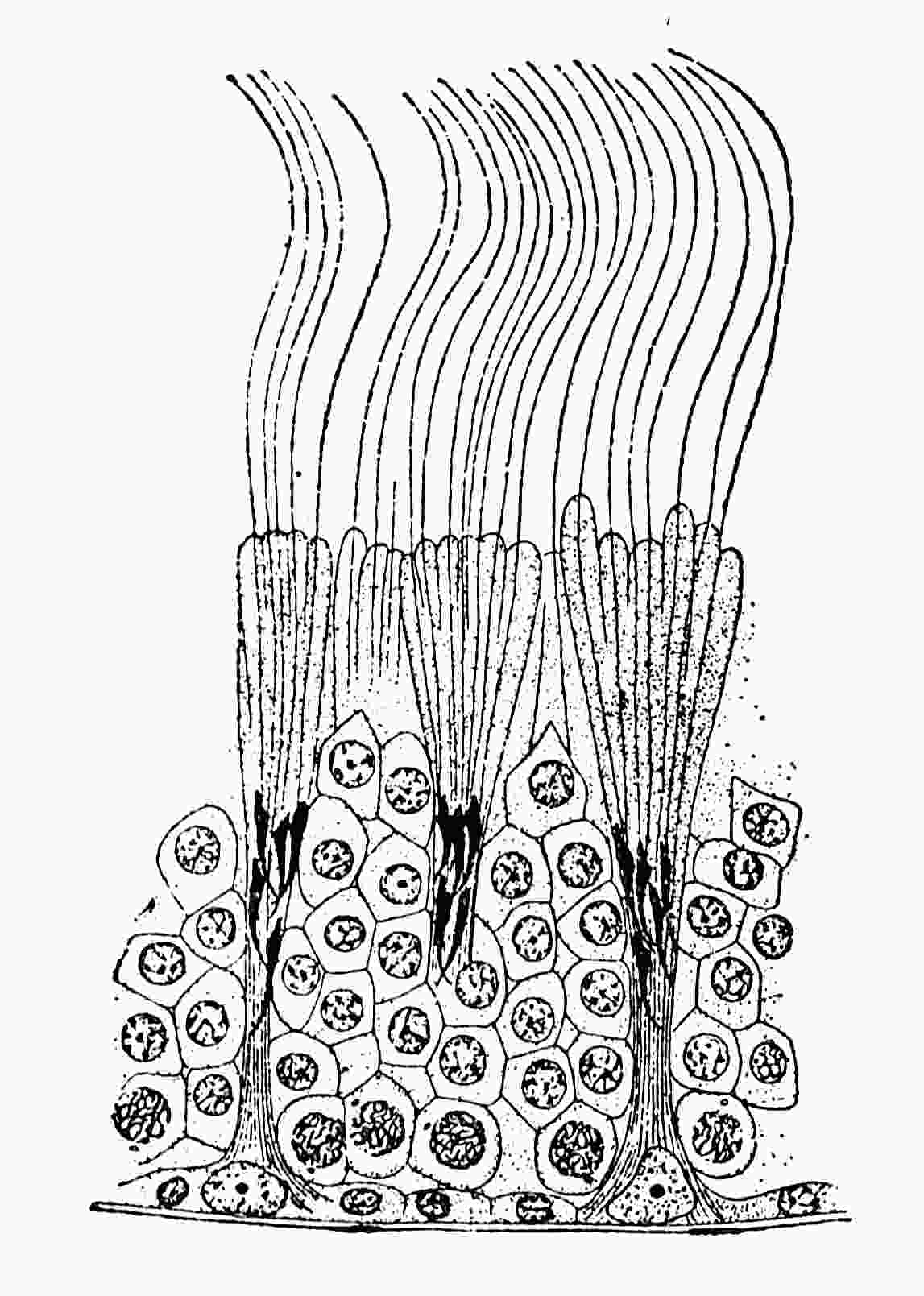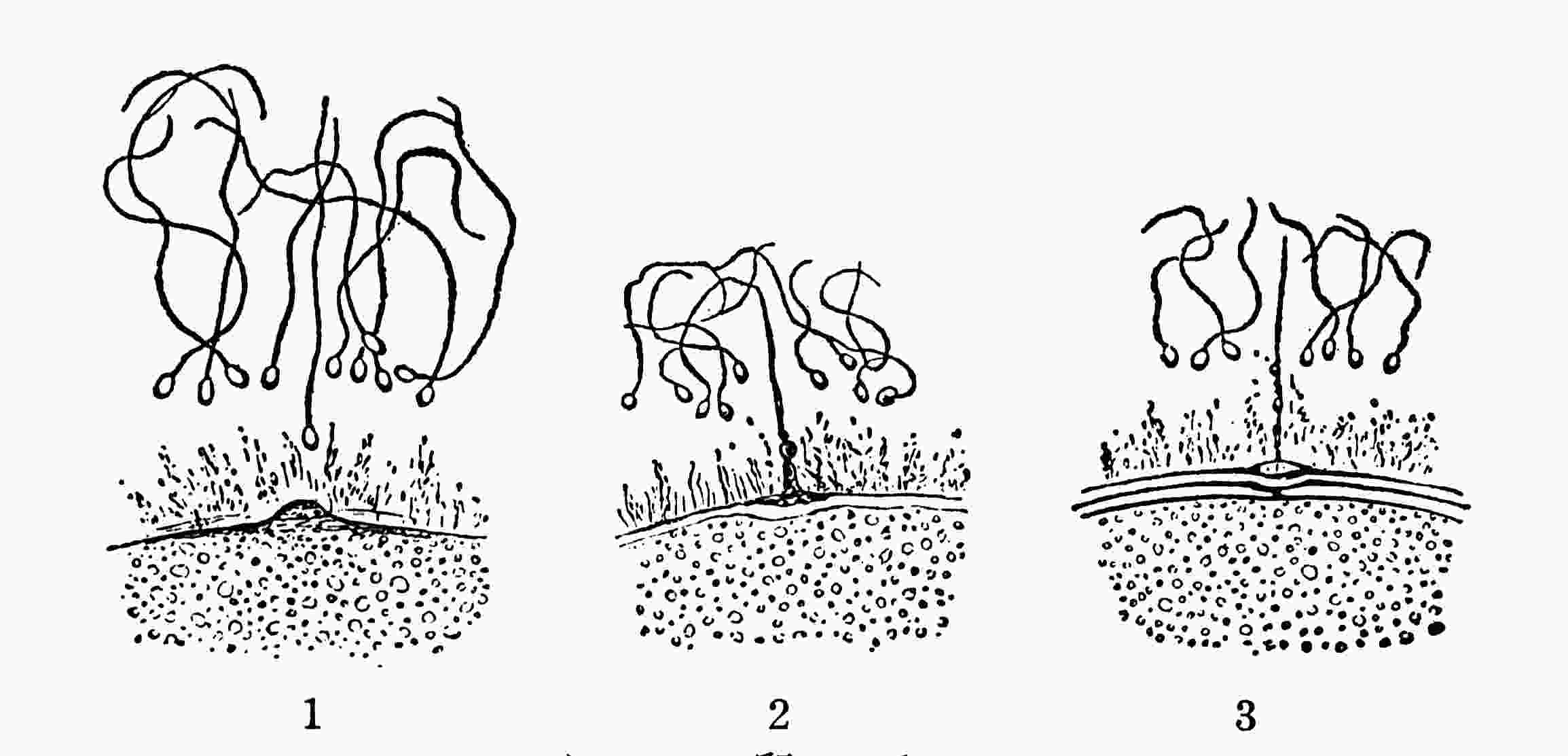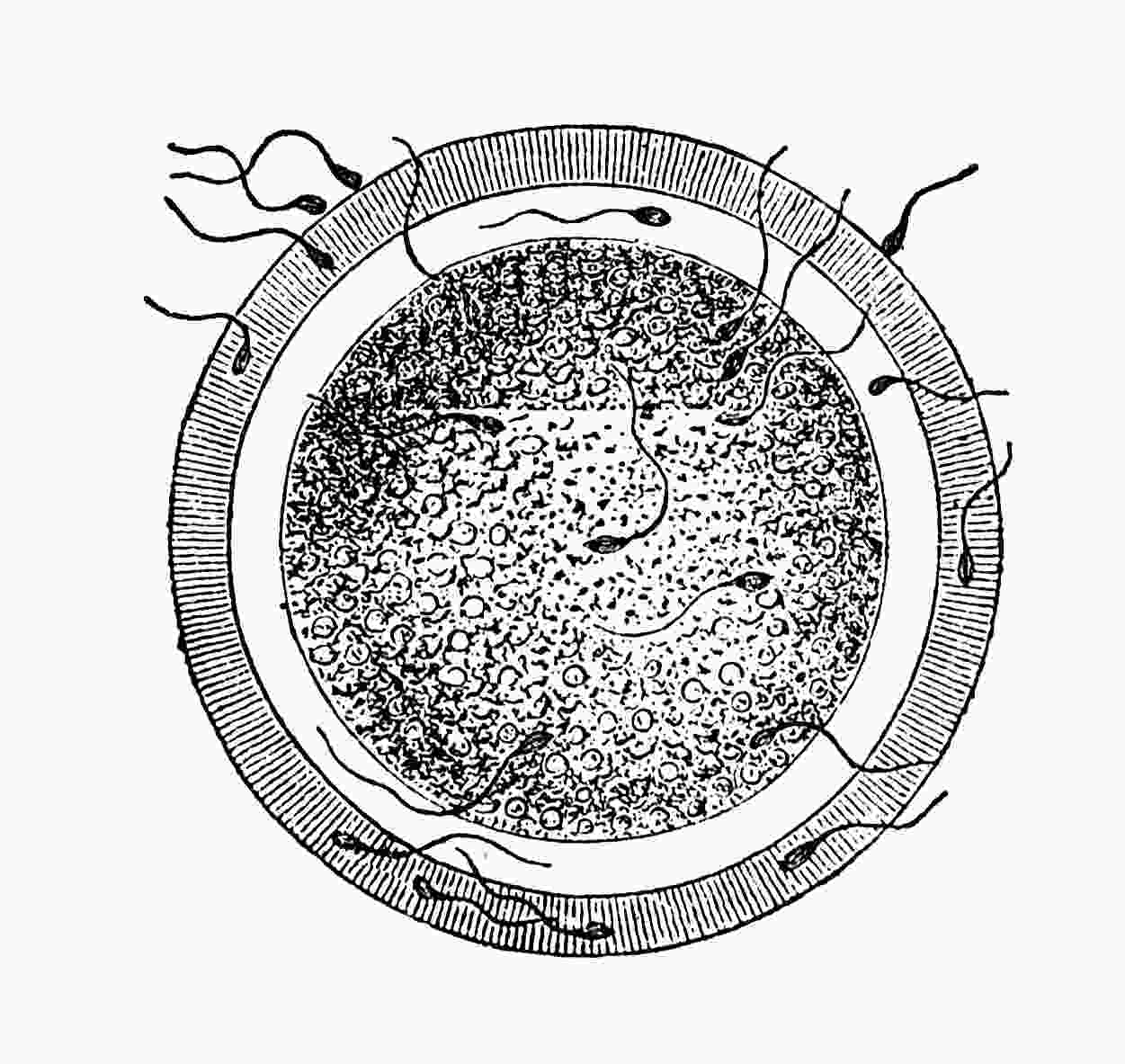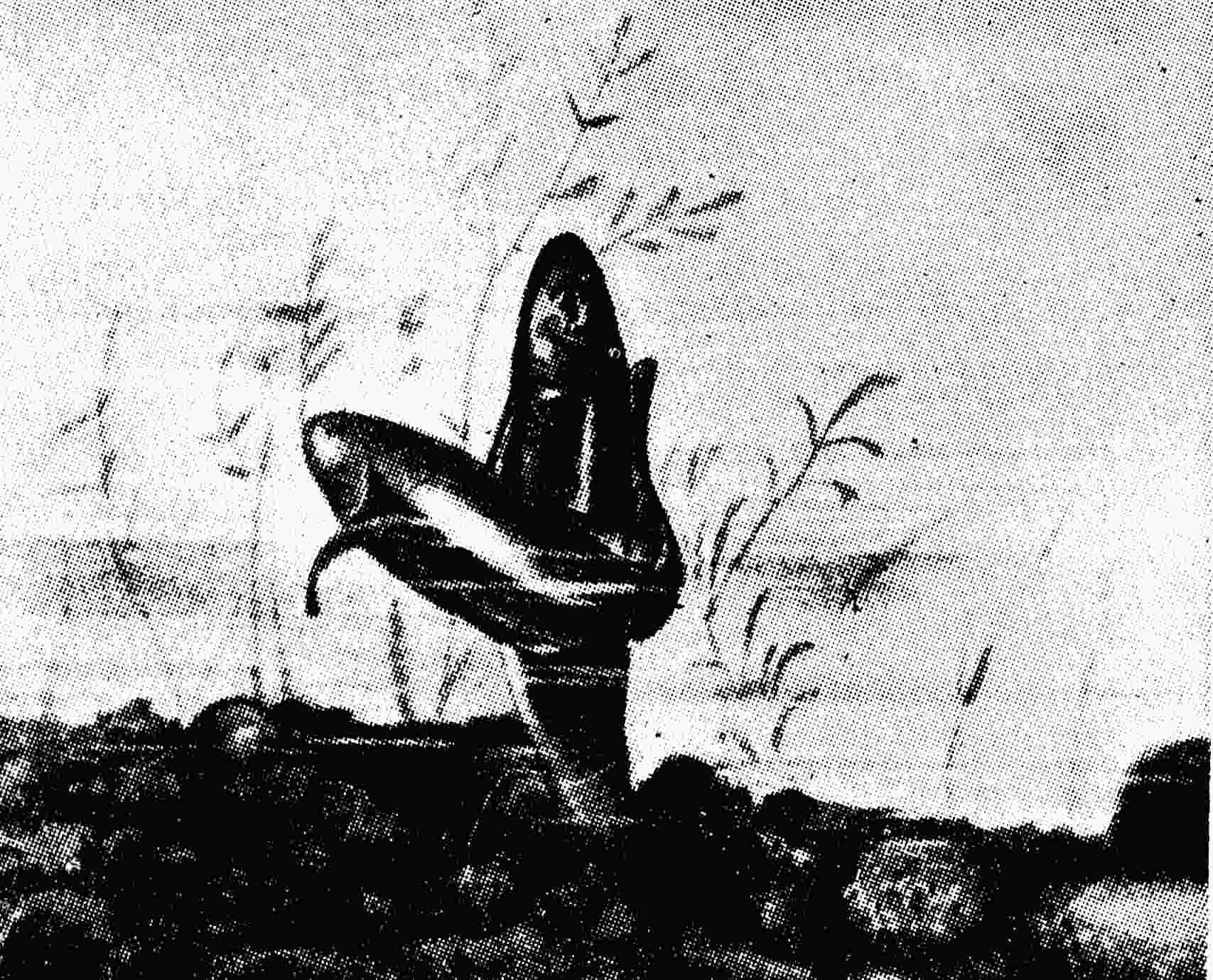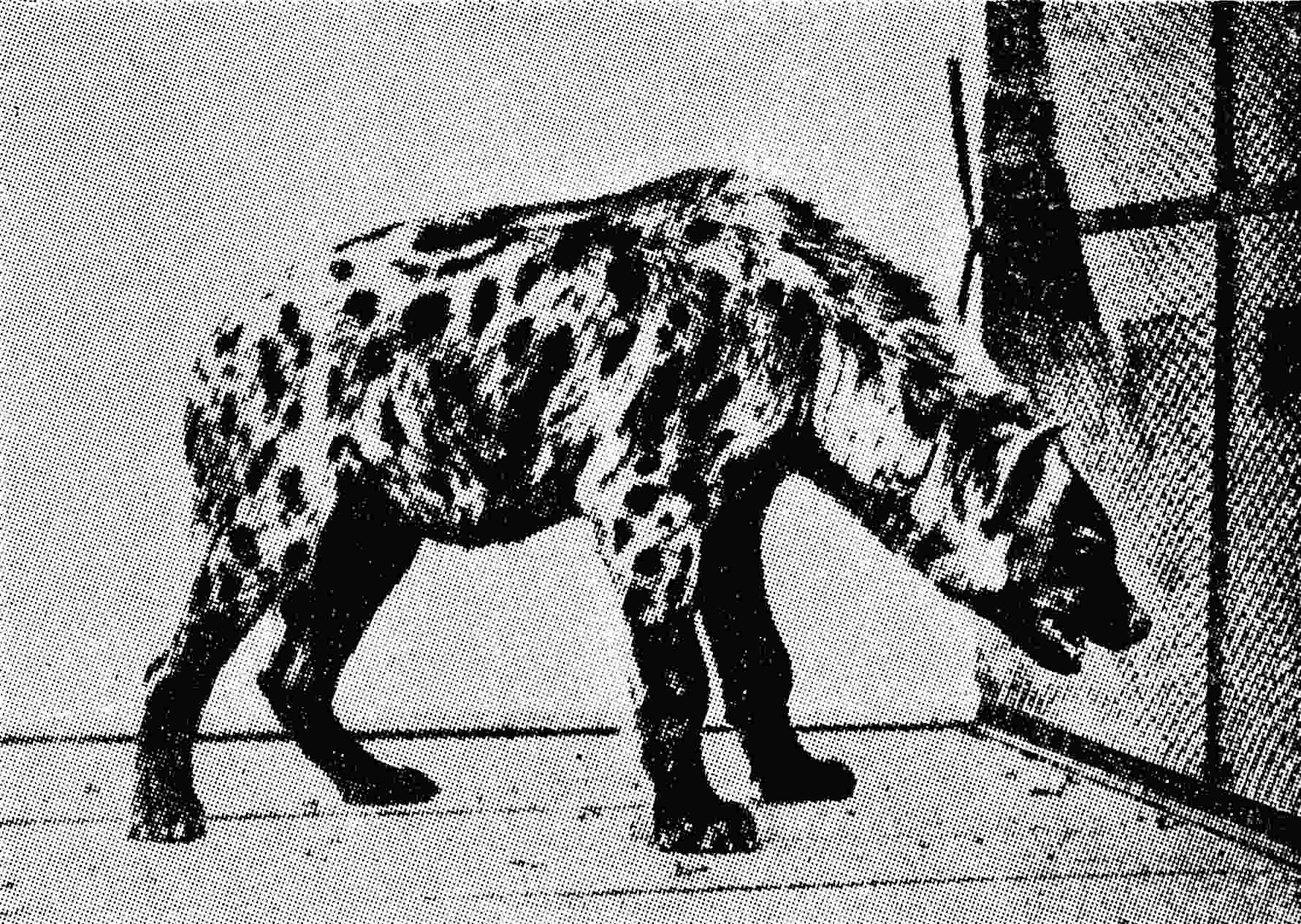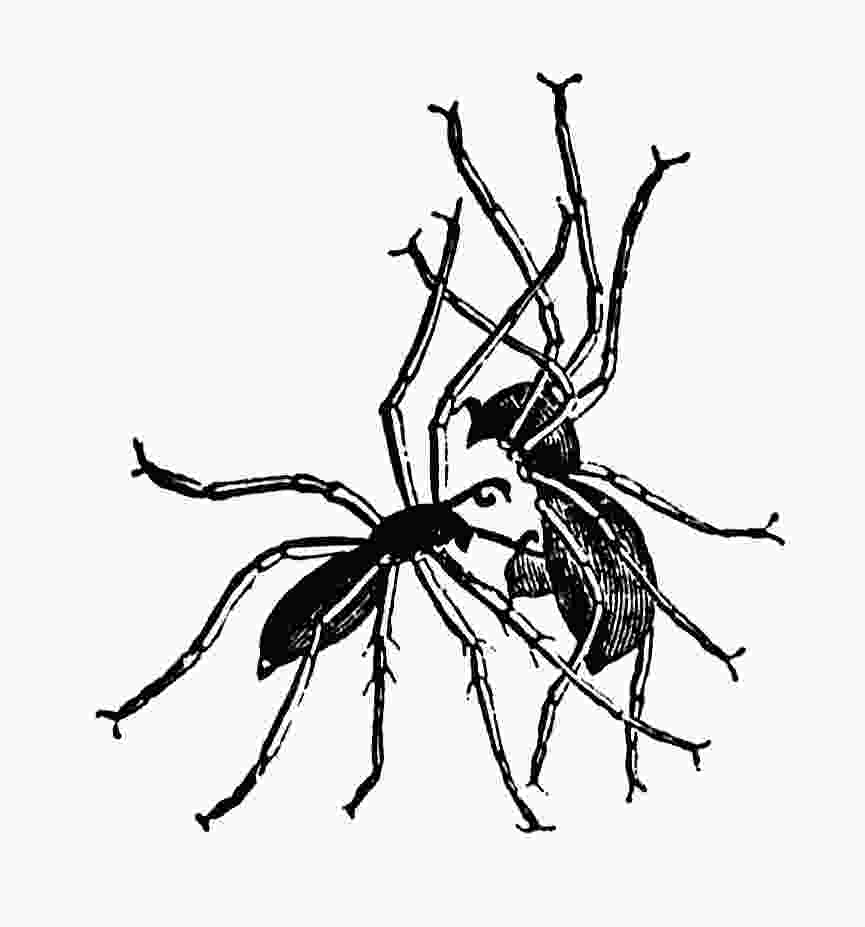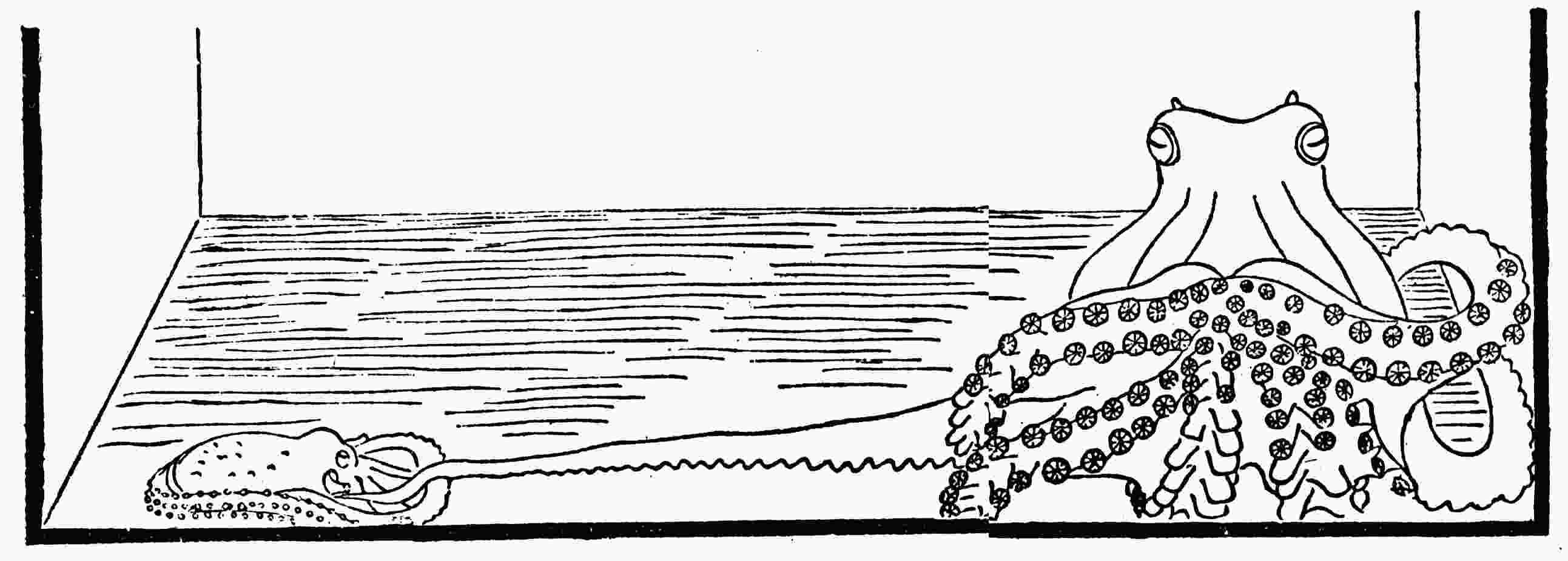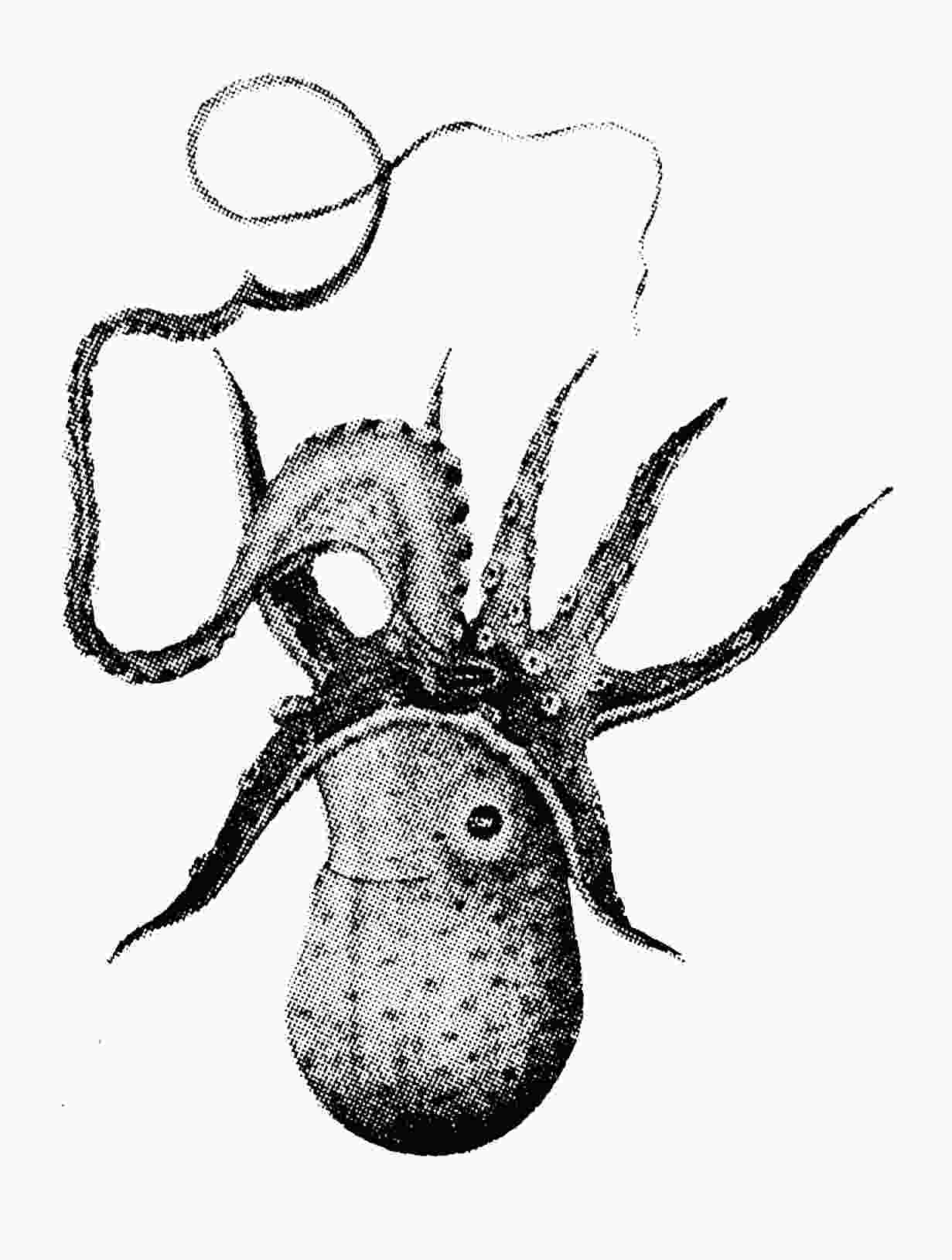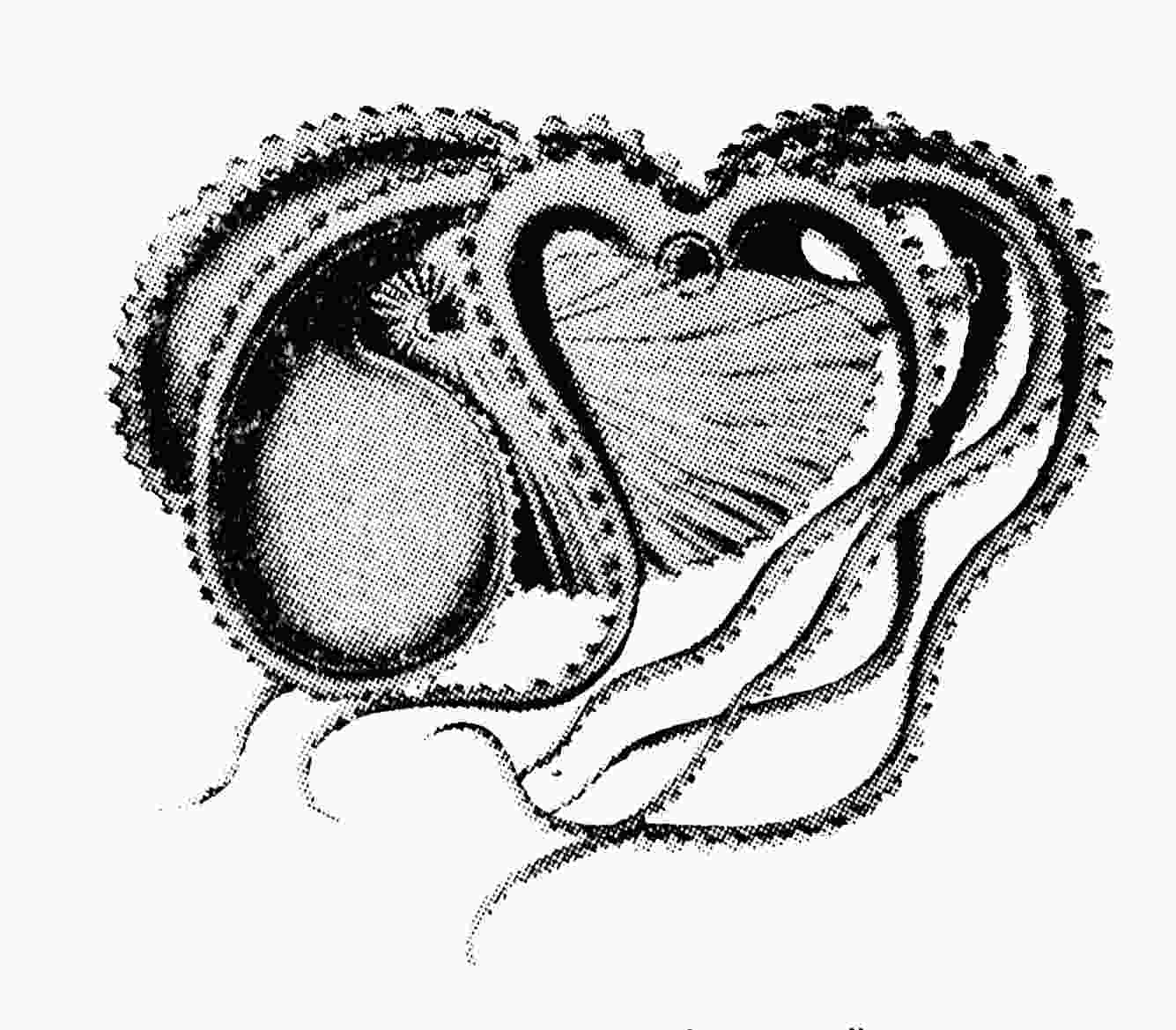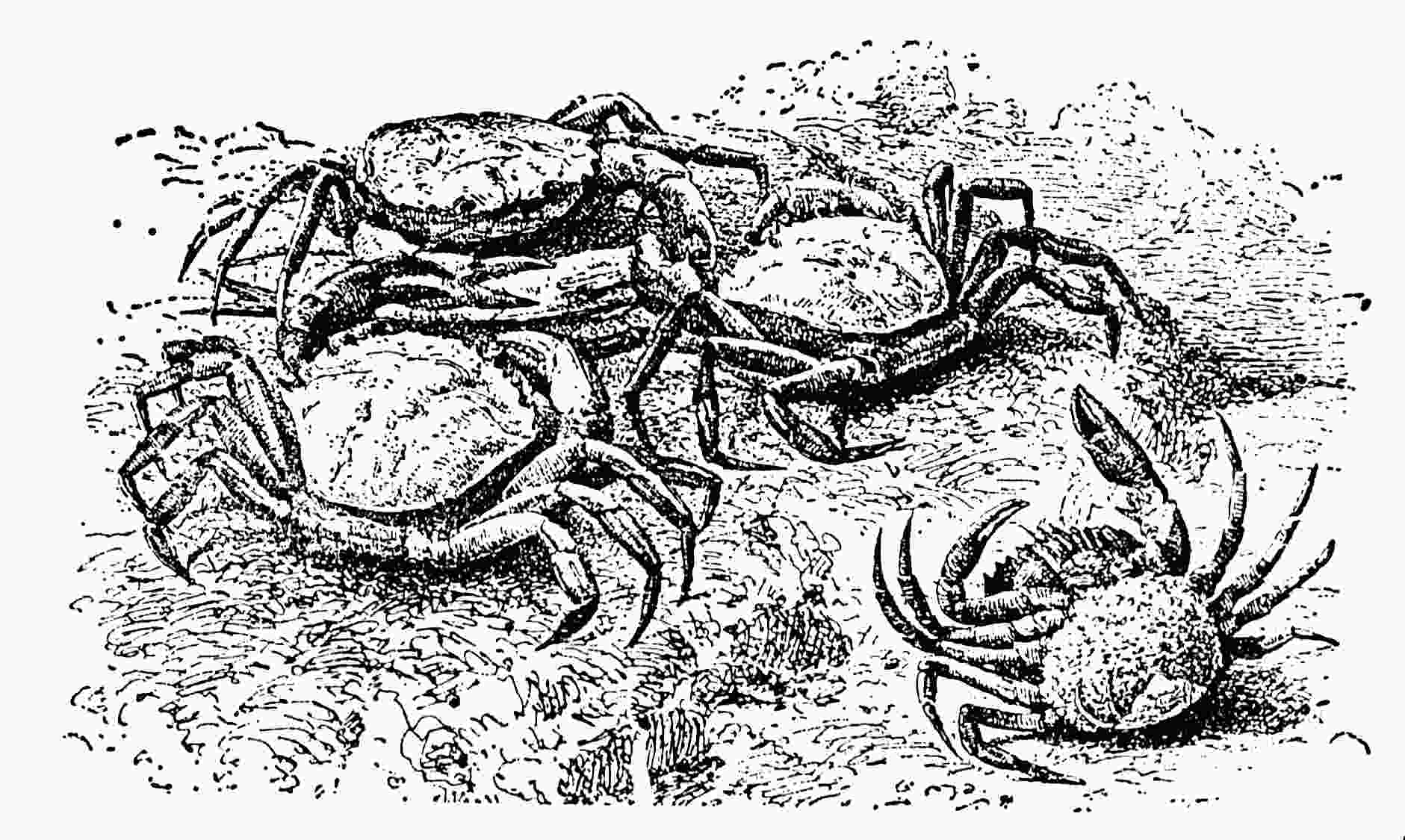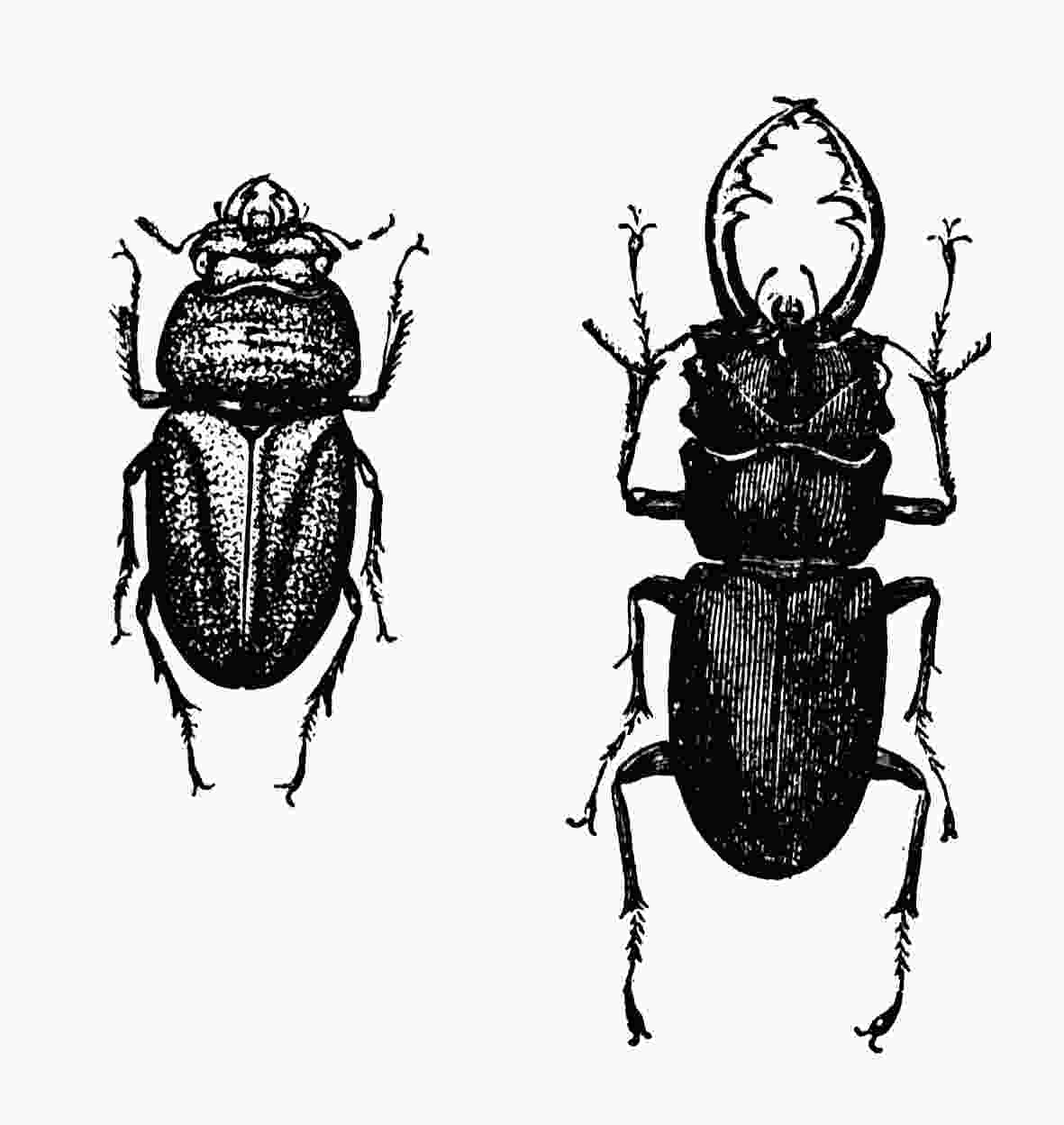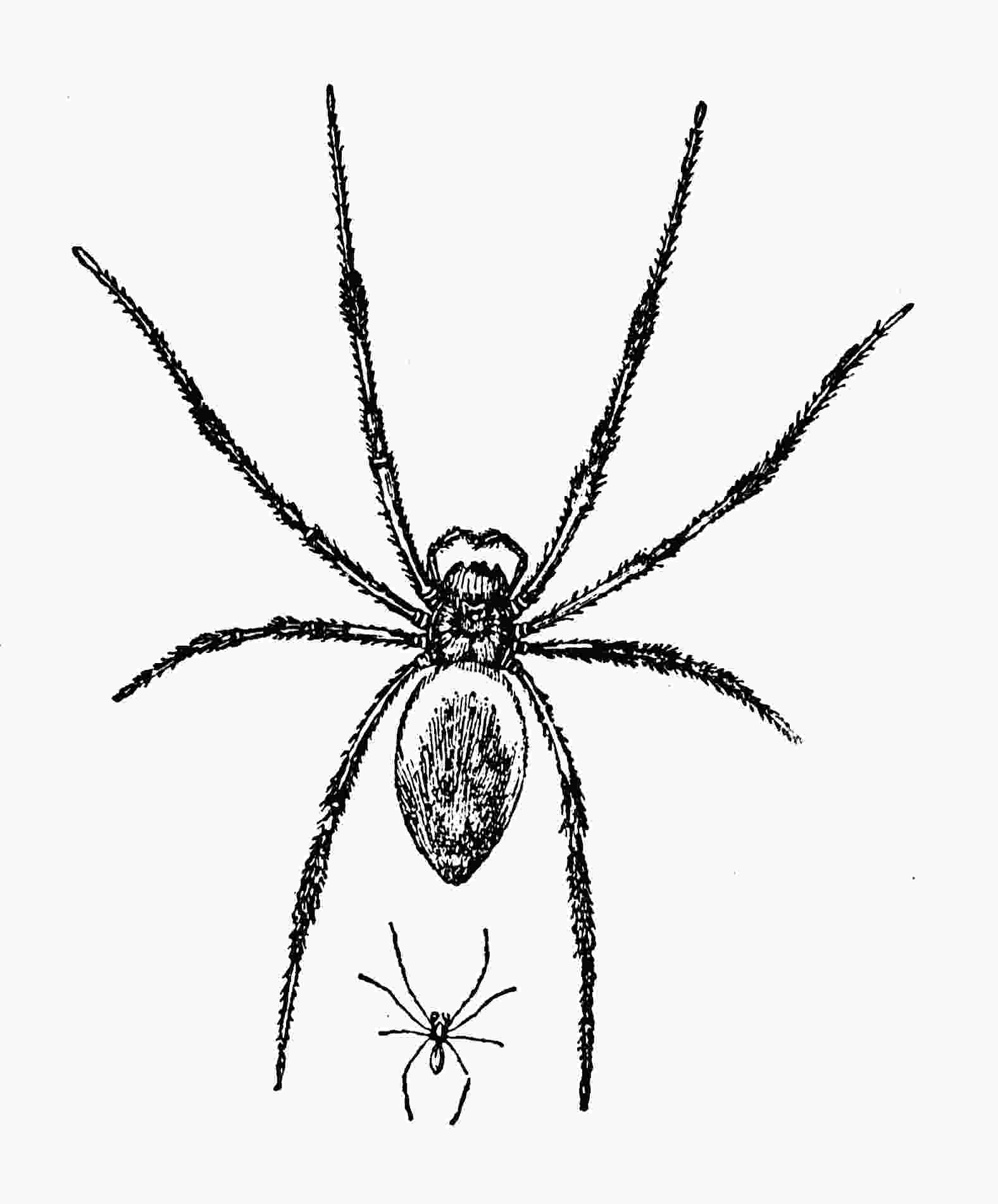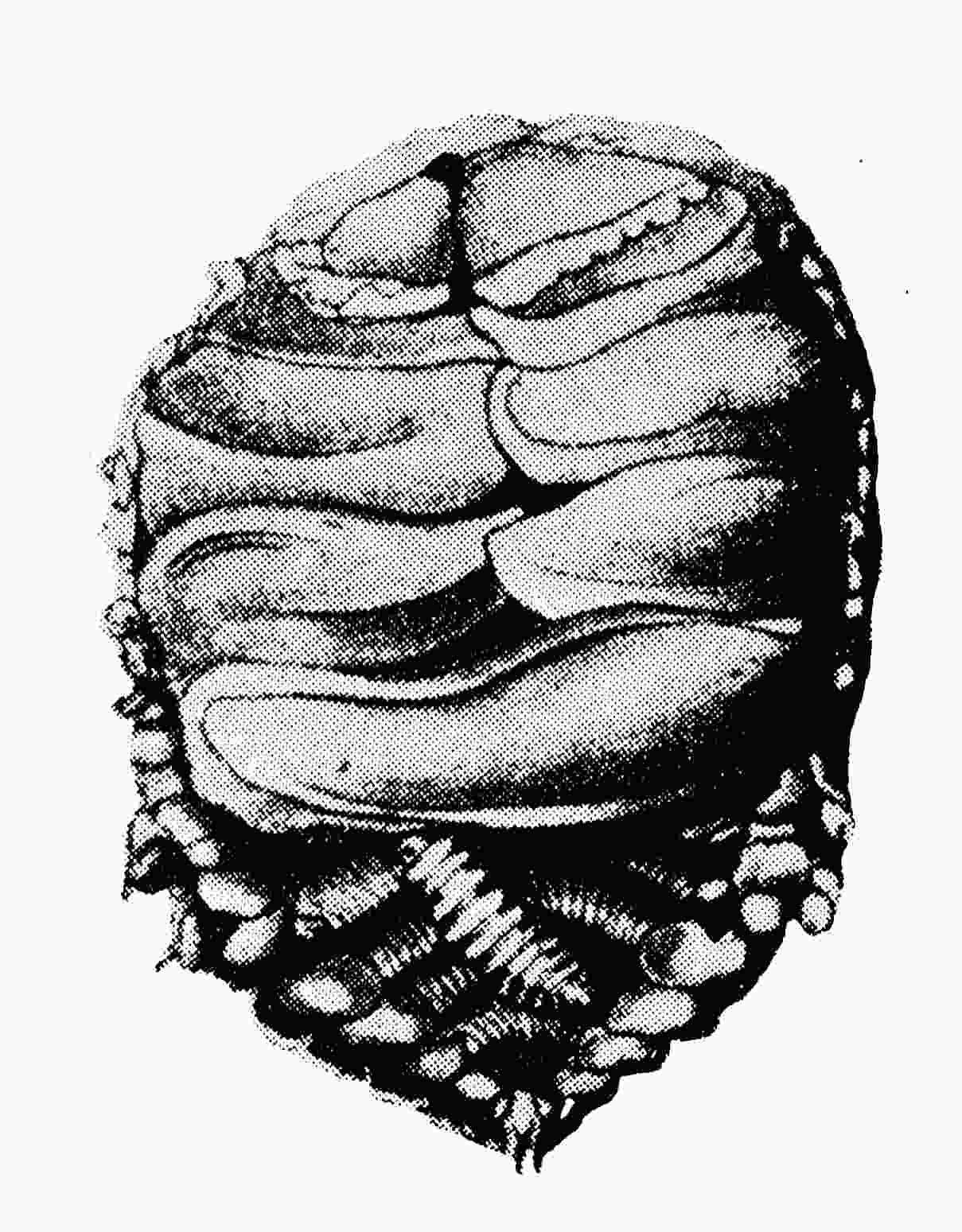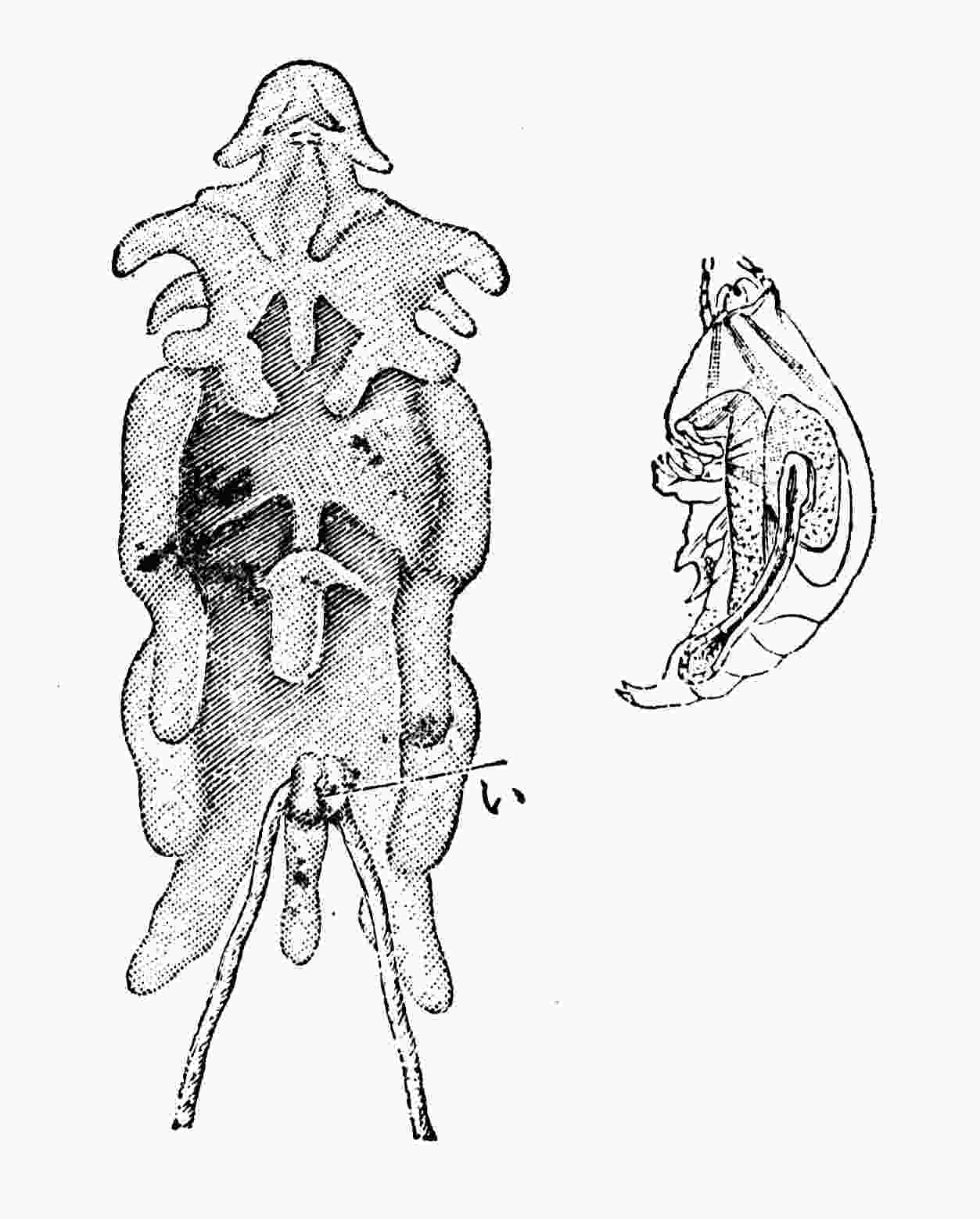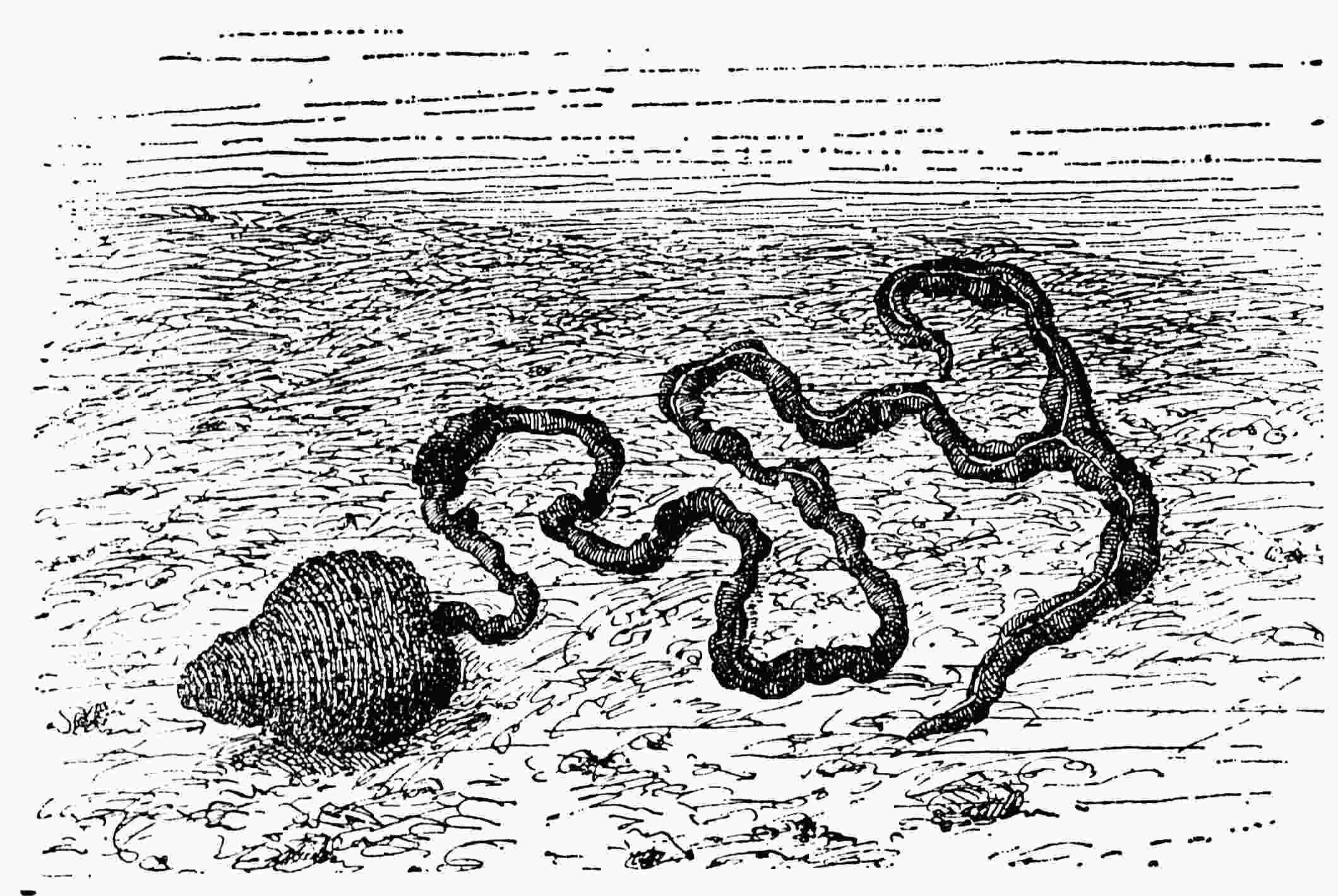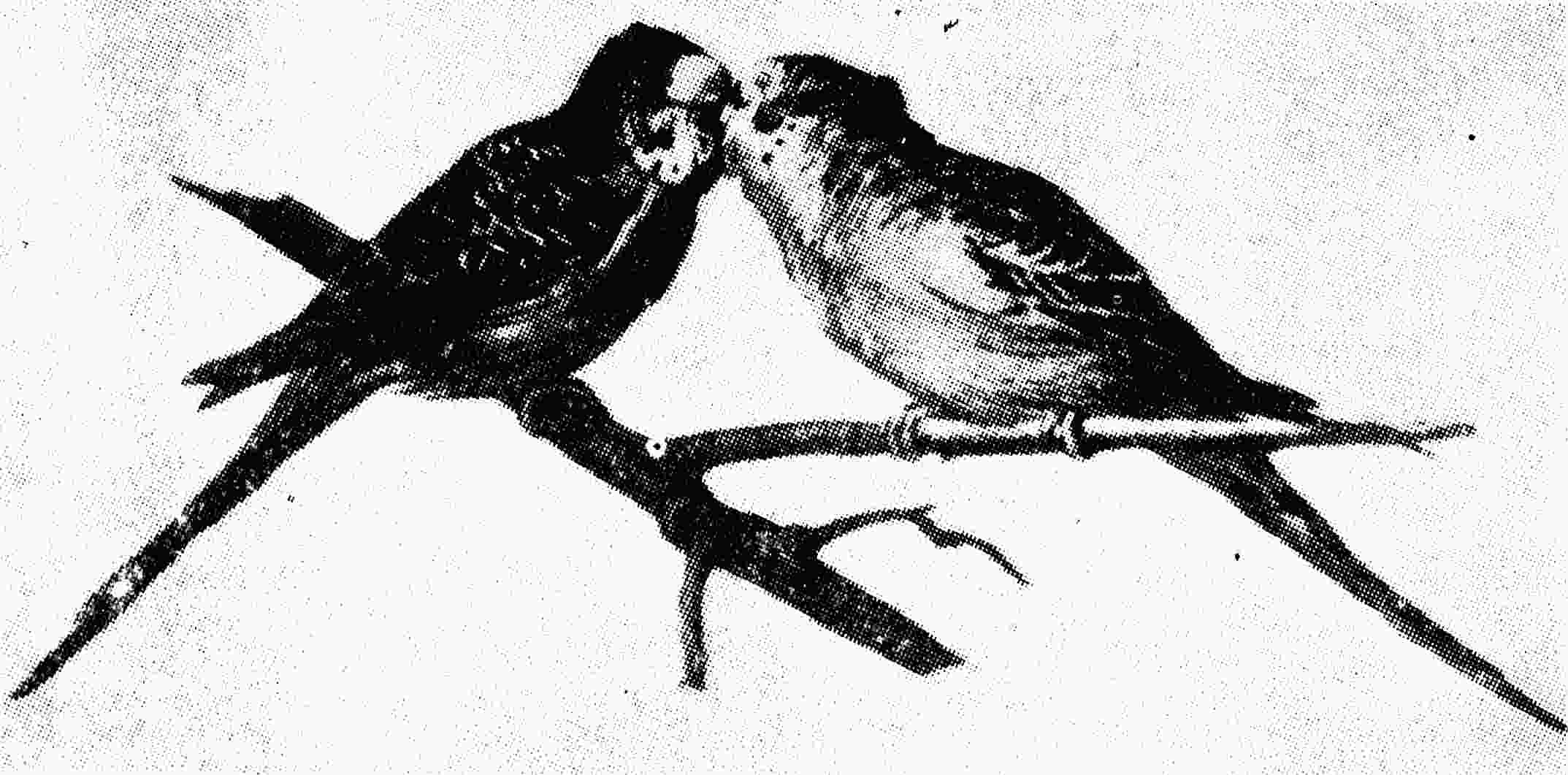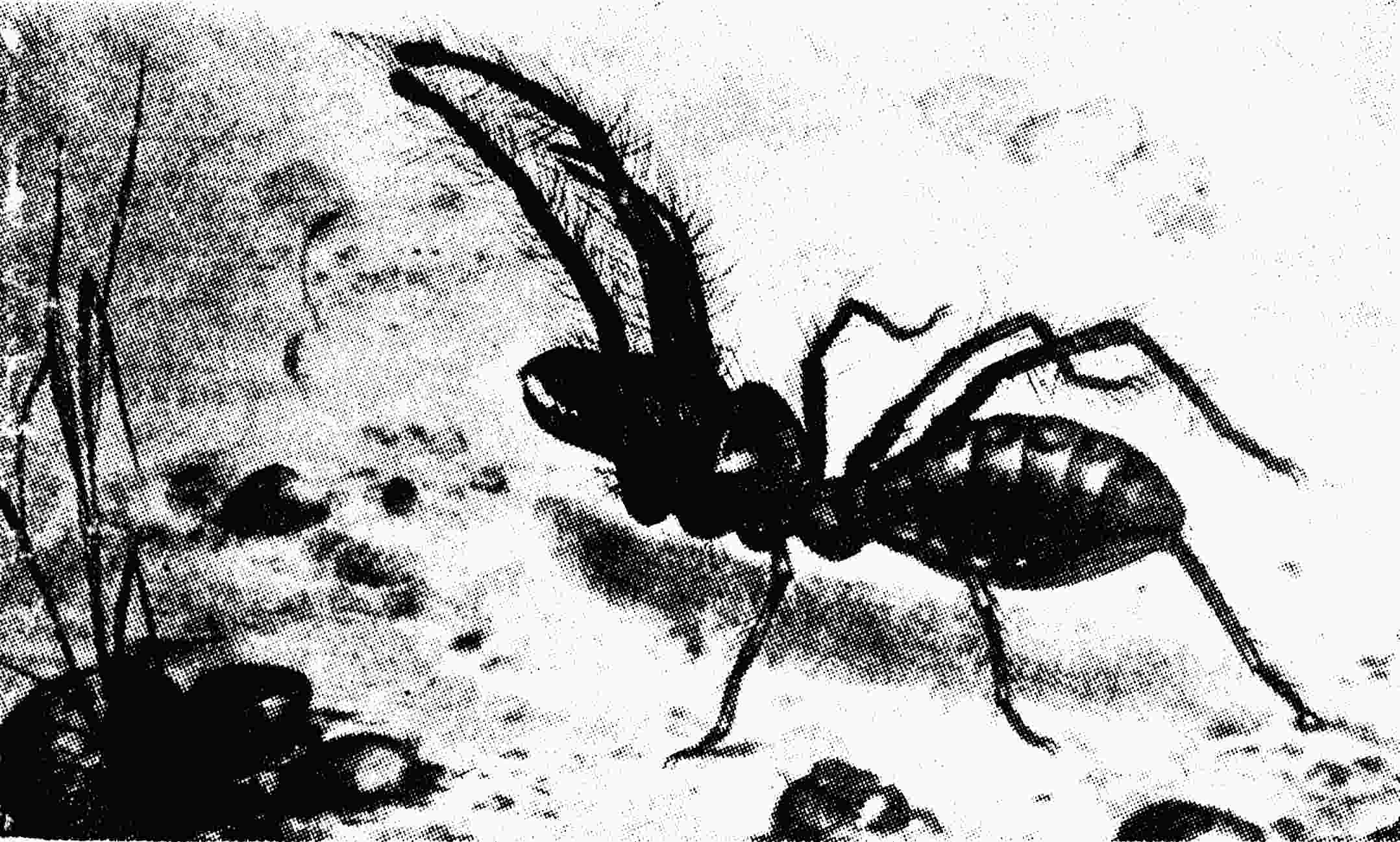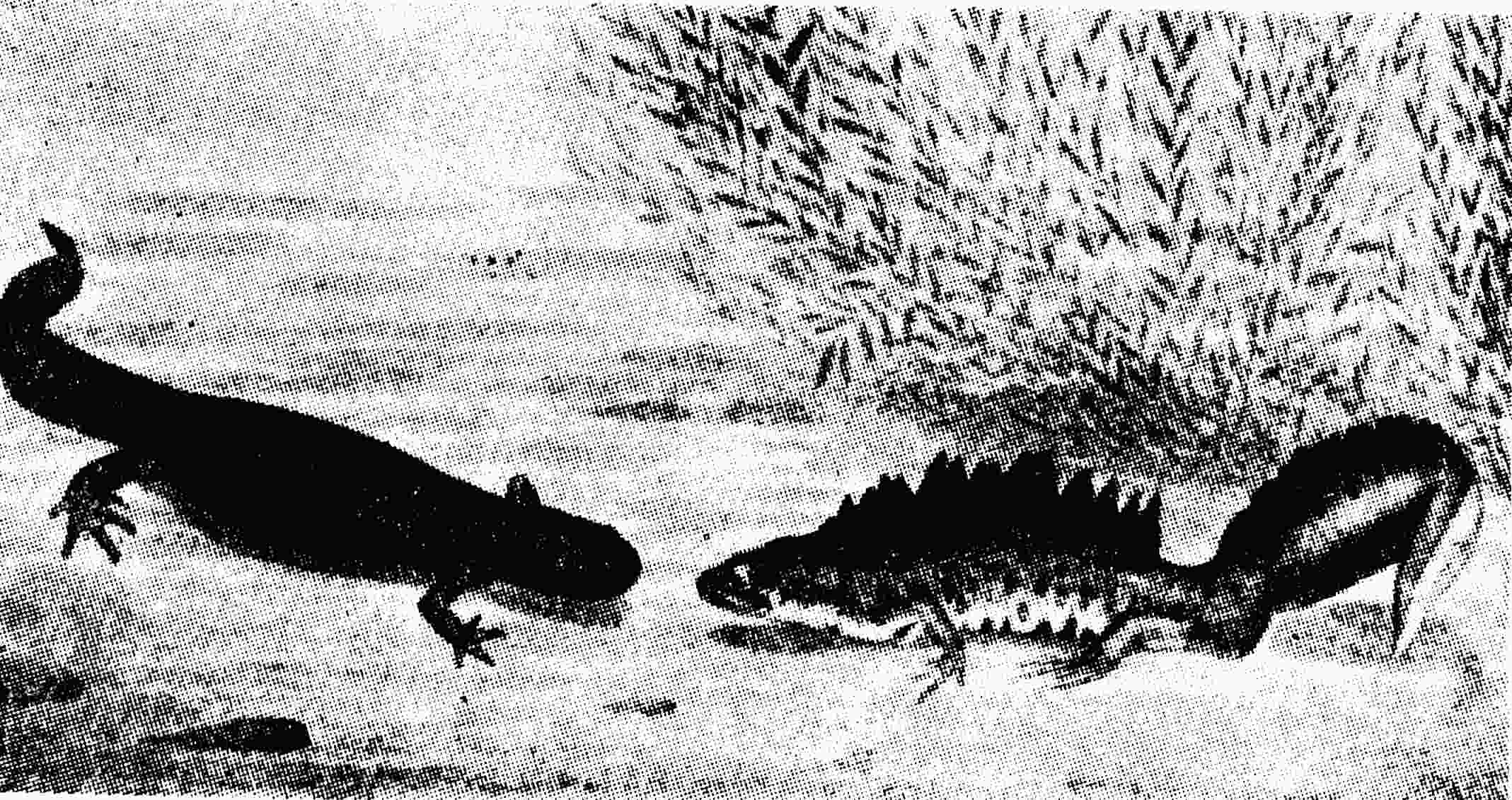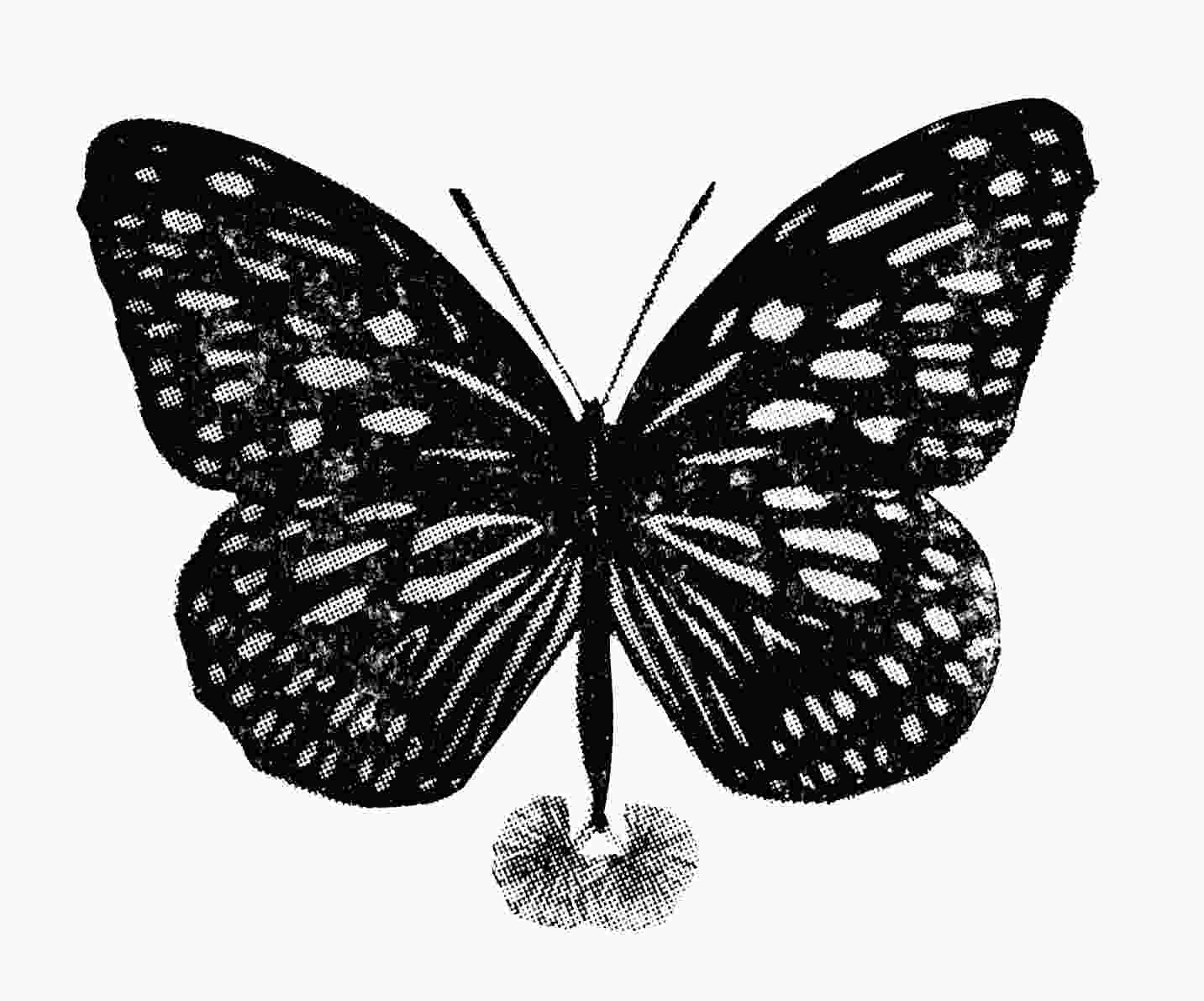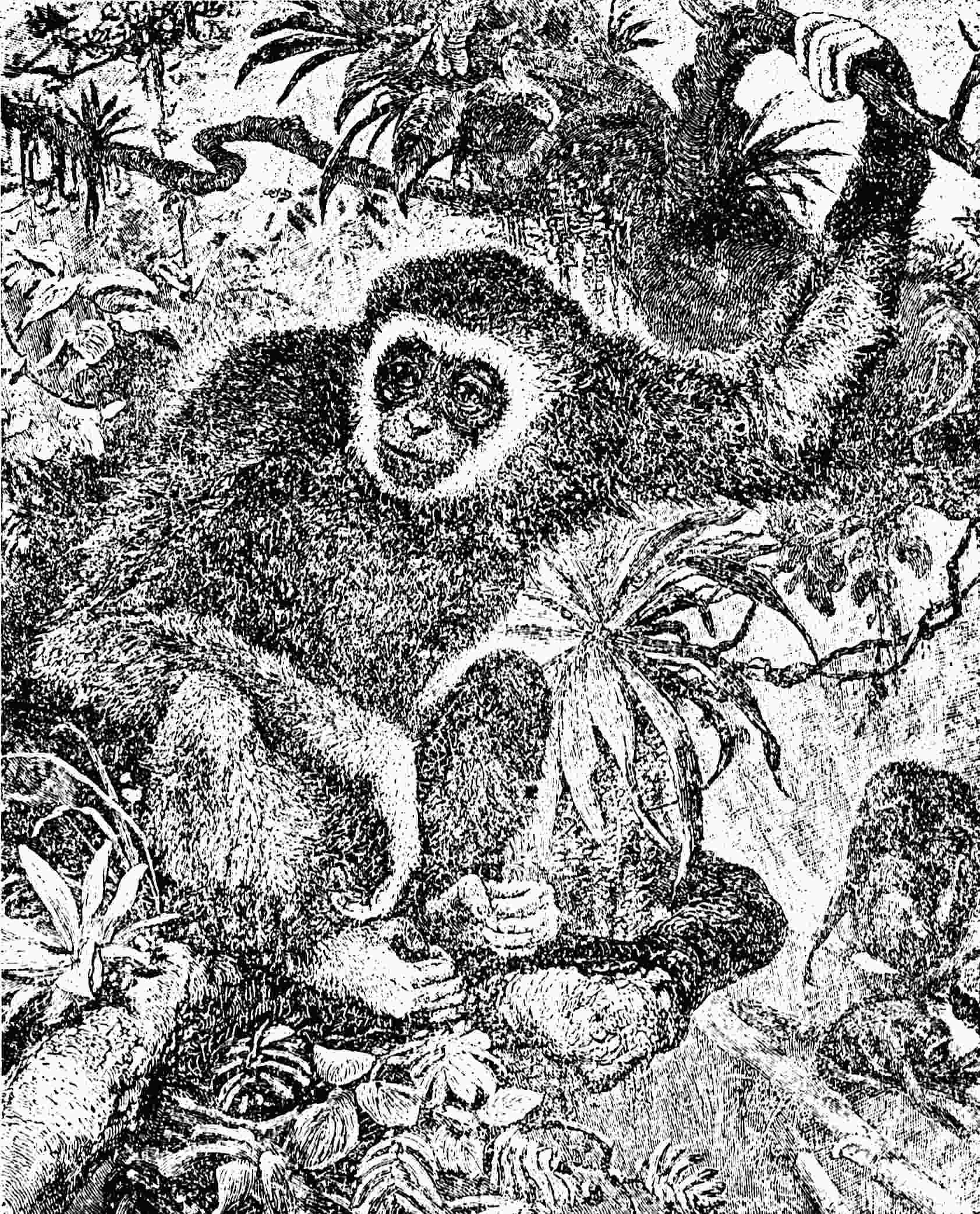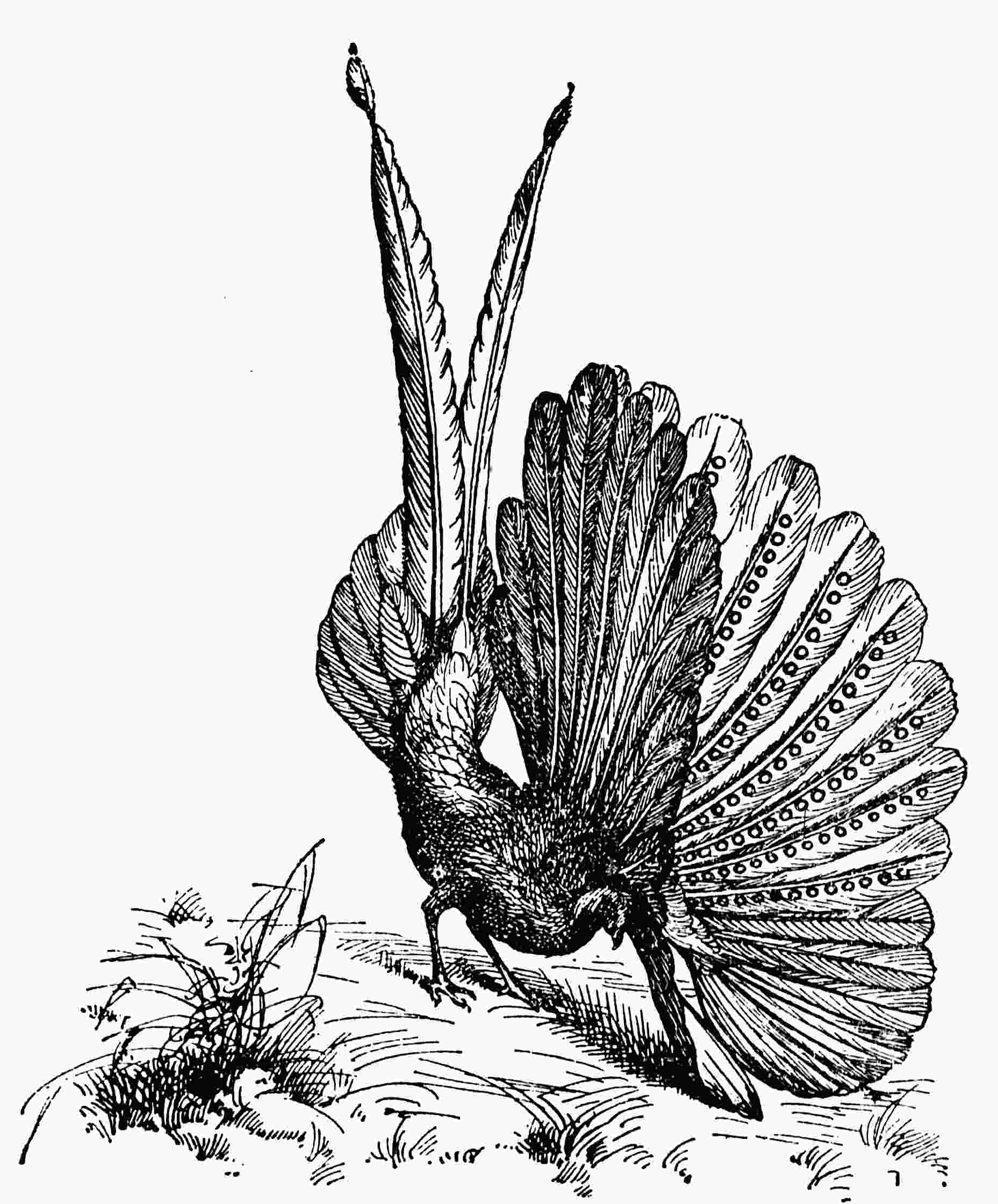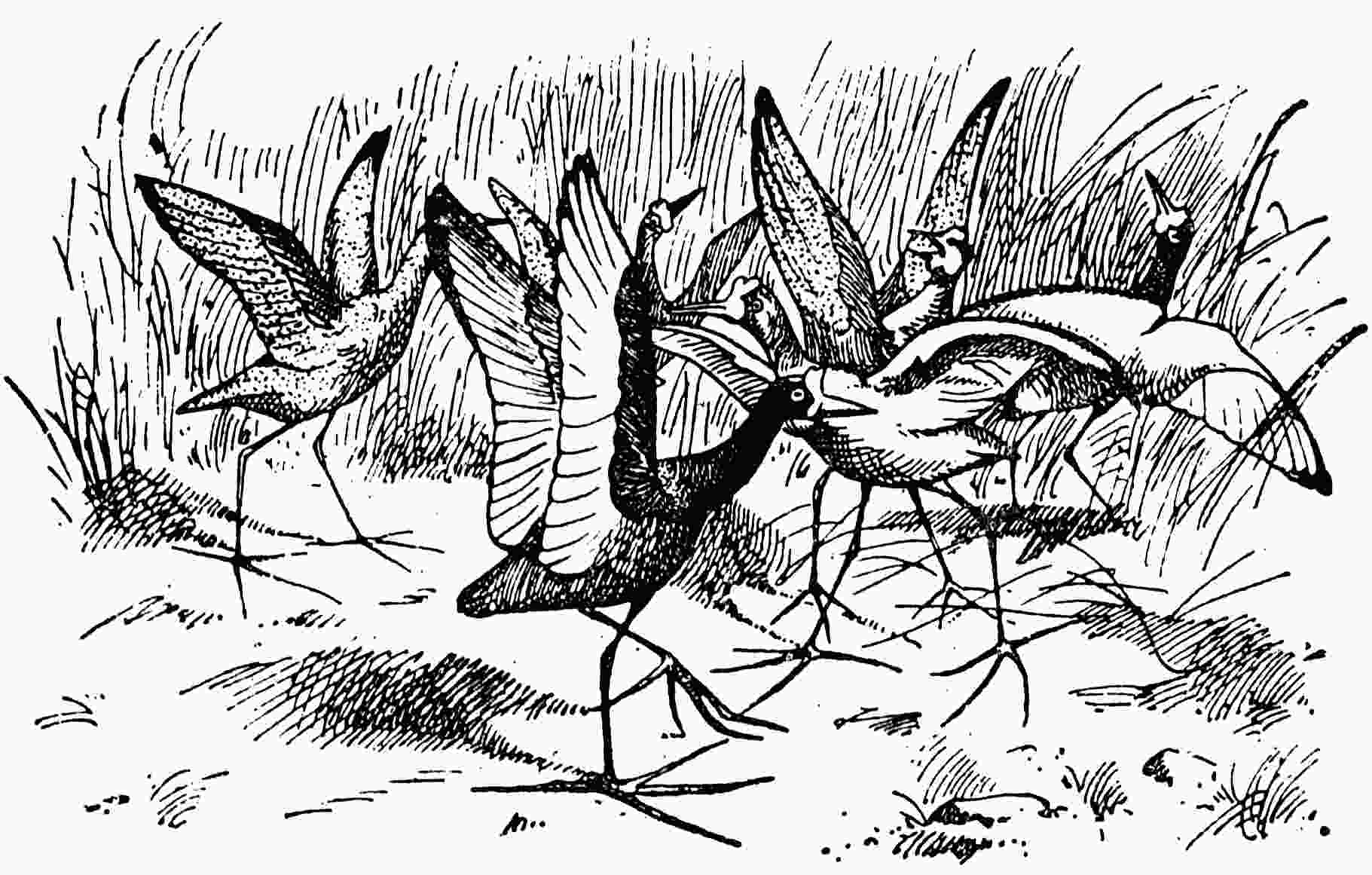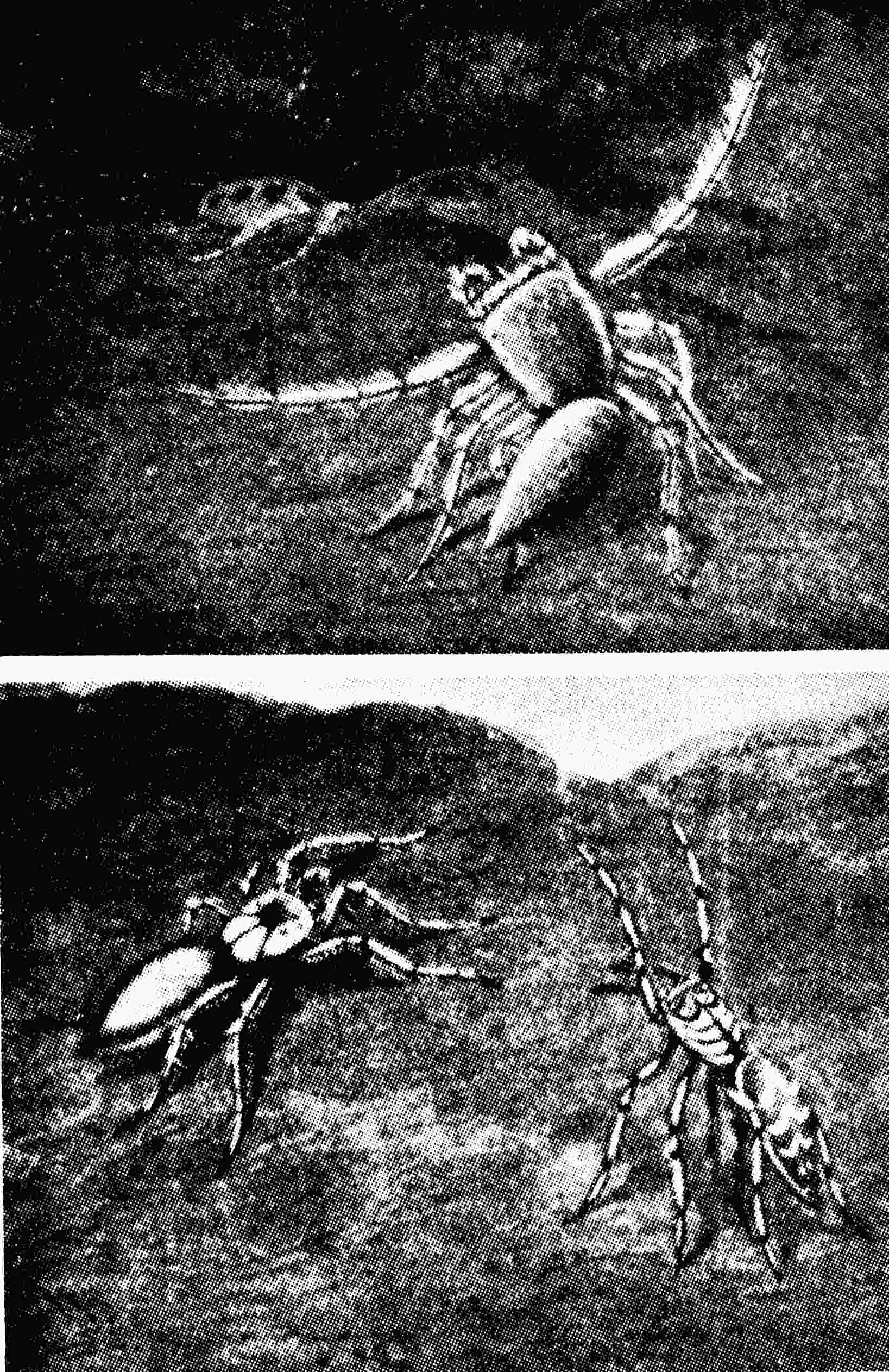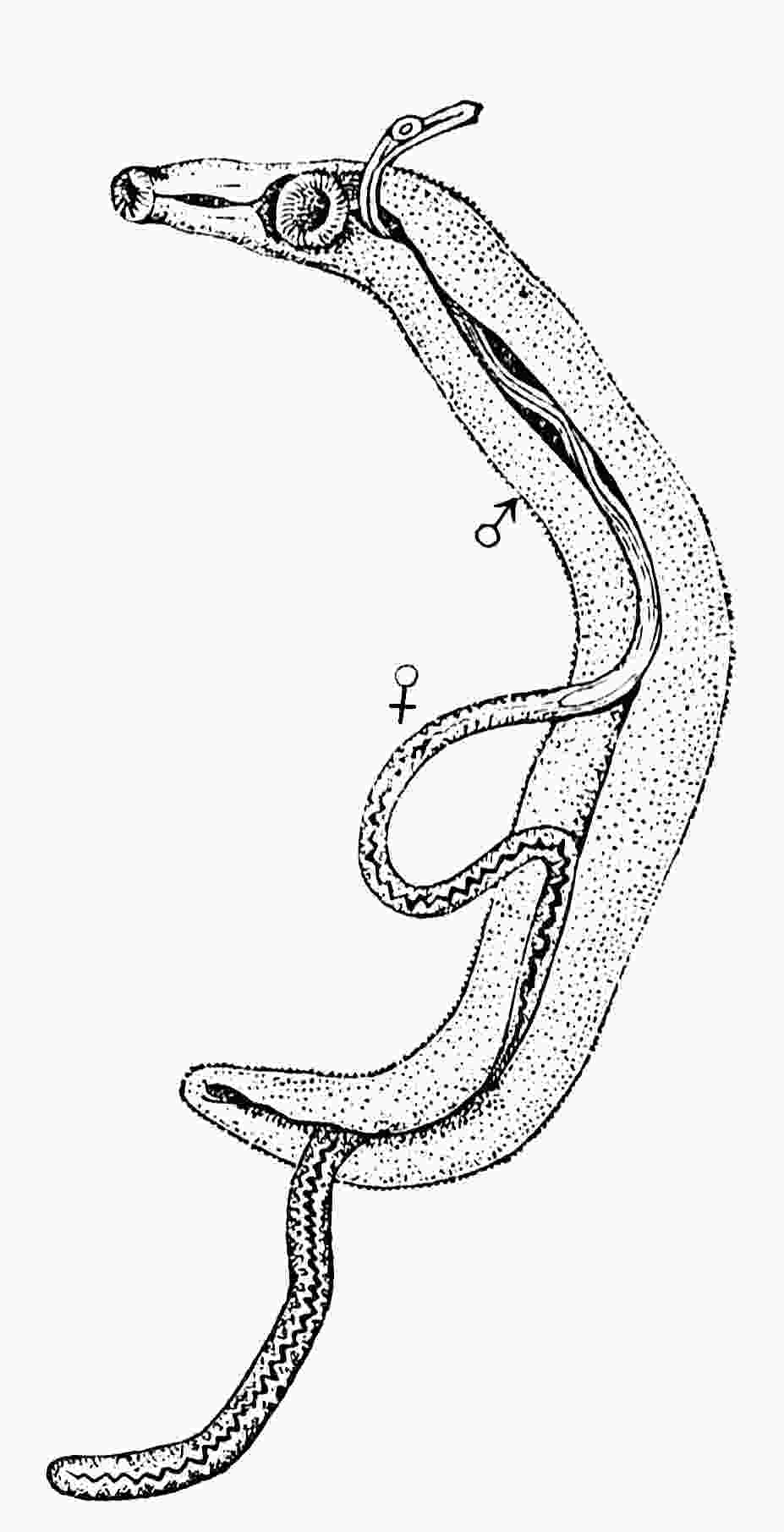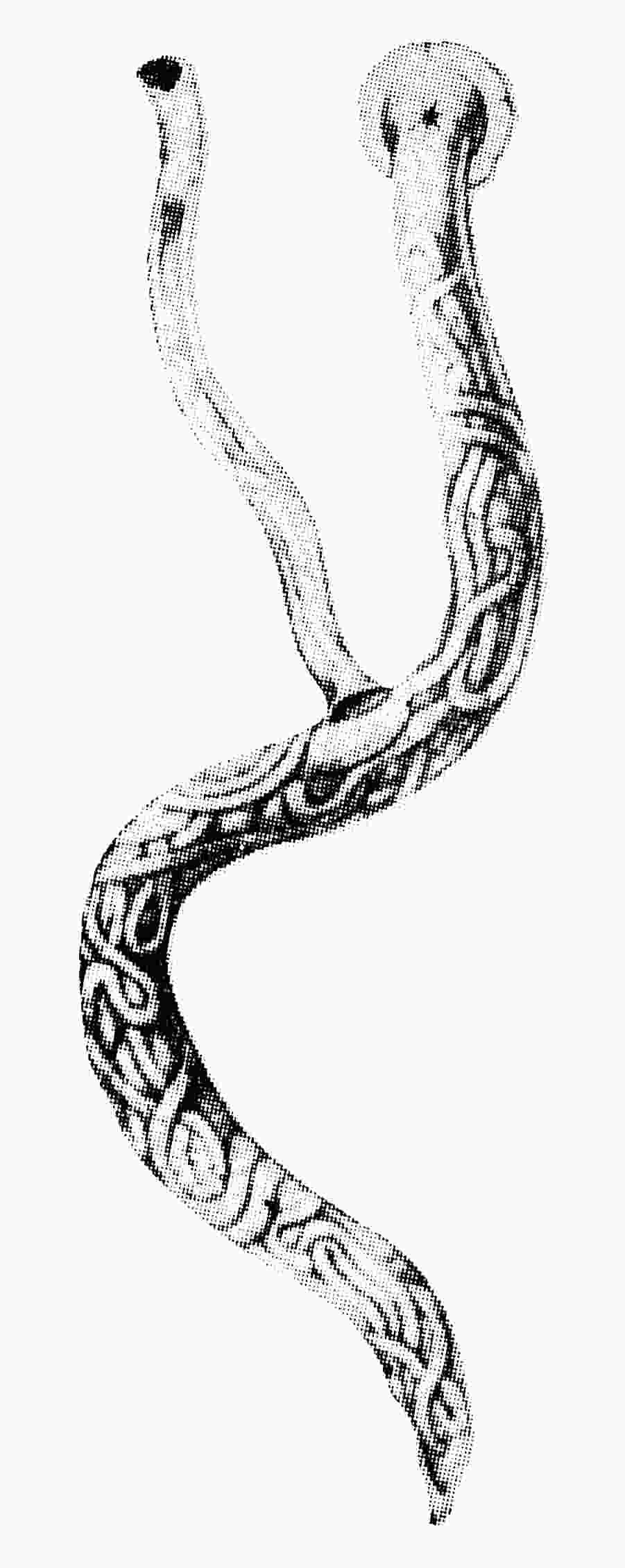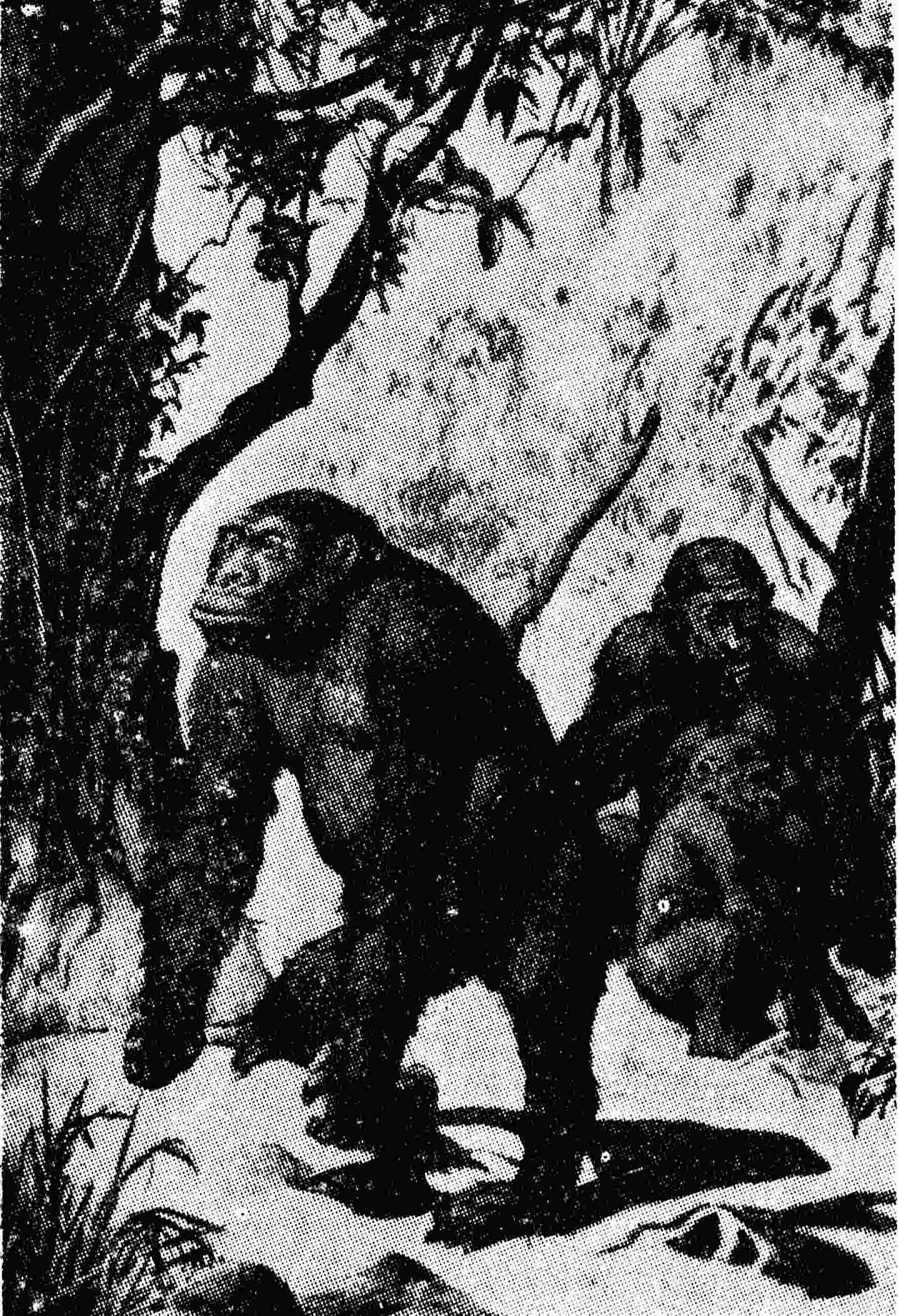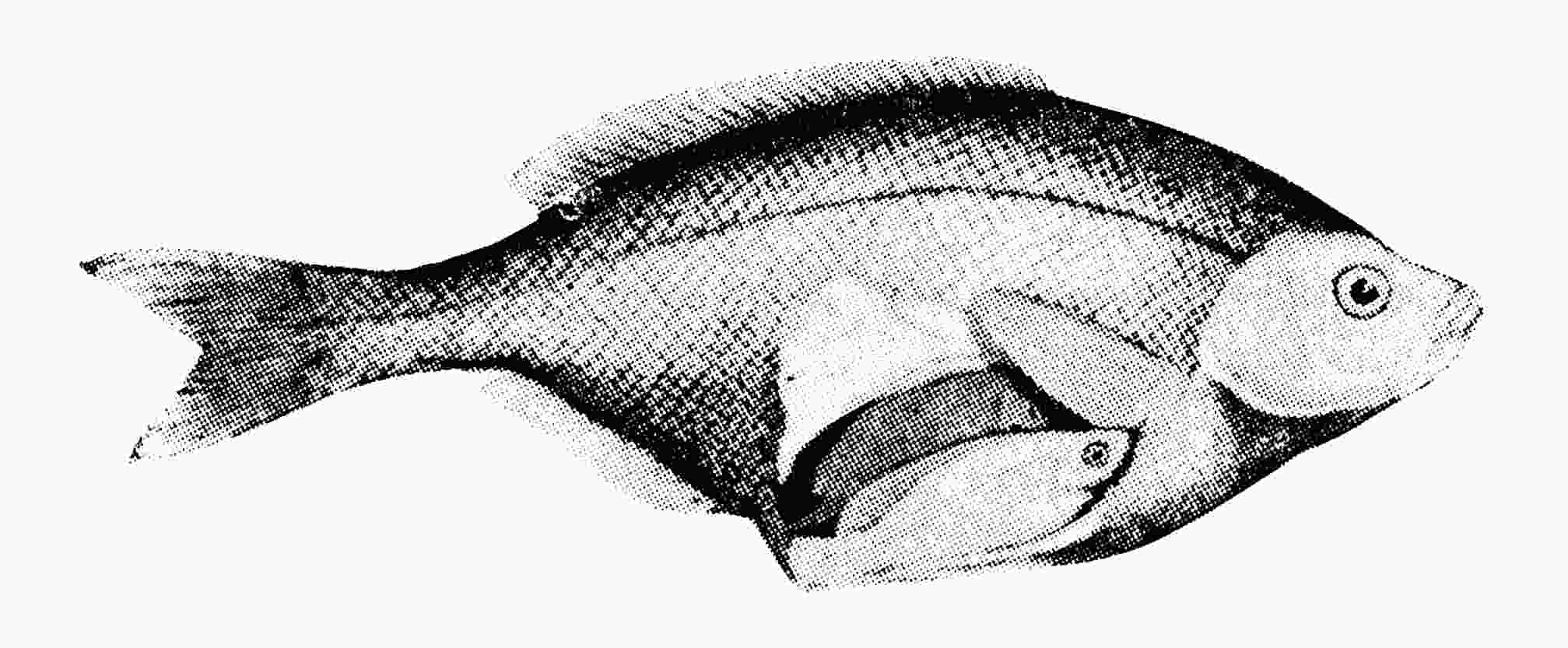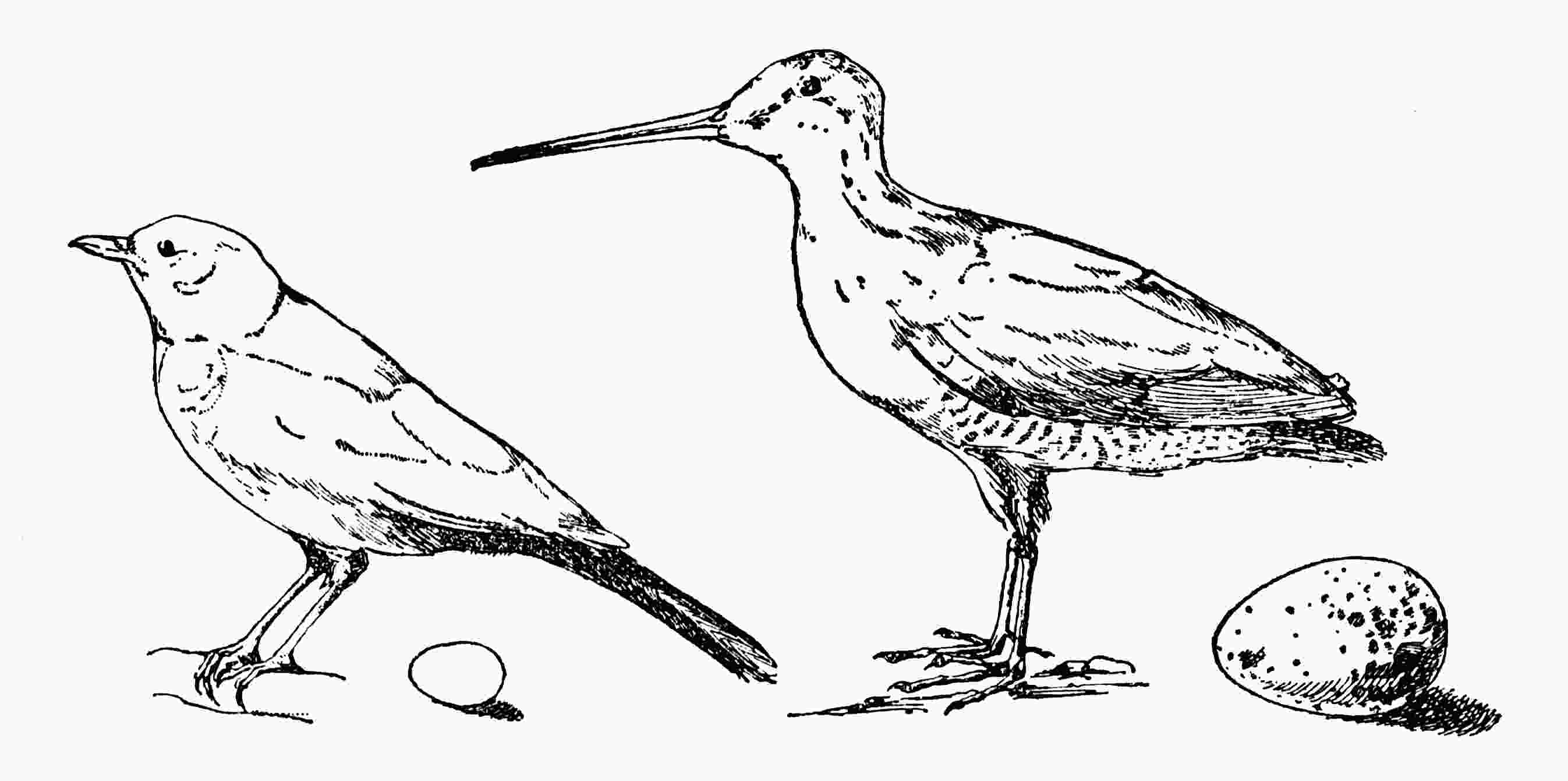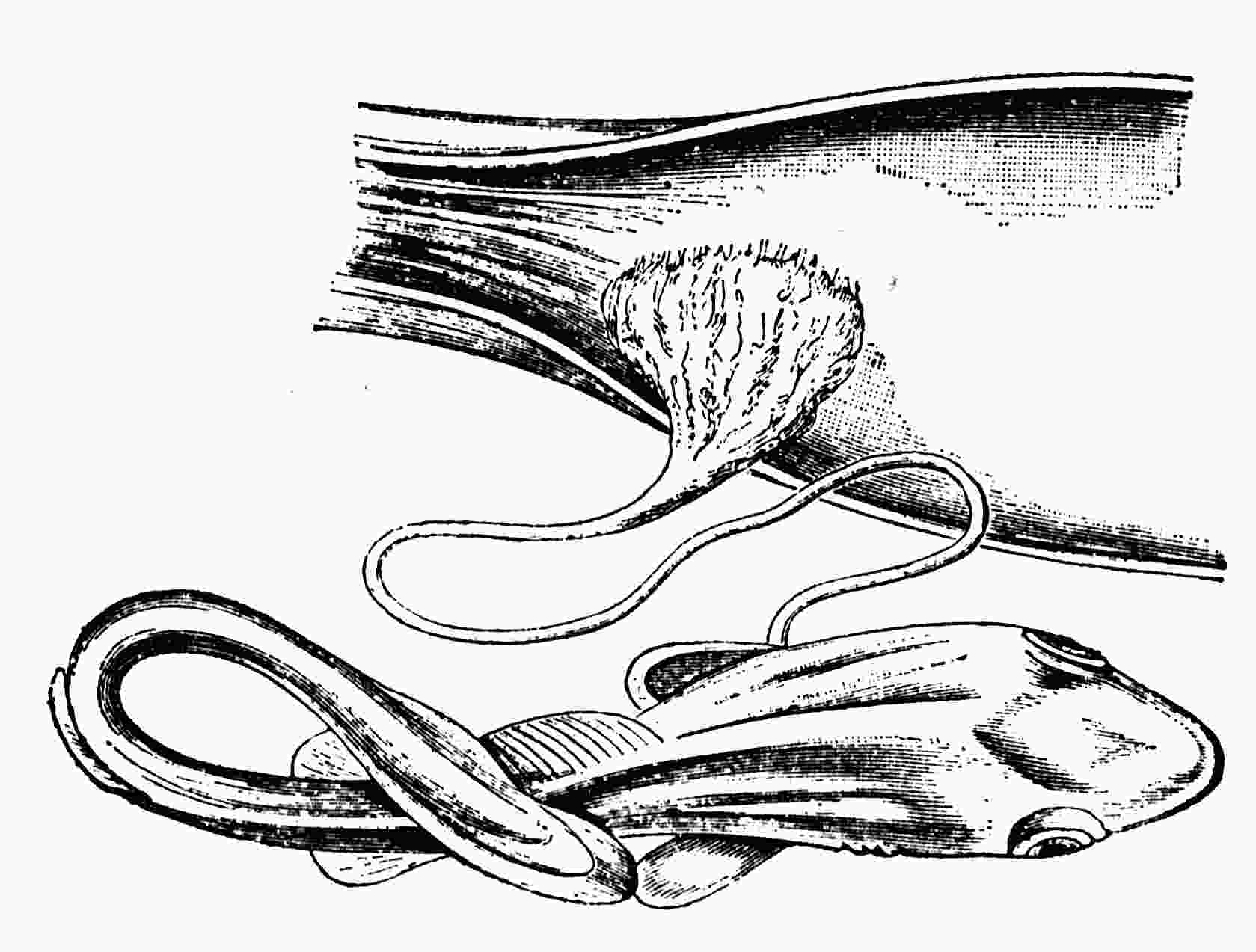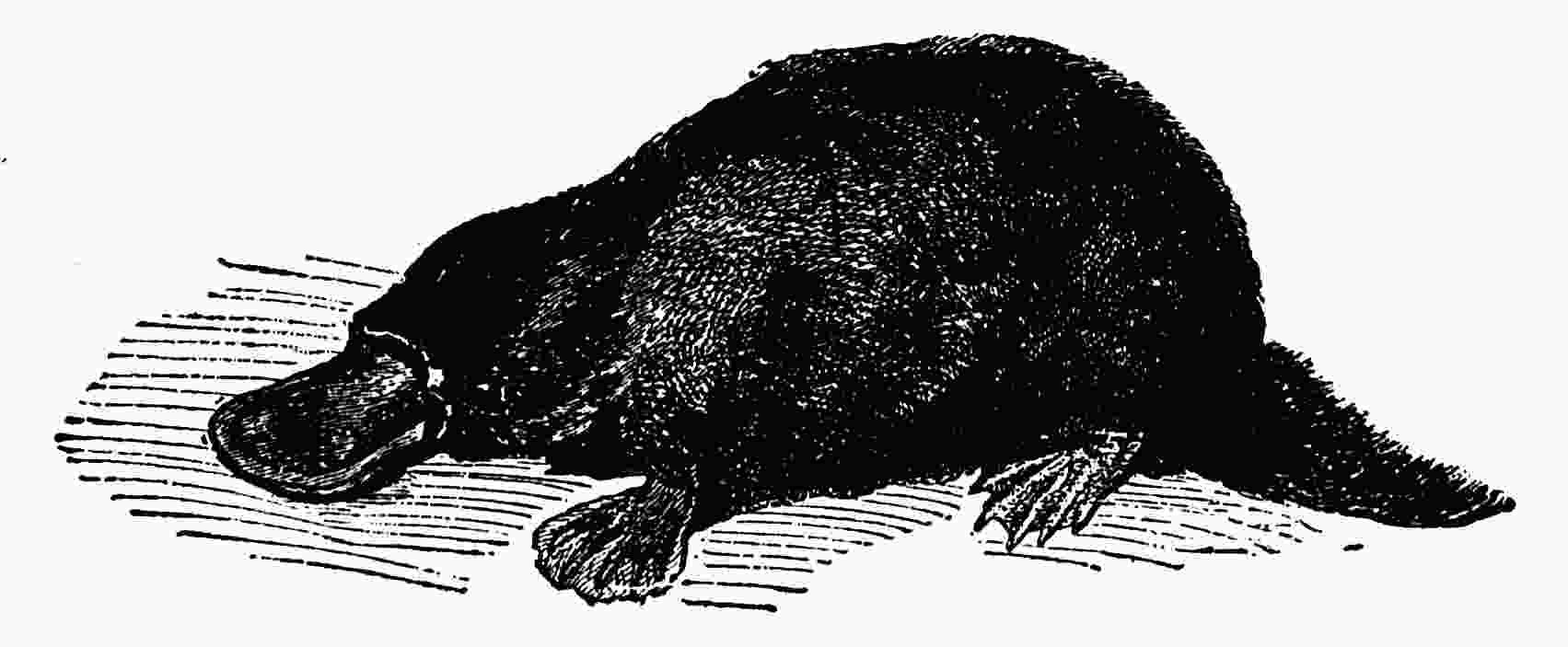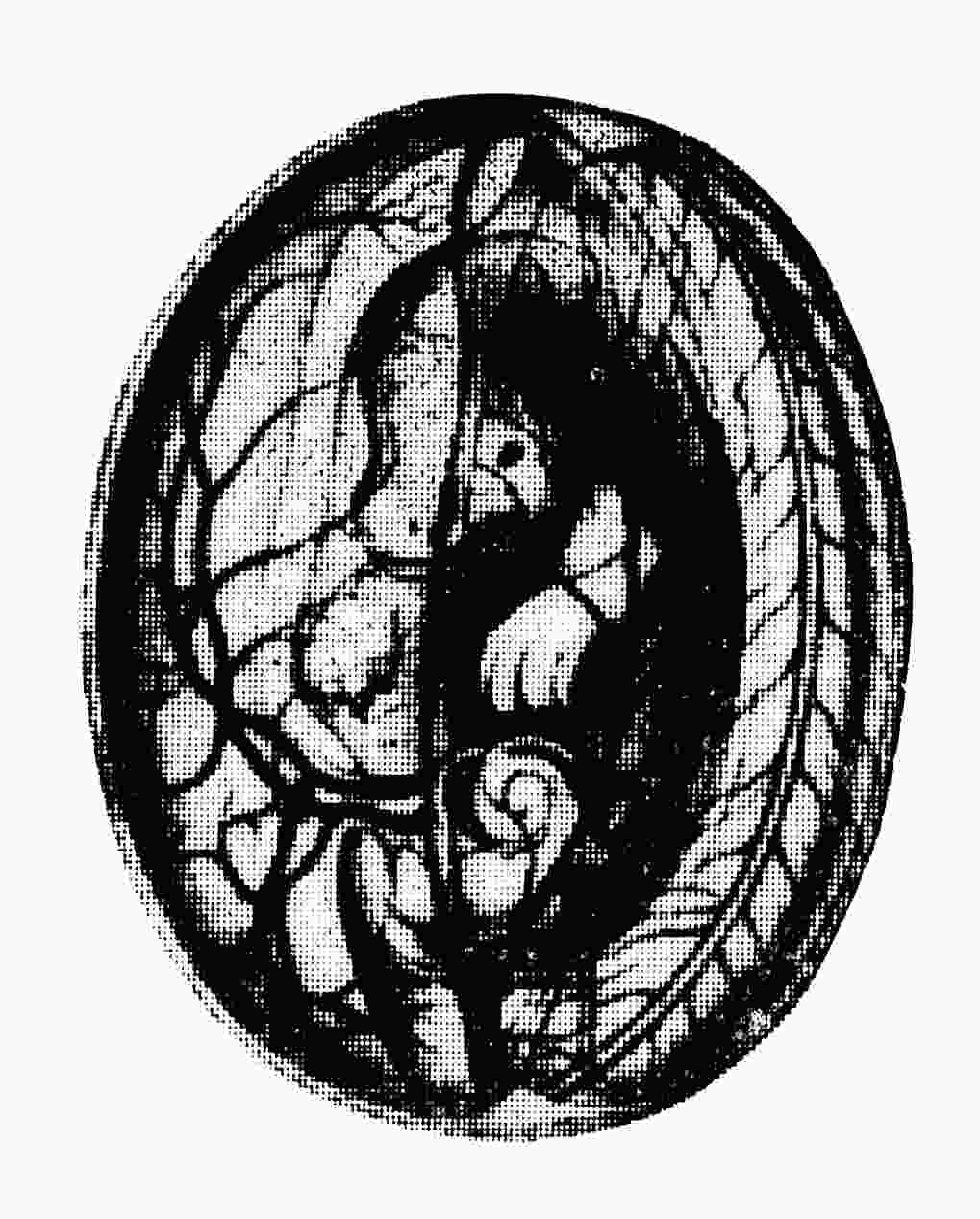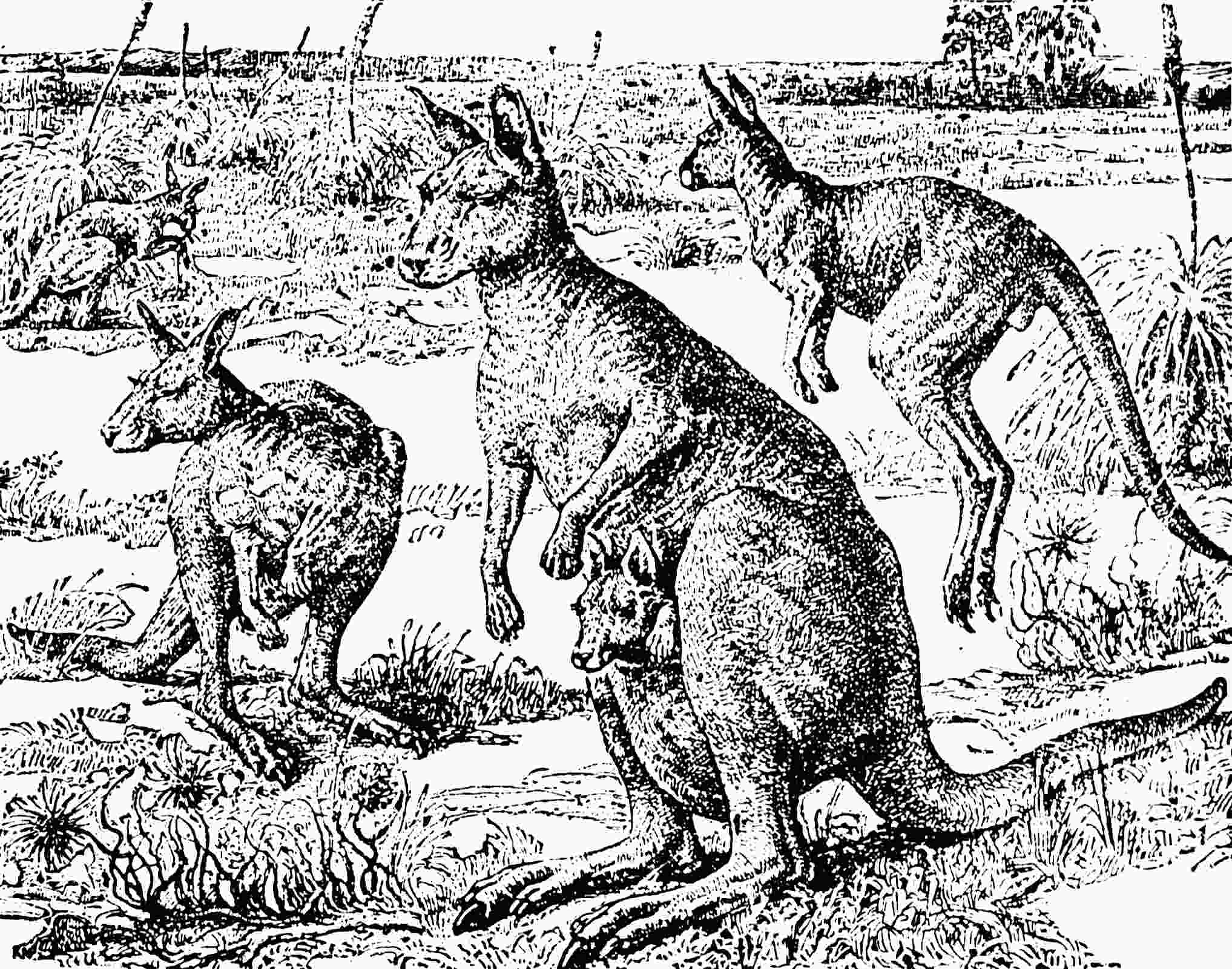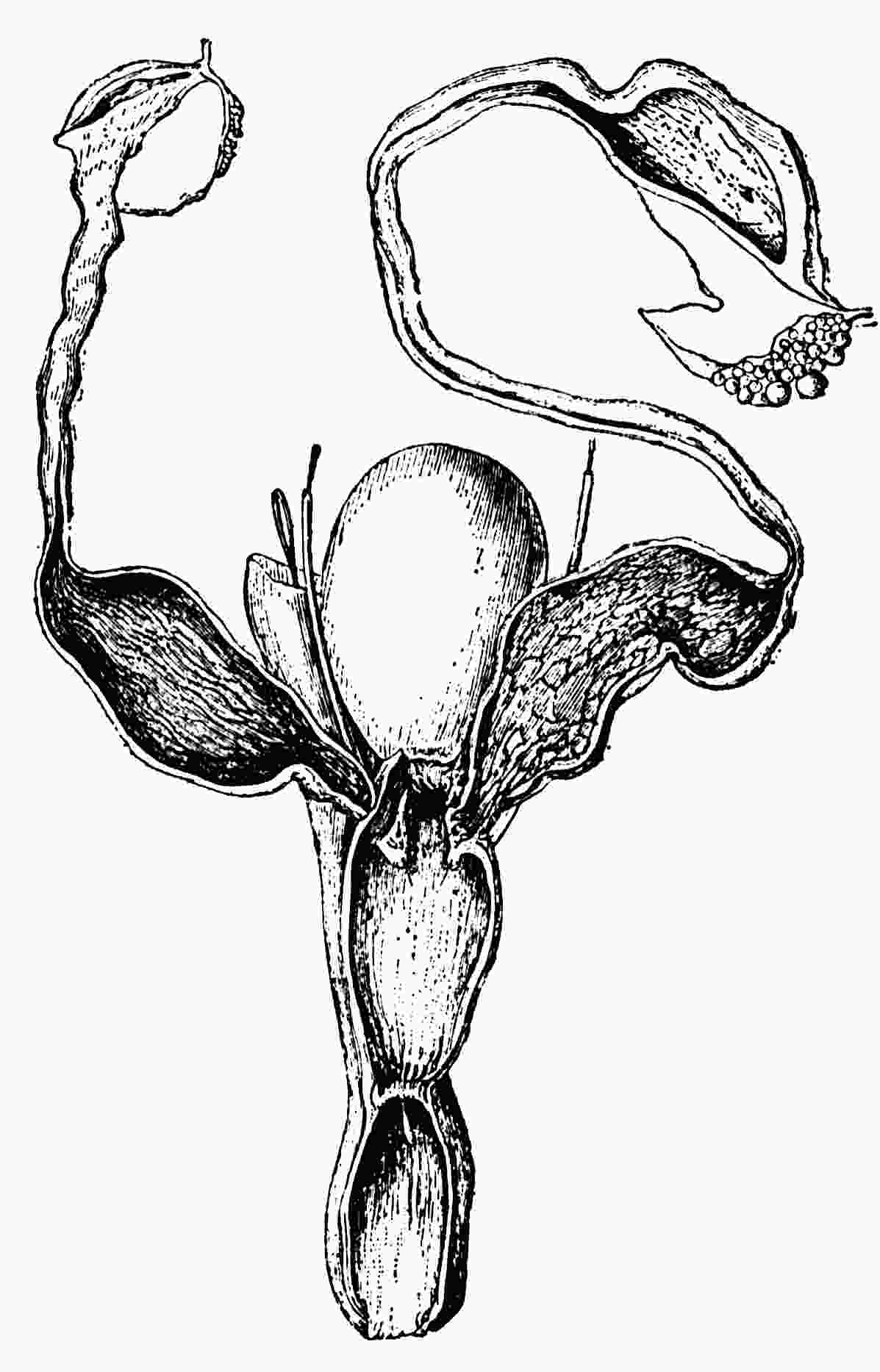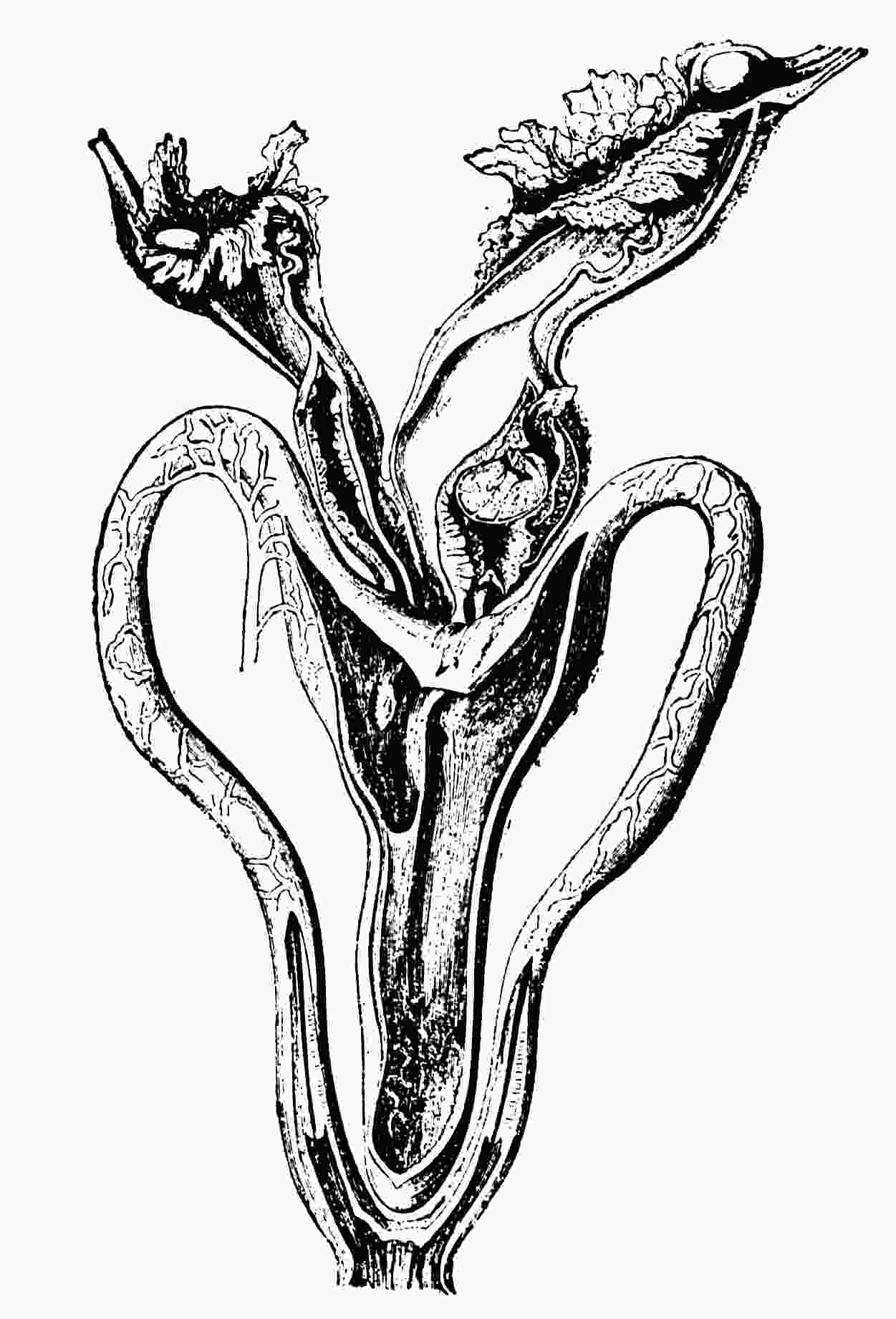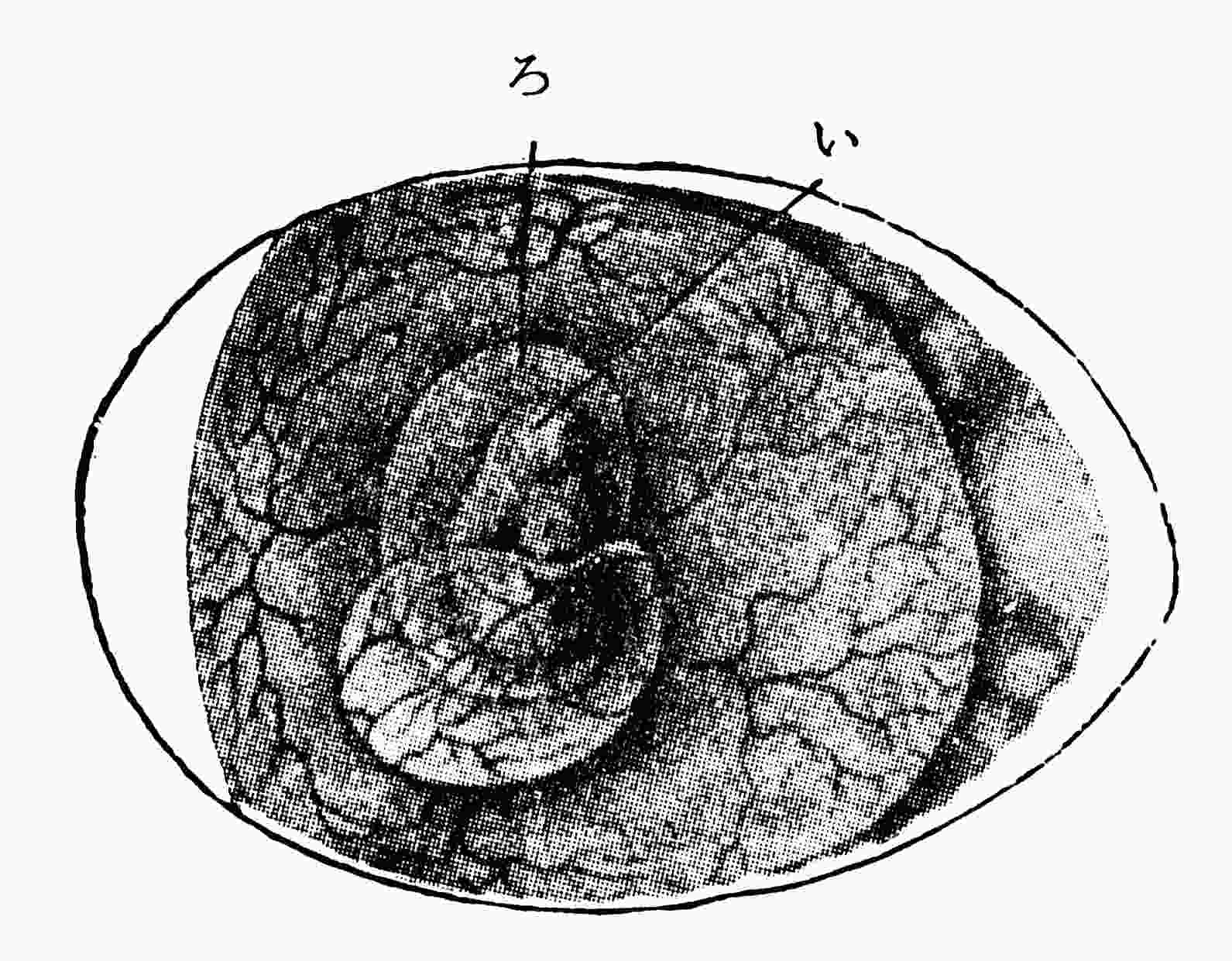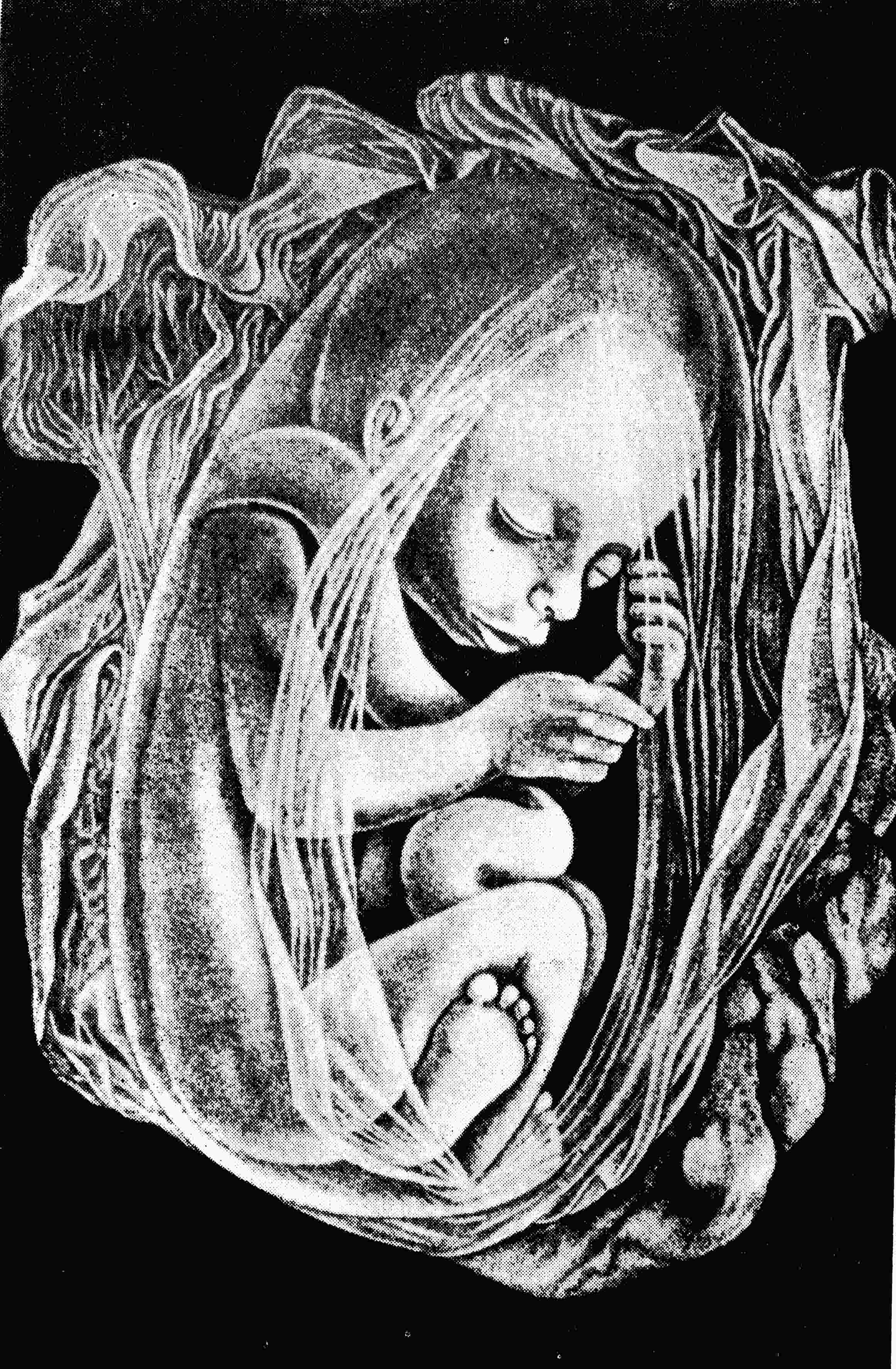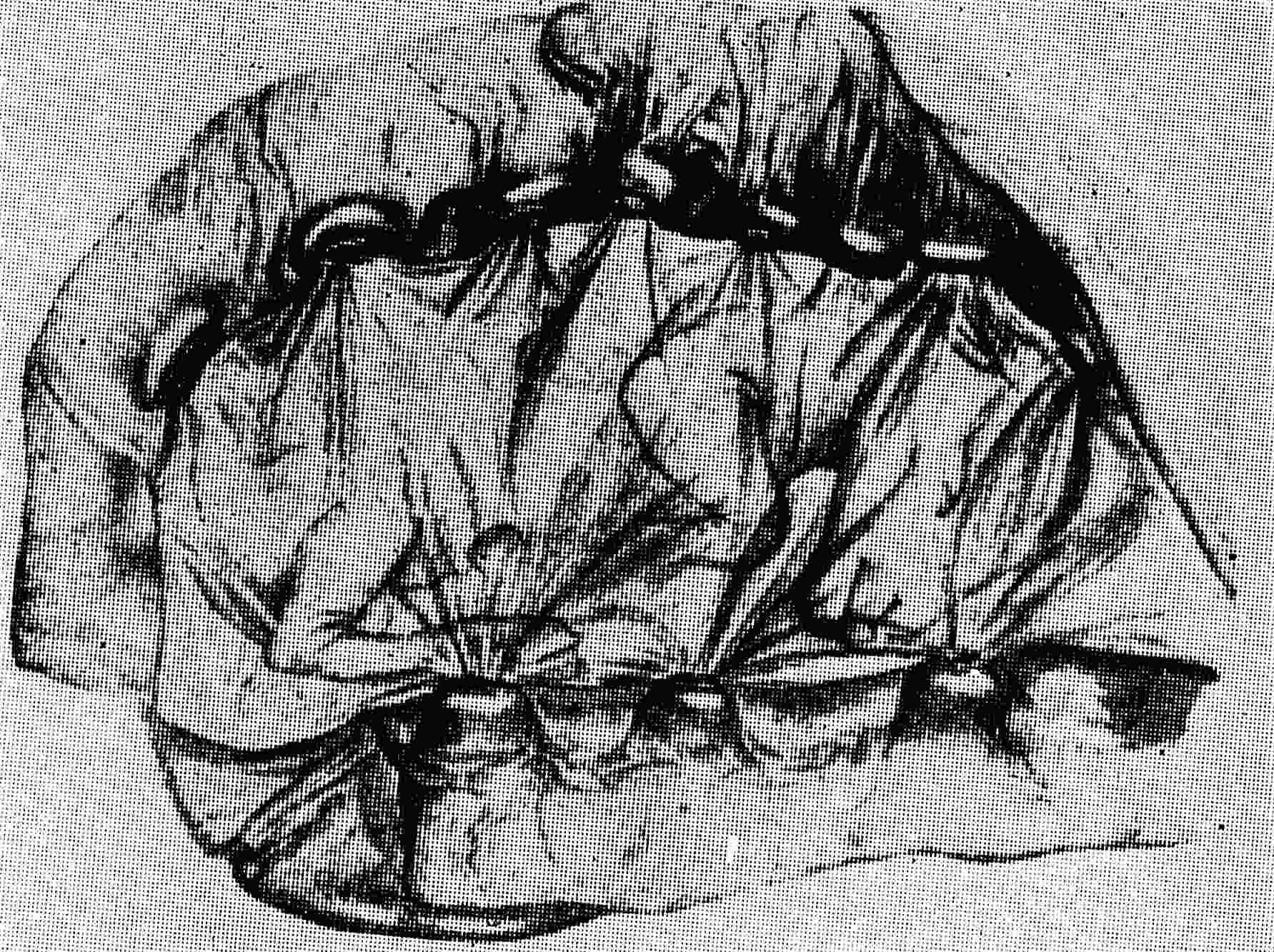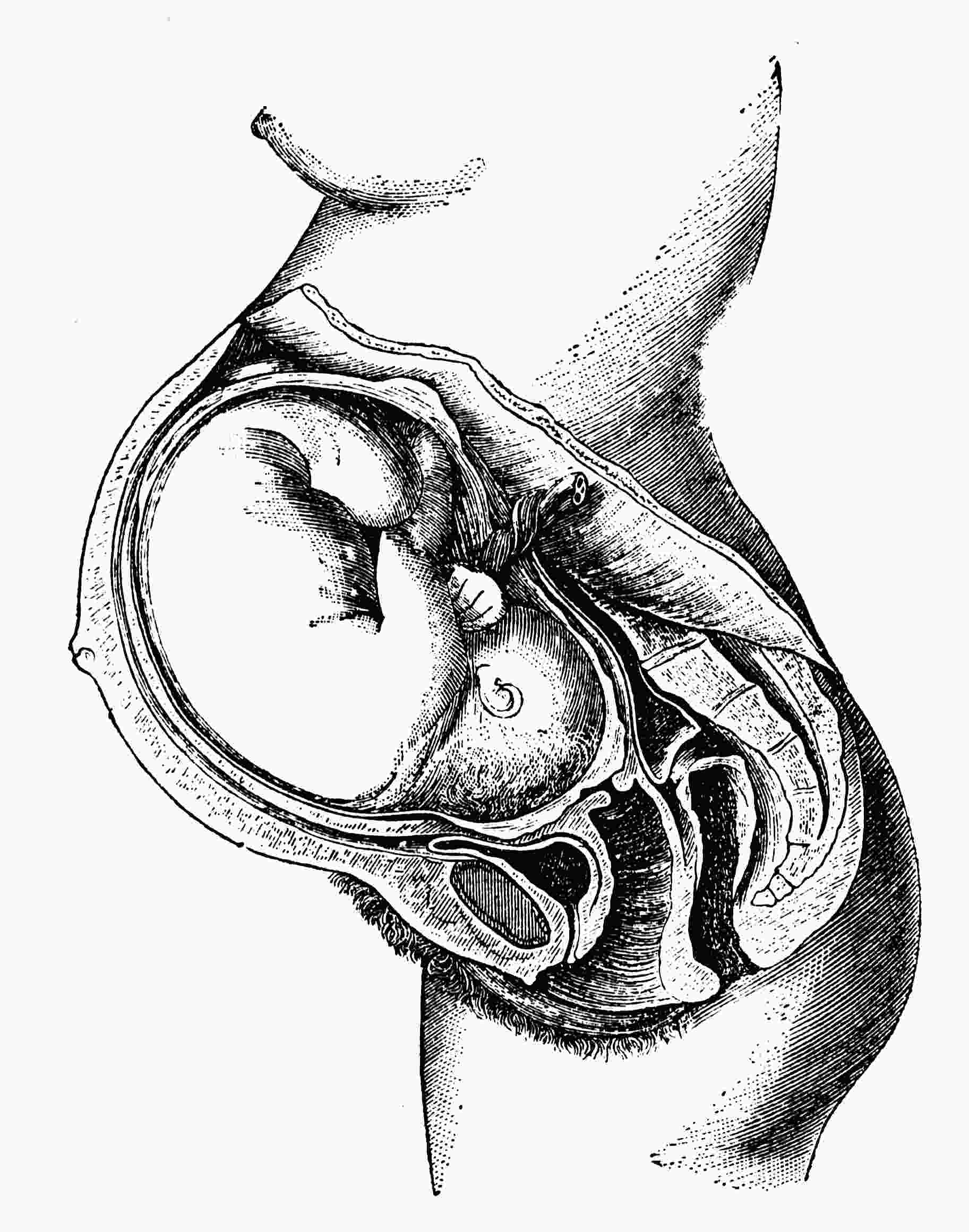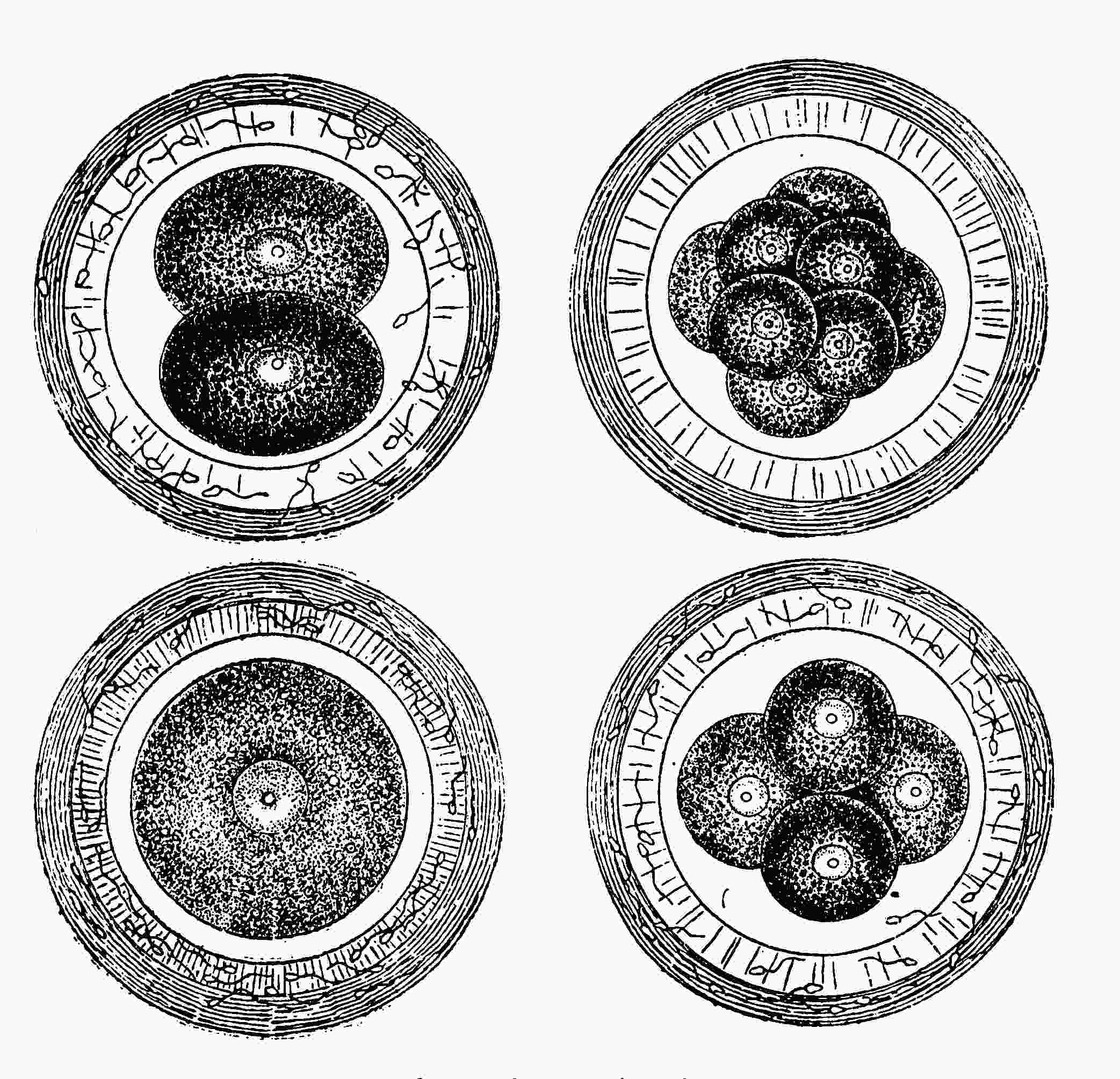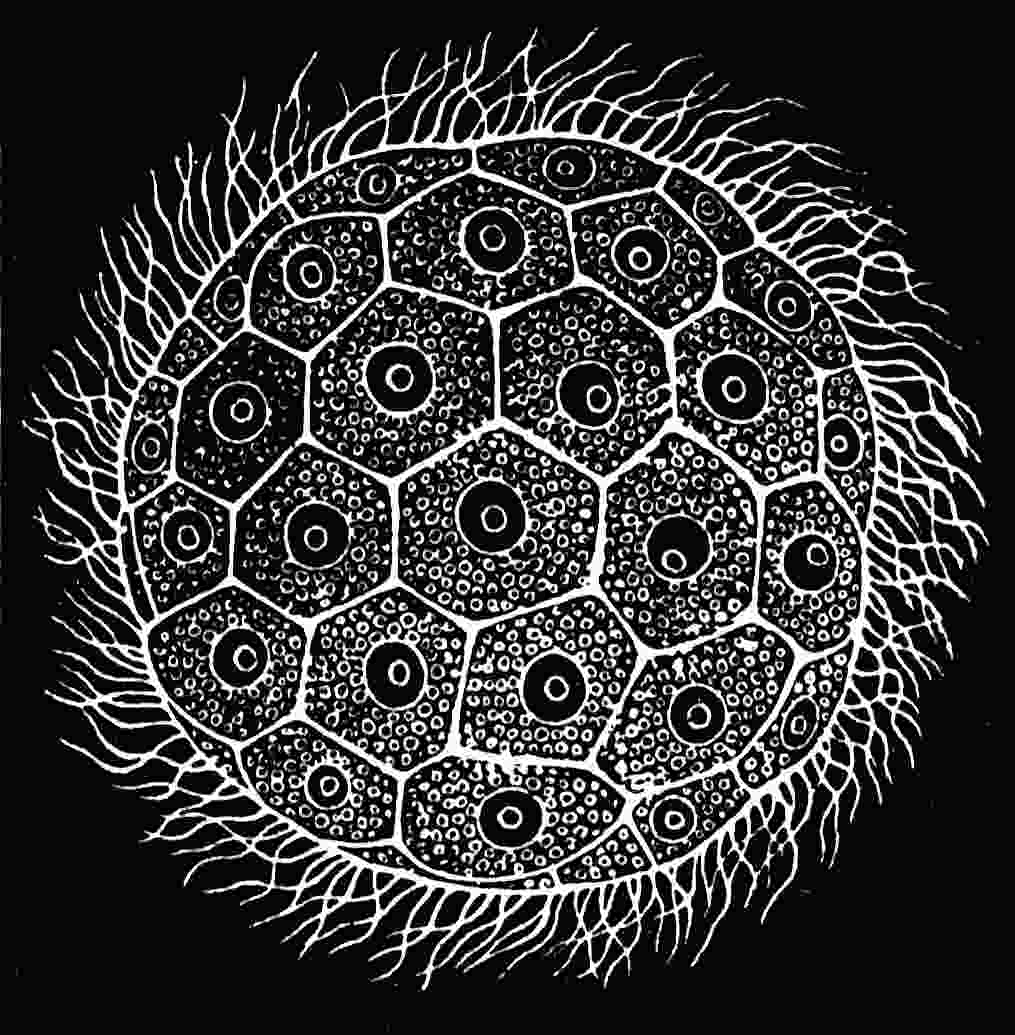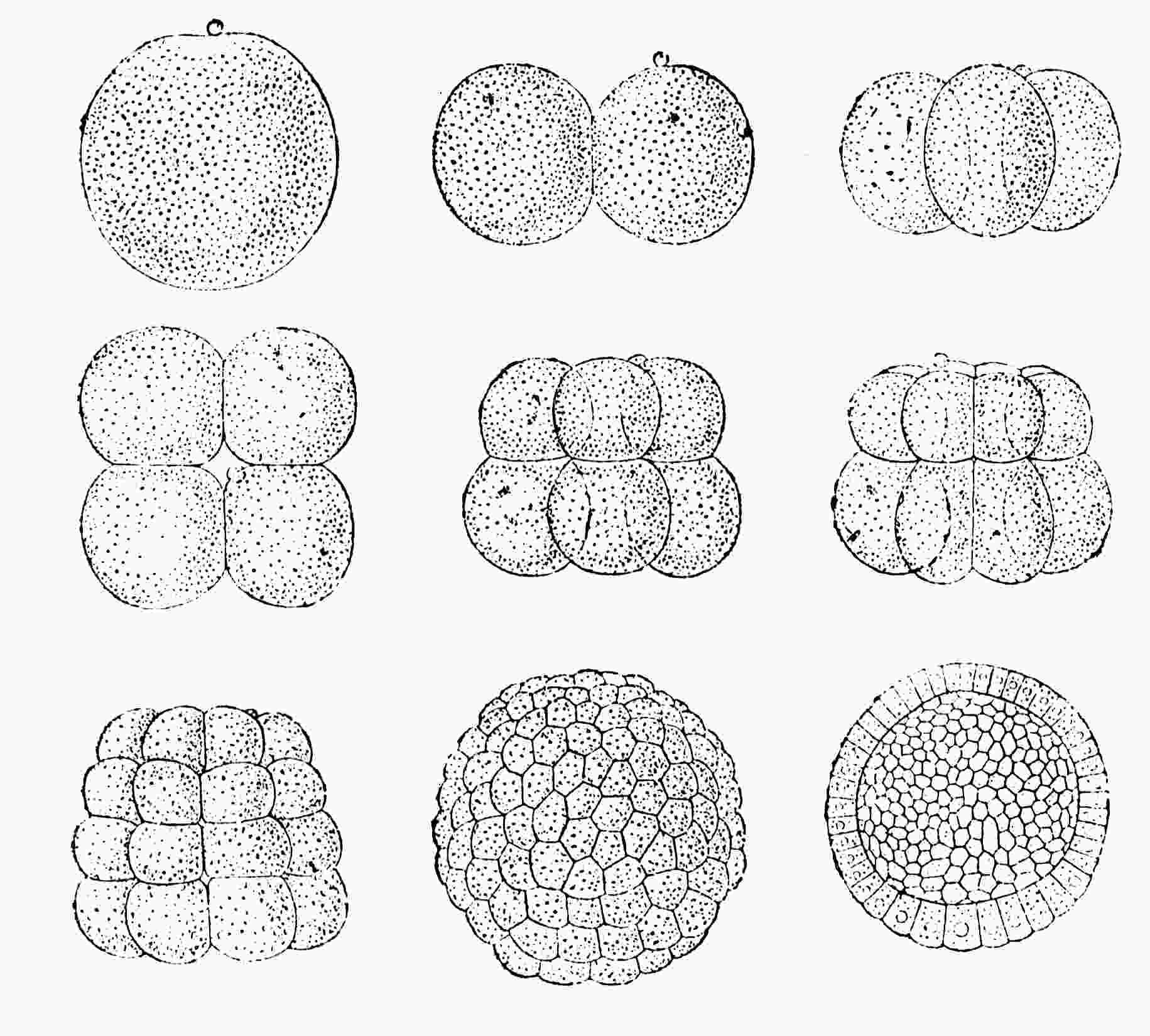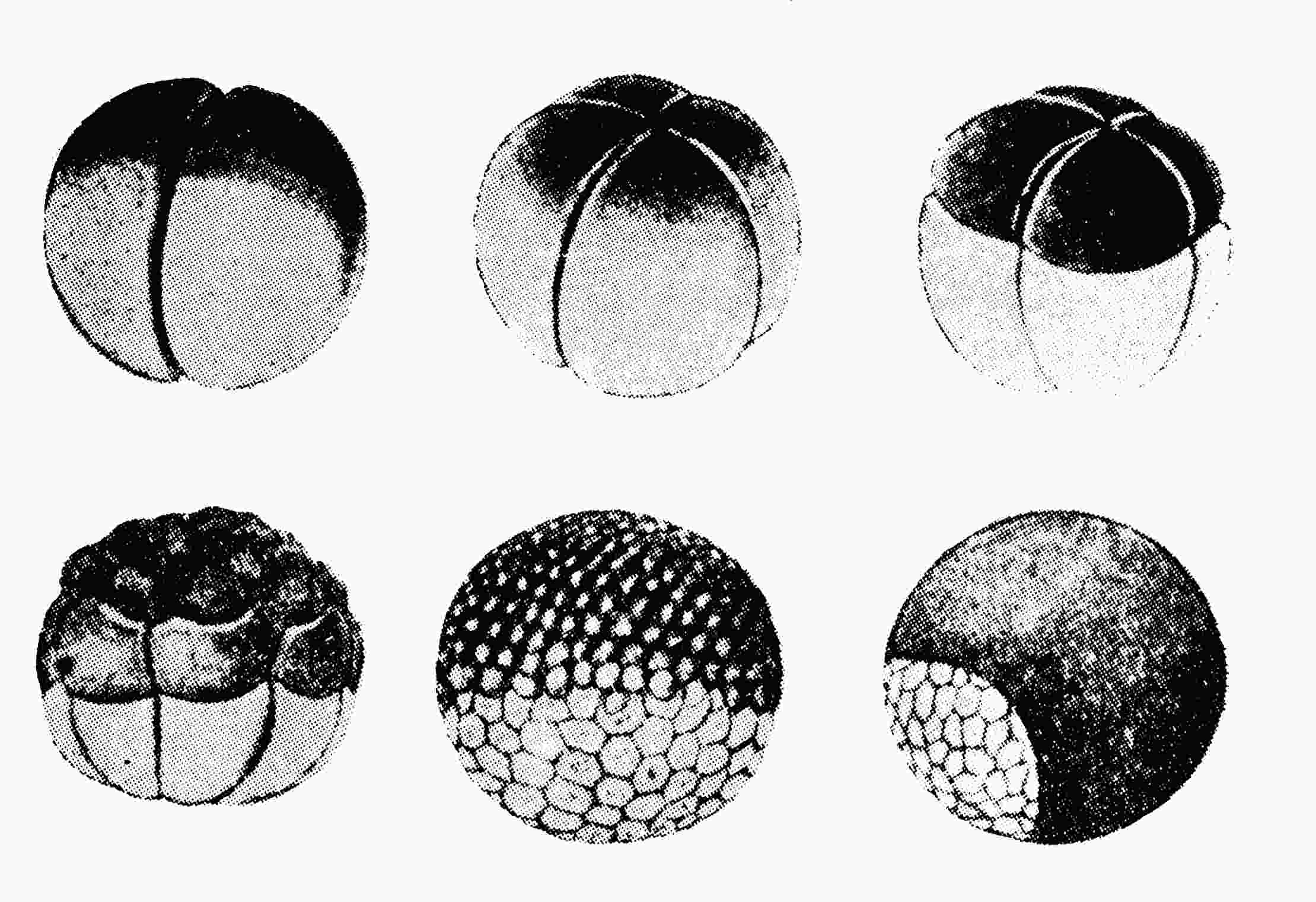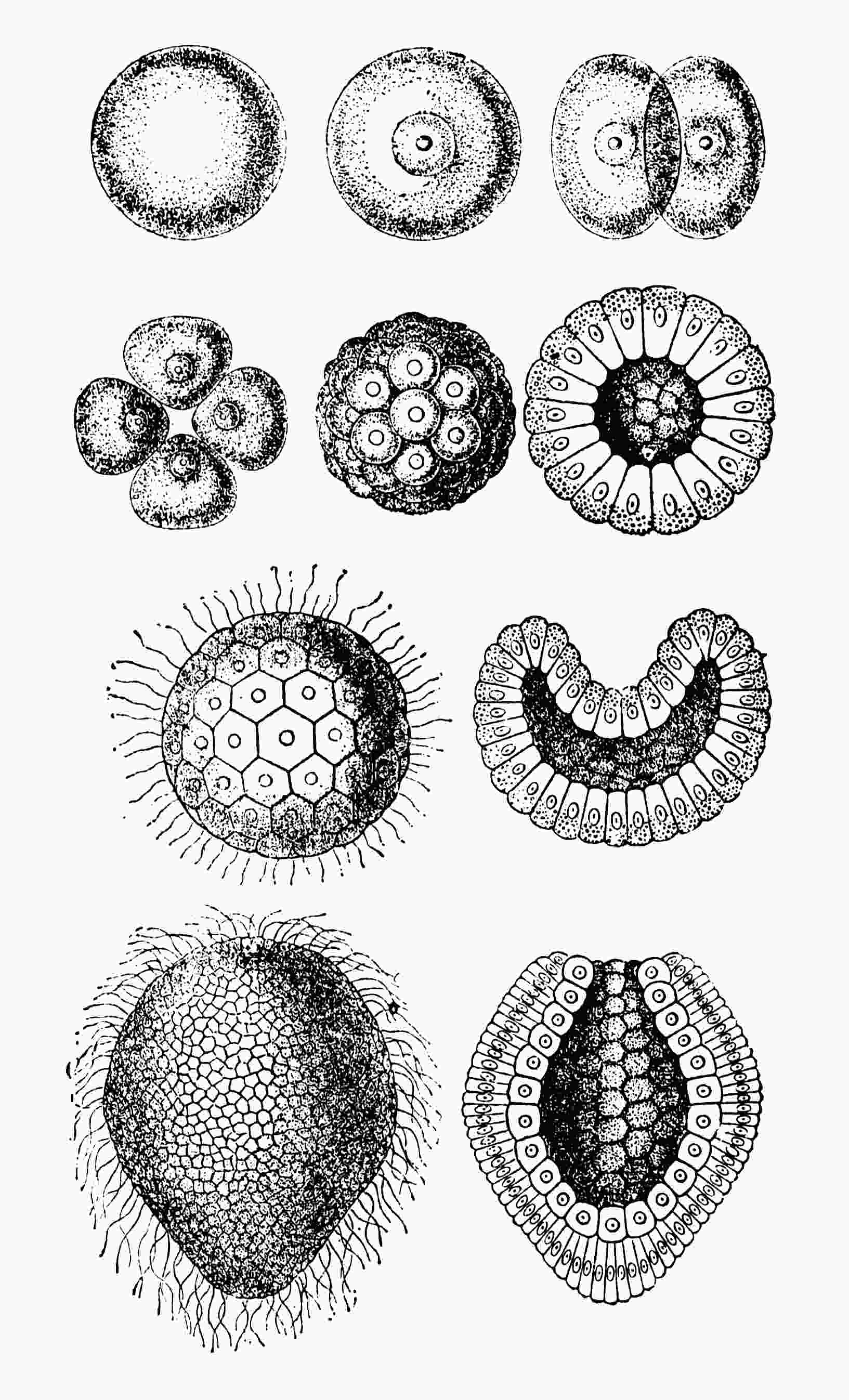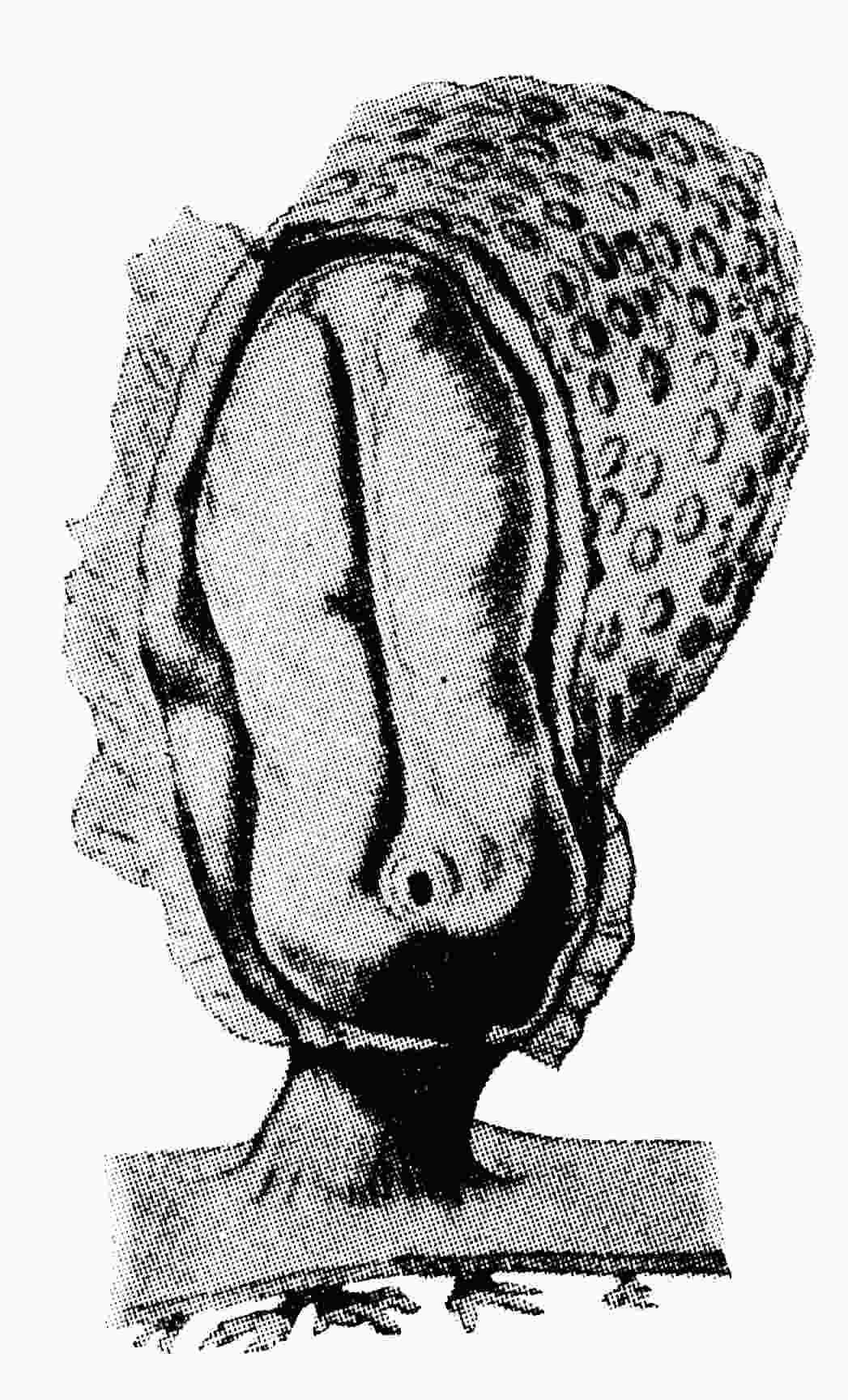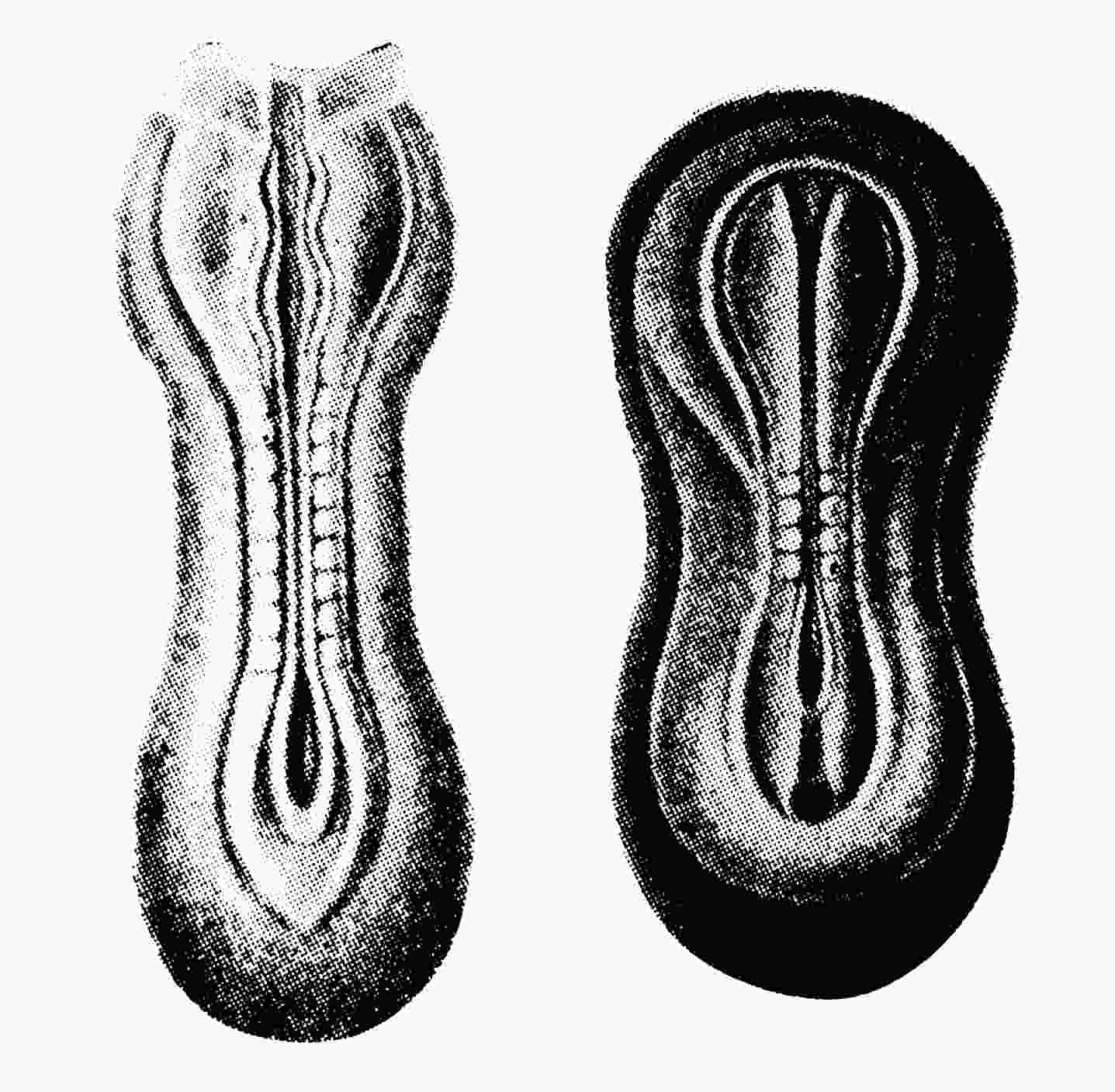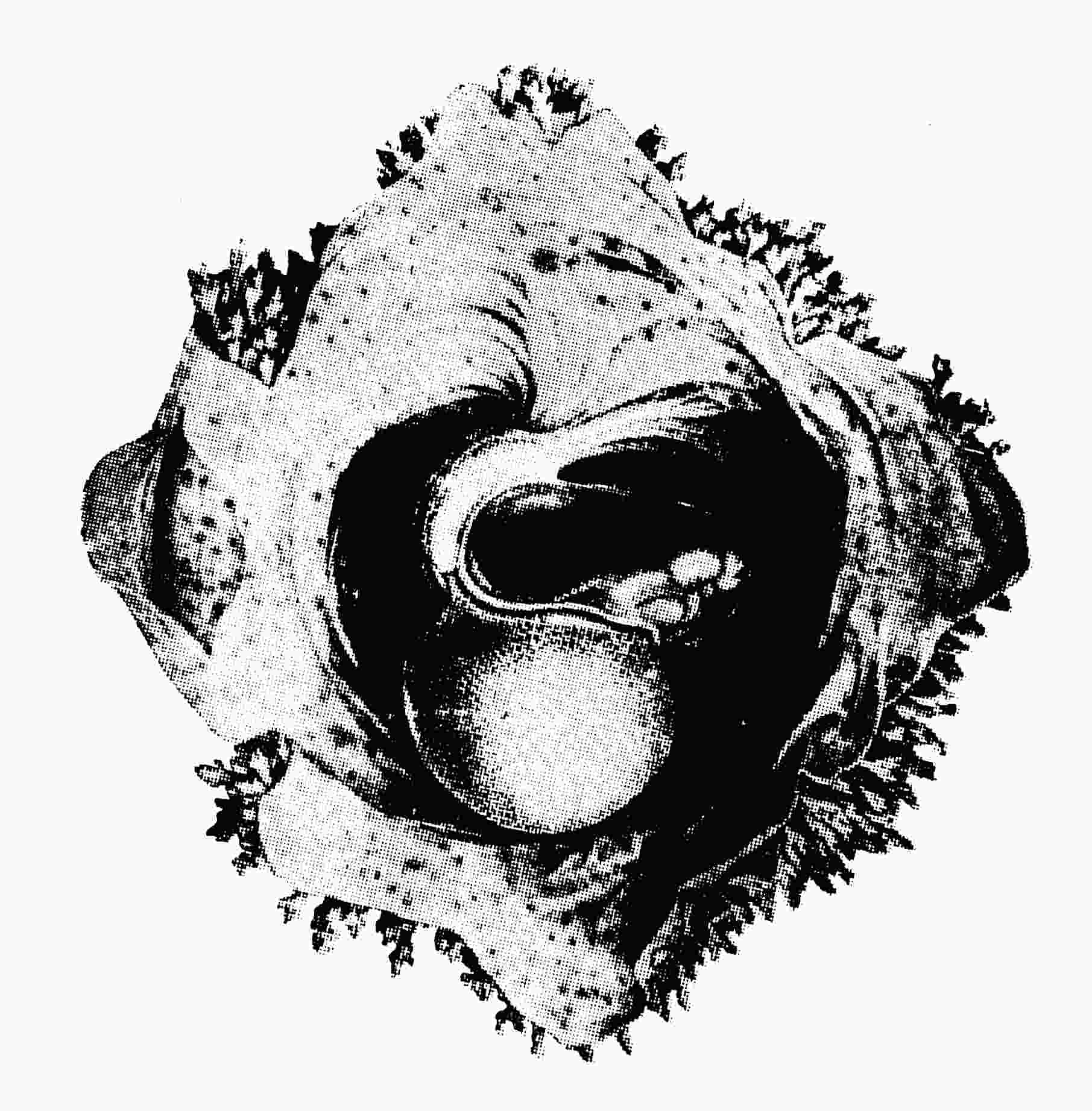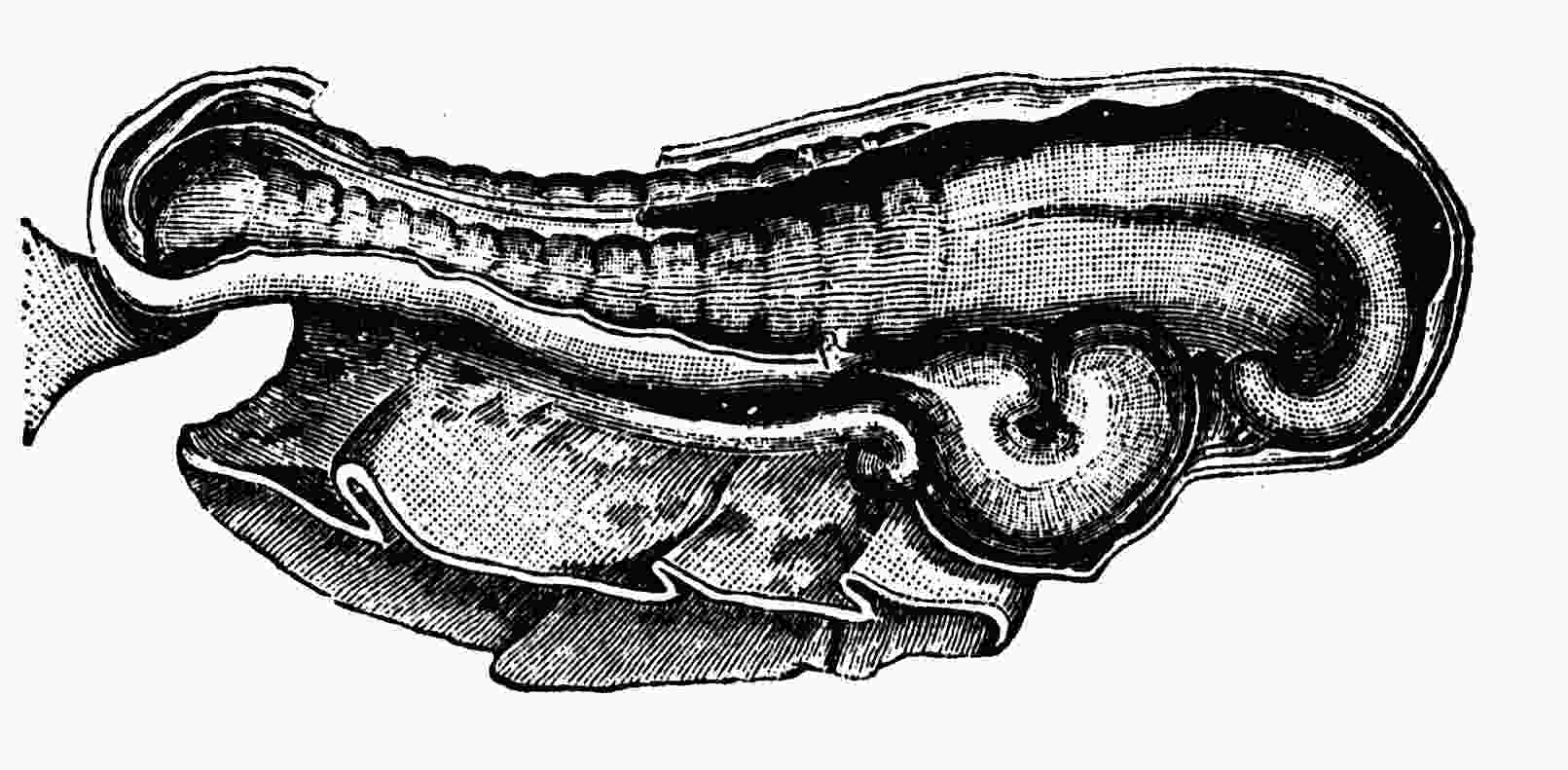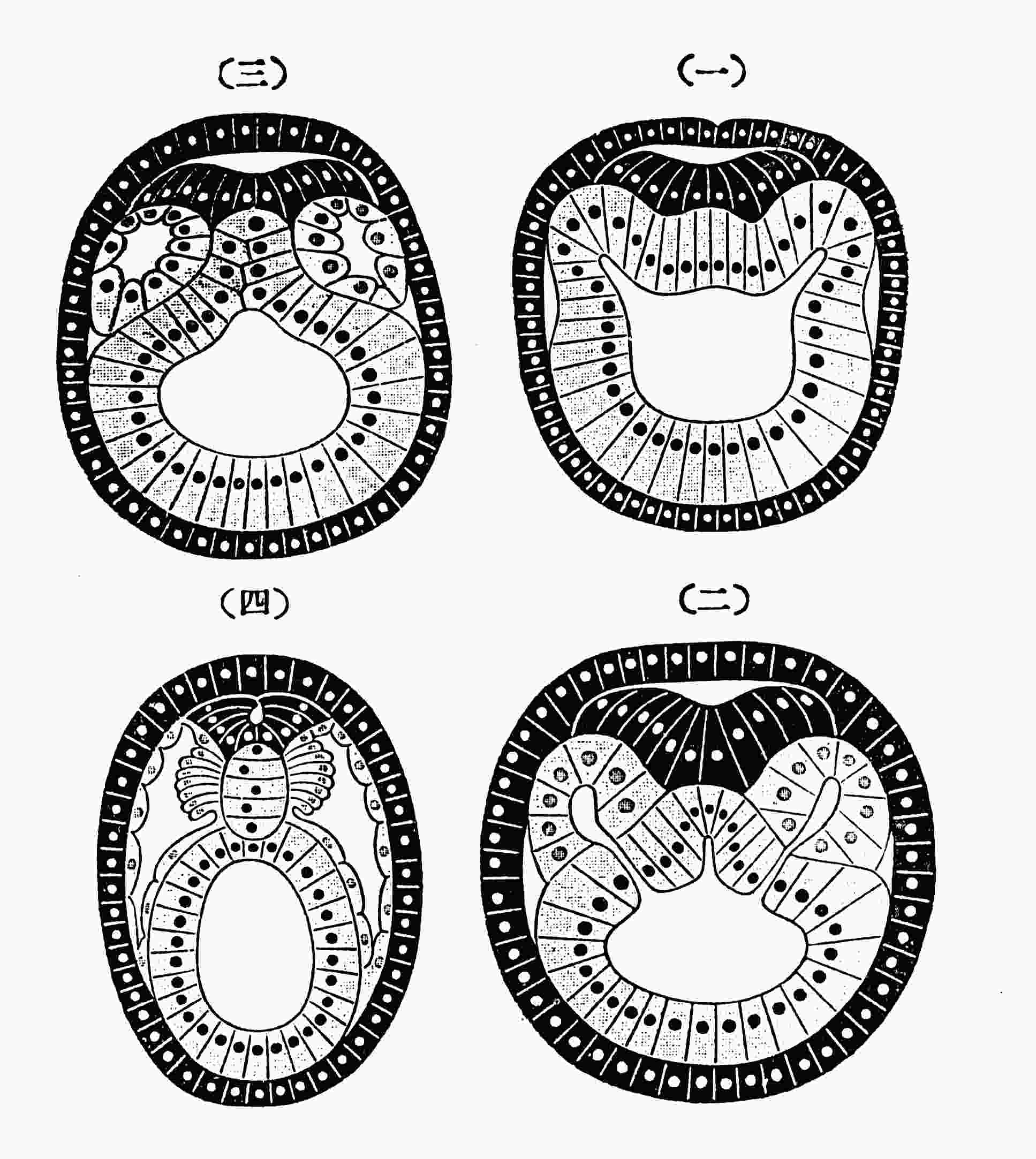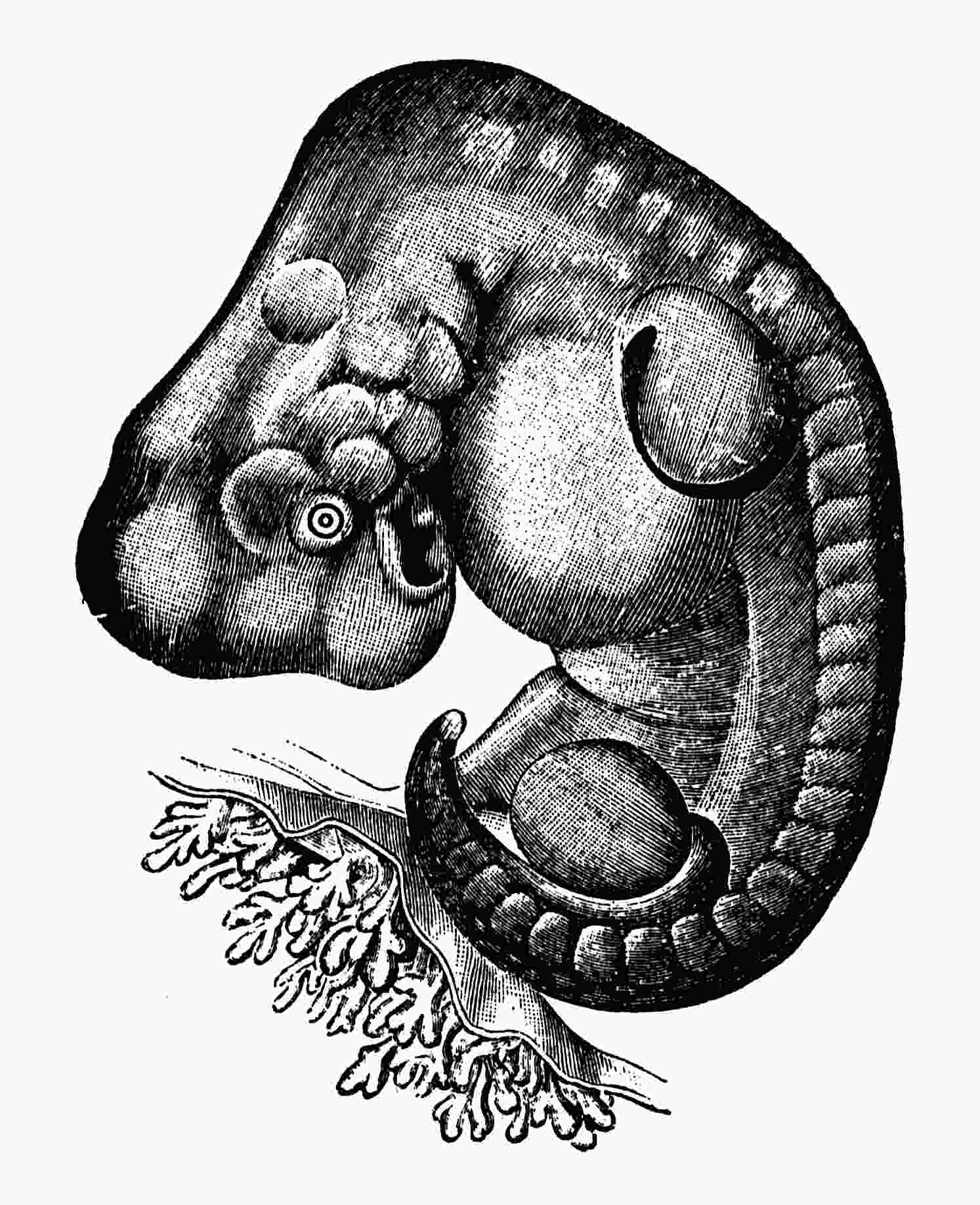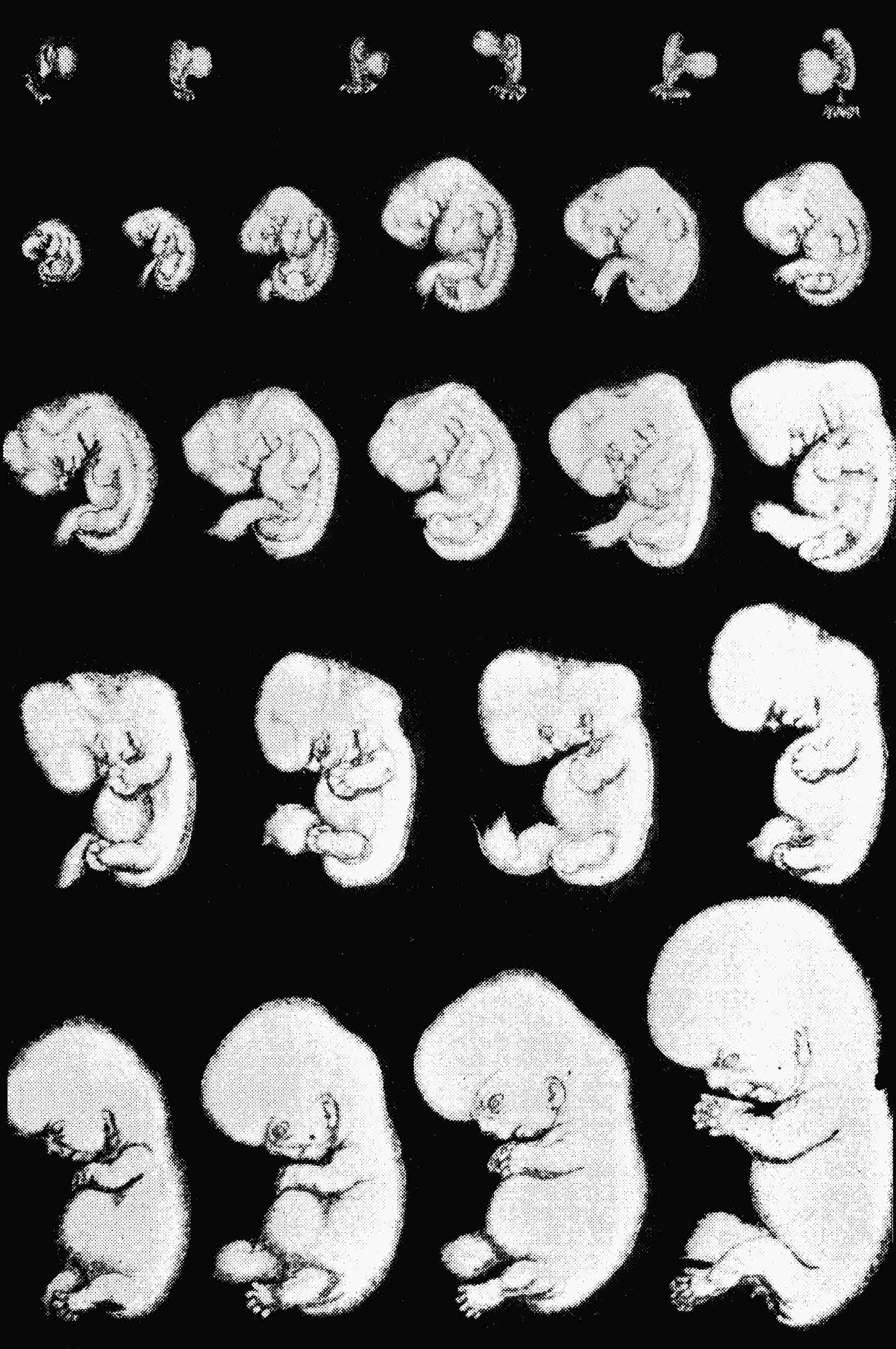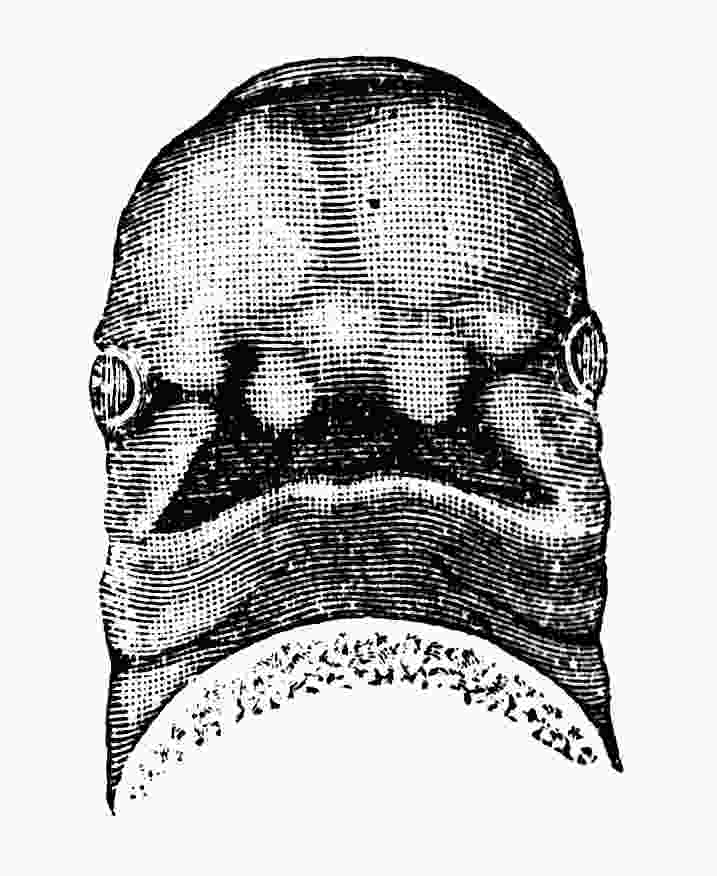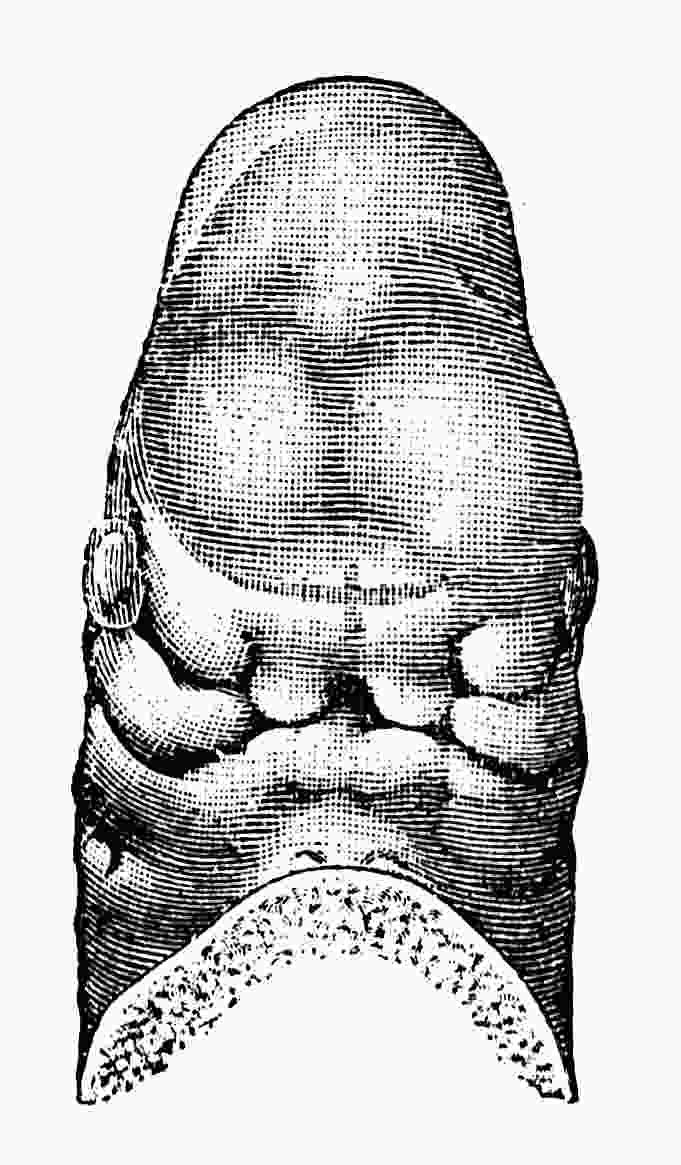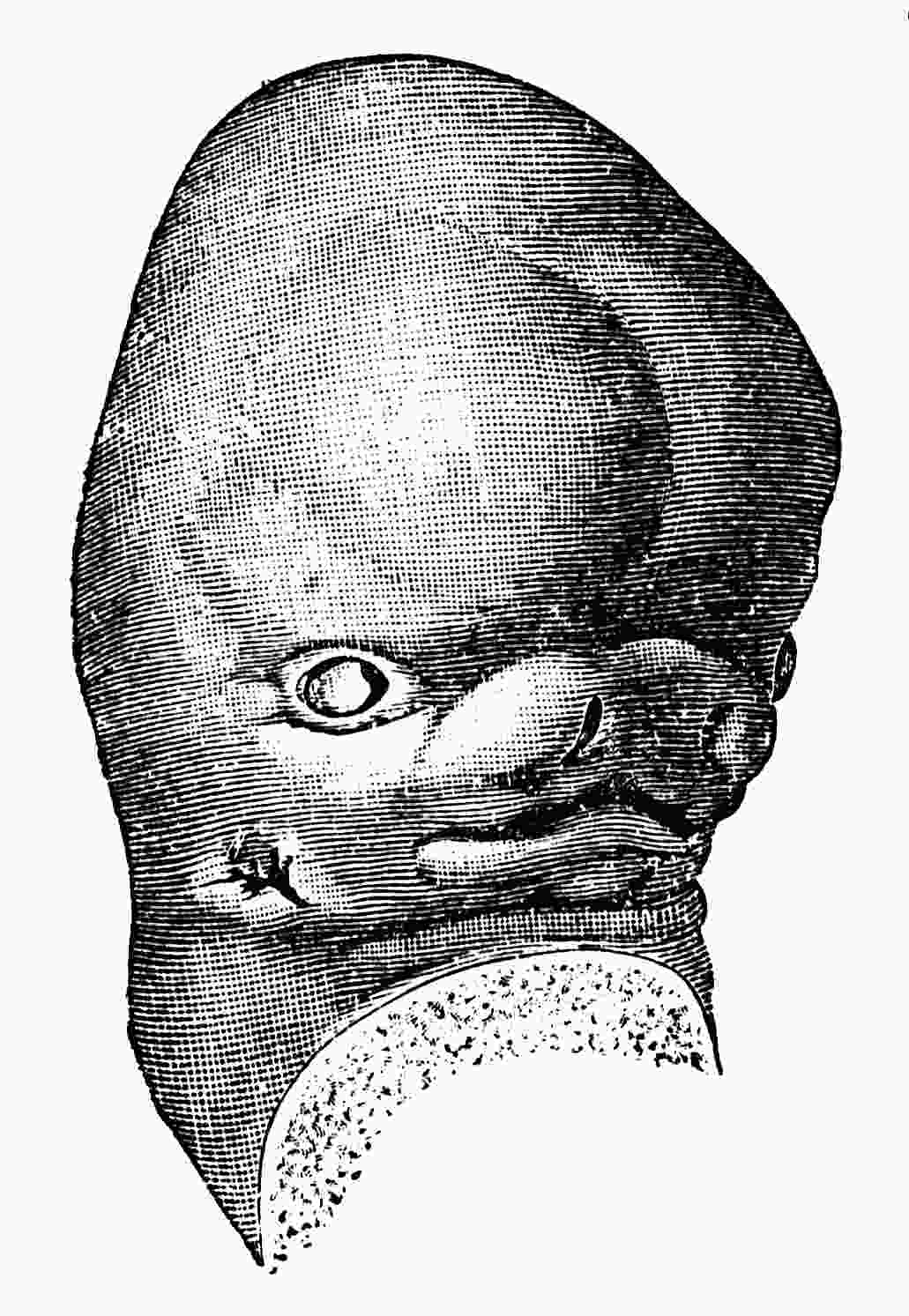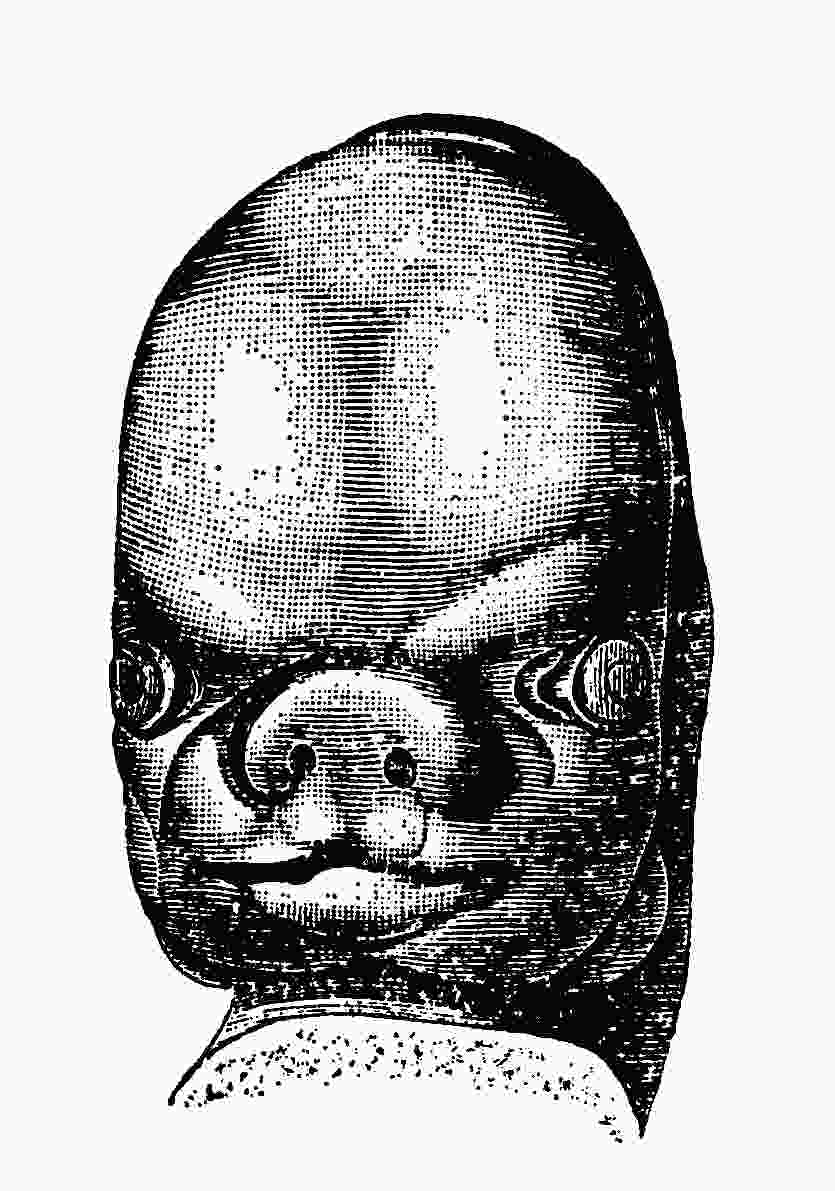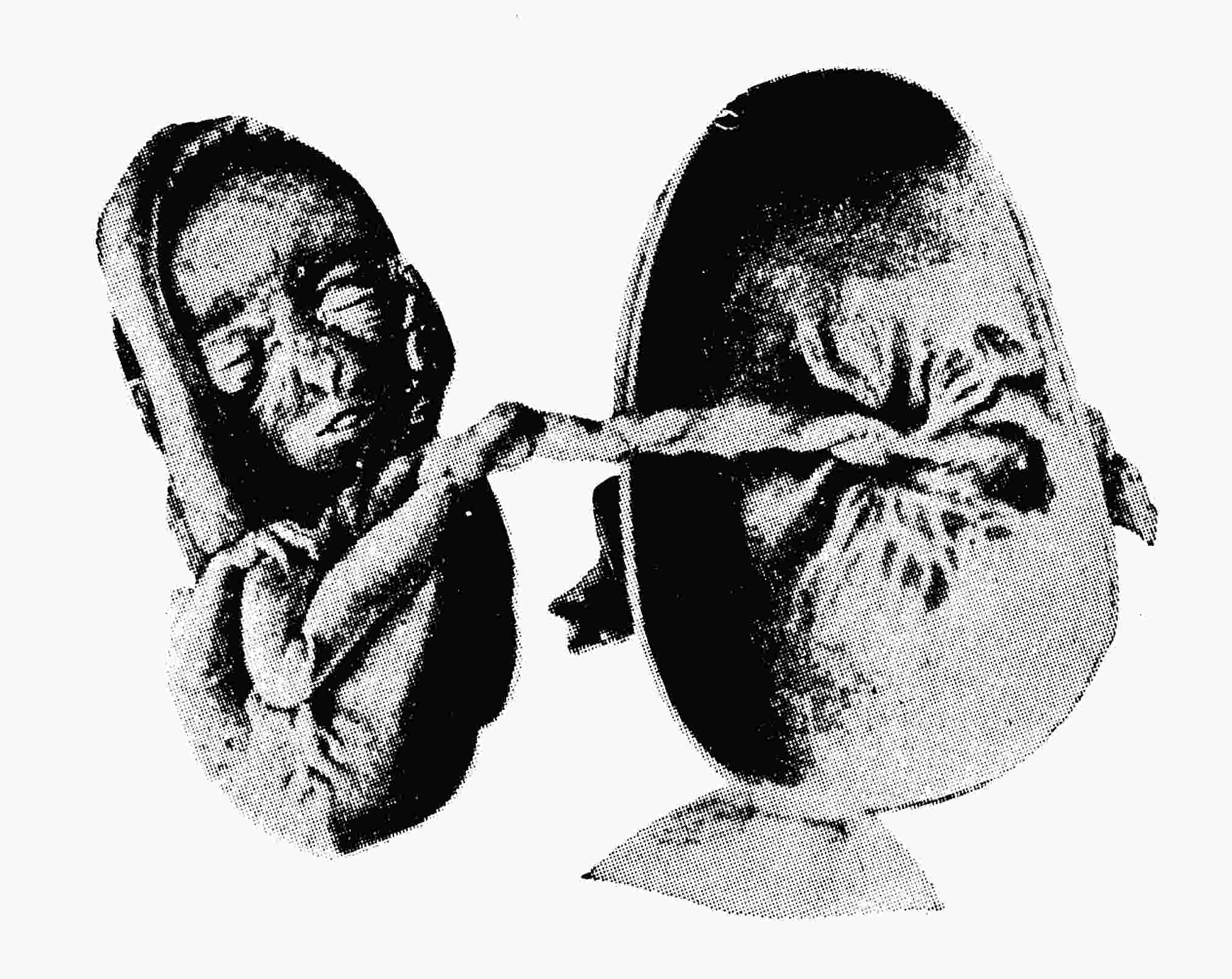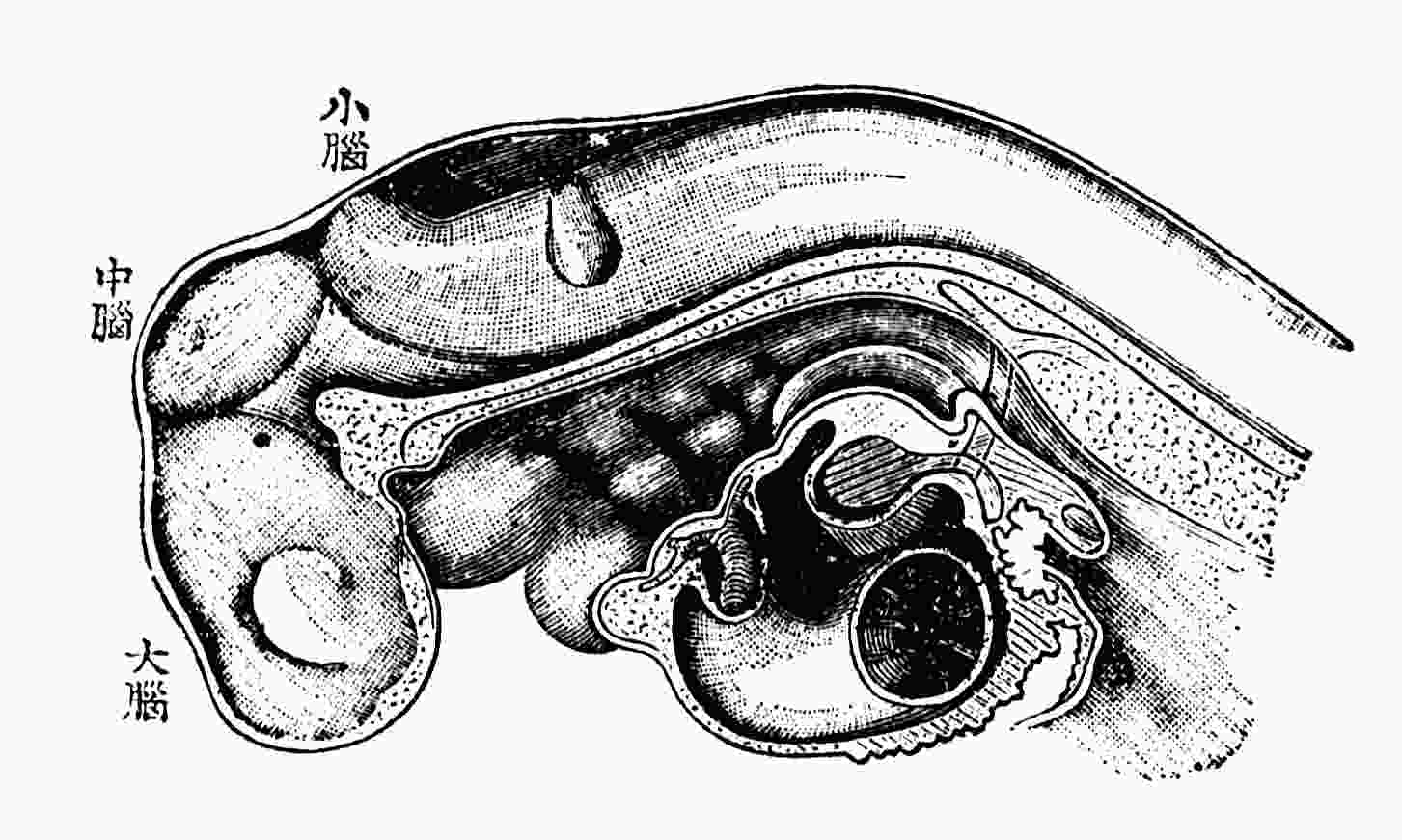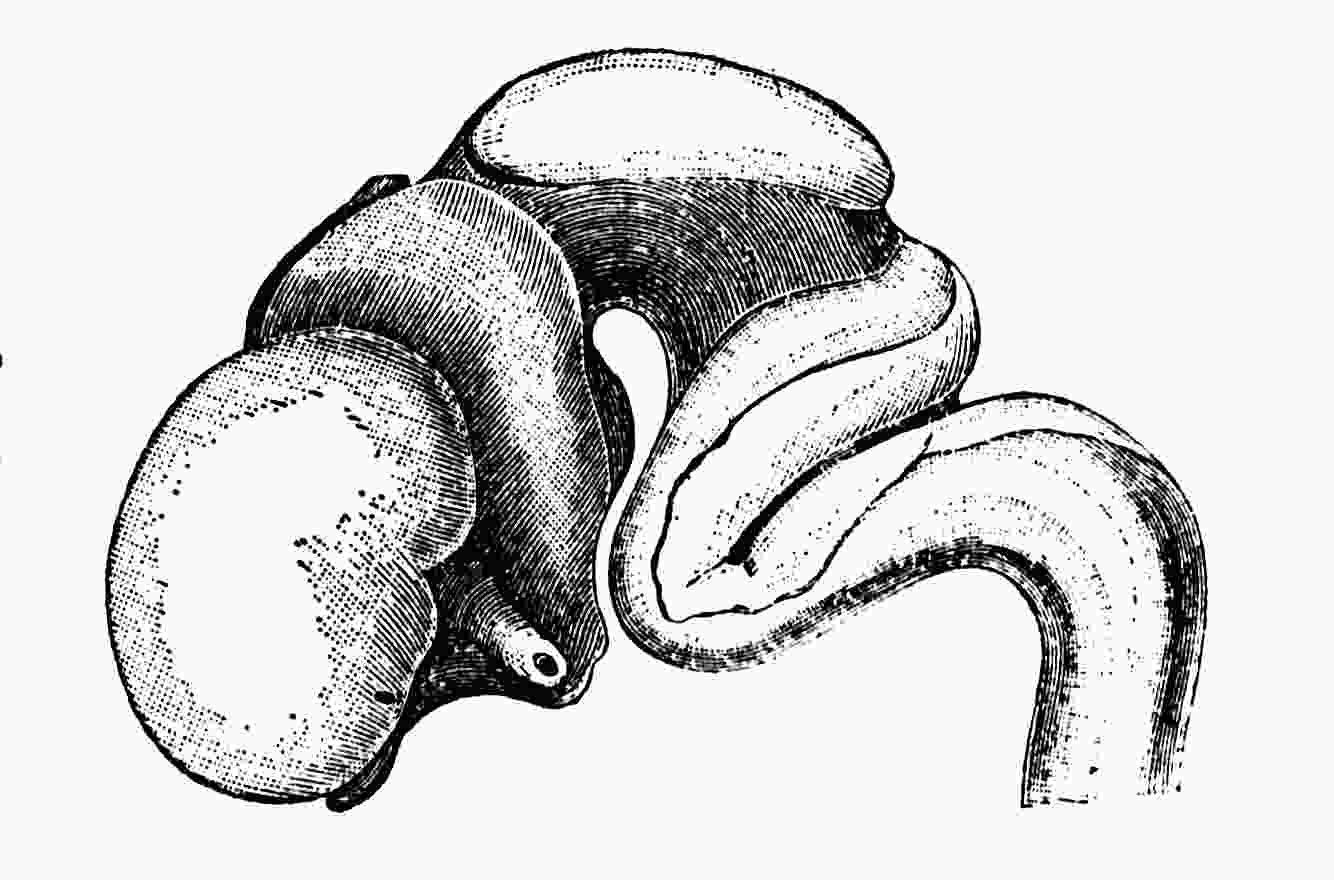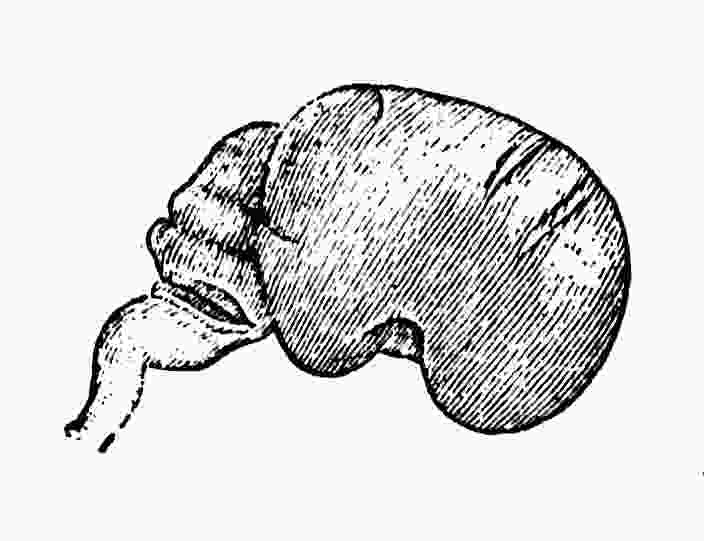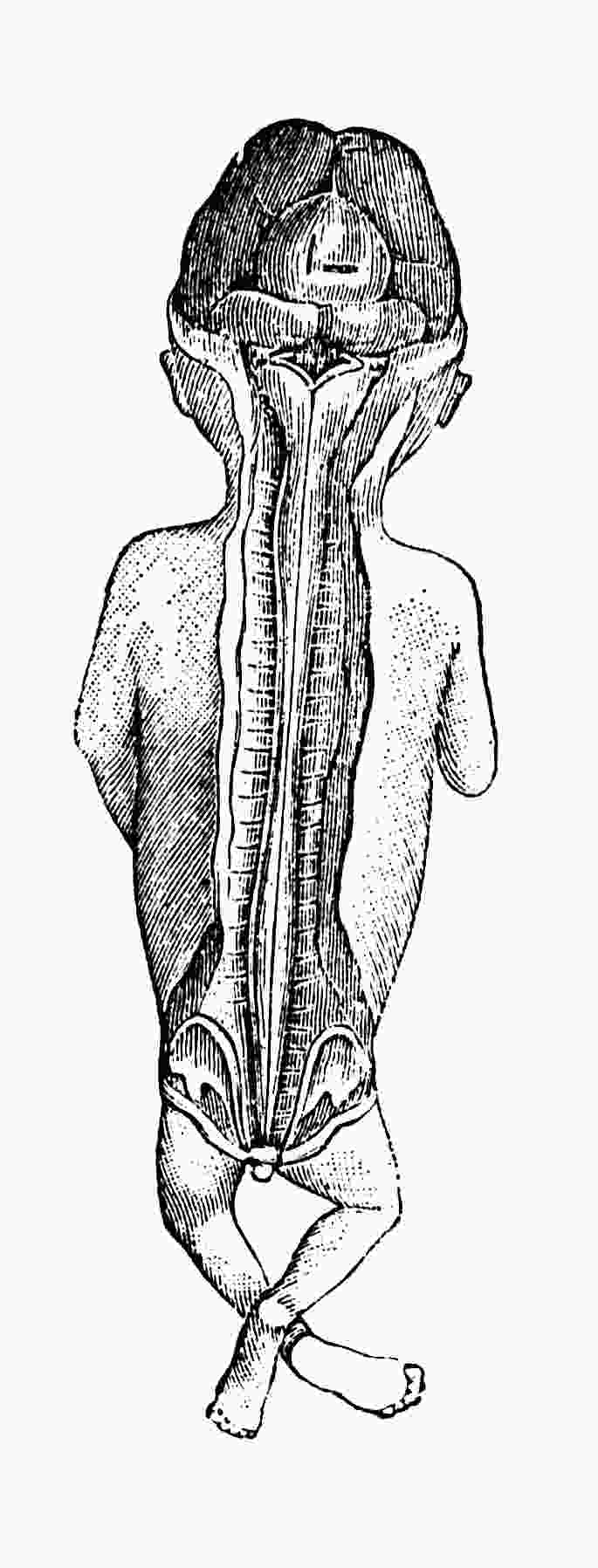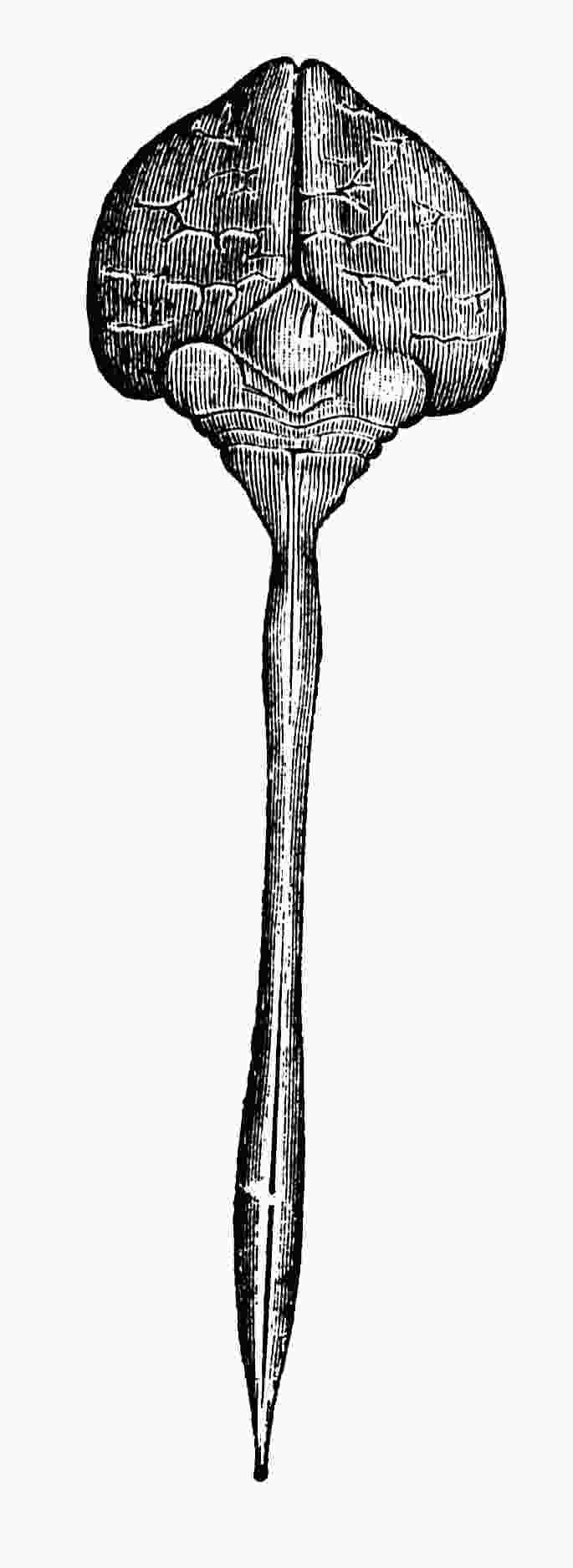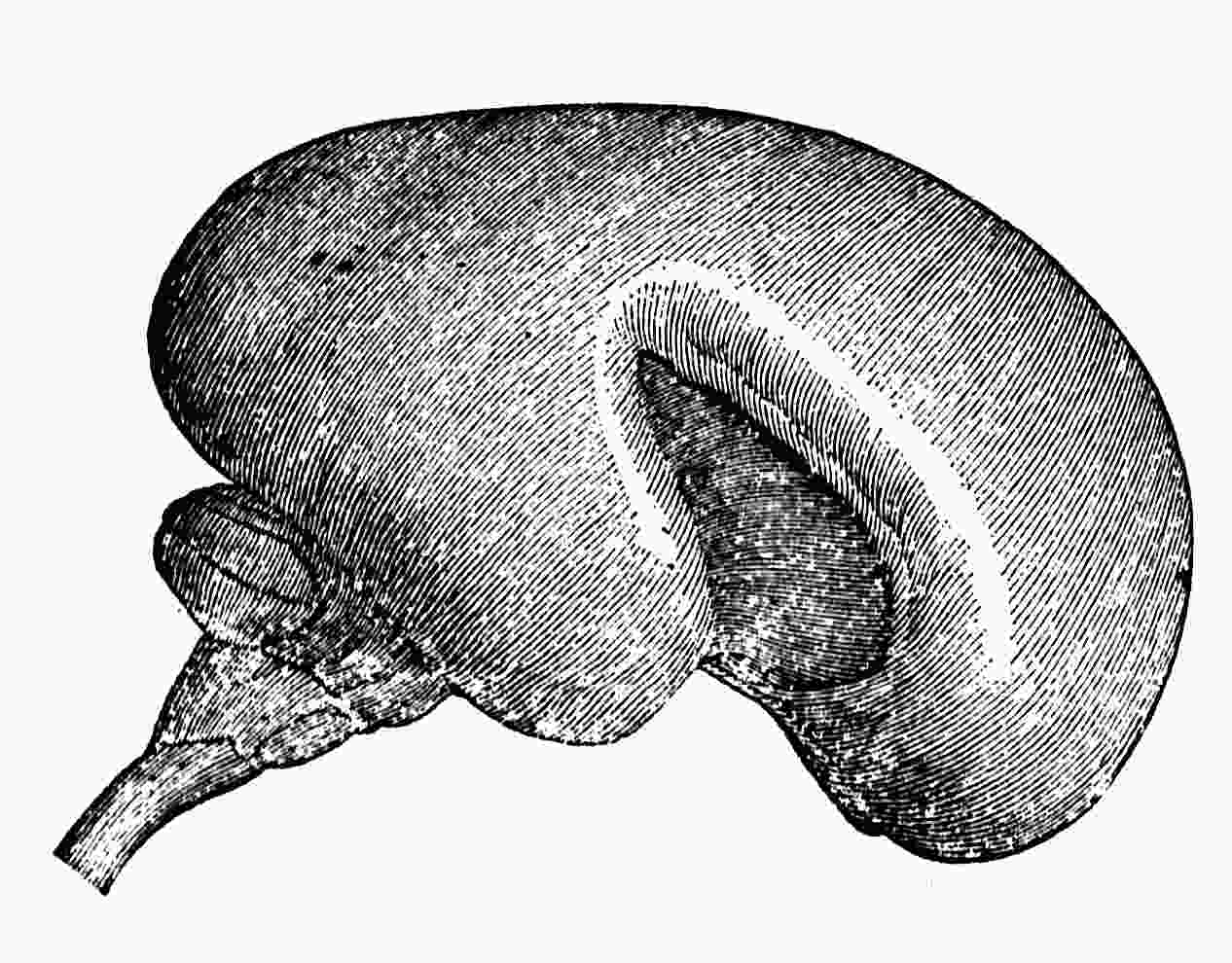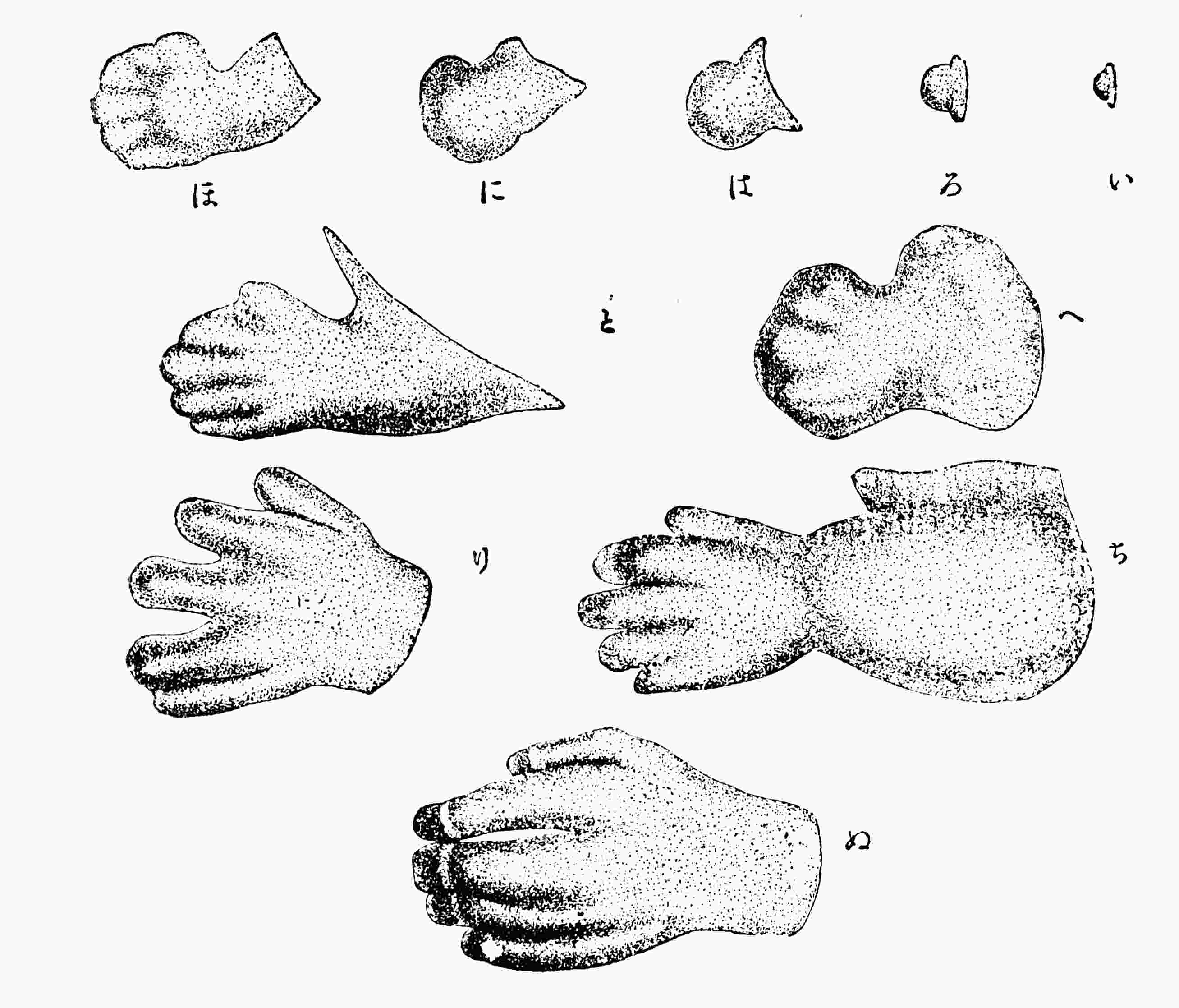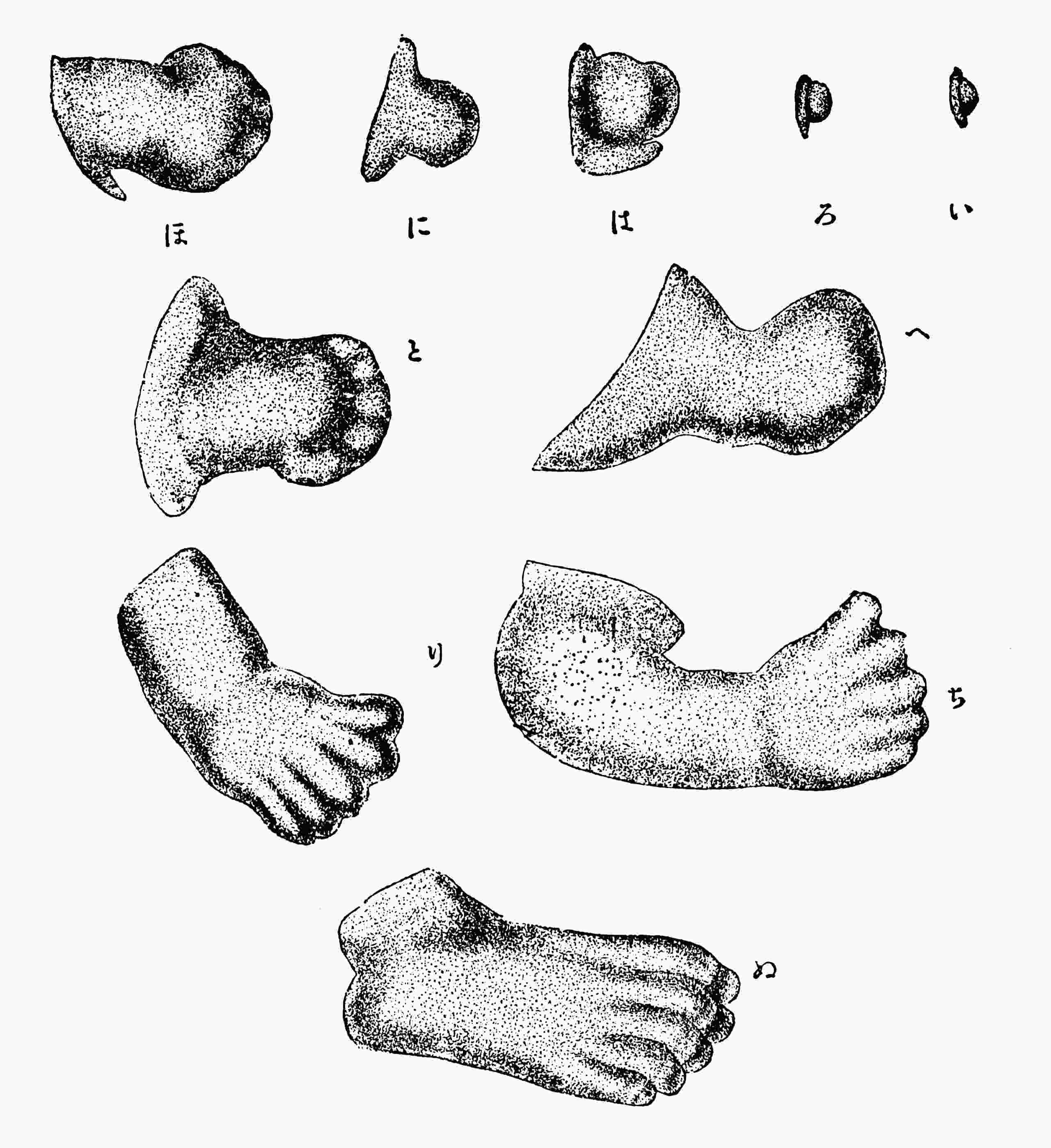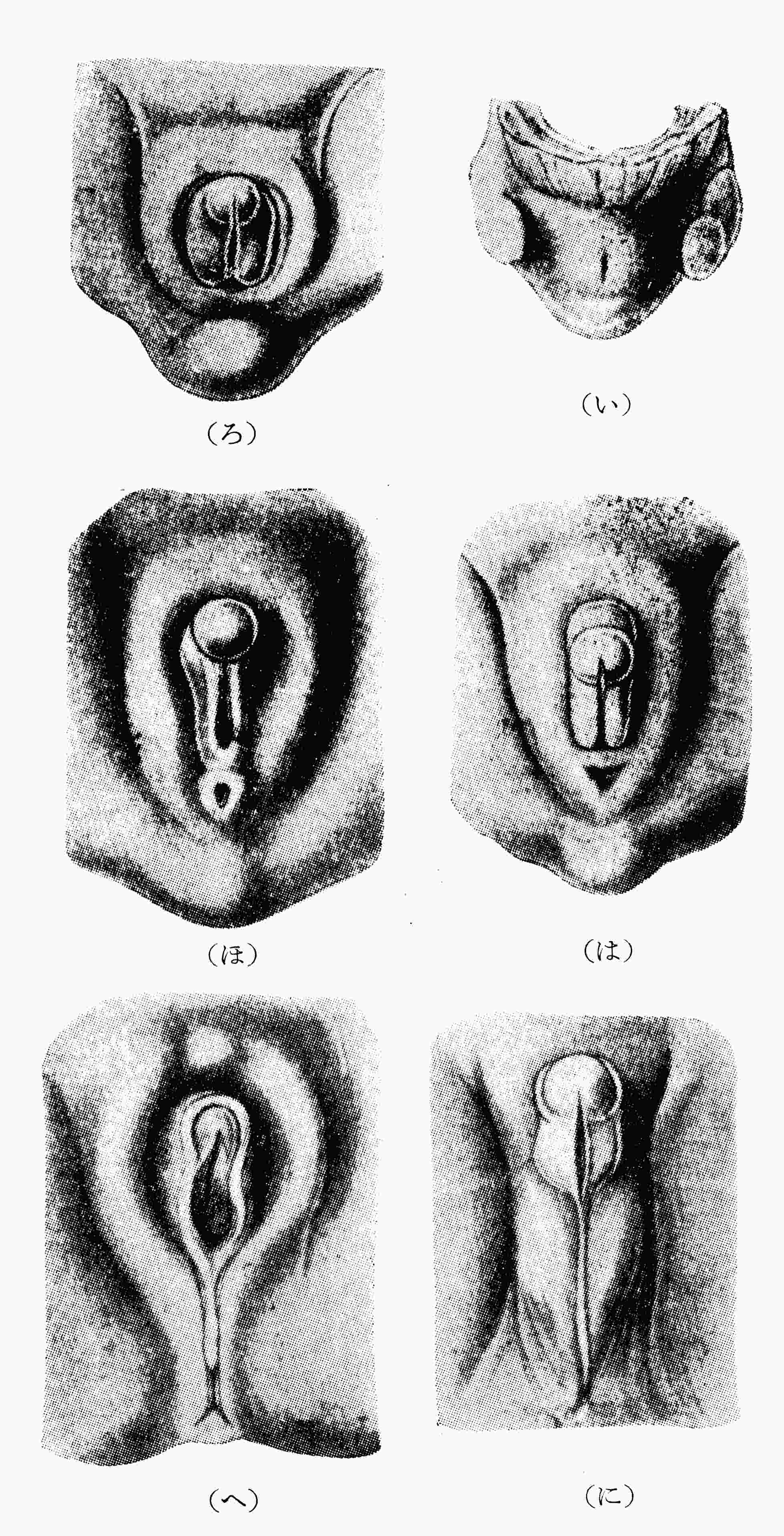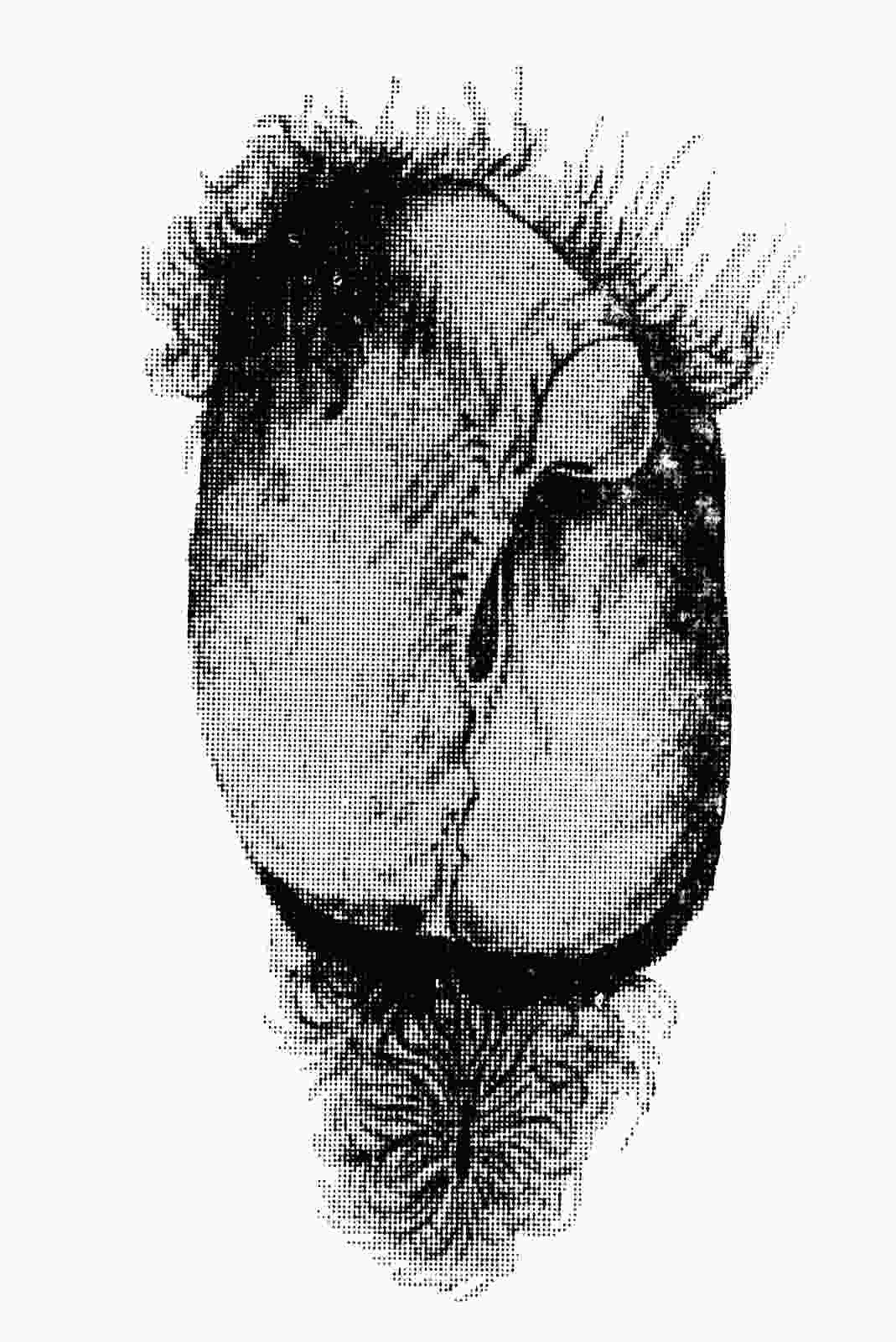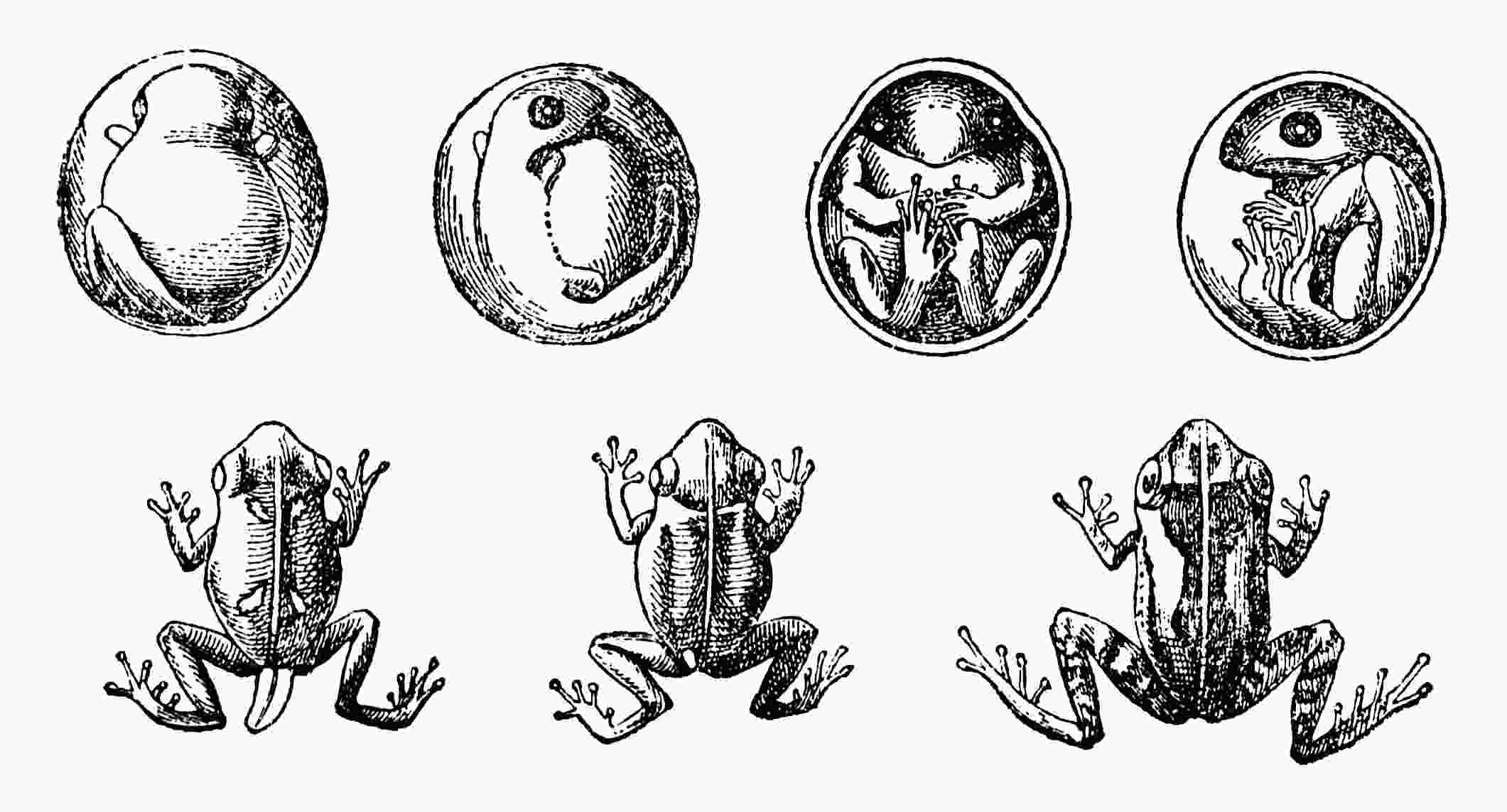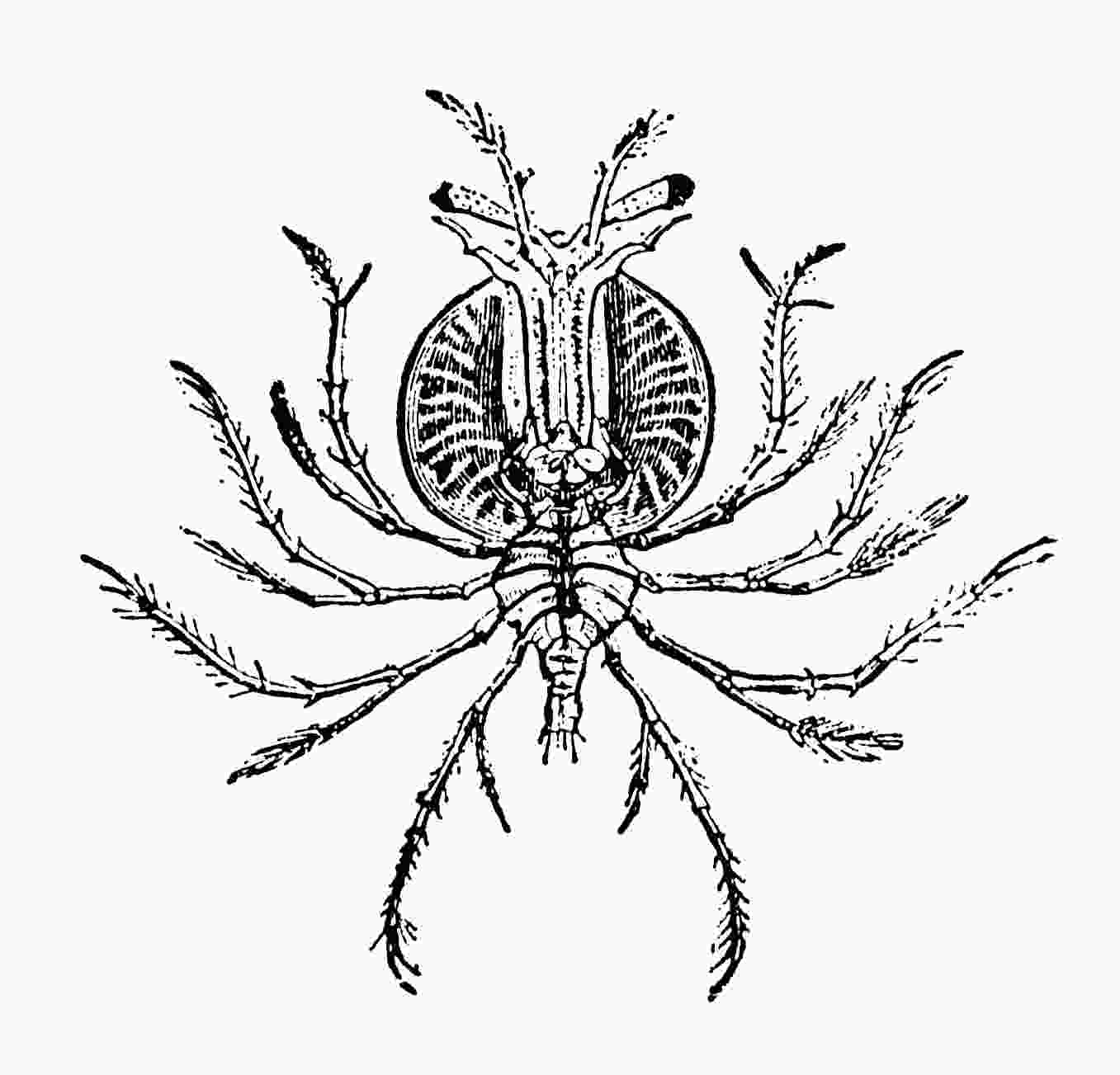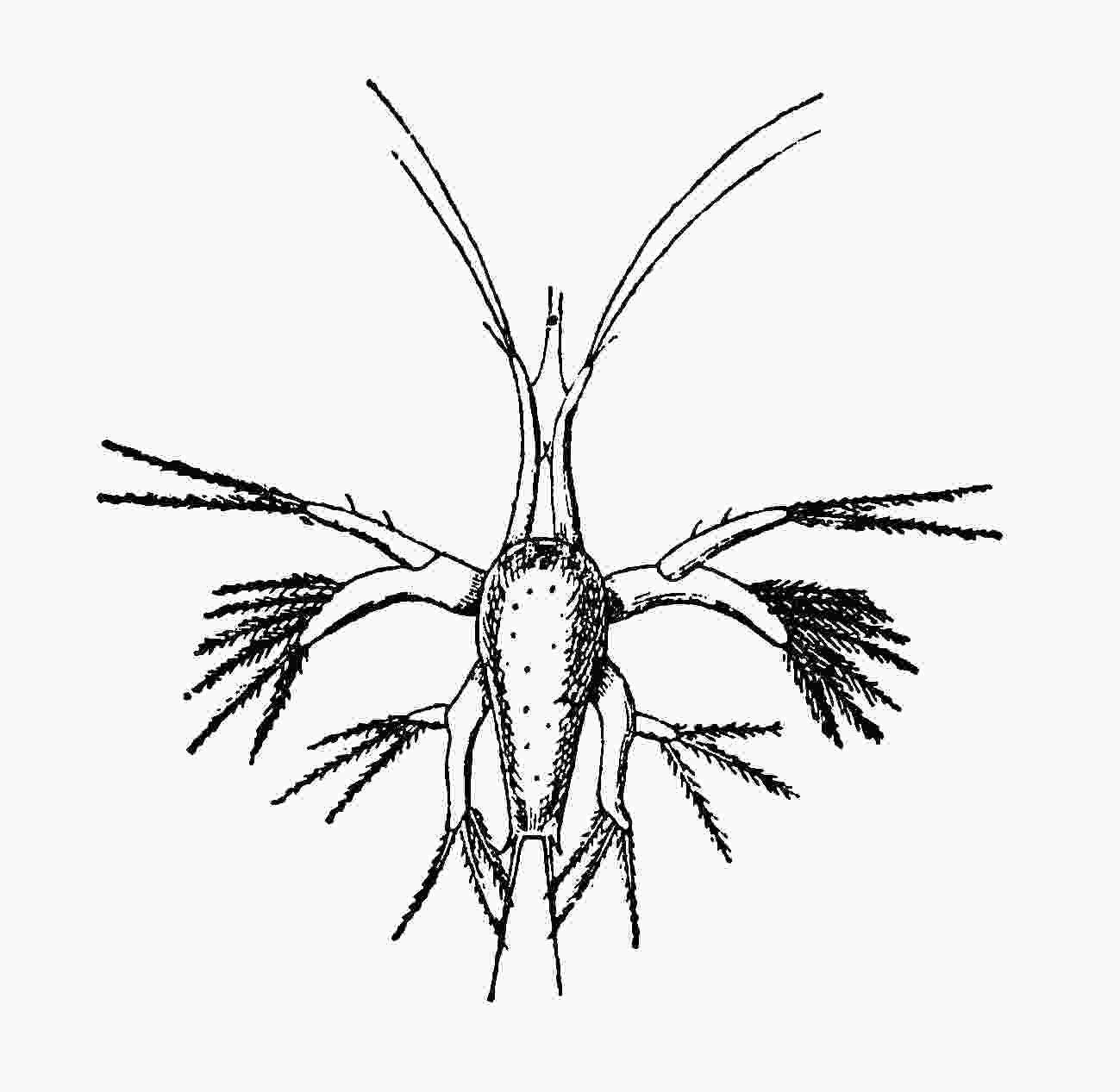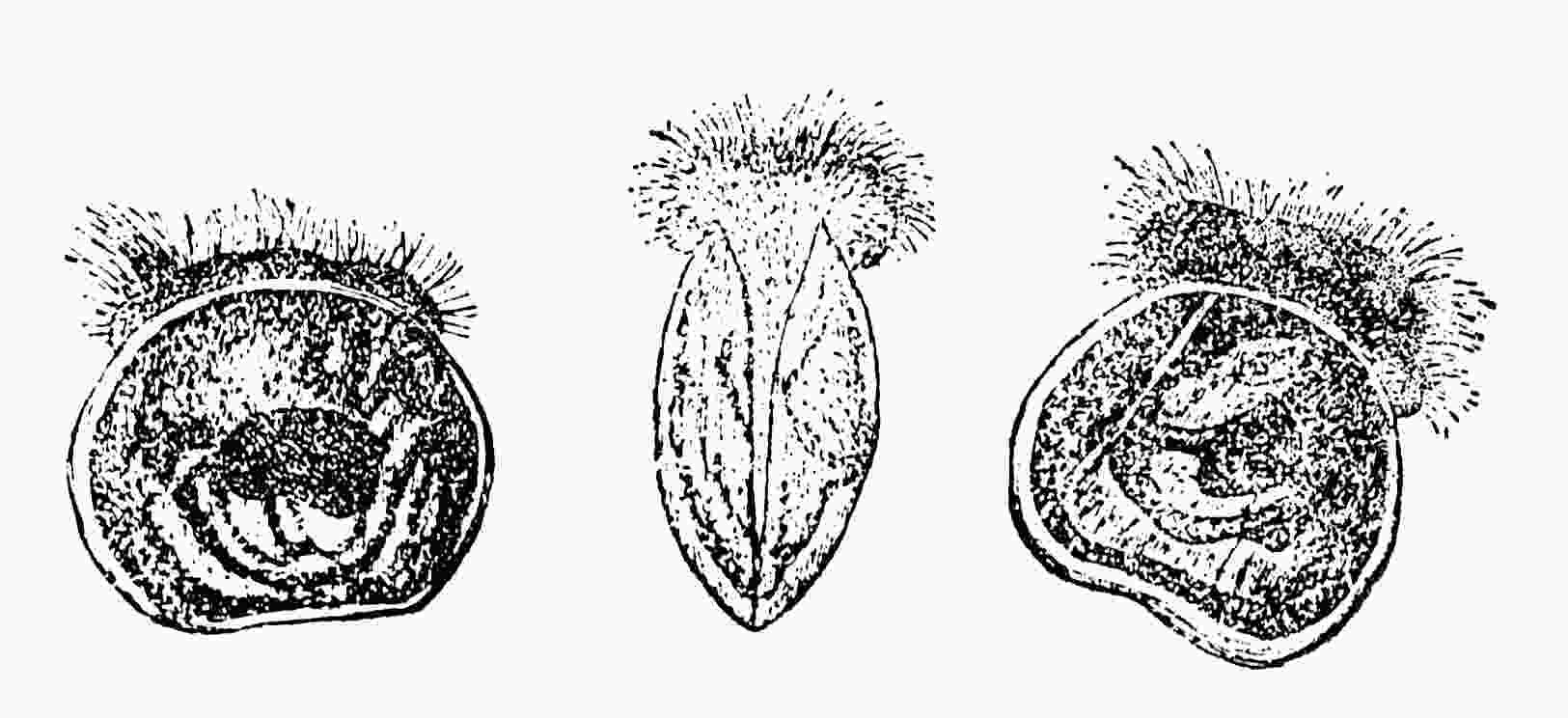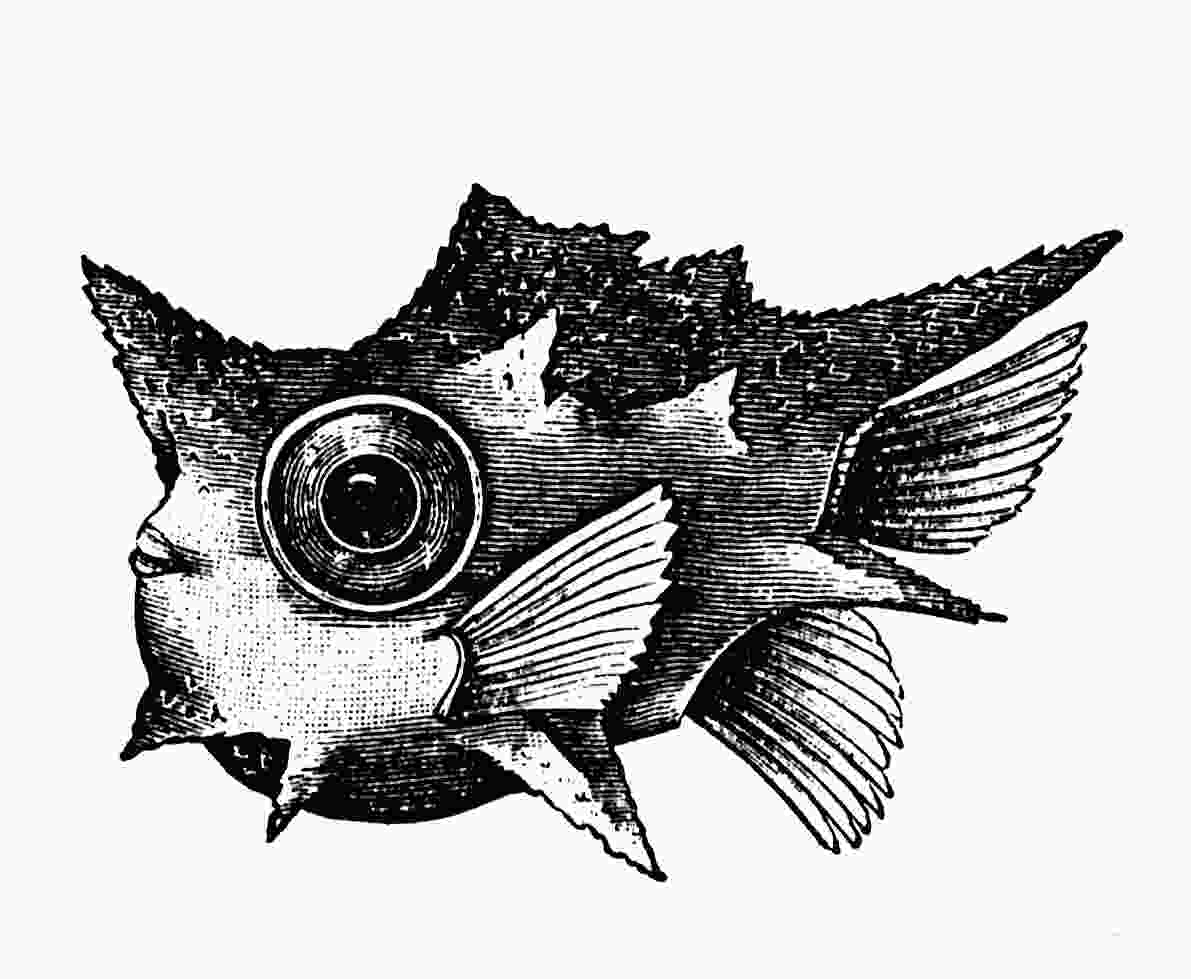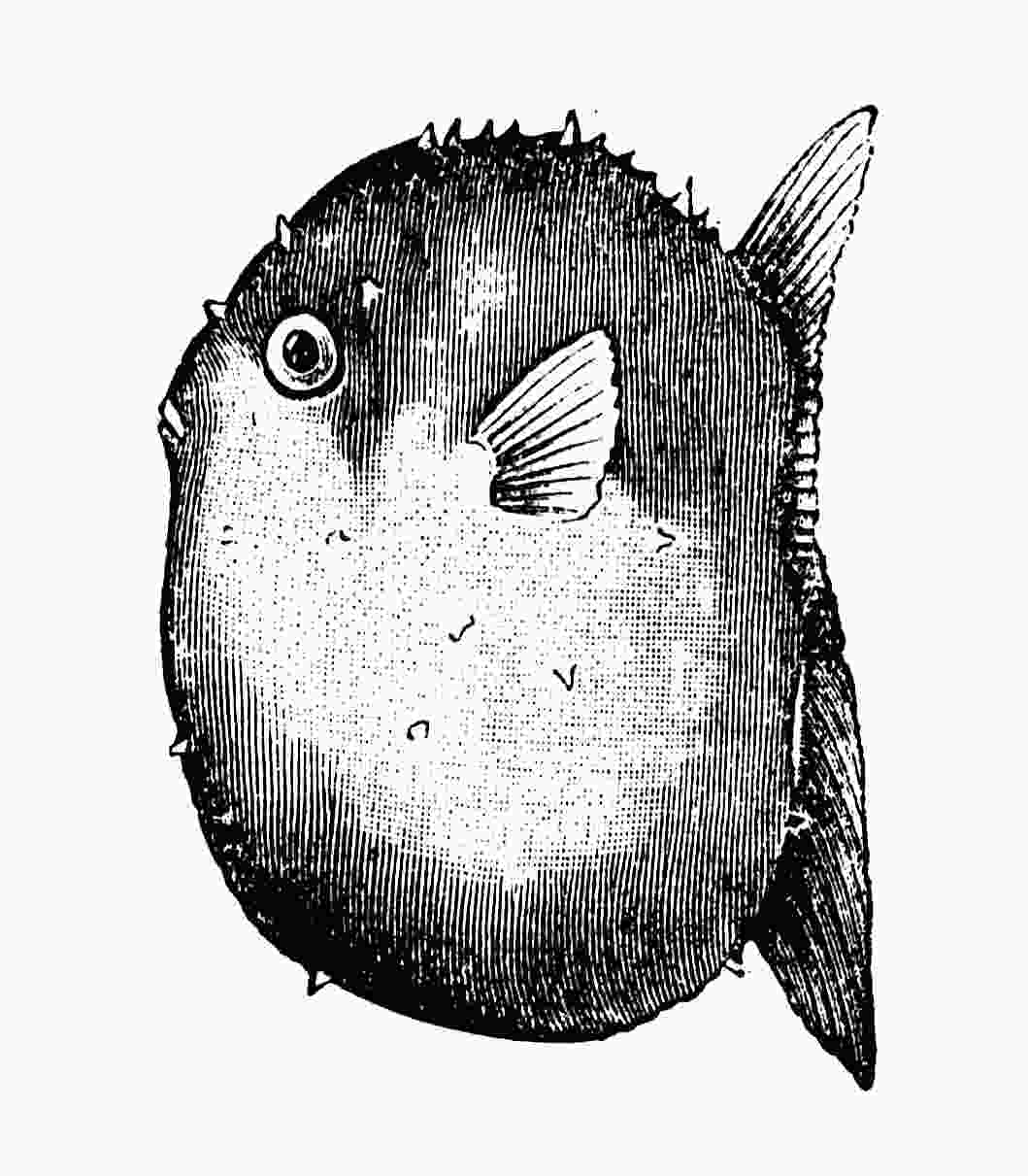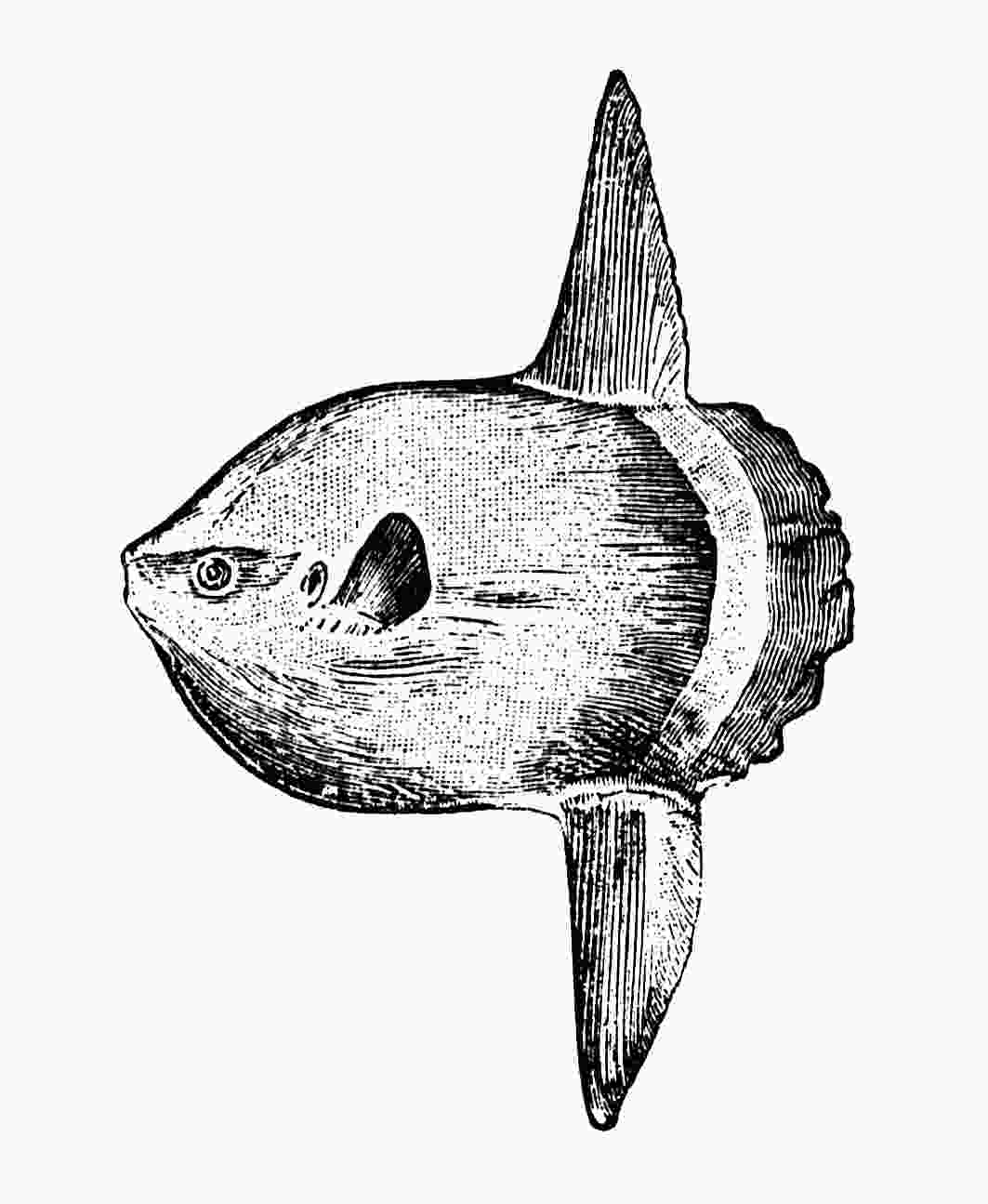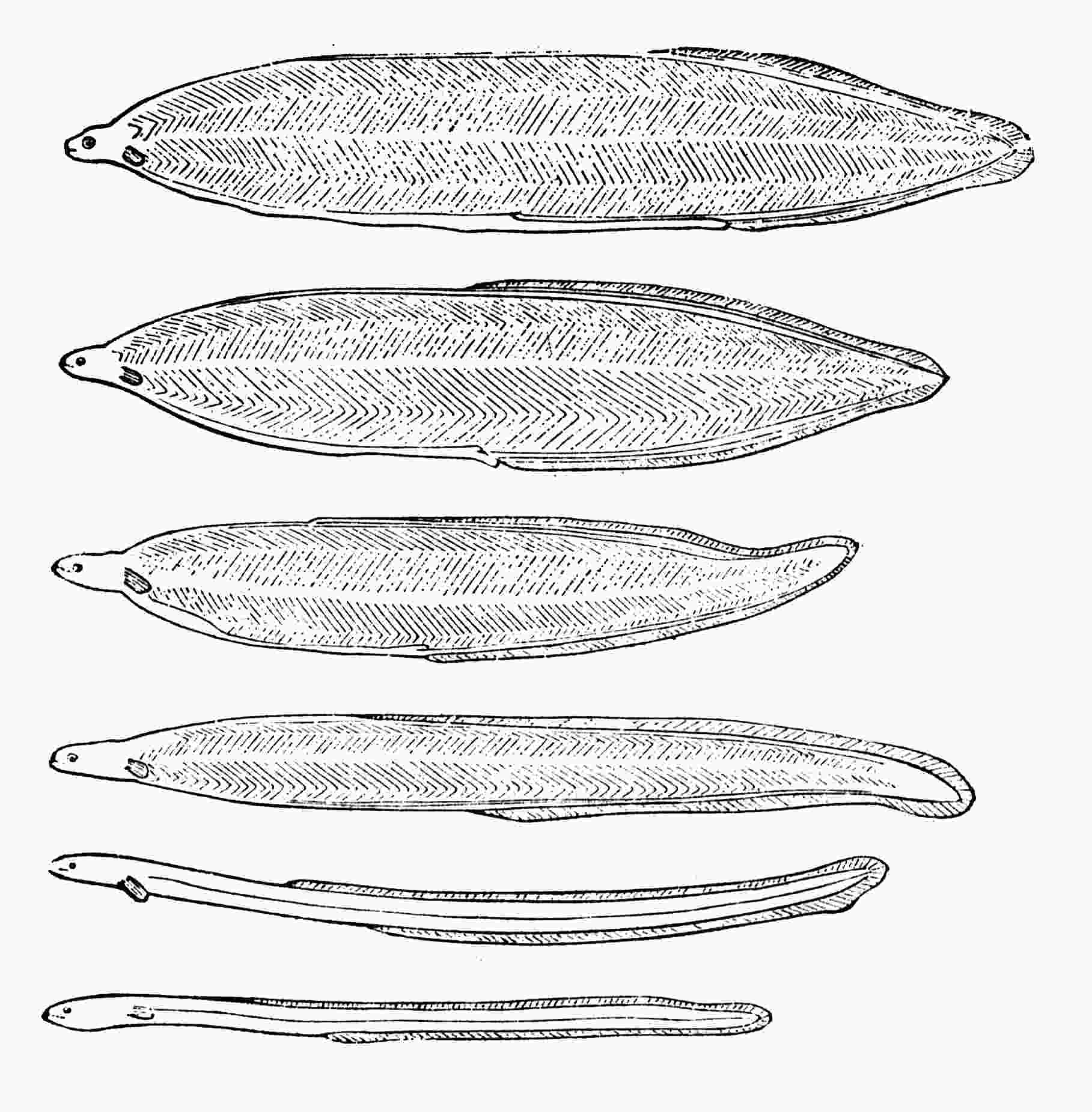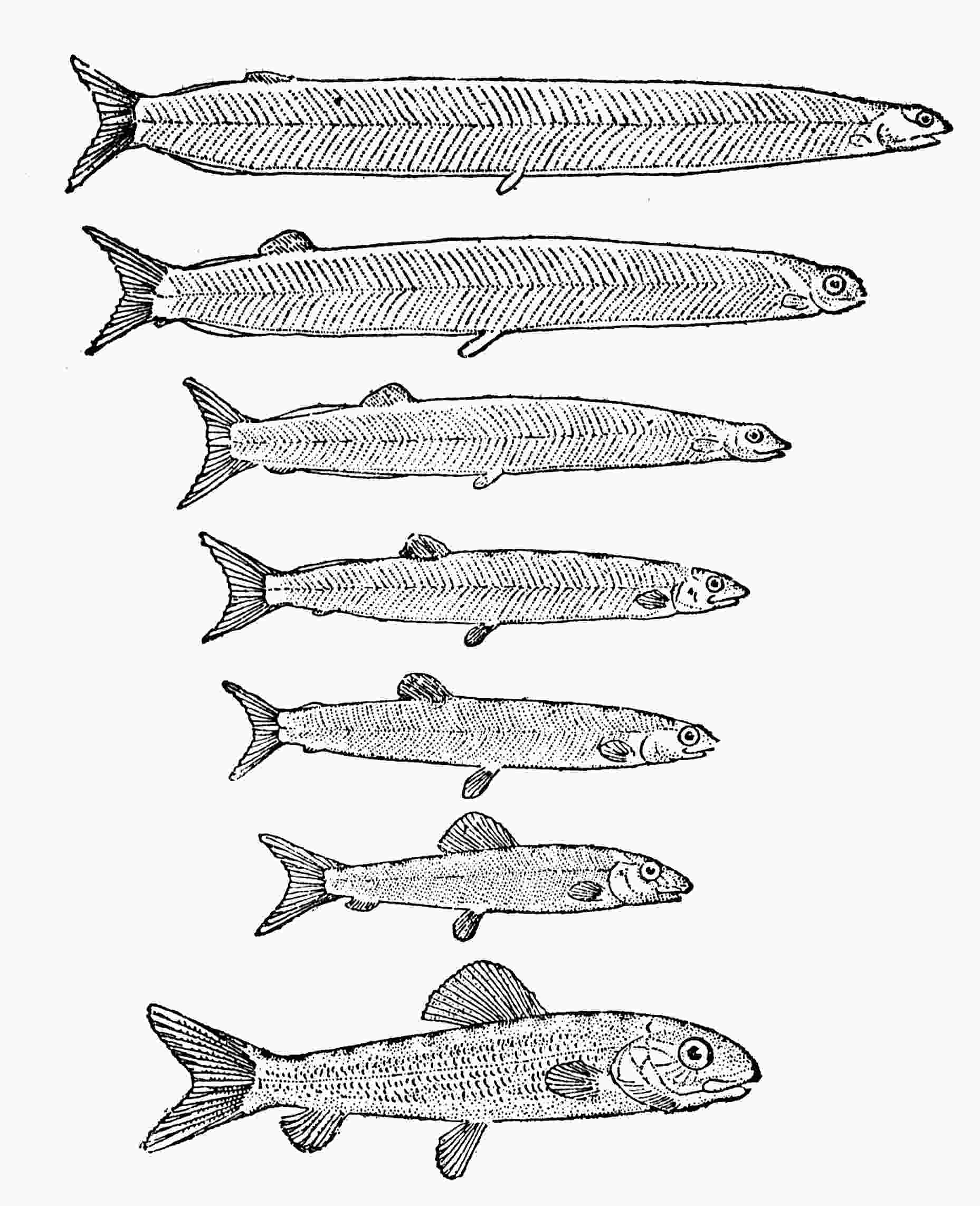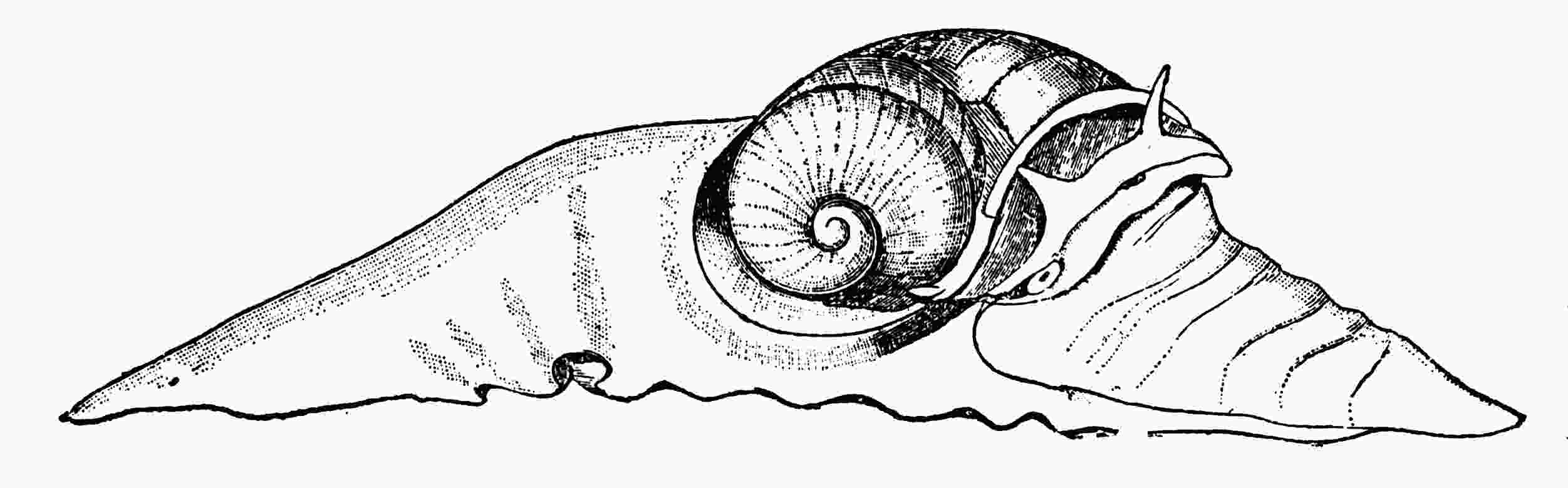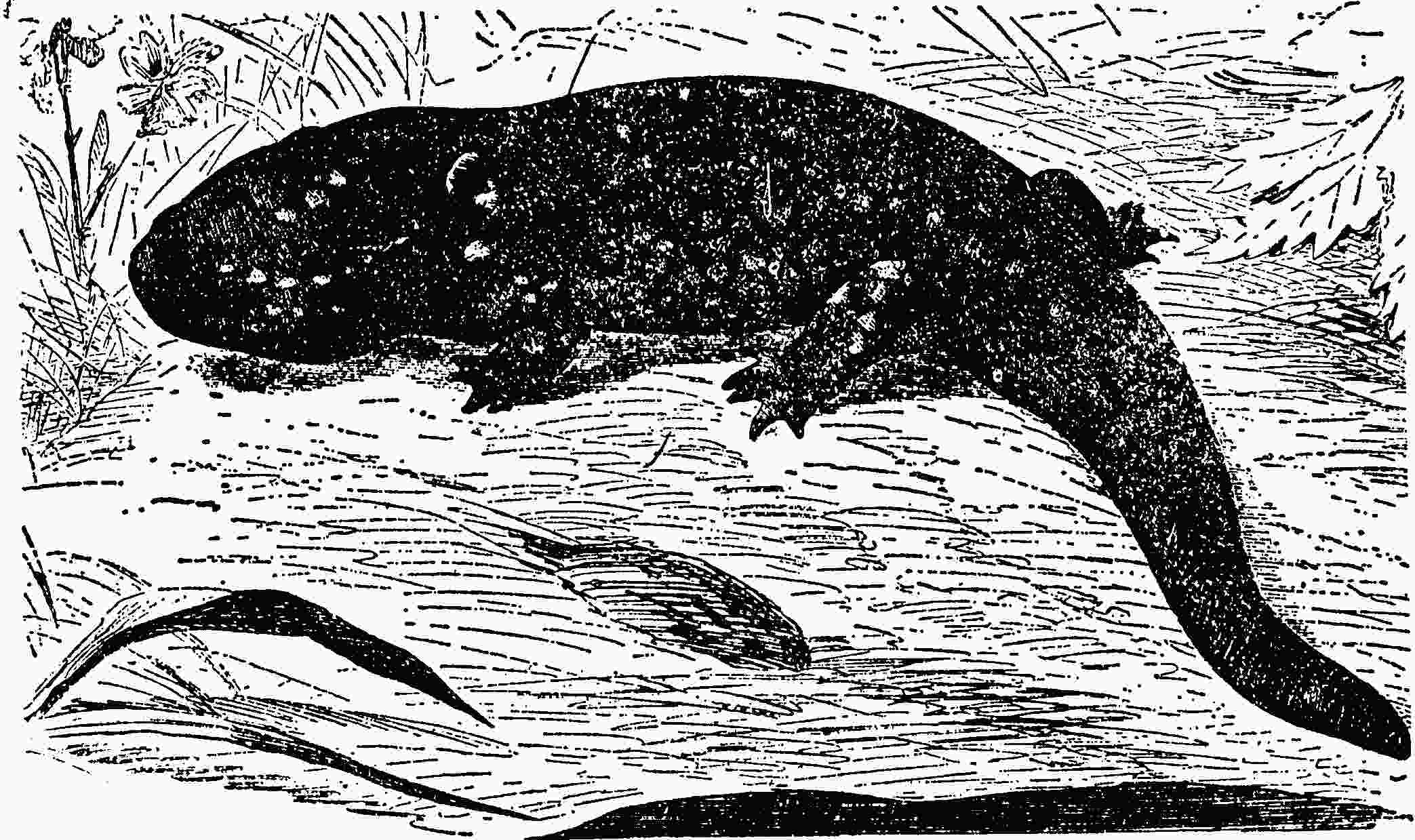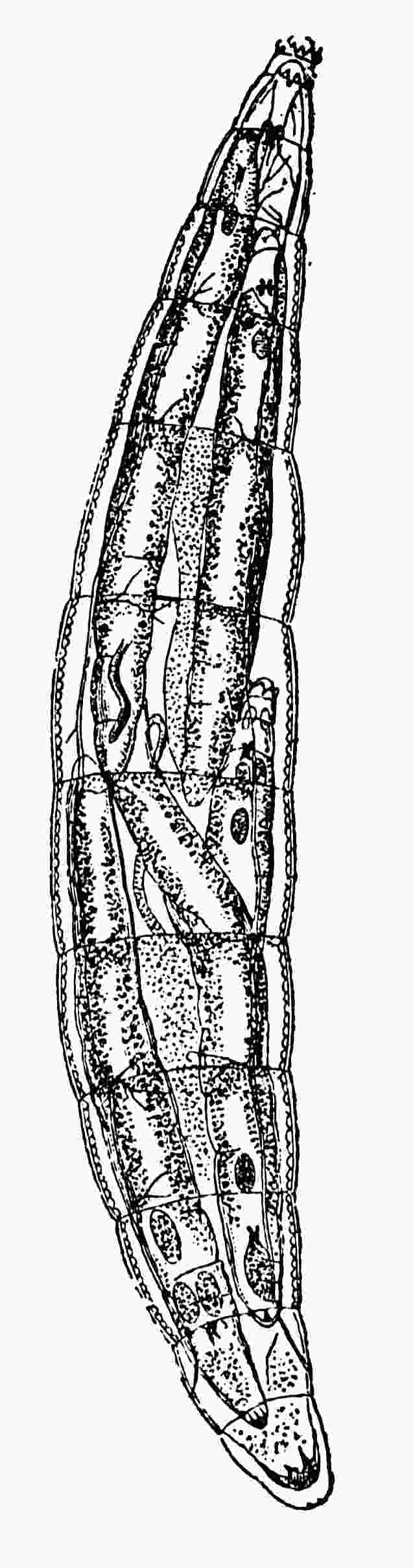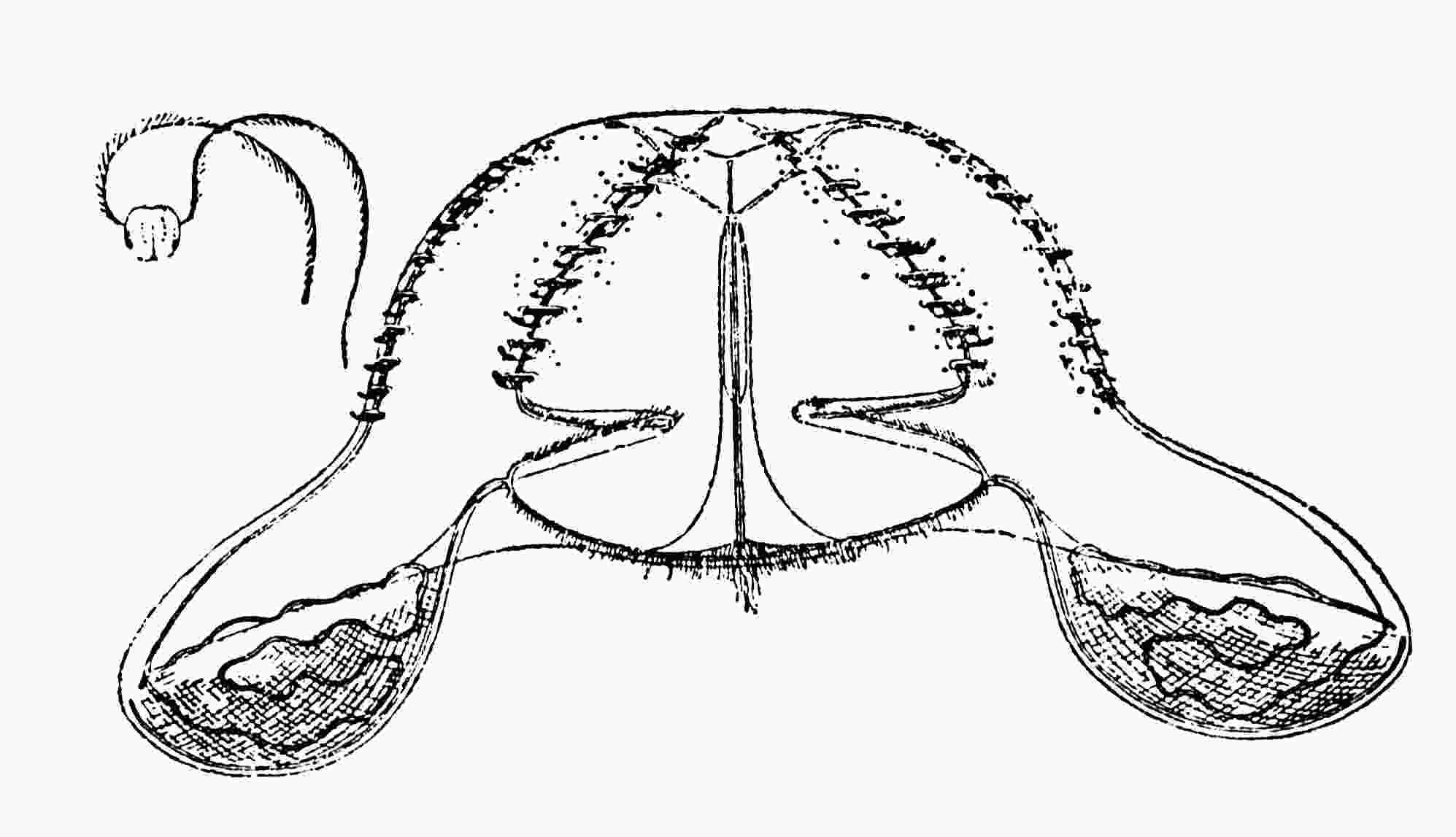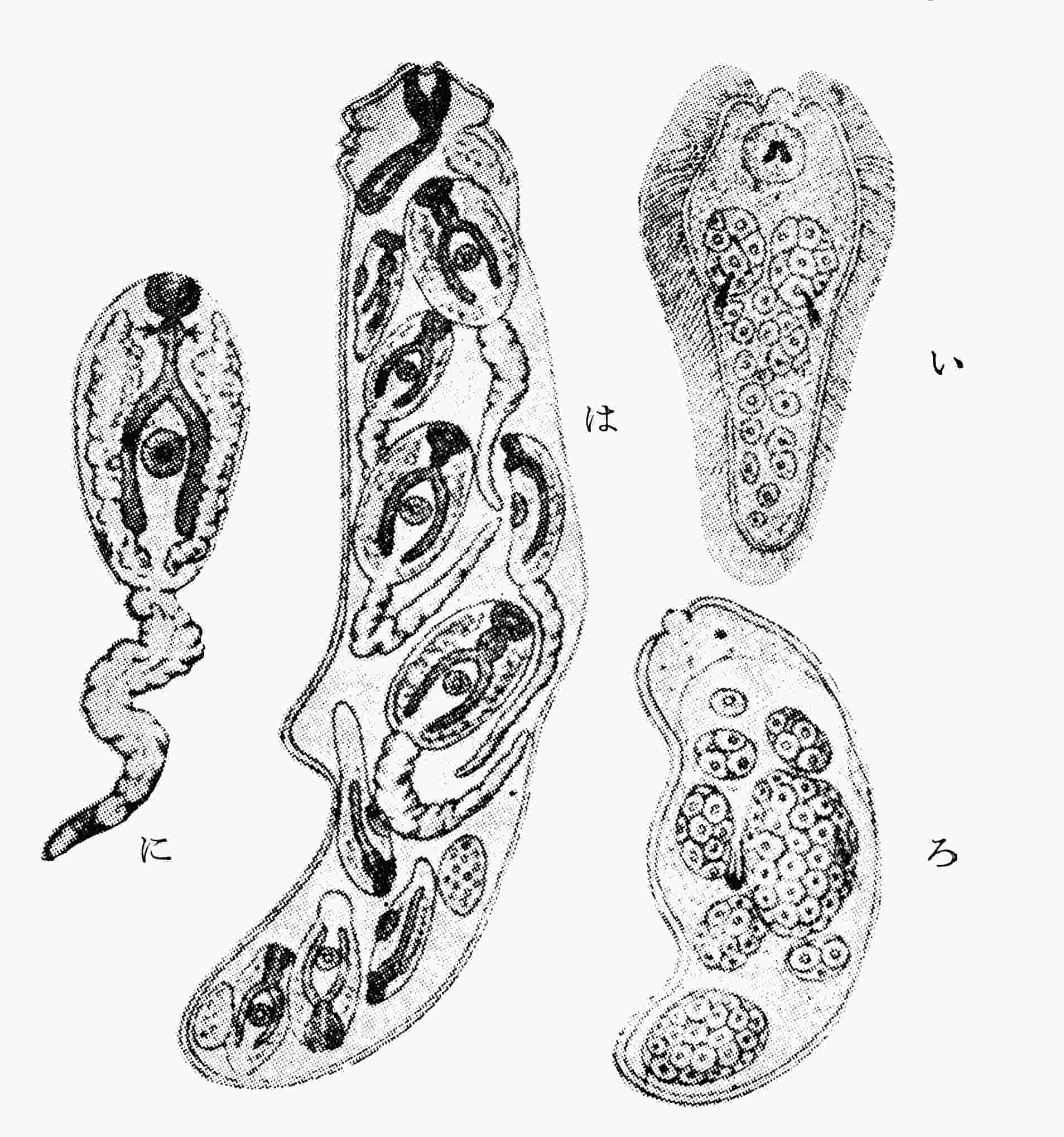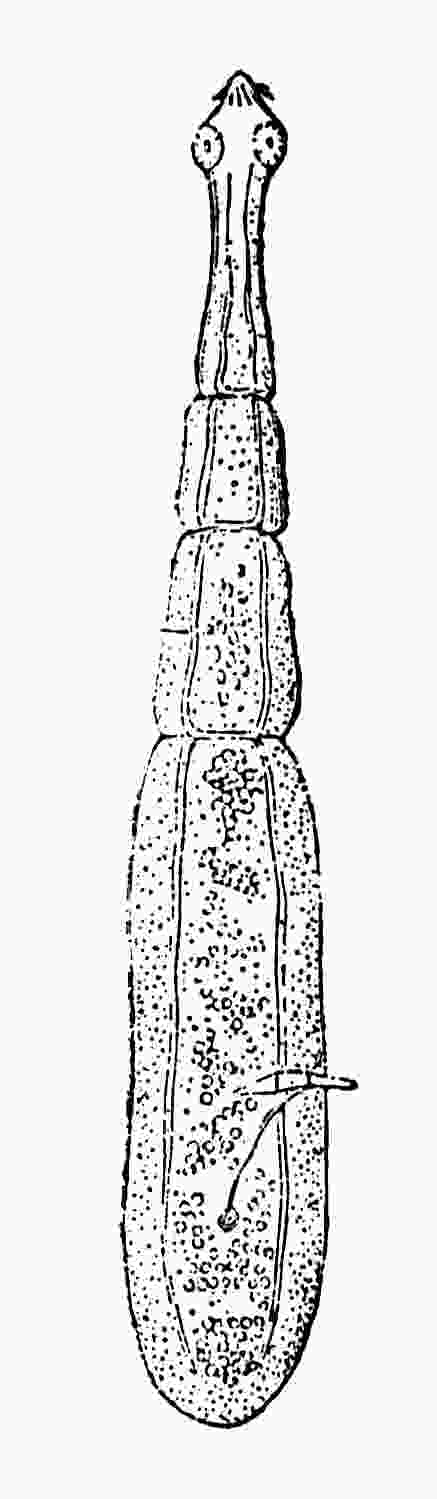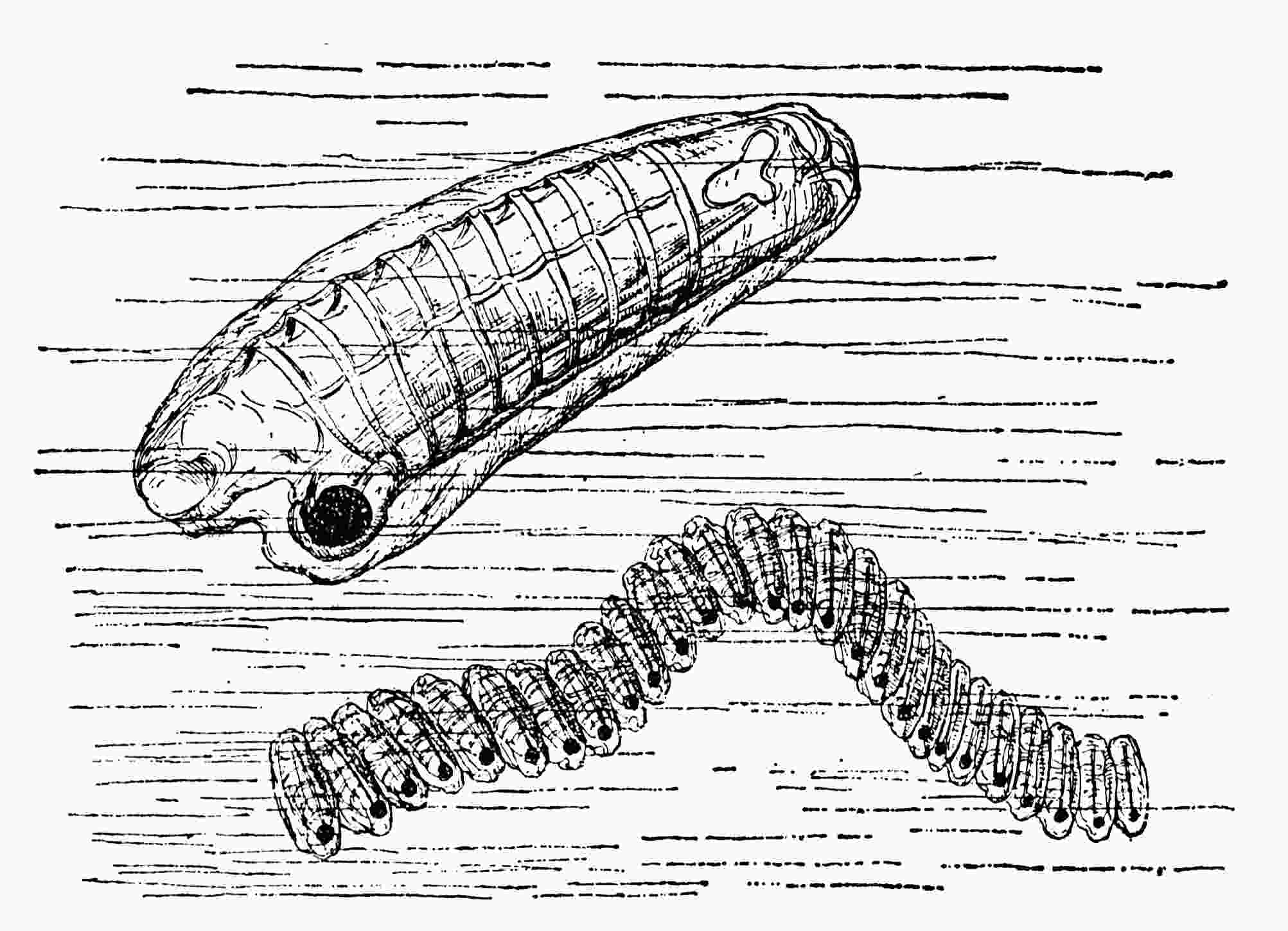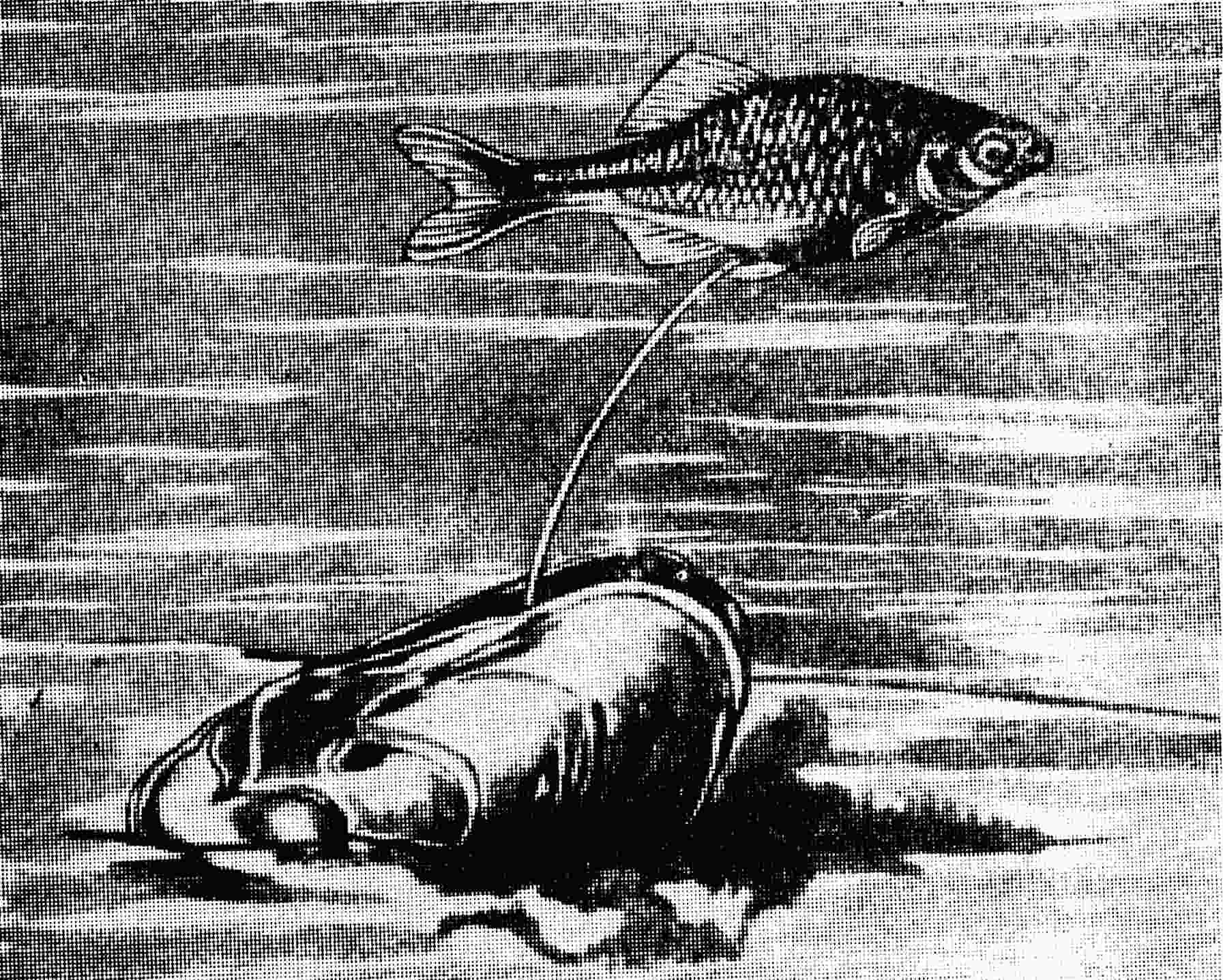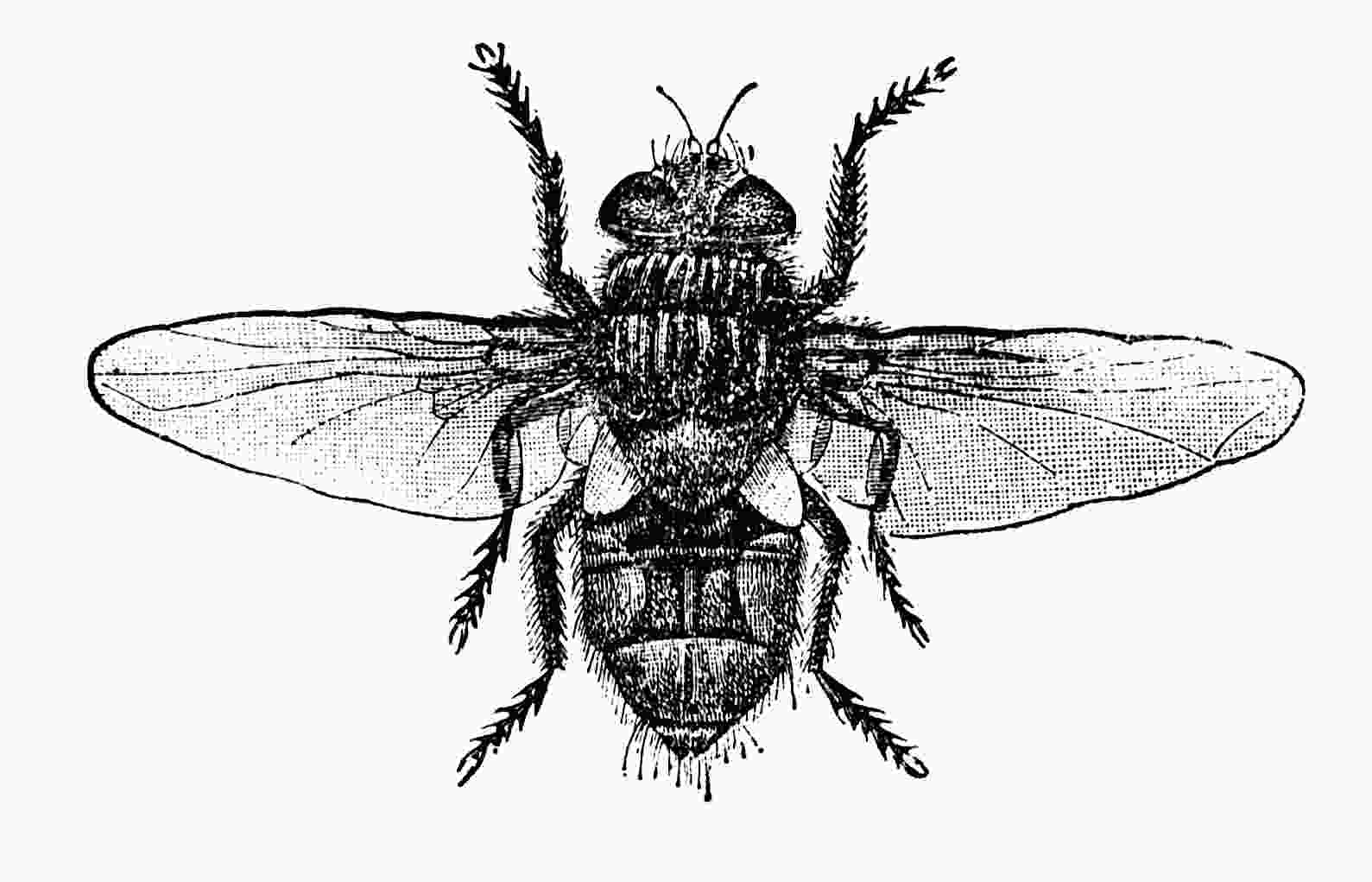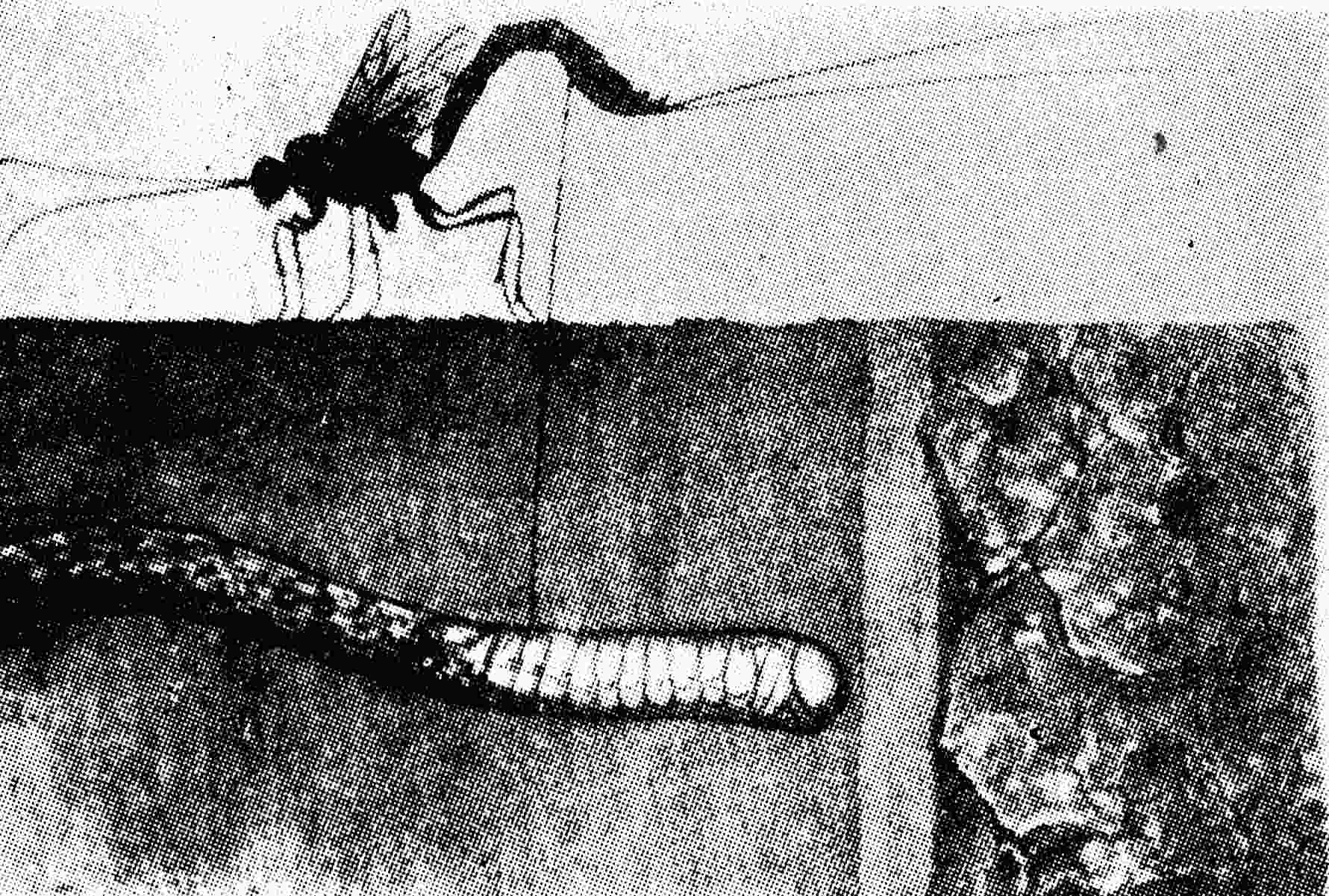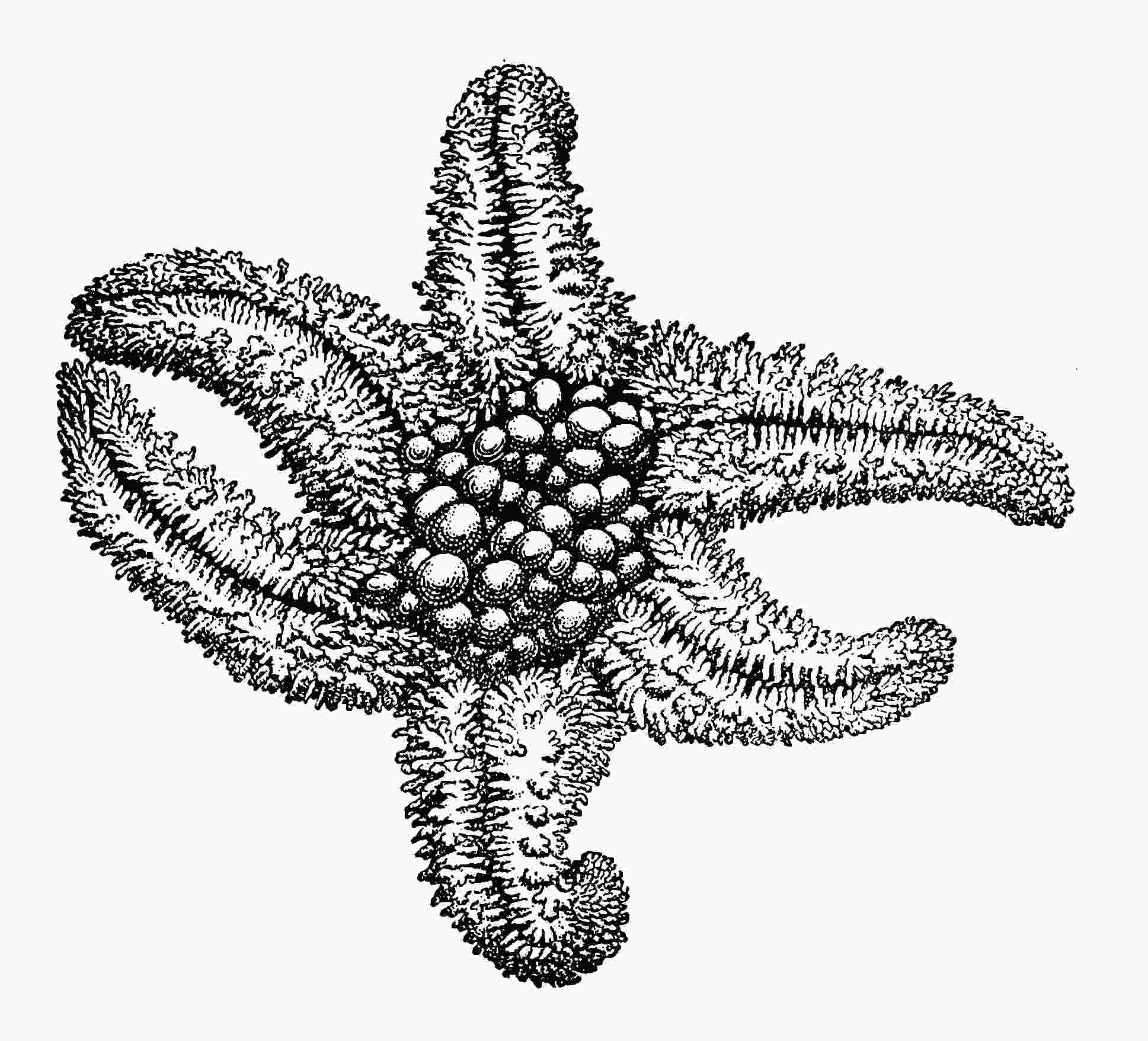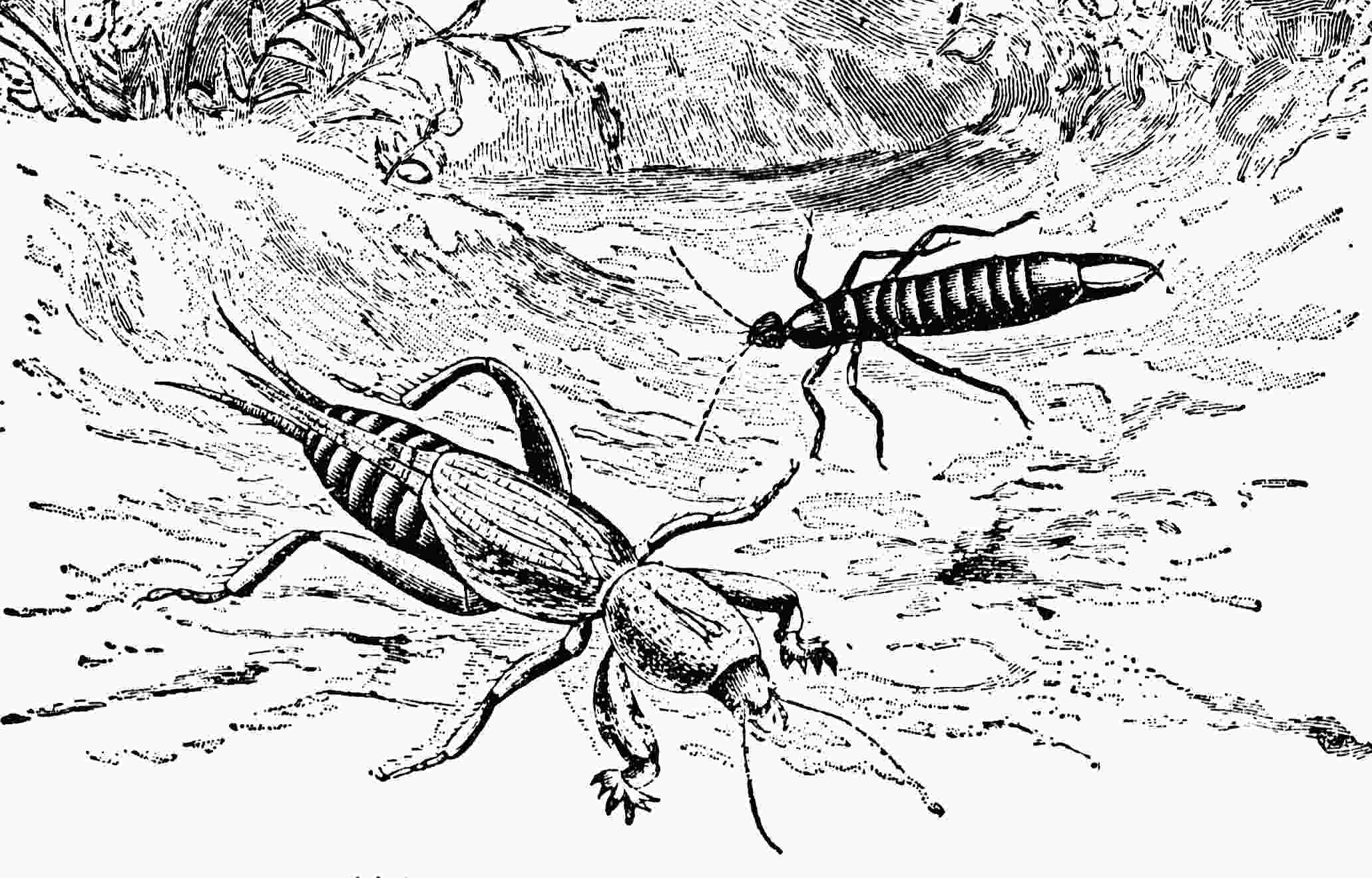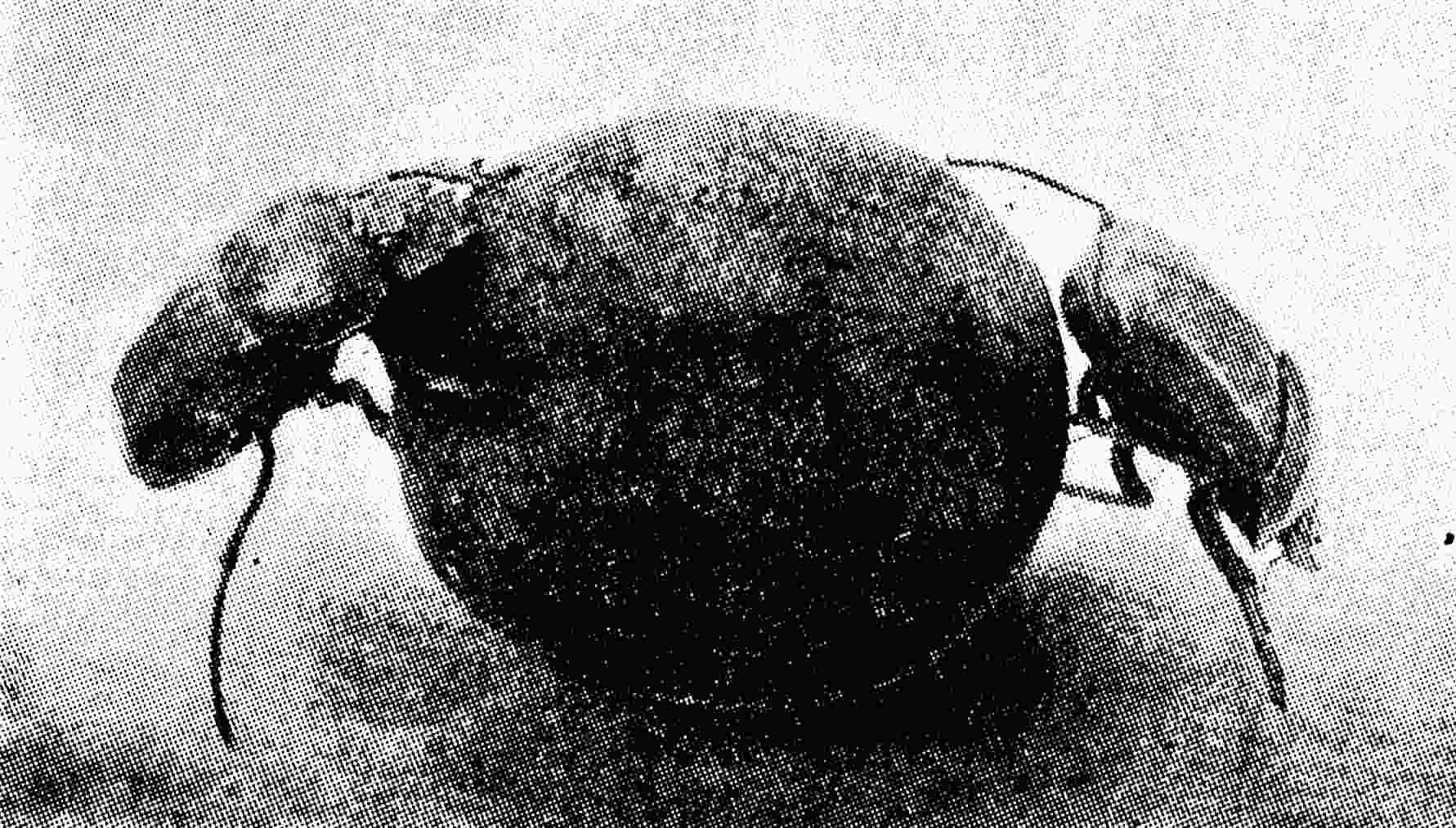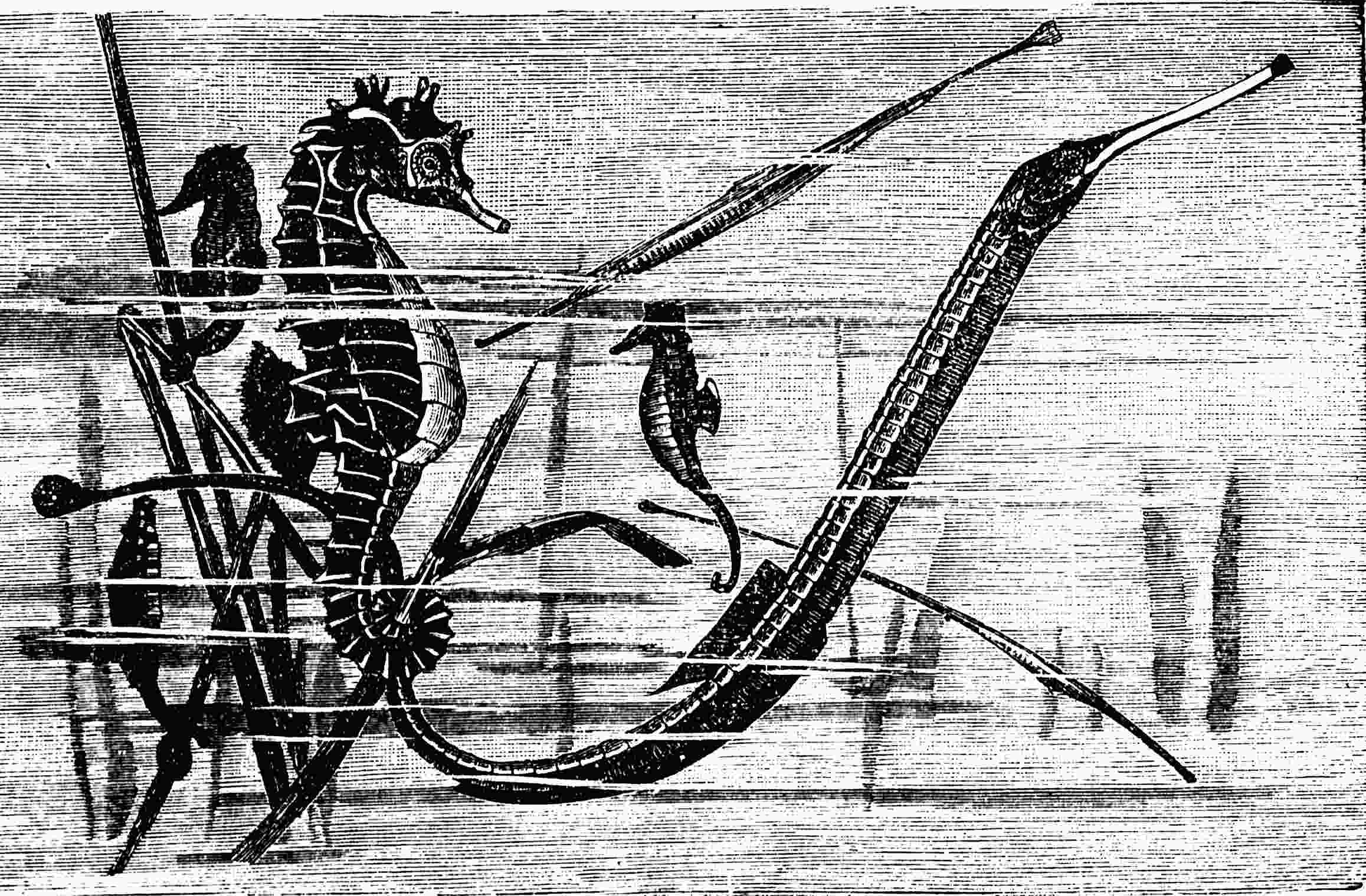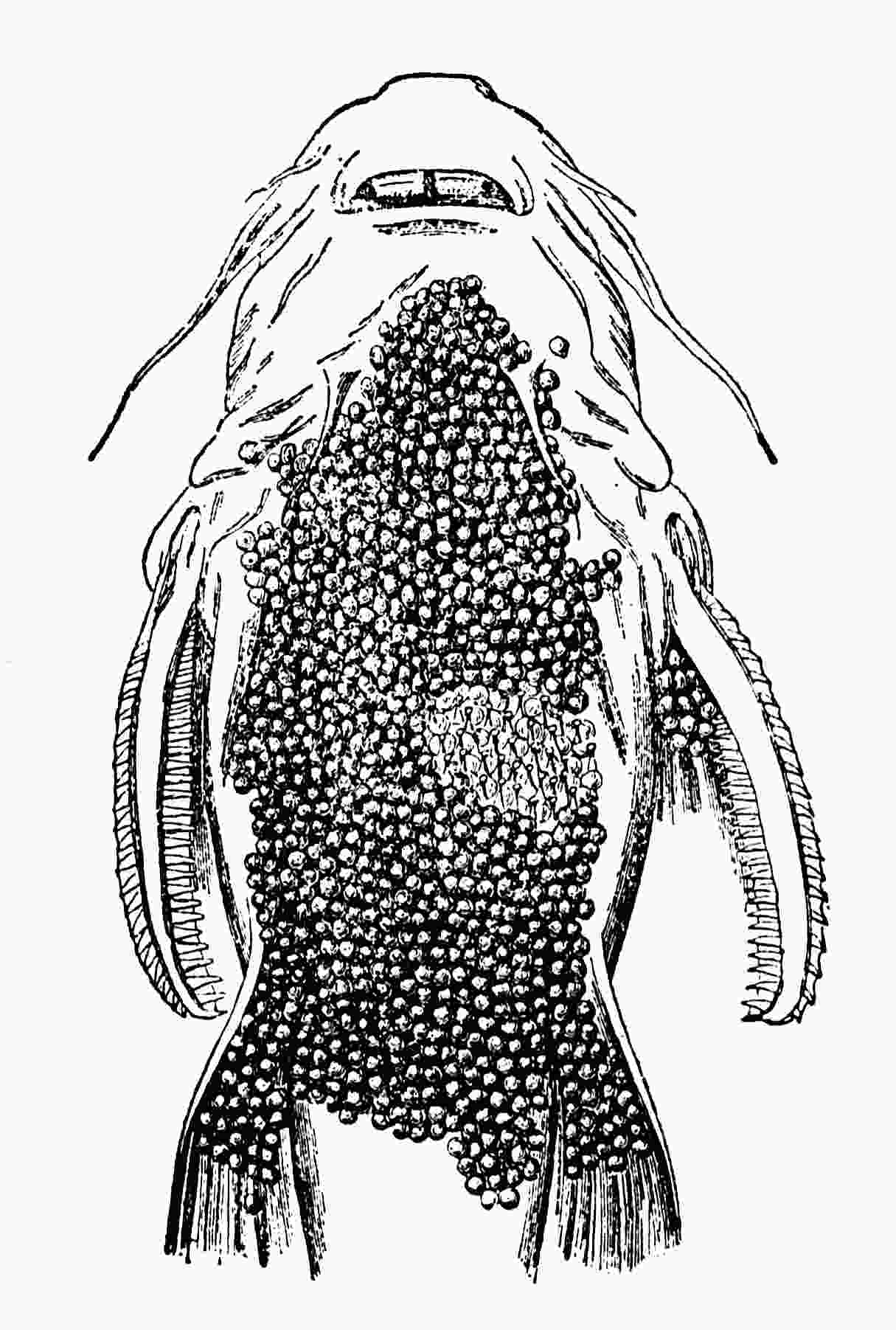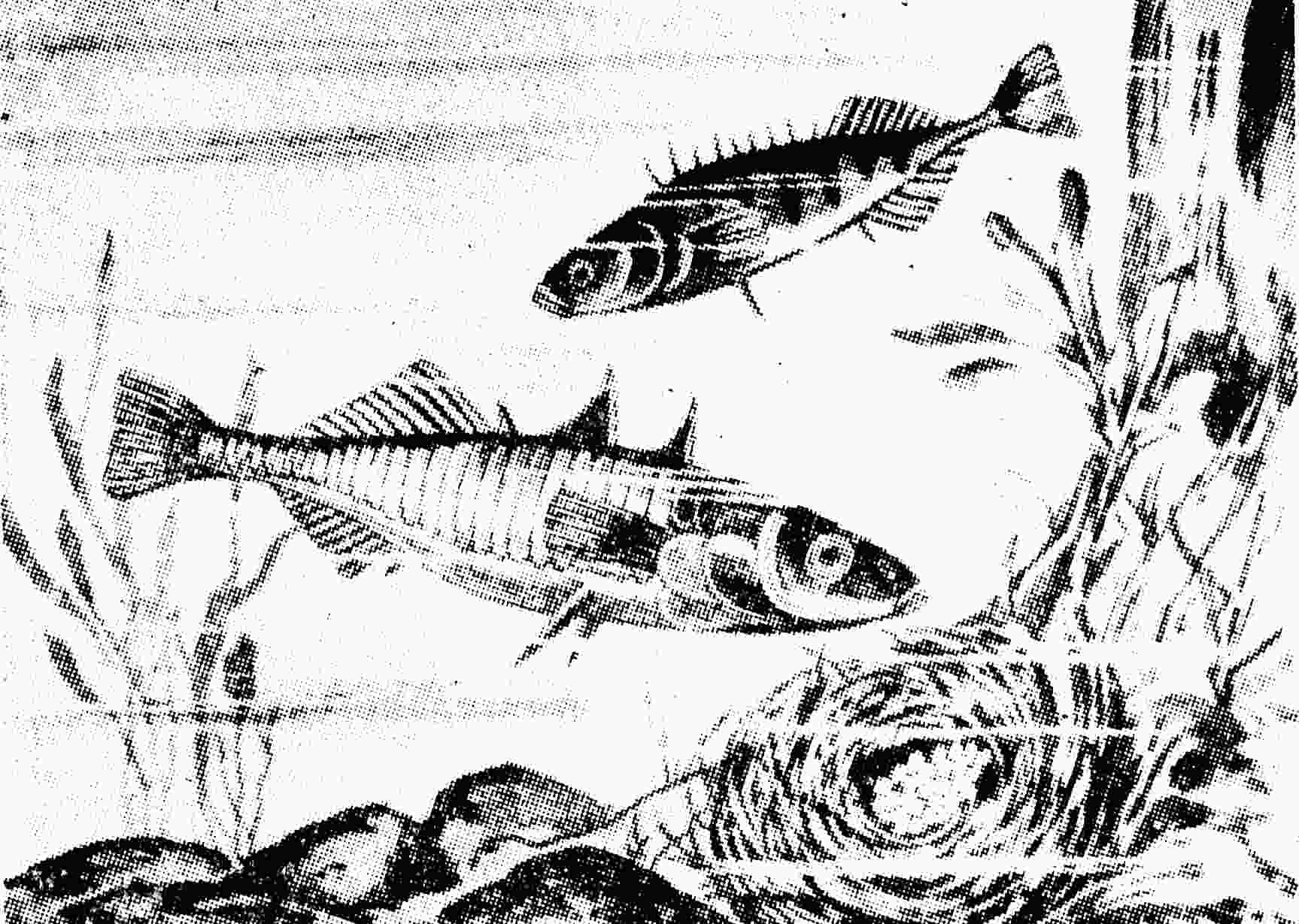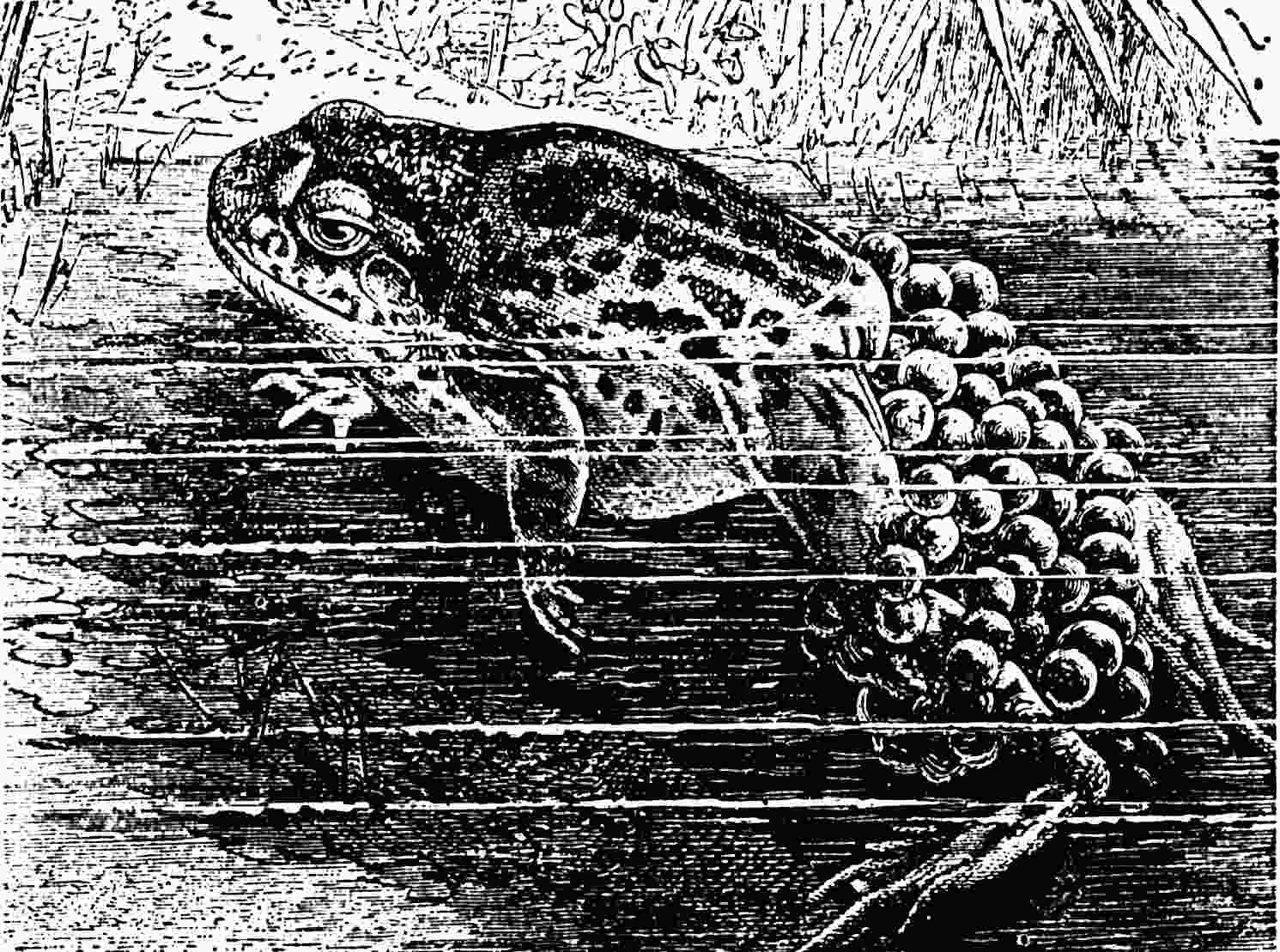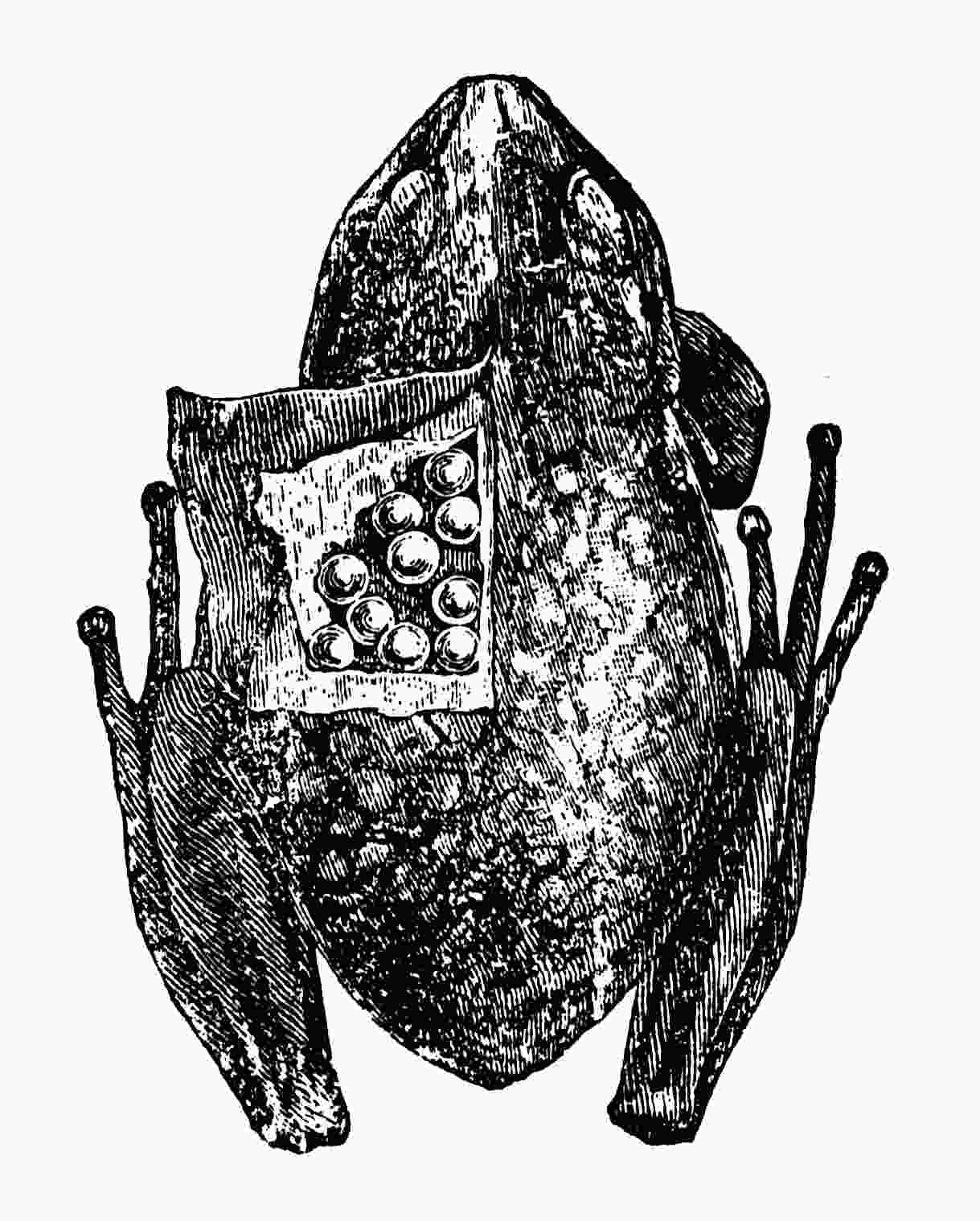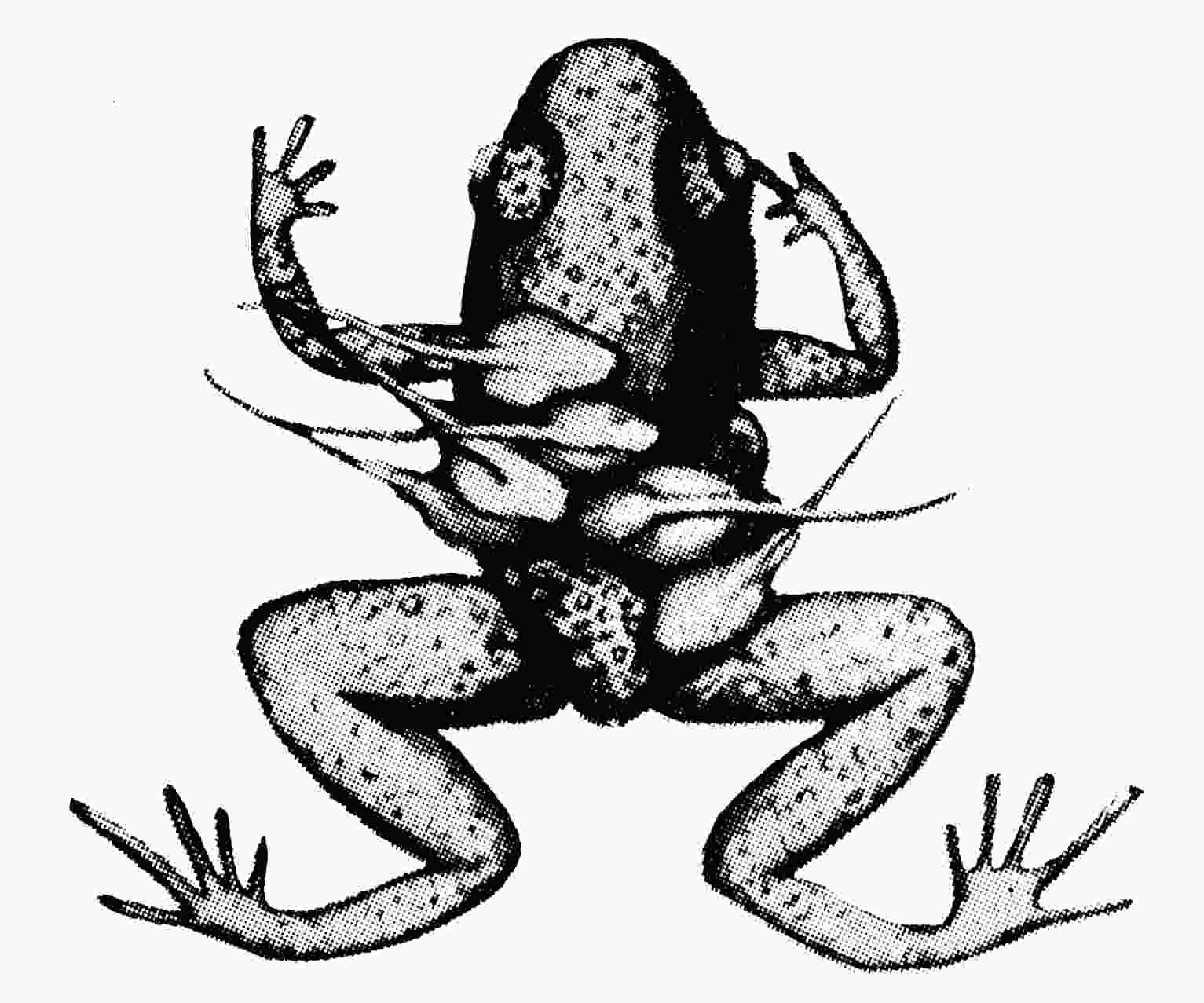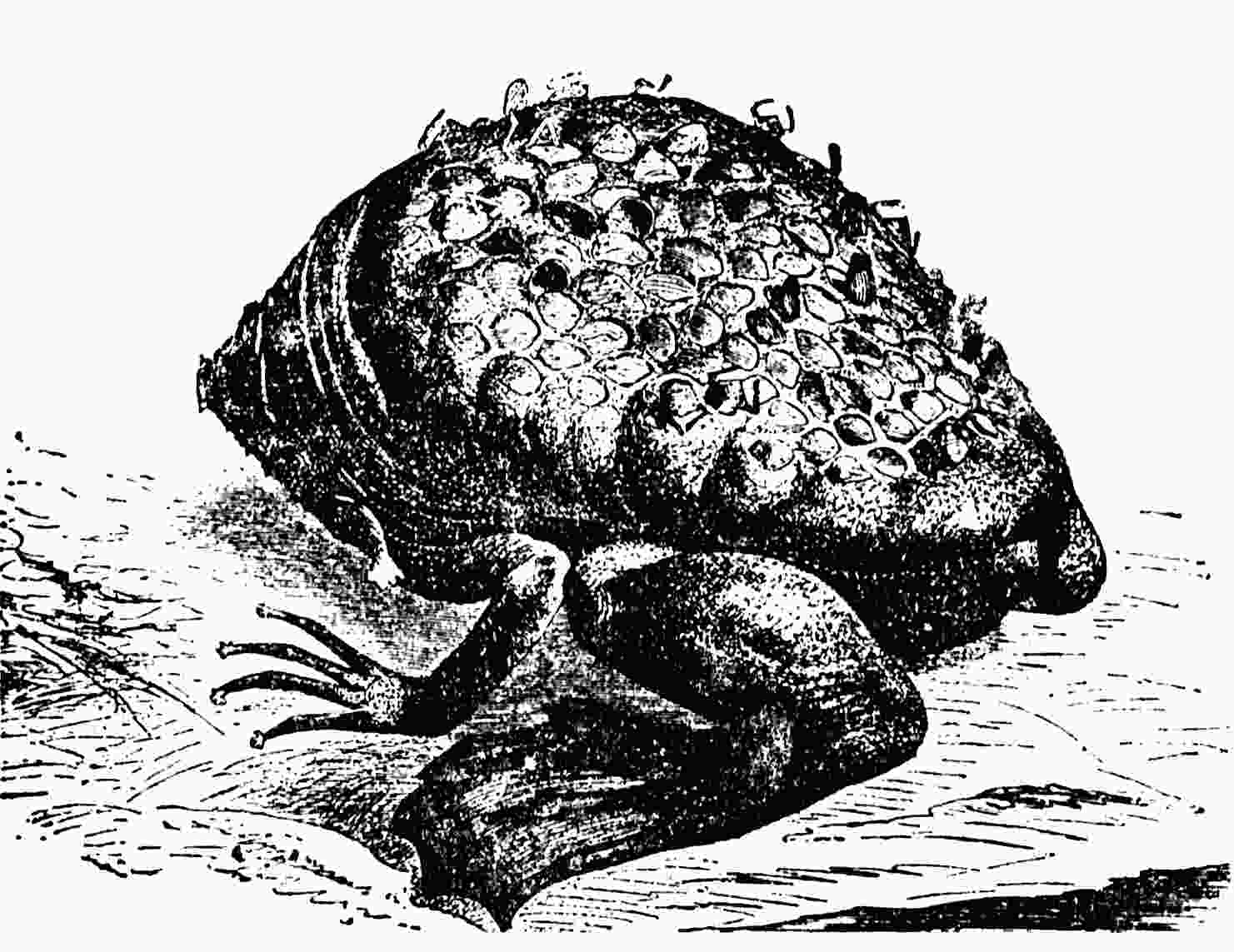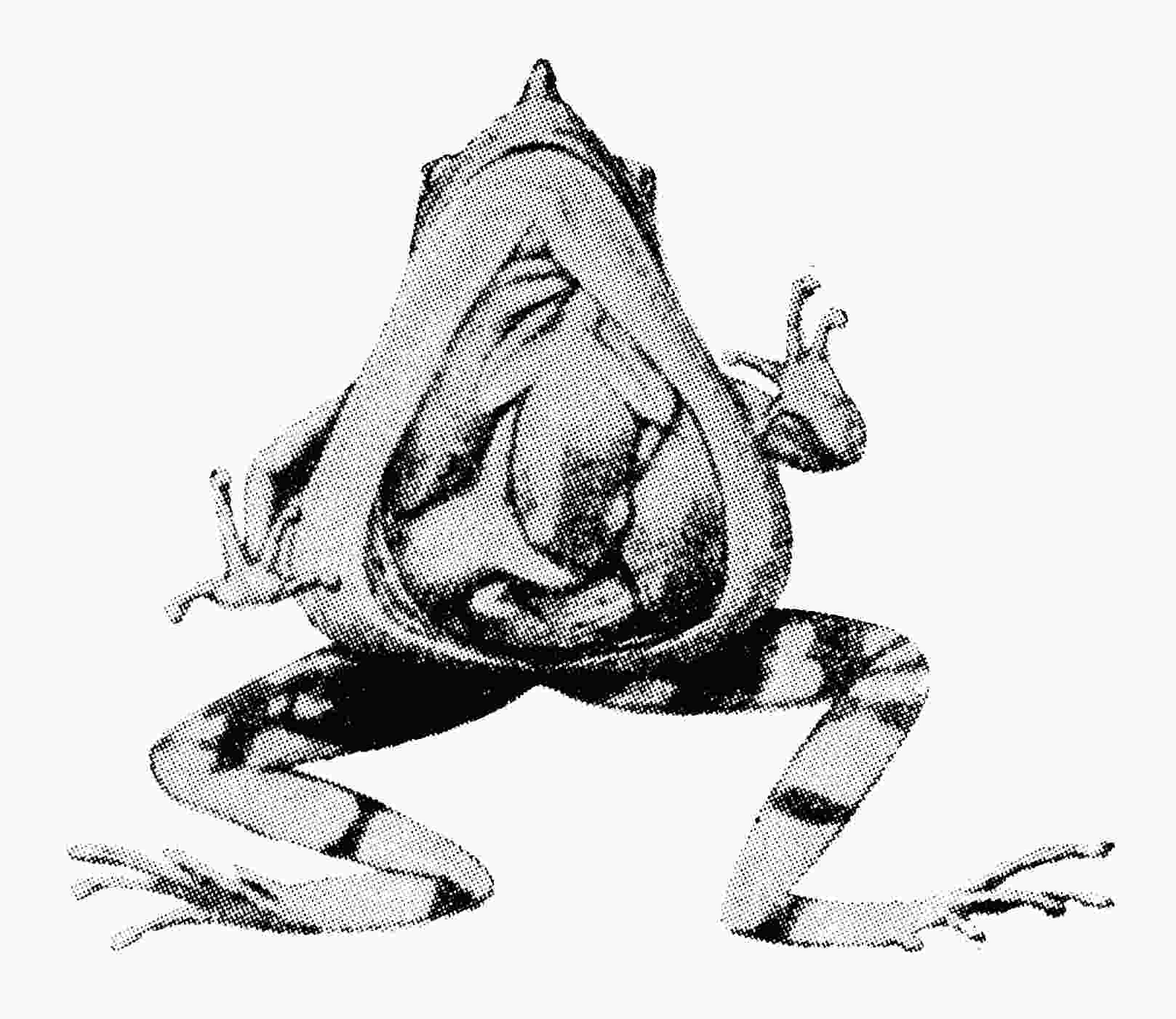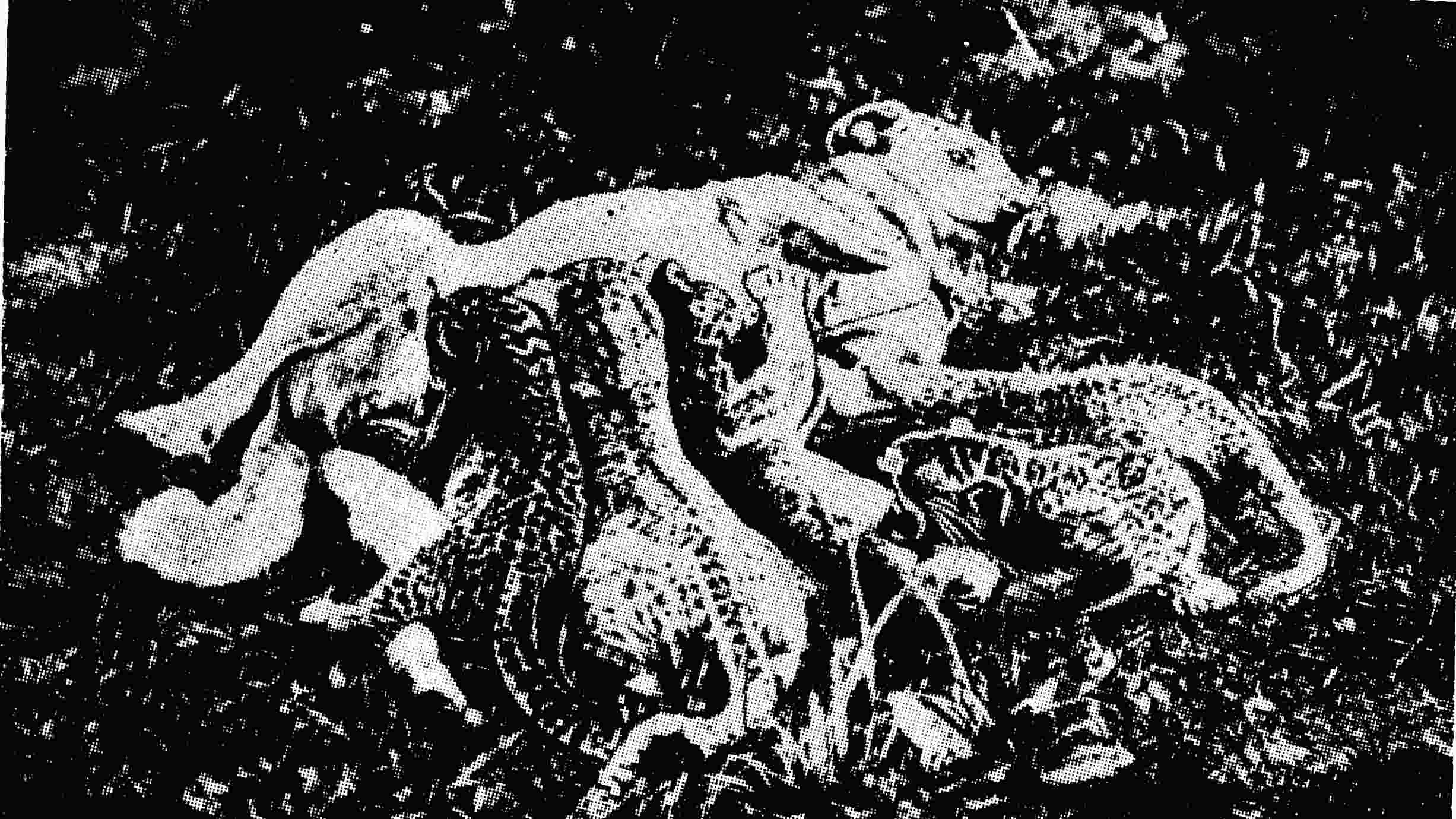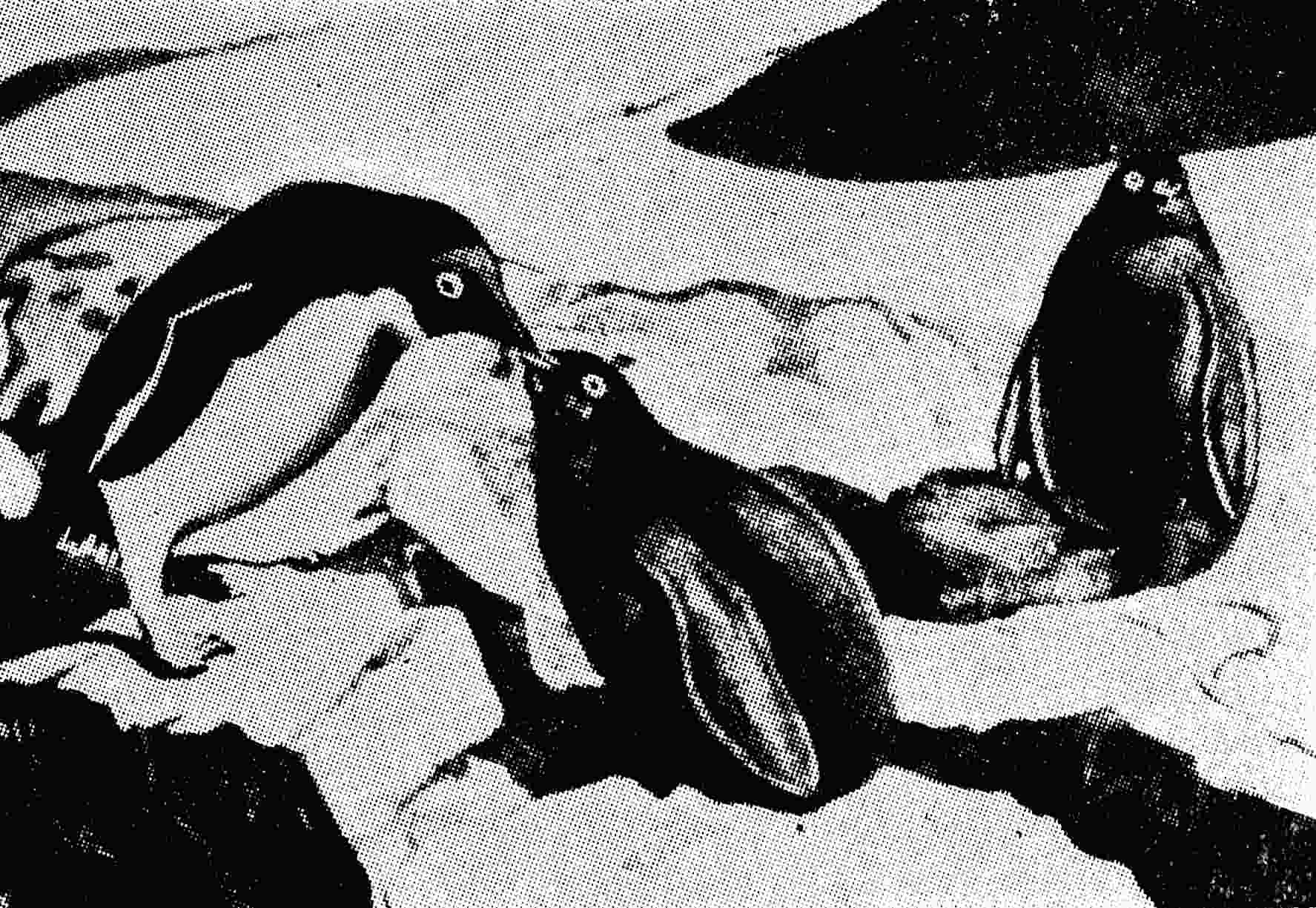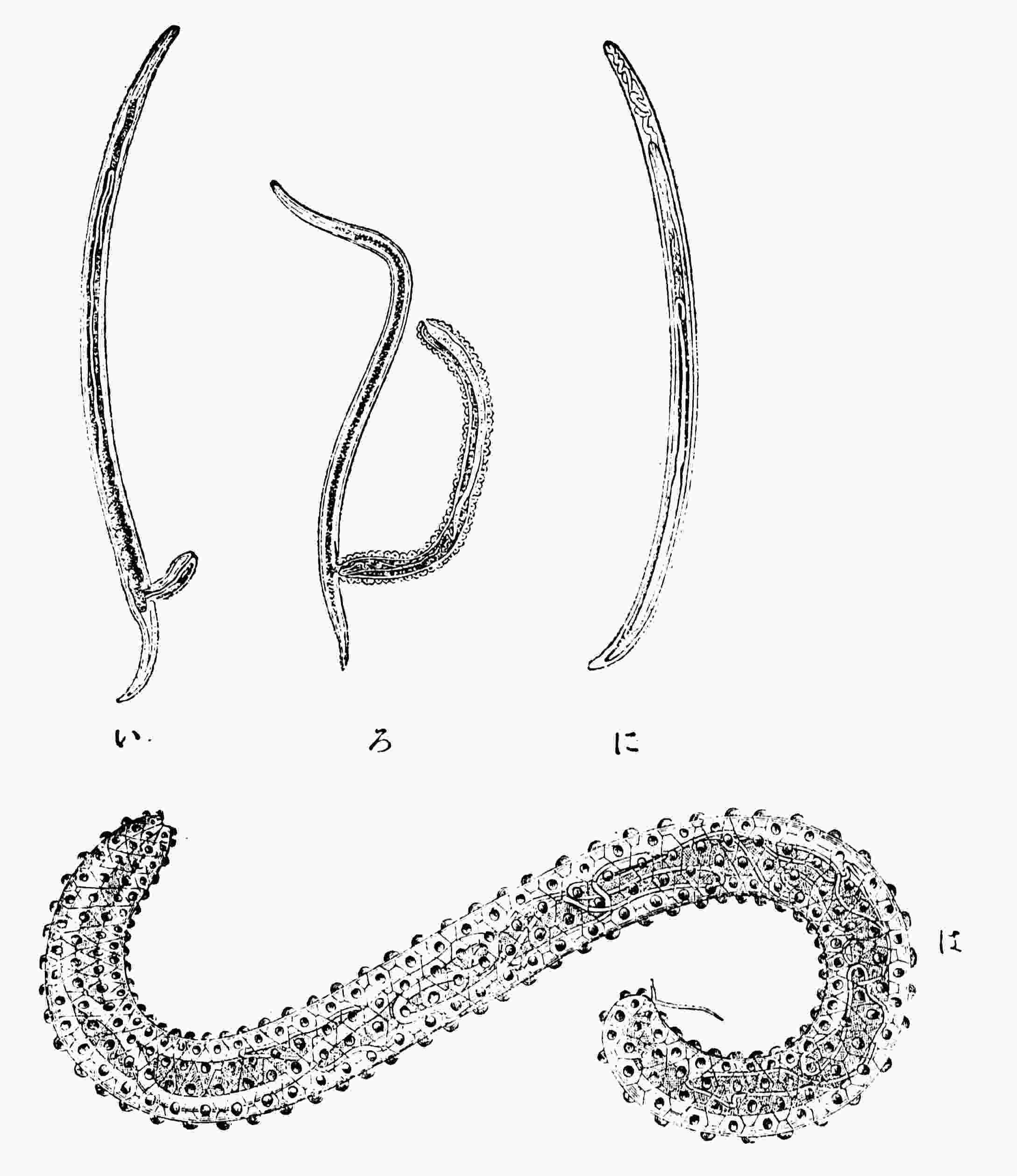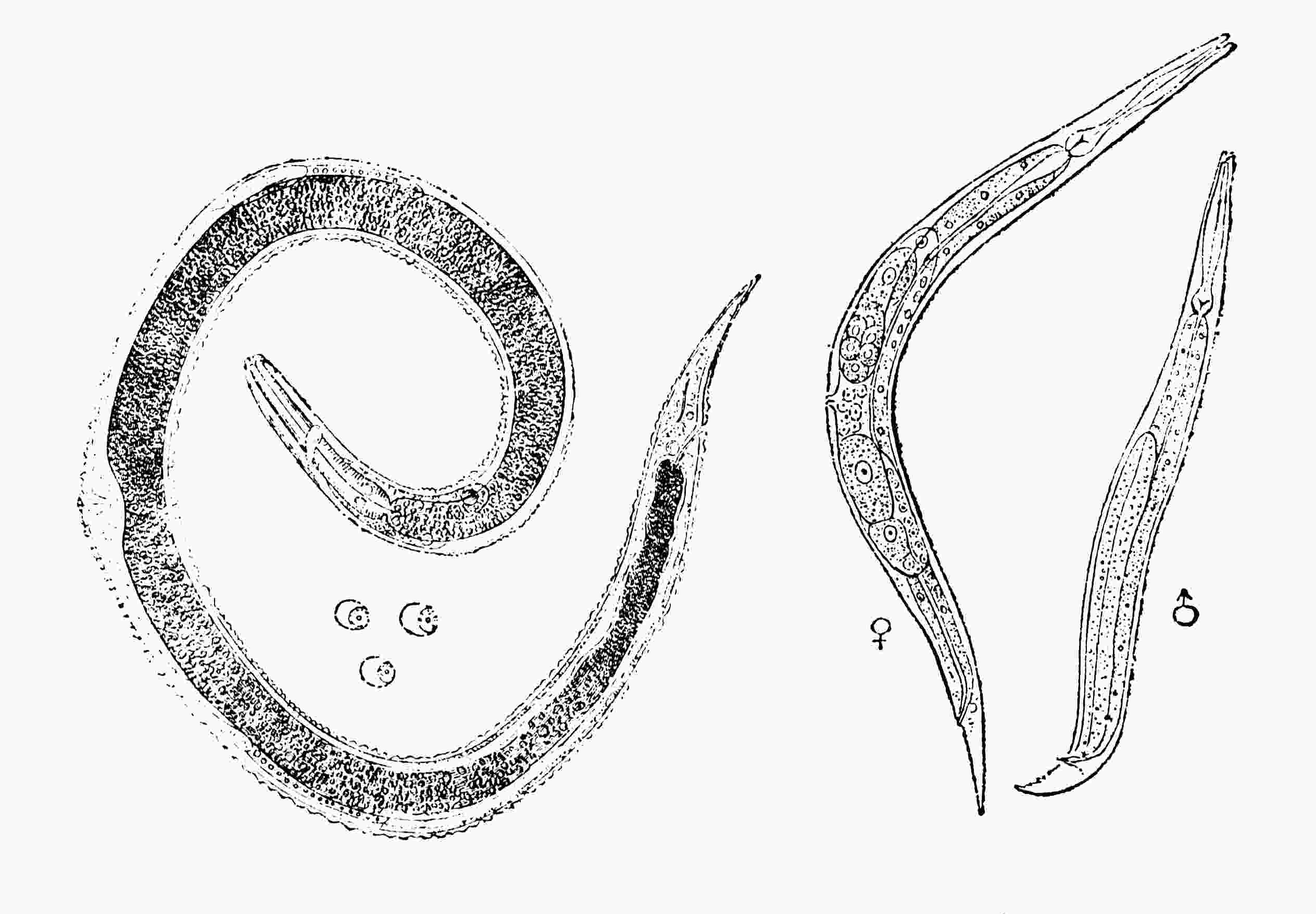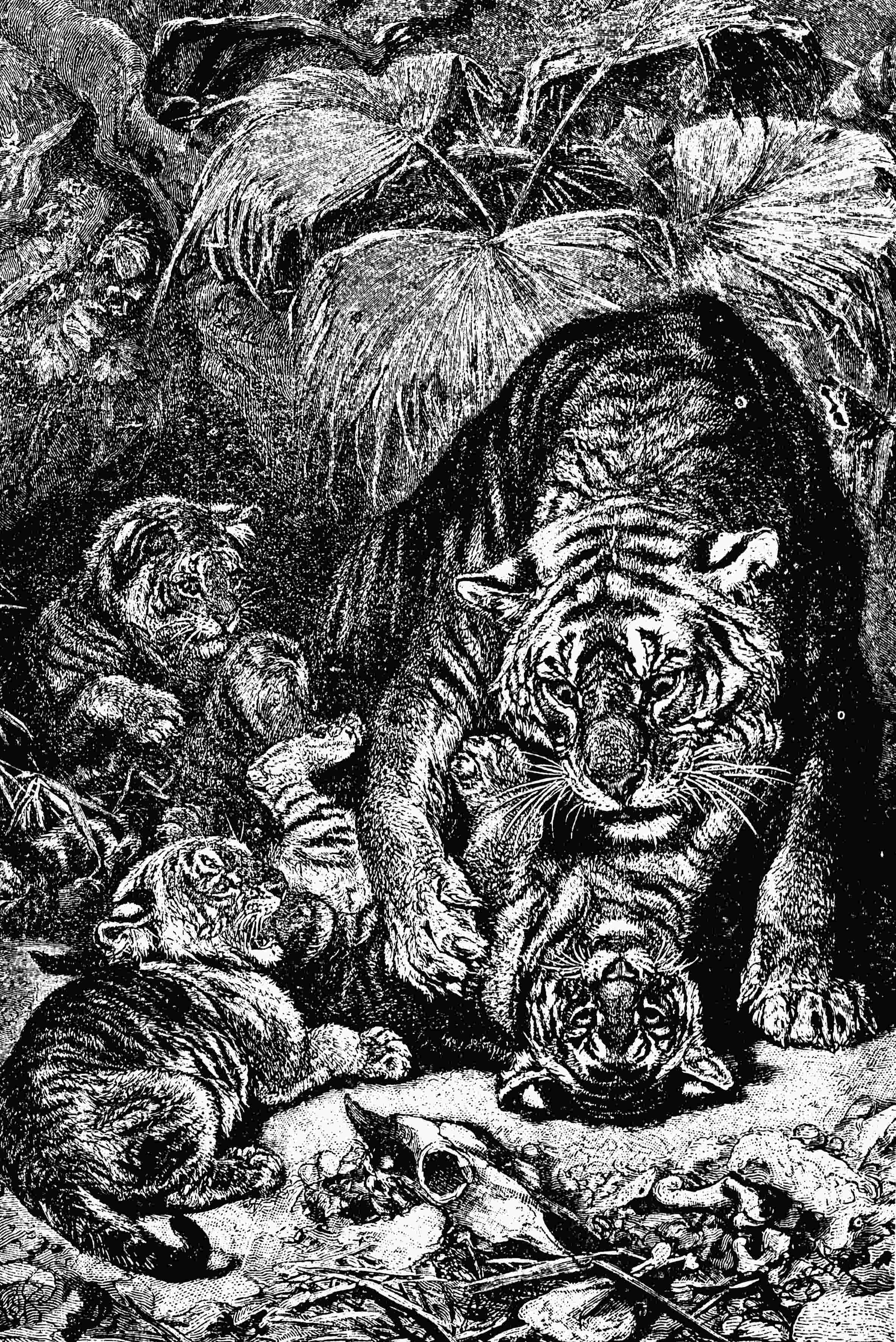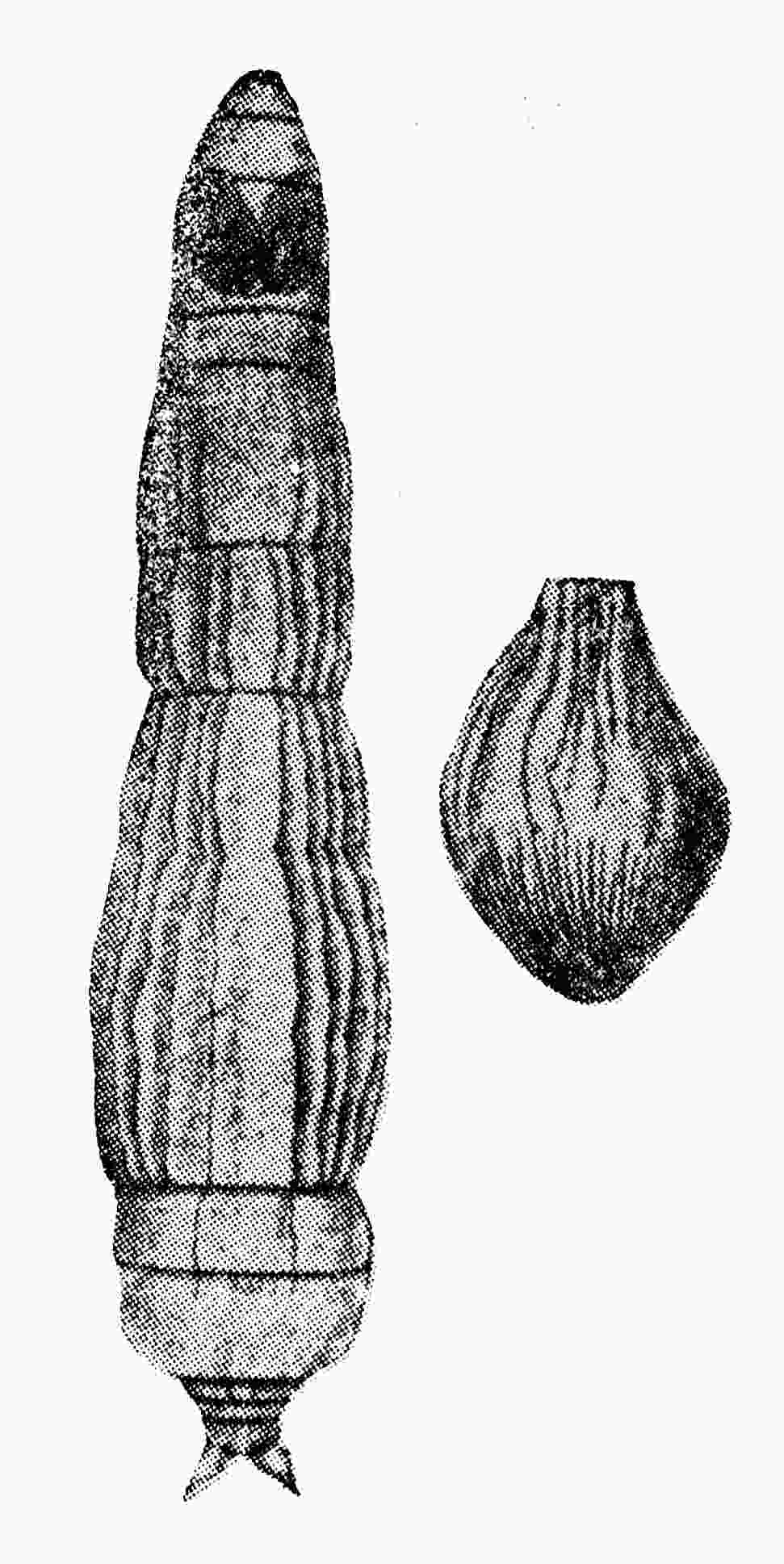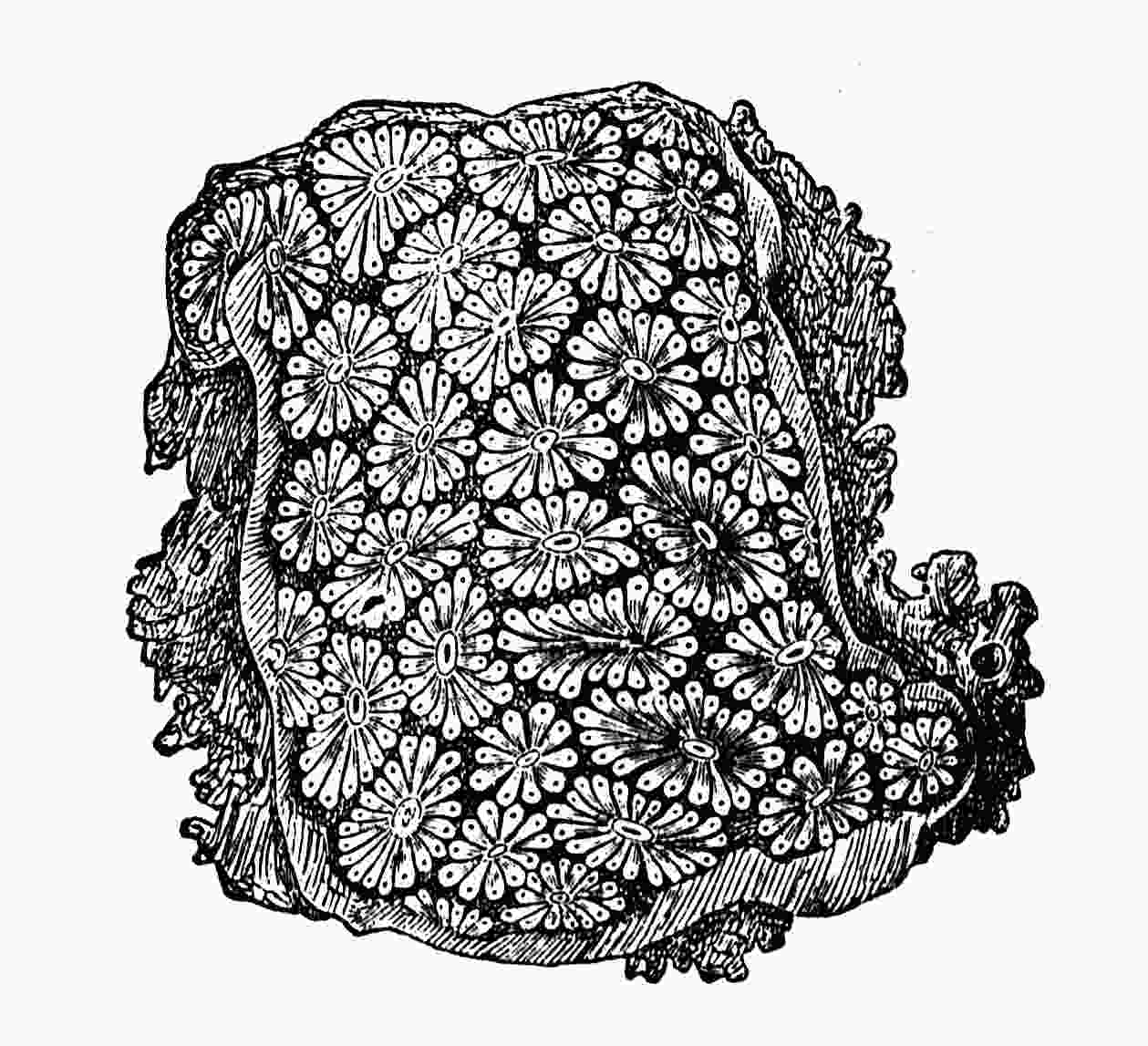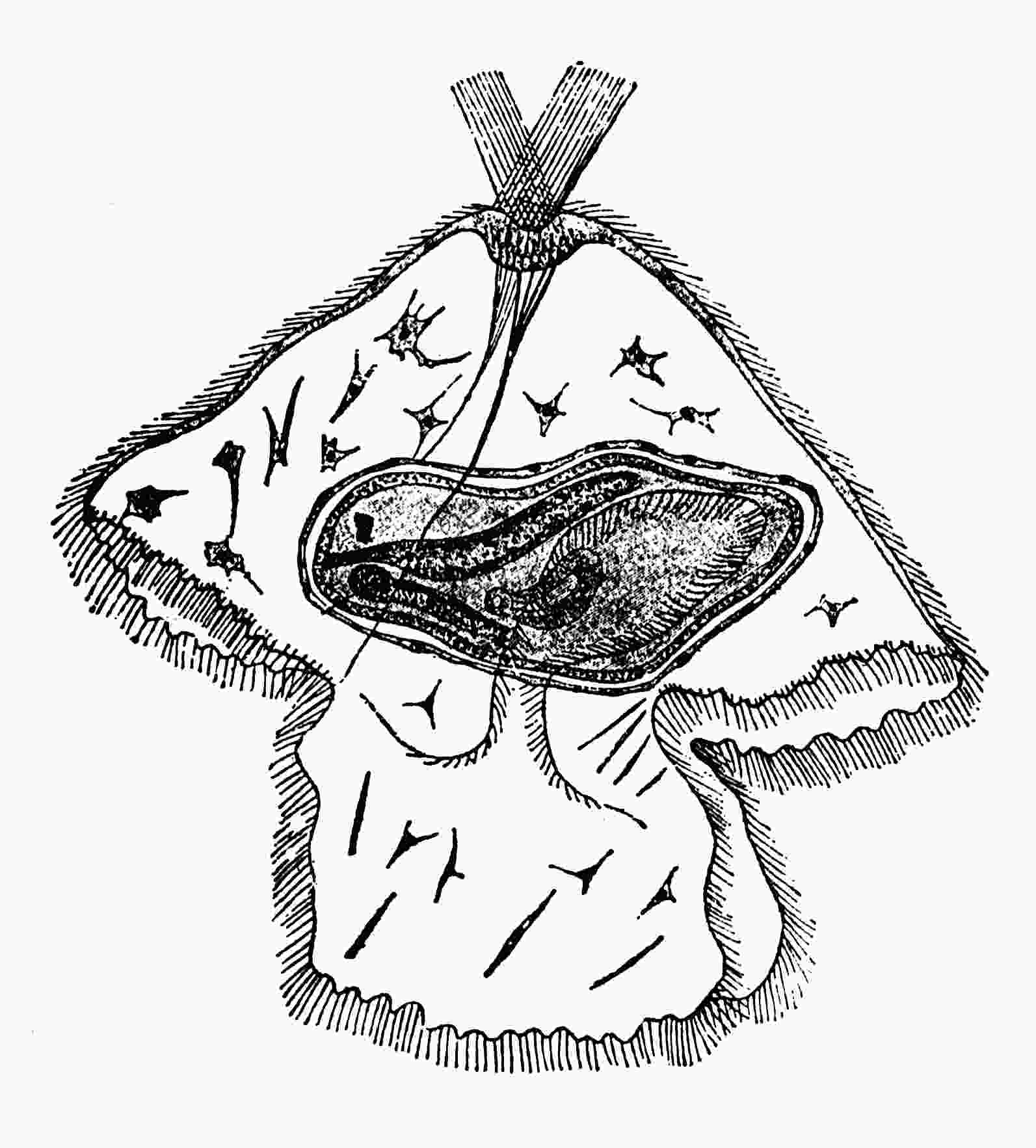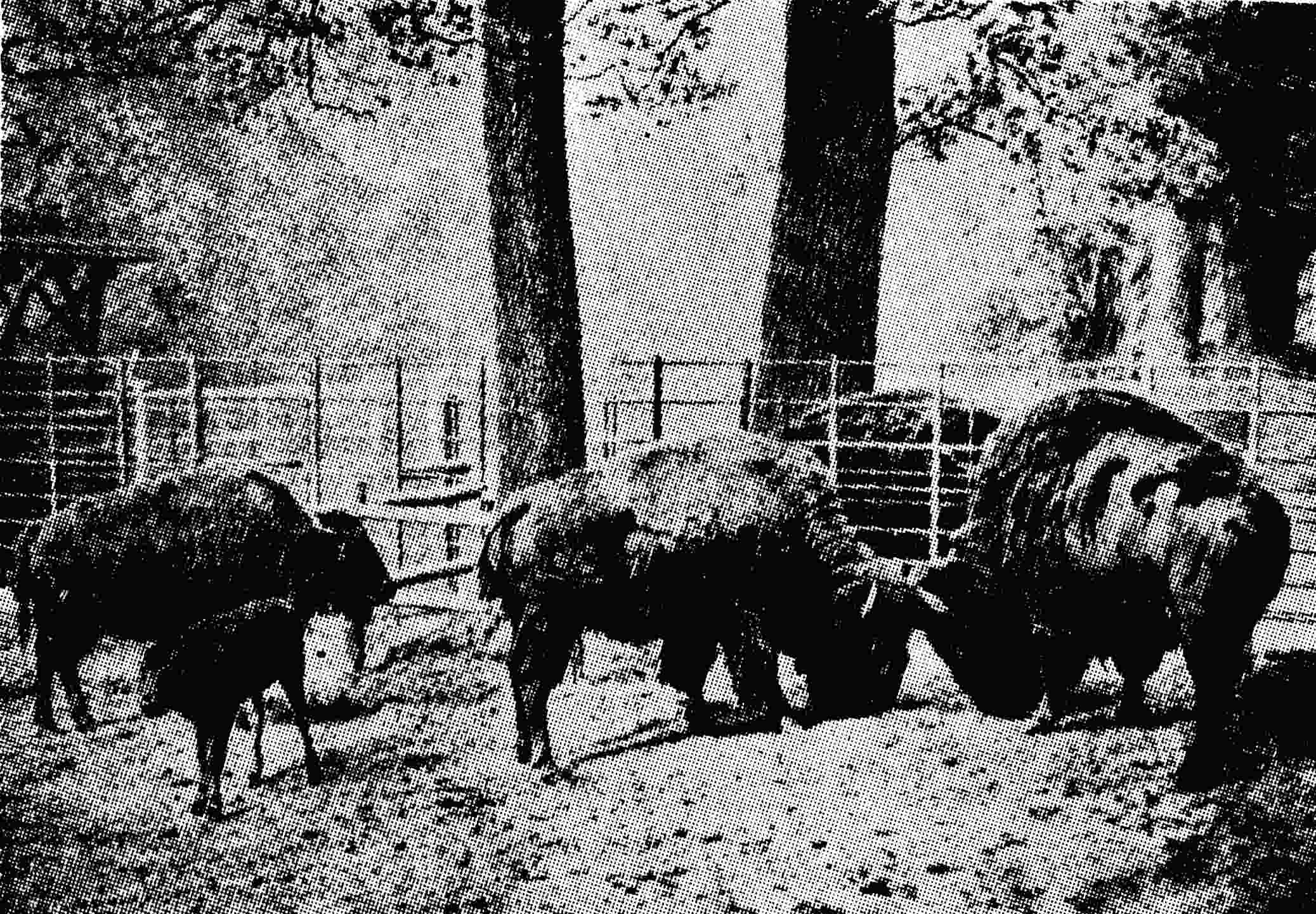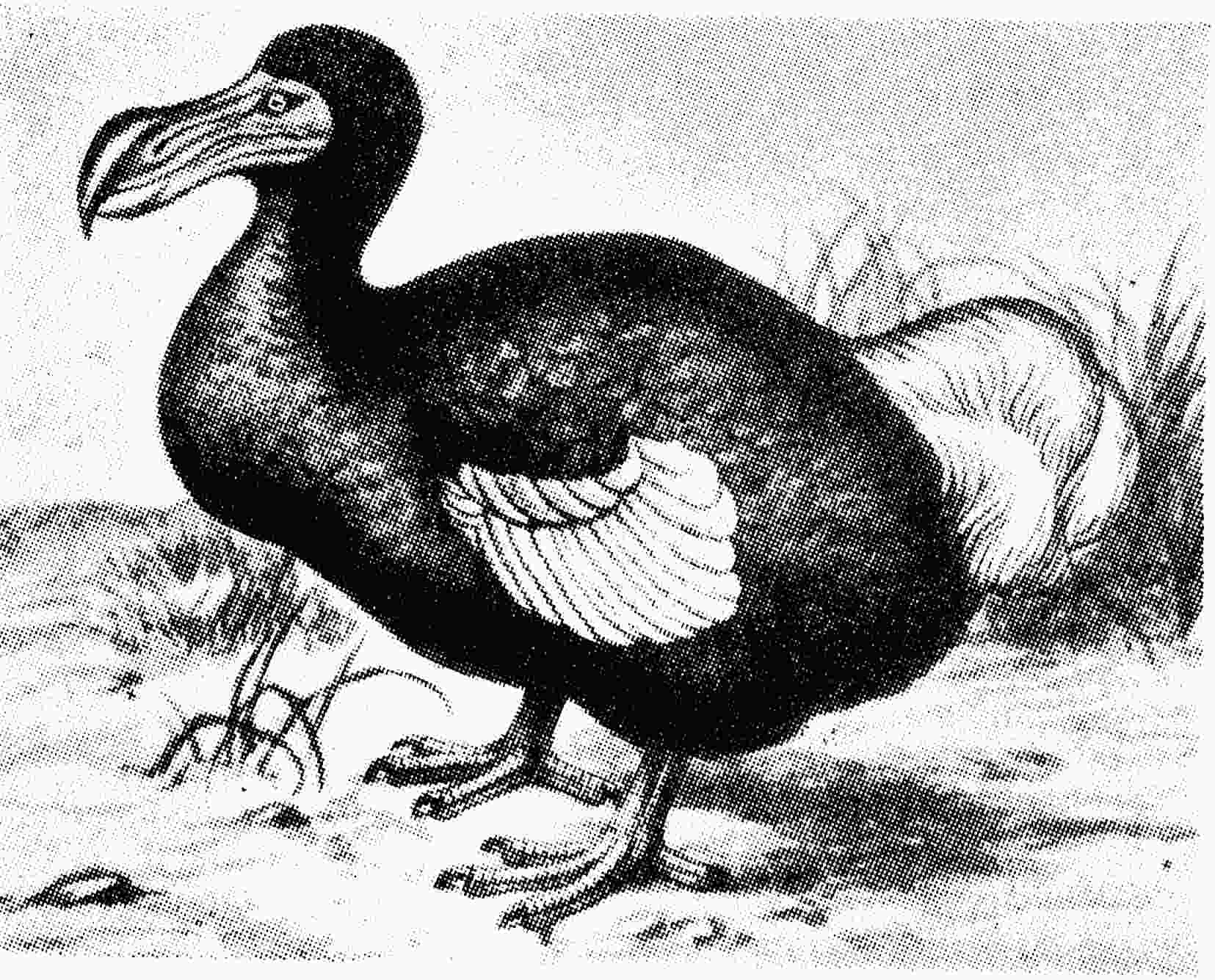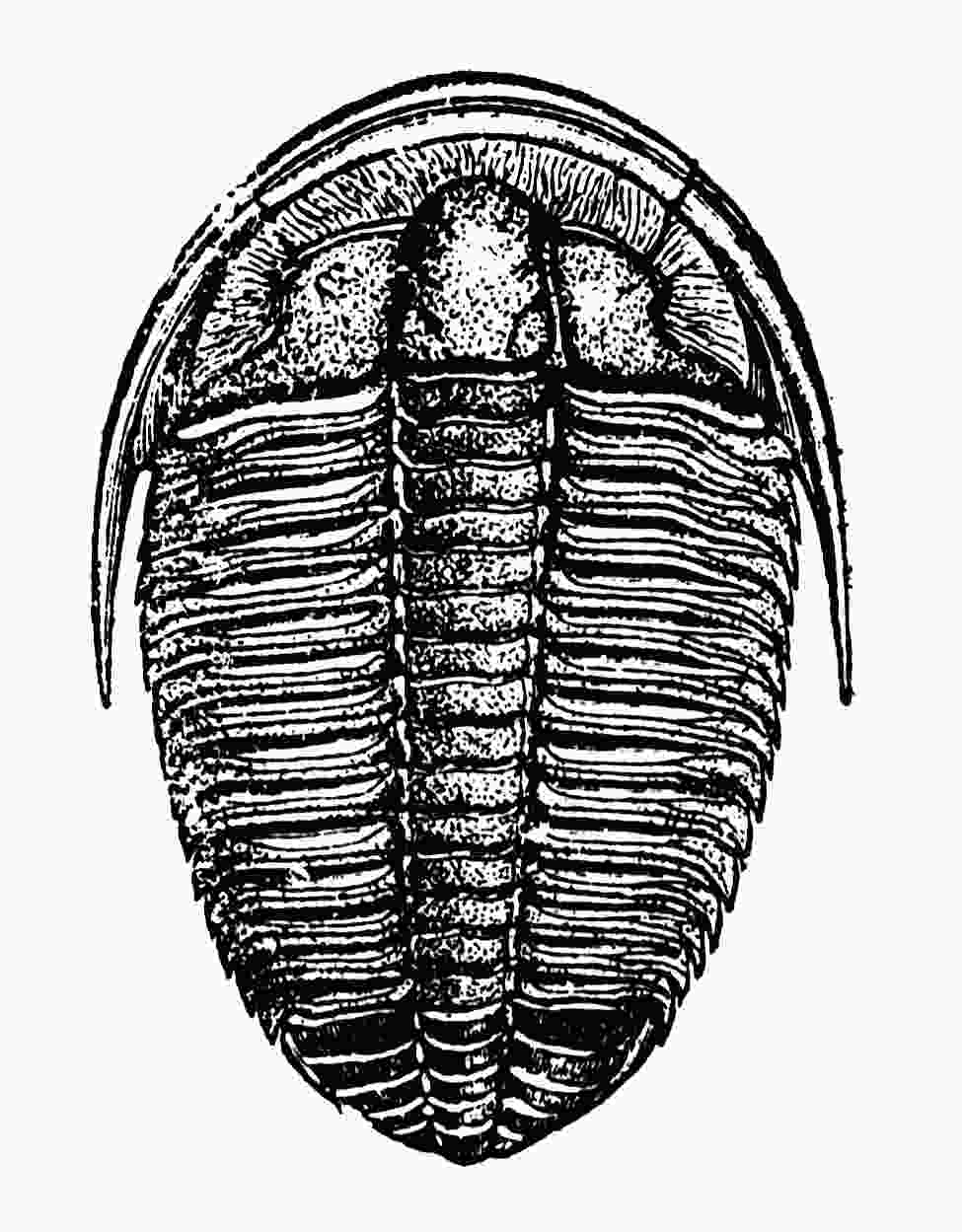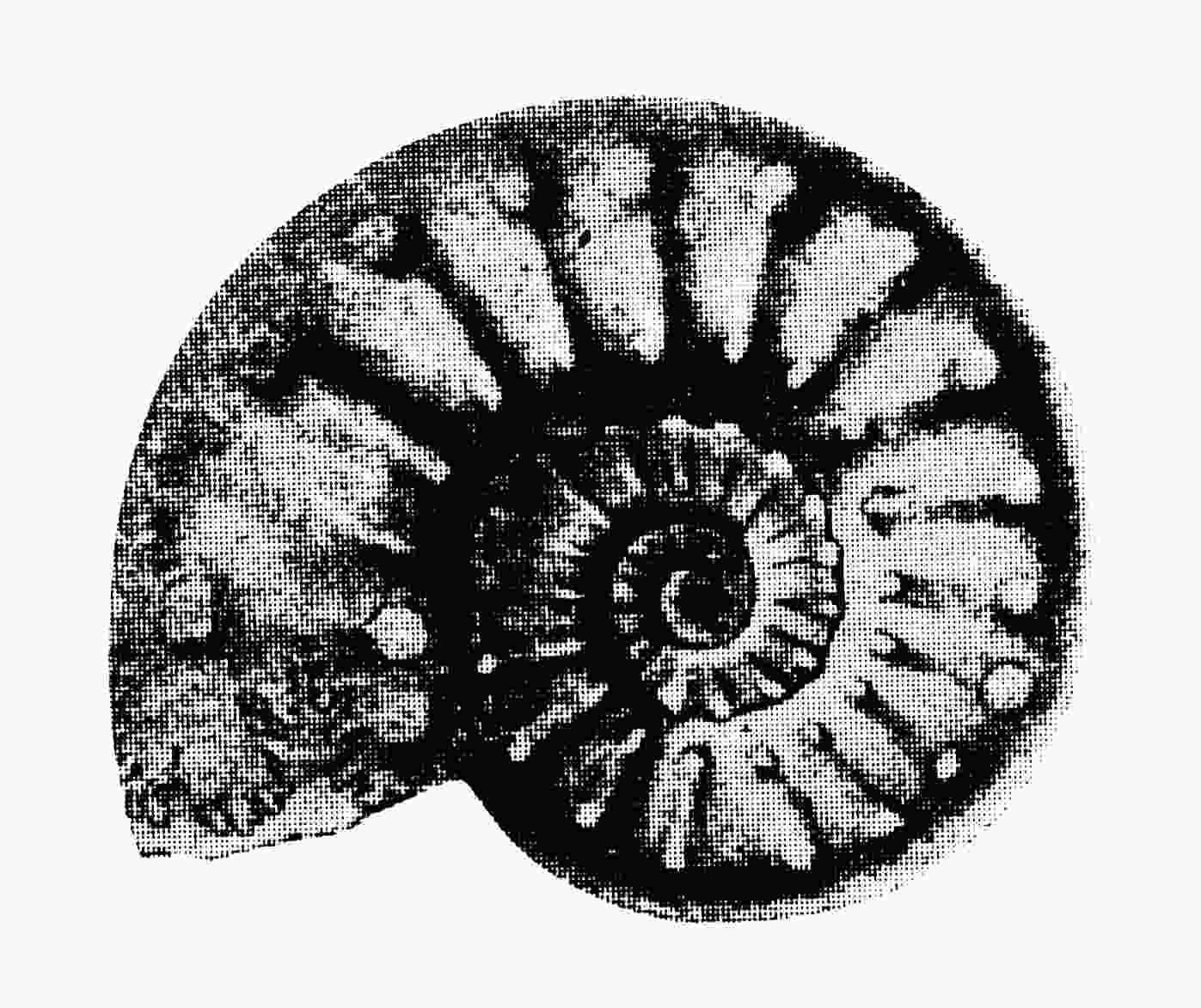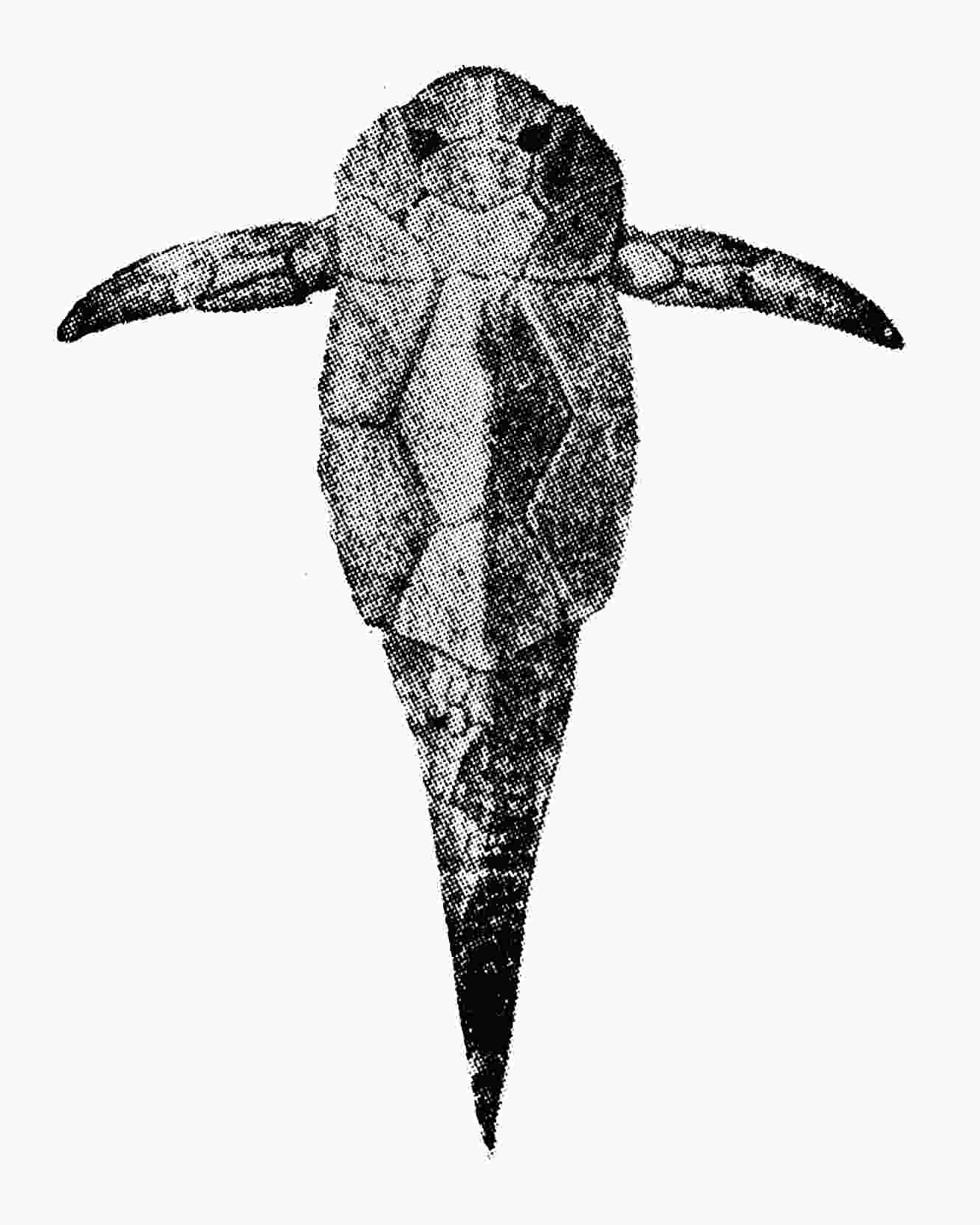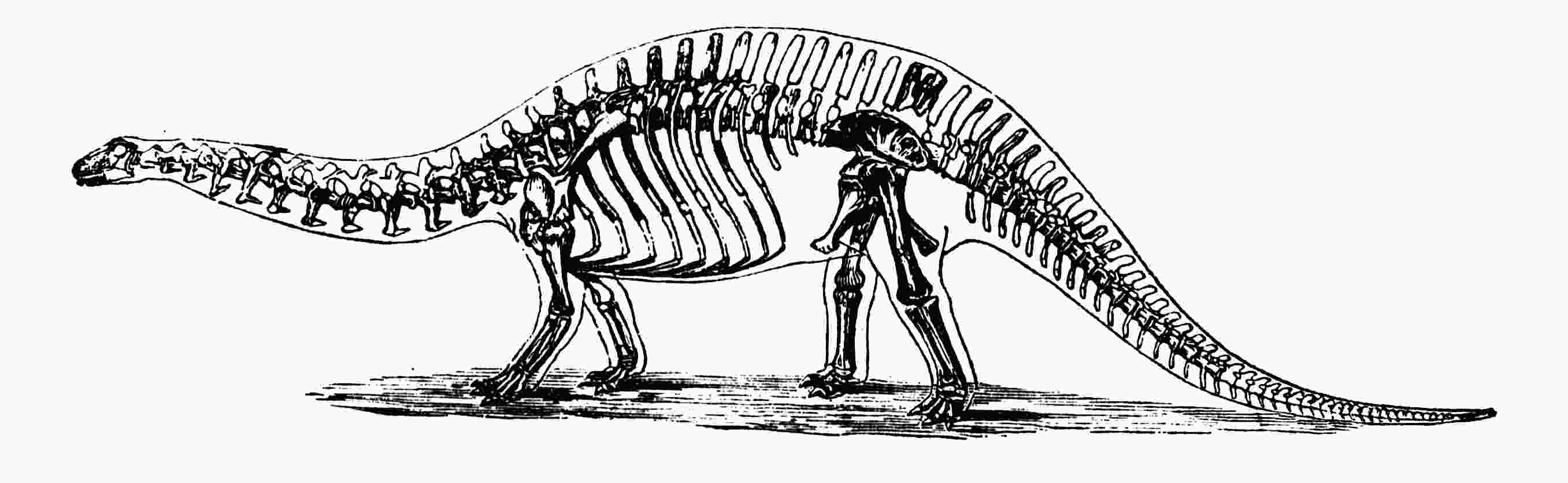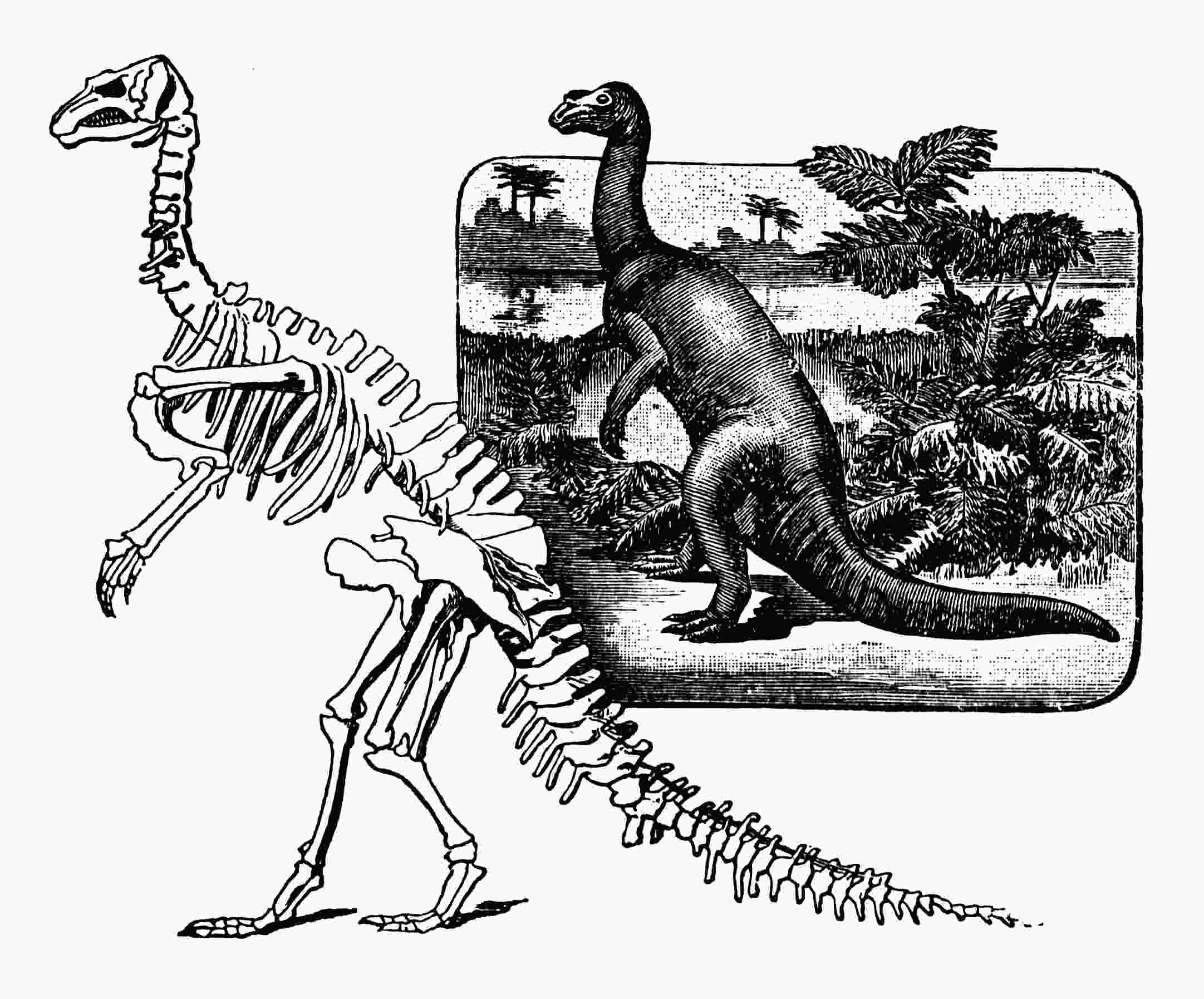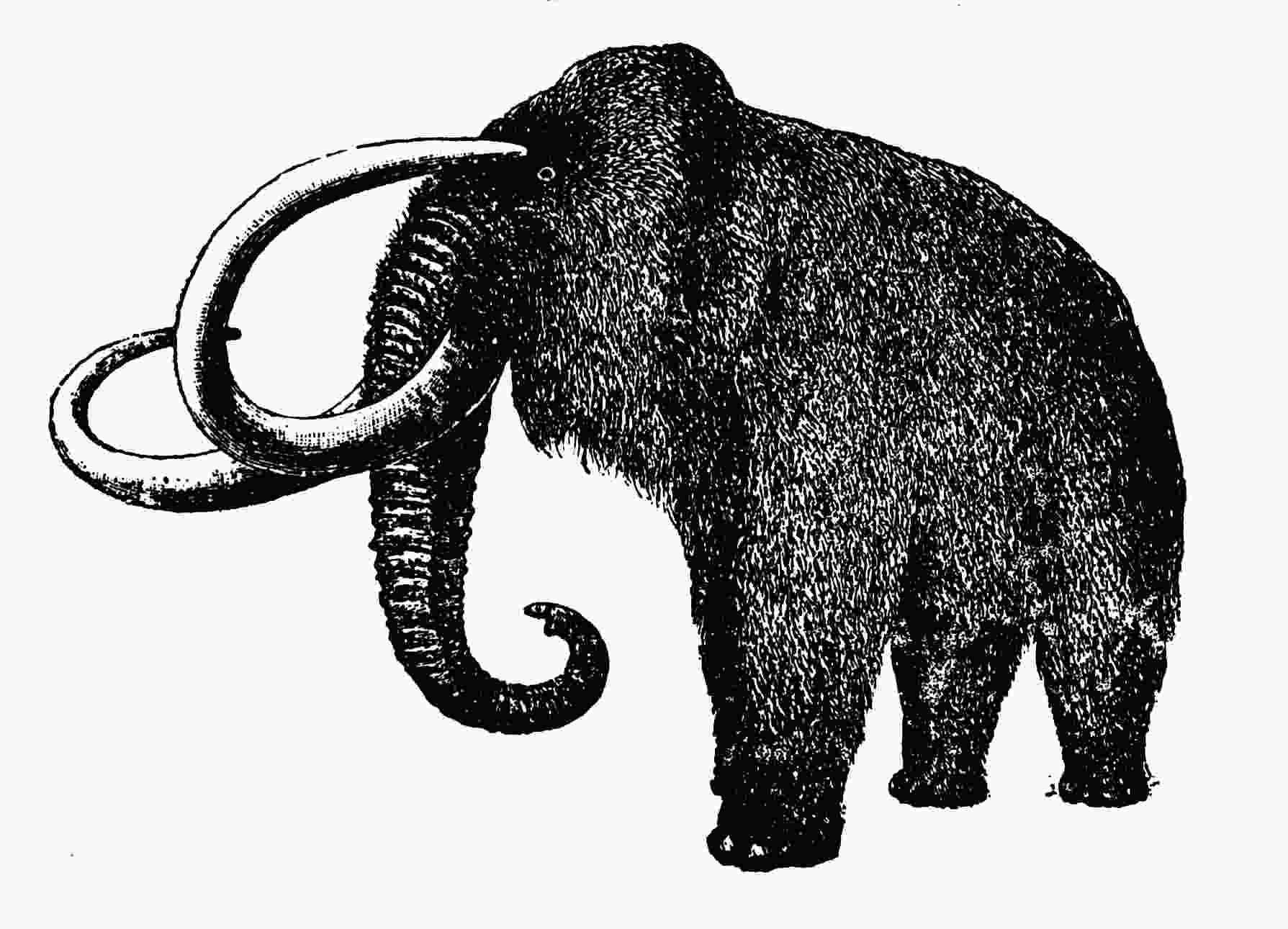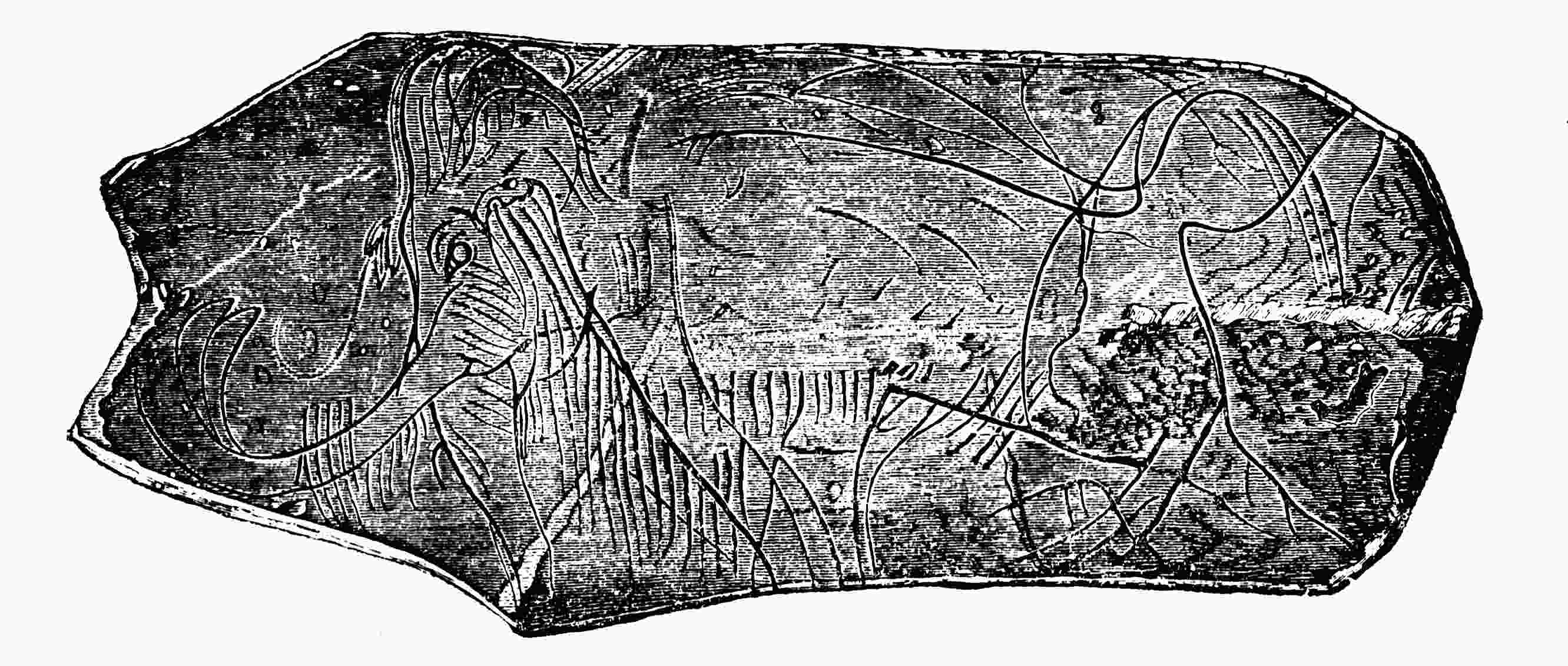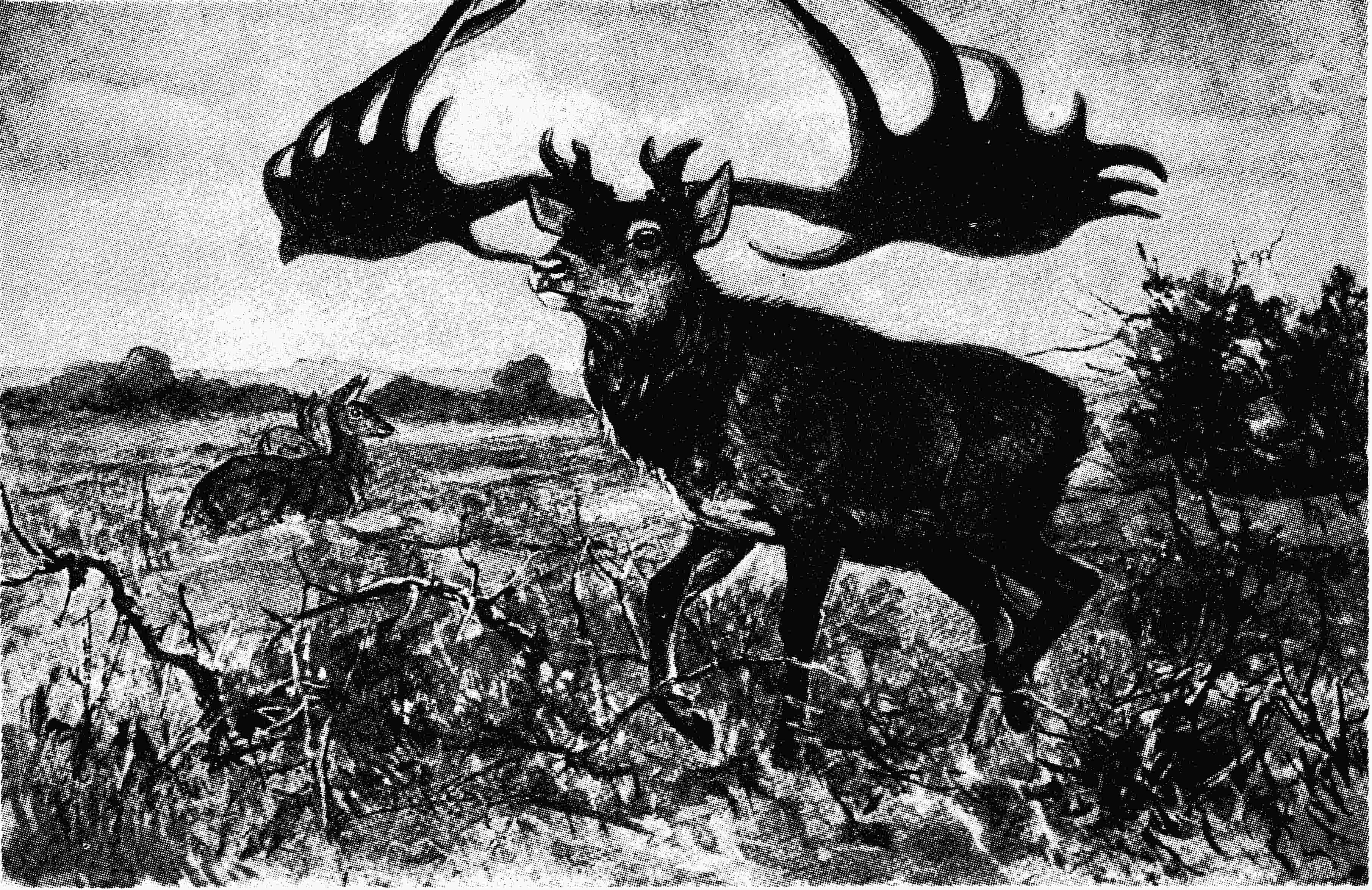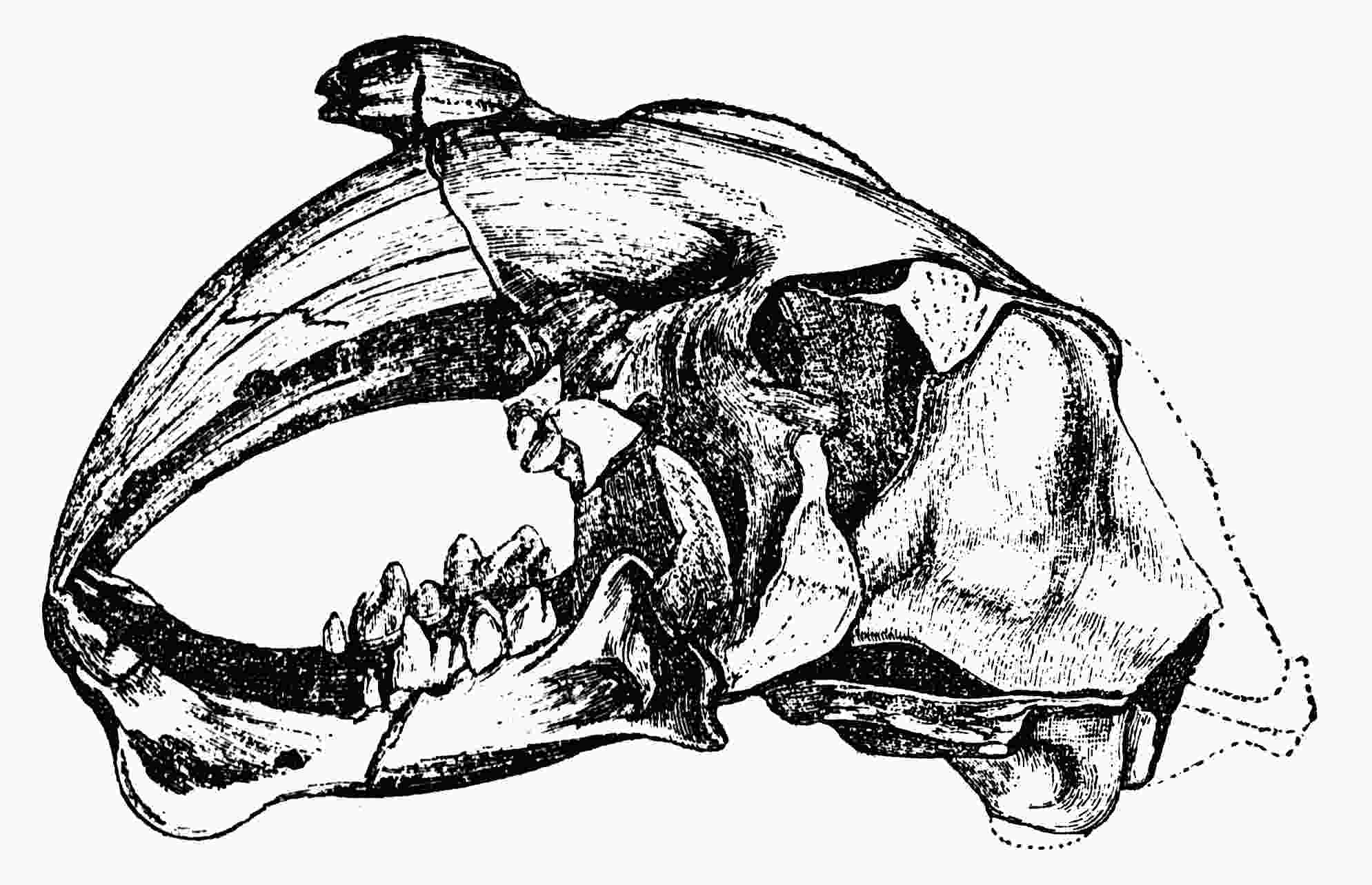長い
浮世に短い命、いっそ太く
暮そうと考える男もあれば、
如何に細くともただ長く長く生きながらえたいと思う
老爺もある。
恋人と
添われぬくらいならばむしろ死んだほうがましと、
若い
身体を汽車に
轢かせる
娘もあれば、
頽れ
果てた手足と
眼鼻も分らぬ顔とを
看板にして、道行く人の
情に
縋りながらなお生きんと
欲する
癩病の
躄もある。十人
十種に
相異なる
所行は、いづれも当人らの
相異なった人生
観に
基づくことで、
甲のなすことは
乙には
不思議に思われ、一方の決心
覚悟は他方からは全く
馬鹿馬鹿しく見える。
著者はかつて
或る有名な漢学の
老先生が、
眼も
鈍り、耳も聞こえず、教場へ出ても前列の
生徒にさえ
講義が分からぬほどに
耄碌しながら、他人に
長寿の
秘法を
尋ねられて、自分は
毎晩床についてから手と足と
腹と
腿とを
百遍ずつ
静かに
撫でると、
得意気に答えているのを
側から聞いて、
問う者をも、
答える者をも
愍然に思わざるを
得なかったが、これもやはり人生
観の
相異なったゆえであろう。かように人々によって人生
観のいちじるしく
異なるのは、もとより
先祖からの
遺伝により、
当人の
性質にもより、
過去の
経歴にもより、
現在の
境遇にもよることであろうが、その人の有する
知識の
如何も大いにあずかって力あることは
疑いない。しこうして、その
知識という中にも、生物学上の
知識のあるなしは人生
観の上にすこぶるいちじるしい
影響を
及ぼすものであることは、
著者の
固く
信ずるところである。
そもそも、生物学とは動物学と植物学との
総称であるゆえ、生物学
講話という表題を見て、読者はあるいは学校で用いる教科書を
敷衍したごときものかと思われるかも知れぬが、本書はけっして、さような
性質のものではない。本書はむしろ生物学の
範囲内からもっぱら人生
観に
相触れると考えられる
事項を
選み出し、これを
通俗的に
述べて生物学を
修めぬ
一般の読者の
参考に
供するのが
目的である。それゆえこれと
関係のやや少ない方面は全く
省略しておいた。
例えばこの
種類の虫の
翅には
斑点が一つよりないが、かの
種類の虫の
翅には
斑点が二つあると
述べるごとき
記載的の
分類学、ここの山にはこのような
獣がいる、かしこの海にはあのような魚がいるというごとき生物の地理
分布学、
甲の動物の
筋肉繊維には
横紋があるが、
乙の動物の
筋肉繊維には
横紋がないと
論ずるごとき
比較組織学等は、いっさい
略して
述べない。されば、本書はけっして生物学のすべての方面を平等に
残りなく
講述するものでないことを、まず
最初にことわっておかねばならぬ。
さて、人間も
一種の生物であるから、生物学を
修めた者から見ると人間の生活中に
現われる
各種の作業は、みなそれぞれ生物界にこれに
類似することまたはこれと
匹敵することが
必ずある。人間が生まれ死ぬごとくに他の生物も生まれて死ぬ。人間が
恋するごとくに他の生物も
恋する。人間に苦と楽とがあるごとくに他の生物にも苦と楽とがある。人間社会に
戦争や
同盟があるとおりに生物界にも
戦争や
同盟がある。しこうして人生をみるにあたってこれらと
比較して考えるのと、人間だけを
別に
離して他と
比較せずに考えるのとでは、
結論の大いに
異なるべきは言うを待たぬ。
芝居で同じ役者が同じ役をつとめても、
背景が
違えば見物人の感じも大いに
異なるのと同じ
理屈で、人生をみるにあたっても、何を
背景とするかによって、
結論もいちじるしく
異なるをまぬがれぬ。本書において今より
説こうとするところは、すなわちかかる
背景として役に立つべき
事項を生物学の中から
選り出してならべたものである。
願わくば読者は本書の
内容を
背景と見立てて、人間なるものを
舞台の上に
連れ来たって日々の
狂言を
演ぜしめ、自分は
棧敷から
眺めている心持ちになって
虚心平気に人生を
評価することを
試みられたい。
遊興の場、
愁歎の場、
仇討の
幕、
情死の
幕などが、それぞれ
適当な生物学
的の
背景の前で
演ぜられるときは、見物人に
如何に
異なった感じを
与えるであろうか。もしかくすることによっていくぶんかなりとも、人生の真
意義をよく
解したるごとき感じが読者に起こったならば、
著者は本書を
著わした
目的が
達せられたこととして
誠に
満足に思う
次第である。
人間と
普通の生物とを
比較して見ると、ささいな点ではもとより
無数の
相違があるが、その
生涯の
要点を
摘んで見ると、全く
一致しているということができる。少なくとも生まれて食うて
産んで死ぬということだけは、人間でも他の生物でもごうも
相違はない。動物のほうは人間と
相似ている点が多いゆえ、この事も明らかであるが、人間とは大いに
異なるごとくに見える植物でも、
理屈はやはり同様である。まず親木に実が生じ、
種が落ちて一本の
若木が生ずるのは、木が生まれたのである。それからその木が空中に
枝葉を広げて
炭酸ガスを
吸い、地中に根を
延ばして水と
灰分とを取るのは、すなわち食うているのである。かくてだんだん
成長して、花を
咲かせ、実を生じ、
種子を
散らせて、多くの子を
産み、
寿命が来ればついに死んでしまうのであるから、これまた生まれて食うて
産んで死ぬにほかならぬ。しこうして
一匹の動物一本の植物をとって言えば、その
生涯の中に生まれる時と
産む時とが
別にあるが、数代を
続けて考えると、生まれると
産むとは同じであって、
単に同一の
事件を親のほうからは
産むといい、子のほうからは生まれると言うているにすぎぬ。それゆえこれを一つとして数えると、生物の
生涯なるものは、食うて
産んで死ぬという
三箇条で
総括することができる。
かくのごとく、ただ食うて
産んで死ぬということだけは、どの生物でも
相一致するが、しからば、
如何に食うか、
如何に
産むか、
如何に死ぬかと
尋ねると、これは実に
種々様々であって、そこに生物学の面白みが
存するのである。
例えば食うと言うても、進んで食物を
求めるものもあれば、とどまって食物の来るのを待つものもある。
武力で相手に
打勝つものもあれば、だましてこれをおとしいれるものもある。同じ
餌を多数のものが
求める場合には
競争の起こるはもちろんであるが、
競争にあたっては、あるいは
筋肉の強いものが勝ち、あるいは
感覚の
鋭いものが勝ち、あるいは知力のすぐれたものが勝つ。中には他の生物の食い
残しを
求めて生活しているものもある。また食うほうにのみ
熱中していると、自身が他に食われるおそれがあるゆえ、安全に食うためには、一方に
防御を
怠ることはできぬ。しこうして
防御するにあたっても、主として
筋肉を用いるもの、
感覚によるもの、知力を
頼むものなど、おのおの
種類にしたごうて
相違がある。
餌を
攻めるにも、身を
護るにも、多数力をあわせることはすこぶる
有利であるが、かく集まってできた
団体中には、
敵を
亡ぼし終わるや
否や直ちに
獲物の分配についてはげしい
争いの起こるごとき一時
的の
集団もあり、またいつまでも真に
協力一致を
続ける
永久的の社会もある。次に
産むというほうについて見ても、
単に
卵を
産み
放すだけで、さらに後を
構わぬものもあれば、
産んでからこれを大切に
保護するものもある。
卵を長く
胎内にとどめて
幼児の形の十分に
備わつた後に
産むものもあれば、
産んだ後さらにこれを教育して
競争場裡に生活のできるまでに仕立てるものもある。
特に
雌をして
卵を
産ましめる前の
雌雄の間の
関係に
至っては実に
種々様々で、中には
奇想天外より落つるとでもいうべき思いがけぬ
習性を有するものも少なくない。また同じく死ぬと言うても、その仕方は色々あって、全身一時に死ぬものもあれば、一部だけが死んで
余は生き
残るものもあり、
瞬間に死ぬものもあれば、
極めて
緩慢に死ぬものもある。親の
死骸が子の
食糧となるものもあれば、兄が死なねば弟が助からぬものもある。また同じ
種類の
個体が
次第にことごとく死んでしまうて、
種族が全く
絶滅することもある。かように数えて見ると、生物の食いよう、
産みよう、死にようには、実に
千変万化の
相違があって、人間の食いよう、
産みよう、死にようは、ただその中の
一種にすぎぬ。何事でもその
本性を知ろうとするには、他物と
比較することが
必要で、これを
怠るととうてい正しい
解釈を
得られぬことが多い。
例えば地球は何かという問題に対して、ただ地球のみを調べたのでは、いつまですぎても
適当な答はできぬ。これに反して、他の遊星を調べ、その運動を
支配する
理法を
探り
求め、これに
照らし合わせて地球を
検査して見ると、はじめてその太陽
系に
属する
一小遊星であることが明らかに知れる。人間の生死に
関する問題のごときもおそらくこれと同様で、ただ人間のみについて考えていたのでは、いつまでも真の意味を
了解し
得べき
望みが少ないではなかろうか。
普通に人の知っている生物は、
必ず物を食うて生きている。何を食うか、
如何に食うか、いつ食うかは、それぞれ
異なるが、とにかく食うことは食う。小鳥
類のごとくに、一日でも
餌を
与えることを
忘れるとたちまち死んでしまうほどに、
絶えず食物を
要求するものもあれば、
蛇類のごとくに、一度十分に物を食えば、その後は
数箇月も食わずに平気でいるものもある。
蛭のごときは一回血を
吸いためると、
約二年は生きている。しかしその後はやはり食物を
要する。しからば、生まれてから死ぬまで少しも物を食わぬ生物はないかというと、そのようなものも全くないことはない。
例えば
輪虫類の
雄などはその一である。
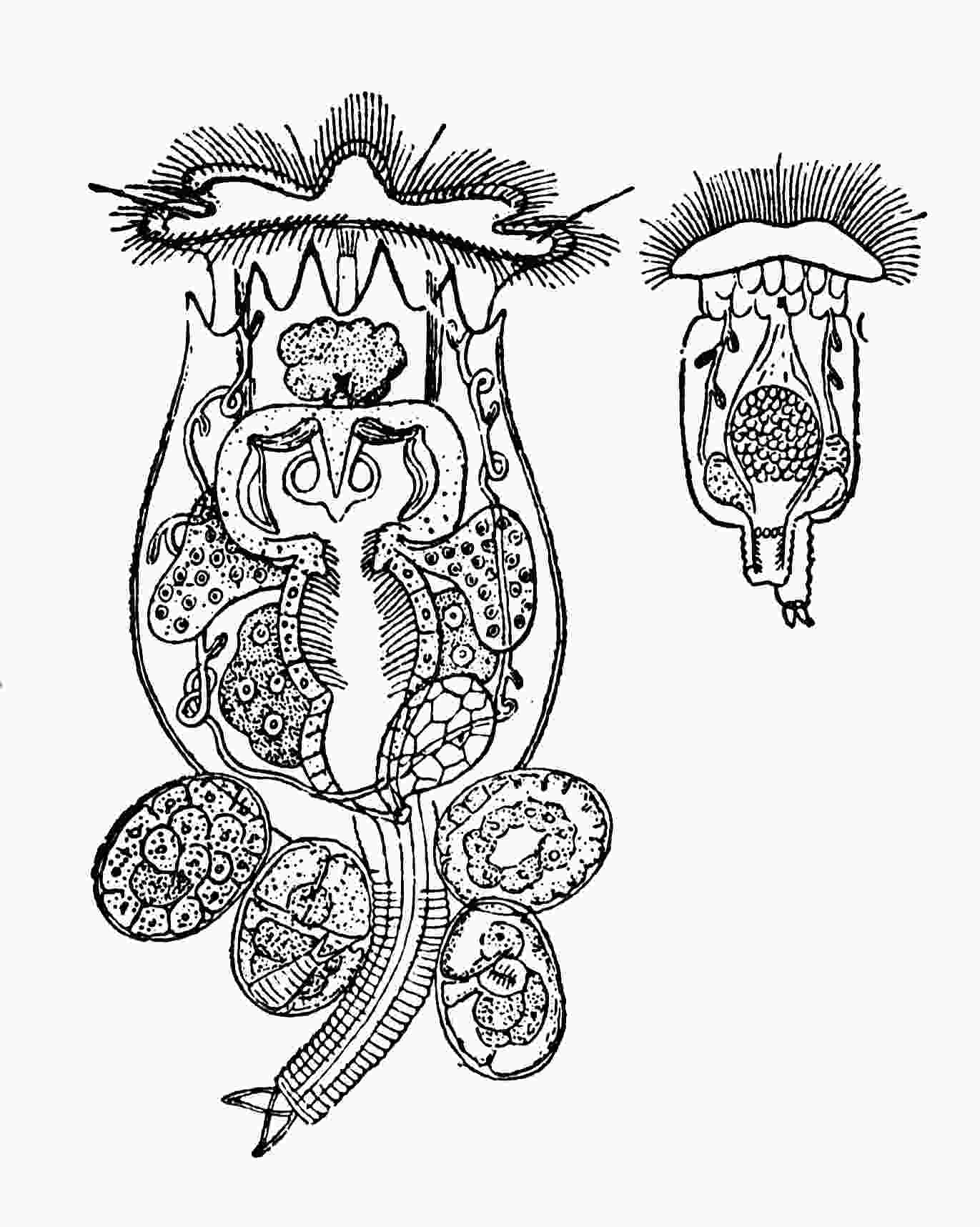 輪虫 雌(左) 雄(右)
輪虫
輪虫 雌(左) 雄(右)
輪虫というのは、
顕微鏡を用いねば見えぬほどのきわめて小さな虫であるため、いっこう世間の人に知られてはいないが、池や
沼の水草の間、ひさしの
樋の中などに、どこにもたくさんいる
普通なものである。その形は図に
示したとおりで、体の
前端にやや
円盤状の部分があり、その
周辺に
粗い毛が
並んで生え、つねにこれを
振り動かして水中に小さな
渦巻を起こし、
微細な食物を口へ流し入れる。これを
顕微鏡で見るとあたかも
車輪が回転しているごとくであるゆえ、学名も、
通俗名も、みな「
車輪を有する虫」という意味に名づけてある。ところが
不思議なことには池からこの虫を
採集して見ると、いずれも
雌ばかりで
雄はほとんど
一匹もいない。それゆえ昔はこの虫の
雄は学者の間にも知られなかった。しかしよく注意して調べると、
雄もときどき発見せられる。しかして
雄と
雌とを
比較して見ると、体の大きさも内部の
構造もいちじるしく
違い、
雄のほうははるかに小さく、かつ口もなければ
胃も
腸もなく、体の内部はほとんど
生殖器だけというてよろしいほどで、
卵から
孵って出ると、直ちに
忙しく水中を
游ぎ回って、
雌を
探し
求め、これに
出遇えばたちまち
交尾して
暫時の後には死に
失せるのである。すなわち
輪虫の
雄の
寿命は生まれてからわずかに数日にすぎぬが、その間に物を食うということはけっしてない。
条虫などは口も
腸胃もないが、他の動物の
腸内に住んでつねに
溶けた
滋養物に
漬かっていることゆえ、体の表面から食物が
浸み
込んで来るが、
輪虫の
雄はこれと
異なり、自由に水中を
游いでいるのであるから、真に
一生涯中に少しも物を食わぬ生物である。
しかしながらよく考えて見ると、
輪虫の
雄自身は
一生涯何も食わずに生活するが、かく食物なしに活動し
得るのは、生まれながら身体内に一定の
滋養分を
貯えているからである。
輪虫の
卵は
比較的に大きなものであって、中に
比較的に
多量の
滋養分を
含んでいるゆえ、
卵の内で
雄の身体ができるにあたって、その身体の内には
初めから
若干の
滋養分がある。
輪虫の
雄は、あたかも
満腹の
状態で
卵から
孵り、その
続く間だけ
生存して、しかる後に死に去るのであるから、これは全く食物を体内に
含ませて親が
産んでくれたおかげと言わねばならぬが、
卵の内の
滋養分はかつて親の食うた食物の中からこし取られたものゆえ、子が
一生涯食わずに生きていられるのは、実は親が子の分までも食うておいた
結果にすぎぬ。されば食わずに生活のできるということは、親がまえもって子に代わって食うておいた場合に
限ることであって、
一種類の生物が
絶対に食物なしに生活し
得るというごときことのないのは明らかである。
次に子を
産まぬ生物はないかと考えると、これにも
普通な
例がいくらかある。
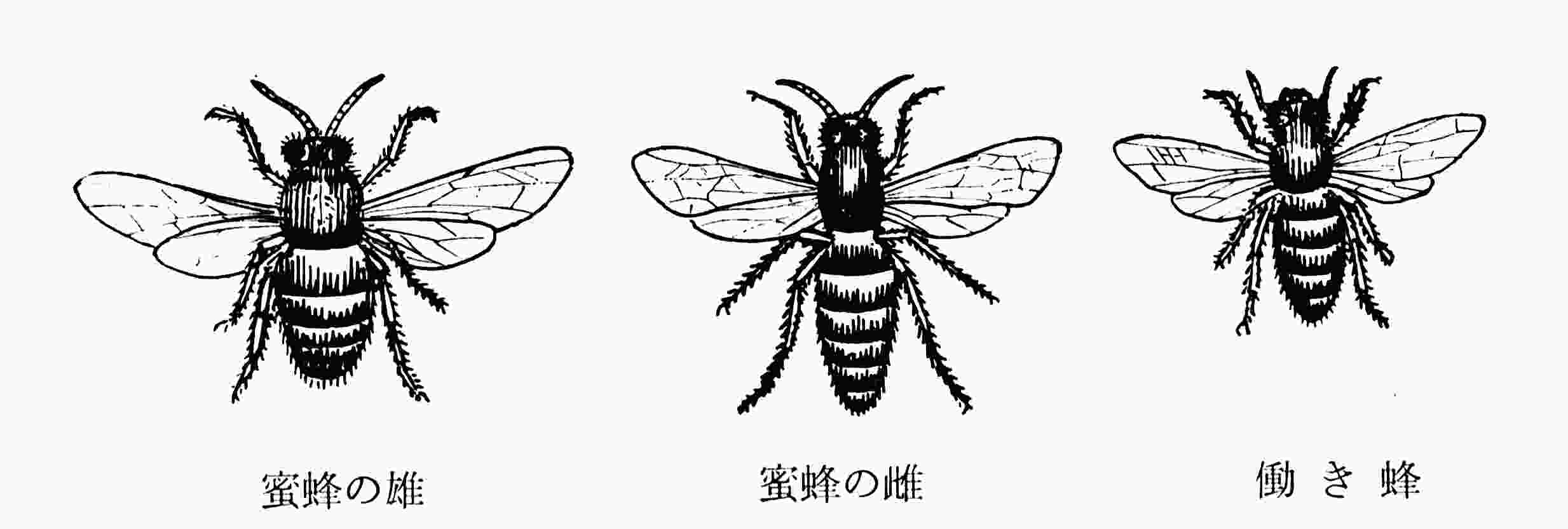 蜜蜂の雄 蜜蜂の雌 働き蜂
蜜蜂の雄 蜜蜂の雌 働き蜂
世人も知るとおり、
蜜蜂や
蟻の
類には
雄と
雌とのほかに
働き
蜂とか
働き
蟻とか名づけるものがあるが、これらは
一生涯他の
産んだ
子供を
養い育てるだけで、自身に子を
産むということは決してない。
蜜蜂でも
蟻でも多数集まって社会を
造る
昆虫であるが、その社会の大部分を
成すものは右の
働き
蜂または
働き
蟻であって、
雄と
雌とはいずれも実に少数にすぎず、
蜜蜂においては子を
産む
雌はただ女王と
称するもの
一匹よりほかにはない。しこうしてこの少数の
雌雄は子を
産むことを
専門の仕事とし、全社会のために
生殖の
働きを引き受けている。したがって食物を集めること、
敵の
攻撃を
防ぐこと、
巣を
造ること、子を育てることなどは、すべて
働き
蜂または
働き
蟻の役目となり、朝から
晩まで
非常に
忙しく
働いているゆえ、
通常人の
眼に
触れる
蜂や
蟻は、みな
働き
蜂働き
蟻のみである。しからば
働き
蜂、
働き
蟻なるものは
雌雄両性のほかに
一種特別の
性を有するかというと、けっしてさようではない。なぜかと言うに、
解剖によって体の内部の
構造を調べて見ると、小さいながら
卵巣も
輸卵管も明らかに
備えているから、たしかに
雌と見なすべきものである。ただこれらの
生殖器官はみなはなはだ小さくて
実際その
働きをなすに
適せぬというにすぎぬ。言を
換えれば
働き
蜂働き
蟻は
生殖器官の
退化した
雌である。これから考えて見ると、
蜜蜂や
蟻の
雌は、分業の
結果二種類の形に分かれ、一は
生殖器官が
特に
発達して、全社会のために
生殖の
働きを引き受けるに
適するものとなり、他は
生殖器官が
退化して
生殖の
働きができなくなり、その代わりに他の体部の
働きが進んで、食物を集めること、子を育てることなどは、十分にできるようになったものと見なさねばならぬ。
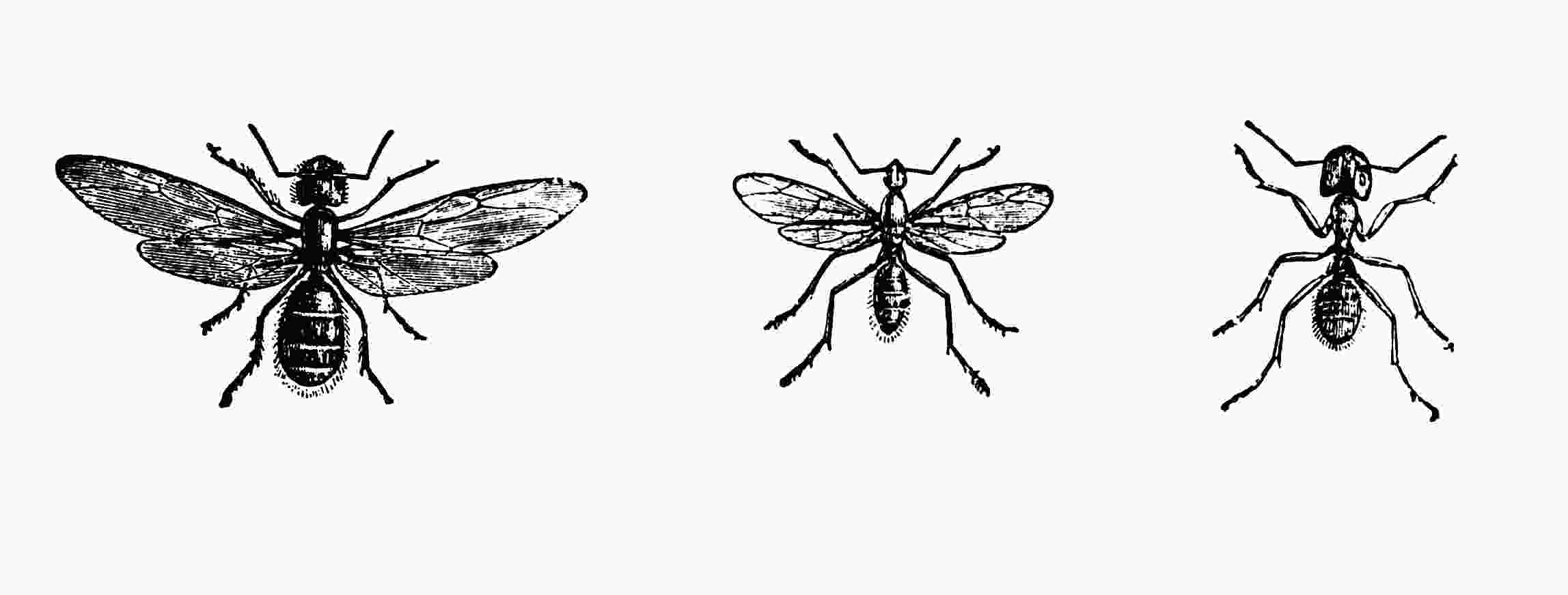 雄蟻 雌蟻 働き蟻
雄蟻 雌蟻 働き蟻
右のほかにもなお、一度も子を
産まずに
生涯を終わる生物は、人の
見慣れぬような
海産の下等動物にはたくさんに
例があるが、いずれも
団体を
造って
生存する
種類で、その中の
個体の間に分業が行なわれ、
栄養をつかさどるものと、
生殖の
働きをするものとの
別が生じたものである。かくのごとく
一個体をとって見ると、子を
産まずに
一生涯を終わるものはあえて
珍しくはないが、
種族全体として子を
産まなかったならば、その
種族はむろん一代
限りで
種切れとなるに定まっているゆえ、そのようなものは
実際にはけっしてない。生物でありながら、子を
産まぬものは、
必ず子を
産む役を
同僚に
譲って、自分はその他の仕事を引き受けている
個体に
限ることである。
「生あるものは
必ず死あり」とは昔から人の言うところであるが、
実際生物界に死なぬ生物はないかと
尋ねると、「死」という言葉の意味のとりようによっては、死なぬ生物がたしかにある。
長寿は
何人も
望むところ、死は何人も
恐れるところであると見えて、
不老不死の
仙薬の話はいつの世にも
絶えぬが、かような薬を用いずとも、元来死ぬことのない生物があると聞いたらこれを
羨ましがる人がたくさんあるかも知らぬ。まず
如何なるものが「死なぬ生物」と名づけられているかを
述べて見よう。
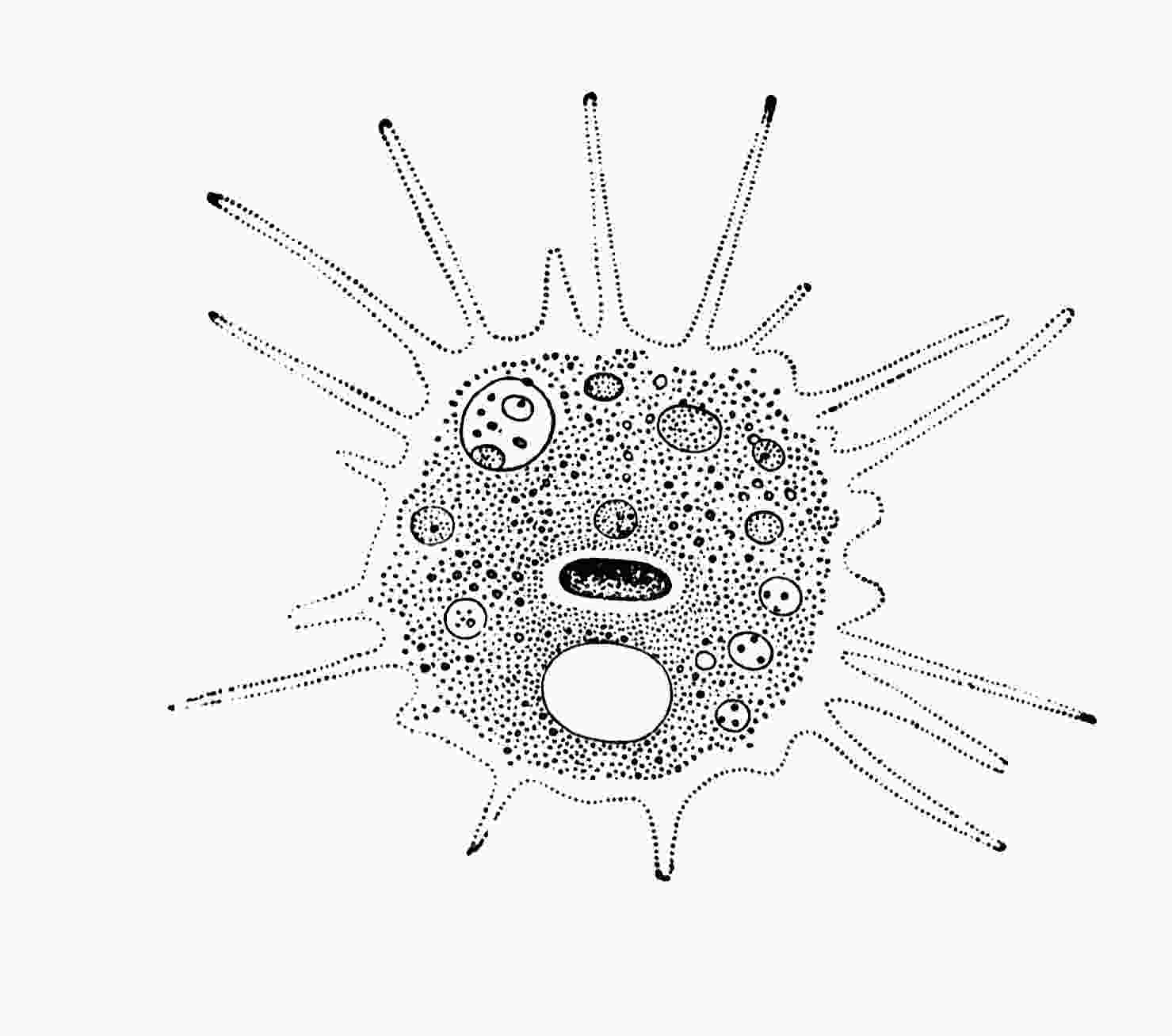 アメーバ
アメーバ
動物でも植物でも
顕微鏡で見なければ分からぬような
微細なものは、多くは全身がただ
一個の
細胞から
成っている。もっとも前に
述べた
輪虫などは
例外としてやや高等のものであるが、かかるものを
除けば、他はたいてい
構造のすこぶる
簡単なもので、その
最も
簡単なものに
至っては、あたかも
一滴の油か、
一粒の
飯のごとくで、手足もなければ、
臓腑もない。しばしば書物で引き合いに出される「アメーバ」という虫などもその
一例であるが、その他になお「ぞうりむし」、「つりがねむし」、「みどりむし」、「バクテリア」などはみなこの
類に
属する。
夜海水を光らせる夜光虫は、やや形が大きくて、
肉眼でも「数の子」の
粒のごとくに見え、風の
都合で海岸へ多数に
吹き
寄せられると、水が全体に
桃色に見えるほどになるが、これも
一匹の体はただ
一個の
細胞から
成っている。死なぬ生物と
称えられるのはかような
単細胞の生物である。
 夜光虫
夜光虫
この
類の生物は、
生殖の
方法がきわめて
簡単で、親の身体が二つに
割れて
二匹の子となるのであるゆえ、何代
経ても
死骸というものがない。
煮るとか、
干すとか、または
毒薬を
注ぐとかして、わざわざ
殺せばむろん
死骸が
残るが、
自然に
委せておいたのでは、
老耄の
結果死んで
遺骸を
残すというごときことはないから、もしも
死骸となることを「死ぬ」と名づけるならば、これらの生物はたしかに死なぬものである。
普通の生物では死ぬということと、
死骸を
残すということとは
常に同一であるゆえ、死ねば
必ず
死骸が
残るもののごとくに思うが、死ぬとは
個体としての
生存の
消滅することとも考えられるゆえ、この意味からいうと、
甲の虫が二分して
乙と
丙とになった時には、
甲の虫はすでに死んだと言えぬこともない。
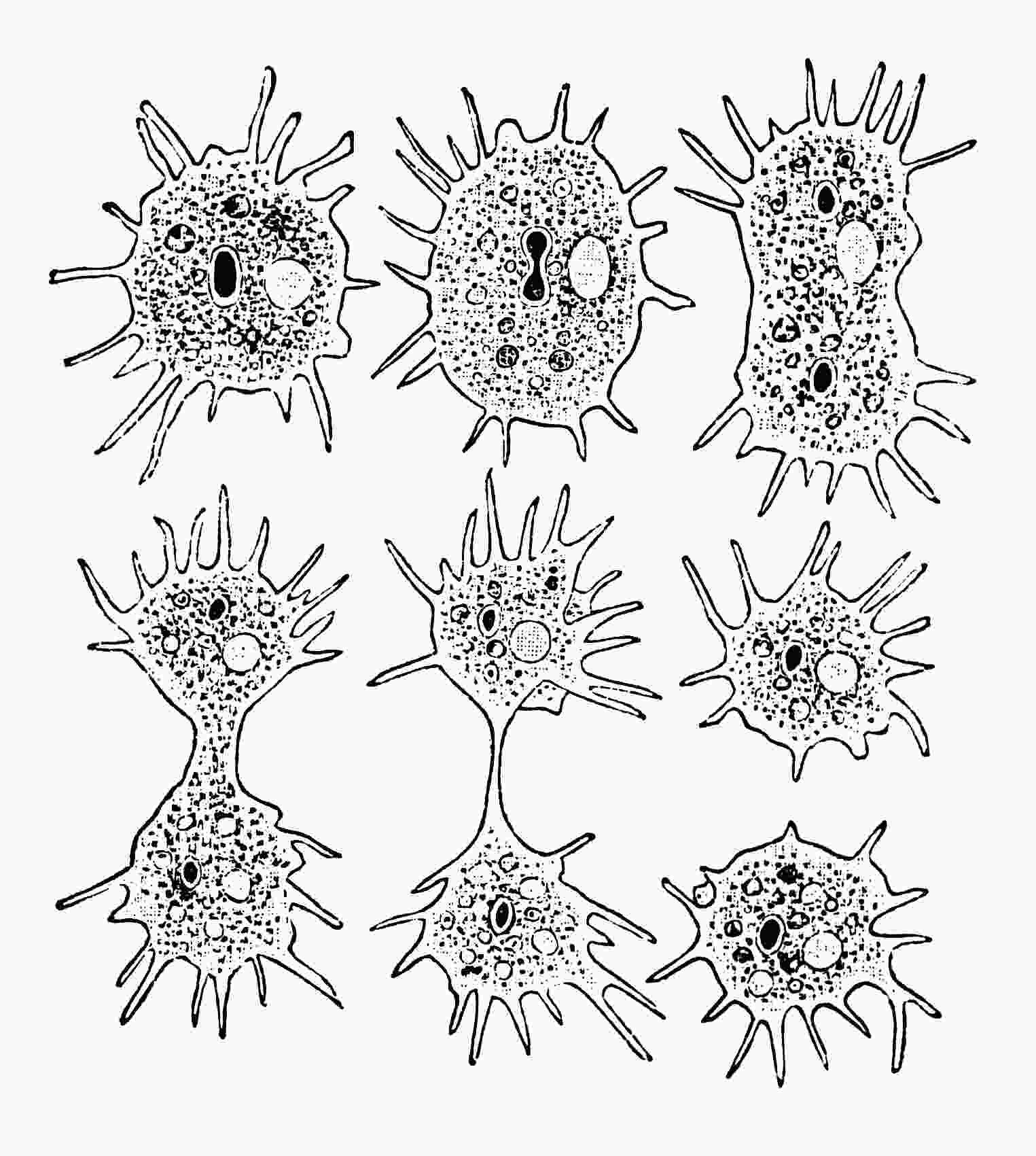 「アメーバ」の分裂
一例
「アメーバ」の分裂
一例として「アメーバ」
類の生活
状態を
述べて見ると、この虫は
淡水、海水または
湿地の中に住み、身体は
柔かくてあたかも
一滴の油のごとく、つねに定まった形はなくて流れるがごとくに
徐々と
匍い歩き、
微細な食物を
求めて身体のどこからでもこれを食い入れ、
滋養分を消化した後は、
滓を
置き去りにして
他処へ
匍うて行く。かくして少しずつ生長し、一定の大きさに
達すると体の
中程にくびれたところが生じ、
初めはまず
瓢蕈のごとき形と
成り、次にはくびれがだんだん細くなって、ついに
柔かい
餅を引きちぎるように切れて
二匹となってしまう。これはもと
一匹のものが
殖えて
二匹となるのであるから、たしかに
一種の
生殖には
違いないが、世人がつねに
見慣れている
生殖とは
異なり、
産んだ親の身体と生まれた子の身体との
区別がないゆえ、何代
経ても親が
老いて死ぬというごとき事が起こらず、したがって
死骸が生ずるということはけっしてない。さればもしも
死骸となることを死ぬと名づけるならば「アメーバ」はたしかに死なぬ生物である。しからば「アメーバ」は昔から今日まで同一の
個体が
生存し
続けているかといえば、もちろんけっしてさようではない。
一匹が分かれて
二匹となるごとに、前の
一匹の
生存は終わって新たな
二匹の
生存が始まるのであるから、
一個体としての
生存の
期限は、親が分かれて自身が生じたときから、自身が分かれて子となるまでのわずかに数十時間にすぎぬ。
さてかようなものを
捕えて、これは死ぬ生物であるとか、死なぬ生物であるとか
論ずるのは
畢竟言葉のたわむれで、その
原因は人間の言葉の
不十分なことに
存する。元来、人間の言葉は
日常の生活の用を
弁ずるためにできたもので、世が進み
経験が
増すにしたごうて
次第に
発達し来たったが、「死」という言葉のごときも、もと人間や犬、
猫の死をいい
現わすためにできたものゆえ、これと
異なった死にようをする生物にはそのままには当てはまらぬ。世の中には死なぬ生物があるといえば、
素人には
不思議に聞こえ、したがって世の注意を引いて
評判が高くなるが、
実際を見るとただ死にようが
違うというだけである。
従来の
不完全な言葉を用いて、生物を死ぬものと死なぬものとに分かち、「アメーバ」のごときものを、そのいずれに
属するかと
議論することは、ほとんど時間を
浪費するにすぎぬかとも思われるが、およそ
生殖によって
個体の数の
増加し行く生物ならば、
各個体には
必ず
生存に一定の
期限があって、同一の
個体が
無限に
生存するというごときことのないのはたしかである。
前に
述べたとおり、生物の
生涯は食うて
産んで死ぬという
三箇条に
約めてみることができるが、これだけはまずすべての生物に通じたことで、生物
以外には見られぬ。食わぬ生物、
産まぬ生物、死なぬ生物など、一見しては
例外のごとくに思われるものがないでもないが、これらもよく調べて見ると、けっして真に食わず
産まず死なぬわけではなく、ただ親がたくさんに食うておいてくれたゆえに、子は食うに
及ばぬとか、姉が
余分に
産んでくれるゆえに、妹は
産むに
及ばぬとかいうごとき分業の
結果にすぎぬ。また死ぬ死なぬは、
単に言葉の
争いで、
個体の
生存に一定の
期限のあることは、死なぬと
称せられる生物でも他に
比して少しも
変わりはない。されば、生物とは何かという問いに対しては、
森羅万象の中で食うて
産んで死ぬものをかく名づけると答えてたいてい
差支えはなかろう。
しからばいわゆる
無生物にはこれに
類することは全くないかというと、その返答は少々
困難である。
普通の石や金が食いもせず
産みもせぬことは
明瞭であるが、
鉱物の
結晶が
次第に大きくなるのは、外から
同質の分子をとって自分の身体を
増すのであるから、いくぶんか物を食うて生長するのに
似ている。また
一個の
結晶が
破れて
二片となった後に、
各片の
傷が
癒えて
二個の
完全な
結晶となる場合のごときは、
如何にも
或る
種類の
生殖法に
似ている。しかしながらこれらの
例ではいずれも
初めから
同質の分子が表面に
付著するだけで、前からあった部分は
旧のままで少しも
変化せぬゆえ、もとより生物が物を食い子を
産むのとは大いに
違う。生物が物を食うのは、自分と
違うたものを食うて自分と同じものとする。
例えば、牛に食われた草は
変じて牛の身体となり、
鯉に食われた
蚯蚓は
変じて
鯉の身体となるが、かかることは
無生物では
容易に見いだせない。それゆえちょっと考えると、この事の
有無をもって明らかに生物と
無生物との
区別ができるようであるが、よく調べて見ると、
無機化合物の中にも多少これに
類することを行なうものがあるから、
結局生物と
無生物の間には
判然たる
境は定められぬことになる。また一方
理屈から考えて見ても
判然たる
境のないのが
当然である。
元来、生物の身体は
如何なる
物質から
成っているかと
分析して見ると、植物でも動物でもみな、
炭素、
水素、
酸素、
窒素などというきわめて
普通にありふれた
元素のみからできていて、けっして生物のみにあって
無生物には見いだされぬというごとき
特殊の
成分はない。これらの
元素は水や空気や土の中にほとんど
無限に
存在するもので、これが植物に
吸われて
暫時植物の体となり、次に動物に食われて
暫時動物の体となり、動物が死ねばさらに
分解して
旧の水、空気、土に帰って
再び植物に
吸われる。されば今
仮に
炭素か
窒素かの
一分子の
行衛を追うて進むとすれば、
或る時は生物となり、
或る時は
無生物となってつねに
循環する。しこうして生物から
無生物になるときにも、
無生物から生物になるときにも、けっして
突然変化するわけではなく、
無数の細かい
階段を
経て
漸々一歩ずつ
変化するのであるから、とうていここまでが
無生物でここから先が生物であるというごとき
判然した
境のあるはずがない。これらについては次の章と
終の章とでさらに
述べるゆえ、ここには
略するが、
自然界における生物と
無生物との間にはけっして線をもって区画することのできるような明らかな
境はなく、あたかも夜が明けて昼となり、日が
暮れて夜となるごとくに
移り行くものゆえ、生命の
定義なるものを考え出そうとすると
必ず
失敗に終わる。スペンサーの
著わした『生物学の原理』という書物の中には、
哲学者流の
論法で「生活の
現象とは
内的の
関係が
外的の
関係に
絶えず
適応して行くことである」との
定義が
掲げてあるが、これは
様々に考えた
末にできあがった
定義が、生物にあてはまるほかに、空にある雲にもあてはまるので、さらに雲を
除外するように
訂正して
得たところの
最後の
定義である。その
詳しい
説明は
暗記してもおらず、またここに
掲げる
必要もないゆえ
略するが、
著者のごとき
哲学者にあらざる者から見ると、かかる
定義は
単に言葉の使い分けの
巧みなる見本として面白いのみで、真の
知識としては何の
価値もないように思われた。本書においては、生物とは何ぞやという問いに対して、生命の
定義をもって答えるごときことをせず、ただ生物は食うて
産んで死ぬという事実だけを
認めて、今よりこれについて少しく
詳細に
述べて見よう。これだけの事実は生物の
九割九分以上には
適し、
無生物の
九割九分以上には
適せぬものゆえ、いわゆる
定義なるものよりはよほど
確かである。
さて生物は
如何に食い
如何に
産み
如何に死ぬかを
述べる前に、一通り生命の起こりについて
説いておく
必要がある。すでにでき上がっている生物の生活
状態を
論ずるにあたっては、それが
初め
如何にして生じたものであっても
構わぬように思われるが、
事柄によってはその生じた起こりを考えぬと
誤りにおちいりやすいこともあり、
特に死について
論ずる場合のごときは、けっして生の
起源を
度外視するわけにはゆかぬ。しこうして生命の起こりという中には
種々の問題が
含まれてある。
例えば今、目の前にある生物の
各個体は
如何にして起こったかという問題もあれば、その生物
個体の
属する
種族は
如何にして起こったかという問題もあり、さらにさかのぼれば、いったい地球上の生物は
最初如何にして生じたかという問題も
解かねばならぬ。また生物の身体を
成せる生きた
物質は日々取り入れる食物が
変じて生ずるほかに
途はないが、死んだ食物が
如何に
変化して生きた
組織となるか、
熱や運動は
原因なしにはけっして生ぜぬものであるが、生物の日々
現わす運動や
熱はそもそもどこにその
原因があるかというような問題も
自然に生ずる。これらはいずれもなかなかの大問題であるが、その中には今日の
知識をもってやや
確かな
解決のできるものと、ほとんど何の返答もできぬほどの
困難なものとがある。
例えば生物の
各個体は
如何にして起こったかというのは発生学上の問題で、これはすでに研究も進んでいるゆえ大体においては
誤りのない答えをすることができよう。また、生物の
各種族は
如何にして起こったかということは生物
進化論の
説くところで、今日においても
詳細の点に
関してはなお学者間に
議論はあるが、
大要だけはすでに
確定したものと見なして
差支えはなかろう。これに反して、地球上には
初め
如何にして生物が生じたかという問題は
実験で
証明することもできず、
遺物から
推察するわけにもゆかず、ただ
想像によるのほかはないゆえ、これまでずいぶん
出放題と思われるような
仮説さえも
真面目に
唱えられたことがあり、今日といえどもいまだ
確かな返答をすることはできぬ。次に生物の体内における
物質の
変遷や力の
転換はいわゆる生物化学および生物物理学の研究するところで、近来はそのための
専門雑誌もでき、
報告の数から見るとすこぶる
目醒しい進歩をした。
一昨々年の秋、
英国理学
奨励会の
席上でシェーフェルという生理学者が生命の起こりについて
演説したのも、生物化学の進歩に
基づいたことであったが、この
演説はロイターから世界
各国へ
電報で知らせたゆえ、「生命
人造論」などという勝手な見出しで新聞紙に
掲げられ、わが国でも一時
評判になった。いまだ
解からぬほうを見ると、実になお
前途遼遠の感があるが、今日までの研究の
結果、一歩ずつこの問題の
解決の方向に進み来たったことは
疑いない。本章においては、
以上の
諸問題について
極めて
簡単に
述べて、
各種生物の生活
状態を
論ずる
前置きとしておく。
一人ずつの人間、
一匹ずつの犬や
猫が、
如何にして生じたかという問いは、前に
掲げた問題の中では一番答えやすいものである。すなわちまず親があり、親の
生殖の
働きによって新たに生じたものであると答えることができる。犬、
猫のごとく
胎生するもの、
鶏、
家鴨のごとく
卵生するものの
区別はあるが、
常に人の
見慣れている高等動物では、子が
必ず親から生まれることはいずれの場合にも
極めて
明瞭である。しかし少しく下等の動物になると、
卵や
幼虫がすこぶる小さいために
容易に見えず、その
結果としてどの子がどの親から生まれたか少しもわからぬことが
珍しくない。昔の
草本の書物を見ると、生物の生ずるには
胎生、
卵生、
化生、
湿生の四とおりのでき方があると書いてあるが、
胎生と
卵生とは
別に
説明にもおよばぬとして、
化生とは
如何なることかというと、これは
無生物もしくは
他種の生物から
突然変化して生ずるのであって、
腐草化して
螢となるとか、
雀海中に入って
蛤となるとかいうのがその
例である。山の
芋が
鰻になるとか
鰌が「いもり」になるとか「けら」が「よもぎ」になるとかいうごとき
伝説は、どこの国にもあって
一般に
信ぜられていた。また
湿生というのはなんらの
種もなしに、ただ
湿気のある所に
自然に生ずるので、
俗話で「
湧く」というのがすなわちそれである。
例えば古い肉に
蛆が
湧いたとか、新しい
掘に
鰻が
湧いたとか、
腹の中に
蛔虫が
湧いたとかいう
類が、みなこれに
属する。さてかような
化生とか
湿生とかによって、生物のできることは
実際にあるものであろうか。
実物について
実際に調べて見ると、昔から
化生とか
湿生とかとなえ来たったものはことごとく
観察の
誤りで、
無生物からある
種類の生物が
突然生じたり、
甲種の生物が
突然変じて
乙種の生物となったりすることはけっしてない。
 ひとで
ひとで
海岸地方では
漁夫がしきりに「ひとで」が貝を
産むと
主張することがあるが、その理由を聞いて見ると、ただ「ひとで」の
腹の中にはいつでも
必ず小さな貝があるというにすぎぬ。「ひとで」は主として貝を食うもので、小さな貝ならばこれを
丸呑みにするゆえ、その
腹の中に
貝殻のあることはもとより
当然であるが、
漁夫はそのようなことにはかまわず
相変らず「ひとで」は貝を
産むものと思い
込んでいる。田の
籾が小
蝦になるという地方もあるがこれも同様な
誤りである。また
針金虫といって長さ
二尺(注:60cm)
以上にもなる
実際針金のようにきわめて細長い虫があるが、これを馬の
尾の長い毛が水中に落ちて
変じたものと
信じているところがある。おそらく細さと長さとから考えて、馬の
尾の毛よりほかにこれに
似た物はないと定めてかく
信ずるのであろうが、この虫の
幼虫は「かまきり」の
腹の中に
寄生している細長い虫で、
子供らは「
元結」と名づけてよく知っている。
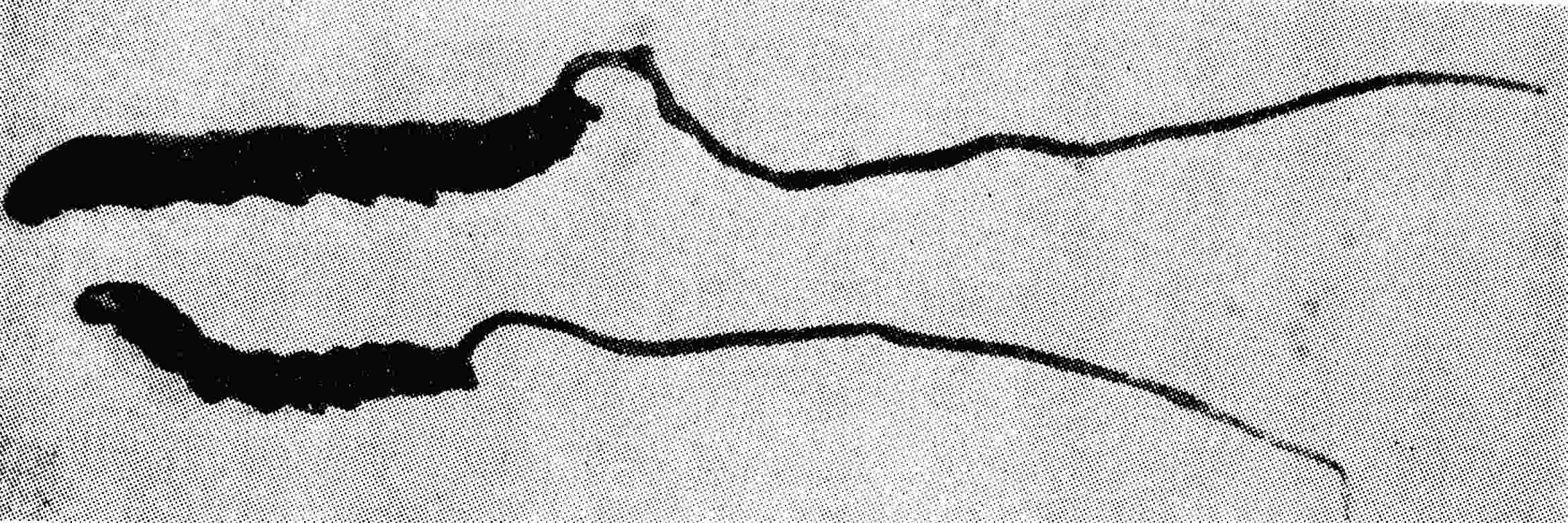 冬虫夏草
田圃
冬虫夏草
田圃道などを
散歩するとしばしば
昆虫が植物に
変じかかったかと思われるものを見つけることがある。これは
冬虫夏草といって、昔の書物には冬は虫になり夏は草になるなどと書いてあるが、実は「けら」、「いなご」、「せみ」などの身体に
菌が
付着し、虫の体から
汁を
吸うて
成長して
幹を
延ばしたものにすぎぬ。「いもり」は
鰌から
変じて生ずるという地方があるが、これはおそらく「いもり」の
幼児が
極めて
鰌の子に
似ているところから起こった
誤りであろう。かくのごとく、
従来化生と思われたものはていねいに調べて見るとことごとく
観察の
誤りであって、
甲種の生物が
突然変じて
乙種の生物を生ずるという
確かな
例は今日のところでは一つもない。
また
湿生というほうもこれと同様で、
如何に
湿っていても今まで何もなかった所へ親なしに子だけが
偶然生ずるというごときことはけっしてない。古い肉に
蛆が生ずるのは
蠅が
飛んで来て
卵を
産み
付けるからであって、もし肉を目のこまかい
網で
覆うておいたならば、いつまでたっても決して
蛆は生ぜぬ。
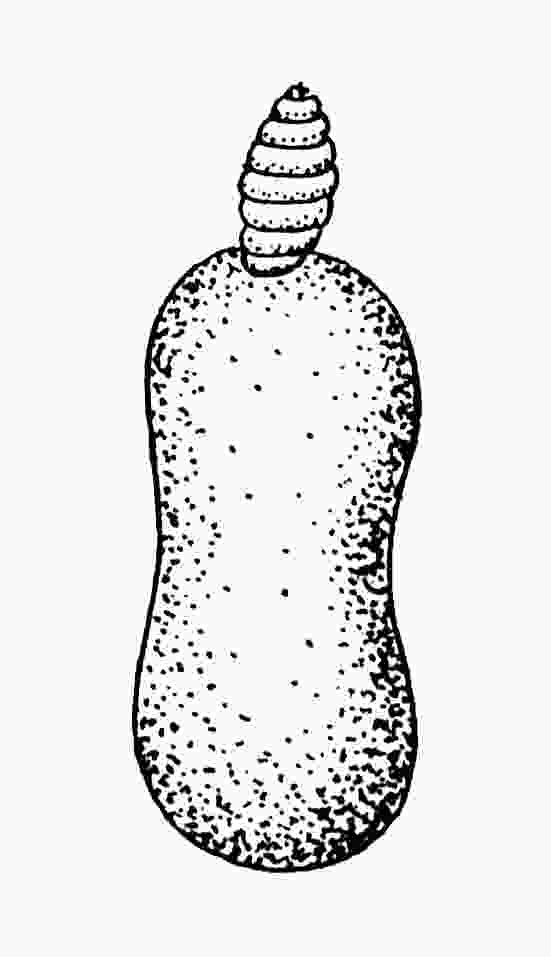 蚕の繭より蛆のはい出すさま
蚕
蚕の繭より蛆のはい出すさま
蚕を
飼うて見ると
往々繭に小さな
孔を
穿けて
蛆がはい出すことがあるが、これも
桑の葉の
裏に
蠅が
卵を
産み
付けておいたのを
蚕が食うゆえに、その体内に生じたものである。人間の
腹の中に
蛔虫や
条虫が生ずるのも
理屈は全く同様で、
極めて小さな
卵か
幼虫かをいつのまにか知らずに食ったゆえ、それが
腹の中で
成長して大きな虫となるのである。中には
微細な
幼虫が人間の
皮膚を
穿って体内に入り
込んで来るものもある。これらの場合には、
卵も
幼虫もすこぶる
微細であるゆえよほど
詳しく調べぬと、いつどこからはいったかわからず、したがって世人は
自然に
腹の中で
湧いたもののごとくに思うている。コップにいっぱいの
清水を入れ、その中に
藁を少し
漬けておき、数日の後に
顕微鏡でその水を見ると、実に
無数の小さな虫が
游いでいて、
一滴の中に何百
匹も何千
匹も数えることができるが、
誰もこの虫をわざわざ入れた
覚えはないゆえ、水の中で
自然に生じたもののごとくに考えるのも
無理ではない。しかしながらかような
微細な虫にもみなそれぞれ親があって、決して
偶然に生ずるものではない。その
証拠には
初め
藁を
漬けた水を一度
煮立てて、その中にある虫の
種をことごとく
殺してしまい、次にこれを
密閉して外から虫の
種の
紛れ
込んで来ることのないように
防いでおくと、いつまで待っても決して虫は生ぜぬ。
藁を
漬けた水の中に
自然に虫が
湧くか
湧かぬかというごときことは、ちょっと考えるといずれでもよろしいようで、かかる問題に
実験研究を重ねるのは、全く
好事家の
慰めにすぎぬごとくに思われたが、いったんその研究の
結果、生物は決して
種なしには生ぜぬとのことが
確かになった後は、直ちにこれが広く
応用せられるにいたった。
例えば今日もっとも
便利な食物
貯蔵法は
鑵詰であるが、これは人の知るとおり、まず
鑵に入れた食物を
熱してその中の
黴菌を
殺し、次にこれを
密閉して他から
黴菌の
紛れ
込むのを
防ぐのであるから、全く
上述の学理を
応用したものである。また外科医学が進歩して、思いきった大
手術ができるようになったのは、一つは
消毒法の
完全になった
結果であるが、
傷口にも
繃帯にも医者の手にも
器械にも、決して
黴菌の
付かぬような
工夫のできたのは、みな
以上の学理の
応用にほかならぬことである。もし生物が親なしに
偶然生ずるものならば、
密閉した
鑵の内にも
自然に
黴菌が生じて食物を
腐らせることもあり
得べく、また
如何に
傷口や
繃帯を
消毒しておいても、そこへ
化膿菌が発生して、
傷が
自然に
膿み始めることがあり
得べきはずであるに、そのようなことが
実際にないのは、
如何に
微細な生物でも決して
種なしには生ぜぬという
証拠である。
要するに、
一匹ずつの生物
個体の生ずるには
必ずまずその親がなければならぬ。人間や、犬、
猫、馬、牛のごとき大きなものはもちろんのこと、
一滴の水の中に数百も数千もいるような
微細な
黴菌といえども、親なしに
自然にわいて生ずるごときことは決してない。しかしてその親なるものは
必ずその生物と
同種同属のものであって、けっして
従来言い
伝えられたごとくに、
甲種の生物が
突然乙種の生物に
変化するというごときことはない。生物
個体の起こりを一言で言えば、
如何なる
種類のものでも
必ずまずこれと
同種の生物が
生存し、そのものの
生殖によって
初めて生ずるのである。
さて生物の
各個体はみなそれと
同種の親から
産まれ生じたものとすれば、何代前までさかのぼって考えても、今日世界に
生存しているだけの生物の
種族が、そのころにもあったわけになるが、もしさようとすれば今日知られている数十万
種の生物はいずれも天地
開闢の
初めから
未来永劫少しも
変化せぬものであろうか、それともまた長い間には少しずつ
変化して、昔の
先祖と今の
子孫との間には、いくぶんかの
相違があるのではなかろうかとの問題が
是非とも起こらざるを
得ない。すなわち生物の
各種族は
如何にして起こったものであるかとの問題が生ずるが、この問いに答えるのは生物
進化論である。しこうして
進化論はそれだけでも一つの
大論で、かつそのためには
別に
適当な書物もあることゆえ、ここには
詳しいことは
略して、
単に
要点だけを短く書くにとどめる。
昔地球上に住んでいた生物が今日のものと同じであったか
否かは、古い
地層から
掘り出された化石を調べて見れば大体はわかることである。今日
地質学者は
地層の生じた時代をその新古によっていくつかに
区別するが、
各時代の
地層から出た化石を
比較して見ると、もっとも古いところから今日まで同一
種類の生物の化石が引き
続いて出るという
例は一つもない。時代が
違えば化石も多くは
異なって、今を去ることの遠ければ遠いほどその時代の
地層から出る化石は、
我らの
見慣れている今日の生物とはいちじるしく
異なっている。さればだいたいにおいては地球上の生物の
種類は時の
移りゆくとともに、
順次変遷し来たったものであるということは
争われぬ事実である。
また今日生きている生物の身体を
解剖し
比較して見ても、その
卵から発育する
状態を調べて見ても、生物
各種は
次第に
変遷して今日の
姿に
達したものであると見なさねば、とうてい
説明のできぬような事実を
無数に発見する。一々の
例をあげることは
略するが、
兎や
鼠では十分に
働いている
上顎の前歯が、牛羊では
胎児のときに一度生じて
産まれぬ前にまた消え
失せることや、
魚類では
生涯開いている
鰓の
孔が人間や
鶏の発生の
途中にも、形だけ一度はできて後にたちまちなくなること、もしくは
游ぐための
鯨の
鰭も、
飛ぶための
蝙蝠の
翼も、
樹に登るための
猿の手も、地を
掘るための「もぐら」の前足も、
骨骼にすると根本の仕組みが全く
相一致することなどを見ると、
如何に考えても生物の
各種が
最初から
互いに
無関係に生じて、そのまま少しも
変わらずに今日まで引き
続き来たったものとは思われぬ。なお生物
各種の地理上の
分布のありさま、または
各種相互の
関係などを調べて見ると、
如何なる
種類でも長い時代の間に
漸々変化して、今日見るとおりのものとなったと
結論するほかに
途はない。
古生物学、
比較解剖学、
比較発生学、生物地理学等の研究の
結果を
総合して、その
結論を
約めて言うと、およそ生物の
各種はけっして
最初から今日のとおりのものができたのではなく、その始めは
如何なるものであったかは知れぬが、長い間に
漸々変化して
現在見るごときものとなったのである。しこうして、
変化するにあたっては
常に少しずつその
種族の生活に
適するように
変じ、だいたいにおいては身体の
構造は
簡単より
複雑に、下等より高等に進み来たったのである。もっともいったん
複雑な
構造を持った高等の生物が、さらに
簡単な下等のものに
退化したと思われる
例もあるが、これはいずれも
特別の場合で、
寄生虫や
固著生活を
営む生物のごとくに、体の
構造が
簡単であるほうが、その
種類の生活に
特に
都合のよろしいときに
限られる。また今日
数種に分かれている生物でも、その昔にさかのぼると
共同の
先祖から起こったらしく思われることがすこぶる多い。世人の
飼養する動物、
栽培する植物にはほとんど
無数にその
実例があるが、野生の動植物においてもおそらくこれと同様で、
初め
一種のものも後には
子孫の中に
種々体形
性質などの
相異なったものが生じて、ついに多くの
種類に分かれたのであろう。されば全体に通じていえば、生物なるものは昔より今日に
至るまでの間に
常に
一種より
数種に分かれ、
簡単より
複雑に進み来たったものと見なすことができる。しこうして、この考えを先から先へと
推し進めると、ついに地球上に
初めて生じた生物はおそらくただ
一種であって、かつもっとも
構造の
簡単な下等のものであったに
違いないとの
結論に
達するが、これは
実際如何であったかは、もちろん
確かな
証拠をあげて
論ずることはできぬ。生物の
各種族は
如何にして生じたものであるかという問いに対して、
進化論は
一応の
確かな答えはできるが、そもそも生物なるものは
初め
如何にして生じたものであるかと、さらにその先の問題を出せば、これに対しては事実に
基づいた
確かな返答はできぬ。人間と
猿とは
共同の
祖先から起こったとか、
哺乳類はすべて
初めは「カンガルー」などのごとき
有袋類であったらしいとかいうごとき、
比較的近代に
属することはずいぶん
確かに知ることができるが、時代が遠ざかれば遠ざかるほど
我々の
知識はあいまいになって、もっとも古い時代までさかのぼると何もわからなくなる。これはわが国の
歴史でも
明治時代のことならば
相応に
詳しくわかるが、神代は
'藐焉として
測度すべからざると同じ
理屈である。
かように生物の
個体の起こりと
種族の起こりとについては、ある
程度まで
確かな答えができるが、そもそも生物なるものは
最初如何にして生じたものであるかとの問いに対しては、今日のところ、学問上
確かと見なせる答えはない。しかし答えのできぬところを何とか答えたいのが人間の
知的要求であると見えて、今まで
種々様々の
想像説が持ち出された。その中には
初めから相手にするに足らぬと思われるものもあれば、また
比較的に
無理の少ない
穏当な
説と思われるものもある。地球は
初め
熱したガスの
塊で、次には
熔けた岩の
塊となり、その後
段々冷却して今日のありさまになったものであろうとは、天文学上
確からしい
説であるが、これから考えると、地球の表面には
最初から生物があったわけではなく、地面がさめて生物に
適する
状態になってから生物が
現われたものに
違いない。しからばいつごろ
如何なる生物が
初めて生じたかと
尋ねると、前に言うたとおり
想像説をもって答えるのほかにしかたはない。
或る人は地球上の生物の
先祖は、流星の
破片にでも
付著して天から
降って来たのであろうと
説いたが、これなどは
如何にも真らしからぬのみならず、
仮に真としても流星についていた生物は
如何にして生じたかという問いがさらに起こるゆえ、
単に
疑問を
一段先へおしやっただけで、実は何の
解決をも
与えぬ。また
或る人は、地球のなお
熱して温度の高かったころは、今日と
違って
種々の
化学的変化も
盛んに起こったであろうから、
無機物から生物の生ずるのに
必要な
条件が
備わっていたのであろうと
論じているが、これはあるいはさようかも知れぬ。しかしながらその
条件とは
如何なることであったかは全くわからず、したがって今日はそのような
条件が
備わっていないと
断然言い切ることもできぬ。当今多数の学者は、生物が
無機物から生じたのは地球の
歴史中の
或る時期に起こったことで、今日はもはやそのころとは地球の
状態も
異なっているゆえ、
無機物から直ちに生物の生ずるごときことは決してないと考えているようであるが、この
説は
実際如何ほどの
根拠を有するものであろうか。
親なくして生物の生ずることは決してないという今日の考えは、多くの
実験の
結果であって、その
応用に
誤りのないところを見ると、おそらく
疑いなく
確かなことであろうが、地球が昔は生物の生活に
適せぬ火の
塊であったとすれば、その後いつか一度
初めて生物の生じたという時があったに
違いなく、その生物には親はなかったに
相違ない。また今日といえどもどこかで、
無生物から
漸々生物ができているかも
測りがたい。
何故というにもっとも
簡単な生物はもっとも
微細なもので、
現に
黴菌の
類には千倍二千倍に
拡大せねば明らかに見えぬものもあり、
病源の中には
微生物であることがよほど
確かに思われながら、
最高度の
顕微鏡を用いてもその正体を見いだすことのできぬものもある。それゆえ
無機化合物から
漸々複雑な分子が組立てられ、ついに生物ができたとしても、これは決して直ちに形には見えぬであろう。
我々が見てこれは明らかに生物であると考えるものは、すでに生物としていくぶんか進歩したもので、まだこの
程度に
達せぬ前のものは、あるいはこれを見ることができぬやも知れぬ。されば
種々の
実験によって、生物は決して親なしに生ずものでないということが
確かになっても、これはすでにいくぶんか進歩した明らかな生物についての
論であって、
出来初まりの生物が
無機物から
漸々生ずることも、決してないと
断言することはできぬ。
前にも
述べたとおり、生物の
個体は
必ず親から生じ、生物の
種族は長い間に
漸々変化してついに今日の
姿に
達したものとすれば、今日の生物はみな長い
歴史の
結果である。かく長い
歴史の
結果として生じた生物
各種と同じものが、今日それだけの
歴史を
経ずして
突然生ずることはとうていできそうに思われぬが、その
歴史の
最初の生物に
似たものが、今もなお生じつつあるごときことはないかとの問いに対しては、
否と
確答するだけの
証拠はない。
著者の考えによれば、
無機物から生物になるまでには
無数の
階段があって、その間の
移り行きは、あたかも夜が明けて昼となるごとく、決してこれより前は
無生物これより後は生物と、
判然境を定めて
区別すべきものではない。地球の表面に
初めて生物ができたという時もおそらくかような具合で、
簡単な化合物から
漸々複雑な化合物が生じ、いつとはなしについに生物と名づくべき
程度までに進み来たったのであろう。されば今日といえども、かようなことの行なはれ
得べき
条件の
備わってある場合には、
無生物から生物の生ずることがあるべきはずで、もしかような場合を
真似ることができたならば、
人為的に
無生物から生物を
造ることもできぬとは
限るまい。新聞や
雑誌に時々出て来る生物の
人造というのは、
現今人の知っているごとき進歩した生物を
試験管内で
突然生ぜしめるとのことであるゆえ、これはおそらく
無理な注文であろうが、生物の
出来初めの
程度のものを
造るということならば、これは決して
不可能であると言い放つことはできぬであろう。
要するに、生物のなかったところに新たに生物の生ずるのは
如何なる場合であるかという問いに対しては、われらの
知識は
極めて
貧弱であって、今日のところとうてい
満足な答えはできぬ。ただ
実験によって、
消毒した
'缶の内に
自然に
黴菌の生ずるごときことはないということを、
確かに知り
得たのみである。
生物の
個体が生活を
続けるには
常に外界から食物を取らねばならぬが、植物と動物とではその食物に大なる
相違がある。まず
普通の植物は何を食うているかというと、空中からは
炭酸ガスを取り、地中からは水と
灰分とを
吸うのであるが、これらのものが
材料となり、
相集まって
次第に植物体の
組織ができる。ためしに
材木を
焼けば、
炭酸ガスと
水蒸気と
灰とになってしまうが、これは一度植物の体内で組合わせられたものを、
熱によって
再び
旧の
材料にくだき
離したと見なすことができる。しこうして植物が
灰、水および
炭酸ガスのごとき
無機成分から、自身の体を
造るにあたって
必要なるものは日光である。
緑葉を日光が
照らせば、緑葉内で水の
成分なる
酸素、
水素と
炭酸ガス中の
炭素とが
結び
付いて
澱粉が生じ、次に
澱粉は
砂糖に
変じ、
溶けて植物体の
各所に流れ行き、あるいは
芽に
達して、新たな
組織を
造ることもあれば、また根や
茎の中で
貯蔵せられることもあろう。
葡萄の中の
砂糖も、
甘藷の中の
澱粉も、
大豆の中の油も、
皆かようにして生じたものである。
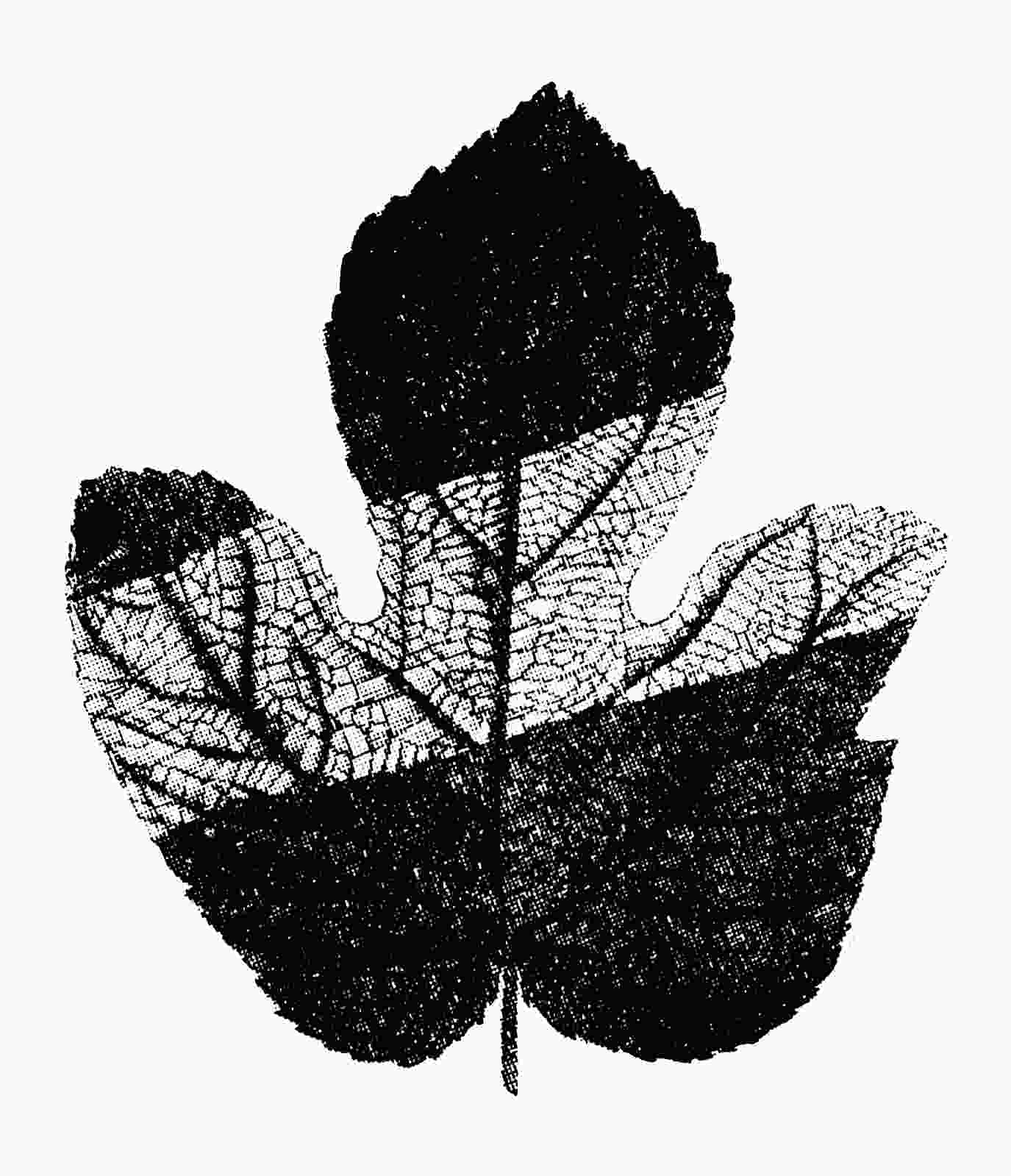 澱粉実験
澱粉実験
日光があたれば緑葉内に
澱粉粒の生ずることは、
極めて
簡単な
試験で、だれでも自身にためして見ることができる。すなわち黒い紙か
錫板かで葉の一部をおおい、
暫時日光に
照らした後にこれをヨジウム
液に
浸ければ、日光のあたっていたところだけはその中に生じた
澱粉粒がヨジウムに
触れて
濃い
紫色になるが、
影になっていたところはかようなことがない。もしアルコールで葉の緑色を
抜いてしまえばそこは白くなるから、
澱粉粒のできたところとの
相違がすこぶる
明瞭に見える。かような
次第で、植物は
常に日光の力を
借り、
無機成分より
有機成分をつくり、これを用いて生活しているのである。
これに反して、動物のほうはすでにできている
有機成分を食わねば命を
保つことができぬ。動物の中には植物を食うものと、動物を食うものとがあるが、食われる動物は
必ず植物を食うもの、または植物を食うものを食うものであるゆえ、動物の食物は、その
源までさかのぼれば
必ず植物である。されば植物なしに動物のみが
生存するということはとうていできぬ。しこうして動物のはき出す
炭酸ガスや、その
排泄する
屎尿は、また植物の生活に
欠くべからざるものである。
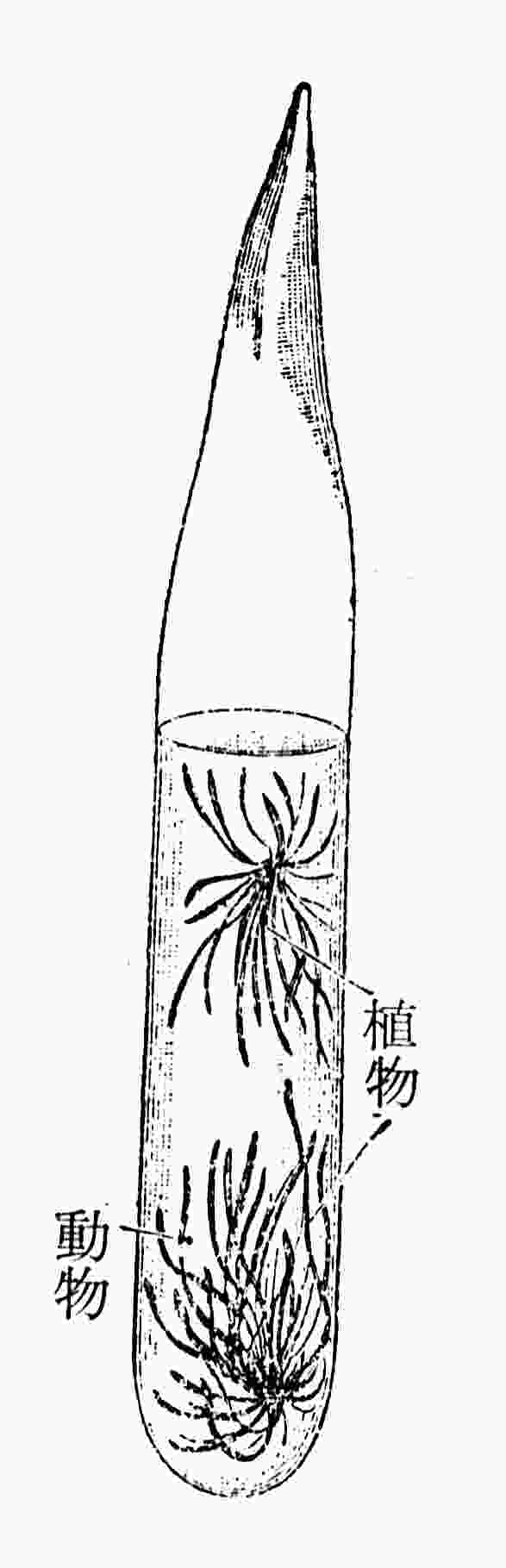 試験管に生物を入れたもの
試験管に生物を入れたもの
すなわち植物と動物とは相より
相頼って生活しているありさまゆえ、もし
適当量の植物と動物とを
硝子器の中に
密閉して外界との交通を全く
遮断しても、日光さえ受けさせておけば長く
生存するはずであるが、
実際ためして見るとそのとおりで、ガラスの
試験管に海水を入れ、
海藻を少しと小さな「いそぎんちゃく」
一匹とを入れて
管の
上端を
閉じれば、海岸から遠いところへ生きたまま
容易に
運搬もでき、また長く
飼うてもおける。かくのごとく植物は日光の力によって
絶えず
無機成分から
有機成分を組立て、これを動物に
供給し、動物は
有機成分を食うてこれを
破壊し、
旧の
無機成分としてこれを植物に返するのであるから、同一の
物質が
常に
循環して
或る時は
無機成分となり、
或る時は
有機成分となって、動植物の身体に出入しているということができよう。
昔は化合物を分けて
有機化合物と
無機化合物との二組とし、
有機化合物のほうは、動植物の生活作用によってのみ生ずるものであって、
人為的に
無機物からつくることはできぬと考えたが、今より九十年ばかり前に
有機化合物の
一種なる
尿素を
人造し
得たのを
初めとして、今日では多数の
有機化合物を
化学的に組立てて
製造し
得るに
至った。
藍、
茜などの
染料は昔はその植物がなければできぬものであったのが、今はたくさんに
人造せられるから、
面倒な手間を
掛けて
藍や
茜を
培養するにおよばなくなった。
有機化合物中のもっとも
複雑な
蛋白質でさえ、近年は
人造法によってややこれに
似たものをつくることができる。されば
有機化合物、
無機化合物という
名称は
便宜上今も用いてはいるが、その間にはけっして
判然たる
境があるわけではなく、分子の組立てが一方は
複雑で一方は
簡単であるというにすぎず、しかもその間には
無数の
階段がある。
緑葉の内で
澱粉が生ずると言うても、むろん
炭素、
酸素、
水素が
突然集まって
澱粉になるのではなく、一歩一歩分子の組立てが
複雑になって、ついに
澱粉という
階段までに
達するのである。また動物が死ねば、その肉や血は
分解して水、
炭酸ガス、アンモニアなどになってしまうが、これまた
急激にかく
変ずるのではなく、
一段ずつ
簡単なものとなり、
無数の
変化を重ねてついに
極めて
簡単な
無機化合物までになり終わるのである。
無機化合物から
有機化合物となり、
有機化合物から
無機化合物になる間の
変化は今日なお研究中であってくわしいことは十分にわからぬが、その
一足飛びに
変化するものでないことだけは
確かである。
生物
個体の身体の
各部についてその
物質の
起源をたずねると、
以上述べたごとく決して同一
分子が長く
変化せずにとどまっているわけではなく、一部分ごとにそこの
物質は
絶えず
新陳代謝する。毛や
爪を見ればこの事はもっとも明白であるが、他の体部とてもやはり同様で、役をすませた古い
組織は
順を追うて
捨てられ、これを
補うためには新しい
組織が後から生ずる。昔の西洋書には人間の身体は七年ごとに全くかわると書いてあるが、これはもとよりあてにならぬ
説で、
障子のごときものも紙は
度々貼りかえる
必要があるが、
框のほうは長く役に立つのと同様に、人間の身体の中にも速やかに
換わる部分と
遅く
換わる部分とがあろう。
例えば
血液のごとく
絶えず
盛んに
循環しているものは
新陳代謝もすこぶる
速やかであろうが、
骨骼などは
新陳代謝がやや
緩慢でも
差支えはない。しかしとにかくつねに
新陳代謝することは
確かであるゆえ、生物の体が
昨日も今日も明日も同じに見えるのはただ、形が同じであるというだけで、その
実質は一部分ずつ
絶えず入れ
換わっている。そのありさまはあたかも
河の形は
変わらぬが、流れる水の
暫時も止まらぬのに
似ている。生物は
一種ごとに
体質が
違うゆえ、人間が牛肉を食うても、決して牛の
筋肉がそのまま人間の
筋肉とはならぬ。まずこれを
分解して人間の
組織をつくる
材料として用いるに
適するものとし、さらにこれを組立て直して人間の
組織とするのであるが、食物をかように
分解するのが消化の
働きである。またいったんできあがった
血液、
筋肉などもこれを
働かせれば少しずつ
分解して
老廃物となり、大小
便となって体外に
排出せられる。
乳のみを飲む
赤児や、
飯と
豆腐とを食うた大人の大小
便に色のついているのを見ても、大小
便が
単に飲食物中から
滋養分を引き去った
残りのみでないことは知れる。かように考えると、生物の身体は一方においては
時々刻々新たに生じ、他方においては
時々刻々死して
捨てられているのであるが、この事については世人は
別に
不思議とも思わずにいる。人間の身体は
無数の
細胞の集まりであるが、その
一個一個の
細胞を見たならば、今生まれるものもあり、今死ぬものもあり、
若いものもあり、
老いたものもあって、あたかも一国内の一人一人を見ると同じであろう。かくのごとく体内の
細胞の生死は
時々刻々行なわれていても、これは
当人が知らずにいるゆえ、
別に問題ともせず、ただ
細胞の集まりなる
個体の生と死に
関してのみ、昔からさまざまの
議論を
闘わせていたのである。生物の起こりに
関する
議論はほとんど
際限のないことで、しかもその大部分は
仮説にすぎぬゆえ、
以上述べただけにとどめておく。
生物の
生涯は食うて
産んで死ぬという
三箇条につづめることができるが、まずその中の食うことから考えて見るに、食物の
種類にも、その食いかたにも、これを
獲る
方法にも、実に
種々雑多の
差別がある。生きるためには食わねばならぬということに
例外はないが、食物の中には
滋養分を多く
含むものと少なく
含むものとがあり、したがって時々
少量の食物を食えば事の足りる生物もあれば、また
多量の食物を昼夜
絶えず食わねば生きていられぬ生物もある。しかしながらいずれにしても食物のほうには一定の
制限があり、生物の
繁殖力のほうにはほとんど
限りがないから、食うためには
是非ともはげしい
競争が起こらざるを
得ない。植物のごときは、日光の力を
借りて
炭酸ガス、水、
灰分などから
有機成分をつくって生長し、これらの物はいたるところにあるゆえ、
競争にもおよばぬようであるが、
適度に日光があたり
適度の
湿気を
備えた地面に
制限があるゆえ、やはり
競争をまぬがれぬ。しかも
一株につき数百、数千もしくは数万も生ずる
種子の中で、
平均わずかに
一粒を
除くほかはみな
生存の
望みのないことを思えば、
如何にその
競争の
激烈であるかが知れる。されば生物の
生涯は
徹頭徹尾競争であって、食物を多く食うものも、少なく食うものも、肉食するものも、草食するものも、食うためには
絶えず
働かねばならず、しこうして
働いたならば
必ず食えるかというと、大多数のものは
如何に
働いてもとうてい食えぬ
勘定になっていて、
暫時なりとも
安楽に食うてゆけるものは金持ちの人間と
寄生虫とのほかにはない。しかもかような
寄生虫類が目前やや
安楽な生活をしているのは、
数多の
難関を切り
抜けて来た
結果で、
初め数百万も
産み出された
卵の中のわずかに一二
粒だけが、この
境遇に
達するまで
生存し
得たのであるから、その
生涯の全部を見ればむろんはげしい
競争である。本章においては動物が食物を
獲るために用いる、
種々の
異なった
方法の中から
若干を
選んで、その
例をあげて見よう。
動物の中には自身は動かずに
餌のくるのを待っているものがある。
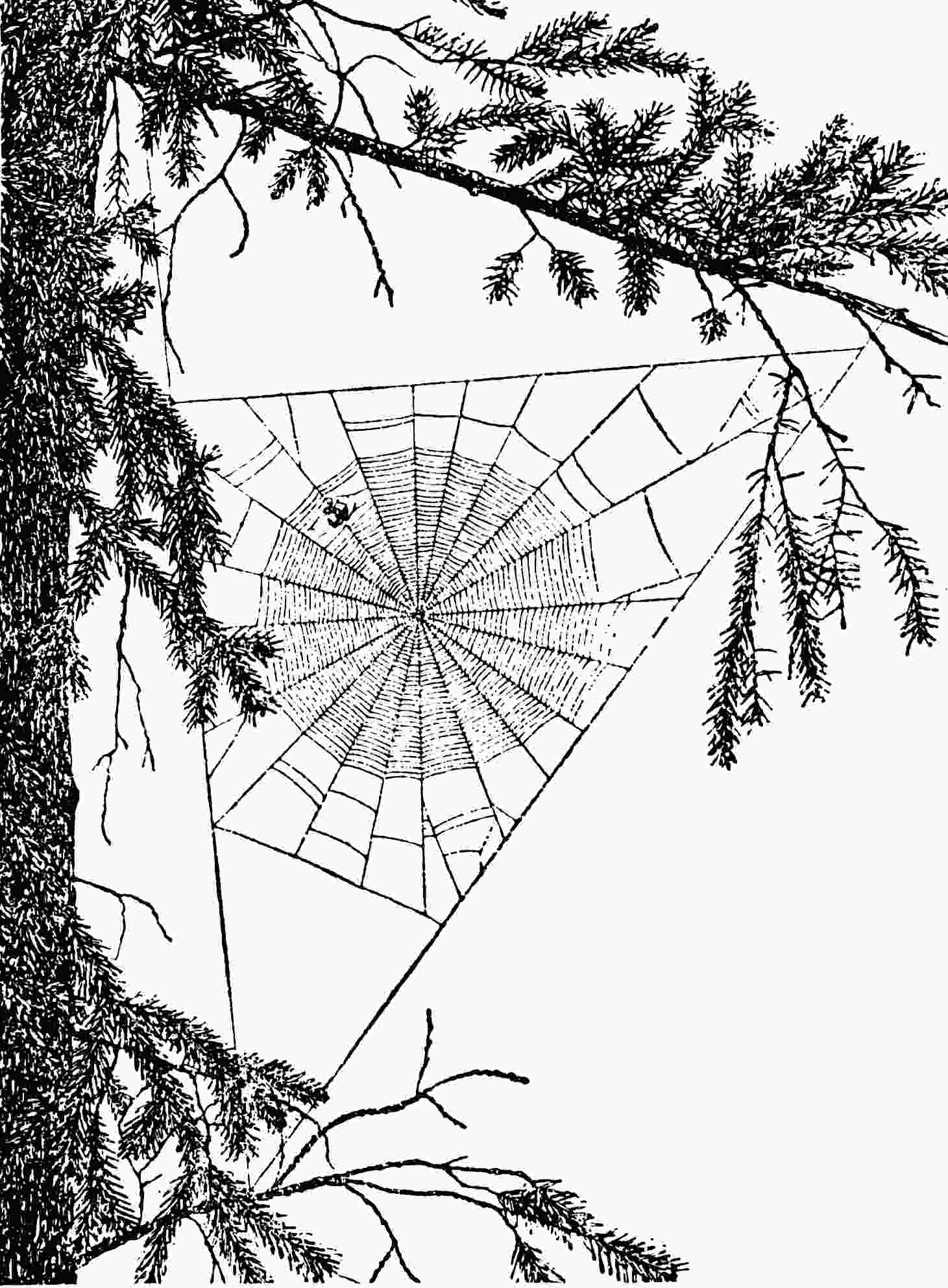 くもの巣
例
くもの巣
例えば、「くも」のごときは庭や林の
樹の間に
網を
張り終われば、その後はただ虫が
飛んで来て引っかかるのを待つだけである。かかるところだけを見ると、さも
安楽らしく見えるが、
初め
網をつくるときの「くも」の
骨折りはなかなか
容易でない。「くも」が糸を
巧みにつかうことは昔から人に知られたところで、ギリシアの神話や
支那の
西遊記の本などにも、その話が出ているが、「くも」の
腹を切り開いて見ると、糸の
材料をつくる
腺と糸の表面を
粘らすための
黐のごときものを出す
腺とがあり、糸は
腹の
後端の近くにある
数個の
紡績突起の先から
紡ぎ出され、足の
爪の
櫛によって
適当の太さのものとして用いられる。
初めは
粘らぬ太い糸を用いて
枝から
枝へ
足場をかけ、全体の
網の形がほぼ定まると、次に細かい
粘る糸を出して細かく
網の目をつくり上げる。
試みに指を「くも」の
巣に
触れて見ると、太い糸は強いだけで
粘らず、細い糸は指に
粘着する。小さな虫が「くも」の
巣に
触れると、あたかもとりもちざおで
差された「とんぼ」のごとくに
逃げることのできぬのはそれゆえである。また「くも」はただ、
網さえ
張れば
餌がとれるかというと、決してさようにはゆかぬ。
一箇所にとどまって、
餌の来るを待っているのであるから、あたかも
縁日の夜店商人と同じく、
往来の
盛んな
良い場所を
選ぶことが
必要であるが、
良い場所を見つけても、そこがすでに他の「くも」に
占領せられている場合には
如何ともできぬ。その上、いったん
網を
張っても雨風のために
無駄になることもあれば、大きな虫や鳥のために
破られることもあるから、しばしば、つくり直さねばならぬ。
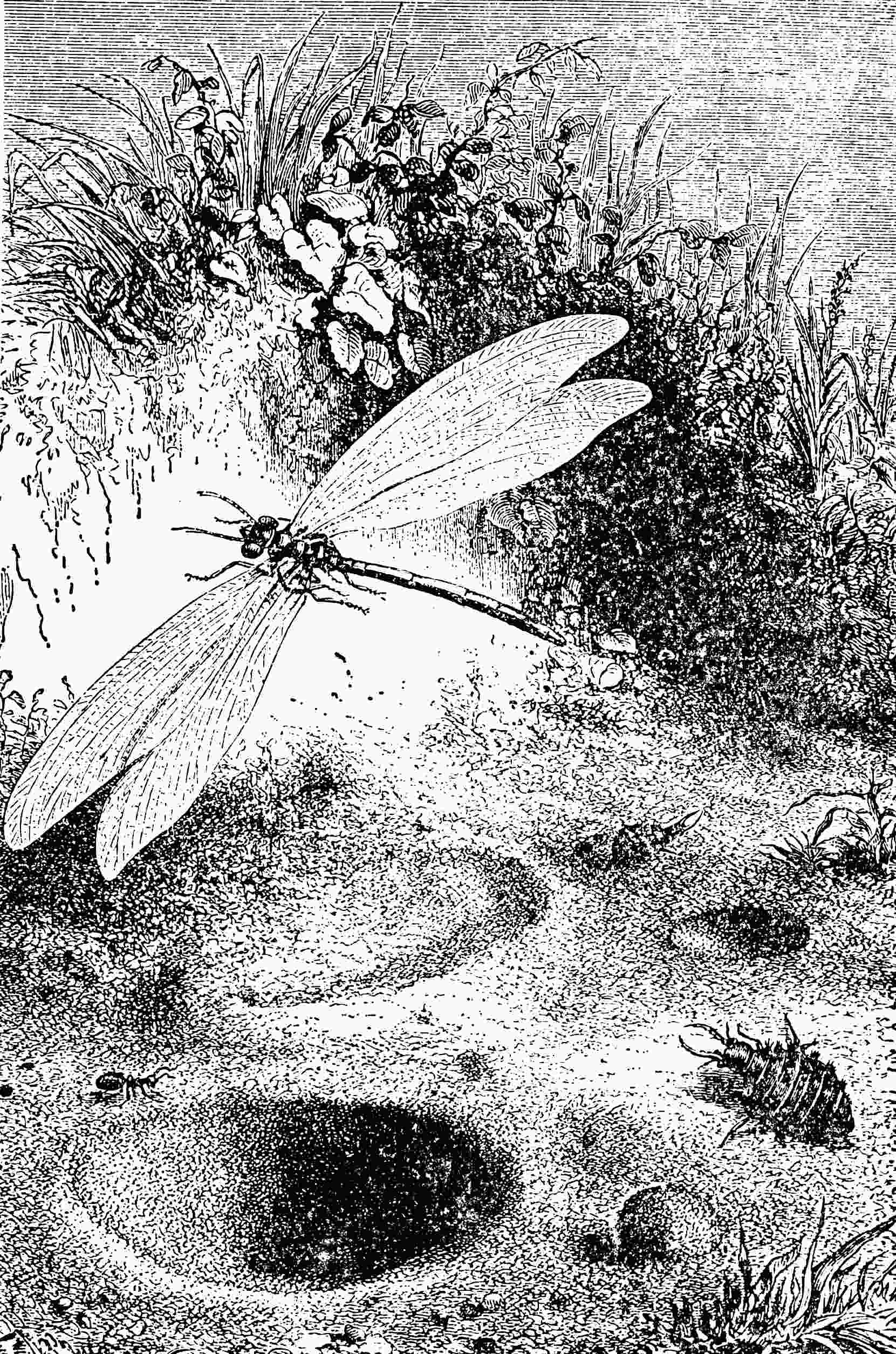 蟻地獄
蟻地獄
また
縁の下などのごとき雨のかからぬ地面には小さな
摺鉢形の
規則正しい
窪みが
幾つもあるのを見つけるが、その
底には
一匹ずつ小さな虫が
隠れている。これは「うすばかげろう」という
昆虫の
子供で、「くも」と同じく自身は動かずに
餌の来るのを待っている
種類に
属する。この虫は
好んで
蟻を食するが、
摺鉢形の
穴のところへ
蟻が来かかると、土が
乾いているために
穴の
底まで転がり落ちるゆえ、直ちにそれを
捕えて食う。もし
蟻が
再び
穴からはい出しそうにでもすれば、
扁平な頭をもって土をすくい、
蟻を目がけて打ちつけ、土とともに
蟻が
再び
底まで落ちて来るようにするから、いったんこの
穴に
滑り落ちた
蟻はとうてい命はない。それゆえこの
穴のことを
俗に
蟻地獄と名づける。ちょっとのんきな生活のごとくに見えるが、同じところに多数の
蟻地獄が
並んであるゆえ、あたかも区役所の
門前に
代書人の店が
並んでいるごとくで、中にはあまりお客の来ぬために
餓を
忍ばねばならぬものもあろう。
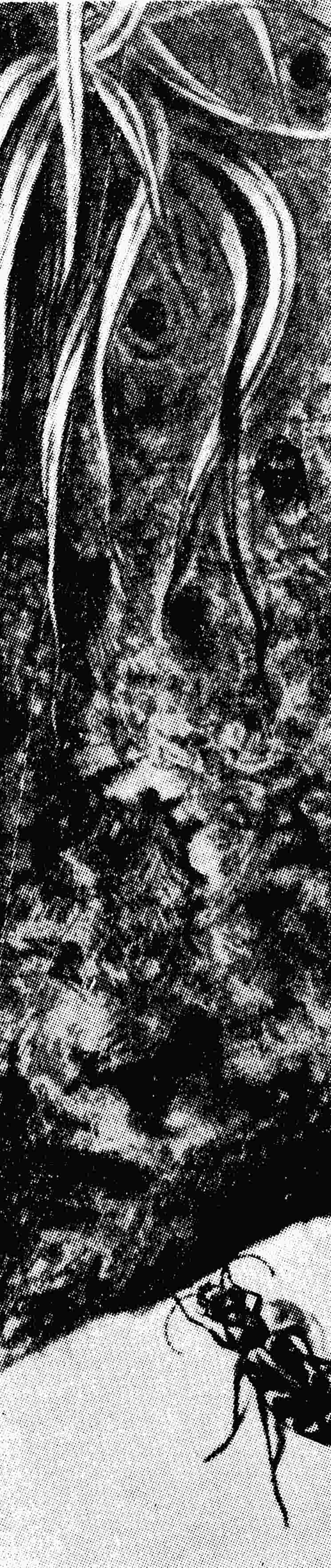 みちおしえ
みちおしえ
また天気のよい日に
田舎道を歩いていると、青色と金色との
斑紋があって、美しい
光沢のある
甲虫が
飛んではとまり、とまっては
飛びして、あたかも道
案内をするごとくに先へ進んで行くのをしばしば見ることがある。これは「みちおしえ」という虫であるが、この虫の
幼虫などもとどまって
餌を待つほうである。すなわち地面に小さな
孔をつくりその中に
隠れて、他の
昆虫が知らずに近づくのをうかがい、急にこれを
捕えて食する。
陸上の動物にはとどまって
餌の来るを待つものは
割合に少ないが、水中に
棲む動物にはかようなものは
極めて多い。その理由は
陸上においては動物の
餌となるものは多くは
固着して動かぬか、または勝手に運動するものかであって、風に
吹きまわされるごときものはほとんどない。それゆえ、牛や羊が
如何に大きな口を開いて待っていても、
自然に口の中へ草の葉が
飛んではいることは決してないが、海水の中には動物の
餌となるべき
微細な
藻類や動物の
破片などがいくらでも
浮游して急に
底に
沈んでしまわぬゆえ、気長に待ってさえいれば口の近所まで
餌の流れて来ることはすこぶる多い。ゆえにこれを集めて口に入れるだけの
仕掛けがあれば、
相応に食物は
得られる。
例えば「かき」のごときは、岩石の表面に
付着して
一生涯他に
移ることはないが、
殻を少しく開いて
絶えず水を
吸うていれば、
必要なだけの食物は水とともに
殻の内にはいり来たって口に
達する。「あわび」の
類は全く
固着してはいないが、つねに岩の
一箇所に
堅く
吸い着いているから
固着も
同然である。「はまぐり」、「あさり」などは
徐々と動くが、その食物を
得る
方法は「かき」と同じで、全くとどまって待つ
仲間に
属する。
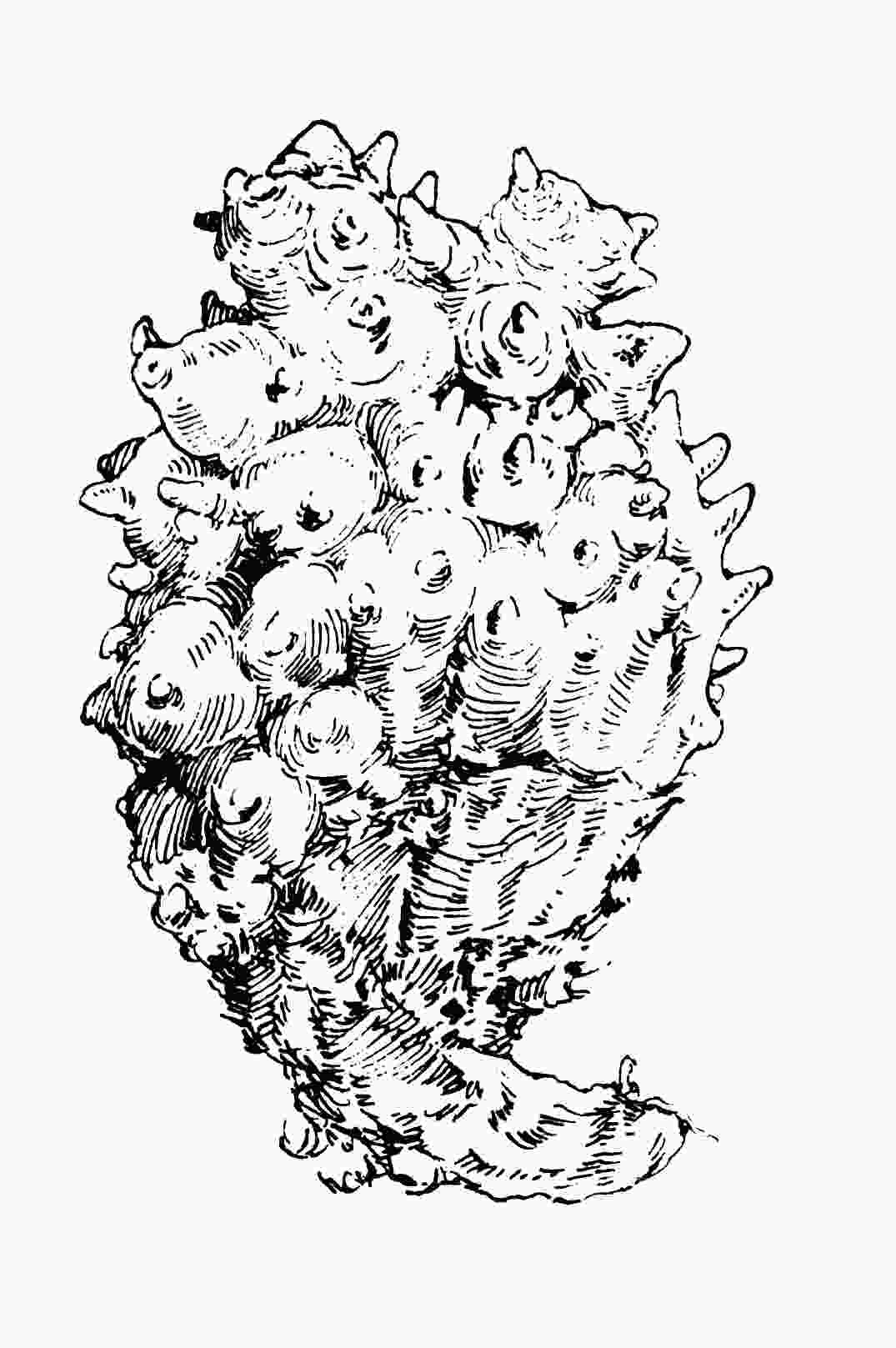 ほや
ほや
青森や
北海道辺で
盛んに食用にする「ほや」という動物は実にとどまって
餌の来るのを待つことでは理想
的のもので、身体は
卵形をなし、根をもって岩石に
固着し、全身
革のごとき
嚢で
包まれているゆえ、動物学上ではこの
種類の動物を
被嚢類と名づけるが、その
革嚢にはただわずかに
二箇所だけに
孔があり、一方からは水が
吸い
込まれ、一方からは水が
吹き出される。「ほや」の体内にはいり来たった水は
鰓を通って直ちに出口の
孔のほうへ出てゆくが、海水中に
浮いている
微細な
藻類などは、食道の
胃、
腸を
通過し、
不消化物だけは出口のところに
達して水とともに流れ出る。この点からいえば一方の
孔は真に口で、他の
孔は
肛門に相当するが、
総じて
固着している動物では、口と
肛門とが
接近して、両方が
並んで前を向いていることが多い。これはあたかも
勧工場の入口と出口とが
並んで
往来のほうへ向いているのと同じ
理屈で、とどまったままで食物を食い、
滓を
吐き出すにはもっとも
便利な仕組みである。
 ふじつぼ
ふじつぼ
なお海岸へ行って見ると、「ふじつぼ」、「かめのて」、「いそぎんちゃく」、
海綿などが一面に岩についていて、これを
踏まねばほとんど歩けぬほどのところがあるが、これらはいずれもとどまって
餌を待つ動物である。またそれより少しく深いところに行けば、「さんご」や
海松、
海柳などと植物に形の
似た動物がたくさんにあるが、これらも食物の取りようは、「いそぎんちゃく」と全く同様である。
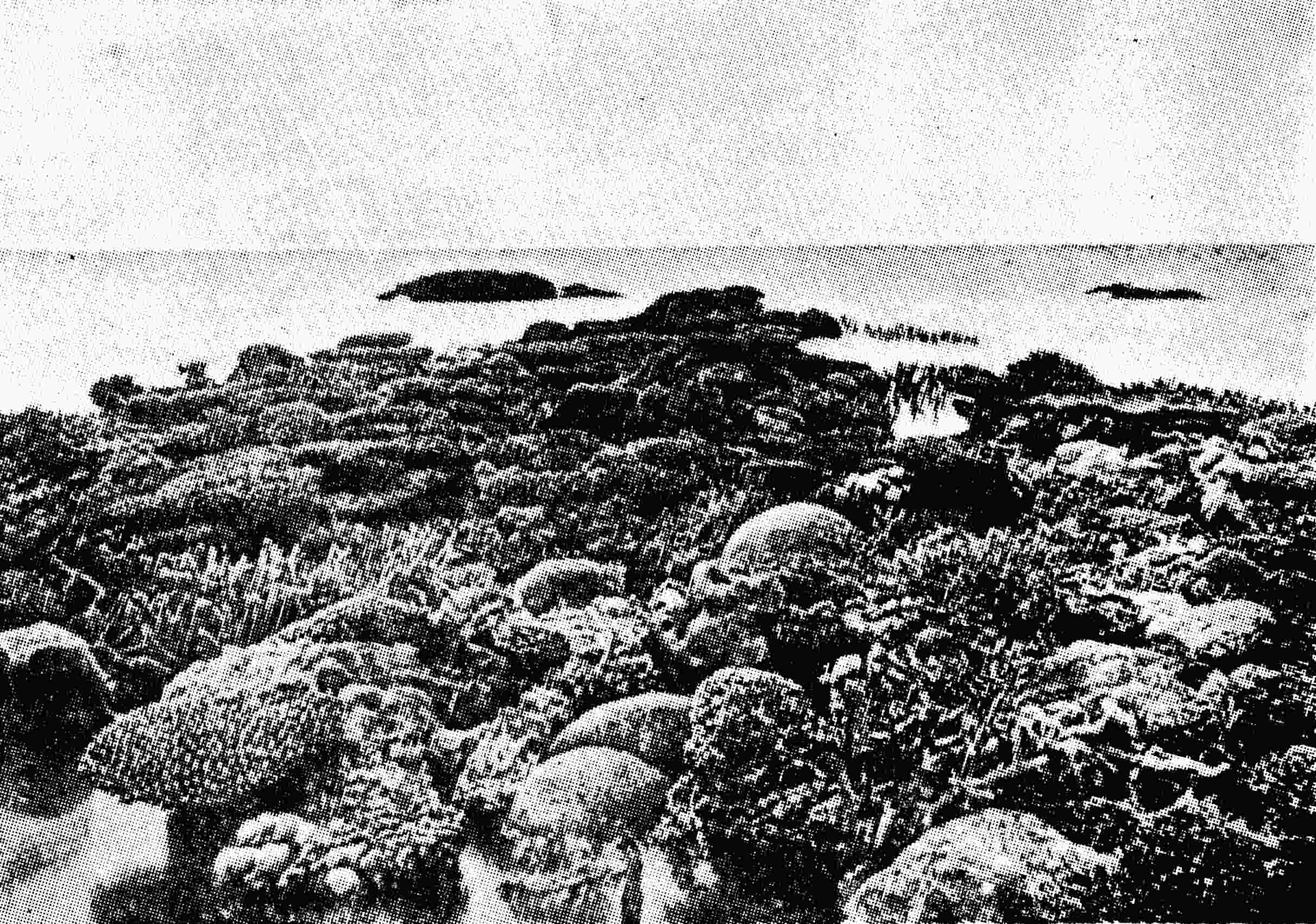 さんご礁
さんご礁
とどまって
餌の来るを待つ動物は、
逃げる
餌を追いまわすわけでないから、ほとんど
筋肉を
働かせる
必要がなく、また
餌のゆくえを
探すにおよばぬから、
眼や耳のごとき
感覚器もいらぬ。
筋肉や
感覚器を用いなければ
疲労することもなく、食物を
要することも
極めて少ないが、少ない食物ならばわざわざ
求めずとも口の
辺まで流れ
寄って来る。そのありさまは、あたかも社会に出て活動すれば
儲かると同時に
費用もかかるが、
隠遁して
暮らせば、
収入も少ない代わりに
出費も少なく、
結局、
静かに生活ができるのと同様である。しかしとどまって
餌を待つに
適する場所には、かような生活をする動物が集まって来て、それぞれよい
位置を取ろうとしてたがいにおし合うゆえ、
生存のための
競争はやはりまぬがれることはできぬ。
たいがいの動物は自身に進んで
餌を
求めるものであるから、この組の中には食物の
種類もこれを取る
方法も実に
千態万状で、とうていこれを
述べつくすいとまはない。植物を食うものもあれば動物を食うものもあり、同じく植物を食うという中にも、葉を食うもの、根をかじるもの、
果実を食うもの、
若芽をついばむもの、花の
蜜を
吸うもの、
幹の
心をかむものなどがあり、大きな
餌を一部ずつ食うものもあれば、小さな
餌を多く集めて一度に丸のみにするものもある。しかしていずれの場合においても動物の口の形、歯の
構造などを見れば、おのおの、その食物の食い方によく
適している。進んで
餌を
求める動物の
餌の取り方を
残らず
列挙することはもちろんできぬから、ここには、ただその中から多少つねと
異なったと思われるもの
数種をかかげるにとどめる。
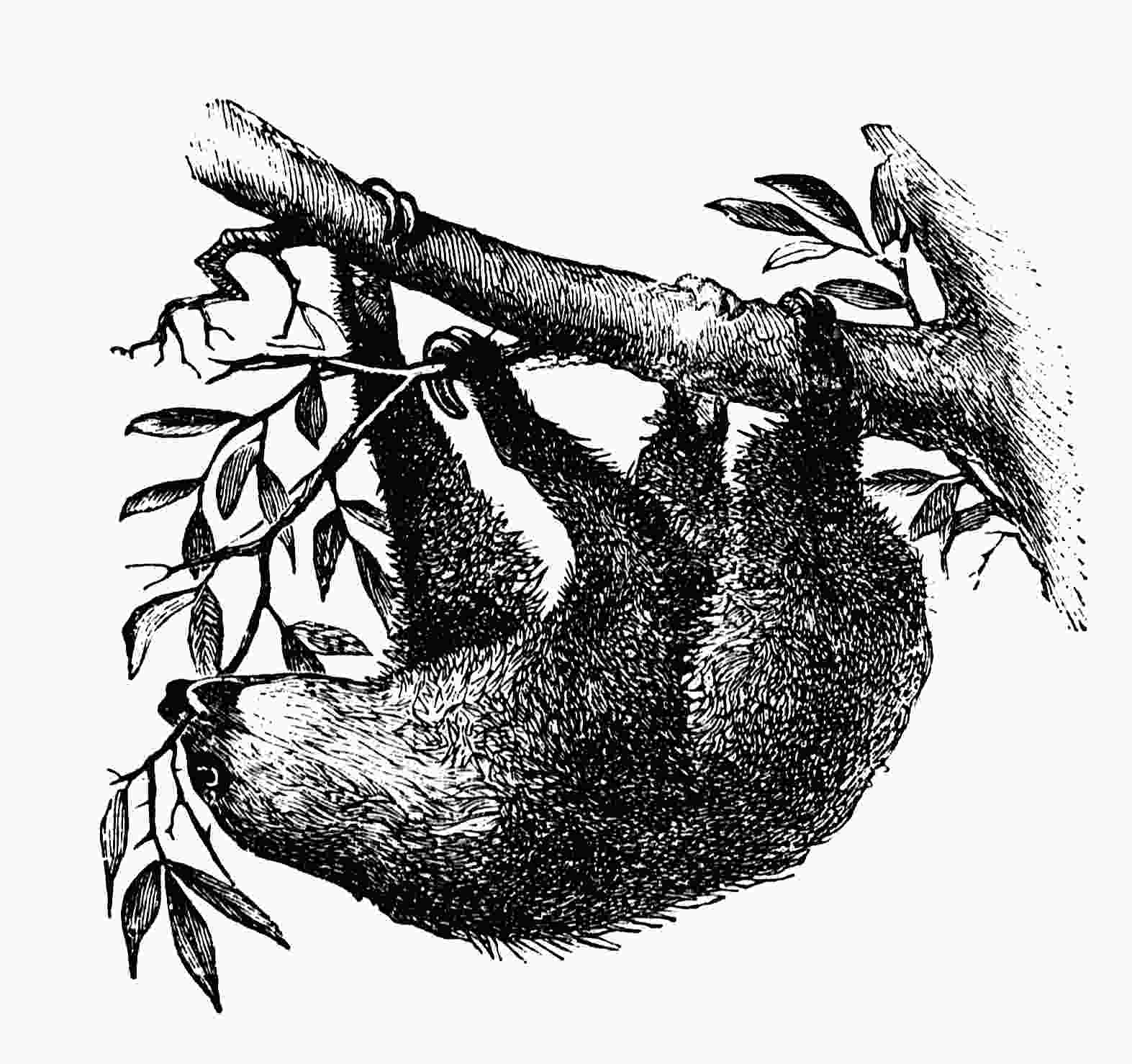 なまけもの
なまけもの
南アメリカの森林に住む「なまけもの」という小犬ぐらいの大きさの
獣はつねに緑葉を食物としているが、
四肢ともに指の先には三日月
状に曲がった大きな
爪があって、これを
樹の
枝にかけ、
背を下に向けてぶら下がりながら木の葉を食うている。木の葉は近い所にいくらでもあって、けっして遠方まで
探しに行く
必要がなく、かつ
繁った森林では
隣れる
樹の
枝と
枝とが
相触れているから、次の
樹に
移るにあたってもわざわざ地面まで
降りるには
及ばぬ。それゆえ、この
獣は生まれてから死ぬまで
樹の
枝からぶら下がって生活して、一度も地上へ
降りて来ることはない。
猿などが
樹の
枝を
握っているのは、指をまげる
筋肉の
働きによることゆえ、死ねば指の力がなくなり
枝を
握ることもできなくなるが、「なまけもの」は曲がった
爪を
枝にかけているのであるから、死んでもぶら下がったままでけっして落ちて来ない。
眠るときにもむろんそのままである。
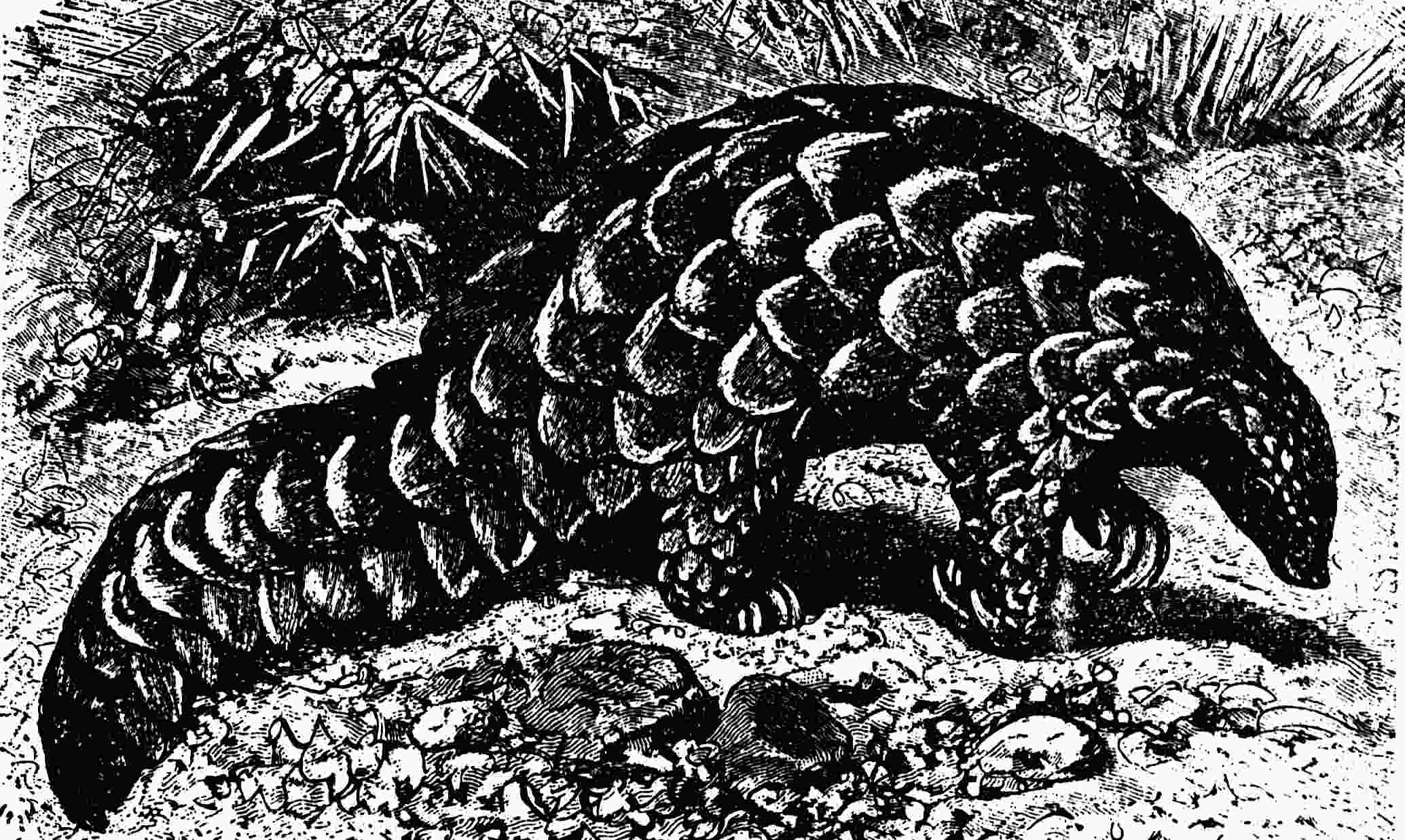 せんざんこう
せんざんこう
アフリカ、アジアの
熱帯地方から
台湾にかけて
穿山甲という
奇妙な
獣がいる。この
獣は
尾が太くて全身大きな
堅い
鱗で
被われているゆえ昔の
本草の書物には
陸鯉などと名をつけて
魚類の中に入れてあるが、
腹側を見れば
普通の
獣類と同じく一面に毛がはえている。つねに
蟻の
巣を
掘って
蟻を食うているが、そのため前足の
爪は
特に太くて
鋭い。また
舌は「みみず」のような形で
非常に長く、かつ
頸の内にある
唾腺から出る
極めて
粘った
唾液はあたかも
黐をつけたごとくによく
粘着する。
蟻や
白蟻の
巣は
熱帯地方にはずいぶん大きなのがあって、一つ
掘れば何十万も何百万も
蟻が出るが、これをたちまちなめて食うにはかような
舌はもっとも
重宝であろう。
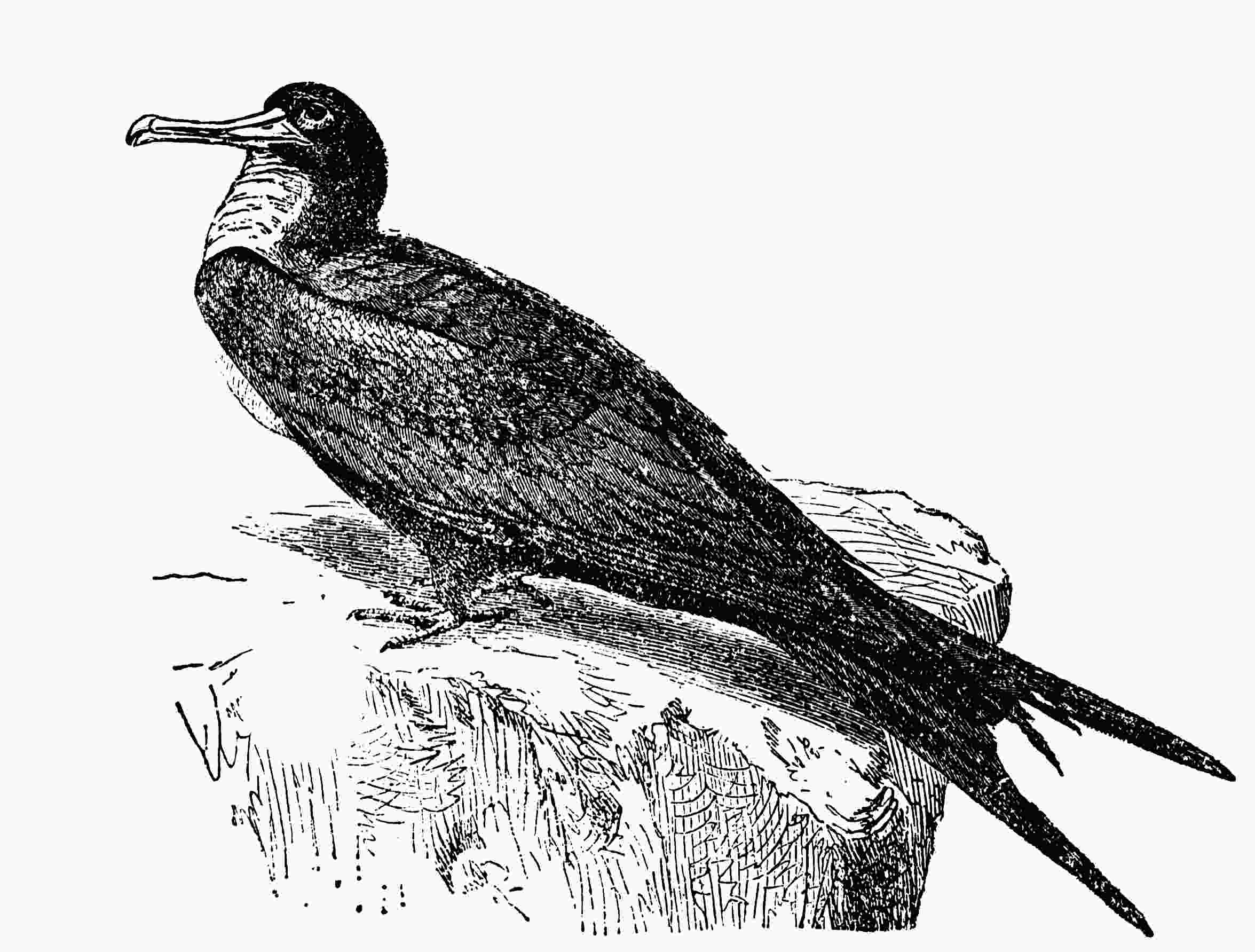 軍艦鳥
軍艦鳥
次に
鳥類に
移って、その中で
餌の取り方のおもしろい
例をあげると、まず海鳥の中に「
軍艦鳥」と名づけるものがある。この鳥は足の指の間に
蹼のある
純粋の水鳥であるが、自身で水に
游いで魚を取るということはほとんどなく、いつも
鴎などが魚を
捕えたのを見つけて、それを空中で横取りすることを
本職としている。さればむしろ
海賊鳥と名づけたほうが
適当であるが、
海賊も商船の数に
比してあまり多数になると
職業が
成り立たぬごとく、この鳥も
鴎などにくらべてはるかに少数だけより生活することができぬから、
自然同僚間に
縄張りの
争いも生じてけっして
油断はならぬであろう。
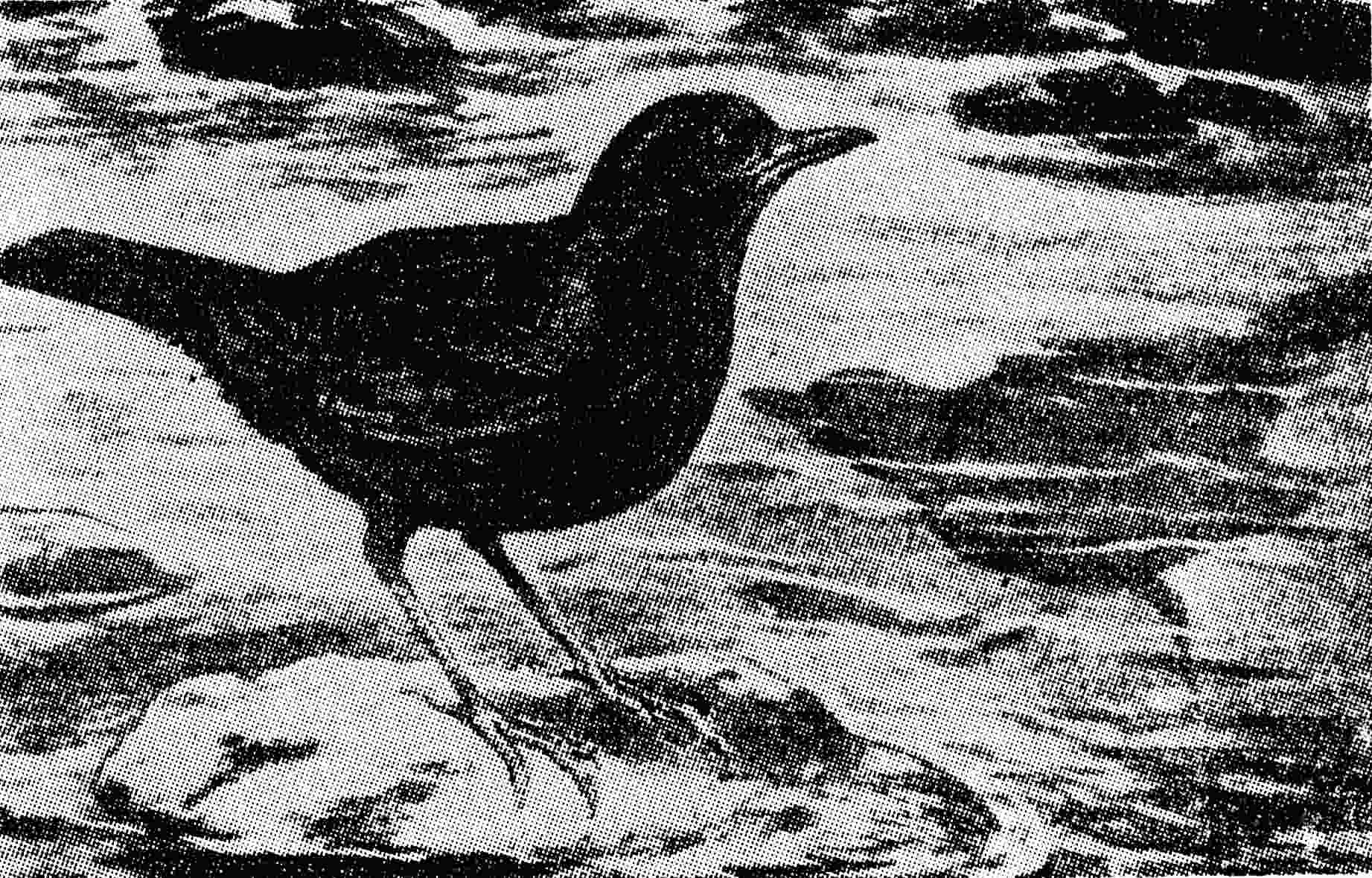 かわがらす
かわがらす
これと反対に水鳥でないものが水の中へもぐり
込む
例には「かわがらす」がある。この鳥は名前のとおり羽毛が黒色であるが、足の指を見ると「つぐみ」や「ひよどり」のごとき
普通の
鳥類と少しも
違わず、
蹼などは少しもないが、つねに
水辺にいて指をもって水草の
茎をつかみ、それを
伝うて
浅い水の
底まで行き小さな
虫類などを
捕えて食う。体形は全く
水鳥類と
異なるにかかわらず、かく水の
底までもぐり
込むのは、おそらく
先祖以来の
因襲を
破り、
冒険的に新
領土の
開拓を
試みて
成功したものとでもいうことができよう。
 蛾と蜂鳥
鳥類
蛾と蜂鳥
鳥類の
嘴はおのおの食物の
種類に
応じて形の
異なるもので、
穀粒を拾う
雀では太く、虫を食う
鶯では細く、魚をはさむ「かわせみ」でははなはだ長く、
蚊をすくう「よたか」ではすこぶる短く、「きつつき」では
真直ぐで、
鸚鵡では曲がっているなどは人の知るとおりであるが、同じ
仲間の鳥で、ほとんど
一種ごとに
嘴の形の
違うのはアメリカ
熱帯地方に
産する
蜂鳥である。
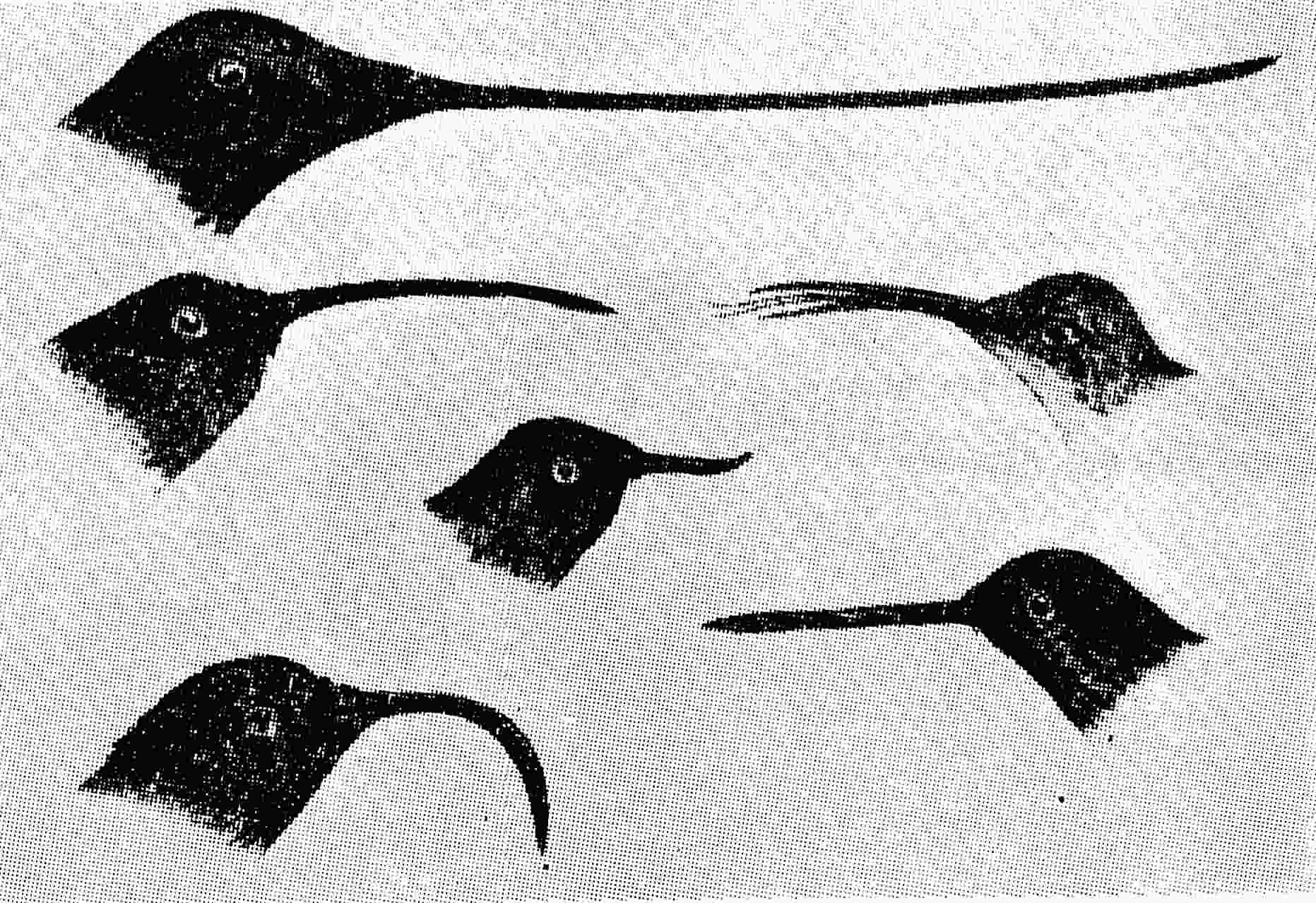 蜂鳥のくちばし
蜂鳥のくちばし
この
類は鳥の中で
最も小形のもので、
雀よりもはるかに小さく
栂指の
一節にも足らぬが、あたかも
昆虫類の
蝶や
蛾と同じようにつねに花の
蜜を
吸うて生きている。たいがい
孔雀の
尾のごとき色と
光沢とを
備えているゆえ、その
飛びまわっているところはまるで
宝玉を
散らしたごとくでまことに美しい。
蝶や
蛾が花の
蜜を
吸うにはおのおの
専門があって、
筒の長い花に来るものは
吻が長く、
浅い花に来るものは
吻が短いが、
蜂鳥もこれと同様で、おのおの花の
形状に
応じて長い真直ぐな
嘴を持った
種類もあれば、いちじるしく曲がった
嘴を
備えた
種類もあって、あたかも
錠と
鍵とのごとくに相手が定まっている。ついでながら
述べておくが、およそ
鳥類の中で
蜂鳥ほど
巧みに
飛ぶものはない。その
花蜜を
吸うときのごときは、空中の一点にとどまって進みもせず
退きもせず、あたかも糸で
釣ってあるかのごとくに
静止し、
蜜を
吸い終われば
電光のごとくに
飛び去るが、他の鳥にはかような
芸はとうていできぬ。もし
飛行機で空中の一点に
暫時なりとも
静止することができたならば、
偵察用、
攻撃用ともにその
効用は
莫大であろうが、今日の
飛行機ではこの事は
不可能である。
蜂鳥はかく自由
自在に
飛ぶ代わりに、
翼を動かすことも
非常に
速やかで、そのため空気に
振動を起こして
蜂や
虻の
飛ぶときのごとき
一種の
響きを生ずる。
蜂鳥という
名称はこれより起こったものである。古き書物には
蜂鳥は
往々くもの
巣にかかって命を落とすことがあると書いてあるが、これは
信偽のほどは
請合われぬ。
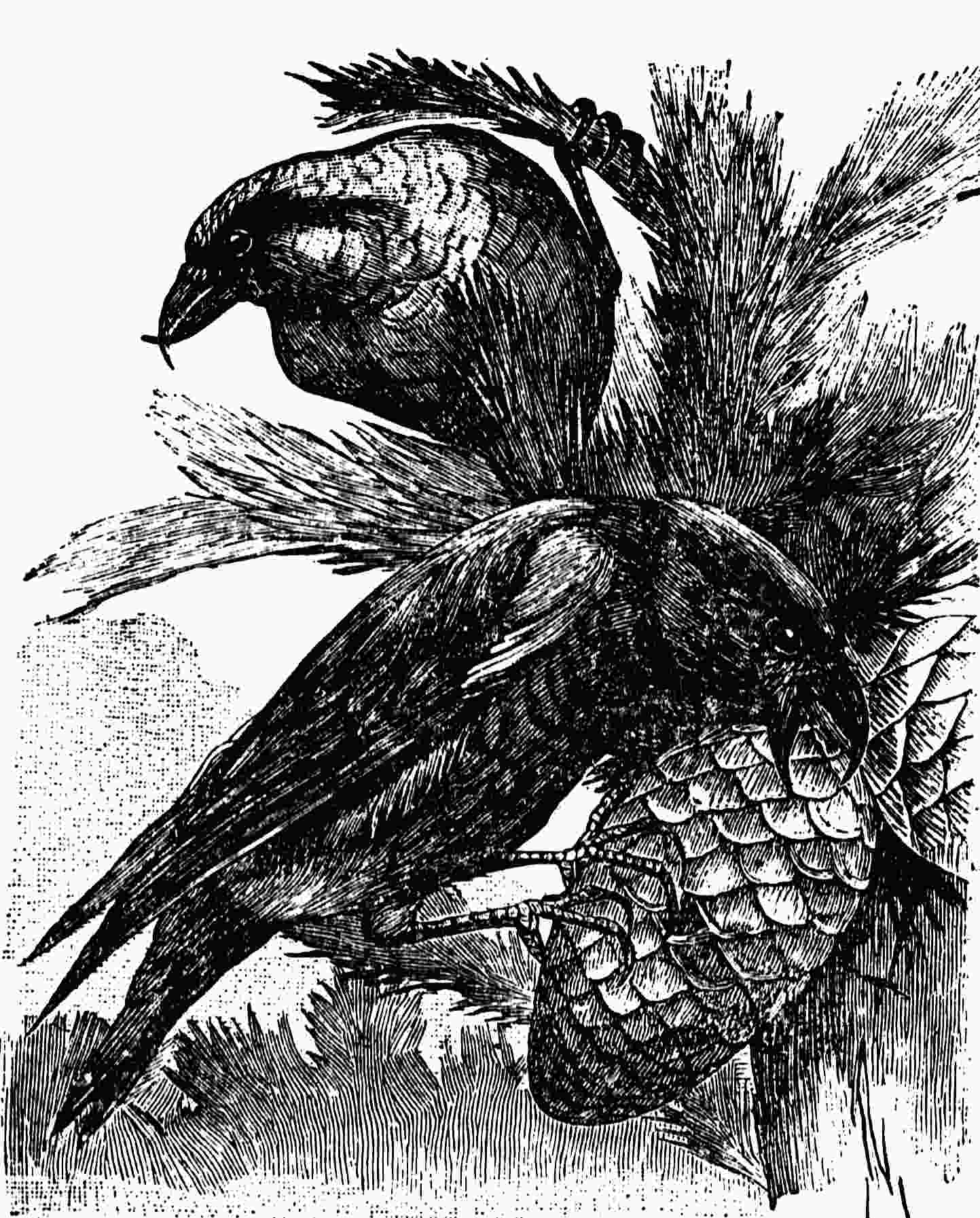 いすか
いすか
鳥の
嘴にはずいぶん
奇妙な形のものがある。「いすか」の
嘴の上下
相交叉していることはだれも知っているが、これは「いすか」にとっては
都合がよい。「いすか」が
松の実を食うところを見るに、足でつかんで
嘴を
鱗片の間に
挿しいれ、一つ頭を
振ったかと思うと、その
奥にある
松の
種はすでに「いすか」の口に
移っているが、
雀や「やまがら」のような真直ぐな
嘴ではとうていかく
速やかにはとれぬに
違いない。せっかくの
目論見が「いすか」の
嘴と食い
違うことは人間にとってははなはだ
都合の悪いことであるが、「いすか」はもしも
嘴が食い
違うていなかったならば、日々の生活に
差支えが生ずるであろう。
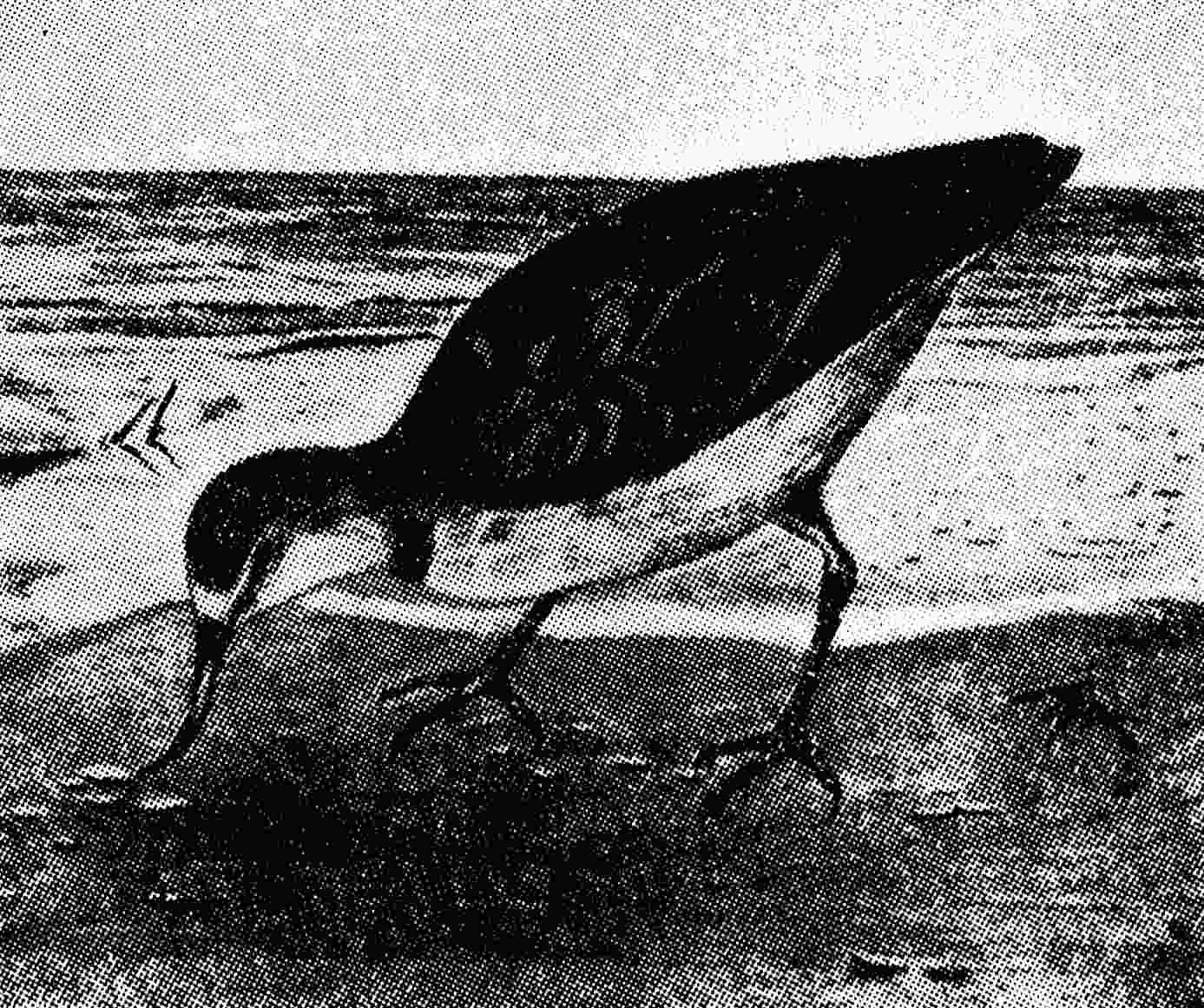 嘴曲がりしぎ
嘴曲がりしぎ
また「そりはししぎ」に
似た
鴫の
一種では、細長い
嘴の先のほうが右に曲がってすこぶる
不自由らしく見えるが、これは
海浜の
泥砂の上に落ちている
貝殻を起こして、その下の虫を
探したりするにはかえって具合いがよろしい。
 窓嘴鶴
外国産
窓嘴鶴
外国産の
鶴の
類には、口を
閉じても上下の
嘴がよく
締まらず、その間に大きな
窓のあいているものがあるが、これも
蛤などをくわえるにはあるいは
便利かも知れぬ。すべて動物にはそれぞれ
専門の
餌があって、口の
構造はそれを取るに
適するようになっているから、なかなか他の
習性の
異なったものが、急に
競争に
加わろうとしても
困難である。
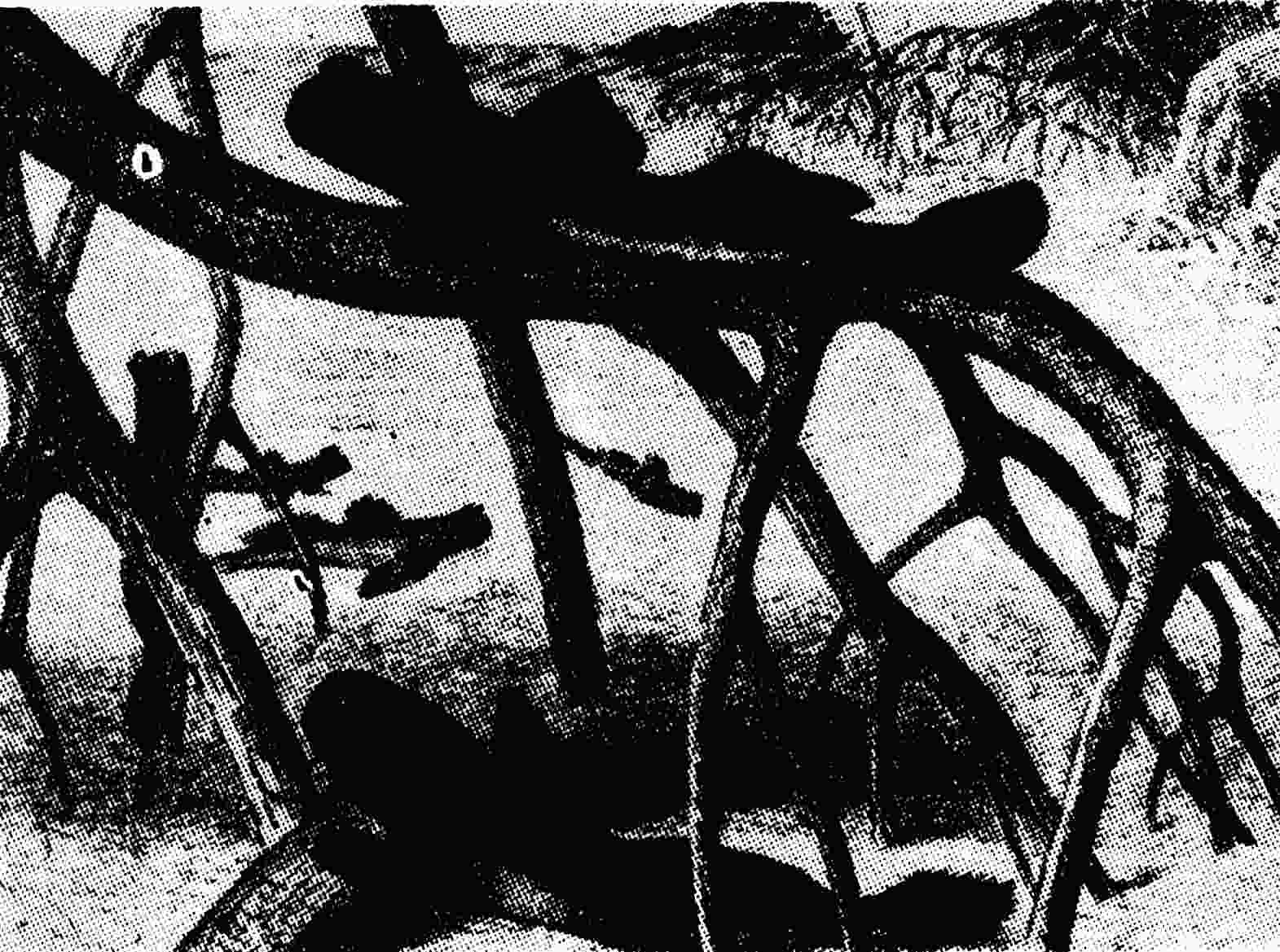 とびはぜ
魚類
とびはぜ
魚類はすべて水中に住むものゆえ、昔からとうていできぬことを「木によって魚を
求むるごとし」と言うているが、よく調べて見ると、魚でありながら
陸上に出るものが全くないこともない。
熱帯地方から
東京湾あたりまでの海岸に住む「とびはぜ」という小さな魚があるが、これなどは
潮の引いたときは、
砂や
泥の
乾いた上を何時間も
蛙のごとくにはねまわって、
柔かい虫を拾うて食うている。
比較的大きな
眼玉が頭の
頂上に
並んでいるので、
容貌までがいくぶんか
蛙めいて見える。
 木登り魚
木登り魚
さらに
驚くべきは
印度地方に
産する「きのぼりうお」という
淡水魚で、形はやや
鮒に
似て大きさは
一尺(注:30cm)近くにもなるが、
鰓の
仕掛けが
普通の魚とは少しく
違うので、水から出ても
容易には死なず、
鰓蓋の外面にある小さな
鉤を用いて
樹の
幹を登ることができる。されば東
印度まで行けば、「木によって魚を
求める」という語は、物事のできぬたとえとしては通用せぬ。
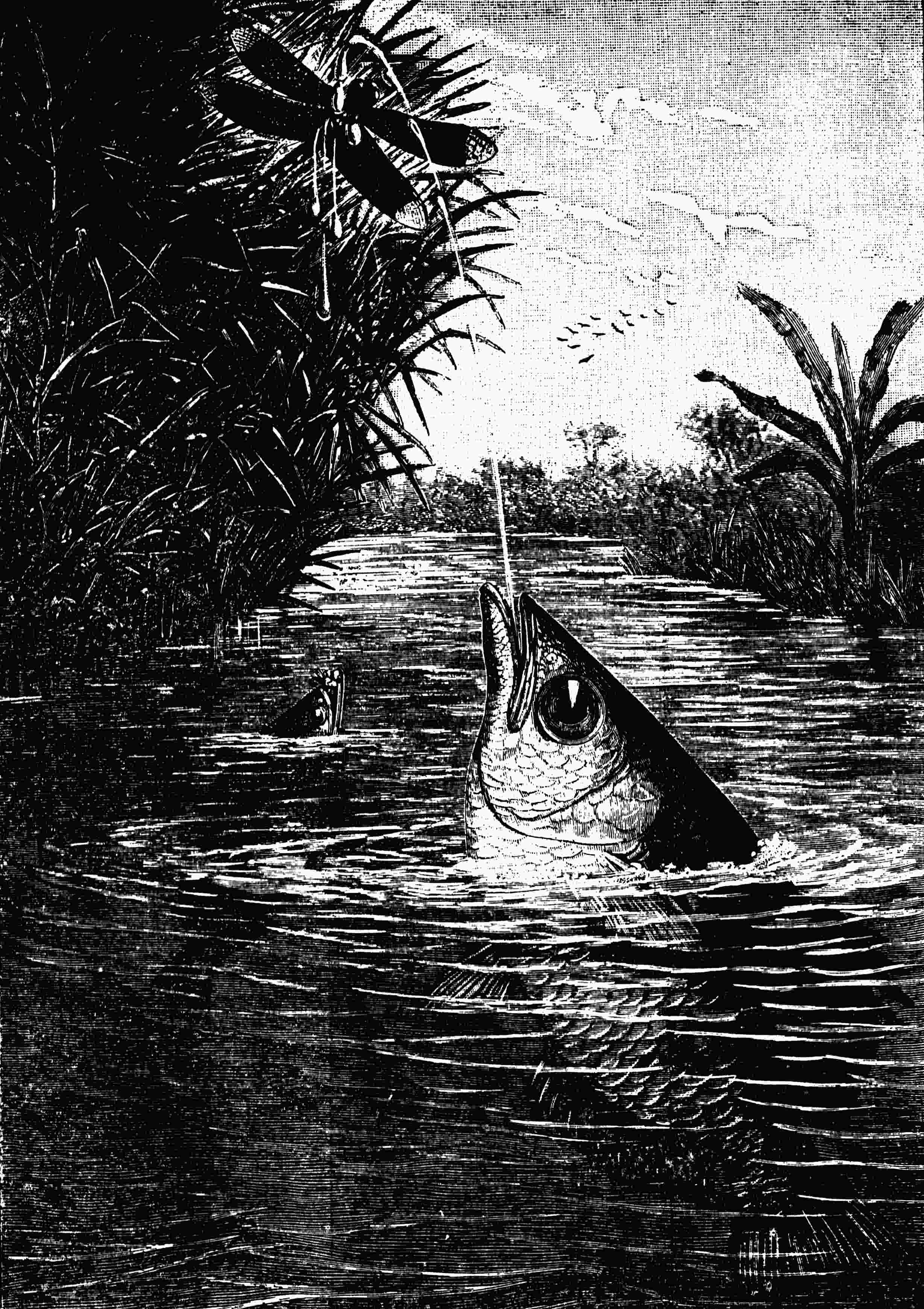
みずたまうお
長さ5,6寸(注:15~18cm)の淡水魚なり。東印度の河に産す。水上を飛ぶ昆虫を狙い口より一滴の水を吹き当てこれを落として捕え食う。
なお東
印度にに「
水玉魚」というおもしろい
淡水魚がいる。これは身長
五六寸(注:15~18cm)の
扁平な魚であるが、自身は水の中にいながら
巧みに空中の虫を
捕えて食う。その
方法は、まず水面まで
浮かび出で、口を水面上に
突き出して、
飛んでいる
昆虫をねらって
一滴の水玉を
吹き当てるのである。当てられた虫は水玉とともに水中へ落ちてたちまち食われてしまう。「あんこう」の
類は海の
底にいて、
上顎の前方から
突出している
鉤竿のごときものを動かし、
巧みに小さな
魚類を
誘うて急にこれを
丸呑みにするが、数百
尋(注: 1尋=約1.8m)の深い
底で年中日光の
達せぬ暗黒なところにいる「あんこう」の
類には、
鉤竿の先が光ってあたかも
提燈を
差出しているごときものもある。みな口が
非常に大きくて、口を開けば直ちに
胃の
奥までが見えるかと思うほどであるが、深海の
底に
棲む魚にはこれよりもはるかに口の大きな
種類がいくらもある。
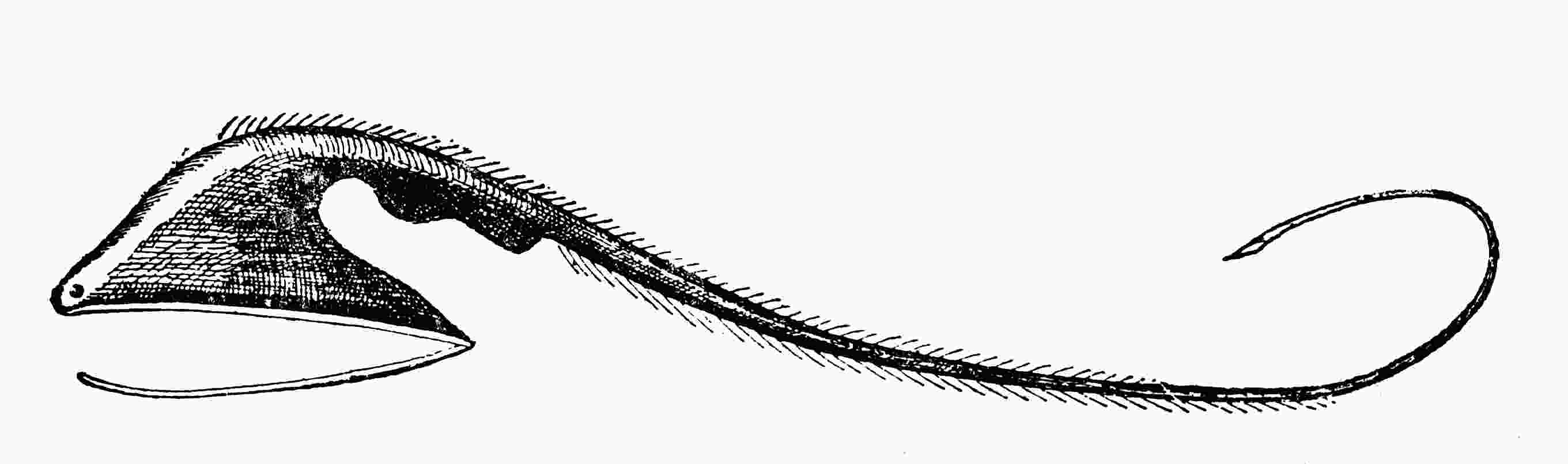 おおのどうお
おおのどうお
ここに図をかかげた「おおのどうお」と
称するものは、身体はほとんど全部口であるともいうべきほどで、口だけを切り去ったら、ただ細長い
尾だけとなって身体は何ほども
残らぬ。ただし二千
尋(注:9000m)
以上の深い海に住む魚であるゆえ、
餌を
求めるにあたって
何故かような
驚くべく大きな口が
必要であるか、その
習性の
詳しいことはわからぬ。
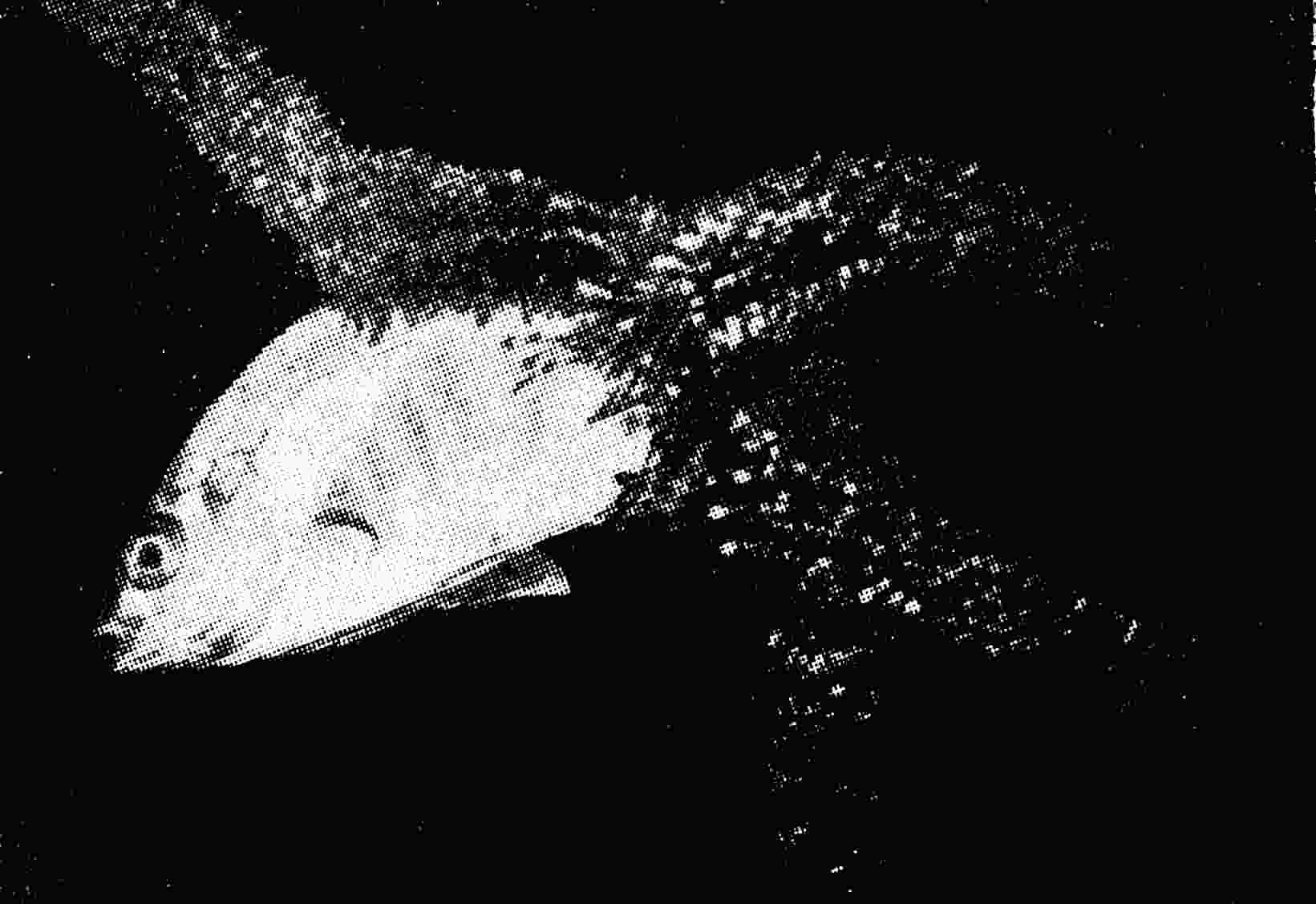 「ひとで」魚を食う
「ひとで」魚を食う
進んで
餌を
求める動物の
例としてなお一つ「ひとで」
類の
餌の食い方を
述べよう。「ひとで」
類は
浅い海の
底に住む星形の動物で、どこの国でも「海の星」という名がつけてあるが、体にはただ
裏と表との
別があるだけで前も後もない。
裏からはたくさん細長い
管状の足を出し、足をのばして何かに足の先の
吸盤で
吸いつき、次に足を
縮めて身体をそのほうへ引きずって
漸々進行する。
好んで
貝類を食するから、かきや
真珠の
養殖場には
大害をなすものであるが、その食い方を見るに、小さな貝ならば体の
裏面の中央にある口で
丸呑みにし、口にはいらぬような大きな貝ならば、まず五本の
腕でこれを
抱え、
胃を
裏返しにして口より出し、これをもって貝を
包んでその肉を
溶かして
吸い入れるのである。「ひとで」が
暫時抱えていた貝をとって見ると、
貝殻はもとのままで少しも
傷はないが、内はすでに
空虚になっている。海水の中に「ひとで」と魚とをいっしょに
飼うておくと、
往々「ひとで」が魚を食うことがあるが、その時も同様な食い方をする。
以上かかげた
若干の
例によってもわかるとおり、進んで
餌を
求めることは大多数の動物の行なうところで、その
方法にいたっては、世人のつねに
見慣れているもののほかにずいぶん意表に出た食いようをするものがある。しこうして
如何なる場合にも、同様な
方法で食うている
競争者がたくさんにあるからけっして楽はできぬ。
動物は
餌を見つけしだい直ちに食うのがつねであるが、中には後に食うために食物を
貯えておくものもある。
猿が
人参を'
頬の内に
貯え、
鳩が豆を
餌嚢の内にため、
駱駝が水を
胃の内にためることは人の知るとおりであるが、かように身体内に
貯えるのでなく、
別に
巣の内などに食物を
貯え
込んでおく
種類も少なくない。
 もぐらの巣
例
もぐらの巣
例えば「もぐら」のごときはつねに「みみず」を食うているが、地中で「みみず」を見つけるごとに直ちに食うのではなく、多くはこれを
巣の内に
貯えておく。しこうして
達者なままでおけば
逃げ去るおそれがあり、
殺してしまえばたちまち
腐る心配があるが、「もぐら」は「みみず」の頭の
尖端だけを食い切って生かしておくゆえ、「みみず」は
逃げることもできず
腐りもせず、生きたままで長く
巣の内に
貯えられ、
必要に
応じて
一匹ずつ食用に
供せられる。また
畠鼠の
類はあぜ道などの土中に
巣をつくり、米や麦の
穂を
摘み来たってその中に
貯えておくが、
猿が
人参を
狭い'
頬嚢に入れるのと
違い、いくらでも
貯えられるゆえ、この
鼠が
繁殖すると農家の
収穫はいちじるしく
減ずる。はなはだしい時はほとんど
収穫がないほどになるが、かかるときは
毒を
混じた
団子を
蒔いたり、
鼠に
伝染病を起こさせる
黴菌の
種を
散らしたり、村中
大騒ぎをしてその
撲滅を
図っている。「もず」は
蛙や「いなご」を
捕えると、これを
尖った
枝に
差し通しておくが、
田舎道を
散歩するといくらもそのひからびたのを見る。昔から「もず」の「はやにえ」というて歌にまで
詠んだものはこれである。
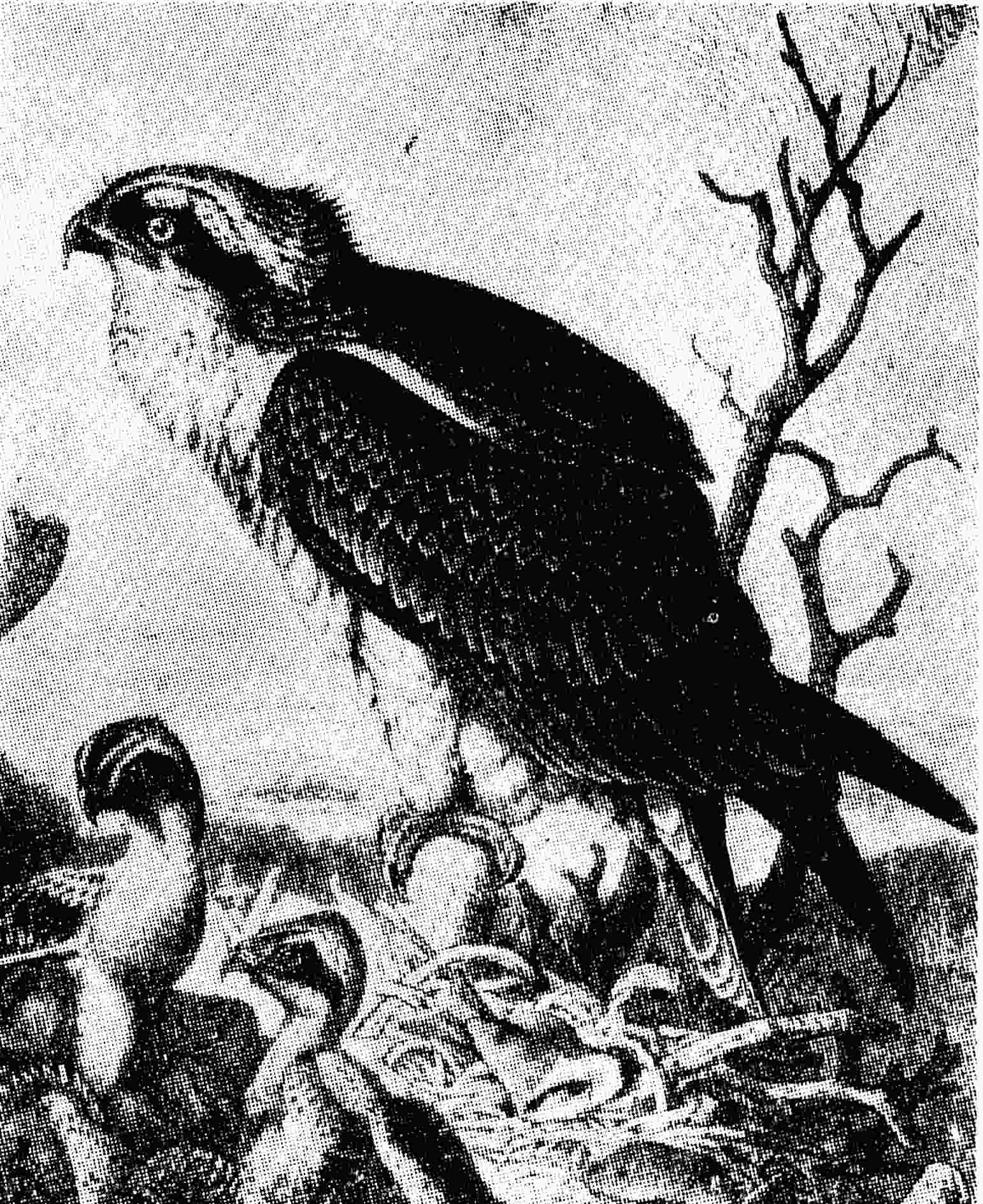 みさご
みさご
また
海辺に住んで魚を
常食とする「みさご」という
鷹は、
捕えた魚を岩の上の
水溜りに入れたままで
捨てておくことがしばしばあるが、
漁師はこれを「みさご
鮓」と名づけている。これらも
不完全ながら食物を
貯える
例である。その他、
蜜蜂が
巣の中に
蜜を
貯え、「じが
蜂」が
穴の中に「くも」を
貯えるなど、
類似の
例はいくらもある。
特に
穀物を
貯える
蟻の
類になると、雨の
降った後に
穀粒を地上に
並べ、日光に当てて一度
芽を出させ、次にその
芽を
噛み切って
萌しを
再び
巣の内に運んで
貯蔵するなど、実に
驚くべきことをする。しかし
以上述べたところはみな、後日の用意に食物を
貯えておくというだけで、
特に食物をつくるのではない。
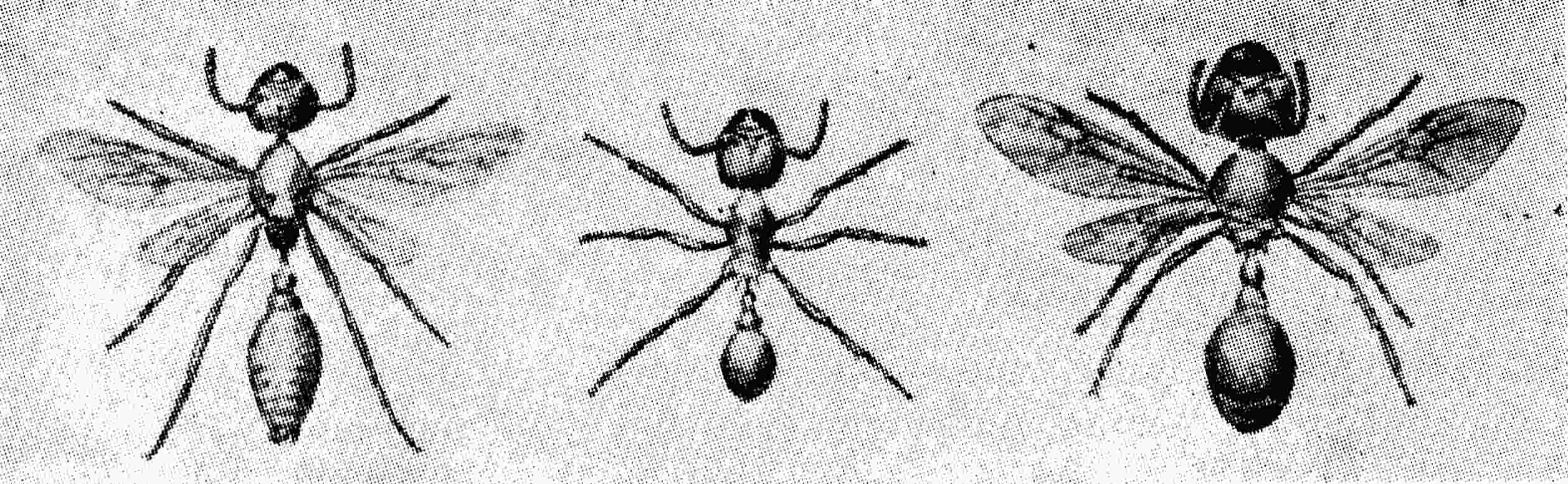 収穫蟻
収穫蟻
アメリカ
合衆国のテキサス
辺に
棲む
蟻には
一種、
収穫蟻と名づけるものがある。これは昔の
博物書には、自身にわざわざ
種子を
蒔いて、
絶えずよく世話をしておわりに
刈り入れまですると書いてあったために、
非常に有名になった。
蟻がわざわざ
種子を
蒔くということは真実でないらしいが、
一種の草だけを
保護し、他の
雑草を
除いて、おわりに
熟して落ちた
種を拾い集めて
巣の内に
貯えることは事実である。

収穫蟻
中央にあるは地下の蟻の巣に入るべき入口。列をなして多数に匍いいるは収穫蟻の働蟻。周囲の草は「蟻の米」と名づくる禾本科の植物。産地は北アメリカの中部。
この
蟻も
普通の
蟻と同じく地中に
巣をつくるが、
巣の入口の
孔を中心としておよそ
一坪か
二坪かの円形の地面には、ただ
一種のいつも定まった草のみが生えていて、他の草の
混っていないところを見ると、
如何にも
蟻がわざわざその草の
種を
蒔いたごとくに見えるが、これはおそらく落ちた
種から生えるのであろう。しこうしてこの草は米や麦と同じく
禾本科の植物で、
茎の先に
穂ができて細かい
粒状の実がなるゆえ、その地方では「
蟻の米」と
呼んでいる。この
蟻のことはわが国の小学読本にも出ているが、
確かに農業を
営むものというても
差支えはない。
 葉切蟻
葉切蟻
なお南アメリカの
熱帯地方には
菌を
培養する
蟻がある。これは葉切り
蟻と名づける大形の
蟻で、
巣は地面の下につくるが、つねに多数で出歩いて
樹に登り、
鋭い
顎で葉を
噛み切り、
一匹ごとに
一枚の葉をくわえて、あたかも
日傘でもさしたごとき
体裁で
巣に帰ってくる。
 蟻の菌畠
蟻の菌畠
この事はだれにもいちじるしく目に
触れるゆえ、昔は何のためかと大なる
疑問であったが、その後の
周到なる研究の
結果によると、この葉は
巣に持ち帰られてからさらに他の
働き
蟻によって
極めて細かく
噛み
砕かれ、
菌を
栽培するための
肥料に用いられることが明らかに知れた。
巣にはところどころに
直径一尺(注:30cm)
以上もある大きな部屋があって、細い
隧道(注:トンネル)で
互いに
連絡し、部屋の内では
働き
蟻が葉を
噛み
砕いたもので
畠をつくり、そこへ
一種の
菌を
繁殖させる。この
菌は
松蕈椎蕈などと同じような
傘のできる
類であるが、
蟻の
巣の中では
働き
蟻がしじゅう世話しているために、
傘状にはならずただ細い糸のごとき根ばかりが
茂って、
蟻の
餌となるのである。
 白蟻の菌畠
白蟻
白蟻の菌畠
白蟻にも
菌をつくる
種類がいくらもある。
白蟻というと
素人はやはり
蟻の
一種かと思うが、
昆虫学上から見ると
蟻と
白蟻とは全く
別の
類ではなはだ
縁の遠いものである。しかしながら両方ともに数万も数十万も集まって社会をつくって生活するゆえ、
習性には
相似たところが少なくない。
菌の
培養のごときもその一つで、
白蟻の
巣においてもほぼ同様のことが行なわれている。ただし
菌の
種類も、その作りようもいささか
蟻とは
違い、また
白蟻の
種族によっても
違う。
白蟻が
菌を
養う
畠は、
蟻のごとくに木の葉を
噛み
砕いたものではなく、
白蟻自身の
糞であるが、
白蟻は主として
木材を食するものゆえ、その
糞は
木材を細かく
砕いたごときものである。
木材はまことに
滋養物に
乏しいものであるが、
白蟻の
糞の
畠に
繁茂する
菌は
多量の
窒素を
含み
滋養分に
富んでいるゆえ、
白蟻のためにははなはだ大切な
食料である。
蟻のほうはわざわざ木の葉を
噛み
砕いて
畠をつくるのであるから、真に
菌を
培養することが
確かであるが、
白蟻のほうは自身の
糞の
塊に
菌が
繁茂しているのであるから、あるいは
自然に生ずるものではなかろうかとの
疑いも起こるが、
働き
蟻を遠ざけておくとたちまち部屋中が
黴だらけになるところを見ると、
白蟻の場合においても、やはり
働き
蟻の
不断の
努力によって、
菌がつねに
適度に
培養せられていることが
確かに知れる。これらはいずれも後に
餌となるべきものを、前もって作るのであるから、明らかに
一種の農業である。
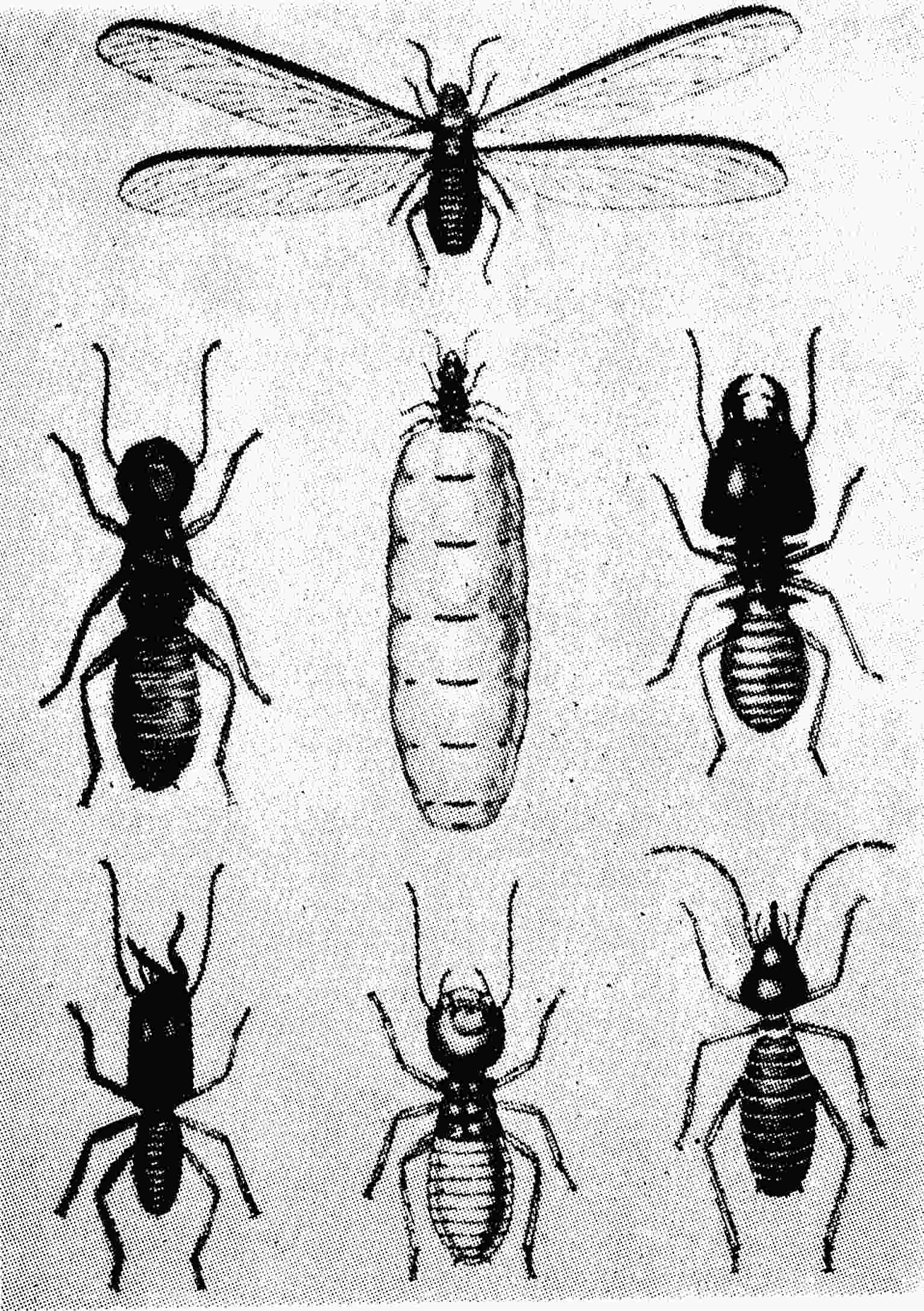
白蟻
一種類の中に見られる種々形態の異なった個体を示す
樹木の
幹の中に生活する小さな
甲虫の中にも
菌を
利用するものがある。「ゴム」、茶、
甘蔗、
蜜柑など
熱帯地方の有用植物は、
幹を食う小
甲虫のために年々
大害を受けるが、これらの
虫類のつくった細い
随道の内面には、ところどころに
微細な
菌類がたくさんに生じ、
甲虫は少しずつこれを食うて生きている。これなども
不完全ながら
蟻や
白蟻が
菌を作るのに
比較することができよう。農業などのごとき、やや遠き
未来の
成功を予期して
現在の
労働に
従事するということは、生物界にけっして多くはないが、しかしその
皆無でないことは
以上の
数例によって
確かに知ることができる。
動物には植物を食うものと動物を食うものとがあるが、いずれにしても食われただけの
餌は死んで消化せられるのであるゆえ、すべて
殺されるのであるが、植物は
泣きも
叫びもせぬため
殺して食うという感じを起こさぬ。これに反して、動物のほうは、
攻められれば多少
抵抗し、
傷つけられれば
痛みの声を発し、力が
尽きれば悲しく鳴くなど、いよいよ
殺され食われてしまうまで、
一刻一刻と死に近づく様子が
如何にも
憐れに見える。しこうして植物を食う動物と、動物を食う動物とはいずれが多いかというと、
陸上では植物が
繁茂しているために、植物を食う動物も多数にあるが、一度海岸を
離れて大洋へ出て見ると、ほとんどことごとく肉食動物ばかりで、植物を食するものというてはわずかに表面に
浮かんでいる
微細な
種類のみにすぎぬ。されば
殺して食うことは動物生活のつねであって、前に
述べたとどまって
餌を待つものも、進んで
餌を
求めるものも、
結局は
殺して食うのである。ただし同じく
殺して食うという中にも、相手と
戦い、その
抵抗に打ち勝って
殺すものもあれば、
無抵抗の弱い者を
探して食うものもあり、
殺してから食うものもあれば、食うてから
殺すものもあり、また中には
死骸を
求めて食うものなどもあって、
種属が
違えば、
殺しようや食いようにも
種々相異なるところがある。
獅子、
虎、
鷲、
鷹などのようないわゆる
猛獣や
猛禽の
類は、あくまで強い
筋肉と
鋭い
爪牙とをもって
比較的大きな
餌を引き
裂いて
殺すが、「たこ」、「いか」の
類、「えび」、「かに」の
類なども、同様の
手段で生きた
餌を引き
裂いて食う。
昆虫の中でも
益虫と名づけて他の
虫類を食う
種類は、多くは
顎の力によって
餌を
噛み
殺すものである。「とんぼ」などはその
一例で、
盛んに他の
昆虫類を生きたまま
捕えて食うが、それがため
養蜂家に対してははなはだしく
害を
与える。「げじげじ」なども夜間
燈火の近くに
匐うて来て
蛾の来るのを待ち受け、多数の長い足で
蛾の
翅を
押さえて動かさず、たちまち頭から
噛み
初めるが、その
猛烈なることは、
虎が羊を食うのと少しも
違わぬ。
猫が
鼠を
捕り、
鷹が
雀を
捕ることはだれも知るとおりで、このぐらいに
互いの力が
違うと
容易に食われてしまうが、動物には
餌を
殺すにあたって何か
特殊の
手段を用いるものもある。そのもっとも
普通なのは
毒をもって
攻めることで、
獣や鳥には
毒のあるものは少ないが、
蛇類にははげしい
毒を有するものがたくさんにあり、
熱帯地方では年々そのために命を落とす人間が何万もある。
毒蛇が
餌を食うときにはまず口を開いて
上顎の
前端にある長い
牙を直立させ、これで
速やかに打って
傷口に
毒液を
注射するのであるが、その運動も速いが
毒のきくのも実に
速やかなもので、打たれたかと思うと
餌になる動物はたちまち
麻痺を起こし、
腰が
抜けて動けなくなってしまう。
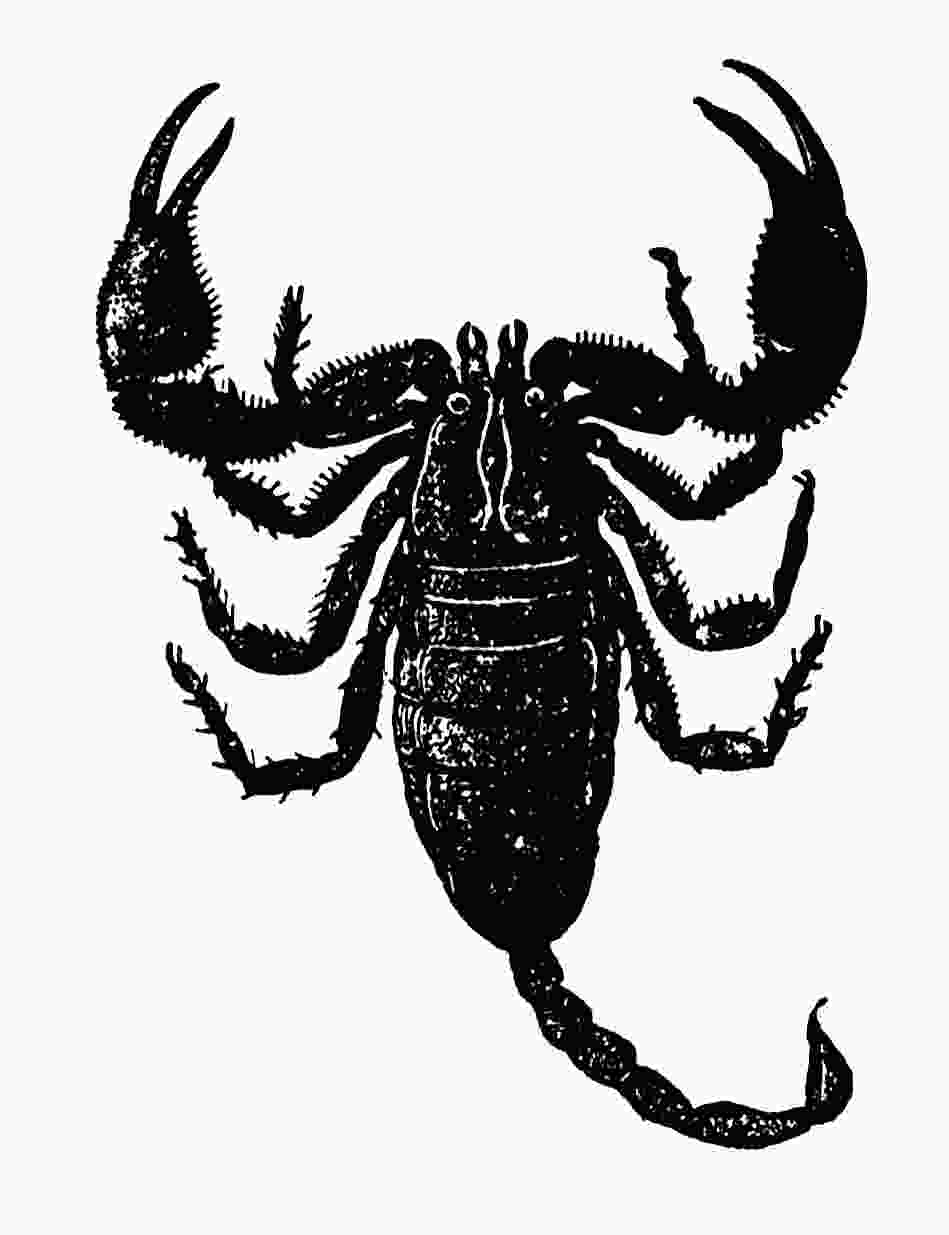 さそり
さそり
「くも」、「むかで」にさされると
毒のためにはげしく
痛むが、「さそり」の
尾の先の
毒針はさらに
恐ろしい。なお
海産動物にも
有毒のものはいくらあるか知れぬ。
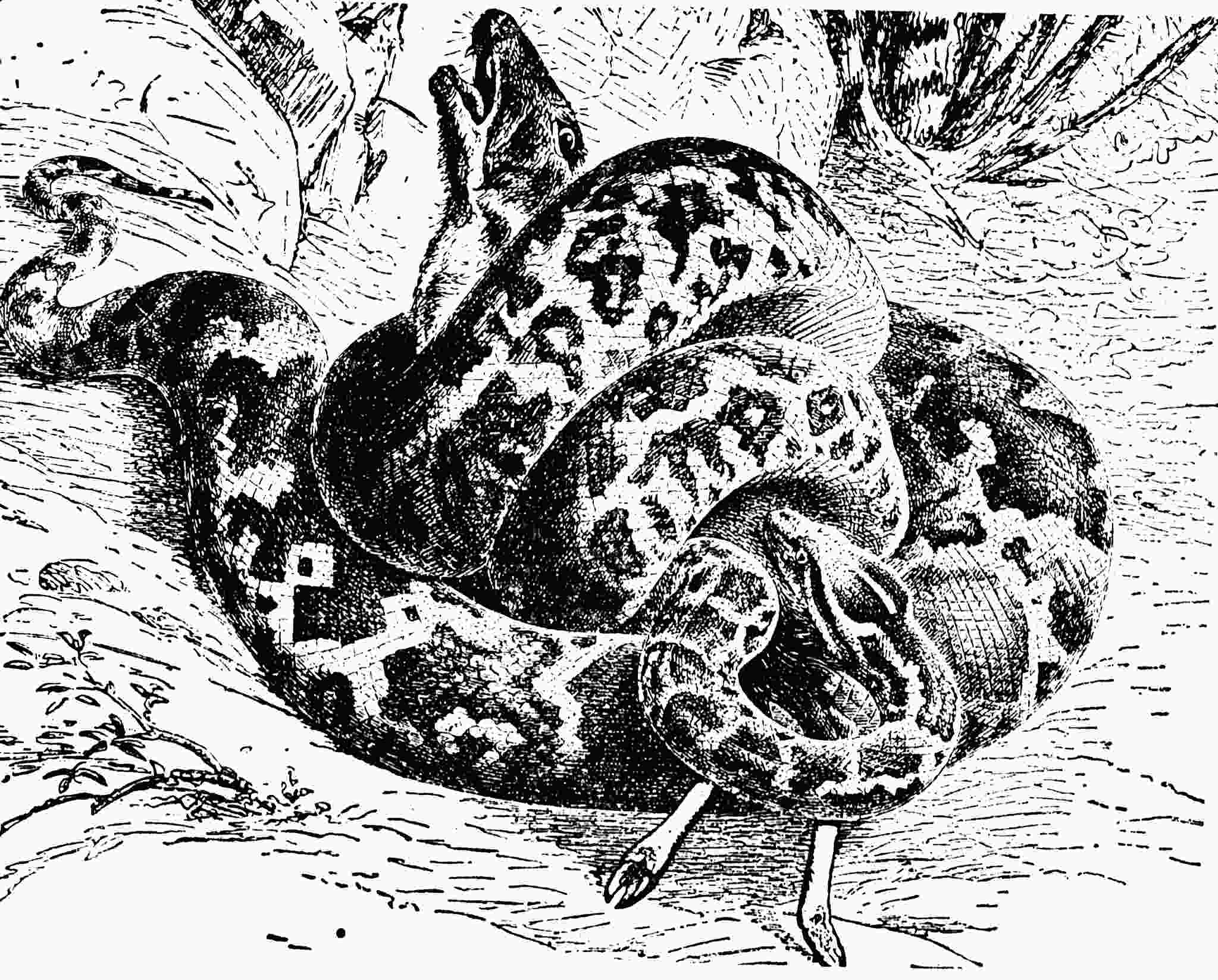 大蛇うさぎを殺す
大蛇うさぎを殺す
大きな
蛇が
餌を
殺すには長い身体を
巻きつけ、
順々に
締めて
窒息させ、さらに
骨片なども
折れるまで
圧縮する。
熱帯地方に
産する
蛇には、長さが四間(注:7.2m)も五間(注:9m)もあるものがあるが、かような
大蛇はずいぶん馬や牛でも
締め
殺すことができる。また
鰐などは
陸上の動物が水を
呑みに来るところを水中で待っていて、急にくわえて水中に引き入れ
溺れさせてからこれを食うのである。
餌となる動物を生きたまま引き
裂いて食う動物は、
自然性質も
残忍で、
単に引き
裂くことをたのしむごとくに見える。「いるか」の
類はつねに「いか」を
食とするが、「いるか」が「いか」の
群を見つけると、食えるだけこれを食うのみならず、食われぬものもみな
噛み
殺す。かような
跡を船でとおると、半分に
噛み切られ死んでいる「いか」が
無数に
浮いている。これは「いるか」に
限らず他の
猛獣類にも多少その
傾きがあるように見える。
餌を
噛まずに
丸呑みにするものには生きたまま食うものが多い。
鶴や
鷺が「どじょう」を食うのもその
例であるが、もっともいちじるしいのは
蛇である。
蛇が
蛙を
呑むところを見るに、まず後足を口にくわえ、次に体の
後端から
呑み
初めて
漸々呑み終わるが、
蛙はなお生きているゆえ
強いて
蛇に
吐かせると、
蛙はそのままはねて
逃げて行く。
蛇が自身の
直径の数倍もある大きな動物を
丸呑みにするのも
驚くべきことであるが、深海の
魚類などには、身体の大きさに
比してさらに大きなものを
呑むものがある。
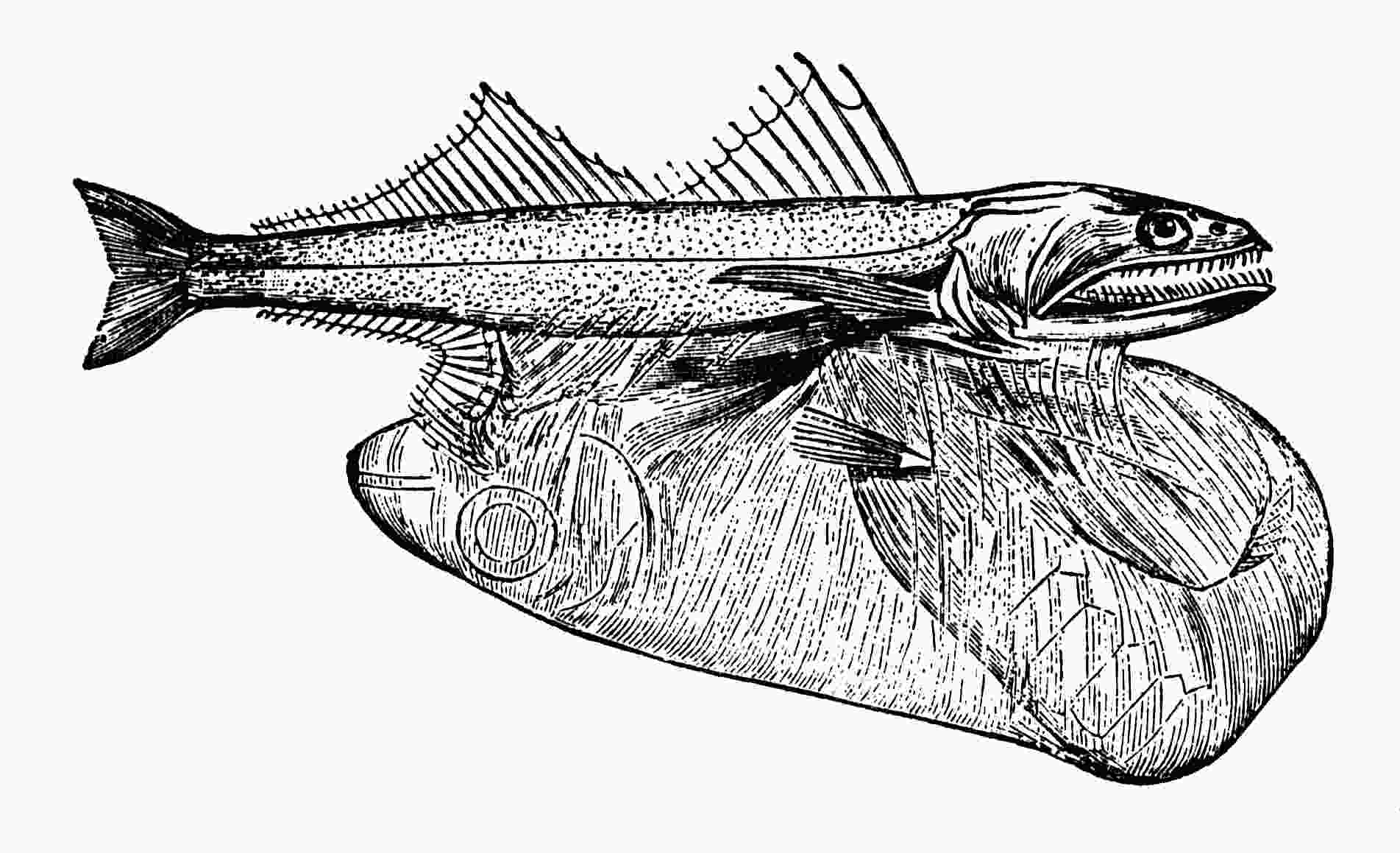
魚をのんだ魚
呑まれた魚の尾鰭の上に重なって見えるは呑んだ魚の腹びれ
ここに図をかかげた魚などは自身より大きな魚を
呑んだので、
呑まれた魚は二つに曲がって、ようやく
呑んだ魚の
胃の中に
収まっている。
肉食動物の中には、自身で
餌を
殺さずに
死骸の落ちているのを
探して食うて歩く
種類もある。エジプトの
金字塔の絵などに、よく
虎と
狼との中間のような
猛獣の画いてあることがあるが、これは「ヒエナ」という
獣で、つねに
屍体を
求めて食物とする。
 はげわし
はげわし
鳥の中では「はげわし」と
称するものが
屍体の
腐りかかったのを食うので有名である。この
類の鳥は日本の内地には
一種もいないが、
朝鮮からアジア
大陸、ヨーロッパ
大陸辺にはたくさんいる。
頸はやや長く、頭と
頸とは
露出して、あたかも
坊主のごとくであるが、馬や牛の
死骸でもあるとたちまちそこへ集まって来て、皮を
噛い
破り、
腹の中へ
頸を
突き
込んで
腐った
腸や
腎などをむさぼり食する。
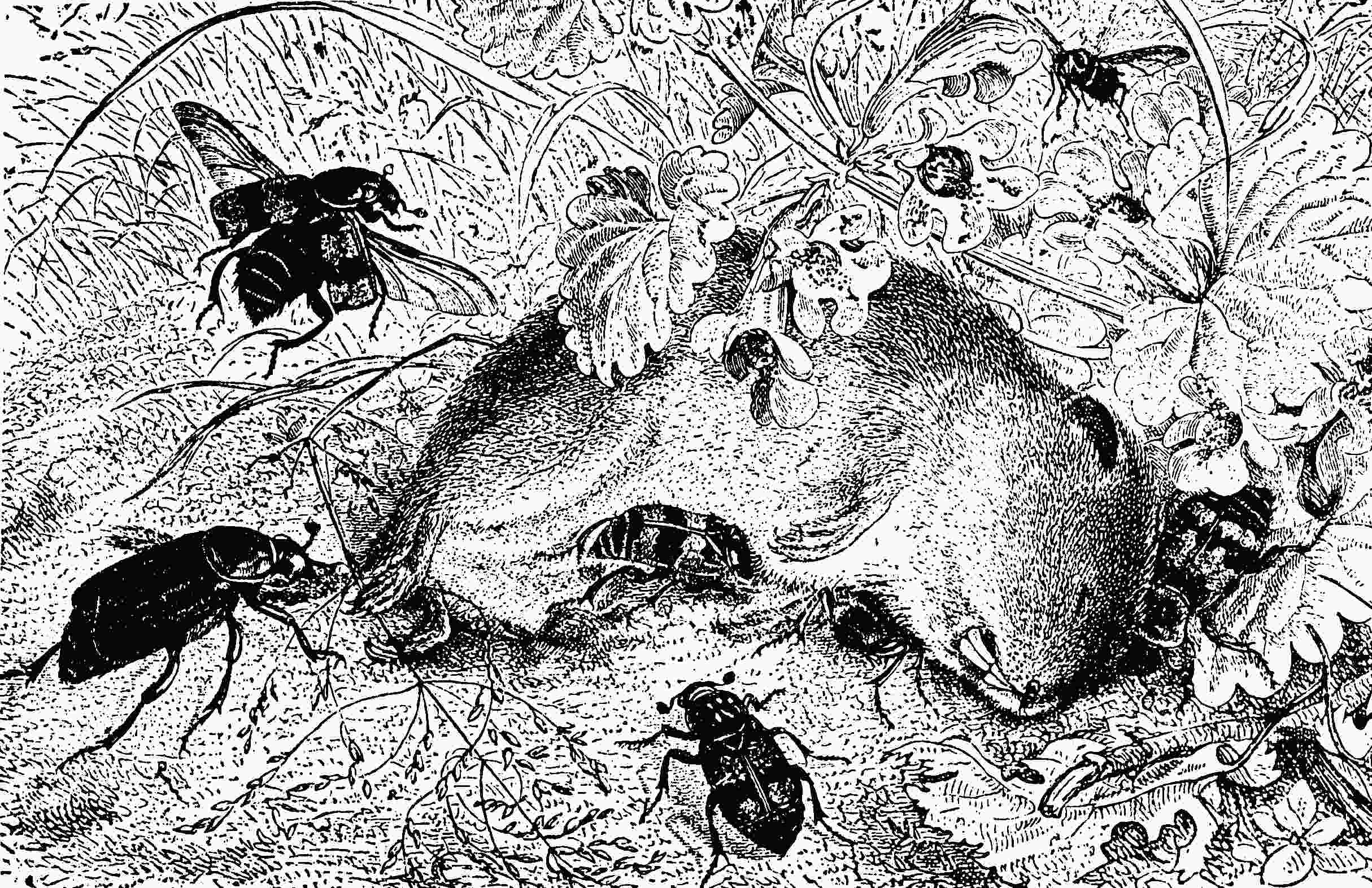 しでむし
昆虫
しでむし
昆虫の中に「しでむし」というのがあるが、これなども
屍体を食うのが
専門で、
鼠や「もぐら」の
屍体でも見つけると、そのところの土を
掘ってしまいに土中に
埋めてしまい、後にこれを食うのである。海岸の岩の上などにたくさんに活発に走りまわっている「ふなむし」も、
好んで
屍体を食うもので、
海浜に打ち上げられた動物の
屍骸はたちまちのうちにこれに食いつくされ、ただ
骨骼のみが
綺麗に後に
残る。
血は動物体の大切なもので、血を
失うては命は
保てぬ。食物が消化せられて
滋養分だけが血の方へ
吸収せられるのであるから、血はほとんど動物体の
精分を集めたものというてよろしい。動物を全部食えば、毛、
爪、
骨などのごとき
不消化物もともに
消化器の内を
通過するが、血にはかような
滓がない。それゆえもし血だけを
吸いとってしまえば、
遺骸は
捨て去っても、あまり
惜しくはない。肉食する動物の中には
実際餌を
捕えると、血だけを
吸うて
残りは
捨てて
顧みず、その肉を食う手間でむしろ第二の
餌を
捕えてその血を
吸おうとする
贅沢なものがある。「いたち」などはその
一例で、
鶏を
捕えて
殺しても、ただ、血を
吸うだけで肉はそのままのこしてある。「くも」が「はえ」を
捕えてもただ血を
吸うて皮を
捨てる。南アメリカの「こうもり」にも
生血を
吸うとて
評判の高いものがある。血を十分に
吸うてしまえば、
吸われた動物は、むろん死ぬにきまっているが、
吸う動物が小さくて、
吸われる動物が大きな場合には、わずかに血の一部分を
吸うだけであるゆえ、
吸われたほうは死ぬにいたらず、
吸うたほうだけが十分に
滋養分を
得る。「のみ」、
蚊、「だに」、「しらみ」などはかような
例で、つねに相手に少しく
迷惑をかけるだけで、これを
殺さずにしばしば生血を
吸うて生活している。
蛭などは毎回やや多くの血を
吸うゆえ、血をとる
療法として昔から医者に用いられた。広く動物界を
見渡すと、
陸上のものにも、
海産のものにも、他の生血を
吸うて生きているものはなおたくさんにある。金魚や
鯉の表面に
吸いつく「ちょう」、
鮫の
皮膚に
付着している「さめじらみ」、そのほか
普通には知られていない
種類がすこぶる多い。しこうして血を
吸うには相手の動物の
皮膚に
傷をつけ、もしくは細かい
孔を
穿つことが
必要であるから、血を
吸う動物にはむろんそれだけの
仕掛けは
備わってある。

ひるの体の前端
を腹面より切り開きて3個の顎を示す
例えば、医用
蛭には口の中に
三個の小さな
円鋸状の
顎があり、これを用いて人の
皮膚に
傷をつける。それゆえ
蛭に
吸われた
跡を
虫眼鏡で見ると、あたかも三つ目
錐で
突いたごとき形の切れ目がある。
貝類や
魚類の血を
吸う
蛭には口の中に細長い
管があり、これを口から
延ばし出して、相手の
皮膚に
差し入れる。
蚊の口は細い
針をたばねたごとく、「のみ」、「なんきんむし」の口は医者の用いる
注射針のごとくで、いずれも
尖端を
皮膚に
差し
込み、
咽喉の
筋肉をポンプのごとくに
働かせて
血液を
吸い
込む。
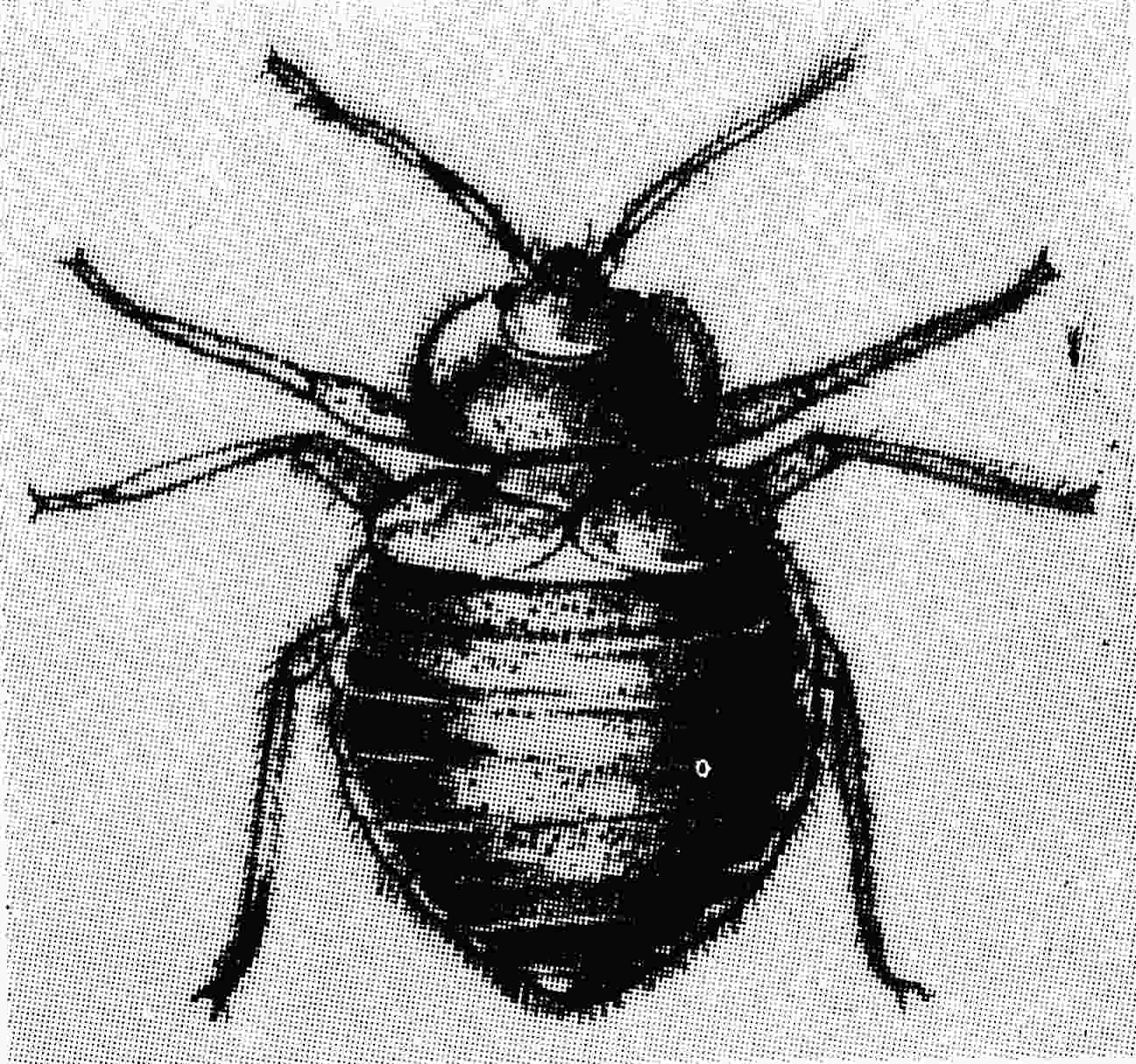 南京虫
南京虫
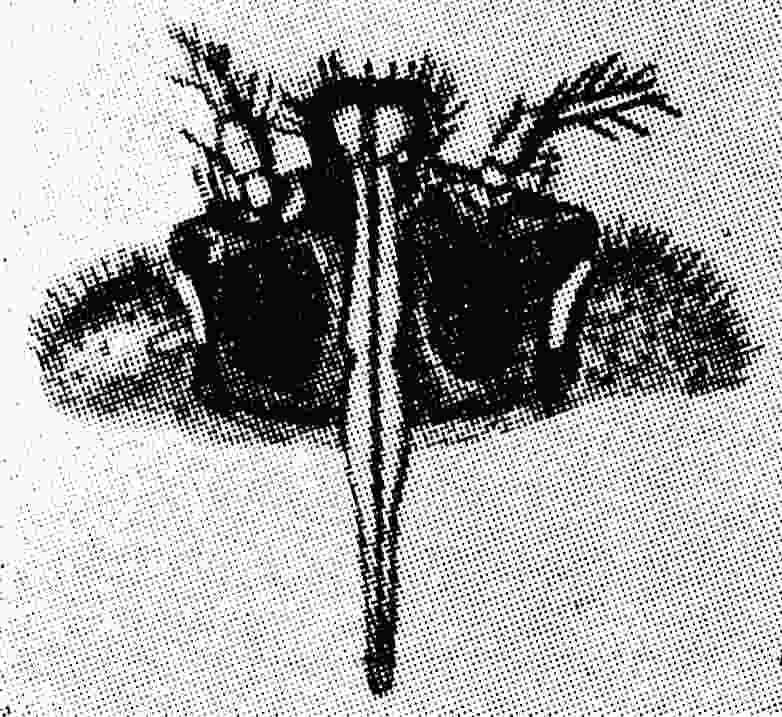 南京虫の口
南京虫の口
「しらみ」、「だに」などの口の
構造もほぼ同様である。かような口の
構造は血を
吸うには
至極妙であるが、その代わりほかの食物を食うには全く
適せぬ。およそ何事によらず全く
専門的に
発達してしまうと、それ
以外にはいっこう役に立たぬようになるが、動物の口の
構造なども
或る
一種の食い方だけに
都合のよいように十分
発達すると、すべてほかの食い方にはとうてい間に合わなくなる。それゆえ、血を
吸うて生きている動物は、血を
吸う相手のない時は、たとい
眼の前にほかの食物がどれほどあっても食うことができぬのがつねであり、したがって一度血を
吸う機会に
遇うた時に
腹いっぱいに血を
吸い
込んでおく
必要がある。血を
吸うた
蚊をたたき
殺すと、身体の大きさに
似合わぬほどの
多量の血の出ることは人の知るとおりであるが、
蛭類のごときも、身体の
構造はあたかも血をいれるための
嚢のごとくで、頭から
尻までがほとんど全部
胃嚢であると言える。
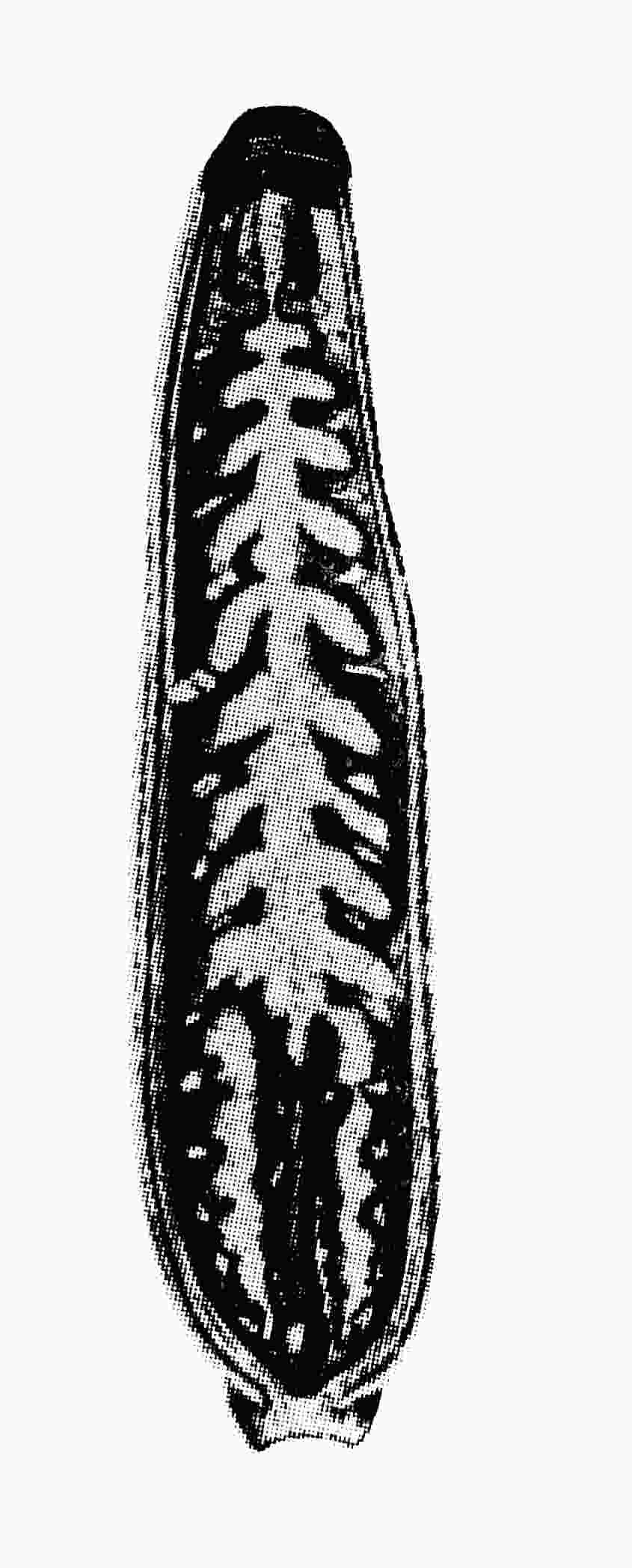
ひるの解剖図
胃の全身に満ちたるを示す
身体がかくのごとくであるのみならず、
性質もこれに
伴うて血を
吸い
初めると、
腹いっぱいに
吸いためるまではけっして口を
離さぬ。ヨーロッパ
産の医用
蛭は日本
産のものよりははるかに大きくておよそ五倍も多く血を
吸うが、医者がこれを用いる時には
尻のほうを切っておく。かくすると
吸い入れた血は
尻の切れ口から
[#「口から」は底本では「から口」]体外へ流れ出るゆえ、いつまでたっても
腹いっぱいにならず、
蛭はいつまででも血を
吸うている。
動物の中には植物の
液汁を
吸うて生活するものがあるが、植物の
液汁はやはり
滋養分を体内に
循環させるもので、あたかも動物の
血液に相当する。それゆえ、これを
吸う動物の口の
構造は血を
吸う動物と同じようで、細長い
管状になっているものが多い。
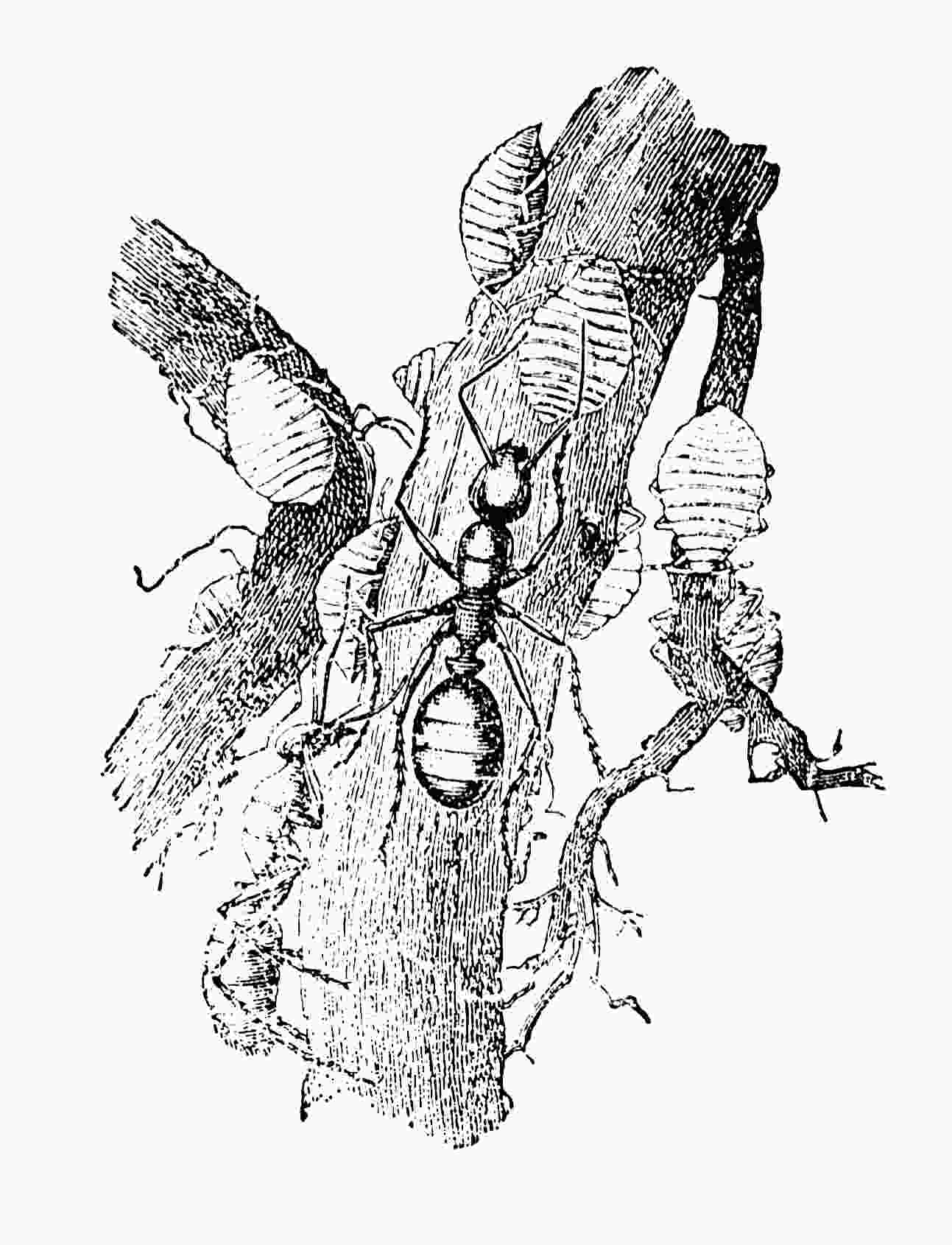 ありまき
ありまき
「ばら」や
菊の
若芽に集まる「ありまき」、
稲田に
大害を
与える「うんか」の
類はその
例であるが、かような
昆虫の
種類はすこぶる多くて、
陸上の植物には虫に
液汁を
吸われぬものがほとんど
一種もないくらいである。植物は
季節に
応じて
盛んに
繁茂しかつ、
固定して動かぬものゆえ、その
液汁を
吸う虫は実に十分な
滋養分を
控え、あたかも
無尽蔵の
食料を
貯えたごとくで生活は
極めて
安楽らしく見えるが、これまたけっしてさようなわけでない。
何故というに、
滋養分が十分にあれば
繁殖も
盛んになるのが動物のつねで、「ありまき」でも「うんか」でも、たちまちのうちに
非常に
殖えるが、数が多くなると生活が直ちに
困難になる。
一匹ずつでは植物にいちじるしい
害を
与えぬ小虫でも、多数になれば
液汁を
吸われる植物は
枯れてしまうが、植物が
枯れれば
液汁の
供給が
絶えるから
昆虫も
生存ができなくなる。またかような
昆虫が
殖えれば、これを
餌としている動物も同じく
殖えて、ややもすればこれを食い
尽くそうとする
傾きが生ずる。なおその他にも
種々のことが生ずるために、植物の
液汁は
無尽蔵のごとくに見えながら、これを
吸う虫はけっして
無限に
繁殖し
跋扈することを
許されぬ。
血液は全部
滋養分よりなるゆえ、これを
吸う動物は一回
腹を
満たせば長く
飢えを
忍ぶことができるが、これと正反対に
極めて
少量の
滋養分より
含まぬ
粗末な食物を、
昼夜休まず食い
続けることによって生命をつないでいる動物もある。
「みみず」のごときはその
一例でつねに土を食うているが、土の中には
腐敗した草の根など
僅少の
滋養分を
含んでいるだけで、その大部分は、
不消化物として、
単に「みみず」の
腸胃を
通過するにすぎぬ。血を
吸う動物を、
仮に
戦争の
際などに一度に大金をもうけるものにたとえれば、「みみず」のごときは真の
薄利多売
主義の商人のごとくで、口から入れて
尻へ出す食物の
量は実に
莫大であるが、その中から
濾しとって、自身の
血液のほうへ
吸収する
滋養分ははなはだ少ない。されば「みみず」は生命を
保つに足りるだけの
滋養分を
得るためには、
絶えず土を食い
続けておらねばならぬ。「みみず」は地中に
隠れているので人の目に
触れぬが、ところによってはずいぶん多数に
棲息していて、それが
一匹ごとに
絶えず土を食うては
糞を地面に出すゆえ、「みみず」の
腸胃を通り
抜けて地中から地面に
移される土の
量は、年に
積もれば実に
夥しいことである。
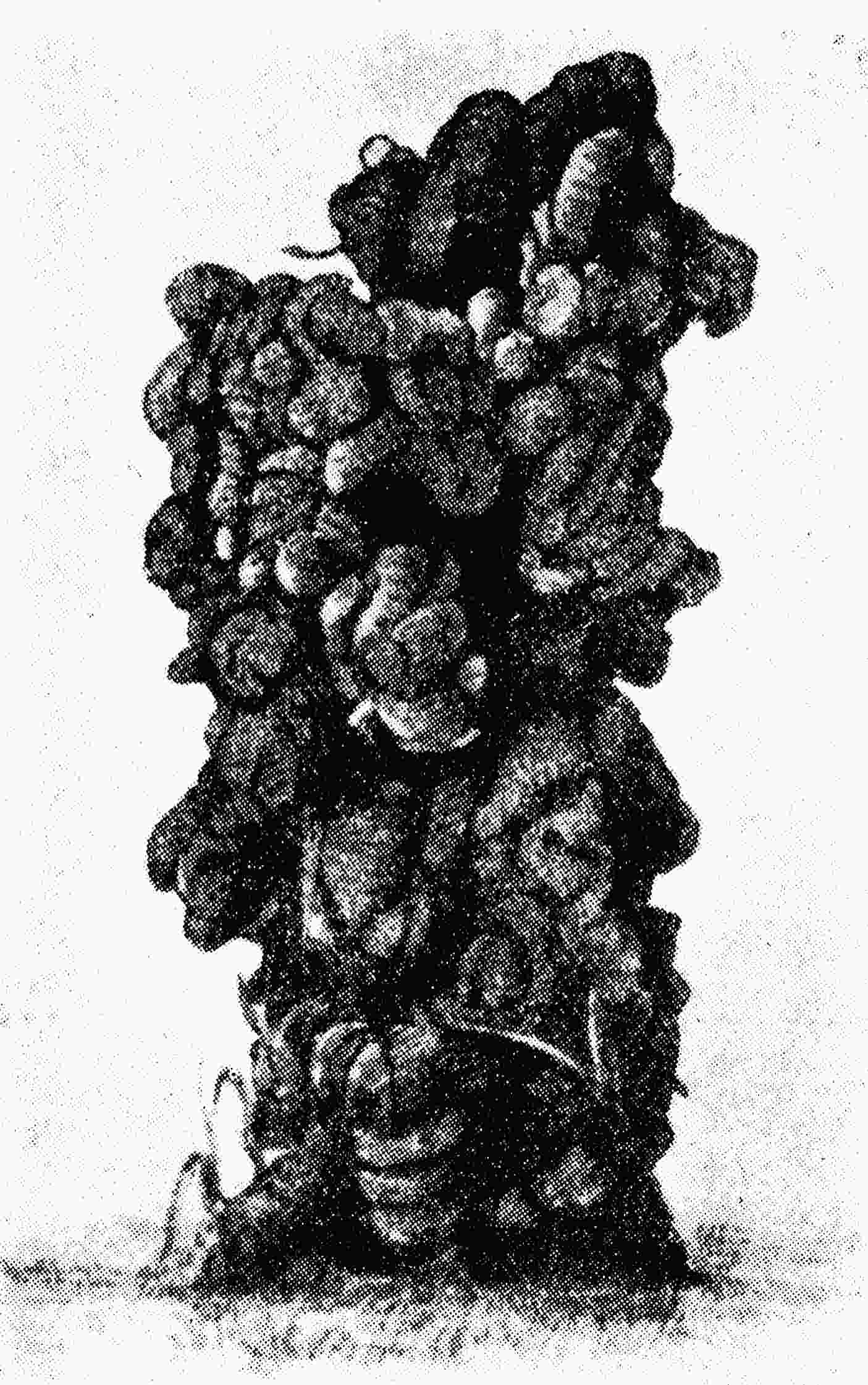 みみずの糞
熱帯
みみずの糞
熱帯地方の大形の「みみず」では、
一匹が一度に地面に
排出する
糞塊でもここの図に
示したごとくになかなか大きい。
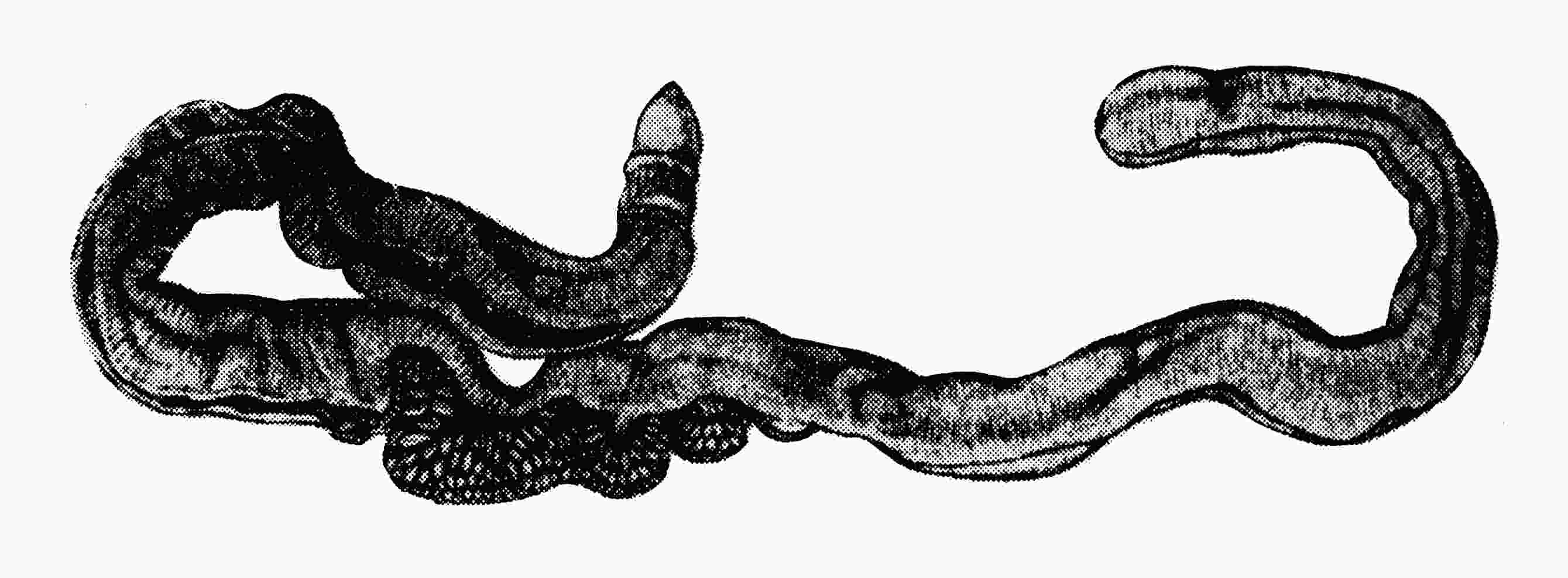 ぎぼしむし
浅
ぎぼしむし
浅い
海底の
砂の中には「ぎぼしむし」と
称する細長い
紐のような形の動物がいるが、これなども全くみみずと同様な生活をしている。全身黄色ですこぶる
柔らかく、手につまんでぶら下げようとすると、
腸胃の中の
砂の重みで身体が
幾つかに切れてしまう。いちじるしくヨードフォルムの
香のすることはだれも気のつく点である。
普通のもので長さが二三
尺(注:60~90cm)、大きなものになると五
尺(注:1.5m)
以上もあるが、
前端には
伸縮自在な「ぎぼし」
状の頭があり、これを用いて
砂を
掘り、
絶えず
砂を食いながら
砂の中をしずかに
匍匐しているから、この虫の身体を
通過する
砂の
量はすこぶる多い。時々体の
後端を
砂の表面のところまで出して
腸の内にある
砂を
排出するが、
砂は
粘液のためにやや
棒状に
固まって出て来る。しこうしてかような
砂の
棒ははなはだ長くて後からおいおい出て来るゆえ、
次第にうねうねと曲がってあたかも太い
饂飩のごとくに
砂の表面にたまるが、波の動くために直ちに
壊れてわからなくなる。しかし春の
大潮などに
浅瀬のかわいたところへ行って見ると、「ぎぼしむし」の
糞は
砂の
饂飩のごとくにかしこにもここにもうずたかくたまっている。
 ぎぼしむしの糞
ぎぼしむしの糞
ここにかかげた図は
房州(注:千葉県)
館山湾内の
洲の
現われたところでとった写真であるが、これによってもおよそ
一匹の「ぎぼしむし」が一回にどれほどの
砂を
排出するかたいがいの見当がつくであろう。
かわいた
材木を食う虫なども、ずいぶん
多量に食物をとらねばならぬ。
箪笥の
桐の木を食う虫、
柳行李の
柳や竹を食う虫なども、しばしば人を
困らせるものであるが、その食物は
滋養分を
含むことがいたって少ないゆえ、小さい虫ながらつねに食い
続けるために、その
害は
存外にはなはだしい。かような虫に食われた
箪笥や
柳行李をたたくと、
際限なく
木材の
粉が出て来るが、これはみな一度虫の
腹の中を
通過した
糞のかわいたものである。
木造の
建築に
大害を生ずる
白蟻も、食物に
滋養分が
乏しいために
多量にこれを食うので
害もすこぶるはなはだしい。
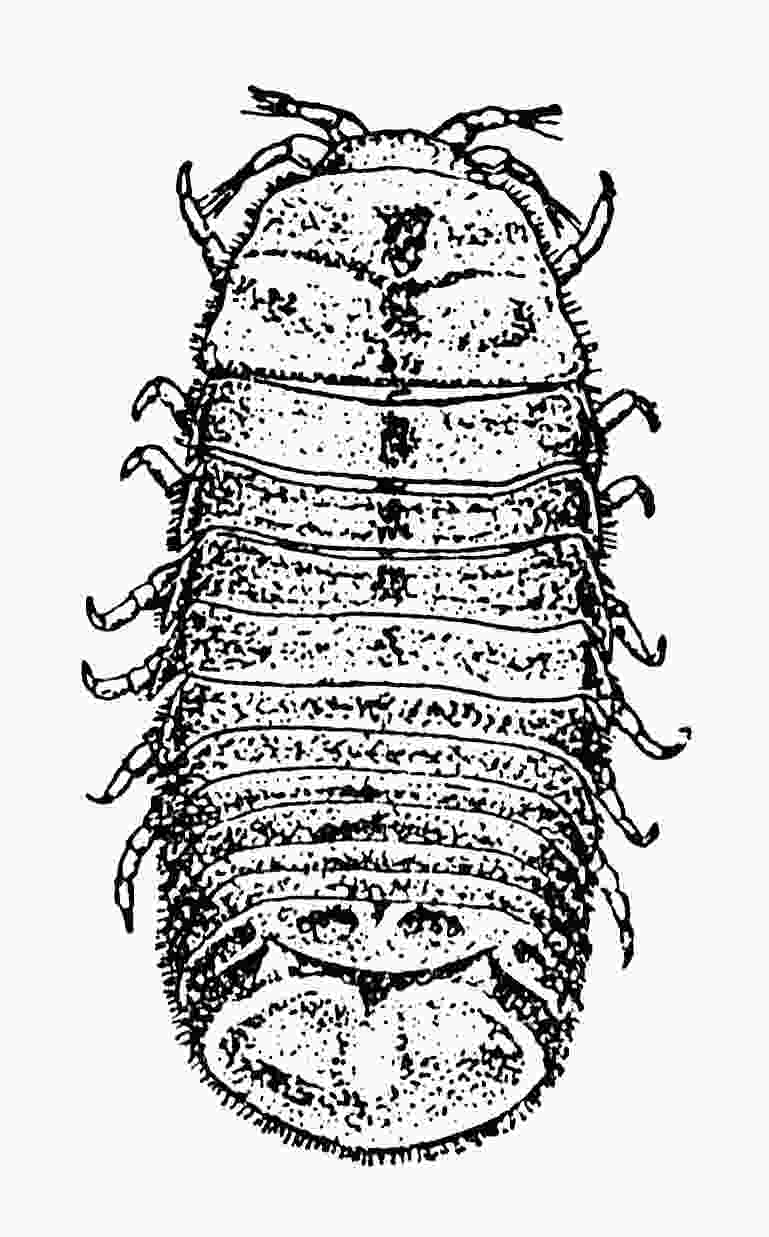 船食虫(郭大図)
船食虫(郭大図)
港の
桟橋の
棒杭などは「わらじむし」に
似た小さな虫に
盛んに食われるが、これなども
絶えず食い
続けるゆえたちまち
棒杭を
孔だらけにして弱らせる。この船食虫は
往々海底電信のおおい物をかじって
害をおよぼすことがあるが、つねに
堅い
材木を食うために強い
顎を
備えているゆえ、かようなこともできるのであろう。
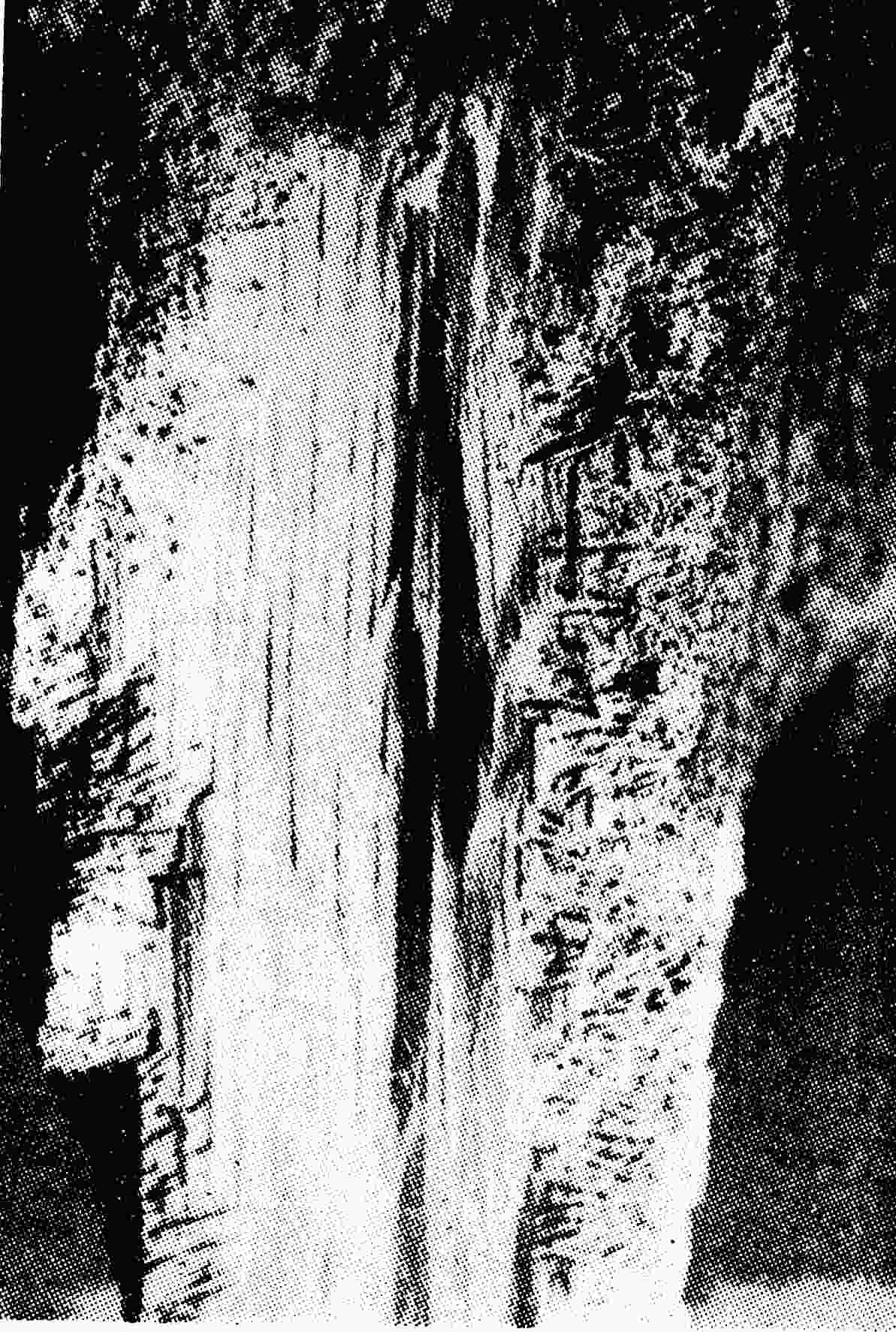 船食虫の害
以上述
船食虫の害
以上述べたとおり、動物の
餌の
種類とこれを食う
方法とには、
種々異なったものがあるが、
如何なる
方法でどのような食物を食うとしても、
絶対に
安楽というものはけっしてない。
滋養分に
富んだ
餌を食おうとすれば
競争が
激烈であり、
滋養分に
乏しい食物で
満足すれば日夜休まず食うことにのみ
努力せねばならぬ。食物が
不足なれば
飢えに苦しまねばならず、食物が十分にあれば
盛んに
繁殖する
結果としてたちまち食物の
不足が生ずる。草食すれば
餌が
豊かな代わりに他動物に
襲われる心配があり、肉食すれば
餌の
供給に
際限があるため、
縄張りの
区域を定めて
隣のものと
対抗せねばならぬ。進んで
餌を
求めれば体を動かすゆえ
腹が
減り、とどまって
餌を待てば、いつ
満腹するを
得るか見定めがつかぬ。されば
如何なる生物も生まれてから死ぬまで、それぞれ
特殊の
方法によって
餌を
求め、他とはげしく
競争しながらかろうじて生命を
継続しているのであって、
安楽に
暮らせるという
保険つきの生物は
一種たりともあるべきはずはない。この事は生物の生活
状態を
観察するにあたっては、
一刻も
忘るべからざる重大な
事項である。
動物の中には
同一種族のものが
互いに食い合い、
同胞を
殺して自身が生活する者がいくらもある。ちょっと考えると、かような
共食いは
生存競争の
極端な場合で、
普通の食物が
皆無になった時にのみ行なわれる
非常手段のように思われるが、少しく注意して見るとつねづねたくさんにあることでけっして
珍らしくはない。今ここに二三のもっとも
普通な
例をあげて見よう。
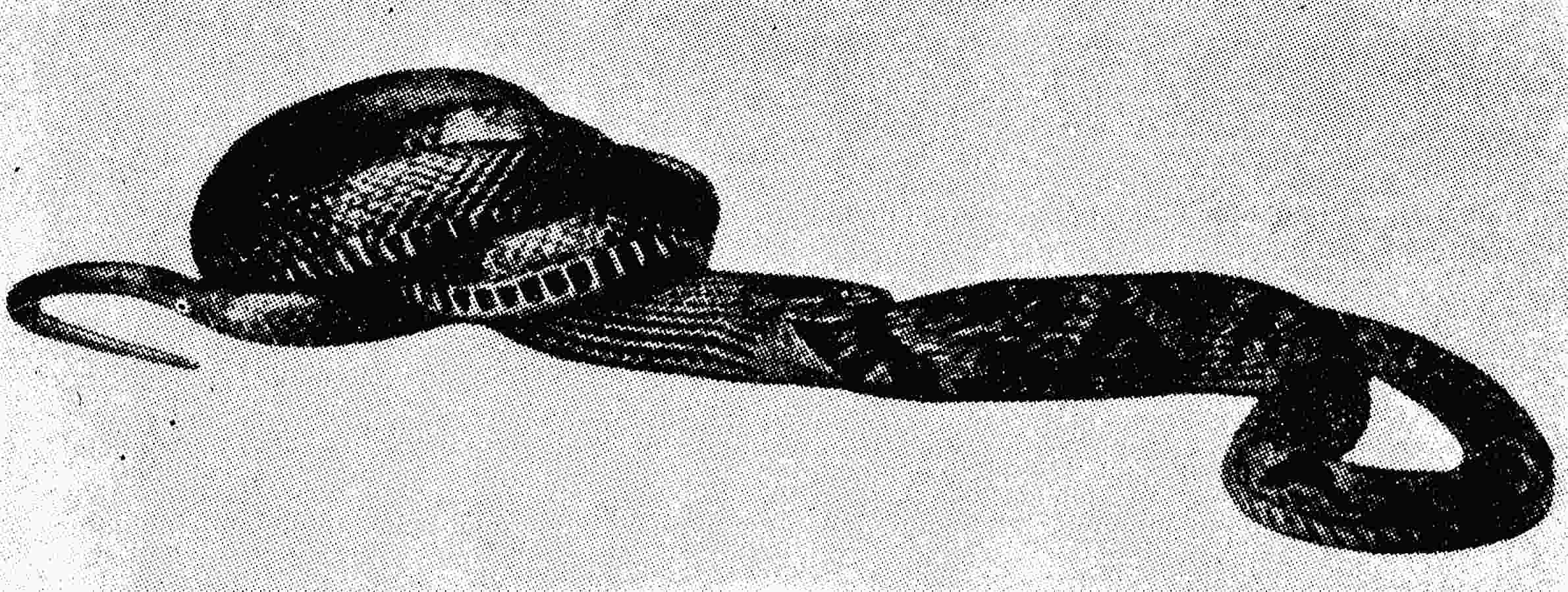 蛇蛇をのむ
獣類
蛇蛇をのむ
獣類を
獣類が食い、
魚類を
魚類が食うというごとき、同
部類に
属するものの
相食うことまでも
共食いと見なせば、その
例はすこぶる多くなるが、かようなものを
除き、真に
同一種のものの
共食いだけとしても、
相応に
例をあげることができる。
昆虫などでも
同一種のものを一つの
籠にたくさん入れておくと、
共食いを
初めるものがずいぶん多い。「いなご」、「ばった」なども
共食いをするが、「かまきり」のごときつねに肉食するものでは
特にはなはだしい。食物を十分に
与えておいても、やはり
共食いを
初める。
魚類にも一つの
鉢にいっしょに入れておくと、大きいほうが小さいほうを食うてしまうごときものはたくさんにある。
卵から
孵ったばかりの小さな
幼魚などは、注意して
別に
離しておかぬとたいがいは親に食われる。大きな
蛙が
同種の小さな
蛙をのむことのあるのは、これまでたびたび見た人もあるが、日本に有名な「大さんしょううお」も
盛んに
共食いをする動物で、かつてオランダへ
雌雄二匹送ったものなどは、
途中で
雄が
雌を食うてしまうて、
雄一匹だけが
肥って先方に着した。
蛙や「さんしょううお」の
卵を
飼うておくと、
幼児はたくさんに生まれて出るが、しばらく
飼うているうちにだんだん数が
減じて、
初め数百
匹いたものが、後にはわずか
数匹になることがあるが、これも主として
共食いの
結果である。
或る時「さんしょううお」の
幼児をたくさん
飼うておいたまま、二週間ばかり旅行して帰って見たら、ただ
一匹だけ
非常に大きくなって
残っていた。かようなことはほかの動物についてもしばしば
経験するところである。
蟹類も多く
共食いするが、海岸の
浅いところに
普通にいる「やどかり」なども、
一匹がその
腹部を
貝殻から
抜き出したところを
他かのものが見つけると、直ちに走り
寄ってこれを
挾み切り食い
初める。それゆえ身体の
成長につれて、小さな
貝殻を
捨てて大きな
貝殻に住み
換える
必要のあるときにも、
極めて用心してそばに
他のものがいるときにはけっして
抜けて出ない。
女の
子供がもてあそぶ「うみほおずき」は
螺(注:巻貝)の
類の
卵嚢であるが、その中には
初め
卵が
十個も二十
個もある。
初めはみな同じように
揃うて発育するが、そのうちにだんだん
相違が生じて大きな強いものと、小さな弱いものとができ、小さなものは大きなほうに食われてしまうゆえ、
成長して
卵嚢から出るころには数がいちじるしく
減ずる。これなどは
臨時に起こることでなく、
産卵ごとに
必ず行なわれるのであるから、その
種族の予定の仕事で、あたかも
鶏の
雛が
卵殻内で黄身を
吸うて
成長するのと同じく、少数の
幼児に十分の
滋養物を
与える
方便とも見なすことができる。
共食いの中で
一種異なるのは、自身の一部を自身で食うことである。「たこ」は
腹が
減ると自分の足を先のほうから一本ずつ食うとは
漁師らのつねに言うところであるが、あまり
妙なことゆえ
信偽のほどを
疑うていたが、十年ばかり前に小さな「たこ」を半年ばかり
飼うておいたら、ついに自分の足を三本食うて五本だけになった。かような
例はほかの
種類の動物についてあまり聞かぬが、よく調べて見たらなおいくらもこれと
似たことがあるかも知らぬ。
以上はいずれも真の
共食いの
例であるが、
共食いという言葉の意味を少しくゆるくすれば、その
範囲は
極めて広くなる。もしも生物が生物を食うことを
共食いと名づけるとすれば、生物の生命は大部分
共食いによって
保たれるといわねばならぬ。
無機物から
有機成分をつくるのは緑色の植物のみであるゆえ、そのほかの生物はすべて
直接または
間接にこれを食うている。肉食でも、草食でも、
寄生でも
共食いでも、みな
甲の生物の肉であった
物質が、
乙の生物の肉に
姿を
変えるにすぎぬゆえ、生きた
物質の
総量を
勘定すれば、
別に
増減も
損得もない。かように広く
論ずると、
共食いは生物の
常態とも見えるが、同一
種類内の
共食いは一定の度を
超えると、生き
残った少数のものが、食われた多数のものに代わるだけの
働きをなし
得ず、そのため
種族にとってはすこぶる
不利益なことになるをまぬがれぬであろう。
前章に
述べたところはいずれも生物が
各自独立に生活する場合であったが、なおそのほかに
一種の生物が
他種の生物からその
滋養分の一部を横取りして生活を
営んでいることがしばしばある。
寄生生活と名づけるのはすなわちこれであるが、この場合には、相手の生物に
寄りすがって、多少これに
迷惑をかけながら生活するのであるから、
独立生活とは大いに
趣の
異なるところがあるゆえ、今
若干のいちじるしい
例によってそのおもなる
相違の点をあげて見よう。
それについてまず
断っておかねばならぬことは、
寄生生活と
独立生活との間にはけっして
判然たる
境界の
ないことである。肉食動物でも草食動物でも、食うほうの生物が小さくて、食われるほうの生物がはるかに大きかったならば、わずかに一小部分ずつを食われる
のであるゆえ、大きなほうは急に死ぬようなことがなく、小さいほうはつねにこれに食いついていることができるが、かような場合に小なるほうの生物を
寄生生物と名づける。しかし大小はもとより
比較的の言葉であって、その間には
無数の
階段があるゆえ、いずれに
属せしむべきか
判然せぬ場合がいくらもある。「いたち」は一度に血を
吸うて
鶏を
殺しこれを
捨て去るゆえ、
寄生動物とは名づけぬが、
仮に「いたち」が百分の一の大きさとなり、
鶏に
吸い
着いたままで生活を
続けるものと
想像すれば、これは
確かに
寄生動物である。かく考えると、
寄生動物なるものは
畢竟小なる
猛獣にすぎぬ。また
如何に小さくとも、つねに食いついて
離れぬものでなければ
寄生動物とは名づけぬ。
例えば、
蚊は人の血を
吸うても
普通には
寄生虫とはいわぬ。これに反して、「
頭しらみ」はつねに人体を
離れぬゆえ、
寄生虫と名づけられる。「のみ」、「しらみ」などはその中間にくらいする。
されば
寄生生活と
独立生活との間にはけっして
判然とした
境界があるわけではなく、半分
寄生生活を
営むものもあれば、時々
寄生生活を行なうものもある。かように
程度の
違う
寄生生物を数多くならべて、
順々に
比較して見ると、
独立生活から
寄生生活に
移り行く
順序も知れ、
寄生の
程度が進むにしたごうて、身体に
如何なる
変化が
現われるかをも知ることができる。
寄生生活に第一に
必要なものは
吸着の
器官である。宿主生物の体の表面に
付着する場合にも、
腸や
胃の内にとどまる場合にも、
吸着の力が足らぬとたちまち
振り
離され、または
押し出されるおそれがあるが、
寄生生活をする生物が宿主から
離れたのは、
猿が
樹から落ちたのよりははるかに
憐れでとうてい命は
保てぬ。されば、
如何なることがあっても宿主に
離れぬように、
確かに
吸いついていることは
寄生生活の
第一義であるが、そのために用いられる
器官は
吸盤と
鉤とである。同じ
仲間の動物で
独立の生活をしているものと、何かに
寄生しているものとを
並べて
比較して見ると、後者のほうに
吸着の
器官のいちじるしく
発達していることが直ちに知れる。
 八目うなぎ
例
八目うなぎ
例えば
魚類では
寄生するものは
一般に少ないが、
八目鰻の
類はほかの
魚類の
皮膚に
吸いついて肉を食うゆえ、まず
寄生生活に近いものである。しこうしてその口は
普通の
魚類のごとく上下
顎を
備えてかむのではなく、
単に円く開いてあたかも
煙管の
雁頸のごとく、物に
吸い着けば、「たこ」の足の
疣と同じようで
容易に
離れぬ。これを
普通の
魚類の口の
構造にくらべると、
吸着に
適することにおいては
雲泥の
違いがある。
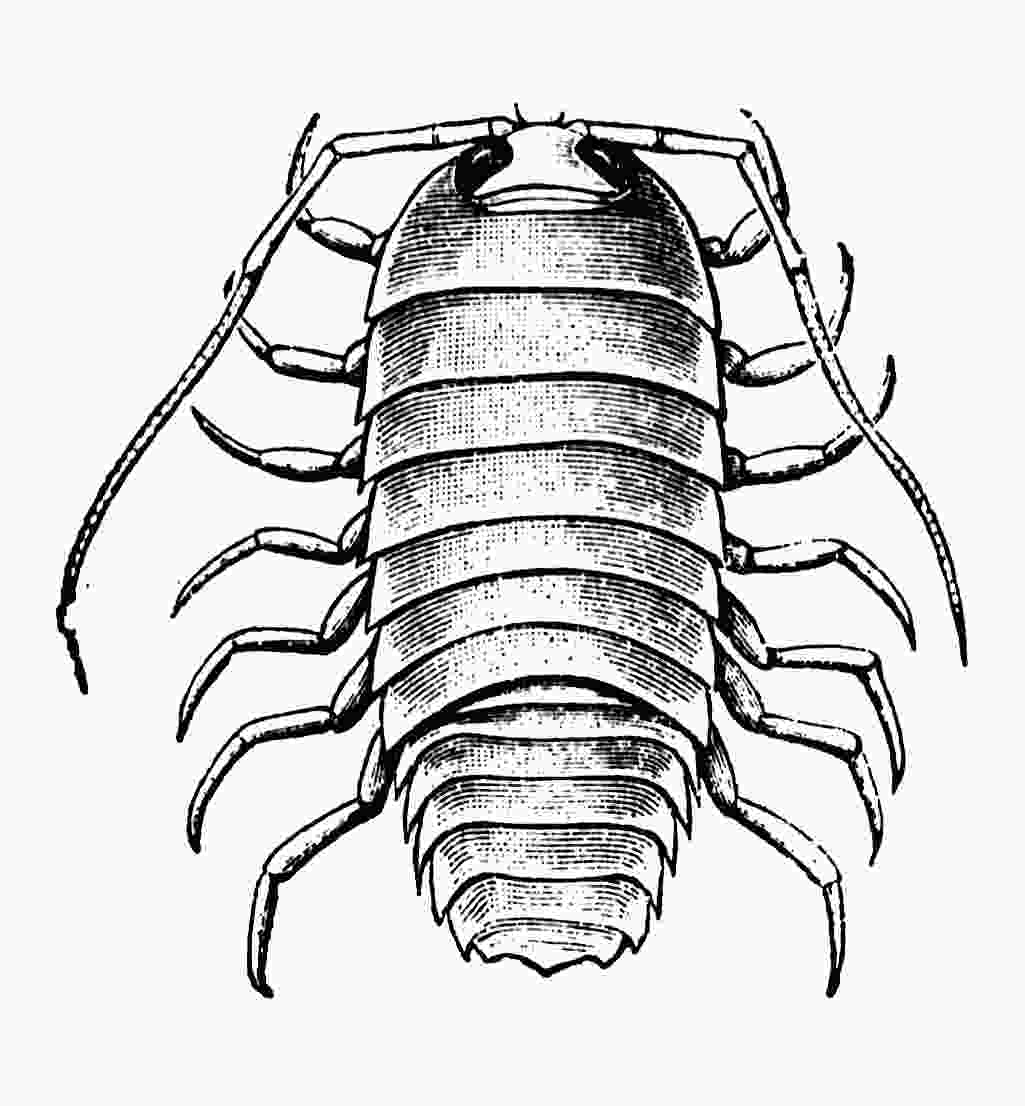 ふなむし
ふなむし
「ふなむし」は海岸の岩の上や船の中などを活発に走りまわって
容易に
捕えられぬほどゆえ、その七対ある足は
相応に長いが、
尖端が細く真直ぐであるから物にかじりつくことはできぬ。
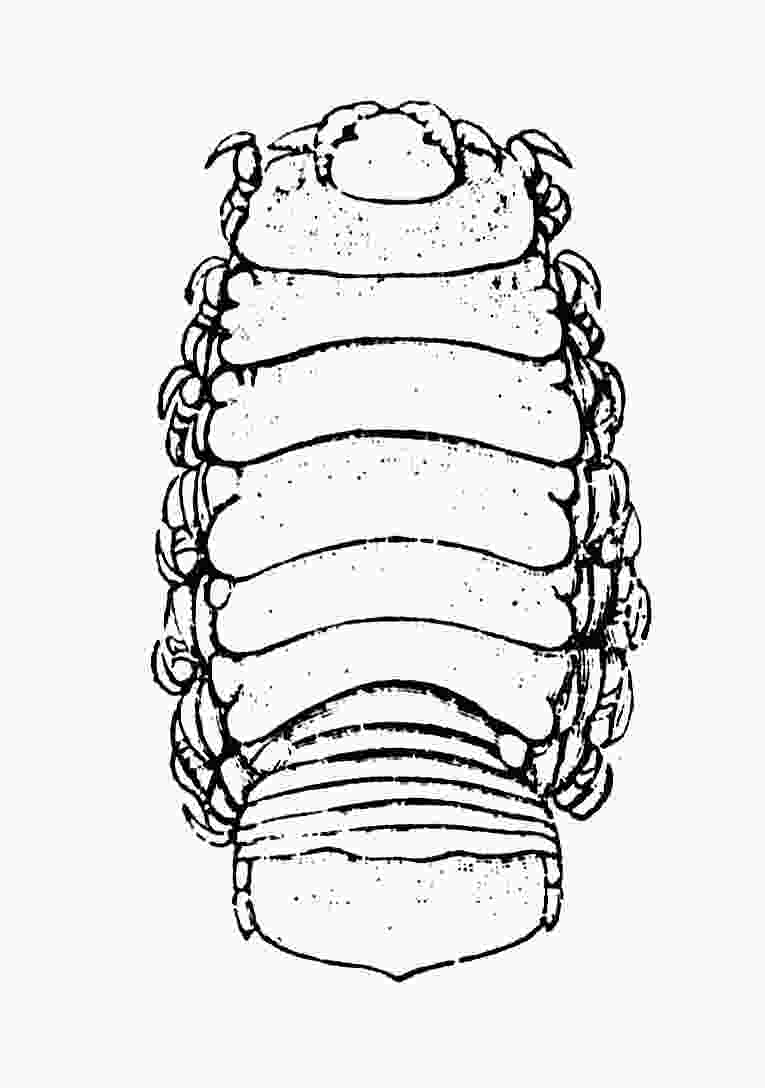 小判虫
小判虫
これに反して、
鯛そのほかの大きな魚の口の中などに
吸いついている
小判形の虫は、「ふなむし」と同じ
仲間の動物であるが、足は
七対ともに太くて短く、
爪は
鉤状に曲がって先が
尖っているゆえ、しがみついていると
容易には
離れぬ。この虫と「ふなむし」とを
並べて
比較して見ると、体の
形状も
節の数も足の数も足の
節の数もすべて同じであるが、一方は
独立して走り歩き、一方は他動物に
寄生しているだけの
相違で、かように
吸着の
仕掛けが
違う。「ふなむし」の
類には
種々寄生の
程度の
異なるものがあるが、これらを
順に
見渡すと、
吸着の
装置が一歩一歩
完全になるありさまが明らかに知られる。
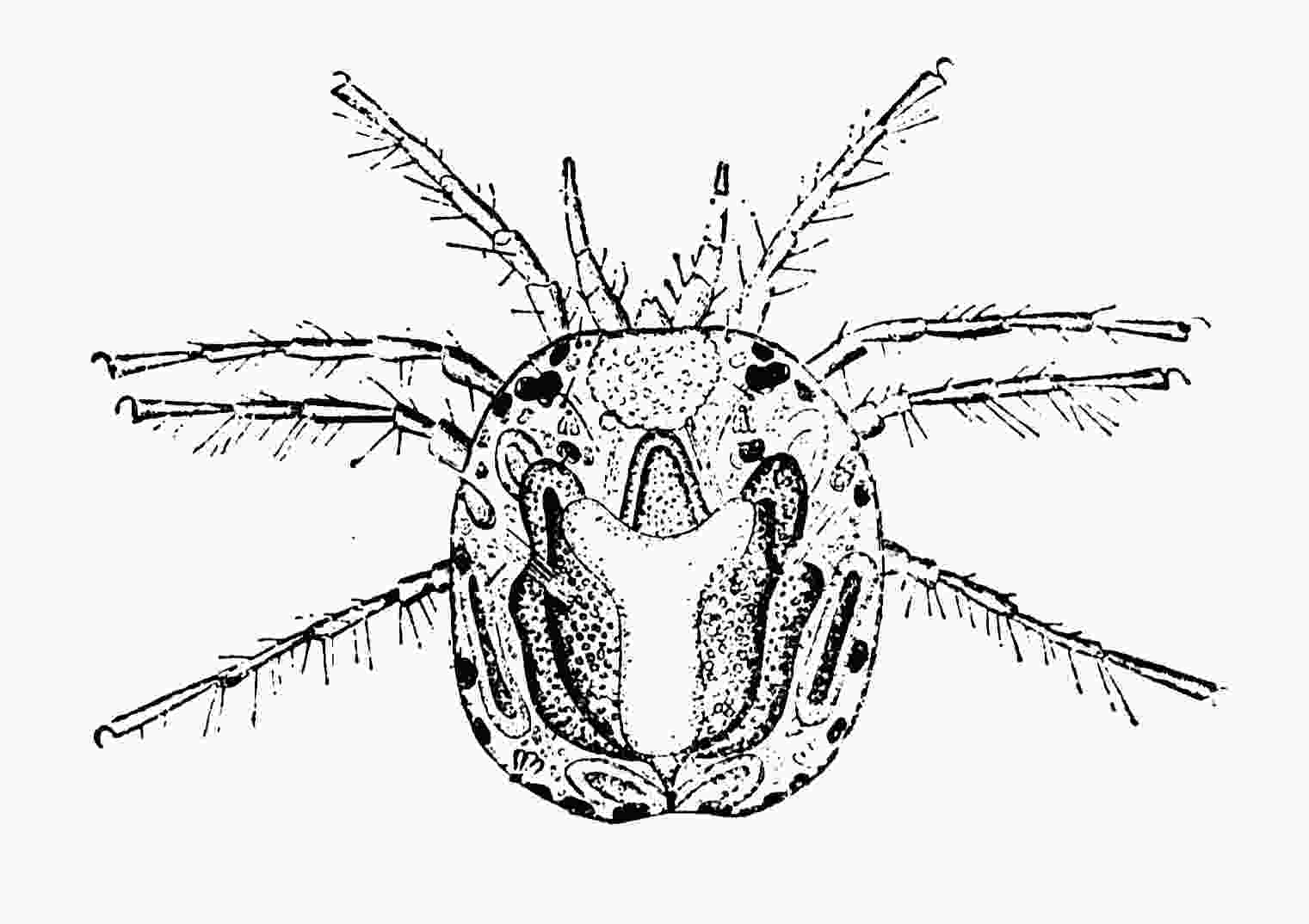 独立だに
独立だに
「だに」の
類には
独立の生活をするものと、
寄生するものとがあるが、これもくらべて見ると、
寄生するものほど、足が短くて
爪が
鉤状に曲がっている。土の上や水の中を自由に運動している
類では八本の足がみな身体の
直径より長いが、犬や牛などに
寄生する「だに」では足はすこぶる短く、かつ
吻を深く
皮膚の中へ
差し入れているゆえなかなか
離れぬ。
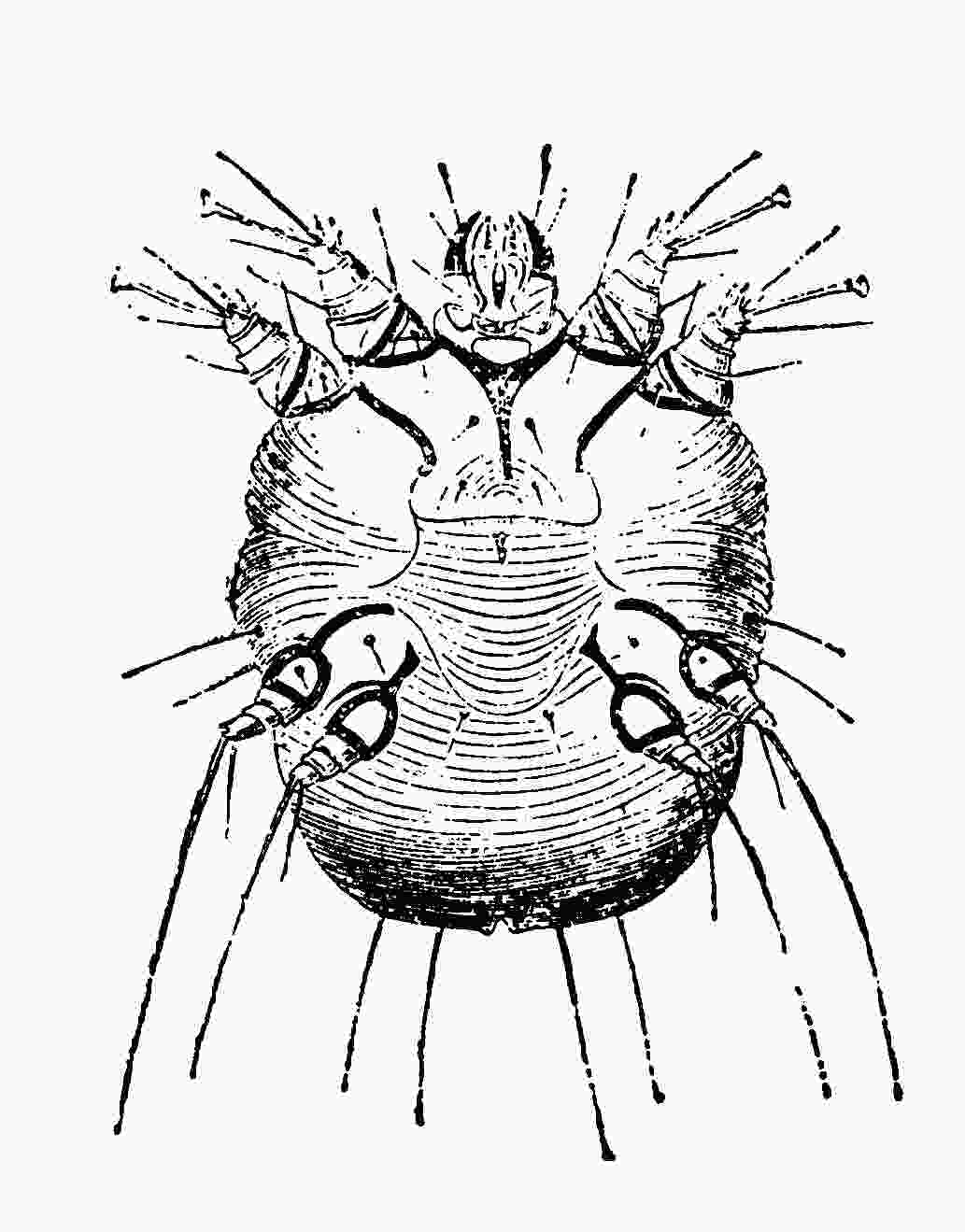 ひぜんのむし
ひぜんのむし
「ひぜんのむし」も「だに」の
一種であるが、これなどは人間の
皮膚の中に細かい
随道を
縦横に
掘って住んでいるので、足はきわめて短く、ほとんどあるかないかわからぬほどである。しかし
爪だけは明らかにある。
鯉や金魚の表面につく「ちょう」は「みじんこ」の
類であるが、
普通の「みじんこ」とは
違うて左右の
上顎が
変形して「たこ」の
疣のごときものとなり、これを用いて
確かに魚の
皮膚に
吸いついている。かような
吸盤は
独立生活をする「みじんこ」ではけっして見ることはできぬ。「ひる」は身体の
構造からいうと「みみず」と同じ
類に
属するが、「ひる」の中でも
魚類や
亀などに
吸いついている
種類になると、ほとんど
一生涯同じところに
吸着しているゆえ
立派な
寄生虫である。年中土を食うている「みみず」には、頭から
尻までどこにも
吸盤も
鉤もないに反し、「ひる」のほうには体の
両端に強い
吸盤があって、これで
吸いつくと
如何に魚がもがいてもけっして
離れることはない。
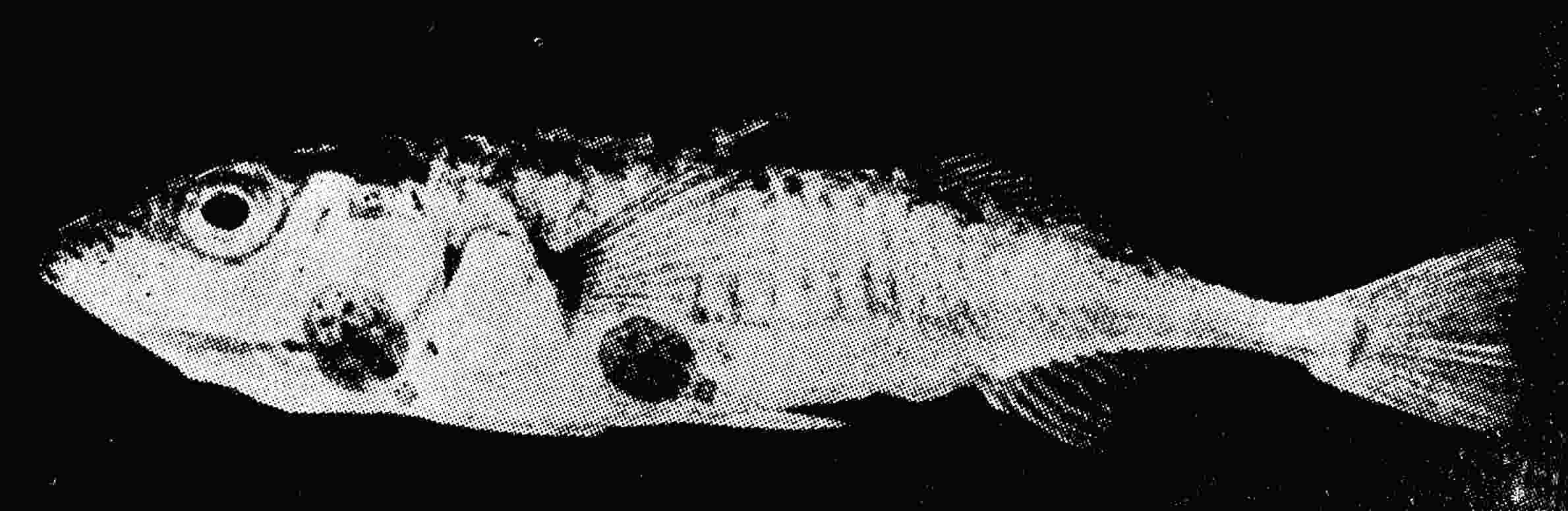 魚に「ちょう」の吸いついているさま
魚に「ちょう」の吸いついているさま
「さなだむし」や「ジストマ」は
寄生虫の
模範ともいうべきものであるが、みな
固着の
器官が
発達している。「さなだむし」のほうには
種類によってあるいは
吸盤、あるいは曲がった
鉤、あるいは
吸盤と
鉤とが頭の
端にあって、これを用いて
腸の
粘膜に
付着している。また「ジストマ」のほうは、
腹面の前方に
二個の
吸盤が
縦に
並んでいるが、これをもって同じく
粘膜などに
吸いつく。漢字で二口虫と書くのは、
二個の
吸盤が口のごとくに見えるからである。
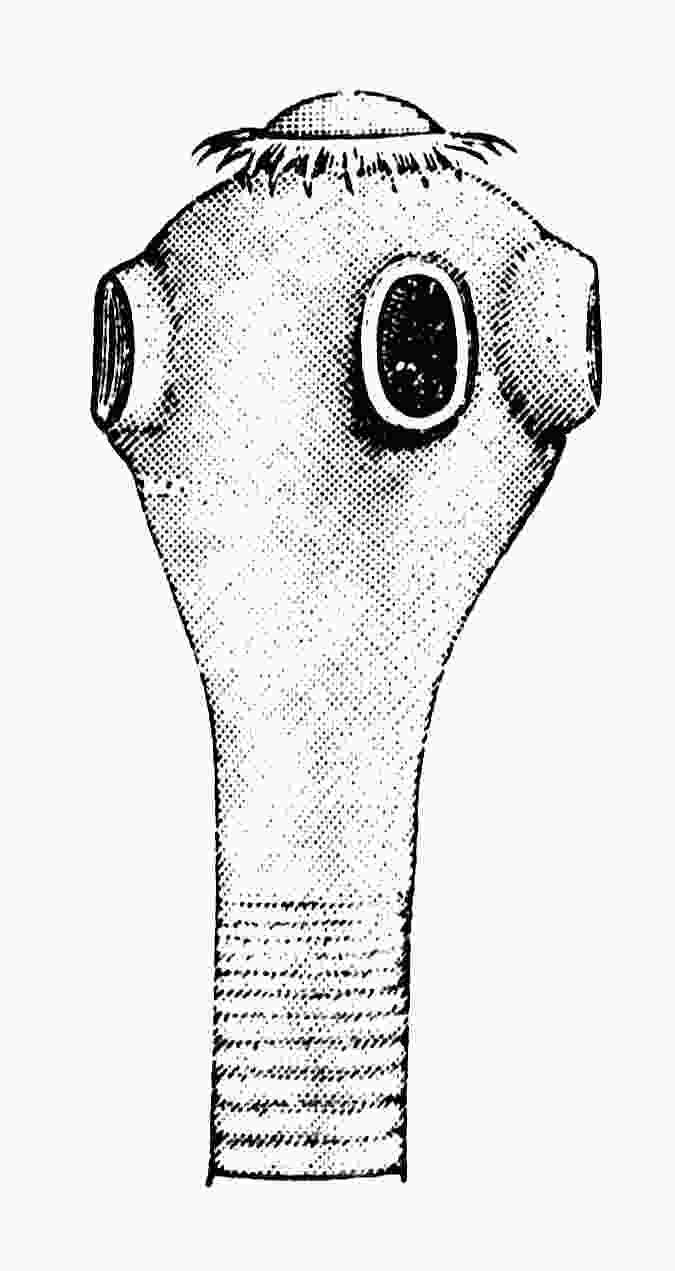 条虫の頭
条虫の頭
かくのごとく
寄生動物には
吸着の
器官が
発達して、
如何なることがあってもけっして宿主動物をとり
逃がさぬようにできているが、その代わり運動の
器官ははなはだしく
退化するをまぬがれぬ。前に
比較した「
独立だに」と「ひぜんのむし」とでも、「ふなむし」と
鯛の口の
小判虫とでも、
吸着の
仕掛けの進んだほうは運動の力は
衰えている。けだし
寄生動物は、後生大事に宿主動物にかじりついていさえすれば生活ができるから運動の
必要がないのみならず、少しでも自由の運動を
試みれば、宿主動物との
縁が切れるおそれがあって生活上すこぶる
危険であるゆえ、
自然必要な
器官が
発達し、
不必要な
器官が
退化して、
爪は大きくなり、足は短くなるというような
結果を生じたのであろう。
種々の
程度の
寄生生物を
通覧すると、
吸着器官の
発達と運動
器官の
退歩とはつねに
並行し、両方とも
寄生生活の
程度と
比例しているように見える。すなわち時々
寄生するものや、
半ば
寄生するものには、運動の
器官がなお
備わっているが、
宿主動物から
離れぬようになれば、
吸着の
器官が
完備して運動の
器官がなくなり、「さなだむし」や「ジストマ」のごとき
模範的の
寄生虫になると、自由運動の力は全く
消滅してしまう。
寄生動物は
独立に生活するものとは
違い、ほかの動物が食物を消化してその
滋養分を
濾しとった
液を
吸うのであるから、自分でさらにこれを消化する
必要がない。それゆえ
寄生動物では消化の
器官は
退化するばかりで、
特に他動物の
腸の中に
寄生するものの中には、全く消化
器官のない
種類もある。宿主動物の外面に
吸いついている
寄生虫は、
血液を
吸いとるに
適した
特殊の口がなければならぬが、宿主動物の内部に住んでいる
寄生虫は、全身
滋養液の中に
浸されていることゆえ、
皮膚の全面からこれを
吸収さえすれば、
別に口がなくとも
差支えはない。
いったい動物の消化
器官の
発達は食物の
如何によって大いに
違うもので、
腸の長さなども肉食動物と、草食動物とでは
非常な
相違がある。羊と
豹とはほぼ同大であるが、
豹の
腸は体の長さの三倍よりないに反し、羊の
腸はその二十七、八倍もある。かように長い
腸が
狭い
腹の中にしまってあるから、
勢い何回も曲がりくねっている。
支那人が
屈曲した山道を
形容して「
羊腸」というのはもっともな語である。動物園へ行って見ても、
豹の
腹はいつも小さいが、山羊の
腹は
太鼓のように
膨れている。これも
腸の長短とその
内容物の多少とによって起こる
相違である。
何故草食動物は
腸が長くて、肉食動物は
腸が短いかというに、草の葉には
滋養分が少なくて
滓が多いゆえ、これを消化して
吸収するにはよほど手間がかかるが、肉のほうは
滋養分に
富んでいるゆえ、
溶けて
濃い
液となり、
速やかに
吸収せられるからであろう。人間でも植物を多く食う国の人は
腸が長く、肉を多く食う国の人は
腸が短い。かつその
排出する
糞便も肉食の人は
少量であるが、植物のみを食う人のは太くてみごとである。されば
腸の長さを
測れば、それによってその動物が肉食
性のものか、草食
性のものかおよその
判断ができる。
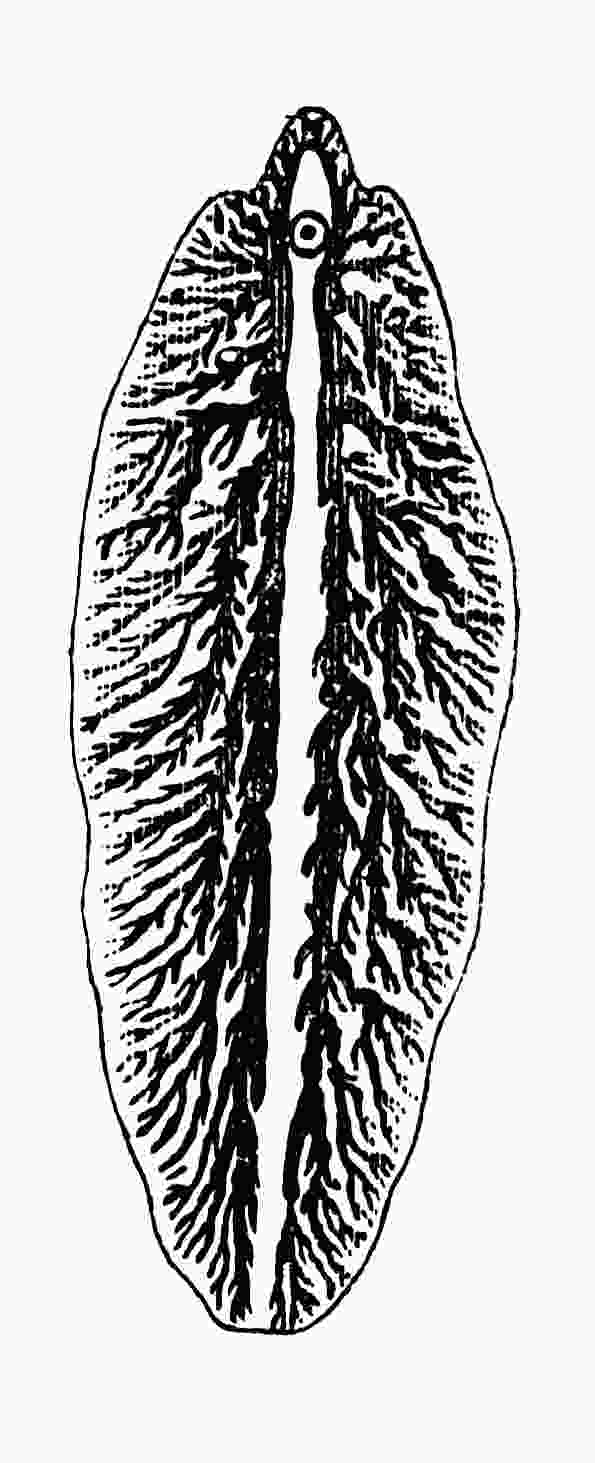 ジストマ
ジストマ
動物の中で
滋養分のもっとも多い、
不消化物のもっとも少ない、もっともぜいたくな食物をとるのは
寄生虫である。
寄生虫の食物は多くは宿主動物の
血液か、または
組織をうるおすリンパ
液などであるが、これらは、その動物が食物を消化してその
滋養分だけを
吸収してつくるものゆえ、ほとんど
滓を
含まぬ
純粋な
滋養物である。それゆえ、これを
吸うている
寄生虫には
肛門のないものがいくらもある。
蛔虫は人の
腸の内にいて
腸の
内容物を食うているゆえ、口も食道も
腸も
肛門もあるが、
肺や
肝の内に
寄生する「ジストマ」の
類になると、口と
腸とはあるが、その先は行きどまりになって
肛門はない。おそらく、これらの虫は生まれてから死ぬまで食物を食うだけで、けっして、
糞便を
排出することはないのであろう。また「さなだむし」の
類はつねに
腸の内に住んで、
溶けた
滋養分の中に
漬けられているゆえ、ただ全身の表面からこれを
吸収するだけで、
特に体内の
一箇所へ
吸い入れるということはない。それゆえこの
類には口も
腸胃も
肛門もなく、消化の
器官は
影も形もない。このようなことは外界に
独立生活する動物では
夢にもあり
得べからざることである。生活するには食わねばならず食うには
消化器を
要することは、
独立生活する動物の
通則であるが、
寄生動物は、食うて消化することは宿主動物にさせておき、でき上がった
滋養分を分けてもらうのであるゆえ、自身に
消化器がなくとも生活ができる。
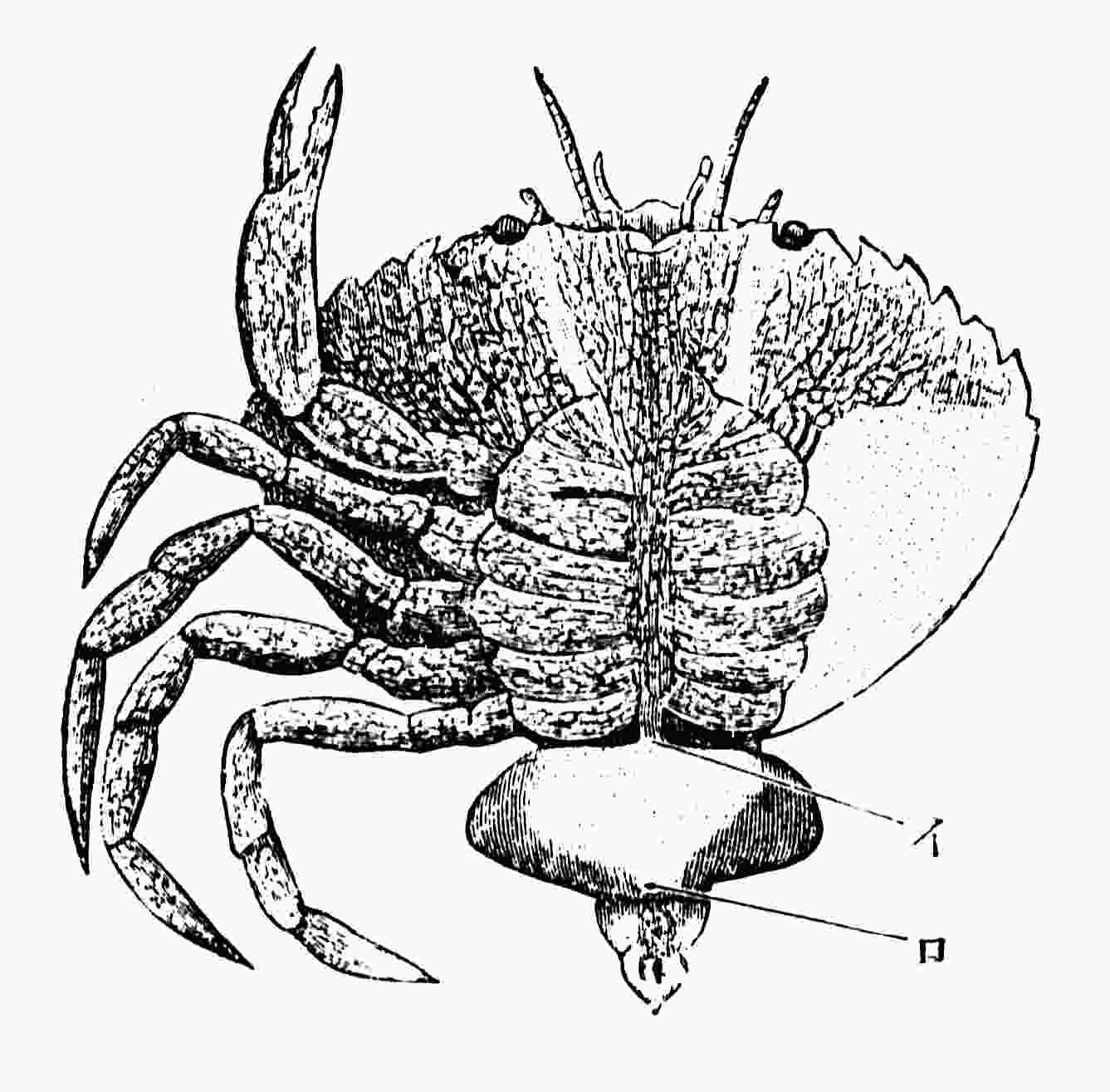
かにとその寄生虫
(イ)根状の頭の基部 (ロ)生殖孔
全く
消化器を持たず、しかも
宿主動物の身体の全部から
滋養分を
吸い取りながら、自身は宿主動物の外面に
付着しているおもしろい
寄生虫がある。海岸の岩の間を走っている
蟹を
捕えて見ると、
往々腹に丸い
団子のごときもののついているのを発見するが、この丸いものは
一種の
寄生虫で、
卵から
孵化した時の
姿を見ると「ふじつぼ」、「かめのて」などの
仲間であることが
確かに知れる。この虫は
蟹の
俗に
褌と名づける部の根元に
付着し、全身が
現われているが、その
吸い着いている部を
探って見ると、長く
蟹の体内に入り
込み、あたかも
樹の根のごとくに
枝に分かれ数多くの細い糸となって、
内臓はもとより足の
爪の先から
眼の中、
鋏の
末端までも
達している。これを用いて
蟹の全身から
滋養分を
吸い取るありさまは、全く
樹木が根によって地中から
養分を
吸い
込むのと同じである。しこうして根のごとき形をしているのは、実はこの虫の頭部にあたるゆえ、この
類を
根頭類と名づける。
動物が運動するのも
感覚するのも、一は
餌をとるためであるが、
寄生動物は
餌を
求め歩く
必要がないゆえ、運動の
器官が
退化すると同時に
感覚の
器官もだんだん
衰える。
独立動物と
寄生動物とを
比較して見ると、
寄生動物のほうは運動の
器官が
退化していることは前にも
述べたが、
感覚の
器官もこれと同様で、「ジストマ」や「さなだむし」などのごとき
模範的の
寄生虫には、
眼も耳も鼻も全くない。いったい動物の
感覚器の
発達はよほどまでは、その動物の運動の速さに
比例するもので、運動の速い動物では
一刻ごとに今まで遠く
離れていた新たな外界に
接することゆえ、前もってこれに
応ずる
手段として
視覚などは
特に
発達する
必要がある。
鳥類の
飛翔はすべての動物中でほかに
類のない
速やかな運動
法であるが、これに
伴うて
鳥類の
視力の
鋭さは他動物の遠くおよぶところでない。されば運動せずに
固着して生活する
寄生動物には、
比較的感覚器の
発達せぬのは
当然のことと思われる。
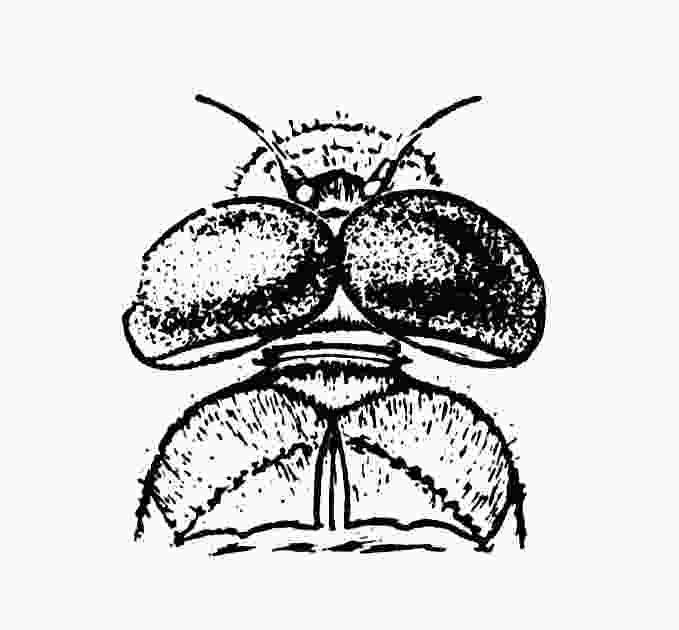 とんぼの頭部
昆虫
とんぼの頭部
昆虫などでも、
速やかに
飛ぶ「とんぼ」、運動の
遅い「かめむし」、犬、
猫の毛の間に住む「のみ」と
順を追うてくらべると、
眼のだんだん小さくなることが知れるが、「のみ」の
或る
種類になると
眼は全くない。
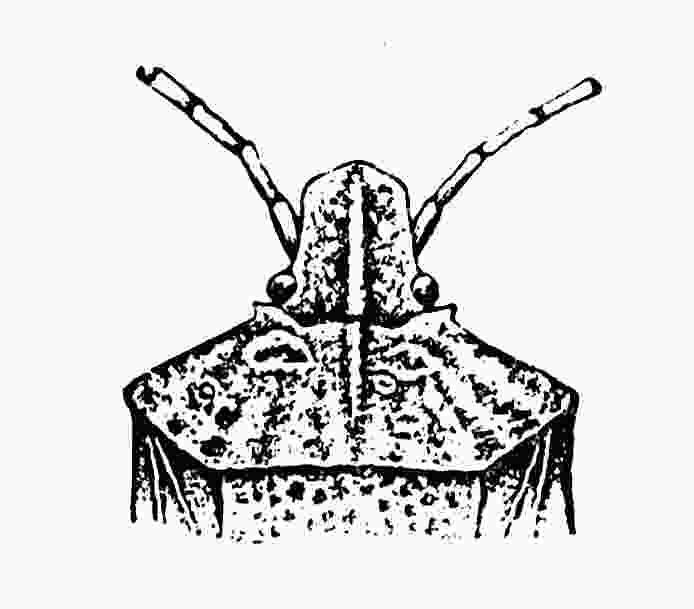 かめむしの頭部
かめむしの頭部
これを見ても運動の
必要のない
寄生生活をする動物では、
感覚器および
神経系が
次第々々に
退化するものであることは
確かである。
かくのごとく
寄生虫類では運動の
器官と
感覚の
器官とはいちじるしく
退化するが、その代わりに
盛んに
発達するのは
生殖の
器官である。動物の
働きには、
滋養分を集めてためるほうと、これを
費やして
捨てるほうとがあるが、消化は
滋養分を取るほうであり、運動と
感覚とはこれを
費やすほうに
属する。これを
簿記の帳面に記入するとすれば、消化
吸収は
入の部で、運動と
感覚とは出の部に書き
込まねばならぬ。もしも
或る動物が毎日食うただけの
滋養分を運動と
感覚とによって全く
費やしてしもうたならば、その動物の体重は
殖えもせず
減りもせず、ちょうど出入
平均のありさまにとどまる。
成長した人間の体重がいちじるしく
増減せぬのは、かような
状態にあるからである。これに反して、生まれて間のない赤ん
坊は、ただ
乳をのむだけで、ろくに動きもせずに
眠っているゆえ、
滋養分の
輸入超過のために
盛んに
成長し、わずか
四箇月で体重が二倍になり、
一箇年で三倍にもなる。また学校へ行くころになると、運動がはげしくなって、
滋養分を
費やすことがすこぶる多いが、これを
補うてなおその上に
成長せねばならぬから、
食欲の
盛んなことは
驚くばかりである。ところが、
寄生虫は
如何というと、宿主の外面に
吸いついているものでも、
滋養分に
不足はなく、体内にいるもののごときは、全身
滋養液に
浸されているために、
消化器の
必要がないほどであるが、運動も
感覚もほとんどせず、
滋養分をつこうて
減らすことが
極めて少ないゆえ、ただたまるのほかはない。しこうして、
滋養分が多くあるときには、
繁殖の
盛んになるのは動物のつねであって、人間のごとくに
随意の生活をするものでも、
統計をとって見ると
豊年には子の生まれる数が
殖え、
飢饉年には子の生まれる数が
減る。
寄生虫のごときは、
滋養分の
出納がいつも
不平均で、入のほうがはるかに多いが、これがすべて
繁殖の
資料となるゆえ、この方面においては全動物界中に
寄生虫に
匹敵するものはけっしてない。ためしに
一匹の
産む
卵の数をかぞえても、
億以上におよぶものは
寄生虫のみである。また
胎生するものでは、この
差はさらにいちじるしい。犬、
豚などはずいぶん子を
産むことの多いほうであるが、一回に
十匹産むことはまれであり、
鼠のごときも、
十二匹以上産むことはほとんどない。しかるに
豚の肉から人の
腸に
移り来る「トリキナ」という
寄生虫などは、親と同じ
形状の
胎児を一度に
二千匹も
産む。かく多数の
卵を
産み、多数の子を生ずるには、むろん
卵巣や
子宮などのごとき
生殖器官が大きくなければならぬが、
独立生活をする動物に
比べて
如何ほど大きいかは、同じ組に
属する
虫類で、
独立せるものと
寄生せるものとを
並べて見ると
明瞭にわかる。
例えば前に名をかかげた船虫と
鯛の口の中にいる
小判虫とをくらべて見るに、船虫のほうが体がやや
扁平で身軽にできているが、
小判虫のほうは丸く
肥ってすこぶる
厚い。しこうして、この丸く
肥った身体の内部を
満たしているのは主として
卵巣である。
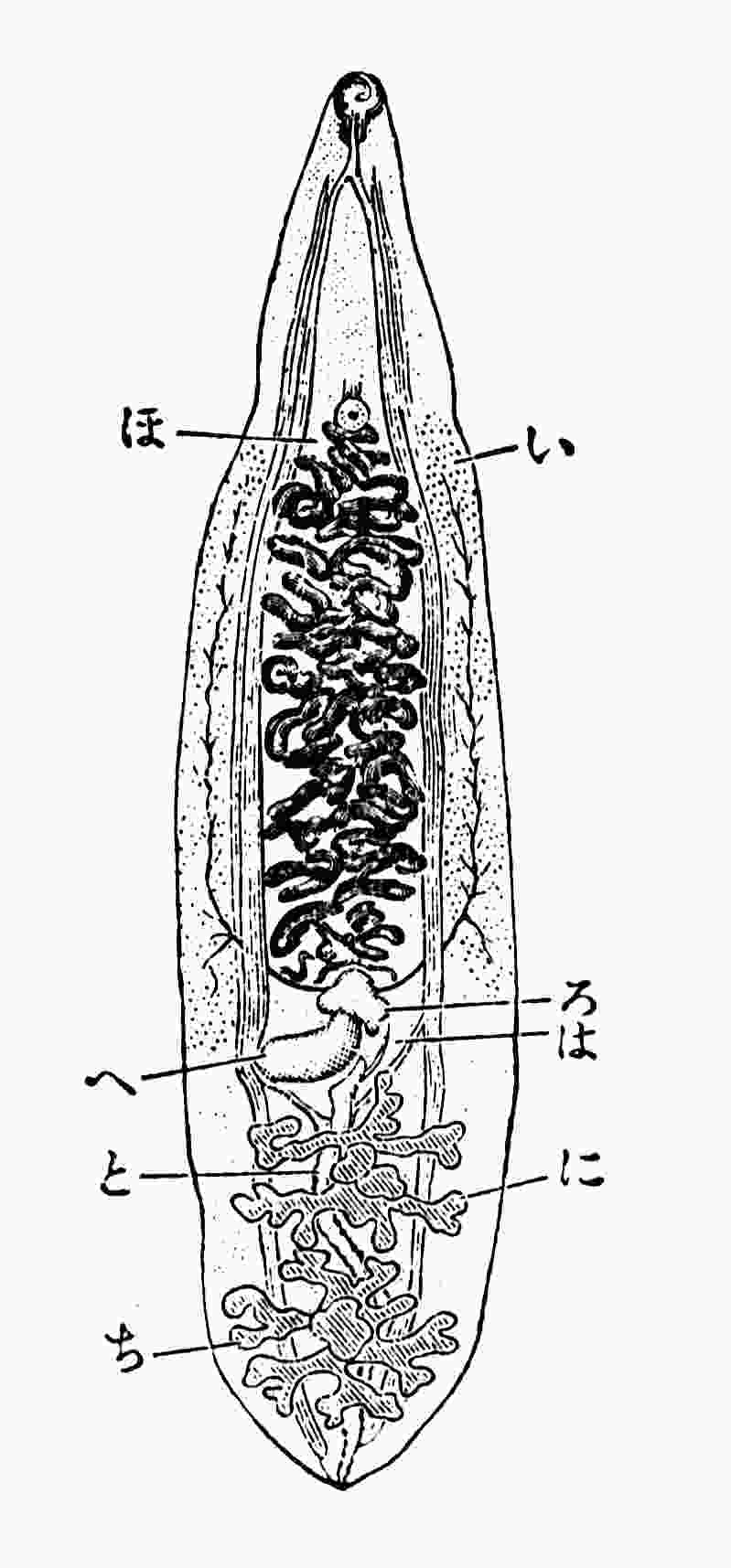
「ジストマ」の生殖器
(い)卵黄巣 (ろ)卵巣 (は)フウレル管 (に)睾丸 (ほ)子宮 (へ)受精嚢 (と)排泄管 (ち)睾丸
「ジストマ」のごとき真の内部
寄生虫であると、消化の
器官は
極めて小さく
簡単で、
内臓といえばほとんど
生殖器のみである。その代わり
生殖器はすこぶる
複雑で、
睾丸もあれば
卵巣もあり、
輸精管、
輸卵管、
成熟した
卵をいれておく
子宮をはじめ、
卵の黄身をつくるための
卵黄腺、これより
卵黄の出て行く
卵黄管、
卵の
殻を
分泌するための
殻腺などがあって、ほとんど体の全部を
占めている。それゆえ「ジストマ」の
解剖といえば、すなわちその
生殖器の
解剖ともいうべきほどで、それがまた
一種ごとに細かい点で
相違しているゆえ、「ジストマ」の
種類を
識別するには、まずその
生殖器を調べなければならぬ。これをもっても
寄生虫の身体では、
生殖器官が
如何に
重要な
位置を
占めているかがわかる。
さらに
条虫の
類になると、
消化器は全くなくなり、
吸着の
器官も頭の
端だけに
限られてあるゆえ、
一節ずつを取って見ると、その内部はことごとく
生殖器官のみで
満たされている。
卵の
熟するころのものは、
生殖器はすこぶる
複雑で、あたかも「ジストマ」と同じく
種々の部分から
成り立っているが、
卵が
熟し終わると、ただ
子宮のみが
残って、
卵巣、
睾丸、
卵黄腺、
殻腺など
残余の部分は
漸々消えてしまう。その代わり
子宮はだんだん大きくなって、ほとんど
一節の大部を
占めるようになる。
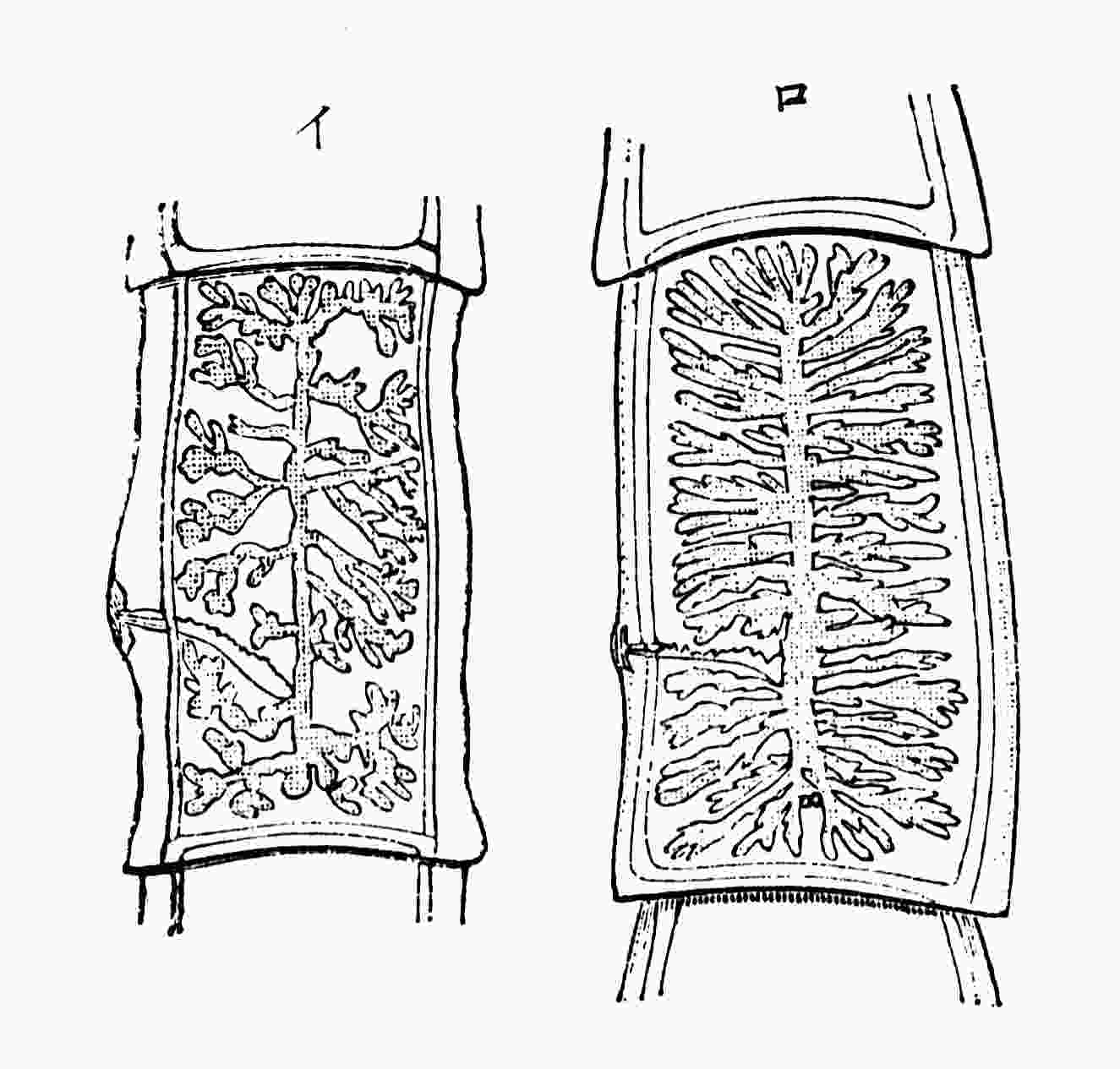
条虫片節2種
(イ)豚肉よりくるもの (ロ)牛肉よりくるもの
牛からくる
条虫でも
豚からくる
条虫でも
成長したものは、長さが四間(注:7.2m)
以上もあって
節の数が一千を
超えるが、
後端に近いところでは
節がみな大きくて、
生殖器官は
子宮ばかりとなっている。
一節ずつ
離れて、
大便とともに出て来るのはかようなものに
限る。
前に
例にあげた
蟹の
腹に
付着している
嚢状の
寄生虫なども、
生殖器官ばかりが大きく
発達して、そのほかの
内臓はほとんど何もない。この虫は頭部が
樹の根のごとき形にのびて、
蟹の全身にはびこり
滋養分を
吸い取ることはすでに
述べたが、ことに
卵巣や
睾丸のところから
滋養分を
絞りとるゆえ、
蟹はそのため全く
生殖力を
失うて子を
産むことができなくなる。その代わり、
寄生蟹のほうはそれだけの
滋養分がまわってくることゆえ、
卵が
非常に多くできて、身体はあたかも
無数の
卵粒を
包んだ
嚢のごとくになってしまう。実にこの
蟹などは理想
的の
寄生生活をなすものと言うてよろしいほどで、
蟹に
稼がせてその
滋養分を
吸いとり、しかもこれを
殺すまでには
絞らず、ただ、子を
産むというごときぜいたくをさせぬ
程度にとどめておいて、自身は運動の
器官も持たず、
感覚の
器官も
備えず、
吸い取った
滋養分は全部
生殖の
資料に用いて
限りなく子を
産んでいるのである。
いったん
宿主動物の体内にはいった後は
寄生虫の生活はよほど
安楽であるが、そこへはいり
込むまでは
容易なことではない。宿主動物の外部に
吸いつくだけならばあえて
困難というほどではないが、その
腸、
胃、
肺、
肝などの内まではいり
込もうとするには、
尋常一様の
手段では
成功がおぼつかない。
如何なる動物でも、自分の体内に
敵のはいりくるのを
防がずにいるものはなく、そのためにはなんらか相当な
仕掛けが
備わってあるゆえ、
寄生虫は正体を
現わしたままで正々
堂々と表門からはいり
込むことはとうていできぬ。
例えば「ジストマ」でも
条虫でも
蛔虫でも、そのままの形で口、鼻もしくは
肛門からはいって、
腸まで
無事に
達することはむろん
望みがない。もっとも
十二指腸虫や、そのほかの
若干の
寄生虫は、
幼虫時代の
極めて
微細なときに水の中に
游いでいて、もし人が
皮膚を
露出してかような水に
触れると、
直接に
皮膚にもぐりはいって
血液、リンパなどの通路に
達し、それより
迂回して
腸にいたるものであるが、これらの
例外を
除けば、たいがいの
寄生虫はみな口からはいり
込んでくる。
俗に「病は口から」というが、
寄生虫の場合には
実際口から起こるのがつねである。しからば
如何にして人に知られぬように口の
関門を
通過するかというに、これは
卵または小さな
幼虫の時代に食物などに
混じてはいりくるのであるが、次に二三の
例によってその
経過の
筋道を
述べて見よう。
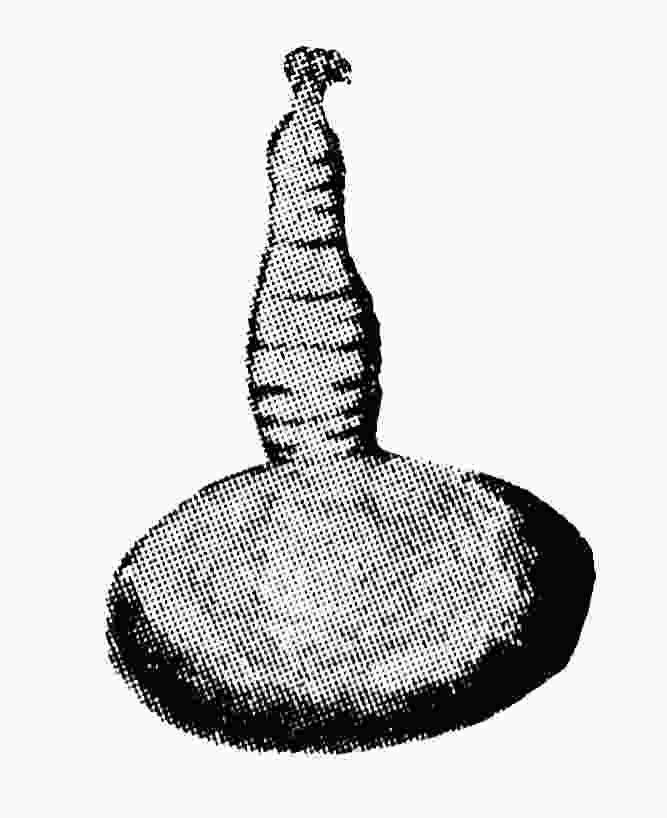 条虫の幼虫
普通
条虫の幼虫
普通に人間の
腸に
寄生する
条虫は
三種類あるが、そのうち
二種は
相似たもので、両方とも
節は
縦に長い長方形で、
成熟すると
一節ずつ
離れて出るが、ほかの
一種は
節の
幅が広くて
縦ははなはだ短く、かつ
幾節も
連続したままで
排出せられる。わが国でもっとも多いのはこのほうである。これらの
条虫が人間の体内にはいり
込むのは、むろんその形のはなはだ小さい時であるが、前の
二種の中の
一種は
豚肉の間に、
一種は牛肉の間にはさまり、後の
一種は
鮭や
鱒などの肉の中に
隠れ、いずれも肉とともに食われて人の
腸胃に
達する。
豚肉の間にはさまれている
条虫の
幼児は
直径三分(注:9mm)ばかりの
卵形の
嚢で、その表面の一点から中へ向こうて
条虫の頭が、あたかも
手袋の指を
裏返しにしたごとくに
裏返しになってついている。
嚢の中には水があるゆえ、かような
嚢状の
幼虫を指につまんで、力を
加減しながらやや強く
圧すると、頭部が
飛び出て真の
条虫の頭のとおりになる。
嚢状の部は後に
必要のないところで、食われる
際にかみ
破られても何の
差支えもない。ただ頭さえ
無事で
腸に
到着すれば、直ちに
吸盤をもって
腸の
粘膜に
吸いつき、
速やかに
成長して
一箇月の後には大きな
条虫に
成り終わる。牛肉の間にはさまっているほうは、これよりも小さいから見のがしやすいが、その
構造にはほとんど
変わりはない。また
鮭、
鱒の肉の間にあるのは形が細長くやや太い
木綿糸のごとくで
伸びれは
一寸(注:3cm)にもなる。これらはいずれも
柔らかい虫で、火で
熱すればたちまち死ぬゆえ、
牛豚肉でも魚肉でも十分に
煮るか
焼くかして食えば、けっして
条虫が生ずることはないが、とかく
肉類は中央が少しく生で赤色を
帯びているくらいのほうが味が
良いので、十分に火の通らぬものを食するゆえ、よく
条虫ができるのである。
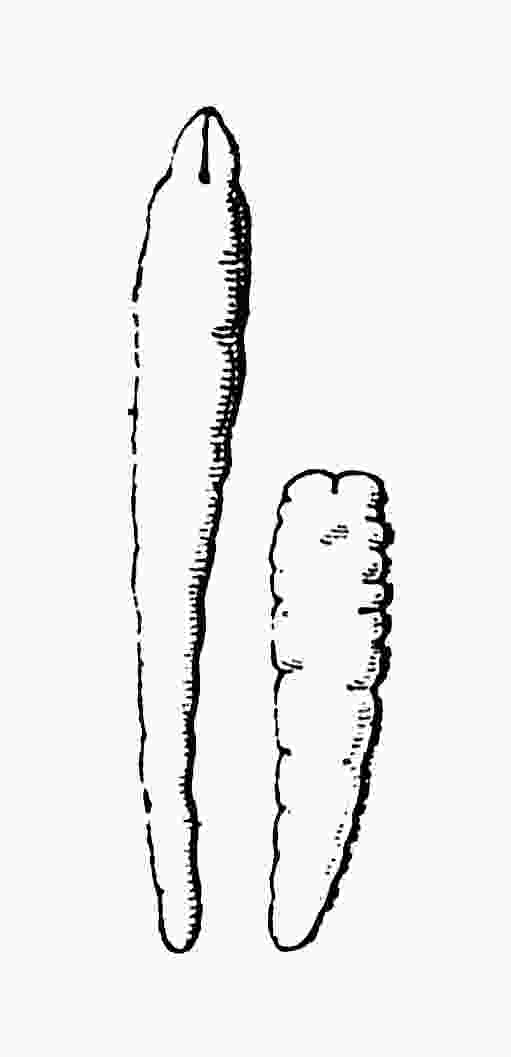 みそさなだの幼虫
鼠
みそさなだの幼虫
鼠を
解剖して見ると、ほとんど毎回
肝臓の中に
豌豆ぐらいの白い
柔らかな
嚢が
幾つも
埋もれているのを見出すが、これを取り出して切り開いて見ると、中から
条虫の
幼虫が出て来る。長さは時によって
違うが、大きいのはのばすと
一尺(注:30cm)にも
達する。しかしこれは
幼虫であって、そのまま
鼠の体内にとどまっていたのでは、いつまで待っても
成長せぬ。もし
猫がこれを食うと、
腸の中で
成熟して「ふとくびさなだ」と名づける
猫に
固有の
条虫となる。
 魚さなだ
魚さなだ
また
鰹の
刺身を食うと、
往々肉の上を白い虫のはうのを見ることがある。
極めて
柔らかい虫で、頭から四本の細い角を出したり入れたりするが、これも
条虫の
幼児で、もし
鮫がこれを食えば、その
腸の中に行って
成長した
条虫となる。
寄生虫は
宿主動物が死ぬと、自身も
暫時の後には死ぬものゆえ、この虫の生きてはいまわっているのは
鰹の肉の新しい
証拠で、古い肉に
蛆の生じたのとは全くわけが
違う。
鰹の
盛んにとれる地方では人がみなこの事を知っているゆえ、生きた
寄生虫が
匍うていなければ
鰹の
刺身をほめぬ。人間の
腸胃にはいれば、この虫はたちまち死んで消化せられるから少しも心配はいらぬ。「
肝臓ジストマ」はわが国にもっとも多い
寄生虫であるが、近年の研究の
結果、その
幼児が「もろこ」・「はや」などのごとき
淡水魚類の
筋肉の間にはさまっていることが知れた。これを
猫か人間かが食うと、
肝臓内にはいり
込んでたちまち
成熟し、日々多数の
卵を生ずるようになる。
条虫のごとく
腸の内にいるものとは
違い、
駆虫薬を用いて
退治するわけにゆかぬから、ほとんどこれを
除く
途はない。羊の
肝臓に
寄生する「ジストマ」の
幼児は、
極めて小さな
粒状をなし、
牧草の葉に
付着して羊に食われるのを待ち、もし食われれば直ちに
肝臓にはいって
成長する。すべて宿主動物の内部に生活する
寄生虫は、かくのごとくにいつも宿主動物の
好んで食するものの内にひそんでこれとともに体内にはいり
込むのであるが、中には
往々意表に出でた
手段を取るものがある。
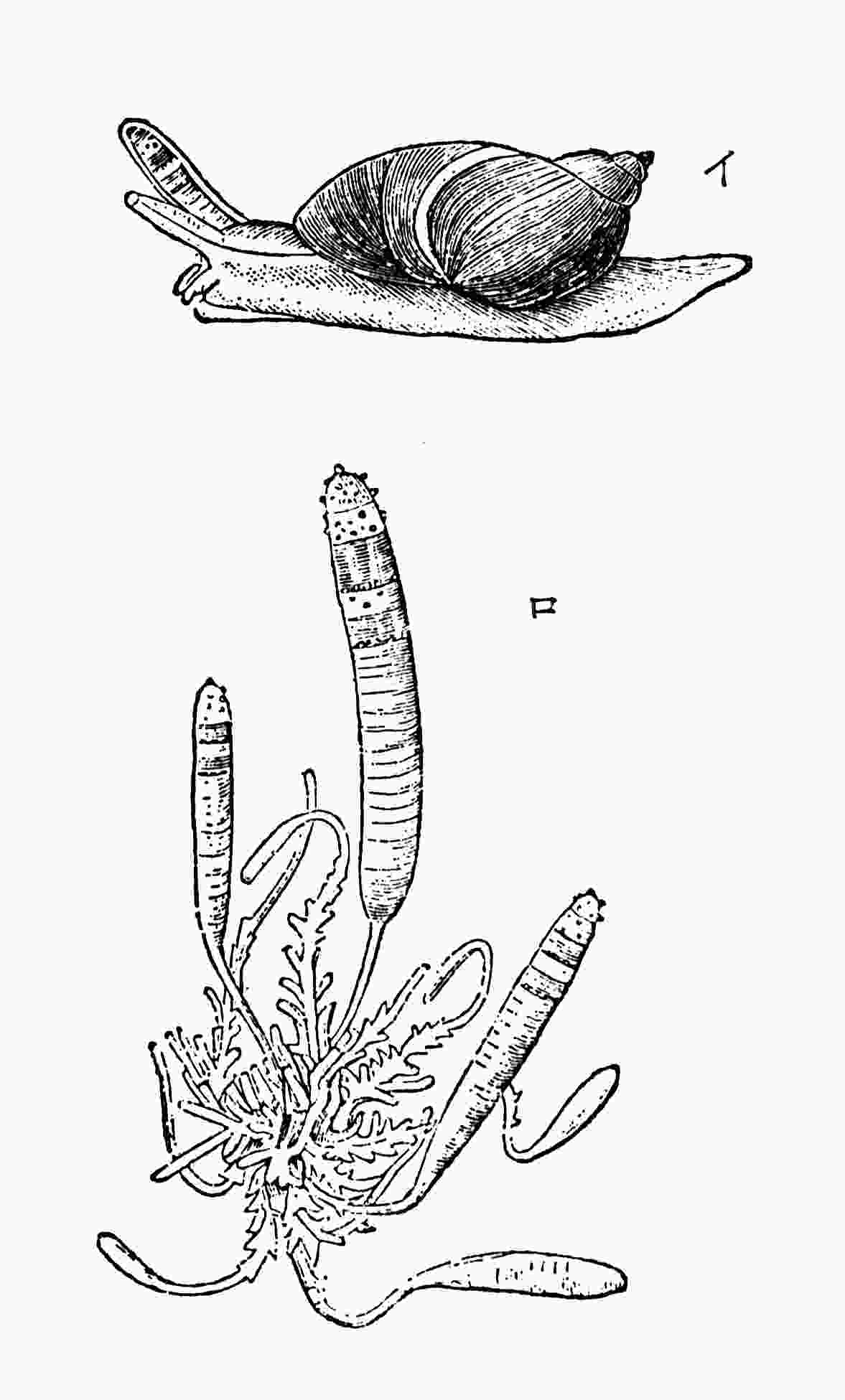
(イ)「ジストマ」の幼虫を含めるかたつむり。一方の角が太いのはその中に幼虫の一枝がはいっているため。
(ロ)その幼虫,枝の先の太いところはかたつむりの角の中に入り込む部分。
その
一例をあげて見るに、木の実を食う
鳥類に
寄生する
一種の「ジストマ」では、その
幼児は「かたつむり」に
似た
一種の
陸産貝類の体内に生活しているが、あたかも「つくね
芋」のごとき
極めて
不規則な形をしてかつその表面から
幾つも長い
枝のような
突起を出している。また貝のほうは
薄い黄色の
殻を持ち、頭には「かたつむり」のごとくに四本の角があって、長い二本の
尖端には
眼があるが、「ジストマ」の
幼虫の体から生じた
枝は、この角の中まで
延び入り、太くなって角を
椎の実のごとき形までにふくらませ、かつ赤い色や緑の色を生じて、
極めて目立つようにする。鳥はこれを見つけて木の実と
誤り、角だけをついばみとって食うが、角の中には「ジストマ」の
幼虫から生じた
枝があり、その中には
成長すれば「ジストマ」になれるだけの部分が
含まれてあるゆえ、たちまち鳥の
腸の内で発育して、
何匹かの
成熟した
寄生虫になる。また角を食い取られた貝のほうは一時は角を
失うが、
再びこれを生ずる
性質があるゆえ、
暫時の後にはもとに
復して角が
揃う。しこうして体の内にいる
寄生虫の
幼児の本体からは、さらに
枝が
延びて新しく生じた角の中にはいり
込み、
再びこれを
椎の実のごとくにふくらませ、かつ赤と緑との色を生ずると、また鳥がこれを見つけて食う。かく一度
寄生虫の
幼児が貝の肉の内にはいり
込むと、これが
基となって何回でも鳥の
腸の内にその
種類の
成熟した虫が生ずることになるが、これなどは
淡水魚類の肉にはさまれて人の体内にはいり来る「
肝臓ジストマ」等に
比して、さらに
手段が
巧妙である。
以上述べたとおり、
宿主動物の体内へ
寄生虫がはいり
込むには、その動物の
好んで食する
餌の内にひそんで待っているのが
最上の
方便であり、
餌の内にはいるには、まずその
餌が食物とするものの内に
隠れているに
如くはない。それゆえ、内部に
寄生する
種類の
卵から
成長するまでの発育の
順序を調べて見ると、二度も三度も宿主を
換えて、しまいに終局の宿主に
達し、そこで始めて
成熟して
産卵するにいたるものがすこぶる多い。
猫の
腸にはいろうとするにあたって、ただ
目的なしにとどまって待ったのでは、いつ
猫に食われる
機会に
遇うかほとんど
望みがないが、
猫のもっとも
好む
鼠の体内にはいっていれば、よほど食われる
見込みが多い。また
鼠の体内にはいるには
鼠の
好んで食いそうな食物に
混じて待っているよりほかに
上策はない。あたかも金持ちや
貴人に取り入るのに、
碁が
好きならば
碁をもって、
謡が
好きならば
謡をもって近づくのが、もっとも
成功の
望みある早道であると
理屈は
変わらぬ。しかしかような
方法は
籤を引くのと同じような
性質のもので、真に
目的を
達するものはわずかに一部分にすぎず、多くは
失敗に終わるをまぬがれぬ。
例えば
鼠の食物に
混じていなければ、
鼠に食われる
機会のないことはもちろんであるが、
鼠の食物に
混じていたとて
必ず
鼠に食われるとは
限らぬ。
鼠と同様の食物を食う者は他にいくらもあるから、せっかく
鼠の食物に
混じていても、
鶏に食われるかも知れず、または水に流され、風に
飛ばされなどして、ついに何物にも食われずに終わるやも知れぬ。また運よく
鼠に食われてその体内にはいり
得たとしても、
鼠が
猫に食われずして、
鼬か
狸か
鷹か
梟かに食われたならば、
寄生虫の
幼児はそのまま消化せられて
滅びねばならぬ。されば
寄生虫の
生涯は始めから終わりまで
投機的であって、終局の宿主の
腹の内に
到着するまでには
幾度か幸運を重ねなければならず、
成功した上は多少
安楽に
暮らせるが、
一匹を
成功せしめるためには、何千何万かは
犠牲となって
途中に
失敗せざるを
得ぬゆえ、
寄生虫は
無限の
繁殖力を有しながら、
実際はけっしてその
割合に
増加することはない。
二種の
相異なった生物が、一方は
滋養分を
吸い取られ、他は
滋養分を
吸い取りながら、
共同の生活をしていればこれを
寄生と名づけるが、このほかに
二種の生物がいくぶんずつか
互いに
利益を
交換するためか、もしくは一方だけが
利益を
得るために
相密着して生活する場合がある。これを
共棲と名づける。
 地衣の一種 梅の木苔
地衣の一種 梅の木苔
植物界でももっとも
著しい
共棲の
例は
樹木の
幹や、石の表面に
付着している
地衣類であるが、これは人も知るとおり、
菌類と
藻類との
雑居しているもので、
藻類は
有機分をつくって
菌類に
供給し、
菌類は
藻類をつつんで
保護し、両方から
相助けて
初めて
完全な生活ができる。しかもその
雑居の仕方が
極めて
親密で、
顕微鏡で見なければ
菌と
藻との
識別ができぬゆえ、昔は両方の
相合したものを
一種の植物と見なしていた。また動物と
微細な
藻類との
共棲はいくらもある。
例えば
淡水に
産する「ヒドラ」には緑色の
種類があるが、これは「ヒドラ」の体内に
単細胞の
緑藻が多数に生活しているためで、
藻類は「ヒドラ」に
保護せられ、「ヒドラ」は
藻類からいくぶんか
滋養分を
得て、
双方から助け合うている。
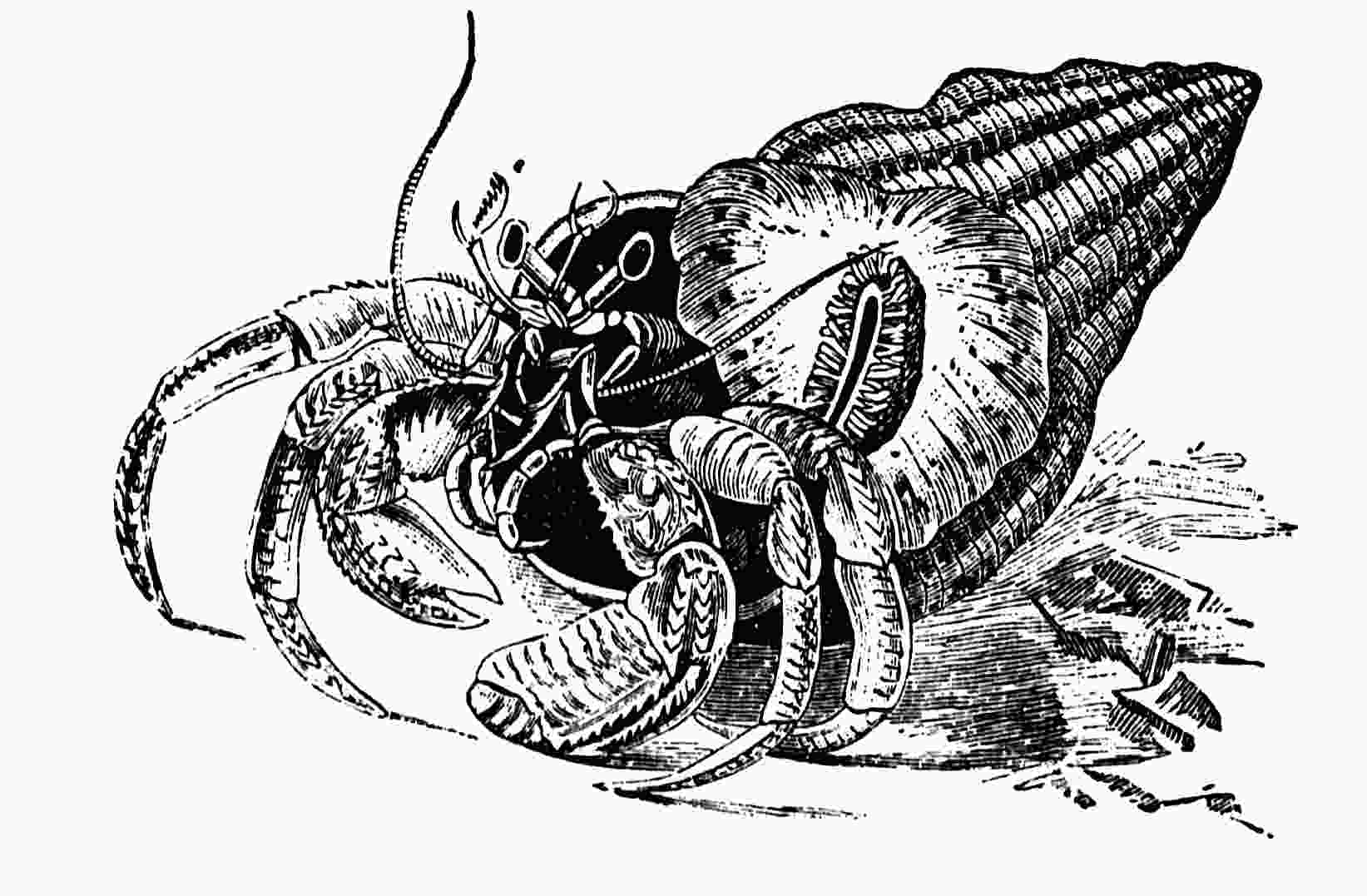 「やどかり」と「いそぎんちゃく」
「やどかり」と「いそぎんちゃく」
動物間の
共棲でもっとも有名になったのは、「やどかり」と「いそぎんちゃく」との
相助けることである。
浅い海で
手繰り
網などを引かせると、「やどかり」の住む
貝殻の外面に「いそぎんちゃく」の
付着しているのがいくらも取れるが「いそぎんちゃく」は自身には速く運動する力がないが、「やどかり」が
盛んにはい歩いてくれるために、つねに
変わったところへ
移り行くことができて、したがって
餌に
接する
機会も多く
得られる。また「やどかり」のほうは「いそぎんちゃく」の
痛くさすのを
恐れて、いずれの動物も
近寄らぬゆえ、
敵の
攻撃をまぬがれて、安全に身を
護ることができる。イタリア国ナポリの水族館で同じ
水槽の中に「いそぎんちゃく」のついた「やどかり」と「たこ」とが入れてあったとき、「たこ」はがんらい「えび」、
蟹類を
好んで食うものゆえ、「やどかり」を取って食おうとして足を
延ばしてつかみかかったところが、たちまち「いそぎんちゃく」にさされ
驚いて足を
縮め、その後はけっして「やどかり」を
攻めなくなった。
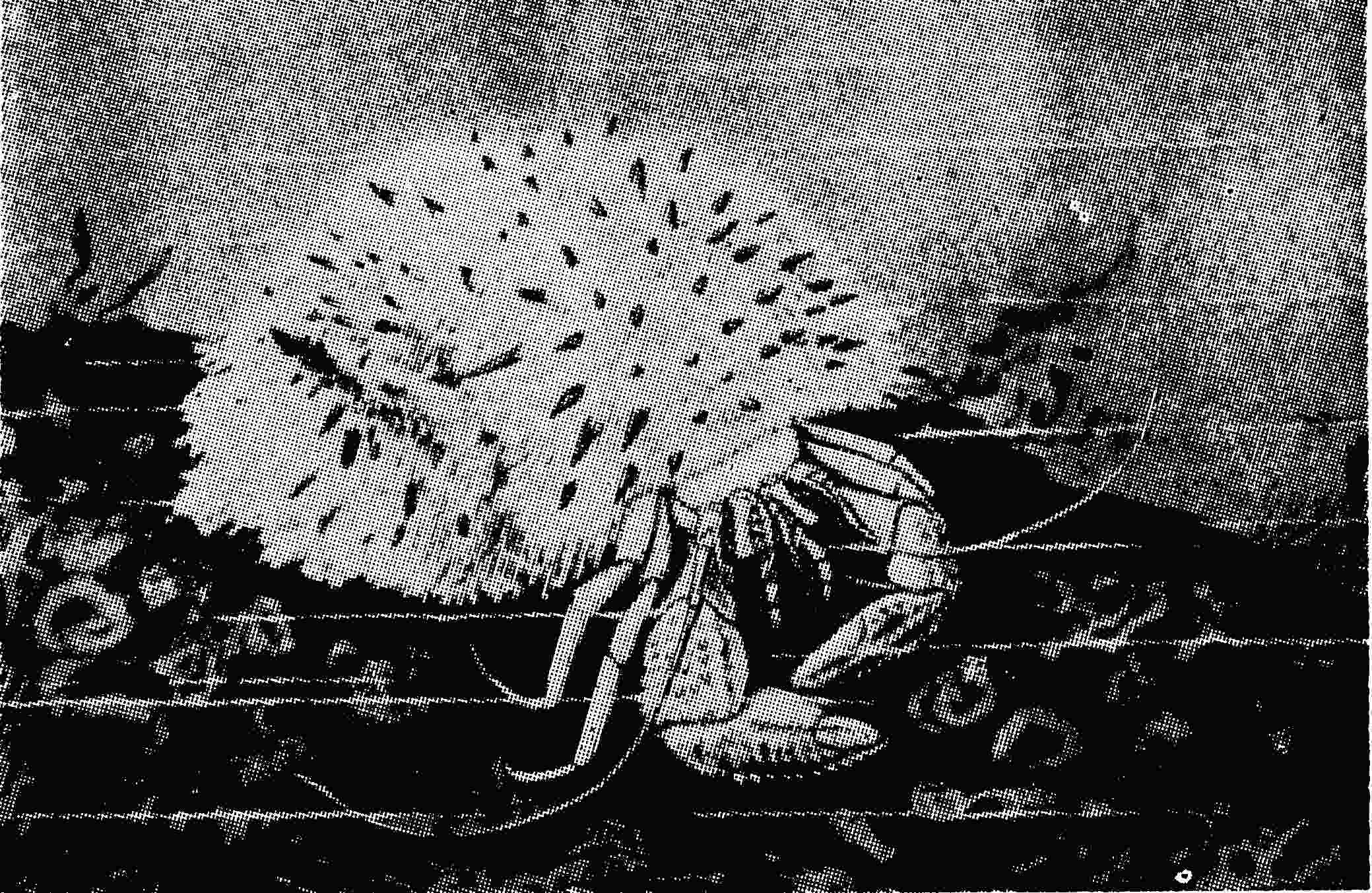 「やどかり」とさんご類の群体
「やどかり」とさんご類の群体
「やどかり」にはまた「さんご」に
似た動物の
群体を
殻の代わりに用いている
種類がある。これは始め小さいときに住んでいた
貝殻の表面に「さんご」のような虫が
固着し、これが
芽生によって
扁平な
群体をつくり、「やどかり」の
成長するとともに
群体のほうも
成長して、あたかも
貝殻と同じような
螺旋状の形となったのである。海岸を
散歩すると、
往々かような
群体の
骨骼だけが
浜に打ち上げられているのを見つけるが、形は
貝類の
殻のとおりで、しかも
質はやや
柔らかく、色はやや黒く、内面はなめらかで、外面には短い
針がたくさん出ているゆえ、
以上の
関係を知らぬ者には何の
殻であるかちょっと
鑑定ができかねる。その他「やどかり」には赤色のきれいな
塊状の
海綿を家とし、これをかついではい歩く
種類もある。
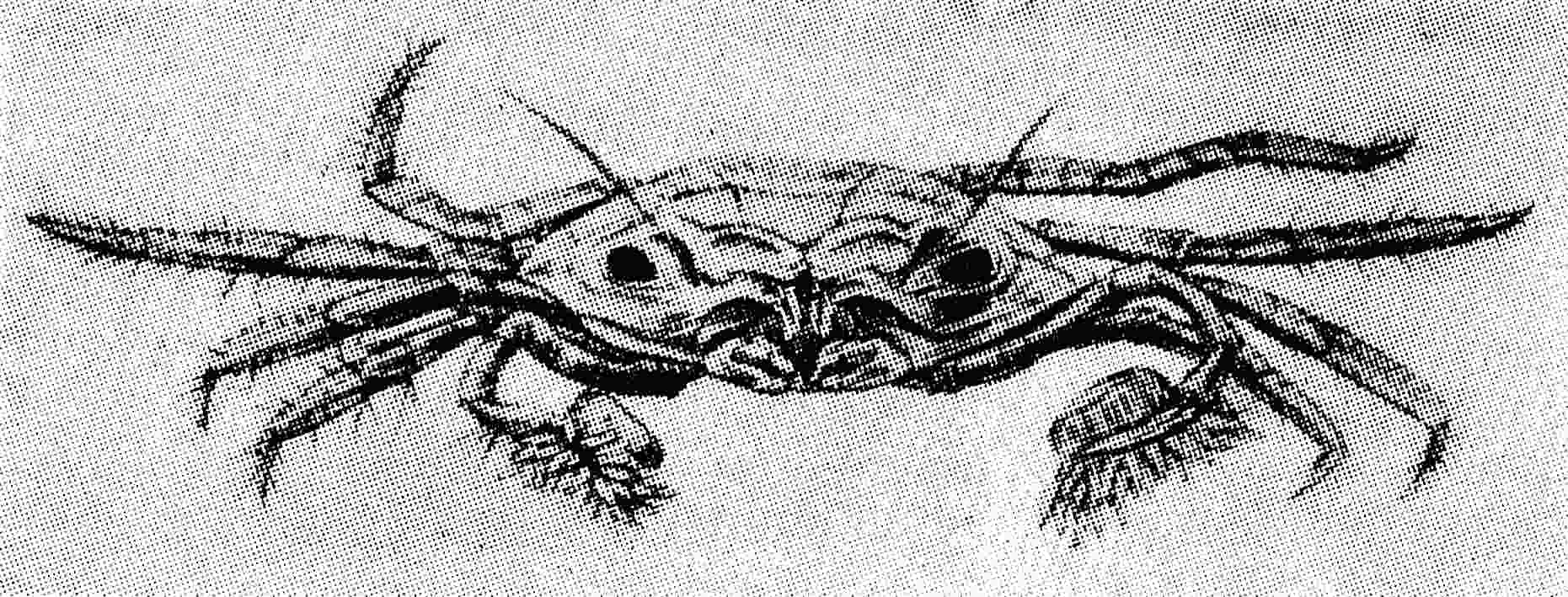 「いそぎんちゃく」をはさむ蟹
「いそぎんちゃく」をはさむ蟹
これらはいずれも前の「いそぎんちゃく」の場合と同じく「やどかり」は身を
護るの
便宜を
得、相手の動物は「やどかり」の運動力を
利用して、両方ともに生活上の
都合がよろしい。なお
蟹類の
一種にはつねに左右の
鋏に「いそぎんちゃく」を
一匹ずつはさんでいて、
敵が
攻めに来るとこれを
突き出して、
辟易させるものがある。この場合には
蟹が「いそぎんちゃく」を
護身用の
武器として
利用するだけで、「いそぎんちゃく」のほうはあるいは
迷惑かも知れぬが、はさむ
蟹も、はさまれる「いそぎんちゃく」も
種類がつねに定まっているところを見ると、これまた
一種の
共棲であって、けっして
偶然の思いつきではない。
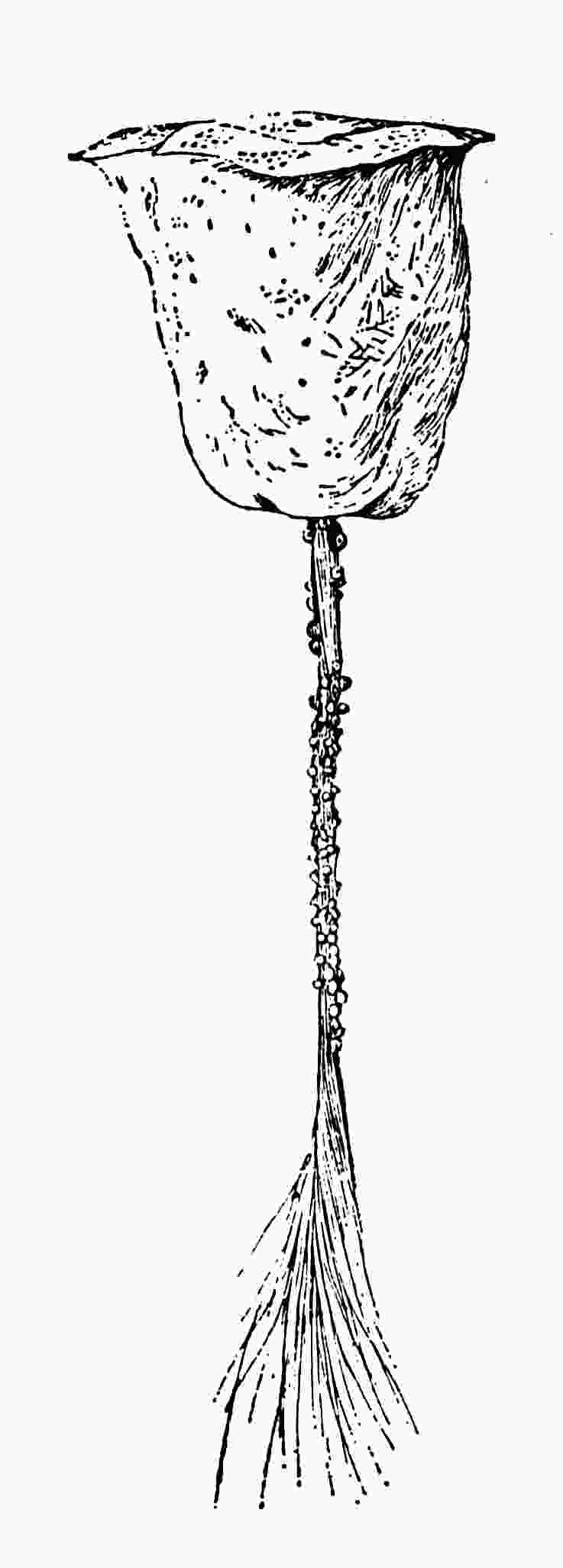 ほっす貝
相模灘
ほっす貝
相模灘の深い
底から取れる有名な
海綿に、
払子貝というものがあるが、そのガラス糸を
束ねたような細長い
柄の表面には、いつも
必ず
一種の「さんご虫」がたくさんに
付着している。しこうしてこの「さんご虫」は
払子貝の
柄よりほかのところにはけっしていない。今では
払子貝は
一種の
海綿であって、その
柄も
海綿体の一部であることを小学校の
生徒でも知っているゆえ、
江の島辺の
土産にも全部
完全したものを売っているが、昔は
柄だけを
抜き
離し、さかさに立てて
植木鉢に植えたものが店に
並べてあった。しこうしてその
茎と見える部の表面に、「たこ」の足の
疣に
似た形のものが一面にあるのは、すなわちこの「さんご虫」のひからびた
死骸である。
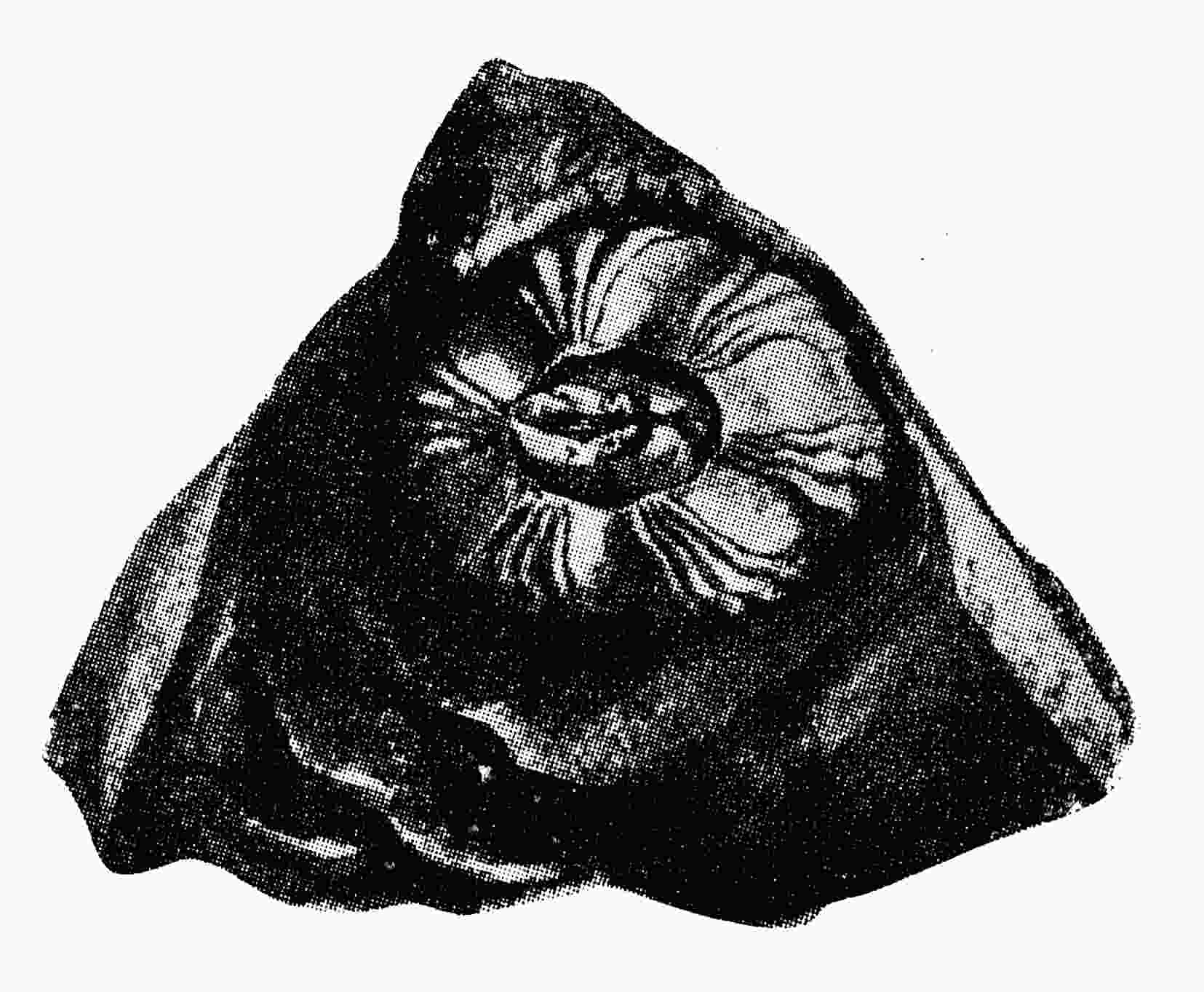 鯨のふじつぼ
鯨のふじつぼ
また
鯨の体の表面にはところどころに大きな「ふじつぼ」が
付着しているが、この
種類の「ふじつぼ」は
鯨の体に
限って
付着し、そのほかの場所にはけっしていないゆえ、これも
一種の
共棲である。
海亀の
甲についている「ふじつぼ」もつねに
種類が一定して、
海亀の
甲よりほかのところにはけっしていない。すべてこれらの場合には、大きなほうの動物はただ場所を
貸し、小さなほうの動物はただ場所を
借りるだけで、それ
以外に
別に
利益を
交換するごときことはないように見える。
 こばんいただき
こばんいただき
「さめ」やその他の大きな
魚類の表面には、
往々「こばんいただき」という
奇態な魚がついていることがある。この魚は「さば」、「かつを」などに
類するものであるが、頭部の
背面に
小判形の大きな強い
吸盤があって、これを用いて他の
魚類の口の
近辺に
吸い着き、その魚の
游ぐにまかせてどこまでも
従うて行く。いったい「さめ」の
類は
鋭い歯をもって他の大魚の肉をかみ
裂いて食うものゆえ、そのたびごとに肉の
小片が水中に
溢れ
浮かぶが、「こばんいただき」はかような肉の
残片を口に受けて
餌とするのである。それゆえまず
魚類中の
乞食となづけてもよろしかろう。海岸の
漁師町では
往々この魚の生きたのを
子供がもてあそんでいることがあるが、たらいに海水を入れた中へ放すと、直ちに
底へでも
横側へでも頭で
吸い着いてけっして
離れず、頭のほうへ向こうてならば動かすことができるが、
尾を
握って後のほうへ引いてはとうてい動かず、力まかせに引っ
張ると、たらいごと動く。かように強く
吸い着く
性があるゆえ、オーストラリアの北にあたる
或る地方では、土人がこの魚の
尾に
縄をしばりつけ、
海亀のいるところに放して
吸い着かせ、
縄を
手繰り
寄せて
亀を
捕える。この魚などはつねに「さめ」や「あかえい」に
付着しているゆえ、
鯨と「ふじつぼ」とを
共棲と見なせば、これも同じ
理屈で
共棲と名づけねばならぬ。また
仮に、「こばんいただき」がつねに「さめ」の口の内面に
吸い着いているものと
想像すれば、
必ず
寄生と名づけられるに
相違ない。かくのごとく
共棲は一面には、ただ場所を
借りるだけの
独立生活に
移り行き、一面には
寄生生活に
移りゆいて、をその間にはけっして
判然たる
境界定めることはできぬ。
生物界の活動が大部分は
餌を食うためである
以上は、どの
種族のどの
個体でも、食われぬ
術に
秀でたものでなければ生命は
保たれぬ。今日
生存する六十
余万
種の動物を見るに、みななんらか
敵に食われぬための
方法を
備えている。しかし
餌を
捕えて食う
側の
方法も進歩しているゆえ、なかなか安心してはいられず、食う
方法と食われぬ
方法との
競争に勝ったもののみが、よく
天寿を
全うすることができるのである。動物が
敵の
攻撃に対して身を
護る
方法は実に
種々雑多で、これだけを集めて書いても大部な書物になるくらいゆえ、ここにはいちいち
詳しいことを
記述するわけにはゆかぬが、その
方法の
相異なったもの
若干をあげ、それぞれ二三の
実例によってこれを
説明しておこう。
ここにちょっと
断っておくべきことは、動物が自ら身を
護る
方法でも、
餌を
捕えて食う
方法でも、
一種ごとにその相手とするものはほぼ定まっていて、けっしてすべてのものに対して同等に
有効というわけにはゆかぬ。
例えば
堅い
殻をおおって身を
護るにしても、多数の
敵はこれで
防ぐことができるが、その
殻をも
破り
得るほどに力の強い
敵、またはその
殻を
溶かすほどの強い
劇薬を
分泌する
敵に
遇うてはとうていかなわぬ。しからば
如何に強い
敵が来ても、これを
防ぎ
得べき
厚い
殻を
備えたらばよろしかろうと考えるかも知らぬが、それでは
普通の
敵を
防ぐためには
厚すぎて
不便である。
如何なる
器官でも、これをつくって
維持してゆくには
必ず
資料を
要する。しこうして
器官が大きければ大きいほど、これに
要する
資料も多いから
必要以上に
殻を
厚くすることは、すなわち
滋養分を
浪費することにあたる。
極めてまれに
出遇う
特殊の
強敵をも
防ぎ
得んがために、
日常莫大な
滋養分を
浪費するのと、
普通の
敵を
防ぐに
有効なる
程度にやめて
滋養分を
節約し、
剰余を
生殖の方面に向けるのとではいずれが
策の
得たるものであるかは問題であるが、多くの場合には後のほうが
割がよろしい。かような
関係からたいていの動物では、その
護身の
方法には一定の
標準があって、相手と見なす
敵動物はほぼ定まってある。ここに
述べる食われぬ
方法というのも、
各動物の
標準とする
敵に対して
有効ならば、それで
目的にかなうたものと見なさねばならぬ。
なお一つ言うべきことは、先方から
攻めて来るのを待たず、当方より食うてかかるのも、食われぬ
法の
一種である。およそ
如何なる
武器でも、
攻撃にも
防御にも役に立つもので、同一の
剣と
鉄砲とで、
敵を
攻めることも味方を
護ることもできるとおり、動物でも
攻める
装置の
備わってあるものは、
特に食われぬためのみの
方法を取るにはおよばぬ。
堅い
甲をおおった
亀は
敵に
遇うごとに、頭と手足と
尾とを
縮めるに反し、「すっぽん」は
敵を見れば進んでかみつこうとする。それゆえ
甲は
柔らかくてもこれを
襲う動物はかえって少ない。ここには
敵を
攻めるのと同一の
武器を用いて身を
護る場合はいっさい
略して
述べぬこととする。
「三十六計
逃ぐるに
如かず」とは昔からよく言うことであるが、生物界においても
敵にまさった速力を有すること、および
敵の来たり
得ざるところへ
速やかに
逃げ
移ることは、食われぬ
法の中でもっとも
有効なものである。およそ
速やかに
飛び、走り、
游ぐ動物は、多くはこの
方法を用いている。しかし、またこれらを
餌とする動物は、さらにこれにまさった速力が
必要であるが、かような
敵に
出遇うてはむろん
成功を期することはできぬ。
獣類中では
兎、
鼠等の
齧歯類、
鹿、羊等の
食草類がそのもっとも
著名な
例であるが、これらは毎日
逃げることによってのみ、その身を全うし
得るもので、万一足が弱くなった場合には
一刻も
生存はおぼつかない。
鳥類のごときはほとんど全部速力を
頼みとしている。
山間の
渓流で美しく鳴く「かじか
蛙」、夏草の間を走る「とかげ」、「かなへび」を始め、
捕えようとしても
容易に
捕えがたいのはみな
巧みに
逃げるからである。池の表面に
游ぐ「めだか」でも、水の上を走る「あめんぼ」でも、なかなか
網ですくえぬことはだれも
子供のころの
経験で知っている。
速やかに
逃げる動物に
必要なことは、
敵のいまだ近くまで
寄り来たらぬうちにこれを知ることである。それには
視るための
眼、もしくは
聴くための耳、または
嗅ぐための鼻が大いに
発達していることが
肝要である。
兎は耳の長いので有名であるが、他の
獣類でも
速やかに
逃げるものならばみな
相応に耳が大きい。
鳥類が
鉄砲打ちを
容易に近づかせぬのは
眼が
鋭いからであるが、
鹿などは少しでも
怪しい
香がすると、たちまち遠くへ
逃げて行く。それゆえ風上からはとうてい近づくことはできぬ。かように
逃げる動物には運動の
器官のほかに、
感覚の
器官も
必ず
発達しているゆえ、これを
捕えて食うものは
必ずそれ
以上に
発達した運動、
感覚の
器官を
備えねばならぬ。
逃げる動物と追う動物とは、つねにこの両方面の
競争をしているわけで、これに負けたものは、食われて死ぬか食わずに死ぬか、いずれにしても
生存ができぬ。
単に
敵と速力を
競うだけではあたかも
競馬のごとくで、もし少しでも
敵より早く
疲れたならば、
必ず
敗れねばならぬが、
敵の追いかけて来られぬところへ
移れば一時はとにかく安全である。
例えば
狼に追われて
樹に登るとか、
虎に
攻められて水中に
潜るとかいうごとき
法をとれば、
当座の
危難をまぬがれ、
疲れを休め、力を
回復することもできる。
 ももんが
ももんが
動物の中には、この
法を用いて
敵からのがれるものがすこぶるたくさんある。
樹の
茂った山に住む「むささび」、「ももんが」などはその
一例で、つねに
樹の
枝を
昇降して
果実を食うているが、「てん」に追い
詰められたりすればたちまち
枝を
飛び
離れ、前足と後足とを開いてその間の
膜を
張り、空中を
滑走して谷の向こうにある
樹までも
逃げて行く。
 とびかえる
とびかえる
「とかげ」の
類にも
肋骨を左右に開き、その間の
膜を用いて空中を
滑走するものがあり、
雨蛙の
類には、四足ともに指が長く
蹼が広くこれを
開けばあたかも
蝙蝠傘のごとき形となって、やや遠いところまで
枝から
枝へ空中を
飛び
得るものがあるが、これらはいずれも
昆虫を
捕え食うものゆえ、その空中に
飛び出すのは、
敵から
逃げるための時もあり、また自ら
餌を
求めるための時もあろう。
飛ぶ「とかげ」も
飛ぶ
蛙もともに
印度熱帯地方の
産である。
 とびうお
飛魚
とびうお
飛魚が水上に
飛び出すのも
敵からのがれるためである。水中では
飛魚を追いかけ
捕えて食おうとする大魚がたくさんにいるが、これから
逃げるために、
飛魚はまず全身の
筋肉を
働かせ、
尾で水を
跳ねて空中におどり出で、ほとんど身体と同じ長さの大きな
胸鰭を
扇のごとくに開き、空中に身を
支えながら三四回も波形を画いた後に、出発点よりは
約二丁(注:218m)もへだたったところで
再び水中に帰る。かくすれば水中の
敵からは
逃げられるが、空中にはまた
'鴎の
類が
飛魚の
飛び出すのをねらうて、
捕え食おうと待ち受けているゆえ、
何匹かは
必ずその
餌となるをまぬがれぬ。どこへ行っても生活はけっして
安楽ではない。
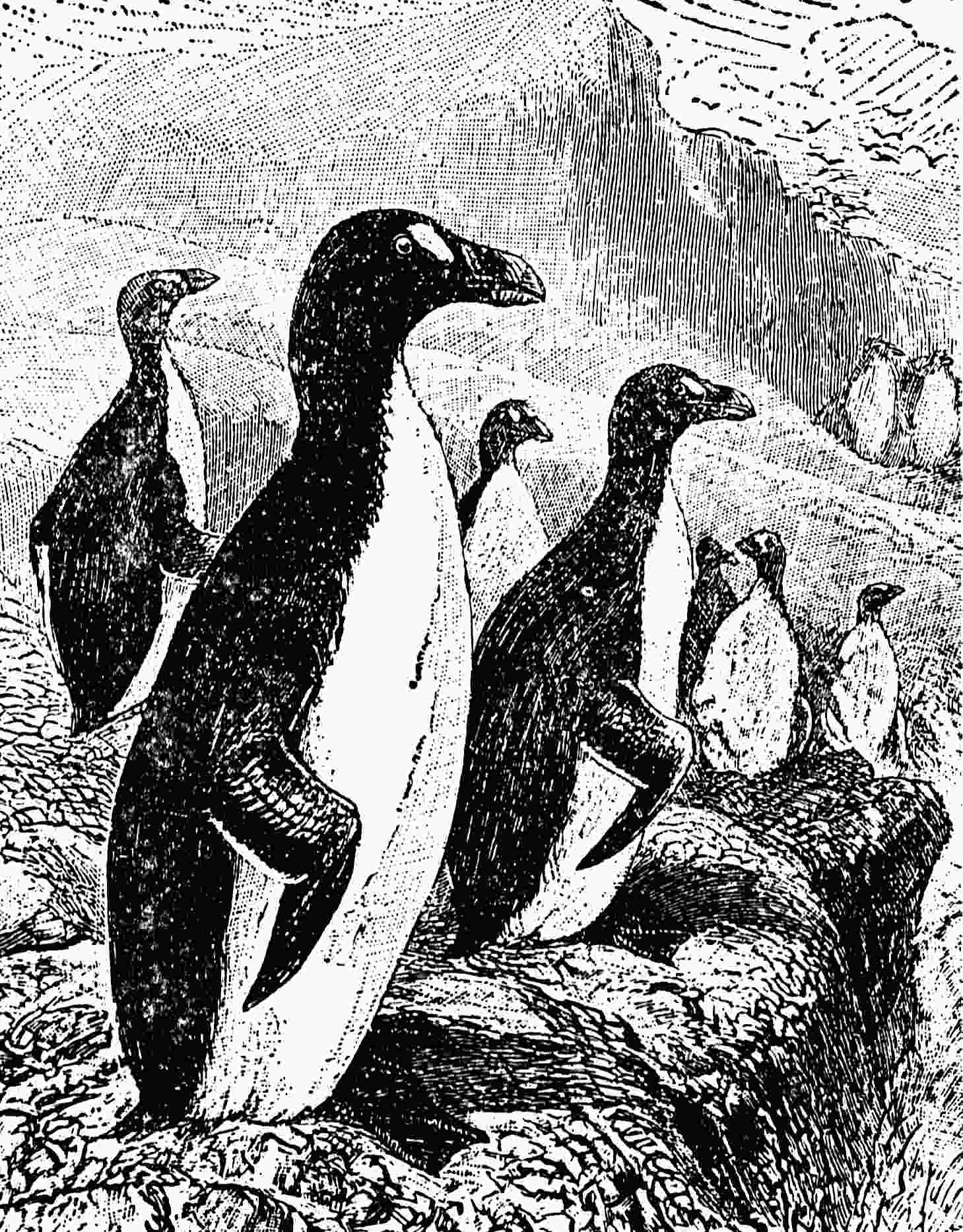 ペンギン鳥
以上
ペンギン鳥
以上はいずれも
敵を後に
残して空中へ
飛び出すものであるが、
敵に食われぬために水中へ
逃げ
込む動物もたくさんある。「おっとせい」、「あしか」、「あざらし」のような
海獣は身体の
形状が
遊泳に
適して、
陸上では運動がすこぶるへたであるゆえ、
敵に
遇えば直ちに水中に
飛び
込んで
逃げる。「かわうそ」なども
危険に
遇えばまず水中に
逃げ
込む。
南極に近いほうの
無人島に
非常に数多く
棲息する「ペンギン鳥」も、つねには岩の上に一面に
並んでいるが、
責められればたちまち水中に
飛び
込んで
逃げる。
翼がきわめて短く、かつ羽毛がほとんど
鱗のごとくであるゆえ、むろんこの鳥は空中に
飛翔することはできぬが、その代わり水中にはいれば
翼を用いてあたかも魚のごとくに自由
自在に
遊泳する。
雁や
鴨が
游ぐのは全く足の運動によるが、「ペンギン鳥」では足はただ
舵の役をつとめるだけである。なお
逃げることによって身を
護る運動はいくらでもあって、だれも知っているものが多いから、わざわざ
例をあげることは
以上だけにとどめておく。
隠れるという中には、
敵に見える場所から
敵に見えぬ場所へ
移ることと、
平常から見えぬ場所にとどまっていることとが
含まれてあるが、両方ともに動物界にはその
例がたくさんにある。
巧みに
隠れることは、
敵に食われぬ
法の中で、もっとも
有効なしかも
労力を
費やすことのもっとも少ない
経済的なものであるが、しかしまたこれを
探し出すことを
専門とする動物が
必ずあるゆえ、
隠れたりとてけっして全く安全とはいわれぬ。ただし
隠れなければ数百数千の
敵に
襲われるべきところを、
隠れているためにわずかに二三の
特殊の
敵に
攻められるだけですむのであるから、
隠れただけの
効能はもちろんある。そのうえ
獅子、
虎のごとき
無敵の
猛獣でも、安心して休息するためにはやはり
隠れ場所を
要するゆえ、動物中で真に
穏れる
必要のないものは、おそらく大洋の表面に
浮かんでいる
水母のごとき
種類のほかにはなかろう。
敵が近づけばたちまち
隠れる動物はすこぶる多い。これは見えるところから見えぬところへ
移るのであるから
逃げるのの
一種であるが、その時
即座の
鑑定によって
適当な
隠れ場所を
求め
逃げ
込むものと、あらかじめ
隠れ場所をつくっておき、つねにその
近辺のみにいて、
敵が見えればたちまちそこへ
逃げ帰るものとある。海岸の岩や
石垣の上にたくさん走りまわっている船虫は、人の
影を見れば直ちにもっとも近い
割目にはい
込むだけで、
別に
巣のごとき定まった場所はないが、
砂浜に多数にいる
小蟹は
各自に一つずつ
孔を
穿ち、つねにその近くにいて、もし人が来たり近づくと、みないっせいに自分の
孔に
逃げ
込む。
潮のひいたときに、
鋏で
砂粒をはさんで
餌を
求め食う
挙動が、あたかも
招くごとくであるゆえ、
俗に「
潮招き」と名づける。走ることが
極めて
速やかで、かつ
孔が近くにあるゆえ、
捕えることはすこぶる
難い。
狐、
狸でも
兎の
類でも、追われれば直ちに
穴に
逃げ
込むものゆえ、これを
猟するには
特に足の短い
猟犬の助けを
借らねばならぬ。
敵の多い世の中に、全身を
露出していることはよほど
不安の感じを起こすものと見えて、
海産動物を
飼養する場合に、もし
砂や
石塊を入れて
隠れ家をつくってやると長く元気に生活するが、ただ水ばかりの中に入れておくと、
暫時的なしにはいまわった後にだんだん
衰弱して死ぬものが多い。動物を
採集に行った人はだれでもよく知っているとおり、
現われたところのみを
探しては何もおらぬようなときにも、石をくつがえし、
泥を
掘り、皮を
剥がし、
枝を打ちなどすると、意外に多くの動物が出て来る。海の
底から取って帰った石を海水に
漬けておくと、二三日すぎて水が少し
腐りかかるころになって、はじめ見えなかった虫がたくさんにはい出すことがあるが、これは石の
孔の中に
隠れていたのが苦しくなって、出て来るのである。
特に
不思議に見えるのは、岩に
孔を
穿って、その中に生きた貝が、はまり
込んでいることで、
蜆や
蛤と
同類の
二枚貝が
如何なる
方法で岩石に
孔を
穿ち、その中へ
固くはまって取り出せぬようになるかは、よほど
詳しく研究せぬと明らかにならぬ。ところによると海岸の岩に一面に
孔があって、その中に「にほ貝」という
貝殻の
薄い貝が
一匹ずついる。
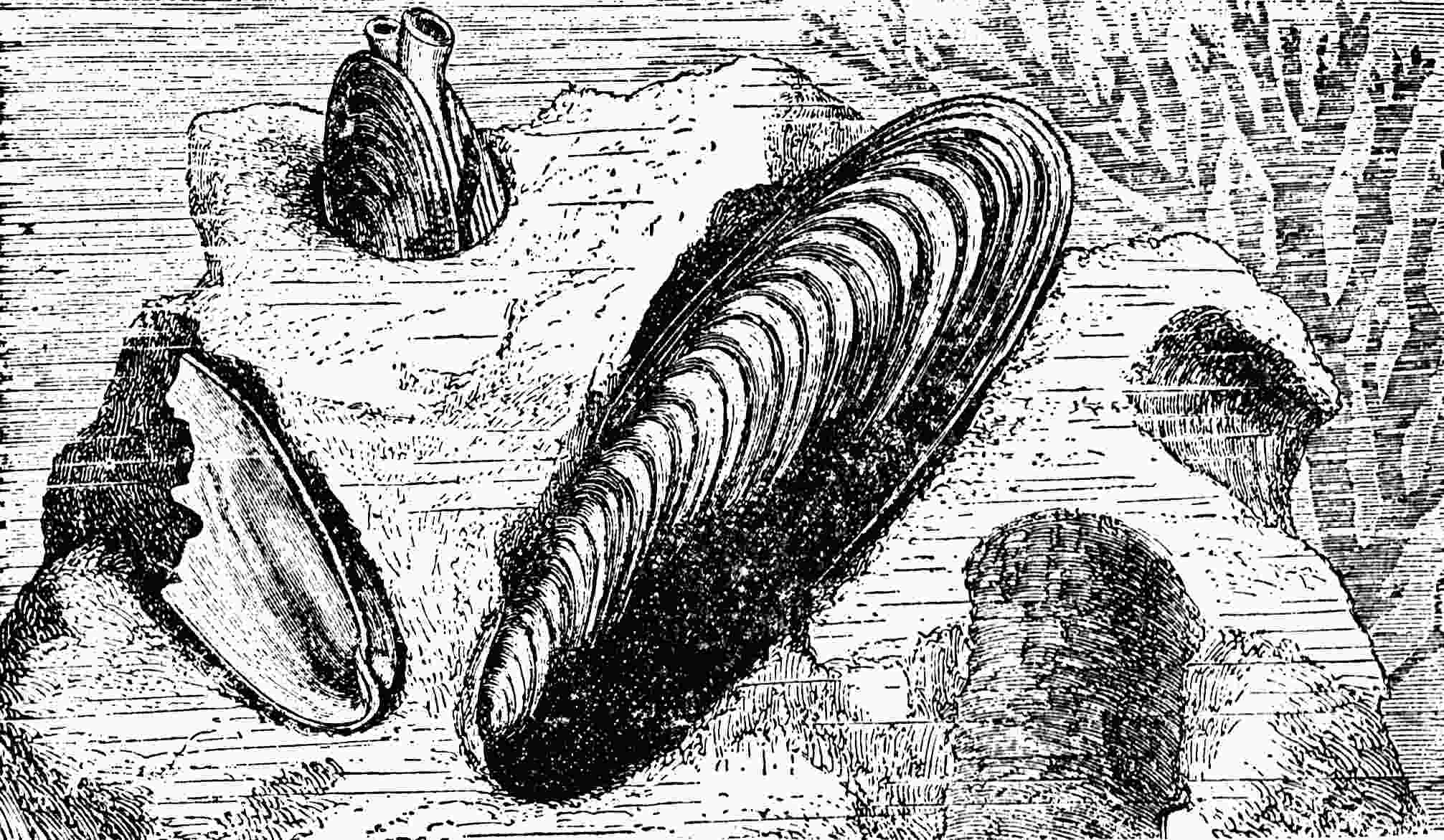 石食い貝
石食い貝
また海岸の岩を
破ると、中から「石食い貝」または「石まて」と名づける、
椎の実を長くしたごとき形の貝がたくさん出て来るが、これらは自身で
穿った
孔の中に
隠れていたものである。「にほ貝」は夜光を発するゆえ、イタリアの
漁師の
子供などはこれをかんで口中を光らせ、暗いところで人を
驚かしてたわむれる。
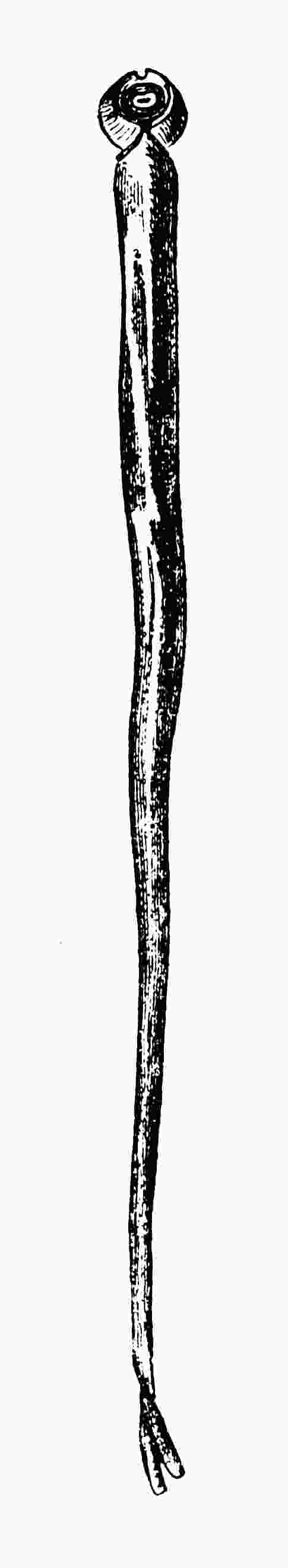 船食い貝
船食い貝
海中には
材木に
孔を
穿ってその中に
隠れる貝もある。岩に
孔をあけるとは
違い、人のつくった
桟橋や
船底の木を
孔だらけにするゆえ、なかなか大きな
損害を生ずる。
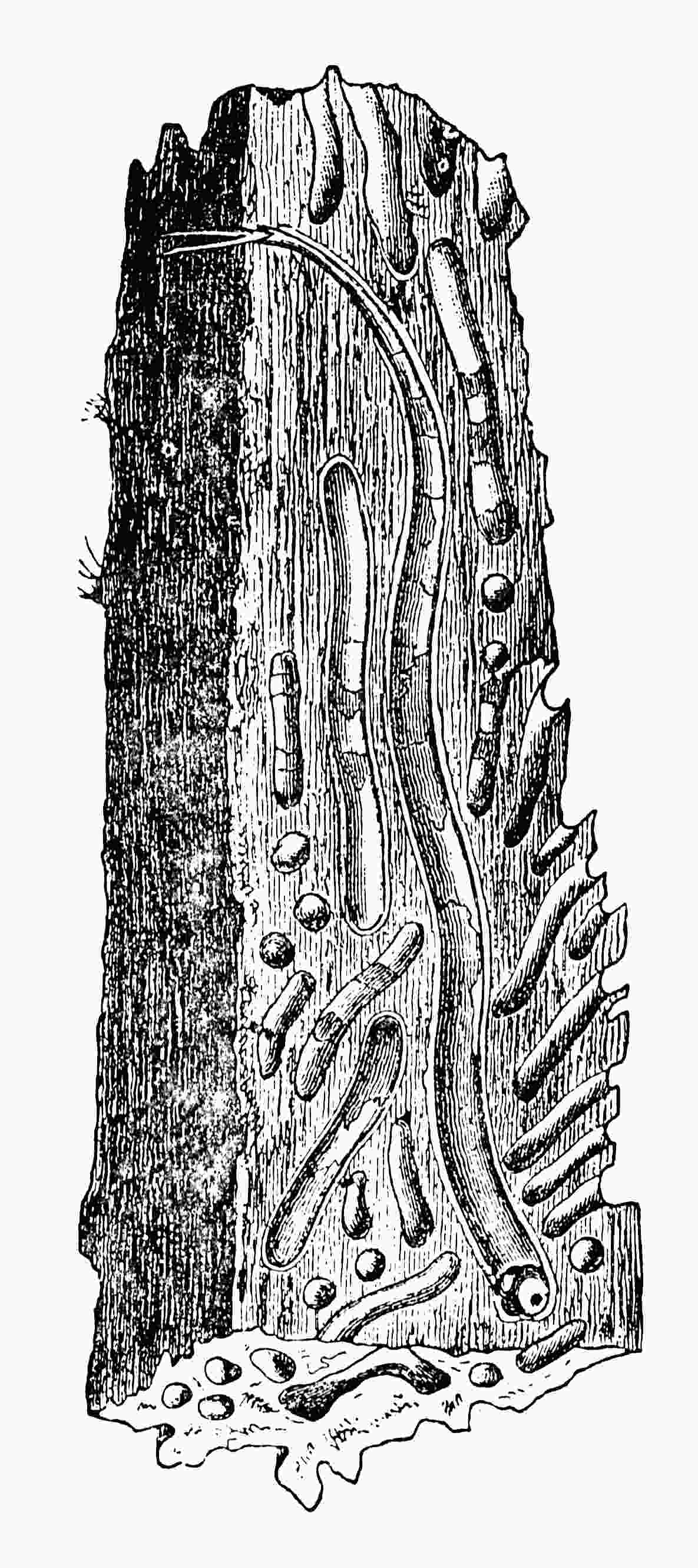 船食い貝の害
船食い貝の害
日本で
風流な
住宅の
周囲の
塀に用いる船板には、表面にわん曲した長い
凹みがたくさんに見えるが、これがみな、「船食い貝」のしわざであって、このために船は
廃物となり、板のみが後に
利用せられているのである。たいていの
二枚貝は、
蛤でも「あさり」でも「かき」でも
蜆でも、
殻を
閉じれば
柔らかい肉は全部その内に
収まるが、「船食い貝」だけは、
普通の貝とは
違い、体は「みみず」のような細長い形でほとんど全部
露出し、
殻は左右とも
極めて小さく、わずかに体の
前端をおおうにすぎぬ。
幼時は水中を
游いでいるが、
材木の表面に
付着すると直ちにこれに
孔を
穿ってはいり
込み、だんだん
随道をのばしてその内面に
薄い
石灰質の
壁をつくり、自身はその内部に
隠れて、ただ体の
後端だけを
材木の表面に出している。多くの
二枚貝には体の
後端に二本の
管が
並んであって、
殻を開いている間は
絶えずその一本から水を
吸い入れ、他の一本から水を
吐き出しているが、
吸い入れられる水の中にはいつも
微細な
藻類などが
浮かんでいるゆえ、貝はこれを食うて生きていることができる。
「船食い貝」の生活もかような具合で、
材木の中に
隠れてはいるが、体の
後端を表面まで出しているところから考えると、やはり水とともに
微細な
餌を
吸い
込んで食うのであろう。今では大きな船はみな
鋼鉄でつくるから、この貝のために受ける
損害は
非常に
減じたが、昔の
木造船のこうむった
害は実にはなはだしいものであった。それゆえこの貝の学名には「船の
恐れ」という意味の字がつけてある。
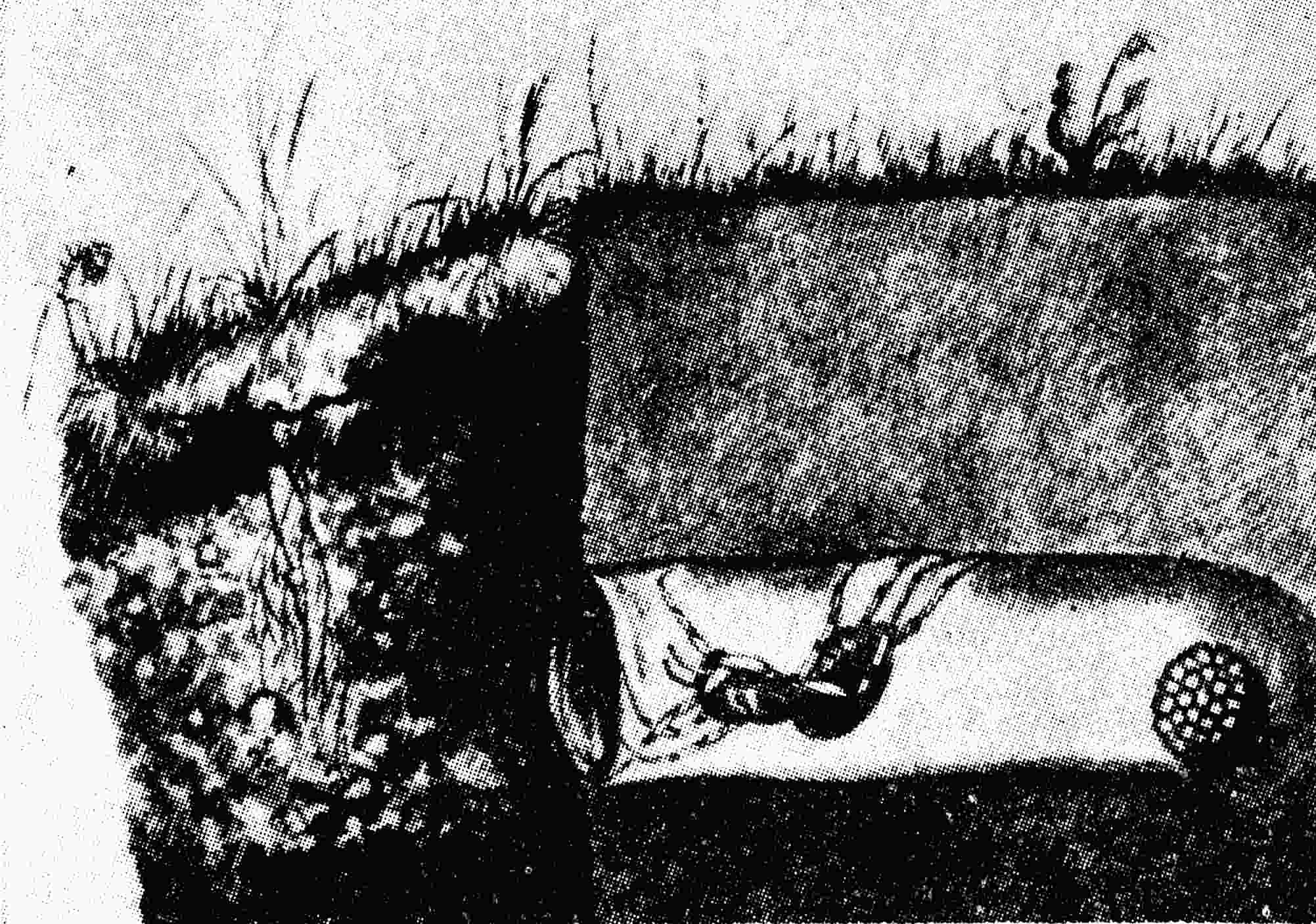 とたてぐも
とたてぐも
くも
類の中には地中に
孔をつくって、その中に
隠れているものが
幾種類もあるが、その中で「とたてぐも」と名づけるものは、糸を
編んで
孔の入口にちょうどはまるだけの円形の開き戸をつくり、つねはこれを
閉じておくので外面からは
孔のあり場所が少しもわからぬ、平地にも
崖のところにもあって、けっして
珍しいものではないが、
蓋の外面にはその
周囲と同じように、赤土のところならば赤土、
苔のあるところならば
苔がつけてあるから、よほど注意して見てもなかなか見出しにくい。今からもはや三十年ばかりも前になるが、東京
本郷の大学
構内の池の
傍で、この
類の「くも」が
偶然見つけられたのは、「くも」の体に
寄生した
菌が
孔の
蓋を下から
押しあけて、地上へのび出していたからであった。この「くも」は箱の中に
飼うておいても、
巧みに
土中に
孔を
穿ち
蓋をつくるから、つまびらかにその
挙動を
観察することができるが、もっともおもしろいことは戸の
裏に二つ小さな
凹みをつくっておき、もし何者かが来て、外から戸を開こうとすると、「くも」は内から足の
爪をこれに
懸けて開けさせぬように力を
込めて引いている。
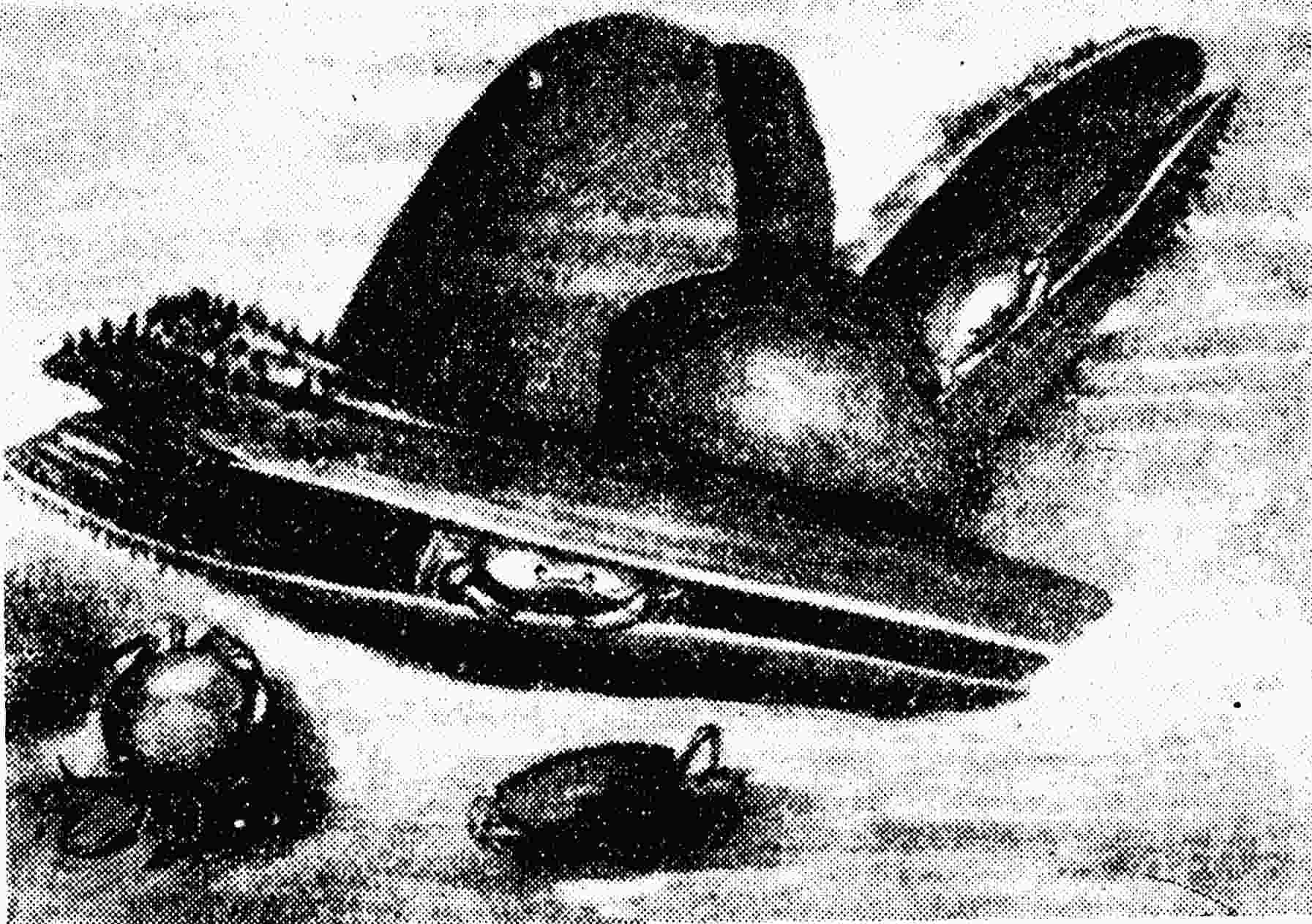 かくれかに
敵
かくれかに
敵に対して身を
護るためには、岩や木や土の中に
隠れるもののほかに、生きた動物の体内に
仮の
住居を定めるものがある。
蛤や「たいらぎ」の貝の内には
往々小さな
蟹がいるが、この
蟹はつねに肉の間に
隠れていて、
殻の開いているときでも外へははい出さぬ。しかしただ場所を
借りているだけで、貝の血を
吸うのでもなく肉を食うのでもないゆえ、けっして
寄生とは名づけられぬ。
支那の古い書物には
'さきつ'という名で、この
蟹のことが出ているが、その
説明を見ると、
蛤には
眼がないゆえ、
敵が近くへ来ても知ることができぬが、かかる場合には'さきつ'がつねに宿を
借りている
恩返しに、
鋏で軽く貝の肉をはさんで
警告すると、貝は急に
殻を
閉じて貝も
蟹もともに
敵の
攻撃をまぬがれると書いてある。これはもとより
想像であるが、全く
類の
異なった
二種の動物が
共同の生活をしているのを見て
奇妙に思い、考えついたことであろう。つねに貝の内部に住んでいて、生活の
状態がやや
寄生動物に
似ているゆえ、いくぶんか
寄生動物の
通性を
備え、
甲は
柔らかく、足は短く、体は丸く
肥えて、
眼はきわめて小さい。
卵を
産むことのすこぶる多いのも、やはり
寄生動物と
相似ている。
或る
種類の「なまこ」を切り開いて見ると、内からこれと同じような
蟹の出て来ることがしばしばある。
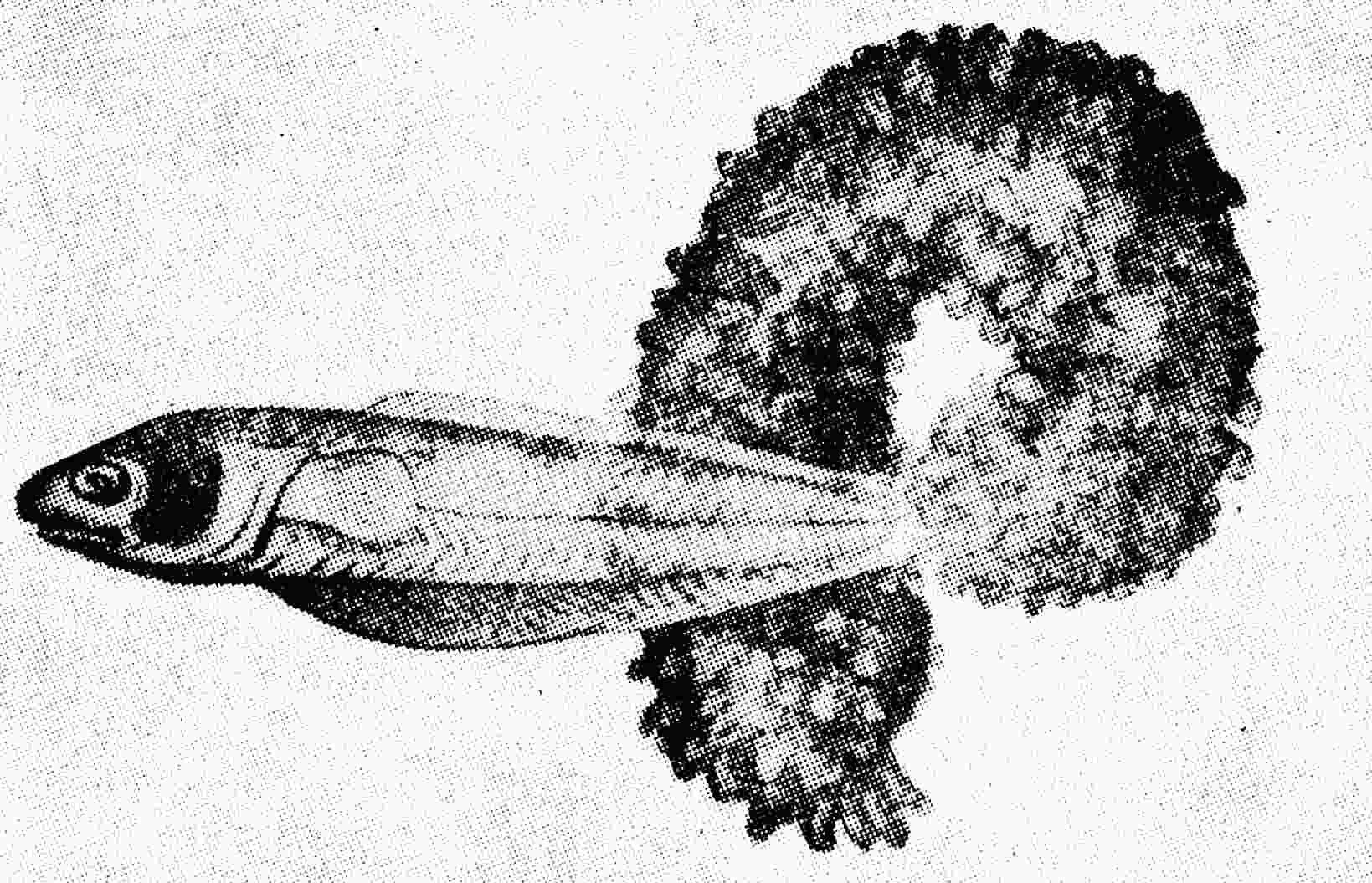 かくれうお
かくれうお
「なまこ」はちょっと見ると、どこが頭かどこが
尻かわからぬようであるが、生きているのを
観察すると、頭のほうには口があって、その
周囲に
枝分かれした指のごときものが
並び生じて、つねに
微細な食物を口の中へ運び入れている。また
尾のほうには大きな
肛門があって、人間が
呼吸するのとほぼ同じくらいの回数で
絶えず
開閉して
多量の海水を
吸い入れたり
吹き出したりする。されば「なまこ」の
尻の内はつねに新たな海水が出入りして、小さな動物の住むには
適するものと見えて、
蟹が
往々その中に
隠れていることは、前に
述べたが、なお、そのほかに
一種の魚が住んでいることがある。前の
蟹を「
隠れ
蟹」といい、この魚を「
隠れ魚」と
称するが、いずれも
単に「なまこ」の体内の空所を
利用しているにすぎぬから、「なまこ」に
害をおよぼすことなしに、自身はやや安全に生活ができる。「
隠れ魚」は形がいくぶんか「あなご」に
似た細長い魚である。日光に当たらぬゆえ色はよほど白い。大きな
餌を食いたいとか
大勢集まってにぎやかに
暮らしたいとか思う
普通の
魚類にくらべると、
競争を
恐れる意気地なしのように見えるが、
紛々たる魚界の
俗事を
余所にして、「なまこ」の
尻の内にゆうゆう
自適している「
隠れ魚」は、いわゆる風流人に
似たところがないでもなかろう。
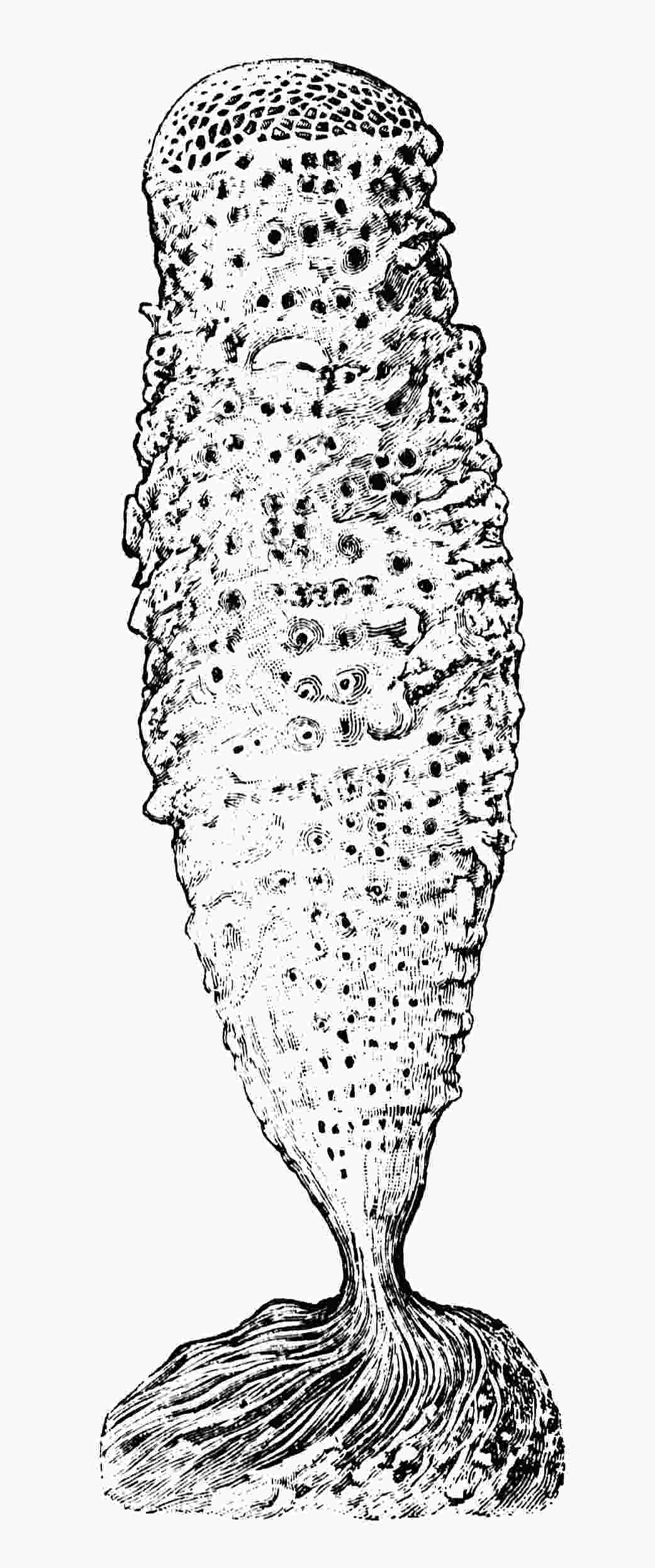 同穴海綿
同穴海綿
「
隠れ
蟹」でも「
隠れ魚」でも、
好んで貝や「なまこ」の体内に
隠れているだけで、もし出ようと思えば
随意に出ることができる。
現に
網にかかった「なまこ」の
尻からは、
往々「
隠れ魚」がはね出ることがある。これに反して
海綿の体内に
隠れている「えび」の
類は、全く
海綿の
組織に
包まれて
一生涯外に出ることができぬ。そのもっともいちじるしい
例は、
相模灘の深いところなどから取れる
偕老同穴と名づける美しい
海綿で、その内部には
必ず
雌雄一対のえびが
同棲している。
海綿の体は中空の
円筒形で、
骨骼は全部
無色透明の
硅質の
針からできているゆえ、かわかした
標本を見るとあたかも
水晶の糸で
編んだ
籠のごとくで実に
麗わしい。西洋人がこの
海綿のことを「
愛の女神ビーナスの
花籠」と名づけるのはもっともである。ただし
普通の
花籠とは
違い、
籠の口には目の細かい
網があるゆえ、その
孔を
通過し
得るほどの小さなものでなければ
籠の内に出入りはできぬ。されば、この
海綿の内に住んでいる「えび」は、
牢の内に
閉じ
込められたごとくで終身その外へは出られぬ。おそらく
幼い時に水流とともに
海綿の体内にはいり
込み、その中で
成長してついに出られなくなったのであろうが、それが
必ず
雌雄一対に
限るのは、後にはいり来るものがあっても、これを食い
殺すか、追いのけるかして、家庭の平和を
保つことに
努めるからであろう。
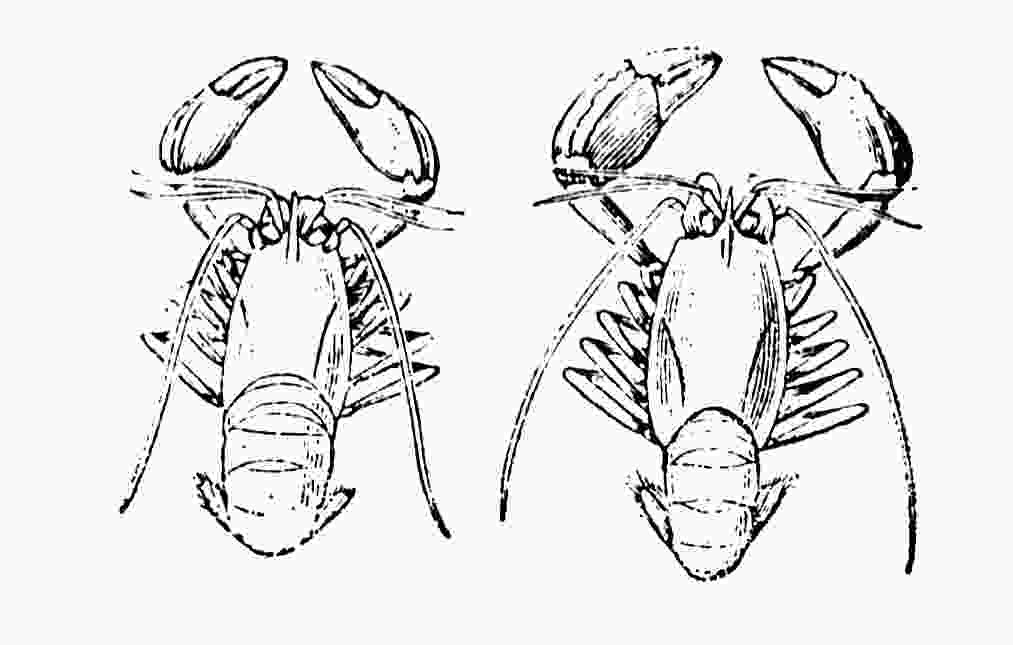 同穴えび (左)雌 (右)雄
同穴えび (左)雌 (右)雄
かくのごとく
同穴海綿の内に住む
同穴えびは、水流とともにはいり来る
少量の
餌を食うて
満足し、外に出て大いに活動するというような野心は
夢にも起こさず、明けても
暮れても
夫婦差し向いで、
雄のほうも
厳重に
貞操を守り、
或る
種の
女権論者の理想とするところを
実現しているのである。
以上述べたとおり、
敵の
攻撃をまぬがれるには
隠れることはもっとも
有効であって、たいがいの動物は
必ずこれを
試みるものであるが、ただ
隠れていることによってのみ身を
護る動物では、身体の
形状、
構造にもこれに
応じた
変化が
現われ、あたかも
寄生動物などのごとくに、運動の
器官と
感覚の
器官とは少しずつ
退化し、
生殖の
器官は
発達して、子を
産む数は
比較的に多くなるのがつねであるように思われる。
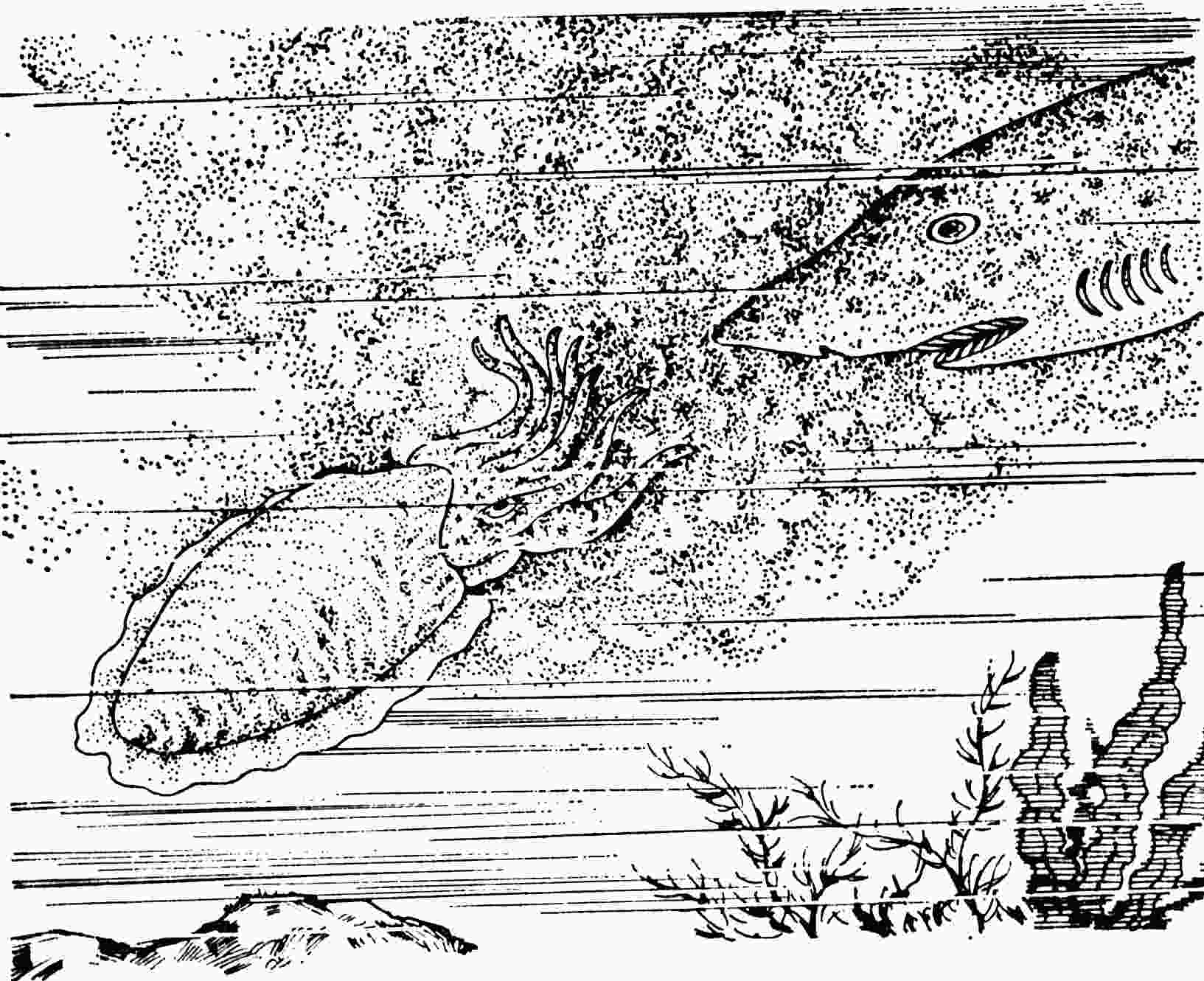 「いか」墨を吹く
「いか」墨を吹く
「たこ」、「いか」の
類は
敵に
遇うたとき身を
隠すに
一種特別の
方法を用いる。すなわち
濃い
墨汁を出し、これを海水に
混じて
漏斗から
吐き出すのであるが、かくすれば海水中ににわかに大きな
不透明な黒雲が生ずるから「たこ」、「いか」の体は全く
敵から見えなくなり、黒雲が
漸々薄くなって消え
失せるころには、すでにどこか遠くへ
逃げ去った後であるゆえ、
敵は
如何ともすることができぬ。「たこ」、「いか」の
胴を切って見ると、
腸の
側に多少銀色の
光沢を
帯びた
楕円形の
墨嚢があるが、これを少しでも
傷つけると、たちまち中からきわめて
濃い
墨が流れ出てそこら
中が真黒になる。このような
特別の
隠遁術を用いて身を
護るものは、全動物界の中におそらく「たこ」、「いか」の
類よりほかにはなかろう。
逃げも
隠れもせずして
敵を
防ぐものの中には、
攻撃用の
武器を用いて
対抗するものと、
単に受動
的の
防御装置のみによって、
敵をして
断念せしめるものとがあるが、ここには
攻撃用の
武器を用いるものの
例はいっさい
省いて、ただ
純粋の
防御装置による場合をいくつかかかげて見よう。
 しゃこ
しゃこ
まず
敵の
攻撃をいながら
防ぐ
普通の
方法は、
堅固な
甲冑をもって身を
包むことである。これは
貝類では
一般に行なわれている
方法で、
巻貝でも
二枚貝でも、多くは
敵に
遇えば直ちに
殻を
閉じるだけで、そのほかにはなんらの
手段をもとらず、ただ
敵が
断念して去るのを根気よく待っている。「たにし」や「しじみ」のような
薄い
貝殻でも
彼らの
日常出遇う
敵に対しては
相応に
有効であるが、「さざえ」、
蛤などになると
殻はなかなか
堅固で、われわれでも道具なしにはとうていこれを開くことも
破ることもできぬ。さらに
琉球や
小笠原島など
熱帯の海に
産する、夜光貝とか「しゃこ」とかいう大形の
貝類では、
貝殻がすこぶる
厚いゆえ、
防御の力もそれに
準じて十分である。夜光貝は「さざえ」の
類に
属するが、
往々人間の頭ぐらいの大きさに
達し、
貝殻が
厚くて
堅く、かつ
真珠ようの美しい
光沢があるゆえ、
種々の細工に用いられる。また「しゃこ」は
蛤と同じく
二枚貝であるが、大なるものは長さが四
尺(注:1.2m)
余りもあり、重さが五六十
貫(注:187~225kg)にも
達する。
殻の
厚さは七八
寸(注:21~24cm)もあって
純白で
緻密であるゆえ、
装飾品を
製するにはもっとも
適当である。それゆえ、昔から
七宝の一に数えられ、
珊瑚の柱、
'蝦'蛄の屋根と
相並べて
竜宮の歌に
謡われる。フランスパリのサン・シュルピスの寺では、この
貝殻を
手水鉢に
応用している。
貝殻が
厚ければ、
敵を十分に
防ぐという
利益がある代わりに、その重い目方のために、運動が
非常に
妨げられるという
不便を
忍ばねばならぬ。されば
貝類はすべて運動の
遅いのがつねで、よく進行の
遅いたとえに用いられる「かたつむり」などは、
貝類仲間ではなお速いほうの部に
属する。「しやこ」のごとき重いものは、一定の場所にとどまって全く動かぬ。海岸の岩石には「かき」や「へびがい」が一面に
付着しているところがあるが、いずれも
厚い
貝殻をただ一つの
頼りにして
敵の
攻撃をまぬがれている。「かき」のほうは
鰓で水流を起こして
微細な
餌を集めて食い、「へびがい」のほうは、
粘液を出して
微細な
餌をこれに
付着せしめ、
粘液とともにこれを食う。「へびがい」は「さざえ」などと同じく
巻貝類であるが、
貝殻の
巻き方が
極わめて
不規則である上に、岩の表面に
固着しているゆえ、これを
貝類と思わぬ人が多い。なおこれらの
貝類のほかに、「ふじつぼ」や「ごかい」の
類で
石灰質の
堅い
管をつくる虫などがたくさんに
付着しているが、これらは動物の
種類が全く
違うにかかわらず、
敵を
防ぐ
方法が
一致しているために、
外観にも
習性にも
固着貝類によほど
似たところがある。それゆえ、少し古い書物には「ふじつぼ」をいつも「かき」などと同じ
貝類の
仲間に入れてある。また
石灰の
管をつくる虫のほうは、はじめて海岸へ
採集に行く人がしばしば「へびがい」の
類と
混同する。
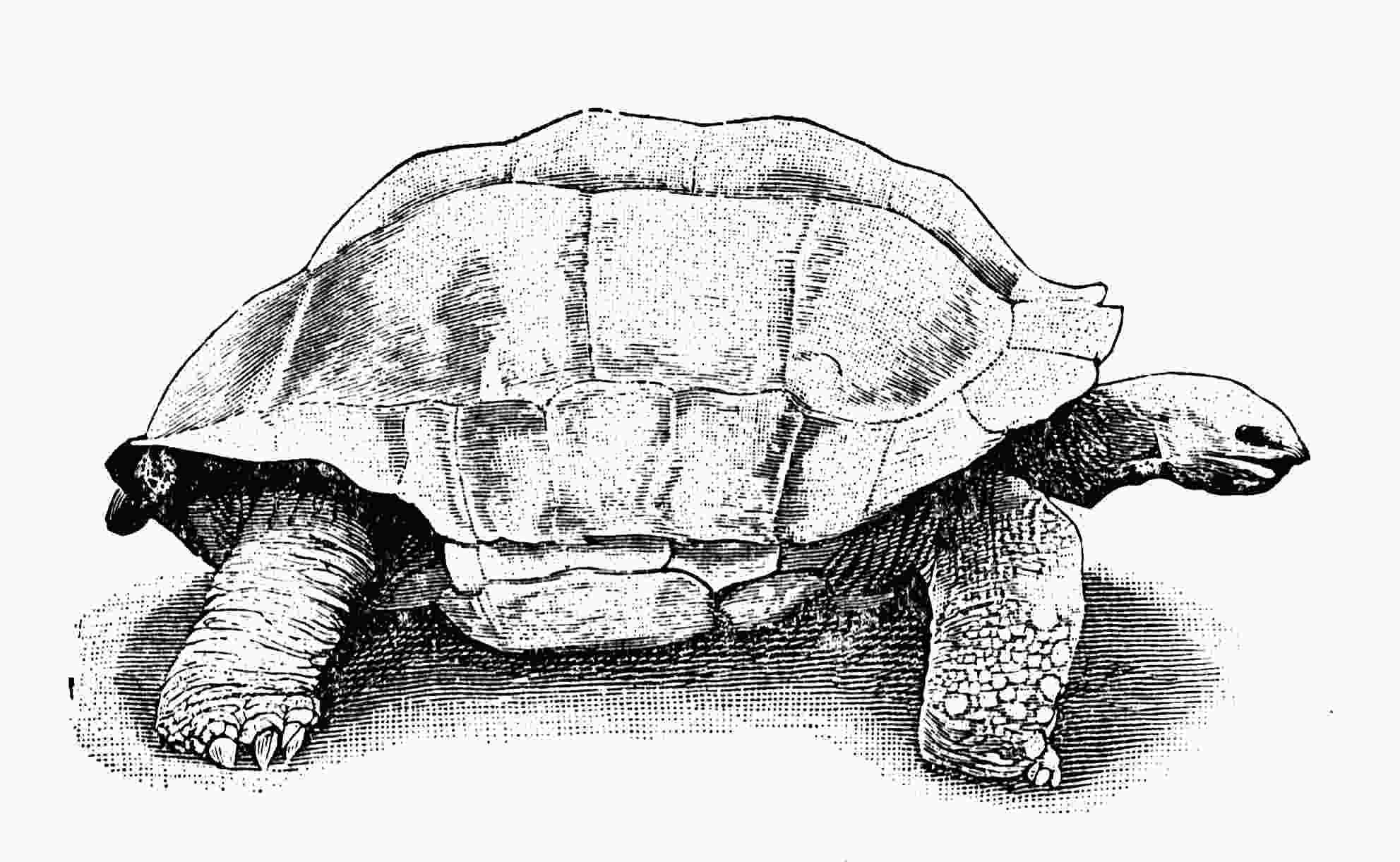 陸上にすむ大亀
陸上にすむ大亀
次に全身
甲でおおわれているので有名な動物は
亀類である。
普通の
石亀でも
甲はなかなか
堅いから、頭、
尾と四足とを
縮めていれば、犬にかませても平気でいるが、
琉球八重山島に
棲む
箱亀では、
腹面の
甲が
蝶番のごとき
仕掛けで中央が
曲折するから、頭、
尾を
縮めたところをも全く
閉ざして少しも
空隙を
残さぬ。
熱帯地方の島に
産する大形の
亀になると、
甲もその
割に
厚く力も強いから、大人が
靴のまま乗っても苦もなくはい歩く。ただし
兎と
亀との
寓話にもあるとおり、
亀の歩みはすこぶる
遅いが、これは
甲をもって
敵を
防ぐことができるゆえ、急いで
逃げ去る
必要がないからである。だれよりも重い
甲鎧を着て、だれよりも速く走ろうというのはとうてい
無理な注文で、何事においても一方で勝とうとするには、他のほうで
劣ることを
覚悟しなければならぬ。
昆虫類の中でも皮の
薄い「とんぼ」は
飛ぶことが速いが、
厚い
鎧を着た「かぶとむし」は運動がすこぶる
緩慢である。
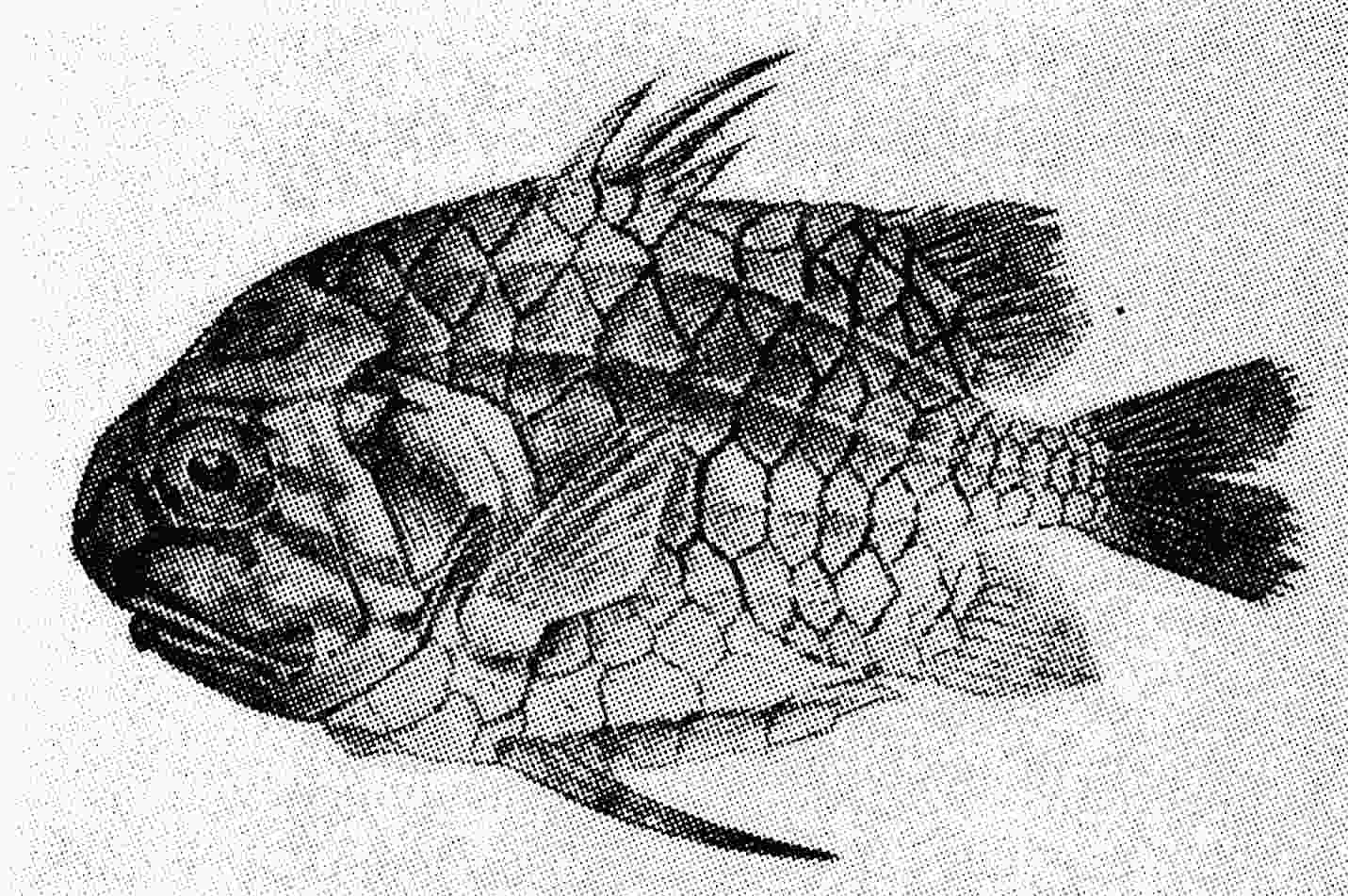 まつかさうお
魚類
まつかさうお
魚類は
概して
游泳の
敏活なもので、つまんで拾えるようなものは
滅多にないが、「はこふぐ」、「すずめふぐ」、「まつかさうお」のごとき
堅固な
鎧で身を
固めているものは
游ぐことがすこぶるまずい。他の魚では
鱗が屋根の
瓦のごとくに重なり合うてならんでいるゆえ、身体を
屈曲するときに
邪魔にならぬが、「はこふぐ」などでは
硬い
厚い
鱗が
敷石のように
密接しているから、身体はまさに箱のごとくで、少しも曲げることができず、したがって力強く水をはねることができぬ。それゆえ、もし
盥の水の中に、これらの魚を入れて手で水をかきまわすと、水の流れに
押されていっしょにくるくるまわる。これを
鯉や
鮭が急流をさかのぼるにくらべれば実に
雲泥の
相違である。
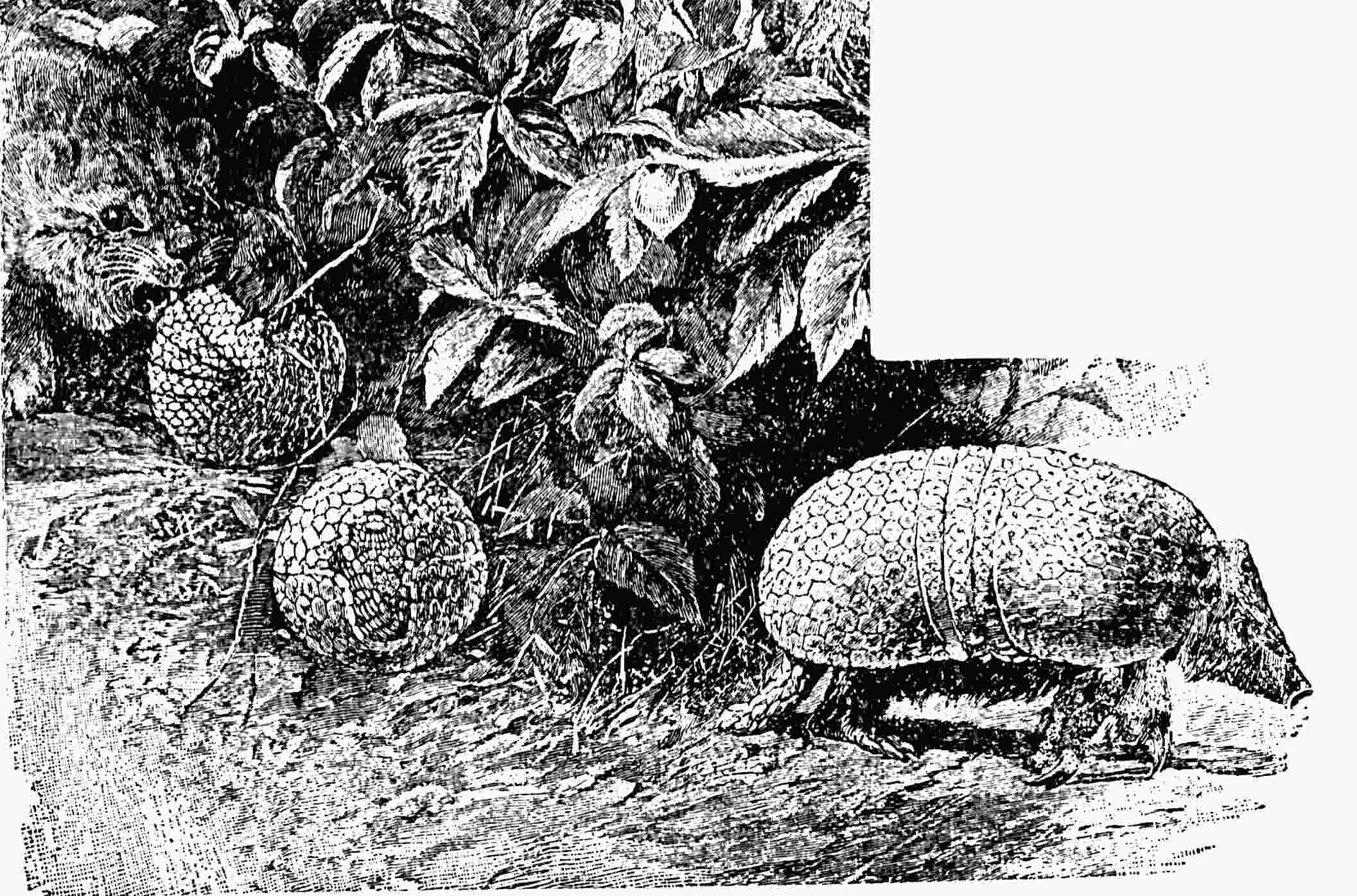 アルマジロ
獣類
アルマジロ
獣類の中でも、
穿山甲や「アルマジロ」は
甲冑をもって
敵の
攻撃を
防ぐ。
穿山甲の
鱗はあたかも
魚類の
鱗のごとくに
並んでいるが、「アルマジロ」のほうはまるで
亀のごとくで、
胴は
堅固な
甲でおおわれている。いずれも
普通の
獣類とは見たところが大いに
違うゆえ、
獣類と見なされぬことが多い。
穿山甲が古い書物では
魚類の中に入れてあることは前にも
述べたが、「アルマジロ」のほうは、先年東京で南米
産物展覧会のあった
節、地を
掘る
害虫という
札をつけられ、
虫類の
取扱いを受けていた。この
獣は
敵に
遇うと頭も
尾も四足も
縮めて全身を球形にし、ただ
堅い
甲冑のみを外に
現わすゆえ、犬でも
豹でもこれを
如何ともすることができぬ。アルゼンチン国では、この
獣の
甲に
絹の
裏を
付け、
尾を曲げて
柄として
婦人用の
手提かばんに用いる。
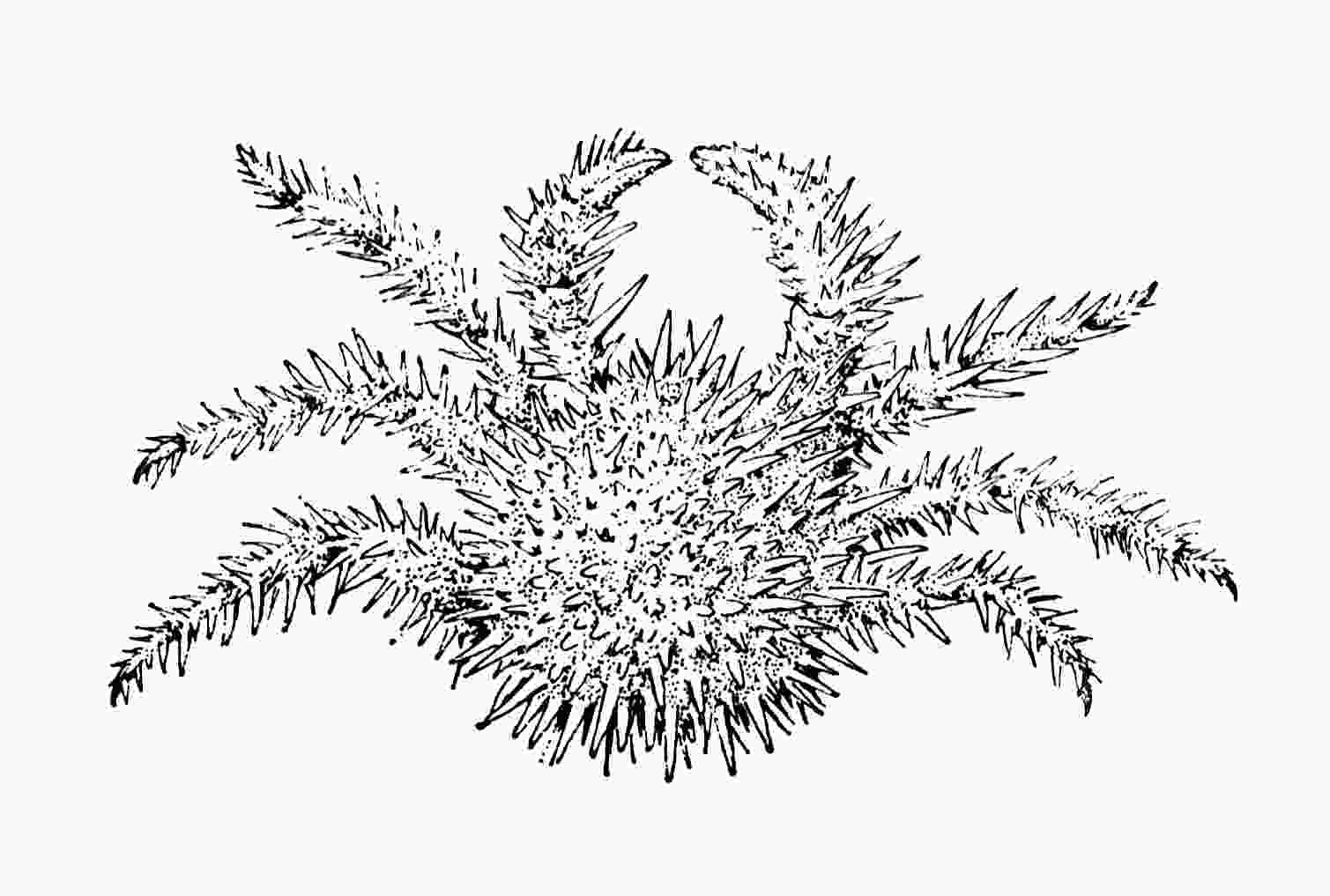 いばらがに
敵
いばらがに
敵の
攻撃を
防ぐために、全身にとがった
針を有する動物も
幾種かある。
次頁に図をかかげた
棘蟹などはそのもっともいちじるしい
例で、ほとんど手を
触れることもできぬ。カラフト
辺で年々
多量に
'缶詰にする味の
好い
蟹は、これほどに
棘はないが、やはりこれと同じ
類に
属する。
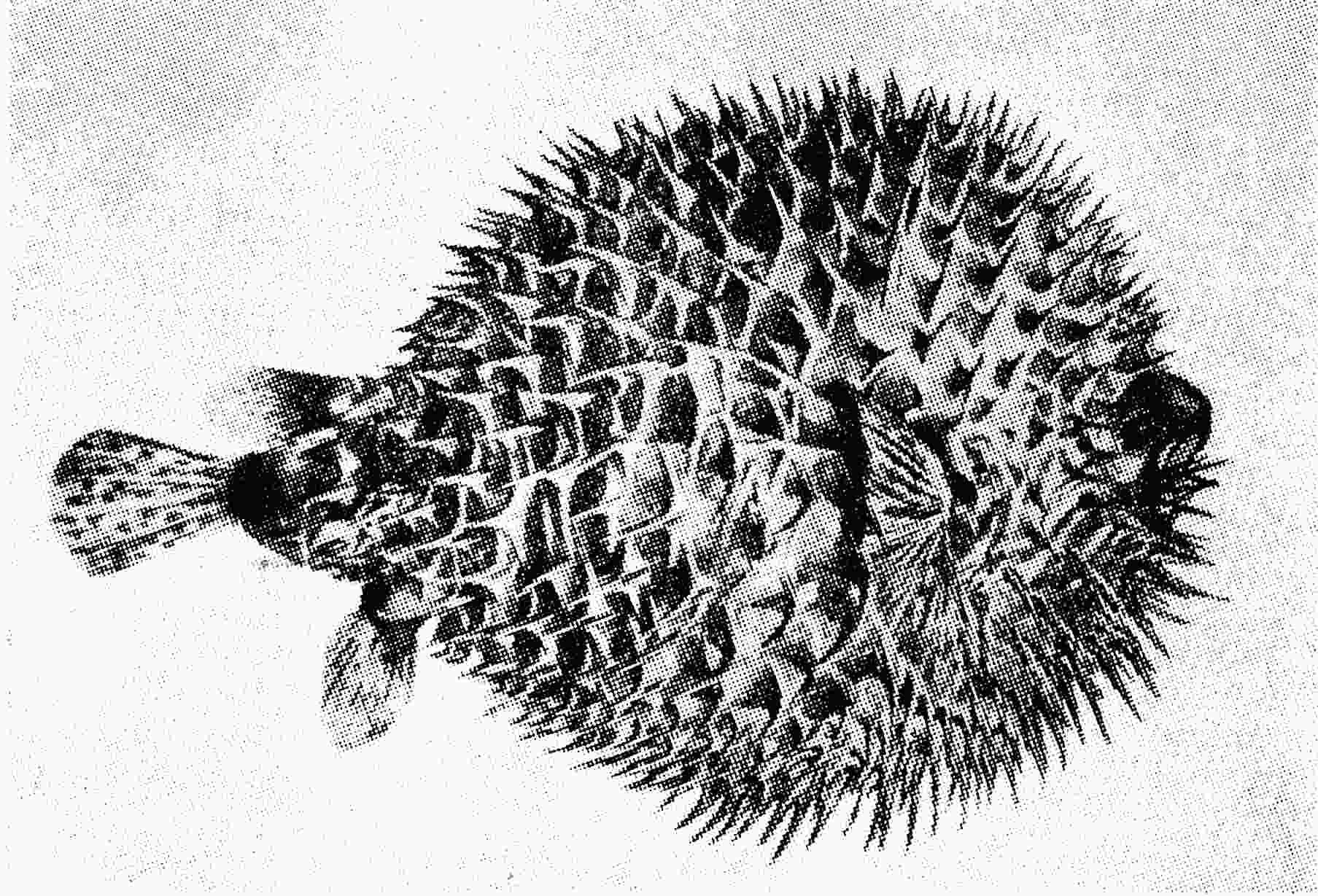 針千本
針千本
また
河豚の
一種で「はりせんぼん」という魚も全身に太い
針がはえている。
通常は後に向いて横になっているゆえあまり
游泳の
妨げにならぬが、もしも
敵に
遇うと体を球形にふくらせて
針をことごとく直立せしめるゆえ、さながら大きな「いが
栗」のごとくになって、とてもつかまえることはできぬ。
獣類の中でこれに
似たものは「
山荒し」である。この
獣は、
兎などと同じく、
齧歯類という
仲間に
属し、植物
性の物ばかりを食ういたって
怯儒なものであるが、全身にペン
軸ぐらいの太いとがった毛がはえて、物に
恐れる時はこの毛がみな直立するゆえ、たいがいの食肉
獣もかみつくわけにゆかぬ。
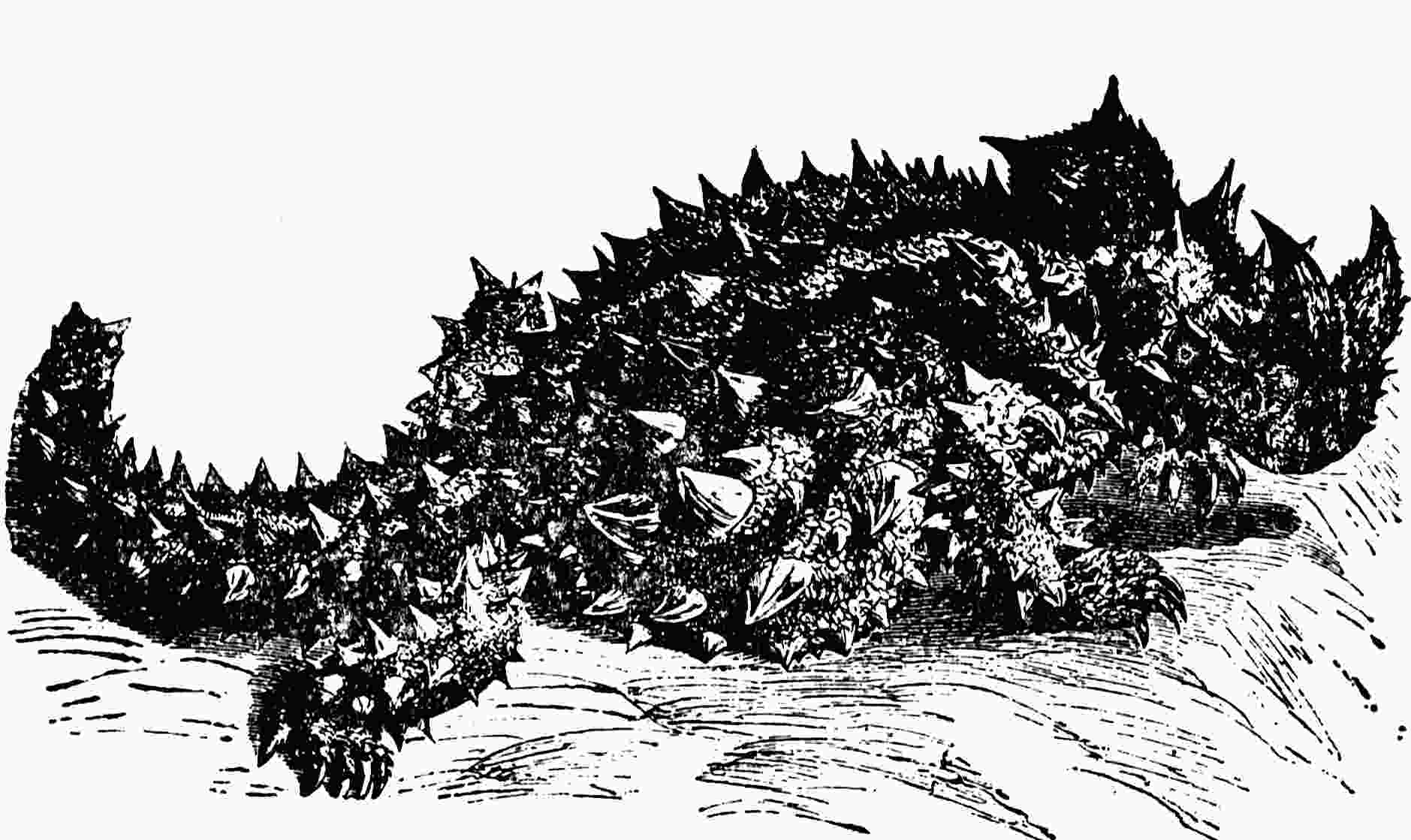 はりとかげ
はりとかげ
オーストラリア地方に
産する「とかげ」の
一種にも全身
棘だらけで、おそろしげに見えるものがある。長さは
一尺(注:30cm)に足らぬぐらいであまり大きな動物ではないが、顔を正面から見ると、二本の角のような太い
棘があるために多少
鬼に
似ているので、数年前に新聞紙上に
鬼のアルコール
漬けという見出しで
評判せられたことがあった。
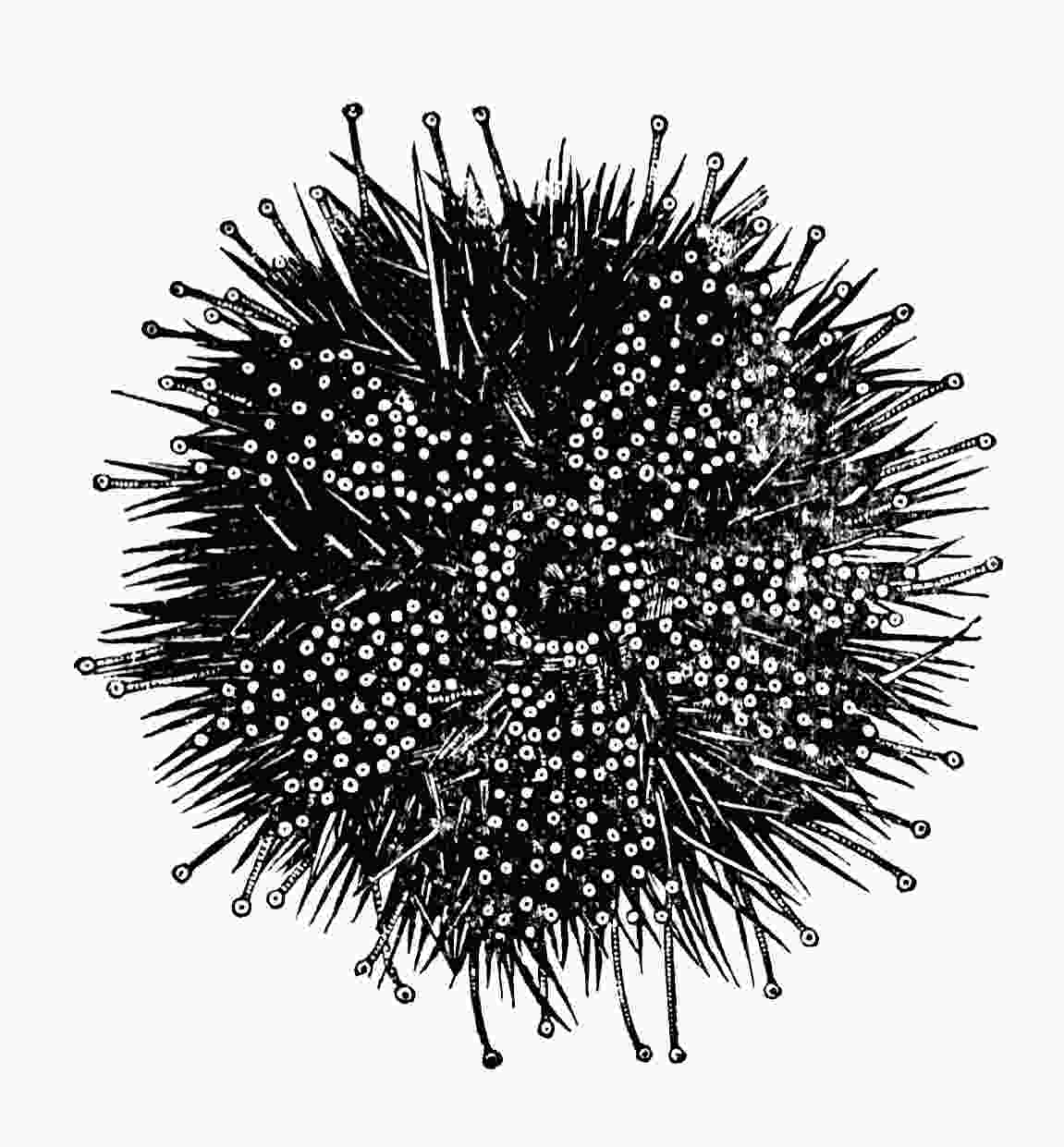 うに
うに
かように全身に
針のはえた動物は色々あるが、もっとも
普通な例といえばまず
海胆類であろう。食用にする「
雲丹」はこの
類の
卵巣から
製するのであるが、岩のある
磯にはどこにも
産し、形が丸く
棘で
包まれて、少しも「いが
栗」に
異ならぬ。
棘がとがっているから、たいていの
敵はこれを
襲うことをあえてせぬ。
特に「がんがせ」と
称する
一種のごときは、
針がすこぶる細長いゆえ、手の
掌から
甲のほうへ
突き
抜けるというて、
漁夫らは
非常におそれている。
堅い
甲でも、
鋭い
針でも、
敵の
攻撃を
防ぐ
器械的の
装置であるが、そのほかになお、
化学的の
方法を用いて身を
護るものがある。
例えば「ひきがえる」のごときは、
敵に
遇うても
逃げることも
遅く、
隠れることもへたである。しかし、
皮膚の全面にある大小の
疣から
乳のごとき白色の
液を出すが、この
液が
眼や口の
粘膜に
触れると、しみて
痛いゆえ、犬などもけっして、「ひきがえる」には食いつかぬ。
魚類には「おこぜ」、「あかえい」などのごとくに、
毒針でさすものが
幾種もある。
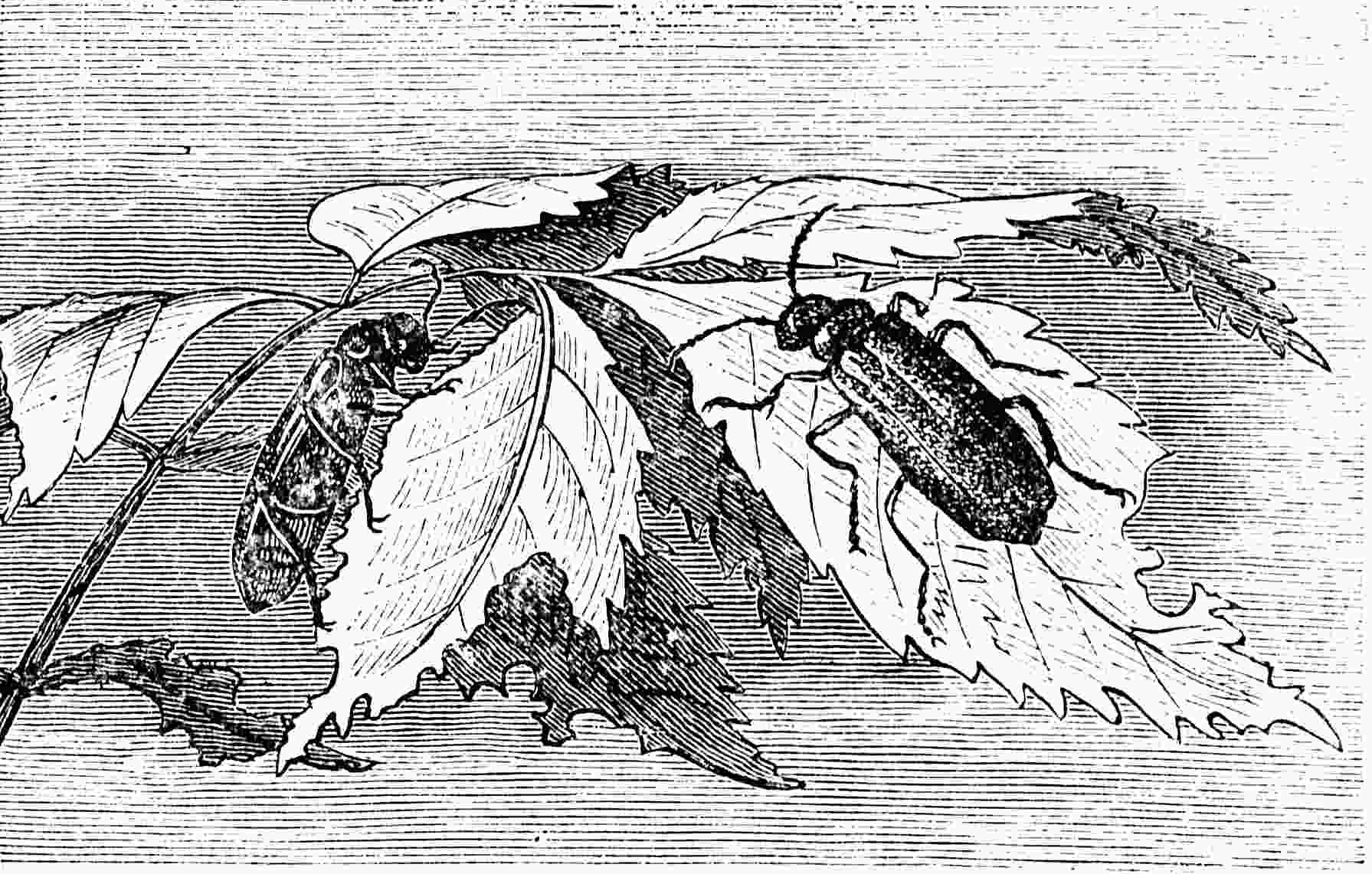 まめはんみよう
まめはんみよう
豆につく「はんみょう」という
昆虫はこれを
捕えると、足の
節から
激烈な
液を
分泌するが、強く
皮膚を
刺激するゆえ、この
種の虫をかわかせば、
発泡剤として用いられる。また「くらげ」、「いそぎんちゃく」の
類は、体の外面に
無数の
微細な
嚢を
備え、
敵に
遇えばこれより
毒液を注ぎ出して
防ぐが、
餌を
捕えるにもこれを用いるから、これは
防御、
攻撃、両用の
武器である。
 スカンク
スカンク
アメリカに
産する「スカンク」という
鼬に
似た
獣は、
非常な
悪臭のあるガスを発するので有名であるが、これも
敵を
防ぐための
化学的方法の
一種といえる。
臭気を出す
腺は
肛門の
両側にある。
海綿の
類は全身いずれの部分にも
角質または
硅質の
骨骼が、
網状をなして広がっているゆえ、他の動物のために食われることはほとんどない。海岸の岩の表面には黄色、赤色、
鼠色などの
海綿が一面にはえているところがあるが、
固着して
逃げも
隠れもせず、
甲もかぶらず、
棘も出さず、
毒を
含まず、
臭気を放たず、しかも
敵に
襲われることのないのは、全く身体が食えぬからである。「
彼は食えぬ
奴だ」などとは、よく聞く言葉であるが、動物中でまさに食えぬものといえば、おそらくまず
海綿ぐらいなものであろう。
敵が
攻めて来たときにまず
示威的の
挙動を
示してこれをの
退けんとするものがある。
鼠のごとき小さなものでも、追いつめるとかみつきそうな
身構えをして、一時
敵を
躊躇せしめ、その間にひまをうかごうて急に
逃げ出すが、たいがいの動物はこれに
似たことをする。
亀や
貝類のごとき
厚い
殻を
備えたもの、「くらげ」、「さんご」、
海綿のごとき
神経系の
発達していないものなどは
別であるが、その他の動物は、たとい日ごろ弱いものでも
危急存亡の場合には
威嚇的の
態度をとるもので、それがずいぶん
効を
奏する。せっかくつかまえた虫が食いつきそうにするので
驚いて手を放し、虫に
逃げられてしまうというようなことは、動物を
採集する人でなくとも、
子供のころの
経験でよく知っているであろう。
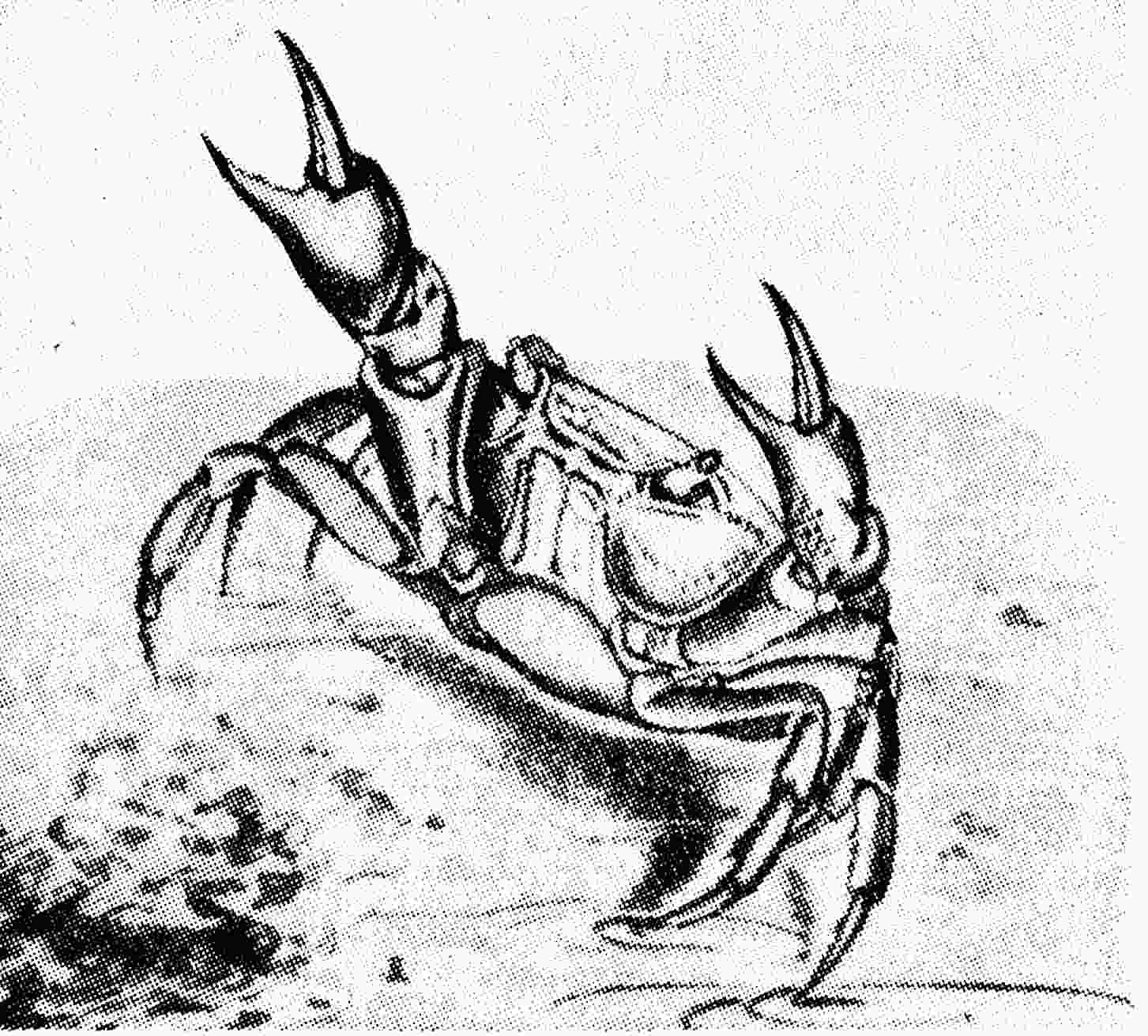 蟹の威嚇せる態
蟹の威嚇せる態
「
弁慶蟹」や「
磯蟹」なども、これを
捕えようとすると両方の
鋏を
差し上げ、広く開いて今にもはさみそうにしながら
逃げて行く。「えび」の
類も
敵に
遇うと、そのほうへ頭を向け
威張ってにらみながら
徐々と
退却する。また
敵をおどかすには身体を大きく見せて
威厳を整えることが
有効であるゆえ、「ひきがえる」などは
敵が来れば空気を
腹にのみ入れて体を丸くふくらせなる。
河豚類が食道に空気を
詰め
込んで、球形にふくれるのも、やはり
護身を
目的とする
一種の
示威運動である。
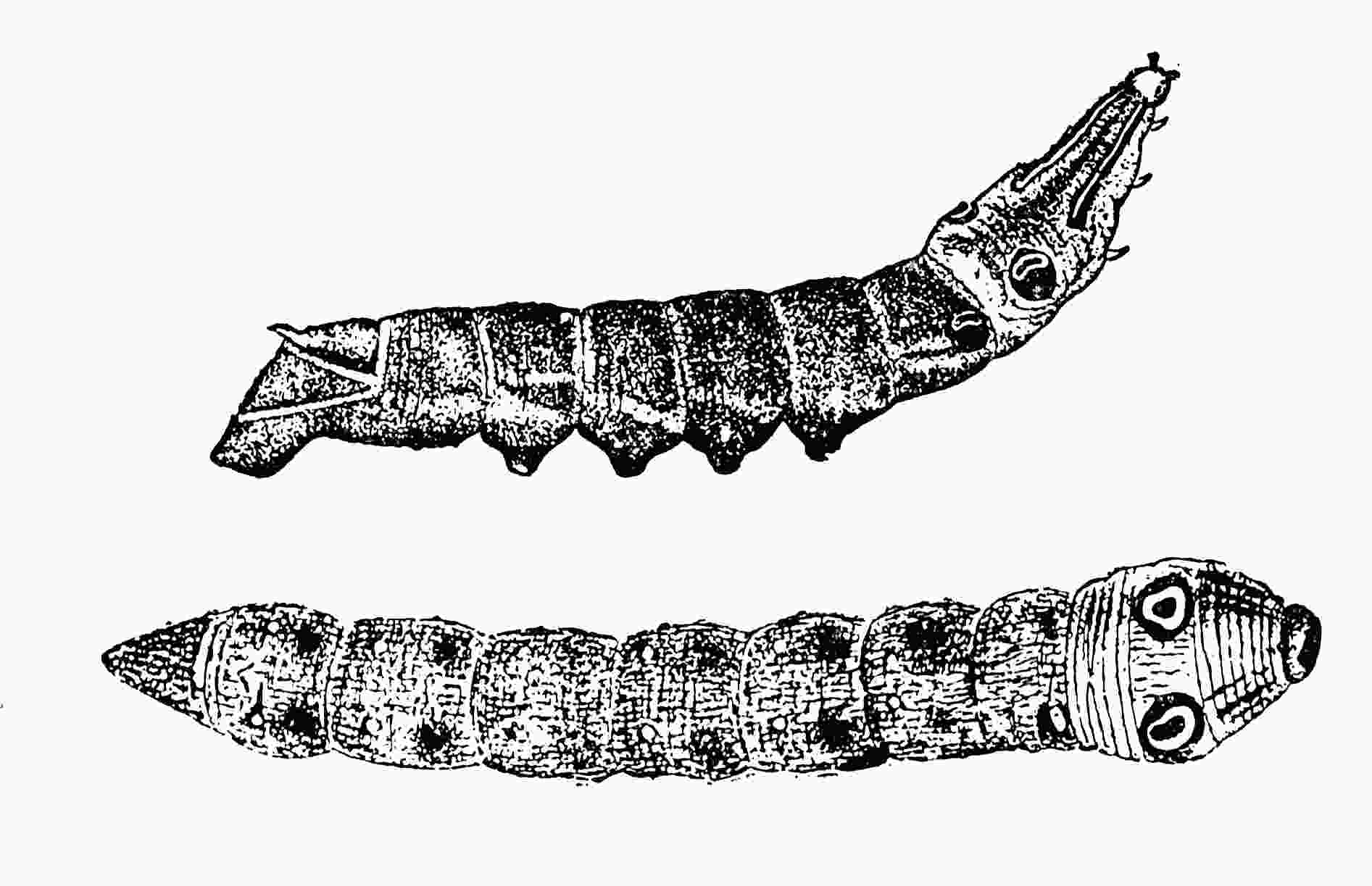 蛾の幼虫
蛾の幼虫
この
種の運動で
特におもしろい
例は
蝶蛾類の
幼虫に見られる。「すずめちょう」、「せずしすずめ」などの
幼虫は大きな
芋虫であるが、その中の
一種では頭から第四番目の
節の
辺に、
眼玉のごときいちじるしい
斑紋が左右一対
並んである。
子供らはこれを目と名づけるが、むろん真の
眼ではない。しかし
敵に
遇えば、この
芋虫は体の前部を
縮めて短く太くするゆえ、
以上の
斑紋はあたかも
眼玉であるかのように見え、全体が
怒った顔のようになる。小鳥や
蜥蜴などは
驚いてこれをついばむことを
断念し、ほかへ
餌を
求めに行くから、
芋虫は命を拾うことになる。
或る人が
試みにこれを
鶏に
与えたところが、
牡鶏でもこれをついばむことを
躊躇したものが
幾匹もあり、ついに
一匹が
勇を
鼓してこれを食い終わった。されば強い
敵に対しては、一時これを
躊躇せしめるだけの
効よりないが、やや小さな
敵なればこれを
恐れしめて
首尾よくその
攻撃をまぬがれることができる。かような
蛾の
幼虫は
眼玉のごとき
斑紋のないものでも、
敵に
遇えば急に体の前部を
縮めて太くしたり、そり返って
腹面を見せたりして、
敵をおどかそうと
試みる。
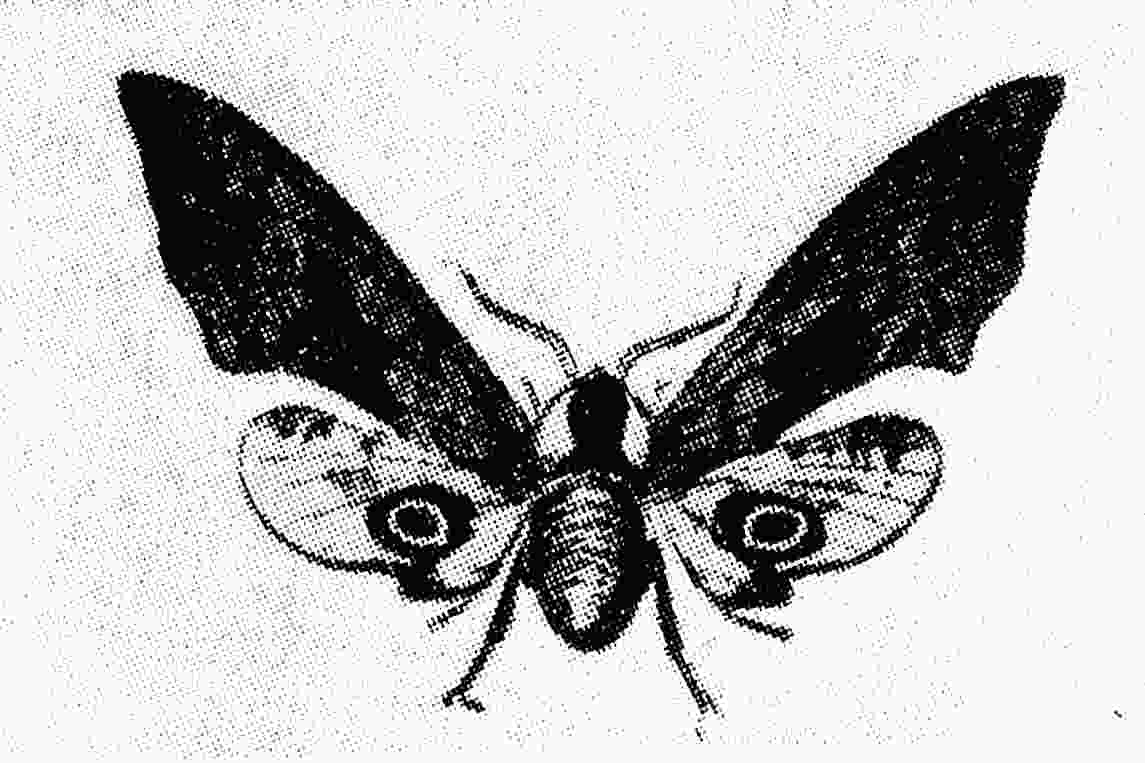 うちすずめ
うちすずめ
「うちすずめ」と
称する
蛾は、
後翅に
蛇の
目状の大きな黒い
斑紋がある。
翅をたたんでいる時は、
前翅におおわれているゆえ少しも見えぬが、
敵に
遇うと急に
翅を二対とも広く開くゆえ、
後翅の表面が
現われ、にわかに
紅色の地に大きな
眼玉のごときものが二つ
並んで見えるので、小鳥などは
肝をつぶして
逃げる。これも強い
敵をも
防ぐというわけにはゆかぬが、一部の
敵に対しては十分に身を
護るの役に立つことである。
蛾の
類には、
前翅が目立たぬ色を有するに反し、
後翅は
鮮明な
色彩といちじるしい
斑紋とを
呈するものがなかなか多いから
以上のごときことの行なわれる場合はけっしてまれではなかろう。
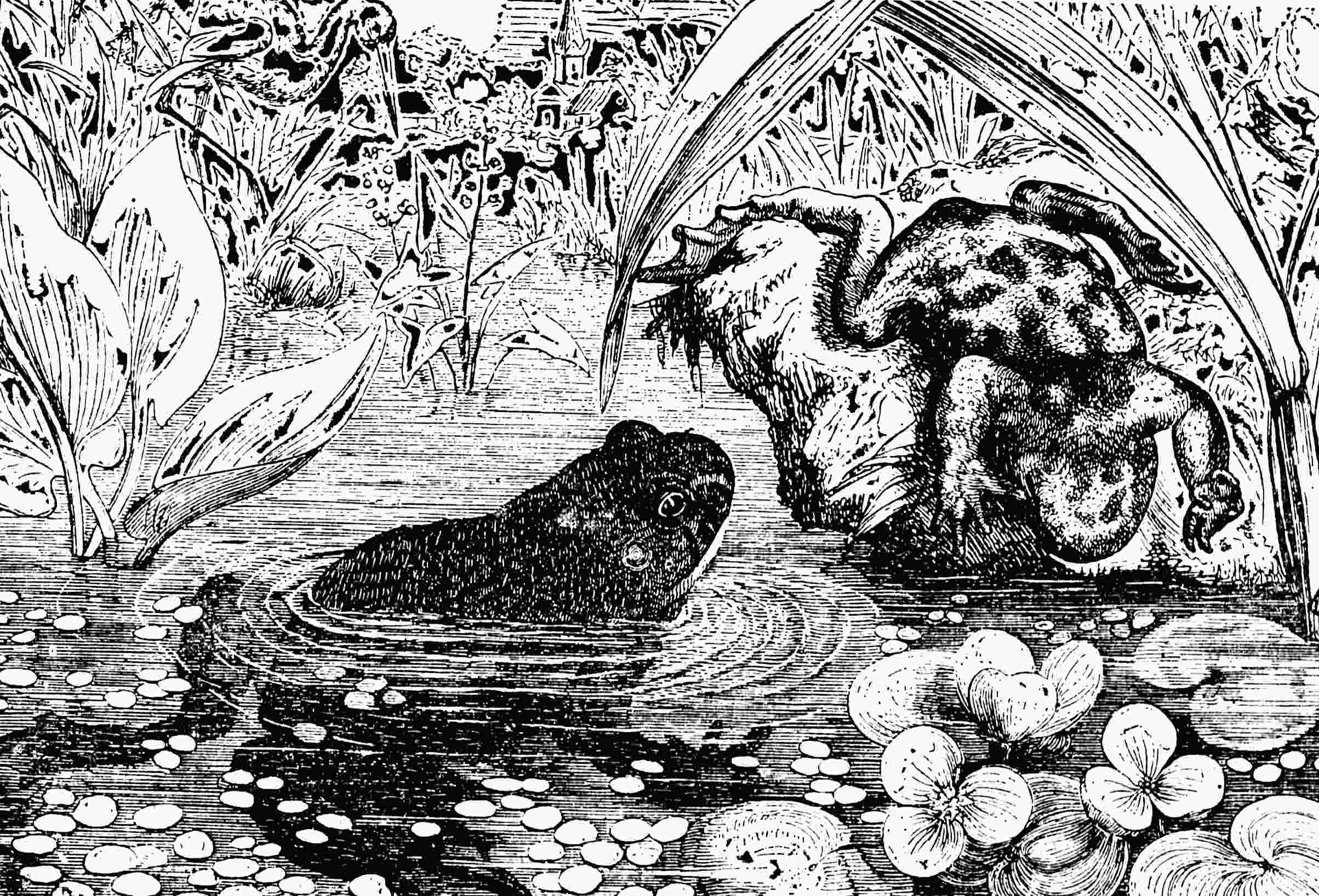 腹を見せる蛙
腹を見せる蛙
ヨーロッパから
朝鮮までに
産する
蛙の
一種に
背は
普通の色であるが、
腹には一面に美しい
朱色または
橙色の
斑紋のあるものがある。形は「ひきがえる」に
似てさらに小さく、運動もあまり活発ではないが、
敵に
遇うと急に
転覆して
腹面を上にし、かつそり返って
腹面をわざわざ
押し上げ、四足をも曲げて、
極めて
奇態な
姿勢をとるくせがあるゆえ、
初めて見る人は
如何にも
不思議に思う。これもおそらく一時
敵を
驚かせ、気味悪く思わせて
危難をまぬがれるための
習性であろう。
今まで
静かにしていたものが急に動き出すことも、
往々敵を
驚かすに足りる。くもの
類は
車輪のような
網を
張って虫の来るのを待っているが、もし人が近づいて
網に
触れようとすると、にわかに身体を
振って
網を
揺り動かすことがある。小鳥などに対しては、おそらく一時
攻撃を見合わせしめるだけの
効能はあろう。また
敵の近づいたとき
一種の声を発して、今にこちらから
攻撃を始めるぞという
態度を
示すのも、一時
敵をして近づかしめぬ
方便である。
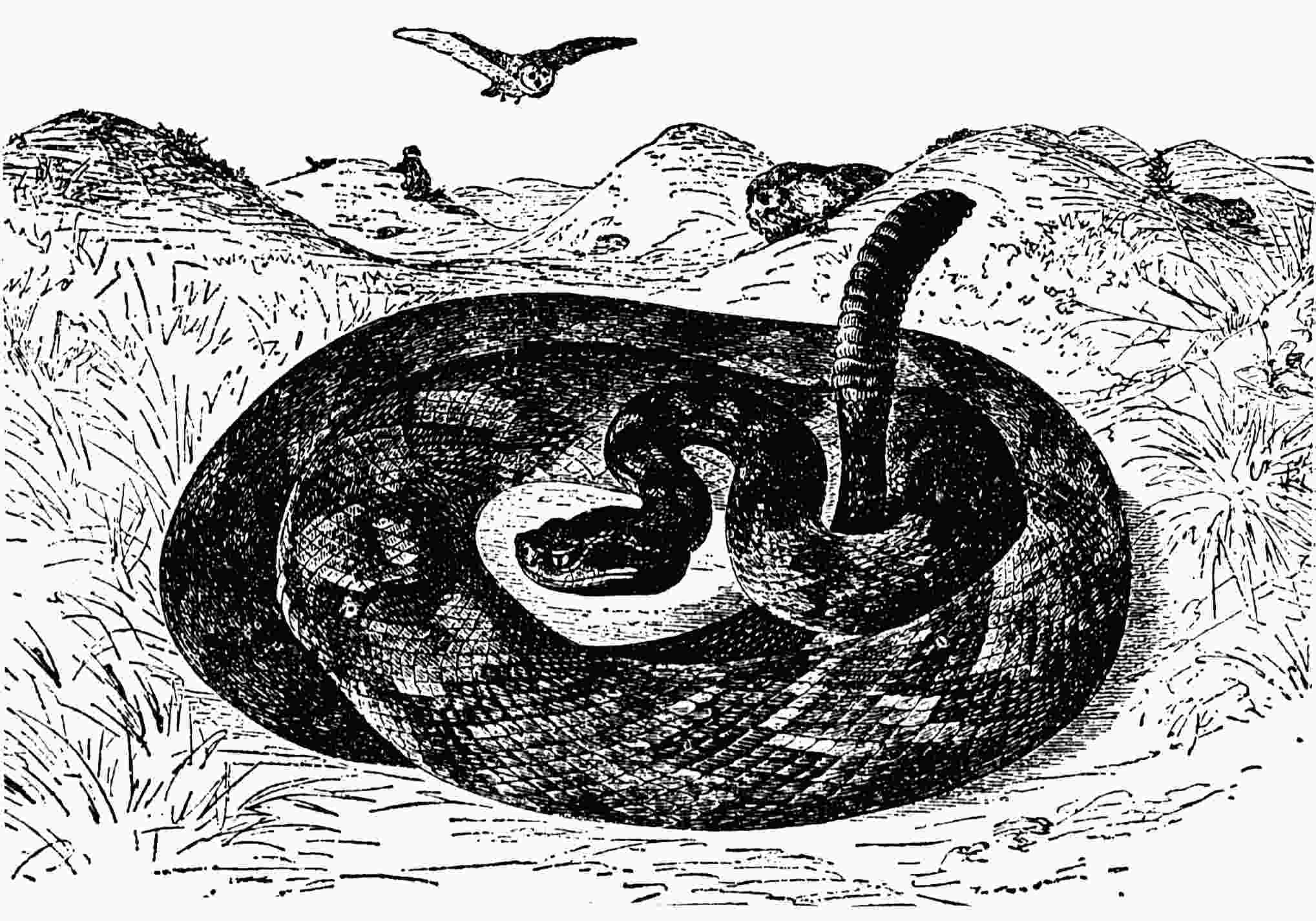 がらがら蛇
蛇類
がらがら蛇
蛇類が
敵に対するときに、
必ず空気を
吹くような
鋭い音を発することはだれも知るとおりであるが、アメリカに
産する
毒蛇類は、
尾に
特別の
装置があって、
敵が近づくとしきりにこれを鳴らしつづける。その
装置というのは、
堅い
角質の
環で、
尾の
端のところにいくつも重なってはまっている。
抜けることはないが、一つずつ自由に動けるゆえ、
蛇が
尾を
振動させると、
歯車の
速やかに回転するところへ、
金棒でも当てたような
一種の
不快な
響きを生ずる。教科書などには、原名を
直訳して「がらがらへび」と名づけてあるが、むしろアメリカ
在住の日本人のつけた「
鈴蛇」という名前のほうが、
尾の鳴らし方を
適切に
現わしている。
 しびれうなぎ
しびれうなぎ
電気を発することも
一種の
威嚇法である。「しびれえい」の生きたのに手を
触れると、はげしく電流を感ずるゆえ、だれも思わず手を放すが、
海底に
棲んでいるときにも
敵が近づくごとに電気を発してこれを
驚かしているのであろう。電気を発する魚は「しびれえい」のほかに、アフリカの
河に
産する「しびれなまず」、南アメリカの
河に
産する「しびれうなぎ」などがあるが、いずれもずいぶん強い電気を出すので有名である。ただし電気は
攻撃にも
防御にも
有効に用いられるから、けっして
単に相手を
威嚇するためのみのものではない。なお動物には光を発するものがあるが、これも多少
敵を
驚かせ、またはおそれしめるに役に立つことであろう。
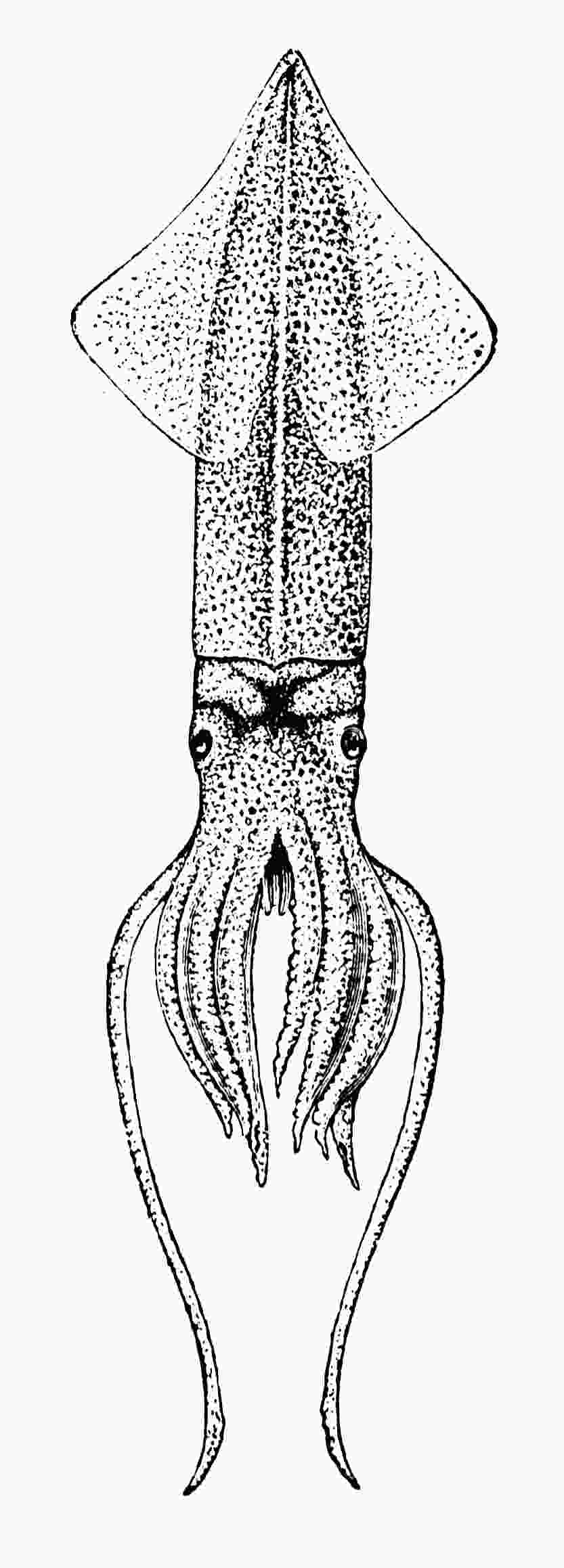 ほたるいか
陸上
ほたるいか
陸上では
螢のほかにはほとんど光る動物はないゆえ、はなはだ
類が少ないように思うが、海へ行けば
富山湾の名物なる「ほたるいか」を始めとして、「くらげ」や「えび」の子などにいたるまで光を発する
種類はすこぶる多い。それが何の役に立つかは場合によってもとより
違うであろうが、少なくも一部のものは
敵に
恐怖の
念を起こさせて、その
攻撃をまぬがれているように思われる。
すでに身体の一部を
敵に
捕えられた時、思い切ってその部だけを
捨てれば、生命は
失わずにすむが、これも全身を食われぬための
一種の
方法である。人間でも手なり足なりに
性の悪い
腫物ができて、そのままにしておいては一命にもかかわるという場合には、これを切り
捨てるのほかに
策はないとおり、身体の一部分がすでに
敵の手におちいった上は、あきらめてこれを
敵に
与えるよりほかに自分を
救う
手段はない。ただし人間では、一度切り
捨てた手や足が
再び生ずる
望みはなく、
手術後は
一生涯片輪で終わらねばならぬゆえ、かかる場合にすこぶる思い切りがたい感じがあるが、動物の
種類によっては、一度
失うた部分を
容易に
回復するゆえ、身体のある部分を
失うことは少しも苦にならぬ。しこうしてかような
際に体の一部が切れ去るのは、
敵がくわえて引く力によるのではなく、動物自身のほうに一定の
仕掛けがあって、
随意にその部を切り
捨てるのである。それゆえこの
方法を
自切と名づける。
「とかげ」の
尾がたやすく切れ取れることは人の知るところであるが、これが自切の
一例である。夏庭先などへ出て来て、
鶏につつかれた場合には、「とかげ」は
尾だけを
捨てて自身は
速やかに
石垣の間に
逃げ
込んでしまうが、後に
残った
尾は、
胴から切れても直ちには死なず、長く活発にはねまわるゆえ、
鶏はこれのみに気をとられて、
逃げた身体のほうを
追及せぬ。かくすれば「とかげ」はむろん一時は
尾なしとなるが、
餌を食うて生活してさえおれば、
暫時の内にまた元のとおりの
尾ができる。もっとも
中軸にあたる
骨骼はもとのとおりにはならぬが外見では、ただ色が少し
薄いだけで、古い
尾と少しも
違わぬ。
子供らが
靴で軽く
踏んでも直ちに切れるくらいであるから、
尾を
捨てることは「とかげ」にとってはすこぶる
簡単なことで、もしこれによって命を全うすることができるならば、一時
尾を
失う
不自由のごときはほとんど言うに足らぬであろう。
「ばった」、「いなご」などの
昆虫類も、足を一本つまんで
捕えると、その足だけ
残して
逃げ去ることが多い。ただし
寿命が短いゆえでもあろうが、一度
失うた足を
再び生ずるにはいたらぬ。夜出て来て
障子などを走る「げじげじ」も、
押さえて
捕えようとすれば
必ず
幾本かの足を
残して
逃げて行く。
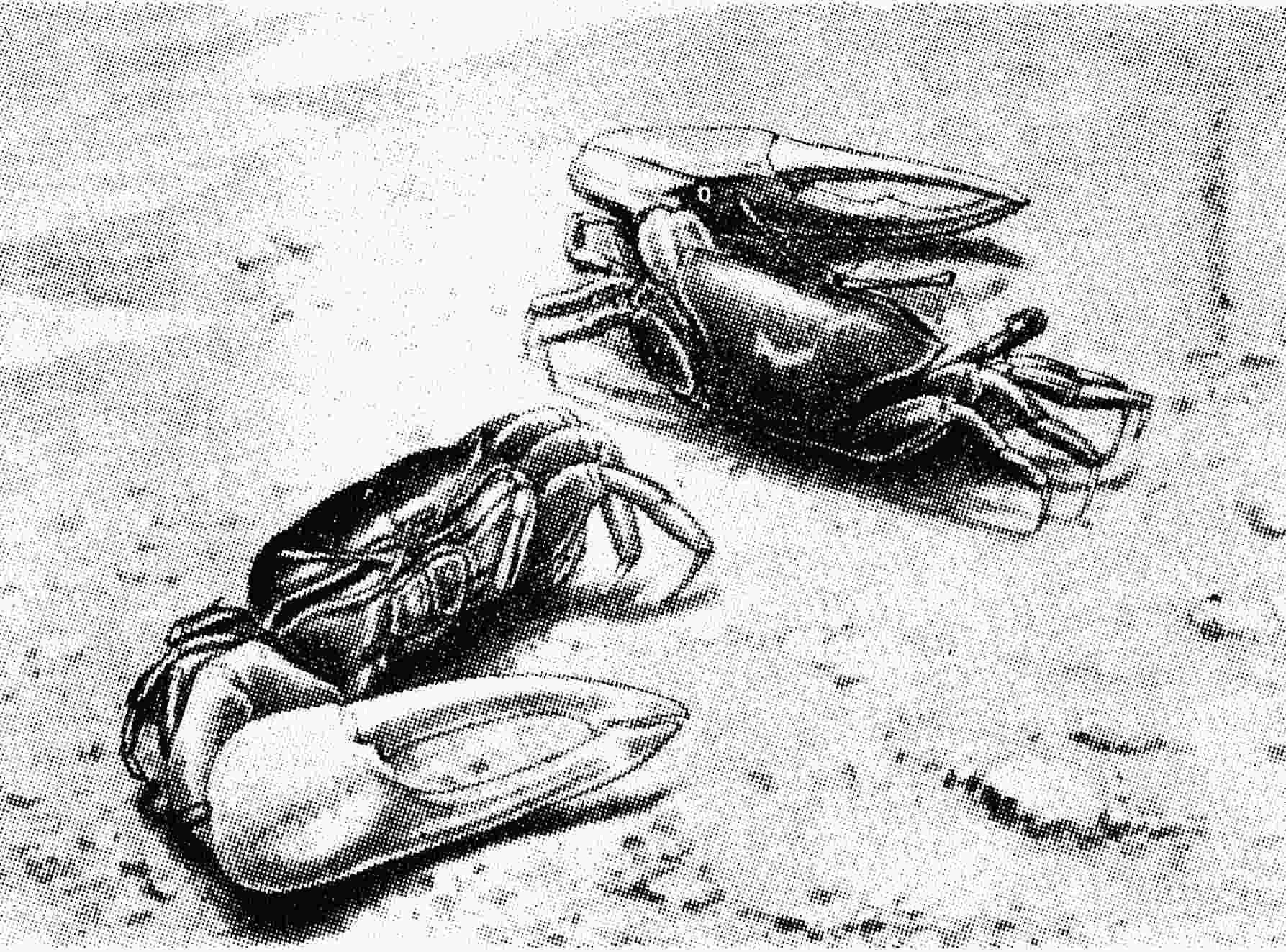 てんぼ蟹
てんぼ蟹
海岸へ行って
蟹を多数に
捕えて見ると、
往々足や
鋏が
満足に
揃うていないものがあるが、これらはなんらか
危険に
遇うた
際に
捨て去ったのであろう。中には七本の
普通の足と一本の
極めて小さい足を持ったもの、左の
鋏は
普通の大きさで、右の
鋏はその十分の一もないものなどがあるが、これは一度
失うた
跡へ新たな足か
鋏かが生じていまだ間がないゆえ、十分に
成長せぬものである。「
潮招き
蟹」の
一種に
俗に「てんぼ
蟹」などと名づけているものがあるが、その
雄の
鋏は一方だけ
非常に大きくて、身体の
格好に
釣り合わずすこぶる
奇観を
呈する。しかしかような大きな
鋏でも、切り
離した後には
再び生じてもとのごとくになる。スペインの海岸地方では、この
蟹の
鋏だけをゆでて
紙袋に入れ、あたかも
南京豆などのごとく大道店で売っているのを
子供らが買うて食う。
一袋の中には
鋏の数が何十もあるが、
鋏は
蟹一匹について一つよりないゆえ、
一袋の
鋏を取るには
蟹を
何十匹も
殺さねばならず、すこぶるむだなように考えられるが、その地方ではけっして
蟹をいちいち
殺すのではなく、ただ一方の
鋏を切り取るだけで、自身は生きたまま
逃がしてやり、新しい
鋏が大きくなったころまたこれを
捕えて
鋏だけを切り取るのである。かつて人の話に、
豚は
腿の肉を
一斤(注:600g)ぐらいそぎ取っても、しばらくでなおるゆえ、
一匹飼うておけば年中肉が食えると聞いたが、
蟹の
鋏の
詰もあたかもこれと同様なつくり話のように聞こえる。しかしこのほうは
実際である。
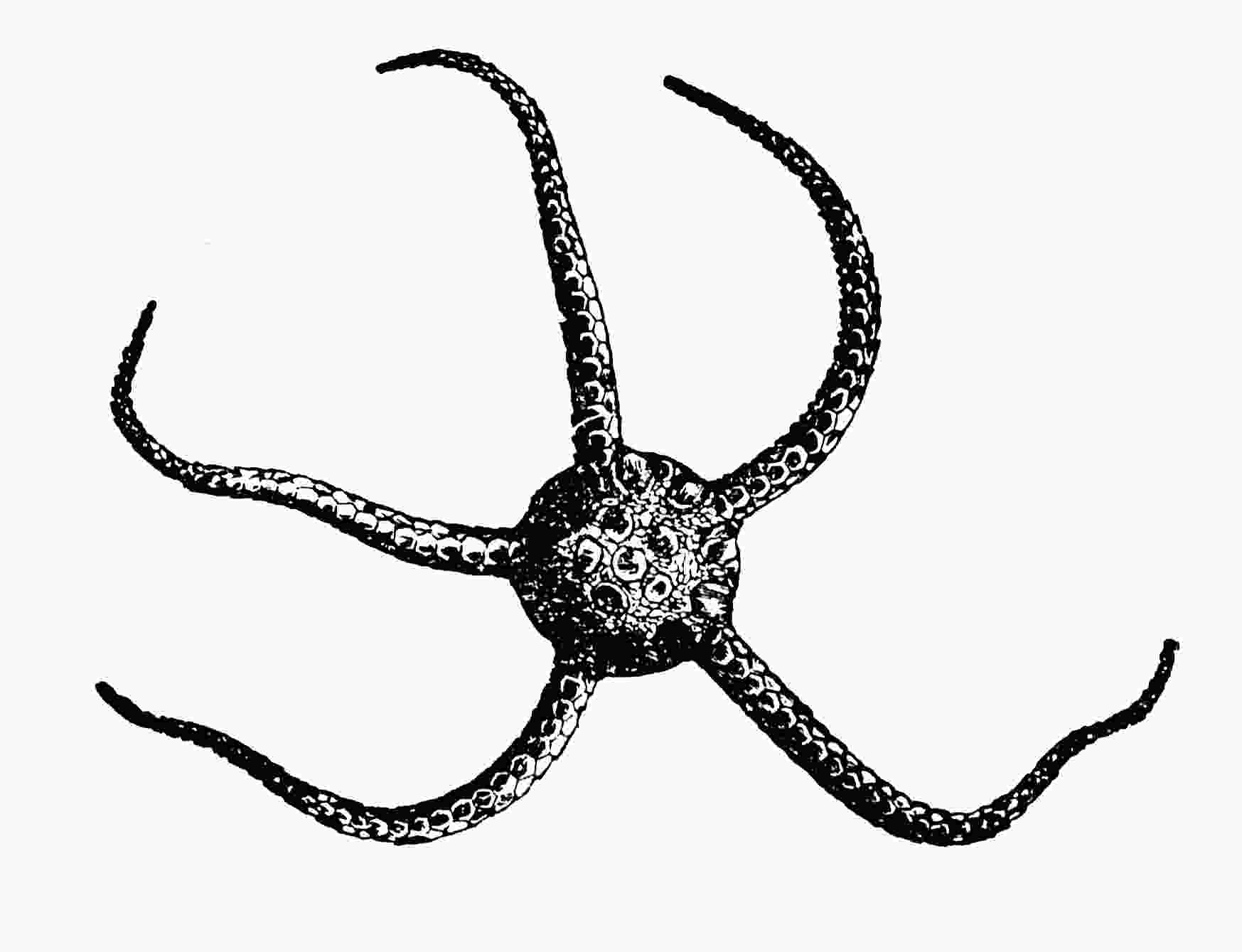 くもひとで
くもひとで
海岸の石を起こすと、その下に「ひとで」、「くもひとで」などがたくさんにいるが、この
類も
失うた体部を
再び
回復する。
特に「くもひとで」のほうは
腕がもろくて、よほど
鄭重に
取扱うても
腕が
途中で
折れて、
完全な
標本の
得られぬことが多い。しかしたちまち
折れ口から新たな
腕の先が生じて
延びるゆえ、他のものと
揃うようになる。
何匹も
捕えて見ると、
腕の
中途に
段があって、それより先はにわかに細くなって、色の
薄いものがたくさんにあるが、これはみな
折れた後に
復旧しかかっているところである。すなわち「くもひとで」の
類も、
敵に体の一部を
捕えられた場合には、
速やかにその部を
捨てて
逃げ
去って、全身
敵に食われることをまぬがれるが、後にまた少時で
回復するから、
損失はわずかに一時のことにすぎぬ。命を全うせんがために身体の一部を
犠牲に
供することは、
普通の動物にとってはずいぶん苦しい事であるが、ここに
例にあげたごとき
回復力の
盛んな動物から見れば、実に何でもないことで、かつ日々行なう予定の仕事である。列強の
圧迫に
堪えかねて、やむを
得ず一部分ずつを
割愛する
老大国などから見れば、これらの動物は
如何にも
羨やましく思われるであろう。
以上若干の
例について
述べたとおり、
敵に食われぬためにはさまざまの
手段があって、
尋常に勝負を決することのほかに、
逃げる
法、
隠れる
法、
攻められても平気でいる
法、
脅喝によって一時をしのぐ
法、身体の一部を切り取らせてあきらめる
法などがつねに用いられている。
目的とするところは一つであるが、それぞれ一長一短があって、いずれを
最上の
策ということはできぬ。
要するに
自然界には
絶対に
完全なというものはけっしてなく、何事もただ間に合うという
程度までに進んでいるだけであるが、食う
方法でも、食われぬ
方法でも、他と
競争して自分の
種族を後にのこすのに間に合いさえすれば、それで
目的にかのうていると見なさねばならぬ。
敵を
攻めるに当たっても、その
攻撃を
防ぐに当たっても、
敵の
眼をくらませて、自分のいるのを
悟らしめぬことはすこぶる
有利である。
敵が知らずにいれば、
不意にこれを
攻めてたやすく打ちとることもできる。
敵が知らずに通り
越せば、全く
危難をまぬがれることができる。いずれにしてもこのくらい、
都合のよいことはないゆえ、生物界においては、
詐欺は食うためにも食われぬためにも
極めて広く行なわれている。しこうしてだまして
暮らす動物は代々だますことに
成功せねば生活ができず、その相手の動物は代々だまされぬことに
成功せねば
餓死するをまぬがれぬから、一方のだます
手際と他方のだまされぬ
眼識とは、つねに
競争のありさまで
相伴うてますます進んで行く。あたかも
器械師が
精巧な
錠前を
造れば、直ちに
盗賊がこれを開く
工夫を考え出すゆえ、さらになおいっそう
巧妙な
錠前を
造らねばならぬのと同じである。されば
精巧な
錠前は
盗賊が
造らせると言い
得るごとく、動物界に見る
巧みな
詐欺の
手段は、みなその
敵なる動物が進歩
発達せしめたと言うことができよう。すなわち
詐欺のつたないものは、代々
敵が間引き去ってくれるゆえ、
巧みなもののみが代々後に
残って、ついに次に
述べるごときものが生じたのであろう。
動物の色が、その生活する場所の色と
相同じためにすこぶるまぎらわしい
例は、ほとんど
際限なくある。
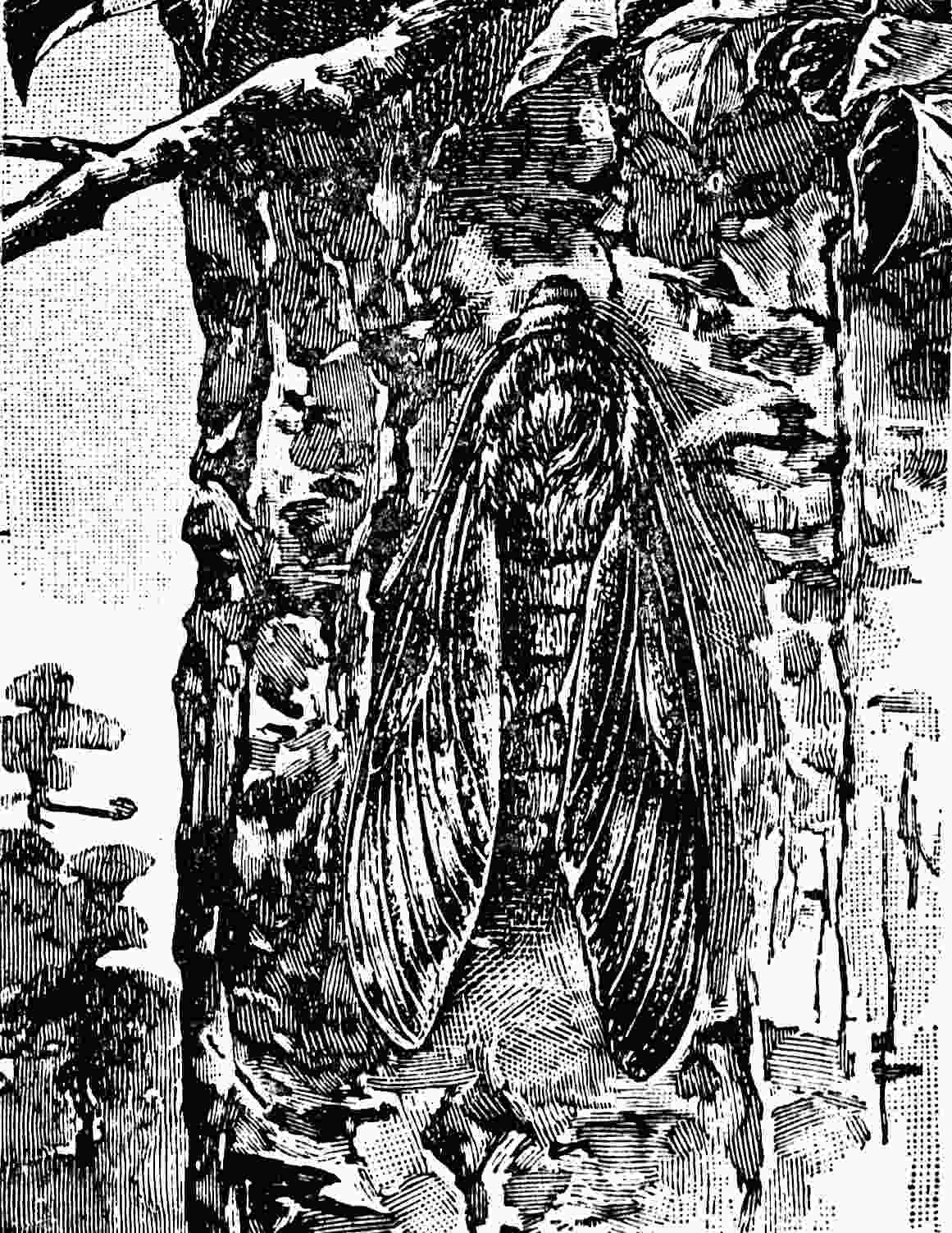 樹皮に似た蛾
樹皮に似た蛾
緑色の「いなご」が緑色の
稲の葉に止まっているとき、黄色い
胡蝶が黄色い
菜の花に休んでいるとき、土色の
雀が土の上に
下りているとき、
鼠色の
蛾が
鼠色の
樹の
幹にとまっているときなど、いずれもよほど注意せぬと見落しやすい。また
潮干に海へ行って見ると、
浅い
底の
砂の上に「かれい」、「こち」、「はぜ」、「かに」などがいるがいずれもみな
砂色で
砂のような
斑紋があるので、
静止していると少しも見えぬ。それゆえ、ときどき知らずに「かざみ」などを
踏んで、急にはい出されて大いにびっくりすることがある。アジア、アフリカ等の広い
砂漠に住する動物は
獅子、
駱駝、
羚羊などの大きな
獣から
鼠、小鳥などにいたるまで、さまざまの
種類の
異なった動物が、
残らず
淡褐色の
砂漠色を
呈している。これと同様に年中雪の
絶えぬ
北極地方へ行くと、
狐でも
熊でも全身
純白で、雪の中ではほとんど見分けがつかぬ。
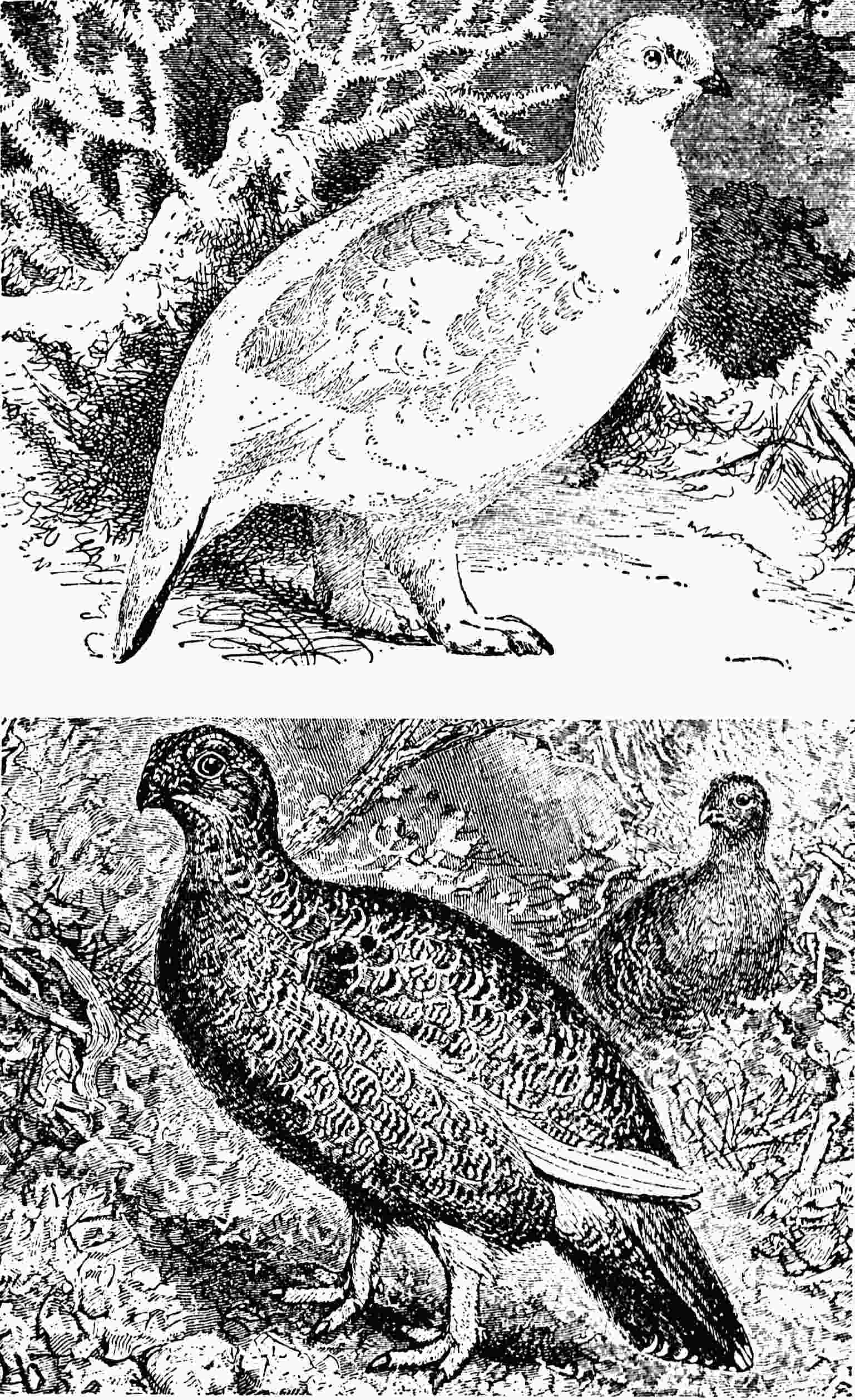
雷鳥
(上)冬の羽毛 (下)夏の羽毛
右に
似てややおもしろいのは、日本の東北地方にいる「
越後兎」や
高山の
頂上に
棲む「
雷鳥」である。これらは冬雪の
積もっているころは
純白で雪と
紛らわしく、夏雪のないころは
褐色で地面の色によく
似ている。
周囲の色の
変わるころには、そこに住む
鳥獣の毛も
抜け
換わって同様に
変化するのも、やはりかように
変化せねば
敵に
攻められて
生存ができぬゆえであろうが、さてかかる
性質はもと
如何にして起こり、
如何にして
完成したかは、なかなか
困難な問題で
容易に
説明はできぬ。しかし
仮に外界の色はいくぶんずつか動物の色に
影響をおよぼすもので、その上、冬は雪の色にもっとも
似たもの、夏は地面の色にもっとも
似たものだけが代々生き
残るものと
想像すれば、
以上のごとき事実は
必然生ずべき
理屈と思われる。
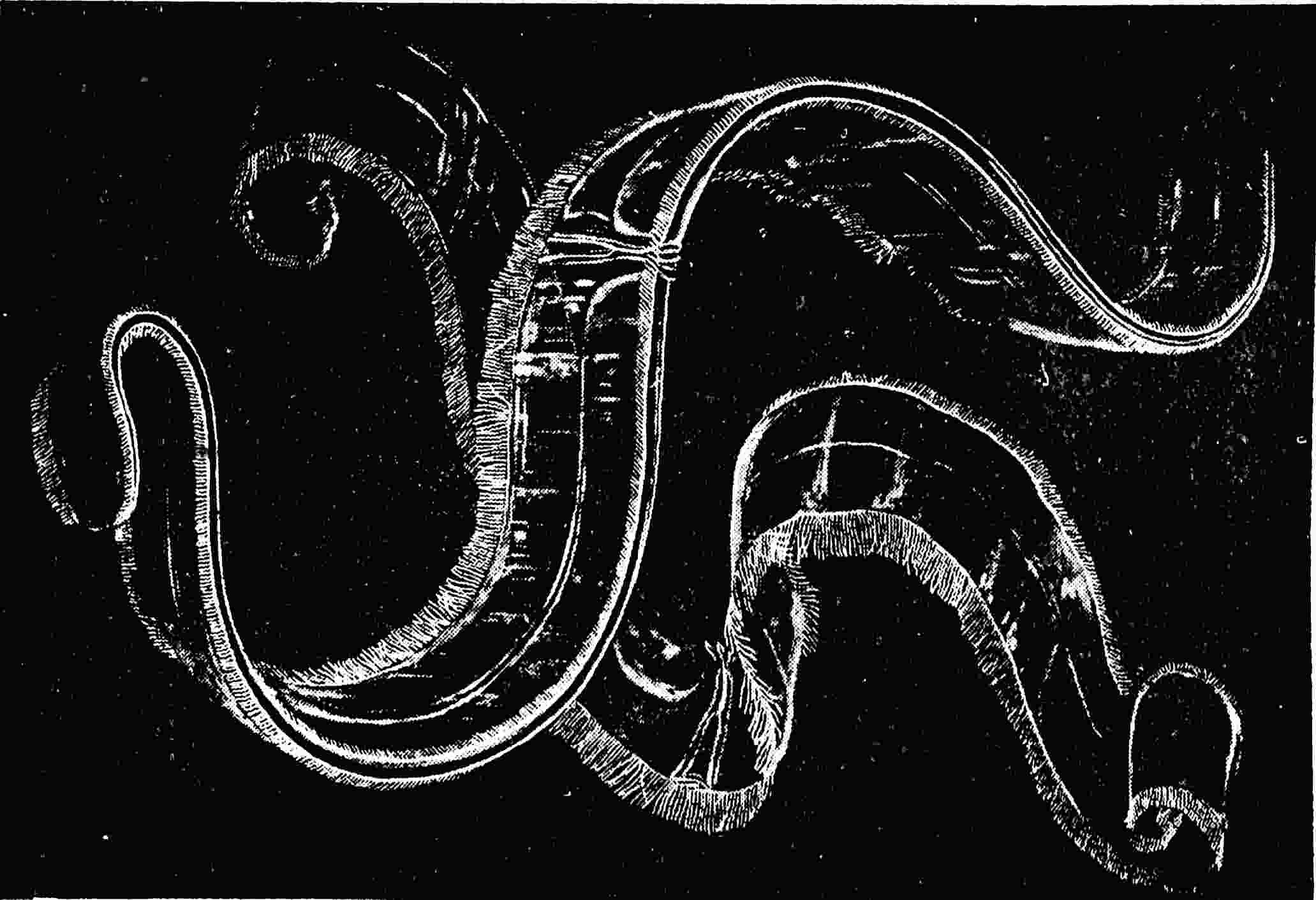 帯くらげ
帯くらげ
海の表面に
浮游している動物には、
無色透明なものがすこぶる多い。これを集めて見ると、ほとんどあらゆる
種類の代表者があって、中にはこのような動物にも
透明な
種類があるかと
驚くようなものも少なくない。くらげには全く
透明なものがいくらもあるが、「
帯くらげ」と
称する
帯状のくらげなどは、長さが
二尺(注:60cm)、
幅が
二寸(注:6cm)近くあるものでも、あまり
透明なために
慣れぬ人には
眼の前にいても見えぬことがある。ただし
或る角度のところから
眺めると、
薄い
虹色の
艶が見えてすこぶる美しいゆえ、ヨーロッパではこのくらげのことを「
愛の女神ビーナスの
帯」と名づける。また
貝類は
普通は
不透明なものばかりであるが、海の表面に
浮かんでいる
特別の
種類になると、身体が全く
無色透明ではなはだ見いだしにくい。大きなものは長さ
一尺(注:30cm)にも
達するが、
普通の
貝類とはよほど外形が
違うから、知らぬ人はこれを
貝類と思わぬかもしれぬ。「たこ」の
仲間でも「くらげたこ」と
称する
一種のごときは全身ほとんど
無色透明で、ただ
眼玉二つだけが黒く見えるにすぎぬゆえ、そこに「たこ」がいることにはだれも気がつかぬ。正月の
飾につける
伊勢えびは、生では
栗色、
煮れば赤色になって、いずれにしても
不透明であるが、その
幼虫時代には全く体形が親とは
違うて、
水面に
浮かんでいる。しこうしてそのころには全く
無色透明で、ガラスでつくったごとくであるから、よほど注意せぬと
見逃しやすい。
魚類にも、
往々無色透明なものがある。
鰻、「あなご」などの
幼魚は多くは海の
底に近く
棲んでいるが、
網にかかったものを見ると、
極めて
透明で水の中ではとうてい見えぬ。
魚類でも
鳥類、
獣類でも血は赤いものと定まっているが、
鰻類の
幼魚では血も水のごとくに
無色である。それゆえ、人の
眼に見える部分はただ、頭にある一対の小さな
眼玉だけにすぎぬ。
漁師は昔からこの魚を見てはいるが、
鰻類の
幼魚とは知らず、
別種の魚と見なして「ビイドロ魚」と名づけている。
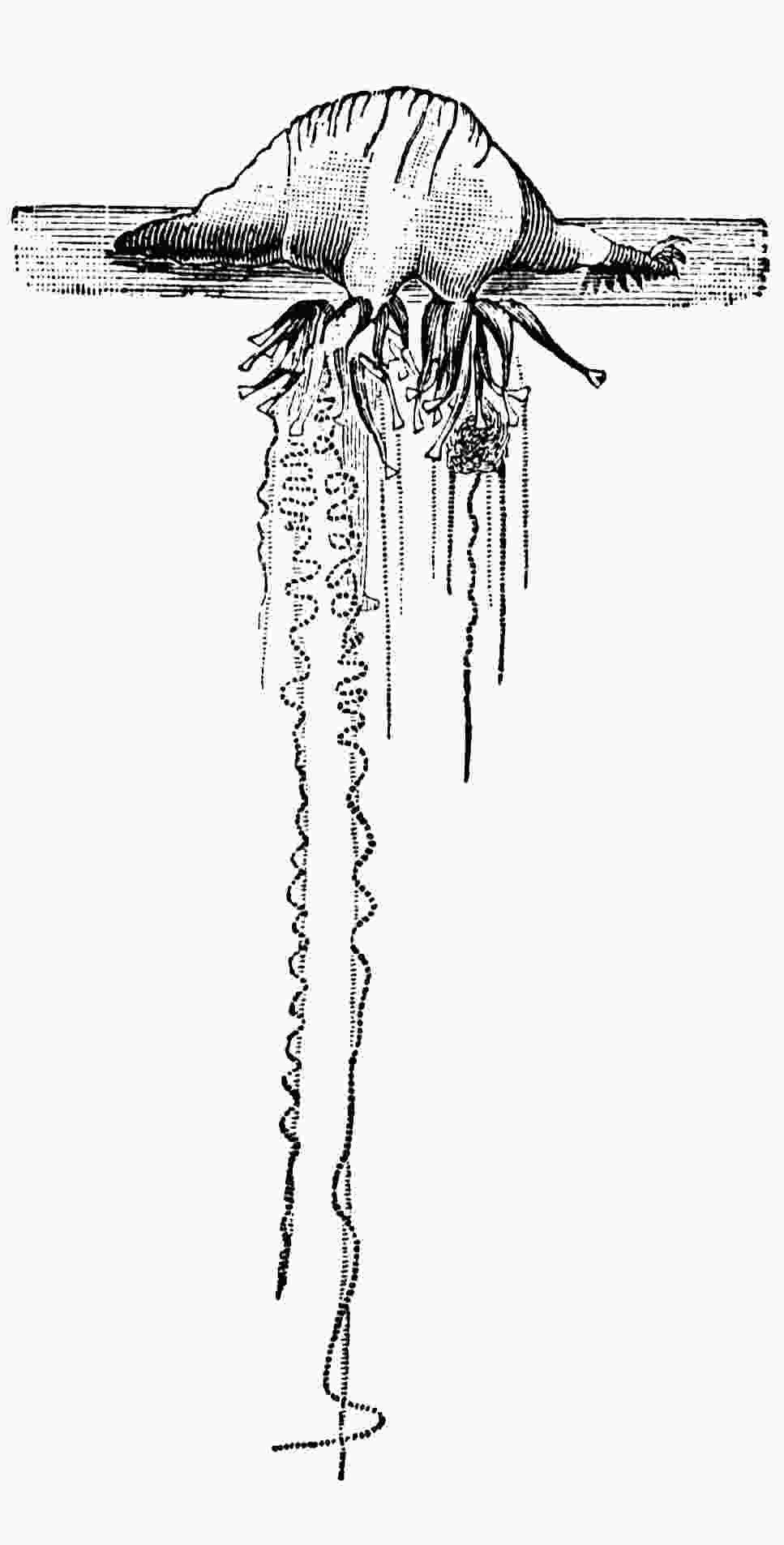 かつおのえぼし
かつおのえぼし
海岸から少しく
沖へ出て、
鰹などの取れる
辺まで行くと、海の表面に「かつおのえぼし」と名づける動物がたくさんに
浮いている。その一つを拾い上げて見ると、あたかも小さな空気
枕の下へふさをつけたごとき形のもので、水上に
現われている部分は白色、水中に
浸っている部分は
濃い
藍色である。ふさのごとくに見えるものは、実は「さんご」や「いそぎんちゃく」に
似た動物
個体の集まりで、つねに小さな
魚類などを食うているが、これを
捕えるために
伸縮自在な長い
紐を
幾本となく水中に
垂れている。しこうしてこの
紐にはところどころに
特殊の
毒刺があって、人間の
皮膚にでも
触れると、
接したところだけ赤くなってはげしく
痛むくらいであるゆえ、小さい魚などはこれに
遇うとたちまち
殺され、引きずり上げられて食われてしまう。されば、この動物が
小魚を
捕えるには水中に見えぬことが
必要であるが、
黒潮の水の中で
濃い
藍色をしているのは、そのためにはもっとも
都合がよろしい。また水面上に
現われている部分が白色であるのは、波の
泡立っているのと
紛らはしくて、うえから見てはなかなか
区別ができぬ。このほかに「かつをのかむり」と名づける動物も、同様のところに住み同様の生活をしているが、外形がやや
異なるにかかわらず、やはり水上の部は白色、水中の部は
濃藍色である。
以上はいずれも動物の色がつねにその住む場所の色と同じであるために、そこにいながらあたかもおらざるごとくに
装うて、食うことおよび食われぬことに
便宜を
得ているものであるが、
或る動物では体の色が行く先々で
変わって、どこへ引っ
越しても
相変わらず
留守を使うことができる。
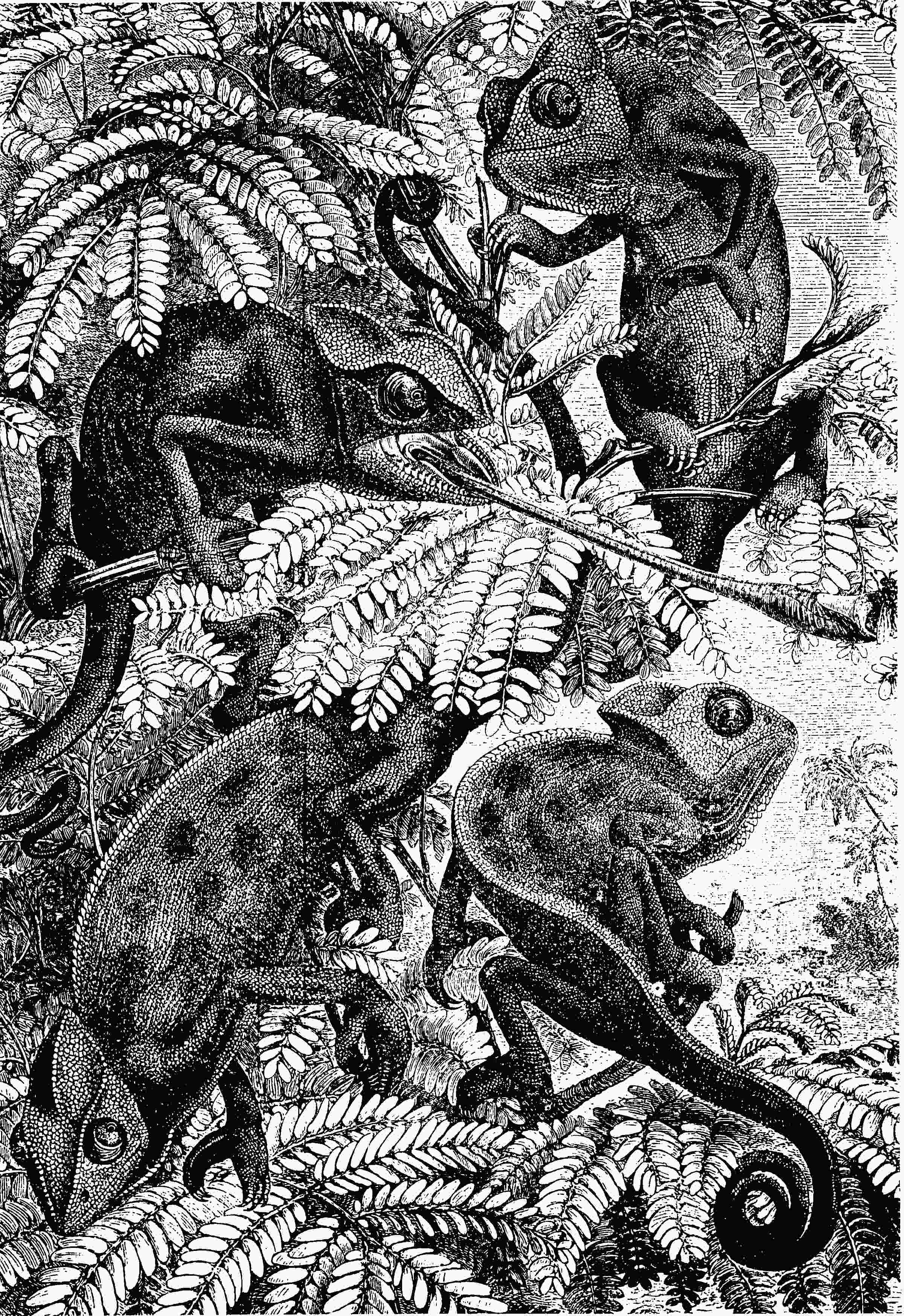
カメレオン
アフリカの北部に産する「やもり」類の一種にして,つねに樹上に棲み,昆虫を見れば急に長き舌を延ばしその先端に粘着せしめて捕え食う。随意に体色を変じてそのいるところと同色となるをもって有名なり。
この点でもっとも有名なのは「カメレオン」の
類である。
皮膚の内にある
種々の
色素があるいは
隠れあるいは
現われるために、その
混合の
程度に
従うて実にさまざまの色が生ずる。しこうして、その色はいつも自分のいる場所の色と同じにすることができて、緑葉の間におれば全く緑色となり、
褐色の
枝の上では
褐色となり、白紙の上に
置けばほとんど白に近い
淡い
灰色となり、炭の上に
載せれば
極めて
濃い暗色となるから、いつも外界の物と
紛らはしくて見つけがたい。いったいこの動物は
樹の
枝にとどまって、
飛んで来る
昆虫を待っているもので、これを
捕えるにあたっては
極めて長い
舌を急にのばし、あたかも
子供が、
黐竿で「とんぼ」を取るごとくにして
捕えるが、身体の色がいつも
周囲と同じであるゆえ、虫は何も知らずにその
近辺まで
飛んで来る。つねには長い
舌を口の中に
収めているゆえ、
下顎の下面は半球形にふくれ、かつ左右の
眼も
別々に動かすゆえ、
容貌が
如何にも
奇怪に見える。身体の色が
周囲の色と同じであることは、
昆虫を
驚かしめぬためのほかに、
敵の
攻撃をまぬがれるの役にも立つであろうから、これは食うためにも、食われぬためにも
至極有利なことであろう。わが国に
産する
雨蛙なども、いる場所しだいで
随分いちじるしく色を
変えるもので、緑葉にとまっている間はあざやかな緑色でも、
枯木の皮の上にくればこれに
似た
褐色になる。なおその他、体の色を
種々に
変ずる動物の
例はいくらもあるが、多くは
周囲の色に
紛れて身を
隠すためである。
色や
模様のみならず身体の形までが何か他物に
似ていれば、
敵の
眼をくらますにはむろんさらに
都合がよろしい。
 木の葉虫
琉球
木の葉虫
琉球、
八重山辺に
産する「木の葉
蝶」が
枯葉に
似ていることや、内地に
普通に見る
桑の「
枝尺取り」が
桑の
小枝にそのままであることは、小学読本にも出ていてあまり有名であるゆえ、ここには
略して二三の他の
例をあげて見るに、東
印度に
産する「
木の葉虫」などはそのもっともいちじるしいもので、「いなご」の
類でありながら身体は平たくて木の葉のごとく、六本の足の
節々までがそれぞれ平たくて小さな葉のように見え、
翅を
背の上にたたんでいると、
翅の
筋があたかも
葉脈のごとくに見える。しこうして全身緑色であるゆえ、緑葉の間にいるとだれの目にも
触れぬ。
印度コロンボの
博物館には、
玄関の入口に生きた「木の葉虫」がたくさん
飼うてあったが、その真に緑色の木の葉に
似ていることはだれも
驚かぬものはない。この虫に
限らず、およそ他物に
酷似するには、色も形もともにその物と同じでなければならぬゆえ、形の
似ている場合にはむろん色も
極めてよく
似ている。
同じく「いなご」
類のものに「
七節」という
昆虫がある。これは体が
棒状に細長く、足を前と後とに一直線に
延ばすと、全身があたかも細い
枝のごとくに見えてすこぶる
紛らわしい。中央アメリカに
産する「
七節」の
類には、体の表面から
苔のごとき形の
扁平な
突起がたくさんに出ているが、つねに
苔のはえているような場所に住んでいるゆえ、見分けることが
特に
困難である。
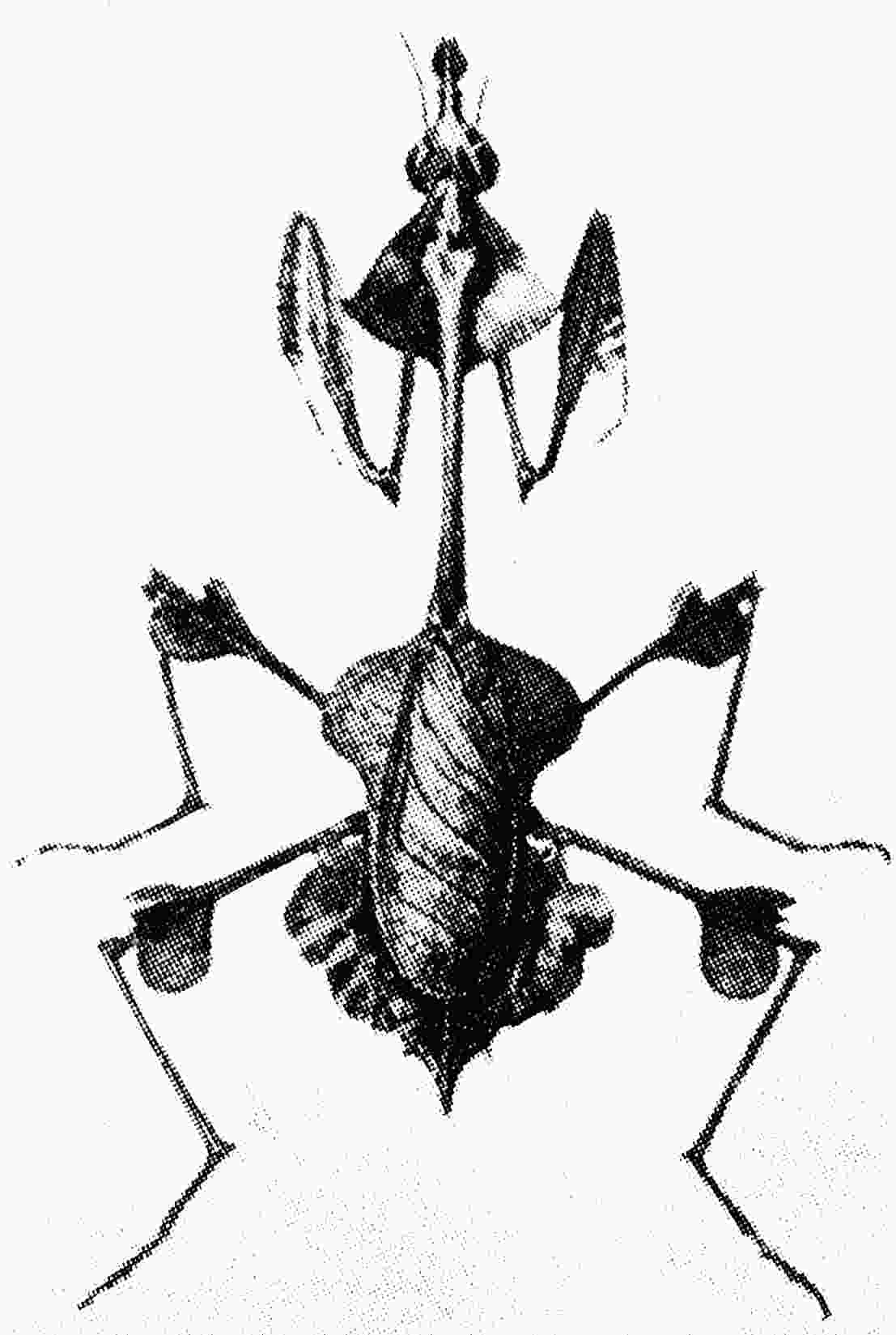 木の葉かまきり
木の葉かまきり
「かまきり」の
類にも
巧みに木の葉をまねているものがある。内地
産の
普通のものでも色が緑または
枯葉色であるゆえ、緑葉や
枯草の間にいると
容易にはわからぬが、東
印度に
産する
一種では
胴の後半も
扁平であり、後足の
一節も平たくなっているので、
灌木の
枝にとまっていると、その葉と
紛らはしくてとうてい
区別ができぬ。
 蘭の花かまきり(右)
蘭の花かまきり(右)
さらに
巧みなのは、
蘭の花に
似たものである。これも
印度の
産であるが、身体の
各部がそれぞれ
蘭の花の
各部に
似て、全部そろうと形も色も
蘭の花のとおりになる。
胸部は
幅が広くて上向きの
花瓣のごとく、
腹部も平たくて下向きの
花瓣のごとく、
前翅と
後翅とは
両側に出ている
花瓣のごとくで、かつつねにこれを左右に開いているゆえ、よほど注意して
観察せぬと虫か花か
識別ができぬ。この「かまきり」はかような花に
紛らわしい形をして、花に交じって待っていると、多くの
昆虫が花と
誤って近よって来て、
容易に
捕えられ食われるのである。

蟻くも
右側の葉の上部にいるのは蟻に似たくも。下部にいるのは真の蟻。
「くも」の
類にも
巧みに他物をまねて
餌を
捕えるものがいくつもある。庭園の
樹の葉の上には
往々すこぶる
蟻に
似た「くも」が走り歩いているが、これは「
蟻くも」と名づけてつねに
蟻を
捕えて食う
種類である。いったいならば
蟻には足が六本あり「くも」には足が八本あって、身体の
形状も大いに
違うはずであるが、「
蟻くも」では
胴の形も色も全く
蟻のとおりであるのみならず、一番前の足は
蟻の
触角のように前へ
差し出してあたかも物を
探るごとくに動かし、
残りの六本の足だけではいまわるゆえ、
挙動が
如何にも
蟻らしく見える。これはアフリカの土人が
砂漠で
駝鳥を
捕えんとするにあたって、まず
駝鳥の皮をかぶり、その
挙動をまねして
驚かしめぬように
駝鳥に近づき、急に矢を放ってこれを
殺すのと同じ
趣向で、すこぶる
巧妙な
詐欺である。また草原には時々緑色で細長い「くも」がいるが、これは四本の足を前へ、四本の足を後へ、一直線にそろえて
延ばすと、全身が細長い緑色の
捧のごとくになって、
篠などの
若芽とほとんど
区別ができぬ。かように「くも」
類には
種々他物をまねるものがあるが、その中でも一番ふるっているのは、おそらく鳥の
糞に
似た
種類であろう。これについては
熱帯地方を旅行した
博物学者のおもしろい
報告がいくらもある。
或る一人は終日大形の
蝶を
捕えようと
捜しまわったすえ、
樹の葉の上にある鳥の
糞に
一匹とまっているのを見つけ、
大喜びで
抜き足
差し足これに近づいたところが、
蝶はいっこう
逃げる様子もないので、
静かに指をもってこれを
捕えた。しかるに
蝶の
胴は半分に切れて、一方は鳥の
糞に
付着したままで
離れなかったゆえ、
不思議に思うて指で
触れて見たところが、今まで鳥の
糞であると思うたものは、実は
一匹の「くも」であって、
背を下にし、
腹側を上に向け、足を
縮めていたのである。新たに落ちた鳥の
糞は、中央の部は
厚くて
純白色と黒色との交じった
斑紋があり、
周辺の部は少しく流れて
薄い半
透明の
層ができるが、この「くも」は糸をもって木の葉の表面に
適宜の大きさの
薄い
層をつくり、その中央に
背を下にしてすべらぬように足の
鉤で身を
支えながら、終日
静止して
蝶の来たり近づくのを待っている。かような
計略があろうとは
夢にも知らぬから、
蝶はいつものとおり鳥の
糞と思うて「くも」の上に止まり、たちまち
捕えられ血を
吸われるのである。
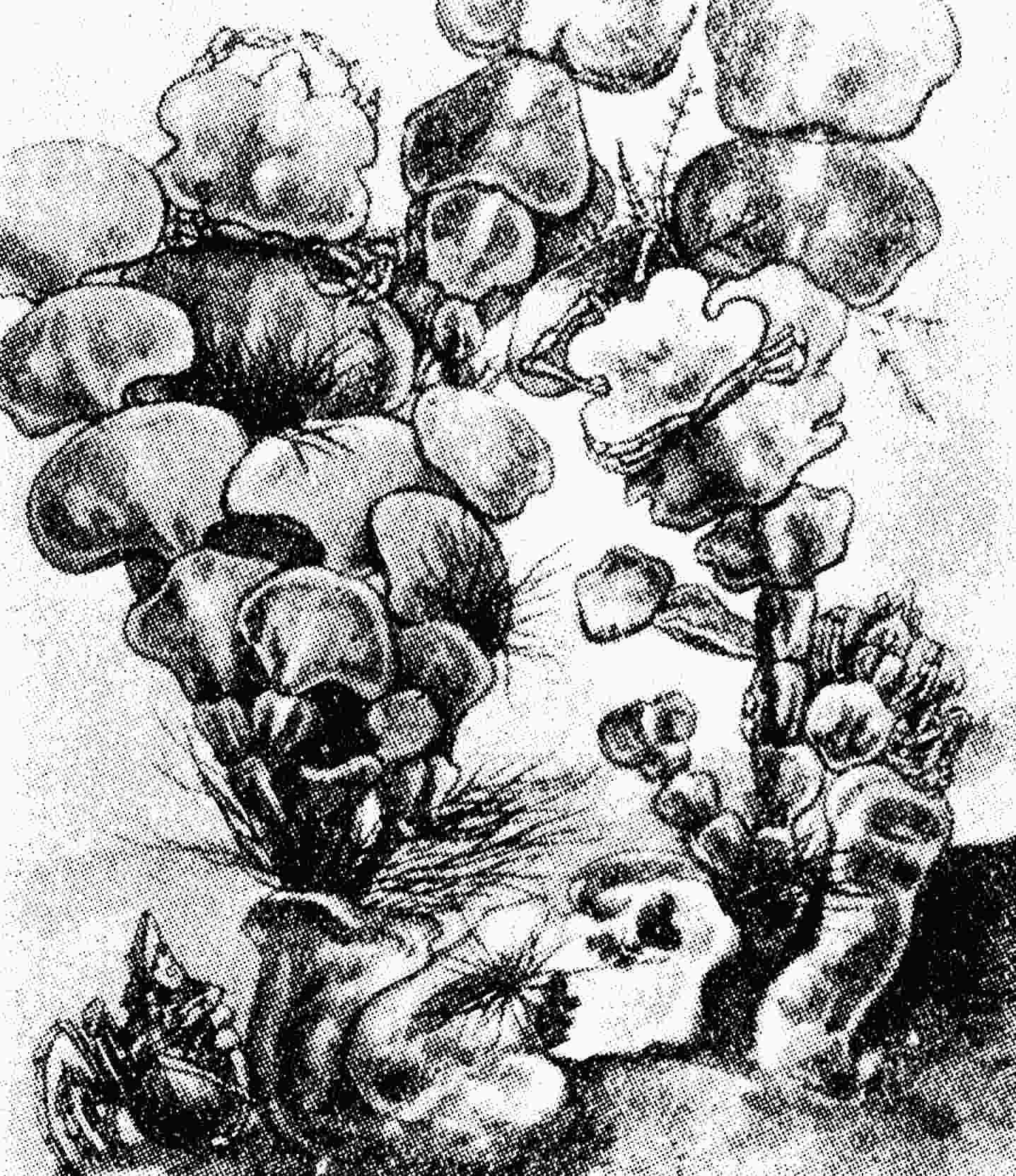 木の葉蟹
海産
木の葉蟹
海産動物にも他物をまねて
敵の
眼をくらますものがずいぶんたくさんにある。
蟹でも運動の
遅い
種類は何かの
方法で
敵の
攻撃をのがれようとつとめるが、「木の葉
蟹」と名づけるものでは、
甲の
両側から
不規則な平たい
突起が出て、あたかも
海藻のごとくに見えるから、
海藻の上に止まっているときはほとんどこれと見分けられぬ。また「石ころ
蟹」では
甲が
石塊のごとき形で、その
裏面には足や
鋏がちょうどはまるようになっているゆえ、足を
縮めていると全身が丸で小石のとおりになる。
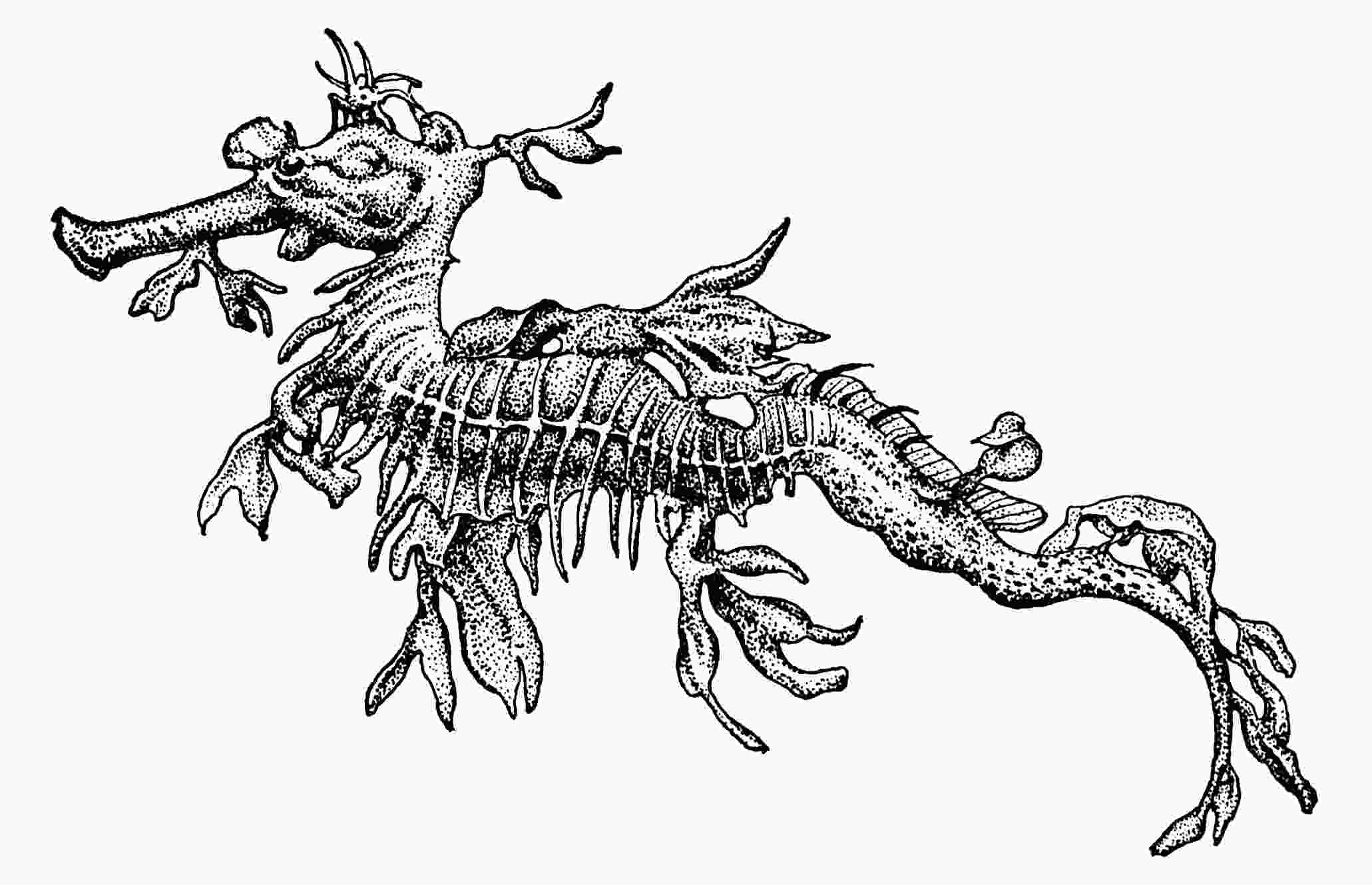 海草魚
魚類
海草魚
魚類の中でも「たつのおとしご」や「ようじうを」などが
褐色の
藻の間にいると、すこぶる
紛らわしくて見いだしにくいものであるが、オーストラリア
辺の海に
産する「海草魚」のごときは、身体の
各部から
海藻のようなびらびらしたものが生じ、これが水に
揺られているゆえ、
海藻の間に
静止しているときは、そこに魚がおろうとはとうていだれにも気がつかぬ。
以上述べたごとく、動物には
敵の
眼をくらますために、色も形も他物に
似たものがすこぶる多く、ただ色だけが
周囲の色に
一致しているものは、ほとんど
枚挙にいとまないほどであるが、またその反対に
周囲とはいちじるしく色が
違うてそのため、
格段に
眼立って見える動物がないこともない。かようなものはたいてい
昆虫などのごとき小形のもので、しかも味が悪いか、
悪臭を
放つか、
毒があるか、
針でさすか、何か
一角の
護身の
方法を
備えている
種類に
限る。
例えば
蜂のごときはその
一例で、家の
軒に
巣をつくる
普通の
黄蜂でも、
樹木の高い
枝に大きな
巣をこしらえる
熊蜂でも、身体には黄色と黒との入り交じったいちじるしい
模様があって、遠方からでも直ちにその
蜂であることが知れる。これは前に
述べた
種々の動物が、
詐欺の
手段によって、相手の
眼をくらますのと
違うて、かえって
敵の注意を引いて
損であるごとくに思われる。が、この場合には少しく
事情が
違う。すなわち
蜂には
鋭い
針があって、これにさされるとすこぶる
痛いから、一度こりた鳥はけっして
再びこれを
捕えようとはせぬ。
特に
熊蜂のごとき大きな
蜂はさすこともはげしくて、
子供などは
往々そのために死ぬことさえある。先年京都の文科大学の先生
達が山へ遠足に出かけ、
途中に
山蜂の
巣を見つけてたたいたところが、
数百匹の
蜂が
飛び出して
攻めかかったのでみなみな大いに
狼狽したとの記事が新聞に出ていたが、えらい人々でも
閉口するくらいであるから、たいていの動物がこれを
敬して遠ざけるのはもっともである。しこうして
敬して遠ざけられるためには、まずもって他とたやすく
識別せられる
必要があるが、いちじるしい
色彩をそなえているのはそのためにはすこぶる
都合がよろしい。
昆虫などのごとき小形の動物で、
特に目だつような色のものは、多くはかような
理屈で、
生存上他と
識別せられることを
利益とする
種類に
限るようである。
しかるに
不思議なことには、味も悪くなく
悪臭も放たず
毒もなくさしもせぬ
昆虫で、しかもいちじるしい
色彩を有するものが何
種類かある。しこうしてこれらは、よく調べて見ると
必ず同じ地方に
産して
鳥類などに
敬して遠ざけられている
種類のいずれかにすこぶるよく
似ている。
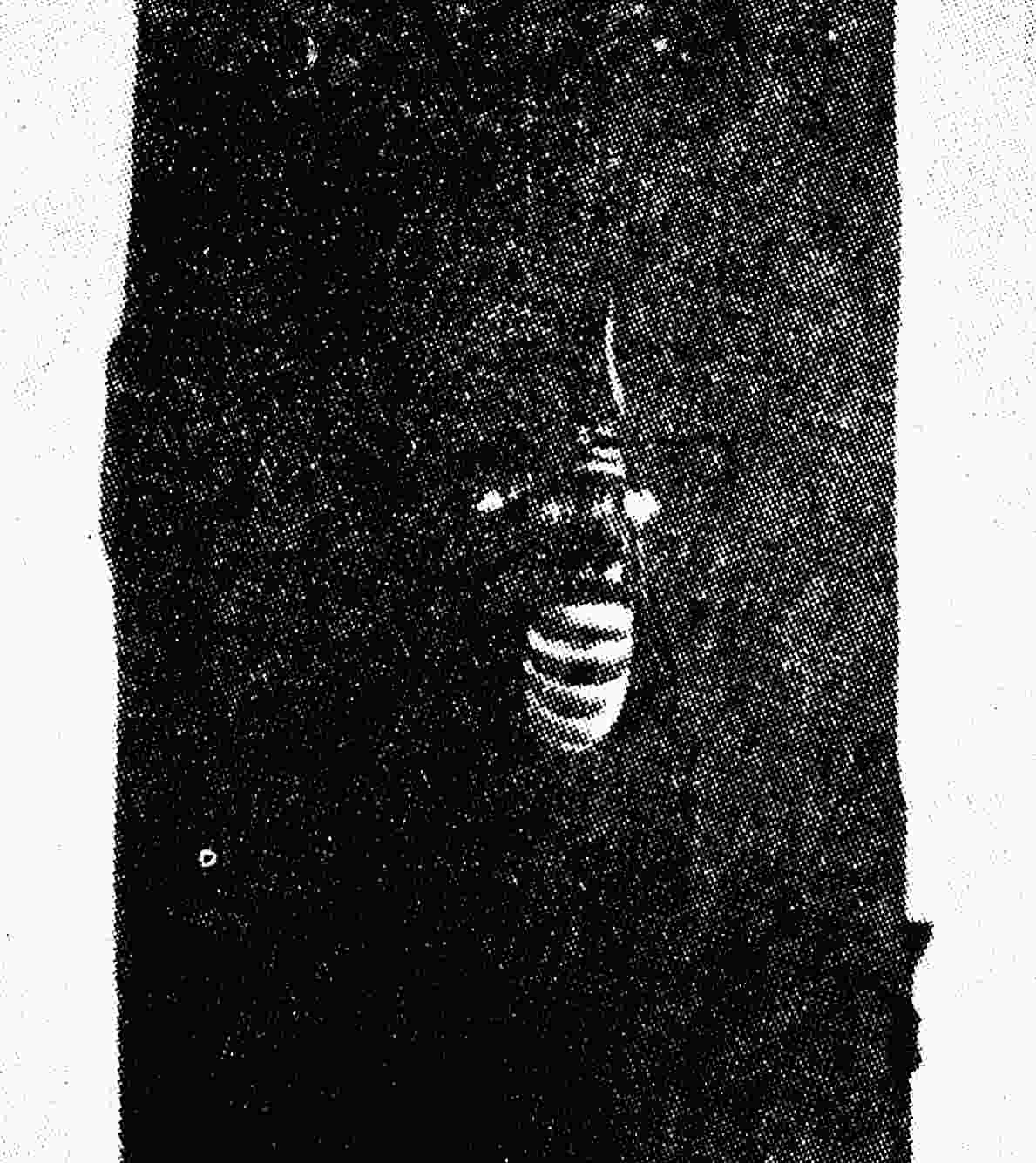 すかしば
例
すかしば
例えば
蛾の
類に「すかしば」と名づけるものがあるが、他の
蛾類が
通常灰色または
鼠色でいっこう目だたぬに反し、体には黄色と黒との
横縞があってすこぶるいちじるしい。いったい、
蝶、
蛾の
類は
鱗翅類というて、
翅は一面細かい
鱗粉でおおわれて
不透明であるのが
規則であるに、この
蛾では
蛹の皮を
脱ぐやいなや
翅を
振うて
鱗粉を落とし
捨てるゆえ、
例外として全く
透明である。その上他の
蛾類は昼は
隠れ夜になって
飛びまわるものであるが、この
蛾は昼間日光の当たっているところを
好んで
飛んでいる。かくのごとく
白昼身を
現わすことを少しもおそれぬが、その
飛んでいるところを見るとまるで
蜂のとおりであるゆえ、
蜂と
見誤られて
敵の
攻撃をまぬがれることができる。外見が
蜂に
似ていれば、
敵の
攻撃をのがれる
望みが多いゆえ、「すかしば」のほかにもちょっと、
蜂に
似た
昆虫はいくらもあるが、かように
敵に食われぬために、
他種類に
似ることを
擬態と名づける。
桑の木につく「
虎かみきり」もすこぶる
蜂に
似ている。これは
甲虫で、名前のとおり「かみきりむし」の
一種であるが、他のものとは
違い、体に黄色と黒とのあらい
横縞があるゆえ、よほど
蜂と
紛らわしい。その上、頭、
胸、
胴などの大きさの
割合や、その間のくびれ具合いなども、
普通の「かみきりむし」とは
異なって、かえって
蜂の外形に近い。
蜂に
似ている
昆虫は
蛾の
類、
甲虫類のほかにもなおいくらもある。
蠅と同じ
仲間の
昆虫にも、
飛んでいる
姿があたかも
蜂のとおりに見えるものが少なくない。それゆえかような
種類は、
子供などはつねに
蜂類と
混同して
恐れている。
擬態のもっともおもしろい
例は外国
産の
蝶類にある。
蝶類の中には
飛翔が
速やかで、
巧みに
敵から
逃げるもの、色や形が他物に
似て
敵の注目をまぬがれるもの、味がすこぶる悪いために鳥のほうが
避けてついばまぬものなどがあるが、味の悪い
種類は
特にあざやかな色を
呈し、ゆらゆらと
遅く
飛ぶ
癖がある。しかるに南アメリカ
産の
蝶などを調べると、味の悪くない
類に
属しながら自分らの
仲間とは
翅の形も色もいちじるしく
違うて、かえって味の悪い
種類と見分けのつかぬほどに
似ているものが
幾種も見いだされる。
翅の形や色は
如何に
変化しても
翅の
脈は
容易に
変わらぬゆえ、かような
蝶も
翅の
脈を
検査せられては
素性を
隠すわけにはゆかぬが、これなどは実に
擬態の
模範ともいうべきもので、
見誤らせて
敵の
攻撃をまぬがれることに
成功しているのである。
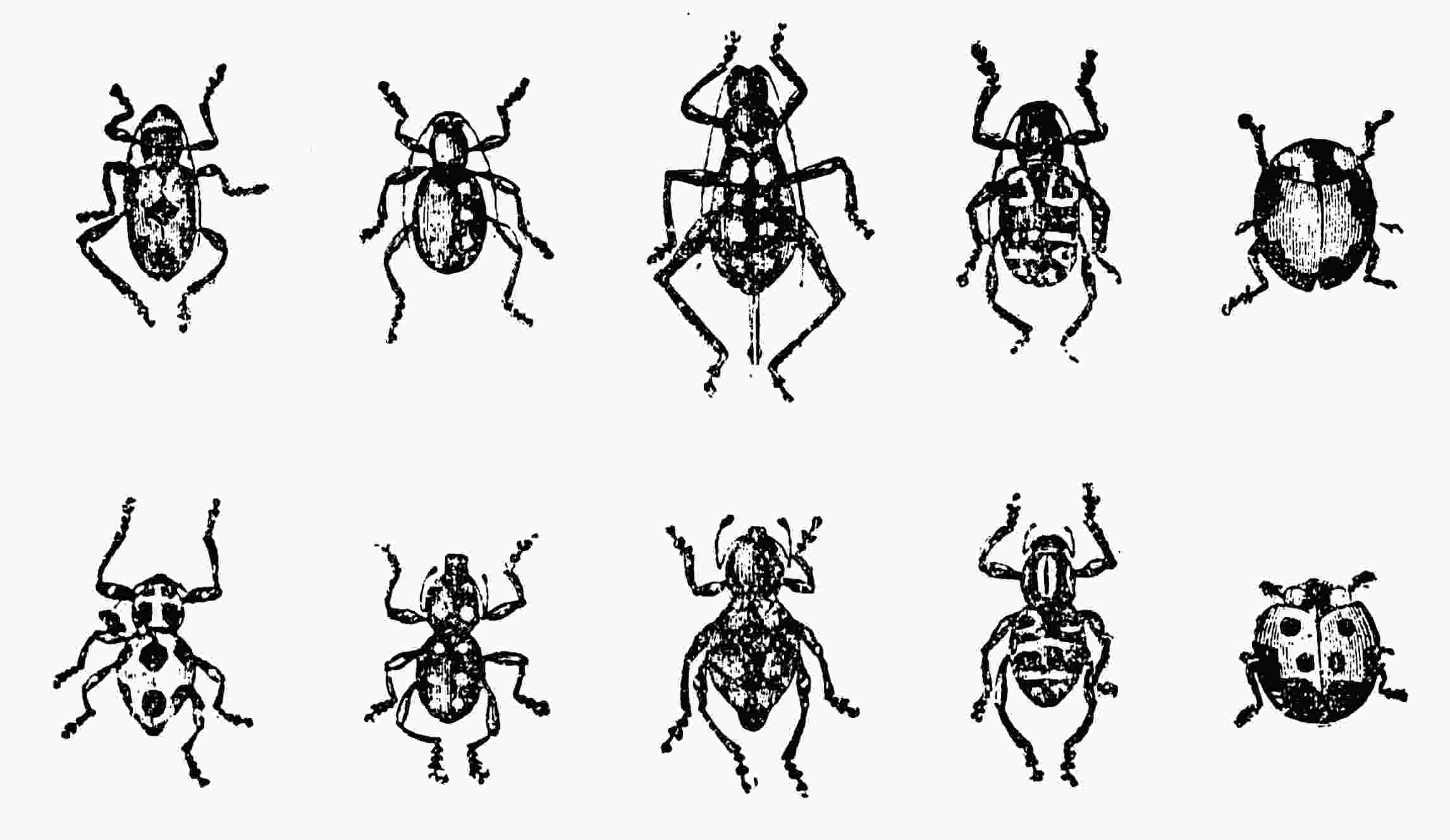 昆虫の擬態
昆虫の擬態
なお上に図をかかげたのは、皮が
堅くて食えぬ虫と、味が悪くて食えぬ虫、およびこれらに
似た他の
昆虫類の
擬態である。下の
段にならべたのはいずれも
甲虫類で、
極めて皮の
厚い「こくぞうむし」と、味の悪い「てんとうむし、」また上の
段のは、これらに
似た「かみきりむし」と「いなご」とであるが、その中でも、「いなご」の
類は
甲虫とは全く
別の組に
属するにもかかわらず、あたかも「こくぞうむし」や「てんとうむし」のごとくに見えるように、体の
形状が全く
変化している。「いなご」の中には
蟻のとおりに見える
種類があるが、これなどは身体がまさに
蟻のごとき形になって、
胸と
腹との間にくびれができたのではなく、
彩色によって
巧みに
蟻の
姿をまねているにすぎぬ。また南アメリカに
産する
蟻の
一種で、つねに木の葉をかみ切って
一枚ずつくわえて歩くもののあることは前に
述べたが、この
蟻に交じって歩く
一種のありまき
類の
昆虫は、
背から緑色の平たい
突起が
縦に生じて、あたかも
蟻が緑葉をくわえているごとくに見える。これなどは
擬態の中でももっとも
巧妙なものの
例で実に
驚くのほかはない。
動物の中には、
敵の
眼をくらますために他物をもって身体をおおうものがある。庭園の
樹木などにたくさんに
付く「
蓑虫」はその
一例で、
樹の皮や
枯葉の
破片を
寄せ集めて小さな
筒をつくり、その中に身をしずめているゆえ、なかなか生体が見えぬ。
蓑虫はみな小さな
蛾の
類の
幼虫で、つねに木の葉を食する
害虫であるが、「かいこ」などと同じく
幼時には口から糸を出すことができるゆえ、これを用いてさまざまな物をつなぎ合わせて
筒をつくるのである。
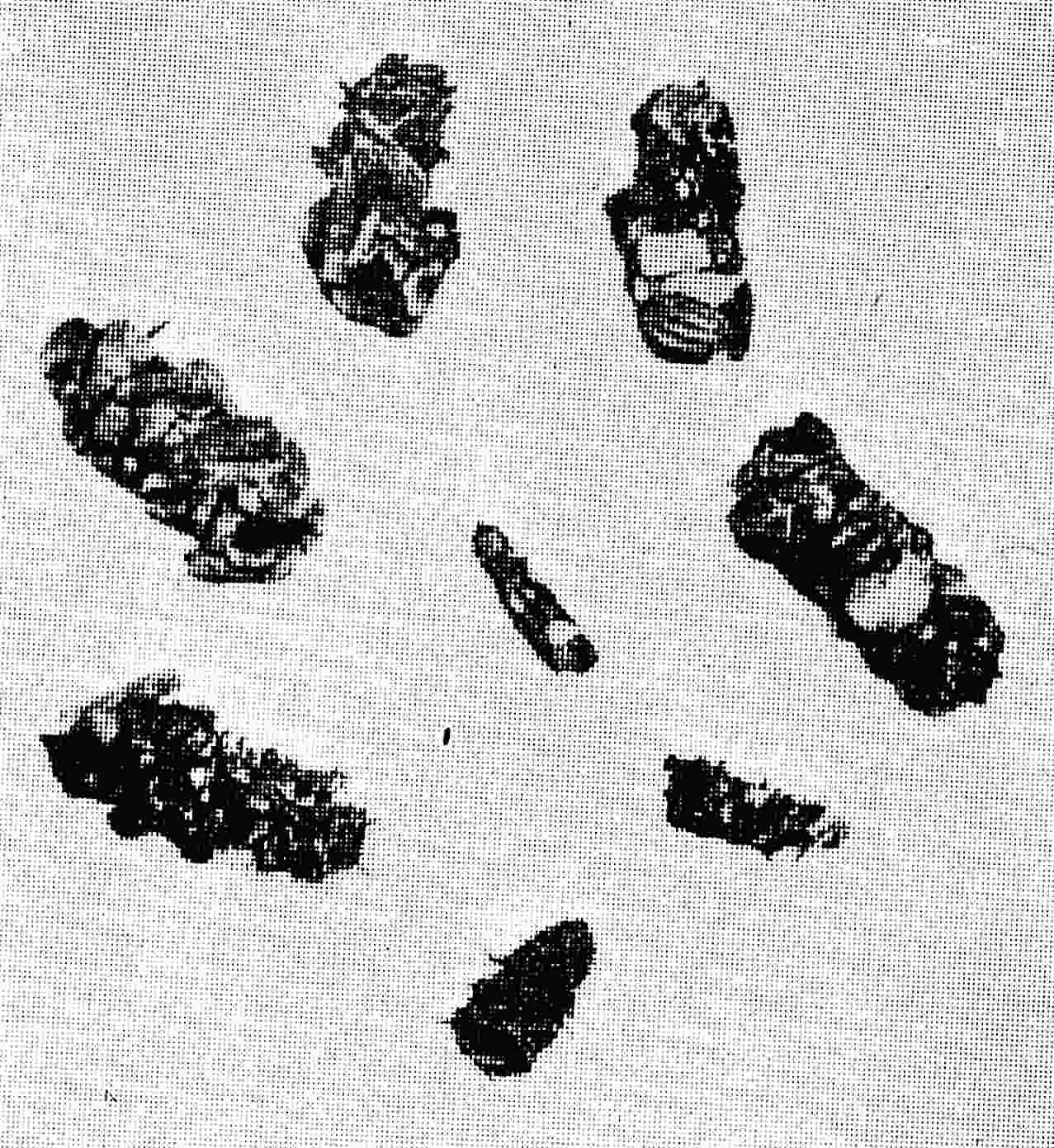 いさごむし
いさごむし
また
蛾とは全く
別の
昆虫類で、その
幼虫が他物を集めて
筒をつくるものがある。これは「いさご虫」と名づけるもので、
幼虫は水の中に住み、糸をもって細かい
砂粒などをつなぎ合わせ、その中に身体を入れ、頭と足だけを出して水中を
匍匐し食物を
探して歩く。
枯葉の
軸や
樹の皮の
筋などを集めて、あたかも
陸上の
蓑虫と同じような
筒をつくるものは、
溝の中にも
普通にいるが、
石粒を集めるものであると、
筒の形がいくぶんか人形らしくなることもある。
周防(注:山口県南東部)の
錦帯橋の
辺で
土産に売っている「人形石」と
称するものは、この
類の
幼虫の住んだ
筒である。これらの
幼虫は
成長すると水上に出て皮を
脱ぎ、「とんぼ」に
似た虫となって空中を
飛ぶが、
幼時はかくのごとく他物をもって身をおおい、
敵の
眼をくらましているありさまは
陸上の
蓑虫と少しも
異ならぬ。
樹木の
幹のへこんだところを
探すと、「やにさしがめ」と名づける虫が
往々いるが、これは体の表面に
脂のようなもので
砂の
粒をたくさんに
付けているため、足を
縮めて
静止していると、
砂の
粒だけのごとくに見えて、虫のいることはちょっと知れにくい。また海岸の岩石に多数に
付着している「いそぎんちゃく」にも、体の表面に
砂粒を
付けているものがすこぶる多い。口を
閉じ体を
縮めているときは、ただ
砂ばかりに見えるゆえ、目の前に「いそぎんちゃく」がたくさんいてもたいていの人は知らずにとおりすぎる。かつて
房州(注:千葉県南端)
館山湾の
沖の島で、
三尺(注:90cm)四方のところに、
百匹以上もかぞえたことがあるが、かように多数にいるところでも、ただ表面を見ただけでは少しもこれに気がつかぬ。
 平家蟹
平家蟹
「
平家蟹」は
甲の表面に
凸凹があって、それがあたかも
恨み
怒っている人の顔のごとくに見えるので有名であるが、これも
姿を
隠すことがすこぶるうまい。
普通の
蟹には足が四対あって、走るときにはこれをことごとく用いるが、
平家蟹では、四対ある足の中で前の二対だけははうのに用いられ、後の二対は上向きに曲がって、つねに空いた
貝殻を
支える役をつとめる。それゆえこの
蟹が海の
底で
静止しているときは、あたかも死んだ
蛤の
貝殻が
一枚離れて落ちているごとくに見えて、その下に
蟹の
隠れていることは少しも分からぬ。かように
平家蟹は年中
貝殻を
背負うて歩き、自身の
甲を
露出することがないが、つねに
保護せられている体部がしだいに弱くなるのは
自然の
規則であると見えて、他の
蟹類にくらべると
甲がやや
薄くて、内部にある
種々の
器官のある
位置が表面から明らかに知れる。
普通の
蟹では
甲は
厚くて、その表面は
平滑であるが、
平家蟹では
筋肉の
付着しているところなどがいちじるしくへこんでいるゆえ、
心臓のあるところ、
胃のあるところ、
鰓のあるところ、
肝臓のあるところが、みな
判然と
境せられ、その形が
偶然人の
怒った顔に
似ているので、
平家の人々の
怨霊であるなどとの
伝説を仕組まれた。ただしこの
蟹はけっして
平家の
討死した
壇の浦辺に
限り
産するものではなく、日本
沿岸にはどこにもいるであろう。
現に
東京湾でも
網を引くといくらもかかってくる。また前の二対の足は
匍行に用いられるから、
普通の
蟹の足と同じ
形状であるが、後の二対は役目が
違うから形もよほど
違うて短く小さく、かつ
先端の
爪は
貝殻を
保つことのできるように半月形に曲がっている。その上、根元の
位置も
甲の上面のほうへ
移って、
甲の
後端に近いところからあたかも
牙がはえているごとくに左右へ
突き出しているので、顔の相がますます
鬼らしく見える。この
蟹は
生のときは
泥のような色であるが、
蟹でも
蝦でも
煮ると、他の
色素は
分解して赤色のものが
残るゆえ、一度ゆでたら、先年
帝劇で
平家蟹という外題の
狂言にたくさん出したような赤いものとなるであろう。
足で他物を
支えて身体を
隠す
蟹は、
平家蟹のほかにも
幾程もある。その中でもっとも
普通なものは
海綿を
背負うている
蟹であるが、やはりこの
類でも、四対の足のうち、後の二対は短くて上向きになり、その
先端の
鉤状の
爪でつねに
海綿を引っ
懸けて
離さぬようにしている。しこうして
海綿のほうには、またちょうど
蟹の丸い
甲のはまるだけのくぼみがあって、
相重なっているときはその間に少しも
空隙がない。その上おもしろいことには、このくぼみの内面の
両側には二つずつ小さな
穴があって、足の
爪がこれにかかるようにできている、されば、この
蟹はどこへ行くにも
海綿を
背負うたままでもしあぶないと思うときにはたちまち
静止し、足や
鋏を引き
込めてあたかも
海綿だけのごとき
外観を
装うて、
巧みに
敵の
攻撃をまぬがれるのである。
平家蟹でも「
海綿蟹」でも、足を用いてわざわざ他物を
背の上に
支えているのであるが、
或る
蟹類は海草や
海綿などを自身の
甲や足の表面に直ちに植え
付けて
姿を
隠している。海の
浅いところで
網を引くとかような
蟹はいくらもかかってくるが、海草などに
混じているとほとんど
眼につかぬ。
蟹類は
昆虫などと同じく
成長する間にたびたび皮を
脱ぐが、
脱ぎ
換えた
当座はむろん皮は
綺麗である。しかるに外国の水族館で
飼養した
実験によると、この
類の
蟹は
脱皮後直ちに
適当な海草や
海綿を
選んで、自身でこれを
甲に
粘着せしめ、
暫時の後には
再び全身がほとんど見えぬほどに、他物をもっておおわれてしまう。
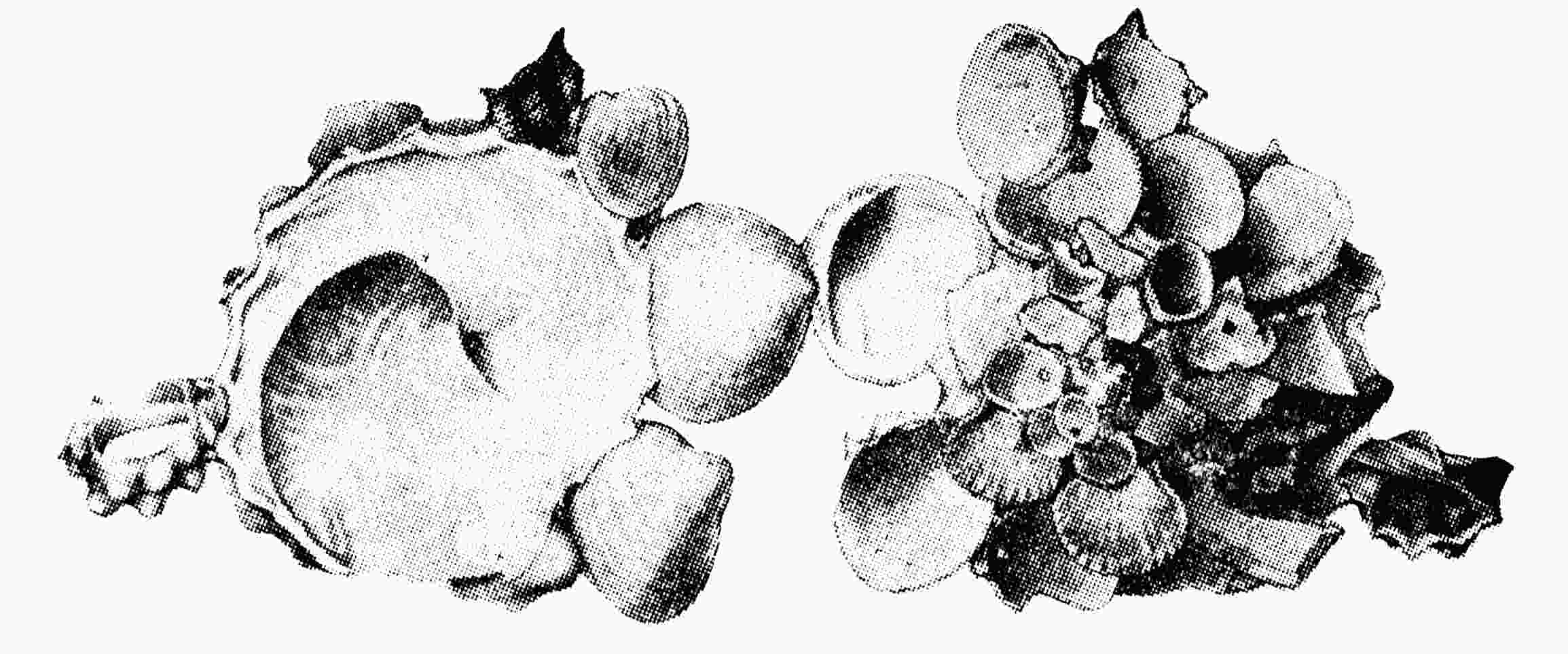 熊坂貝
巻貝
熊坂貝
巻貝の中にも「
熊坂貝」と名づけるものがあるが、これも同様の
手段で身体を
隠している。この貝は
摺鉢をふせたような
丈の
低い
巻貝であるが、
貝殻の外部には一面に他の
貝殻または小石などを
付けているゆえ、
海底に
静止しているときには、そこに生きた貝がいるとはとうてい見えぬ。小石や
貝殻の
破片などが、この貝の
貝殻の表面に
付着しているありさまは、あたかもセメントて
堅めたごとくであるゆえ
容易には
離れぬ。この貝をたくさん集めて見ると、その中には小石のみをつけたもの、小さな
巻貝の
殻のみをつけたもの、主として
二枚貝の
破片をつけたものなどがあるが、これはいずれもその住んでいる海の
底に落ちている物が、場所場所によって同じでないゆえ、それぞれ自分のいるところに
普通な物を取ってつけているのであろう。
イソップ物語の中に、二人の
友達が森の中で
熊に
出遇うたとき、
逃げおくれた一人が地上に横たわり、死んだ
真似をして
無事に助かったという話があるが、
実際動物の中には死んだ
餌は食わぬものがある。かような動物に
出遇うた時は、動くことはすこぶる
危険で、一時死んだ
真似をしていればその
攻撃をまぬがれることができる。小さな動物には、つねにこの
方法を用いて食われることをまぬがれているものがけっして少なくない。
昆虫類を
採集する人はだれも知っているであろうが、
甲虫などにも指でつまむとたちまち足を
縮めたままで転がしても落としても少しも
姿勢を
改めず、全く死んだとおりに見せるものがいくらもある。また、「くも」の
類にも
捕えると直ちに死んだ
真似をして、足を
縮めて動かぬものがすこぶる多い。これらはいずれも
捕えられそうになっても、
逃げもせず
隠れもせず
単に
静止するだけであるゆえ、
採集者のほうからいうとこのくらい
都合のよいことはない。
かような動物が
実際どれほどまで
敵の
攻撃をまぬがれ
得るかは、
自然の生活
状態を
詳しく
観察しなければわからぬことであるが、相手となる動物について
実験して見ても大体の見当はつく。
昆虫類を主として食う「ひき
蛙」で
実験して見るに、何でも動くものには直ちに注目するが、動かぬものは少しも
顧みない。小さく丸めた
紙片でも、
巻煙草の
吸殻でも、糸で
釣って上下に動かして見せると、たちまち近づいて来て一口にのんでしまうが、毛虫や
甲虫のごとき日ごろもっとも
好んで食うものでも、死んで動かぬようになったのは知らずにいる。また「とんぼ」などもつねに
昆虫類を食うているものであるが、ほとんど頭の全部をなすほどの大きな
眼はいわゆる
複眼であって、
幾万の
小単眼の集まったものゆえ、動く物体を
識別するには
特に
有効である。
博覧会や
共進会へ行って見ても、
脳漿を
絞って
工夫した
巧妙な
器械の前には見物人が少なくて、
単に人形が
頸を
振っているだけのくだらぬ
広告の
周囲には、人が黒山のごとくに集まっているところから考えると、
普通の人間も「ひき
蛙」と同様に、ただ動くものにのみ注意するようであるが、死んだ
真似をしていれば、かかる
性質の
敵からは見のがされる
望みが多い。また
小鳥類などは
鋭い
眼で、
絶えず注意して
昆虫を
捜しているゆえ、その
攻撃をまぬがれることは
容易でないが、中には
嘴で
触れて見て、はい出せばこれをついばみ、動かなければ死んだものと見なして、
捨てて
顧みぬものもあるから、死んだ
真似をするものの
何割かは
無事に助かることになろう。いずれにしても、この
方法は
護身のために
効を
奏する場合がけっして少なくない。
死んだ
真似をするものは、
昆虫や「くも」のような小さな動物のみに
限るわけではない。
獣類の中でも、
狸などは昔から死んだ
真似をするので有名なもので、いけどられてから打たれてもたたかれても少しも動かず、少々皮をはがれても知らぬ顔で
我慢するとまで言い
伝えられている。しこうして
敵が
油断すれば、そのすきをうかごうてにわかに
躍ね起き
逃げだそうとする。「
狸寝入り」という言葉は、おそらくこれから起こったのであろう。
猛獣の中には生きたものでなければ食わぬという
習性のものもあろうから、
狸の
計略が
効を
奏して、
巧みに助かることもしばしばあり
得ることと思われる。
死んだ
真似をすることは、
危険に身をさらして
僥倖を待つのであるから、
必ずしも安全な
方法とは言えぬが、
或る
種類の相手に対しては、もっとも
容易なしかも
労力を
要することのもっとも少ない
経済的の
護身の
方法である。たとえて言えば、
言論の自由を
許されぬ国で、新思想家が
沈黙によって
刑罰をまぬがれているのと
理屈は
変わらぬ。ただし自分がたしかに死んでいるか
否かを
確かめるために
敵がさまざま
検査する間、少しも生活の
徴候を
現わさずして
堪え
忍ぶことは、
大なる
苦痛であると同時に大なる
冒険であるから、どの
種類の動物でもこれを行なうて
利益があるというわけにはゆかず、ただこの
方法によって
有効に
敵の
攻撃をまぬがれ
得べき
望みのある
若干の
種類だけが、
専門にこれを行なうているにすぎぬ。
以上種々の
異なった
例をあげて
述べたとおり、相手を
欺くということは
自然界にはきわめて広く行なわれている。色や形を他物に
似せて、自分のいることを相手に心づかさぬことは、
餌を取るにあたっても
敵を
防ぐにあたっても同じく
有効であるが、これを十分
有効ならしめるには、それぞれこの
目的にかのうた
特殊の
習性を
備えねばならぬ。
例えば、
菜の花の色と同じ黄色の
蝶が、平気で赤い
牡丹の花に止まるようでは何の役にも立たず、
如何に
桑の「
枝尺取り」が
桑の
小枝に
似ていても、
枝と一定の角度をなして止まり、体を真直ぐにして少しも動かずにいるという
習性がなければ、とうてい
敵の
眼をくらますことはできぬ。それゆえ、かような動物を見ると、あたかもみな、
故意に
敵を
欺くことを
努めているかのごとくに思われる。また
擬態のごときも、十分
効を
奏するには
種々の
条件が
備わらねばならぬ。
例えば、
如何に
巧みに
或る味の悪い
蝶に
似ていても、その
蝶が
普通におらず、したがって
鳥類がその
蝶の味の悪いことを知らぬというような地方ではむろん何の
効もない。また
擬態せられる
蝶よりも、これを
擬態する虫のほうが多くなれば、この場合にも
無効になるおそれがある。
何故かというに、
餓えに
迫って
冒険的になった鳥、または
経験に
乏しい
若い鳥が、この
蝶をついばむとき、まず
擬態のほうを食いあてれば、その味の悪くないことを
覚えて、ことごとくこれを食おうとするから、たちまち
擬態する虫も
擬態せられる
蝶も、ともに
恐慌をきたすにいたるからである。なおその他の場合においても、
詐欺が
完全に行なわれるには
種々の
事情がこれに
適していなければならぬが、
適当な
事情の
下においては、
詐欺は食うためにも食われぬためにも、すこぶる
有効な
方法である。
要するに、動物は
餌を食うため、
敵に食われぬためには、あらゆる
手段を用いている。
一種ごとについていえば、あるいは速力によるもの、あるいは
堅甲によるもの、または
勇気によるもの、
回復力によるものなど、
各種にもっとも
適する
方法をとっているが、全部を
通覧するとほとんど
如何なる
方法でも用いられ、生きるという
目的のためにはけっして
手段を
選ばぬごとき
観がある。しこうして
詐欺はただその中の一部分にすぎぬ。人間社会では
武器をもって正面から
戦うのは
立派なこと、
詐欺で相手を
陥れるのは
卑劣なことと見なし、その間には
雲泥の
相違があるごとくに感ずるが、全生物界を
見渡せば、いずれも同一の
目的を
達するための
異なった
手段にすぎず、けっして
甲乙を
論ずべきものではない。すなわち
詐欺で
敵の
眼をくらますのも、
堅い
甲で
敵の
牙を
防ぐのも
理屈は全く同じことで、
詐欺の
巧みなものと
甲の
厚いものとは
生存し、
詐欺のへたなものと、
甲の
薄いものとは
亡びる。だまし
得たものとだまされなかったものとが代々助かって生き
残り、だまし
得なかったものとだまされたものとが
飢えて死ぬか
殺されるかするのは、あたかも水が高いところから
低いほうへ流れるとか、
天秤の一方が上がれば一方が下がるとかいうのと同じく、ほとんど自明の理のごとくに思われる。ただ
団体をつくって生活する動物では、同一
団体の内の
個体の間に
詐欺が
盛んに流行したならば、その
結果として
協力一致が行なわれず、
全団体の
戦闘力が
減じ、
敵なる
団体に
対抗することが
困難になって、しまいに
団体の
維持生存ができなくなるが、
団体が
亡びればむろんその中の
各個体はともに
滅亡をまぬがれぬ。全生物界の中で
詐欺を行なうたために
罰の当たるのは、かような場合に
限ることである。
動物が生活している間は、
餌を食うため
敵に食われぬためにも、また子を
産み子を育てるためにも、まず外界の
状況を知り、外界に
変化が起きれば直ちにこれに
応ずべき
策を
講ぜねばならぬが、主としてこの
衝に当たるものは
神経系である。もとより
神経系の
判然と
発達していない生物でも、生きている
以上は多少この
能力がなければならぬが、
神経系の
発達したものにくらべれば、その
働きがはるかに
鈍い。
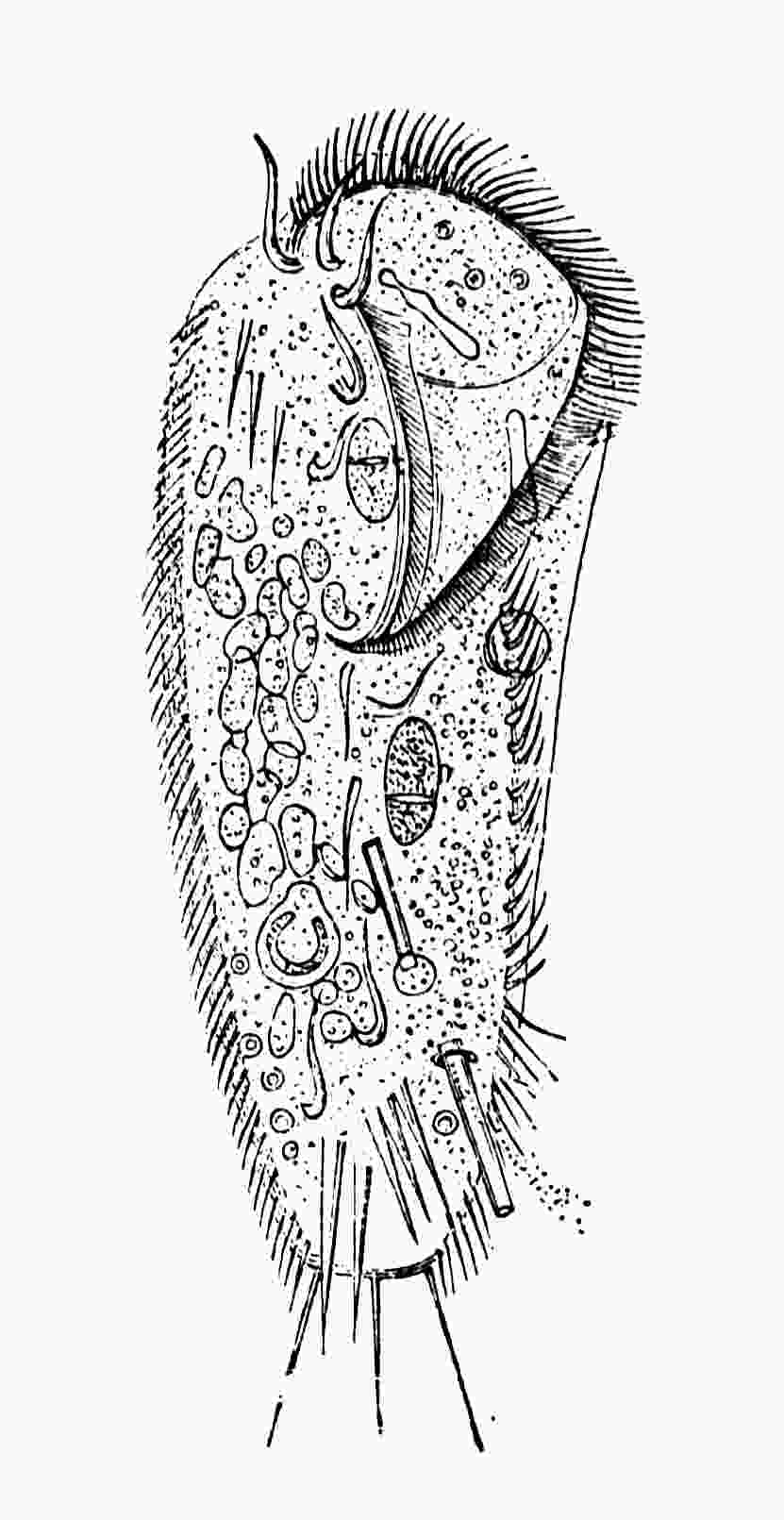 ぞうり虫
例
ぞうり虫
例えば
一滴の水の中にも
無数に
棲息し
得る「アメーバ」や「ぞうりむし」のごとき
微細な動物には、
別に
神経と名づくべき
器官はないが、光に当てれば
薄暗いほうへ
逃げ、
酸素を
与えればそのほうへ
寄って来る。すなわちこれらの虫も、外界の
変化を感じ、外界の
現状を知り、
不快のほうを
避けて心持ちのよいほうへ
移ろうとするが、これは
神経系の
発達した動物ならば、みな
神経を用いて行なう
働きである。ただ「アメーバ」や「ぞうりむし」には
特に
神経系というものがなく、全身の生きた
物質をもってこれを行なうているというにすぎぬ。また植物でも「おじぎそう」のごときは
感覚がすこぶる
鋭敏で、ちょっと
触れても直ちに葉が
閉じて下りる。
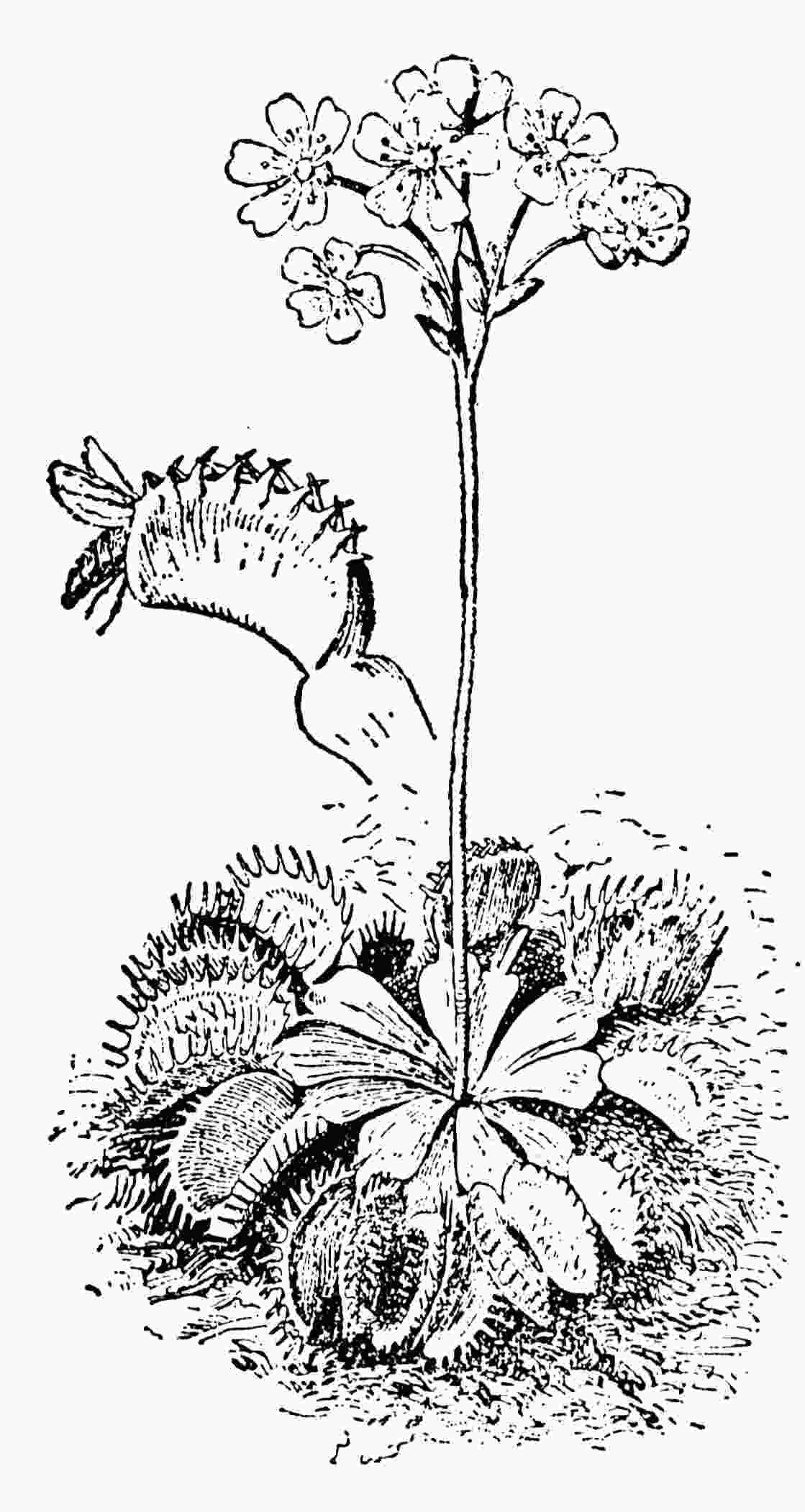 アメリカ蠅取草
アメリカ蠅取草
米国
産の「
蠅取草」は、葉の表面に
蠅が来てとまると、たちまち葉を
閉じてこれを
捕え
殺して食うので有名である。しかもおもしろいことには、これらの植物に
麻酔薬をかがせると、あたかもねむったごとくになって少しも動かぬ。その他「ひまわり」の花が朝は東を向き夕は西を向き、「かたばみ」の葉は昼は開き夜は
閉じるなど、外界の
変化に
応じて
姿勢を
異にするものはいくらもあるが、植物には
特に
神経と見なすべきものはないから、これらの運動はただ身体の生きた
組織の
感覚力に
基づくことであろう。
そもそも動物体における
神経系の役目は、外界からの
刺激によって外界の
事情を知り、これに
応じて身を
処するにあるが、
実際身を
処するにあたって
働くのは、主として
筋肉である。しかしこれだけの
働きは、
必ずしも
神経系と
筋肉とがなければできぬというわけではなく、
或る
程度までは
神経筋肉なしに行なわれている。ただし、これを
神経系の
発達した動物にくらべて見ると、その
程度に
雲泥の
差があることは、あたかも
野蛮人はだれでも自分で家をつくり
得るが、文明国の
専門技師が
建てた大
建築物とはとうてい
比較にならぬのと同じ
理屈であろう。その代わり
建築家以外の文明人は
鉋の持ちようさえも知らず、
速やかに小家を
建てる
手際においては遠く
普通の
野蛮人にかなわぬごとく、
神経を
備えた動物の
神経以外の
組織は、「アメーバ」や「ぞうりむし」等のごとく
刺激に
応じて
適当に身を
処することはとうていできぬ。
植物の全部と動物中の
最下等のものとには
特に
神経と名づくべきものはないが、それ
以上の
普通の動物には
必ず身体の内に、
特に外界からの
刺激に感じ、これを他の体部へ
伝達する力を
備えた
組織がある。この
組織は「ヒドラ」、「さんご」等のごとき下等の動物では、くもの
巣のごとくに
薄く全身に広がっているにすぎぬが、それより
以上の動物になると、しだいに明らかになって白い糸のごとき形に
現われ、さらにその中に
幹部とも名づくべき部分を
区別し
得るようになる。
幹部というのは、人間でいえばすなわち
脳や
脊髄のことで、これと身体の
各部とを
連絡する細い糸がいわゆる
神経である。それゆえ、
神経なるものはやや高等の動物では
一端は
必ず
幹部に
連なり、
他端は身体のいずれかの部分に終わっている。外界に
変化が起これば、まず身体の外面にある
眼、耳、鼻、口、
皮膚等が
刺激を受け、
神経はこれを
幹部に
伝達する。次に
幹部はさらに
別の
神経を通じて
或る
筋肉に
刺激を
伝え、
筋肉が
収縮して身体を
適宜に運動させる。かくのごとく、
普通の動物が外界の
変化に
応じて
適宜に身を
処してゆくには、外界からの
刺激を受けつけるための
感覚器官と、これを
処理判断するための
神経系幹部と、
幹部よりの
命令に
従うて
収縮し運動するための
筋肉とを
要するが、これらのものを
互いに
連絡するのは
神経である。されば
神経はあたかも
電信の
針金のようなもので、
眼、耳ないし
皮膚の内にある
発信器と、
幹部内の
受信器との間、もしくは
幹部内の
発信器と
筋肉や
腺の内にある
受信器との間に
張られてあることにあたる。また
神経系の
発達せぬ動物はあたかもいまだ
電信のない
未開国のようなもので、
各部の間の
通信にはあるいは
烽火をあげ、あるいは
旗を
振り、または
飛脚を走らせ、
駕籠を
飛ばせなどして、それ
相応に間に合わせているのに
比較することができよう。
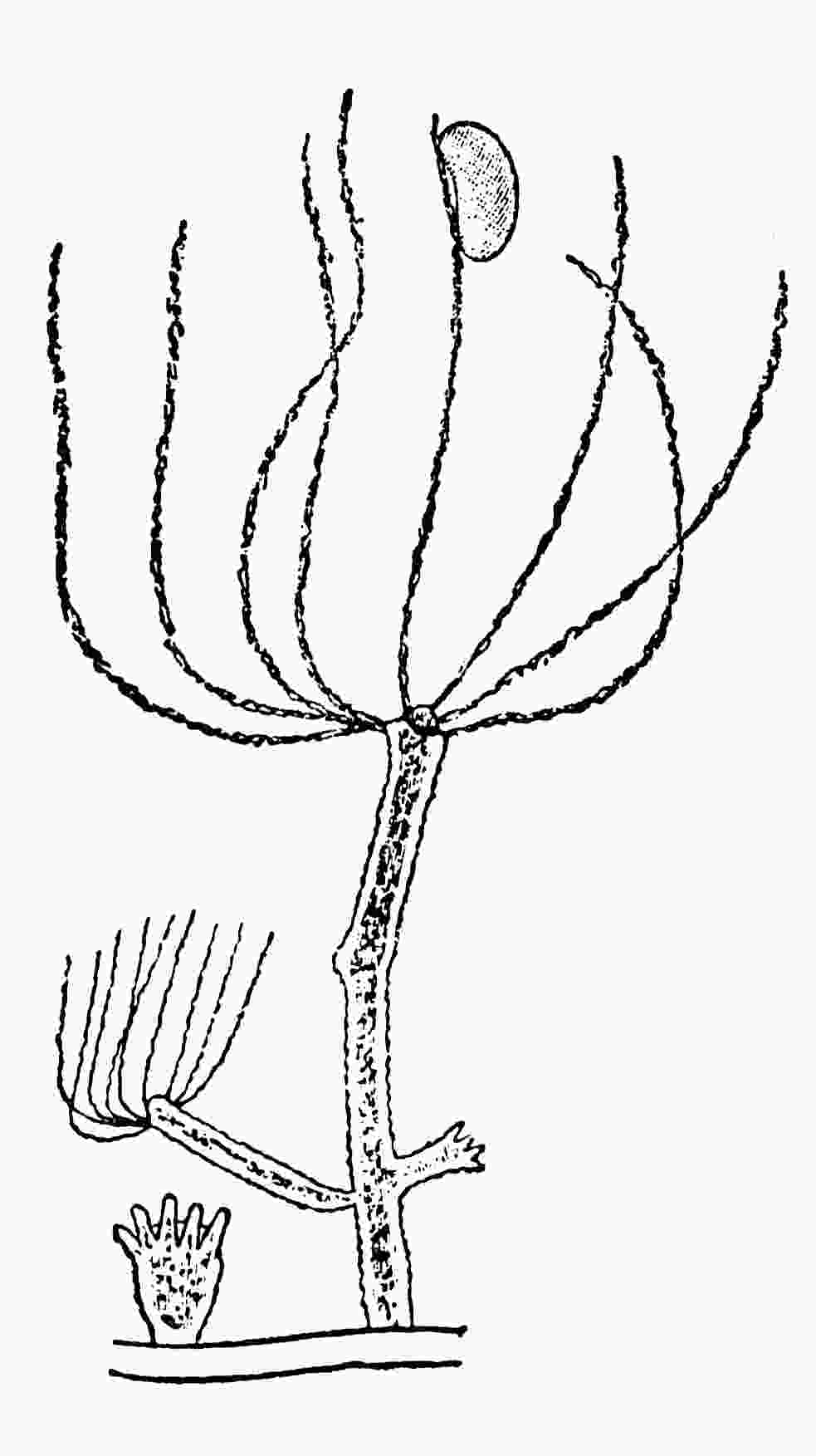 ヒドラ
ヒドラ
前に名をあげた「ヒドラ」という動物は体の
構造が
極めて
簡単で、あたかも
湯呑コップ、または
底のある竹の
筒のごとき形を
呈し、口の
周囲から生えている数本の糸のような指で食物を
捕えて食うが、
別に
肛門というものがないゆえ、
不消化物はまた口から
吐き出してしまう。
沼や池の水草に
付着している
普通の
淡水産動物で、つねに「みじんこ」などを食うているゆえ、
採集も
飼育も
極めてたやすい。
二またの
針で口のところを
押さえながら、細いガラス
棒で
尻のほうから
突くと、あたかも
嚢を
裏返すごとくに「ヒドラ」の
柔らかい身体を
裏返すことができるが、かくすると、この動物の外界に対する内外の
位置が
'顛倒するから、
宇宙が「ヒドラ」の
腹の内にはいったともいえる。
著者は
幼年のころ「ヒドラ」に
宇宙をのませてやるというて、しばしばこれを
裏返して遊んだが、かくしてもそのまま
置けば
自然にもとに
復して、また平気で「みじんこ」などを食うている。かような
簡単な動物であるから、その
神経系のごときも
極めて
憐れなもので、わずかに少数の
神経細胞が、身体の
諸部に
散在しているにすぎぬ。「さんご」、「いそぎんちゃく」のごとき
海産動物も
神経系の
発達の
程度はほぼこれと同じである。ただしくらげ
類になると、つねに
浮游しているから、
眼、耳のはじめともいうべき
簡単な
感覚器も
備わり、
神経組織もいくぶんか
発達して、
傘の
周辺に
沿うて細い
輪の形に
現われている。
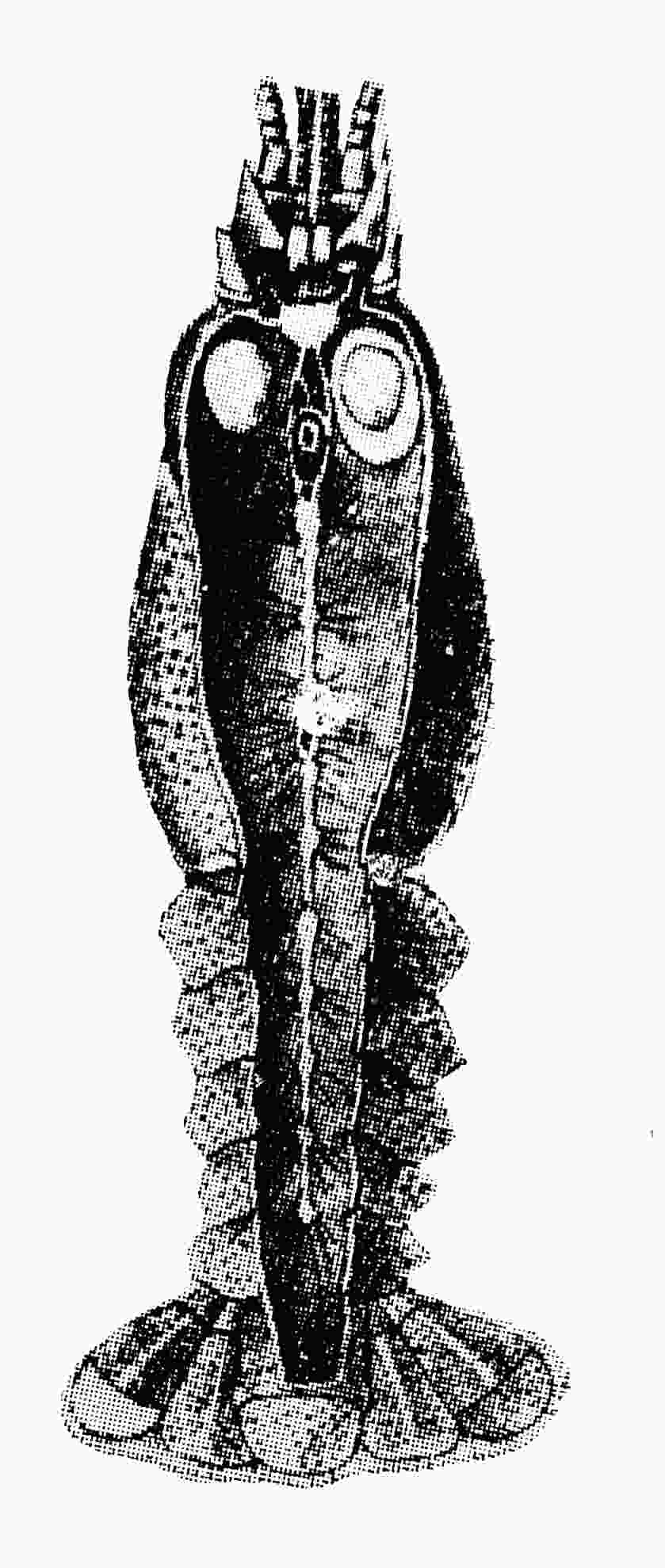 えびの神経
神経系
えびの神経
神経系の
幹部の
形状は動物の
種類によって根本から
違うものがあるから、すべてを一列に
並べて、これを高等、かれを下等と
断定するわけにはゆかぬ。だれも知っているような
普通の動物だけについていうても、
相異なる
型が三つはたしかにある。すなわち一つは「えび」、
蟹、
昆虫類などのもの、一つは「たこ」、「いか」、
貝類などのもの、一つは
獣類、
鳥類より
魚類までを
含む
脊椎動物のものであるが、そのうち、「えび」、
蟹、
昆虫等では身体が多くの
節からなっているとおり、
神経系の
幹部も
各節に一つずつあって、これが
神経によってあたかも
鎖のごとくに前後
互いに
連なっている。また「たこ」、「いか」などは身体に
節がないごとく、
神経系の
幹部のほうも
一塊となって、食道を取り
巻いている。これなどはいずれも人間の
脳、
脊髄などとは根本から仕組みが
違うゆえ、形の上からは
相くらべて
論ずることはできぬ。
次に
脊椎動物を見ると、これにももっとも
簡単なものからもっとも
発達したものまでさまざまの
階段がある。この
類では
必ず身体の
中軸に一本の
脊骨があって、その
背側に
神経系の
幹部がとおっているが、もっとも下等の
脊椎動物になると、これに
脳、
脊髄という
区別がない。
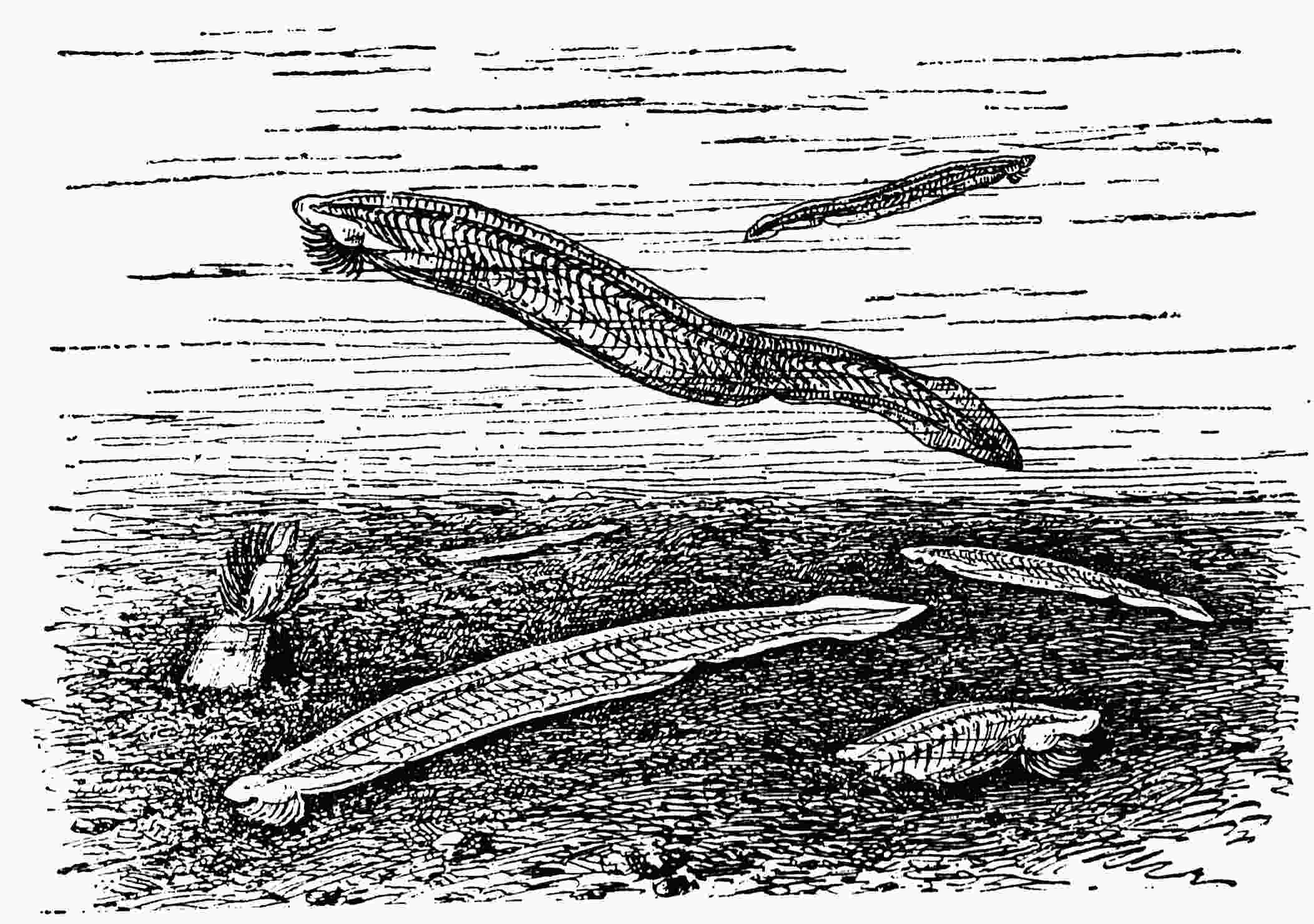 なめくじ魚
例
なめくじ魚
例えば
浅い海の
底の
砂の中にいる「なめくじ魚」の
類では、身体の
中軸の
背側に長い
紐の形の
神経系の
幹部はあるが、全部
脊髄のごとくで、
特に
脳と名づくべき太い部分が見当たらぬ。元来
脳なるものは
脊髄のつづきで、ただその
前端のいちじるしく
発達した部分にすぎぬゆえ、
脳がなければ、
神経系の
幹部は全く
脊髄のみから
成っているごとくに見える。
脳があれば、これを
包み
保護するための
頭骨も
要るが、「なめくじ魚」のごとき
脳のない動物ではむろん
頭骨も
発達せぬから、身体の
前端に
特に頭と名づくべき部分がない。それゆえ、動物学上では、この
類を
無頭類と名づける。かように
脳はないが、この動物の生きているところを見ると、なかなか運動も活発で、
特に
速やかに
砂の中へもぐり
込むことなどはすこぶる
巧みである。さればこの動物の
神経系の
幹部は、
簡単ながらもこの動物の
日常の生活に対して、用が足りるだけの
程度には
発達しているものと考えねばならぬ。
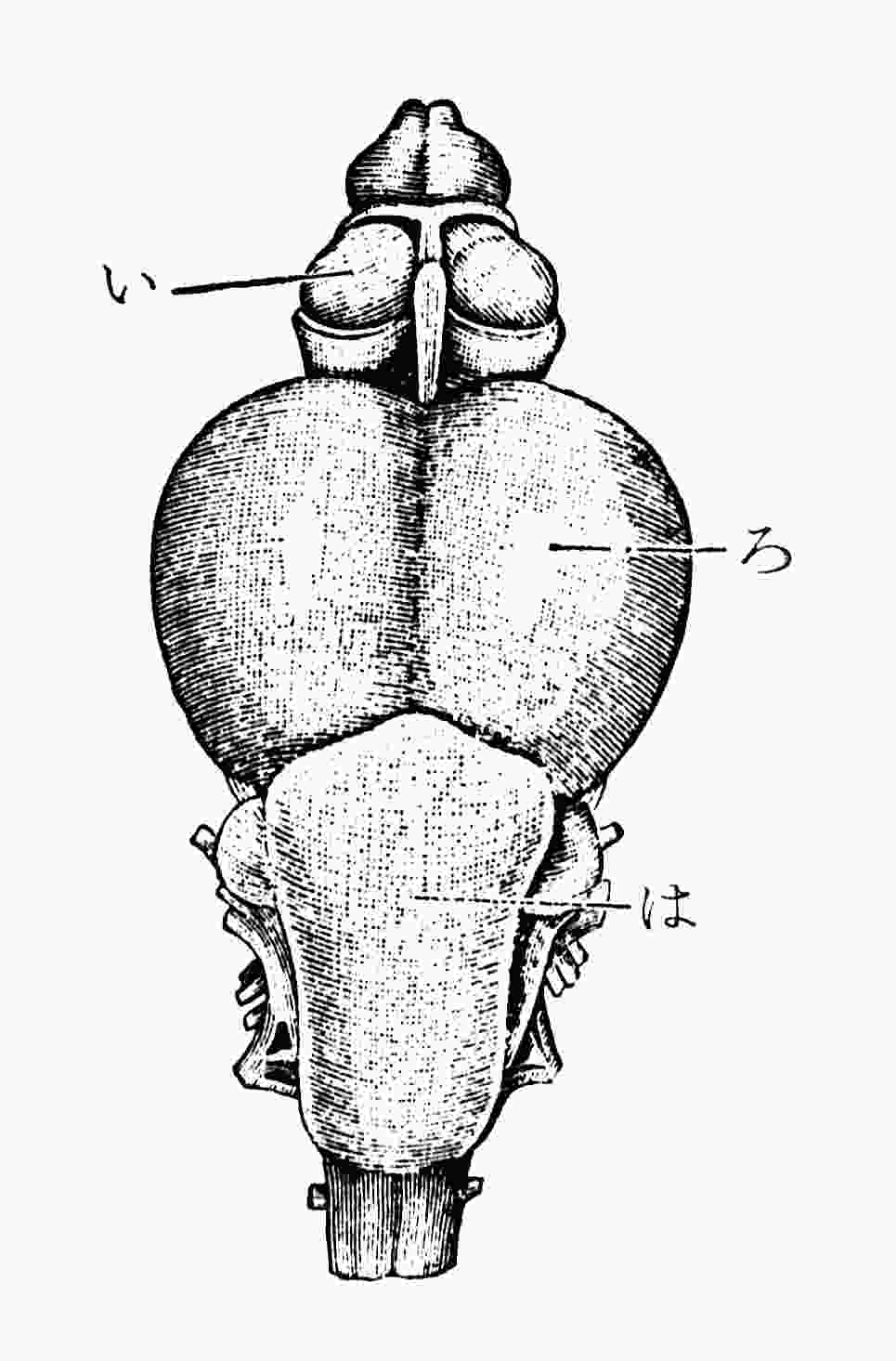
魚の脳
(い)大脳 (ろ)視神経葉 (は)小脳
普通の
魚類では
脊髄の
前端につづいて明らかな
脳があるが、これを人間の
脳などにくらべると、その
形状がよほど
違う。人間の
脳ならば、
脳の大部分をなすものはいわゆる
大脳であって、
小脳はただその
後端の下面に
隠れているにすぎぬが、
魚類の
脳では
大脳ははなはだ小さくて、
脳の
前端の
付属物のごとくに見え、
小脳のほうが、はるかにこれよりも大きくて、
脳の後部の大半をなしている。しこうして
脳の中央部にあって、あたかも
大脳のごとくに見える左右一対の
大塊は何であるかというに、これは
視神経葉もしくは
中脳と名づけるもので、人間の
脳では、
大脳と
小脳との間の
割れ目を開いてのぞかなければ見えぬほどの小さな
隠れた部分である。かようなしだいで、魚の
脳にも人間の
脳にも、同じだけの部分が
備わってはあるが、
各部の
発達の
程度に
非常な
相違があって、人間で大きな
大脳は
魚類ではすこぶる小さく、人間で小さな
中脳は
魚類でははなはだ大きい。もっとも
脳全体の
重量が人間では体重の四十分の一もあるに反し、「まぐろ」などではわずかに三万分の一にも当たらぬから、
実際の大きさをいえば、
魚類の
中脳はけっして人間よりも大きなわけではなく、ただ他の
脳部に
比して大きいというまでである。
実験観察によると、
大脳は
知情意等のいわゆる
精神的作用をつかさどり、
小脳は全身の運動の調和を図るというように、
脳の
各部分には、それぞれ
分担の役目が
違うから、
各部の大きさのいちじるしく
違う動物では、その作用にも
種々の
相違のあるべきは言うをまたぬ。
蛙の
類では
大脳がやや大きいが、やはり
大脳と
視神経葉と
小脳とが前後に一列に
並んでいる。
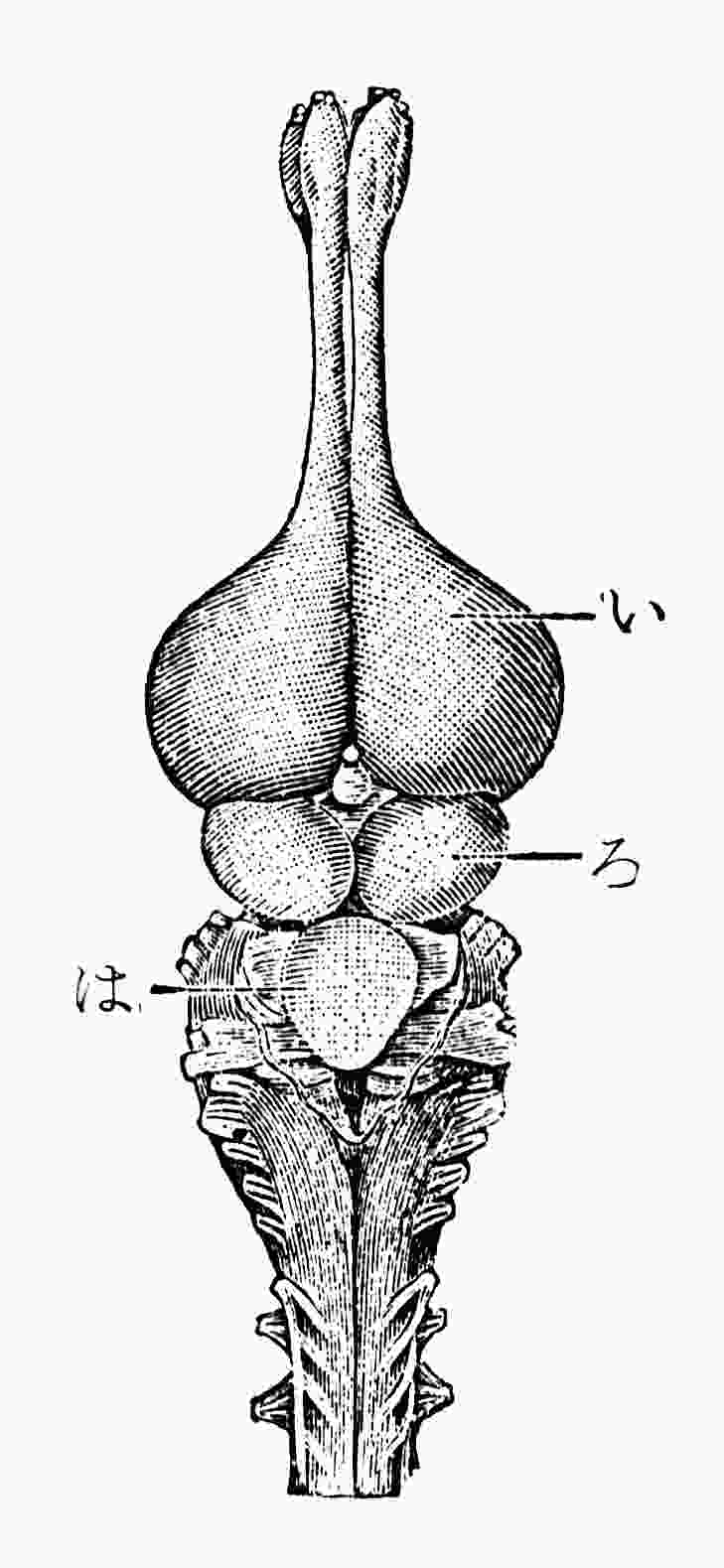
鰐の脳
(い)大脳 (ろ)視神経葉 (は)小脳
図に
示した
鰐の
脳は、
蛙の
脳に
比してただ
大脳が少しく大きいだけである。
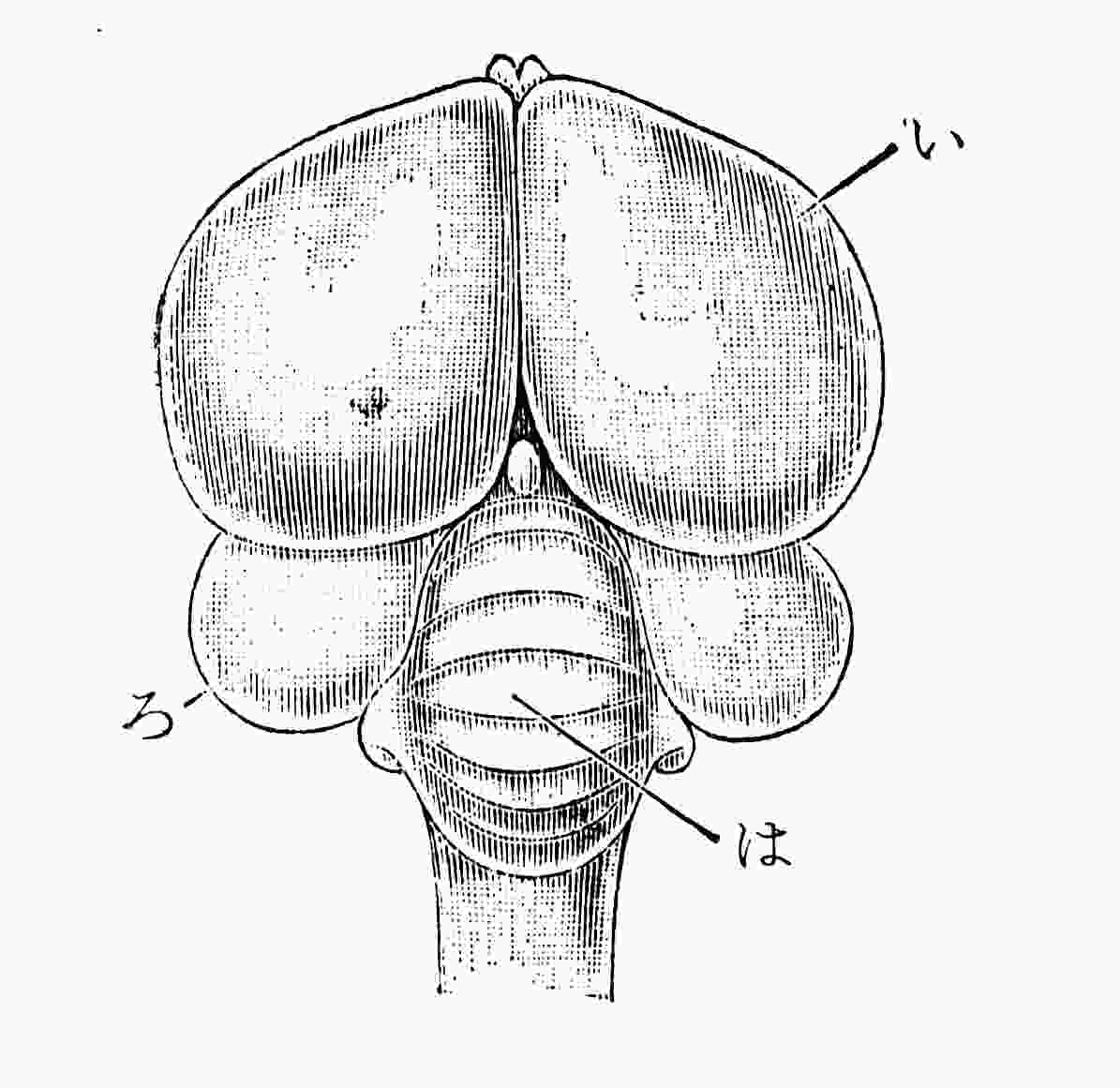
鳥の脳
(い)大脳 (ろ)視神経葉 (は)小脳
また
鳥類では、
大脳がさらに大きく、その
後縁は
小脳と
相接し、そのため
視神経葉は左右へ
圧し出され、
脳の
側面に丸くはみ出している。
獣類の
脳はすべての動物の中でもっとも大きく、かつだいたいにおいては全く人間の
脳と
構造が
一致している。ただ
大脳の
発達の
程度には
種々の
階段があって、その
低いものでは
大脳の表面が
平滑で少しも
凸凹がないが、その高いものほど表面が広くなり、それがために
大脳の表面には回転、
裂溝などと名づける雲形の
複雑な
凸凹が生じて、ついに人間に見るような形のものとなる。
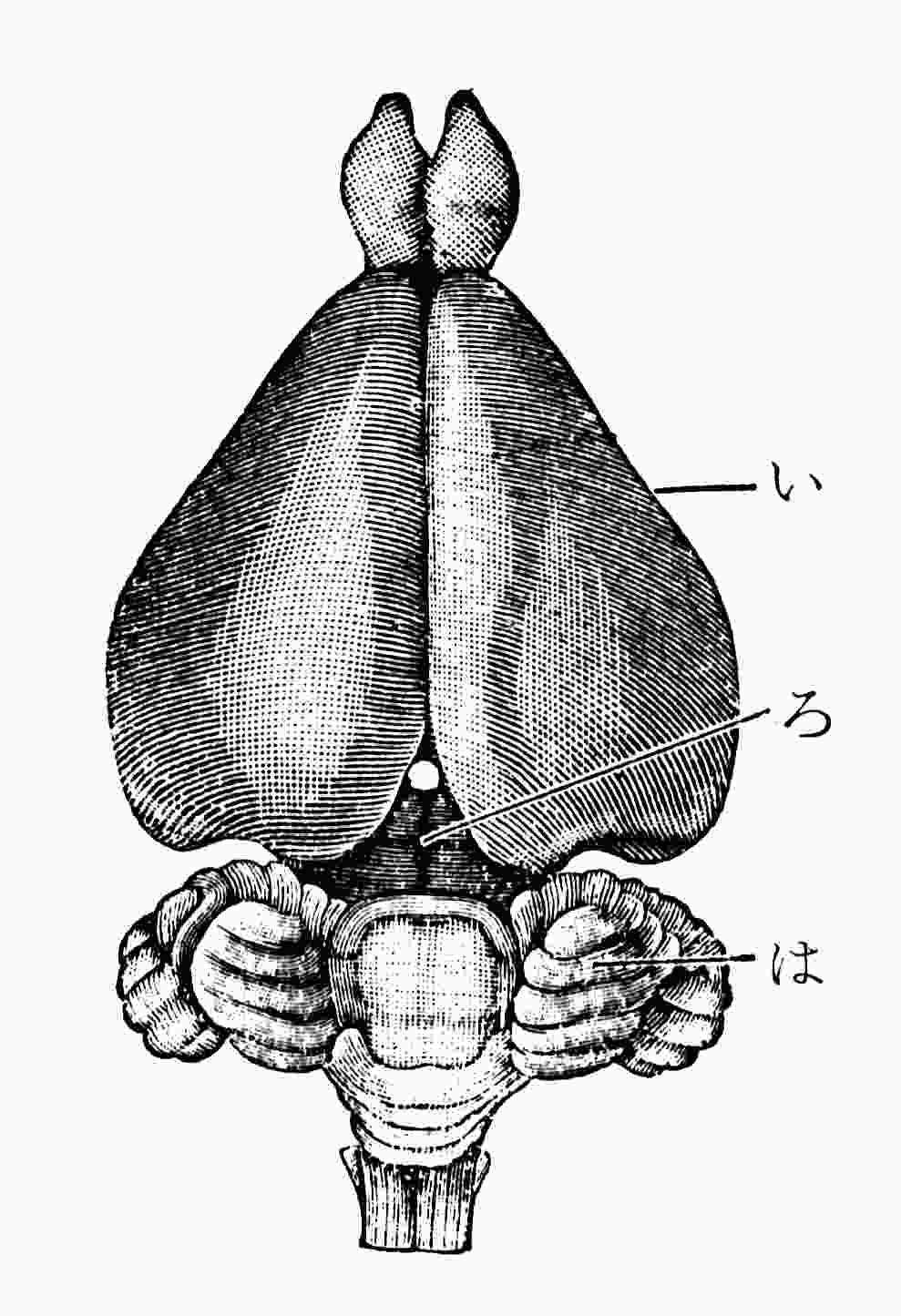
兎の脳
(い)大脳 (ろ)視神経葉 (は)小脳
二三の
例をあげて見れば、
兎や
鼠などでは
大脳の表面はほとんど
平滑で、回転も
裂溝もないが、馬でも
鹿でも
大脳の表面には
若干の
溝があってやや
複雑に見える。
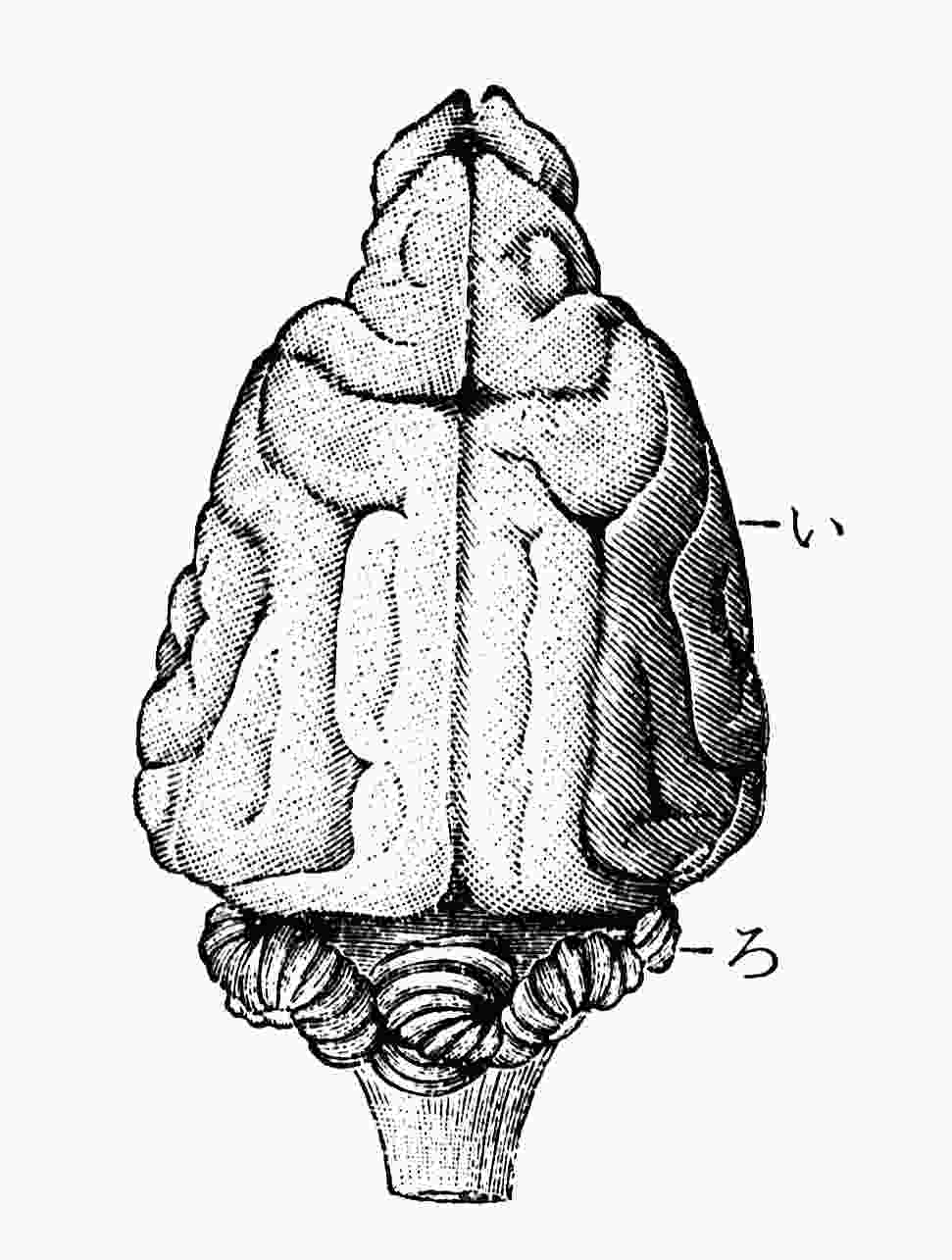
犬の脳
(い)大脳 (ろ)小脳
犬ではさらに回転が多く、
猿の
類ではよほど人間の
大脳に
似てくる。
特に
猿の中でも
猩々などのような大形の
種類では、
大脳の表面にある回転、
裂溝の
配置が、だいたいにおいては人間のとよく
似ていて、いちいちの部分を
互いに
比較することができる。近来
大脳の
働きを
実験的に研究するには、生きた動物の
頭骨を切り開いて
脳を
露出せしめ、その表面の
各部を弱い電気で
刺激して、その動物の
知覚と運動とに
如何なる
結果が
現われるかを調べるが、
欧米の学者が
競うて
猩々の
類をその
材料に使いたがるのは、全くその
脳が人間の
脳によく
似ていて、研究の
結果を直ちに人間に当てはめることができるからである。
以上述べたとおり
神経系の
幹部の
形状や、その
発達の
程度は、動物の
種類によって大いに
違うが、もし同じ
構造を有するものは作用も
相同じと
仮定すれば、
魚類より人間までを
含む
脊椎動物の
脳、
脊髄の
働きは、
性質はたいてい
相同じで、ただその
程度に
相違があるものと考えねばならず、また
蟹、「えび」や「たこ」、「いか」などでは
神経系の
幹部の
形状が根本から
違うが、これは同じ
目的を
達するために、
相異なる形式をとったと見なすべきもので、あたかも同じく空を
飛ぶ
機械に、
飛行船もあれば
飛行機もあり、また
飛行船の中にもガス
嚢に
硬い
骨のあるものもあればないものもあり、
飛行機の中にも
単葉もあれば
複葉もあり、なお
別に
工夫すれば
子供の
玩具の竹のとんぼと同じ
理屈を
応用した
航空機もできるのと同じことであろう。しこうしてその
目的とするところはいずれも、外界の
変化に
応じて
適宜に身を
処するということであって、その
働きの
程度は
各種の動物の
現在の生活
状態に
従うて、それぞれ間に合うぐらいのところを
限りとしているのである
外界の
変化に
応じて
適宜に身を
処することは、もとより
如何なる生物にも
必要なことで、この
働きのない生物はとうてい生活する
資格がないが、
神経系のない生物は全身をもってこの事を行ない、
神経系のある生物では主として
神経系がその
衝に当たり、
神経系に明らかな
幹部の
備わってある動物では、主として
幹部がこれをつかさどることになっている。ただし
神経系の
発達には
無数の
階段があって、一歩一歩進み来たったものゆえ、
神経系のあるものとないものとの間にも、
神経系に明らかな
幹部のあるものとないものとの間にも、けっして
判然たる
区別はないから、
以上の
働きがいずれの部分で行なわれるか、
確かと
断言のできぬ場合もむろんあるべきはずである。
さて食われぬために外界の
事情に
応じて
適宜に身を
処する
働きには、また
種々の行ない方がある。
例えば人間について見ても、
眠っている人の足の先へ火のついた
線香を持って行くと、たちまち足を引き
込めるが、
覚めた後にたずねて見ると何も知らぬ。また
眼の前へ急にとがった刀の先を
突きつけると直ちに
眼を
閉じるが、これもけっして刀は
危険であるから
眼瞼を
閉じて内なる
眼球を
保護せずばなるまいと考えた
結果行なうことでなく、刀の先が見えたと思うころには、
眼瞼はすでにひとりで
閉じている。かくのごとく外界から
刺激が来たときに、全く知らずにもしくは知って考えるひまもなしに、直ちにこれに
応じた運動をするのを
反射作用と名づける。また生まれたばかりの赤ん
坊の口に
乳首を入れると、直ちに
吸うてのむが、これはだれに教えられたのでもなく、自分で習うたのでもなく、生まれながら
自然にこの
能力を
備えているのである。かように
自然に持って生まれた
能力によって、よく外界の
事情に
応じた
働きをなし
得ることを
本能と名づける。またかくすればかくなるべきはずと考え、
目的に
相応した
手段を
工夫して、自身でよく
承知しながら行なうことはみな知力の
働きで、人間が日々
骨を
折ってわざわざ行なう仕事の大部分はこの
類に
属する。生物の
行為を
観察すると、その多くは
以上の
三種類の
型の中のいずれかに相当するが、その間の
区別はけっして
判然たるものではなく、いずれに
属せしめてよろしいかわからぬ場合もすこぶる多い。
特に
反射作用と
本能との間にはほとんど
区別がつけられぬ。
例えば赤子の口に
乳首を入れてやれば直ちに
吸いつくのは、持って生まれた
本能によるが、その
働きはやはり
一種の
反射作用である。
畢竟反射作用とか、
本能とか、知力とかいう言葉は、人知の進むに
従い
必要に
応じて、一つずつつくったもので、それぞれ
若干のいちじるしい行動に
冠らせた
名称にすぎぬ。
まず
反射作用について考えて見るに、これにも
簡単なものから
複雑なものまで
種々の
程度があるが、わざわざ
自然と
異なった
状態においてためして見る場合のほかは、すべて自身の安全を図るに
必要な
働きをするように思われる。医者が
脚気の
患者を
診察するとき、
膝の下を手で軽く打って
脚がはねるか
否かを
試みるが、これなどは
反射作用のもっとも
簡単な
例で、
健康な人ならば
膝の下の
腱に
刺激を受けると、直ちに
腿の前面の
筋肉が
収縮してわれ知らず
脚部が動くのである。しかし
普通の人間が
普通の生活をしているときには、
膝の下の
腱に医者が手で打つのと同じような
刺激を受けるという
機会はほとんどないであろうから、これに
応じて
脚部をはね上げる
反射作用の
働きがあっても何の役にも立たぬ。これに反してなお少しく
複雑な
反射作用になると、みな何らか生活上の
効用がある。
例えば鼻の
孔に
紙撚を入れて内面の
粘膜を
刺激すると、
反射作用で直ちに
嚏が出るが、これなどは鼻の中に
異物のはいり来たった場合にこれを
除き去るために
必要である。
子供の鼻の
孔が
詰まって空気の流通が悪くなると、注意が
散漫になり、学業の
成績もしだいに下落するとさえ言われるから、鼻の内を
掃除するための
反射作用は生活上ずいぶん大切なものであろう。また急いで食するとき
飯粒が
気管のほうへでもはいると、
喉頭の内面の
粘膜を
刺激するため、
反射作用で直ちに
咳をするが、その
結果として
喉頭内の
異物は口から
吐き出される。
肺病患者がつねに
咳をするのも、
肺の
組織がだんだん
壊れて
粘液となり、
喉頭まで出て来て
絶えずこれを
刺激するからであるが、
咳は気道を
掃除する
働きとして生活上
必要なものである。強い光に
遇えば
眼の
瞳が小さくなり、暗いところへ行けば
瞳が大きくなって、
適当量の光線を
眼球内へ入れるのも
時機にかのうた
反射作用であるが、生活上さらに大切な
反射作用はすなわち
呼吸の運動である。
呼吸は
或る
程度までは
故意に
加減することができるが、
平常はほかの事をなしながら知らずに
呼吸している。しこうして、その行なわれるのは、
肺内にたまる
炭酸ガスが
肺の内面を
刺激して、
反射作用で
肋間筋や
横隔膜を
収縮せしめる
結果である。
睡眠中も
絶えず
呼吸の行なわれるのはそのためである。されば、もしこの
反射作用がなかったならば、人間はもとより他の多くの高等動物も一日も生活はできぬ。
実験研究の
結果によると、物を知る
働きは
大脳のつかさどるところのごとくに思われるが、もし
大脳に
限るとすれば、
大脳を切り去った動物は物を知る力がないはずであるゆえ、そのなすことはみな
反射作用によると見なさねばならぬ。ところが
蛙などでためして見ると、
大脳を切り去っても、なかなか
複雑な
働きをする力が
残っている。生理の
実験としてどこの学校でもよくやることであるが、
大脳部を切り去った
蛙を平らな板に
載せておくと、
行儀よく
坐っていつまでも動かずにいるが、少しずつ板を
斜めにすると、
平均を
失わぬように体の
姿勢を少しずつ
変じ、板がいちじるしく
斜めになって、
滑り落ちる
危険が生ずると、
徐々とはい出して上方に進み、板の
縁まで行って、安全に
坐れるところで止まる。また
大脳部を切り去った
蛙の
皮膚の一点に
薄い
酸類を
塗って見ると、直ちに手足をそのところえ向け、曲げたり
延ばしたり、
種々に
工夫して、これを
拭い去ろうと
努める。これらの
挙動は、いずれもよく
目的にかのうたことで、もし人間がこれをなしたならば、見る者は
必ず
意志により知力を
働かせてなしているものと見なすに
違いない。かくのごとく
反射作用はその
複雑なものになると、ほとんど知力を用いてなす運動と同じ
程度のことができるが、これらはおそらくみなその動物の生活中に、
敵に食われぬためか、
餌を食うためか、子を
産むためか、子を育てるためか、何かの
際に
直接もしくは
間接に役に立つことで、かつその動物の生活にとって
必要な
程度までに
発達しているのであろう。
動物の中には、人間が知力によってなすこととよく
似たことを、生まれながら
自然になし
得るものがあるが、
本能とは始めかような場合に当てはめて用いた言葉である。
例えば、
蜜蜂がその
巣に
規則正しい六角形の部屋をつくること、「かいこ」が
蛹になる前に
丈夫な
繭をつくつってその内に
隠れること、くもが
巧みに
網を
張って
昆虫を
捕えること、
蟻地獄が
摺鉢状の
穴を
掘って
蟻をおとしいれることなどは、いずれもその動物にとっては大切なことであるが、一つとして他から習うて行なうのではなく、生まれたままで、なんらの
経験もなく、なんらの練習もせずに、直ちに着手してしかも
間違いなく
成功する。これが
如何にも
不可思議に見えるので、人間の知力などと
区別して、この
働きを
本能と名づけた。
特に昔は何とかして人間と他の動物との
相隔たる
距離をなるべく大きくしたいとの考えから、人間には知力があるが動物にはけっして知力はない。動物は
如何に
巧みに
目的にかのうた
挙動をしても、これは
本能によるのであってけっして人間のごとくに
知恵を
働かせた
結果ではないと、
説いた学者が多かった。かようなしだいで昔は
本能の
範囲を
極めて広くし、動物のなすことならば何でも
本能によると見なしたが、近来はまた
本能の意味を
非常にせまくして、その大部分を
反射作用の中に入れる人もある。
本能という言葉の
定義については今日なお
議論の
最中であるが、ここにはめんどうな
論を
省いて
仮に
経験にもよらず、知力をも用いずして、生活の
目的にかのうた
行為を
自発的になすことを
本能と名づけ、そのいちじるしい
例をいくつかかかげるだけとする。
植物の
種から
芽の出るとき、
茎になるべきほうは
必ず上に向かいて
延び、根になるべきほうは
必ず下へ向かいて
延び、
如何に
位置を
転倒しておいても、その後に生長する部は
必ずこの方角に向く。もし植物にこの
性質がなかったならば、
種子から
芽生えの生ずるとき、根が空中に向かい、葉が地中にはいり
込んで、生活のできぬこともしばしばあろうから、この
性質は植物の生活にとっては
極めて大切なものであるが、これなども、
経験にもよらず、知力をも用いずしてなすことゆえ、やはり
一種の
本能と見なして
差し
支えがなかろう。
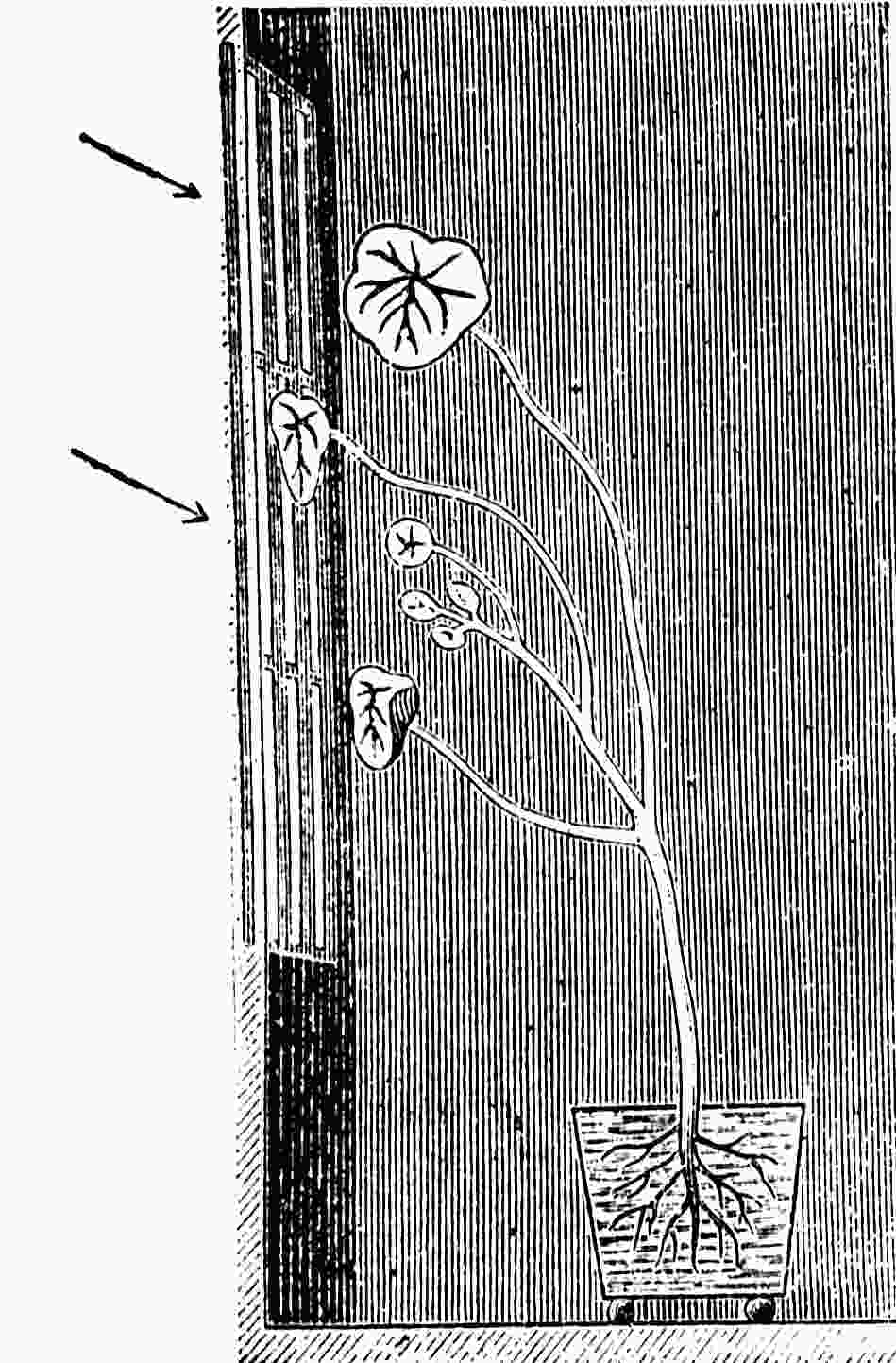 植物の向日性
植物の向日性
また
芽生えの植物に箱をかぶせて光をさえぎり、ただ一方にのみ
窓を開けておくと、
茎は光の来る方角に向かいそろうて
斜めに
延びる。これは植物の生活に
欠くべからざる日光をできるだけ十分に受けるに
必要な
本能であるが、日光という
刺激に
遇うてこれに
応ずる運動をするのであるから、
一種の
反射作用とも言うことができる。その他植物の葉がなるべく日に当たるような
位置に向くことも、根が
湿気の多いほうへ
延びることもみな
本能であってかつ
反射作用でもある。
動物が
餌を
捕え食うためにさまざまの
手段を用いることは、前に
若干の
例をあげて
述べたが、その中の多くは
本能による
働きである。くもが
網を
張るのも、
蟻地獄が
穴をつくるのも、みな生まれながらにその
能力を
備えているので、どこに
置いても
独力で
巧みに
餌をとる
装置をつくり上げる。これは人間にたとえていえば、あたかも工業学校を
卒業しただけの学力を、赤子が生まれながら持っているわけに当たるゆえ、人間からは
如何にも
不思議に思われるが、広く動物界を
見渡すとかような
例はいくらでもある。
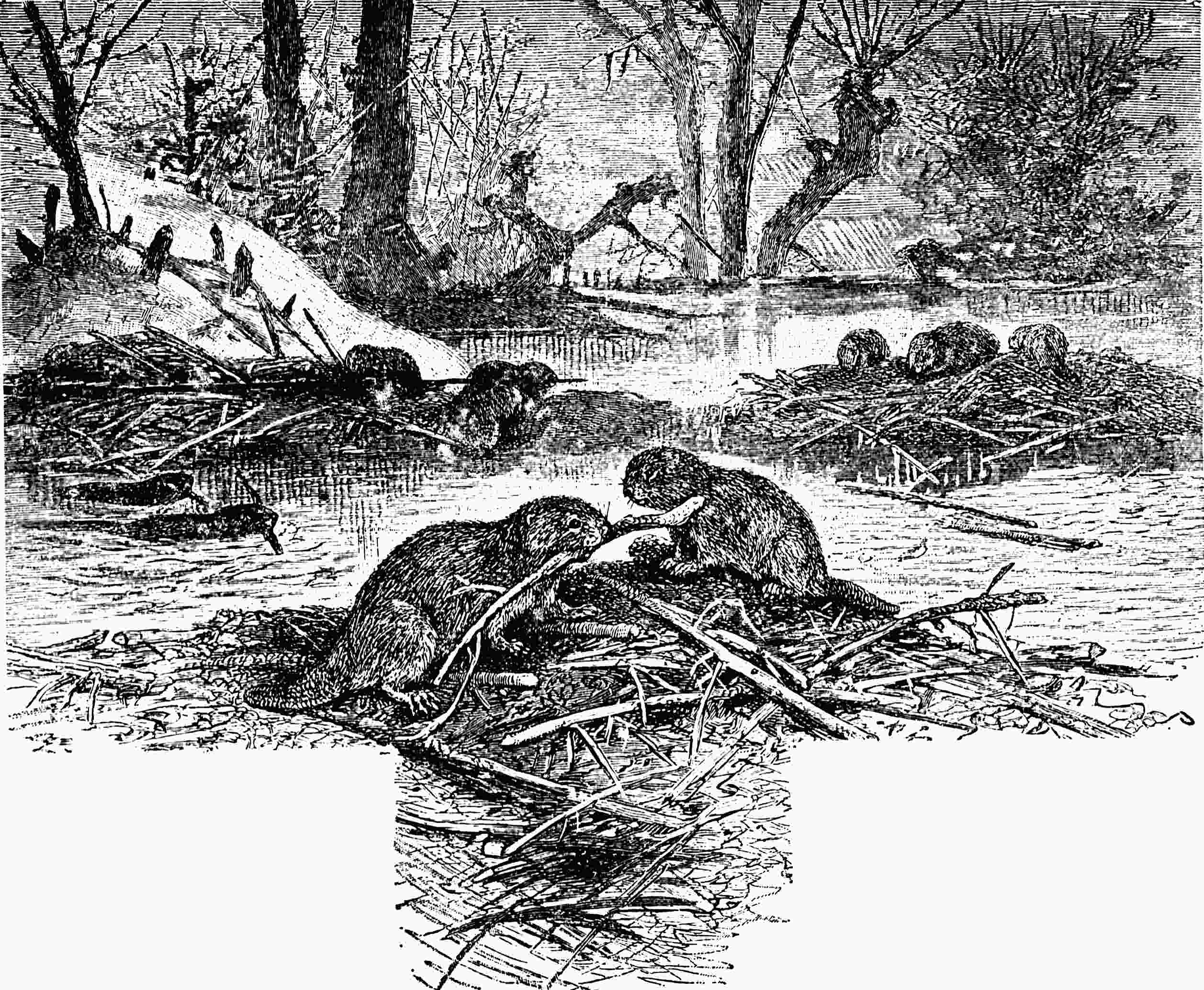 海狸
獣類
海狸
獣類の中でも北アメリカの
河に
棲む
海狸(注:ビーバー)などは
大規模の土木工事を起こすので名高いが、これをなすには、まず多数の
海狸が立木の
幹を前歯でかじって
倒し、長さ
三尺(注:90cm)ないし
一間(注:1.8m)ぐらいの手ごろな
材木を
幾つとなくつくる。次にこれを用いて森の間を流れる
河をせき止めるのであるが、そのためにはこの
材木を
河底に
縦に
埋め
込み、
別に
枝をもってその間をつなぎ、
葭の
類で
空隙を
閉じ、
泥を
塗って
堤防をつくり終わる。でき上がった
堤は長さが二丁(注:218m)もあり、高さは一間(注:1.8m)あまり、
幅は二三間(注:3.6~5.4m)もあるから、
獣類の仕事としてはずいぶん
驚くべき大きなものである。この
堤防のために、
河の水はせき止められ広い
湖水のごときところができるが、
海狸の住家としてはこれがもっとも
都合がよろしい。
海狸は足に
蹼を
備えた
水獣で、
敵に
遇えば直ちに水中に
逃げ
込み、
泥で
巣をつくるに当たっても、一方は水中へ
逃げ出せるように道がつけてあるくらいゆえ、
浅い水が広い
面積のところに広がっているのは生活に
便利である。
海狸が多数力をあわせて
堤防をつくるのは、すなわち自分らの生活に
都合のよろしい場所をつくるためであるが、これらは動物の
本能の中でもずいぶんいちじるしいほうであろう。
海狸は動物園に
飼うてあるものでも、
材木を
与えるとこれをかんで手ごろの大きさとし、
堤防用として
幾つもそろえるところを見ると、この動物の
神経系は、
現在の
境遇の
如何にかかわらず、
先祖代々の
因襲に
従うて、
働くものと思われる。
蝶蛾類の
蛹時代は、
芋虫、毛虫などの
幼虫から、大きな
翅を
備えた
成虫に形の
変わる
過渡時代で、外面からは実に
不活発に見えるが、内部は
極めて
忙しい。しかも運動のできぬ時期であって、
敵に
襲われた場合に
逃げも
隠れもせられぬから、多くの
蝶蛾類ではまえもって
繭をつくって、あらかじめ自身を
護る
工夫をする。「かいこ」の
繭は
単に
俵のごとき形であるが、他の
種類の
繭にはずいぶん、形の
変わったおもしろいものも少なくない。
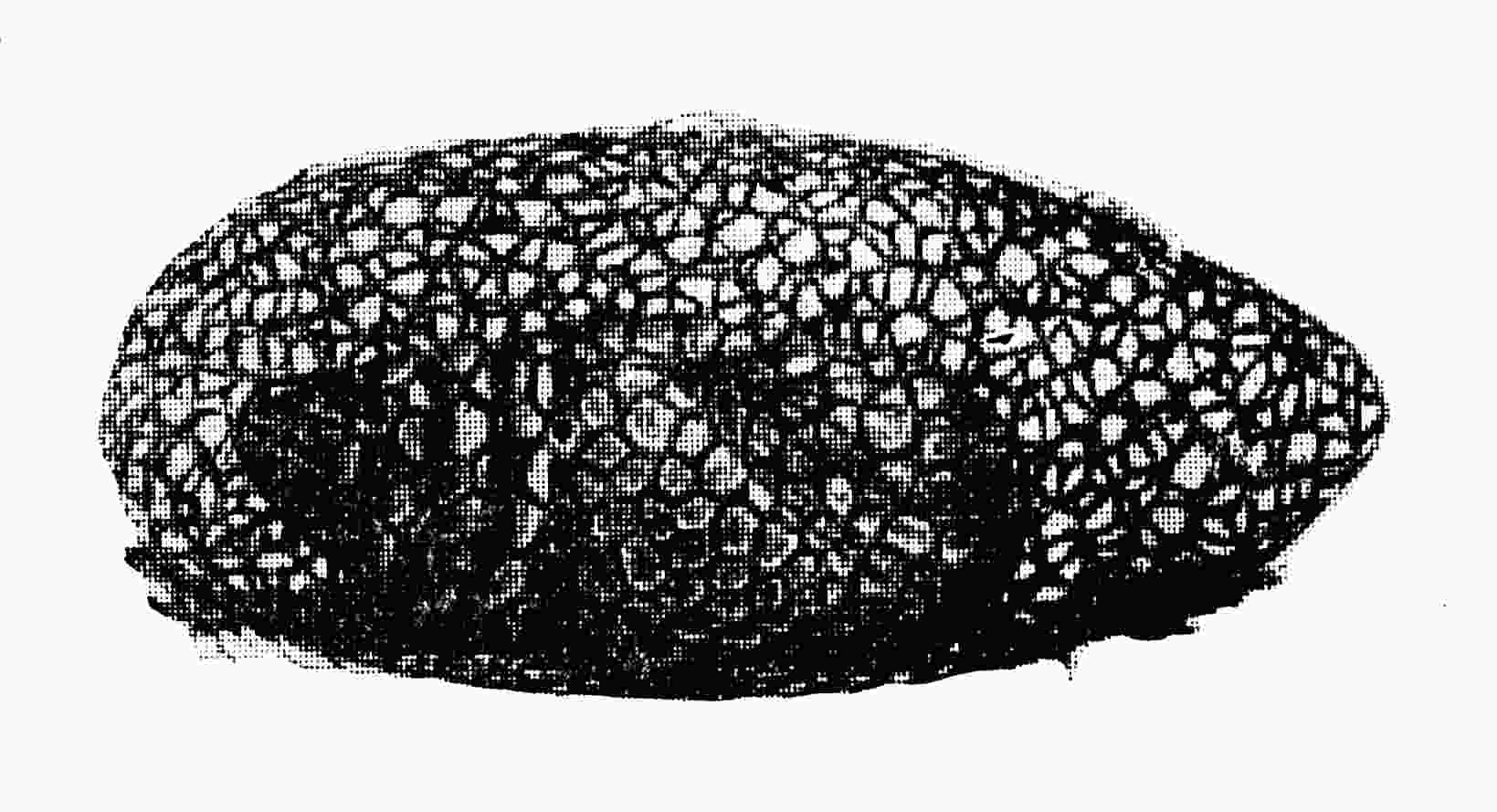 すかし俵
栗虫
すかし俵
栗虫の
幼虫には白色の長い毛が一面にはえているので、一名を
白髪太郎というが、これが
蛹になる時には、内部のよく見える
網状の
繭をつくる。
俗に「すかし
俵」と
呼ぶのはこれであるが、空気の流通を
妨げずして、しかもたいていの
敵を
防ぎ
得るようにすこぶる
巧みにできている。
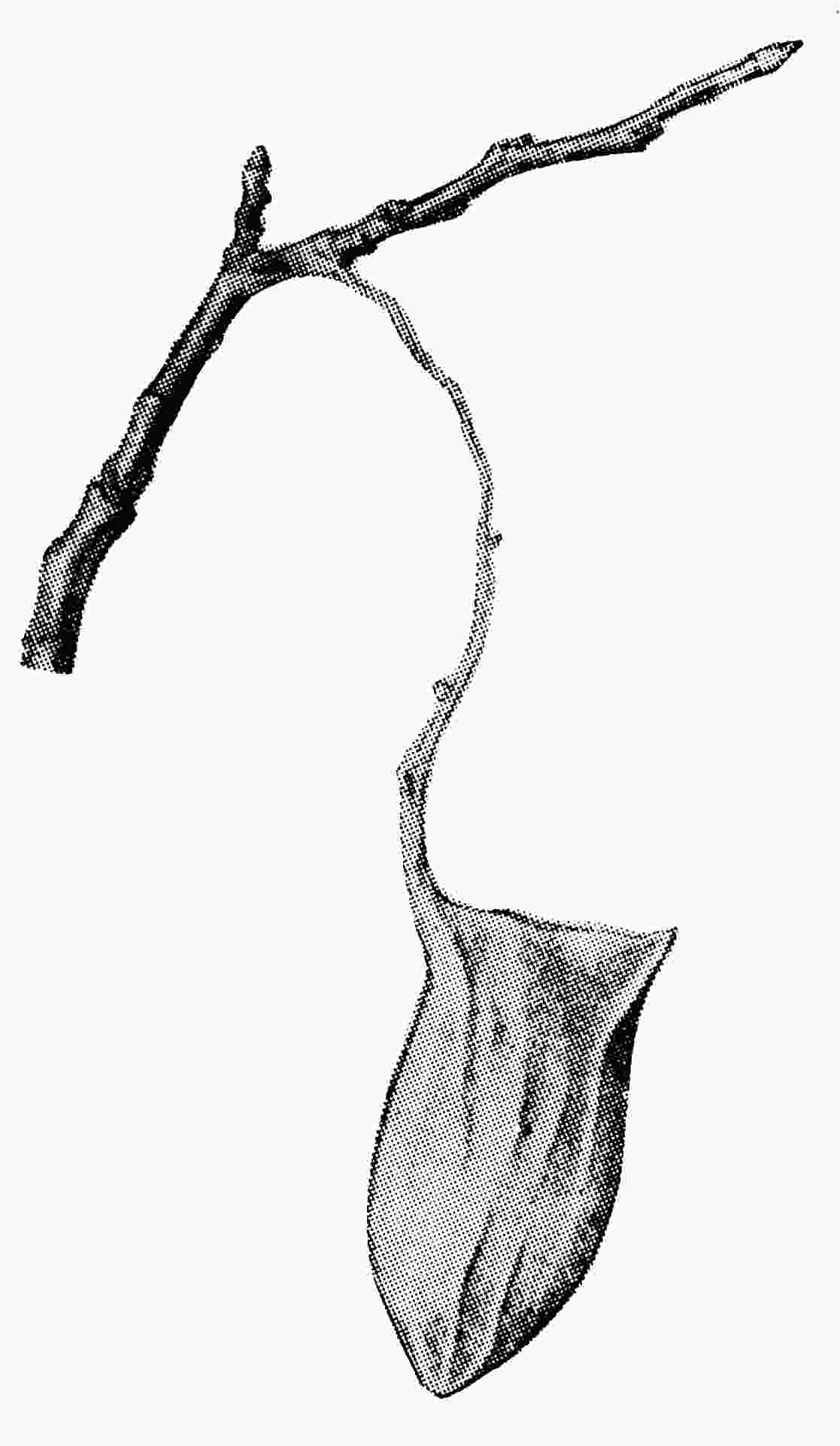 つりがます
つりがます
また
山繭に
似た
一種の
蛾はあたかも
袋を
一端で
釣るしたごとき形の「
釣りがます」と名づける
繭をつくる。これらはいずれもなかなかおもしろくできて、考えて見れば実に
不思議であるが、道ばたの
雑木林に
普通にあるゆえ、だれも
見慣れて
不思議とも思わぬ。さらに
巧妙な
繭には次のごときものがある。すなわち
卵形の
繭の
一端は
閉じ
一端は開いてあって、開いた
端の
孔の
周囲からは、
硬い糸が筆の
穂のごとき形に外へ向いて
並んで、
孔の入口を
閉ざしている。そのありさまはあたかも
一種の
弁のごとくで、
繭の内から
成虫が出るときには、これを
押し開いて何の
妨げもなく出られるが、外からは何物も
繭の内へはいり
込むことができぬ。しこうして、かように
巧みなものをつくるのも
本能の
働きである。
子を
産み育てる
働きのほうには、
本能のもっとも
驚くべき
例が少なくない。他は後の章に
譲って、ここにはただ一つだけ
例をあげて見るに、
琉球八重山産の有名な「
木の葉蝶」は、
産卵するにあ当って、その
幼虫の食物とする「
山藍」のはえている場所のちょうど上にあたる
樹木の
枝に
産みつけておくということである。これはおそらく
山藍という草は谷間にはえる
丈の
低い草で、日当たりが
極めて悪いために
昆虫類の
卵の発育するにはすこぶる
不利益な
位置にあるゆえであろう。一体
蝶類はいずれも、その
幼虫の食する植物に
卵を
産みつけるもので、
紋白蝶ならば
大根等に、
揚羽ならば「からたち」などに、それぞれ定まっているが、「木の葉
蝶」は
山藍の葉には
産みつけず、ちょうどその上にあたる高い
樹木の
枝に
卵を
産みつけておくと、それから
孵って出た小さな
幼虫は、口から糸を
吐き糸にぶら下がって
枝から地上へ
降り、ちょうどその下にはえている
山藍の葉に
達して、直ちにこれを食うことができるのである。昔ならばたしかに
造化の
妙とでも言うたに
違いない。
餌を食うため
敵に食われぬために、動物が行なうことの中には、人間が知力を用いてなすことと
程度は
違うが、
性質は同じであるごとくに思われるものがすこぶる多い。
例えば、
猿が番人のすきをうかごうて
桃林から
桃を
盗んで行くのも、
猫が
鼠の出て来るのを待って根気よく
孔のそばに
身構えているのも、人間の
挙動にくらべてほとんど何の
相違もない。昔、人間と他の動物との間の
距離をなるべく大にしたいと思うたころには、
猿が
桃を
盗むのと、人が
桃を
盗むのと、また
猫が
鼠の
穴をうかがうのと、人が
鉄砲を持って
兎の
穴をうかがうのとを
厳重に
区別し、一方は
本能の
働き、一方は知力の
働きと見なしたであろうが、
虚心平気に両方の
挙動をくらべて見ると、その間に
根本的の
相違があるものとはけっして考えられぬ。今
仮に自分が
猫になったと
想像したならば、
鼠を
捕えるにあたっては、やはり
実際猫のするとおりのことをするであろう。また
仮に自分が
猿になったと
想像したならば、
桃を
盗むにあたっては、やはり
実際猿のするとおりのことをなすに
違いない。されば、一方のみを知力の
働きと見なし、他方は知力の
働きでないなどと
論ずべき
根拠は少しもない。かように考えると、知力を有するものはけっして人間のみに
限るわけではなく、動物界には広くこれを
備えたものがある。ただし、その
発達の
程度には
種々の
階段があって、
或るところまで
降るともはや
本能と
区別することが全くできなくなってしまう。
猿が
桃を
盗み、
猫が
鼠を
捕えるのを知力の
働きとすれば、他の動物のこれに
類する
挙動も同じく知力の
働きと考えねばならず、
順々にくらべて進むと、しまいには「さんご」の虫が「みじんこ」
類を
捕えて食うのまでも、知力があずかっていると
論ぜねばならぬことになる。さらに一歩進めば「
蠅取り草」が
蠅を
捕えるのも知力の
働きの
範囲内に入れねばならぬとの
結論に
達するが、かくてはあまり広くなって
際限がない。
著者自身の考えによれば、知力といい
本能というも、いずれも外界の
変化に
応じて
適宜に身を
処する
神経系の
働きの中で
特殊に
発達した部分を指す
名称で、そのいちじるしい
例を
互いに
比較すれば
相異なる点が明らかであるが、
程度の
低いものの間にはけっして
境界はない。他物にたとえていえば、知力と
本能とはあたかも
相隣れる二つの山の
頂のようなもので、そこに
絶頂が二つあることはだれの目にも明らかに見えているが、少しく下へ
降りると、山と山とは
相連絡してその間に何の
境もなくなる。生物はすべて食うて
産んで死ぬものであるが、食うて
産んで死に
得るには、つねに外界に対して
適宜に
応接して、
目的にかのうた行動をとらなければならぬ。しこうして
神経系のある動物では主として
神経系がその
衝に当たるが、動物の
種類によって生活の
状態も大いに
違うから、
或る
種類の動物では
神経系の
働きは一方に
発達して、ついに知力と名づくべき
程度に進み、他の
種類の動物では他の方面に
発達して、明らかに
本能と名づくべきものとなったのであろう。また
簡単な
反射作用はあたかも山の
麓に
比較すべきもので、
本能とも知力とも名づけることはできぬが、さればとてまた
本能からも知力からも明らかな
境界線を引いて区画することはできぬ。今日、知力、
本能などに
関しては学者間に
際限なく
議論が
闘わされているが、
著者の見るところによるとその大部分は、本来
境界線のなかるべきところに強いて
境界線を定めようと
試み、その
境界線をどこの
辺に定めようかと、
議論しているにすぎぬようである。 なお一つ
例をあげて見るに、
子供の
金魚鉢に
飼うてある「
弁慶蟹」と「
石亀」とを
捕えようとすると、
蟹のほうは
鋏を上げて
触れればはさむぞと
嚇かしながら
逃げ行き、
亀のほうは頭も足も引き
込めて動かずにいるが、これらの
挙動を、人間が
淋しい道で人相の悪い男に
出遇うた
際に、ピストルに手を
掛けて相手の顔を
睨みながらすれ
違うて行く
挙動、もしくは
泥棒が雨戸をこじ開けんとする音を聞いて、中から戸を
押さえて
防いでいる
挙動にくらべると、その間に
性質上の
相違があろうとは思われぬ。したがって、一方を知力の
働きと見なす
以上は、他を知力の
働きでないと言うべき
論拠はない。かようにくらべて見ると、ついには「いそぎんちゃく」が体を
縮め、「おじぎ草」が葉を下げるのまで
順々に引き
続いて、どこにも
判然たる
境界を
設けることはできぬ。
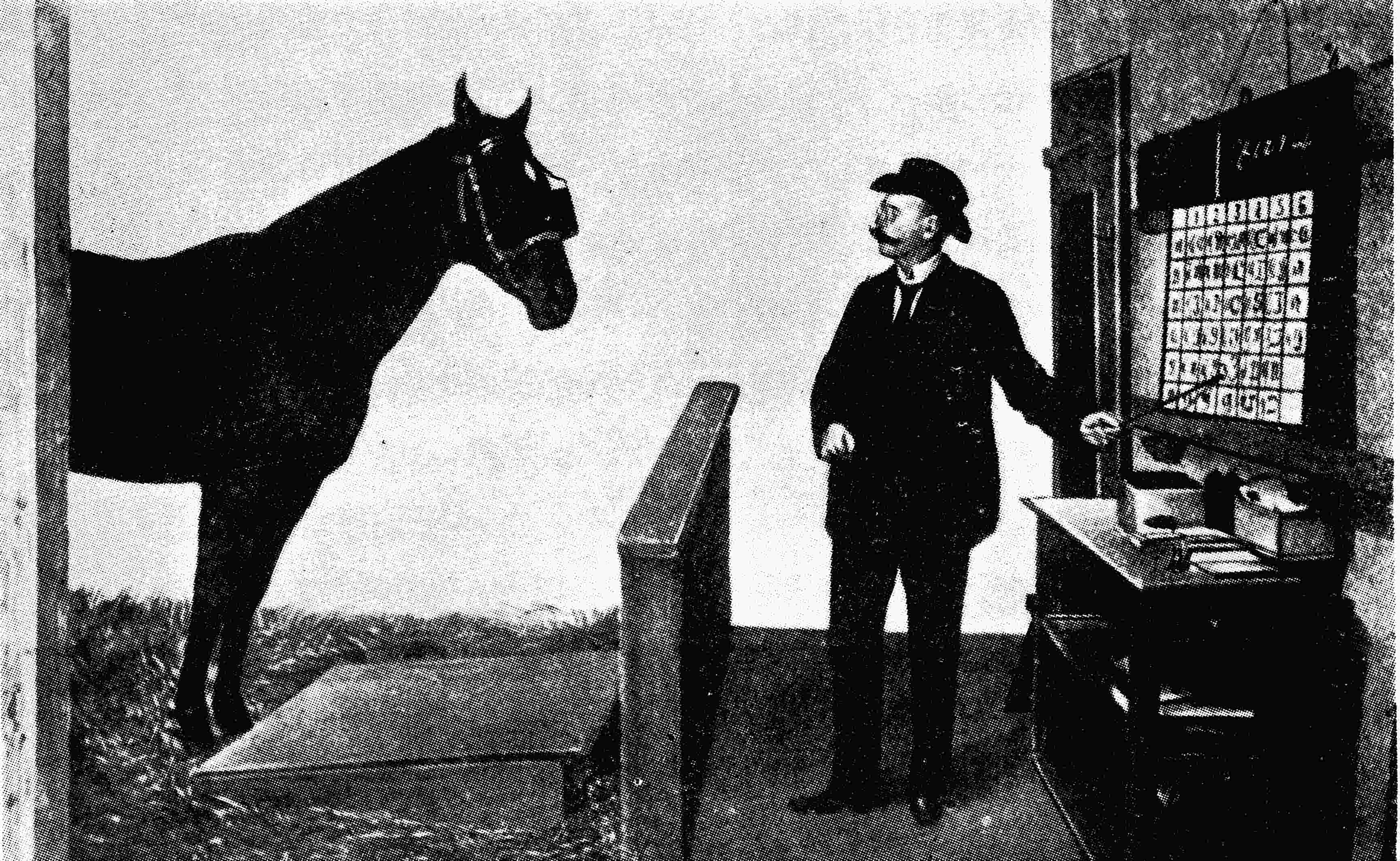
馬に文字を教う
ドイツのクラルという人その飼馬ツァリフに文字を教え各文字に対して左右の前足をもって一定の度数だけ板をたたかしむ。例えばAには左一回右一回とか,Bには左一回右二回とかいうごとし。馬は字を指し示さるればこれに応じ,かねて覚えたるとおりの度数だけ板をたたき,物を尋ねらるれば字を綴りてたたき答う。また数を加え減じ,掛け割るなどの問題に対しても正しき答えをなす。
さて知力のもっとも
発達した動物は言うまでもなく人間であるが、これは今のたとえでいうと、一方の山の
頂上にあたる。しからば人間についで知力の
発達した動物は何かというに、これは
脳髄の
構造が人間にもっともよく
似た
獣類であって、その中でも
特に
大脳の表面に
凸凹の多い
猿、犬、馬などは知力も
相応に進んでいる。今よりすでに十四、五年も前の事であるが、ドイツである人の
飼うていた
悧巧な、ハンスという馬が、字も読め数もかぞえられるというて
大評判であった。
例えば五と七とを
加えるといくつかと
尋ねると、馬は前足で
床板を十二たたいて答えたのであるが、その当時これを調べた心理者の
鑑定によると、馬が前足で
床板をたたいてちょうど答えの当たる数まで
達すると、
尋ねた人が知らずに頭を一ミリメートルの何分の一とかを動かすので、馬は
鋭くもこれを
識別してたたくことを止めるゆえ、あたかも
算術ができたかのごとくに見えるのである。実はけっしてかぞえる力などがあるわけではないとの事であった。しかし、この
説明には
満足せぬ人があって、その後さらに
別の馬を
飼うて
種々試験を
続けたところが、馬に文字を
覚えさせ、これを自分で
綴って人の問いに答えさせることも
容易にできるようになった。この
種類の
試験については、今日では数多く
報告があって、すでに馬のほかに犬や
象についても同様の
結果を
得ている。
著者は自身にかような
試験を行のうたことはないが、犬や馬について
日常見ていることから
推して、
以上のごときことは
或る
程度までは
当然行なわれ
得べきことと考えていたゆえ、
別に
不思議にも思わぬが、人間の知力と他の動物の
脳の
働きとの間に
根本的の
相違があるように
論じたい人等は、
種々の
論法を用いて、
右様の
働きが知力の
結果でないことを
証明しようと
骨折っている。
ここに一つ
断わっておくべきは、
本能でも知力でも、時々
無駄な
働きをすることである。
蛤の
貝殻が
如何に
堅くても「つめた貝」には
孔をうがたれ、
蜂の
針が
如何にはげしくさしても「はちくま」という
鷹には平気で食われるごとく、
防御の
装置にはそれぞれ
標準とするところがあって、
例外のものに対しては
有効であり
得ぬとおり、
本能でも知力でもその動物の
日常の生活を
標準として
発達し来たったものゆえ、生活の
条件を
変えると、ずいぶん
目的にかなわぬ
働きをする。
例えば「走りぐも」は
巣をつくらずつねに草の間を走りまわり、
卵を
産めば糸をもって
繭の形にこれを
包み、どこへ行くにも大事に持っているが、
強いてこれを
奪い取って、その代わりに
紙屑を同じくらいの大きさに丸めたものを投げてやると、直ちにこれをかかえ
極めて大切に
保護して持ち歩く。これなどは、
本能が
盲目的に
働いて
無駄なことに
骨を
折っているのであるが、
紙屑でも何でも
構わず大切に
保護するまでに
発達した
本能こそ、この「くも」の生活にとってはもっとも
必要なものである。知力のほうでもこれと同様に、
往々生活の
目的のためには何の役にも立たぬ
働きをすることがある。
或る
程度まで知力の
発達することは、人間の生活にとっては
必要な
条件であるが、
相応な知力を出し
得るまでに
脳の
構造が進歩すると、これを生活に
必要なより
以外の方面にも
働かせる。しかしこの場合には知力が
如何ほどまで
有効に用いられているかは大いに
疑わしい。
如何にしてこの魚を
捕えようか、
如何にしてかの
獣を
殺そうかと考えて、
網の
張りようや落し
穴の
掘りようを
工夫し、
如何にして
甲の
蕃社を
攻めようか
如何にして
乙の部落からの
攻撃を
防ごうかと
思案して、
槍の
穂先の形を
改良し、味方
同志の暗号を定めなどするのは、すべて知力の
働きであるが、かようなことができるまでに
脳の
構造が進歩すると、
退屈のときにはこれを用いて
種々のことを考え始め、何でも物の起こる
原因を先の先まで知ろうとつとめれば、
哲学が生じ、人間
以外に何か目に見えぬ強い者がいると
信ずれば、
宗教が始まり、
不完全な
推理によって勝手に物と物との間に
因果の
関係をつければさまざまの
迷信が
現われる。これらはいずれも
生存に
必要な知力の
発達したために生じた
副産物であるゆえ、いわば知力の
脱線した
結果と見なすことがてきよう。その後、物の
理屈を考える力が進めば、
脱線的の方面にもますますこれを用いて、
哲学も
宗教も
迷信も
盛んになり、そのため
莫大な
費用と
労力とを
費やして少しも
惜しまぬようになる。有名なエジプトの
金字塔のごときも
畢竟、知力が
無駄な方向に
働いたための
産物にすぎぬ。
無線電話や「ラジウム」や
飛行機や
潜航艇を用いるにいたったまでに、人間の知力がつねに
生存のために
有効であったことはいうまでもないが、その間に
宗教、
迷信のために、人間がどのくらい
無駄な仕事をしたかと考えると、これはまた実に
驚くべきもので、今日といえどもなお「走りぐも」が丸めた
紙屑を大事にかかえ歩くのと同じようなことをしながら
毫も
怪しまずにいるのである。
本能とか知力とか
違うた名をつけてはいるが、
詰まるところいずれも
生存に間に合うだけの
神経系の
働きであって、これらの
働きが
敵に
比して
劣っていては
生存ができぬゆえ、代々少しずつ進歩し来たったのであろうが、その進歩の
程度はいつも
生存競争にあたって
敵に負けぬというところを
標準として、けっしてこれを
超えてはるかに先まで進むことはない。されば人間の知力のごときも、
生存競争における
武器としてはようやく間に合うてゆくが、もとより
絶対に
完全なものではなく、
特に
生存競争以外の
暇仕事の方面に向けて
働かせる場合には、その
結果はすこぶる当てにならぬものと思われる。
本能によって
働く
昆虫や「くも」は、その
境遇を
変えて
試して見ると
盛んに
無駄な仕事をするが、知力のほうもこれと同様で、
当然働かせるべき方面
以外に向けて
試して見ると、
大間違いの
結論に
達することがあるゆえ、そのため今後もずいぶん
無駄な
骨折りをなしつづけることであろう。
人が目をさましているときは
意識があると言い、
熟睡しているときは
意識がないと言う。しからば
意識とは何かと
尋ねると、これは
容易に答えられぬ。
何故かというに、
意識のある
状態とない
状態との間には
自然の
移り行きがあって、
判然たる
境界線を定めることができぬからである。だれも自身に
経験のあるとおり、夜
寝床にはいって
眼を
閉じていると、いつとはなしに
意識が
朦朧となって、
暫時うとうとしたる後についに真に
寝いってしまう。また急に起こされた時には、直ちに
意識が
明瞭にならず、方角もわからず、物の
識別もできぬようないわゆる
寝ぼけたありさまを
通過してようやく
精神が
判然する。赤子の生まれたばかりの時にはとりたてて
意識と名づくべきほどのものもないようであるが、日数が重なる間にしだいに人間らしく、
笑ったり
怒ったりするようになり、長い
時日の後にいたって
普通一人前の
意識が
完全になり終わる。また病人が死ぬときにもまず
意識が
混濁して
昏睡の
状態におちいり、一歩一歩真の
無意識の
境遇に近づいてゆく。かくのごとく人間だけについて言うても、
明瞭な
意識のある
状態から、全く
意識のない
状態までの間に
無数の
階段があるが、他の生物は
如何と見ると、ここにも
意識には
種々の
程度の
違うたものがあるごとくに思われる。昔の
或る有名な学者は
意識を有するものは人間ばかりで、他の生物には
意識はない。
彼らは
単に
自働器械のごときもので、あたかも時計や、ぜんまい
仕掛けの
玩具などのごとくに
器械的に動いているにすぎぬと
説いたが、これなどは人間と他の生物とを
絶対に
区別したいと思うたころの考えで、今日
虚心平気に
判断すると、全く何の
根拠もない
説である。生物の中には、
眼つきや
挙動から
鑑定すると人間に
劣らぬ
明瞭な
意識を
備えたものもあれば、人間の
寝ぼけたときくらいの
程度以上に
意識の進まぬものもあり、また
一生涯を
昏睡の
状態で
過ごすものもある。
野蛮人が、
鳥獣はもとより草木金石にいたるまで、自分と同じ
程度の
意識があるごとくに考えるのも
誤りであるが、昔の西洋の学者が、その正反対に人間
以外の生物には
意識はないと
論じたのも同じく
誤りと言わねばならぬ。
著者が実物を見て考えるところによれば、多くの生物にはたしかに人間のと同じような
意識がある。ただしその
程度はけっして同じでない。
本能や知力も
各種の生物によって
発達の
程度が
違い、それぞれその生活に
必要な
程度にまでより進んでいないが、
意識なるものも
各種の生物が食うて
産んで死ぬのに
必要なだけの
程度より
以上にはのぼらぬ。すなわち
一生涯昏睡の
状態にあっても、食うて
産んで死ぬのに
差支えのない生物には、
昏睡の
状態以上の
意識は
現われず、
寝ぼけ
程度の
意識さえあれば食うて
産んで死ねる生物には、
寝ぼけ
程度より
以上の
意識は生ぜぬ。すきをうかごうて電光のごとくに魚を
盗み去る
猫の
意識と、
静かに草を食うている
芋虫の
意識と、追われても
逃げず
突かれても平気でいる「くらげ」の
意識との間には、もちろんはなはだしい
相違はあるが、人間が生まれてから死ぬまでの間、または起きてから
眠るまでの間には、これらと同等の
階段を
順次に
経過するゆえ、その間に
境界を定めることはできぬ。
無意識の
状態から
有意識の
状態に進むありさまは、あたかも夜が明けて朝となり、また昼となるごとく、いつとはなしに
変化して行くから、
両端をくらべるとその間の
相違はいちじるしいが、ここまでは
意識がなく、そこより先は
意識があるというごとき
境界はどこにもない。かようなところに
強いて
境界を定めようとすれば、あたかも汽車や電車の
賃金を
十二歳以下は
半額とか、
五歳以下は
無賃とか定めるごとくに、相談によって
便宜勝手なところに
境をつくるよりほかにいたし方はないであろう。
意識の
程度が、
各種の生物の生活に
必要なところまでより進まぬごとく、
意識の
範囲も、
各種の生物の生活に
必要なだけより
以上にはおよばぬようである。がんらい
意識は
神経系の
働きの全部にわたるわけではなく、わずかにその一部を
含むだけで、あたかも
闇の夜に
懐中電燈で
照らしたところだけが明るく見えるのと同じく、
残余の部分は全く
意識の外にある。
一例をあげて見るに、われわれが
或る物体を
視る時には、その物体の
像が
眼球の
奥の
網膜の上にさかさまに小さく
映ずるが、この事は少しも
意識せられぬ。また
種々の
実験でわかるとおり、
網膜の上に
映じた
像をそのままに感ずるわけではなく、これを
材料として
一種の
判断力を
働かせ、その
結果を感ずるのであるが、この
判断の
働きも
意識の
範囲以外にある。しこうして、ただその
結論だけを直感
的に知ることができる。
網膜に
如何なる
像が
映じようとも、また
先祖以来の
感覚の
記憶や、その
連絡の
記憶が
如何であろうとも、そのようなことは知っても生活上何の役にも立たぬゆえ、
意識の中に
現われぬが、自身の前面に当たる外界の一部に、自分より
約何尺へだたるところに何ほどの大きさの
如何なる形の物があるかを知るのは生活上もっとも
肝要であるゆえ、ただこれだけが
意識せられるのである。されば
意識の
範囲内に
現われるのは、
神経系の
働きの中で生活上
明瞭に
意識する
必要のある部分だけであって、その他の
働きは、たといこれと
密接な
関係のあるものでも、みな
意識以外に
隠れている。これに
類似したことはわれわれの
日常の生活中にもいくらもある。
例えば時計を用いるには
時刻の読みようと、
鍵の
巻きようと、
針の動かしようとを知っていれば十分であって、内部の細かい
機械の
仕掛けなどは知らずとも
差支えはない。また電話をかけるには、
呼出しようと切りようとを知っていればよいので、
別に電話
器械の
構造や
理屈を知っている
必要はない。生物の有する
意識なるものもこれと同様で、
神経系の
働きを全部知っている
必要はないゆえ、他の部分はすべて
無意識の
縄張り内に
残しておいて、ただ
直接に知る
必要のある部分だけを引き受けているのである。
意識に
現われることは、みな
無意識の
範囲内における
神経系の
働きを
基礎とし、かつこれと
密接な
関係のあることは言うまでもない。
本章においては主として知力のことを
述べて、
情の
働き、意の
働きのことは全く
省いたが、
著者の考えによればこれもやはり前と同様の
関係で、
各種の生物が食うて
産んで死ぬのに
必要な
程度までには
発達しているが、けっしてそれ
以上には進んでいない。しかもそれが
意識に
現われるのは当事者が
自覚する
必要のある部分だけに
限る。
情の力、意の力が
無意識の
範囲内で
働き、その
結末だけが
意識せられる場合には、
何故にこのような事がしたいか、
何故にかような事をなさずにいられぬかは、むろん自身にもわからず、ただ
本能的にその事をなし終わるであろうが、かくすれば、それが
必ず
種族の
生存のために役に立つ。すなわち当事者が自身の
行為の理由を知っていても知らずにいても、それは
種族の
生存のためにはいずれでも
差支えはない。ただ
必要なだけのことが行なわれさえすればよろしいのである。身体に水分が
不足すれば
渇を感じて水が飲みたくなり、水を飲めば水の
不足はたちまち
補われるごとく、
意識して感ずるのはただ
直接に
必要なことだけでよろしい。それより
奥のことは
必ずしも感ずるにおよばぬ。かように考えて見ると、意の力、
情の力を
備えて、生物が
敵を
防ぎ、子を育てなどしているありさまは、あたかも電車の運転手がハンドルの回しようと、歯止めの
掛けようとだけを知って、日々車台を運転せしめているごとくで、そもそも
如何なる理由で車の
輪が回転するかという問題などは
捨てておいても少しも
差支えはない。ただ緑の
旗が出れば進み、赤い
旗が見えれば止まりさえすればよいのである。しこうして
実際如何なる生物でも
意識内に
現われる
神経系の
働きは、
必ずかかる
性質の部分のみに
限られているように見受ける。
なお
各種の生物が食うて
産んで死に
得るために有する
種々の
構造や
習性を
通覧して、心づかずにいられぬ点が一つある。それはほかでもない。いずれの
構造でも
習性でも
種族全体としての
生存に
有利であればよろしいので、
例外の場合に少数の
個体が
犠牲となることは全く
度外視せられている。言を
換えていえば、
自然なる者は
種族の
生存を図るにあたって、いつも全局を通じての
利益を
標準とし、多少の
無駄は始めから
覚悟しているのである。本章に
述べた
本能でも知力でも
反射作用でも、みな
各種の生物の
種族全体にとっては
必要なものであるが、
特殊の場合に
若干の
個体が、そのため生活の
目的にかなわぬ
所業をなすことを
避けられぬ。「走りぐも」が
紙屑の丸めた球を
卵塊と
誤って大切に
保護するのは、
本能のために
無益な
労力を
費しているのであるが、
蛾の
類が
燈火を見て
飛び
込んでくるごとき場合には、
本能のために命を
捨ててしまう。しかしながら、「走りぐも」が
紙屑を
卵と
間違えるのは、人がわざわざ
試験して見るきわめてまれな場合に
限ることで、これは全く
勘定にははいらず、また人が
燈火をともし始めたのは、地球の長い
歴史中の
最後の
頁で、しかも
燈火の光の
達する
区域は、地球の表面の広さから見ればほとんど言うにたらぬから、もし
蛾をして
燈火に向かわしめる
神経系の
構造が、
蛾の生活上他の方面に
有効な
働きをなしているものとすれば、
差引き
勘定むろんはるかに
得になっている。半紙を
漉くにあたって、始めから
毫も
無駄の出ぬようにでき上がりだけの
寸法につくろうとすれば、これはすこぶる
困難なことで、
如何に手数をかけてもなかなか行なわれがたい。これに反して、始めから
若干の
無駄を
見越し、でき上がりの
寸法よりもやや大きく
漉いて、後に
周辺の
余分のところを
裁ち切ることにすれば、すこぶる
容易に
目的を
達することができる。生物界における
本能、知力ないし
情の力、意の力なども、これと同じ
理屈で、
無駄な部分を
裁ち切って
余ったところが生活上の役に立てば、それですでに
目的にはかのうている。
特殊の場合に
出遇うた
本能の
働きや、生活に
必要なより
以外の方面に向けた知力の
働きなどは、時としては
若干の
個体の
生存のために
無益または
有害なこともあるが、これはあたかも半紙の
裁ち
屑のようなもので、
各種族の全体の
経済からいえば、
捨ててもけっして
損にならぬくらいのものであろう。
同
種類の生物
個体が多数
相集まっていることは、
餌を
捕えるにあたっても
敵を
防ぐにあたってもすこぶる
都合のよいことが多い。
一匹ずつではとうていかなわぬ相手に対しても、多数集まれば
容易に勝つことができる。また
非常に強い
敵に
攻められてさんざんな目に
遇うたとしても、多数に集まっていればその中のいくぶんかは
必ず
難をまぬがれて
生存し、
後継者を
遺すことができる。
特に
生殖の
目的に対しては、
同種族のものが同所に多数集まっていることは
極めて
有利であって、
一匹ずつが遠く
相離れているのとは
違い、すべてのものが
残らず手近いところに
配偶者を見いだして、
盛んに子を
産むことができる。されば
事情の
許す
限り、同
種類の生物は同じところに集まって生活しているほうが、食うにも
産むにもはるかに
好都合であるに
違いない。
そもそも生物は親なしにはけっして生まれぬものゆえ、
一生涯絶対に
単独というものは
一種たりともあるべからざる
理屈で、少なくとも親から生まれたときと、子を
産んだときとは、同
種類の生物が
何匹か同じところに
接近しているに
違いない。
特に多数の生物では、同時に生まれる子の数が
相応に多いから、これらがそのままとどまって生活すれば、すでに一つの
群集がそこに生ずる。しこうして
相集まって生活しておれば、上に
述べたごとき
利益がある。かようなしだいで、同
種類の生物が一所に集まって
生存することは
自然の
結果であるように思われる。しかるに
単独の生活を送る生物もけっして少なくないのは
何故かというと、これは生活
難のために
一家離散したのであって、
生存の
必要上群集生活を思い切るように
余儀なくせられたものに
限る。
例えば
陸上の食肉
獣類には
群棲するものはほとんどない。これは
獅子、
虎などのごときものが
一箇所に多数集まって生活し、多数の牛や
鹿を
殺して食うたならばたちまち食物の
欠乏を生じ、みなそろうて
餓死せねばならぬからである。これに反し、草食
獣類のほうは
餌がたくさんにあるゆえ、
大群をなして生活していても、急に食物が
皆無になる心配はない。
昆虫類などでも木の葉を食う毛虫は
枝一面に
群集していることがあるが、虫を
捕えて食とする「かまきり」や「くも」
類などは、
一匹ずつ
離れて
餌を
求めている。もっとも肉食するものでも、
餌となる動物が
多量に
存する場合には、
群棲しても
差支えはない。「おっとせい」、「あざらし」の
類は肉食
獣であるが、その
餌となる
魚類は
極めて
多量に
産し、あたかも
陸上の
牧草のごとくであるゆえ、数千も数万も同一
箇所を
根拠地に定めて生活している。つまるところ、生物が
群棲するか
単独に
暮らすかは、食物
供給の
量と
関連したことで、
群棲してはとうてい食物を
得られぬ
種類の動物だけが、親子兄弟
離ればなれになって世を
渡っているのである。
同じ
種類の生物
個体が、ただ
相集まっているだけでも生活上に
種々都合のよいことがあるが、もしも多数のものが同一の
目的を
達するために力をあわせて
相助けたならば、その
効力は実に
偉大なもので、たいがいの
敵は
恐れるにたらぬようになる。
各個体が食うにも
産むにも死ぬにも、すべて
自己の
属する
団体の
維持生存を
目的としたならば、その集まった
団体は、
生存競争にあたって、
個体よりも
一段上の
単位となるから、
攻めるにも
防ぐにも勝つ
見込みがすこぶる多い。かような
団体を社会と名づける。
実際動物界を
見渡すと
昆虫類の中でも、
蜂や
蟻などのごとき社会をつくって生活する
種類はいたるところに
盛んな
勢いで
跋扈し、場合によっては
獅子や
虎のような
大獣をさえも苦しめることがある。
個体のただ集まった
群集と、全部
一致して活動する社会との間には、
順々の
移り行きがあるが、同じく社会と名づけるものの中にも
種々の
階段があって、そのもっとも進んだものになると、
個体間の
関係が、
猫や犬で
普通に見るところとは全く
違うて、ほとんど
一個体の体内における
器官と
器官との
関係のごとくになっている。次に
若干の
例によって、これらの
関係を一とおり
述べて見よう。
或る
種類の動物が、
一箇所にたくさん集まっていることのあるは、だれにも気のつくいちじるしい事実である。
例えば春から夏にかけて、あたたかな
時節になると、毛虫がたくさんに出てくるが、中には
樹の
膚が見えぬほどに
幹にも
枝にもいっぱいにいることがある。また
薔薇、
菊、
萩その他の
草花類の新しい
芽のところに、「ありまき」が
圧し合うほどに一面に集まっていることがある。
田畝の流れに「めだか」が
游いでいるのを見ても、
禁猟地の池に
鴨の
浮かんでいるのを見ても、みな
必ず
群をなしていて、
単独に
離れているものはほとんどない。かく多数に集まる
原因は場合によって
必ずしも一ようではないが、
相集まっている
以上はとにかく、
群集に
基づく
利益を
得ていることはたしかである。
生物の中には風に
吹かれ波に流されて、同じところに
無数に集まるものがある。「夜光虫」などはその
一例で、海岸へ
吹き
寄せられたところを見ると水が一面に
桃色になるほどで、その数は
何億匹いるか
何兆匹いるかとうてい
想像もできぬ。「
数の子」の
一粒にもおよばぬ小さな虫が、ほとんど水を交じえぬほどに
密集して、数里にわたる
沿岸の波打ち
際に打ち
寄せられていることがしばしばあるが、わずか
二三十匹ずつガラス
瓶に入れて、
五十銭にも売っている
標本商の
定価表に
従うたならば、世界中の
富をことごとく集めてもその一小部よりほかは買えぬであろう。ただし、これは
潮流の
都合で
芥が
寄るのと同じく
単に
器械的に集まるのであるから、自身から
求めてわざわざ集まる他の生物の
群集とはもとより
趣が
違う。時々海水を
腐らせて
水産業者に
大害を
与える
赤潮の
微生物も、ほぼこれと同じような具合いで、
突然無数に
寄ってくることがあるかと思うと、その
翌日はまるで
一匹も見えぬこともある。もっとも
絶えず
繁殖するゆえ、その
増加するのは
単に他から集まるのみではない。同じ方角の風が
吹きつづくと、
沖のほうから「かつおのえぼし」が
無数に
浜へ
寄って来て、何万となく打ち上げられたものが
腐敗して
臭気を放つので、その
辺の者が大いに
迷惑するようなことも時々ある。
動物にはそれぞれ生活に
必要な
条件があるが、かような
条件の
備わってあるところには、これに
適する動物が集まってくる。日光を
好むものは日なたに集まり、日光を
嫌うものは
日蔭に集まる。
掃溜めを
掘って「やすで」の
塊を見出すのはそれゆえである。食物が
多量にあるところへはむろんこれを食うものが集まってくる。毛虫や
芋虫が
大群をなしている場合はすなわちかかる
原因による。また「ありまき」のごときものは、運動の
遅いために遠くへ行かずみな生まれたところの
近辺にとどまるので、
大群を生ずることがある。
 かげろうの群集
かげろうの群集
「かげろう」という「とんぼ」に
似た虫の
幼虫は長い間水中に生活しているが、それが
孵化するときは何万となく、同時に水から
飛び出すゆえ
暫時大群が生じ通行人の顔や手にとまって、うるさくて
堪えられぬ。「いなご」が
非常な
大群をなして
移動し、いたるところで緑色の植物を
残らず食いつくすことは昔から有名な事実であるが、これもおそらく同じ時に
卵がそろうて
孵化した
結果であろう。
右のごときもののほかに、動物には自ら
同種相求めてわざわざ
群集をつくって生活するものが少なくない。
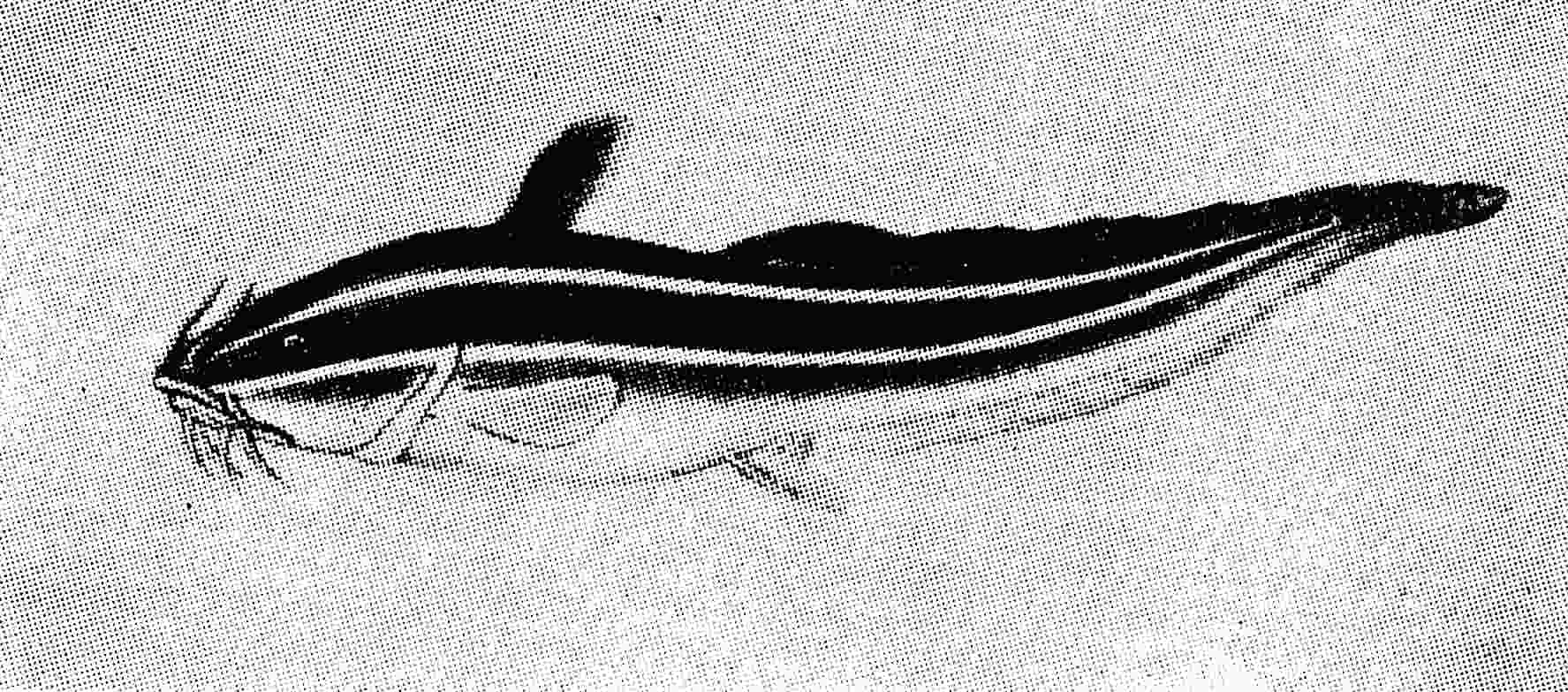 ごんずい
浅
ごんずい
浅いところに住む
海産魚類の中に、形が「なまず」に
似て、口の
周囲に
幾本かの
鬚を有する「ごんずい」と名づける魚があるが、これなどは
特に
群集を
好むもので、水族館に
飼うてあるものを見ても、つねに多数
相集まって、ほとんど球形の
密集団をつくっている。
五分(注:1.5cm)か
一寸(注:3cm)にも足らぬ
幼魚でも明らかにこの
性質を
現わし、球形の
塊になって
游ぎ歩くゆえ、
漁師の
子供らはこれを「ごんずい玉」と
呼んでいる。ためしに
竹竿をもってかような「ごんずい玉」を
縦横に切り
乱すと、一時は多少
散乱するが、
竹竿をのけるやいなや、直ちにもとのとおりの球形に
復する。「ごんずい」は小さな球形の
群集をつくるゆえ
特に
眼に立つが、
見渡し切れぬほどの大
群集をつくる
魚類も少なくない。
鰯、
鰊などはその
例で、大きな地引き
網を引き上げるところを見物すると、実に
無尽蔵のごとくに思われるが、その
盛んに
密集しているところでは、魚が
互いに
押し合うために、海の表面より上へ
現われ出るぐらいであるという。その他、
鰹でも
鯖でも
鱈でも一定のところへ
非常にたくさんに
寄ってくるので、
漁獲の
量もすこぶる多く、したがって
水産物中の
重要なものと見なされるのである。
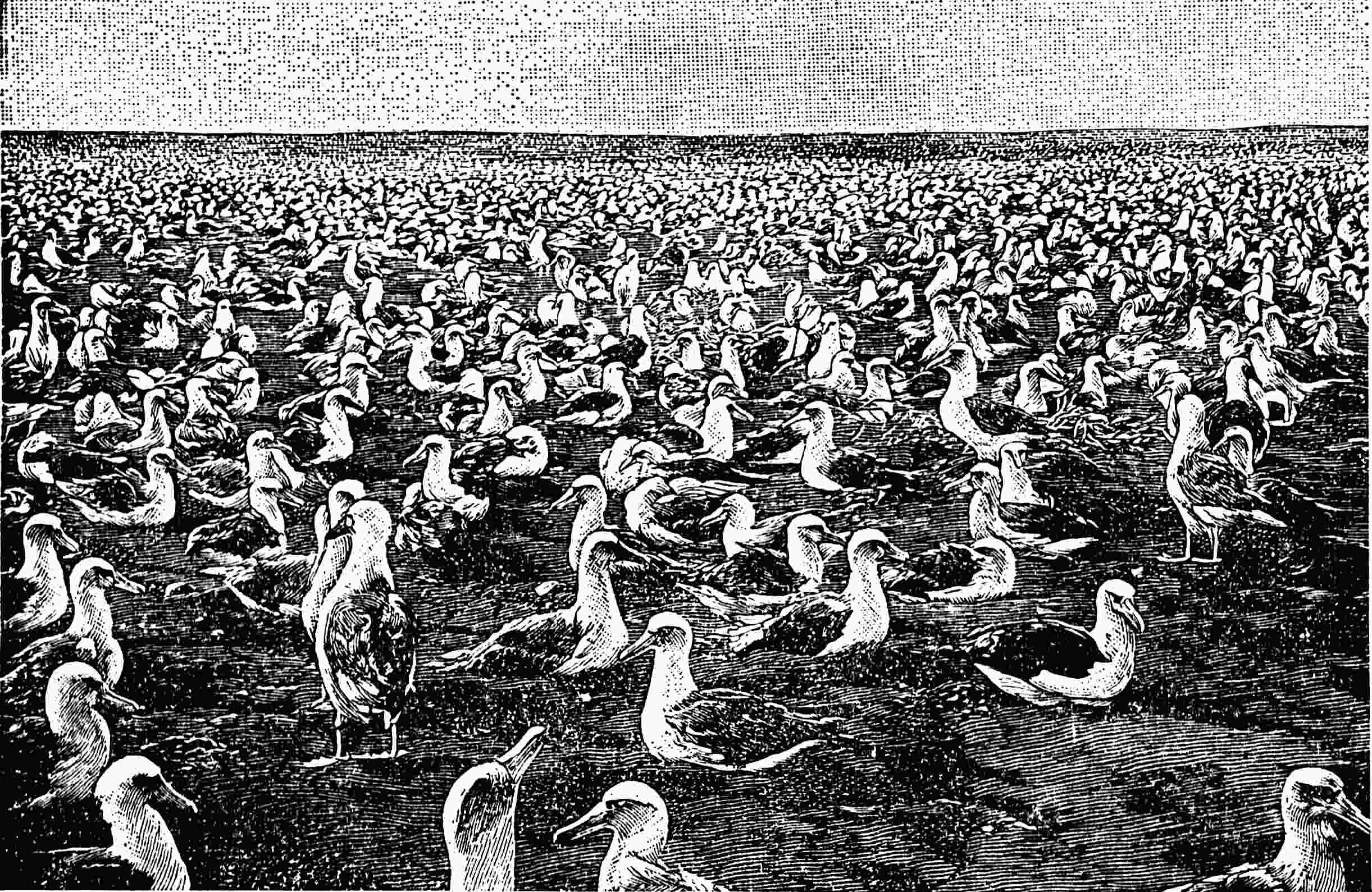 あほうどりの群集
鳥類
あほうどりの群集
鳥類や
獣類にも
群居するものははなはだ多い。その中でも
特にいちじるしいのは海鳥や
海獣の
類で、遠洋の
無人島における海鳥
群集のありさまは、実地を見たことのない人にはとうてい
想像もできぬ。
南鳥島とか東鳥島とかいう名も、島中が鳥でいっぱいになっているところからつけたのであろう。海鳥は
魚類を
常食とするから
糞の中に
多量の
燐が
含まれてある。それゆえ海鳥の
糞は
肥料としてははなはだ
有効なもので、
価も
相応に高い。海鳥の
群集している島にはこの
貴重な
糞が何百年分も
堆積しているゆえ、これを
掘り取ると
一角の
富源となる。
無人島にいる海鳥の中で主なるものは「あほうどり」で、
翼を
拡げると
四尺(注:1.2m)あまりもある大鳥であるが、人が来ても
逃げることを知らず、ただ魚の消化した
臭い
汁を
吐き
掛けるだけゆえ、
棒で打ち
殺すことは何でもない。
南極近くにいる「ペンギン鳥」も、ほとんど
無数に
群がっているところがあるが、これらの鳥はただ集まっているというだけで、
互いに
相助けるというごときことはけっしてせず、あたかも電車の乗合客のように、
相ののしりながら
押し合うている。「ペリカン」なども、動物園や見世物で
一二匹を見るとすこぶる
珍しい鳥のごとくに思われるが、その集まっているところにはほとんど
無限にいる。
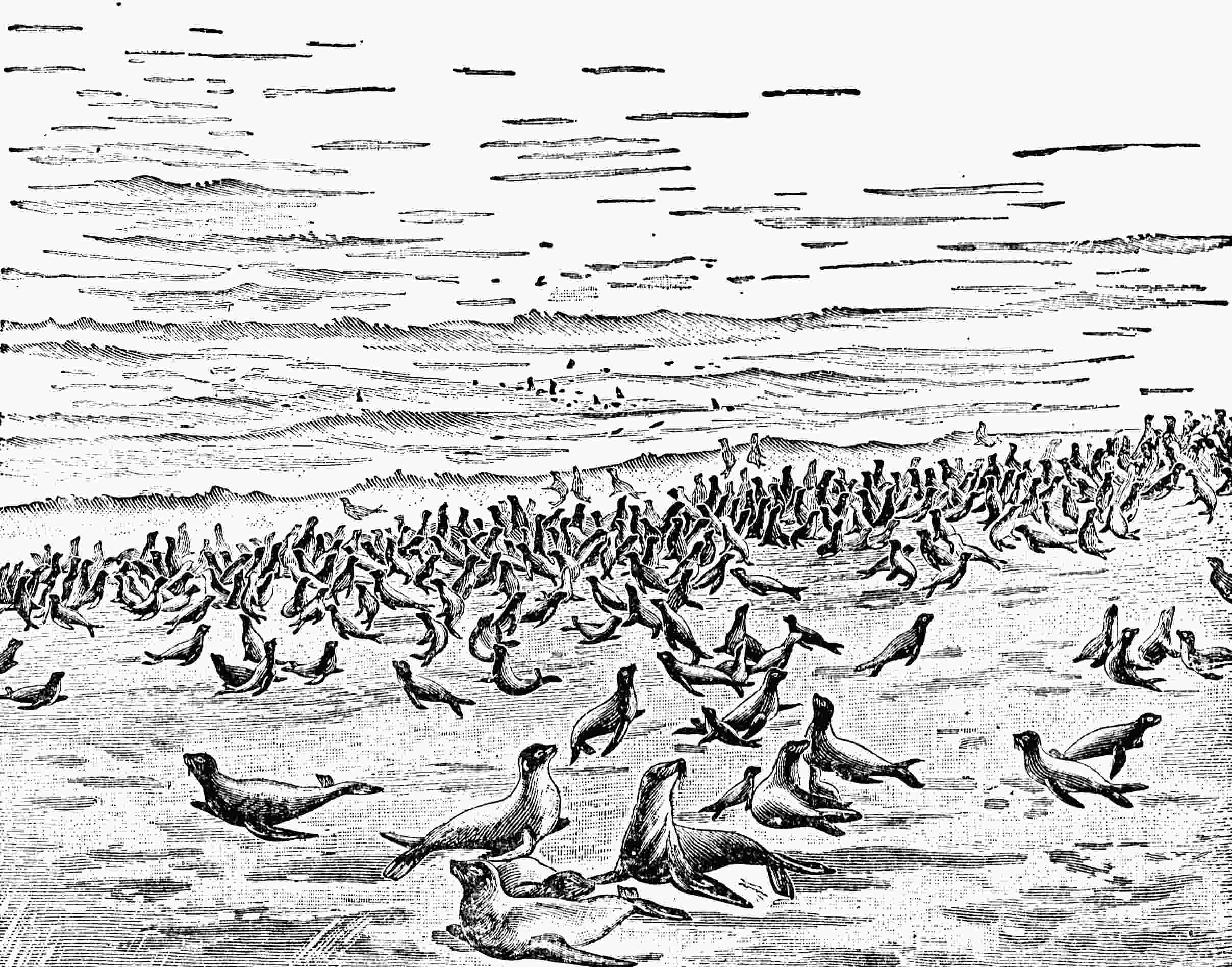 おっとせいの群集
おっとせいの群集
「あざらし」、「おっとせい」のごとき
海獣はみな
大群をなして生活する。「
海豚」なども、
何十匹かそろうて汽船と
競争して泳いで行くのを見かけることがある。
陸上の動物でも羊、
山羊、「しか」、「かもしか」などを始め、
兎、
鼠の
類にいたるまで、植物を食う
獣類には
群棲するものがはなはだ多い。これらはみな
単独の生活をおそれ、なるべく
群集から
離れぬように注意し、万一少しく
離れることがあっても、直ちに
群集のほうへ帰ってくる。しかし
群集の中では
互いに
相助けることはなく、食物を
奪い合うてけんかをするものも
絶えぬ。
或る書物に、人間の社会を冬期における「はりねずみ」の
群集ににたとえて、全く
相離れては寒くてたまらず、また
密接しすぎては
痛くて
困る。その中間にあたる
適度の
距離が、いわゆる
礼儀遠慮であると書いてあったが、
普通の動物の
群集も多くはこれに
似たものであろう。ただし
一匹が
危険を見つけて
逃げ出せば、他はこれに
雷同して全部
残らず
逃げ去るという
便宜はある。
野牛の
群れが
虎などに
襲われた場合には、強い
雄牛は前面に
並んで
敵に向かい、弱い
牡や
子供はなるべく
奥へ入れて
保護するが、かような
団体は「あほうどり」や「ペンギン鳥」の
群集とはいくぶんか
違い、
若干の
個体が
共同の
目的のために力をあわせて
働くのであるゆえ、多少社会を
形造る方向に進んだものと見なせる。また
狼なども多数
相集まって、牛のごとき大きな
獣を
攻めることがあるが、これもその時だけは一つの社会を組み立てていると言える。ただし元来
互いに
相助ける
性質のないものが、ただ
餌を食いたいばかりに合同しているのであるから、相手を
倒してしまえば、
利益分配について
説が
一致せず、たちまち
互いに
相戦わざるを
得ぬようになる。これらの
例を見てもわかるとおり、
簡単な
群集から
複雑な社会までの間には
種々異なった
階段があって、
臨時の社会、
不完全な社会などを
順々に
並べて見ると、その間に
判然たる
境界のないことが明らかに知れる。
水中に生活する動物には
芽生によって
繁殖するものがいくらもあるが、これらの動物は多くは親と子との身体が
一生涯離れず
相続いたままでいるゆえ、だんだん大きな
群体ができる。
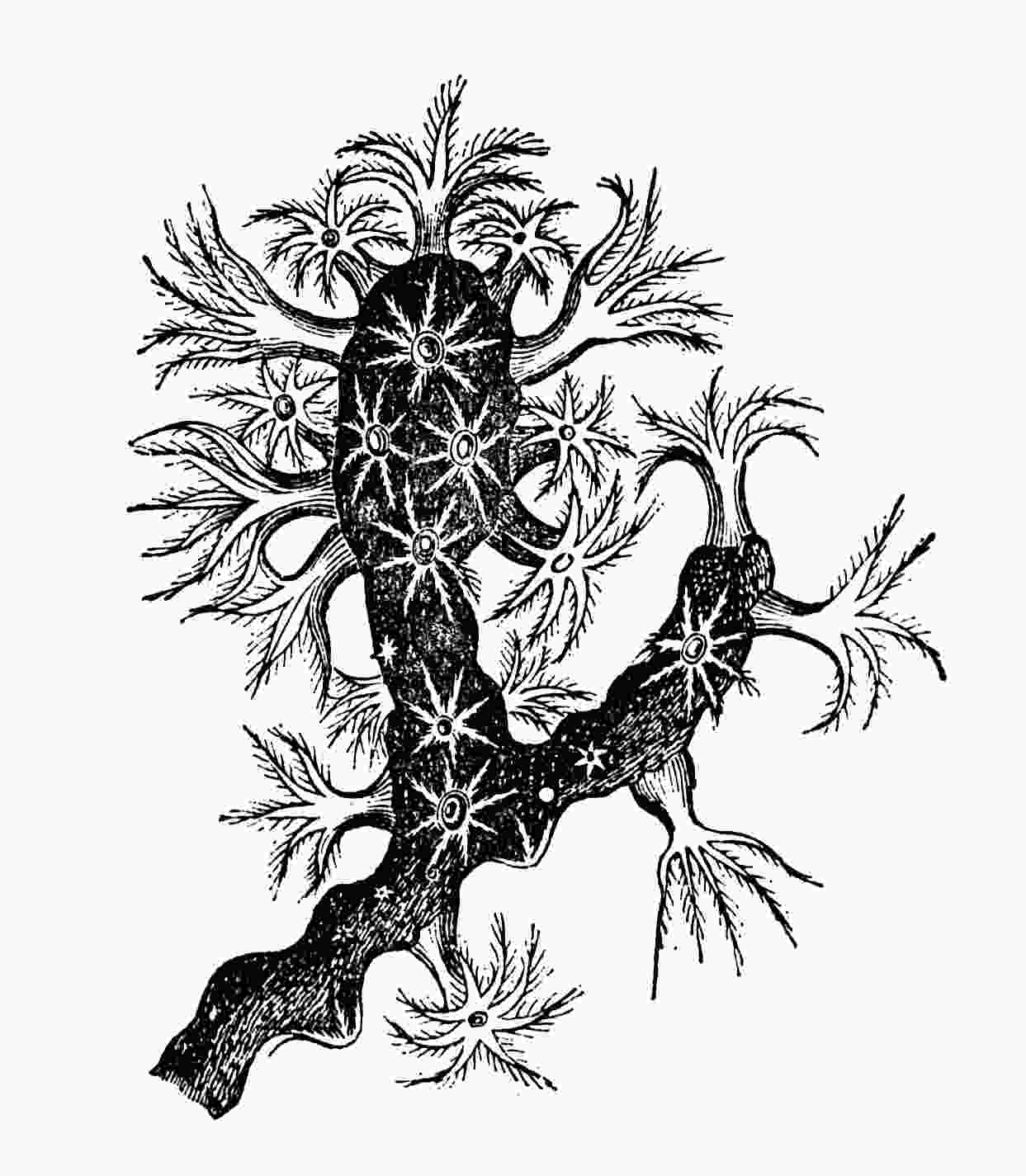 さんごの群体
例
さんごの群体
例えば「さんご」の虫なども、
初め
卵から生ずる時は
一匹であるが、しだいに
芽生してしまいに
樹枝状の
群体となり終わる。そのありさまを人間にくらべて見たならば、あたかも一人が
椅子に
腰をかけていると、その人の
腰の
辺から横に
芽が生じ、それが少しずつ大きくなり、しまいに
完全な
成人となって、
隣の
椅子に
腰をかけ、またその人の
腰の
辺から横に
芽が生えて、三人、四人としだいに人数が
増加して行くごとくである。かようにして生じた
群体では
一個一個の身体は
互いに
連続していて、同じ
血液が全部に
循環し、同じ
滋養物が全部に分配せられるから、生活上には全部があたかも
一匹の動物のごとくに
働き、
各個体が
互いに
相争うということはない。
仮に
甲乙二
個体の中間のところへ
餌になる物が流れ
寄ったとしても、
甲か
乙か近いほうが
静かにこれを
捕えて食うだけで、引っぱり合うて
争うごときことはけっしてせぬ。ただし
甲が食うても
乙が食うても、その消化した
滋養分は
隣から
隣へと流れて
順々に分配せられるから、
初め
相争うて食う
必要はない。このような動物では
生存競争における
単位は
一匹ずつ
相離れた
個体ではなく、多数の
個体の集まった
群体である。したがって、
生存のために
相戦うにあたっては
必ず
群体と
群体とが
対抗し、
各個体は、ただ自分の
属する
群体の
戦闘力を
増すために
同僚と力をあわせて
必死に
働くだけで、
隣の者と
相争うごときことは
絶対にない。
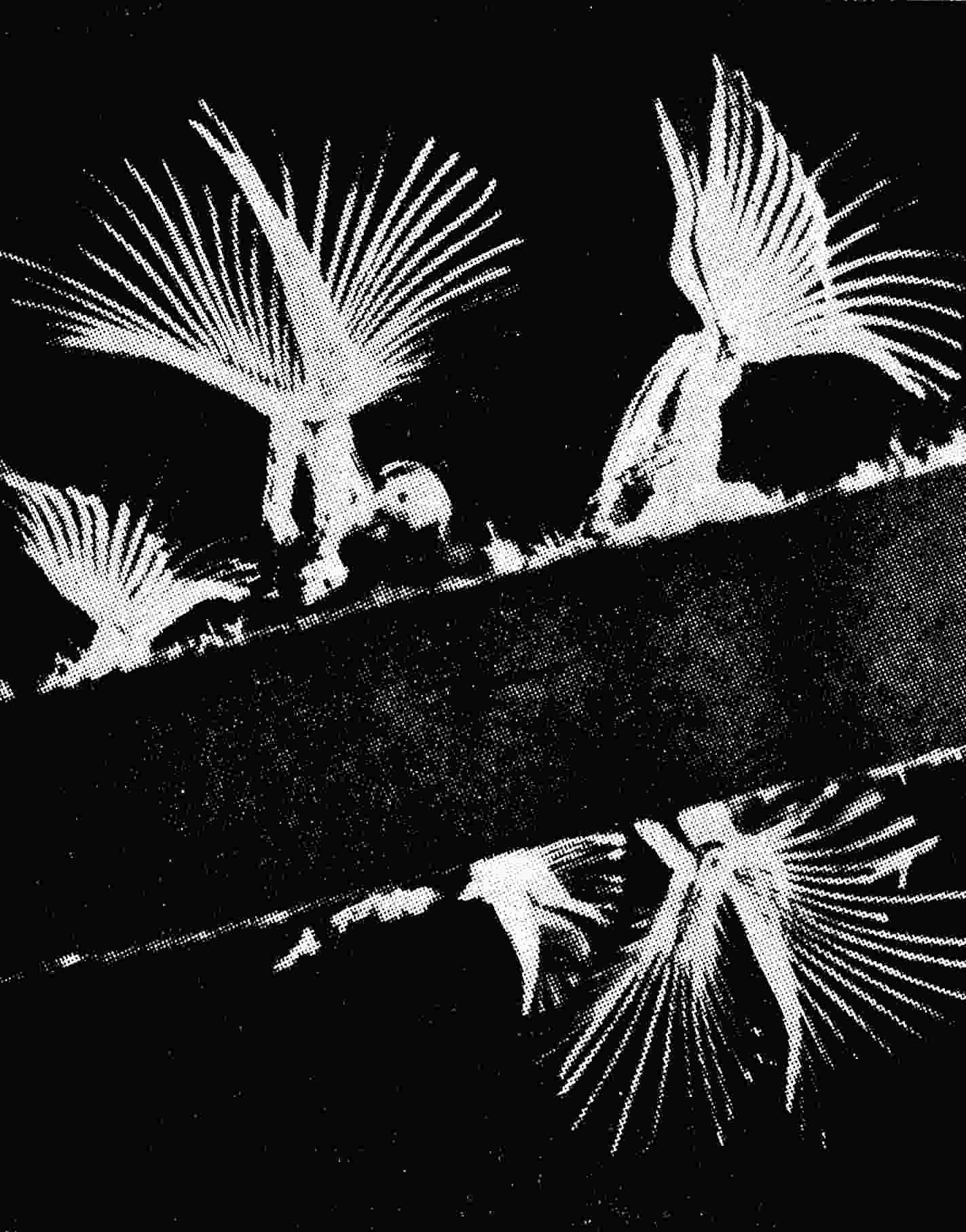 淡水こけむし
海産
淡水こけむし
海産の
固着動物にはかような
例がたくさんにあるが、
淡水の池や
沼に
棲む「こけむし
類」なども、生活の
状態は全くこのとおりで、実に理想
的の
団体生活を
営んでいるということができる。
身体の
互いに
連続している動物の
群体では、上に
述べたごとき
団体的生活が
完全に行なわれるのがあたり前のように思われるが、
個体が
一個一個相離れている動物にも理想
的の
団体生活を
営んでいるものがある。
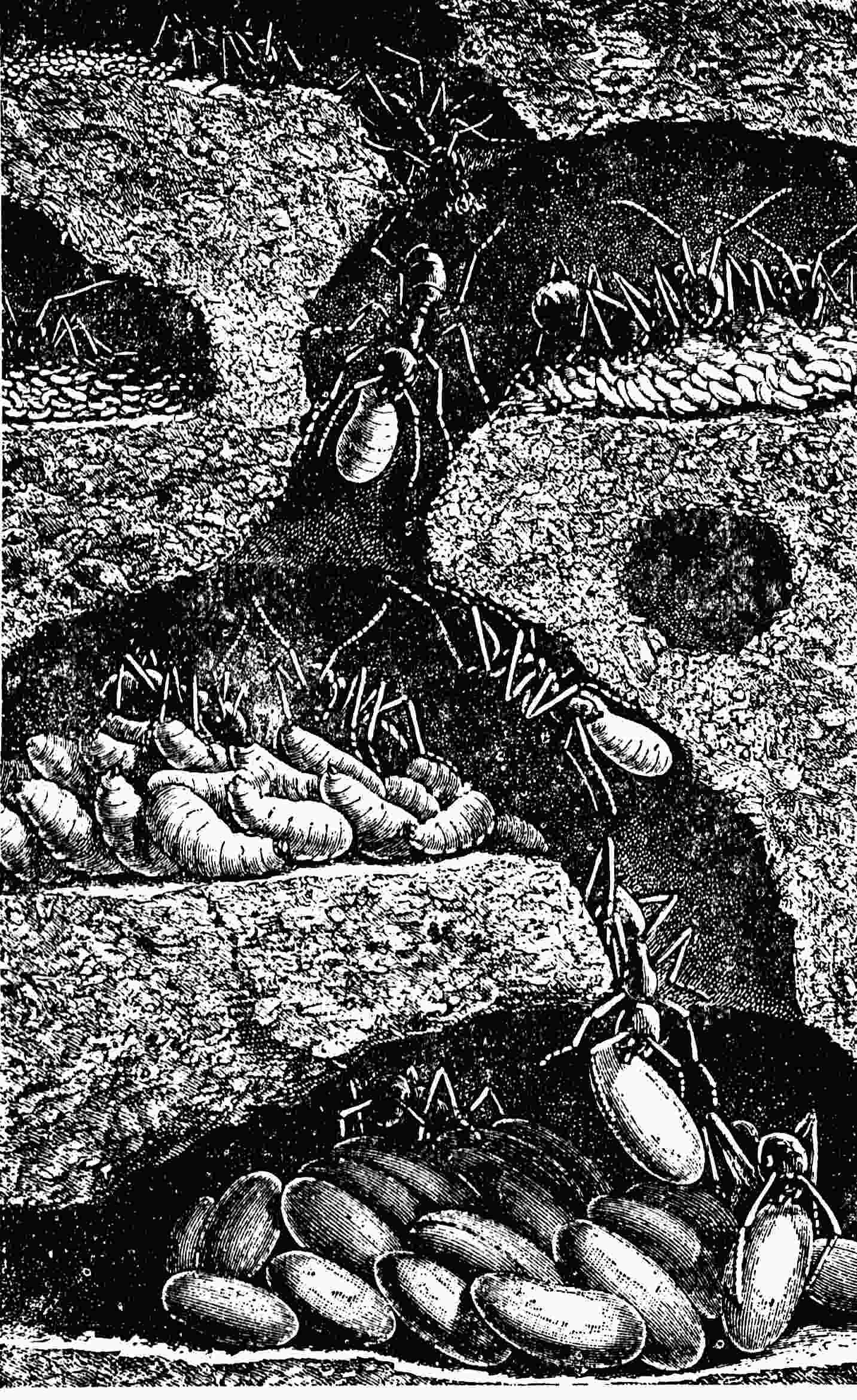 ありの巣
昆虫
ありの巣
昆虫の中の
蜜蜂、
蟻、
白蟻などはそのいちじるしい
例であるが、これらにおいても、
各個体がただ
自己の
属する
団体の
維持と
繁栄とのためにのみ力を
尽す点は、身体の
連続した
群体に
比して少しも
相違はない。かような
個体の集まりを社会または国と名づける。
蜜蜂でも
蟻でも
白蟻でも数千数万もしくは数十万の
個体が、力をあわせて
共同の
巣をつくり、
餌を集めるにも
敵を
防ぐにもつねに
一致して活動する。外へ出て
餌を
求めるものは朝から
晩まで出歩いて
熱心に勉強し、とられるだけは集めてくるが、これはむろん自身
一個のためではない。また
巣の内にとどまって、子を育てるものは、あるいは
幼虫に
餌を食わせたり、
蛹をあたたかいところへ
移したりして
一刻も休んではいない。
蜂や
蟻の
卵から出た
幼虫は小さな
蛆のようなもので、足もなく
眼も見えず
捨てておいてはとうていひとりで生活はできぬから、係りの者が毎日その口に
滋養物を入れてまわる
必要があって、これを育てるにはなかなか手数がかかる。また
敵を
防ぐにあたっては、
各個体は始めから命を
捨てる
覚悟でいる。
蟻も
蜂も
腹の
後端に
鋭い
針を
備え、かつ
一種の
酸を
分泌して
針で
注射するから、
刺されるとすこぶる
痛いが、
蜜蜂などが他のものを
刺すと、
針は相手の
傷口に
折れ
込み根元からちぎれるゆえ、一度
敵を
刺した
蜂は
腹の後部に大きな
傷口ができて、そのため命を落とすにいたる。しかし、自身の死ぬことによって、自身の
属する社会を
敵から
防ぐことにいくぶんかでも
貢献することができる場合には、
蟻や
蜂は少しも
躊躇せず直ちに
難におもむいて命を
捨てるのである。
徴兵忌避者の多い人間の社会にくらべては実に
愛国心が理想の
程度まで
発達しているごとくに見えるが、これがみなその虫の持って生まれた
本能の
働きである。
動物の中にはたくさんの
個体が集まって多少
共同の生活を
営みながら、
蟻や
蜂ほどに
完結した社会をつくるにはいたらぬものがいくらもある。
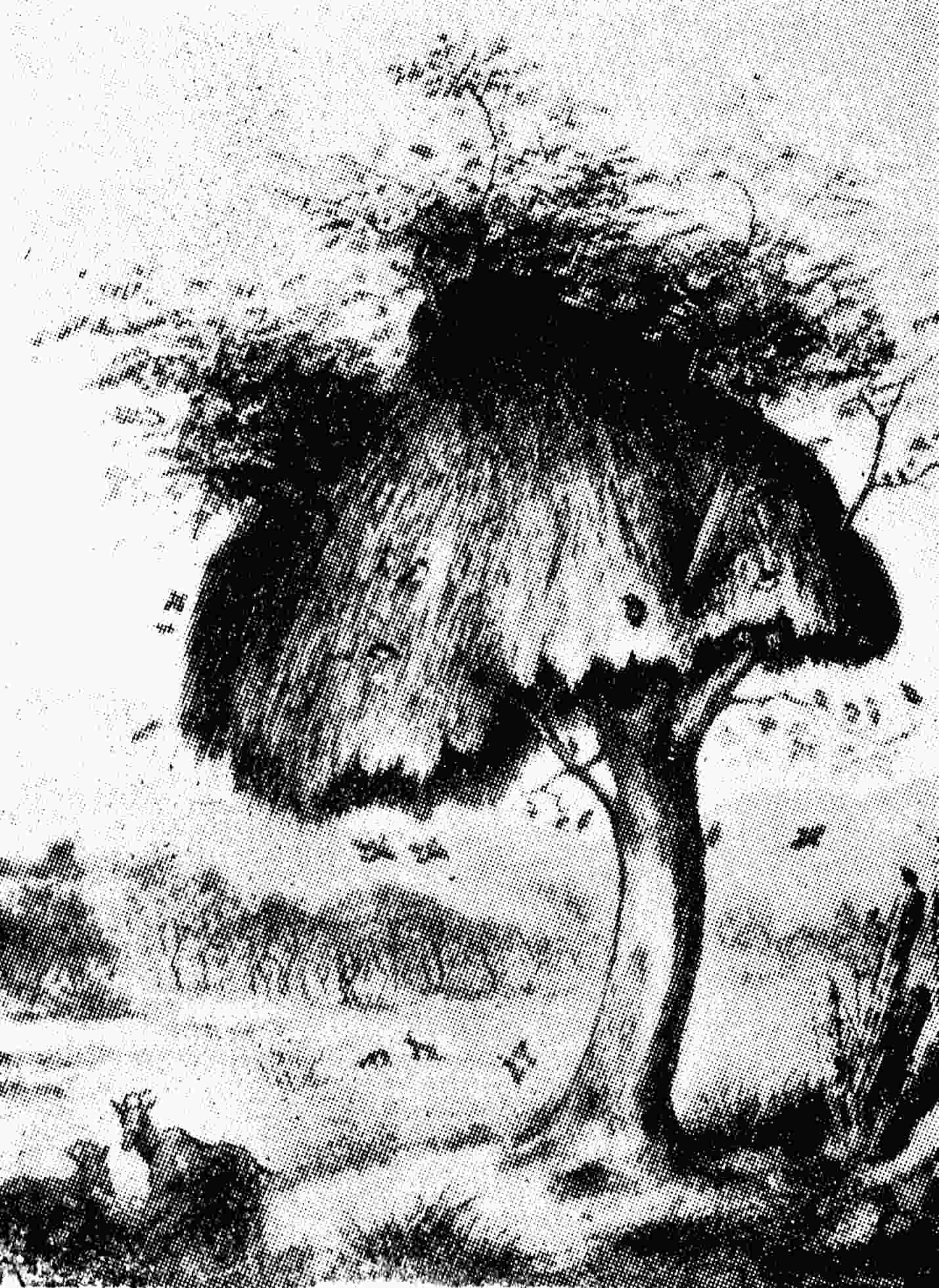 鳥類の共同の巣
鳥類の共同の巣
アフリカのある地方に
産する
鳥類の
一種に、
八百匹ないし
千匹も集まって
樹木の上に
共同の屋根をつくり、その下に一組あてで
巣をこしらえるものがある。ただしこれは風雨に対して
巣を守るために力をあわせるだけで、
一匹が
危険に
遇うた場合に他のものがこれを助けるというまでにはいたらぬ。されば、「
共和政治鳥」という
俗称がつけてはあるが、
大統領を
選挙して
政治を
委ねるらしい
形跡は見えぬ。また前に
例にあげた
海狸などは、多数集まって
働いている時には
必ず番をする役のものがあって、
危険のおそれがあれば、直ちに平たい
尾で水面を打って
相図をすると、その
響を聞いてみな
残らず水中へ
飛び
込んで
逃げてしまう。かような
団体はすでに多少の
組織が
備わって、事実
互いに
相助けているから、もはや社会という名を
冠らせてもよろしかろう。「おっとせい」や「あしか」などが、多数岸に上がって
眠る場合にもこれと同様のことをする。野牛の
団体については前にも
述べたが、
象のごときも
群をなして森の中を進む時には、
必ず強い
雄が
周囲を
警護し、
雌や
子供は中央の
完全なところを歩かせる。
猿の
類には
猩々などのごとく、
夫婦と
子供とで一家族をつくって生活しているものもあるが、また多数集まって
群居しているものもある。しこうして
群居している場合には、むろん
或る
程度までは
協力一致して
働くが、
個体の間には
必ずしも
争闘がないわけではなく、あちらでもこちらでも小さな
争いは
絶えず行なわれている。
猿の
群では、その中でもっとも力の強くもっとも
牙の大きな
雄が
大将となって
総勢を
指揮し、
強制的に全部を
一致させているが、
猿の
程度の
群集には生活上この仕組みがかえって
目的にかのうているように思われる。
以上二三の
例でもわかるとおり、動物の社会にもさまざまの
程度のものがあるが、
蜂や
蟻で見るごとき
完全な社会は
如何にして生じたかと考えるに、
比較的小さな
群集が数多く
相並んで
存在して
絶えずはげしく
競争したと
仮定すると、その
結果として
必ずかような
完結した社会ができ上がるべきはずである。
群集と
群集とが
相戦うときには、
協力一致する
性質の少しでもまさったほうが勝つ
見込みが多く、
特に味方のためには命をも
惜しまぬものの集まりと、
危難に
遇えば友を
捨てて
逃げ去るものの集まりとが
相対する場合には、前者の勝つべきはもちろんであるゆえ、これらの
性質のすぐれた
群集がつねに勝って
生存し、その
劣った
群集は
絶えず
敗けて
滅亡し、年月の重なる間にはますますこれらの
性質が進歩して、ついに今日
蜂や
蟻の社会に見るごとき
程度まで
発達したのであろう。されば
蟻の
勤勉も
蜂の
勇気もともに
生存に
必要なる
性質として、
自然淘汰の
結果、
次第次第に進み来たったもので、
一個体を
標準として見ると
損になる場合がしばしばあるが、その
属する
団体を
標準として見ると、むろん
極めて
有効である。すなわち
蟻の
挙国一致も、
蜂の
義勇奉公も、実は
団体が食うて
産んで死ぬために
必要なことで、
種族生存の
目的からいえば「
山荒し」が
棘を立て、「スカンク」が
臭気を放つのと同じ役に立っている。ただ同一の
目的を
達するために、それぞれ
異なった
手段を
採っているというにすぎぬ。
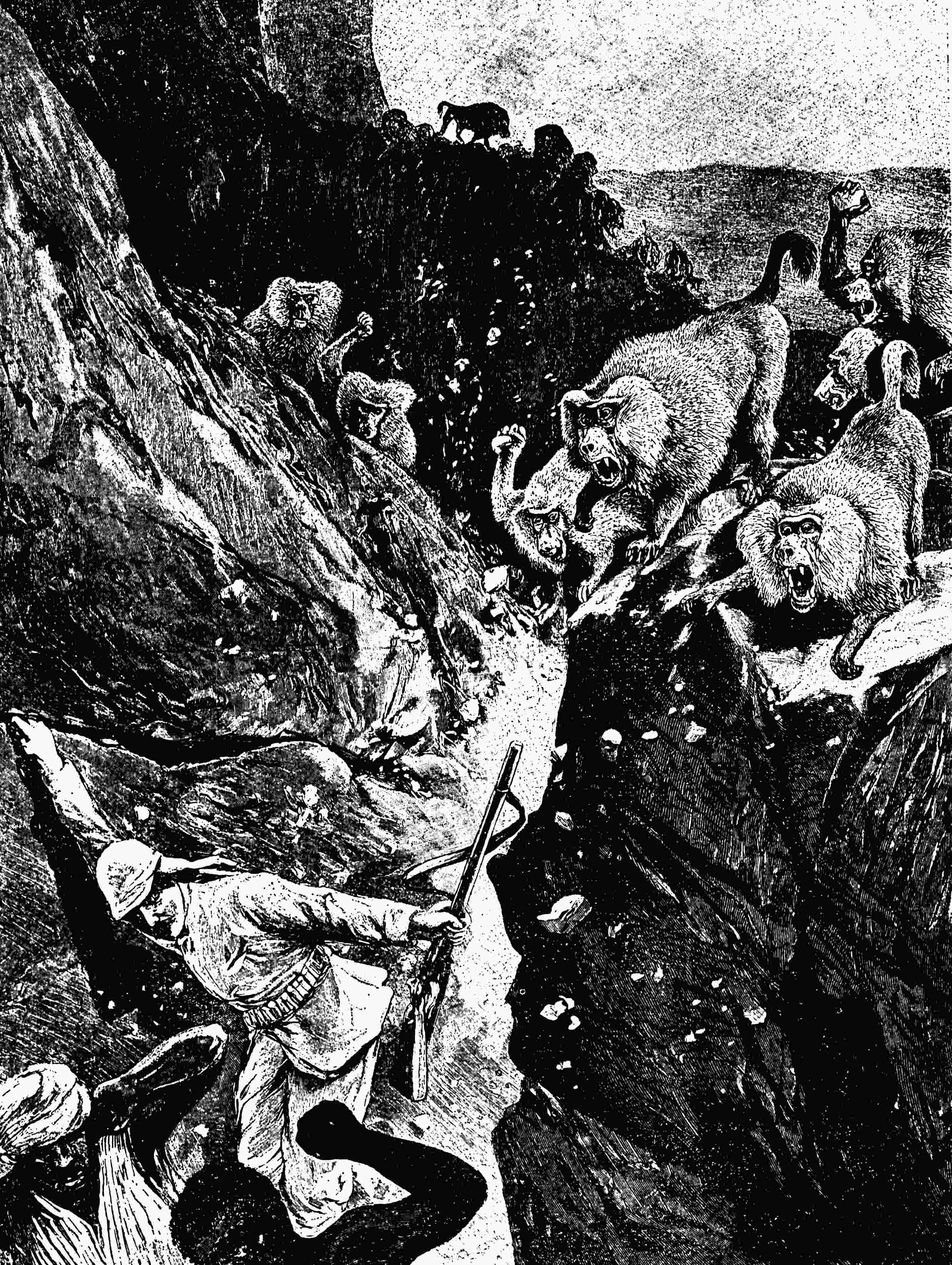
「ひひ」石を投ぐ
ひひの類は口吻突出せるをもって,横より見れば顔の形やや犬に似たり。鋭き牙をそなう。つねに岩石等の上に群居し,盛んに石を投げて敵を防ぐがゆえに容易に近づきがたし。図に示すはアフリカ産の一種なり。
社会が
完結すると同時に生ずることは分業である。身体の
連続した動物の
群体を見るに、
個体の
形状も
働きも全部一ようのものもあるが、
個体の間に分業が行なわれ、
分担の仕事がおのおの
専門に定まって、体の
形状もこれに
応じて
幾とおりか
区別のできるようになった
種類がすこぶる多い。
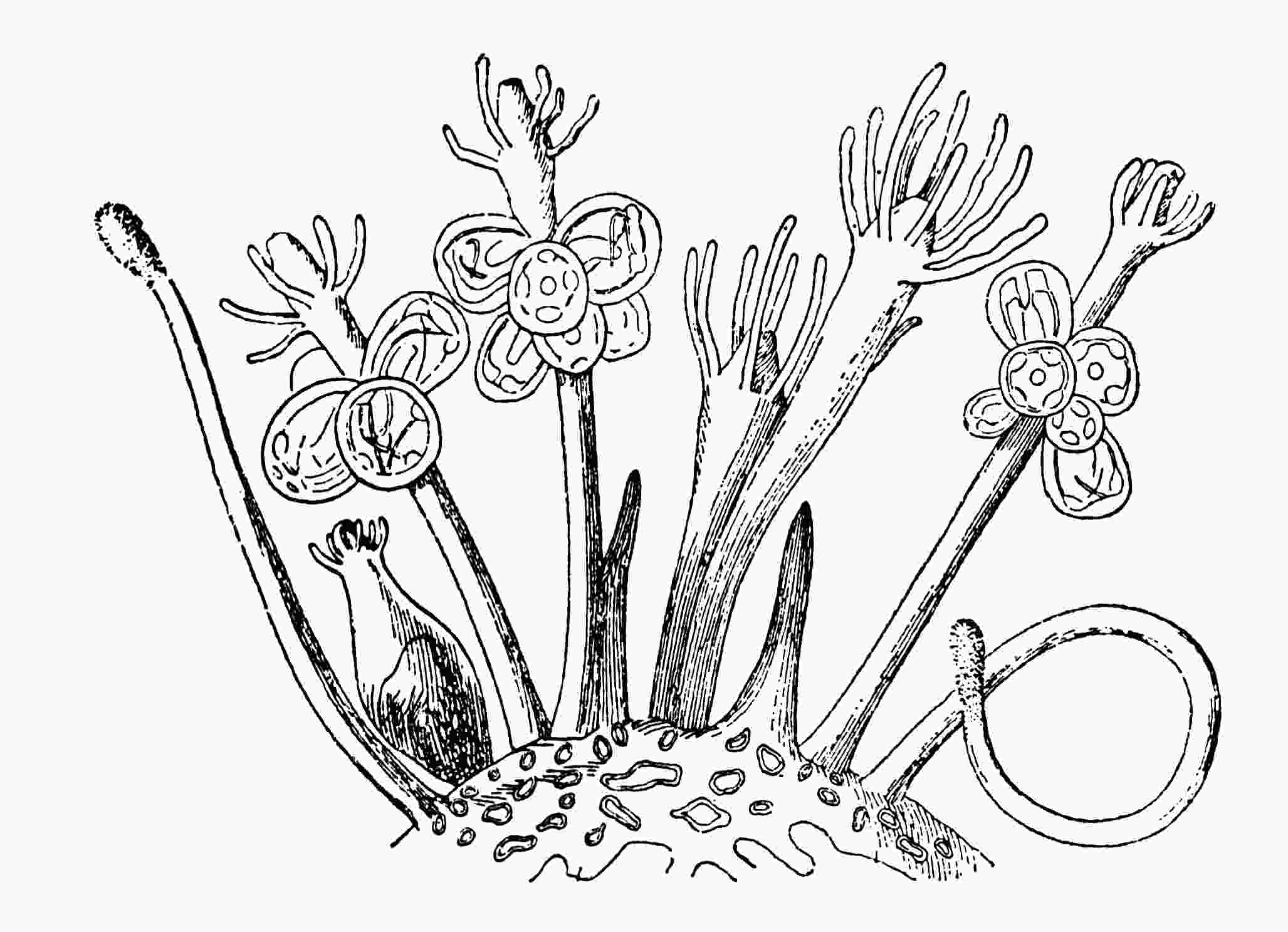
さんご類の分業
群体中の個体八匹だけを示す
左より一番目と八番目との個体は群体の防御を引き受けるもの。二番目,五番目,六番目の個体は餌を食うことを専門とするもの。三番目,四番目,七番目の個体は生殖をつかさどるもの。
淡水に
産する「こけむし」では一
群体内の
個体は形がただ一とおりよりなく、「さんご」などでも表面から見える
個体はみな形が
相同じであるが、「さんご」に
似た動物で、「やどかり」の
殻の外面に
付着した
群体をつくるものには
個体に
三種類の
別があって、
一種は食物を
捕えて食うことをつかさどり、
一種はただ
生殖のみを役目とし、他の
一種は
敵に対して
群体を
防御することのみをおのがつとめとしている。この動物の
構造は「ヒドラ」を数多く集めて、
尻のところで
互いに
連絡させ、これを
芝のごとくに一平面の上に広げたと
想像すれば、たいがいの見当はつくが、その「ヒドラ」のごとき形の
個体を調べて見ると、
触手も長く口も
発達して、
餌を食うに
適すると思われる形のものが多数を
占めている間に交じって、形がやや細く
触手も短いものがいくつもある。しこうしてこれらのものには、
必ず体の中央からあたかも
柿の木の
枝に
柿の実がなっているごとくに、小さな丸い実のごときものが
突き出しているが、これがすなわち
生殖の
器官で、
成熟すればその中から子が
游ぎ出すのである。一
群体の
内個体は、ことごとく身体が
互いに
連絡して
滋養分はいずれにも行き
渡るから、食物を
捕えて食う役目の
個体がよく勉強してくれさえすれば、
生殖をつかさどるほうの
個体は四方から十分に
滋養分を
得て、
盛んに子を
産みつづけることができる。
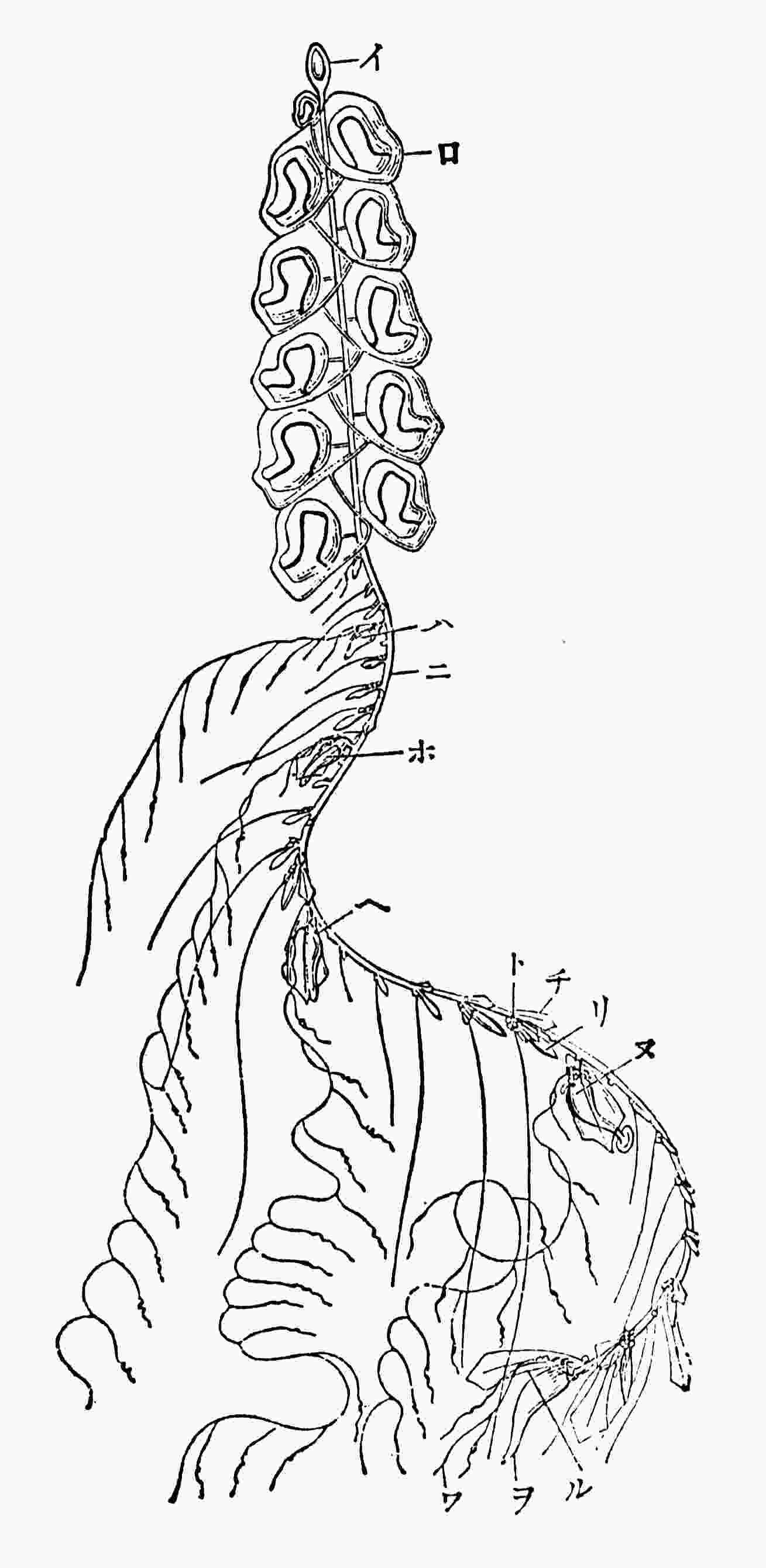
くだくらげ
(イ)浮子の役をつとめる個体 (ロ)運動をつかさどる個体 (ハ)食物を食う個体 (ニ)群体の中軸 (ホ,ヘ)保護する個体の蔭に隠れたる食物を食う個体 (ト)生殖をつかさどる個体 (チ)保護する個体 (リ)食物を食う個体 (ヌ)保護する個体の隠に物を食う個体の隠れたるところ (ル)保護する個体 (ヲ)食物を食う個体 (ワ)触手の糸
群体内で
個体の間に分業の行なわれているもっともいちじるしい
例は、おそらく「くだくらげ」と名づける動物であろう。これもその
構造は、あたかも数多くの「ヒドラ」を
束にしたごときものであるが、分業の
結果各個体の
形状にいちじるしい
相違が生じ、すべてが
相集まって
初めて
一匹の動物をなせるかのごとくに見える。すべて「くだくらげ」の
類は
群体をなしたままで海面に
浮かんでいるが、その
中軸として一本の
伸縮自在の糸を
備え、この糸に、「ヒドラ」のごとき
構造の
個体が列をなして
付着しているものが多い。しこうしてこの数多い
個体の間にはほとんど
極度までに分業が行なわれ、
各個体は自身の
分担する
職務のみを
専門につとめ、そのためそれぞれ
特殊の
形状を
呈して、中にはその一
個体なることがわからぬほどに
変形しているものさえある。まず
中軸なる糸の
上端のところには、中にガスを
含んだ
嚢があって
浮子の役をつとめているが、ていねいに調べて見ると、これも
一匹の
個体であって
全群体を
浮かすことだけを自分の
職務とし、それに
応じた
形状を
備えて他の作用はいっさいつとめぬ。次に
透明なガラスの
鐘のごときものが
数個並んでいるが、生きているときはこの
鐘がみな「くらげの
傘」のごとくに
伸縮して水を
噴き、その反動によって
全群体を
游がせる。もっとも一定の方向に進行せしめるわけではなく、
単に同じところにとどまらぬというだけであるが、
浮游性の
餌を
求めるには、これだけでも大いに
効能がある。それより下の部には、木の葉のごとき形のものがところどころに見えるが、これは他の
個体を自分の
蔭におおい
隠して
保護することを
専門のつとめとする。前の
鐘形の物と同じく、これもそれぞれが
一個体であってその発生を調べると、
初め「ヒドラ」と同じ形のものが、
次第に
変形してついにかようになったのである。木の葉の形の物の
蔭から
延び出ているのは、食物を食うことを
専門とする
個体で、
形状はまず「ヒドラ」と同じく
円筒形で、その
一端に口を
備えている。ただし「ヒドラ」とは
違うて口の
周囲に
触手がない。さすが食うことを
専門とするだけあって、
極めて大きく口を開くことができて、時とするとあたかも
朝顔の花の開いたごとき形にもなる。またこれに交じって指のような形で口のない
個体があるが、これは物に
触れて感ずることをつとめる。そのそばからは一本長い糸が
垂れているが、これはすなわち
伸縮自在の
触手であって、その先には
敵を
刺すための
微細な
武器が
塊になってついている。「くだくらげ
類」にはげしく
刺すものの多いのはそのためである。この
類は水中で
触手を長く
延ばし、
浮游している動物に
触れると、この
武器を用いて
麻酔粘着せしめ、
触手を
縮めて物を食う
個体の口のところまで近づけてやるのである。そのほか、
別に
生殖のみをつかさどる
個体がところどころにかたまっているが、これは大小の
粒の集まりで、あたかも
葡萄の
房のごとくに見える。「くだくらげ」の一
群体はかように
種々雑多に
変形した
個体の集まりで、
各種の
個体は生活作用の一部ずつを
分担し、
餌を
捕える者はただ
捕えるのみで、これを食う者に
渡し、食う者はただ食うだけで、
餌が口のそばに
達するまで待っている。
浮く者は
浮くだけ
游ぐ者は
游ぐだけの役目を引き受けて、他の仕事は何もせず、木の葉の形した
個体のごときは、
単に他のものに
隠れ場所を
与えるだけで、ほとんど何らの生活作用をもなさぬ。
各個体の
構造がみな一方にのみ
偏しているありさまは、これを人間に
移したならば、あたかも口と
消化器のみ
発達して、手も足もない者、手だけが大きくて他の体部のことごとく小さな者、
眼だけがむやみに大きな者、
生殖器のみが
発達して
胴も頭も小さな者というごとき
奇形者ばかりを
紐で
珠数つなぎにしたごとくであるが、これが全部力をあわせると何の
不自由もなしに
都合よく生活ができるのである。
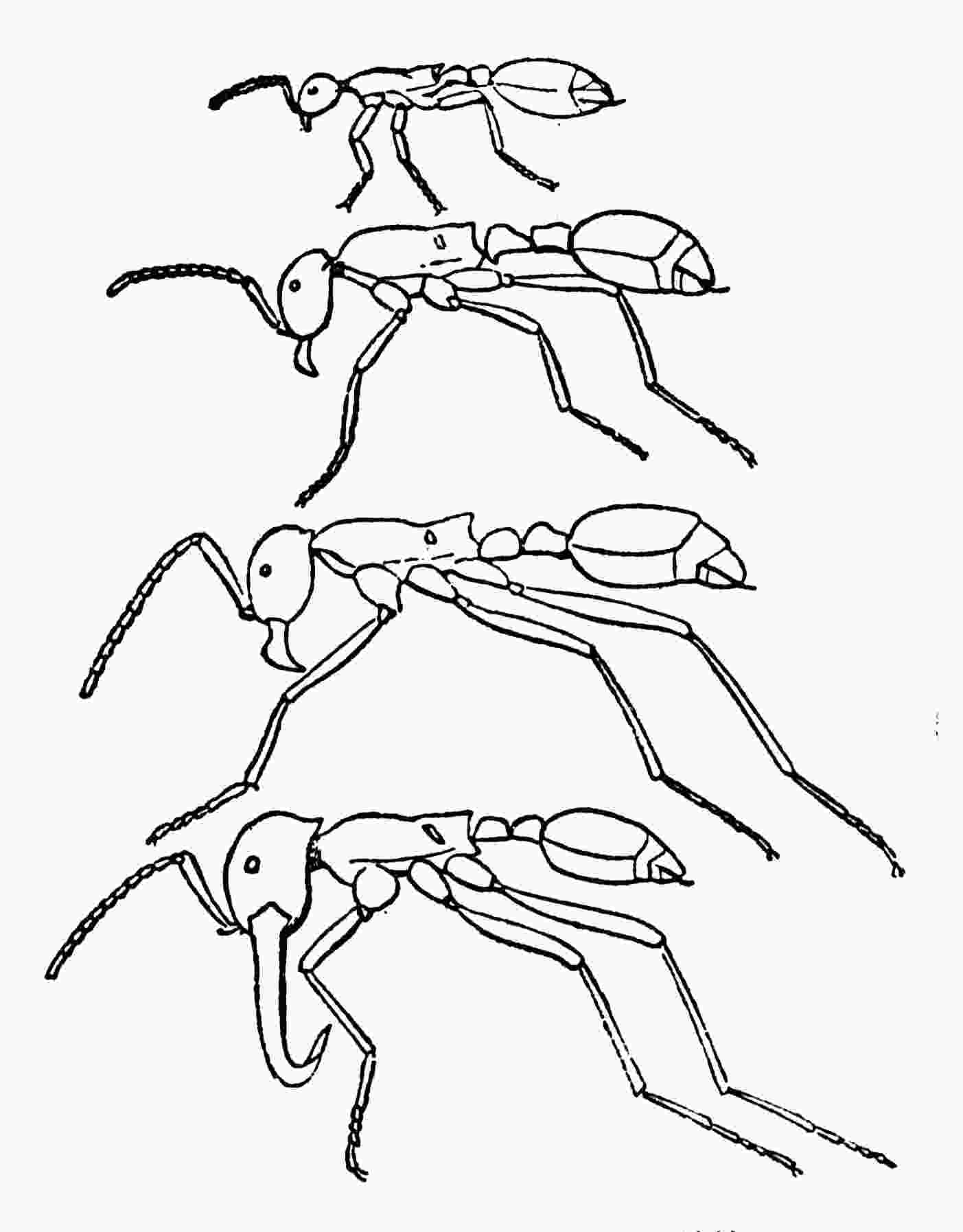 同一の種類に属ししかも形状を異にする働き蟻4種
個体
同一の種類に属ししかも形状を異にする働き蟻4種
個体が
一個一個に
離れながら社会をつくって生活する動物にも分業の行なわれているものが多い。
蜜蜂のごときものでも、
生殖をつかさどる
雌蜂雄蜂のほかに、
巣の内外のすべての仕事を一手に引き受けて
働く
働き
蜂というものがあって、
個体の
形状が
三種類になっているが、
蟻の
類ではさらに分業が進んで、
個体の
形状にも
種類の数がふえている。
雌蟻、
雄蟻のほかに
働き
蟻のあることは
蜂と同じであるが、
働き
蟻の中にまたさまざまの
分担が行なわれ
形状の
異なったものが
幾種類もある。地面に少し
砂糖を
散らして多数の
蟻の集まって来たところを見ると、
顎が
非常に大きく、したがって頭のいちじるしく大きなものが
普通の
働き
蟻に交じつてところどころにいるが、これは
兵蟻というて、
特に
敵に対して自分の
団体を守ることを
専門とする
働き
蟻である。また
普通の仕事をする
働き
蟻の中に
猫と
鼠ほどに大きさの
違う二組を
区別することのできる
種類もある。
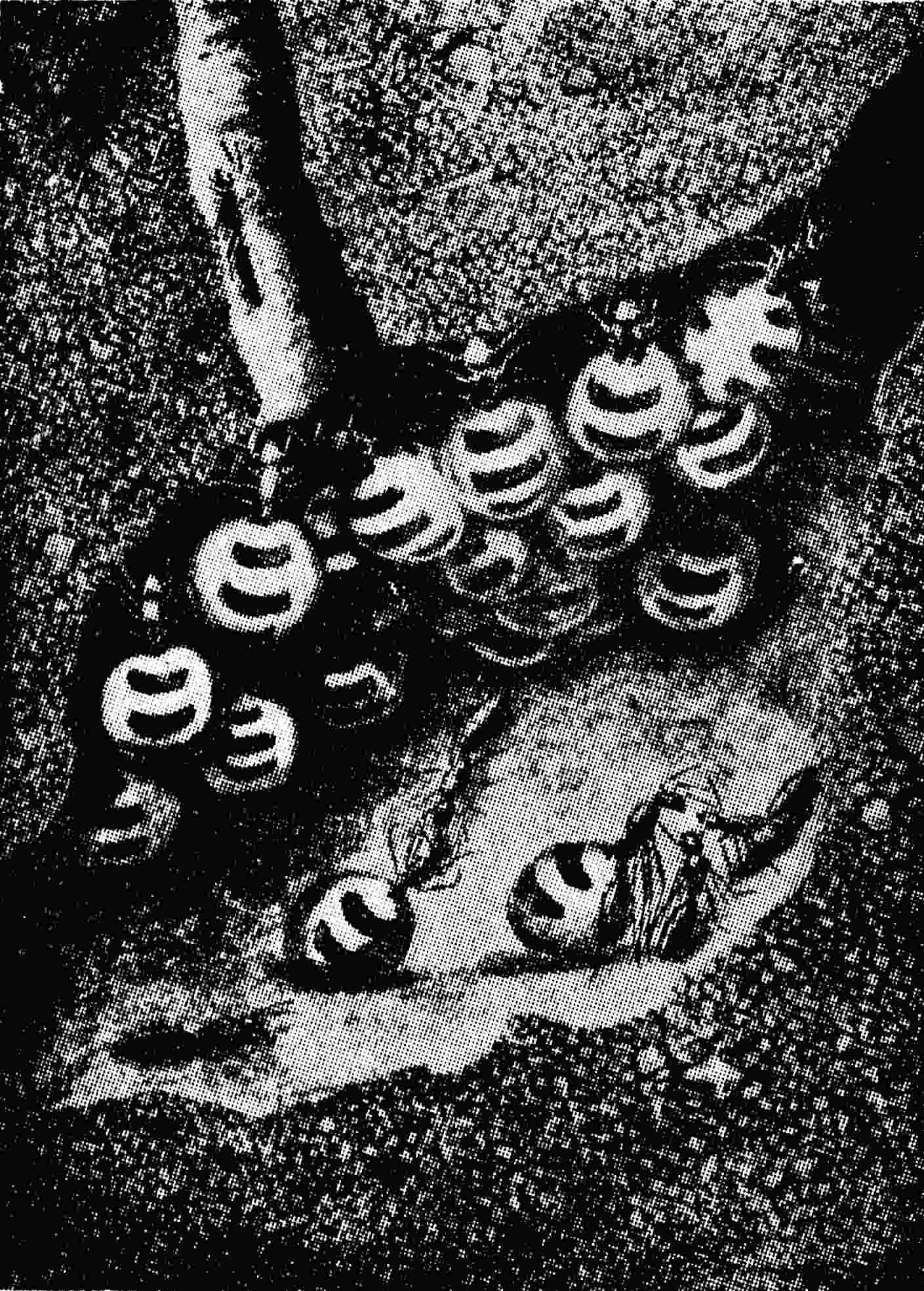 壺蟻
壺蟻
これらはどこの国でも見かけることであるが、北アメリカのメキシコに
産する
蟻の
一種では、
働き
蟻の中の
若干のものは、ただ
蜜をのみ
込んで
腹の中に
貯えることだけを
専門の役目とし、生きながら
砂糖壺の代わりをつとめる。他の
働き
蟻の集めて来た
蜜をいくらでも引き受けてのみ
込むから、身体の
形状もこれに準じて
変化し、頭と
胸とは
普通のものとあまり
違わぬが、
腹だけは
何層倍にも大きくふくれてあたかもゴム
球のごとくになっている。しこうして活発に運動することはもちろんできぬゆえ、ただ足で
巣の
壁に引きかかって
静止しているが、その
何匹もならんでいるところを見ると、
棚の上に
壺がならべてあるのと少しも
違わぬ。
蜜の
入用が生ずると、他の
働き
蟻がこの「
壺蟻」のところへ来て、その口から
一滴ずつ
蜜を受け取ってゆくのであるから、
働きにおいても
棚の
砂糖壺と全く同じである。前に
述べた「くだくらげ」のガス
嚢でもこの「
壺蟻」でもそれぞれ
一匹の
個体でありながら、
単に物をいれる
器としてのみ用いられているのであるから、
個体を
標準として考えると何のために生きているのか、ほとんどその
生存の
意義がないごとくに見える。しかし
団体を
標準として考えると、かような
自我を
没却した
個体の
存在することは、その
団体の生活には
有利であって、かかるものが
加わっているために
全団体が
都合よく食うて
産んで
生存しつづけ
得るのである。
団体と
団体とが
競争する場合には一歩でも分業の進んだもののほうが勝つ
見込みが多いから、長い年月の間には
次第に分業の
程度が進んで、しまいに
浮子の代わり
壺の代わりなどを
専門につとめる
個体までができたのであろう。
単独に生活する動物では
成功すれば自身だけが
利益を
得、
失敗すれば自身だけが
損害をこうむるのであるから、
笑いたいときに
笑い、
泣きたいときに
泣くのも勝手であるが、多数
相集まって力をあわせ
敵に当たる場合には大いに
趣が
違い、つねに
全団体の
利害を考えて、
各自の
挙動を
加減しなければならぬ。
笑いたいときにも、もし自分の
笑うことが
団体にとって
不利益ならば、
笑わずに
堪えていなければならず、
泣きたいときにも、もし自分の
泣くことが
団体のために
不利益ならば、
泣かずに
忍ばねばならぬ。これがすなわちいわゆる
義務であって、
義務のために自由の一部を
制限せられることは、
団体生活を
営む動物のまぬがれぬところである。しかし
団体生活によって生ずる生活上の
利益は、この
損失を
償うてなおあまりあるゆえ、
種族全体の
利害からいえば、
個体の自由の
制限せられることはすこぶる
有望な方面に進み行くものと見なすことができる。「自由を
与えよ。しからざれば死を
与えよ」との
叫び声は
如何にも
壮快に聞こえるが、
絶対の自由は
団体生活をする動物には
禁物であって、もしこれを
許したならば、
団体は
即座に
分解して、
敵なる
団体と
競争することができなくなる。
団体内の一部の者が
暴威を
振うて
残りの者を
圧制するために、
個体間に
反抗の
精神が
盛んになって、自分の
属する
団体をも
呪うごとき者の生ずることは、その
団体の
生存上大いに
不利益であるゆえ、かかる場合に
圧制者に対して自由を
叫ぶもののあるのは
当然であるが、
団体生活をなす
以上は、
条件付きの自由よりほかに
許すことのできぬは
論を待たぬ。
群体をつくって生活する動物でも、
個体間にいまだ分業の行なわれぬ
種類ならば、
一匹ずつに
離しても
生存ができぬこともないが、いくぶんかでも分業が進んで、
個体間に
形状や作用の
相異なったものの生じた場合には、これを
別々に
離してはとうてい
完全な生活を
営むことはできぬ。
仮に大工と仕立屋と
百姓とが
一箇所に住んでいると考えれば、大工は三人分の家を
建て、仕立屋は三人分の
衣服を
縫い、
百姓は三人分の田を
耕して、三人ともに
安楽に
暮らせるが、これを一人ずつに
離したならば、大工も
縫針を持たねばならず、仕立屋も
肥桶をかつがねばならず、
極めて
不得手なことをもつとめねばならぬであろうから、
衣食住ともにすこぶる
不自由なるをまぬがれぬ。
個体間に分業の行なわれている動物を
一匹ずつに
離したならば、いつでもこれと同様な
不便が生ずる。人間ならばだれも身体の
形状が同じであるから、大工が
縫針を持ち、仕立屋が
肥桶をかつぐこともできるが、
群体をつくる動物では、
各個体の
形状構造がそれぞれその受持ちの役目に
応じて、
変化しているものが多いゆえ、
一匹ずつ
離してはとうてい一日も生活ができぬであろう。
例えば、「くだくらげ」の
群体をばらばらに
離したと
仮定すると、
鐘形の
個体は
游ぐだけで
餓死し、
葉状の
個体は
蔭に
隠れるものがないから何の役にも立たず、物を食う
個体は口を大きく開いていても
餌をくれるものがなく、
触手は
餌を
捕えて
収縮してもこれを持って行く先がない。かような動物では
種々の
個体が集まって、始めて
完全な生活ができるのであるから、
個体は
互いに
離れることができぬ。しこうして他と
離れることができぬということはすでに大なる
束縛である。
蜜蜂や
蟻の社会では
個体の身体は
相離れているが、
各自分担が定まってみなそろわねば
完全な生活ができぬという点では、「くだくらげ」と同様である。
雌蜂、
雄蜂だけでは
卵を
産むだけはできても、これを
保護する
巣もつくれず、
卵から
孵化した
幼虫を
養育することもできぬ。また
働き
蜂だけでは子が生まれぬから一代
限りで
種族が
断絶する。
働き
蟻のほうでもこれと同様であるが、メキシコ産の
壺蟻のごときにいたっては、
一匹ずつに
離しては全く
生存の
意義がなくなる。されば
蜂でも
蟻でも、ただ
自己の
属する
団体のためにのみ力をつくすように
束縛せられているのである。ただし、「くだくらげ」でも、
蜂、
蟻でも
各個体は事実上かように
束縛せられてはいるが、これを人間社会で用いる
普通の意味の
束縛と名づくべきか
否かはすこぶる
疑わしい。
何故というに、
束縛といえば
必ずその反対に自由のあることを予想する。自由に動きたがるものに、
制限を定めることがすなわち
束縛であるが、
束縛せずともそれ
以外のことをなさぬものに対しては
束縛という文字は当てはまらぬ。くだくらげでも
蜂、
蟻でも長い年月の
団体的競争を
経て、
自然淘汰の
結果今日のありさままでに
達したのであるから、
各個体の
神経系は、ただ
団体のためにのみ力を
尽くす
本能が
現われるように
発達して、生まれながらに
団体に
有利なことのみを行なうのである。
蟻が終日
働くのは
怠けたいところをつとめて
働くのではなく、
働かずにいられぬ
性質を持って生まれたゆえに
働くのである。
蜂が
敵を
刺すのは、
自己の
属する
団体の
危険を知り、大切なる命をも
捨ててかかるわけではなく、
敵がくればこれを
刺さずにはいられぬ
性質を生まれながら
備えているゆえである。かような
次第で、
各個体は自身の役目だけをつとめる
天性を持って生まれ、
相集まって
団体をつくっているのであるから、そのつとめ
以外のことは
特に
禁ぜずとも行なうことはない。したがって
禁ぜられても少しも
束縛とは感ぜぬ。あたかも
胃が
呼吸を
禁ぜられ
肺が消化を
禁ぜられても
束縛とは名づけられぬのと同様である。
かように
論じて見ると、
団体生活のために
個体の行動を
束縛せられるのは、ただ同一の
目的のために力をあわせて
働く
群集、もしくは
低度の社会だけである。
単独生活を
営む動物は何の
束縛をも受けぬ。もっとも魚が水より出られぬとか、
蛙が海を
渡れぬとかいうごとき、
天然の
束縛はむろんあるが、その他の
束縛は少しもない。「さんご」や「こけむし」のごとき
群体をなす動物では
個体の身体がみな
互いに
連絡し、
全群体があたかも
一匹のごとくに生活して、
各個体はただその一部分として
働くゆえ、また
特に
束縛と名づくべきことは起こらぬ。また
蟻や
蜂の社会では、
各個体の
神経系がただ
団体生活にのみ
適するように
発達し、身体は
相離れていても生活上には
各社会が全く
完結して、あたかも
一個体のごとくに
働くゆえ、大なる
束縛が行なわれていながら、何らの
束縛ともならぬ。ただ多くの
鳥類、
獣類の
群集のごとき場合には、
各個体には
個体を
標準とした
生存競争に勝つべき
性質が
発達し、これが
相集まって力をあわせんとつとめているのであるから、
各個体には自分を中心とした
欲があり、他と力をあわすには多少この
欲を
押さえねばならぬ。
団体をなして生活するために
各個体が行動を
束縛せられるのはこのような
類に
限ることである。
束縛のないところでは
束縛を
破るものもなく、したがって
制裁を
加える
必要も起こらぬが、
鳥類、
獣類のごとき、
各自勝手の
欲情をそなえたものが
群集をつくって
共同の生活をしているところで、もし
一匹のものが、自分
一個の
欲情のために
全団体に
不利益な
行為をした場合には、これに
制裁を加えねばならぬ。
団体生活をなす動物が
全団体の
利害を
標準として自分
一個の自由の一部を
犠牲とするのはその
個体の
義務であるが、
団体の一員として、
団体生活より生ずる
利益にあずかり
得ることは、これに対する
権利である。されば
義務をつくさぬ者には
制裁として、その
権利を
剥奪すればよろしいのであるが、
団体をなす動物では、
自己の
属する
団体以外のものはみな
敵であるゆえ、
団体の一員たる
権利を
奪われたものは、
残余のものから
敵として
取扱われ、
衆寡敵せずしてとうてい
殺され終わるをまぬがれぬ。ただし
二個以上の
団体が
相対立して
競争している場合には、
各団体ともにその内の員数の
減ることは、
戦闘力を
減少するから大いにいましむべきであるゆえ、
単に
折檻を
加えて
将来を
誡めるだけで
殺さずにおくこともつねである。
猿類には
団体生活を
営む
種類がたくさんあるが、
各団体には力の強い
経験に
富んだ
牡が
大将となって全体を
指揮し、つねに
一致の行動をとるようになっている。
大将の
命にそむいた者はきびしく
罰せられ、
暫時はこれに
懲りて全く
温良な
臣民となる。ただし日数を
経る間には、また前の
刑罰を
忘れて、
大将の命に
従わぬようなことも生ずる。
 からすの巣
からすの巣
「からす」なども近所に
巣をつくるものの中に、
隣より
巣の
材料を
盗み来たったもののあることが知れると、多数集まってその
一匹の「からす」を
責め、かわるがわるつついてついにこれを
殺してしまう。これはただ
一例にすぎぬが、
共同の
目的のために力をあわせて
働く動物の
群集には、
必ず何かこれに
類することがある。
鳥類、
獣類ともにかような
習性を有するものはすこぶる多いが、多数の
個体が集まって組合をつくる場合には、その
秩序、
安寧を
保つためには何らかの
規約が行なわれなければならず、したがってこれを
破るものは組合から
制裁を受けねばならぬ。しこうして
制裁の
程度には軽重があって、
殺され終わるものもあれば、
半殺しぐらいで
免されるものもある。
以上述べたところから考えて見るに、大部の
道徳書や
複雑な
法典を所持しているものは、人間
以外の動物にはむろん
一種もないが、
義務、
権利、
規約、
制裁などの
芽生えのごときものは
種々の動物の
群集ですでに見るところである。また
善とか悪とか
良心とか
同情とかいう言葉も、かような
程度の社会には多少あてはまらぬこともない。これらの
関係は人間のごとき大きな
複雑な
団体では
種々の
事情のために
判然せぬようになっているが、
比較的小さな
団体がいくつも
相対してはげしく
競争している場合を
想像するともっとも
明瞭に知れる。
団体の一員である
以上は、
各団体はあるいは
戦線に立つかあるいは後方
勤務に
従事するかいずれかにおいて
奮闘し、
団体の
不利益になることはけっしてせぬようにつつしまねばならぬが、人間の社会で
善と名づけることは、これを小さな
団体で実行すればみな
戦闘力を
増すことのみである。また悪と名づけていることはみな
戦闘力を
減ずることばかりである。
例えば
同僚を
殺すことは悪というが、これは
戦闘力を
減ずる。
同僚の
危険を
救うことは
善というが、これは
戦闘力を
増す。
虚言は悪というが、これは
同僚を
誤らせて
戦闘力を
減ずる。正直は
善というがこれは
同僚互いに
信じて
戦闘力を
増す。一
個体が命を
捨てたために
全団体が助かればこれは
最上の
善であり、一
個体が
誤ったために
全団体が
亡びればこれは
極度の悪である。大きな
団体では、
自殺は
各個体の勝手のように思われるが、
百匹よりなる小
団体では
一匹が
自殺すれば
戦闘力が明らかに百分の一だけ
減ずるゆえ、悪と名づけねばならぬであろう。小さな
団体では
各個体の
行為が
全団体のために
有利であったか、
有害であったかが直ちに明らかに見えるゆえ、
善のほめられ悪の
罰せられる理由も
極めて
明瞭に知られ、
善のほめられずして
隠れ、悪の
罰せられずしてのがれるごときことはけっしてない。しこうして悪の
必ず
罰せられることを日ごろ知っておれば、自分がたまたま悪を
犯したときには、
罰ののがるべからざることをおそれてなかなか平気ではいられぬ。これがすなわち
良心ともいうべきものであろう。
小団体同志の間に
生存競争がはげしく行なわれ、
善を行なう
個体より
成る
団体はつねに
生存し、悪を行なう
個体より
成る
団体は
亡び
失せれば、しまいには
各個体が生まれながらに
善のみを行なう
団体が生じ、今日の
蟻、
蜜蜂のごとくに
善もなく悪もなく
良心もなく
制裁もなしに、すべての
個体がただ自分の
属する
団体のためのみに
働くものとなるであろう。これに反して
各団体がますます大きくなり、
団体間の
競争よりも
団体内の
個体間の
競争のほうがはげしくなれば、
善は
必ずしも
賞せられず、悪も
必ずしも
罰せられず、
規約は
破られ
良心は
萎靡して、
単独生活を
営む動物の
状態にいくぶんか近づくをまぬがれぬであろう。
生物の
生涯は食うて
産んで死ぬのであるが、食うて
産んで死のうとすれば
絶えず
敵と
戦わねばならぬ。しこうして
団体を
形造ることは
敵と
戦うにあたって、
攻めるにも
禦ぐにもすこぶる
有効な
方法である。身体の
互いに
連絡している
群体では、全部があたかも
単独生活を
営む一
個体のごとくに
働くが、
若干の
離れた
個体がいっしょに集まっていくぶんか力をあわせ
不完全な社会をつくり、
共同の
敵と
戦いながら食うて
産んで死のうとすれば、そこに
義務と
権利とが生じ、
是非と
善悪との
区別ができ、
同情も
良心も
初めて
現われる。
小団体の間にはげしい
競争の行なわれることが長くつづけば、
各団体はますます
団体生活に
適する方向に進歩し、その内の
各個体の
神経系も
次第に
変化して、生まれながらに
義務と
善と
同情とを行なわずにはいられぬものとなるであろうが、人間などのごとくに
団体が大きくなって、その間の勝負が急にかたづかなくなると、この方面の進歩はむろん止まってしまい、いったん
発達しかかった
同情愛他の心は、
再び
個体各自の
生存に
必要な
自己中心の
欲情のために
圧倒せられるようにならざるを
得ない。しかも
意識に
現われるところは
神経系の
働きの一小部分であって、その
根底はすべて
無意識の
範囲内に
隠れているゆえ、今日の人間の
所業には
善もあれば悪もあり、
同情もすれば
残酷なこともして、自分にも
不思議に思われるほどに
相矛盾したことが
含まれるであろう。
人類における
道徳観念は
如何にして起こり、
如何なる
経路を
経て今日の
状態までに
達したかは、もとより大問題であって、そのためにはずいぶん大部な書物もできているくらいであるから、むろん本書の中にかたわら
説き
尽くせるわけのものではない。それゆえここには生物全体について
以上簡単に
述べただけにとどめておく。
前章までは主として食うため食われぬために生物の行なうことを
述べたが、
何故食うこと食われぬことにかくまで力を
尽くすかといえば、これは子を
産み終わるまで生き
延びんがためにほかならぬ。されば食うことは
産むための
準備とも考えられるが、しからば何のために
産むかとたずねると、これはまたさらに多く食わんがためともいえる。
一匹が一代
限りではどれほども食えぬが、
繁殖して数多くなれば、それだけ多く食え、さらに
繁殖すればさらに多く食える。食うのは
産むためで、
産むのは食うためだといえば、いずれが
目的かわからぬようであるが、およそ生物の生活は他物をとって自体とするにあることを思うと、食うのも
産むのもそのためであって、けっして一方だけを
目的と見なすことはできぬはずである。言を
換えれば
個体の食うことと
産むこととによって
種族の生活が
成り立っているから、一方だけに
離しては生活を
継続することができぬ。他物を食うて
自己の身体に
加えれば、
自己の身体はむろんそれだけ大きくなるが、これがすなわち
成長である。しかしながら生物の
各種には
種々の
原因から、それぞれ
個体の大きさに定まりがあってこれを
超えることはできぬゆえ、さらに食うてさらに大きくなろうとすれば、数が
殖えるよりほかに
途はない。これがすなわち
繁殖である。かように考えると、
繁殖は
個体の
範囲を
超えた
成長であると言うてもよろしい。ただ一つ
不思議なのは
何故普通の動植物では
個体の
殖えるためには、まえもって男女
両性の
相合することが
必要かという点であるが、これについては今日もなお
議論があって
確かなことはいまだ知られていない。あるいは
老いたる
体質を
若くするためともいい、または生まれる子に
変異を多くするためともいい、その他にも
種々の
説がある。
著者自身はむしろ食うために
働いて古くなった
体質をさらに多く食うに
適した
若い
体質に
回復するためであろうという
説に
傾いているが、いずれにしても
生殖のために男女の
相合することは、
種族の
生存上何か
特に
有利な点があることだけは
疑いない。犬でも
猫でも
鶏でも
蚕でも世人の
普通に知っている動物にはみな
雌雄の
別があって、
生殖にあたっては
必ず
雌雄が
相合するゆえ、
生殖といえばすなわち
雌雄の
相合することであるごとくに考えるが、広く生物界を
見渡すと、
雌雄に
関係のない
生殖法もあれば、
雌雄の
別はあっても
雌雄相合するにおよばぬ
生殖法もある。しこうしてこれらの
相異なった
生殖法を
順々にくらべてゆくと、しまいには日ごろ
生殖とは名づけていない身体の
変化まで
達して、その間に
境を
設けることができぬ。されば
生殖の真の
意義を知ろうとするには、まず生物界に
現に行なわれている
種々の
生殖法から調べてかからねばならぬ。
雌雄異体とは
個体に
二種の
別があって、一方は
雄一方は
雌である場合をいう。
普通に人の知っている動物はほとんどみなかようになっている。人間をはじめ
獣類、
鳥類はもとより
蛇、「とかげ」、
亀、
蛙、および
魚類にいたるまで
脊椎動物はことごとく
雌雄異体である。また
日常人の目に
触れる
昆虫類、「えび」、「かに」の
類なども
雌雄は
必ず
別である。それゆえ
雌雄異体は動物の
通性のごとくに思われ、わざわざこれを
論ずる
必要がないかのごとくにも感ぜられるが、生物には
雌雄の
別のないものも少なくないゆえ、それらにくらべて
雌雄異体の動物にのみ
特に
備わっている
性質について考えて見よう。
個体に
雌雄の
別があって、その間に
生殖の行なわれる動物の中にもさまざまのものがある。
烏や
鷺のごとくに一見しては
雌雄の
別のわからぬものもあれば、
鹿や
鶏のごとくに遠くからでも
雌雄の
区別の
判然と知れるものもある。犬や
亀のごとくに
交尾して
暫時離れぬものもあれば、「うに」、「なまこ」などのごとくに
雌雄相触れずして
生殖するものもある。これらの
相違およびその生じた
原因については後の章に
述べることとしてここには
略するが、
雌雄異体の動物にはかように
相異なる
性質のほかに全部に通じた
肝要な点がある。それはすなわち
雌性の
個体は
卵細胞を生じ、
雄性の
個体は
精虫を生ずることであって、この一事に
関してはけっして
例外はない。
卵細胞を生ずる
個体ならば
如何なる
形状を
呈し、
如何なる
性質を
備えていてもこれは
雌であって、
精虫を生ずる
個体ならば
如何なる
形状を
呈し、
如何なる
性質を
備えていてもこれは
雄である。
雌雄異体の動物が
生殖する
際には、
雌の身体から
離れた
卵細胞と
雄の身体から
離れた
精虫とが
一個ずつ
相合して、新たなる一
個体の
基礎をつくる。しこうして
雌雄の身体
性質等に
相違のある場合には、これはみな
卵細胞と
精虫とを
相出遇わしめるため、または新たに生じた
個体を
保護し
養うためのものである。
雌雄両性による
生殖は、
種々の
生殖法の中でもっとも進んだもっとも
複雑なものであるが、
雌雄の間にいちじるしい
相違のある
種類では、さらにいっそう
働きが
複雑になっているゆえ、ただこれだけを見るとすこぶる
不思議に思われ、何か
神秘的の
事情が
含まれてあるかのごとくにも感ぜられる。しかしこれを他の
簡単な
生殖法にくらべて見ると、始めてその
理屈がやや
明瞭になってくる。そのありさまはあたかも人間だけを調べたのでは人間とは
如何なるものであるかがとうていわからぬが、他の下等動物と
比較して見ると、その
素性が明らかに知れるのと同じである。
卵細胞を生ずる
器官は
卵巣であって、
精虫をつくる
器官は
睾丸であるゆえ、
雌とは
卵巣を有する
個体、
雄とは
睾丸をそなえた
個体というて
差支えはない。一方は
卵巣を一方は
睾丸をそなえているというほかに何の
相違もない
雌雄は、外見上には少しも
区別ができぬ。「うに」や「なまこ」はこの
類に
属する。しかし
雄の身体から
離れた
精虫を
確実に
卵細胞まで
達せしめるには、これを
雌の身体の内へ
移し入れるのがもっとも
有効である。しこうして、
雄が
精虫を
雌の体内へ
移し入れる
器官は
交接器であるが、これを
備えた動物になると、
如何に
雌雄の
形状が
相似ていてもその部さえ見れば
容易に
区別することができる。犬、
猫などはこの
程度にある。なお
雌雄異体の動物には、
雌雄によって体形の
非常に
相違するものがあり、中には
雄と
雌とが
同一種の動物とは思われぬほどのものもあるが、これらについてはさらに後の章に
詳しく
述べるゆえここには
略する。
とにかく、
雌雄異体の
生殖は、すべての
生殖法の中でもっとも進んだもので、それだけ他にまさった
利益はあるに
違いないが、物には
必ず
損と
得とがあるもので、
雌雄異体の
生殖にもまた多少
不利益な点がないでもない。
例えばこの
類に
属する動物では、
一匹ずつ
離しておけば全く
生殖ができぬ。
仮に
一匹の
雌鼠が
鼠の
一匹もいない
離れ島へ
漂着したと
想像するに、もしその後他の
鼠が
漂流して来なかったならば一代
限りで死んでしまう。また
偶然第二回の
漂着者があったとしても、もしこれが同じく
雌であったならば、
二匹寄っても子を
遺すことはできぬ。
雌と
雌とが
出遇うても、
雄と
雄とが
出遇うても子を
産むことができぬゆえ、
雌雄異体の動物では、
二匹の
個体が
偶然相出遇うたときに子を
産む
機会は五
割により当たらぬ。それゆえ、新
領土に
種族を
分布するにあたっては、
雌雄の
別のあることはよほどの
損になる。もっとも同
種類の
個体が多数に
近辺にいる場合にはかような
不都合はむろん起こらぬ。
雌雄同体とは
一匹の
個体で
雌雄両性の
生殖器官をかね
備えていることである。
雌雄異体のものに
比べると、その
種類の数ははるかに少ないが、世人の
通常知っている動物の中にもいくつも
例がある。
「かたつむり」、「なめくじ」、「みみず」、「ひる」などはみな
雌雄同体であるが、その他「ジストマ」、
条虫のごとき
寄生虫も
一匹ごとに
両性の
生殖器を
備えている。これらの動物では、
一匹の身体の内に
睾丸と
卵巣とがあって
精虫と
卵細胞とが両方とも生ずるから、場合によっては自分の
卵細胞に自分の
精虫を
加えて、
一匹で
完全に
生殖をすることもできる。しかし
二匹相寄って
互いに
精虫を相手の体内に入れ合うのがほとんど
規則である。
雌雄異体の動物とは
違い、この
仲間の動物は
二匹出遇いさえすれば
必ず
生殖ができるという
便利がある。運動の
速やかな動物に
雌雄同体のものが
一種もなく、
一匹で
両性をかねたものはことごとく
遅く
匍匐する
種類ばかりであるのも一つはこのゆえであろう。
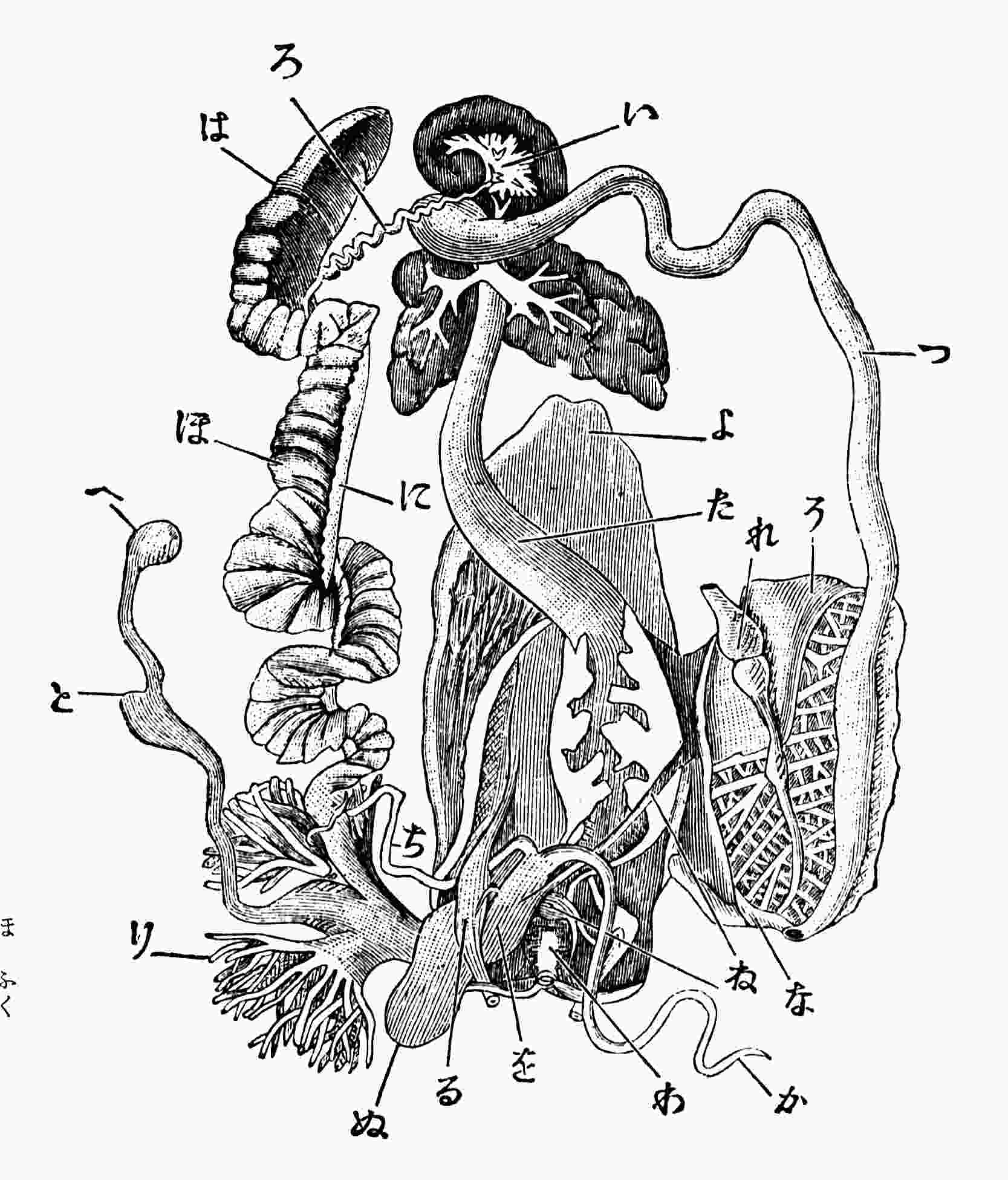
かたつむりの生殖器
(い)卵巣兼睾丸 (ろ)輸卵管兼輸精管 (は)蛋白腺 (に)輸精管 (ほ)輸卵管 (へ)受精嚢 (と)同管 (ち)輸精管の続き (り)付属腺 (ぬ)矢の嚢 (る)触手 (を)輸精管の末端 (わ)口 (か)鞭状腺 (よ)足 (た)腸の前部 (れ)心 (そ)外套膜 (つ)腸の後部 (ね)筋肉 (な)外套膜の縁
「かたつむり」の
類はすべて
雌雄同体であって、これを
解剖して見ると内部の
生殖器は
種々の部分から
成りすこぶる
複雑である。まずもっとも
奥に
位するのは
卵巣兼睾丸ともいうべき
器官で、
卵細胞も
精虫もひとしくその内で生ずる。
輸卵管と
輸精管とは始め
共通で
途中から
別々にあるが、その
末端は
再び合して一つの
孔となり、頭部の
右側で体外に開く。この
孔は口より少しく後へ
寄ったところであるゆえ。
強いて人間にくらべていえばあたかも右の'
頬か
頸筋ぐらいのところにあたる。
孔の内は直ちに
輸卵管につづくほうと
輸精管につづくほうとの
二途に分かれているが、
輸精管につづくほうはやや細くて、内に一本の長く
柔らかい
陰茎があり、つねには
隠れているが、
二匹交接するときにはこれを
生殖孔から
突き出して、相手の
生殖孔にさし入れる。また
輸卵管につづくほうは、相手の
陰茎を受けるための
膣であって、その
奥には相手から入り来たった
精虫を一時
貯えておくための小さな
嚢がつづいている。なおそのほかに、
粘液を
分泌する
腺、
蛋白を生ずる
腺などがあって、
複雑になっているが、
特におもしろいのは
膣の出口に近いところ、すなわち相手の
陰茎の入り来たるところのそばに一つの
嚢があって、その中に「
恋愛の矢」と名づける
鋭くとがった
針がおさまってある。キューピッドの放つ
恋愛の矢は
心臓を
刺すそうであるが「かたつむり」の
恋愛の矢は
直接に相手の
交接器を
刺激して、
輸精管の
筋肉を
収縮せしめ、
精虫を出させるように
働く。
 かたつむりの交接
かたつむりの交接
「かたつむり」が
交接するときには、
二匹相接近して長い間
互いに体をすり
寄せからみ合わせなどして、
如何にも
恋愛の
情に
堪えぬらしい
挙動をつづけた後に、
生殖孔を
互いに
密接せしめ、
双方から
交接器を相手の体内にさし入れる。
生殖孔は頭の
右側にあるゆえ、これを
互いに
密接せしめたときは、あたかも'
頬をすり合わせているかのごとき
体裁である。
獣類の
交接を
交尾というならば、「かたつむり」の
交接はむしろ交頭と名づけねばならぬ。かくしてしばらく
相つながっていた後に、
交接器を
抜き取り自分の体内に
収めて
別れていく。
卵を
産むのはそれより後のことで、その時には、
各自勝手に
柔らかい土のところに
一塊として
産むのである。「なめくじ」の
交接も全くこれと同様である。
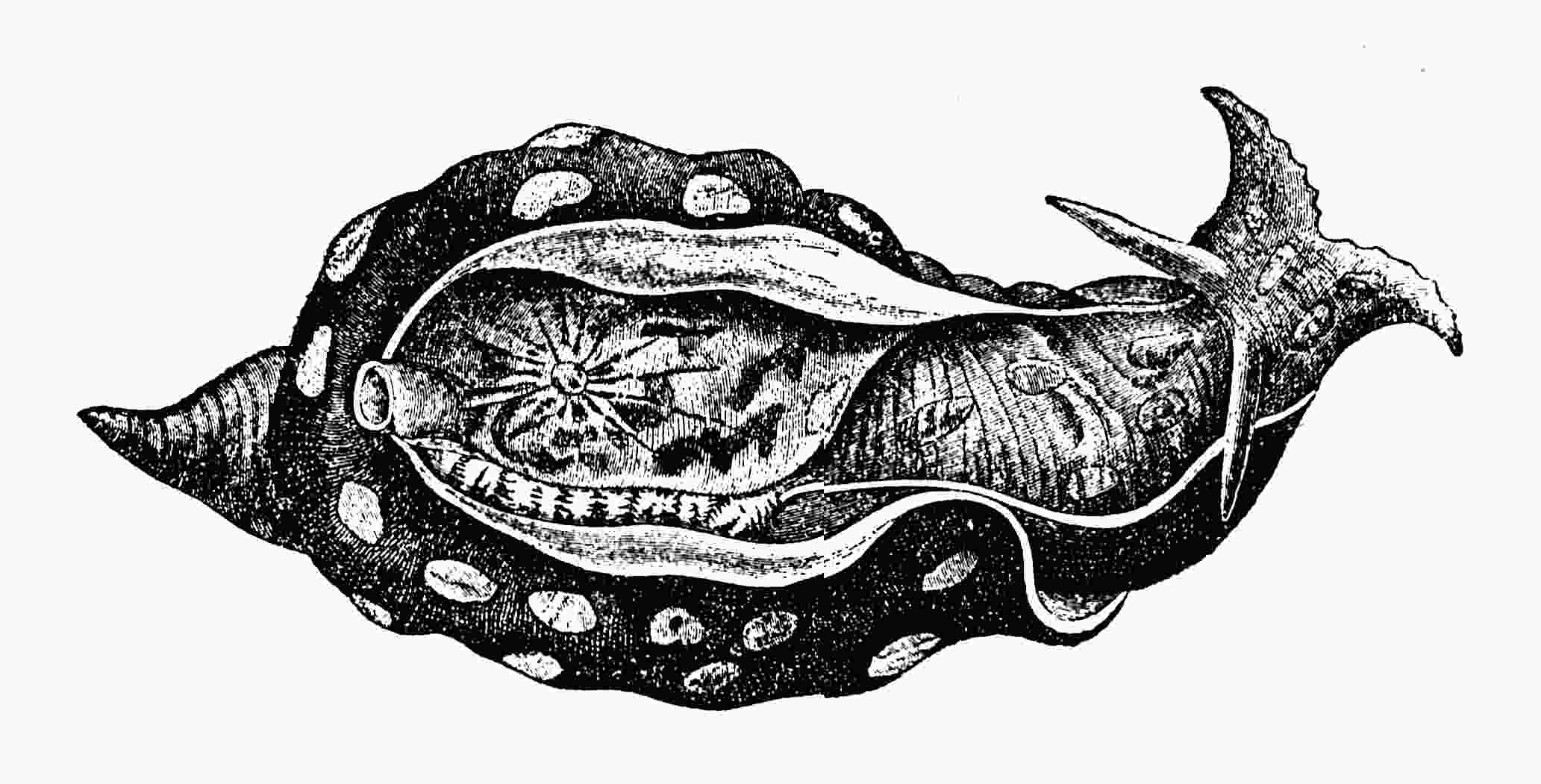 うみうし
うみうし
海岸へ行って見ると、海草のおい
茂ったところに「うみうし」というものがいくらも
匍うている。体は
肥え太って、頭からは二本の
柔らかい角がはえ、
徐々と草の上をはいながらこれを食うて歩く様子は
如何にも牛を思い出させるが、この動物はやはり「かたつむり」や「なめくじ」の
仲間である。ただし海中に住んでいるものゆえ、
鰓をもって水を
呼吸する。
鰓は体の
背側にあるが、
柔らかい
褶ようのものでおおわれているからほかからは見えぬ。また
鰓を
保護するために、
薄い皿のような
貝殻があるが、これもほかからは見えぬ。しかし動物が死んで
柔らかい体部が
腐れ
溶けてしまうと、
貝殻だけが
残って
浜に打ち上げられる。「
立浪貝」と名づける貝はこれである。さてこの「うみうし」の
類も
生殖器の
構造は「かたつむり」と
大同小異で
生殖孔の
位置はやや後にあるが、
精虫を相手の体内に
移し入れるための
管状の
交接器は頭の
右側のところにあるゆえ、
二匹相寄って
互いにこれを相手の
生殖孔にさし入れようとすれば、いきおい体を
互い
違いの方角に向けねばならぬ。春から夏へかけて海水も
温くなるような
浅いところでは、海草の間に「うみうし」が
二匹すつあたかも二つ
巴のごとき形になってつながっているのをしばしば見つける。
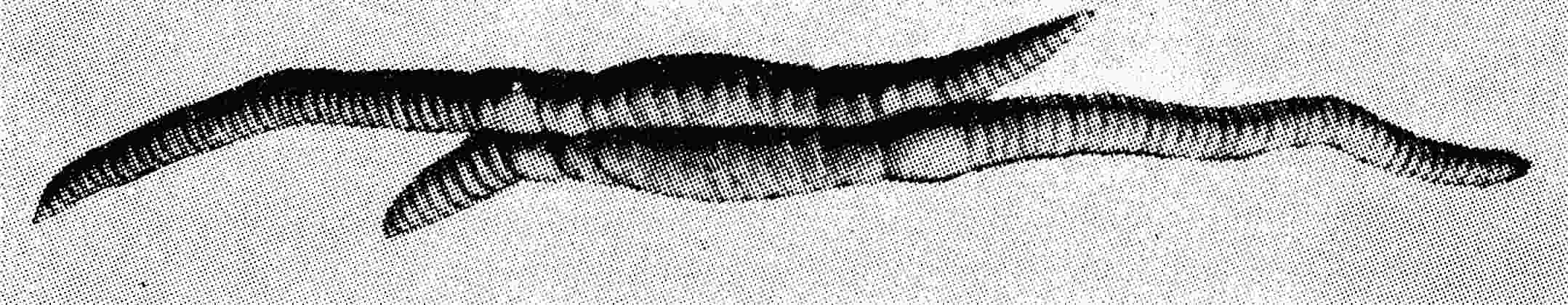 みみずの交接
みみずの交接
「みみず」も
雌雄同体であるが、その
生殖器の
模様は「かたつむり」などのとはよほど
違う。まず
生殖器が体外に開く
孔が数多くある。すなわち
精虫の出る
孔が一対、
卵の出る
孔が一対、および相手から
精虫を受け入れるための
孔が二三対もある。ただしこの数は「みみず」の
種類によって少しは
違う。また内部の
構造を見ると、「みみず」では
卵巣と
睾丸とは全く
別であって、それぞれ一対ずつ
備わり、それより体外へ出るまでの
輸卵管も
輸精管も一対ずつ
別になっている。それゆえ、「みみず」では体内で自分の
卵に自分の
精虫を
遇わせることはけっしてできぬ。
交接するときには
二匹が
互い
違いに向かいて体を
相近づけ、
皮膚の表面より
分泌した
濃い
粘液ではなれぬように
結びついて、
互いに
精虫を相手の体内に送り入れる。
精虫はその
際には相手の
受精嚢にはいるだけでいまだ
卵とは
相触れず、後にいたり
卵が生まれるときにはじめて
受精嚢から出され、親の体外で
卵に
接する。かくして
卵はさらに
多量の
蛋白に
包まれ、
塊状をなして地中に
産みつけられるのである。「ひる」
類も
雌雄同体であるが、
生殖器の
構造はいくぶんか「みみず」とは
違い、
受精嚢はなく、
輸精管、
輸卵管ともに体外へ出る
孔は、体の中央線に当たって一つずつあるだけで、
輸精管の出口の内には
管状の
交接器がある。しこうして
交接するときには
二匹が
相接して、
互いに自分の
交接器を相手の
輸卵管の
末端にさし入れ、その内へ
精虫を送り
込むのである。
産卵の
模様は「みみず」によく
似ている。
条虫では
一節ごとに
雌と
雄との
生殖器官が一組ずつそろうてあるが、
双方ともに
種々の部分から
成りすこぶる
複雑である。
生殖器の体外につく
孔はただ
一個であるが、その内部は直ちに二本の
管に分かれている。すなわち一方は
輸精管のつづきで、出口に
管状の
交接器を
備え、他のほうは
交接の
際に相手から
精虫の入り来たる
膣であって、その先は
輸卵管、
殻腺、
子宮などに
連絡している。それゆえ
条虫では
生殖器の出口を
閉じ、自身の
輸精管から自分の
膣に
精虫を
移して
卵を
産むことができぬこともない。しかし
特に
交接器をそなえているところから考えると、相手を
求めて
精虫を
交換するのがつねであって、自分
一個の体内で自分の
卵細胞と
精虫とを
出遇わせるのはおそらくやむを
得ぬ場合に
限ることであろう。
肝臓や
肺臓に
寄生する「ジストマ」の
類も、
生殖器の
構造は
条虫と
大同小異であるから、これもおそらく相手を
求めて
精虫をやり取りするのがつねであろう。
以上かかげた
例はいずれも
一生涯を通じて
雌雄の
生殖器を
兼ね
備えたものであるが、動物の中には
年齢によって
雌雄の
性の
変化するものもある。
例えば深い海に
産する「
盲鰻」という
八目鰻に
似た魚は、
若いときは
雄であるが年をとると
雌となる。
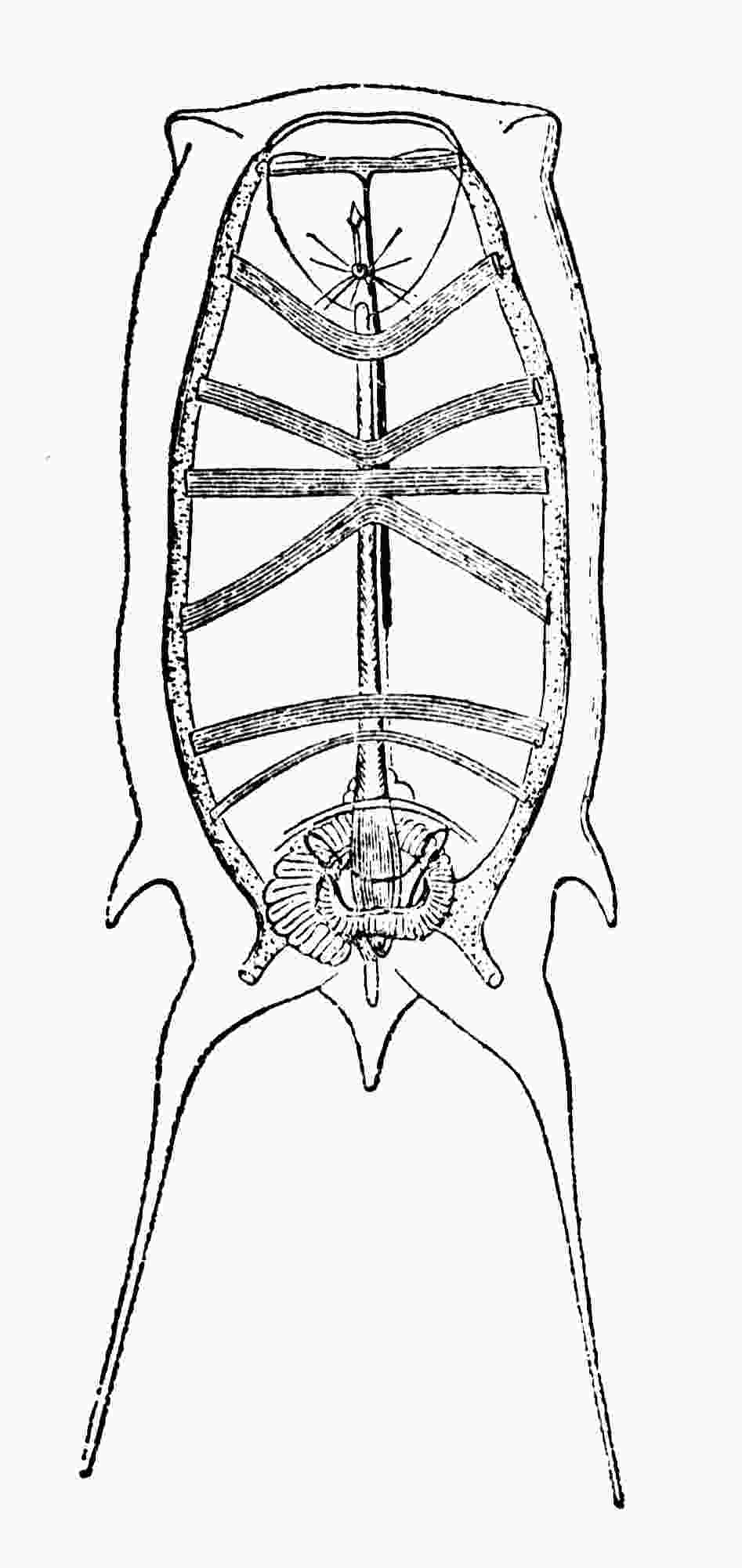 サルパ
サルパ
また海の表面に
浮いている「サルパ」と
称する動物は、体が
透明でちょっと「くらげ」のごとくに見えるが、これは生まれた時は
雌で後には
雄に
変ずる。これらは
一匹の動物で
雌雄を
兼ねているから
雌雄同体と名づけねばならぬが、
生殖器官の
雄の部と
雌の部との
成熟する時が
違うから、
働きからいうと
雌雄異体のものと
異ならぬ。
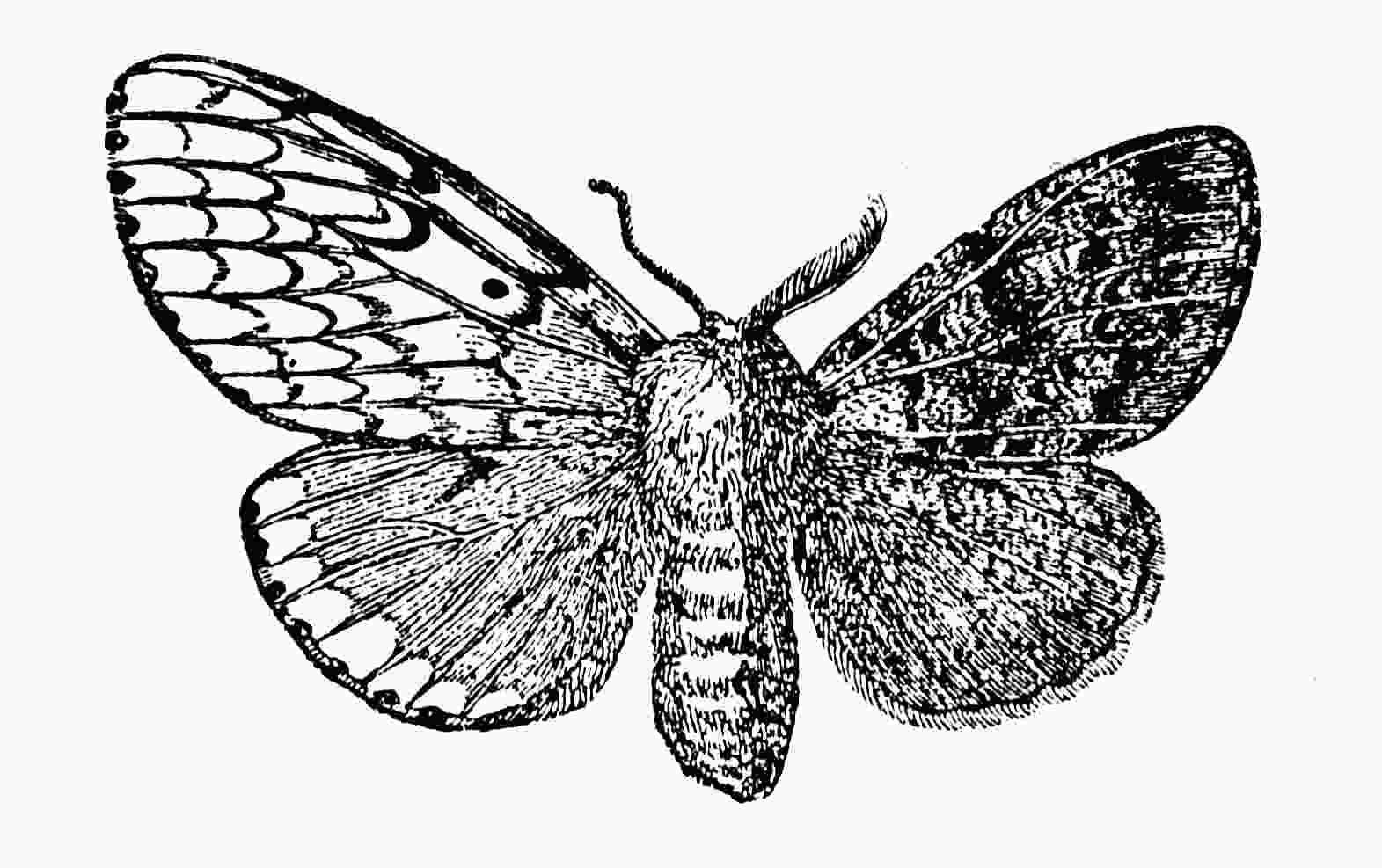 左右性の異なる蛾
左右性の異なる蛾
また
昆虫などには
往々左が
雌で右が
雄というように身体の両半の
性の
異なるものが見つけられるが、これは全くでき
損じの
奇形であって、けっしてかような
特別の
種類が定まってあるわけではない。
雌雄異体の動物でも
雌雄同体の動物でも、
生殖を
営むにあたってはまず
卵細胞と
精虫との
相合することが
必要であるが、
若干の動物では
精虫に
関係なく
卵細胞だけから子ができることがある。かような場合にはこれを
単為生殖または
処女生殖と名づける。
昆虫類の中では植物の
芽や
枝に
群集して
液汁を
吸う「ありまき」、水中に住む動物では
魚類の
餌になる「みじんこ」の
類などは、つねに
単為生殖によって
盛んにふえる。その他にもなおいくつも
例をあげることができる。「ありまき」には
種類がなかなか多いが、いずれも植物の
若い
茎や
枝に止まり、細長い
吻をその中にさし入れて
液汁を
吸う。形は小さいが
繁殖が
盛んでたちまち何千にも何万にもなるゆえ、植物はそのため
大害をこうむるにいたる。
繁殖法の
詳細な点は
種類によっていろいろ
相違があり、中には
極めて
複雑な
関係を
示すものもあるが、もっとも
簡単な場合でも他の
普通な動物にくらべるとよほどこみいっている。まず春あたたかくなったころに
卵から
孵化して
雌が生まれ出て、植物の
汁を
吸うてたちまち
成熟し、
雄なしに
卵を
産み、その
卵からはまた
雌が出て、また
雄なしに
卵を
産む。かくして何代も
繁殖をつづけて秋にいたり少しく
涼しくなってくると、こんどは
卵から
雌と
雄とが出て、これが
相寄って前のとはやや
違うた
殻の
厚い
卵を
産む。この
卵は直ちには
孵らず、そのまま冬を
越し
翌年の春になって始めて、それから
雌が出て、
再び同じ
歴史を
繰り返すのである。
以上はもっとも
簡単な場合を
示したので、
実際はこれよりなおいっそう
複雑な
経過を
示すものが多い。また
卵生でなく、子の形ができてから生まれることもつねである。夏日「ありまき」が
樹に止まっているのを見ていると、
腹部の
後端から小さな子が
続々生まれ出て、直ちにはい歩くのをしばしば見かける。されば「ありまき」の
類では
雌と
雄とがそろうているのは、一年のうちでも
或る短い時期に
限ることで、その他の時にはただ
雌ばかりである。しかもその
雌は
雌雄そろうてあるときの
雌とは
違うて、おのおの
独身で子を
産み
得る
特殊の
雌である。たいていの「ありまき」では
雌ばかりの間は
翅がなくて、ただ
遅くはうだけであるが、
雌雄がそろうて
現われるころには両方とも
翅があって数多く
飛びまわり、遠いところまで自分の
種を
分布する。「ありまき」と
蟻との
関係は有名なもので、
蟻は「ありまき」の
腹部の
後端から
滴り出る
甘い
汁をなめる代わりに、つねにこれを
保護して
敵から
防いでやる。それゆえ「ありまき」は運動が
遅くとも多少安全な場合もあるが、また「ありまき」を食うことを
専門とする
昆虫もたくさんにあるゆえ、よほど
盛んに
繁殖せぬと
種切れになるおそれがないでもない。しこうしてそのためには
普通の
生殖法によらず、
単為生殖という手軽な
変則法によるのがもっとも
有効であろう。「ありまき」では、ほとんど今日
吸うた植物の
汁が明日は子となって生まれるのであるから、
生殖は
個体の
範囲を
超えた
成長であるということが、実に
適切にあてはまる。
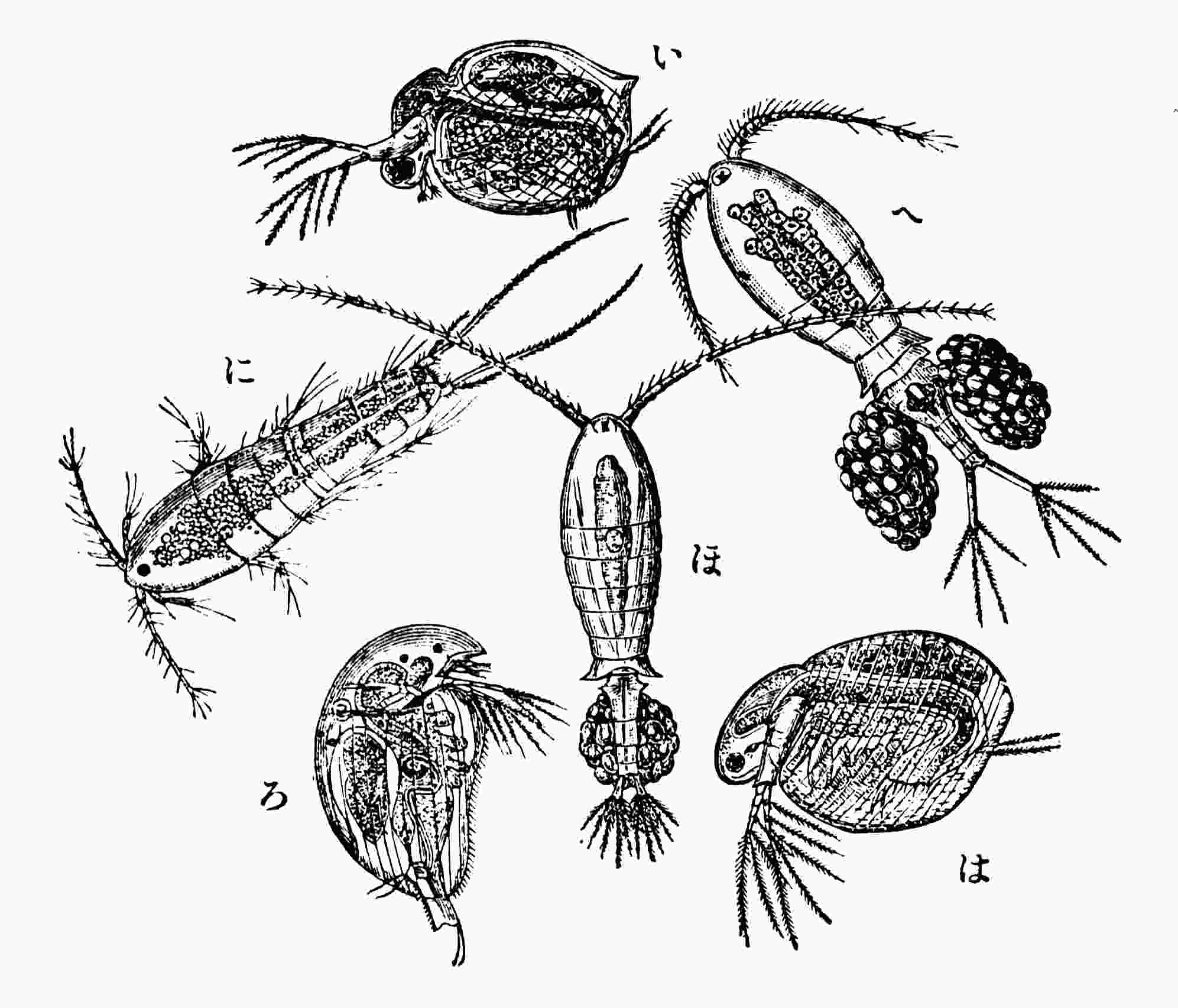 (い,ろ,は)みじんこ類 (に,ほ,へ)けんみじんこ類
天水桶
(い,ろ,は)みじんこ類 (に,ほ,へ)けんみじんこ類
天水桶などの中にたくさん
游いでいる「みじんこ」は「えび」、「かに」などと同じく
甲殻類に
属するが、身体は「のみ」ほどの大きさよりない。これも
魚類などに
盛んに食われるから、
敵に
攻められぬすきに急いで
繁殖せぬと
種族の
維持がむずかしい。「ありまき」も「みじんこ」もともに
敵に対して身を
護る
装置は
特に
発達せず、その代わり
繁殖のほうに全力を注いで、いくら食われてもなお
残るようにつとめる動物である。すなわち
旺盛な
生殖力を
唯一の
武器として
生存している。それゆえ「みじんこ」なども「
鬼の
留守に
洗濯」という
諺のごとく、
熱い夏の間にすこぶる
盛んに
繁殖するが、その
方法はすべて
単為生殖による。「みじんこ」のたくさん
游いでいるところをすくい取って見ると、たいていは
雌ばかりで
雄はほとんどない。しかもそれがみな子を持っている。
普通の「みじんこ」の身体は、あたかも
羽織か
外套を着たごとくに、
一種の
殻でおおわれていて、
殻と
胴との間には空所があるが、夏
盛んに生まれる
卵は直ちに親の体からは
離れず、
暫時この空所にとどまって、その中で
速やかに発育し、親と同じ形になって水中へ
游ぎ出すのである。「みじんこ」を度の
低い
顕微鏡でのぞいて見ると、親の
背にある
殻の
内側に
何匹も小さな子が
圧し合うているが、これは
単為生殖によってできた子であるゆえ、
一匹として父を有するものはない。秋の
末になって水が
冷たくなると
雄も生まれ、
雌は
特に
殻の
厚い大きな
卵を
産むが、この
卵は冬氷が
張っても死なずに
翌年の春
孵化して、その中からまた
雌が出てくる。ただしこの
雌だけには明らかに父がある。しこうしてこの
雌がまた
盛んに子を
産んで夏の間に
無数にふえる。かくのごとく水中の「みじんこ」の
生殖の
模様は、だいたいにおいては
陸上の「ありまき」の
生殖と
相似たもので、
双方ともに
速やかに
繁殖するときには
単為生殖により、冬を
越して
種族を
継続せしめるにあたっては
雌雄両親のそろうた
生殖法を行なうのである。
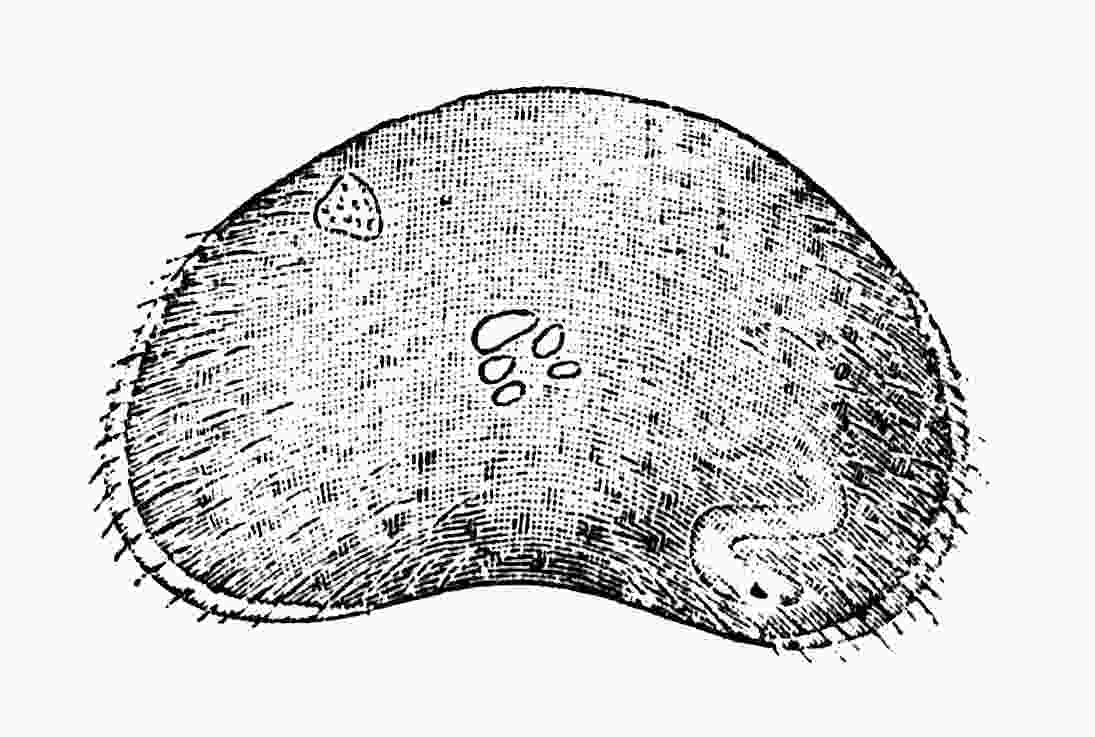 貝みじんこ
貝みじんこ
「みじんこ」の中でも
蜆や
蛤の形に
似た「貝みじんこ」と名づける
類には、冬になっても
単為生殖をつづけ、そのため今日まで一度も
雄が見いだされぬものもある。
以上はいずれも
個体の数を
速やかに
増加させるための
単為生殖であるが、他の場合には
単為生殖か両親
生殖かによって生まれる子に
雌雄の
差の生ずる
例がある。
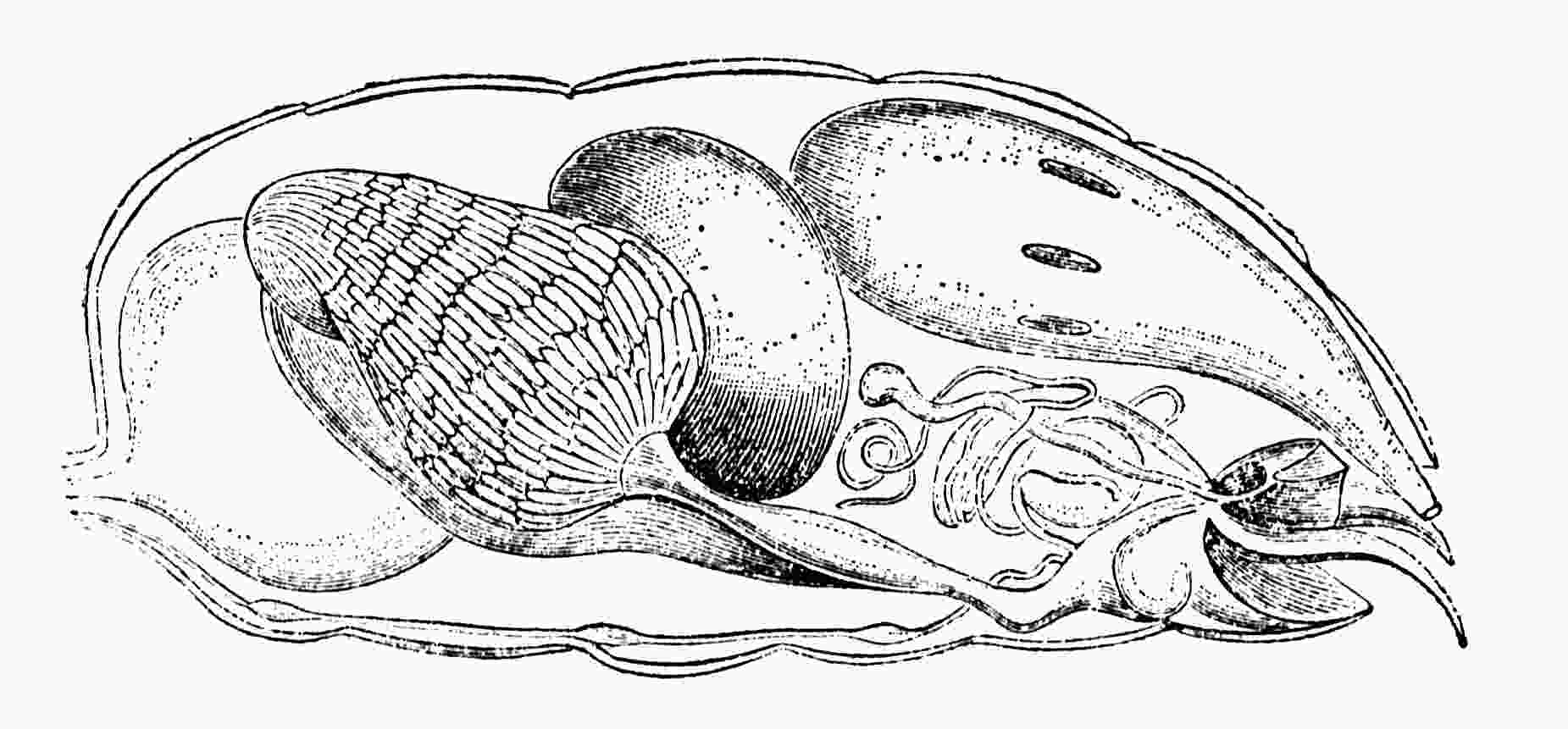
雌の蜜蜂の腹部の内臓を左側より見たる図
図の中央より左にあたり米粒をならべたごとくに見えるものは卵巣。卵巣よりでたる管は輸卵管。輸卵管の上に見える球形の小嚢は受精嚢。
その有名なものは
蜜蜂であるが、
蜜蜂の一社会には
卵を
産む
雌はただ
一匹よりない、これがいわゆる女王である。
雄はこれに対して
数百匹もあるが、
実際雌と
交尾するものは、その中でただ
一匹よりない。しこうして女王がこの
雄と
交尾するのは
一生涯中にただ一回で、それより後
卵を
産むにあたっては、
卵に
精虫を
加えることも
精虫を
加えずして
卵のみを
産み出すことも、女王の
随意である。
交尾すればむろん
雄蜂から女王の体内に
精虫がはいり
込むが、女王の
生殖器にはこれを受け入れるための
受精嚢があるゆえ、まずその中へ
収めておき、後にいたって
産卵するとき、この
嚢の口を開いて
精虫を出すこともできれば、それを
閉じて
精虫を出さぬようにもできる。されば女王の
産んだ子には父のあるものと父のないものとがあるが、父のあるものはすべて
雌になり、父のないものはすべて
雄になる。しこうして
雌は
産まれてからの
養育のしかたにより、あるいは
働き
蜂ともなりまたは女王ともなる。かようなしだいで
雄蜂は母から
産まれ、母には
夫があるがこれはただ
義理の父とでもいうべきもので、真に血を分けた父ではない。同じ母から
産まれた兄弟でありながら、姉や妹にはみな父があって、兄や弟には父がないというのは、動物界でも他にあまり
類のない
例で、これにはまた何か
種族の
生存上に
都合のよい点が
必ずあったのであろうと思われるが、今日のところではいまだ
確かな理由はわからぬ。
単為生殖では、ただ
卵細胞だけから子ができるのであるが、これは
卵細胞と
精虫とがそろうてあるべきはずのところを一方が
欠けているというわけであるゆえ、やはり
雌雄両性の
区別のある
範囲を出ない。それゆえ、
雌雄による
生殖でも
単為生殖でも、
雌雄が同体であっても
異体であっても、みなこれを
有性の
生殖と名づける。これに反して
雌雄両性の
別とは全く
無関係の
生殖法も生物界にはずいぶん行なわれている。
例えば一
個体から
芽が生じ、その
芽が
成長して新しい
独立の一
個体となることもある。また一
個体が分かれて
二片となり、
各片が
成長してついに
二個の
完全な
個体となることもある。かような
芽生または
分裂などによる
生殖を
総称して
無性生殖と名づける。
有性生殖と
無性生殖とは、その
模範的の
例をくらべて見ると、全く
互いに
無関係のごとくに思われるが、
種々の
異なった
例を
残らず集めて見ると、いずれの組に
属するか
判断に苦しむようなものもあるゆえ、けっしてその間に
明瞭な
境界を定め
得べきものでない。「
自然は一足
飛びを
為さず。」という
古諺は、この場合にもよく当てはまるようである。
淡水に
産する「ヒドラ」という小さな虫についてはすでに前の章でも
述べたが、夏この虫を
金魚鉢に
飼うて「みじんこ」などを食わせておくと、
円筒形の身体の
側面のところに小さな
瘤のごとき
突起が
現われ、次に
瘤が
延びて短い
横枝となり、
枝の
末端には口が開き、口の
周囲には細い糸のような
触手が何本か生じて、二、三日のうちにまるで親と同じ形の子ができ上がる。ただし体の内部はまだ親と
連絡しているゆえ、親の食うたものも子の食うたものも消化してしまえば
互いに
相流通する。そのうちに親の身体からはさらに
別の方角に
芽が生じ、子の身体からは小さな
孫の
芽が生じて、しばらくは小さな
樹枝状の
群体をつくるが、子はやや大きくなると親の身体から
離れて
独立するゆえ、
永久的の大きな
群体をつくるにはいたらぬ。
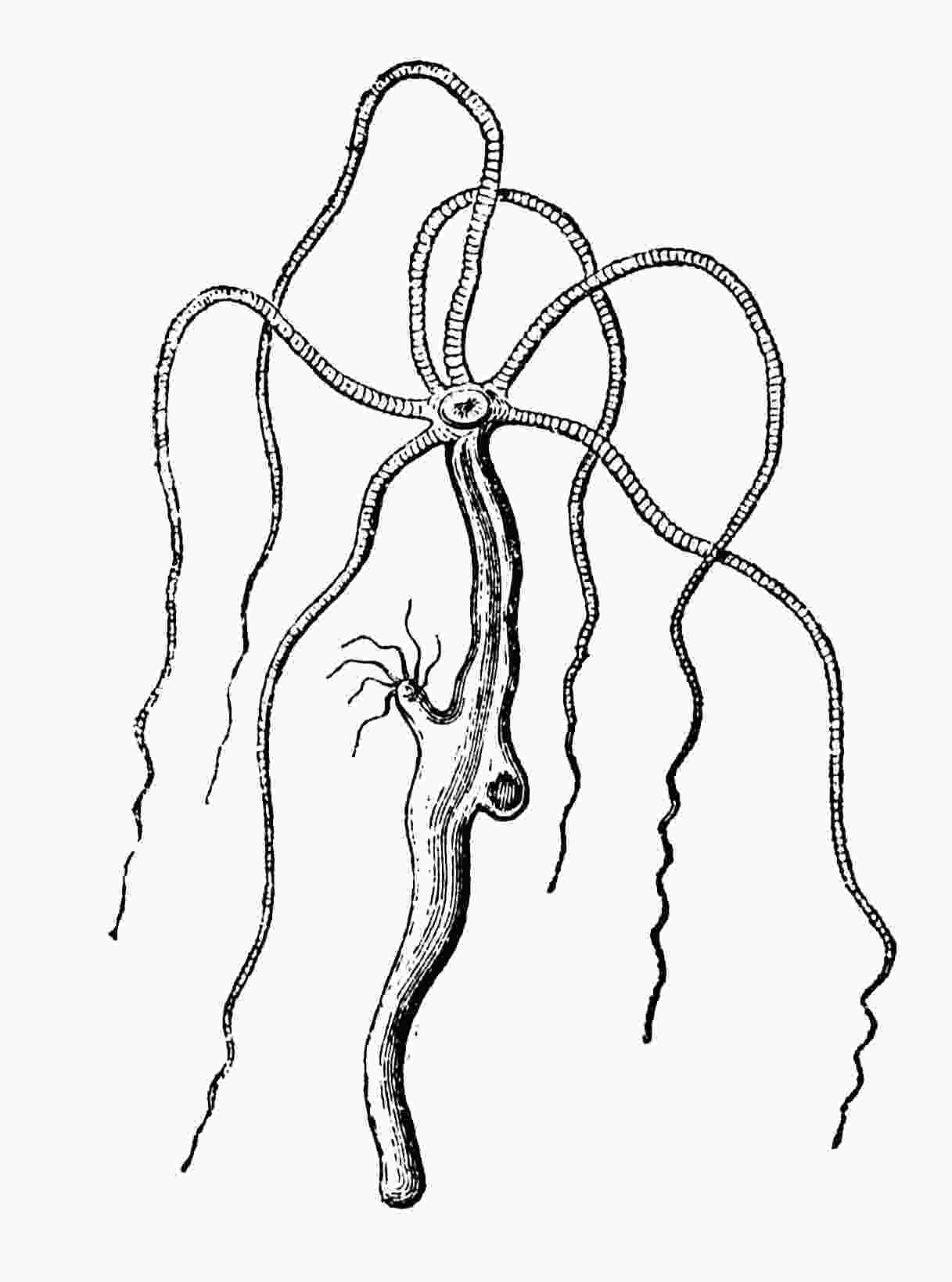 ヒドラ
ヒドラ
「ヒドラ」の
芽生によって
繁殖するありさまを明らかに
説明するために、
仮にこれを人間にたとえていうと、まず親の
横腹に
団子のような
腫物ができ、これが
次第に大きくなり横に
延び出し、いつとはなしに頭、
頸、
胴などの
区別が生じ、頭には
眼、鼻、口、耳などが
漸々現われ、
肩の
辺からは
両腕が生じてついに親と同じだけの体部を
備えた一人前の
子供となる。
子供は
最初の間は親の身体につながり、親から
滋養分の分配を受けているが、小学校を
卒業するくらいの大きさに
達すると親から
離れて
随意な場所に
移り行き、親も子もともに
芽生によってさらに
繁殖する。かように
想像して見たら「ヒドラ」の
生殖法が
如何なるものか明らかに知ることができよう。
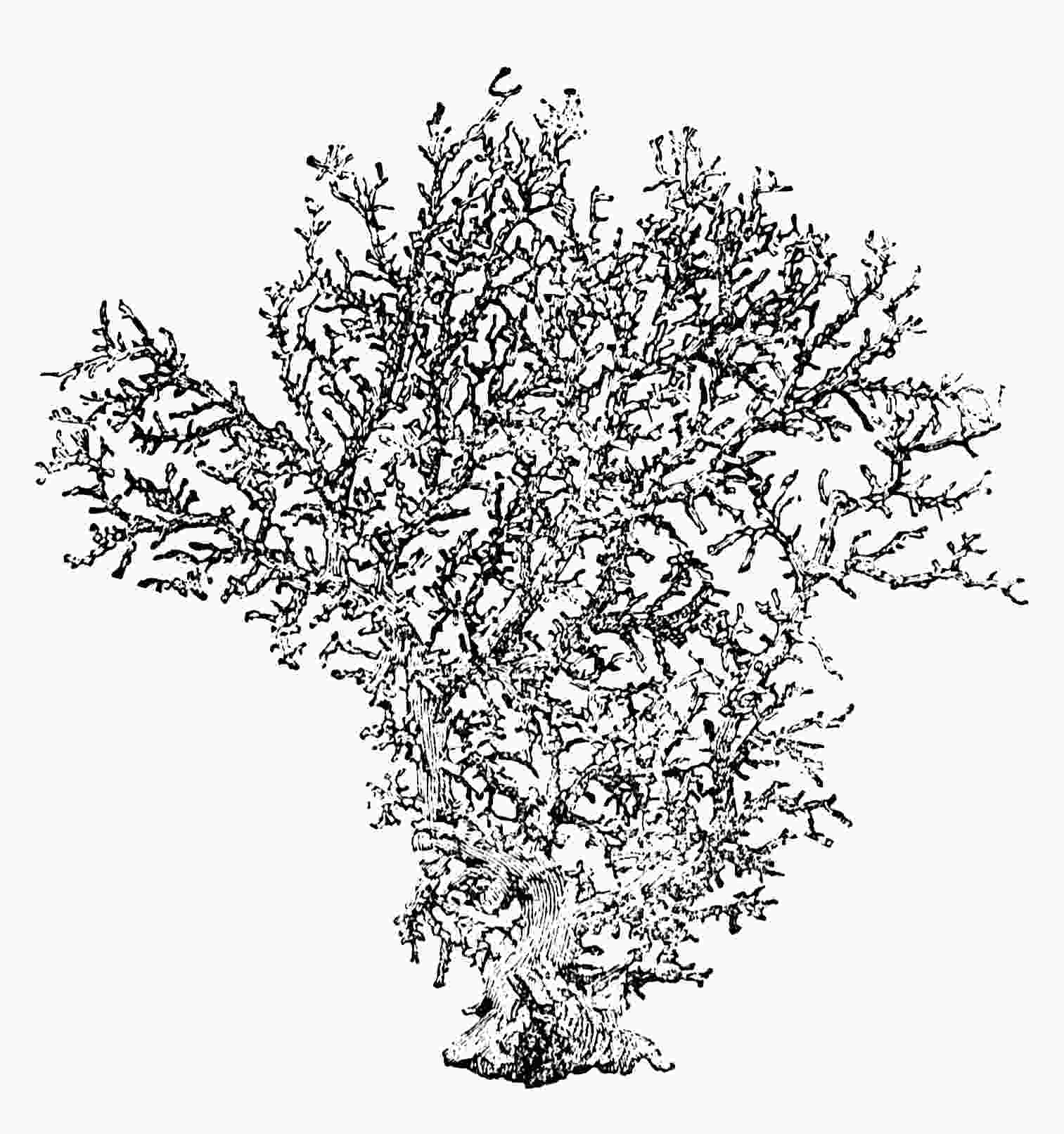 赤さんごの群体
赤さんごの群体
「ヒドラ」は
芽生をしても、子が
暫時の後に親から
離れ去るゆえ、
群体をなすにいたらぬが、「さんご」の
類などではできただけの
個体がみな
相つながったままで
離れぬゆえ、
種々の形の大きな
群体ができる。しこうして
群体をささえ
各個体を
保護するために、
石灰質の
堅い
骨骼を
分泌するゆえ、死んだ後まで
群体の形はそのままに
残る。
価の高い
装飾用の「赤さんご」はかようにして生じた「さんご虫」の
群体の
骨骼である。
樹木にもそれぞれ
枝ぶりに
相違があるごとく、動物の
群体にも
芽の出方によって
苔状に
拡がるもの、竹のように直立するもの、丸い
塊になるもの、鳥の羽の形に
似たものなどができる。「赤さんご」の
群体は
樹枝状になっているゆえ、「さんご
樹」とも書き、昔は西洋の
博物学者もこれを植物と思うていた。
概して
固着生活を
営む動物には
芽生によって
群体をつくるものが多い。これは運動する動物とは
違うて、数多くの
個体が
相つながっていても生活上
差支えが生ぜぬためと、
群体をなしていたほうが
個体の食物の
過不及を
平均して全体として
生存上に
利益が多いからであろう。「こけ虫」
類、
群生「ほや」
類などはかような
仲間で、いたるところの海岸の岩石の表面などに
盛んに
繁茂している。
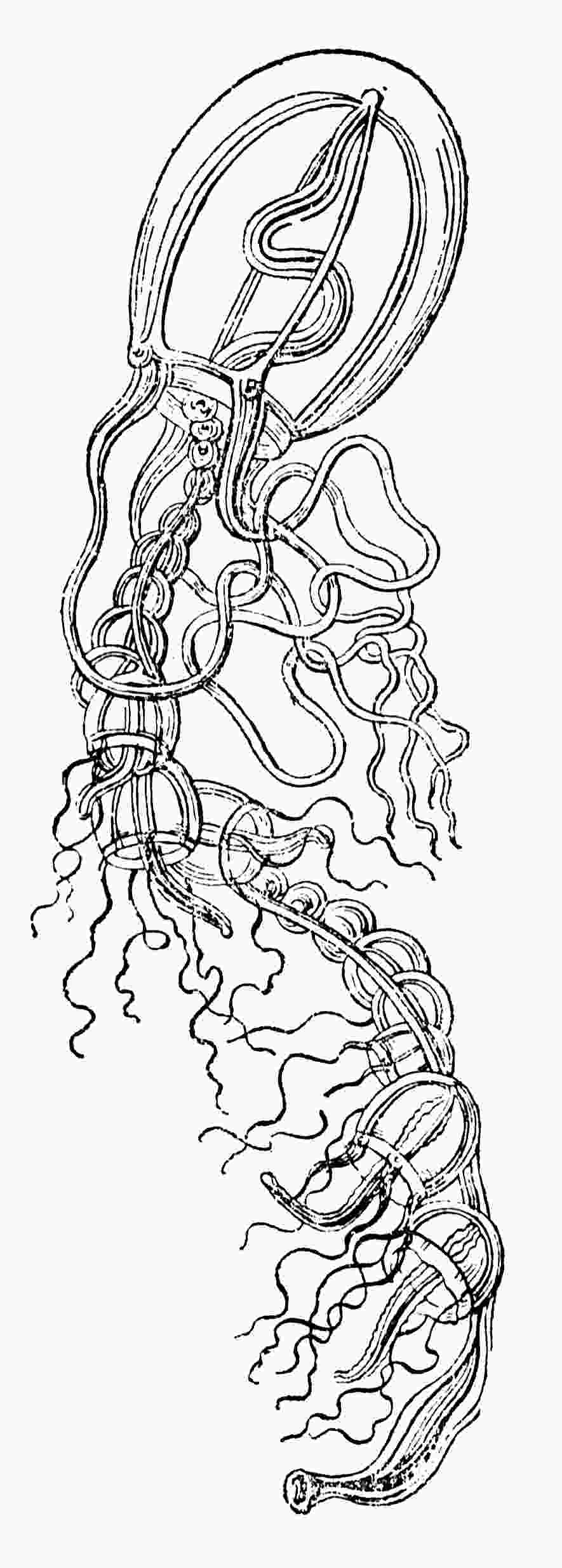 芽生するくらげ
芽生するくらげ
海面に
浮かんでいる動物にも
芽生で
繁殖する
種類がいくらもある。くらげの中でも
或る
種類は
傘の
縁または
柄に
盛んに
芽を生じ、
芽は直ちに小さな「くらげ」の形になって
暫時親の「くらげ」に
付着していた後に、一つ一つ
離れて勝手に
游いで行く。「かつおのえぼし」なども、
一匹のごとくに見えるものは実は一
群体であって、始め一
個体から
芽生によって生じたものである。また前に名をあげたが「サルパ」と
称する
透明な動物では、身体の一部から細長い
紐が生じ、その
紐に多数の
節ができ、後には
各節一匹ずつの
個体となる。それゆえ、同時にできたたくさんの「サルパ」が
鎖のごとくに一列に
連なったままで海の表面に
浮いているのをつねに見かける。この場合には同時に多数の
個体がそろうて発育するゆえ、一回に
一匹ずつを生ずる
普通の
芽生とはいささか
趣が
違うがこれもやはり
芽生の
一種である。
以上かかげた
例ではいずれも
芽が親の身体の外面に生ずるから、それが
芽であることが明らかに知れるが、
芽が親の身体の内部にできると
往々芽生とは考えられぬような場合が生ずる。海の水は冬でも温かいゆえ、
海産の動物は冬を
越すために
特殊の
方法を
採るにおよばぬが、池や
沼に住む動物は、寒くなって親が死ぬときに、
凍っても死なぬような
種子をのこしておかぬと
種族が全く
断絶する。それゆえかような動物は冬になると
特に
厚い
殻をかぶった
卵を
産むか、または
特に
厚い
殻をかぶった
一種の
芽を生ずる。
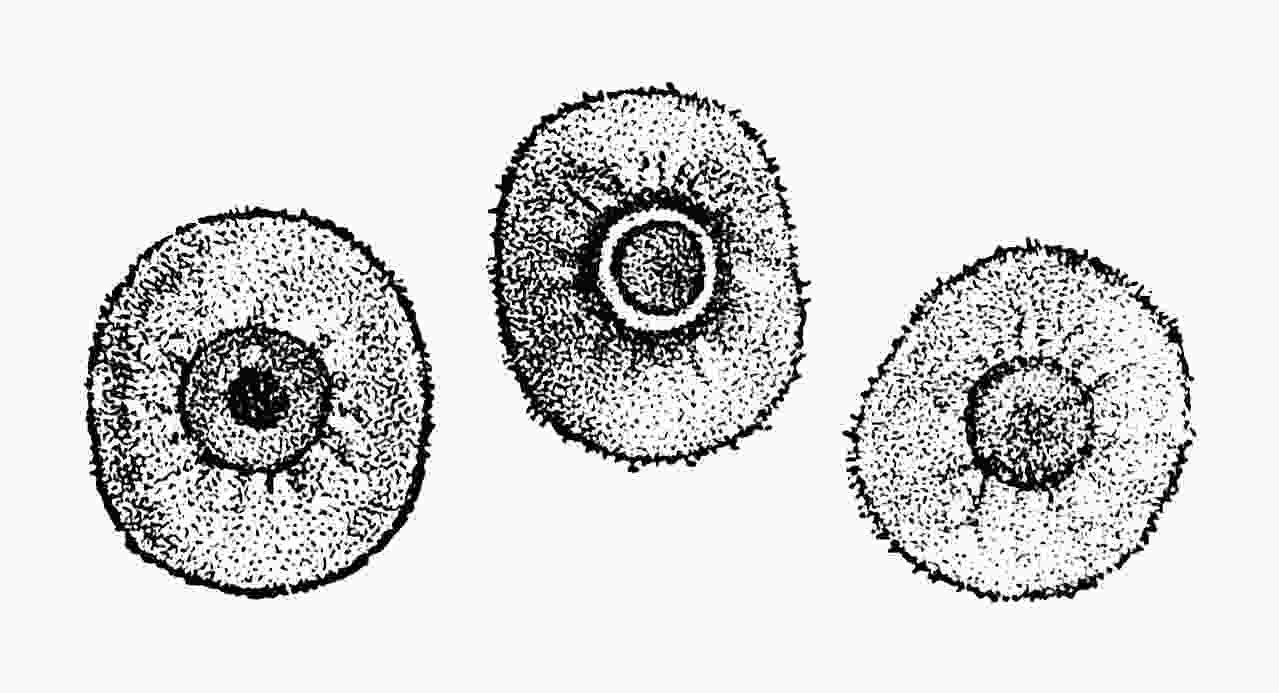 こけ虫の冬芽
淡水産
こけ虫の冬芽
淡水産の「こけ虫」や
海綿は冬のこぬ間に
盛んにかような
冬芽をつくるが、親の身体の内でできてしかも形が
卵に
似ているゆえ、近いころまでは学者もこれを真の
卵と思い
誤っていた。わが国ではいまだに
淡水海綿の
冬芽を「
鮒の
卵」などととなえている地方がある。さて親の体内に生じた
冬芽と真の
卵とはいずれの点で
相異なるかというに、
卵ならば全体でただ
一個の
細胞であるが、
冬芽のほうは始めから多くの
細胞の集まったもので、ただそれが
球形の
塊になっているというまでである。植物の
芽にもそのまま
延びて親の身体のつづきとなるものと、親の身体からは
離れて
別に新しい
一株の
基をつくるものとがある。「ゆり」の
或る
種類では
茎と葉との
隅のところに黒い小さな玉ができて、これが地上へ落ちると一本の「ゆり」が生ずるが、「こけ虫」や
海綿の
冬芽はこれと同じような
理屈で、発育すれば
一匹の
個体になり
得べきだけの
細胞の
塊が親の身体から
離れ、
厚い
殻におおわれて寒い
時節を安全に
通過し、
翌年になって
一匹の
個体までにでき上がるのである。それゆえ、もしもこれだけの
細胞が
最初一個の
細胞から生じたならば、
単為生殖で
卵から発生したのと少しも
違わぬ。「ジストマ」の
繁殖する
途中にも
一匹の虫の体内に多数の子が生ずる時期があるが、これなどは実に内部の
芽生かあるいは
単為生殖かほとんど
判断ができかねる。
有性生殖と
無性生殖とは全く
別物のごとくに考える人もあるが、
有性生殖中の
単為生殖と、
無性生殖中の体内
芽生とをくらべて見ると、その間にはかようなあいまいな場合があって、けっして
判然と
境が定められるものではない。
普通の「みみず」でも身体を二つに切ったくらいではなかなか死なぬが、
溝の中にたくさんいる「糸みみず」などは、
一匹を二つに切ると両半とも長く生活し、頭のないほうには新しい頭が生じ、
尾のないほうには新しい
尾が生じて、
二匹の
完全な虫になる。さればかような動物は切られたためにかえって
繁殖することになるが、
実際「糸みみず」の
類には
分裂によって
個体の数の
増すことを
普通の
生殖法としているものがいくらもある。「ものあら貝」に
吸い着いている小さな「糸みみず」の
類を取って
拡大して見ると、
必ず身体の中央にくびれがあって、後半の
前端のところにすでに頭ができかかっているものが多い。すなわちこの虫では体が切れて
二片となる前に、すでに前半には
尾端ができ、後半には頭部が生じ、そのままなおつながっているのである。
普通の「糸みみず」は切られてから
各片がその足らぬところを
補うために新しい
尾、もしくは頭を生ずるが、この
類では切れることを予期して、切れても少しも
差支えの起こらぬようにあらかじめ
準備して待っている。まさに切れ
離れんとする
程度のものでは、後半にはすでに
立派な頭ができ上がって
咽頭、
神経などもほとんど
完全になっているから、あたかも
二匹の虫を
捕え来たって、一方の
尻に一方の頭をつなぎ合わせたごとくで、前の者が食うた
餌は、その者の
肛門から後の者の口へ
移り、引きつづいて
後端の
肛門をすぎて体外へ出て行く。
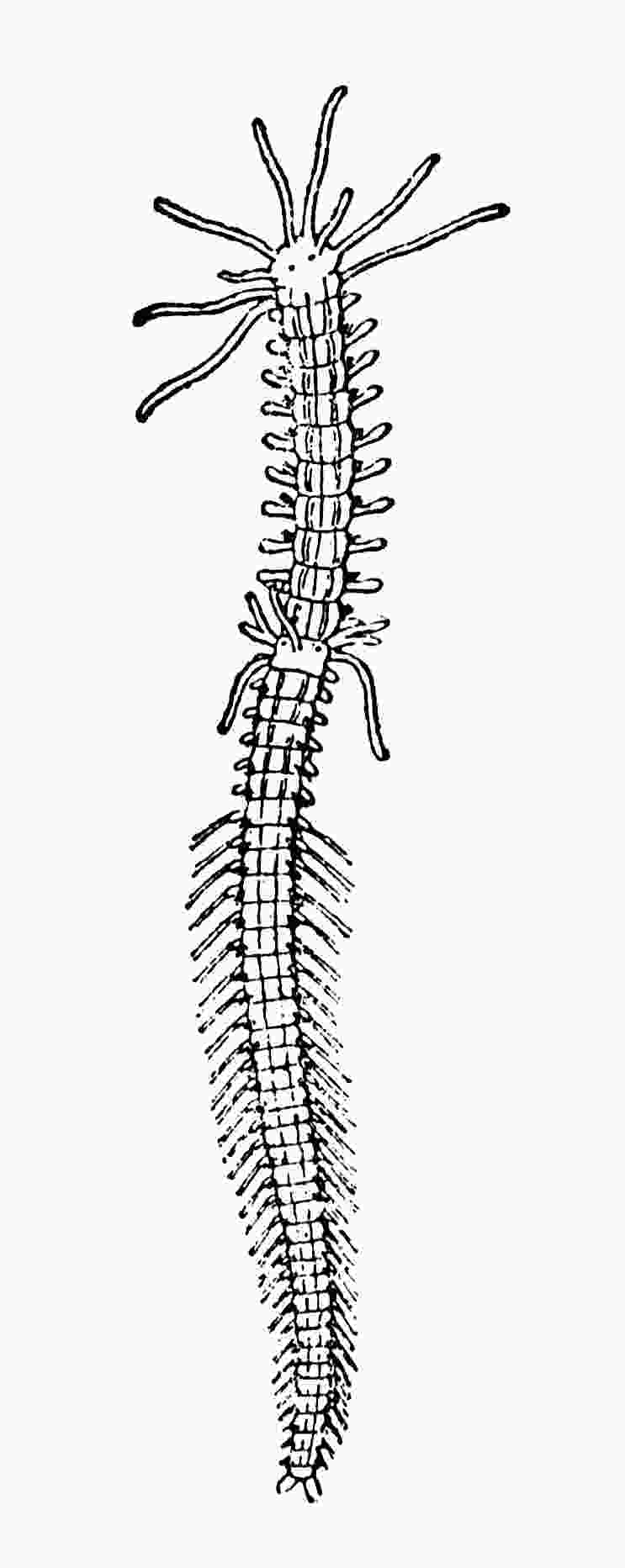 ごかい類の分裂
ごかい類の分裂
海に住む「ごかい」の
類では
盛んに
分裂法によって
繁殖するものがある。ただし前後同じ大きさの両半に切れるのではなく、体の
後端に近いところにくびれが生じ、始め小さな後半がしだいに大きくなってしまいに
完全な
一匹となるのであるから、
分裂と
芽生との中間の
生殖法である。そのうえ
二匹が
離れぬ間に両方ともさらに何回も同様な
生殖法を
繰り返すゆえ、しまいには大小さまざまの
個体が
鎖のごとくにならんで
臨時の
群体ができる。ただし
各個体が
成長するにしたごうて、ふるくくびれたところから
順々に切れ
離れる。
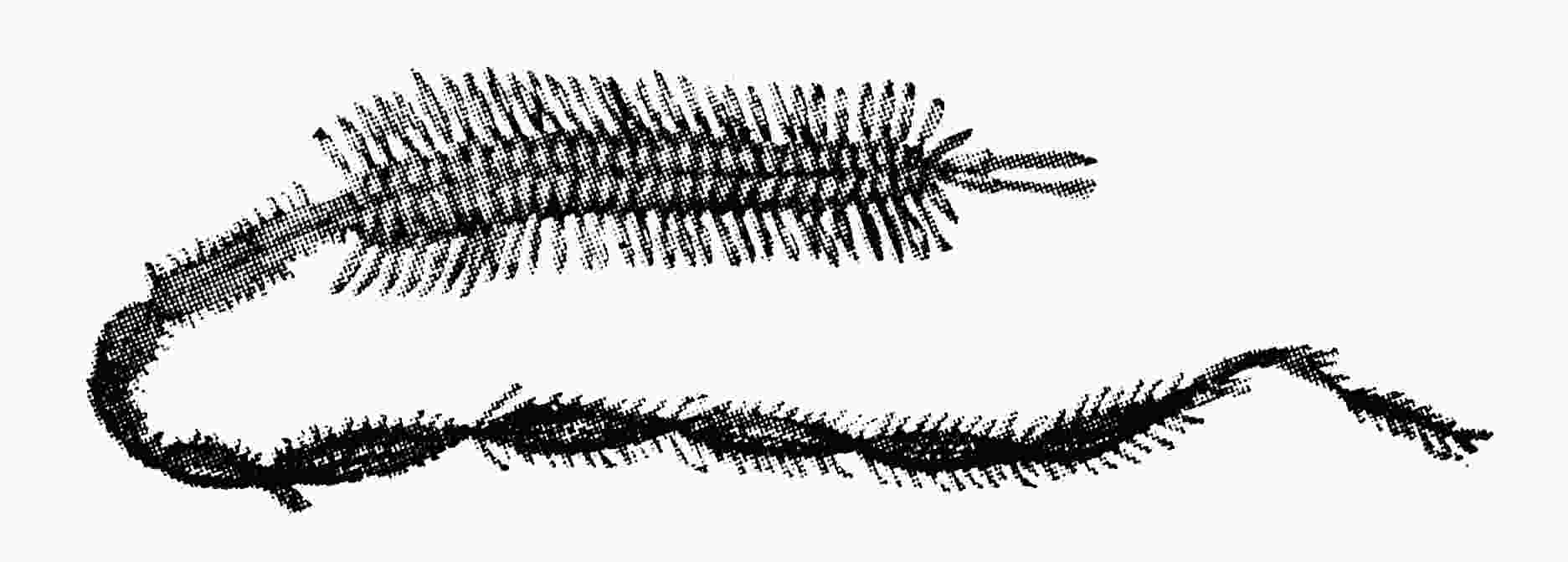 館山湾で捕れたごかい類(約四倍大)
館山湾で捕れたごかい類(約四倍大)
ここにかかげたのは先年
房州館山湾で
捕れた「ごかい」
類の写生図であるが、大小
数匹の
個体があたかも汽車の客車のごとくに前後に
連続している具合いは、
分裂生殖の見本としてもっともよろしかろう。「いそぎんちゃく」も
分裂によって
繁殖する。多くの
種類では体は
引臼か
茶筒のごとき
円筒形であるゆえ、上から見ればまるいのがつねであるが、
分裂せんとするときには、まず
楕円形になり、次にひょうたんのごとき形になる。それより両半はしだいに
相遠ざかり、ひょうたんのくびれはだんだん細くなって、しまいに体の下部より分かれ始め、
最後にはわずかに一本の細い糸で両半が
連絡しているだけになり、さらに後にはこの細い糸も切れて全く
二匹に分かれてしまう。これだけの事は「いそぎんちゃく」を長く海水中に
飼うておくと
容易に見られる。「さんご」の
類にも全くこれと同様な
分裂を行なうものがすこぶる多い。「
菊目石」と名づけるものはその
一例である。
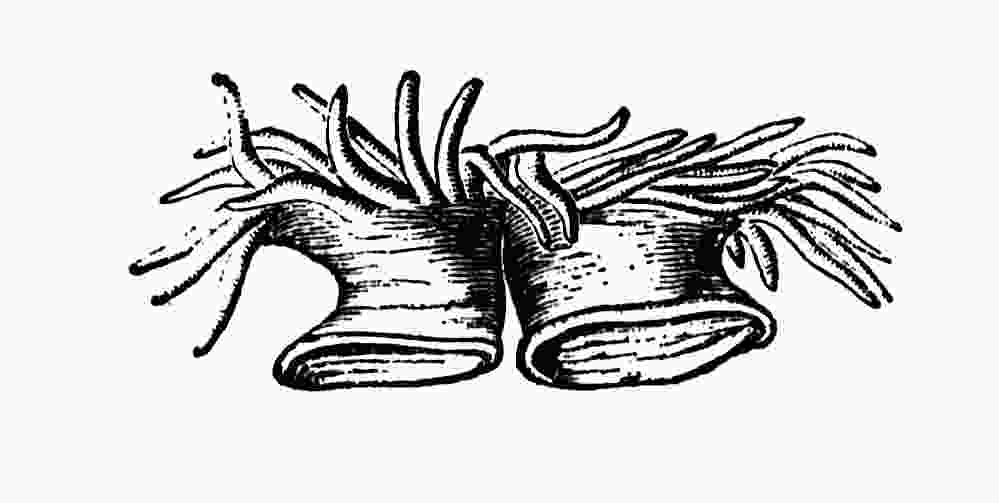 いそぎんちゃくの分裂
いそぎんちゃくの分裂
「いそぎんちゃく」は
各個体が
相離れて
独立に生活しているゆえ、
分裂は
完全に行なわれ、始め
一匹のものが
後には
必ず
二匹になり終わるが、「さんご」
類のごとき
群体をつくる動物では
分裂が
往々不完全に行なわれ、
一匹が
二匹に分かれ終わるまでにいたらず、
途中で止まって両半がさらにおのおの
分裂を始めることがある。すなわちひょうたんのくびれが細くならぬ間に両半がさらにひょうたん形になり、その新しいくびれが深くならぬうちに
四半分ずつのものがさらにおのおのひょうたんの形になりかかる。かように
分裂し始めるだけで
分裂し終わらぬ
生殖法が引きつづいて行なわれると、むろん多数の身体の
相つながった一
群体が生ずるが、
個体の間のくびれが
不明瞭でどこにあるかわからぬような場合には、その
群体の中に
何匹の
個体があるかかぞえることができぬ。
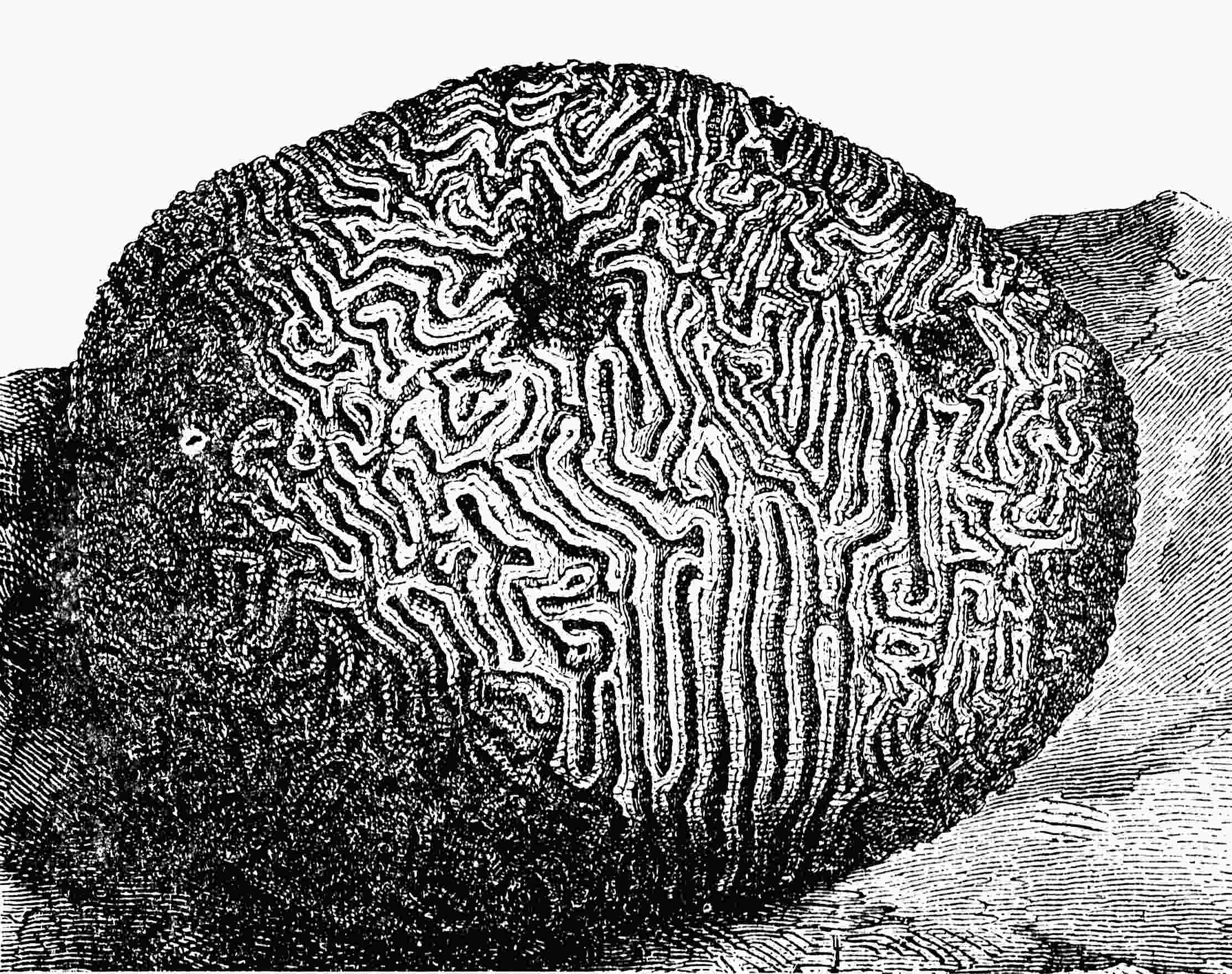 脳さんご
脳さんご
「
脳さんご」と
称するさんごの
一種はその
一例で、
群体であることはだれにも明らかに知れるが、
個体の
境がないゆえ、
一匹二匹と
勘定することはできぬ。
言を
換えれば、この動物の身体は
群体として
存在するだけで
個体には分かれていない。一体、「
脳さんご」という名は、その
塊状の
骨骼の表面に
個体の区画が少しも見えず、あたかも人間の
脳髄の表面に見るごとき
彎曲した
凸凹があるところからつけたのであるが、この「さんご」の海中に生きているところを見ると、
石灰質の
骨骼の外面には
極めて
柔らかい身体の
薄い
層があり、その表面には食物を食うための
若干の口と、食物を
捕えるための多数の
触手とが、波形をなしてならんでいる。これを人間にくらべていえば、百人分の身体をあつめて
一塊とし、これを
百畳敷の
座敷に
薄く
延ばして広げ、
百箇所に口をつけ、二百本の
腕を口の間にならべ植えつけたごとくであろう。食物が流れ
寄れば、もっとも近くにある
腕でこれを
捕え、もっとも近くにある口の中へ入れる。
個体の
境界などはあってもなくても、食うて
産んで死ぬるには何の
差支えもない。世人はつねに
個体に分かれた動物のみを
見慣れているために、
個体に分かれぬ動物のことには考えおよぼさぬが、生物はすべて
種族として食うて
産んで死ぬのに
都合のよい形を
採るもので、
個体に分かれているほうが食うて
産んで死ぬに
都合のよい
種類では、
個体が
判然と分かれ、その
必要のない
種類では
必ずしも
個体に分かれるにはおよばぬ。人間は自分らが
個体に分かれているゆえ、何事でも
個体の
区別を
基として定めてあるが、これはあまり
当然のことでかえってだれも気がつかずにいる。しかし生物界にはここに
述べたような
個体の
差別のない社会もあるゆえ、
哲学者などが物の
理屈を考えるときに、
戯れにこれをも
参考して見るとおもしろかろう。
権利とか
義務とかいう
個体間のやかましい
関係は言うにおよばず、毎日用いる「君」とか「
僕」とかいう言葉までが、かような社会へ持ってゆけば全く意味を
失うてしまう。しかもいずれでも食うて
産んで死ぬことはできる。
「ひとで」の
類にもつねに
分裂によって
繁殖するものがある。
普通の「ひとで」でも
腕が一本切れたときには、直ちにその代わりが生ずるが、
熱帯地方に
産する
種類には、自身で体を二分し
各片が
成長してしまいに
二匹の
完全な
個体となるものがある。
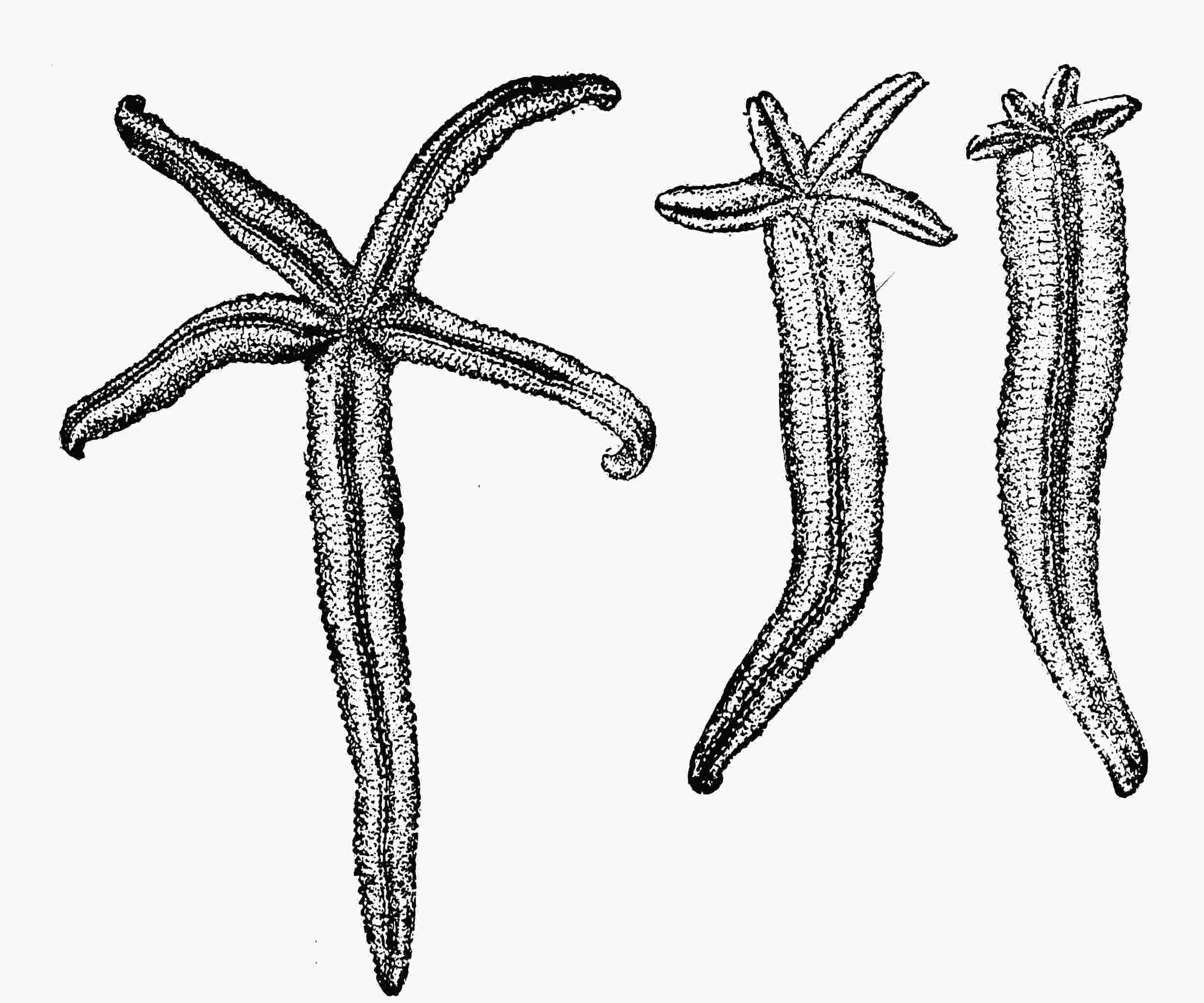 ひとでの分裂生殖
ひとでの分裂生殖
「ひとで」の体は中央の
胴と、それより出ている五本の
腕とから
成るが、
普通の「ひとで」では
腕が一本切れると、
胴のほうから
再び
腕を生じて体が
完全になる。しかし切れた
腕のほうはそのまま死んでしまう。しかるに
或る
種類のものでは
胴から新たに
腕が生ずるほかに、切れた
腕のほうからは新たに
胴と四本の
腕とが生じて
都合二匹になる。人間にくらべていえば、右の
腕を一本切り取ると
胴のほうからは右の
腕が新たに生じ、その切り取った右の
腕は
傷口から肉が
増してまず
胴ができ、次に頭と左の
腕と両足とが
延び出て、しまいに二人の
完全な人間になることにあたる。これは
分裂ではあるが、体の一小部分が
基礎となって
残余の部分がことごとく新たに生ずるのであるから、よほど
芽生にも
似ている。
畢竟分裂といい
芽生というのも
一個体が
二片に分かれるときの両半の大いさによることで、もしも両半の大いさがほぼ
相ひとしければこれを
分裂と名づけ、両半の大いさがいちじるしく
違うて大きいほうはもとの
個体そのままに見える時には、これを
芽生と名づけるにすぎぬ。前に
例にあげた「ごかい」
類の
分裂生殖でも、今ここに
述べた「ひとで」の
分裂生殖でも、見ようによっては
芽生の
一種と名づけられぬこともなかろう。
ここに
再生というのは、一度死んだ者が
再び生き返ることではない。一度
失うた体部を
再び生ずることである。
敵に
襲われたとき、身体の一部を自身で切り
捨てて
逃げ去るもののあることは、すでに前の章で
述べたが、かような動物では
再生の
能力がよく
発達して、たちまちの間に
失うた体部を
回復する。
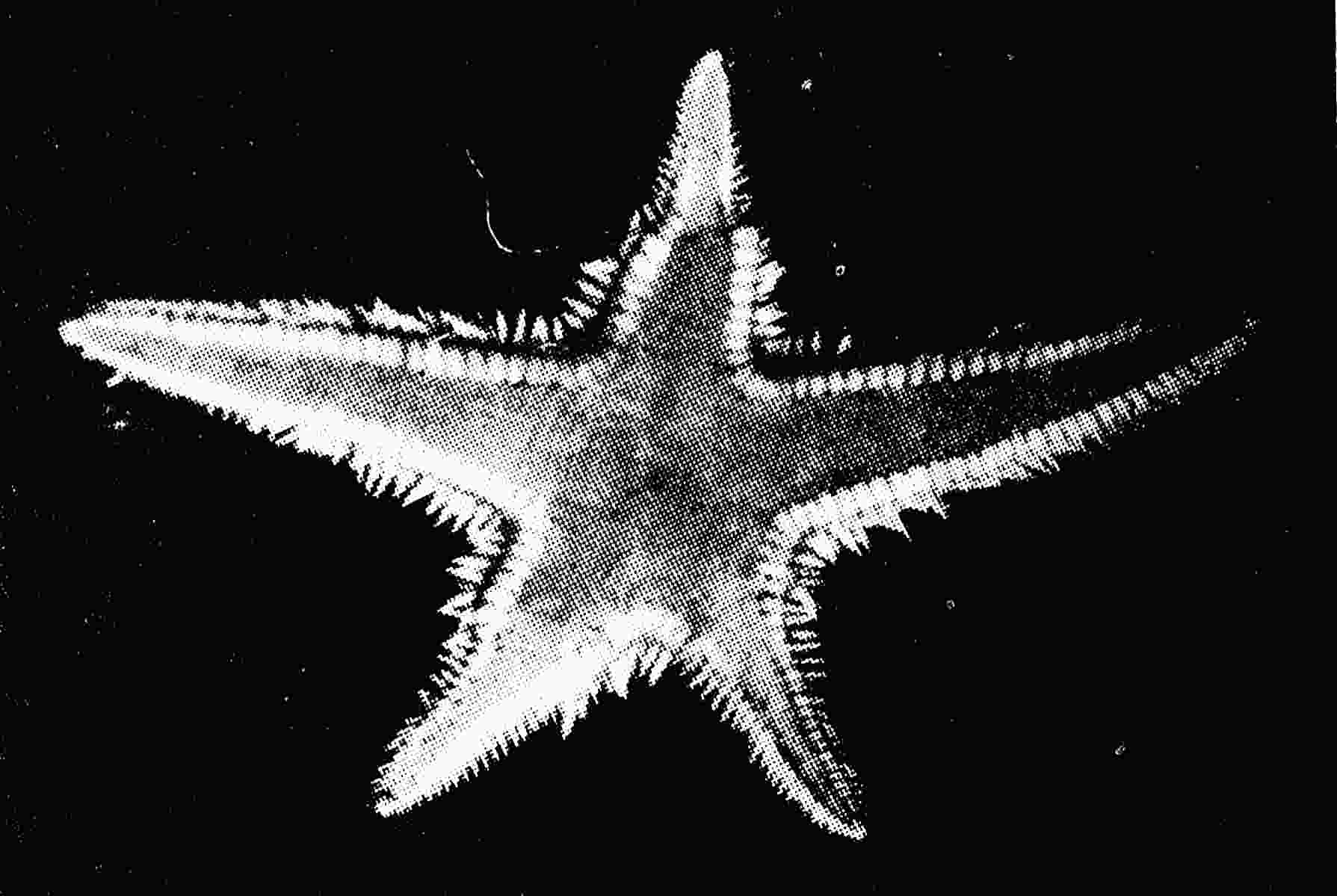 ひとでの再生
例
ひとでの再生
例えば、「かに」は足を切られても
再び足が生じ、「ひとで」は
腕の先を
折られてもたちまち
腕の先が
延びる。これはその動物にとってはもっとも
必要なことで、もしこの力がなかったならばたとい
一応は
敵の
攻撃をまぬがれ
得ても、その後食うて
産んで死ぬのにたちまち
差支えが生ずるに
違いない。しかしながら
再生ということはかような動物に
限ったわけではなく、よく調べて見ると
如何なる動物でもこの力の
備わっていないものはない。元来
再生とは、
失うた部分を
再び
得るだけであって、
別にそのために
個体の数がふえるわけでないゆえ、
生殖という中にはむろんはいらぬが、
分裂や
芽生のごとき
無性生殖にくらべて見ると、その間にはけっして
境が定められぬほどに
性質の
相ひとしいものゆえ、
参考のためにこの章に
加えておく。
分裂生殖では、親の身体が二分して
二匹の子となるのであるから、できたばかりの子は、大きさが親の半分よりないというほかに、身体の部分が半分
不足している。「いそぎんちゃく」のごとくに
縦に切れるものでは、右の半分には左半身だけ足らず、左の半分には右半身だけ足らぬ。また「ごかい」のごとくに横に切れるものでは、前の半分には後半身が足らず、後の半分には前半身が足らぬ。それゆえ
分裂によって生じた
各個体は、まずこれらの
不足する体部を生じなければ
完全なものとはならぬが、
不足する体部を生ずるのはすなわち
再生である。されば
分裂生殖は
再生とは
離るべからざるもので、
再生によって
補わなければ、とうてい
分裂生殖は行なわれぬ。
芽生もこれと同様で、ほとんど
極度まで
発達した
再生力と見なすことができる。「こけ虫」の
横腹に生じた小さな
瘤から
一匹の新しい「こけ虫」ができるのも、一本の
腕の切れ口から新しい「ひとで」のほとんど全部が生ずるのも、発生の
模様は全く同じであり、「いもり」の足が一度切られた後に
再び生ずるのも、人間の
腕が
胎内で
漸々でき上がるのも、ほとんど同一の
経路を
通過するのを見れば、
分裂も
芽生も
成長もみな同一の
現象の
異なった
姿にすぎぬように思われ、かような
例を数多くならべて見ると、
個体の数をふやす
生殖も、その根本をたずねれば、
個体の大きさを
増す
成長と同じ
性質のものであることが明らかに知れる。次に人体にも
普通に行なわれている
再生の
例をあげて見よう。
失うた手や足を
再び生ずるほどのいちじるしい
再生力は高等の動物には全く見られぬ。「いもり」の切られた足が
再び生ずるのを
除けば、
脊椎動物には目だつほどの
再生の
例はほとんどない。しかし目だたぬ
再生ならばいたるところに
絶えず行なわれている。
例えばわれわれが湯にはいって
皮膚をこするとたくさんに
垢が出るが、
垢はけっして外から
付着した
塵や内から
浸み出した
脂ばかりではない。その大部分は
皮膚の表面から
削り取られた
細胞である。それゆえ、
垢が取れただけ
皮膚は
薄くなるべきはずであるに、何度湯にはいって何度こすっても
皮膚が
実際薄くならぬのは、全く
皮膚の下の
層で
絶えず新たな
細胞がふえるからである。人間や
獣類の
皮膚は
表皮と
真皮との重なったもので、表皮はさらに表面の
乾いた
角質層と、その下の
濡れた
粘質層とに分けることができる。
皮膚を深くすりむくとむろん血が出るが、
極めて
薄くすりむいたときには血が出ずして
単に
湿った表面が
現われる、これがすなわち
粘質層である。さて
垢となって取れるのは、いうまでもなく
角質層の上部であるが、新たな
細胞の
絶えずふえているのは
粘質層の下部である。
粘質層の下にある
真皮までは
血管が来ているから、
粘質層の下部に
位する
細胞はこれより
滋養分を
得てつねに
増殖し、ふるい
細胞をたんだん上のほうへ
押し上げると、その
細胞は
次第々々に
形状も
成分も
変化し、始め
濡れて丸くあったものが、
漸々扁平になり
角質に
変わって、ついに
皮膚の表面まで
達するのである。されば
皮膚の
厚さは始終同じであっても、けっして同じ
細胞が長くとどまっているわけではなく、表面のふるい
細胞は
絶えず
垢となって
捨てられ、深い
層の
細胞がつねにふえてこれを
補うているから、あたかも
滝の形は
昨日も今日も同じでありながら、
滝の水の
一刻も止まらぬのとよく
似ている。 かように
細胞の
新陳代謝することは、けっして
皮膚に
限ったわけではない。身体の内部においても
理屈はほぼ同様である。食道や
腸胃の内面の
粘膜でも、けっして同じ
細胞がいつまでもとどまっているのではなく、つねに新しい
細胞と入れ
換わっている。その他
如何なる
組織でも生きている間は
細胞の入れ
換わらぬものはないが、
特に毎日
忙しく全身を
循環して、
瞬時も休まぬ赤血球のごときは、
一箇一箇の
寿命ははなはだ短いもので、
暫時役をつとめた後は新たにできたものと交代する。身体内ではつねに新たな
細胞ができて、ふるい
細胞の
跡をふさぐゆえ、すりむけたところも少時でなおり、
傷口もしだいに
癒える。
赤痢や「
腸チフス」で
傷の内面が
壊れたのが後にいたって
全快するのも、同じく新しい
細胞が生じてふるい
細胞の
不足を
補うからであるゆえ、これなども
立派な
再生と言える。かくのごとく
再生は
如何なる動物の生活にも
必要なことで、日々の生活はほとんど
再生によって
保たれるというてよろしいが、人間や
獣類では
表皮の
不足を
残りの
表皮から
補い、
粘膜の
不足をつづきの
粘膜から
補うぐらいの
程度にとどまり、指を一本
失うてもこれを
再び生ずる力はない。それゆえ、「かに」が足を
再び生じ、「ひとで」が
腕を
再び生ずるのを見て、よほど
不思議なことのごとくに感ずるが、よく考えて見ると、これは
垢として取れた
表皮細胞をその
下層からつねに
補うているのにくらべて、ただ
程度が
違うのみである。
低度の
再生と高度の
再生との間にはもとより
判然たる
境界はないが、高度の
再生と
分裂、
芽生等の
無性生殖との間にも
境界がなく、体内
芽生と
単為生殖との間にも、いずれともつかぬあいまいな場合があるとすれば、世人が
生殖といえば、ただそれのみであるごとくに思うている
雌雄交接を
要する
有性生殖から、世人が
生殖とは何の
関係もないごとくに考えている
表皮の
再生までの間に
順々の
移り行きがあるわけで、その間にはどこにも
明瞭な
境界線はなく、すべて新しい
細胞の
増殖に
基づくことである。ただその
結果として
個体の数がふえれば
生殖と名づけ、
個体の大きさが
増せば
成長と名づけ、一度
失うた部を
補う場合にはこれを
再生と名づけて
区別するにすぎぬ。
前章に
述べたとおり、生物の
生殖には
種々の
異なった
方法があるが、その中でもっとも進んだ、かつもっとも広く行なわれているものは、むろん
雌雄による
有性生殖である。人間をはじめとして多数の高等動物では、
生殖といえばすなわちこの
方法のみで、その他には
個体の数をふやす
途はない。しこうして
雌雄の間には
生殖器官の
構造を
異にするほかに、
雌雄相求めるための
特殊の
性質を
備えたもの、生まれた子を育てるための
特殊の
構造を有するものなどがあり、
特に多数
相集まって
団体をつくる
種類では、
雌雄の
別に
基づく
複雑な
心理的の
関係も生じて、生物界における
各種の
現象中でももっとも
興味の深いものがある。
雌雄の
相合するため、ならびに子を育てるために、
両性の間に分業の行なわれる場合には、
雌のほうに
乳房が大きくなり、
雄のほうに
牙が
鋭くなるというごとき身体上の
変化のほかに、
慈愛、
勇気、
堪忍、
冒険などのごとき
精神上の
性質も、
雌と
雄との間に
不平均に分かたれ、
心理状態もいちじるしく
異なるにいたるであろうから、長い間かような分業の行なわれていた動物では、
雄は
心理的に
雌を
理解することができなくなり、
雌の
挙動を見て
永久に
不可解の
謎のごとくに感ずるかも知れぬ。しかもかく
相異なるにいたったみなもとをただせば、一方は
卵巣内に
卵細胞を生じ、一方は
睾丸内に
精虫を生じて、
互いに
性質の
相異なった
生殖細胞を体内に生ずるからである。されば
雌雄の
別に
基づく身体の
構造や
精神の作用を
論ずるにあたっては、まず
卵細胞と
精虫との由来を十分明らかにしておかねばならぬ。
さて
普通の動植物の身体が
無数の
細胞より集まり
成ることは、今日ではほとんどだれでも知っているようであるが、
卵と
精虫との
素性を明らかにするには、まず
細胞や
組織のことをやや
詳しく
述べておく
必要があるゆえ、
念のためここに一とおり
細胞のことから
説明する。
そもそも生物の身体が
細胞からなることの始めて知れたのは、今よりわずかに七八十年前のことで、それ
以前にはかようなことには少しも心づかずにいた。しこうしてその後にも
細胞という考えはだんだん
変化して今日まで進み来たったゆえ、同じ
細胞という文字を用いても七・八十年前と今日とでは大分意味も
異なっている。植物の
組織では
各細胞に
膜質の
壁があって、
互いの間の
境がすこぶる
判然している。
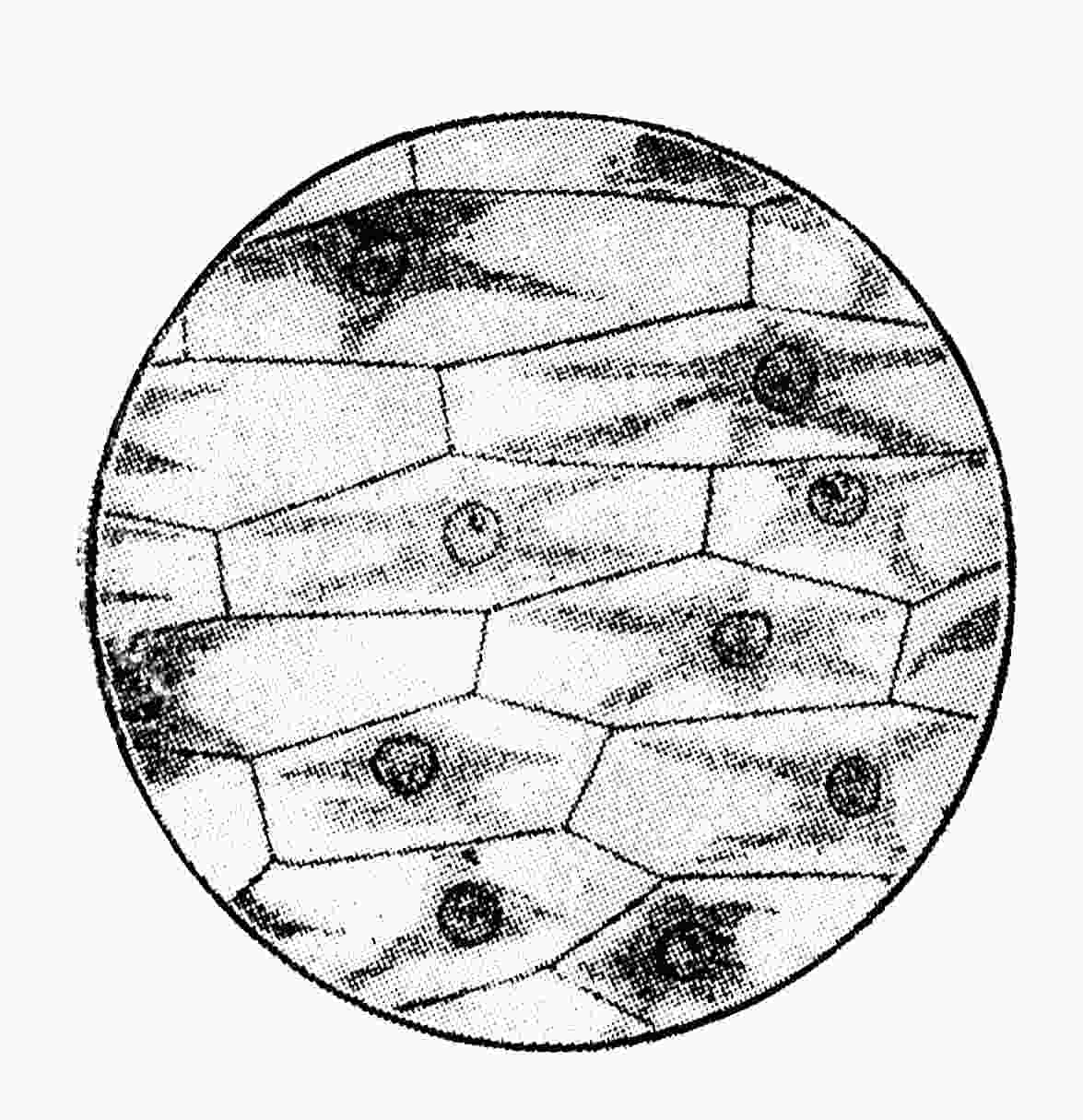 葱の葉の表皮
試
葱の葉の表皮
試みに草の葉を取って、その表面の
薄皮をはぎ取り、これを度の
低い
顕微鏡でのぞくと、
無数のほぼ同大の区画があって、あたかも細かい
小紋の
模様のごとくに見えるが、その区画の一つ一つがすなわち
細胞である。またコルクの
一片を
薄く
削って
顕微鏡で見ると、一面に
孔だらけでまるで
蜂の
巣のようであるが、その
孔の一つ一つが
細胞である。ただしこの場合には全部がひからびているゆえ、
細胞はただ
壁ばかりとなって内部は全く
空虚である。かように植物では
細胞を見ることが
比較的容易であるゆえ、
最初細胞の発見せられたのも植物であった。しこうして
最初は
細胞の
壁のみを重く考え、
細胞を
一種の
嚢と見なし、植物の体はかような
顕微鏡的の小さな
嚢の
無数に集まって
成れるものと思った。しかしだんだん調べて見ると、
嚢の
壁は
必ずしもなくてならぬものではなく、かえってその
内容のほうが生活上もっとも大切なものであることが明らかになった。そのわけは植物でも、
芽の出たての
若い
柔らかい部分を取って見ると
細胞の
壁は
極めて
薄く、もっとも
若いところではあるかないかほとんどわからぬほどで、ただ
内容のほうが
充満している。
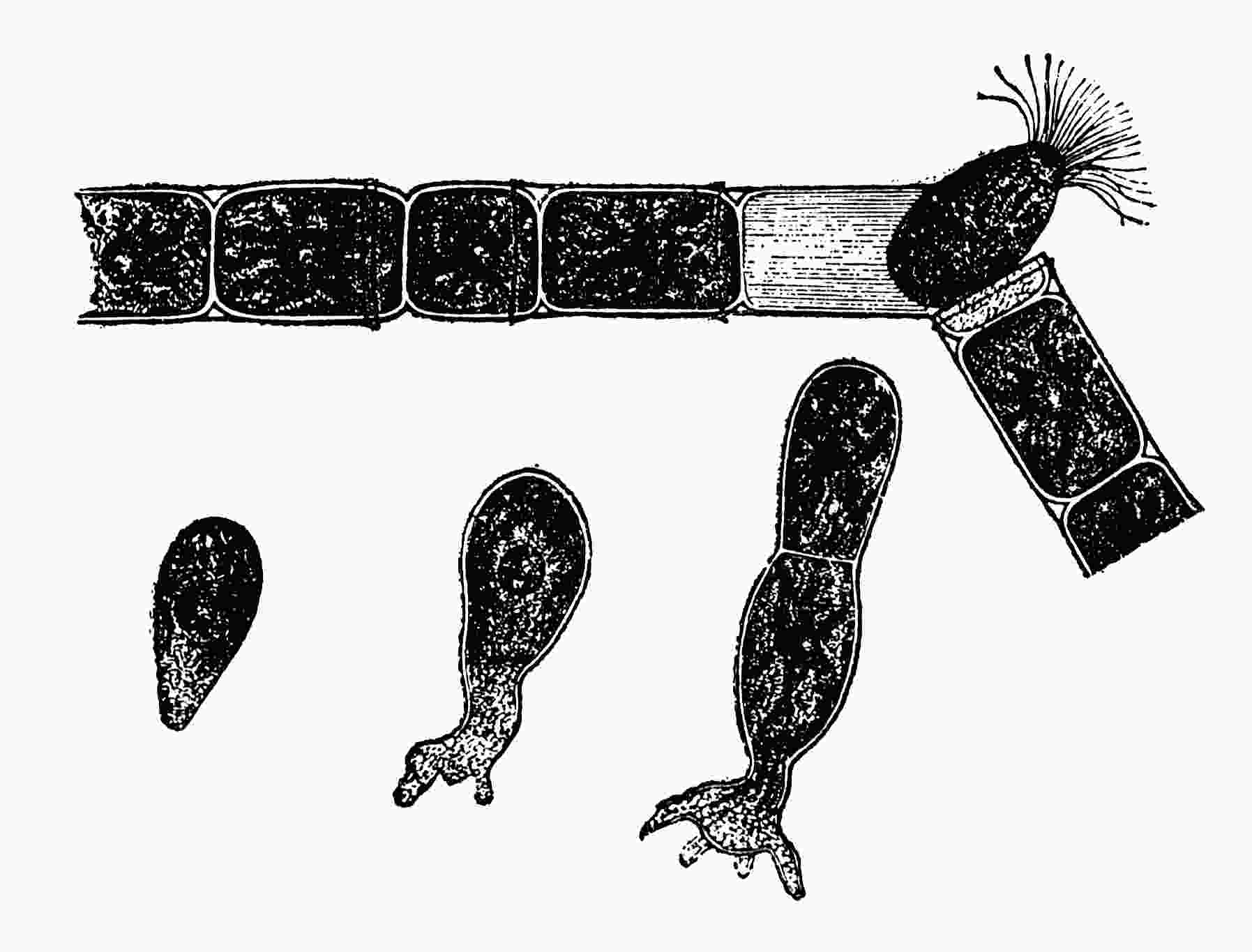 藻類の細胞の内容が壁から離れて水中へ游ぎ出し後にいたって新たに壁を生ずるを示す。
藻類の細胞の内容が壁から離れて水中へ游ぎ出し後にいたって新たに壁を生ずるを示す。
また
淡水産の
微細な
藻類などを
顕微鏡で見ていると、
往々細胞の
内容だけが
壁から
離れ、
壁の
割れ目から水中へ
游ぎ出すことがある。
初めてこれを見つけた学者は、植物が
変じてにわかに動物に
成ったと言うて
大騒ぎをしたが、かように
游ぎ出した
内容物は、直ちに
壁を
分泌して
完全な
藻類となり、
内容の
抜け出した
壁のほうは、ついにそのまま
枯れてしまう。
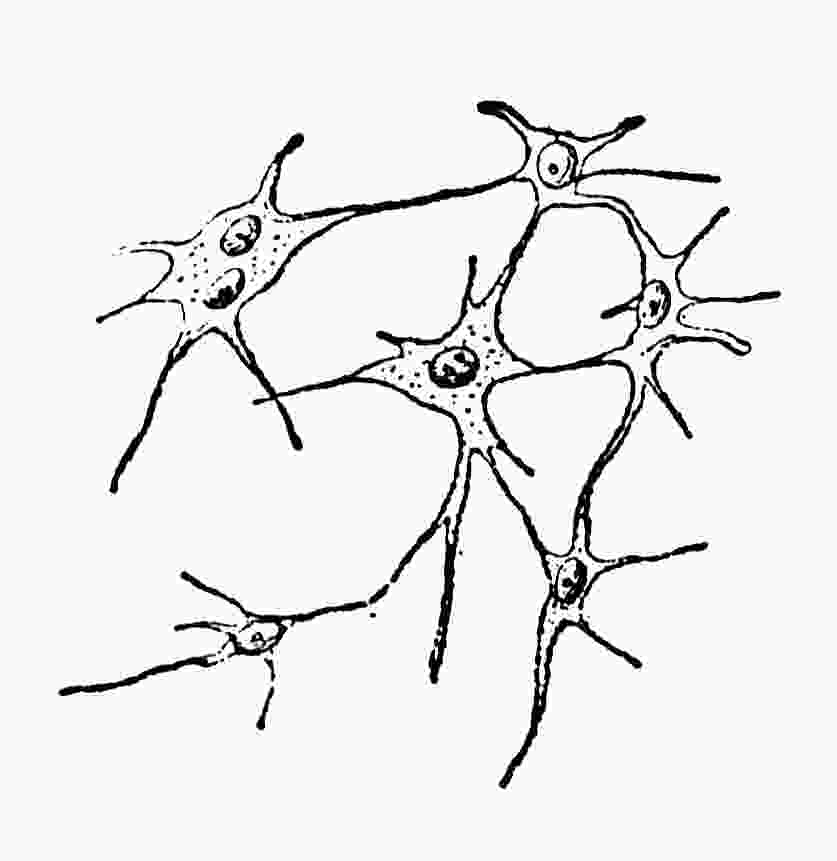 結締組織の星形細胞6箇
結締組織の星形細胞6箇
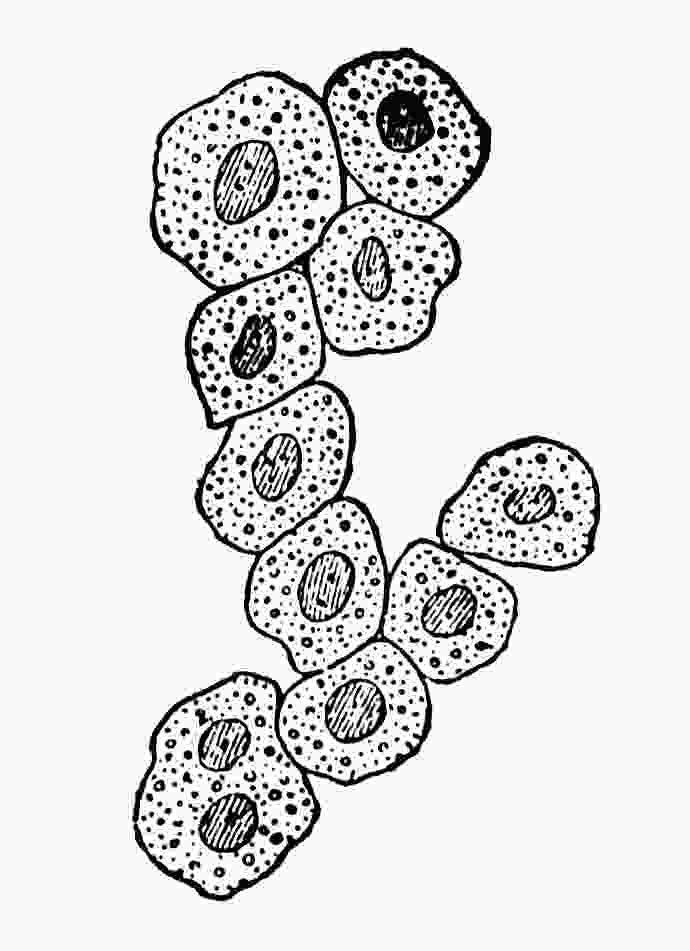 肝臓の球形細胞10箇
肝臓の球形細胞10箇
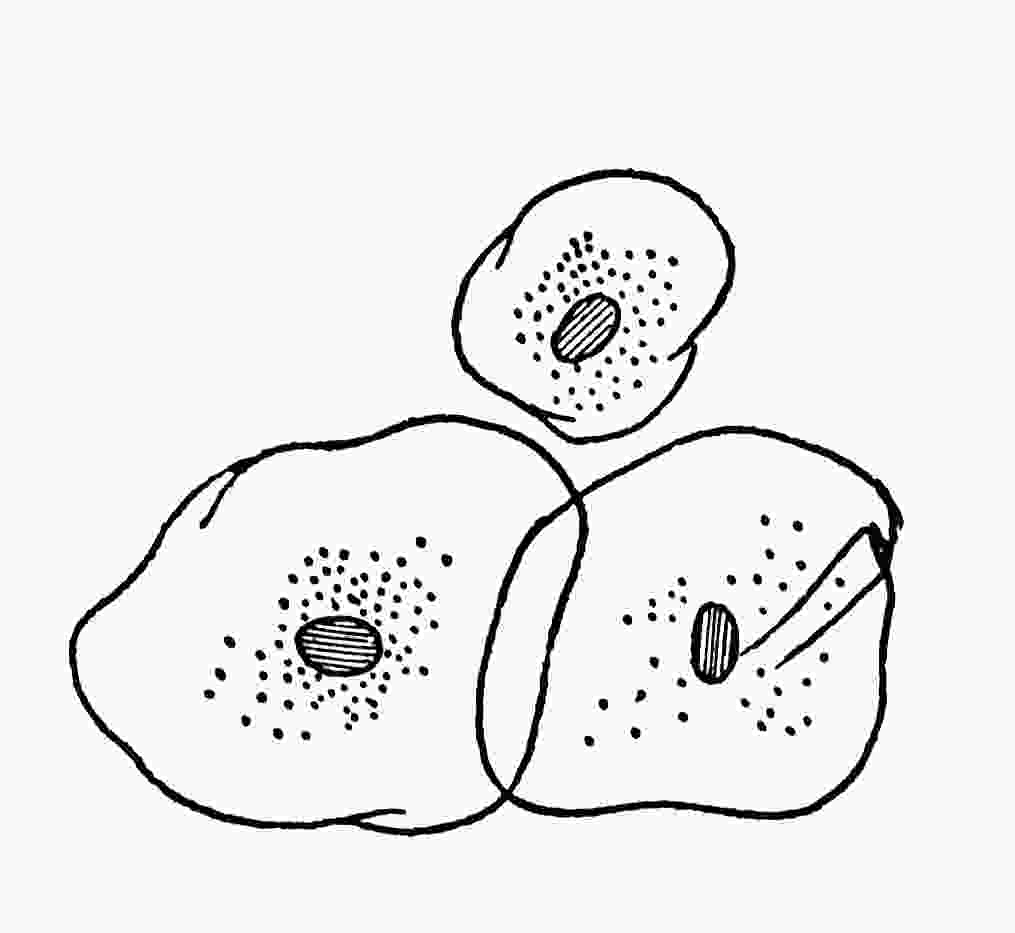 '頬の内面の扁平細胞3箇
'頬の内面の扁平細胞3箇
すなわち真に生活するのは
嚢の内部を
満たす半流動体の
柔らかい
物質であって、
壁はただこれを
包み
保護するにすぎぬ。今日ではこの
柔らかい生きた
物質を
原形質と名づける。されば昔植物の体は
無数の
小嚢より集まり
成れるもののごとくに考えたのは
誤りであって、実は
原形質の
小塊の
無数に集まったものである。しこうして
各小塊はその
周囲に
細胞膜質を
分泌して
壁をつくり、後には
原形質は死んでなくなり、
細胞の
壁のみが
残るゆえただ
嚢のように見える。なお
各細胞をなせる
原形質の
小塊の中央には、あたかも
桃や
梅の実の中央に
核があるごとくに
必ず
一個の
特別な丸いものが見える。これを同じく
核と名づける。それゆえ今日では
細胞の
定義を次のごとくに言うことができる。すなわち
細胞とは
一個の
核を有する
原形質の
小塊であると。植物でも動物でも身体は多数の
細胞の集まりであるというのは、かような意味の
細胞であって、けっして昔考えたような
嚢のことではない。
細胞という
訳語もこれに対する原語もともに
嚢という意味の字であるが、これは昔
細胞を
一種の
嚢と考えたころからの
遺物であって、今日ではただ
習慣上用いつづけているにすぎぬ。
動物でも植物でもその身体には、
柔らかいところや
堅いところ、ぬれたところやかわいたところと
種々の
異なった部分があるが、これはみなその部をなせる
細胞の
形状性質や集まり方に
相違があるによる。
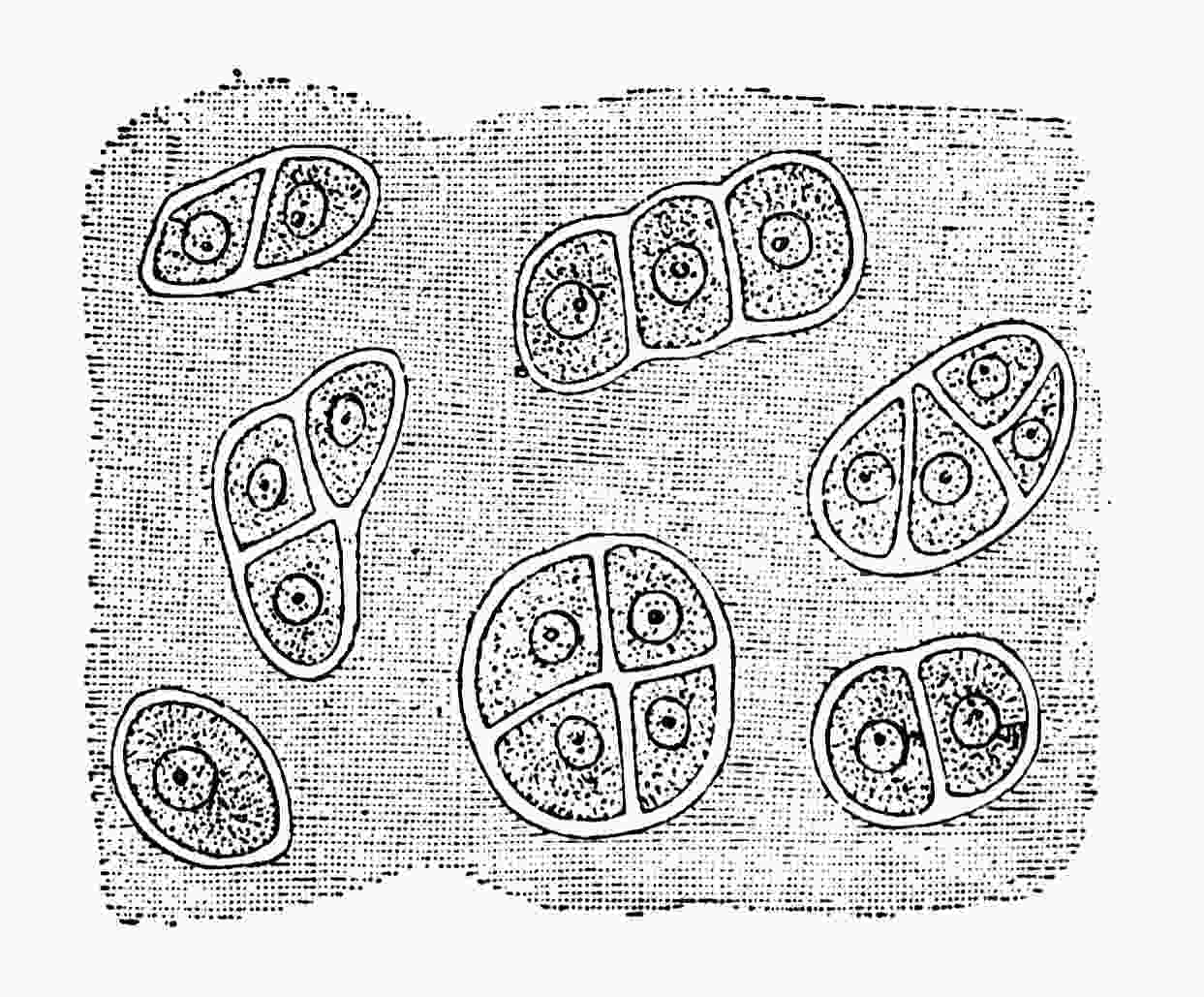
軟骨組織
細胞間質の多きを示す
例えば人間の身体にもかわいた
表皮やぬれた
粘膜、
柔らかい
筋肉や
堅い
骨などがあるが、それぞれその部分の
細胞が
違う。しこうして
細胞は細長いものや平たいもの、
柔らかいものや
堅いものが、
雑然と一ところに
混じているごときことはけっしてなく、
必ず同じような
細胞ばかりで数多く集まっている。なわち
扁平な
細胞ならば多数集まって
層をなし、細長い
細胞ならば多数ならんで
束となり、かわいて
堅い
細胞は
相集まって
爪などのごときかわいて
堅い部分をつくり、ぬれて
柔らかい
細胞は'
頬の内面のごときぬれて
柔らかい部分をつくる。かように
同種の
細胞の数多く集まったものを
組織と名づける。
細胞が
組織をつくるにあたっては、
互いに
直接に
相触れて集まることもあれば、また
各細胞が
或る
物質を
分泌し、
細胞はその
物質のために
隔てられて
相触れずに集まっている場合もある。かような
物質を
細胞間質という。
細胞間質によって
細胞が
隔てられているありさまは、あたかも
煉瓦がモーターで
隔てられているごとくであるが、
組織の
種類によっては
細胞間質が
細胞よりもはるかに
分量の多いものもある。かような場合には
細胞間質が
堅ければ
組織全体も
堅く、
細胞間質に
弾力があれば
組織全体にも
弾力があることになる。
骨の
組織の
堅いのは
細胞間質が
石灰を
含んで
堅いからであり、
骨膜や
腱の
組織の強
靭なのは
細胞間質が
繊維性で強いからである。両方とも
細胞自身はすこぶる
柔らかい。
以上述べたごとく、
細胞にも
組織にもさまざまの
種類があるが、これはみな身体を組み立てる
材料であって、
如何なる
器官でもそのいずれかより
成らぬものはない。身体を家屋にたとえて見れば、
種々の
組織は板、柱、
壁、
畳などに相当するもので、
肺、
肝、
腸、
胃などの
器官はあたかも
玄関、
居間、
座敷、台所などにあたる。すなわちこれらの
器官は形も
違い
働きも
異なるが、いずれも
若干の
組織の組み合わせでできているという点は
相ひとしい。されば
細胞が集まって
組織をなし、
組織が組み合うて
器官をなし、
器官が
寄って全身をなしているのであるから、
細胞は身体
構造上の
単位とも見なすべきもので、これをよく
了解することは身体の
如何なる部分を
論ずるにあたっても
必要である。しこうして
各細胞の
寿命は全身の
寿命に
比してはるかに短いゆえ、
絶えず
新陳交代しているが、
子供が
漸々成長するのも、病気でやせたのが
回復するのもみなその間に
細胞の数がふえることによる。あたかも毎日人が生まれたり死んだりしている間に、三千五百万人が四千万人五千万人となって、日本
民族が大きくなったのと同じである。また人間でも他の生物でも親なしには
突然生ぜぬとおり、
細胞のふえるのもけっして
細胞のないところへ
偶然新たな
細胞が生ずるというごときことはなく、
必ずすでにあった
細胞の
繁殖によって数が
増してゆくのであって、その
際には毎回まず始め
一個の
細胞の
核が
分裂して
二個となり、次に
細胞体も
二個に分かれてその間に
境ができ、しまいに
二個の
完全な
細胞になり終わるのである。ただし場合によっては
核が
分裂しただけで
細胞体は分かれぬこともあり、また
細胞と
細胞との
境が消え
失せて
相つながってしまうこともあるゆえ、実物を調べて見ると
幾つとかぞえてよいかわからぬようなことも
往々ある。
 細胞なき海藻類
特
細胞なき海藻類
特に
或る
種類の
海藻では、大きな体が全く
境界のない
原形質からなり、その中に
無数の
核が
散在しているだけゆえ、
細胞という字は全く当てはまらぬ。生物体は
細胞より
成るというのはけっして
間違いではないが、かような
例外とも見える場合のあることを
忘れてはならぬ。
普通の動植物の身体をなせる
細胞は、おのおのその
専門の役目をつとめるに
適するように
変化しているゆえ、
種類の
異なったものが多数に
相集まって、始めて
完全な生活を
営むことができる。もしも一つずつに
離して
互いに
相助けることを
妨げたならば、
各細胞はとうてい長く生活することはできず、
暫時の後には
必ず死んでしまう。
例えば
胃の
細胞は
胃液を出して
蛋白質を消化する
働きはあるが、
呼吸もできず運動もできぬから
独立しては生きてはいられぬ。また
肺の
細胞は
酸素を
吸い入れ
炭酸ガスを
排出して
呼吸する
性質を
備えているが、食う力も消化する力もないゆえ、
血液と
離れては命を
保つことはできぬ。しかるに広く生物界を
見渡すと、かようなもののほかに
細胞が一つ一つで長く生活しているものがある。これはすなわち
単細胞生物と名づける
顕微鏡的の
極めて小さな生物で、そのうち植物らしいものを原始植物、動物らしもいのを原始動物と名づける。高等の動物と植物とではその間の
相違がいちじるしいからだれも
間違うものはないが、
顕微鏡で見るような下等の動植物になると、その間の
区別がすこぶるあいまいでとうてい
判然した
境界は定められぬ。それゆえ
或る
種類の
単細胞生物は、動物学の書物には動物としてかかげてあり、また植物学の書物には植物として
掲げてある。
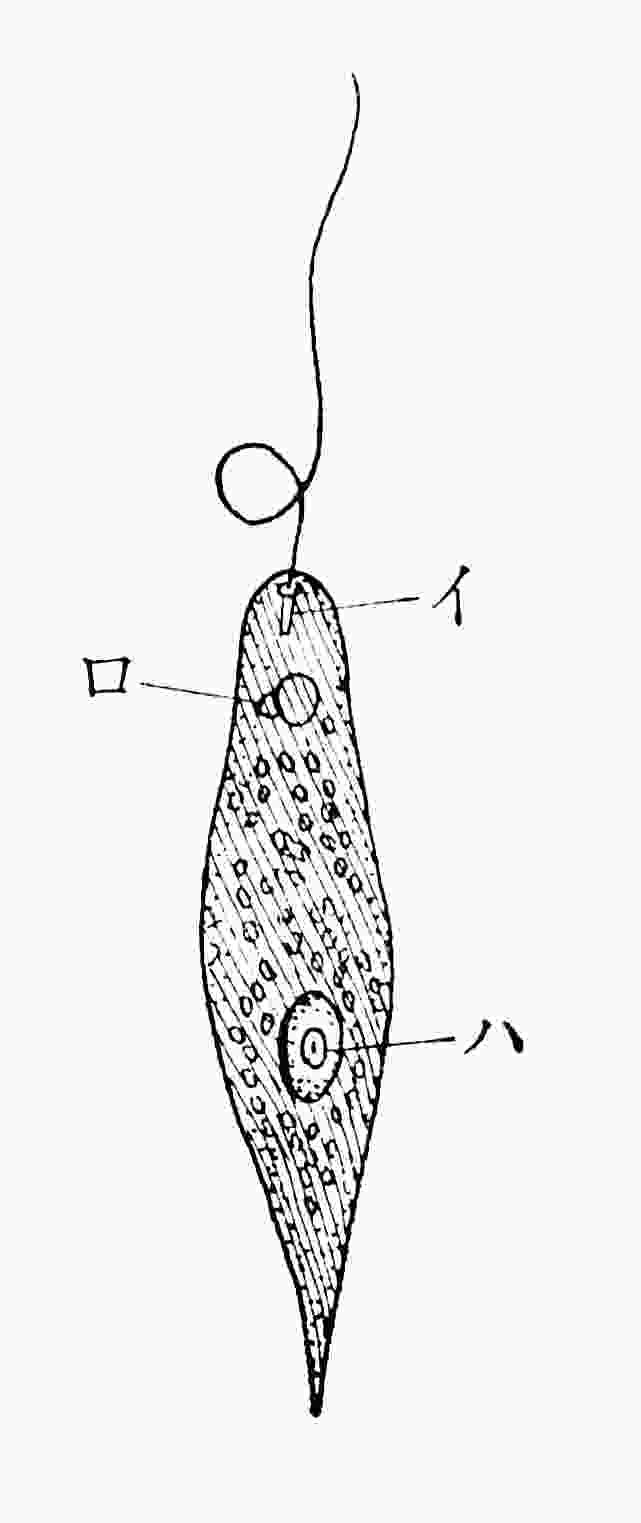
みどり虫
(イ)口 (ロ)収細胞 (ハ)核
例えば「みどり虫」や「
虫藻」の
類はみなかような
仲間に
属する。
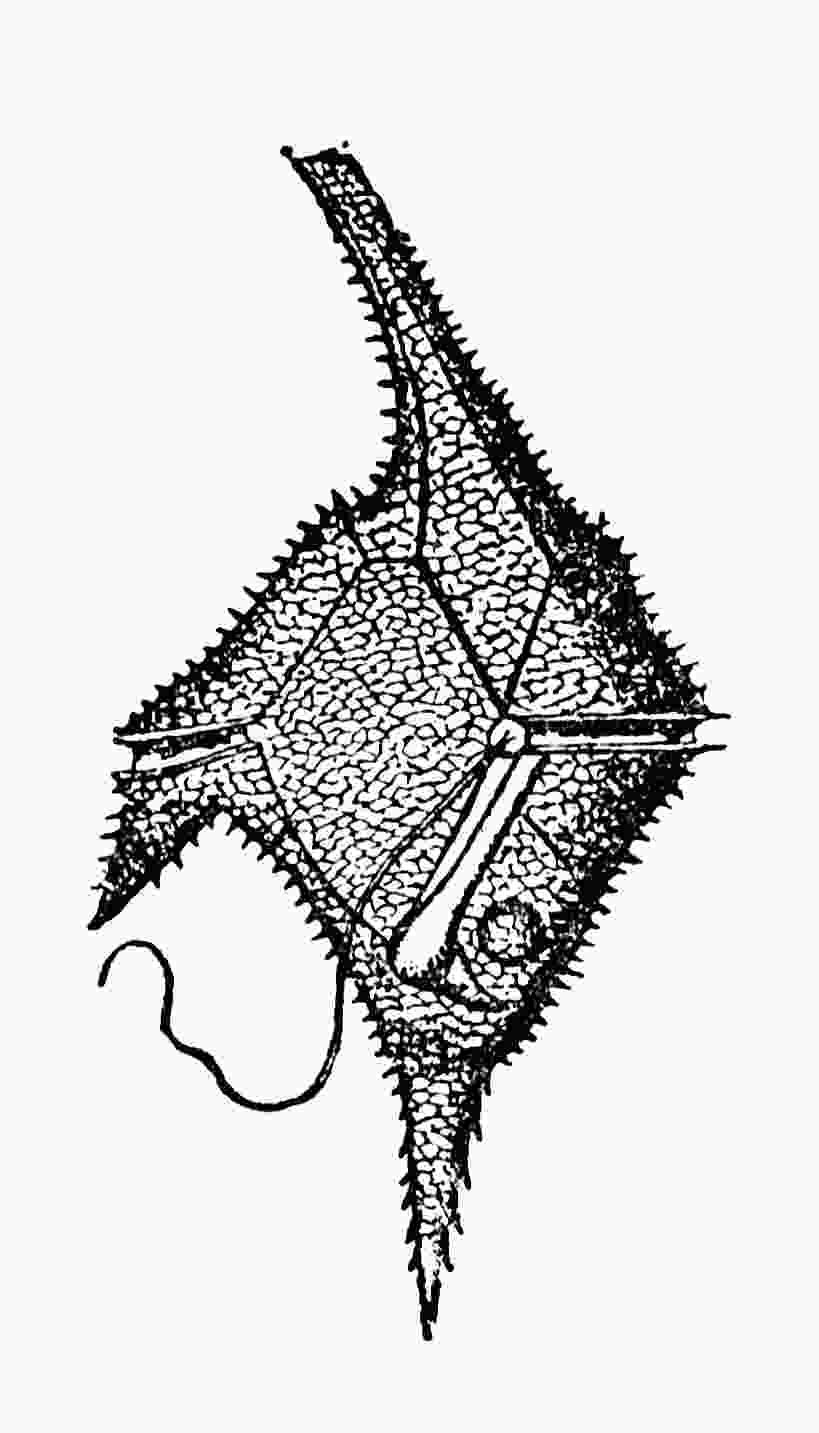 虫藻
単細胞
虫藻
単細胞の生物は全身が
単一の細細より
成るが、この一つの
細胞をもって、運動もすれば消化もし、
呼吸もすれば
感覚もする。しこうして
生殖するにあたっては、
通常は
簡単な
分裂法によって
二匹ずつに分かれるが、多くの
種類ではなおそのほかにときどき
二匹ずつ
相接合して身体の
物質を
混ぜ合わすことが行なわれる。これは高等生物の
雌雄生殖によく
似たことで、
確かにその
起源とも見なすべき
極めておもしろい
現象であるゆえ、次に少しく
詳細に
述べておこう。
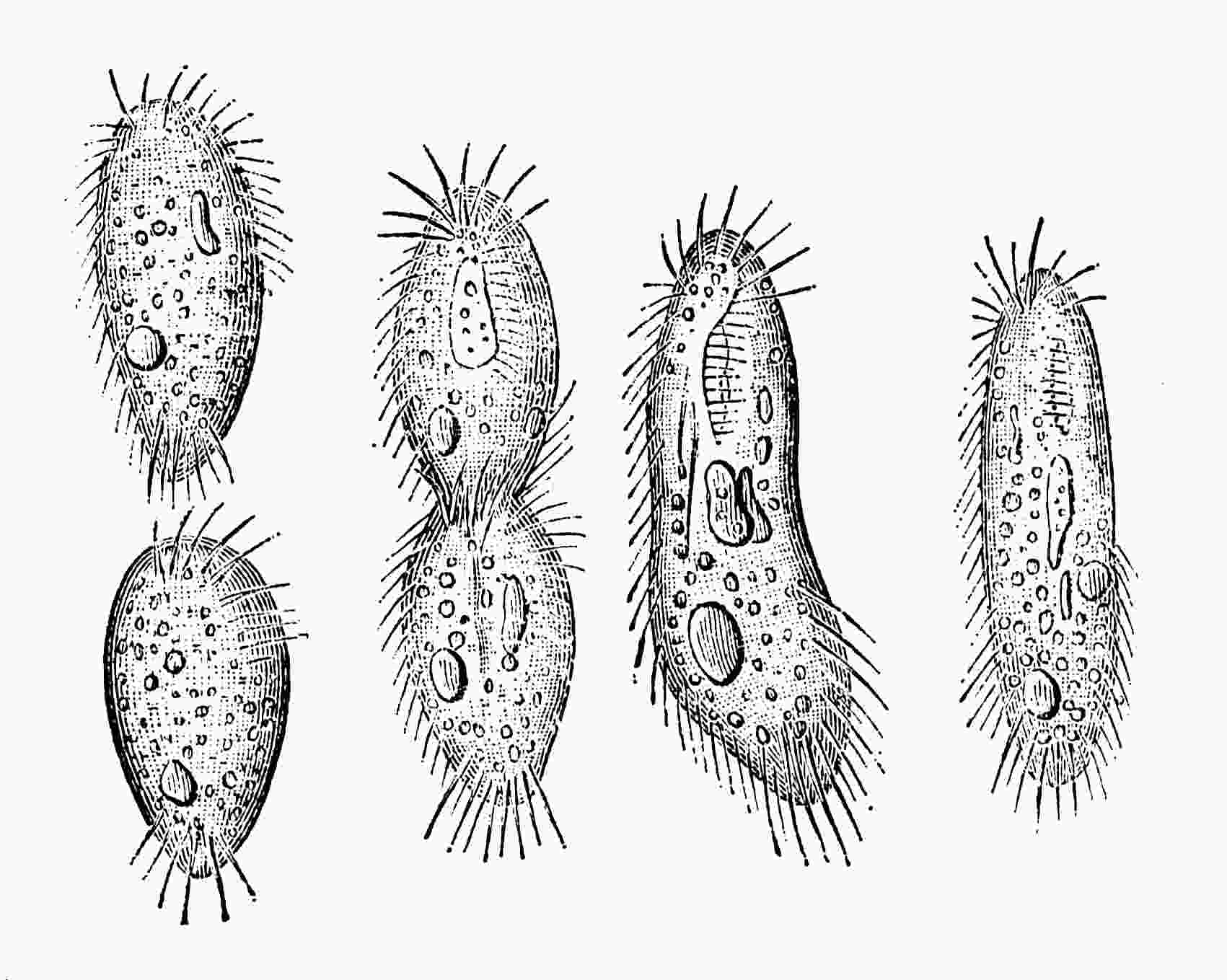 ぞうり虫の分裂
花瓶
ぞうり虫の分裂
花瓶内の古い水を
一滴取ってこれを
顕微鏡で調べて見ると、その中に
長楕円形で全身に
繊毛をかぶった虫が活発に
游ぎまわっているが、これは「ぞうり虫」と名づける
一種の原始動物である。体の
前端に近いほうの
腹側に
漏斗状の
凹みがあるが、これはこの虫の口であって、
黴菌や
藻類の
破片などの
微細な食物が
絶えずここから体内へ食い入れられる。つねに
忙しそうに
游ぎまわって食物を
探し
求め、
砂粒などにつきあたればこれを
避けて
迂回し、さらにあちらこちらと
游ぐ様子を
顕微鏡でのぞいていると、
如何にも運動も活発、
感覚も
鋭敏であるように思われ、まるで
鼠か「モルモット」でも見ているような心持ちがする。かく
絶えず食物を
求めてこれを食い、
漸々成長して一定の度に
達すると体が二つに分かれて
二匹となるが、その
際にはまず
核がくびれて二つとなり、
一個は体の前方に
一個は体の後方に
移り、次に身体が横にくびれてあたかもひょうたんのごとき形になり、しまいに切れて
二匹の
離れた虫となってしまう。「ぞうり虫」の
繁殖法は
通常はかような
簡単な
分裂法によるが、しかしこの
方法のみによっていつまでも
繁殖しつづけることはできぬらしい。
或る人の
実験によると、
如何に食物を十分に
与え生活に
差支えのないように注意して
飼うても、
分裂生殖を何度も
繰り返して行なうていると、虫がだんだん弱ってきて、身体も小さくなり
勢いも
衰え、二百代目か三百代目にもなると、ついには
自然にことごとく死に
絶える。しからば「ぞうり虫」が
実際種切れにならずに、どこにも
盛んに生活しているのは
何故であるかというに、これは
分裂生殖をつづける間におりおり
系統を
異にする虫が
二匹ずつ
寄って
接合するからである。
接合によって
二匹の虫が
体質を
混じ合わせると、いったん
衰えかかった体力を
回復し
勢いが
盛んになって、さらに
分裂によって
繁殖しっづけ
得るようになるのである。
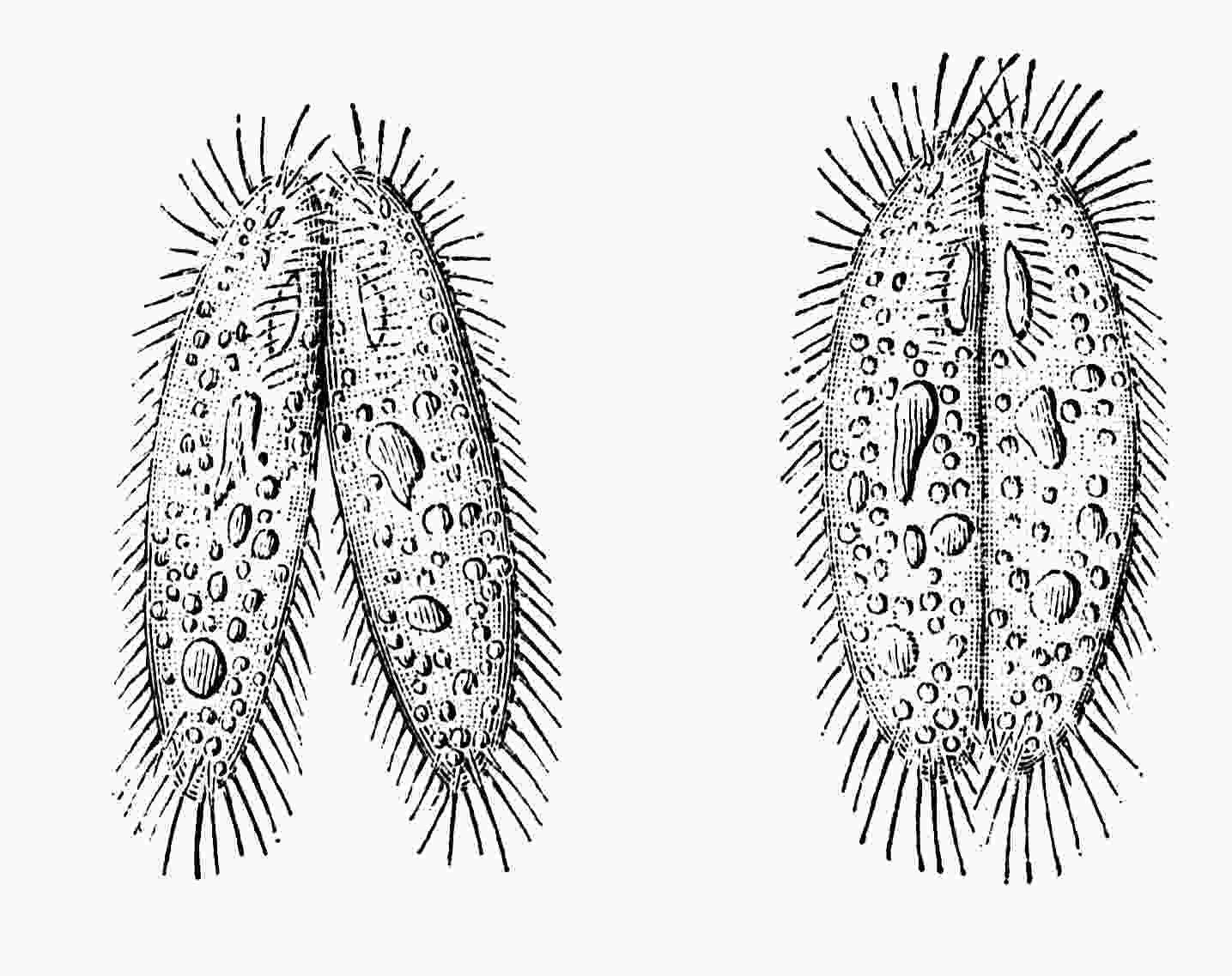 ぞうり虫の接合
ぞうり虫の接合
かように
二匹の「ぞうり虫」が
接合するところを見るに、まず
腹と
腹とを合わせ、口と口とで
吸いつき、
互いにできるだけ身体を
密接せしめ、次に
腹面の一部が
癒合し、身体の
物質が
相混ずる。この
際もっともいちじるしいのは
核が
複雑な
変化をすることであるが、
結局いずれの虫も
核が二分し、一半はその虫の体内にとどまり、一半は相手の虫の体内に
移り
行いてその内にある
核と
結びつき、両方ともに新たな
核ができる。これだけのことが
済むと、今まで
相密接していた
二匹の虫は
再び
離れて、おのおの勝手なほうへ
游いで行き、さらに
盛んに
分裂する。しこうしてかく
接合するのは
必ず
血縁のやや遠いもの
同志であって、同一の虫より
分裂によって
繁殖したばかりのものはけっして
互いに
接合せぬ。それゆえ
一匹の「ぞうり虫」を他と
離隔して
飼うておくと、ただ
分裂して虫の数がふえるだけで、一度も
接合が行なわれず、後には
漸々体質が弱ってくる。そこへ
別の
器に
飼うてあった
別の「ぞうり虫」の
子孫を入れてやると、
非常に待ちこがれていたかのごとく、ことごとく相手を
求めて同時に
接合する。これから考えて見ると、
接合とはいくぶんか
体質の
違うたものが
二匹寄ってその
体質を
混じ合うことで、
体質の全く
相同じものの間にはこれを行なうても何の
効もなく、また
実際に行なわれることのないものらしい。絵の具でも、
紅と青とを
混ぜれば
紫という
別の色となるゆえ
混ぜたかいがあるが、同じ
紅と
紅とでは
混ぜても何の役にも立たぬのとおそらく同様な
理屈であろう。
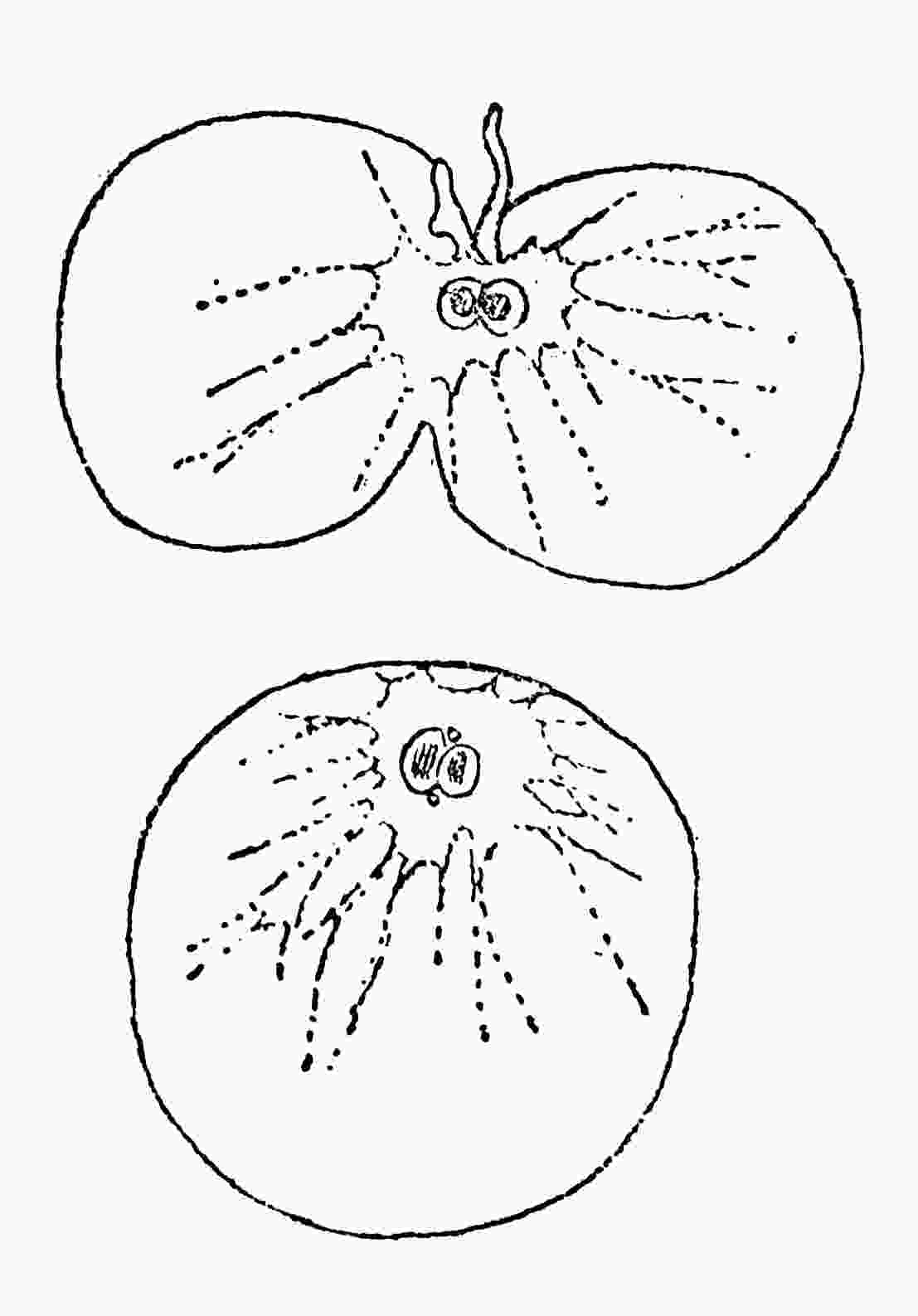 夜光虫の接合
夜光虫の接合
海の表面に
無数に
浮かんで夜間美しい光を放つ「夜光虫」も
単細胞生物であるが、これもつねには
分裂によって
繁殖し、その間にときどき
接合をする。夜光虫の身体はあたかも
梨かりんごのごとき球形で、
柄の根本にあたるところに口があるが、
二匹接合する時にはこの部分を
互いに合わせて身体を
密接させ、始めはひょうたんのごとき形となり、後にはしだいに
融け合うてしまいには全く
一個の球となってしまう。「ぞうり虫」では
接合する
二匹の虫の身体は始終
判然した
境があり、ただ
一箇所で一時
癒着するだけにすぎぬが、夜光虫のほうでは、始め
二匹の虫が
接合によって全く
一匹となり終わり、同時にその
核も
相合して
一個となる。しこうして
接合の後には、この
一匹となった大きな虫が
続々分裂して
繁殖すること、あたかも
接合後の「ぞうり虫」などと同じである。
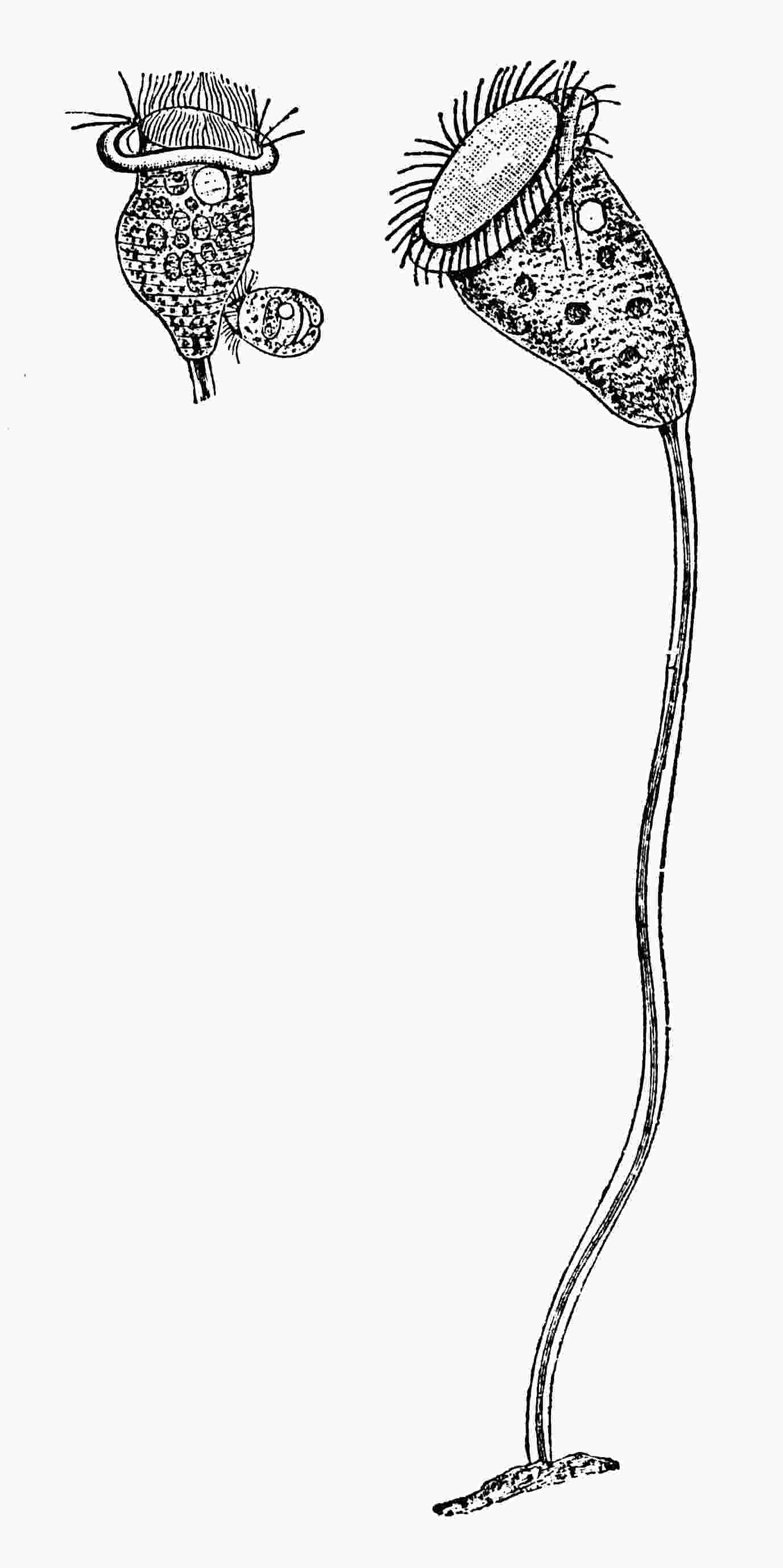
(右)つりがね虫の普通の一匹
(左)とどまって待つ大きな一匹のところへ、群体からはなれて水中を游ぎ来たった小さな一匹が、まさに接合せんとするさま。
「ぞうり虫」でも夜光虫でも、
接合する
二匹の虫は外見上全く同様で少しも
区別がないが、原始動物の中には
接合する
二匹の形に明らかな
相違の見えるものがある。池や
沼の水草にたくさんに
付着している「つりがね虫」はその
一例であるが、この虫は夜光虫や「ぞうり虫」が
遊離しているのとは
違い、長い
柄をもって
固着しているゆえ、あたかも根の生えた植物のごとくで、勝手にどこへでも行くことはできぬ。始めは
一匹の虫も
分裂によってだんだんふえるが、みな同じところにとどまり、
柄をもって
互いにつながっているゆえ、しまいには
樹の
枝のような形の
群体をつくるにいたる。
通常水草などに
付いているのはかかる
姿のものである。ところがこの虫もときどき
接合する
必要があるが、それには
系統の
異なった
二匹の虫が
出遇わねばならず、そのためには
必ず運動を
要する。
二匹ともに動くか、または
一匹だけが動くか、いずれにしても全く動かずにいては
二匹が
相接蝕する
機会はない。さて
実際には「つりがね虫」は
如何にして
接合するかというに、そのころになると、
分裂生殖によって
二種類の
個体ができ、
一種は身体が大きくて内に
滋養分の
顆粒を
含み、
群体の
枝から
離れずにあるが 他の
一種は体が小さくて有力な
繊毛をそなえ、自分の
群体から
離れて水中へ
游ぎ出し、他の
群体に
達してそこに相手を
求める。しこうして
接合するときには小さいほうの虫は大きなほうの体内にもぐり
込み、これと
融合して全く
一個の
細胞となってしまう。かくのごとく、「つりがね虫」では
接合する
二匹の虫が、形も
挙動も明らかに
違うが、その
相違は高等動物の
生殖細胞なる
卵と
精虫との
相違と全く同
性質のものゆえ、大きなほうを
雌と名づけ小さなほうを
雄と名づけてもけっして
無理ではなかろう。
接合を
目的として
二匹の虫が
互いに
相慕い
相求めることは、原始動物に
普通に見るところであるが、この
二匹の間に
雌雄の
相違の明らかに
現われる場合は、「つりがね虫」のほかにもなおたくさんある。
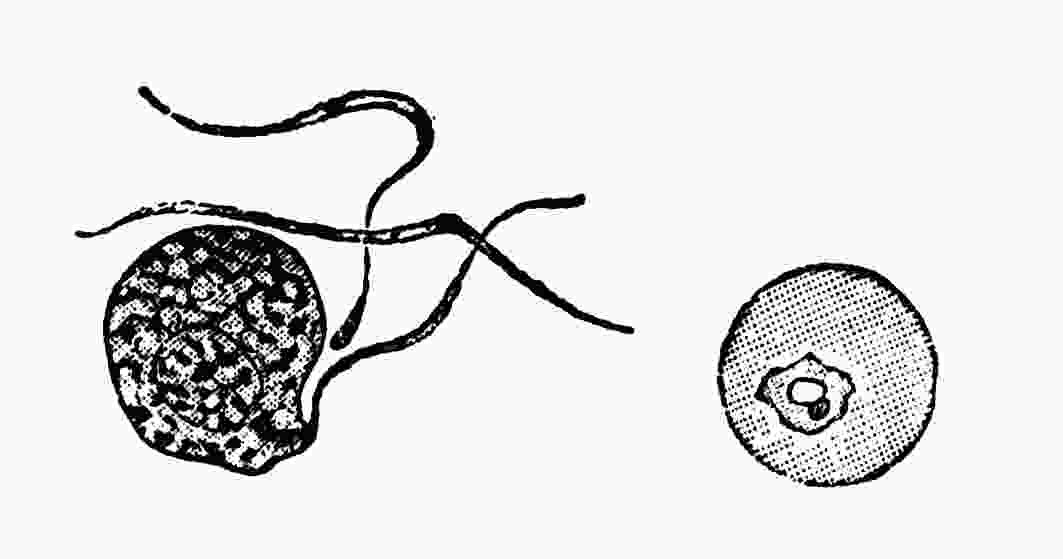 (右)マラリア病原虫が人の赤血球に寄生せるところ。(左)同虫の雄と雌との接合するところ。
(右)マラリア病原虫が人の赤血球に寄生せるところ。(左)同虫の雄と雌との接合するところ。
人間の
血液内に
寄生してマラリア病を起こす
微細な原始動物なども、
普通には
分裂によって
繁殖する。
患者が
隔日に
発熱するのは、この虫の
分裂生殖に毎回四十八時間を
要するゆえである。しかし
蚊が
患者の
血液を
吸うと、病原虫は
蚊の体内で
漸々変形し、大小
二種の虫ができて
互いに
接合するが、その
形状の
相違は「つりがね虫」などにおけるよりもはるかにいちじるしく、
雌のほうは球形でだれが見ても
卵細胞と思われ、
雄のほうは小さな頭から細長い
尾が生えて、
普通の
精虫と少しも
違わぬ。
以上述べたごとき
単細胞生物では、いずれも
種族を長く
継続させるためには、ときどき
系統を
異にする虫が
二匹ずつ
接合して
体質を
相混ずることが
必要であるが、
二匹の虫が
出遇うには運動をせねばならず、
接合後
速やかに
分裂するにはあらかじめ
滋養分を
貯えておかねばならぬ。しかるに、活発に
游ぐにはなるべく身軽なことが
便利であり、
滋養分を
貯えれば身体が重くなって運動が
妨げられる。それゆえこの二つの
必要条件は、
相接合すべき
二匹で一方ずつ
分担し、長い年月の間にそれぞれそれに
適するように身体が
変化したるものと
推察せられるが、かく
想像すると全く
実際に見るところと
一致する。すなわち一方は体が
次第に小さくなり、運動の
装置のみが
発達して活発な
雄となり、一方は
滋養分をためて体がだんだん大きくなり、ついに重い動かぬ
雌となったと考えねばならぬ。
動物の
卵の中でもっともよく人の知っているのはいうまでもなく
鶏の
卵である。それゆえ
卵のことを
述べるには、まず
鶏の
卵を手本として他のものをこれにくらべるのが
便利であろう。
鶏の
卵は外面に
石灰質の
殻をおおっているが、ゆで
卵の
殻をむいて見ると、その下にはなお
二枚のきわめて
薄い
膜があり、
産まれてやや時を
経た
卵であると、この
二枚の
薄い
膜は
卵の
鈍端のところで少しく
離れてその間に空気を
含んでいる。むいたゆで
卵の一方が
凹んでいるのはそのためである。
以上だけの皮に
包まれた
卵の
内容はだれも知るとおり白身と黄身とであるが、黄身の表面にはまた
一枚の
透明な
薄い
膜がある。生の
卵の黄身を
箸ではさむと形のくずれるのはこの
膜を
破るによる。かく
鶏の
卵にはさまざまの部分があるが、その中には
是非なくてならぬ
主要部と、ただこれを
包み
保護するための
付属部との
区別がある。まず
卵は
如何にして生ずるかを見るに、
牝鶏の
腹を切り開いて
腸などを取り去ると、正面の
脊骨の
側に
粒のそろわぬ小球が数多く集まったあたかも
葡萄の
房のごとき
器官があるが、これが
卵巣であって、ここではただ
卵の黄身だけができる。
葡萄の
粒のごとくに見えるものは後に一つずつ
卵の黄身となるものである。また
卵巣のそばから始まって、
肛門の
内側まで
達する
蜿曲した太い
管は
輸卵管であって、
卵巣を
離れた黄身はこの
管を
通過する間に、その
壁から
分泌した白身によって
包まれる。かくして白身と黄身とのそろうた
卵は
輸卵管の出口に近い太いところまで来てしばらくとどまるが、その間に
石灰質の
殻がつけ
加えられ、
初めて
完全な
卵となって
産み出されるのである。
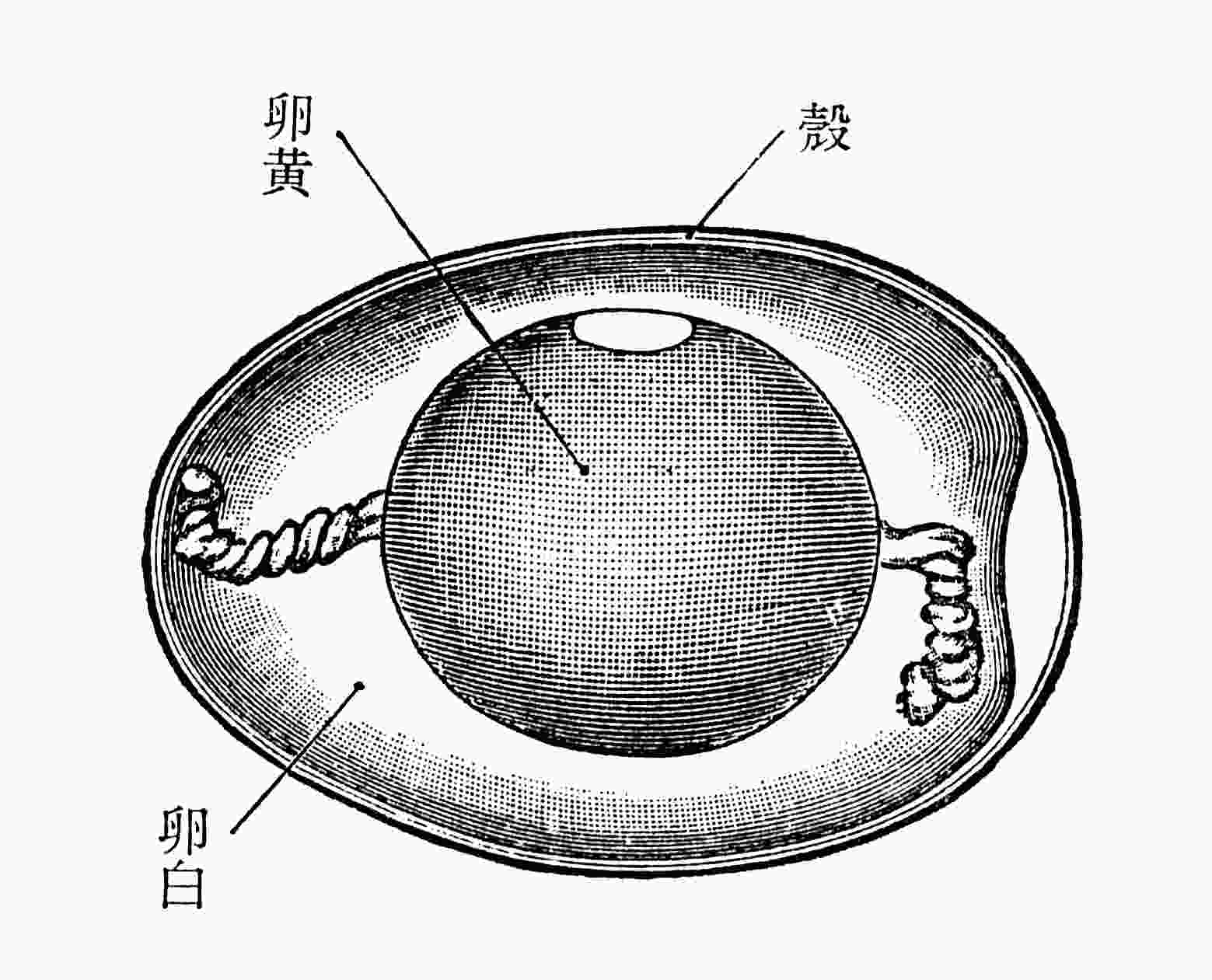 鶏卵の断面
鶏卵の断面
かくのごとく、
鶏の
卵の中でも白身や
殻は、
卵が
産み出される
途中に外からつけ
加わったもので、後に
鶏となるのはただ黄身だけであるゆえ、真の
卵というのは、どうしても黄身ばかりと見なさねばならぬ。しからば黄身とは何かというに、
卵巣を調べて見ると、黄身が大きくなる
順序が明らかにわかるが、その始めは小さな球形の
普通の
細胞で、
成熟するにしたがいだんだん
脂肪その他の
滋養分を
細胞体の内にため
込み、ついに他の
細胞ではとうてい見られぬほどの大きさに
達するのである。されば
卵の黄身なるものもやはり
一個の
細胞で、ただ
滋養分を
多量に
含むために
特に大きくなったものというにすぎぬ。しこうして
卵巣から
離れて
輸卵管にはいった
以上は、親と
卵との
組織の
連絡は
絶えるが、いまだ
卵巣内にあって
卵巣の一部を
形造っている間は、
卵細胞もたしかにその部分の
組織に
属し、したがって親の身体を
成せる
幾千億かの
細胞の
仲間に
加わっている。すなわち
卵が生まれるとは、親の身体の一
細胞が親から
離れて
独立することである。
卵には鳥の
卵のように大きなものから、
顕微鏡的の
極めて小さなものまでさまざまある。
蛇、
亀、「とかげ」、
鰐などの
卵は形も大きく内部もすこぶる鳥の
卵に
似て、ただ
殻が
脆くないだけである。海岸地方では
海亀の
卵をいくらも食用として売りに歩いているが、
大蛇や
鰐の
卵もオムレツなどにつくればうまく食える。
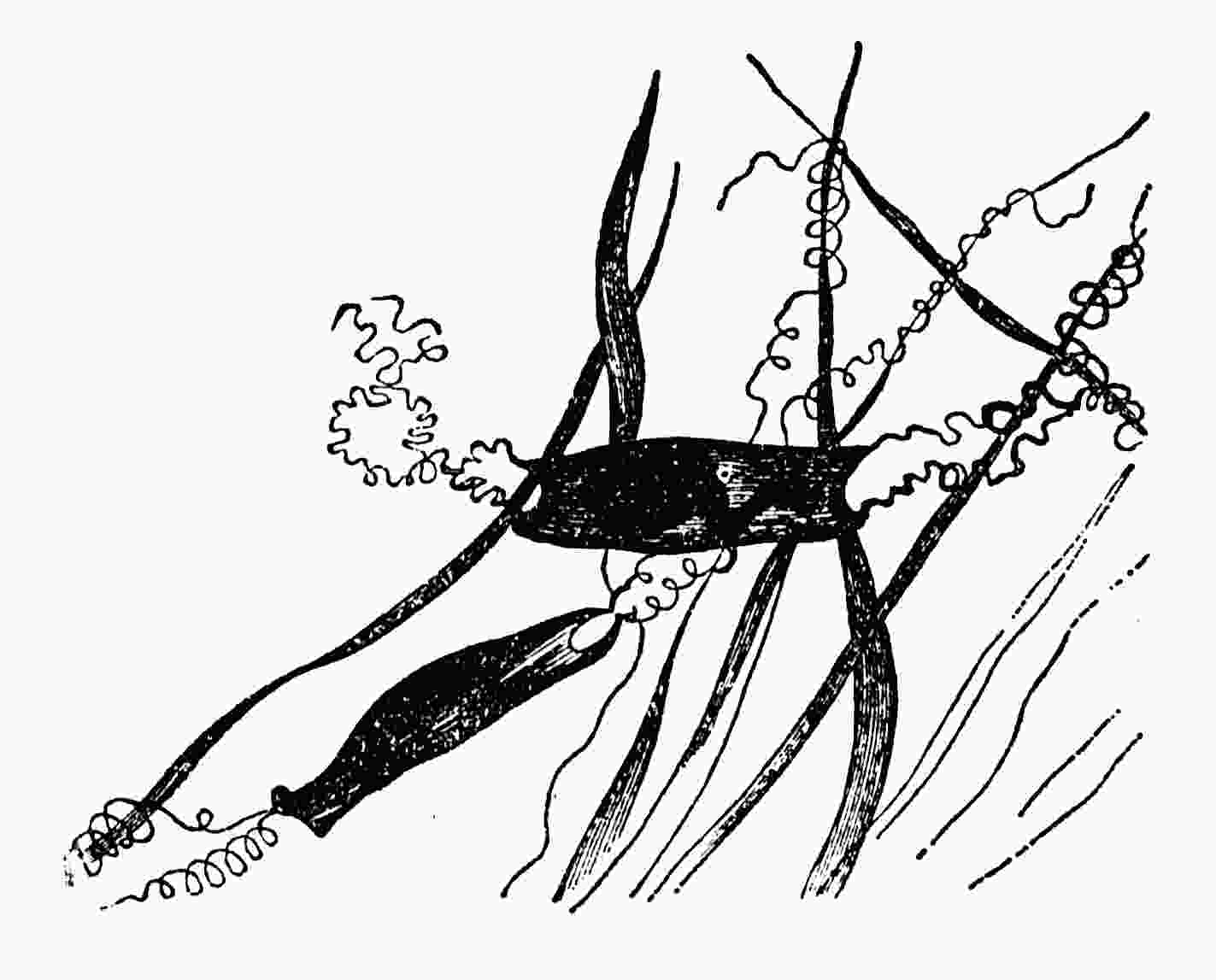 さめの卵
魚類
さめの卵
魚類の
卵は
通常粒が小さいが
鮫類のはすこぶる大きく、
革のごとき
丈夫な長方形の
嚢に
包まれ、その
四隅から出た細長い
紐は海草の根などに
巻き
付けられてある。
俗に
鮫の「
掛け守り」と名づけて、
江の島辺で
土産に売っているのはこれである。
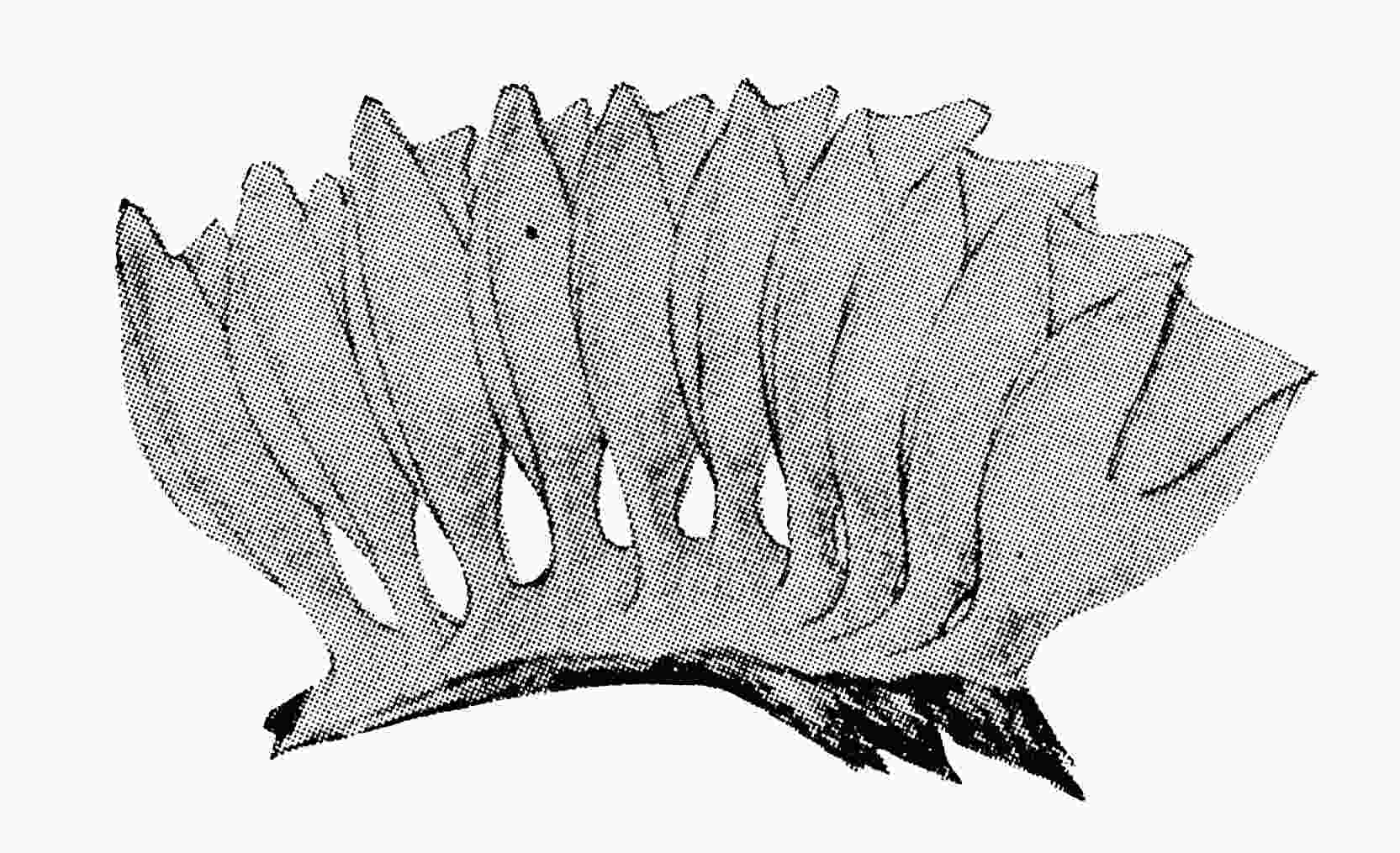 うみほおずき
うみほおずき
また
海産の
螺の
類は小さな
卵を
幾つずつか
卵嚢に
包んで数多く
産みつけるが、その
卵嚢がすなわち女の子が
玩具にする「ほおずき」である。平たい「うみほおずき」、細長い「なぎなたほおずき」、こっけいな「ひょっとこほおずき」などさまざまの
種類があるが、仕事しながら
絶えずしゃべるのを
防ぐ
方便として、
製糸や
機織工女の口に入れさせるために、今ではわざわざ海中に
螺の
類を
飼育し
餌を
与えて
盛んに「ほおずき」を
産ませ、千葉県だけでも年々数万円の
産額を
得るにいたった。その他、
蚕種、
数の子などは、もっとも人に知られた
卵であるが、「うに」や「ひとで」などの
卵になると、すこぶる小さくてほとんど
肉眼では見えず、あたかも
鶏の
卵巣内におけるでき始めの
卵細胞と同じく、
単に球形をした
裸の
細胞にすぎぬ。
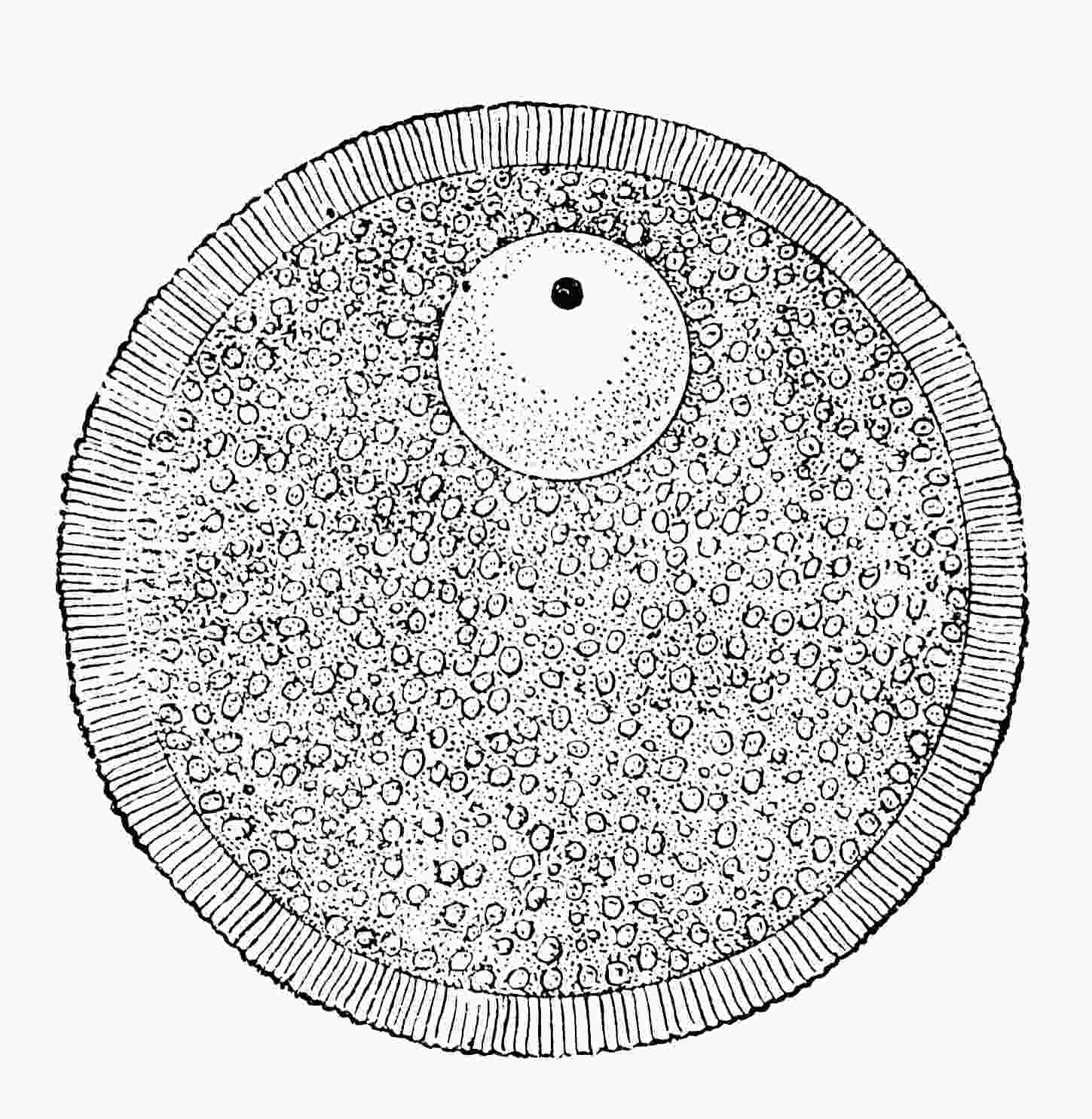 人間の卵
以上
人間の卵
以上は
卵生する動物の
卵の
例であるが、
卵は
必ずしも
卵生する動物に
限ってあるわけではない。
哺乳類のごとき
胎生する動物でも
胎児の始めは
必ず一つの
卵である。しかし
鳥類などの
卵とは
違うてすこぶる小さいから、その発見せられたのも
比較的近いことで、昔はだれもこれを知らずにいた。人間の女などは年に十二三回も
卵を
産み落としていながら、あまり小さいゆえ
当人さえ気がつかぬ。人間の
卵でも犬、
猫、馬、牛の
卵でも形も大きさもみなほぼ同様で、
直径わずかに一分の十五分の一(注:0.2mm)にも足らぬ小球であるから、
肉眼ではただ
針の先で
突いた
孔ほどにより見えず、
顕微鏡でのぞいて見てもほとんど何の
異なるところもない。すなわち
卵の時代には、人間でも
猿でも犬でも
猫でも全く同じである。
哺乳類の
卵の外面にはやや
厚い
透明な
膜があるが、この
膜を
度外視して
内容だけを「うに」や「ひとで」などの
微細な
卵にくらべて見ると、いずれも
嚢状の大きな
核と多少の
顆粒とを
含んだ
原形質のかたまりで、その
一個の
細胞なることは明らかに知れる。されば鳥の
卵などに
比して
違う点は、一は
滋養分をほとんど
含まぬために小さく、他は
滋養分を
多量に
含むために大きく、一は親の体内で発育するために
単に
膜をもっておおわれ、他は親の体外で発育するためにさらに白身と
殻とで
包まれているというだけで、いずれも
一個の
細胞である点にいたっては
毫も
相違はない。
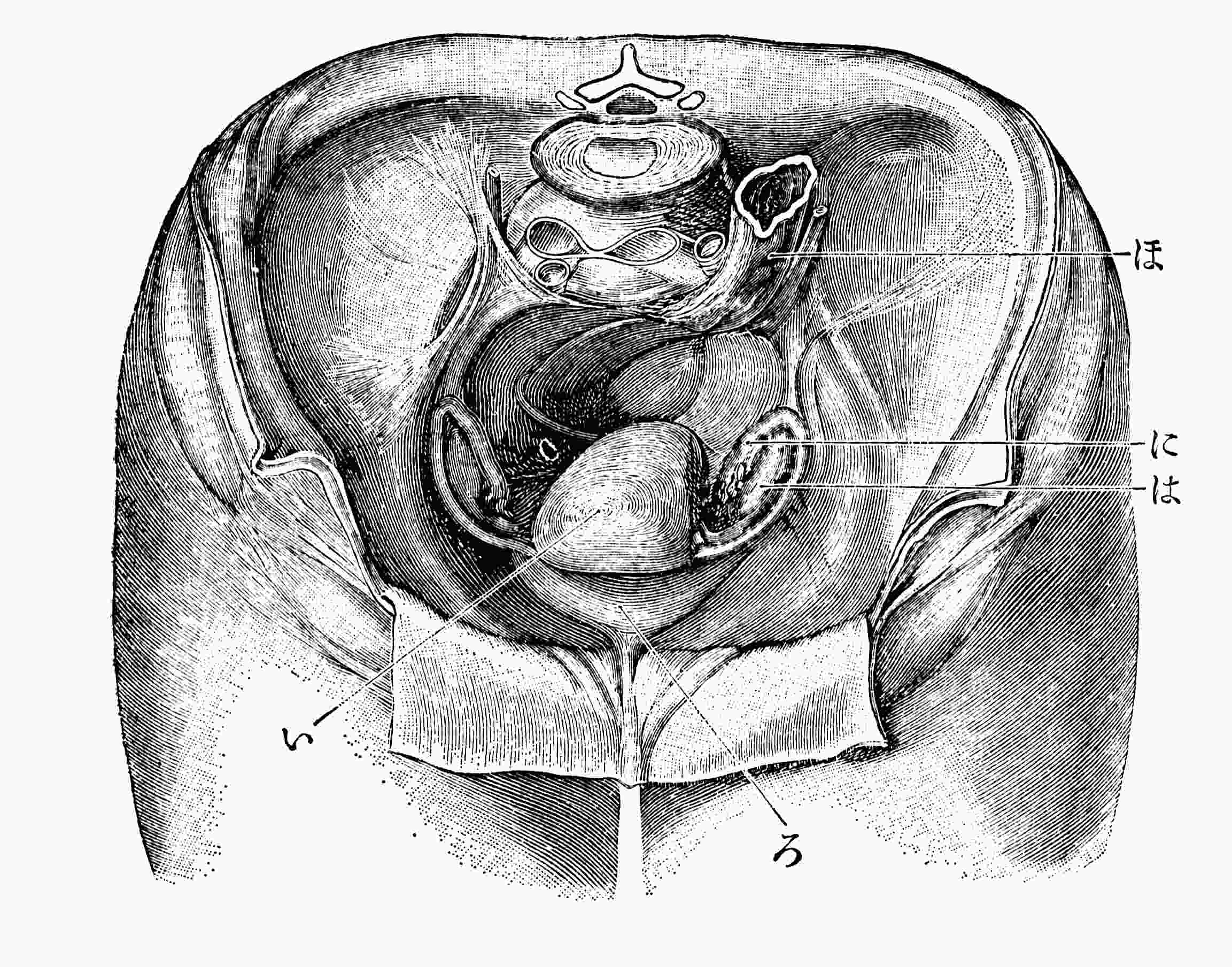
婦人の解剖 卵巣を示す
(い)子宮 (ろ)膀胱 (は)卵巣 (に)輸卵管 (ほ)直腸
婦人の
腹を正面から切り開いて
腸などを取り去ると、
膀胱の後にあたかも
茄子をさかさにしたごとき形の
子宮が見えるが、その左右に一つずつ長さ
一寸(注:3cm)あまりのお多福豆のような
卵巣がある。
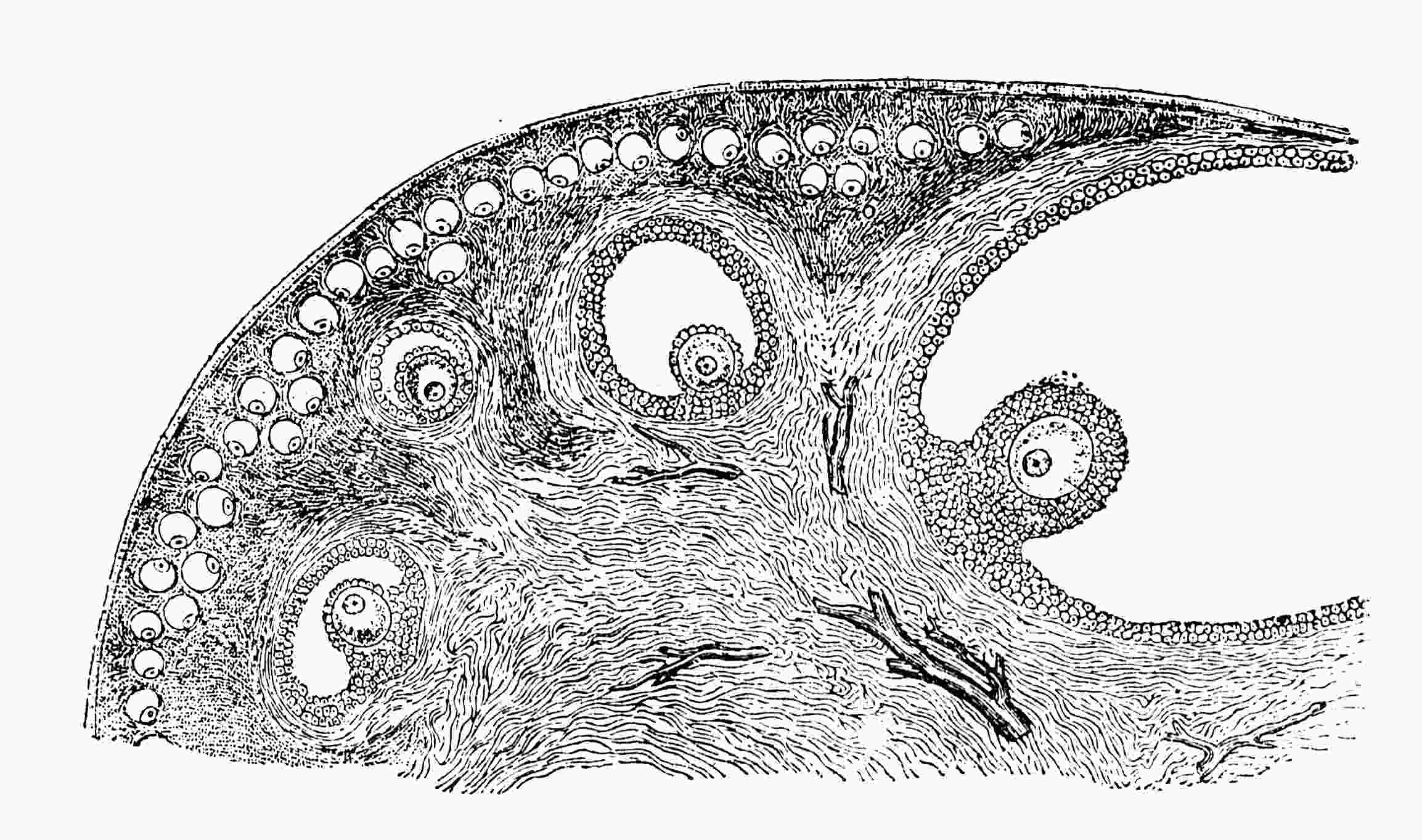 卵巣の断面
鳥類
卵巣の断面
鳥類の
卵巣または世人がつねに「
鯛の子」とか「
鰈の子」とか
呼んでいる
魚類の
卵巣とは
違い、
哺乳類の
卵巣は一見して直ちに
卵のかたまりとは思われぬが、よく調べて見ると、やはり大小
不同の
卵細胞の集まり
成ったもので、その中の
成熟したものから
順々に
離れ出るのである。しこうしていったん
離れ出た後は、あるいは
精虫と合して
子宮内で新たな
個体の
基となるか、あるいは
精虫に
遇わずしてそのまま死ぬか、いずれにしても親の身体との
組織の
連絡は
絶えるが、それまではたしかに母親の身体の一部をなしていたものである。
なお
卵について考うべきことは、その大きさと数とである。前にも
述べたとおり
卵に大小の
相違のあるのは、全くその
含む
滋養分の多少に
基づくことであるが、
滋養分を多く
含む大きな
卵は、それより子の発育するときに速かに大きく強くなり
得るという
利益があるが、その代わり
卵が数多くできぬという
不便をまぬがれぬ。これに反して小さな
卵のほうは、
無数に生まれ
得る
便宜がある代わりに、その
卵より生ずる
幼児は
滋養分の
不足のために
極めて小さく弱いときから早くも
独力で
冒険的の生活を
試みねばならぬ
不利益がある。たとえていえば、新
領土へ少数の者に
富裕な
資本を持たせて
遣るか、または
資本なしの人間を
無数に送り
込むかというごとくで、いずれにも
一得一失があるゆえ、
甲の
適する場合もあれば
乙のほうがかえって
有効である場合もあろう。また
胎生する動物では、
卵は
如何に小さくても
絶えず親から
滋養分を
供給し、長くかかって少数の子を十分に発育せしめるのであるから、あたたかも
初め手ぶらで出かけた社員に月々
多額の
創業費を送っているようなもので、
結局大きな
卵を数少なく生むのと同じことにあたる。
卵生も
胎生も、
卵の大きいのも小さいのも、みなそれぞれの動物の生活
状態に
応じたことで、
利害損得を
差引き
勘定して、
種族の
生存上少しでも
得になるほうが実行せられているようである。
卵には大きなものや小さなものがあるが、もっとも小さな
卵でも
細胞としてはよほど大きい。人間の
卵などは
卵の中ではずいぶん小さなほうであるが、それでも
肉眼で見えるゆえ、
普通の
細胞がみな
顕微鏡的であるのにくらべると、なおすこぶる大きいといわねばならぬ。さればもっとも小さな
卵のほかは昔からだれでもよく知っていたが、その相手となるべき
精虫のほうは、
細胞の中でも
特に小さく、かつ
形状も
普通の
細胞とはいちじるしく
違うゆえ、その発見せられ
了解せられたのも、
卵にくらべてははるかに新しいことである。
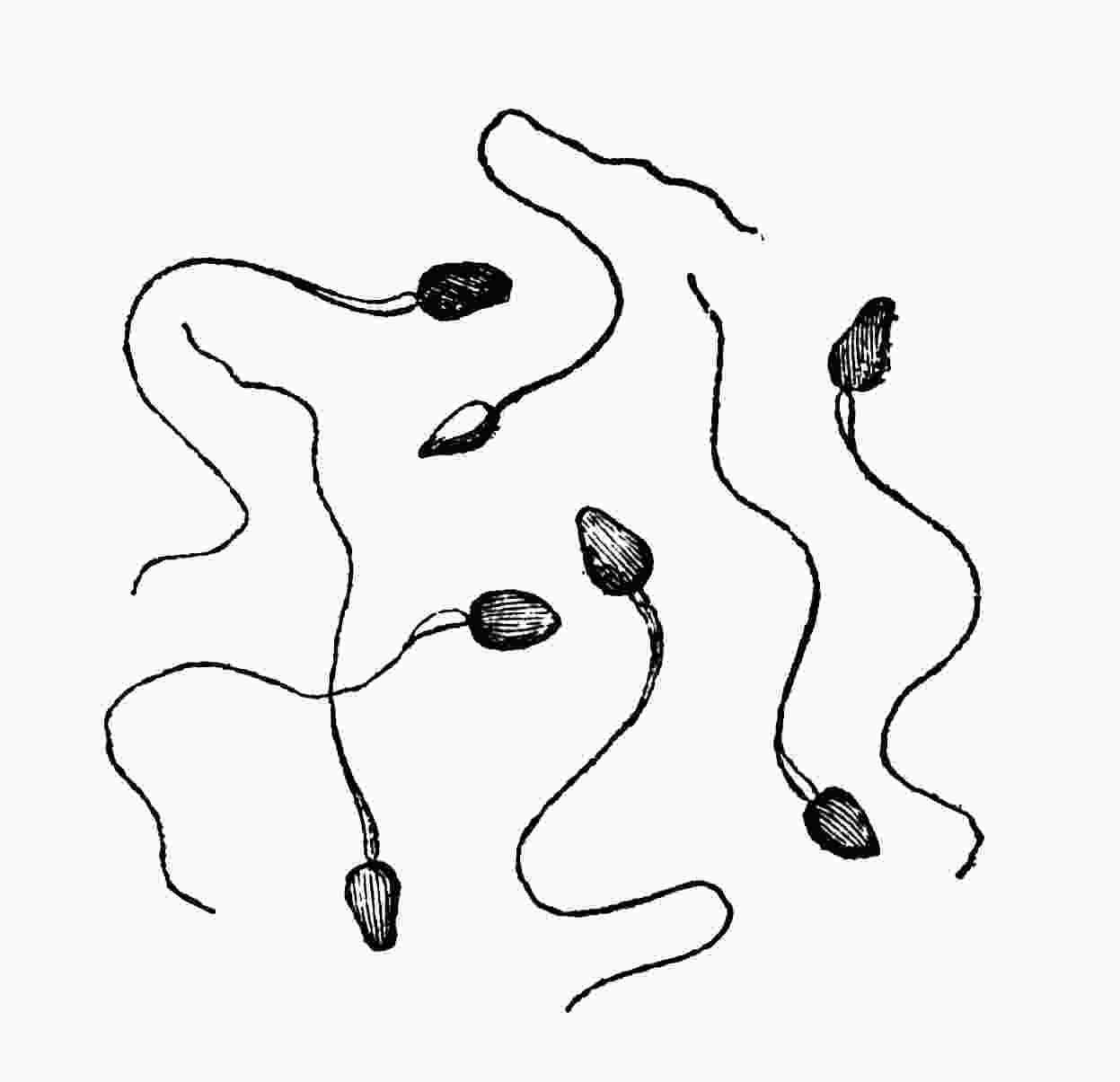 人間の精虫
人間の精虫
そもそも
精虫の
初めて見つけられたのは、今より二百何十年か前のことで、あたかもオランダ国で
顕微鏡が発明せられて間もないころとて、何でも手当たり
次第にのぞいて見ているうち、
或る時一人の
若い学生が、
屠所から新しい羊の
睾丸をもらうて来て、その
汁を
郭大して見たところが、
単に
濁った
粘液のごとくに思うていた物の中に、小さな
粒が
無数に活発に
游いでいるので、大いに
驚いてさっそく
師匠のレウェンフークという人に知らせた。この人は、水中の
微生物などを
顕微鏡で調べことごとく写生して大部な書物を
著わしたそのころの
顕微鏡学の大家であったが、かようなものは
初めて見ることゆえ、もとよりその真の
素性を知るはずはなく、ただ運動が活発で、
如何にも生きた動物らしく見えるところから
推して、これを
寄生虫と
鑑定し、
精液の中に
棲んでいるゆえ「
精虫」という名をつけた。すなわち
精虫の実物を見ることは見たが、これを
条虫や「ジストマ」などのごとき
偶然の
寄生虫と見なし、これが
卵と
相合して新たな一
個体を
造るべき、
生殖上もっとも
重要な
細胞であろうとは
夢にも心づかなかったのである。
その後さまざまの動物の
精液を調べて見ると、いずれにも
必ず
無数の
精虫が
游いでいるので、これは
偶然にはいり
込んだ
寄生虫ではなく、
精液には
必ず
含まれている一
要素であろうと考えるにいたった。動物が
卵を
産むことも、
卵に
精液が
加わると
卵が
孵化し発育することも前からわかっていたが、
精液中に虫のごときものが
常に
無数に
游いでいるのを見ると、
卵を
孵化するにいたらしめるものは
精液の
液体であるか、またはその中の
精虫であるかという
疑問が
当然生じた。そこでこの
疑いを
解決するために、イタリアのスパランザニという
熱心な研究家が次のごとき
試験を行なうた。まず一つの
器に水を
盛り、その中に
雌の
蛙の体内から取り出した
成熟した
卵をたくさんに入れ、
別に
雄の
蛙の体内から取り出した
精液を
濾紙でこして
精虫を
除き去った
液だけを
加えて見た。ところが
精虫を
含んだままの
精液[#「精液」は底本では「精虫」]を
加えると
卵はことごとく発育して
幼児と
成るが、
精虫を
除いた
精液を
混じたのでは
卵は一つも発育せず、ことごとくそのままに死んでしもうた。この
実験で、
精虫なるものは
精液中のもっとも
主要な部分で
卵を
孵化するにいたらしめるのは全くその
働きによることが明らかになった。
精虫のあることを知らぬ間は、子は全く
卵から生ずるもののごとくに思うていたところ、子のできるには
精虫が
必要であることが明らかになってからは、急に
精虫に重きをおくようになり、
別して
獣類のごとき
卵の知れぬ動物においては、後に子と
成って生まれるのは
精虫自身であると考えられ、
如何なる動物でも子に
成るのは
雄の
精虫であって、
卵のごときは
単にこれに
滋養分を
供給するにすぎぬとの
説が
盛んに
唱えられるにいたった。
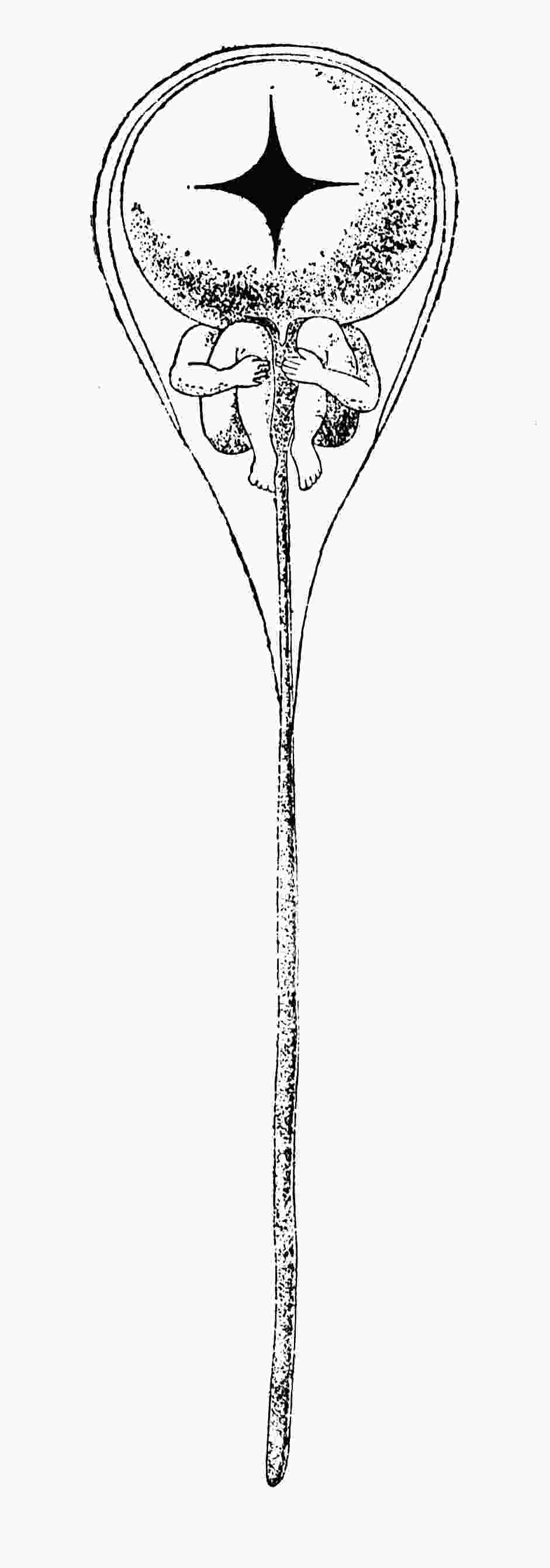 昔の精虫の画
昔の精虫の画
すなわち女の
腹は
畠で、男がそこへ
種を
蒔くものと考えたのであるが、
不完全な
顕微鏡を用い、かかる
想像をたくましうしてのぞいたゆえ、
実際精虫が
子供の形に見えたものか、そのころの古い書物には、人間の
精虫をあたかも頭の大きな赤子から細長い
尾がはえているごとき形に画いてある。
さて
精虫は
実際如何なる形のものかというに、「えび」、「かに」や、
蛔虫などの
精虫のごとくにいちじるしく他と形の
異なったものもあるが、これらはむしろ
例外であって、
一般には高等動物でも下等動物でもほとんど同じである。人間のでも犬、
猫、馬、牛のでも、ないしは
蛤、「あさり」、「さんご」、
海綿のごときもののでも、
精虫といえばみな形が
相似たもので、いずれも小さな頭から細長い
尾が生じ、これを
振り動かして
液体の中を
游ぎまわることができる。
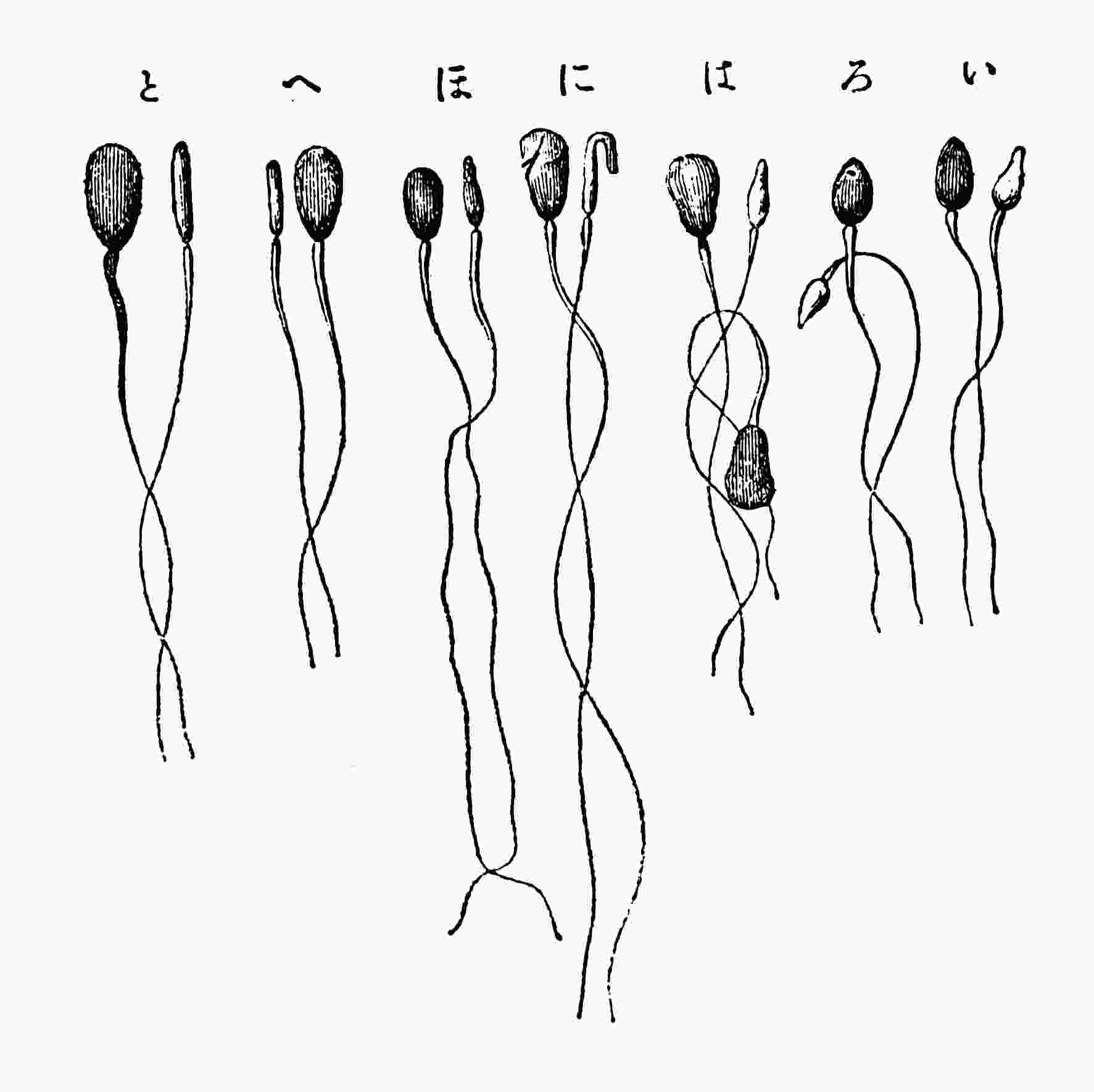
種々の動物の精虫
(い)猿 (ろ)猫 (は)犬 (に)もぐら (ほ)馬 (へ)鹿 (と)兎
もっとも
詳細に調べると、動物の
種類が
違えば、その
精虫の形にもさまざまの
相違があり、
精虫を見ただけでその
種類を
識別し
得るごとき場合もあるが、多くはただ頭が長いとか短いとか、真直ぐであるとか曲がっているとか、全体が少し大きいとか小さいとかいうぐらいの
比較的ささいな
相違にすぎぬ。かくのごとく
精虫には
一種固有の形が定まってあり、
普通の
細胞とはよほど
形状が
違うゆえ、でき上がって
游いでいる
精虫を見たのでは、それがおのおの
一個の
細胞であるか
否かは
容易に
判断しがたい。
精虫のできるところは
睾丸の内であるが、たいがいの動物では、
睾丸はほかの
臓腑と同じく
腹の内に
隠れてある。
例えば
魚類などでは
睾丸は
腹の内にある白い
豆腐のようなもので、
俗にこれを「
白子」と名づける。ただ
獣類だけでは
睾丸は
特別の
皮膚の
嚢に
包まれ
腹より外にたれている。
顕微鏡で調べて見ると、
獣類の
睾丸は細い
管のかたまったごときもので、その
管の
壁をなせる
細胞がしばしば
変形して
精虫と
成るのである。すなわち始め
普通の
細胞と同じく、
原形質の
細胞体と
嚢状の
核とを
備えた
細胞が一歩一歩
変化し、
核は小さくなって
精虫の頭となり、
細胞体の一部は
延びて
精虫の
尾となり、いつとはなしに
精虫の形ができ上がると、しまいにほかの
細胞の
仲間から
離れ、
輸精管を
通過して
粘液とともに体外へ
排出せられるにいたる。されば
精虫は形はいちじるしく
違うが、やはりそれぞれ
一個の
細胞であって、ただ
特殊の
任務を
尽くすために、それに
適する
特殊の
形状を有するだけである。でき上がった
精虫は、自由に運動してあたかも
独立せる小虫のごとくに見えるが、
睾丸の
組織から
離れ出す前にはたしかに親の身体の一部を
成していたので、この点においては
精虫も
卵も
毫も
違いはない。
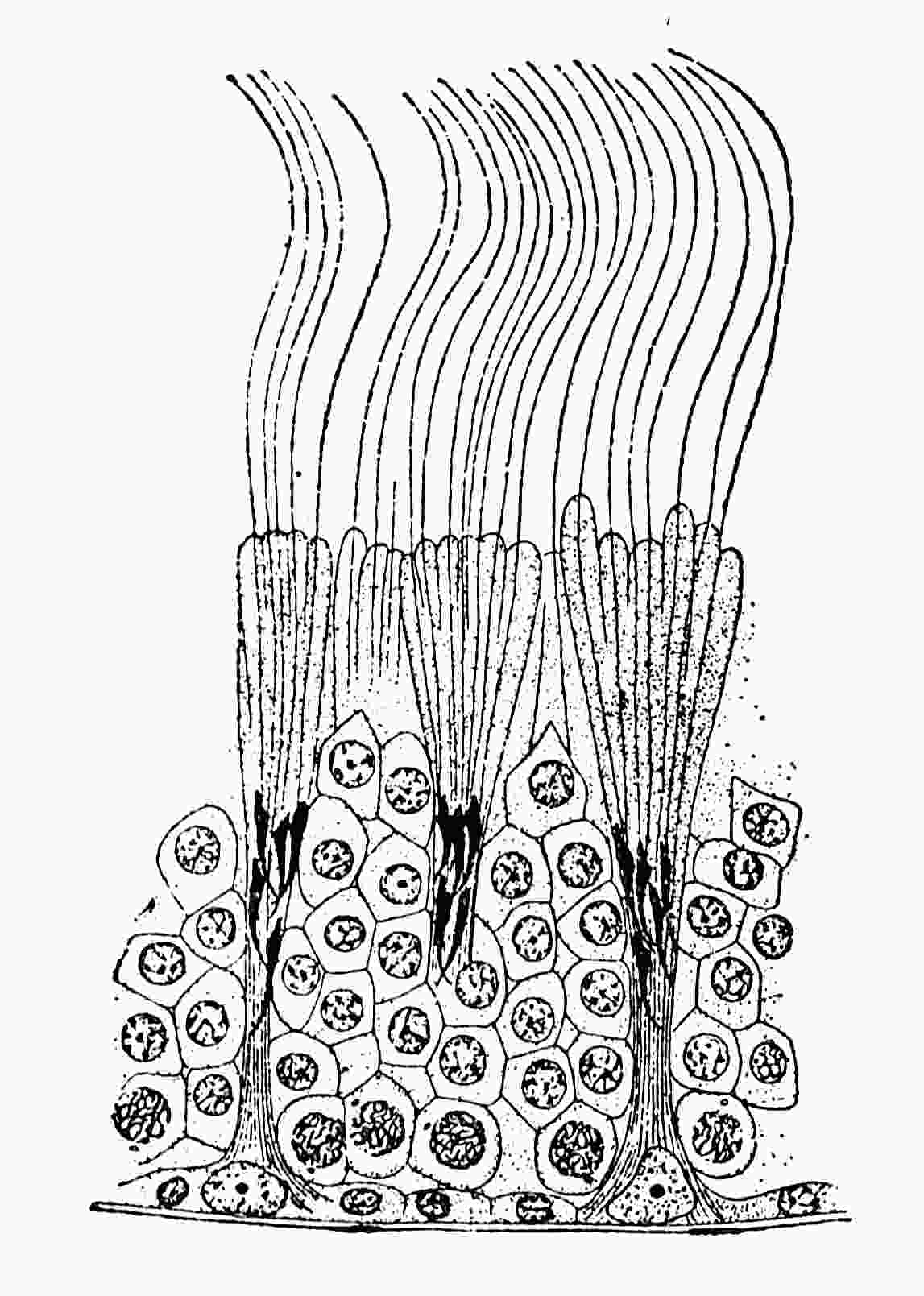 精虫の発生
精虫の発生
ほとんどすべての動物で
卵細胞が球形なるに反し、
精虫が糸のごとき形を
呈するのは
何故かというに、これは
双方ともその役目に
応じたことで、始めはいずれも
普通の
細胞であるが、
卵のほうはできるだけ
多量の
滋養分を
含むに
適した形をとり、
精虫のほうはできるだけ自由な運動をなし
得るような形をとったのである。自由に運動するには身体の軽いほうが
便利で、
抵抗を受けぬためには身体の細いほうがよろしい。また同じ
一斗(注:18リットル)の
餅でも、大きな
鏡餅にすれば一つか二つより
造れぬが、
金柑ほどの
小餅にすれば何千
個もできるごとく、小さければ小さいほど数が多くできる
利益がある。それゆえ
精虫は
卵にくらべるとはるかに小さいのがつねで、人間などでも
精虫は長さがわずかに一分の五十分の一(注:0.08mm)にも足らず、頭の
幅は一分の千分の一(注:3μm)にも
達せぬから、その
体積は
卵にくらべてわずかに二百万分の一にもあたらぬ。その代わり多いことは実に
驚くばかりで、
卵が年々わずかに
十数個より
成熟せぬに反し、
精虫は毎回何万
匹数のも
排出せられる。
動物植物ともに
単為生殖により
卵細胞のみで
繁殖する場合もあるが、これはむしろ
例外であって、まず
卵と
精虫とが
相合しなければ子ができぬのが
一般の
規則である。
卵細胞と
精虫との合することを
受精と名づける。
鶏のような大きな
卵と
極めて
微細な
精虫とが
相合するところを
顕微鏡で見ることは
困難であるが、小さな
卵ならばこれに
精虫のはいり
込むありさまを
実際に調べることは何の
雑作もない。
例えば夏
雌の「うに」を切り開いて
成熟した
卵細胞を取り出し、海水を
盛ったガラス皿の中に入れ、これを
顕微鏡で見ていながら、
別に
雄の「うに」から取り出した
精虫を海水に
混じたものを、
一滴その中へ落とし
加えると、
無数の
精虫は
尾を
振り動かして水中を
游ぎ、
卵細胞の
周囲に集まり、どの
卵細胞もたちまち何十
匹かの
精虫に
包囲せられるが、そのうちただ
一匹だけが
卵細胞の中へもぐり
込み、
残余のものはみなそのまま弱って死んでしまう。
以上は人工
受精と名づけて
臨海実験場などで、学生の実習として年々行なうことであるが、注意して
観察すると、なおさまざまなことを見いだす。まず第一には
精虫が
卵に
出遇うのは、決して
目的なしに
游ぎ回っているうちに
偶然相触れるのではなく、ほとんど一直線に
卵を目がけて急ぎ行くことに気がつく。その
際精虫はあたかも目なくして見、耳なくして聞くかのごとく、もっとも近い
卵をねろうて一心
不乱に
游ぎ進むが、これは
如何なる力によるかというに、下等植物の
精虫が、ことごとく
砂糖やりんご
酸の
溶液のほうへ進み行く
例を見ると、あるいは
卵が何か
或る
物質を
分泌し、それが水に
混じてしだいに広がって
近辺にいる
精虫を
刺激し、
精虫はその
物質の
源のほうへ
游ぎ進むので、しまいに
卵に
達するのかも知れぬ。いずれにせよ、
卵は
精虫を自分のほうへ引き
寄せる
一種の引力を有し、
精虫はこの引力に対してとうてい
反抗することができぬものらしく見える。
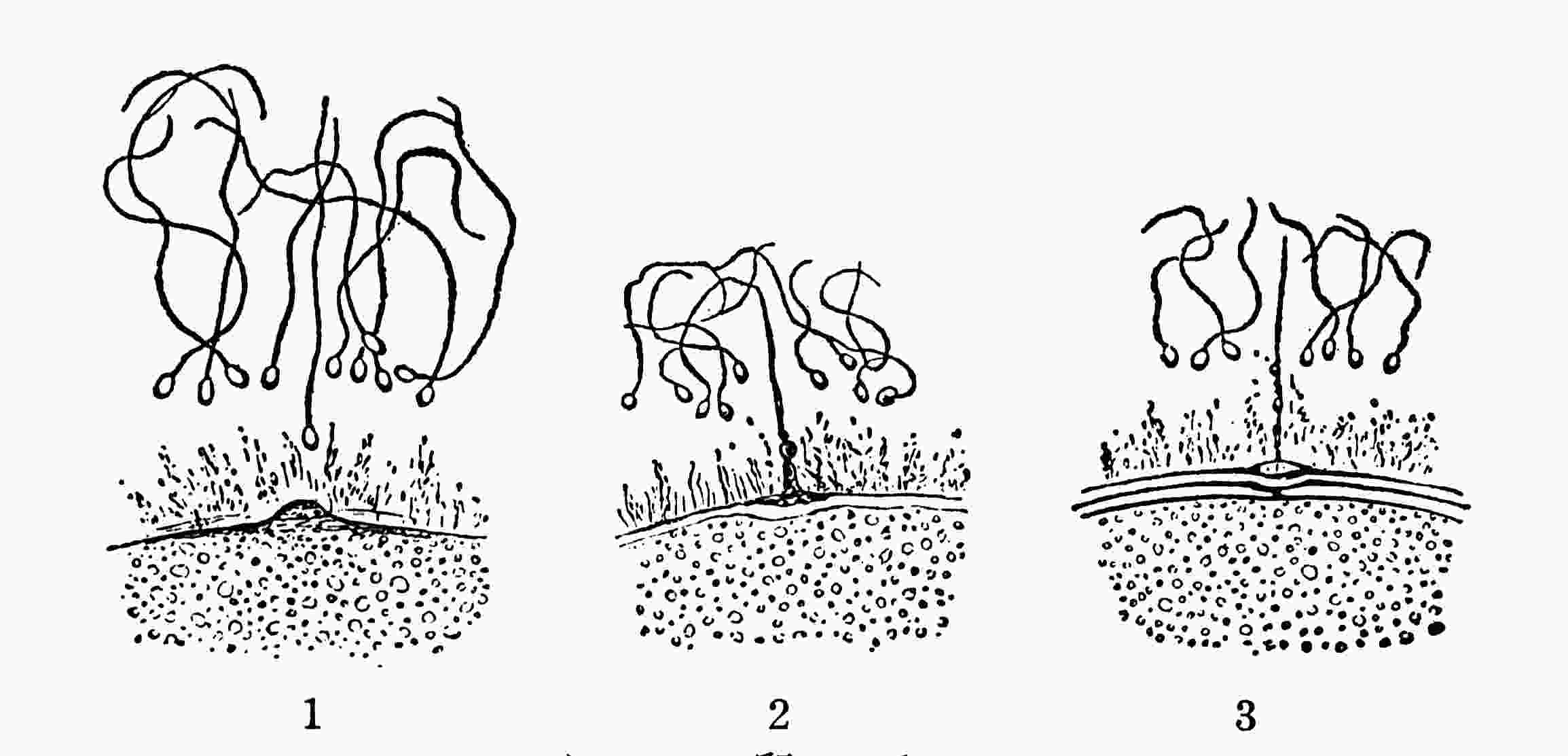 うにの卵の受精
うにの卵の受精
また
卵細胞はとどまって動かず、
精虫のほうが
夢中になって急ぐのを見ると、引力があるのは
卵のほうばかりのように思われるが、
精虫が
卵に
接近してからの様子を調べると、実は
精虫のほうにも
一種の引力があって、
卵はそのために引き
寄せられるものらしい。その
証拠には、
精虫がいよいよ
卵細胞の近くまでくると、その
到着するのを待たず、
卵のほうからも表面より
突起を出してこれを
迎え、
一刻も早く
相合せんと
努める。この
瞬間における
卵細胞の
挙動を、
支那の文人に見せたならば、
必ずこれを
形容して「
落花情あれば流水心あり。(注:散る花には、流れる水にそって流れて行きたいという気持ちがあり、流れる水には散った花を浮かべて流れて行きたいという気持ちがある)」とでも言うに
違いない。
精虫にくらべると
卵ははるかに大きいゆえ、たとい
精虫に引力があっても、丸ごとにそのほうへ引き
寄せられるわけにはいかぬが、相手が
側までくると、それに面した部の
原形質は引力のために引き
寄せられ、
突起となって進み近づくのであろう。つまるところ、
異性の
生殖細胞の間には
互いに
相引く力があるが、
卵のほうは重いために動き
得ず、身軽な
精虫のみが相手を
求めて
盛んに
游ぎ回るのである。
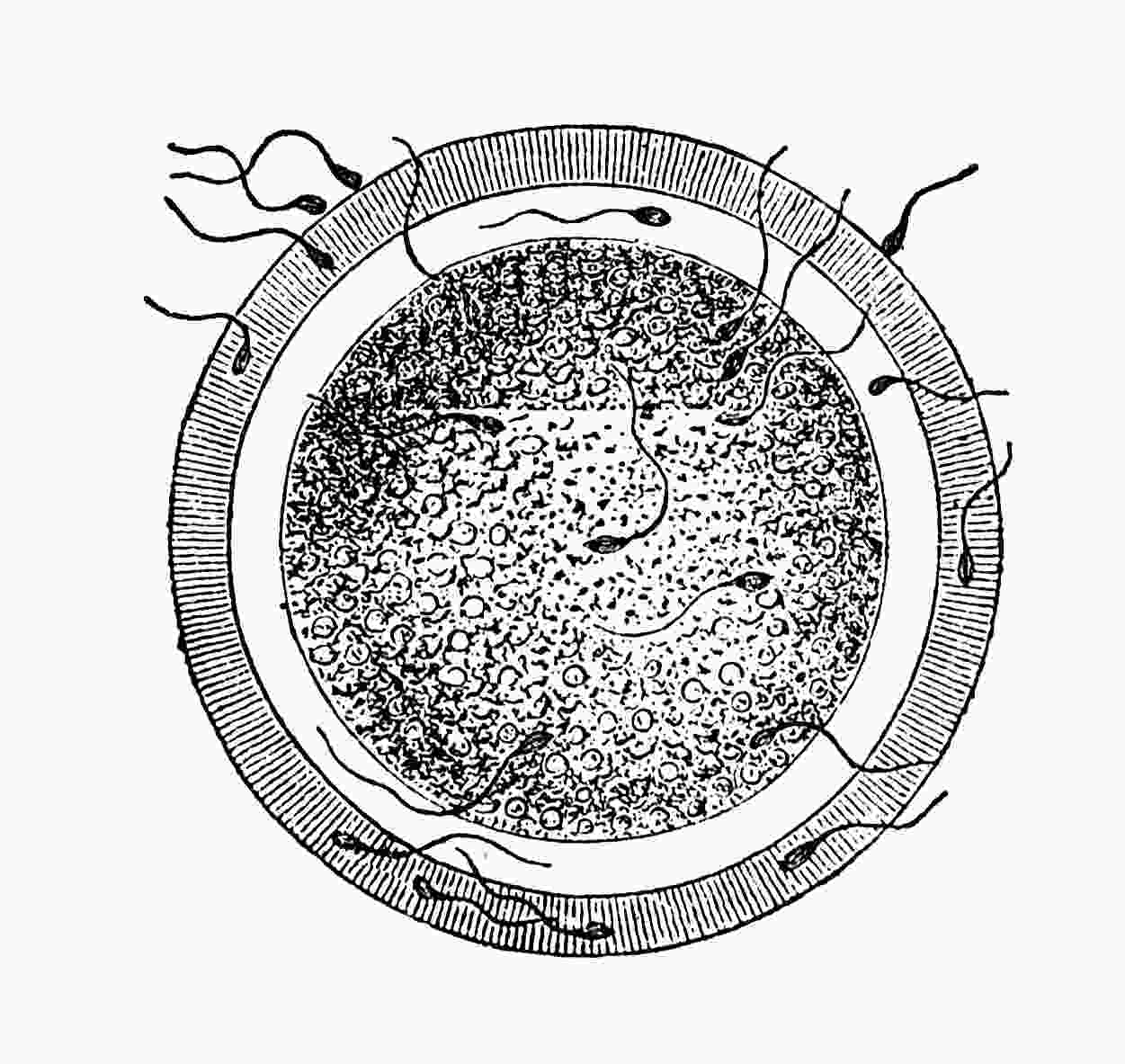 兎の卵の受精
各卵細胞
兎の卵の受精
各卵細胞の
周囲には何十
匹も
精虫が集まってくるが、
最初の
一匹が
卵からの
突起に
迎えられてその内にもぐり
込むと、
卵細胞は直ちに少しく
収縮して表面に
一枚の
膜を生ずる。しこうしていったんこの
膜ができた上は、他の
精虫は
如何に
卵細胞に
接せんと
努めても、これに
隔てられてとうてい
目的を
達することはできぬ。そのありさまはあたかもすでに他に
嫁した
娘に
縁談を申し
込んだのと同様である。ただしあらかじめ薬を用いて
卵を
麻酔させておくと、一つの
卵の中へ
何匹もの
精虫が
続々とはいり
込む。世間には「
娘一人に
婿八人。」というたとえがあるが、
受精のために一
卵細胞の
周囲に集まる
精虫はずいぶん多数にのぼるのがつねで、これらがみな
尾を
振り動かして
卵の中へ頭を
突き入れようと
努力するために、
卵が転がされているのをしばしば見かける。
卵細胞は
濃い
粘液に
包まれたもの、
膠質の
膜をかぶるものなどが多いゆえ、
卵細胞に近づくまでには、
精虫はこれらを
貫き進まねばならず、そのため
精虫の頭の
先端は
往々穴掘り道具のごとき形を
呈している。多数の
精虫はおのおの
我一番に
卵細胞に
達せんと、
粘液や
膠質の中を
競争して進むが、この
競争は
精虫にとっては実に生死の
別れ目で、第一着のもの
一匹だけは
目的どおりに
卵細胞と
相合し、新たな一
個体となって
生存し
続け、第二着
以下のものはことごとく
拒絶せられ、
暫時もがいたのち
疲れ弱って死んでしまう。生物界には、
個体間にも
団体間にもいたるところにはげしい
争いがあるが、いまだ
個体とならぬ前の
精虫の間でも、
競争はかくのごとく
激烈である。
精虫は
卵と
相合することができねば死に終わるが、
卵細胞のほうも
精虫に
遇わねばそのまま
亡びる。
単為生殖をする
若干の動物を
除けば、
卵が発育するには
精虫と
相合することが
絶対に
必要で、もし
精虫に
遇う
機会がなければ、たとい
卵が生まれてもけっして育たぬ。
牝鶏ばかりでも食用に
適する
立派な
卵を
産むが、これから
雛をかえすことはできぬ。しかも近来は薬品を用いて、
種々の動物の
卵を
精虫なしに
或る
程度まで発育せしめることができて、
蛙の
卵などはただ
針の先で
突いただけでもひとりで発育せしめ
得ることが知れたが、かような人工
的の
単為生殖法で、何代までも
子孫を
継続せしめることができるか
否かはすこぶる
疑わしい。元来
卵細胞は子の発育に
要するだけの
滋養分を
貯えており、
蜜蜂類のごとき同一の
卵が、
受精せずとも発育する
例もあるゆえ、ある
刺激を受けて、
不自然に発育することも
当然あり
得べきことであるが、
自然界において
単為生殖がただ
特殊の場合に
限られていることから考えると、
精虫の
働きはけっして
単に
卵細胞に
刺激を
与えるだけではない。もし薬品を用いて、
完全に
精虫の代わりをつとめしめることができるものならば、人間社会もゆくゆくは女と薬とさえあればすむわけで、男は全く
無用の長物となるであろうが、
自然に
単為生殖をする動物でさえ、一定の時期には
必ず
雄が生じて
雌雄で
生殖することを思うと、
雄の
必要なる理由はなお他に
存することが知れる。されば
如何なる生物でも
有性生殖にあたっては、
卵細胞と
精虫とが
相合することは
絶対に
必要であって、けっして長くこれを
欠くことはできぬ。いつまでも
種族を
継続させるためには、その
種族の
卵と
精虫とをなんらかの
方法によって、いつかどこかで
相合せしめることが
絶対に
必要であるが、この事を
眼中において、
各種生物の身体の
構造や生活の
状態を
見渡すと、その全部がことごとく
卵と
精虫とを
出遇わしめるためにできているごとくに感ぜられる。生物の
生涯は、食うて
産んで死ぬにあるとはすでに前に
述べたが、物を食うのはすなわち
卵細胞や
精虫を
成熟せしむるためで、子を
産むのはすなわち
卵細胞と
精虫との
相合した
結果である。しこうして
産み
得るためには、自身の
生殖細胞と
異性の
生殖細胞とを
出遇わしめるように全力を
尽くして
努めねばならぬ。
餓えと
恋とが、
浮世の原動力といわれるのはこのゆえである。また死ぬのは、
卵と
精虫とが
相合して
後継者ができたためにもはや親なるものの
必要のなくなったときで、死ぬ者は
残り
惜しくもあろうが、
種族の
生存から見るとすこぶる
結構なことである。
かように考えると
受精ということは、生物界の個々の
現象を
解釈すべき
鍵のごときもので、生物の
生涯を
了解するにはまず
受精の重大なる
意義を
認めねばならぬ。生物の
生涯が、
受精の
準備と
受精の
結果とより
成り立つことを思うと、
各個体が
生殖細胞を生ずるというよりは、むしろ
各個体は
生殖細胞のために
存するというべきほどで、
各個体は生まれてから死ぬまで、つねに
生殖細胞の
支配を受けているというてよろしい。生物
個体の一生はあたかもあやつり人形のようなもので、
舞台だけを見ると、
各個体がみな自分の
料簡で、思い思いの行動をしているごとくであるが、実は
卵細胞と
精虫とが
天井の上に
隠れて糸をあやつっている。
鹿が角で
突き合うのも、
孔雀が
尾を広げるのも、七つ八つの女の
児が
紅や
白粉をつけたがるのも、
若い書生が太い
杖を持って
豪傑を気どるのも、そのあやつられていることにおいては
相ひとしい。しこうして、
精虫と
卵細胞とがかくあやつる
目的は何かといえば、
受精によって
種族を長く
継続せしめることにある。「女の女たるゆえんは
卵巣にある。
卵巣を
除き去った女は決して女ではない。」と言うた有名なる医学者があるが、これは女に
限ったことではなく、生物
個体の
性質は、肉体上にも
精神上にも、その
生殖細胞の
性と
関係するところがすこぶる深い。次の二章においてはもっぱらこれらの
相違について
述べるつもりである。
雌とは
卵を
産む
個体、
雄とは
精虫を生ずる
個体のことであるが、この両者の
相違の
程度は動物の
種類によっていちじるしく
違い、一見して直ちに
区別のできるほどの
差別のあるものもあれば、また注意して調べても
雌か
雄かわからぬようなものもある。動物園にはいって見ても、
孔雀や
鹿は遠方から
雄か
雌かわかるが、
猿や犬は近づいて見なければたしかにわからず、
鷺や
鶴などは
側まで来てもなかなか
区別ができぬ。さらに他の動物を調べると、「なまこ」などのごとくに外面からはもとより、内部を
解剖して見ても
雌か
雄かが
容易にわからぬようなものもあれば、またその反対に
雌と
雄とがあまり
違いすぎるので、だれも
同一種類に
属するものと心づかぬほどのものもある。かくさまざまに
違うた
種類をなるべく数多く集め、
雌雄の
差の全くないものからそのもっともいちじるしいものまで
順を追うてならべて見ると、動物の
雌雄の
別は、
如何なる
道筋を
経て
次第に進み来たったものであるか、大体のありさまを
推知することができる。
雌雄の身体
構造の
相異なる
個所を調べると、その中には
卵と
精虫とを
相合せしめることに
直接に役にたつ部分と、
間接にその
目的を
達せしめるためのものとがある。
雄に
精虫を送り出す
器官があり
雌にこれを受け入れる
装置があるごときは、
直接に役にたつほうであるが、この
種の
器官の
発達は、
卵と
精虫とが
如何なる
方法で
相合するかによって大いに
違う。また
特に
鋭敏な
感覚器をもって
異性の
所在を知り、美しい色やいい声をもって
異性を引きよせる
仕掛けは、同じ
目的のための
間接の
方便であるが、これは
神経系の
発達に
伴うことで、
最下等の動物ではあまり見られぬ。その他、子を
保護し育てる動物では
雌と
雄との役目が
違い、したがって身体にもこれに
準じた
相違がある。
獣類の
牝のみに
乳房が大きく、「たつのおとしご」の
雄のみに
腹に
袋があるごときはその
例であるが、これは
受精の
結果を
完全ならしめるための
補助器官で、子を
産み放しにする動物にはけっしてない。
原始動物中の「ぞうりむし」や夜光虫などは、
相接合する
二個の
細胞の間になんの
相違も見えぬゆえ、これらこそは真に
雌雄の
別のないものといえるが、その他の動物では、たとい
雌雄の
別が少しもないごとくに見えても、その
生殖細胞を見れば、明らかに
卵と
精虫との
区別がある。すなわち
生殖細胞の
区別を
除いては、他になんの
区別もないというにすぎぬ。
海中に住む「うに」、「ひとで」、「なまこ」などは外形を見て
雌雄のわかるものはほとんどない。
解剖して体の内部を調べても、
雌雄の
別が明らかに知れぬことさえしばしばある。このような
類でも
雄の体内には
睾丸があり
雌の体内には
卵巣があるが、
睾丸と
卵巣とはその
在る場所も
一致し、見たところも
極めてよく
似たもので、わずかに色が少しく
違うくらいである。
卵の
粒の
粗い動物ならば、
卵巣は一目して
卵のかたまりのごとくに見えるが、「なまこ」などでは
卵がすこぶる小さくて
肉眼ではとうてい見えぬゆえ、
顕微鏡を用いなければ
雄か
雌かの
鑑定がむずかしい。「うに」の
卵巣は
雲丹を
製する
原料で、生のを
焼いて食うとはなはだうまい。また「なまこ」の
卵巣は「このわた」中のもっともうまいところで、これをかわかしたものを「くちこ」と名づける。いずれも
鯛や「ひらめ」の「子」と
違うて
卵粒は見えぬ。これらの動物には
輸卵管とか
輸精管とか名づくべきものがほとんどなく、
精虫は
睾丸から、
卵細胞は
卵巣から直ちに体外へ出されるが、その出口の
孔にも
雌雄の
相違は全くない。
卵が
極めて小さいゆえ、その
産み出される
孔もはなはだ小さくて、
雄の
精虫を出す
孔と何ら
異なったところはない。「うに」では
肛門の
周囲に五つ、「ひとで」では五本の
腕の
股のところ、「なまこ」では頭部の
背面の中央に一つ、
生殖細胞の
産み出される
孔があるが、注意して見ぬと知れぬほどの小さなものである。
さてかような動物が
生殖するときには、
如何にして
卵と
精虫とを
出遇わしめるかというに、これは実に
簡単を
極めている。すなわち
生殖細胞の
成熟する
期節がくると、
雌は勝手に海水中へ
卵を
吹き出し、
雄は勝手に海水中へ
精虫を
吹き出すだけであるが、
卵や
精虫が小さな
孔から
吹き出されるところを横から見ていると、人が
煙草の
烟を鼻の
孔から
吹き出しているのと少しも
違わぬ。
彼処では
雄が
精虫を
吹き出し、
此処では
雌が
卵を
吹き出すと、
卵と
精虫とは水中を
漂うている間に
相近づく
機会を
得て、
精虫は
卵の
周囲に
游ぎ集まり、かくして
受精が行なわれるのである。されば「うに」や「ひとで」の
子供にも父と母とはたしかにあるが、
産まれる前にすでに
縁が切れているから、親と子との間には始めから何の
関係もない。父はわが子の母を知らず、母はわが子の父を知らず、しかも何千か何万かの
雄と
雌とが同じ海に住んでいることゆえ、どの
雌の
産んだ
卵がどの
雄の
精虫と
相合するかわからぬ。かかる動物では、
受精は全く
独立せる
生殖細胞の、たがいに
相求める力によってのみ行なわれるのである。
右のごとき
方法による
受精は、むろん水中に住む動物でなければ行なわれぬ。しこうして水中で
卵と
精虫との
出遇うのは、よほどまでは
僥倖によることゆえ、
卵の多数が
受精せずしてそのまま
亡びることもないとはかぎらぬ。
特に水中には小さな
卵や弱い
幼虫を
探して食う
敵が
非常に多くいるから、
精虫に
遇わぬ前に他の
餌食となるものもたくさんあろう。また小さな
幼虫となってから食われるものもすこぶる多かろう。さればこの
類の動物は、かような
損失をもことごとく
見越してよほど多くの
卵を
産まぬと、
種族保存の
見込みが十分に立たぬわけであるが、
実際飼うておいて見ると、その
生殖細胞の
産み出されることは実に
非常なもので、水族箱内の海水が全部白く
濁るほどになる。植物でも
虫媒花の
花粉が
無駄に
散っていることは少ないが、
松などのごとき
風媒植物の
花粉は
驚くほど
多量に生じて、あたかも
硫黄の雨でも降ったかのごとくに地上一面に落ち
散るのも、おそらくこれと同じ
理屈であろう。
卵も
精虫もまず親の身体から
離れ、しかる後に水中で勝手に
受精するような動物は、「うに」や「なまこ」のほかにもなおいくらもある。
普通に人の知っているものから
例を出せば、
蛤、「あさり」、
蜆などの
二枚貝類がみなこれに
属する。
蛤でも
蜆でも
一匹ずつことごとく
雄か
雌かであるが、
貝殻だけで
区別のできぬはもちろん、切り開いて内部を見ても全く同様である。それゆえ、多数の人々はつねに食いなれていながら、
雄と
雌とがあることさえ心づかぬ。一体
雌雄の体形上の
相違は、主として
雄の
精虫を
雌の体内へ
移し入れるための
器官、または
両性を
相近づかしめるための
装置の
差にあるゆえ、
雌雄が
相近づく
必要のないような動物に、
雌雄体形の
相違のないのは
当然である。「くらげ」や「さんご」なども
雌と
雄とがあるが、身体の形にはなんの
相違もない。
外形では
雌雄の
別がないようでも、身体を切り開いて内部を見ると、直ちに
雄か
雌かが知れる動物もなかなか多い。昔から「
誰か
烏の
雌雄を知らんや。」というが、これは
烏を
解剖せぬ人のいうことで、
腹を切り開けば、
雌雄はだれにも直ちにわかる。
雌ならば
卵粒の明らかな
卵巣と太い
輸卵管とがあり、
雄ならば一対の
睾丸と細い
輸精管とがあって、その
差が
極めて明らかであるから、けっして
間違える気づかいはない。
鳥類の中には
鶏、
孔雀などのごとく
雌雄によって形の
違うもの、
雉子、
鴨などのごとく色の
違うものもあるが、
烏のように
雌雄の全くわからぬものもすこぶる多い。
鷲、
鷹、
梟のごとき食肉鳥、
文鳥、「カナリヤ」のごとき
小鳥類、
鶴、
鷺等のごとき
水鳥類も多くは
雌雄全く同色同形で、たとい
僅少の
相違があっても、
素人にはわからぬくらいのものである。
蛙、
蛇、
亀の
類も外形では
雌雄の
区別がわからぬことが多く、
魚類などもほとんど全部
雌雄同じように見える。もっとも
雌は
卵のために
腹のふくれていることが多いゆえ、
腹の丸さ
加減で
雌雄の
鑑定のできる場合もある。いずれにしても、これらの
類はちょっと
腹を切り開いて見さえすれば
雄か
雌か直ちに知れる。さてかような動物では
受精は
如何にして行なわれるかというに、これは水中と
陸上とでは大いに
違わざるを
得ない。前にも
述べたとおり、水中に
棲む動物では、
雄と
雌とが
別々に
吹き出した
生殖細胞が、水中で
随意に
出遇うことができるが、
陸上に
産卵する動物では、そのような体外
受精はとうてい行なわれぬ。植物ならば、
花粉が風に
吹き
飛ばされて遠方まで空中を運ばれることがあるが、動物の
精虫は
乾けばたちまち死ぬゆえ、
液体外に出ることができず、したがって
卵細胞に
達するまで
絶えず
濡れつづけていなければならぬ。それゆえ
陸上の動物では、
精虫は
必ず何らかの
方法で
雄の体から
雌の体へ直ちに
移し入れられる
必要がある。外形上
雌雄の
別のわからぬような動物の
受精の
方法を見ると、
実際体外で
受精するものと、体内で
受精するものとがあり、体外で
受精するものはことごとく水中で
産卵する
種類のみにかぎっている。
親の身体を出てから、
卵と
精虫とが水中で
出遇うことの
難易は、両親のいる場所が
互いに遠いか近いかによって
非常に
違う。
互いに遠く
相隔ったところで、一方では
卵を、一方では
精虫を
吹き出したのでは、その間に
受精の行なわれる
望みは
極めて少ないが、
接近したところで同時に
生殖細胞を
吹き
出せば、ほとんど全部
受精することができよう。それゆえ、体外
受精をする動物は多くは
一個所に
群居しているもので、「うに」などのごときも、小船からのぞいて見ると、
浅い
海底の岩のくぼみにいくつとなくならんでいる。しかしこれは
雌雄相近づくために、わざわざ遠方から集まって来たのではなく、ただ同じところに育ったものである。
魚類のごとき運動の自由なものになると、これと
違い同じく体外
受精が行なわれるのであるが、
産卵期になると
雄は
雌を追うて
接近し、
雌の
産卵すると同時にこれに
精虫を
加えようとつとめる。金魚や
緋鯉を
鉢に
飼うておいても、
卵を
産むころになると
雄がしきりに
雌を追いかけて
游ぎまわるが、これはただ生まれた
卵に直ちに
精虫をそそぐためであって、けっして真の
交尾が行なわれるのではない。
鮭などは日ごろは深い海に住みながら、
産卵の
季節が近づくと遠く
河をさかのぼって
浅いところまで
達し、
尾で
砂利を
掘ってくぼみをつくり、そこで
雌が
卵を
産めば
雄が直ちに
精虫を
加える。そのころの
鮭は
卵も
精虫もともに十分に
成熟して、生まれるばかりになっているゆえ、手で体を
握って
腹をしぼれば直ちにあふれ出るが、かくして出した
卵と
精虫とを水中で
混じ、なお
清水中に
飼うておくと
漸々発育してついに
幼魚となる。これは
鮭の人工
孵化法と
称して、今日ところどころで
鮭をふやすために行なうているが、このようなことはむろん体外
受精をする動物でなければ行なわれぬ。もっともまれには
普通の
魚類にも真に
交尾するものがある。
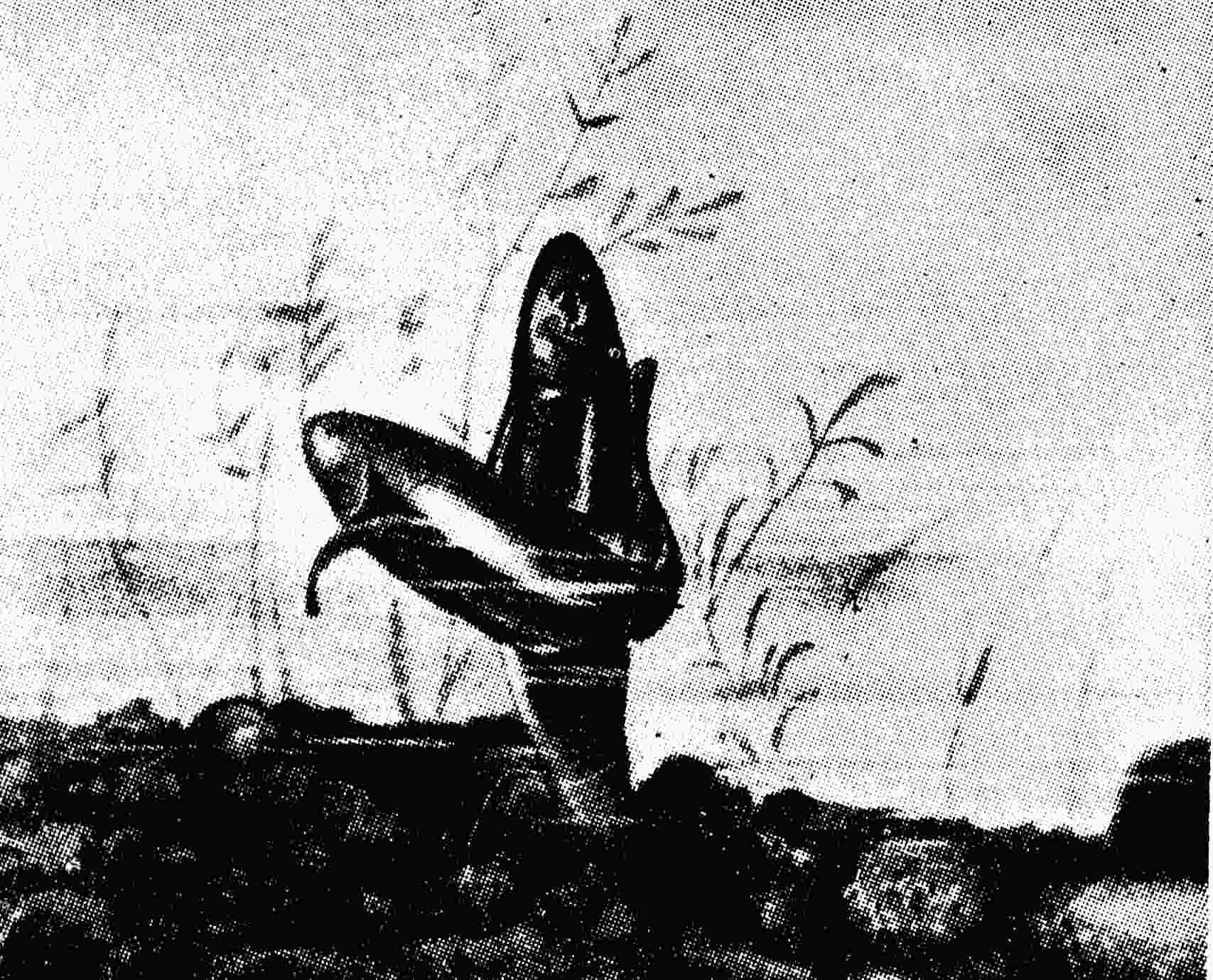 魚の交尾の一例
魚の交尾の一例
ここに図を
示したのはその
一例で、直立しているのは
雌、
巻きついているのは
雄であるが、
雄と
雌とは
生殖器の開口を
密接せしめるゆえ、
精虫は少しも水中にでることなしに直ちに
雄の体から
雌の体に
移り入ることができる。また
鰻は
鮭とは反対で、つねには
河や池にいるが、
卵を
産みに海までくだるものゆえ、人工
的に
受精せしめることはとうてい
望まれぬ。
養魚場に
飼うている
鰻は、すべて
幼い時に
捕えたものに
餌を
与えて
成長させるだけにすぎぬ。
鰻は
胎生すると言い
伝えている地方もあるが、これは
腹の内にいる
蛔虫類の
寄生虫を、「
鰻の子」であると
早合点したためで、全く
観察の
誤りである。
蛙も
魚類と同じく体外
受精をするものであるが、
産卵の
際に
雄が
雌に
固く
抱きついているゆえ、あたかも
交尾しているかのごとくに見える。しこうしてかく
抱きつくのは
一種の
反射作用であって、
産卵期に
雄の
腹の
皮膚をなでると、何物にでも
抱きつくのみならず、いったん
抱きついたものは、
脳髄を切り去っても決して
離さぬ。
俗に「
蛙の
合戦」と名づけるのは
産卵のために多数の
蛙の集まったのであるが、かかる
際には
雄の
蛙に
固くしめられて死ぬものがたくさんにできるくらいである。
雄が長く
抱きしめているうちに
雌は
必ず
産卵するが、それと同時に
雄は
精虫をだし、しかる後に
腕をゆるめ
雌を
離して、また自由に生活する。されば
卵と
精虫との
出遇うのは親の体外であるが、両親が
密接して同時に
生殖細胞を出すゆえ、
卵が
受精せぬおそれは少しもない。「いもり」も水中で
産卵するが、この
類では
受精は
雌の体内で行なわれる。ただし
精虫が
雄の体から直ちに
雌の体へ
移されるのではなく、
雄がまず
水底に
精虫の
一塊を
産み落とすと、
雌が後からこれを
肛門でくわえ、自身の体内へとり入れる。「いもり」は
卵を
一粒ずつ遠く
離して、水草などに
産みつけるが、体内で
受精がすんでいるゆえ、かかることが
髄意にできる。もし
蛙のように
雄がしじゅう
抱きついていたら、これはとうていできぬことであろう。
鳥類は他の
陸上動物と同じく、
受精はすべて
雌の体内で行なわれる。生まれた
卵はすでに
受精後何時間かを
経たものである。水中と
違うて、
精虫は
雄の体から
必ず
直接に
雌の体に
移されねばならぬが、
普通の
鳥類の
雄には
精虫を
雌に
移し入れるための
特別な
器官もなく、また
雌にこれを受けるための
装置もない。それゆえ
精虫を
移し入れるにあたっては、
雌雄はただ
生殖器の出口なる
肛門を少しく開いて、
暫時互いにおし合わすにすぎぬ。そのさまはあたかも
肛門で
接吻するごとくであるが、かくすれば
蛙や「いもり」の場合と
違い、
精虫は少しも外界に
触れず、
無駄なしに全部親の体から体へと
移り
得る
便がある。
以上述べたとおり、外形では
雌雄の
別のわからぬような動物でも、
腹の内には
必ず
卵巣か
睾丸があって、何らかの
方法によって
卵と
精虫とを
出遇わしめる。すなわち
或る者は体外で
受精が行なわれ、
或る者は
雌の体内に
精虫が
移し入れられるが、
雄が
直接に
雌の体内に
精虫を入れる場合には、これを
確実に行なうために
特殊の
器官をそなえている者も少なくない。
例えば
普通の
鳥類にはかような
交接器はないが、
雁、
鴨のごとき
水鳥類の
雄には
生殖器の出口に
肉質の
突起があって、
交接するときこれを
雌の
肛門内にさし入れる。
駝鳥では
雄の
交接器が
特に大きくて長さが
一尺(注:30cm)
以上もある。かような
交接器が体外へ
突出しているときには一目してその
雄なることが知れるが、
平常はこれを体内に
収め入れているため、そとから見ては
雌雄の局部の
相違が少しもわからぬ。
蛇、「とかげ」の
類も
平常は
雄の
交接器が
現われていぬゆえ、
雌雄の形が
違わぬように見えるが、実は
肛門内に
立派な
交接器をそなえている。しかもそれが左右
両側にそれぞれ一つずつある。
雄の
蛇を
捕えてその
腹を強くしめると、
肛門から一対の
突起がでるが、これを見て足と思い
誤り、
蛇にも足があるとか、足のある
蛇を発見したとかいうことがしばしばある。せんだっても
或る新聞紙に
奇蛇と題して、
埼玉県の
或る村で一対の足を
備えた
蛇を
捕えた。その足にはおのおの三十六本の
爪が生えてあったという記事が出ていたが、これはむろん
雄蛇の
交接器で、
爪というのはその表面にある
角質のとがった
突起に
違いない。左右一対あって
位置も
腰のところにあたるゆえ、
素人がこれを足かと思うのも
無理ではないが、実は
交接するとき
雌の体内にさし入れる部分である。
亀の
類も
雄には大きな
交接器があって、
交接のときにはこれを長い間、
雌の体内にさし入れているが、つねには
肛門内に
収めているゆえ、そとからは少しも見えぬ。
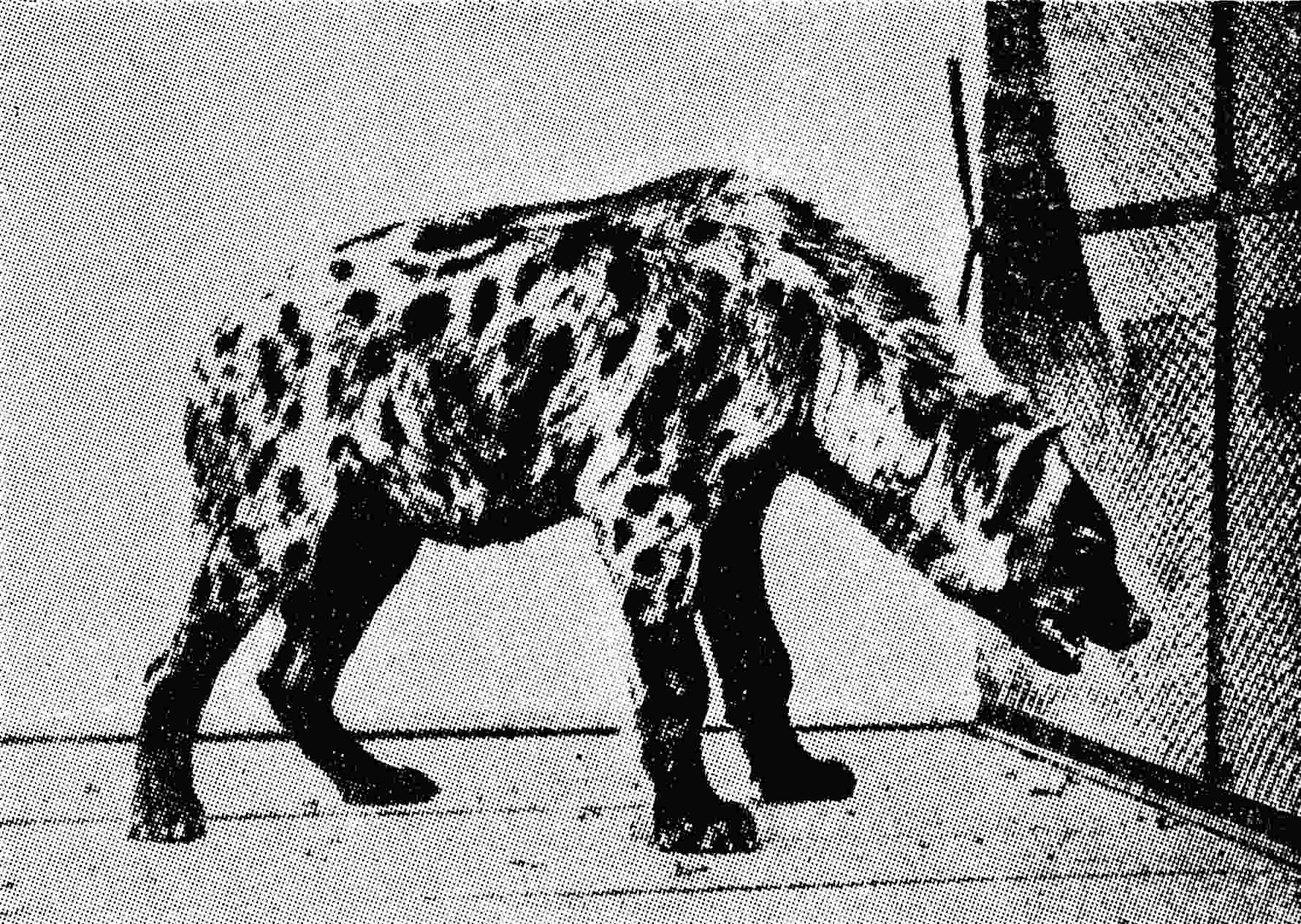 ハイエナ
交接器
ハイエナ
交接器がつねに体外に
現われている動物では、
如何に他の体部が同じであっても、その局部さえ見れば
雌雄の
別は直ちにわかる。
特に多数の
獣類の
雄では、
生殖腺なる
睾丸が
皮膚の
嚢に
包まれて
交接器の後に
垂れているゆえ、
雌との
相違がさらに
明瞭に知れる。もっとも
象のごとくに
睾丸が
腹の内にあるもの、「いたち」、「かわうそ」のごとく
陰嚢の小さなものもあり、「ハイエナ」という
狼に
似た
猛獣などは、動物園で生きたのを
飼うていながら
雌雄がなかなかわからぬようなこともあるが、牛や
山羊などの
飼養畜類では
陰嚢がすこぶる大きく
垂れているから、遠方から見ても、
雌雄を
間違える気づかいはない。また
交接器自身にもずいぶん
巨大なものがあって、北氷洋に住する「セイウチ」などでは、その
中軸の
骨が人間の
腿の
骨よりも大きい。
普通の
魚類は前にも
述べたとおり体外
受精をするゆえ、
交接器を
備える
必要はないが、
鮫、「あかえい」の
類は
例外で、これらはすべて
雌雄交接し、
卵は
必ず
雌の体内で
受精する。多くは
卵生であるが
胎生する
種類も決して少なくない。
雄の
交接器は
腹鰭の
後辺にある左右一対の
棒状の
器官で、
交接のときには
雄はこれを
雌の
輸卵管の
末部にさし入れ、体を
輪のごとくに曲げて
暫時雌の体に
巻きついている。されば同じ
魚類でも、
鯉や
鮒の
雌雄はちょっと
判断しにくいが、
鮫や「あかえい」ならば、体の外面にある
交接器の
有無によって、一目して、その
性を知ることができる。
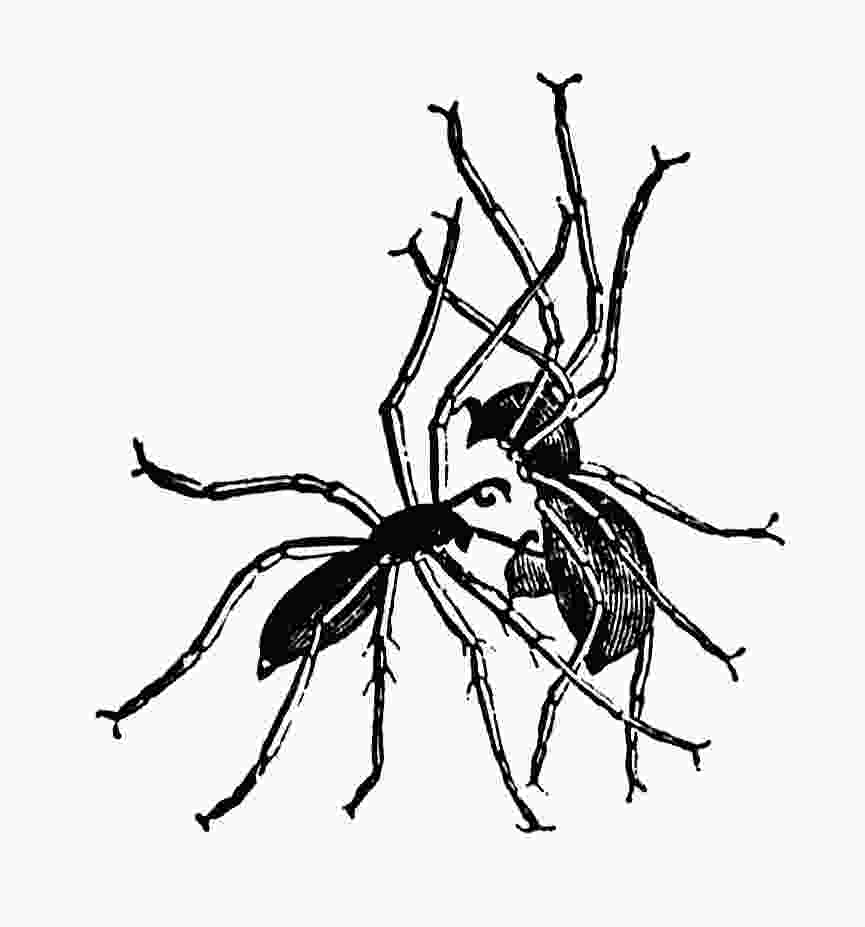 くもの雌雄
精虫
くもの雌雄
精虫を
雌の体内に
移し入れるための
雄の
交接器は、
輸精管の
末端にあたるところがそのまま
延びて
円筒状の
突起となっているのがもっとも
普通であるが、広く動物界を
見渡すと、
必ずしもそれのみとはかぎらず、なかには思いがけぬ体部が
交接の
器官として用いられる場合がある。
例えば「くも
類」のごときはその一つで、
雄は体の前部にある短い
足状のものを
交接器として用いる。「くも」の身体は
通常ひょうたんのごとくにくびれて、前後両半に分かれているが、前半はすなわち頭と
胸との
合したもので、ここからは四対の長い足のほかになお一対の短い足のごときものが生じ、後半は
腹であって、その下面には細い
割れ目のような
生殖器の開き口が見える。短い足のごときものは運動の
器官ではなく、ただ物を
探り
触れ感ずるの用をなすものゆえ、これを「
触足」と名づける。
交接するにあたっては、
雄は決して自分の
生殖器を
直接に
雌の体に
触れるごときことをせず、まず
精虫をもらして自身の
触足の先に受け入れおき、
機を見て
雌に近づき、その
生殖器の開口に
触足をさし入れて
精虫を
移すのである。「くも」
類では
通常雌は
雄よりも形も大きく力も強くて、ややもすれば
雄を
捕え
殺すゆえ、
雄は
交接を終われば急いで
逃げてゆく。
雄の
触足は
精虫をいれるために
先端が太くふくれているゆえ、その部の形さえ見れば
雄か
雌かは直ちに知れる。「たこ」、「いか」
類の
雄も
精虫を
雌の体内に
移し入れるためには足を用いる。八本または十本ある足の中の
或る一本は、
産卵期が近づくと形が少しく
変じ、
先端に近い部分の
皮膚が
柔らかくなり、表面にしわなどができて他の足とはよほど
異なったものとなるが、
交接するにあたっては、
雄はまず自分の
輸精管から出した
精虫をこの
変形した足の先に受け入れ、次いで
雌に近づき、
雌の頭と
胴との間の
割れ目にこの足をさし
込み、
輸卵管のなかへ
精虫を
移し入れるのである。すべて「たこ」、「いか」の
類では
胴は
外套膜と名づける
厚い肉の
嚢で
包まれ、
輸卵管でも
輸精管でも
肛門でもみなその
内側に開いているゆえ、外面からは少しも見えず、したがって
雌雄がその
生殖器の開き口を
互いに
相接触せしめることはとうていできぬ。
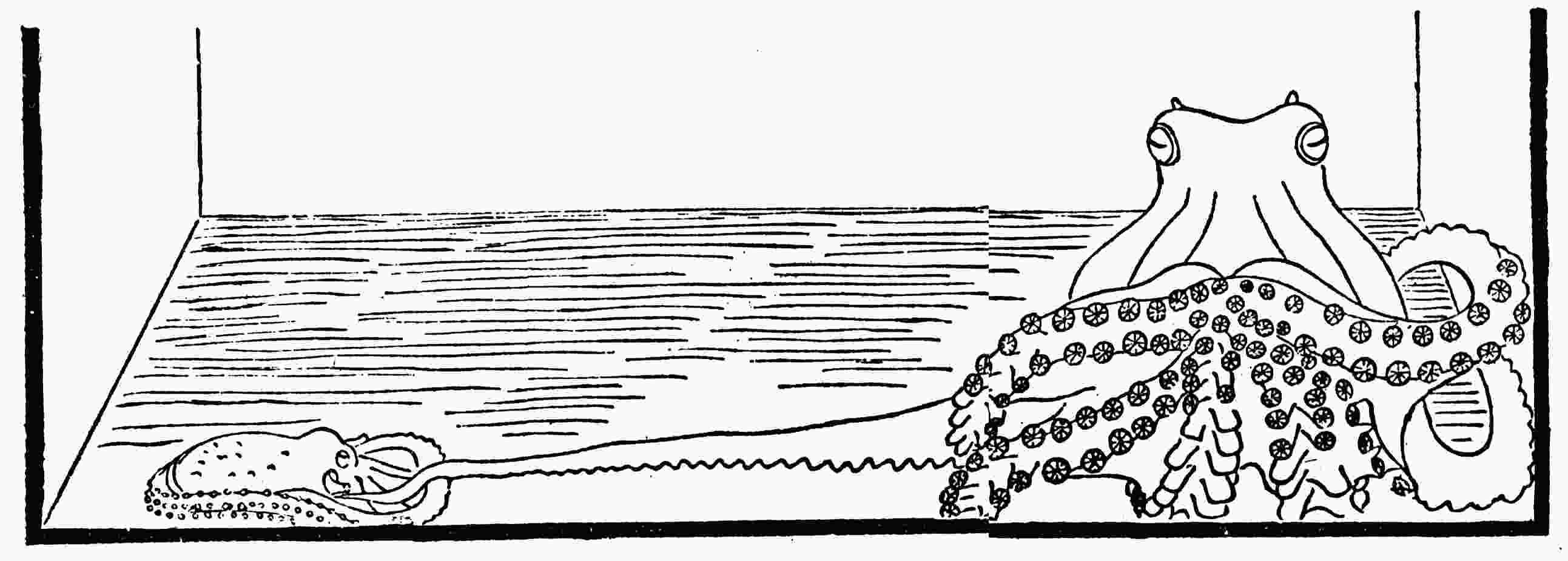 たこの交接
たこの交接
図に
示したのはフランスの
或る水族館で、
普通の「たこ」の
雄がその
変形した足の先を、小さな
雌の
外套膜内へさし入れているところである。
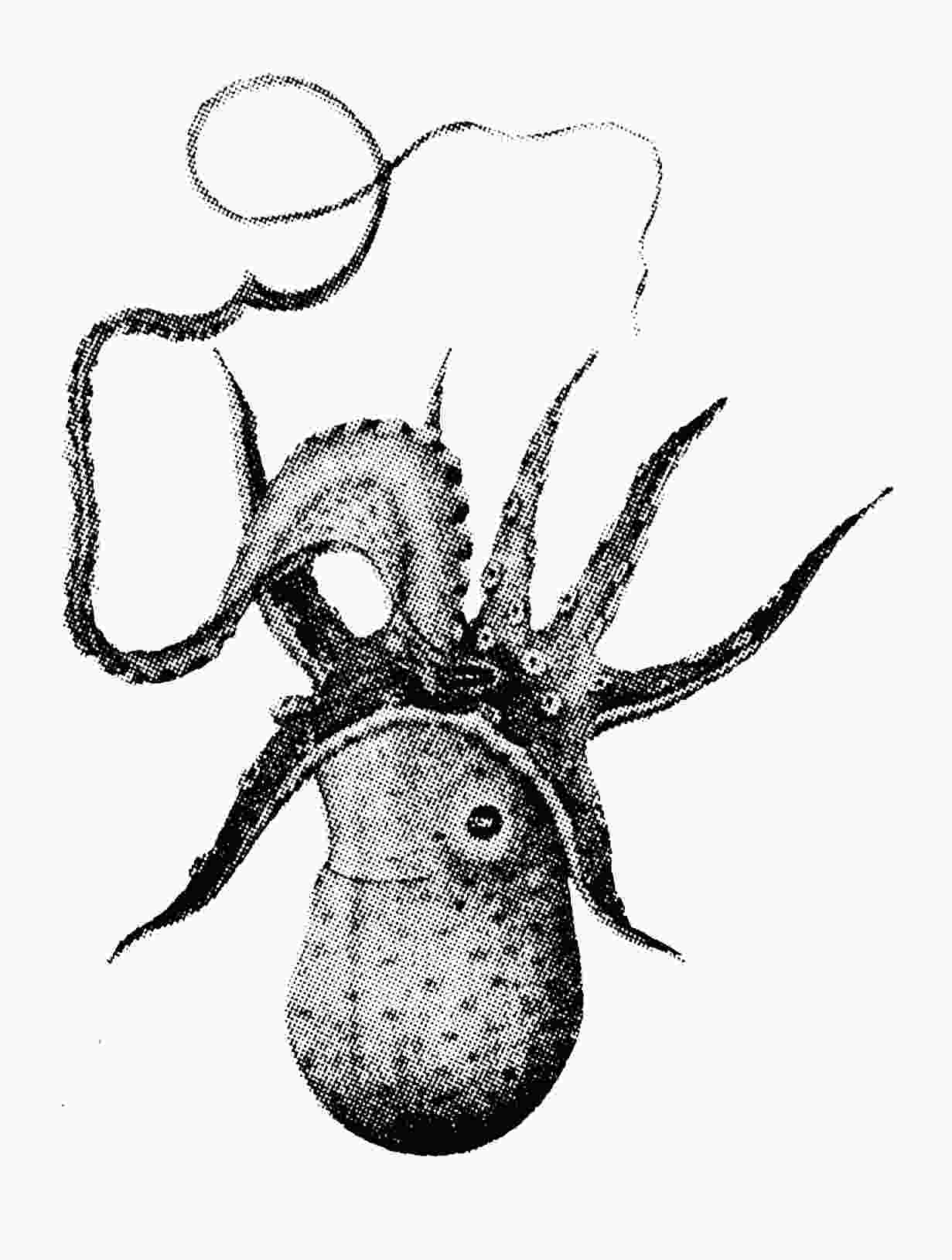 たこぶねの雄
たこぶねの雄
「たこ」の
一種に「たこぶね」と名づけるものがある。
雄は
普通の「たこ」のごとく全身
裸であるが、
雌には
奇麗な船形の
殻があって、
卵を
産むとその
奥に入れて
保護する。
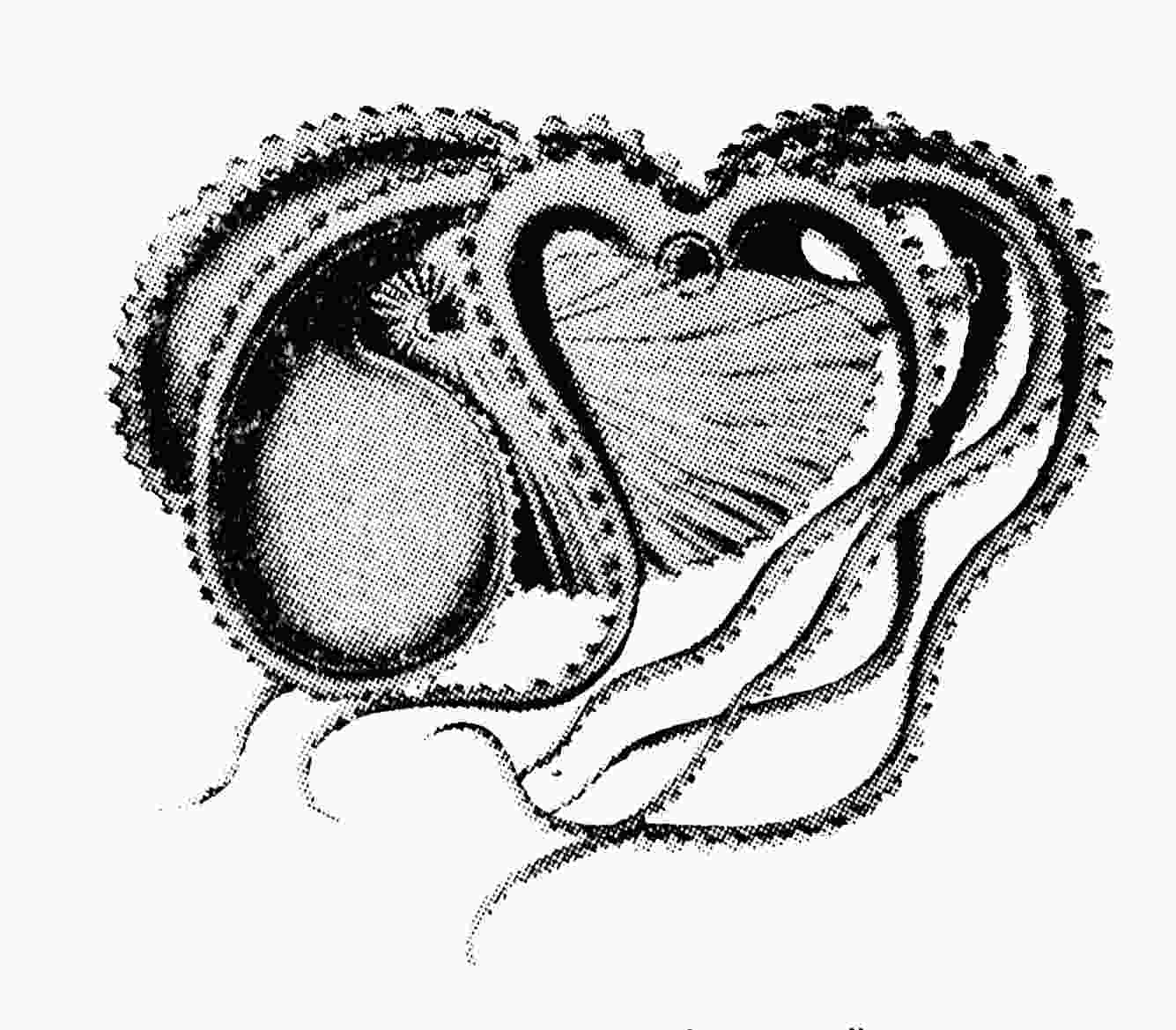 たこぶねの雌
たこぶねの雌
この
殻も他の
貝類のと同じく、体の外面に生じたものであるが
蛤、「あさり」や「たにし」、「さざえ」のとは
違い、肉とつながったところがなく全く
離れているゆえ、生きた「たこぶね」の
雌をあまりひどくつつくと、ついには
殻を
捨てて中身だけが水中を
游ぎ
逃げてゆく。かく
裸になった
雌は
如何にも
不安の様子でしきりに
游ぎまわるが、そこへもとの
空殻を持ってゆくとたちまちこれにつかみつき、体をそのうちへ入れもとのごとき
姿となる。書物には
往々「たこぶね」の
雌が
貝殻にのり、二本の
扁平な足を
帆のごとくに上げ、
残り六本の足を
橈のごとくに用いて水を
漕ぎながら水面を進んでゆくところの図がかかげてあるが、これは全くの
想像であって、
実際には決してさような
芸はできぬ。
何故かというに、
特に
扁平になっている二本の足は
殻をつくり、かつつねにこれをささえているための道具で、もしこれを
離して
帆のごとくに上へ向けたならば、
殻を
保つものがなにもなくなってしまう。さて「たこぶね」は
如何にして
受精するかというに、
雄の足の中の一本が
特に
変形して
交接の
器官となることは
普通の「たこ」と同じであるが、「たこぶね」では
雄が
雌に近づき、この足で
雌に
吸いつくと足は
中途から切れ
離れ、
雄は足の先を
捨ておいてどこかへ
游いでゆく。すなわち
雌に近づき足で
吸いつくまでが
雄の役目で、これがすめば
雄は
随意に
游ぎ去り、その後はただ
残った足の先と、
雌との間に
交接が行なわれるのである。この足は
雄の体から
離れた後にも急には死なず、
吸盤で
吸いつきながら
外套膜のなかへはい入り、
輸卵管の
奥へ
精虫を
移し入れた後は、
自然に生活の力が消えて
廃物となり終わるのである。
仮に人間にたとえて見れば、男が手の指の間に
精虫の
塊をはさみ、とおりがかりの
娘の
肩をたたくと、その手は手首のところから切れ
離れ、手をなくした男は勝手なほうへ行ってしまい、あとに
残った手だけが自分の力ではうて、
腰巻の中まで
潜りこんでゆくのに相当する。
初めて
雌の体内にこの足を見つけた人は、
雄の足の切れたものとはもちろん心づかず、その
伸縮するようすから
一種の
寄生虫であろうと
判定して、これに「百の
吸盤を有する虫」という意味の学名をつけた。この学名は、その
寄生虫でないことの明らかになった今日でも、「いか」、「たこ」
類の
交接用の足を言い
現らわす
名称としてつねに用いられている。
雄のほうに
交接器がある
以上は、
雌の身体にこれを受け入れるだけの
装置のあるは
当然のことと思われるが、小さな
虫類を調べて見ると
必ずしもさようとはかぎらぬ。
輪虫と名づける
淡水産の小虫のことはすでに前の章で
述べたが、この虫の
或る
類では
雄には体の外面に
突出した
錐状の
交接器があるが、
雌にはこれを受けるべき何らの
構造もない。それゆえ
交接するときには
雄はとがった
交接器をもって、どこでもかまわず
雌の体を
突きとおし、そのなかへ
精虫を注ぎいれる。そのありさまは
皮下注射の
器械で「モルヒネ」や
血清を
注射するのとすこしも
違わぬ。
精虫はのちに
組織の間の
空隙をもぐり歩いて、ついに
卵細胞に
達しこれと
相合するのである。
動物の中には、
雌雄の色、形などがいちじるしく
違うて、そのため遠方からでも
容易に
性の
識別のできるものがすくなくない。
獣類では
鹿、
獅子、
鳥類では
孔雀、
鶏などがもっとも人に知られた
例であるが、他の
類からもこれに
似た
例をいくらもあげることができる。しこうしてかようなものを集めて
通覧すると、
雌雄の
異なる点が
生殖の作用と
直接に
関係する場合としからざる場合とがあって、
相違のもっともいちじるしいものはかえって
交接とは
直接に
関係せぬ方面に多い。
鹿の角、
孔雀の
尾などはすべてこの部に
属する。
生殖の作用にやや
直接の
関係を有する
器官が、
雌雄によっていちじるしく
相違する
例をあげれば次のごときものがある。
淡水に
産する「みじんこ」
類を取って
郭大して見るに、
雄の顔の前面には
嗅感器なる鼻の毛が
束をなして長く
突き出ているが、
雌ではこれが
極めて短いゆえ、鼻の毛の
突出する
程度を見れば
雌雄は直ちに
識別ができる。いうまでもなく、
雄は
嗅覚によって
雌のいるところを知りこれに近づくのである。「ひげこめつき」と
称する
甲虫もこれと同様で、
雄の
触角が
櫛状をなしていちじるしく
立派であるゆえ、ひげさえ見れば
雌か
雄かは直ちにわかる。池や
沼に住む「げんごろう」という
甲虫は、
雄の前足は
吸盤があって
幅が広いが
雌のは細いゆえ、この点で直ちに
雌雄の
識別ができる。
雄はこの
吸盤を用いて
雌の
背面に
吸いつき、体をはなさぬようにする。「きりぎりす」や「くつわむし」の
類では
雌の体の
後端からは長い
産卵管が
突出し、
雄にはこれがないゆえ
子供でもその
雌雄を知っている。
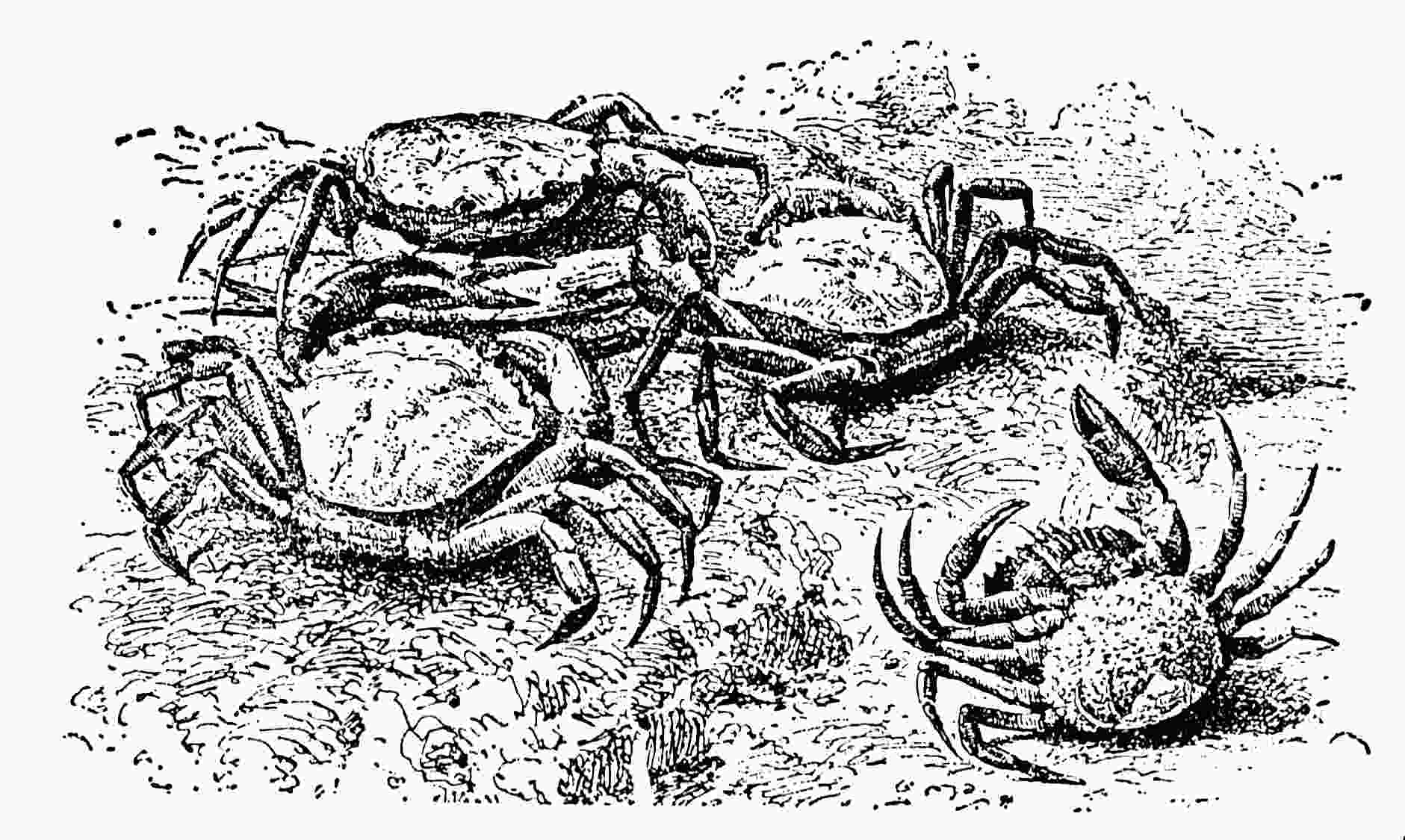 卵をつけた蟹
蟹
卵をつけた蟹
蟹の
腹部は前へ
折れて体の
裏面に
密着しているが、これを
俗に「
蟹の
褌」という。ところで
雄は
褌の
幅がせまく、
雌は
褌の
幅が広いゆえ、
褌の
幅さえ見れば
蟹の
雌雄は
誰にでもわかる。
蟹は
卵を
産むと、これを体と
褌との間にはさみ
孵化するまで
離さぬが、
雌の
褌の
幅の広いのはそのために
都合がよろしい。
以上述べたごとき
雌雄の
相違は、あるいは
雌に近づくためあるいは
雌を
離さぬため、あるいは
卵を
産むためあるいは
卵を
保護するためで、いずれもみな
生殖の作用と
直接関係あるものばかりである。
これに反して、
鹿の角、
獅子のたてがみのごときは
直接には
生殖作用と
関係せず、ただ
雌をうばい合うための
争闘の具として、または
威厳を整えるための
一種の
装飾として役に立つだけである。人間のひげなども同じ組に
属する。かような
性質の
雌雄の
相違は
獣類には
割合に少ないが、
鳥類や
昆虫類などには
極めて
普通で、かつずいぶんいちじるしいものがある。
鶏、
孔雀が
雌雄によって形が
違い、
雉子、
錦鶏、
鴨、
鴛鴦などが
雌雄によって毛色の
違うことは、
誰も知っているが、「大るり」と名づける「もず」に形の
似た鳥は、
雄は全身美しい
瑠璃色、
雌は全身茶色であるゆえ、
初めてその
標本を見た西洋の学者は、
雌雄を
別の
種類と考え、おのおのに学名をつけた。その他にもほとんど同一
種とは思えぬほどに
雌雄の
異なる
鳥類はたくさんあって、ニューギニアに
産する有名な
極楽鳥のごときも、
雄には実に
美麗な白茶色の長い羽毛が
総の形に
両翼から
垂れているが、
雌にはこのようなものが全くないゆえ、見たところがまるで
違う。
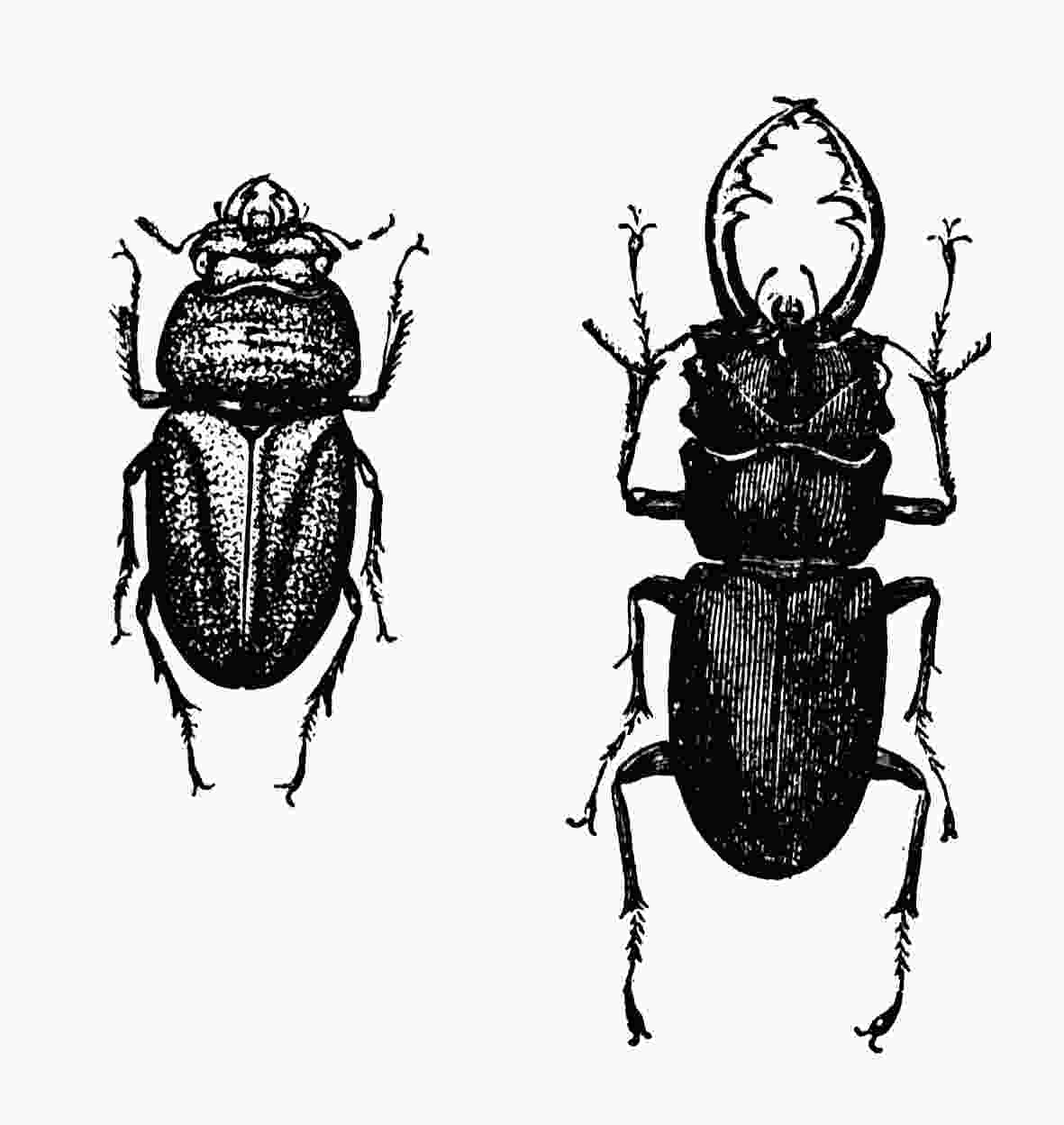
くわがたむし
(左)雌 (右)雄
昆虫類には
雌雄のいちじるしく
違う
例はいくらでもあって、とうてい
枚挙のいとまはない。
甲虫の中で、「さいかちむし」の
雄には頭部に大きな
突起があるが、
雌にはこれがない。「くわがたむし」の
雄は左右の
顎がすこぶる大きくて、あたかも
鹿の角のごとくに見えるが
雌はこれがはなはだ小さい。日本の
螢は
雌雄ともに
飛ぶが、外国の
螢には、
雄だけが空中を
飛びまわり
雌は
翅がなく、
蛆のごとき形で地上をはうている
種類がある。毛虫を
飼うておくと、それからでる
蛾が、
雄だけは
翅を
備え
雌には全く
翅のないような
種類もある。
蝶類には
雌雄で色や
模様の
違うものが
特に多い。「つまぐろひょうもん」という
蝶の
雄は、
豹の皮のごとくに黄色の地に黒い
斑点があるが、
雌は前
翅の外半分が黒いから直ちにわかる。また、「めすぐろひょうもん」では、
雌の
翅は
雄のとは全く
違って、前後ともに全部黒色の中に白い
紋があるだけゆえ、
誰の目にも同
一種の
蝶とは見えぬ。早くから日本の
蝶類を調べていた
横浜のプライヤーという人のごときも、始めはこの
蝶の
雌を全く
別種のものと思うていた。
柳の
枝によく止まっている「こむらさき」という
蝶は、
雌雄とも
翅は元来
茶褐色であるが、
雄は見ようによって
紫色にかがやき、実に美しい。しかるに
雌はどの方角から見ても、決して
紫色に光ることはない。このような
例はいくつでもあるが、かぎりがないゆえ
略する。
動物には
雌雄によって身体の大きさの目だって
違うものもずいぶんある。
獣類の中でも「おっとせい」のごときは
牡は
牝に
比してはるかに大きく、身長は二倍
以上、
重量はほとんど十倍
以上にも
達する。
概して
獣類では
雌雄で大きさの
違う場合には、
必ず
雄のほうが大きい。
猿なども
牡のほうが
牝よりも少しく大きいのがつねである。
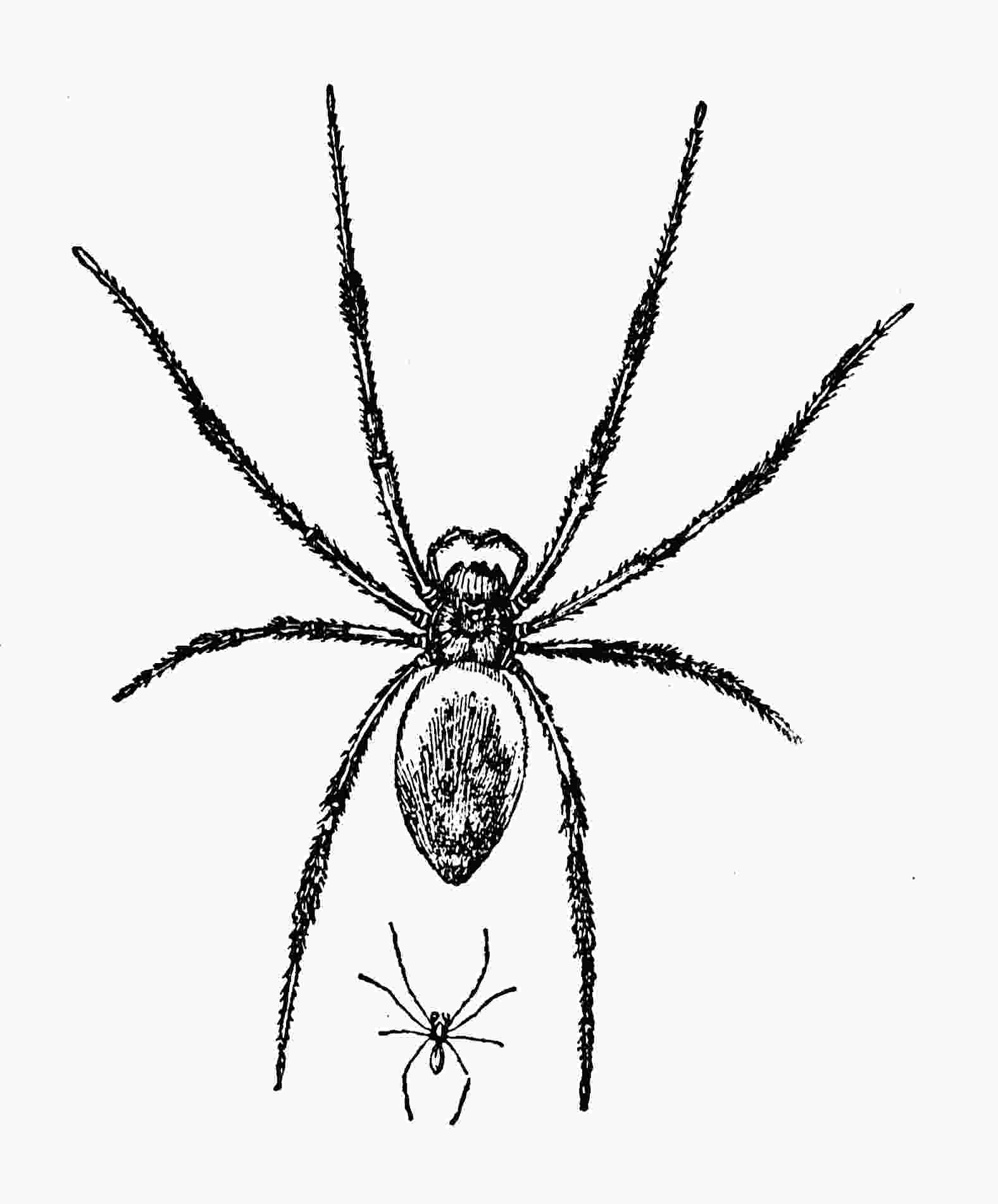
くもの一種
(大)雌 (小)雄
これに反して
昆虫類には、
雄よりも
雌のほうが大きいものが多い。
亭主が小さくて
細君のほうが大きいと、
俗にこれを「
蚤の
夫婦」というが、
実際蚤にかぎらず
蠅でも
蚊でも
雌のほうがいくらか大きい。これは一つは
卵巣が大きくて、そのため
腹が
膨れているゆえでもあろう。
稲の
害虫「うんか」なども
同種のものを調べて見ると、いつも
雄よりも
雌のほうがいちじるしく大きい。外国に
産する「くも」
類の中にはその
相違がさらにはなはだしく、
雄はわずかに
雌の十分の一にもおよばぬものがある。
しかしながら他の動物を見ると、さらに
驚くべきほど
雌雄の大きさの
違うものがある。
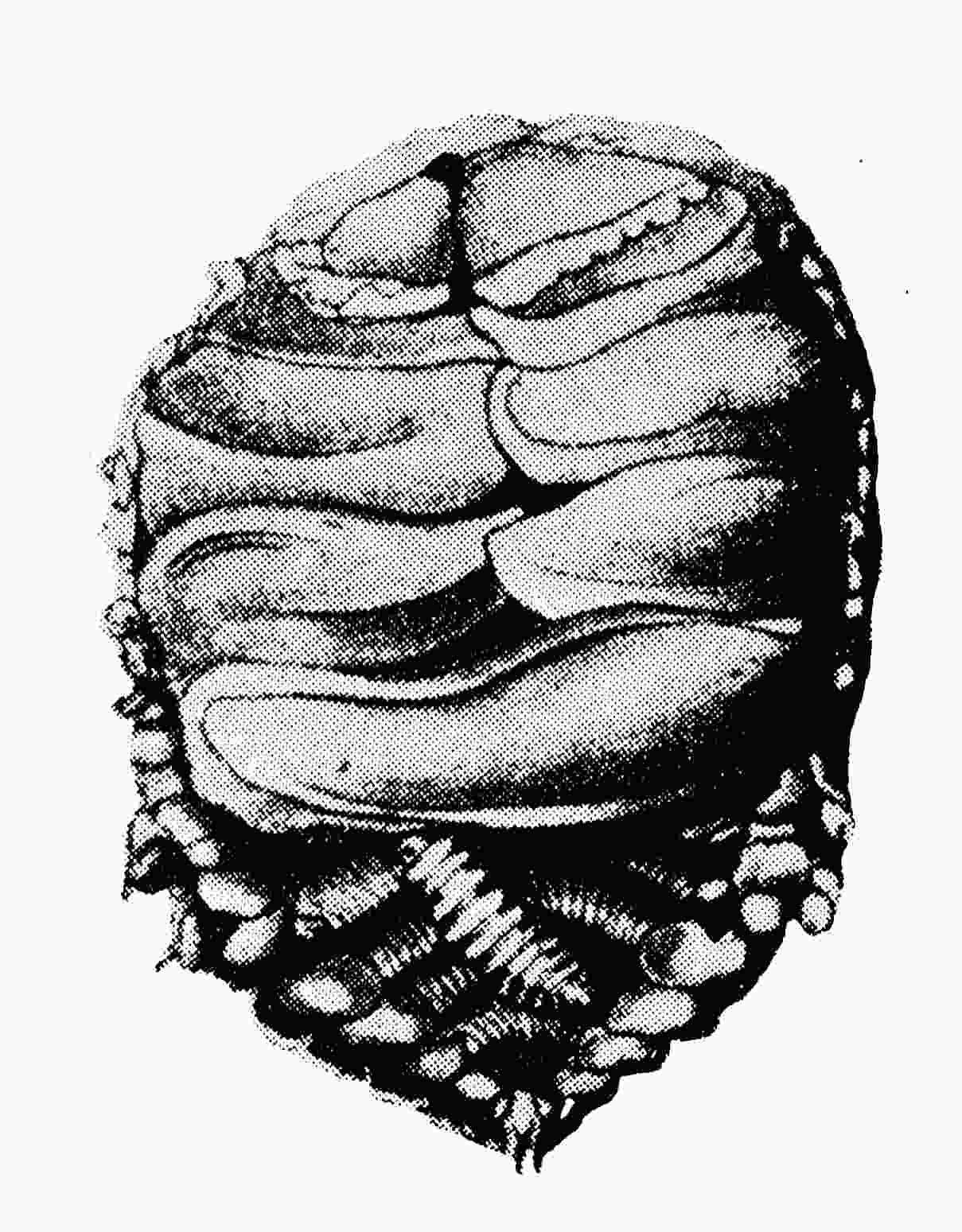 寄生ふなむし
寄生ふなむし
いま二三の
例をあげて見るに、「ふなむし」、「わらじむし」の
類には他動物の体に
寄生する
種類がたくさんあるが、その中には
雄が
非常に小さくて、
一生涯雌の
腹の
生殖器の開き口の
側に
付着したままで
離れぬようなものがある。一体かような
類はつねづね人に知られぬものゆえ、少しく
説明を
加えておくが、「ふなむし」でも「わらじむし」でも体は
長楕円形で、その
両側から七対の足がそろうて生じ、これを用いて
巧みにはい歩いている。ところが同じこの
類でも、他動物に
寄生する
種類では体は
肥えてやや丸く、足は
極めて短い代わりに、
末端の
爪は
鉤状に曲がって
容易にはずれぬようにできて、
魚類の口の中や
鰓の
辺、「えび」の
甲の
裏面などに
固くかじりついているが、図に
示した
一種では、
雌の体はほぼ円形で、その左右の
縁にそうて短い小さな足が
七個ずつ見える。しこうして
腹面の下のほうに
斜に
吸いついている小虫のごときものは、この虫の
雄である。
雄はこのとおりあたかも犬に「だに」が
吸いついたごとくに、
雌の
腹に
固着し、
雌から
離れることなしに
一生涯を終わる。
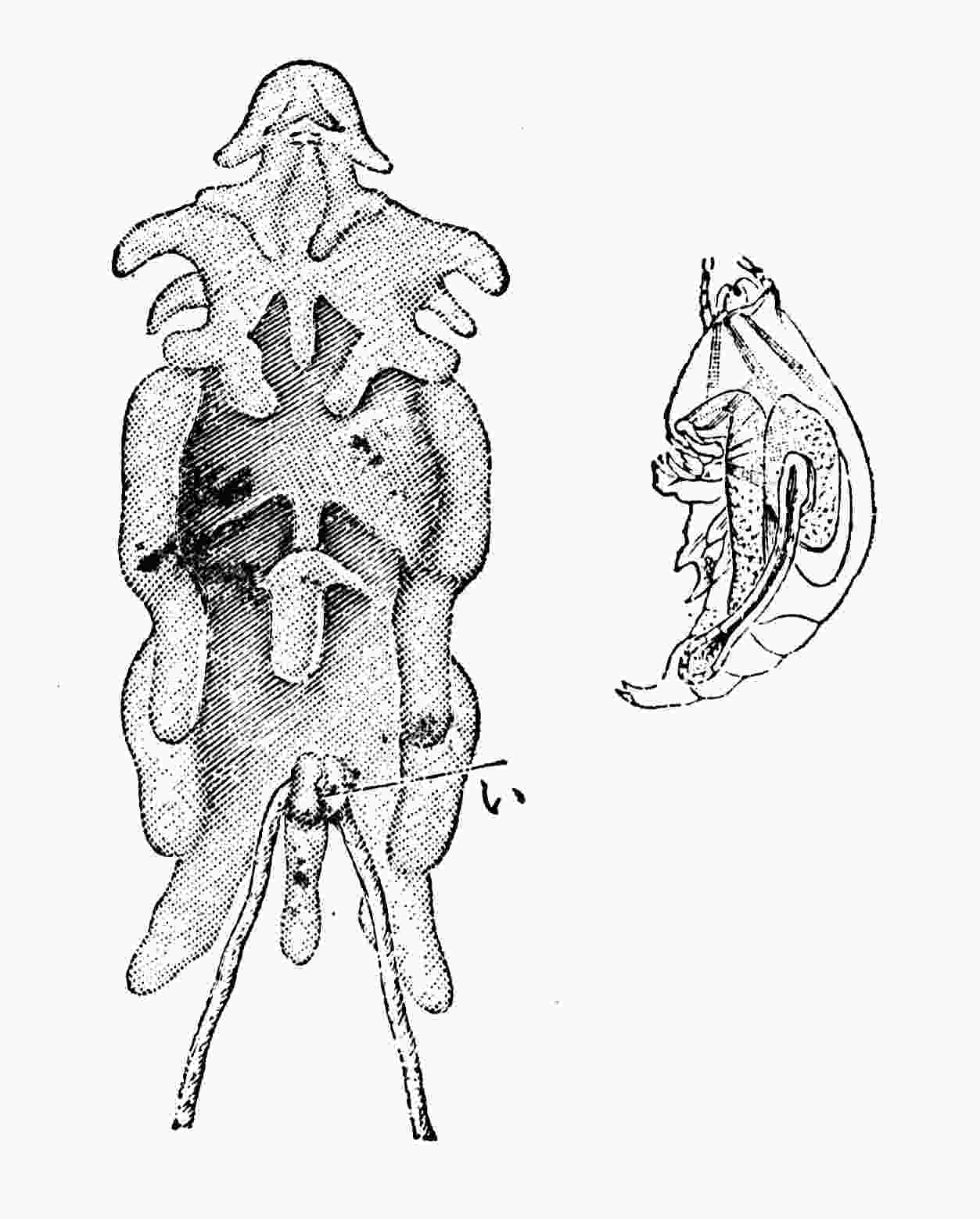
寄生けんみじんこ
(左)雌腹面より (右)雄側面より(い.雄)
天水桶の中などには「けんみじんこ」という小さな虫がたくさんいるが、この虫と同じ
仲間のもので、他動物に
寄生する
種類がいくらもある。上に図をかかげたのはかような
類の中の
一種であるが、
雌は
魚類の
鰓の表面に
寄生し血を
吸うて生きている。運動する
必要はなく、
滋養物はありあまるところに住んでいるゆえ、体の
形状もいちじるしく
変化して、一見したところではほとんど「けんみじんこ」の
類とは思われぬ。体は
肥えて丸くなり、「みじんこ」
類に
固有な体の
環節は全く消えうせ、
触角も足もすべて太く短くなって、あたかも指のごとき形になっている。かような
雌の身体を
腹面から
検すると、その
後端に近いところの
生殖器の開き口のそばに、
必ず
一匹の小さな虫が
吸いついているが、これがこの虫の
雄である。
雄のほうは
雌とは
違い、やや「けんみじんこ」らしい
形状を
備えているが、体の内部はほとんど
睾丸でみたされているというてもよろしいほどで、その役目はただ大きな
雌と
交接して、その
卵細胞に
受精さするだけである。
雌に
比べると、身長がわずかに十五分の一にも足らぬゆえ、
仮に
雌を
普通の大きさの
婦人にたとえれば、
雄はわずかに指の長さほどの小さな男にあたるから、これなどは全動物中でも、
雌雄の
相違のもっともはなはだしいものの一つであろう。
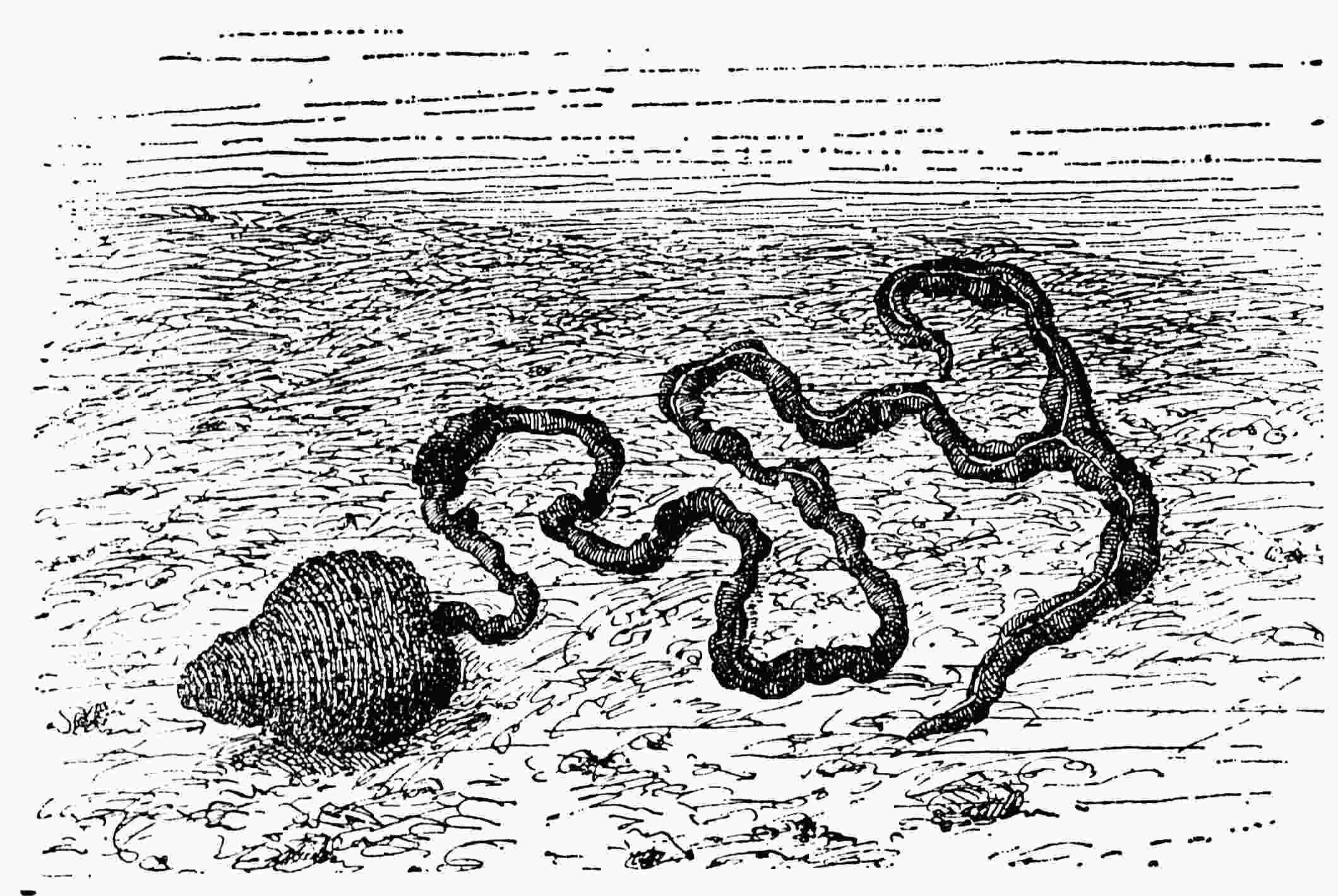 ボネリヤ
以上
ボネリヤ
以上の
例では、
雄は
雌に
比べて
驚くべきほど小さいには
違いないが、それでも
雌の身体の外面に
付着しているゆえ、その同じ
種類の
雄なることがわかりやすい。しかるに
或る動物では、
微細な
雄が真に
寄生虫として
一生涯雌の体内に
隠れている。海岸の
泥砂の中には、「いむし」というて、
鯛などを
釣る
餌として用いられる虫がいるが、これによく
似た
種類で、学名を「ボネリヤ」と
呼ぶ
奇態な虫がある。日本の「いむし」はまるで
甘藷のような形で、口より前に
突出したところがほとんどなく、外国の「いむし」には口より前に
匙のごとき形の
吻と名づける小さな部分があるが、「ボネリヤ」ではこの
吻がすこぶる長く、かつ
先端が二つに分かれてあたかも丁の字のごとくに開いている。すべてこれらの虫は
泥や
砂の中に
隠れていて、水中にただよう
微細な
藻類などを食物とするが、そのさい
吻を用いてこれを集める。しかして
吻の長い
種類では、体だけを
隠し
吻を水中に
延ばし、その表面にある
顕微鏡的の
繊毛を動かして、
餌をしだいに口のほうへ送るのである。さて「ボネリヤ」はいくつ
捕えても
必ず
雌ばかりで
雄は
一匹もないゆえ、昔はこの虫には
実際雄がないものと思うていたが、だんだん
詳しく調べて見て、ついに
雄が見つけられた。しかもその
雄は
如何なるものかというに、
雌とは
比較にならぬほどに小さなもので、かつ形も全くこれと
違い、あたかも「ジストマ」のごとき
扁平な形をして、
雌の
子宮の入口に
寄生している。
雌の身体は長さが
五寸(注:15cm)もあるが、
雄のほうはわずかに
一分の二分の一(注:1.5mm)にも足らぬから、
雄が
雌の体内に
寄生しているありさまはあたかも
五尺(注:1.5m)の人間に五分(注:1.5cm)の虫が
寄生しているのと同じ
割合によりあたらぬ。
雄は体の
構造も
簡単で、
腸も
胃もなく、体内にはほとんど
睾丸があるのみに
過ぎぬ。
以上述べたとおり、
雌雄の
別には
種々の
程度があって、全く
別のないものから、
交接器だけの
相違するもの、ほとんど
別種かと思われるもの、
雄が
雌の体内に
寄生するものまでの間には、実に
無数の
階段がある。しこうして
雌雄の
差の
程度に
相違があれば、したがって
受精の
方法や
雌雄の
互いの
関係もいちいち
異ならざるを
得ぬが、いずれの場合にも
種族の
維持に
差支えを生ぜぬという点だけはみな
相ひとしい。言をかえれば、
雌雄の
差別に
種々の
程度のあるのも、ひっきょう同一の
目的をとげるための
異なった
手段というに
過ぎぬ。「うに」の
雌雄がおのおの勝手に
生殖細胞を
吹き出しているのも、犬や
猫の
牡が
熱心に
牝を追い歩くのも、「ボネリヤ」の
雄が
雌の
腹の内に
生涯寄生しているのも、
結局は
受精が
目的である。いずれの
方法にも
一得一失あるをまぬがれぬが、
得失を
差引き
勘定して、
種族維持の
見込みが十分に立てばいずれの
方法でもよろしいゆえ、
各種の動物はそれぞれの住所
習性に
応じた
方法をとっているのである。人間などは、
直接に
生殖に
関係する体部のほかは男女ほとんど同形であり、かつ身体を
相触れて体内
受精を行なうゆえ、社会の
制度でも
道徳法律でも、ことごとくこれに
準じてできているが、
仮に
受精の
方法、
雌雄の
相違の
程度などの全く
違う世の中を
想像したならば
如何であろうか。
例えば「うに」のごとくに、両親が
相触れぬとしたら
如何。もしくは「
寄生みじんこ」のごとくに、男が女の
付属物のごとくであったら
如何。かかる
想像は
無益な
愚かなことと考えられるかも知らぬが、およそ物はほどほどの
相異なった場合を
比較して見て、
初めて真相のわかることも多いゆえ、あるいはこれによってかえって人間の社会
的生活の
根底を知ることができるやも知れぬ。
卵と
精虫とを
出遇わせる
方法は実にさまざまであって、そのため親なる動物に
種々の
器官の
備わっていることは、前の章に
述べたとおりであるが、ただ
設備がととのうているだけでは何の
効もない。
必ずこれを使用せずには
我慢ができぬという
極めて強い
本能がこれに
伴わねばならぬ。世に
恋愛と名づけるものの
根底はすなわちここに
存する。この
本能を
満足せしめるためには、動物は
如何なる
危険をもおかし、
如何なる
妨害にもうち勝ち、
往々命をも
捨ててかえりみぬが、
各種族の
維持継続は、ただこの
本能の
満足によってのみ行なわれ
得べきことを思えば、これも決して
無理でない。
各個体がこの
本能を
満足せしめるか
否かは、実はその
個体のみに
関する問題ではなく、
種族の生命が
続くか
絶えるかが、それによって決するのであるから、
種族にとっては実に
随一の大問題である。もとより
各種族の内には
個体が数多くあることゆえ、
必ずしも
一個一個がことごとく子をのこさねば
種族が
断絶するというわけではないが、もしも
各個体にこの
本能が強く
発達せず、したがってこの問題に対して
冷淡であったならば、
種族がたちまち
絶えることは
極めて明らかである。
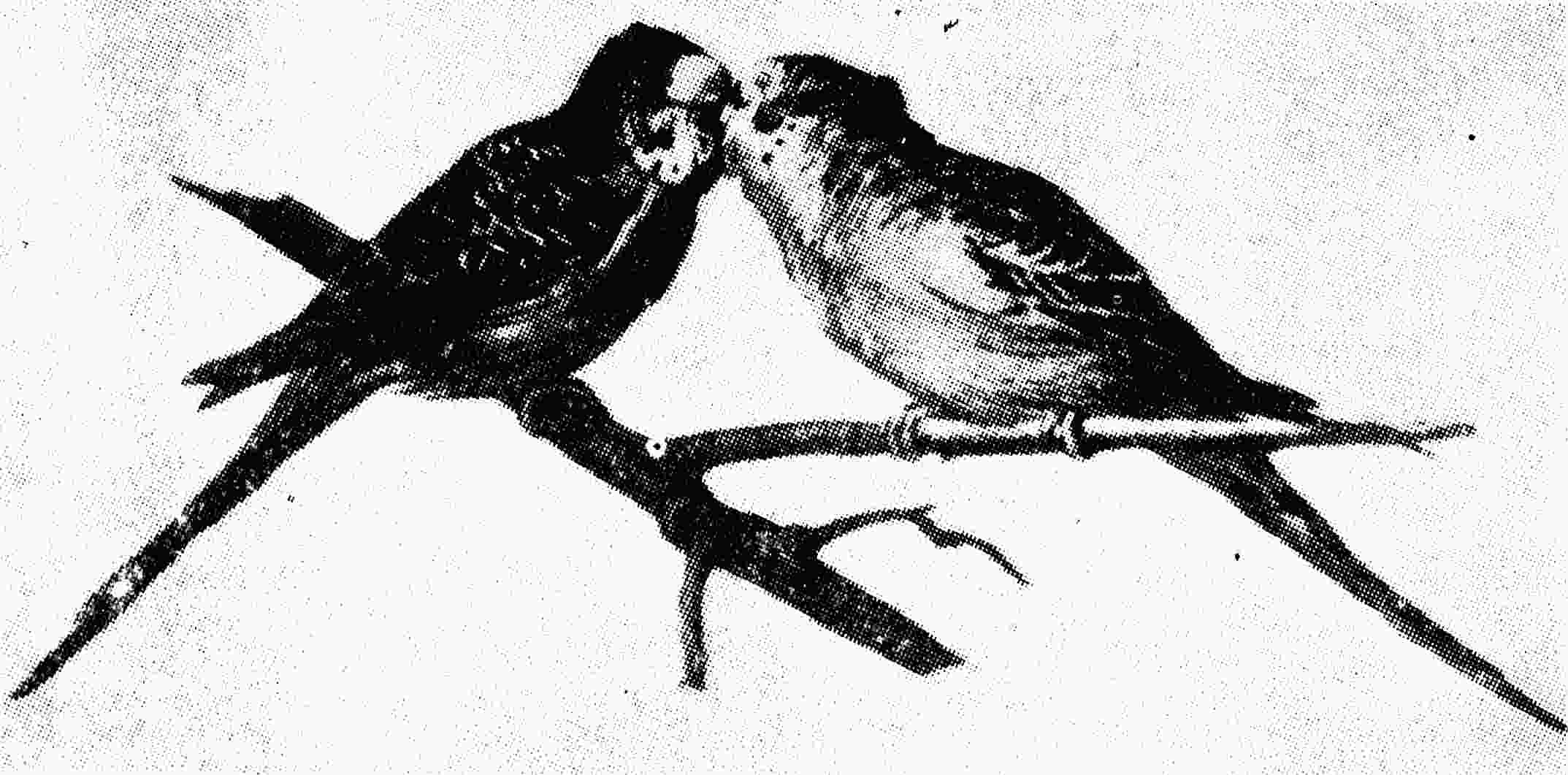 恋愛鳥
雌雄
恋愛鳥
雌雄の間の
恋愛的挙動のとくにめだつ
例は
鳥類に数多くあるが、そのなかでも「いんこ」の
一種で「
恋愛鳥」と名づけるものは
雌雄が
瞬時もはなれず、しじゆう
接吻ばかりしている。
鳩なども
雄と
雌とは
嘴をたがいに
相接して
砥め合うているのをつねに見かける。されば動物界におけるすべての動作の原動力は、一は
個体の
維持を
目的とする
食欲、一は
種族の
維持を
目的とする
色欲であって、追うのも
逃げるのも
闘うのもたわむれるのも
必ずこの
二欲のいずれかが
原因となっている。しこうしてこの
欲を
満足せしめねば
止まぬことは、
各個体の持って生まれた
本能であって、とうてい長くこれをおさえることはできぬ。動物の
挙動を見ると、あたかも
卵と
精虫とにあやつられているごとくであるとは前に一度
述べたが、
雌雄の間に行なわれる
種々の動作を
通覧すると、いよいよその感じが深くなり、
各個体はそれぞれ自分の
意志によって活動しているごとくに見えながら、実は何物かに動かされているのであろうと考えざるを
得ない。すなわち、
卵と
精虫とが
種族からの
依頼を受け、その
維持継続をはかるために
各個体を
操縦しているかのごとくに思われる。しかし
個体を
離れて
別に
種族なるものはないから、
種族の
依頼と見ゆるものは、やはり
各個体の
神経系または
原形質の
構造、
成分等にもとづく
無意識の
働きと見なさねばならぬが、かく
論ずると、
恋愛なるものの
根底は
無意識の
範囲に
属し、その
働きの
意識せられる部分を
恋愛と名づけているのであろう。本章においてこれより
説くところは、
諸種の動物に見る
恋愛のありさまであるが、その中には
無意識のごとくに見えるものもあり、
意識あるごとくに見えるものもあり、その中間にあるものもあって、
判然と分けることはできぬ。しかし
種々の
異なった場合を集めて
比較して見ると、そもそも
恋愛の始まるところから、そのもっともいちじるしくなるところまでの進歩の
道筋がいくぶんか
察せられるであろう。
「うに」、「ひとで」、「なまこ」の
類は
生殖するにあたって
雌雄相触れることなく、おのおの勝手に
生殖細胞を
吹き出すだけであるが、かような動物では
雌雄相近よる
必要がないゆえ、その間にすこしも
恋愛はない。
互いに
相近づこうと
欲するのは、
恋愛の第一歩であるゆえ、近づくことを
欲せぬようでは
恋愛はまるで問題にならぬ。しかも
恋愛がなくても、一部の
卵と
精虫とがどこかで
必ず
相出遇うて
受精するのは何の力によるかというに、これはやはり
一種の
恋愛である。ただし
個体間の
恋愛ではなくて
細胞間の
恋愛であるから、親からいうと
無意識の
恋愛で、親の
意志とは全く
無関係である。すなわち海水中で、
卵細胞と
精虫とが
偶然相近づけば、
精虫は急いで
卵細胞に
游ぎつき、
卵細胞からは
歓迎の
突起をだして直ちに
相合してしまう。すでに親の体を
離れた後のことゆえ、親はその合同を助けることもできねば
止めることもできぬ。
かくのごとき
異性の
生殖細胞間の
恋愛はけっして「うに」や「なまこ」のような
個体間に
恋愛のない
種類にかぎるわけではなく、いかなる動物、植物でもいやしくも
有性生殖を
営む
以上は、その
卵細胞と
精虫との間には
必ず強い
恋愛がある。
受精によって新たな
一個体の生ずるには、
卵細胞と
精虫とが、体と体と合し
核と
核と合して、真に
一個の
細胞となることが
必要であるゆえ、
如何に
卵と
精虫とを
出遇わしめる仕組みが
完全にできていても、
肝心の両
細胞が
相合しなかったならば何の役にも立たぬ。あたかも
如何に他人が
骨を
折って男女を
出遇わせても、
当人らにその心がなければとうてい子ができぬのと同じ
理屈である。それゆえ
如何なる生物でも、
生殖細胞間の
恋愛は
必要であるが、これはいつも
個体の
意志とは
別で、その
当人といえども
如何ともすることはできぬ。
例えば
如何に
道徳堅固の
聖僧でもその
精虫を
卵細胞のそばへ持ちゆけば、
必ず直ちにこれに
突き入るであろう。また
如何に
貞操の
誉れ高い
婦人でも、その
卵細胞の
周囲へ
精虫が集まってくれば、たちまち表面から
突起をだして先着者を
迎えるであろう。これは
当人からいえば
無意識の
範囲に
属することで、
如何なる
念力をもっても止めることはおそらく
不可能であろう。
生殖細胞は
互いに
相近づいた
以上は、
細胞間の
恋愛によって
必ず
受精するが、そこまで
確実に
相近よらしめるためには、
種々の
手段をとらねばならぬ。
個体間の
恋愛は、この
目的のために生じたものである。
恋愛する動物を
有情と見なせば、
恋愛を知らぬものは
当然これを
非情と名づけねばならぬが、水中に
産する動物には
非情の
種類が決して少なくない。「うに」、「ひとで」、「なまこ」
類のほかに
蛤、「あさり」、
蜆のごとき
二枚貝類、「くらげ」の
類、「さんご」の
類、その他海の
底には
生涯固着して動かぬ動物が数多くあるが、これらは
残らず
非情の部に
属する。同じ
貝類の中でも「さざえ」、「たにし」、「ほらがい」などのごとき
巻貝類は、
雌雄相求めて体内
受精を行ない、「たにし」や「にな」は形の
備わった大きな子を
胎生するが、
蛤や
蜆の
類は全く「うに」、「なまこ」などと同じく、
雌と
雄とがおのおの勝手に
生殖細胞を
吹き出すだけゆえ、親と親との間に少しも
恋愛はない。
恋愛には
二匹の
相近づくを
要し、
相近づくには運動が
必要であるゆえ、動かぬ動物はとうてい
恋愛をする
資格がない。「くらげ」
類は動くことは動くが、ただ
傘を
開閉して水を
煽ぎ、その反動によって方角を定めず
漂うにすぎぬゆえ、
目的をうかがうてこれに近づくことはできぬ。また「さんご」や「いそぎんちゃく」の
類では、
雄の
吹き出した
精虫は水に流されて
雌の体に近づき、その口より体内にはいって
卵と合する。「いそぎんちゃく」には
胎生する
種類もあるが、
卵が
受精し発育するのも食物が消化せられるのも同じ場所であるから、かような
類では
胃と
子宮との
区別がないことにあたる。子は
成熟して親と同じ形になると、口から
産み出される。すべて
非情の動物では、親は
単に
生殖細胞を
吹き出すだけで、その後は運を天にまかせておくのであるから、
松や
銀杏などが
花粉を風に
吹き
飛ばさせるのと全く同様である。
虫媒植物の花には美しい色やよい
香のものが多いが、これは
昆虫を
誘うて
花粉を
運搬させるためのものゆえ、やはり広い意味の
恋愛現象の
範囲内に
属する。しかし動物界における色や
香がつねに同
種類の
異性の注意を引くためのものなるに反し、植物の花はただこれによって
甘い
蜜のある場所を
昆虫に
示し、美しい色、よい
香の花にさえゆけば、自分の
食欲を
満足せしめることができるとおぼえこませ、相手の
本能を
利用して、当方の
花粉を知らずしらず運ばせるのであるから、
有情[#「有情」は底本では「友情」]の
恋愛とは全く
趣が
違う。自身の
精虫を他の生物に
託して、先方までとどけしめるものは、動物のほうには
一種もない。
さて
細胞間の
恋は
如何にして起こったものかというに、その真の
原因はいっこうわからぬが、
単細胞の原始動物にも、すでにその
存することは明らかである。
系統を
異にする「ぞうりむし」が、おのおの相手を
求めて
二匹ずつ
接合するのは、すなわち
細胞間の
恋愛の
実現で、夜光虫でも「つりがねむし」でも
接合をする
以上は、
必ずこの
本能を
備えている。しこうして
相接合する
二細胞の間に分業が起こり、一は大きく重く一は小さく軽くなると、重いほうは動かずに待ち、軽いほうが進んで近づくが、この
相違がその
極に
達すると、一方は明らかに
卵細胞一方は明らかに
精虫と名づくべきものとなる。
単細胞動物では
各個体の全身がただ
一個の
細胞より
成るゆえ、
接合する
二匹は全身があるいは
卵あるいは
精虫の形を有せざるを
得ぬが、
普通の動物では身体は
無数の
細胞よりなり、
生殖の役をつとめるのはわずかにその一部なる
生殖細胞のみにかぎるゆえ、
細胞間の
恋愛もただこれらの
細胞のみに
伝わり、他の
細胞は
単に
分裂によって、
無性的に数を
増し
得るのみとなったのであろう。
卵細胞と
精虫との間には
細胞の
恋があって
互いに
相求めることは、前に
述べたとおりであるが、この
両種の
生殖細胞を
相近づかしめるためには、
必ずしも
雌雄の両
個体ともに、相手に対する
恋愛が
備わらねばならぬということはない。
甲乙の
二個体が
双方から
相慕えば、直ちに
相接触し
得ることはむろんであるが、
仮に
甲が全く
冷淡であるとしても、
乙に強い
恋愛があれば
結局二匹は
相接蝕することになる。また
甲が
乙をきらうて
逃げ去ろうとしても、
乙に
甲をして止むを
得ず意に
従わしめるだけの
猛烈な
恋愛があれば、それでも
確かに二者の
接触が生ずる。動物界における
雌雄の間の
関係は実にさまざまであって、
互いに
相慕うものももとより多いが、
雄が
暴力をもって
雌を
屈服せしめ、
強制的に
受精を行なわせるのも決して
珍しくはない。
特に
獣類や
昆虫類にはその
例がいくらでもある。
猿類のごときも
往々この
方法を用いる。
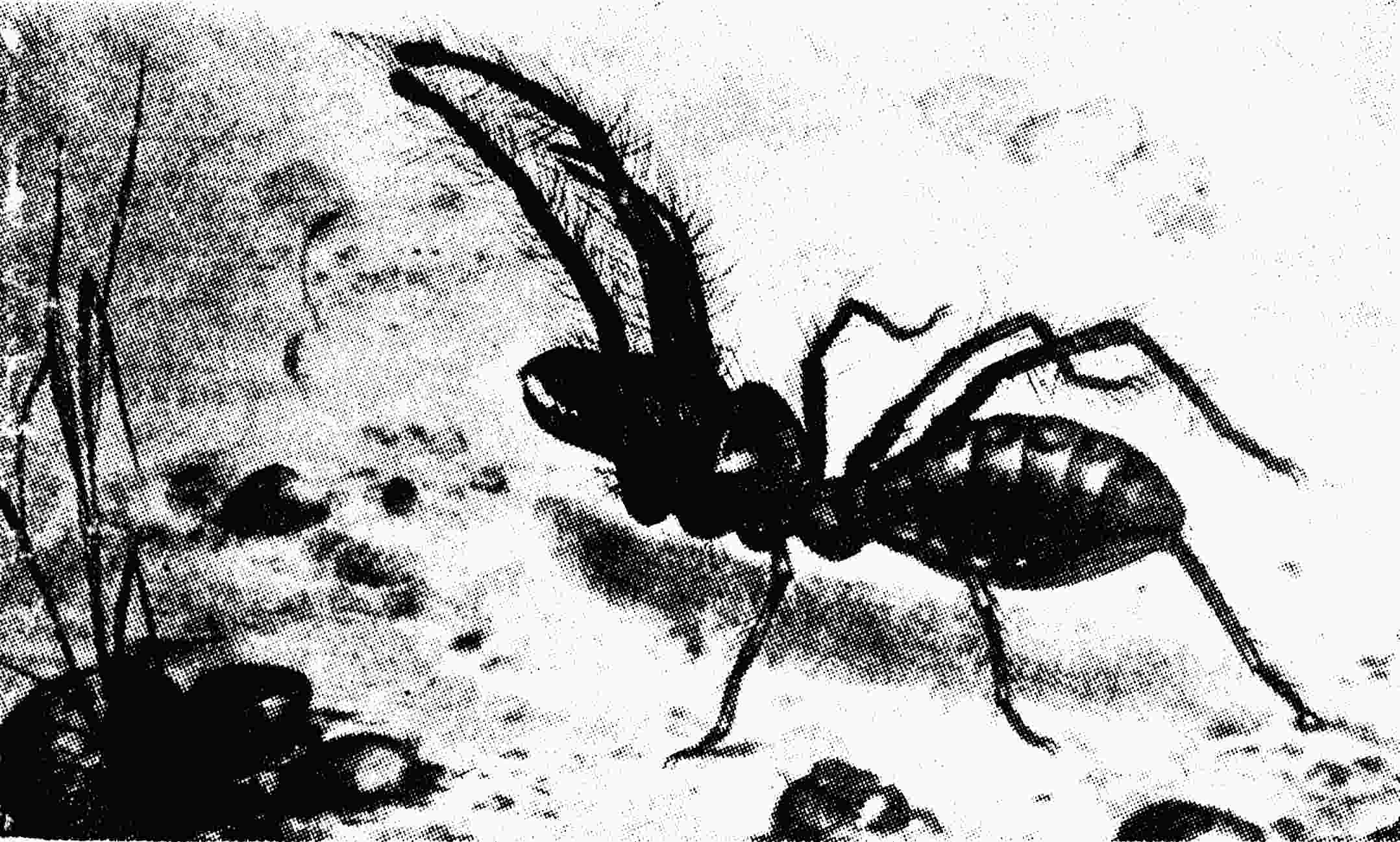 ロシア産のくも類の一種
一例
ロシア産のくも類の一種
一例としてロシアの東部に
産する
一種の「くも」に
似た虫について、
或る人の
詳しく
観察したところを
述べてみるに、この虫では
雄は
不意に
雌を
襲うてその
腹を強くかむと、
雌は直ちに
気絶して半死の
状態となり、全く
抵抗力を
失うが、
雄はかく
無抵抗になった
雌の体をころがして、
腹を上に向けしめ、その一方にある
生殖孔の中へ、自身の
触足を用いて思うがままに何回も
精虫を入れる。かくてやや
時刻が
移ると、
雌は正気に返り体の
位置をもとにもどすが、
雄はこれを見るや急いで
逃げてしまう。
何故というに
雌は
雄よりも体が大きく力も強く、かつすこぶる食をむさぼるものゆえ、
雄といえどもその
付近に
徘徊していては
至極危険なためである。これに
類する
方法で
受精する
種類はなお他にも多くあるが、これらから見ると、
自然は実に
目的のためには
手段を
選ばぬもののように感ぜられ、
結局種族の
維持ができさえすれば、そのために
如何なる
方法で
受精が行なわれようとも、それは
各種の
習性にしたがい、
適宜なもので
差支えがないのであろう。
種々の動物の身体を
検査して見ると、
雄の身体に
雌を
捕えてはなさぬための
装置を見いだすことがすこぶる多いが、これはたいがい
強制的に
雌をして
受精を
承諾せしめるためのものである。「げんごろう虫」の
雄の前足の
吸盤でも、
雄の
蛙の前足にある
皮膚のざらざらした
瘤でも、みなこの
目的に用いられる
器官である。
獣類の
雄も多くは
強制的に
雌を
服従せしめるもので、あるいは追いまわしたり追いつめてこれをかんだり
突いたり
蹴ったり、ずいぶんはなはだしい
残酷な目にあわせ、ついに
雌をして
抵抗を
断念するの止むなきにいたらしめる。これはおそらく
無意味なことではなく、その
種族の
維持継続にとってなにか
有益な点があるのであろう。
詳しいことはわからぬが、
受精のよく行なわれるためにはまず
雌雄の
生殖器も
神経系も、それに
都合のよい
状態にならねばならぬが、
雄が追い
雌が追われなどしている間にこれらの
器官が
受精を行なうに
適する
状態に
達するのではなかろうか。もしさようであるとすれば、他から見て
残酷に見える
所行は実は
受精のための
準備である。
雌雄の
蝶が
出遇うても、決してすぐには
交尾せず、長い間
相たむわれているが、これも
受精を行なうに
適するまでに身体を
準備しているのであろう。動物園で
獅子や
虎が
交尾する前には、
必ず
吼えたりかみ合うたりして、
夫婦で
大喧嘩をするのもこれと同様で、
蝶が平和に
相たわむれるのも
獅子が
残酷にかみ合うのも
目的は同じである。
特に
獣類で
受精が
暴力によって行なわれる場合には、代々もっとも強い
雄の
種が
残るわけとなって、
種族の
発展の上にもいくぶんかよい
結果を生ずるであろう。
なお動物の
種類によっては、真に
暴力を用いるのでなく、ただ形式だけ
暴力を用いる
真似をするものがある。これはむろん
一種のたわむれであるが、
小鳥類などを見ると、
往々雌が
逃げ
雄が追いながら、ここかしこと
飛びまわっている。しかも
逃げる者は決して真に
逃げるつもりではなく、ただ
交尾までに
若干の時間を
愉快についやして、
受精の
準備をするだけである。かような場合には、
雌は
往々一時
雄の見えぬところへ
隠れることがあるが、
雄が直ちに見つければさらに他へ
逃げ、もし
雄が近所ばかりを
捜して
容易に見つけ
得ぬと、
雌はちょっと頭を出し、自分のいるところを
雄に知らせて
再び
隠れて待っている。すなわち
子供らのする「
隠れん
坊」の
遊戯と全く同じようなことをしてたわむれているのであるが、形式だけは
雄は追い
雌は
逃げ、ついに追いつめられて相手の意に
従うような
体裁になっている。これはただ
一例にすぎぬが、
鳥類や
獣類には
雌のならんでいる前で、
雄が
戦争の
真似をして見せるものの少なくないことなどを考えると、真に
雄が
暴力を用いるものから、さまざまの平和
的の
手段によって
雌をして
喜んで
雄の
要求に
応ずるにいたらしめるものまでの間には
無数の
階段があり、しかもその
目的はいずれの場合にも同一であって、ただ
種族の
維持のために
受精を
完全に行なわしめるにあることが知られる。
雌雄の動物が
互いに
相近づくために、
自己を
示して相手の注意を引くには、
感覚の力に
訴えるのほかに
途はないが、そのさい
如何なる
感覚が主として用いられるかは、もとより動物の
種類によって
違う。
眼のよく
発達した
種類ならば、色や
模様により、耳のよく
発達した
種類ならば、音声により、鼻のよく
発達した
種類ならば、
香によるのがつねで、
雄が美しい色を
示せば、
雌はこれを見て
慕い来たり、
雌がよい
香を発すれば、
雄はこれに引かれて集まる。
鳥類は
眼と耳とがよく
発達して、なかでも
視力は動物中の一番に
位するが、鼻の
感覚はあまり
鋭くない。それゆえ美しい色とよい声とで相手を
誘うものはあるが、
香を発するものはほとんどない。これに反して、
獣類は鼻が
非常によく
発達して、ずいぶん遠くからでも
香を
嗅ぎつける。犬が
探偵に用いられ、
鹿が風上の
猟師を知るのはこのためである。
普通の
獣類の鼻の切り口を見ると、
嗅ぐ
神経の広がっている
粘膜はあたかも
唐草のごとくに
複雑なひだをなして、その空気に
触れる
面積は実に
驚くべく広いが、これによってもその
嗅ぐ力の
非凡なことが
推察せられる。されば
獣類には
香を発して
異性を引きよせるもののすこぶる多いのも
不思議でない。人間ももし鼻の内面の
粘膜が犬などのごとくに
複雑なひだをなして、
嗅感が犬のごとくに
鋭かったならば、
必ず絵画、
彫刻、
詩歌、
音曲よりもさらにいっそう
高尚な
香の
美術ができたに
相違ないが、人間の
嗅感は
極めて
鈍いゆえ、
美術といえばほとんど目と耳とに
訴えるものにかぎり、ついに鼻で味わう
美術が
発達するにはいたらなかった。
昆虫類などには、音や
香によって
雌雄相近づく
種類がすこぶる多くあるが、はるかに下等の動物には
神経系の
構造も
簡単で、
感覚器の
発達も
不完全であるゆえ、
両性の
相誘うために
特殊の
手段はあまり行なわれぬようである。
まず色によって相手を
誘うものの
例をあげて見るに、
魚類の中には
産卵期が近づくと
特に体色が
美麗になって、いちじるしく
艶の
増すものがある。魚学者はこれを「
婚礼衣装」と名づける。
雌がこのために
誘われるか
否かはいささか
疑問であるが、かように美しくなった
雄は
必ず
雌を追いまわし、自身の体を
雌の体にすりつけなどして、ついに
雌をして
好んで
卵を
産むにいたらしめるから、やはり
一種の
誘いと見なしてよろしかろう。
淡水に
産する「たなご」、「おいかわ」のごとき
普通の
魚類もこの
例である。
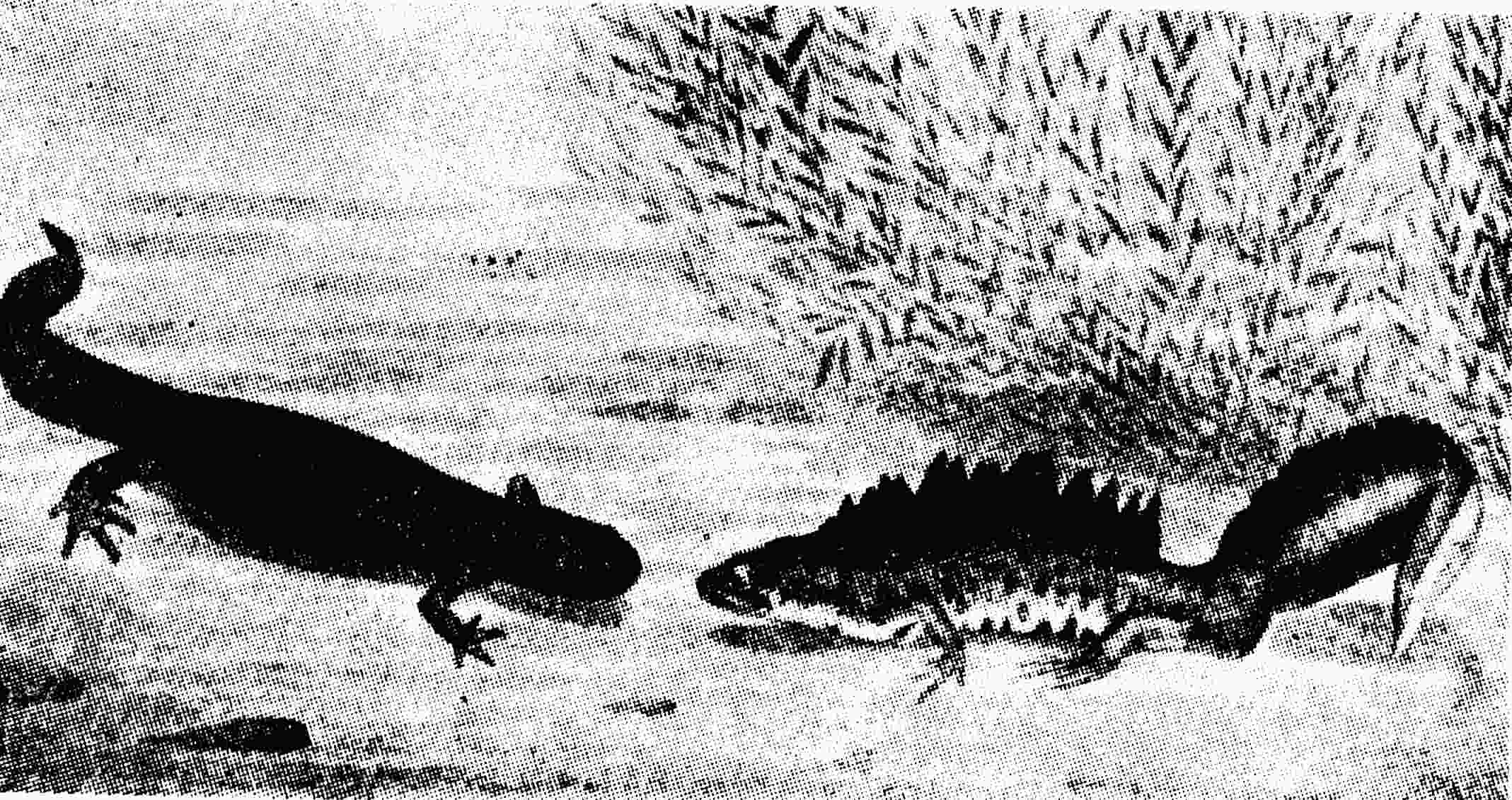 さんしょううお (左)雌 (右)雄
さんしょううお (左)雌 (右)雄
また「さんしょううお」の
類にも
産卵期が近づくと、
雄の
背にそうて
鰭のごときひだが生じ、
尾の
幅も広くなって、体色もいちじるしく美しくなるものがあるが、これも色によって相手を
誘う
一例である。かような
例はなおいくらもあるが、動物中でもっとも美しい色をもって
異性の注意を
求めるものは何かと問えば、これはいうまでもなく
蝶と鳥とであろう。しかし
感覚の力の進んだ動物では、
雌雄相誘うにあたっても
単に
一種の
感覚のみに
頼ることはまれで、多くは
種々の
感覚に合わせ
訴え、美しい色を
示すと同時に、よい声を聞かせおもしろい
踊りを見せなどするもので、
鳥類のごときもその動作のすこぶるこみいった場合もあるゆえ、これはさらに次の
節に
述べることとしてここには
略する。
香によって
雌雄相誘う
例は
獣類にはすこぶる多い。
牡犬が
如何に
牝犬の
香に引きよせられて
夢中になるかは、つねに人の知るとおりであるが、たいがいの
獣は犬と同じく、
牝の
香に
誘われる。「いたち」の
類を「わな」で
捕えるにあたって、
牝の
香をつけておくと、
幾匹もつづいてかかる。また
雄のほうが強い
香を発して
牝に
情を起こさせるもので、もっとも有名なのは「
麝香鹿」であるが、そのにおう
物質は
香料として人間にも用いられる。「
海狸」もこれに
似た
香を発するので知られているが、なおそのほかに「
麝香猫」、「
麝香鼠」などみな
香から名前がつけられたのである。
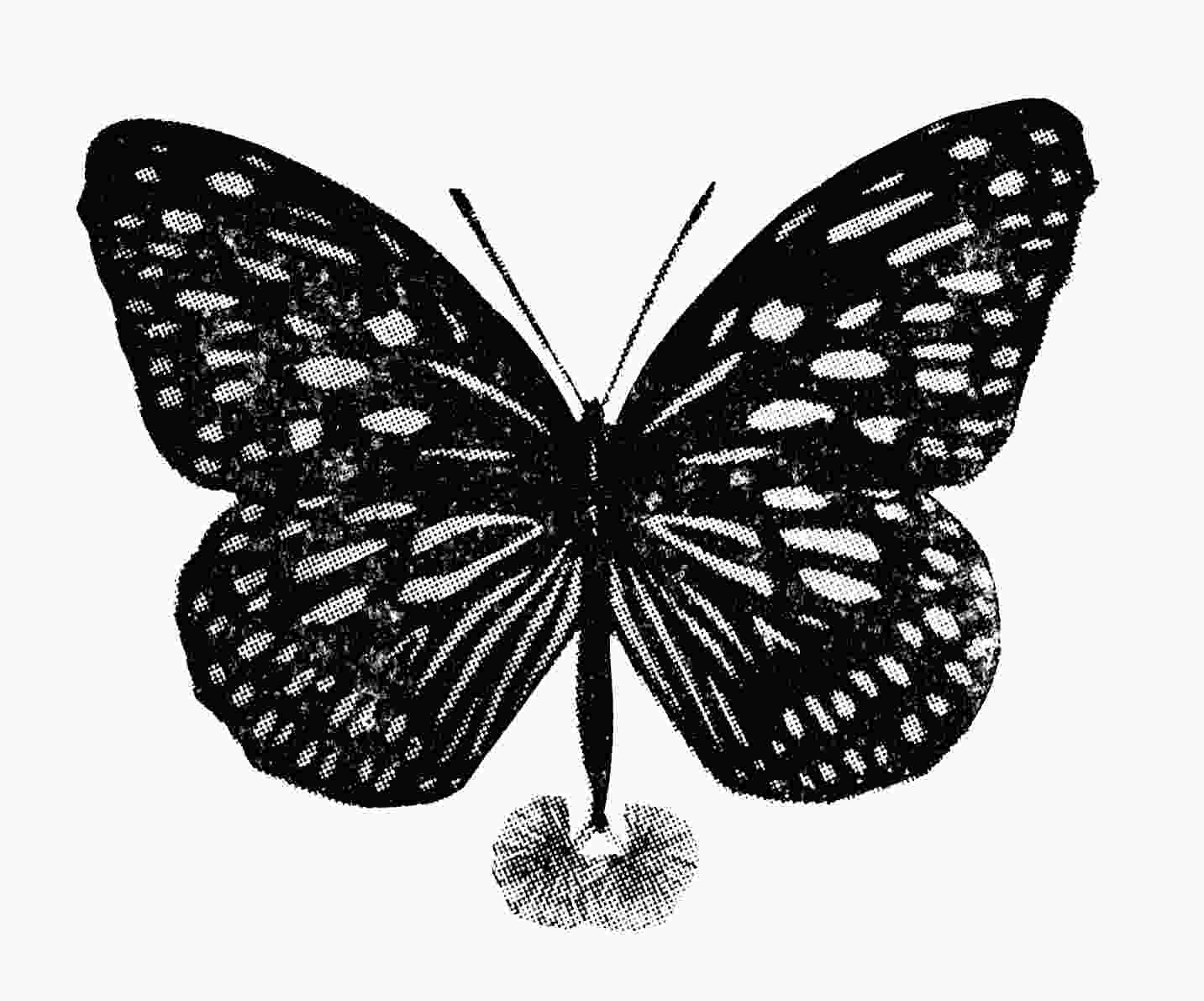 蝶の香毛
昆虫類
蝶の香毛
昆虫類で
香をもって
異性を
誘うものは
蝶、
蛾の
類に多い。
蝶は昼間
飛びまわるゆえ、花のあたりで
雌と
雄とが
出遇う
機会が多いが、
蛾は夜暗い時に
飛ぶゆえ、
香によって
互いにその
所在を知ることが
必要である。
蚕なども
雌の
生殖門のところに小さな
香を出す
腺があり、
雄はこの
香を
慕うて集まってくる。
或る人が
試しにこの部だけを切りはなしておいたところが、
側へよってきた
雄は、
雌の体のほうにはすこしもかまわず、切りはなされたこの体部と
交尾しようと
試みた。
昆虫学者は
蛾のこの
性を
利用し、
雌を
囮として、
往々珍しい
種類の
雄を一夜に
数尾も
捕えることがある。ただ
探して歩いては
滅多に見つからぬ
雄が、室内に
飼うてある
雌の
周囲に
百匹以上も集まってくることがあるが、ずいぶん遠方からかぎつけてくるものにちがいない。
甲虫類でも、「こがね虫」などは
触角に
嗅感器がよく
発達しているゆえ、
香によって
雌の
居所を知る力が
極めて
鋭い。かかる
香はよほど長く
残るものと見えて、かつて一年も前に
雌の
蛾を入れたことのある空箱へ、
雄がよってくることさえ
往々ある。
色でも
香でもけっして
単に
異性と
居所を知らせ合うためばかりではない。前の
例によっても知れるとおり、だいたいの場合にはこれによりて相手の
本能を
呼び起こし、その
満足を
欲せしめることができる。
生殖細胞を
出遇わせたいという
本能は、
如何なる動物にも
備わってあるが、この
本能はいつでも
働いているわけではなく、
生殖細胞の
成熟するころだけいちじるしく
現われる。しこうしてそのさい
特殊の
感覚器を通じて
刺激をあたえると、
本能が急に
猛烈に
働いて、これを
満足せずにはいられぬという
程度までにあがる。
獣類や
蛾類などの発する
香は、主としてこの意味のものである。人間でも
香と
性欲の
興奮との間には
密接な
関係があるが、人間は
獣類でありながら
特に鼻の
粘膜の
面積が
狭く、したがって
嗅感がすこぶる
鈍いゆえ、とうてい他の動物における
嗅覚の
働きを正当に
察し知ることはできぬ。
動物の中でたくみに歌を歌うものは
鳥類と
虫類とであるが、その他にも多少歌うものはいくらもある。
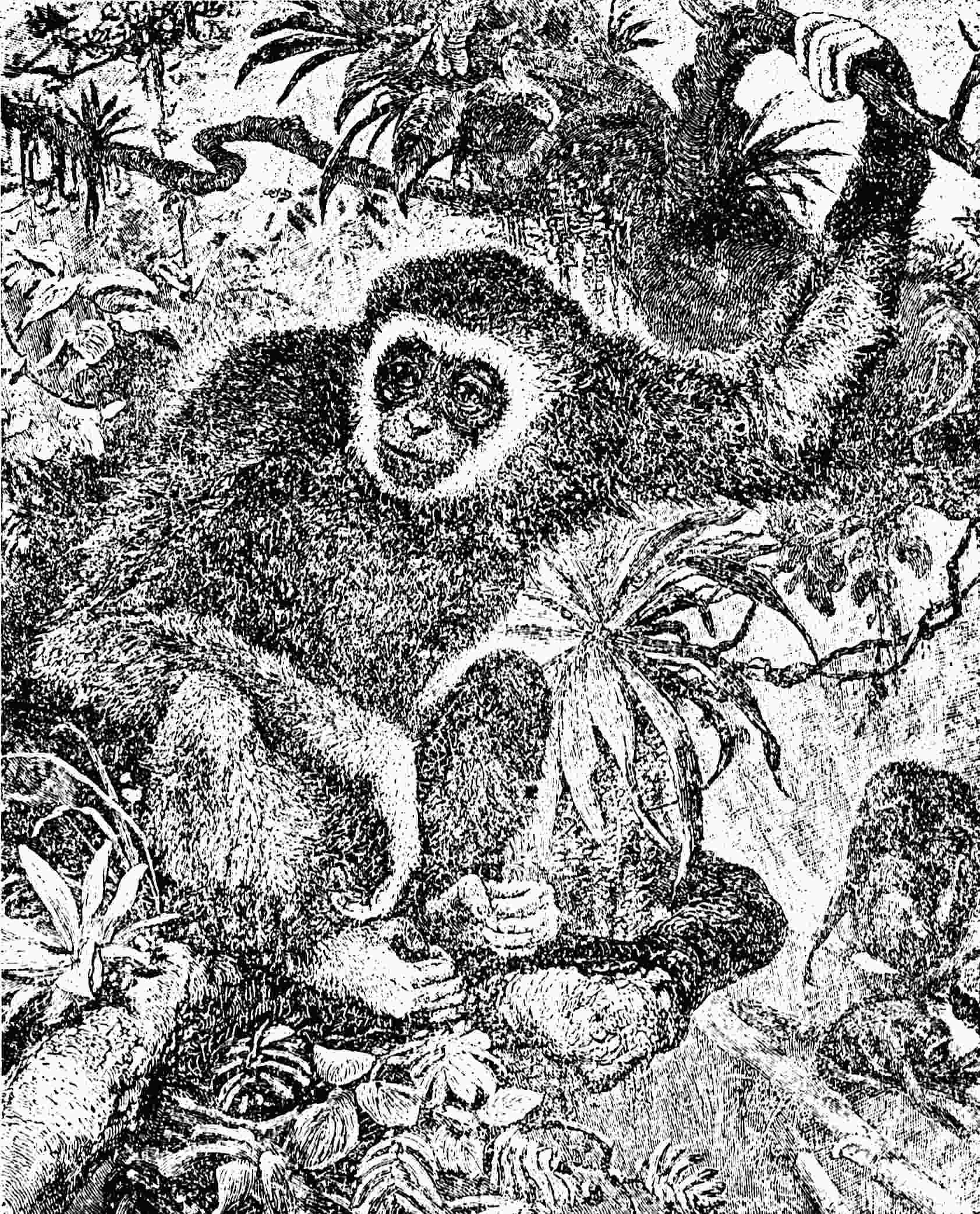 手長猿
獣類
手長猿
獣類では
手長猿などが調子を
十一段にも上下してあたかも音階を練習するごとくに歌う。
蛙の
類がやかましく鳴くことは人の知るとおりであるが、
熱帯地方では
樹の
枝で「とかげ」の
類がなかなかよく歌う。かように歌うものはずいぶんたくさんあるが、それがいずれも
雄だけであることを考えると、その
生殖の
働きと何らかの
関係を有するものなることが、はじめから
察せられる。
昆虫の中で一番大きな声で鳴くのは
'蝉であるが、
雄の鳴いているところをながめていると、どこからか
雌が
飛んできてそのそばに止まり、しばらく上下に
匍うたりして
雄の来たり
接するのを待っているごとくである。「すずむし」、「まつむし」なども
雄がしきりに鳴きつづけていると、そのうちに
必ず
雌が
近寄ってくる。
昆虫の中には
'蝉のごとくに
特に発声だけの
器官をそなえたもの、「すずむし」、「まつむし」などのごとくに
翅をすり合わせて美音を発するもののほかに、
顎で物を打って
響きを生ずるものがまれにある。
静かな古
座敷の
障子に
塵のたまっているようなところには、
往々かような
類の小虫がいるが、
雄が
響きを生じはじめると
雌も
響きを生じてこれに答え、
次第次第に
相近づく。ただし音声も
香などと同じく、
単に相手に自分の
居所を知らしめるためではなく、主として相手の
本能を
呼び起こし、先方より進んでその
満足を
求めしむるにいたるためである。
鳥類でも
獣類でも
交尾期には
鳴声をたくみにまねすると、
容易に
捕えることのできるものが多いのも、全くこれに
原因する。
鹿などもそのころになると、笛のごとき
優しい鳴声を発するが、これに
擬した笛を
吹くと、
雌雄ともに
熱心に耳を
傾け急に
本能の力が
猛烈に
働き出すように見える。
鳥類の
雄が
雌の前で
奇態な
挙動をして見せることは、
普通に人の知っている
例がいくつもある。七面鳥の
雄なども
常に全身の羽毛を立てて体を大きく見せ、
雌の面前を
如何にも強そうにいかめしく歩きながらときどき
一種の
響きを発するが、これはまったく
雌を感動せしめることを
目的とするらしい。
孔雀の
雄がときどきその美しい
尾を開いて
雌に見せびらかすのもこれと同じことである。
 風鳥
風鳥
南洋に
産する「
風鳥」の
類は
雄は羽毛の
極めて美しいものであるが、
産卵期には
雄は
雌の前でわざわざ
翼をひろげ美しい羽毛を左右に開いて見せる。動物園に
飼うてある
駝鳥の
雄もときどき
雌の前に
膝を
折り
頸を後に曲げ、頭を左右に
振って
奇態な
姿勢をとる。
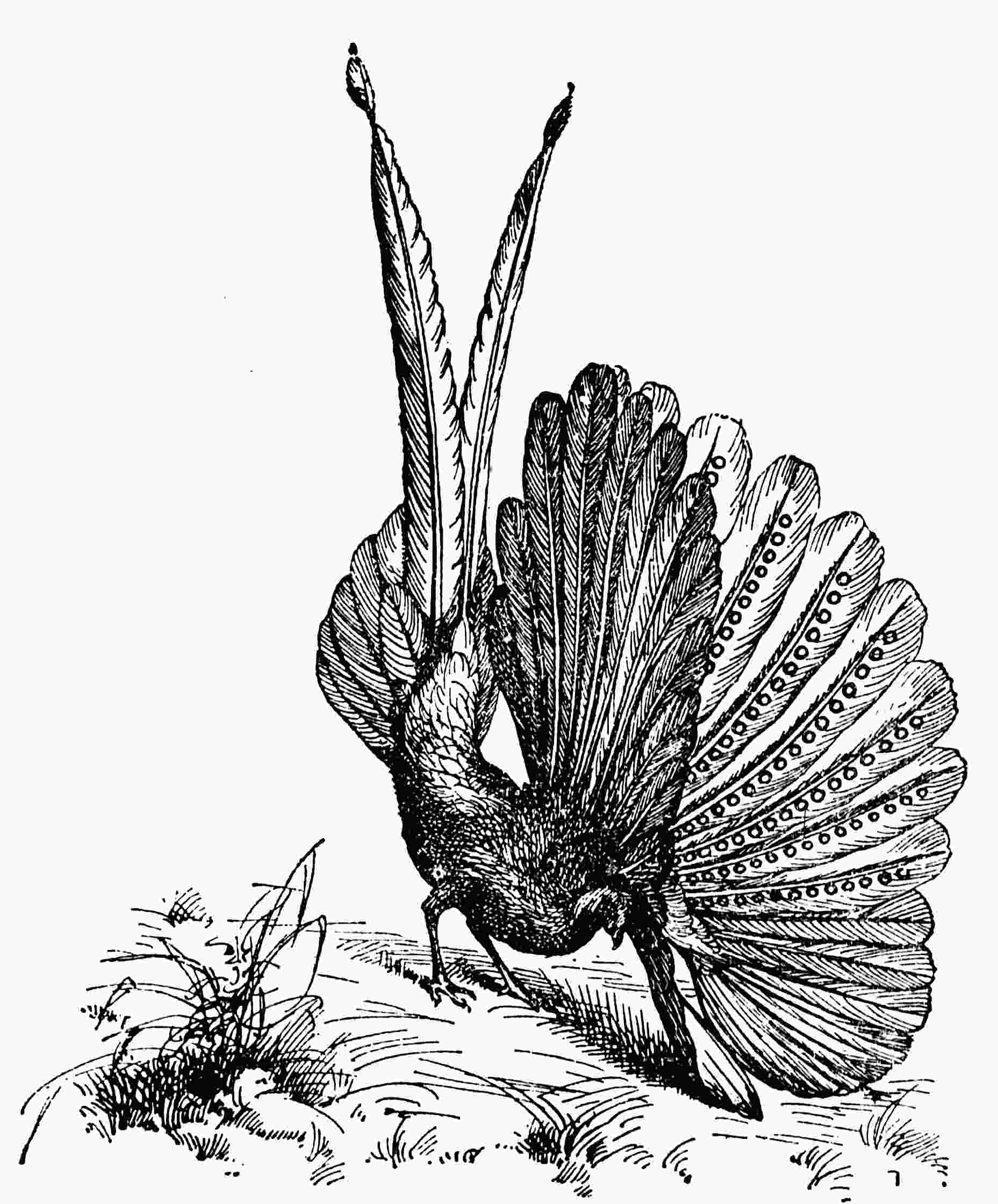 アルグス雉子
アルグス雉子
東インドの島に
産する「アルグス」という大きな
雉子は、ときどき
両翼を半円形に開きあたかも
孔雀が
尾を
拡げた時のごとき形をして
雌に
示すが、その
目的もむろん同じであろう。「アルグス」という名前は昔の西洋の神話からとったもので、がんらい百の
眼を有し、同時に二つずつより
眠らぬという
極めて
寝ずの番に
適した
怪物の名前である。女神「ジュノー」が、その
夫「ジュピター」の
挙動を
監視させるためにつけておいたところが、
睡薬のために百の
眼がみな
眠って
職責を全うすることができなかったので、「ジュノー」は
怒ってその
眼を
残らずけずりとり、これを
孔雀の
尾にうつしたと言い
伝えられている。それゆえ、「アルグス
雉子」の
翼の羽には
眼玉を
抜いた
跡が白茶色にたくさん
残っている。
孔雀の
尾の緑色に光り
輝くのにくらべて、かえって
高尚で
趣が多い。

小屋鳥の一種
この類はオーストラリア地方に産する。大の枝を組み合わせてやや広き遊び小屋を造り,美しき貝殻,花,玉虫,ガラスの破片などにてここれを飾り立て,そのなかにて雌雄とも踊り楽しむ。巣は別にあり。
以上のごとき
特殊の
挙動をするものは
鳥類にははなはだ多くあるが、そのほかになお面白い
舞踊をする
種類がある。そのもっとも
著名なのは、オーストラリアに
産する「小屋鳥」と名づける
類で、この鳥は
普通の
巣のほかに
踊りをするための遊び場所を定め、または遊び小屋をこしらえる。
 小屋鳥の踊り場
踊
小屋鳥の踊り場
踊り場所を定めて
踊る
種類では、まず
樹木の
蔭になる
平坦な地面を
選び、よく
掃除して
清潔にし、
裏面の銀色に光る大きな木の葉などを集めてきて、
裏面を上に向けて
適宜にこれをならべ
飾り、場所の
周囲には白くなった
蝸牛の
殻や
骨などを
散らしておく。また小屋の
造りようは
種類によって少しずつちがうが、まず
樹の
枝を多く集め、これを
密に組み合わせて
床を
造り、その
両側にはやや細長い
枝をならべ立て、
枝の上部を
互いに組み
寄せて屋根とする。面白いことには、この鳥はさまざまのものを用いて小屋をできるだけ
飾りたてる。
例えば、
鸚哥の
尾羽の赤いのや青いのを
枝の間にはさみ、美しい
貝殻やガラスの
破片、光った石などを入口の前にならべたりするが、
往々土人の
住家からさらってくることもある。土人は鳥のこの
習性を知っているゆえ、なにか美しい色の物が
紛失すると、また小屋鳥が
盗んでいったのではないかと、小屋のところへ
探しにゆくが、たいがいはそこで見つかるという。また美しい色の花を用いて小屋を
飾るが、これは毎日
萎れると新しいのと取り
換え、古い花は小屋のうしろへ
捨てる。鳥の大きさは多くは
鴉より小さく、小屋は大きなのも小さなのもあるが、まず
二三尺(注:60~90cm)くらいのが多い。さてこの小屋は何の役に立つかというに、まったく
娯楽のためで、
雌雄は小屋にはいったり出たりして
舞い
踊り、たがいに追いまわしたりして遊ぶうちに
結局、
雌は
喜んで
雄の意にしたがうようになるのである。
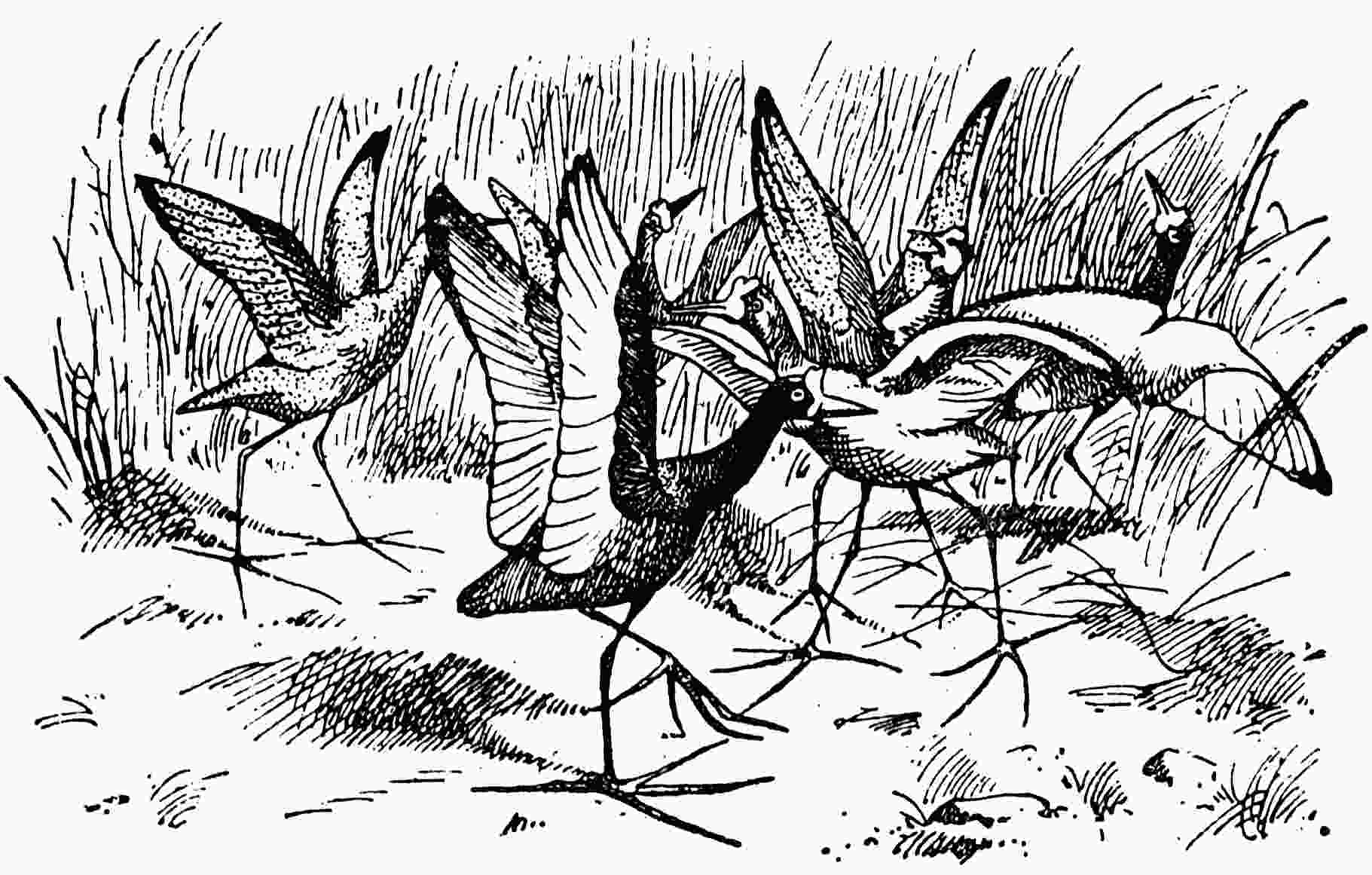 鳥の踊り
獣類
鳥の踊り
獣類の中にも、
雄が
踊って
雌に見せるものがある。「かもしか」
類はその
例であって、
雄は
雌の集まっている前で高く
躍りあがったり
跳ねまわったりする。
鬣のある
種類では、その
際毛が
舞い立って見事になる。また
雄が
雌の前でたわむれに
喧嘩のまねをして見せる
種類がいくらもあるが、
雌はこれを見ている間に
本能が
呼び起こされ、
踊りのすむころにはみずから進んでいずれかの
雄に
従うてゆく。いったい
獣類には
交尾期になると、
牝を
奪い合うために、
牡が
真剣に勝負し、ついに一方が死ぬほどの場合が多くあるが、かような
際には、
牝はそばから
熱心にこれを見物している。こうしてそのうちにだんだん
情が起こってきて、時とすると
偶然その場所へ来合わせた他の
牡のところへより
添うて行くことさえある。これらの事から考えて見ると、鳥や
獣などのごとき
神経系の
発達した高等の動物では、
争闘と
色情との間には
密接な
関係があって、
戦争に
擬した
踊をやって見せても
情を起こさせることのできる場合があり、さらに転じては相手なしにひとりで
戦いの
身振りを
演じて見せても、同じ
目的を
達し
得るにいたったのではなかろうか。鳥や
獣の
踊りは
如何にして起こったものか、その
原因はけっして一とおりではないかも知れぬが、少なくもその一部分は
戦いの
真似にはじまったことはよほど真らしい。人間でも
野蛮人の
踊りには
戦いの
真似が多く、しかもこれを女の前でして見せるのは、すこぶる
獣類などの
踊りによく
似ている。また
精神病者の中には、相手を
残酷な目に
遇わすか、自分が
残酷な目に
遇うかして、
初めて
情の
満足を
得るものがあるが、これなども多少
獣類の
或るものに
似たところがある。
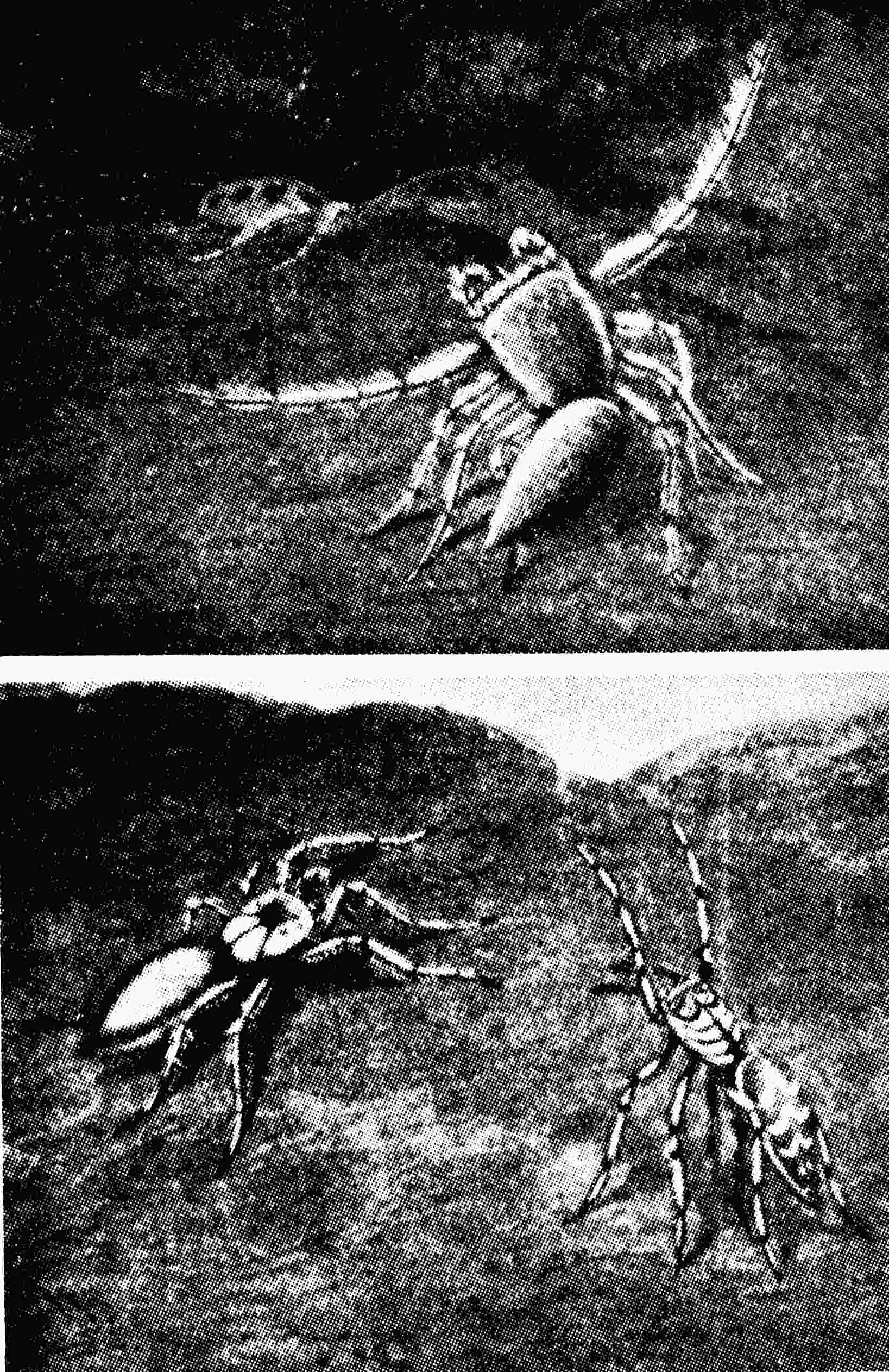 くもの踊り
くもの踊り
小さな虫の中では、「くも」
類の
雄が
雌の前で
種々の
奇妙な
踊りをやって見せる。
尻を上げたり体を
振ったり左右へ
躍ったりして、長い間
雌の注意をうながすが、その
挙動は左にかかげた図でもわかるとおり、実になんともいえぬ
滑稽なものである。がんらい「くも」
類は肉食するもので、つねには
雌雄といえども
相離れて生活し、
雌は
滋養分を
含んだ
卵を多く
産まねばならぬゆえ、ずいぶん
貪食の
癖があり、動くものには何にでも
飛びかかるゆえ、
雄もこれに近づくことはすこぶる
危険である。
雄が
奇妙な
踊りをするのは、これによって、つねに
食欲のために
隠されている
色欲をよび起こし、
雄の近づくのを
許すまでに心をやわらげるためであろう。
動物の中には、どの
雄とどの
雌との間にでも定まりなく
交接の行なわれるものもあれば、
生殖期間だけ
一匹の
雄と
一匹の
雌とが
共同生活をするものもあり、また
互いに相手を定めて
生涯一夫一婦で
暮らすものもある。これにはみなそれぞれ理由のあることで、いずれの場合でも
必ずその
種族の
維持に
差支えのないだけのことが行なわれている。すなわち
甲の
種類には
夫婦の定めがあり、
乙の
種類にはその定めがないのも、ただ同じ
目的のために
異なった
手段が用いられているというにすぎぬ。
偕老同穴という
海綿の内部には、
必ず
雌雄一対の「えび」がいて、この「えび」は死ぬまで
相別れることがないとは、すでに前に
述べたところであるが、これに
類する他の
例をあげて見るに、わが国に近ごろ有名な地方病を起こす
寄生虫がある。もと
岡山、広島両県の
境に近い
片山村というところでもっとも
盛んであったために、
片山病という名がついたが、その病原は、「ジストマ」に
類する
一種の
寄生虫で、つねに
血管内の
血液の中に生活する。他の「ジストマ」
類と
違うて、この虫は
雌雄異体であり、
雄はいくぶんか
扁たいが
雌はまるで糸のように細長い。こうして
雄は
腹面を内にして体を
管状に
巻き、その中につねに
雌を
抱いているありさまは、あたかも
有平を
心にした
巻き
煎餅のごとくである。
雌雄ともに
腹面の
前端に口があり、その後に
吸盤があるが、
雄と
雌とは
腹と
腹とを向け合わせ、口と口とで
互いに
吸いつき、
雄は
雌を
抱きかかえたままけっして
離れぬようにして、死ぬまで
血液の中に
漂うている。
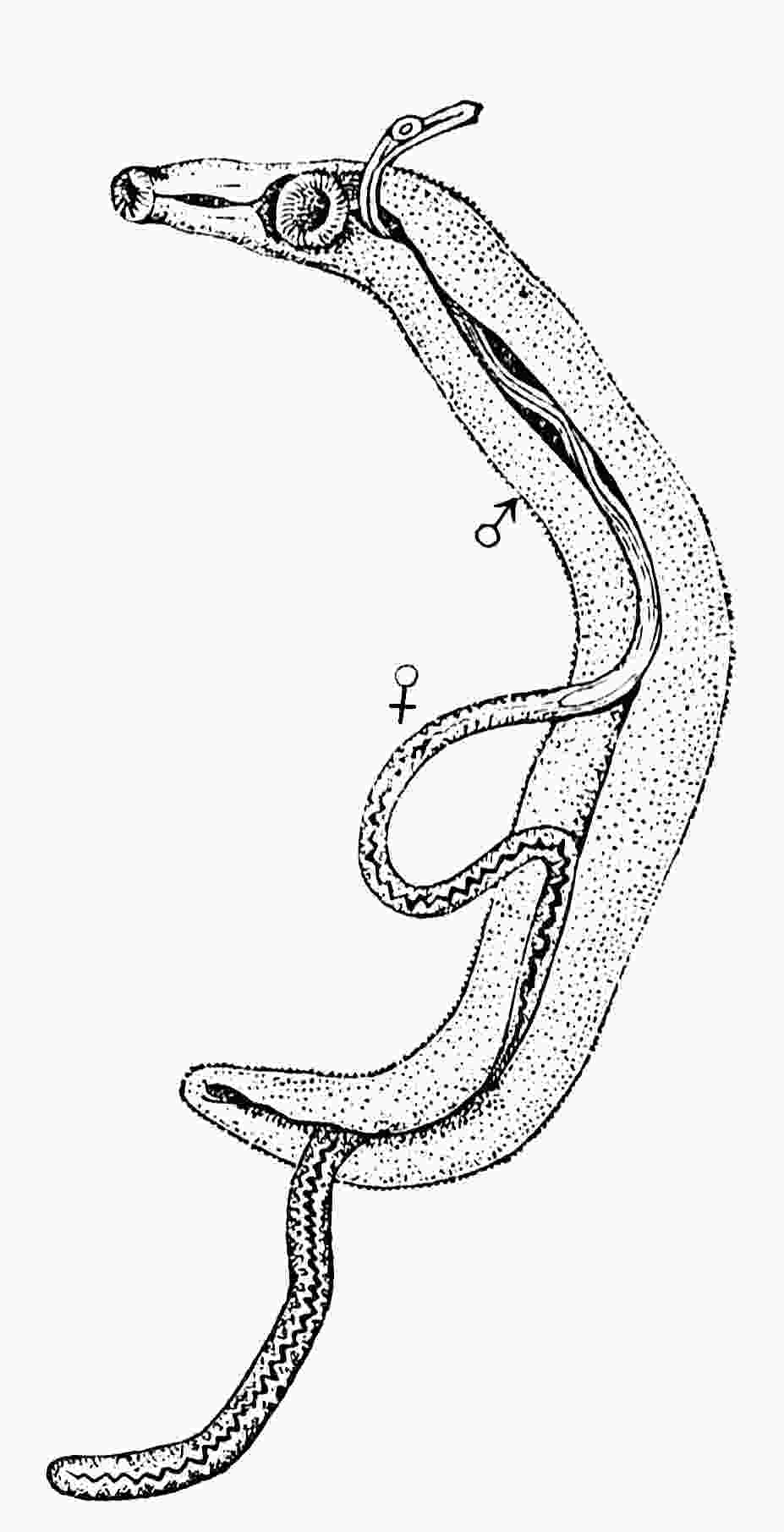 片山病原虫
偕老同穴
片山病原虫
偕老同穴の「えび」は同じ部屋の中に一生
同棲して、けっして遠くへ
離れぬというだけであるが、
片山病の
寄生虫は
雄が日夜
雌を
抱いたままで
一刻も
離さぬから、このほうが
親密の度がはるかに深い。
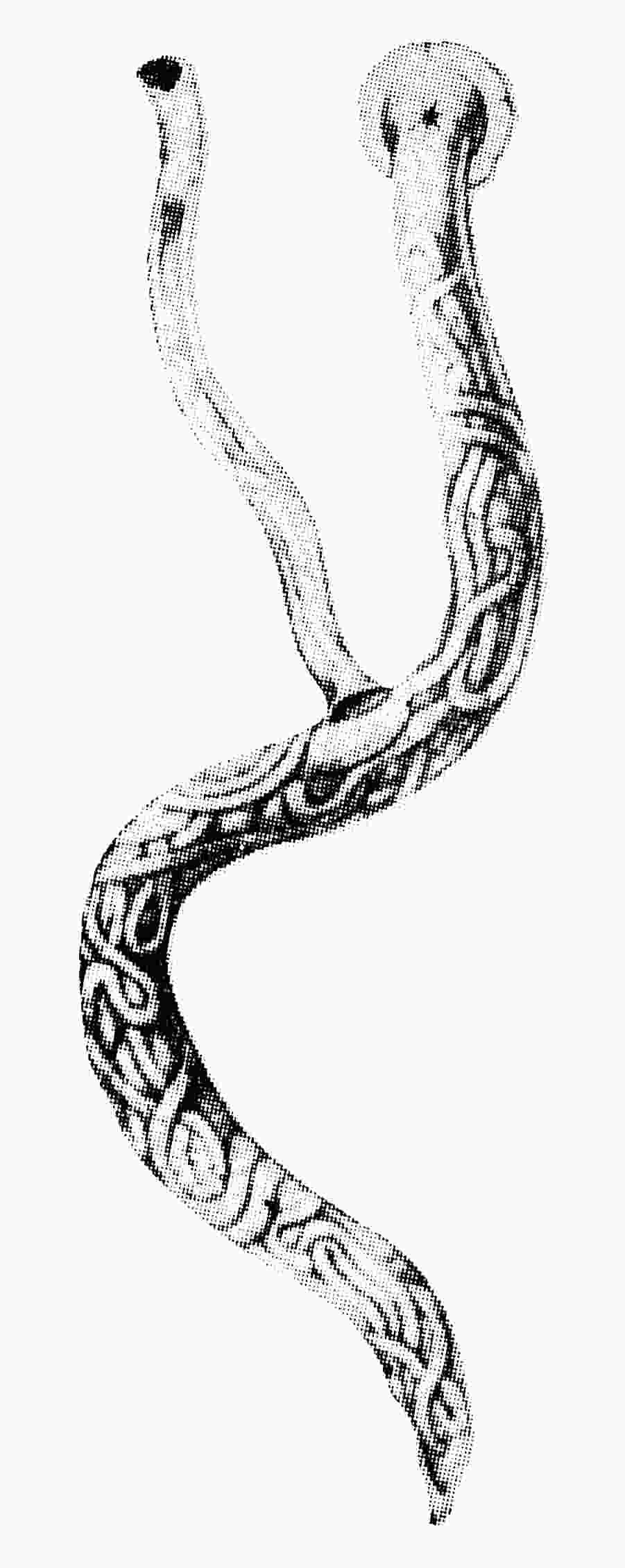 鶏の寄生虫
鶏の寄生虫
また
鶏類の
気管に
寄生して
一種の病気を起こす
蛔虫に
似た
寄生虫があるが、この虫は
雌雄交接したままで
一生涯離れることがない。
雌の
生殖器の開く
孔は
腹面のなかほどにあり、
雄の
生殖器は体の
後端に開いているゆえ、
二匹交接するとあたかも丁の字のごとくになる。しかも
交接したままで
離れることがないゆえ
雌雄の体は
相接蝕するところでゆ着して、しいてこれを
離さんとすればその部が
破れる。この虫は
雌の
産卵する
孔が
雄のためにふさがれているゆえ、
卵を
産むことができず、
卵は
雌の体内で発育し、後に親の体を
破って自分で生まれ出るのである。
片山病の
寄生虫に
比して、この虫のほうが
雌雄の
関係がさらに
親密である。
以上はいずれも他の動物の体内に
寄生する下等の
虫類であるゆえ、その
雌雄が
一生涯相離れずにいるのも、ただ
種族を
継続するために
受精を
確実にする
手段にすぎぬが、
鳥類、
獣類のごとき高等な動物になると、
別に他の
原因から、
雌雄の
縁組を定めて長く
同棲する
必要が生ずる。すなわちこれらの動物は子を
産み放しにしては、
種族継続の
見込みがたたぬゆえ、
産んでからのちしばらくこれを
保護し
養育せねばならぬが、子を
保護し
養育するには、両親が力をあわせてこれに
従事することがもっとも
有効な場合も生ずる。子を育てる
鳥類や
獣類の中には
一夫多妻のものもあり、
雌のみが子の世話をし
雄はいっこうにかまわぬようなものもあるが、
種類によっては
厳重に
一夫一婦で
生涯いっしょに
暮らすものもけっして少なくない。
小鳥類を
飼うた人はよく知っているとおり、
卵を温めるにも
雌雄が交代し、
雛が
孵ってからも両親でこれに
餌を運ぶような
種類はいくらもある。一体
鳥類にはかようなものが多く、
雉子、
鶏の
類を
除けば、その他は
燕、
鳩、
雁、
鴨、白鳥、
鶴などいずれもみな
一夫一婦で子を育てる。
鷲、
鷹なども
一夫一婦で生活し、
生殖のほかの仕事にもつねに力をあわせて
働く。
例えば
餌をとるにあたっても
共同することが多い。
これに反して
獣類には
一夫一婦のものは
極めてまれで、
犀の
類が
牝牡一対で生活すかという話はあるが、これも
真偽のほどが
疑わしい。多くの場合では
牝牡はただ
交尾の時だけ
相近づき、その他のときは
別に生活して、子を育てることは
牝ばかりでする。
猫や犬はその
例である。ただし
狐などは子が育つまでは
牡も
牝といっしょにいるが、子が
相応な大きさまでに育つと
牡は去ってしまう。また
牝牡がつねに集まって生活している
種類ならばたいがい
一夫多妻で、
小鳥類に見るごとき
厳重な
一夫一婦の
縁組は決してない。馬、牛、羊、
鹿なども
一匹の
牡が多くの
牝を
率い、「おっとせい」なども
牡は体がはるかに大きくて、たいてい
一匹で
二三十匹の
牝を
統御している。かような
種類では生まれた子が
成長しても組を
離れぬので、
老若、
牝牡を交えた大きな
群が生ずる。アフリカの平原にいる
縞馬、
玲羊類の
大群や、アメリカの広野にいた野牛の
大群は、かくして
成り立ったものである。
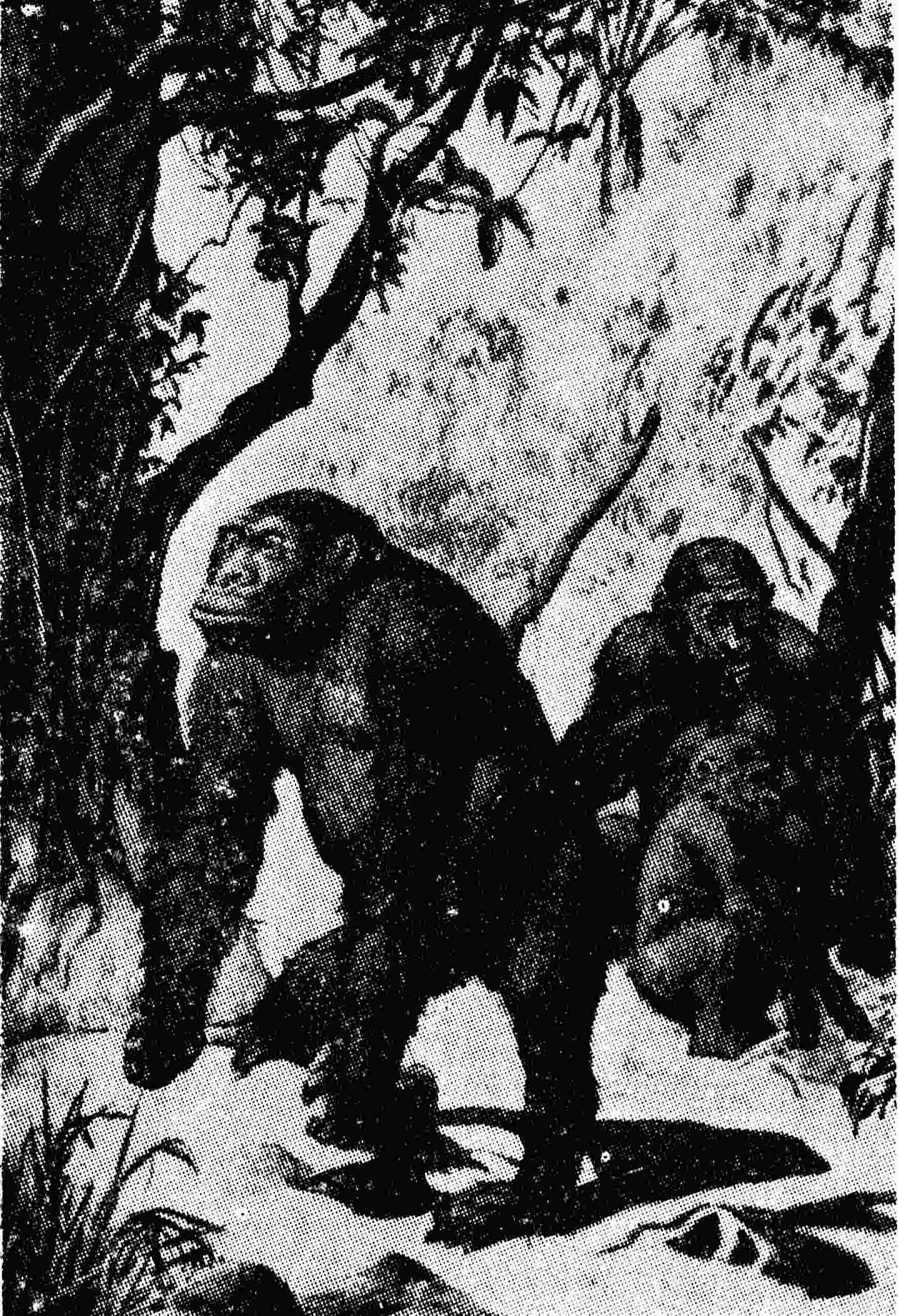 ゴリラの家族
猿類
ゴリラの家族
猿類には
数百匹の
大群をなすものもあるが、
普通の
種類は
十数匹ないし
数十匹くらいずつが
一団をつくって生活する。こうして
各団には
必ず
一匹の強い
牡があって
絶対に
権威をふるい、その命に
従わぬものは
残酷に
罰し
懲らす。その代わり
敵でも近づいた時には、この
牡がひとりふみ止まって部下のものを安全に
逃げ
去らしめる。
団中の
牝はことごとくこの
一匹の
牡の
妻妾であって、もしも他の
若い
牡が
牝に近づきでもすれば、ほとんど死ぬほどの目に
遇わされる。すべての
牝はつねにつとめて
団長の
機嫌をとり、
果物などを持ってきて
捧げ、
団長はいばってこれを食いながら両手で左右に
一匹ずつ
牝を
抱えたりしている。すなわちこの
牡は
牙と
勇気との実力によって、他より
犯すべからざる
位置を
保っているのである。
猩々などのごとき人間に近い大きな
猿はつねに小さな家族をなして、親と子とがいっしょに生活しているが、これもけっして
厳重な
一夫一婦ではないらしい。
かくのごとく
鳥類には
一夫一婦のものがすこぶる多いに反し、
獣類のほうはたいがい
一夫多妻であるのはなぜかというに、これはおそらく子を育てるにあたって、両親が同様の役をつとめるか
否かに
関係することであろう。
鳥類は
卵生であるゆえ
卵を
産んだのちは、
雌も
雄と同様に身が軽く、
卵を温めるにも
雛を育てるにも、
雌雄が同じ仕事をすることができるが、
獣類は
胎生であって、長い間
胎内に
児を
養うことも、生まれ出た
児を
乳汁で育てることも、みな
雌の
独占事業であるから、
雄は
別に世話のしようもない。
鳥類ではこわれやすい
卵を安全に温めるための
巣を
造るにも、
速く
成長する
雛に十分の
餌を
与えるにも、
雌雄二匹が力をあわせてこれに
従事することが
種族維持の
目的にもっとも
適するゆえ、
自然に
一夫一婦の定まりが生じ、
獣類のほうでは形の
備わって生まれた子に、
雌が
乳を飲ませさえすれば
種族維持の
見込みが立つゆえ、
雄はただ子の育つ間、
敵に対して
雌と子とをまもるものがあるにすぎぬのであろう。
受精が体外で行なわれる動物では、
卵はいまだ子と
成らぬ前に親の体から出で去るゆえ、子が直ちに親から
産まれるということはないが、
精虫が
雌の体内にはいりきたる
種類では、子の
生涯はまず母の体内で始まり、
或る
期限の後に生まれ出ることになる。この
期限内の
雌の
状態を
妊娠と名づける。その長さは動物の
種類によっていちじるしく
違い、
蚕のごとくに数分に
過ぎぬものもあれば、
鶏のごとくに十数時間をへるものもあり、また牛、馬、人間などのごとくに
九箇月ないし一年に
達するものもある。
精虫と
卵細胞とが合しても、その大きさは
卵細胞だけの時と少しも
違わぬゆえ、速く生まれるものでは、子はほとんど
受精前の
卵と同じ
姿で生まれるが、長く母の体内にとどまる
類では、その間に子はたえず発育
変形してもとの
卵とは全く
形状の
異なったものとなって世に
現われる。
通常卵のままで生まれるのを
卵生といい、親と同じ形を
備えて生まれるのを
胎生と名づけて
区別するが、
卵生にも
胎生にもさまざまな
階段があって、
産まれた
卵の
殻の内に
幼児が十分に発育している場合もあれば、いまだ親の形に
似ない
不完全な
幼児が
裸で
産み出されることもあるゆえ、この
区別はけっして
重要なものではない。ただ
普通に人の知っている動物の中で、
獣類はことごとく
胎生し、
鳥類は
残らず
卵生するゆえ、昔から
特に人の注意を引いたのである。
卵生と
胎生とを
比較して見るといずれにも
一得一失があって、
種族保存の上にいずれを
有利とするかは、その
種族の
習性によって
違う。
受精後の
卵は親の体からいえばもはや
一種の荷物に
過ぎぬゆえ、
速かに
卵を
産み出してしまえば、親の身体はそれだけ早く軽くなり運動もらくになる代わりに、子はそれだけ多く外界の
危険にさらされる。何動物でも
卵の時代や
卵から
孵ったばかりの時代は、もっとも弱くもっとも死にやすいときであるゆえ、
卵生する動物は
特に
卵を
保護する
種類のほかは、
非常に多くの
卵を
産まぬと
種族継続の
見込みがたたぬ。しこうして数多く
卵を
産めば
卵の
粒は
勢い小さくならざるを
得ぬが、
卵が小さければそれより
孵化して出る
幼児も小さく弱いゆえ、それだけ
卵の数を多く
産まねば安心ができぬ。これに反して、
胎生のほうでは子の発育するはじめは、母の体内にあって十分に
保護せられているから、多数が死にうせるごとき心配はない。それゆえ少数の
卵を生じ、少数の
幼児を
産むだけでも
種族維持の
見込みはたしかにたつ。この点を考えると、
卵生にくらべて
胎生のほうが明らかに一歩進んでいるようであるが、子を長く体内にとどめておけば、その間母親はよけいの子まで負うているわけゆえ、運動もいくぶんか
妨げられ、かつもし自分が
殺される場合には
腹の内な荷物をがともに
殺されて、後に
子孫を
遺すことができぬという
不利益がある。動物の
種類を数多くならべて見ると、全部
胎生するものはただ
獣類だけであって、その他はほとんどことごとく
卵を
産むゆえ、全体としてはむろん
卵生のほうがはるかに多数を
占めている。
鳥類でも
魚類でも
昆虫でも
貝類でもみな
卵生である。しかし、
卵を
産むものの中に
例外として、
胎生する
種類のふくまれていることはけっして
珍しくない。
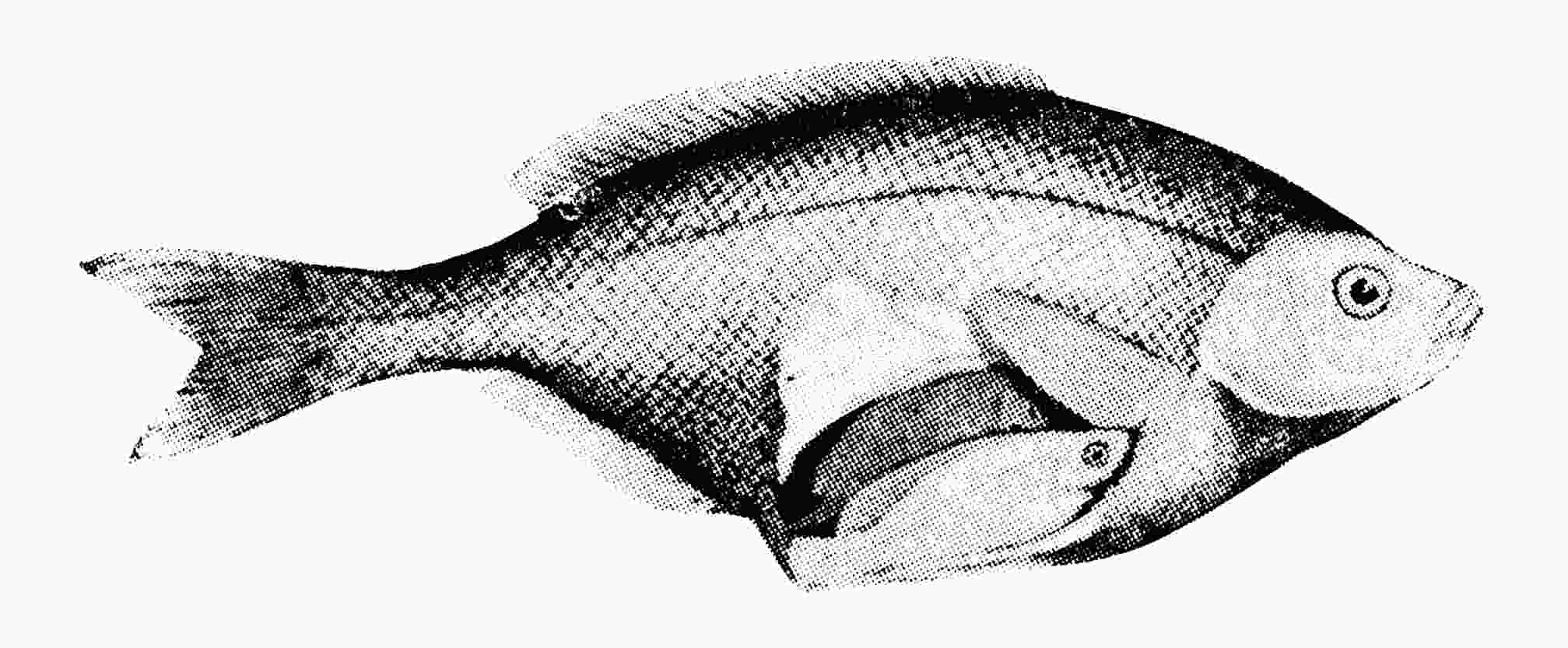 うみたなご
例
うみたなご
例えば
魚類中の「ほしざめ」、「あかえい」、「うみたなご」とか、
蛇類中の「まむし」とか、
昆虫類中の「ありまき」とか、
貝類中の「たにし」とかいうごときものは、いずれも
卵生する
部類に
属しながら、自分は
胎生する。かくのごとく、たいがいの組には
例外として
胎生するものが
一種や
二種はあるが、ただ
鳥類だけはことごとく
卵生であって、
一種として
例外はない。これはなぜかというに、
鳥類は主として空中を
飛翔するもので、
餌を
捕えるにも
敵から
逃げるにも、
飛翔の
巧みなることを
要するが、
妊娠は身を重くしてはなはだしく
飛翔を
妨げるからである。そもそも
飛翔は動物の運動
法の中でもっとも進歩したもので、もっとも速力の大なる代わりにもっとも多く
筋力を
要し、これをよくするものはわずかに
鳥類、「こうもり」
類、
昆虫類のほかにはない。他の運動
法に
比して
飛行の
困難なることは、船や車が何千年の昔から用いられていながら、
飛行機がようやく近年になってできたのを見ても知れる。されば
鳥類の身体は
飛翔のためには他の何物をも
犠牲に
供し、他の方面では
如何なる
不便をしのんでももっぱら
飛翔のよく行なわれ
得るような仕組みになっている。
鳥類の
骨のなかまで空気のはいっていることも、
絶えず
脱糞して
一刻も
腸内に
不用の物を
貯えておかぬことも、
尿が
獣類におけるごとき
多量の
液体でなく、あたかも
煉乳のごとくに
濃くして
少量なることも、みな身を軽くするための
方便にすぎぬ。
生殖器官もそれと同じく、なるべく身を軽くして、しかもなるべく
完全な子の生まれるような
手段が行なわれ、
卵生ではあるが、
卵生中の
特に
発達したものとなり、他に
比類のない大きな
卵を生ずるにいたったのであろう。他の動物の
卵がみな小さくて多くの場合には人に知られぬに反し、鳥の
卵だけは太古から食用に
供せられ、
単に
卵と言えば直ちに鳥の
卵と思われるのもみなその
特に大なるためであるが、その大なる理由は
陸上の高等動物なる
鳥類が安全に
種族を
継続し
得べき
完全な
雛を生ずるにたりるだけの
多量の黄身を
含むからである。
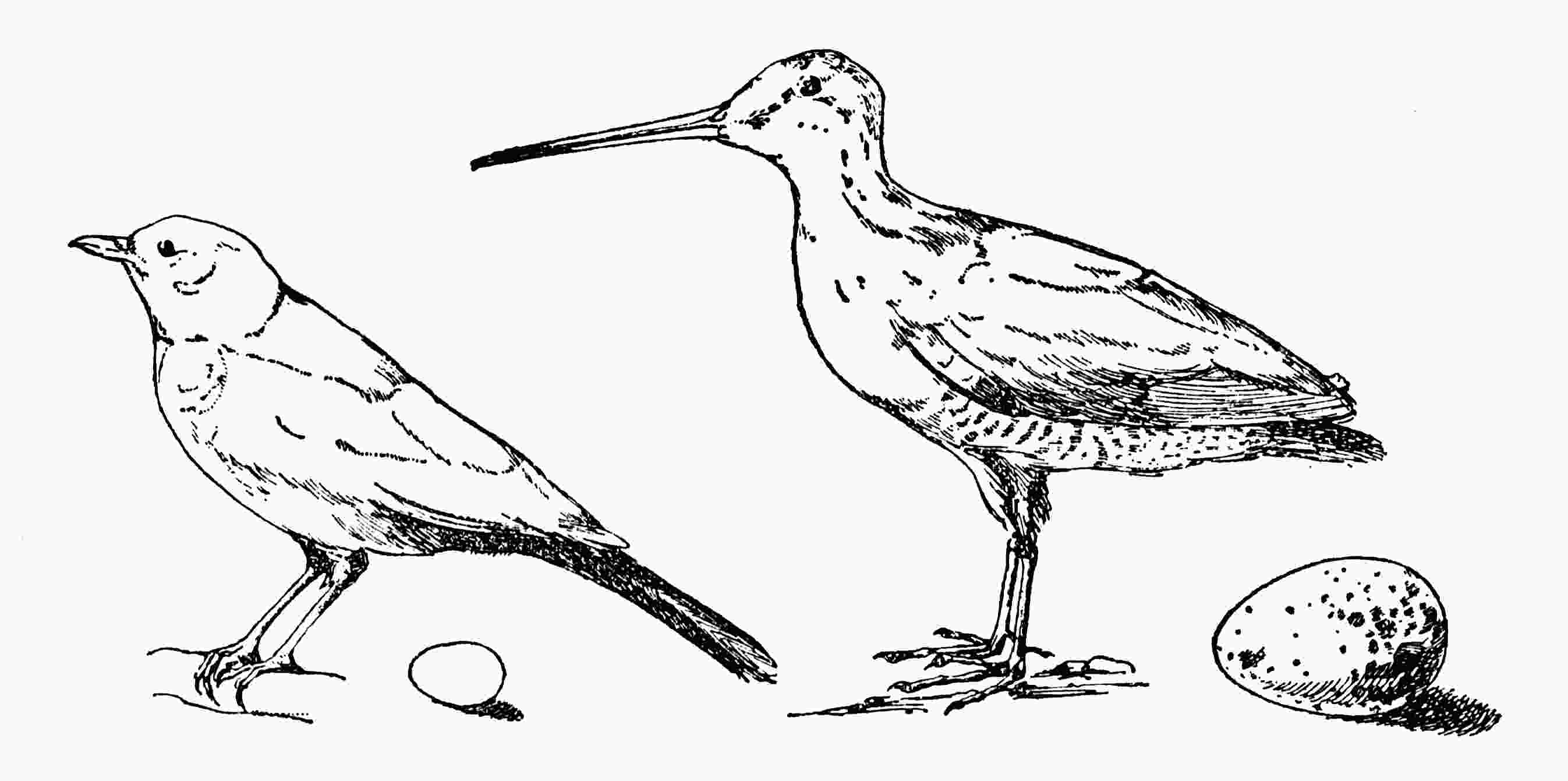
鳥の体と卵
(右)よく飛ばぬ鳥 しぎ (左)よく飛ぶ鳥 つぐみ
なお
鳥類の中にも、親の身体の
割合に
卵のやや小さな
種類と大きな
種類とがあるが、これも
飛翔の力と
関係している。
生存上もっともよく
飛ぶ
必要のある鳥は、なるべく身を軽くするために、
卵巣内の
卵もいくぶんか小さく、したがって
産まれた
卵もやや小さいが、
雉子や
鶏などのごとくつねに地上に
棲んでいて、
飛ぶことが少々
拙でも
生存のできるような鳥では、
卵は十分の
滋養分を
含んでいくぶんか大きくなる。
 ニュージランド産の鴫駝鳥とその卵
ニュージランド産の鴫駝鳥とその卵
そこで、大きな
卵から
孵って出る
雛は発育もそれだけ進んでいるゆえ、始めからひとりで走りまわって
餌を
求めるが、小さな
卵から出た
雛は
勢い発育が
不十分なるをまぬがれぬゆえ、
孵っても始めの間は自分で何をすることもできぬ。小さな
卵を
産む鳥はつねに身が軽くて、よく
飛べるという
利益がある代わりに、
雛が
孵ってから
骨折ってこれを世話せねばならぬ
面倒があり、大きな
卵を
産む鳥は身体がいくぶんか重くなって
飛ぶ時には多少
不便であるが、
雛の
孵ってからの世話はよほどらくである。
自然界はすべてこうしたもので、いずれの方面にも
利益ばかりを
得ることはとうてい
許されぬ。「そうは問屋で
卸さぬ。」という
世俗の言葉は、ここにもよく当てはまるように見える。
胎生という中にも
種々の
階段があって、けっして一ようではない。
例えば
蛇類や「いもり」の
類の
胎生するものでは、そのまま生まれ出ても、子になるべき大きな
卵がただしばらく
輸卵管の
末にとどまり、子の形ができあがったころに生まれるにすぎぬゆえ、親は
単に子に場所を
貸すだけで、名は
胎生というても、実は
卵生とあまり
違わぬ。これに反して
獣類のごときは、
初め
微細な
卵細胞が母の体内にとどまっている間に、
絶えず母から
滋養分をうけて発育
成長し、ほぼ親と同じ
形状を
備えたものとなって
産まれるのであるから、これこそ真に
模範的の
胎生で、
妊娠中の親子の
関係は
極めて
親密である。かように
両極端を取って
比較するといちじるしく
違うが、その間にはむろんさまざまの
途中の
階段に
位するものがある。
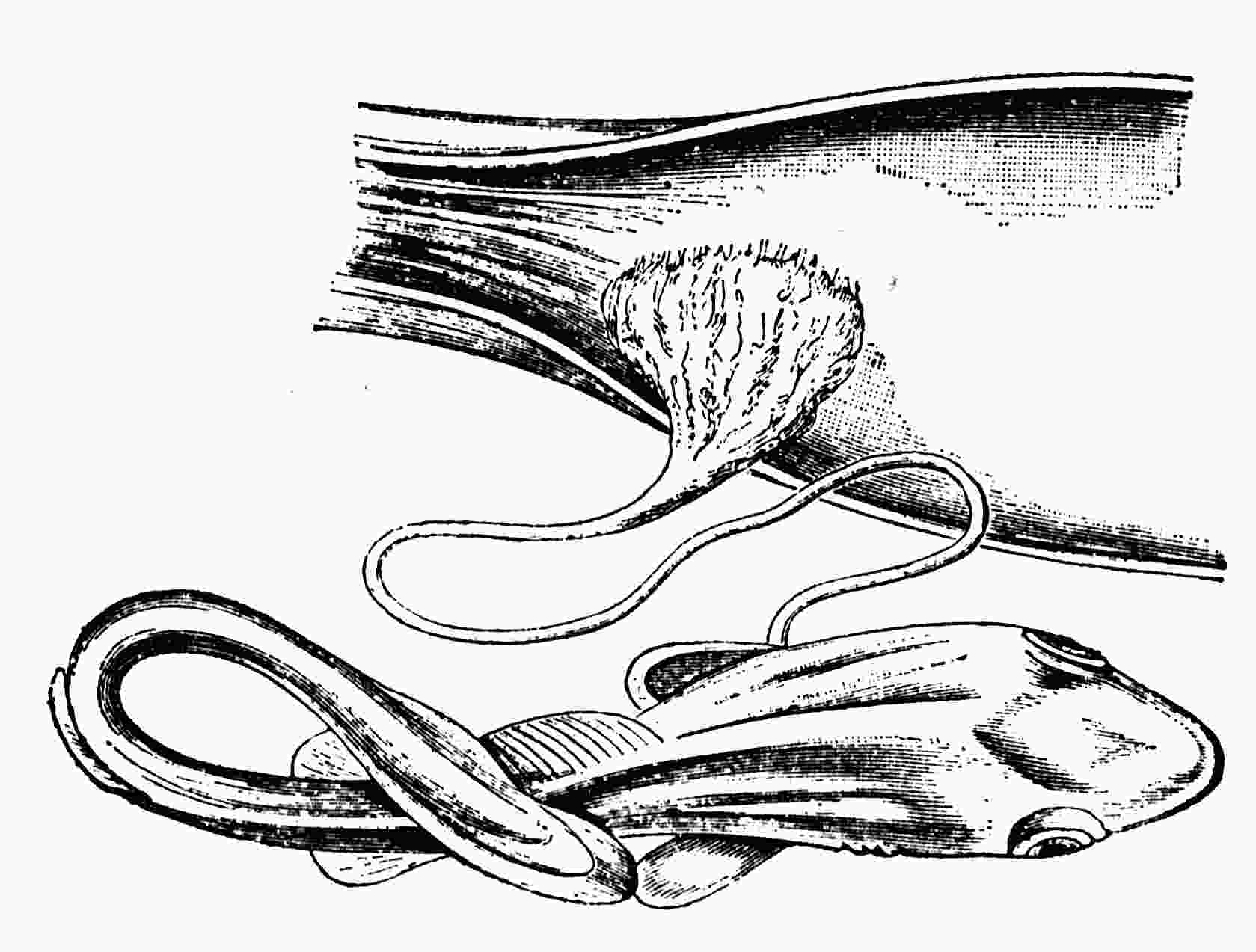 さめの子が黄身の嚢で輸卵管の内面に付着する状
魚類
さめの子が黄身の嚢で輸卵管の内面に付着する状
魚類中で
鮫などには、大きな
卵が親の
輸卵管の出口に近いところにとどまって
発達するものがあるが、かかる場合には親は
単に場所を
貸すにとどまらず、
輸卵管の内面より
乳のごとき
一種の
滋養液を
分泌して子に
供給し、子はこれを受けて
速かに発育する。「あかえい」では
妊娠すると、
輸卵管の内面から細い糸のごとき
突起がたくさんに生じ、これより
滋養液を
分泌するが、この
突起は
束になって
胎児の
眼の後にある左右の
噴水孔からはいり
込み、
胃に
達して
滋養分を直ちにその中へ送り入れる。また「ほし
鮫」では
胎児の
腹からつづいている黄身の
嚢が親の
輸卵管の内面に
密着し、ちょっと
引張ったくらいではなかなか
離れぬが、これも親から子に
滋養分が
供給せられるための
仕掛けであって、そのありさまは後に
述べる
獣類の
胎盤に大いに
似たところがある。かような
次第で、
卵が長く親の
輸卵管内にとどまる場合には、身体の
互いに
密接していることを
利用して、親が子に少しずつ
滋養分を
与え、その発育を助けることが行なわれ、かつ一歩一歩進みゆく様子が見えるが、子はそのためいっそう十分に発育して大きく強くなって生まれるゆえ、
種族保存のうえに
有効であるは
論をまたぬ。
魚類にかぎらず
如何なる動物においても、
輸卵管の一部で
卵がとどまって発育する場所は
特に太くなっているが、その部分を
子宮と名づける。
また
獣類は
模範的の
胎生であると言うたが、これもことごとく
然りとは言われぬ。すなわち
獣類の中にも、その
胎生のありさまには
種々程度の
違うたものがあって、
極めてまれな場合には
卵の形で生まれるものさえある。
卵生する
獣類というのは、今日わずかにオーストラリア地方にかぎり
棲息する二三の
珍しい
種類で、
鳥類のごとくに
生殖器の開き口と
肛門とが一つになっているゆえ、
総括して
単孔類と名づける。
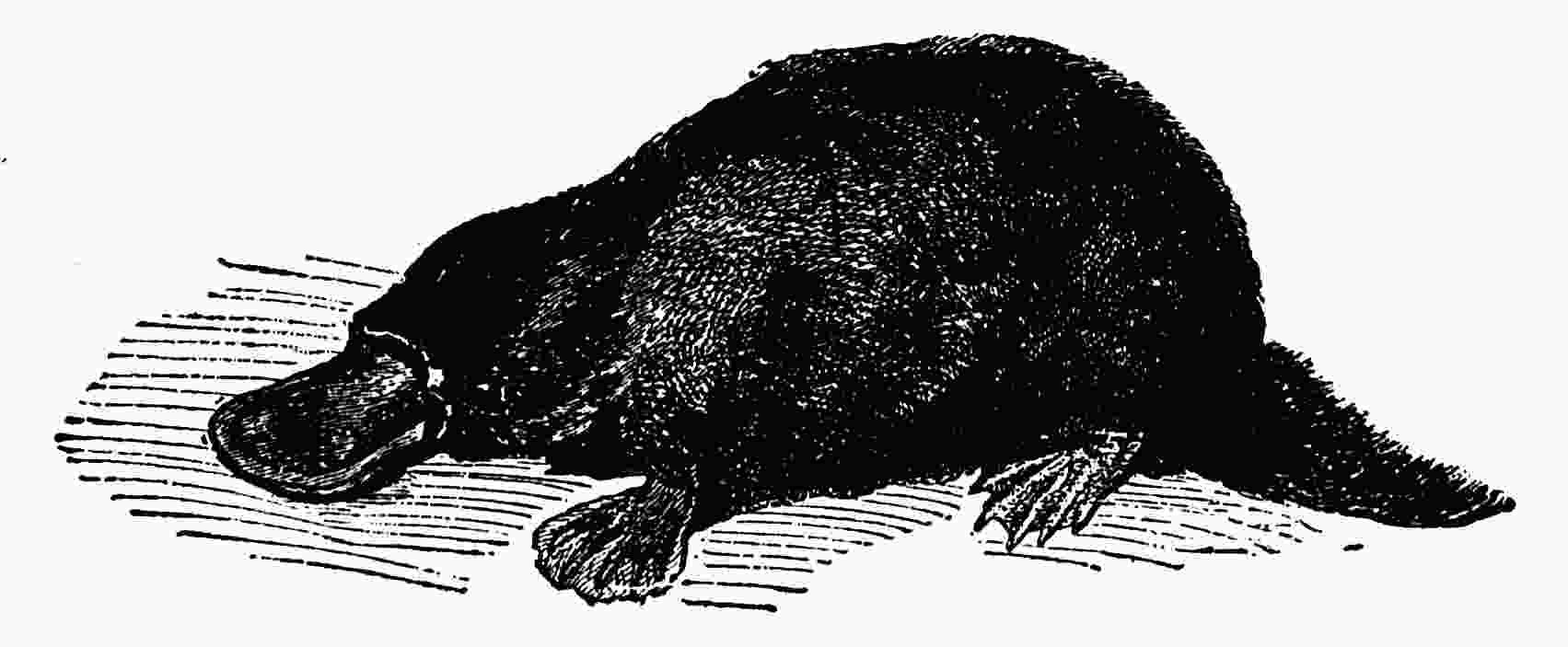 かものはし
家鴨
かものはし
家鴨のごとき
嘴を有する「かものはし」、「
針鼡」に
似てしかも
吻の長い「
針もぐら」などがその
例であるが、これらは
直径六七分(注:1.8~2.1cm)の丸い
卵を一度に
一個ずつ
産む。しかし生まれたばかりの
卵の
殻を切り開いて見ると、中にはすでに
相応に発育した
幼児の形ができているゆえ、
鳥類などの
簡単な
卵生とはおもむきが
違う。かりにこれらの
類で、
卵が
産まれるとたんに
殻が
破れたと
想像すれば、
卵生と名づけてよいか
胎生と名づけてよいか
判断がむずかしかろう。
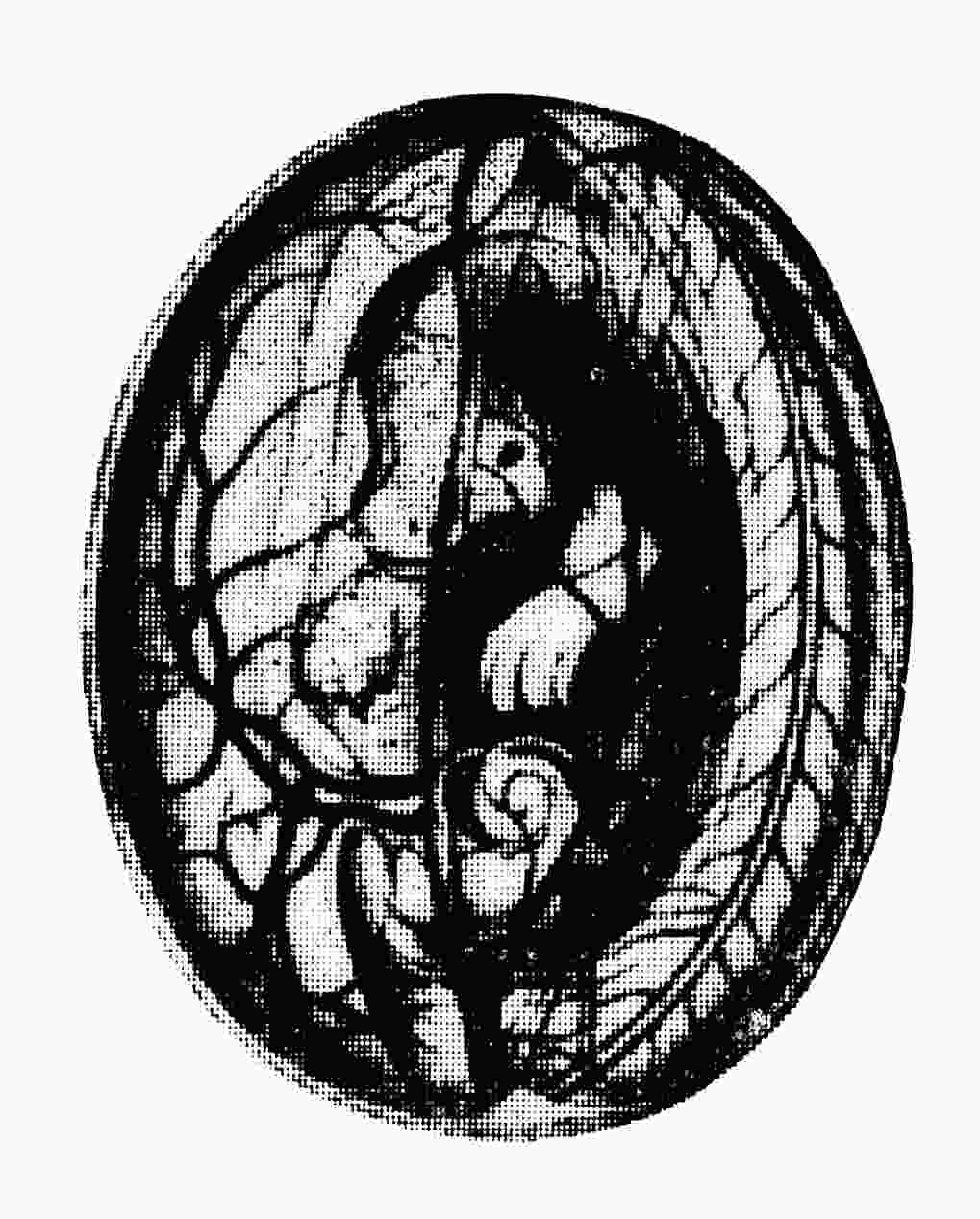 針もぐらの子
針もぐらの子
「
針もぐら」は
産んだ子をさらに
腹の外面にあるくぼみの中に入れて温めるが、「かものはし」のほうはつねに水中を
游ぐものゆえ、
卵を身につけて歩くことはできぬ。
卵が
産まれるまでとどまっているところは、
鳥類におけると同じく
輸卵管の
末端であるが、近来の研究によると、その部の
粘膜から
一種の
乳のごとき
滋養液を
分泌し、子はそれを
吸うて発育するとのことゆえ、この点もいくぶんか
普通の
獣類に
似ている。
獣類で
卵生するのはまれな
例外であって、その他はことごとく
胎生であるが、同じ
胎生というなかにもまた
種々の
階段がある。
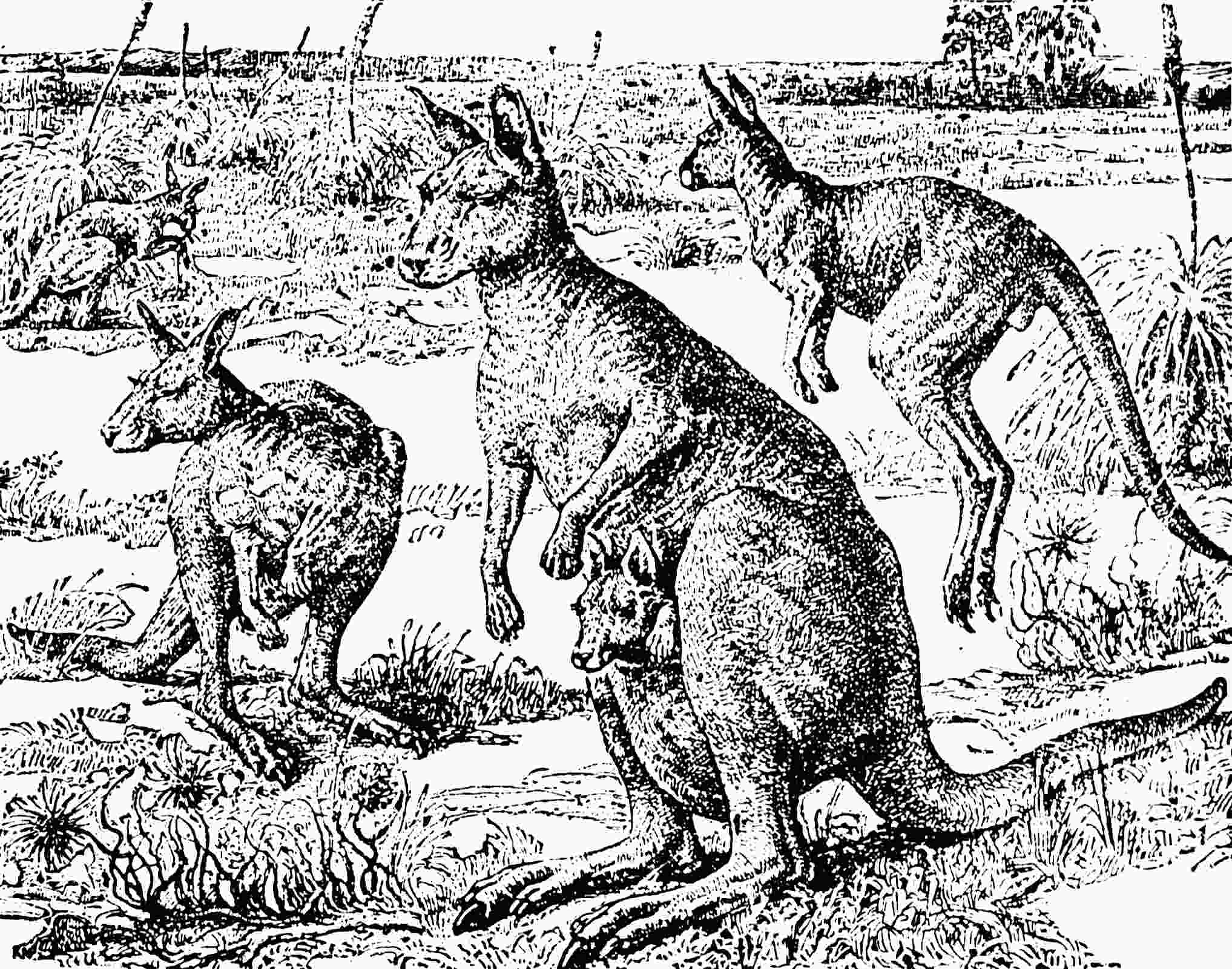 カンガルー
例
カンガルー
例えば大きな「カンガルー」は身の
丈が
六尺(注:1.8m)
以上もあってほとんど人間と同じくらいであるが、その
妊娠の
状態を見ると、人間の女が
九箇月の後に身長
一尺六寸(注:48cm)体重
八百匁(注:3kg)もある大きな子を
産むに反し、
妊娠わずかに
一箇月でほとんど人の
拇指の
一節にもたらぬほどの小さな子を
産む。
 カンガルーの幼児
カンガルーの幼児
この子は人間の
胎児のほぼ
二箇月くらいのものに相当し、手足の指もいまだ
判然とはできぬくらいゆえ、そのままではとうてい生活はつづけられぬ。それゆえ母親はさらにこれを
腹の前面にある
特別の
袋に入れ、
袋の内にある
乳房の先を子の口にはめ、
乳汁をそそぎこんでなお
数箇月間
養育するが、かくしてできあがった子が、
初めて人間の生まれ立ての赤子と同じくらいの大きさに
達する。すなわち人間ならば子を
九箇月の間
子宮の内に入れておくところを、「カンガルー」は
一箇月だけ
子宮内に、
残り
八箇月は
腹のそとの
袋に入れて
養うのである。「カンガルー」の子は一度
乳房を口に入れたら、そのままいつまでも
離さず、また
乳房はのびて子の
胃の
腑までもたっするゆえ、少々
引張ったくらいでは子はけっして親の体からは
離れぬ。それゆえ、昔ヨーロッパ人が
初めて「カンガルー」を見た時には、この
獣は
芽生によって
繁殖すると思い
誤り、そのとおり
報告した。かく
胎生する
獣類の中にも、小さな子を早く
産み出すものと、十分育つまで子を
腹の内に入れておくものがあるのは、
胎生の子を
養うための
仕掛けにさまざまの
相違があるからである。
鳥類などでは
卵が
卵巣を
離れてから体外へ出るまでに
通過する
管を全部
輸卵管と
呼ぶが、
獣類ではこの
管を三部に
区別し、
卵巣にもっとも近くて
卵が
単に
通過するだけの部を
輸卵管または
喇叭管といい、その次にあって子がその内で育つところを
子宮といい、
子宮より体外に開くまでの間を
膣という。この中でもっとも大切なところは
子宮であるが、
種々異なった
獣類をくらべて見ると、
初め
鳥類のと少しも
違わぬような
輸卵管が左右に一本ずつあるものが、
下端のほうから
漸々相合着してついに人間に見るような
一個の
子宮が体の中央線に
位するにいたるまでの進歩の
道筋が明らかに知れる。
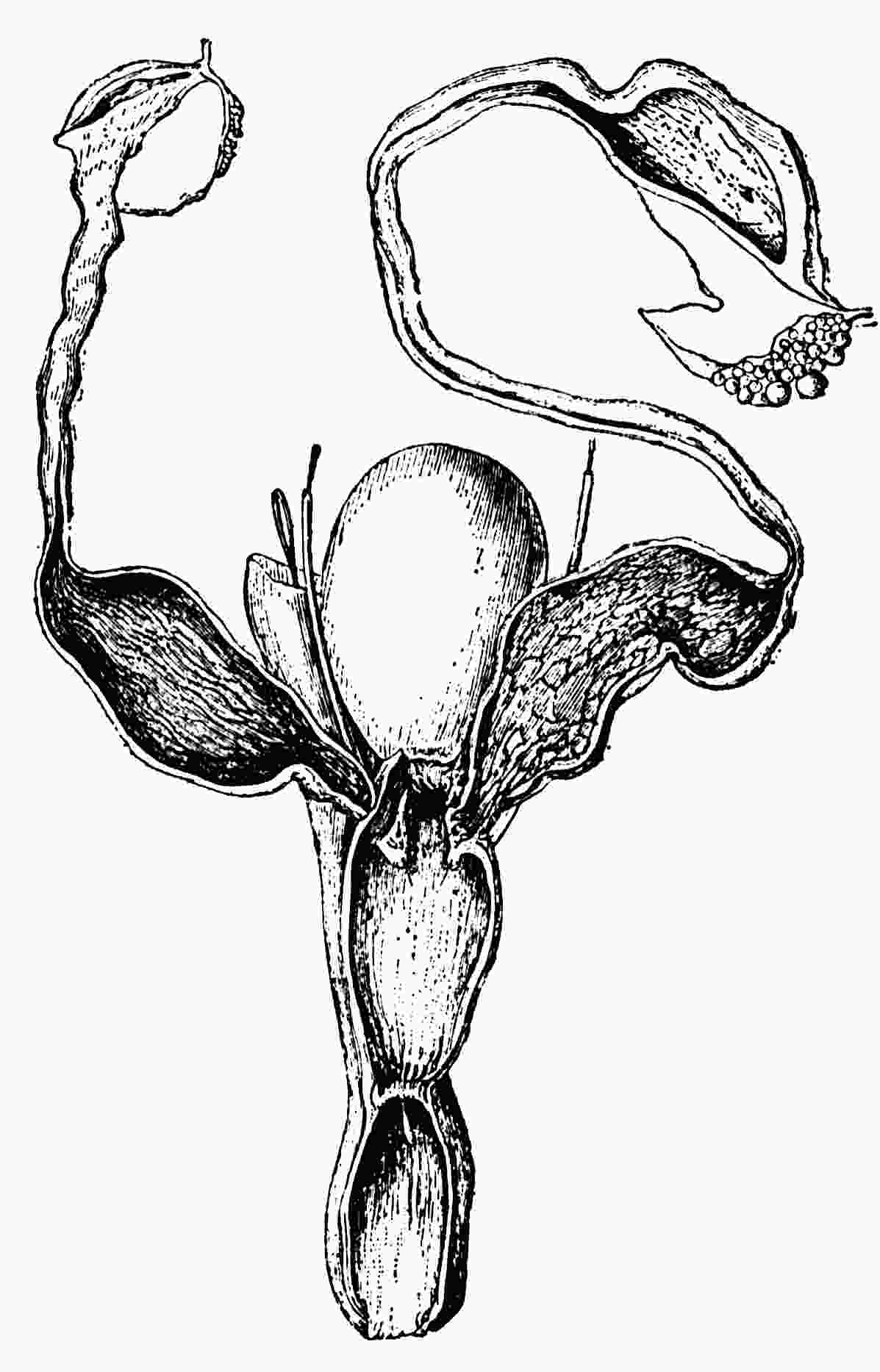 かものはしの雌の生殖器
かものはしの雌の生殖器
まず「かものはし」などを見ると、
輸卵管は左右べつべつに
肛門の
内側に開き、
相合して一本となっているところはどこにもない。出口に近いところに
卵がしばらくとどまって、その内の子が発育するゆえ、その部を
子宮と名づけるが、
鳥類と同じことで、
特に
膣と
称すべき部は全くない。
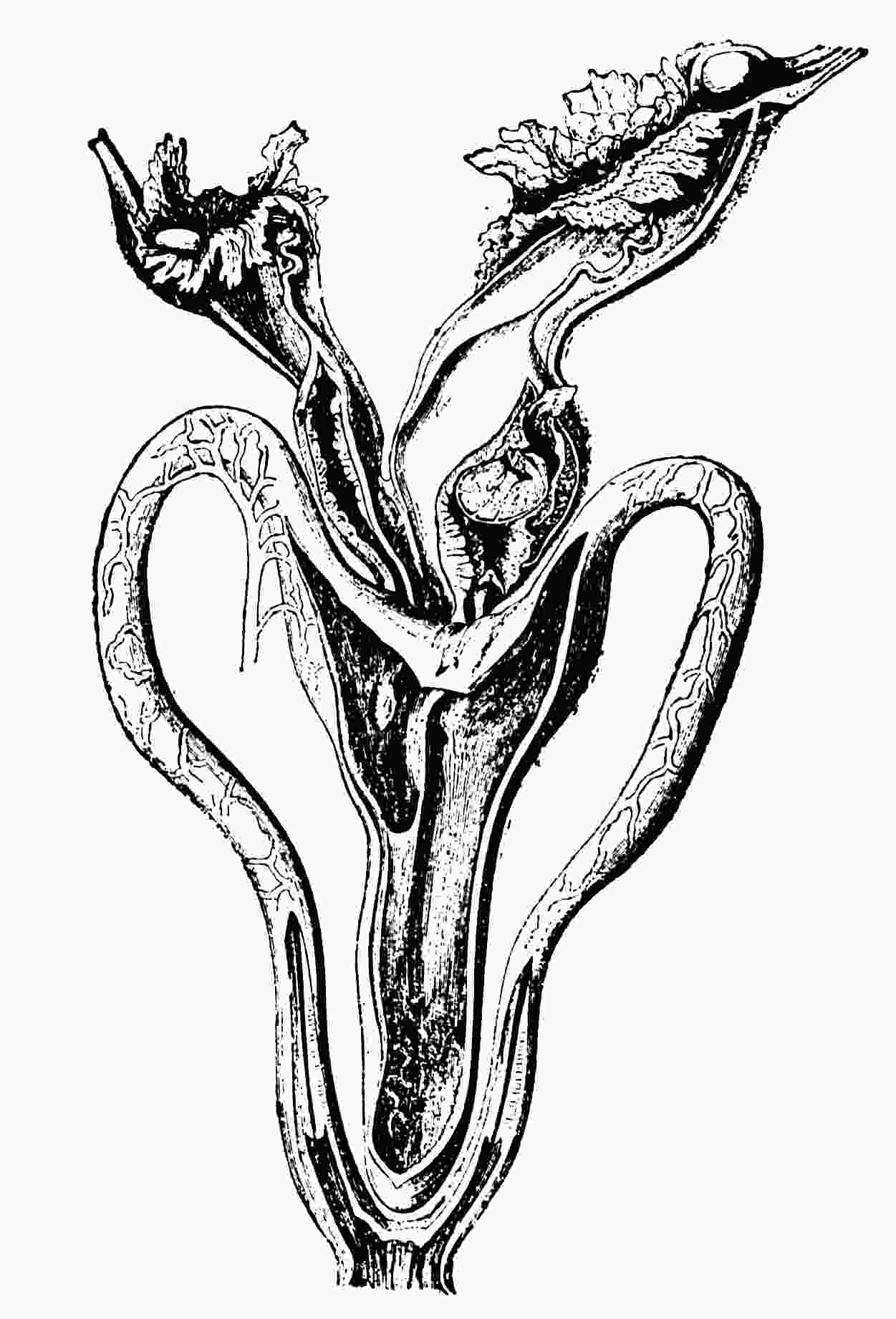 カンガルーの雌の生殖器
カンガルーの雌の生殖器
次に「カンガルー」の
類では
如何というに、この
類では
膣の開口は一つの
孔であるが、その内は直ちに二本に分かれている。これに
準じて
雄のほうの
交接器も左右二本に分かれてある。
膣が左右に分かれているゆえ、それより
奥の
子宮や
輸卵管はもちろん左右に一つずつある。
生殖器の開口と
肛門とは
別の
孔であるが、
共同の
輪状筋肉で、あたかも
巾着の口のごとくにくくられているありさまは、
鳥類や「かものはし」の
類と
普通の
獣類との中間に
位するものといえる。「うさぎ」、「ねずみ」などを見ると
膣は
単一であるが、
子宮は明らかに二つ
並んであって、その
膣につづく
孔も左右べつべつに開いている。また犬、
猫などになると、
子宮は下のほうは合して一つとなり、上のほうは左右に分かれているゆえ、あたかも人という字をさかさにしたごとくである。
最後に
猿、人間などでは
子宮は全く
単一となり、ただ
喇叭管だけが左右一対をなしている。かくのごとく
種々の
獣類をくらべて見ると、人間や
猿などのごとくに、
膣の
奥にただ
一個の
茄子状の
簡単な
子宮があるのは、
初め「かものはし」におけるごとき左右一対の長い
輸卵管が出口のほうから少しずつ
相合着して、一歩一歩進み来たった
最後の
階段であることが明らかに知れるであろう。
さて
子宮なるものは、これを
備える
個体の
生存を
標準として考えると、なくとも日々の生活には
差支えのないはずのものをしばらく
貯えおく
袋にすぎぬゆえ、
尿を
貯えるための
膀胱と同じ
価値のものであるが、
種族の
生存を
標準として見ると、
極めて重大な
価値を有する。
子宮内に子を入れている間は、母親は
種族の生命をおのが手に
預かっているようなもので、自分が死ねば
種族の
将来をも
亡ぼすことにあたる。すなわち子が早く死んで出ても、親は生き
残るが、親が死ねば子はとうてい助からぬゆえ、
妊娠中の母親は
種族維持の上にはもっとも大切なもので、この点では大いに父親と
違う。長い間よけいな重さを
支え、よけいな食物を食うのも、
最後に
非常な苦しみを
堪えるのも、一として
自己一身のためではなく、全く
種族のためであるゆえ、
妊娠は、いわば
種族のために
個体が
奉公をしているごときものである。されば
妊娠中の
婦人は
自己の
属する
種族の
維持繁栄のために一身を
捧げているわけにあたるゆえ、
周囲の者よりは
特別の
待遇をうけ、ただならぬ身として
鄭重に
取扱われるが、自身も
当然のこととしてあえてこれを
辞せぬ。
受精の
際に他人に見られたならば
恥じて
絶え入るべきほどの
婦人が、
受精の
結果なる
妊娠をいくぶんか
誇るがごとき
態度の見えるのは、おそらく
種族のために重大な
任務を
尽くしているとの
無意識的の
自覚が、どこかにひそんでいるゆえであろう。いずれにしても
子宮は
個体の一小部分でありながら、全く
種族のために
働く
特別の
器官であるゆえ、その
影響するところもすこぶる広く、
子宮に何か
異常があれば全身はそのために
健康を
失う。どこの病院に行っても
婦人科はあるが、男子科はない。しこうして
婦人科の
病というのは、ほとんどみな
子宮に
関係のある病ばかりである。
蛙の
卵または
鮭の
卵を生かしておき、その発生を調べて見ると、
初め球形の
卵の
一粒が
漸々形が変わって全部がただ
一匹の子の身体のみとなるが、
鶏の
卵を
雌雄に温めさせてその日々の発生を調べると、
卵からはただ
雛の身体のみができるのでなく、早くから
雛の身体を
包む
薄い
膜の
嚢もできる。
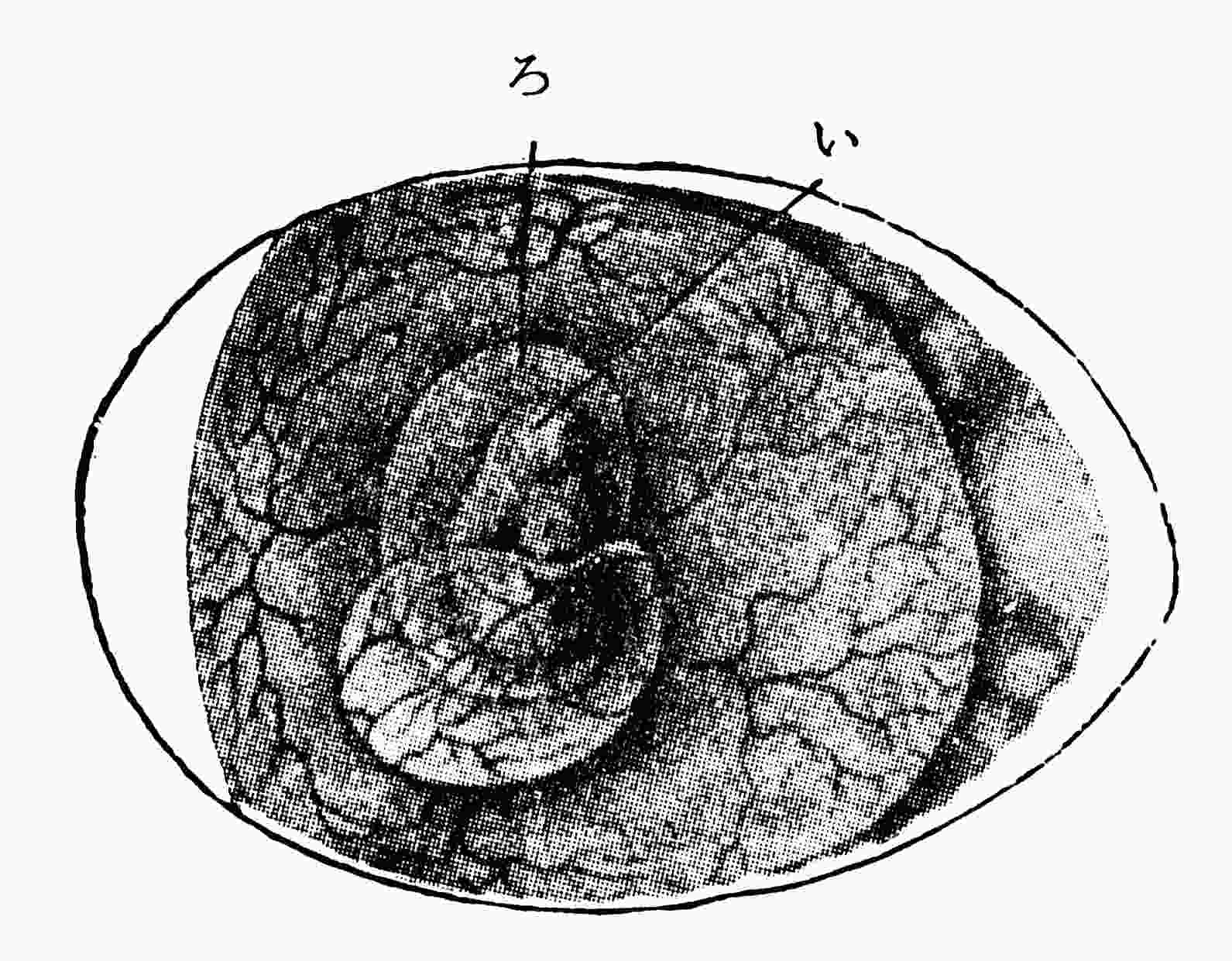
鶏卵内の発育
(い)雛の体 (ろ)羊膜
この
嚢を「
羊膜」と名づける。
鶏の
卵もがんらいは
一個の
細胞であるが、
産まれた
卵は
受精後十数時間をへたものゆえ、その間に
細胞の数はふえて一平面に
並びすでに明らかな
層をなしている。黄身の上面に
必ず一つの小さな円い白いところがあるのは、すなわちこの
細胞の
層である。
俗にこれを「
眼」ととなえて、これから
雛の
眼玉ができるように言うが、それはむろん
誤りで、実はこれから
雛の全身ができるのである。親鳥に温められると、この白い
眼のごときところが
漸々大きな
円盤状となり、その
周囲は
延びてついに黄身を
包みおわり、その中央部すなわちはじめ
眼のあった
辺では、
細胞層が曲がったり
折れたりゆ
着したり切れたり、
極めて
複雑な
変化をへてついに
雛となるが、後に
雛になる部分の
周囲からは、
細胞層があたかも
子供の着物の
縫い上げのごとき
特別の
褶を生じ、この
褶が四方から
雛の身体をかこんで、
卵から
孵って出るときまであたかも
嚢に入れたごとくに全く
包んでいる。前に
羊膜と名づけたものはすなわちこの
細胞層の
薄膜である。かくのごとく
鶏などでは、始め
細胞の
層ができて、その一部は
雛の体となり、
残りの部は
雛を
包む
嚢となるのであるから、これをたとえていえば、あたかも
布を
縫うて人形をつくるにあたり、大きな
布を切らずに用い、人形につづいたままの
残りの部でその人形を
包んだごとくである。同一の
材料の一部で人形をつくり、そのつづきでこれを
包む
嚢をつくったと
想像すれば、ちょうど
雛の
卵の内で、同じ
細胞層から
雛の身体と
雛を
包む
羊膜とができるのと同じわけにあたる。
発生中に
羊膜のできることは、
脊骨を有する動物の中でも
鳥類、
獣類、
亀、
蛇、
蜥蜴の
類にかぎることで、
魚類や
蛙、「いもり」の
類には決してない。「いもり」と「やもり」とは外形がよく
似ているのでずいぶん
混同している人も少なくないが、その発生を調べると、「いもり」のほうは
羊膜ができぬから
魚類と同じ
仲間に
属し、「やもり」には
立派な
羊膜ができるゆえ、むしろ
鳥類のほうに近い。されば発生にもとづいて
分類すると、
脊椎動物を
無羊膜類と
有羊膜類との二組にわかち、前者には
魚類と
両棲類とを入れ、後者には
哺乳類、
鳥類、
爬虫類を組みこむことができる。人間も他の
獣類と同じく、発生中には
羊膜ができてつねに
胎児を
包み、
胎児は
羊膜内の羊水の中にただようている。
二箇月三箇月のころに
流産すると小さな
胎児が
薄い
羊膜の
嚢に
包まれたままで生まれ出るが、
月満ちて生まれる場合には、
羊膜はまず
破れて羊水が流れ出で、それと同時に子が
子宮からでてくる。ただしまれには「
袋児」ととなえて、
羊膜が
破れずこれを
被ったままで
児が生まれることもある。
 第4週の胎児と羊膜
第4週の胎児と羊膜
動物を
通常胎生と
卵生とに分けるが、
以上述べたとおり、
羊膜を生ずるのは
胎生するものと、
卵生するものの一部とにかぎられてある。
蛙も
鶏も同じく
卵生であるが、その発生を調べて見ると、
羊膜の
有無については
卵生の
鶏は
卵生の
蛙に
似ずして、かえって
胎生の
獣類のほうにはるかに近い。大きな
卵を
産む鳥と
微細な
卵細胞を生ずる
獣類とに、なぜ
羊膜ができて、その中間の大きさの
卵を
産む
蛙に、なぜ
羊膜ができぬかとの
疑問は返答がないように思われるが、だんだん調べて見ると、
獣類はけっしてごく昔の
先祖以来つねに
微細な
卵ばかりを生じたのではなく、
最初はやはり今日の
亀や「とかげ」の
類、もしくは「かものはし」などのごとき大きな黄身を
含んだ
卵を
産んだのが、その後
次第に
胎生の方向に進み、
卵は少しずつ小さくなって、ついに今日見るごとき
極めて
微細な
卵細胞を生ずるにいたったものらしい。かく考えねばならぬ
論拠は発生学上の
詳細な点にあるゆえ、ここには
略するが、ただ
羊膜の生ずるありさまだけから見ても、
獣類と
鳥類とはともに
初め
比較的大きな
卵を
産む
爬虫類から起こり、
鳥類のほうは
飛翔の
必要上ますます
完全な
卵生のほうに進み、
獣類のほうは
卵を安全ならしめるために長く体内にとどめおき、母体と子の体との
相接蝕するところから、その間に新たな
関係が生じ、母体から
絶えず
滋養分を
供給し、
卵はそのためあらかじめ
多量の黄身を
含みおる
必要がなくなり、ついに
模範的の
胎生となったのであろうと思われる。かように考えると、
獣類の
微細な
卵から子が発生するにあたって、
鳥類におけると同じように
羊膜の生ずるのは、ともに
先祖の
爬虫類から
遺伝によって
伝わったものとして、
初めて
了解することができる。
人間も他の
獣類とともに
初め
卵生の
爬虫類から起こったものなることは、
羊膜の生ずるありさまからほぼ
推察ができるが、次に
種々の
獣類の
胎盤の
形状を調べて見ると、人間は
獣類中のいずれの
仲間に
属するかがすこぶる
明瞭にわかる。
胎盤とは親の体から子の体へ
滋養分を
与えるための
特殊の
器官であるゆえ、
胎生をせぬ動物にはもとよりあるはずはないが、
胎生する動物でも
胎内の子が親に
養われぬ場合には
胎盤の
必要はない。ただ
胎児が長い間親から
滋養分を
得て大きく
成長するような
種類では、
胎盤がよく
発達しなければならぬ。
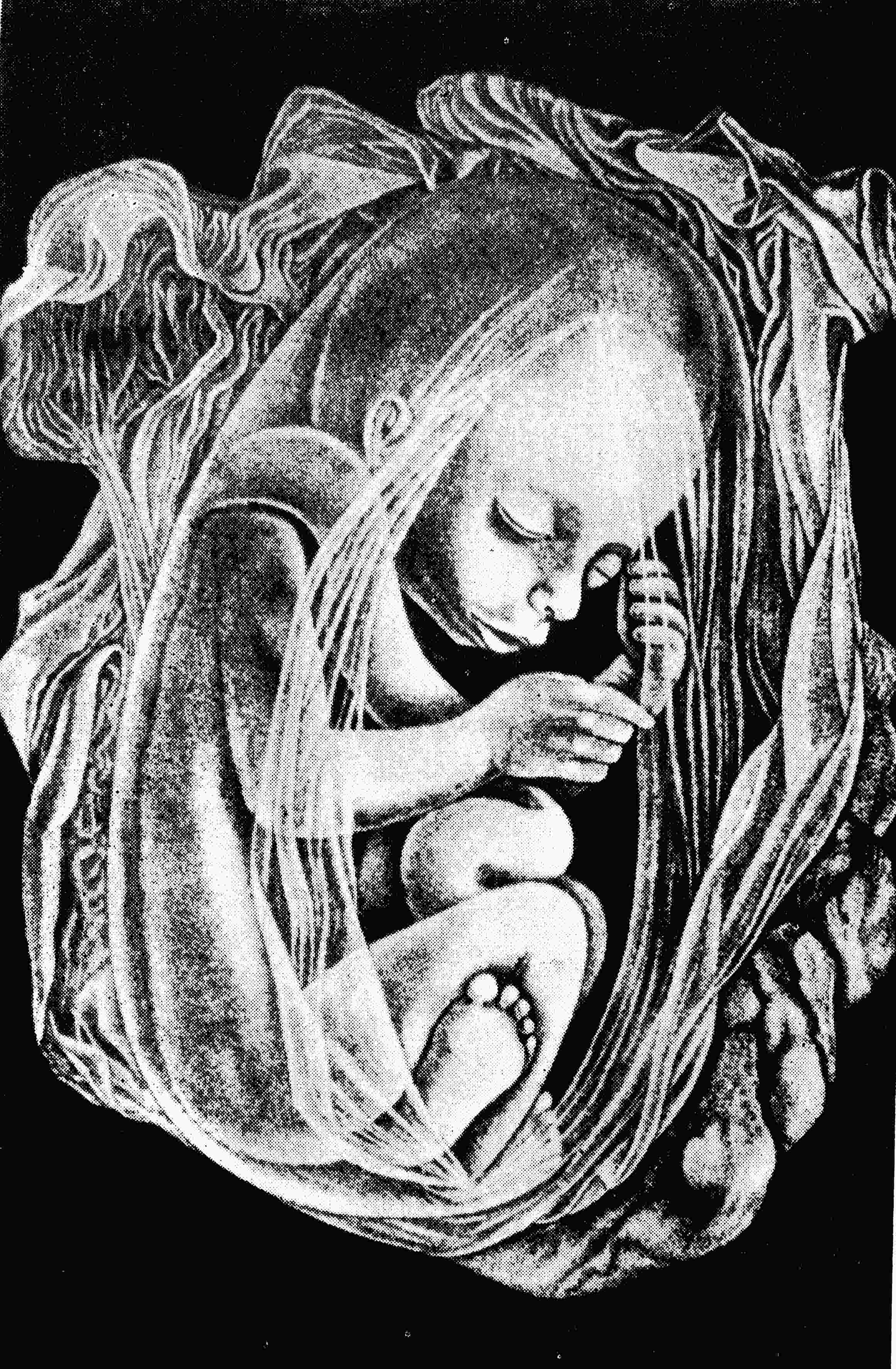
5箇月の胎児
胎児を包める薄き膜の嚢はいわゆる羊膜なり.この図にては羊膜の一部を縦に切り開きて内なる胎児を直接に示したり.胎児の肩の上に乗れるやや大き紐は臍の緒.
獣類の
胎児は
羊膜に
包まれた上をさらになお一つの
膜嚢に
包まれているが、この
膜嚢は母親の
子宮の内面に
密接しているから、親の体から子の体へ、
滋養分が
移り行くには、ぜひともこの
膜を
通過せねばならぬ。親から
容易に
滋養分を
吸い取り
得るために、この
膜の外面からは、早くから
無数の細い
突起が生じ、親の
子宮の
粘膜にはまりこむが、発生がやや進むと、
胎児の身体から
血管が
延び出して、この細い
突起の内までも
達する。かくなると、子の
血管はあたかも
樹木の根が地中で細かく
分岐するごとくに、母の
子宮粘膜の内に根をおろして、そこから
滋養分を
吸収することができる。子の
血管が母の
子宮粘膜に根をおろしているところが、すなわち
胎盤であって、その
形状は
獣類の
種族によってさまざまに
違う。また
胎盤と
胎児の
腹とをつなぐ
紐はいわゆる
臍帯であるが、主として
胎児から
胎盤まで血の
往復するやや太い
動脈、
静脈が
縄のごとくに
撚れてできている。
カンガルーの
類は前にも
述べたとおり、
極めて早く小さな子を
産み出してしまうゆえ、
胎盤は全くない。子はただ
暫時母の
子宮内に場所を
借り、その
壁からしみでる
滋養液を少し
吸うだけにすぎぬゆえ、身体上からは親と子との
関係はすこぶる
簡単で、
産まれることもいたってたやすい。馬では
胎児を
包む
外嚢の全表面から細い
血管がたくさんに出て、親の
子宮粘膜にはまりこんでいる。
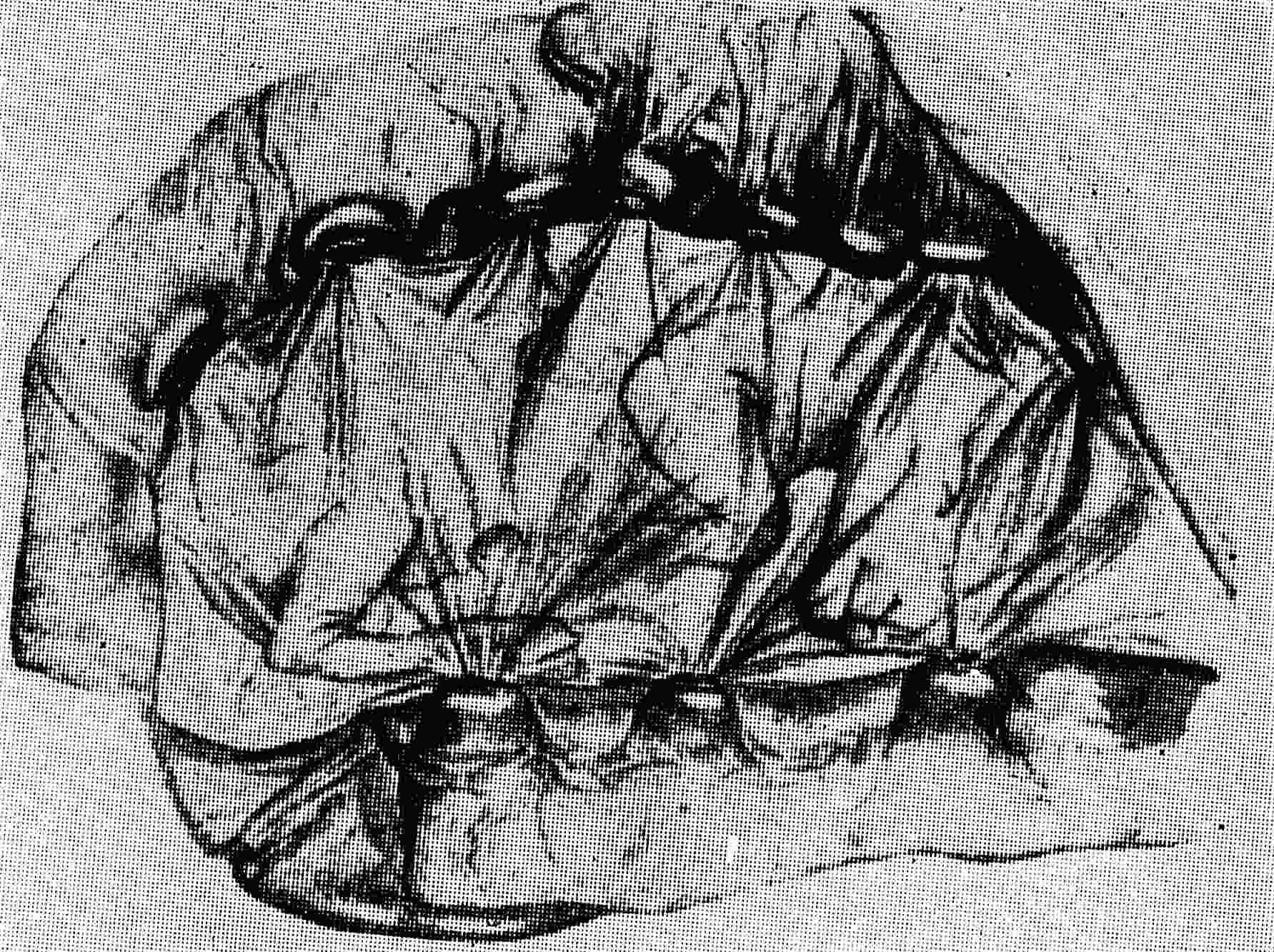 羊の胎盤
羊の胎盤
また牛、羊では同じく細い
血管がでているが、あたかも
豹の皮の
斑紋のごとくにいくつもの
塊となり、
各塊が
総のごとき形をなして
子宮の
粘膜内に
埋もれている。牛でも馬でも
胎児を
包む
嚢の
血管は、
子宮の
粘膜に
差しこまれた
体裁になっているが、
児が生まれるときには母の
子宮の
壁から子の
血管だけが
抜けて、
児のあとから出で去るゆえ、そのさい母親の身体は一部たりとも切れ
失うことはない。すなわち今まではまっていたものが、はずれて
離れ去るだけである。ところが犬、
猫、
猿、人間などになると、
胎児を
包む
膜嚢の表面から
突出している
無数の細い
血管は、母の
子宮の
粘膜と
固く
結びついてはなれぬようになり、子が生まれるときには、子の
血管と親の
子宮内面の
粘膜の一部とは
一塊となって出てくる。これがすなわち
胎盤であるが、牛、馬のとは
違うて、親の
組織の一部が切れはなれて子を
包む
膜とともに出るゆえ、そこの
血管は
当然破れて、
出産の
際にはいちじるしく出血する。犬、
猫、「いたち」などの
食肉獣では、
胎盤は
幅の広い
帯の形で
胎児の
胴のところをゆるく
巻いているが、
猿や人間では
円盤状で、あたかも
蓮の葉を
厚くしたごとくに見える。
 手長猿の胎児と胎盤
手長猿の胎児と胎盤
しこうして
普通の
猿類では
蓮の葉を
二枚ならべたごとき形がつねであるが、ただ
猩々、
手長猿の
類と人間とだけは
蓮の
葉一枚のごとくである。されば
普通の
猿と
猩々と人間とをならべ、
胎盤の形にもとづいて
分類すれば、人間と
猩々とを合わせて一組とし、他の
猿類と
相対立せしめねばならぬが、この事は
解剖上、発生上、ならびに
血清反応の
調査などの
結果と実によく
符合する。すなわち、人間と
猩々、
手長猿などのごとき高等の
猿類との間の
血縁の
程度は、高等の
猿と
尾を有する
普通の
猿類との間の
血縁の
程度に
比して、さらにいっそう近いことが明らかに知れる。
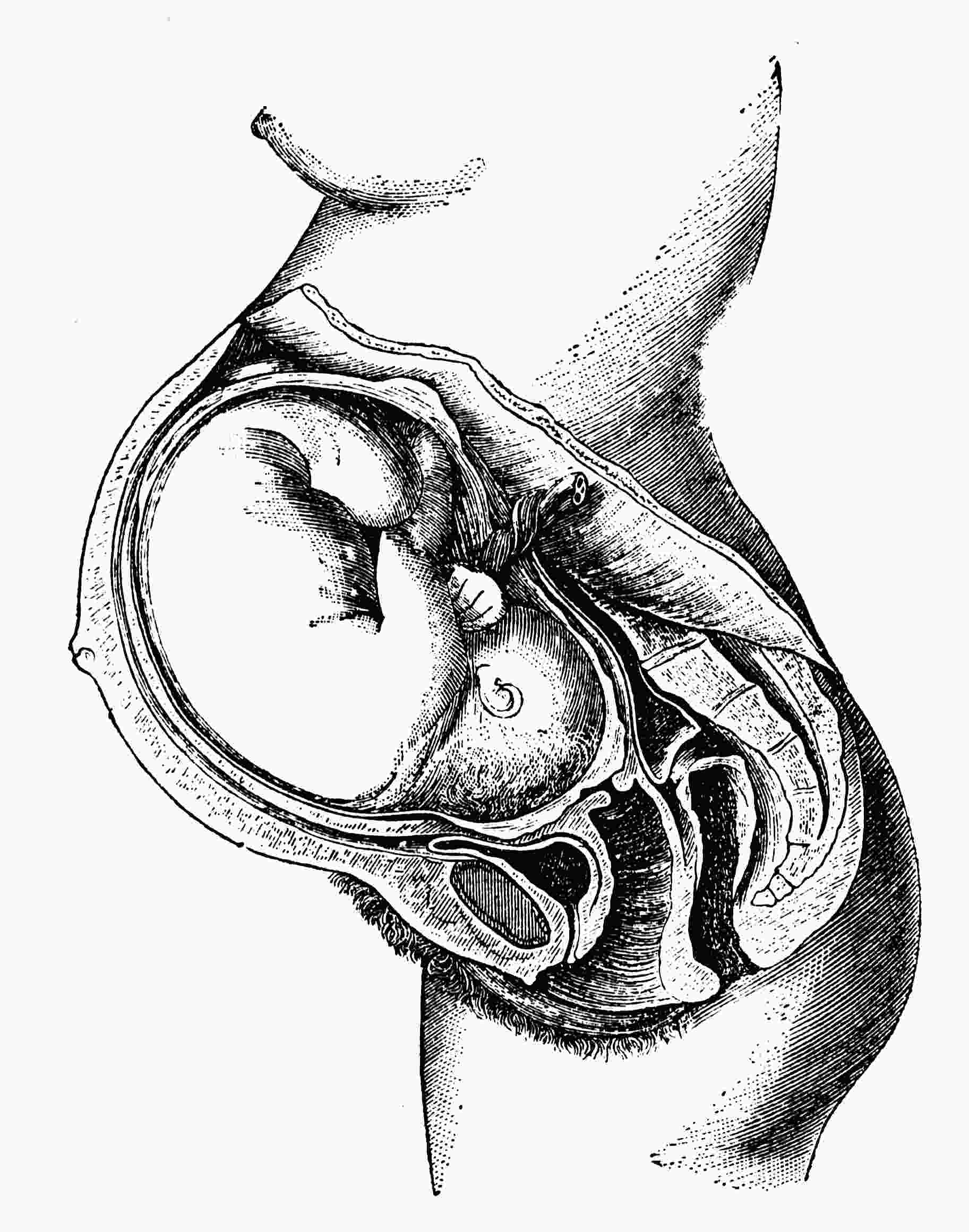 臨月の胎児
胎盤
臨月の胎児
胎盤の
発達は
胎生をますます
完全ならしめるものであるが、親と子との
結合が
密接になるだけ、
出産の
際に
相離れることが
困離になるをまぬがれぬ。ただ
子宮内に子をとどめておくだけならば
出産は
極めて
容易であるが、その代わりに子を長く十分に
養うことができず、
胎盤が
完全に
発達すれば、子を長く
養うにあたって
不足のない代わりに、
出産の
際にはこれが母体から
離れるための
臨時の
苦痛が生ずる。子を
包む
膜の表面から出ている
血管の
突起が、
簡単に
子宮の
粘膜に
差し入っただけならば、あたかも地から
杭を
抜くごとくに、それだけを
抜き取ることができるが、
血管が細く分かれて
子宮粘膜内に根をおろしたようになると、これを
離すのは
容易でない。あたかも根の
張った
樹を力まかせに引き
抜けば、
多量の土がとれて大きな
穴があくごとくに、そのとれた
跡には大きな
傷が
残る。
分娩の
際の出血は、この
傷から出るのである。また
完全な
胎盤によって子が十分に
養われ、大きくなればこれを
狭い
産道から
産み出すときの苦しみは一とおりではなくなる。されば
胎生にも
便と
不便とがついてまわり、一
程度まで
達した
以上はもはやその先へは進まれぬ。人間のごときも、
現在よりもなおいっそう
脳の
発達した頭の大きな赤子を
産むことはとうてい
望まれぬであろう。
胎盤における親子の
血管の
関係を見るに、
如何に
密接しても直ちに
連絡するところはけっしてない。すなわち同一の血が、親の体と子の体とを
循環するごときことはけっしてなく、ただ子の
血管が親の
血管の多い
組織内に根のごとくに
拡がっているだけである。子は
血管を親の
組織内に
延ばし
拡げて親から
滋養分を
吸い取るのであるゆえ、この点からいうと、
獣類の
胎児は
一種の
寄生虫とも見なすべきもので、母親は
種族維持の
目的のために一身を
犠牲に
供し、大きな
寄生虫の宿主となっている
次第である。
卵巣内にある
卵細胞はたしかに母の身体の一部であるが、すでに
卵巣をはなれ
受精した後は、もはや新たな一
個体であって、ただ母の体内に場所を
借りているにすぎず、さらに
血管を
延ばして母の身体から
滋養分を
吸い取るようになれば、
純然たる
寄生生活に
移ったわけで、
産まれ出るまでは
一種の内部
寄生虫である。また
産まれてからは、宿主の
皮膚の一部に
吸いついて
滋養分を取るゆえ、
一種の外部
寄生虫となり、
乳を飲まなくなってからは
蟻の
巣の内に
寄生している
甲虫などと同様な
巣内
寄生虫となる。親が
毒を食えば
胎児もその
害をこうむり、親が病にかかれば
胎児にもその病が
伝わりなどして、その間の
関係はすこぶる
密接ではあるが、
胎児はけっして母の身体の一部をなすものではないゆえ、
妊娠中に母に起こった
変化がそのとおりに子にも
現われるということはない。日の出の
夢を見て
孕んだら
英雄豪傑が生まれたとか、
妊娠中に火事を見て
驚いたら、生まれた子の
額に火の形の赤い
痣があったとかいう話はしばしば聞かされるが、これはおそらくつくり話か思い
違いかであろう。もとより肉体と
精神との間には
密接の
関係があるゆえ、母が
妊娠中に心配をしたために
虚弱な
児が生まれたというごときことならば、あり
得べきように思われるが、
妊娠中に
論語の
講釈をきいたら
聖人が生まれ、ジゴマの活動写真を見たら
泥棒が生まれるというごときことはまずなかろう。母親が
妊娠中に
摂生に意を用いることは、
種族維持の上にもっとも大切なことゆえ大いに
努めなければならぬが、
胎教に言うごとき
胎児の
品性の
陶冶が
妊婦の
心掛けによってできるや
否やはすこぶる
疑わしいと言わざるをえない。
自分の身体は
初め
如何にしてできて、
如何なる
状態の時代を
順次経過し来たったかを知ることは、人生について考えるにあたってもっとも
必要である。これを知ると知らぬとでは、人生に
関する
観念に
非常な
相違を生じ、場合によっては正反対の
結論にたっせぬともかぎらず、またこれを知っていてもしばらく
忘れていると、やはり
異なった
観念を
抱くにいたりやすい。さればいやしくも人生を
論ぜんとする者は、一とおり生物
個体の発生
特に人間の身体のでき始めの
模様を知っておく
必要があろう。実はこの
知識の
欠けた者は人生を
論ずる
資格がないようにも考えられる。本章と次の章とで
述べるところは、
人類および
普通の
獣類の
個体発生の
歴史の中から、もっとも
重要なと思われる点をいくつか拾い出して、その大体を
摘んだものである。
身体の発生について
特に
忘れてはならぬのは、その始めの
極めて
判然たることである。いまだ
顕微鏡を用いなかったころには、
精虫はいうにおよばず、小さな
卵も知られずにあったゆえ、人間その他の
獣類の子のできるのはあたかも
無中に有を生ずるごとき感があって、その間によほど
神秘的の
事情が
存するように思われたが、今日では母の
卵巣から
離れた
一個の
卵細胞と、父の
睾丸から出て母の体内に入りきたった
無数の
精虫の中の
一匹とが、
喇叭管内で
出遇い
相合して一の
細胞となるときが、すなわち子の
生涯の始めであることが明らかになった。
精虫が
卵細胞内にもぐりこみ、
核と
核とが
相合して、二つの
細胞が全く一つの
細胞となりおわるまでは、いまだ子なる
個体は
存在せぬが、これだけのことがすめば、すでに子なる
個体がそこにいるゆえ、
個体の生命には
判然たる出発点がある。地球上に
初めて人間なるものが
現われてから今日にいたるまでに、生まれては死に、生まれては死にした人間の数は、実に
何千億とも
何兆ともかぞえられぬほどの多数であろうが、これがみな一人一人
必ず父の
精虫と母の
卵細胞との
相合する時に新たにできたのであって、その前にはけっしてなかった人間である。しこうしてこれらの人間の
精神的の作用も毎回身体の発生に
伴うて
現われ、
脳の大きさが一定の度にたっすれば
意識が生じ、
脳が
健全ならばさまざまの
工夫をこらし、
脳に
腫物ができれば
精神が
狂い、
心臓麻痺によって
血液の
循環が止まれば、
脳に
酸素がこなくなって、
意識は
消滅してしまう。これらは、肉体は死んでも
魂はいつまでも
残ると
信ずる人等のよろしく
参考すべき事実であろう。
人間も他の動物と同じく、
個体の始めは
単一な
細胞である。
受精のすんだ
卵細胞も、
受精前の
卵細胞も大きさは少しも
違わず、外見は同じようであるが、
生存上の
価値には
非常な
相違がある。人間の
卵は
受精前も
受精後も
直径わずかに一分の十五分の一(注:0.2mm)に
過ぎぬ球形の
細胞であるが、
受精する
機会をえられなかったものは、ただ母体の
組織から
離れた一の
細胞として、その運命は
皮膚の表面や'
頬の内面から取れ去る
細胞と同じく、
捨てられて死ぬのほかはない。これに反して、
受精のすんだ
卵は始めしばらくは
単一の
細胞であるが、これが
基となって
種々複雑な
変化発育をとげて、ついに赤子となり
成人となるのであるから、すでにその
種族を代表する一の
個体と見なさねばならぬ。
法律では
何箇月以上の
胎児は人間と見なすが、それ
未満の
胎児は物品と見なすという
規定があるとか聞いたが、これはもとより
便宜上の
必要から止むをえずつくった勝手の定めで、学問上からは何の
根底もない。
理屈から言えば、
受精のすんだ
卵の時代まで
溯っても、やはり
一個の人間に
違いないゆえ、
我らは
誰でもでき始めには、「アメーバ」や「ぞうり虫」と
同格の一
細胞であったと言わねばならぬ。ただ「アメーバ」や「ぞうり虫」が
独立自営の生活をしているに反し、親の体内に
保護せられ親から
滋養分の
供給を受けて、
寄生的の生活を
営んでいたというだけである。
さてかような
単細胞のものが
基となって、
如何にして
無数の
細胞よりなる身体ができあがるかというに、これまた「アメーバ」や「ぞうり虫」の
繁殖と少しも
違わぬ
分裂法による。
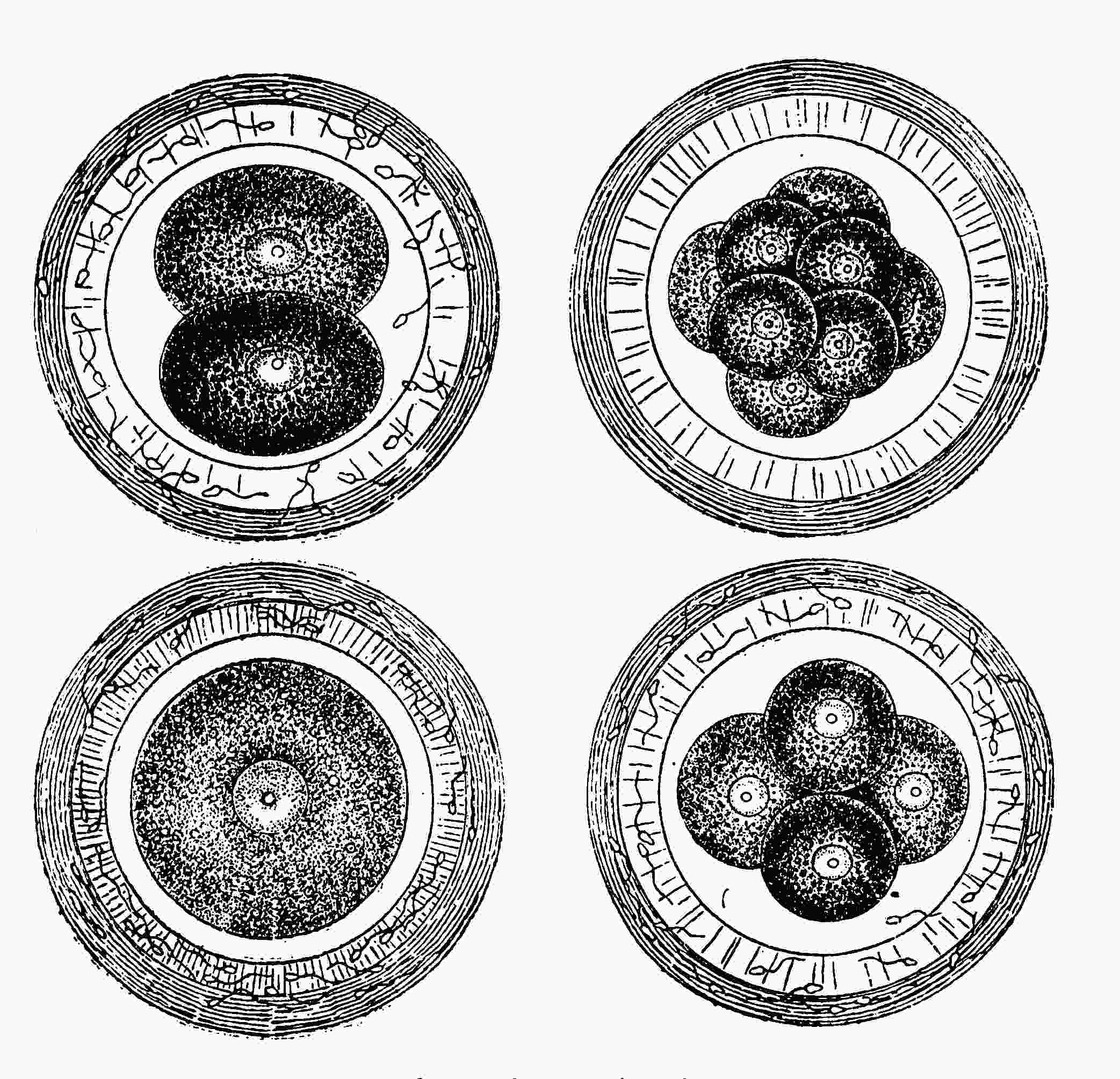 兎の卵の分裂
兎の卵の分裂
次にかかげた図は
兎の
受精後の
卵が
順々に
分裂して、
細胞の数の
殖えてゆくありさまを
示したもので、
初め
一個の球形の
細胞は二分して
楕円形のもの
二個となり、これがまたそれぞれ二分して
都合四個となり、さらに
分裂して
八個十六個三十二個六十四個というように速かに数が
増すと同時に、
各細胞の大きさは
減じてたちまちにして小さな
細胞の
一塊となる。この時代には子の身体はあたかも
鹿の
子餅か
桑の実のごとくに見えるゆえ、
桑実期と名づける。これと同じ
状態で
独立自営の生活をしているものを
求めると、水中に
棲息する原始
虫類の
群体がちょうどそのとおりで、数十もしくは数百の同様な
細胞が
一塊となり、
相離れぬように
透明な
膠質のものでつながっている。すなわち「アメーバ」や「ぞうり虫」に
似たものが
相集まり、一
群体をなして水中に
浮かんでいるのであるゆえ、
構造からいうと
桑実期の
幼児と少しも
違わぬ。
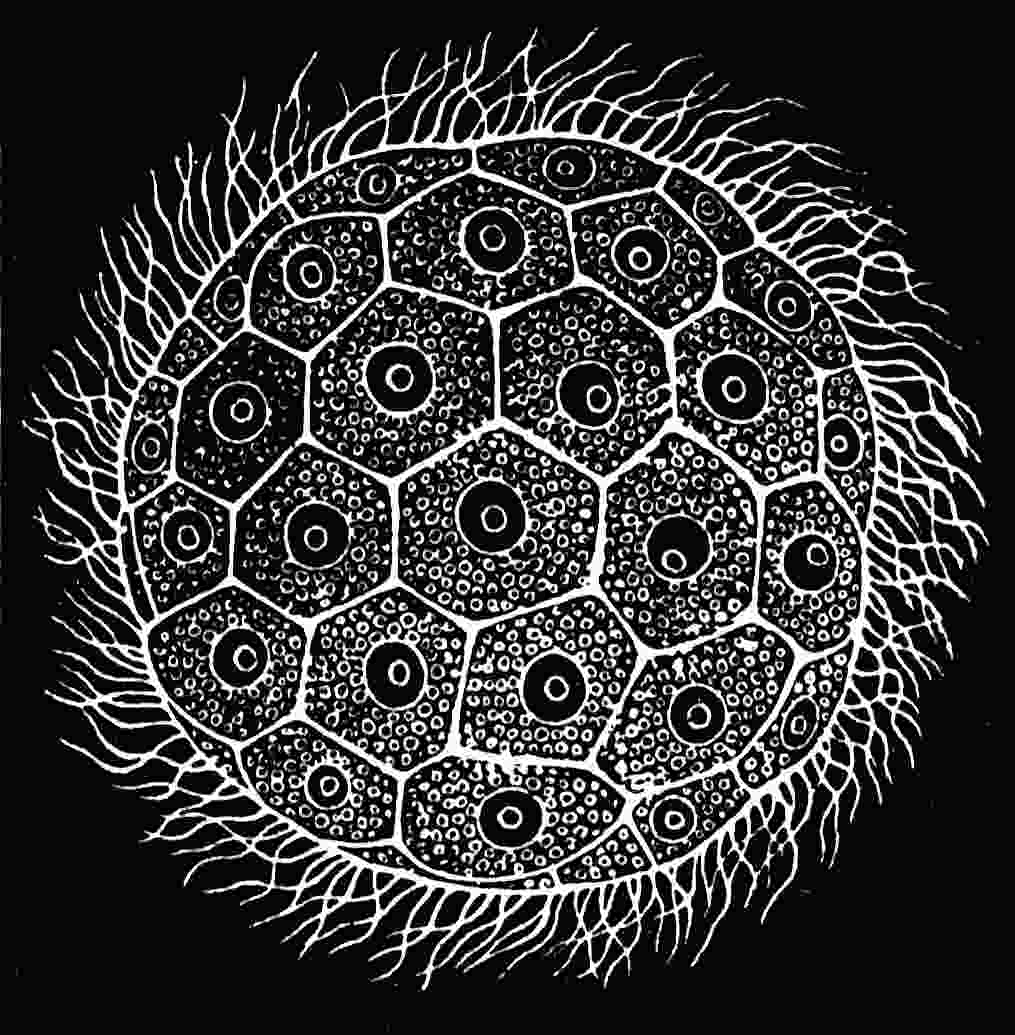 原始虫類の群体
原始虫類の群体
人間の
受精した
卵が
分裂して
細胞の数の
殖えるありさまを
直接に見た者はいまだ一人もない。その理由は
説明するにもおよばぬ明白なことで、人間の
卵と
精虫とが
出遇うことは毎夜
各処で行なわれているが、
受精後直ちに女を
殺してその
輸卵管内を調べることは一回も行なわれぬゆえである。しかし人間のその後の発生が犬、
猫、
兎、
鼡などと全く同様であり、かつこれらの
獣類の
桑実期にたっするまでの
変化がことごとく
一致しているところから考えると、人間でも
兎でもこのころの発生
状態が全く同じであることは
疑いない。これは
類推ではあるがけっして
間違いのない
推察で、あたかも
明朝も太陽は東から出るであろうという
推察と同じく、大地を打つ
槌ははずれても、こればかりははずれぬというくらいに
確かなものである。すなわち人間の
個体のでき始めは、前に
述べたとおり
単一の
細胞であるが、次には
細胞の数が
殖えて原始
虫類の
群体と同様の時代を
経過する。しこうしてこの時代にはいまだすべての
細胞が同様であって、その間に少しも
相違が見えず、また分業の行なわれる様子もない。
或る人の計算によると、
成人の身体は
三十余兆の
細胞からなるとのことであるから、赤子の身体には
約二兆の
細胞があると見なしてよろしかろうが、これがみな
最初の
単一な
細胞の
分裂した
結果である。一つから二つ、二つから四つというごとくに毎回二倍ずつに
殖えるとして、何回
分裂すればこの数に
達するかとかぞえて見ると、おおよそ四十回ですむ。されば赤子の身体は
細胞の数のみについていうと、あたかも「アメーバ」が四十回も引き
続いて
分裂生殖を行なうただけの
細胞が
一塊をなしているものに相当する。ただ「アメーバ」のほうは何万
何億に
殖えてもみな同じような
細胞であるが、人間のほうは発生が進むに
従うて、
細胞間に分業が行なわれ、おいおい
複雑な
組織や
器官ができるので、
驚くほど
違った
結果を生ずるのである。
さて
桑の実のごとき形になった
子供は、次には
如何に
変ずるかというに、
細胞の数が
相応に
殖えると、これがみな
一層にならんであたかもゴム
球のごとき中空の球となり、さらに球の一方がくぼみ入り内部の空所がなくなって、ついに二重の
細胞層よりなる
茶碗のごときものとなる。これだけのことは
如何なる動物の発生中にも
必ずあるが、
卵細胞が
多量の黄身を
含んで大きいか、または黄身を
含まずして小さいかによって、明白に見えるものとしからざるものとがある。なぜというに、黄身を
含まぬ小さな
卵は
分裂するにあたっても、全部分かれて
完全に二つの
細胞となることができるが、黄身を
含んだ大きな
卵であると、黄身がじゃまになって
完全に
分裂することができぬ。
鶏の
卵などは
細胞がいくつに分かれても、
最初の間は黄身の表面の一部にひらたくならんでいて
桑の実のごとき形にはならぬ。
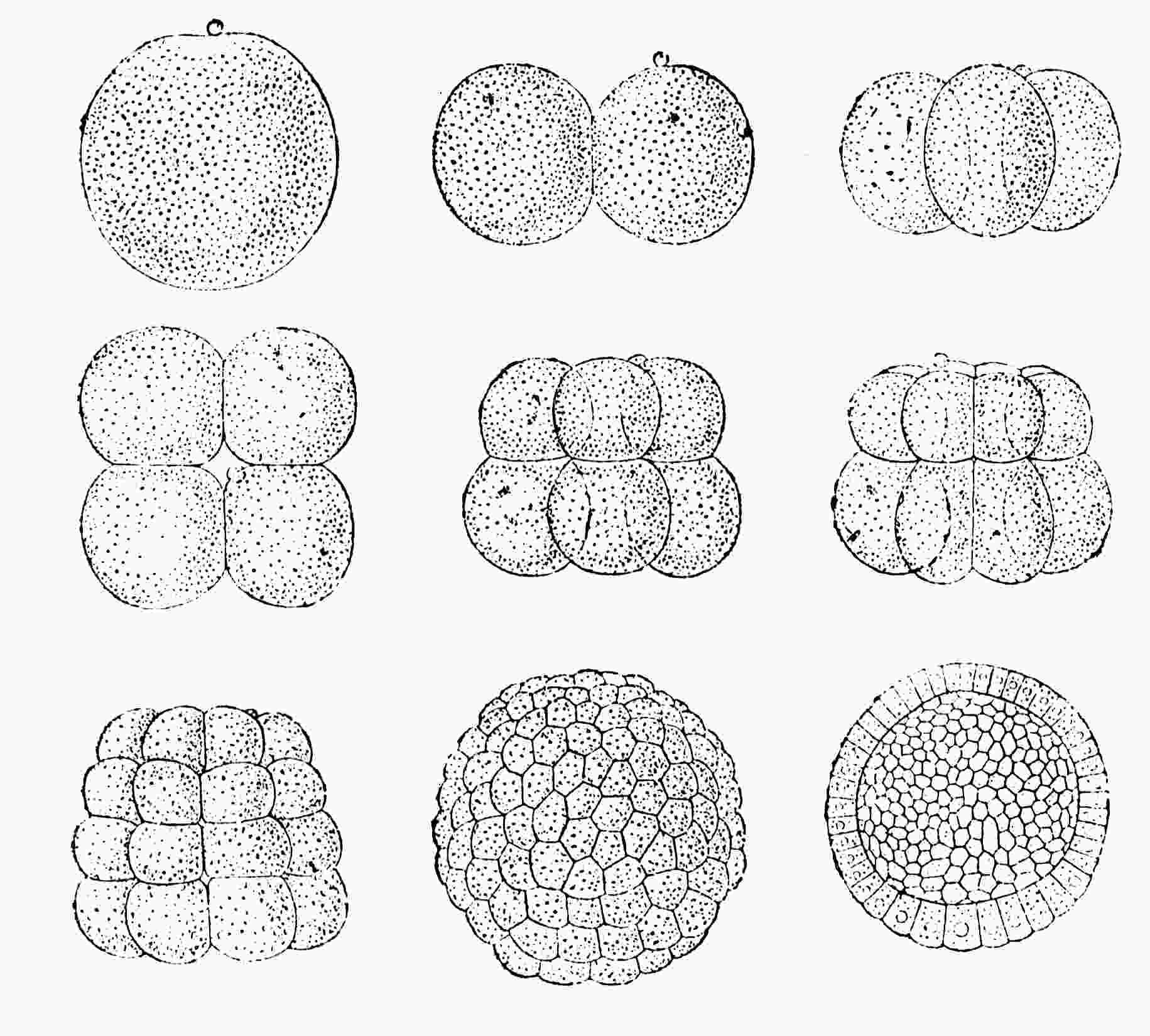 なめくじうおの発生
なめくじうおの発生
しかし他の小さな
卵の発生に
比較して調べて見ると、
鶏の発生にも、やはり
桑実期があって、ただ黄身のために
妨げられて
桑の実のごとき形にならぬだけであることが明らかに知れる。球形になり
茶碗の形になるときもこれと同様で、
鶏の発生では、この時代の
変化がなかなかわかりにくいが、黄身のない小さな
卵で調べると
極めて
明瞭になる。
脊椎動物の中でもっとも下等なものに「なめくじうお」という長さ
一寸(注:3cm)
余の頭のない
奇態な魚があるが、その
卵からの発生を見ると、
以上の
茶碗の形になるまでの
変化がすこぶる明らかであるゆえ、
脊椎動物の発生の見本として図を
掲げておく。
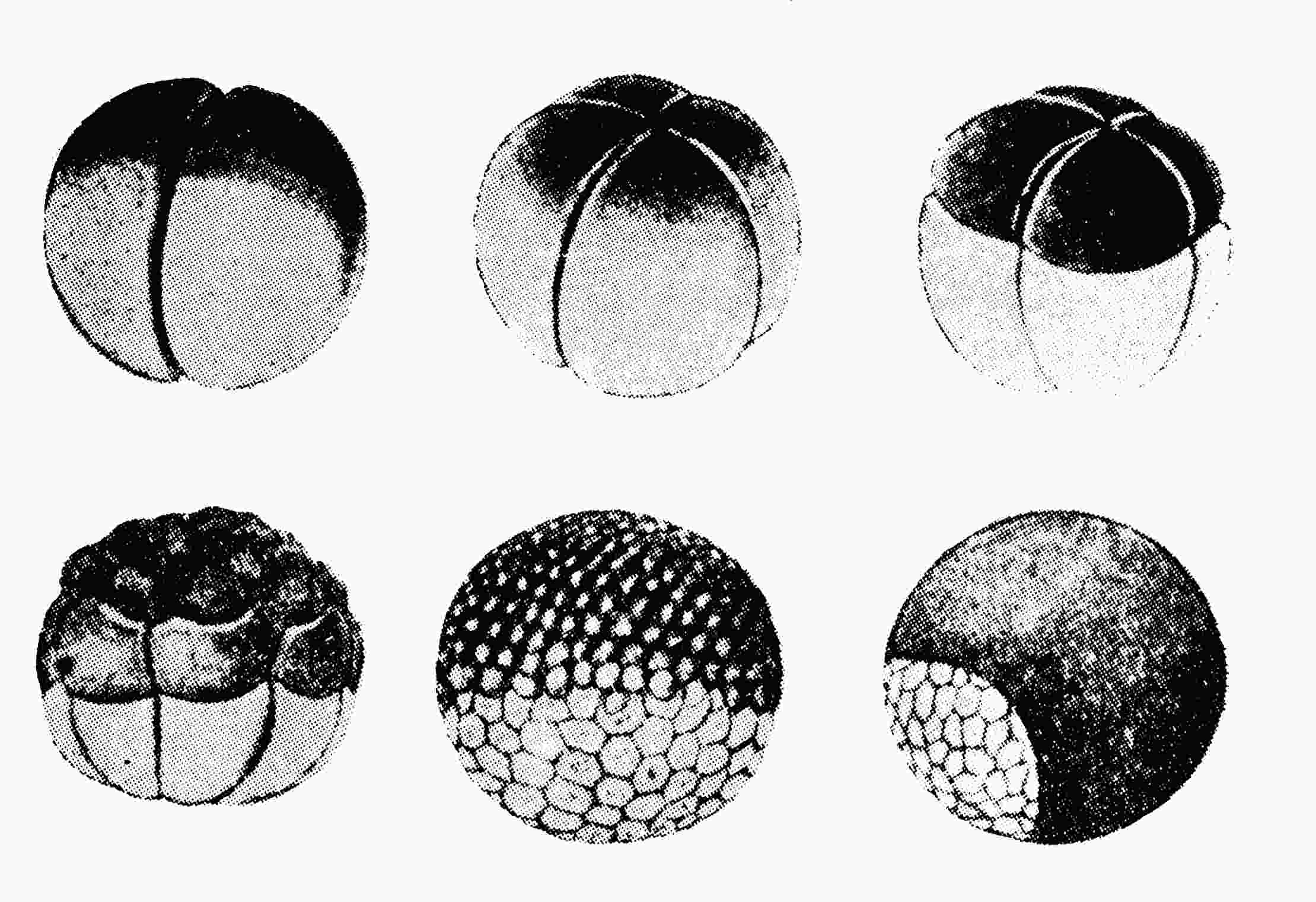 蛙の卵の分裂
受精
蛙の卵の分裂
受精のすんだ
卵細胞が
分裂してたちまちの間に
無数の小さな
細胞の
塊となることだけならば、
蛙の
卵についても
容易く
観察することができる。
獣類の
卵は、あたかも「なめくじうお」の
卵のごとく黄身を
含まず小さいが、その発生は少しく
異なったところがある。しかし大体においてはこれと同様で
桑実期の次には、やはり二重の
細胞層よりなる
茶碗形の時代がくる。
茶碗はまた深くなって
湯呑みや
壺の形になるが、この時代に
達すると、外の
層の
細胞と内の
層の
細胞との間にだんだん
相違が
現われ、
外層のは小さくて数が多く、
内層のは大きくて数がやや少なく、その
働きにも分業が始まり、外
細胞は主として
感覚をつかさどり、内
細胞はもっばら消化をつとめるようになる。
独立自営する動物でこれと同様の
構造を有するものは「ヒドラ」、「さんご」、「いそぎんちゃく」の
類であるが、これらはいずれも身体は
湯呑みのごとき
筒形で、内外
二枚の
細胞層よりなり、
一端には口があり、
他端は
閉じている。発生の
途中とは
違い、自ら
餌を
捕えて食わねばならぬゆえ、そのための道具として口の
周囲に
若干の
触手を
備えているが、これを取り
除いて考えると、他の動物の
湯呑み
状の時期のものと
構造が全く
一致する。
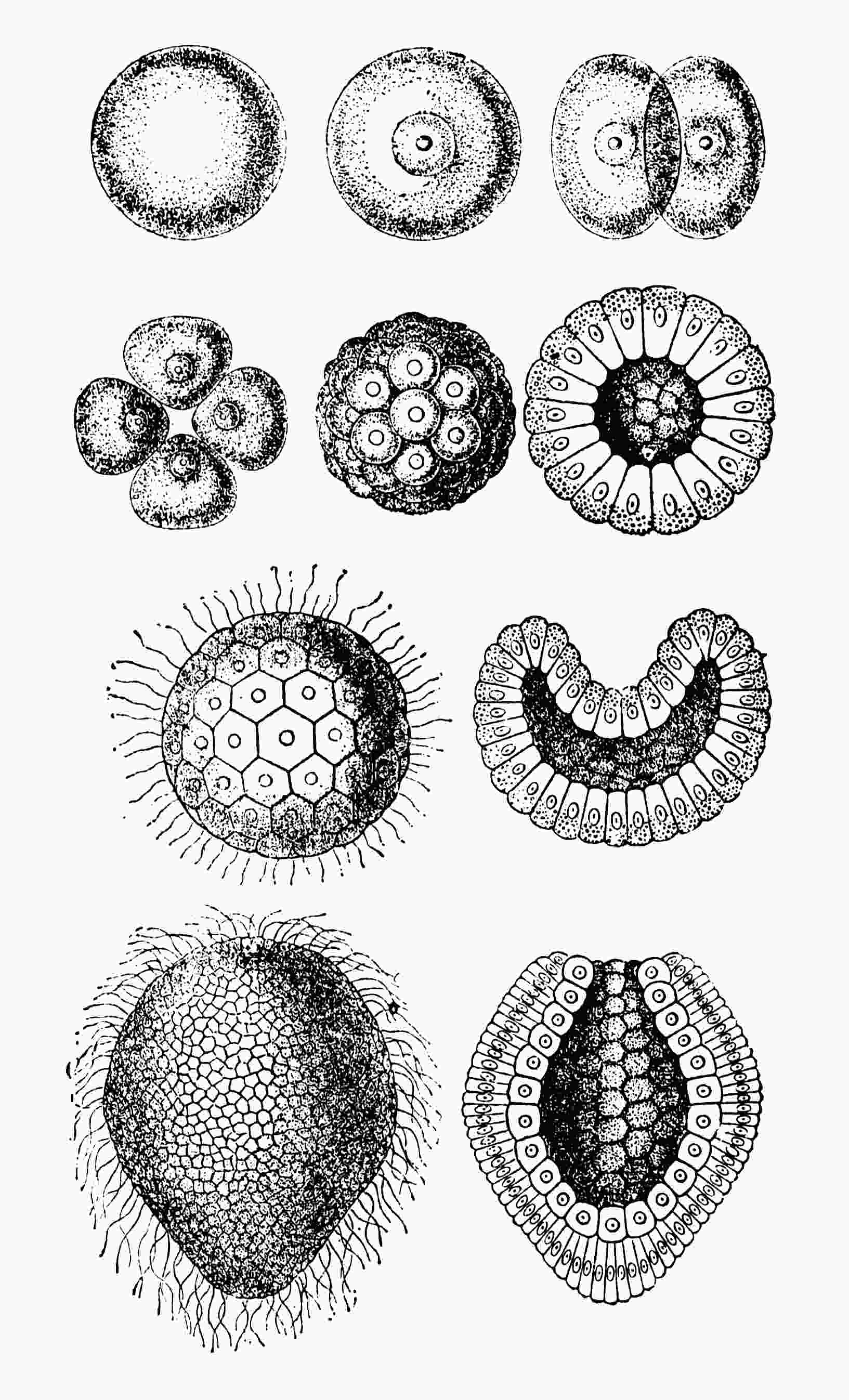 さんごの発生
さんごの発生
すなわち「さんご」は「なめくじうお」などの発生の道を、
湯呑み
状の時期までともに進みきたり、そこで
成長が止まったものと見なすことができる。言い
換えれば、
我々の発生の
初期には、一度「ヒドラ」、「さんご」などと同様な
構造を有する時代を
経過するのである。しこうして「さんご
類」の体内にある空所は食物を消化するところゆえ、
胃と
呼ぶのが
適当であるが、高等動物の発生中の
湯呑み
状の時期も、これにくらべて
胃状の時代と名づける。すなわち
我ら人間も発生の
初めには他の
諸動物と同じく、一度全身が
胃嚢のみである時代があって、
神経や
骨のできるのはそれよりはるかに後である。
或る
文士の
文句に「筆は一本なり。
箸は二本なり。
衆寡敵せずと知るべし。」と、あったように
覚えているが、発生を調べて見ても、食う
器官がまず
最初にできて、思想の
器官はよほど後に
現われる。人生第一の問題は何としてもパンの問題である。
単一の
細胞が
分裂してまず
細胞の
塊となり、次いで二重の
細胞層よりなる
胃状の時代に
達するまでは、
変化が
比較的に
簡単であるが、これより先は
構造がだんだん
複雑になって、
詳しく書けばそれだけでもすこぶる大部な書物となるほどであるゆえ、ここにはもとよりその
一斑をも十分に
述べることはできぬ。しかしながら、その中には人生を考える人々のためによい
参考となるであろうと思われる点がいくらもあるゆえ、その二三をえらんで
要点だけを次に
略述する。
 蛙の発生
胃状
蛙の発生
胃状の時代に
達するまでは、
子供の身体は
茶碗、
湯呑み、
壺などと同じく、ただ
裏と表とがあるばかりで前後左右の
差別はないが、この時代を
過ぎると、身体がおいおい前後に
延びて頭と
尾との
区別が
現われる。この
変化は、
蛙の
卵でもっとも
容易に見ることができるゆえ、まずその図をかかげてこれに人間の
子供を
比較して見よう。
蛙の
卵が
分裂して
桑実期を
過ぎ、
胃状の時代に
達するまでは外形はつねに球のごとくで、前後もなければ左右もないが、この時代を
過ぎると、球形の上面に細長い
溝が生じ、
溝の
両側はあたかも土手のごとくに高まるゆえ、
溝がいっそう明らかになる。この
溝のできる場所は後に身体の
背となる
側で、
溝の
両端の向いている方角は身体の
前端と
後端とにあたる。
溝の
両側の土手は、
溝の
一端を
囲んで
相連絡し、
特に大きな土手をなしているが、これが後に頭となる部分である。これらの土手は後に
脳脊髄となるものゆえ、
神経の土手と名づけ、その間の
溝を
神経の
溝と名づける。発生が進むにしたがい、
神経の土手は高くなり、
神経の
溝は深くなり、ついに
閉じて
管となれば、体内に
隠れて表面からは見えなくなる。
神経の
溝が
現われてからは、今まで球形の
蛙の子の身体に前後の方角が明らかに知れるが、それよりは身体がおいおい前後の方向に
延びて長くなり、球形は
変じて
卵形となり、
卵形は
変じて
瓜の形となり、そのうちには、頭は頭、
尾は
尾として形が
判然するようになり、いつとはなしに「おたまじゃくし」の形に
似てくるのである。
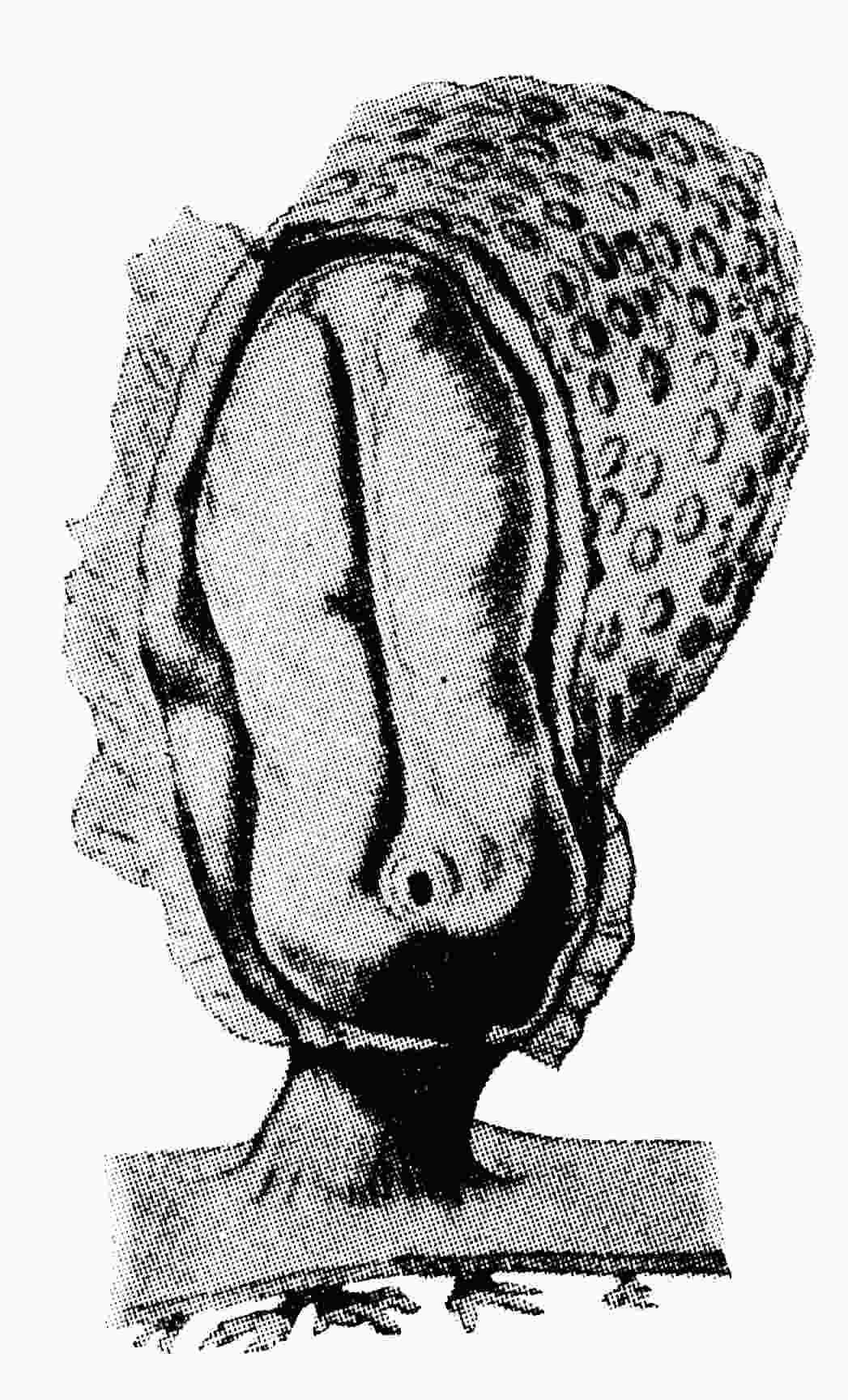 第2週の胎児
第2週の胎児
人間の子も
桑実期や
胃状の時代には、「ヒドラ」や「さんご」などと同様で、いまだ身体に前後の
区別がないが、第二週の終わりころにはすでにいちじるしく前後に
延びて、あたかも
草履のごとき形となる。前にも
述べたとおり、人間では他の
獣類、
鳥類、
蛇、「とかげ」などと同じく、早くから
胎児を
包む
膜嚢ができるゆえ、
蛙にくらべると発生の
模様がいくぶんか
複雑になるをまぬがれぬが、これらの点を
除いて身体だけを
互いにくらべて見ると、第二週の人間の
胎児は、やや長くなりかかった
蛙の子にすこぶるよく
似ている。すなわち図に
示したとおり、体の
背面の中央には一本の
縦溝があるが、これが
神経の
溝である。またその下に小さな
孔が見えるのは、
神経腸孔と名づけるもので、後に一時
脳脊髄内の空所と
腸内の空所とを
連絡する
管である。この
管は
蛙にもあれば鳥にも
獣にもある。
高尚な思想を
産み出す
脳髄の内の空所と、
大便の
溜まり場所なる
大腸とが、発生中たとい一時なりとも
管によって
直接に
連絡していることは、
初めて聞く人には定めし
奇怪な感じを
与えるであろう。
胎児の身体が
縦に
延びて大分長くなったかと思うと、直ちにその中央部に
若干の
節が
現われる。始めはわずかに三つ四つの
節がかすかに見えるだけであるが、たちまち
節の数も
殖え
境界もすこぶる明らかになる。
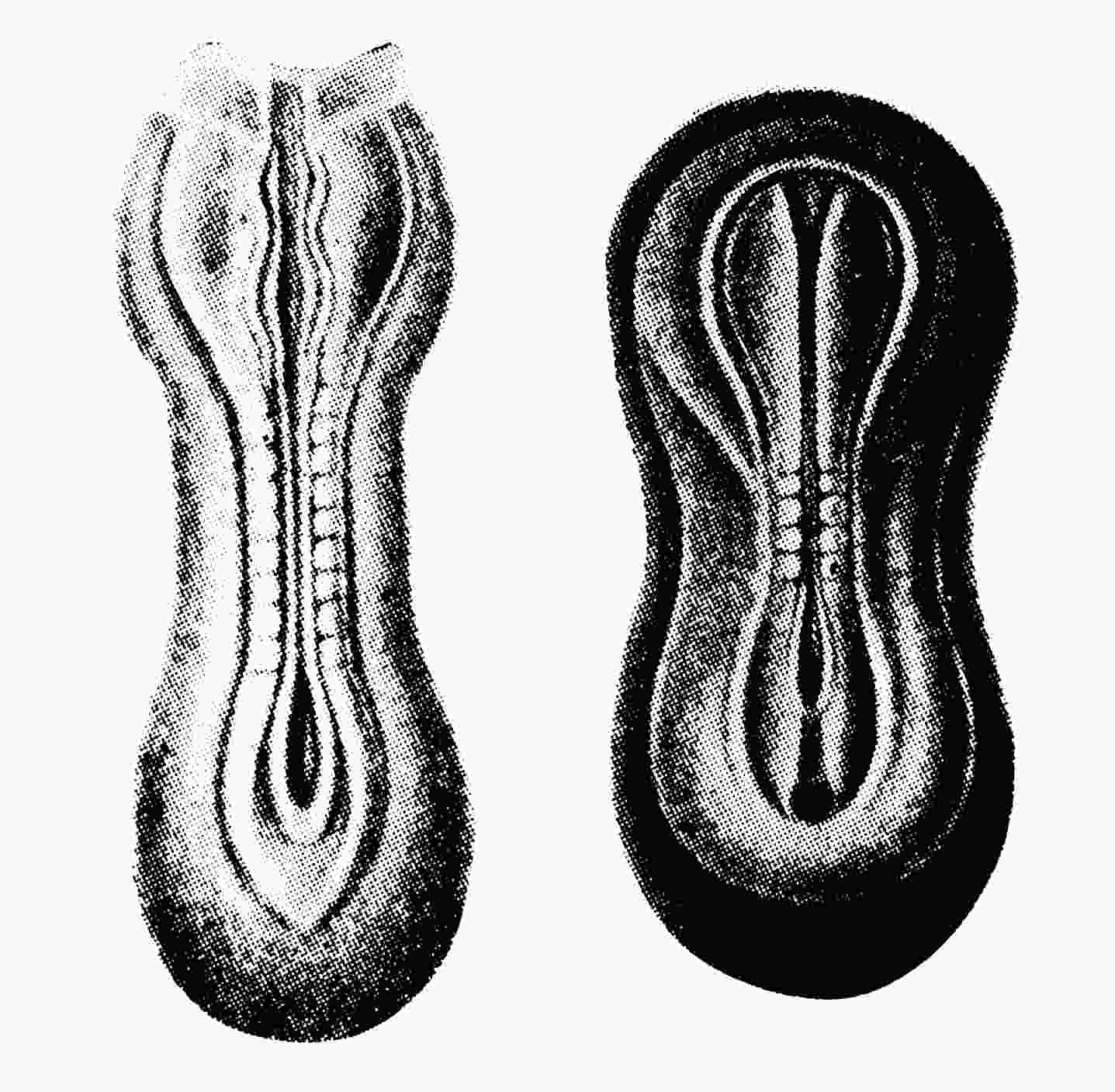
兎の胎児
(右)第8日目 (左)第9日目
図に
示したのは
兎の第八日目と第九日目との
胎児であるが、体の
中軸にあたるところに
脊髄があって、その左右
両側にいくつかの
節が見える。第八日目のものではその数が四つ、第九日目のものでは八つだけあるが、後にはさらにその数が
殖える。人間の
胎児でも全くこれと同様で、第十六日ないし第十八日くらいの
胎児を見ると、頭部を
除いたほかは全身に明らかな
節が見えている。全体
脊椎動物の身体は前後にならんだ
節からなるもので、
魚類などではそれがもっとも明らかに見える。
煮肴の皮を
剥くと、その下の
筋肉があたかも板を重ねたごとくなっているのは、すなわちかような
節である。人間や
獣類では、
腕や
腿を動かす
筋肉が大きいために、
胴の
筋肉の
節が十分に
現われぬが、それでも
腹の前面の
筋肉、
脊骨の後の
筋肉、
肋骨の間の
筋肉などには明らかに
節がある。
胎児の
若いときにはいまだ手も足もなく、身体は
単に
棒のごとくであるゆえ、どこにも
節が
極めて
明瞭に見える。
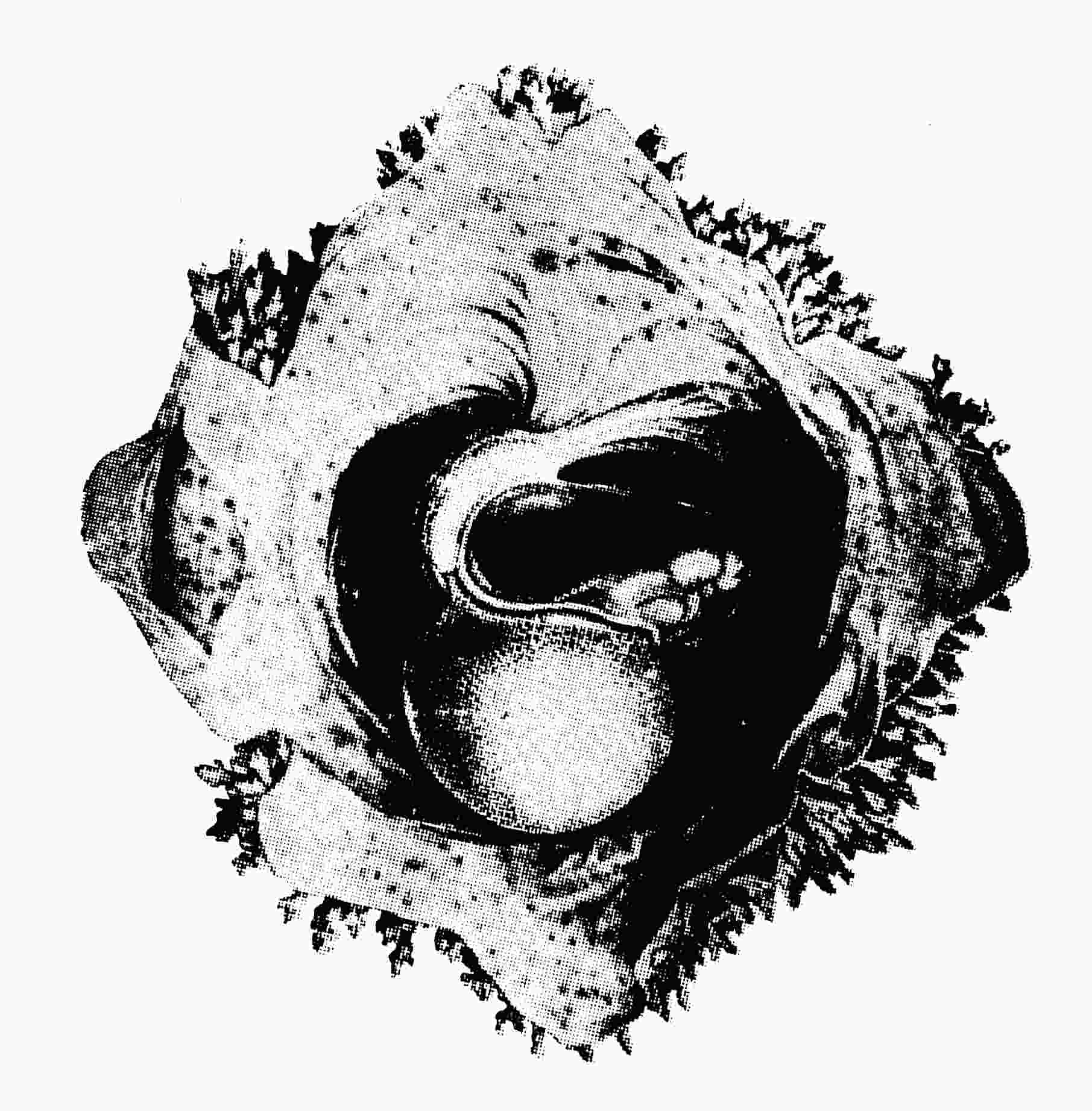 16日ないし18日における子宮内の胎児
節
16日ないし18日における子宮内の胎児
節が生ずると同時に、身体の内部に
体腔と
称する広い空所ができる。
獣でも鳥でも
魚類でも、
腹面から切り開くと一つの広い空所があって、その内に
肝、
胃、
腸、
腎などすべての
臓腑がしまってあるのを見るが、この空所がすなわち
体腔であって、これを
囲む
壁を
体壁と名づける。
腹の
壁は
体壁の一部であるが、これを切り開くと
腸が
現われ、
腸の
壁を切り開くと
初めて
腸の
内容物が見える。かように
体壁と
腸壁との間には一つの広い空所があるが、これがすなわち
体腔である。しかるに動物の中には
体腔のあるものとないものとがある。
例えば「ヒドラ」とか「さんご」とかいう
類は、体の
構造が
簡単で、あたかも
湯呑みか
壺のごとき形をしているゆえ、
体壁を切り開けば、直ちに
腹の内にある食物が
現われるが、かような
類には
体腔はない。
体腔のある動物と、ない動物とを
比較すると、ある動物のほうがすべての点で進んでいるゆえ、
体腔の
有無によって動物を高等と下等との二組に分けることができるが、人間の
胎児が十四五日ころから体内に
体腔の生ずるのは、すなわち下等の
無体腔類から高等の
有体腔類へ上りゆくところと見なすことができる。
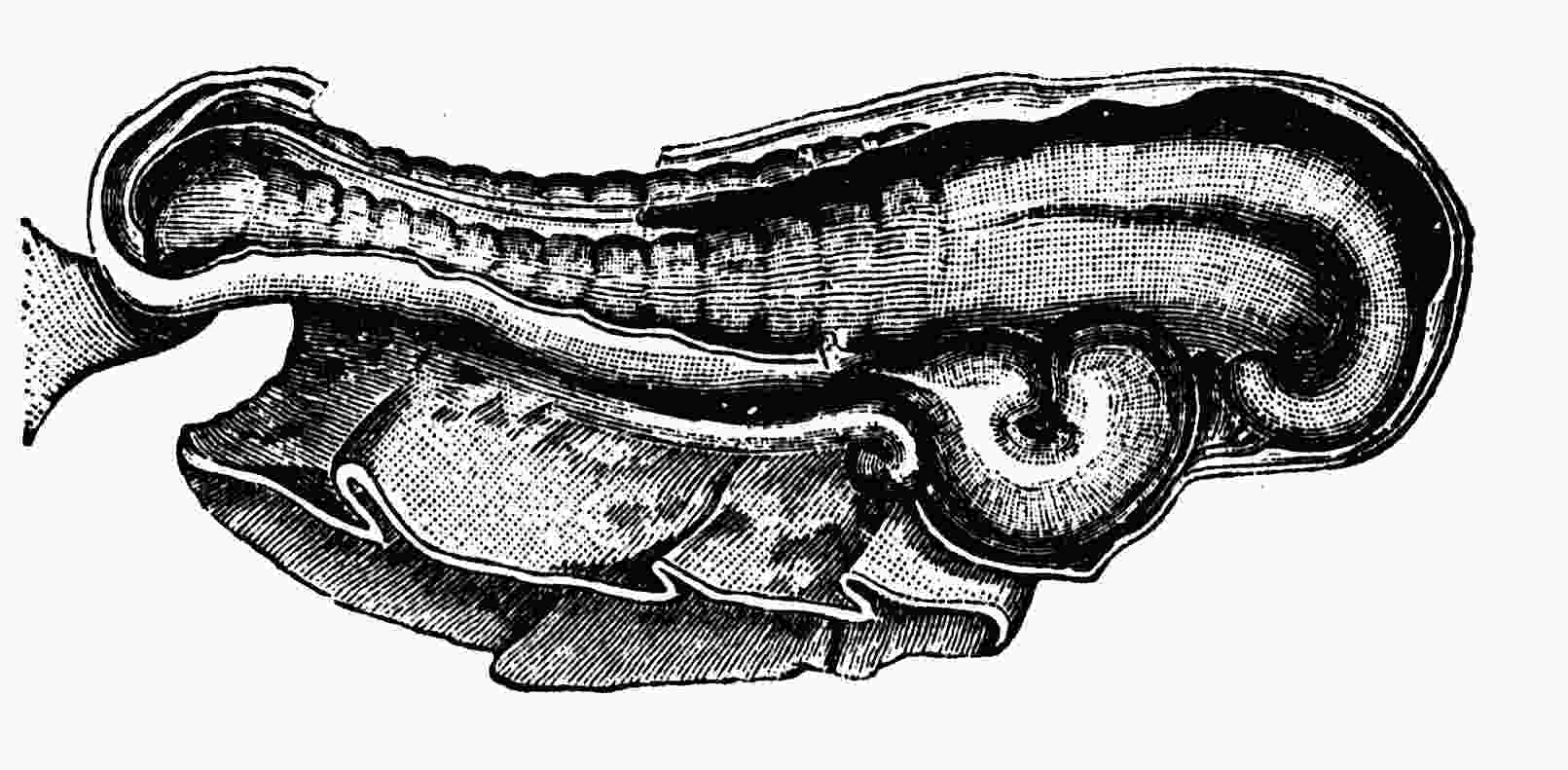 14日ころの胎児
初
14日ころの胎児
初めて
体腔のできる具合いは動物の
種類によって多少
異なるが、少しく進めばみな同様になってしまう。もっともわかりやすい
一例をあげて言えば、「なめくじうお」では
腸の
壁から左右対をなした
若干の
袋のごときものが生じ、後にこれが
腸から
離れ、
互いに
相連絡しかつ
拡がって
体腔となるのである。すなわち
体腔は
初め
腸の
枝のごときものであったのが、後に
腸と
縁が切れて
独立の空所となったわけにあたる。
さて動物の中で体が長くてたくさんの
節があり、かつ
体腔を
備えた
種類は
如何なるものがあるかというと、まず「みみず」、「ごかい」などである。「みみず」は体が
円筒状で、
前端と
後端との
区別があり、頭から
尾までことごとく同様の
節よりなり、これを切り開いて見ると
筋肉質の
体壁の内には広い
体腔があって、
体腔の内を長い
腸が
縦に
貫いているが、これだけの点は、大体において人間の第十六日ないし第十八日目の
胎児にも「みみず」にも
共通である。されば人間も
胎内発生の
途中には一度「みみず」、「ごかい」の
類とよく
似た
構造を有する時代があると言うて
差支えはない。
人間を始めすべて
獣類、
鳥類、
魚類、
亀、
蛇、
蛙などいわゆる
脊椎動物の
特徴は身体の
中軸に
脊骨を有することであるが、この
脊骨なるものはもちろん、
初めからすでにあるわけではなく、発生の進むにしたがうて
次第にできてゆくものである。しかもそのでき始めはけっして
硬骨ではなく、
軟骨よりもさらに
軟かい
一種特別の
組織からつくられ、
脊骨に見るごとき
節は一つもなくて、
単に一本の
索にすぎぬ。これが後にいたって
軟骨となり、さらに
硬骨となって、ついに
成長し終わった
姿の
脊骨となるのであるが、いま
了解をたやすくするため、まず「なめくじうお」について
脊骨のでき始まる具合いを
説明し、つづいて人間の
脊骨の発生を
極めて
簡単に
述べて見よう。
骨格の発生などということは、実は
一般の読者には
無味乾燥で、さだめて読み苦しいことであろうとは思うが、
脊骨は人間をも
含む
最高動物
類のいちじるしい
特徴であるゆえ、その始め
如何にして生ずるかを知っておくことは、考えようによってはやはり人生を
観るときの
重要な
参考とならぬともかぎらぬ。
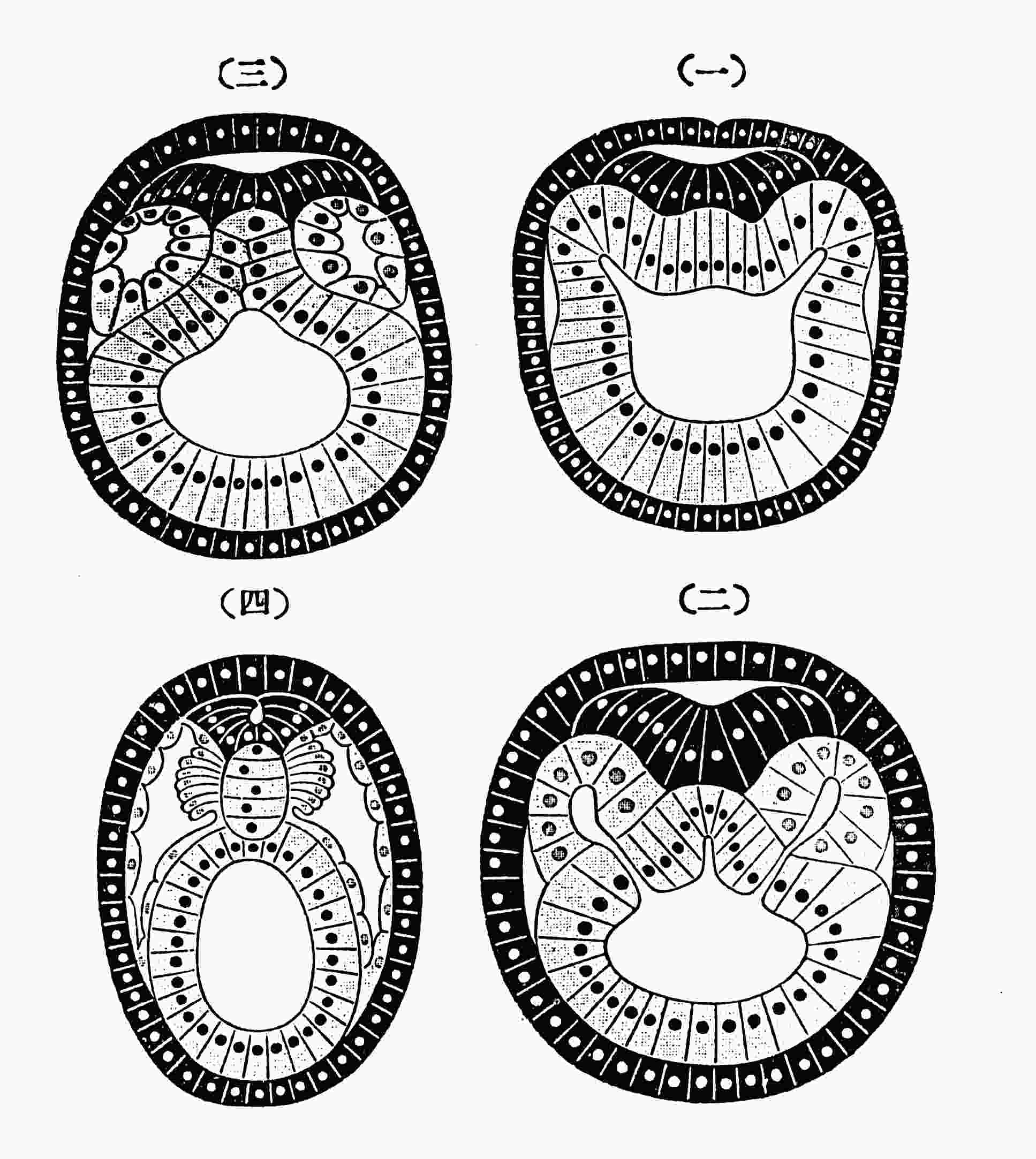 「なめくじうお」の脊索の発生
「なめくじうお」の脊索の発生
ここにかかげた図は、いずれも「なめくじうお」の発生中の
幼魚の
横断面を
示したものである。
鯉や
鮒を
輪切りにした切口にくらべて考えたならば、おおよその見当はつくであろうが、図の上部は魚の
背面、図の下部は魚の
腹面、図の
横側は魚の
側面にあたる。小さな
幼魚の
断面を四百倍
以上に
郭大した図であるから、
一個一個の
細胞の
境が明らかに見えている。この
四個の
横断面はそれぞれ少しずつ
成長の
程度の
異なった
幼魚から取ったもので、(一)は
卵から
孵ったばかりのもの、(二)はそれよりやや後のもの、(三)はなお少しく後のもの、(四)はさらに発生の進んだものであるから、この四図を
順々にくらべて見れば、その間に起こる
構造上の
変化が一目して知れる。体の表面を
包む
細胞の
層は
皮膚であるが、図ではこれが黒く画いてある。
背側の
皮膚の下に同じく黒い
細胞の列があるが、これは
脊髄のできかかりで、後に
神経系の中央部となるべきものである。また
腹側の
皮膚の直下にあって、体内の大部分を
占めているのは
腸の切口である。これだけは四図ともにほぼ同様であるが、
脊髄と
腸との間にあたるところが図によって少しずつ
違う。そのうち、体の中央線のところに起こる
変化が、今より
説こうとする
脊骨のでき始まりであって、その左右
両側に見える
変化は前の
節に
述べた
体腔のでき始まるところである。
体腔のでき方は
簡単ながらすでに
述べたゆえここには
略して、
脊骨のでき始まる具合いだけを見るに、
初め何もなかった
腸の
背側の
壁にまず細い
縦溝が生じ、次に
溝の
空隙は消えて
溝の
両側にあった
細胞のならび方が少しく
変わり、後にはこれらの
細胞だけで
独立の
棒となり、
腸とは
別れて
脊髄と
腸との間に
位するようになる。言うまでもなく、
横断面ではすべて切口だけが
現われるゆえ、
溝はくぼみのごとくに見え、
棒は円形に見える。すなわち(二)の図で
腸の
壁の
背部に下より上に向かうて
割れ目の見えるのは
縦溝である。(三)の図ではこの
溝がすでになくなり、(四)の図では
脊髄と
腸との間に
楕円形のものが見えるが、これは
腸から
別れて
独立した
棒の切口である。この
棒は「なめくじうお」では
生涯身体の
中軸をなし、他の動物の
脊骨に相当するが、
骨にもならず
軟骨にもならぬゆえ、ただ
脊索と名づける。
人間の
胎児においても
脊骨は発生の
途中に
突然脊骨として生ずるわけではなく、まず
初めは、
脊索ができる。しこうしてそのでき始まる具合いは、「なめくじうお」について
述べたところと同じく、
腸壁の中央線にあたる
細胞が
腸から
別かれ、
独立して一本の
棒となるのである。第十三日くらいの
胎児では
腸の
壁はいまだ平らで
脊索のできかかりも見えぬが、そのころからおいおいでき始めてたちまち身体の
中軸を
貫いた一本の
棒となり、この
棒の
周囲に
軟骨が生じ、
脊骨の発育が進むにしたがうて内なる
棒すなわち
脊索は
次第次第にその
量が
減ずる。
脊索は
単に
紐状のもので
節は全くないが、これを
包む
軟骨には
初めから多くの
節があって
脊骨と同じ形にできる。
一箇月半ころまでは
胎児の
骨骼は全部
軟骨のみからなっているが、七週くらいになると
脊骨の
軟骨各片の中央に一つずつ小さな点が
現われ、このところから
漸々硬い
骨に
変化し始める。
軟骨は
葛餅ほどに
透明なものであるが、
硬骨は
石灰質を
含んだ白色
不透明なものゆえ、
軟骨内に
化骨したところができればすこぶる
明瞭に知れる。
特に近来のエッキス光線で写真にでも取れば
硬骨だけは明らかに暗い
影となって写る。いったん
化骨し始めると、だんだん
硬骨の部が大きくなり
軟骨の部はそれだけ
減ずるゆえ、その
割合を見て
胎児の
月齢を
鑑定することもできる。生まれるころになっても、なお
軟骨のままに
残っているところはいくらもある。
かくのごとく人間の
胎児ではまず
脊索ができ、次に
脊索が
軟骨の
脊骨と入れ代わり、次に
軟骨が
漸漸硬骨化して
成人に見るごとき
硬い
脊骨ができ上がるのであるが、
脊椎動物を
見渡すと、これらの
階段に相当する
種類がそれぞれある。すなわち「なめくじうお」は
一生涯脊索を有するだけでそれ
以上に進まず、「やつめうなぎ」は
一生涯脊索を
備えているが、そのほかに少しく
軟骨の部分があり、「さめ」、「あかえい」の
類は全身の
骨骼が
一生涯軟骨でとどまるゆえ、この
類を
特に
軟骨魚類と名づける。「あかえい」の
骨は日本でも肉とともに食うが、「さめ」の
軟骨は「
明骨」と
称えて
支那料理では上等の
御馳走に使う。その他の
脊椎動物では
骨骼は
必ず
硬骨と
軟骨との両方から
成り立っている。
以上本章において
述べたところを
振り返って見ると、人間が
個体としての発生の始めは
極めて
微細な
簡単なもので、まず
最初には「アメーバ」のごとき
単細胞の時代があり、次に同じ
細胞の集まった原始
虫類の
群体のごとき時代があり、次に「ヒドラ」、「さんご」などのごとき時代があり、次に「みみず」のごとき時代があり、それより「なめくじうお」のごとき時代、「やつめうなぎ」のごとき時代、「さめ」のごとき時代などを
順々に
経過して、ついに
獣らしい
形状構造を有するにいたるのである。これだけは実物について調べれば
直接に目の前に見られる事実で、けっして
疑いをはさみ
得べき
性質のものでない。もし母の体にガラスのごとき
透明な
窓があったならば、これだけのことは
何人の発生にも見えたはずのことで、王様でも
乞食でも西洋人でも黒人でもこの点は少しも
相違はない。およそ何物でもその真の
性質価値等を正当に
了解するには、
初めて生じた時から今日にいたるまでの
経過を
参考することが
極めて
必要で、もしもこれを
怠り、ただでき上がった
姿のみについて
判断するとずいぶん
誤った考えを生ぜぬとも
限らぬ。近ごろは「生」を
論ずることがすこぶる流行するように見受けるが、人間についても、そのでき上がったもののみを見るにとどめず、その
単細胞であったころまでも考えに入れて、「みみず」時代には
如何、「なめくじうお」時代には
如何というような問いを
設けて見たならば、あるいは
議論の立て方にも
感情の
程度にも、大いに
変わることもあるであろう。
前章においては人間の
胎児のでき始めだけについて
述べたが、この章においてはさらに
胎児全形の発育および二三の体部の
漸々でき上がる
状態を
簡単に
説いて見ようと思う。人間は
受胎してより生まれるまでに、おおよそ四十週すなわち
満九箇月と十日ばかりかかるが、そのうち
最初の一週間か十日間は
卵が
輸卵管を
通過しながら
分裂するだけでいまだ体の形をなすにいたらず、また
三箇月の終わりになると、すでに小さいながら体の形だけはでき上がり、わずか
三寸(注:9cm)にもたらぬ身体にしては頭が
割合に大きいが、
尾も全くなくなり、手足の形もととのい、指も五本ずつ
揃うて
薄い
爪まであるようになる。されば体形がいちじるしく
変化するのは、第二週から第三
箇月までの間であって、それより後はただ
各部の
発達が進み全身が大きくなるだけである。
まず
胎児全身の形が
如何に
変わってゆくかを見るに、
懐胎第一
箇月のなかほどには前に図(注:14日ごろの胎児の図)に
示したとおり、ほとんど「みみず」の短いもののごとき形で、体の長さわずかに一分(注:3mm)にも
達せぬが、
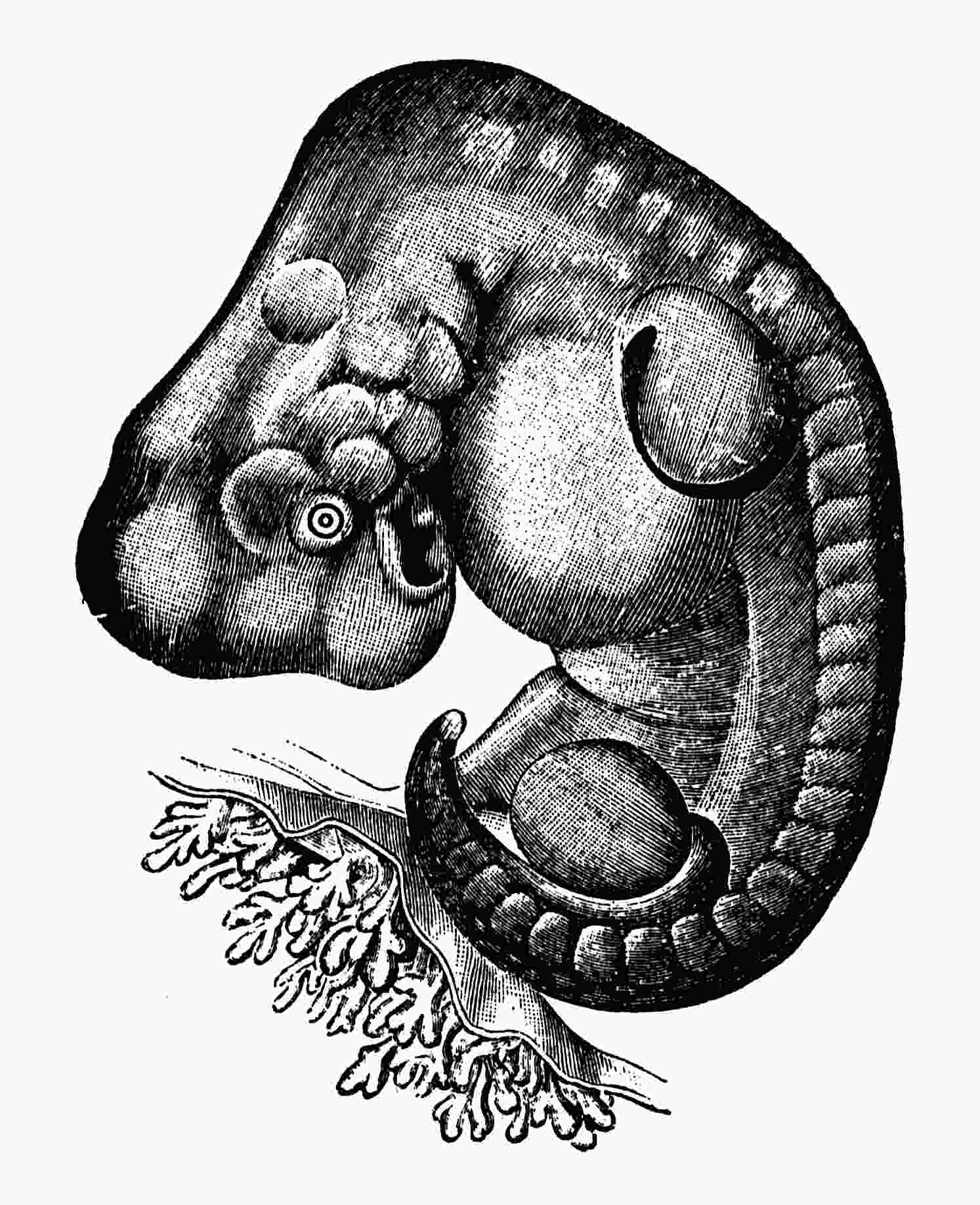 27日ごろの胎児
27日ごろの胎児
二十日目ごろになると、手足のでき始めが
疣のごとき形に
現われ、体の長さも
四分(注:12mm)
以上になる。これより後の体形の
変化は、いちいち
文句で書くよりは図によるほうが
説明にも
了解にも
便利であろうと思うから、ここに第二週ごろから第二
箇月の終わりまでの
胎児の発生を
示した図を
掲げて、読者とともにこれを見ることとする。
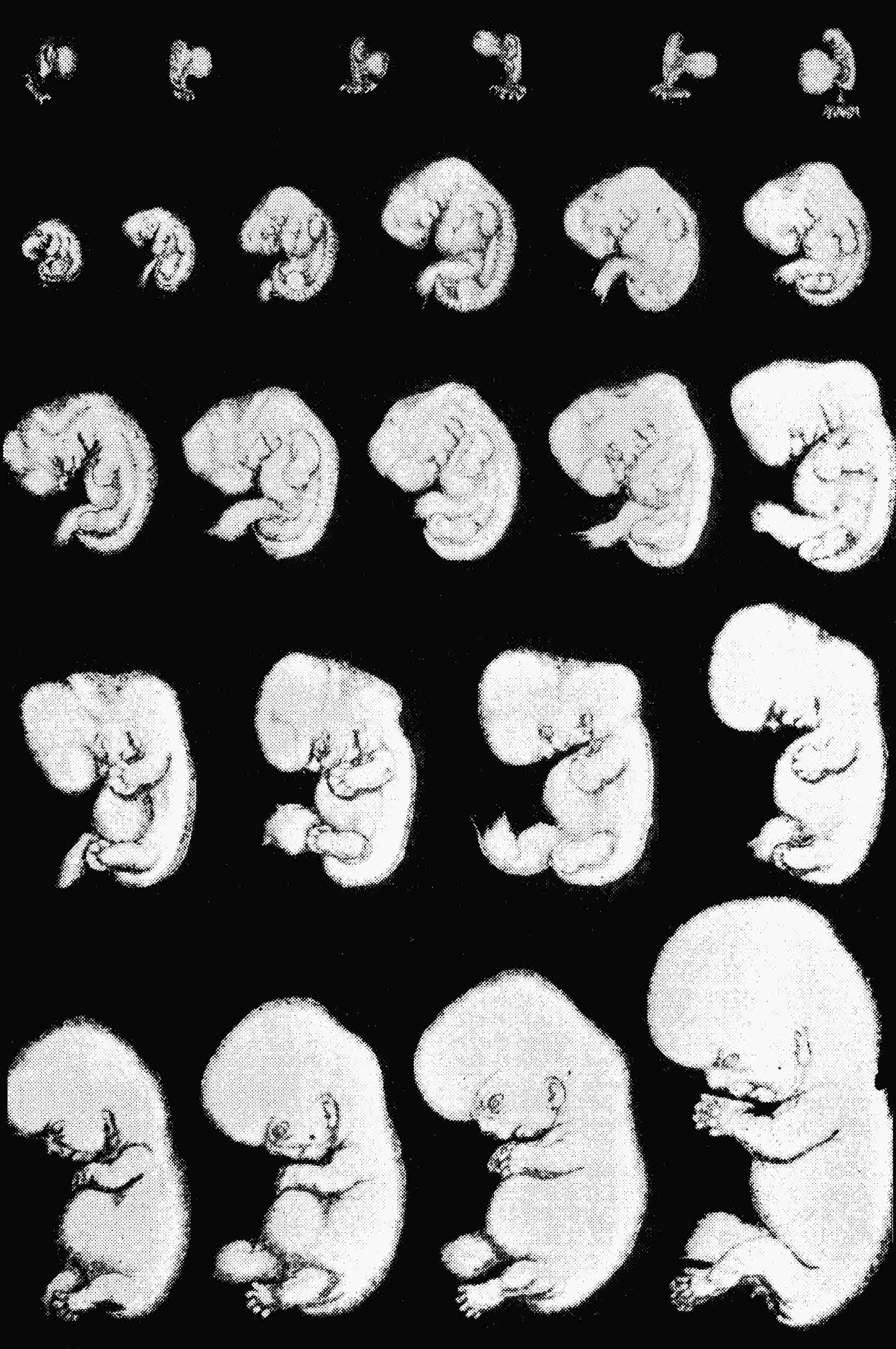
胎児の発育
受精後第2週より第2箇月の終わりにいたるまでの
まず一番上の横列に
示してあるのは、いずれも第三週間の
胎児で、左の
端のがおよそ十三四日くらい、右の
端のが二十日くらいのものであるが、かような
初期の
胎児はいまだすこぶる小さいのみならず、
我々のつねに見なれている
成人の身体に
比して形が
非常に
違うゆえ、
胎児のどの部分が成人のどの部分になるか
簡単に
説明することは
容易でない。この列の
胎児にはみな
腹面に丸い
袋がつながっているように画いてあるが、これは「黄身
袋」と名づける
薄い
膜の
嚢で、後に
子供の身体となるべきものではないゆえ、他の列の図と
比較する場合には、これを
除いて考えるがよろしい。図はことごとく実物の二倍大に画いてあるゆえ、二分の一に
縮めれば実物の大きさが知れる。次に第二列に画いてあるのは、みな
一箇月の
下旬の
胎児で、そのうち左の
端のが二十三四日のもの、中央のは二十七八日のもの、右の
端のがおおよそ三十日くらいのものである。すなわち上二列を合わせて、
懐妊第一
箇月の
下半における
胎児の発育を
示すことにあたる。この列の
胎児はいずれも
脊が丸く
屈し、
特に
頸筋の
辺で急に曲がっているゆえ、顔は直ちに
腹に面している。また体の
後端には明らかな
尾があるが、これは前に向かうて曲がっているゆえ、ほとんど鼻の先にふれそうである。右の
端の図で見ると、
一箇月の終わりごろの
胎児では頭と
胴とはほとんど同じぐらいの大きさで、体の
後端は
脊骨のつづきを
含んだ短い
尾で終わり、
胴の
上端と
下端に近いところから、
腕と
脚とができかかっているが、いまだ開かぬ
松蕈のごとき形で手足らしいところは少しも見えぬ。いずれの図でも
胎児の
腹からは太い
紐が出ているのを、
根本に近く切り
捨てたごとくに画いてあるが、この
紐は後々まで
残る
臍の
緒の始りである。
第三列より第五列までに
並べてあるのは、第二
箇月の
胎児で、第三列の左の
端のはその
初め、第五列の右の
端のはその終わりにあたるものである。これらを
順々にくらべて見るとわかるとおり、第二
箇月の間には顔もだんだん人間らしくなり、手足もしだいに形が
備わり、
尾もすこぶる短くなって、その月の終わりには、もはやだれが見ても人間の
胎児と思われぬほどの形となる。しかしいまだ頭が
非常に大きく、足は手の
割には小さい。また男になるのか女になるのか少しもわからぬ。なお第三週第四週ごろの
胎児には、
頸の
両側に
魚類に見ると同じような
鰓孔が四つずつもあるが、第二
箇月の間にこれらの
鰓孔は
次第に見えなくなって、ただその中の第一番のものだけが、耳の
孔となって後まで
残る。これによって見ると、
陸上動物の耳の
孔は、
魚類の
鰓孔の一つに相当することが明らかに知れる。
胎児の全形は
三箇月の
末にはほぼでき上がるゆえ、
三箇月以後はただ
各部が大きくなるだけで、
別にいちじるしく
変形するところはない。
二箇月ではいまだ男女の
別が
判然せぬが、
三箇月の
末にはもはや
外陰部の
形状が明らかになって、男か女かは
一目して
識別せられる。さらに
五箇月ごろからは全身に細い毛が
密生し、
六箇月になると
胎児が動き始め、
七箇月にはよほど発育が進んで身長も
一尺(注:30cm)
以上となり、もし
産み出されても
生存し
得るぐらいになる。かくて
月満ちれば、大きな赤子となって生まれでるのである。
以上述べたとおり人間の
胎児は、けっして
初めから
成人を
縮小したごとき形にできるのではなく、
最初は全く形の
違うたものができ、それより
漸々形状が
変化し、新たな
器官が生じなどして、ついに生まれるときの赤子の形ができる。
例えば体の
後端にある
尾のごときも、
初め明らかにあったものが後に消え
失せる。すなわち二十日ごろまでは手も足もなく、体は後ほど細くなり長い
尾で終わってあたかも
魚類のごとくであったのが、その後手足が生じ、手足が
延びても
暫時は
尾が明らかに見えて「いもり」、「さんしょううお」または犬、
猫の
胎児と同じ形を
呈している。体がさらに大きくなり、手足がなお
延びるとともに、
尾はだんだん短くなり、
三月目にいたると、
尾は全く
隠れて見えなくなる。しかし
骨だけは
成人になっても
尾'テイ骨として
残り、人によってはこれを左右に
振り動かすための
筋肉までも
存している。
 尾の残っている子供
尾の残っている子供
まれには
前頁の図を
示したごとくに、生まれた後にも
尾が
残っていることがある。頭と
胴との大きさの
割合、
腕と
脚との長さの
割合なども発生の進むに
従い
漸々変わってゆくが、生まれたばかりの赤子はなおそのつづきとして
胴にくらべると頭が大きく、
前肢にくらべると
後肢が短い。
おおよそ人間の身体中で一番人間らしいところ、すなわち他の
獣類にくらべて一番
違うた感じを起こすところはどこかといえば、だれでも
必ず顔と答えるであろう。顔はただに人間と
獣類とで
違うのみならず、一人一人に
違うて、
如何によく
似ていても、ならべて見れば
必ずどこか
相違がある。されば顔はその人の
商標のごときもので、
腹や
背中や
腕や
腿を見たのではだれであるか
容易にわからぬが、顔さえ見ればけっして他と
間違えることはない。昔から
肖像と言えば
必ず顔の画のことで、今日入学
試験に
替え玉を
防ぐために調べるものも顔の写真である。顔はかく
重要な体部であるゆえ、ここに少しくその発生の
模様を
述べて見よう。
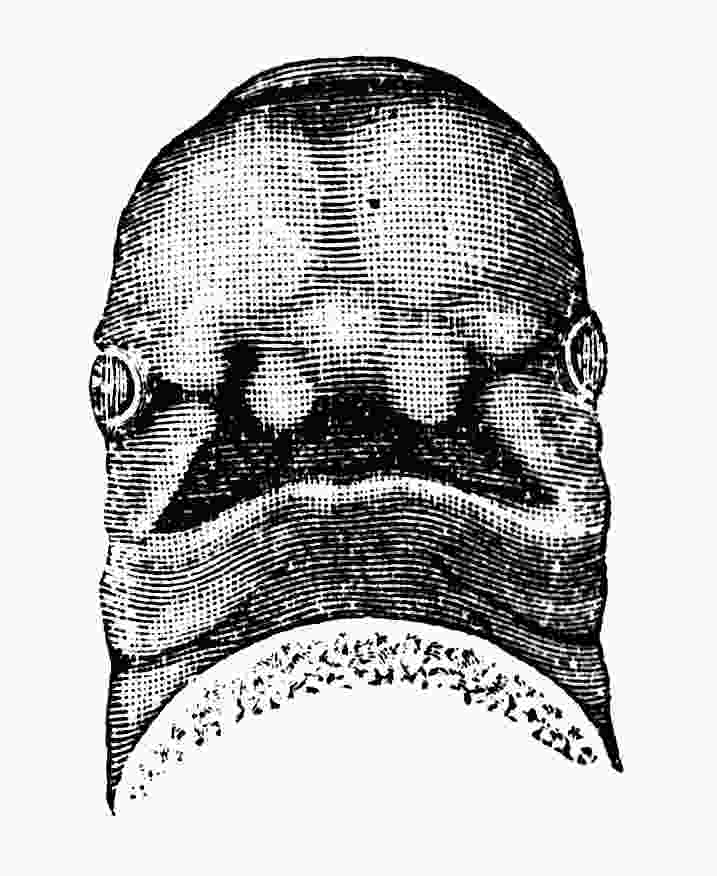 二十八九日ごろの胎児(七倍半大)
単細胞
二十八九日ごろの胎児(七倍半大)
単細胞時代、
細胞のかたまりの時代、「ヒドラ」、「さんご」のごとき時代、「みみず」のごとき時代には、むろんいまだ顔と名づくべき部分はないが、その後になるとおいおい顔という部分が明らかになってくる。すなわち第四週ごろにはそろそろ頭の
側面や
腹面に、
眼、鼻のごとき
感覚器官が生じ、その間に大きな口が開いて、すこぶる
不恰好ながら
一種の顔ができる。
前頁の図は第二十八九日ごろの
胎児であるが、これを見ると
眼はいまだ頭の
側面にあり、口は大きく「へ」の字形に横に
延びて、
上顎はいまだ
完全にでき上がらず、鼻の
孔は
両眼の間に
位して左右
相遠ざかり、かつそれぞれ口と
連絡しているゆえ、「さめ」や「あかえい」の鼻によほどよく
似ている。
絶世の美人でも
非凡な
豪傑でも一度は
必ずこのような顔をしていたので、これから
成長して
眼の
鋭い
掏摸の顔になるか、それとも間の
抜けた
善人の顔になるかは、まえもって知ることはとうていできぬ。
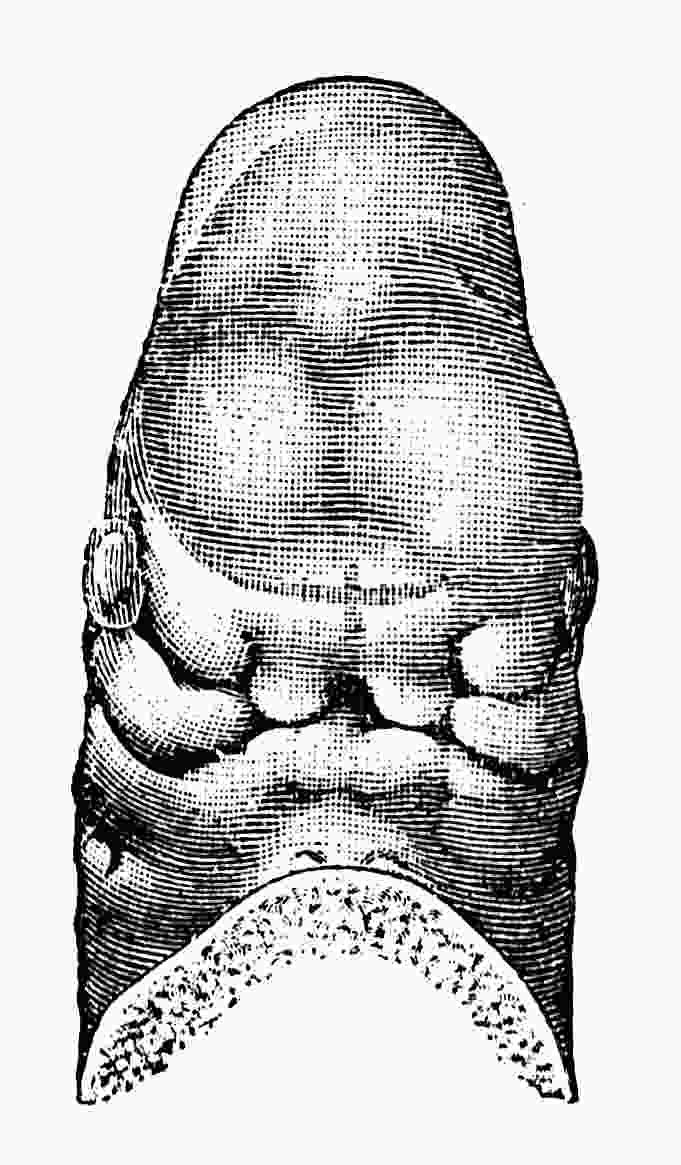 第五週の終わりごろの胎児(五倍大)
第五週の終わりごろの胎児(五倍大)
この図は第五週の終わりごろの
胎児の顔である。大体においては前の図とよく
似ているが、
上顎の
発達がやや進み、鼻の
孔と口との間の
連絡の
溝がだいぶ細くなり、かつ口も
閉じている。
眼はやはり頭の
側面にあり、鼻はただ
孔があるだけで、いまだ左右に
離れている。人間では鼻といえば顔の前面へ
突出した山のごとき形のものと思うが、かく
突出するのはよほど後のことであって、
三箇月ぐらいの
胎児でも鼻はほとんど
扁平である。また
上顎は左右
両側の部と、中央にある部とが後に
相連なってでき上がるものであるが、その
結果として鼻の
孔と口とは表面では
縁が切れる。ただしその
裏のところでは
相変らず
連絡していて、この
連絡は
成長の後まで
残っている。鼻の
孔からとおした
紙撚を口のほうへ引き出すことのできるのはそのためである。また
上顎の中央部と、左右いずれかの
側部との間が
完全につながらず、その間に多少くぼんだところが
残ると、いわゆる「三口」の
児ができる。
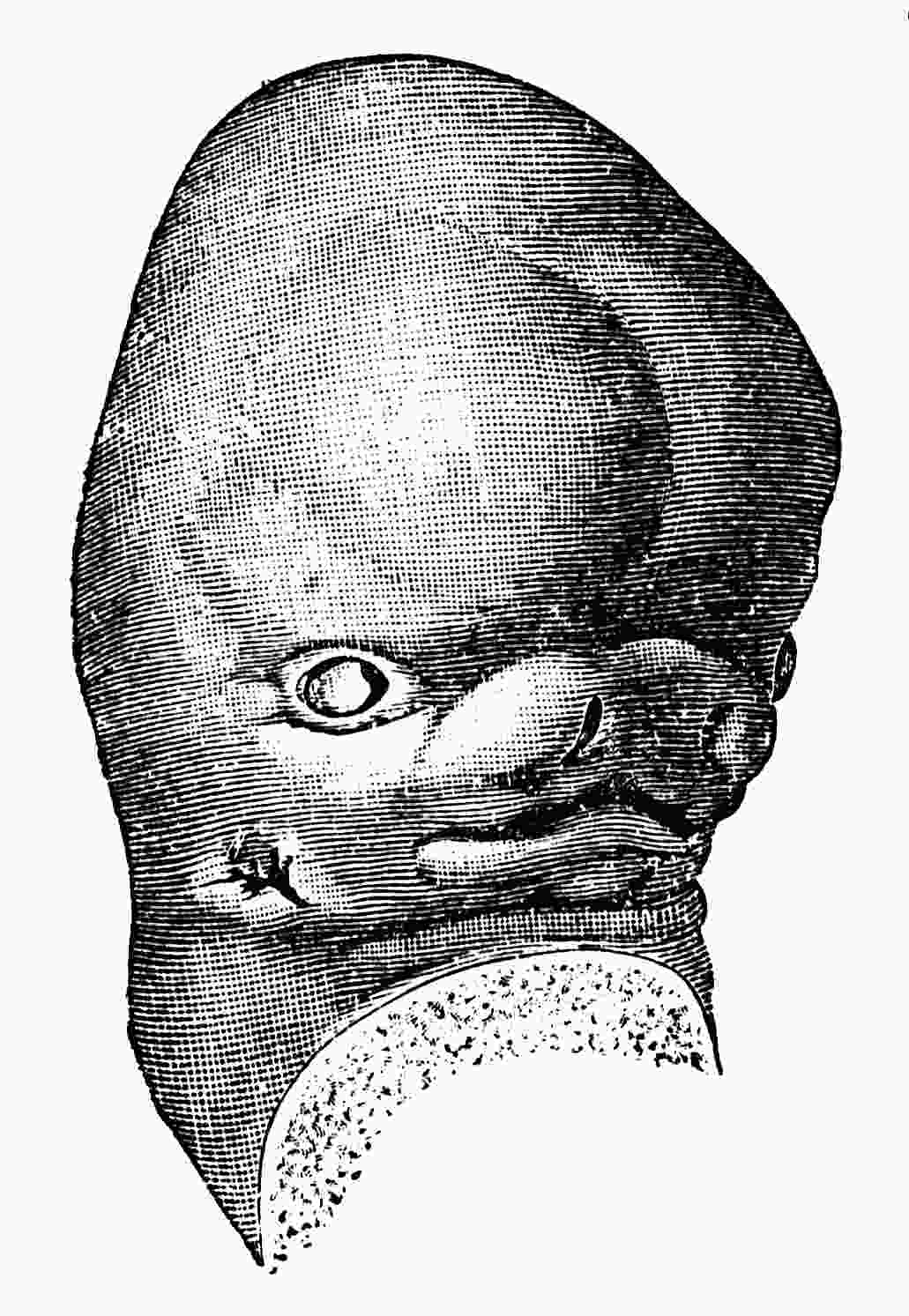 第七週の終わりごろの胎児(五倍大)
第七週の終わりごろの胎児(五倍大)
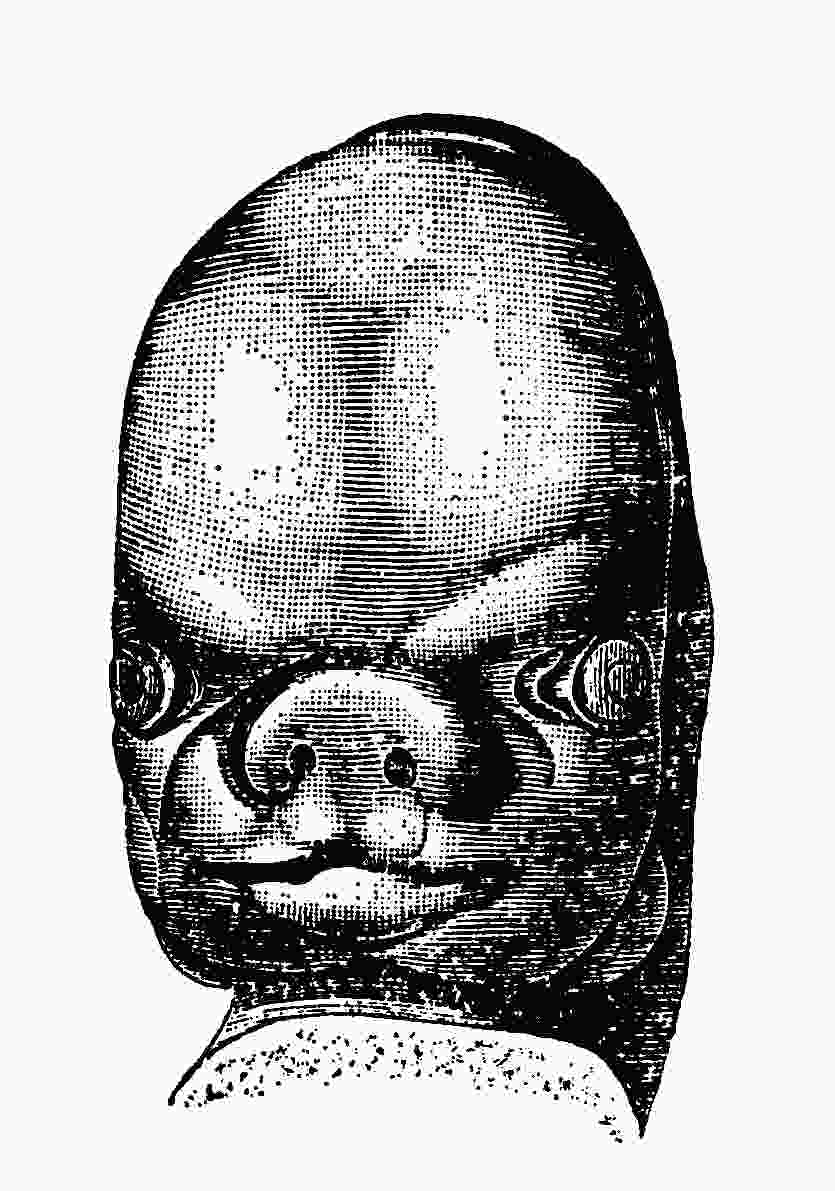 二箇月の終わりごろの胎児(三倍大)
前頁
二箇月の終わりごろの胎児(三倍大)
前頁下図は第七週の終わりの
胎児、右図は第二
箇月の終わりの
胎児の顔である。このくらいまで進むと、すでにいくぶんか人間の顔らしくなる。ただし
眼はいまだよほど左右に向かい、鼻は全く
扁平で下を向くべき鼻の
孔は真正面を向いている。
特に
違うて見えるのは、耳の
孔の
位置で、ほとんど
下顎の下にある。これより
後の顔面の発育はただ一歩一歩赤子の顔に
似てくるだけで、もはやいちじるしい
変化はない。耳は
初め
孔ばかりであったのが、
二箇月のころ少しずつ
耳殻の形ができかかり、
三箇月にはよほど形も整うてくる。
眼は
最初は円く開いたままであるが、
四箇月ごろに
眼瞼ができ上がり、その後は
閉じていて
七箇月から開くようになる。
八箇月では
下顎がやや大きく
頤が明らかになり、
九箇月では頭の
髪が
濃く長くなる。
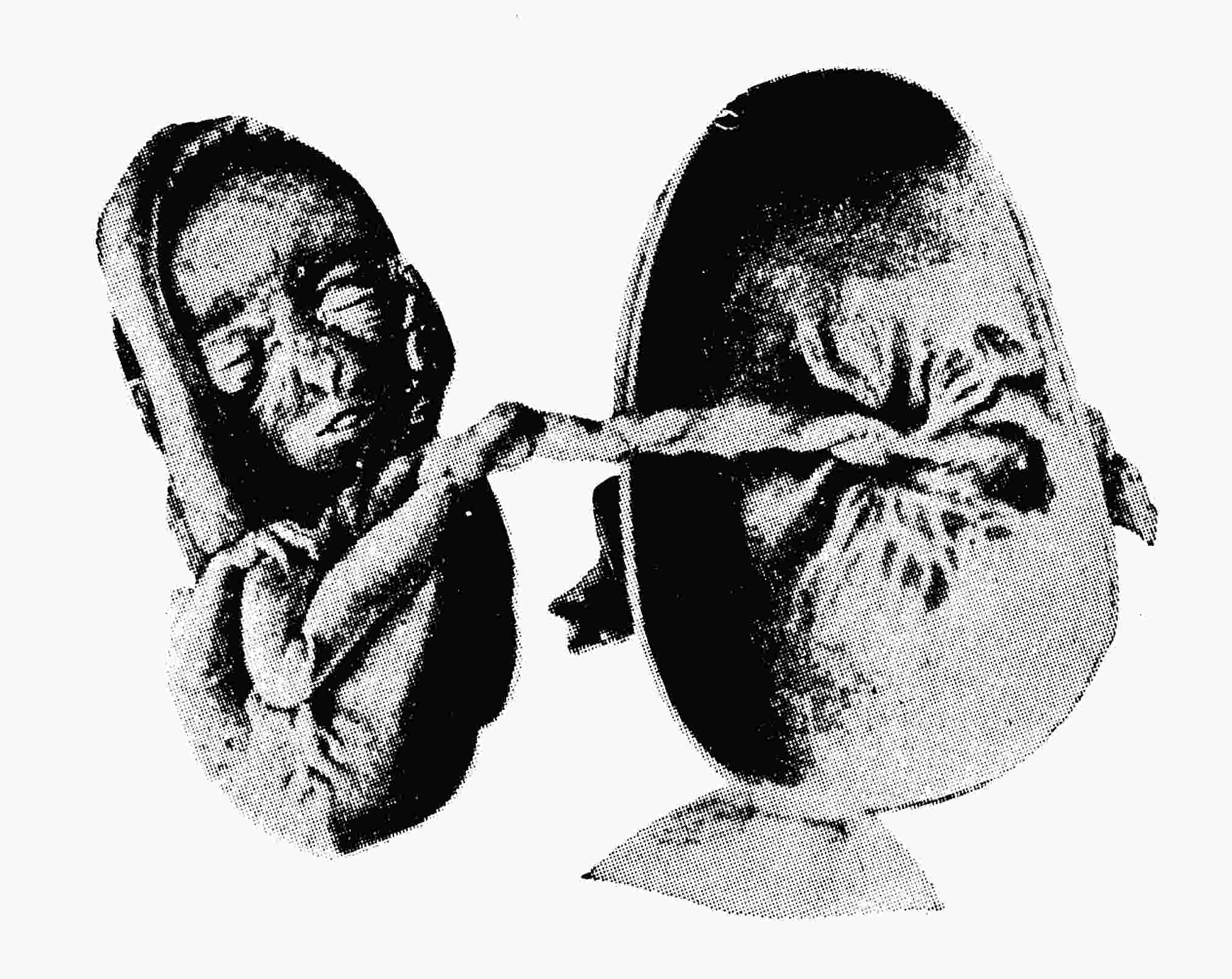 手長猿の胎児
手長猿の胎児
人間の
胎児の顔は
如何なる動物の顔にもっともよく
似ているかというに、
最初のうちはただ他の
獣類の
胎児に
似ているというだけで、
成長した動物でこれに
似たものはないが、
二箇月以後のものはよほど
猿類に
似ている。
特に
猿類の
胎児とならべたならばほとんど取り
換えてもわからぬほどによく
似ている。
前頁にかかげた
手長猿の
胎児のごときは、これを
三箇月の終わりの人間の
胎児にくらべたら、どこが
違うかむしろ
相違の点を見いだすのに苦しむぐらいであろう。
顔は人間が外見上自身を他の
獣類から
区別し、万物の
霊として自負する点の一であるが、さらに人間が日夜その
働きを
自慢しておかぬ
器官は
脳髄である。人間が他の
獣類を
攻め
亡ぼしたのも、文明人が
野蛮人を
征服したのも、主として
脳髄の
働きによることゆえ、これを
自慢するのは
当然であるが、その代わりまた
脳髄の
働きに
頼りすぎて、他の
獣類がかつてせぬような
愚かなことをなしていることもけっして少なくない。ただ両方を
差引き
勘定して、なお
個体の
維持と
種族の
維持とに
有効であったゆえ、それで
脳髄が
尊いのであろう。それはしばらく
別として、ここに
胎児の
脳髄の発生の
模様を一とおり
述べることとする。
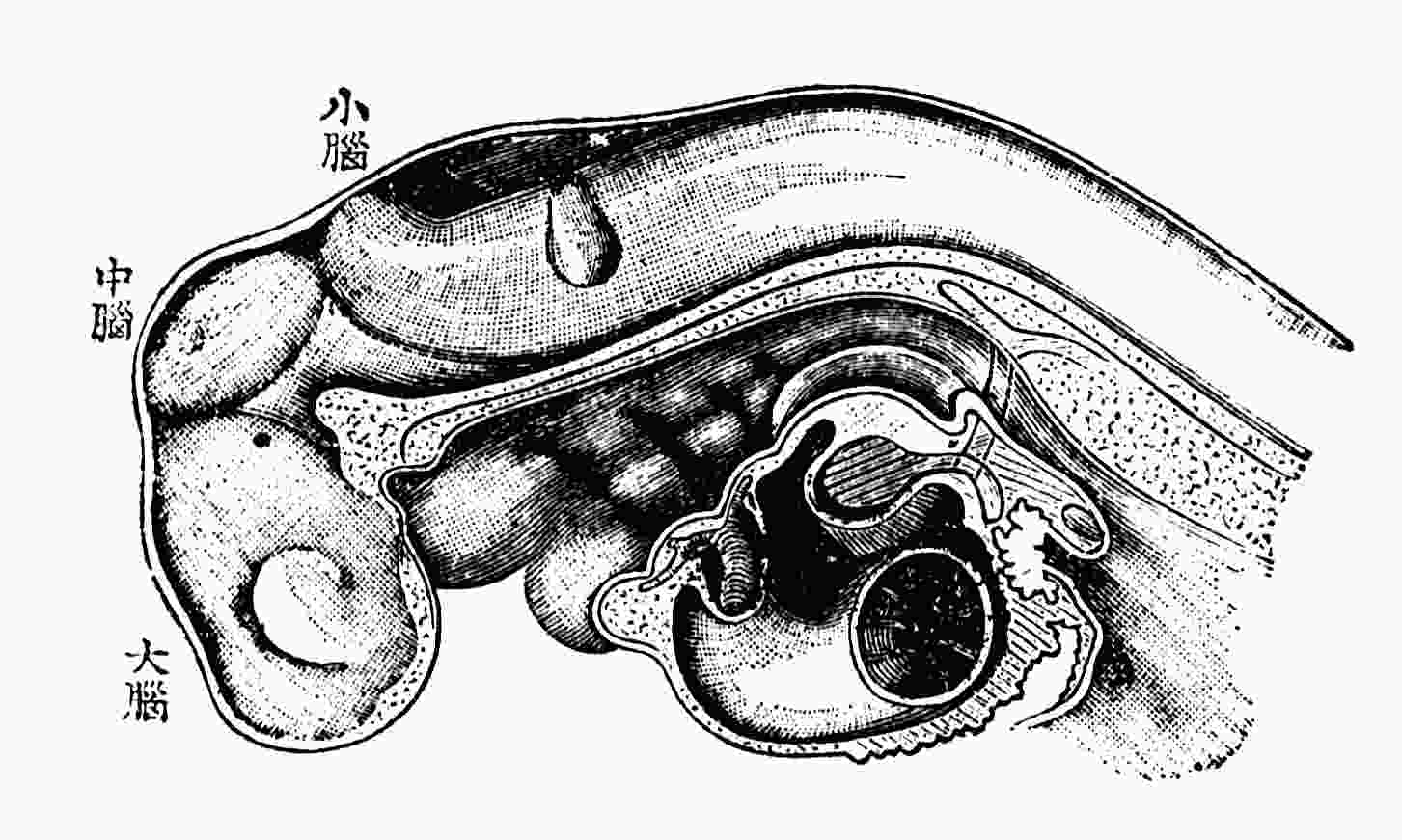 20日ごろの胎児の脳を示す(側面)
20日ごろの胎児の脳を示す(側面)
たいていの動物には、発生の
初期に一度は
必ず全身が
胃嚢のごとき
状態の時代のあることを前に
述べたが、
脊椎動物ではそれに次いでまず
現われる
器官は
脳脊髄である。人間の
胎児でも、十二三日目のものにはすでに
背面の中央に
縦の
溝があるが、これは
脳脊髄のでき始まりで、十五日ごろになると
溝は
閉じて
管となる。しこうして
管の
前端に近い部分には、いくつかややくびれたところができ、くびれとくびれとの間は少しくふくれて多少
珠数に
似た形になる。かようにふくれたところは
大脳、
中脳、
小脳、
延髄などのでき始まりで、
最初は一直線にならんでいるが後には
種々に
屈曲し、
各部の
発達の
程度にも
種々な
相違が生じて、しまいに
複雑極まる
成人の
脳髄までに進むのである。
初め
極めて
簡単な
管から、後に
複雑極まる
脳髄になるまでの
変遷を
逐一調べると、おもしろいことがすこぶる多くあるが、本書ではとうていこれを
詳しく
記述することはできぬゆえ、ここにはただ
大脳、
中脳、
小脳の大きさの
割合の
次第に
変じてゆくありさまを
述べるにとどめておく。右の中で、
大脳は
知情意等のいわゆる
精神的の
働きをするところで、物を
記憶するのも理を
推すのもこの部の役目であるから、人間にとってはすこぶる
必要なところである。人間が他の
獣類にまさるのは主としてこの部の発育の進んでいる点にある。
小脳は全身
各部の運動を調和するところで、この部が
傷けば身体の一部一部は動いても、
目的にかのうた
一致調和した全身の運動はできぬ。また
中脳は一名
視神経葉とも名づけるもので、主として
視神経と
連絡している。
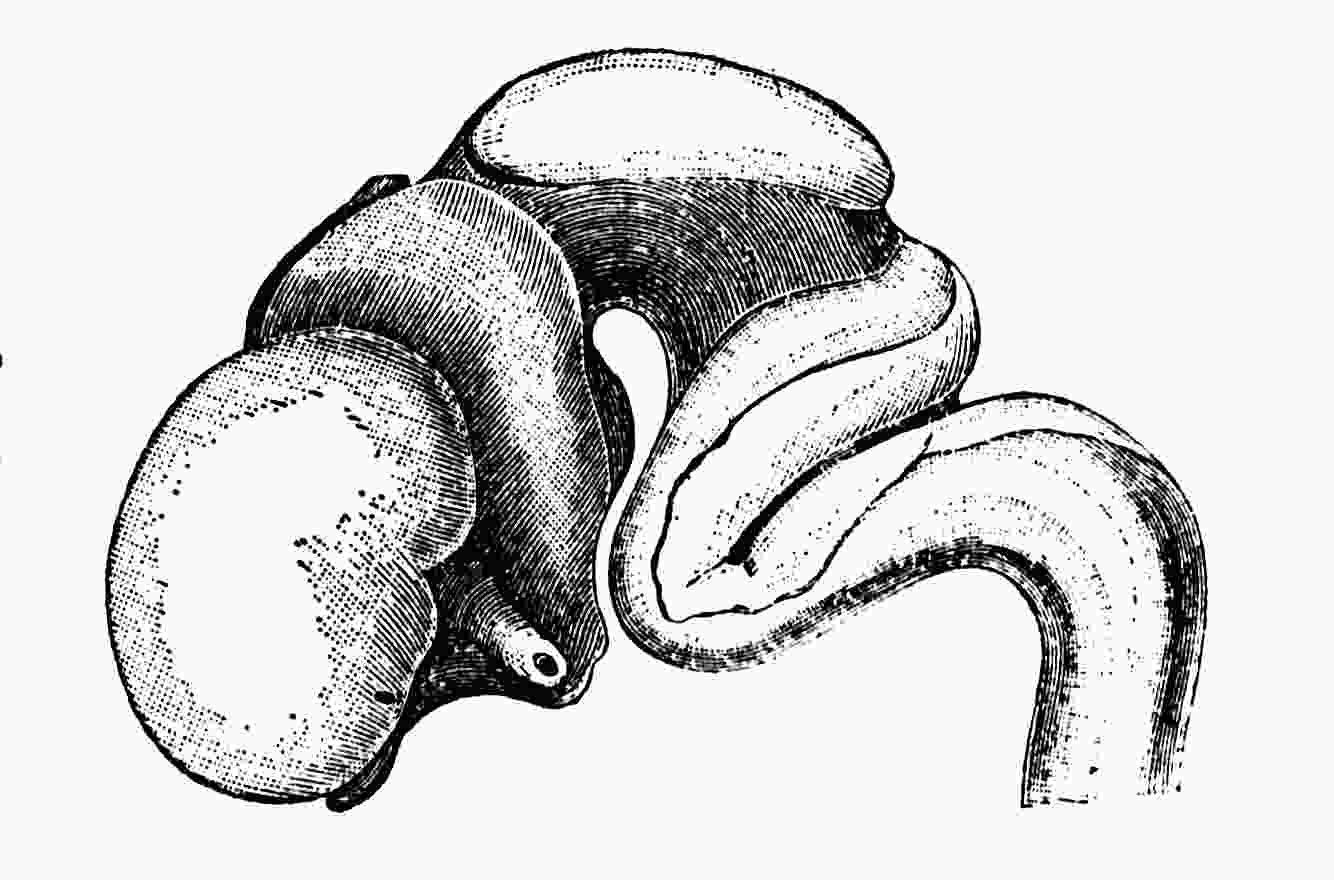 2箇月の胎児の脳
2箇月の胎児の脳
人間の第二十日ぐらいの
胎児でも、すでに
脊髄の
前端に
脳髄の
各部を
識別することができるが、一番大きいのは
中脳で、
小脳も
大脳もこれよりはるかに小さい。すなわちこの点においては
魚類の
脳と同じである。かりにこのまま
成長したとすれば、その者の知力はおそらく
魚類以上に
昇らぬであろう。それより
大脳は他の部に
比して
速かに
成長し、第八週の中ごろには
大脳の左右両半球は
中脳よりもだいぶ大きくなるが、
小脳のほうはなおはるかに小さい。このころの
脳髄を他の動物に
比較すれば、まず
蛙の
脳髄くらいの
程度にあたる。
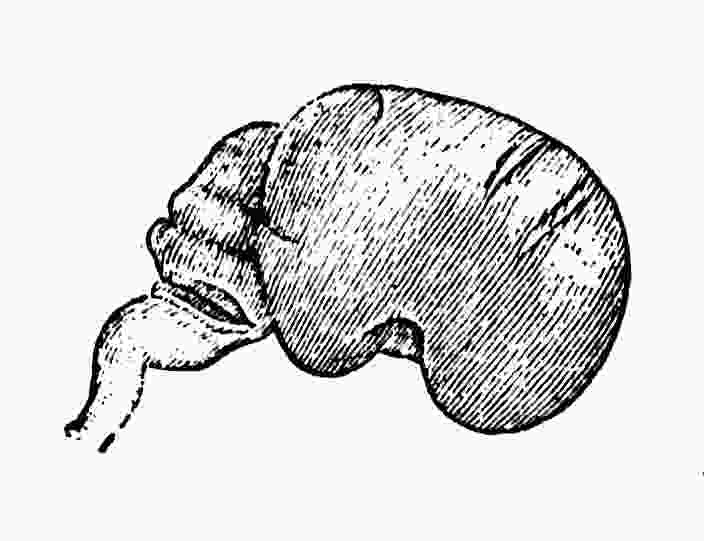 三箇月の胎児の脳(側面)
三箇月の胎児の脳(側面)
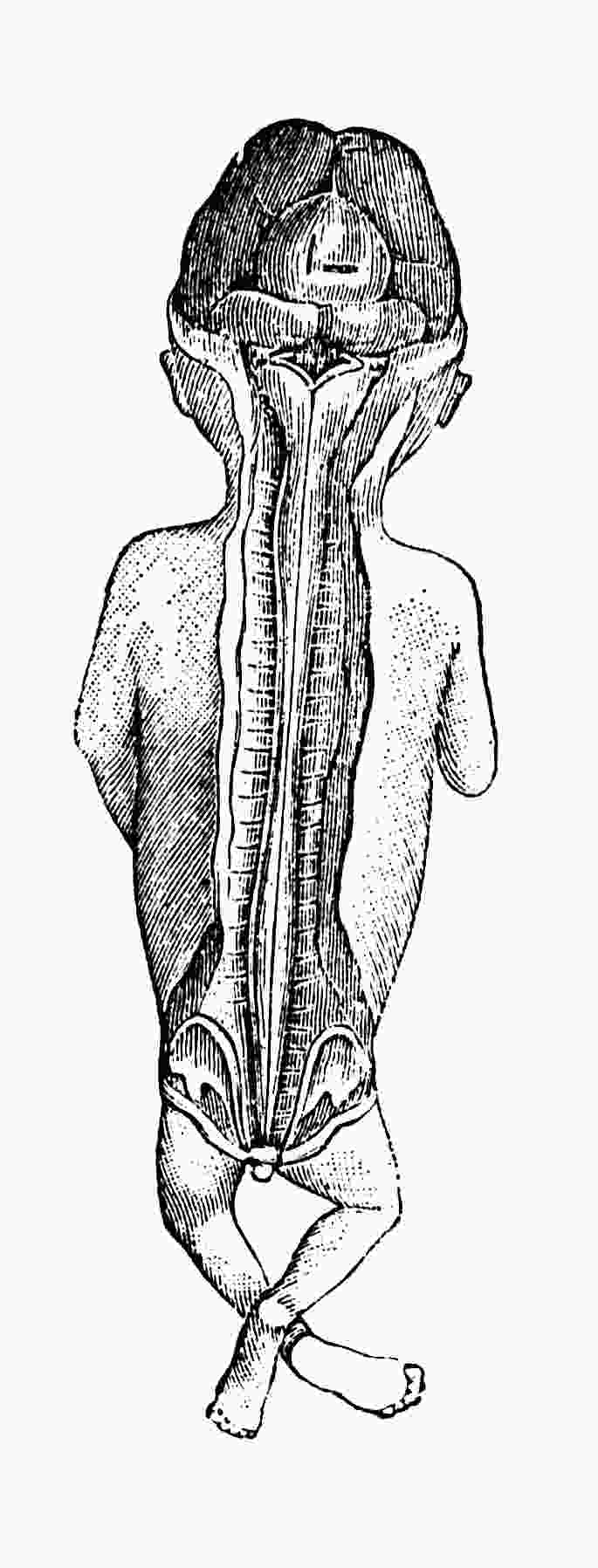 三箇月の胎児の脳、脊髄
大脳
三箇月の胎児の脳、脊髄
大脳はその後ますます
発達して
三箇月の終わりころにはすでに
脳髄の
過半を
占めるにいたる。しかし後面から見ると、
大脳両半球の下には
中脳がやや大きく見え、その下に
小脳がひらたく見える。
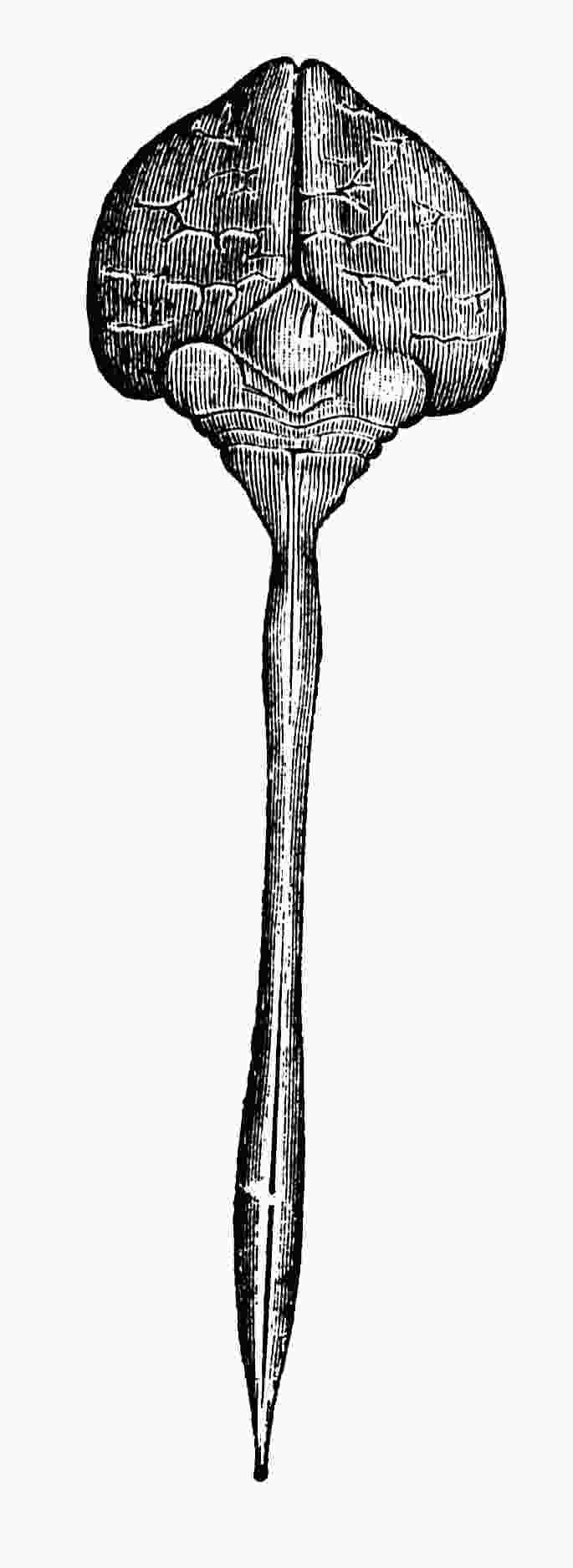 四箇月の胎児の脳、脊髄
四箇月
四箇月の胎児の脳、脊髄
四箇月の
胎児では
大脳がさらに大きくなったために
中脳は
次第にこれに
被われ、わずかに
大脳と
小脳との間に
菱形に
現われるだけとなり、
六箇月の
胎児になると、
大脳は
脳の大部分をなし、他の部はことごとくその下に
隠れ、
中脳は、
大脳と
小脳との間の
溝を開いてのぞかなければ見えぬ。
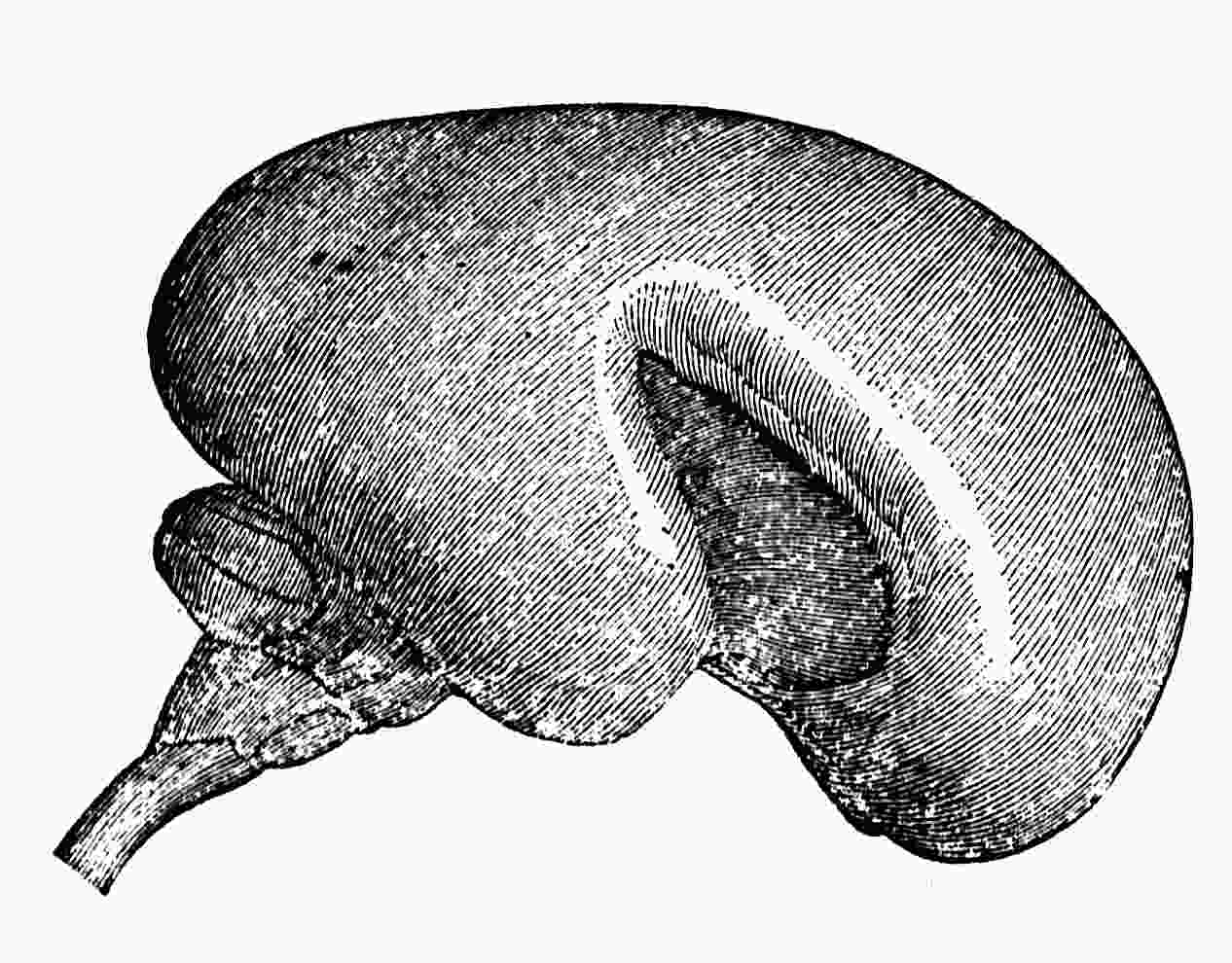 6箇月の胎児の脳
6箇月の胎児の脳
この
程度に
達すると、
脳髄の大体の
形状はすでに
成人の
脳髄のとおりであるゆえ、これより後の発育はただ
大脳の表面に
凸凹が生じ、回転と
溝とがだんだん
殖えさえすればよろしいのである。
五箇月六箇月ごろの
胎児の
脳髄は
大脳の表面がいまだ
平滑であるゆえ、
鼠、
兎などの
脳に
似ているが、
七箇月くらいのものは
大脳の表面にいくつか明らかな
溝ができているから、大体犬などの
脳髄によく
似ている。また
八箇月になれば、
大脳の回転も
溝もさらに
殖えてちょうど
猩々の
脳髄くらいになる。
以上述べたとおり人間の
推理の
器官なる
大脳は、
胎児の発生に
従うて一日一日と大きくなり、
或る時は魚のごとく、
或る時は
蛙のごとく、また
鼠、
兎のごとく、また犬、
猩々のごとく、
次第に進んでしまいに高等
複雑なものとなることは明らかであるが、おそらく人間の
種族が
幾千万年かの昔から今日までに進化し来たった間にも、ほぼこれと同様な
経路を
踏み来たったのであろう。かく考えると、人間の
脳髄なるものも
畢竟、人間
種族の
生存に
必要なだけの
程度までに進んでいるもので、けっして
絶対に
完全な
働きをするものとは思われぬ。
自然界で
完全と名づけるのは、いつもその
種族の
生存に間に合う
程度を
指すに
過ぎぬゆえ、人間の
脳髄などもこれを
生存に
必要なよりほかの方面に向かうて
働かせたならば、どのくらいまで
信頼のできるものか、すこぶる
怪しいとの感じが起こるであろうが、これは世のいわゆる
学説なるものに
捕われず、
経験に
徴してこれを
判断取捨し
得るためには
極めて大切なことである。空理
空論はおおむね
大脳の
働きを
過信するところからくるのであるゆえ、
胎児における
脳髄発育のありさまを知ることは、やがて
経験に重きをおいて事物を
判断する
常識を
発達せしめる助けともなるであろう。
脳髄は物を考える
器官であるが、いくら物を考えてもこれを実行することができなかったならば、何の役にもたたぬ。しこうしてこれを実行するには
必ず手を
要する。また手を
働かせてさまざまの事を実行すれば、新たな
経験の重なるに
従い、これを
記憶し
結びつけるために、
脳髄も
次第に
発達する。すなわち、
脳をもって手の仕事を考え、手によって
脳の
発達を
促すことになるゆえ、その一を
欠いてはけっして十分な
働きはできぬ。人間が他の
獣類に打ち勝ち
得たのは、全く
脳と手との
働きによる。ここに
胎児における手のできかたの
大略を
述べ、ついでをもって足の発生をも
述べる。
次頁の図に
示したのは手のでき始まりからほぼその形のでき上がるまでの
順序を
現わしたもので、もっとも小さいのは三週間、もっとも発育の進んだのは
三箇月くらいの
胎児から取った手である。ことごとく同じ倍数に
郭大してあるゆえ、その間に大きさの
増してゆく具合いは、図によって直ちに知ることができる。
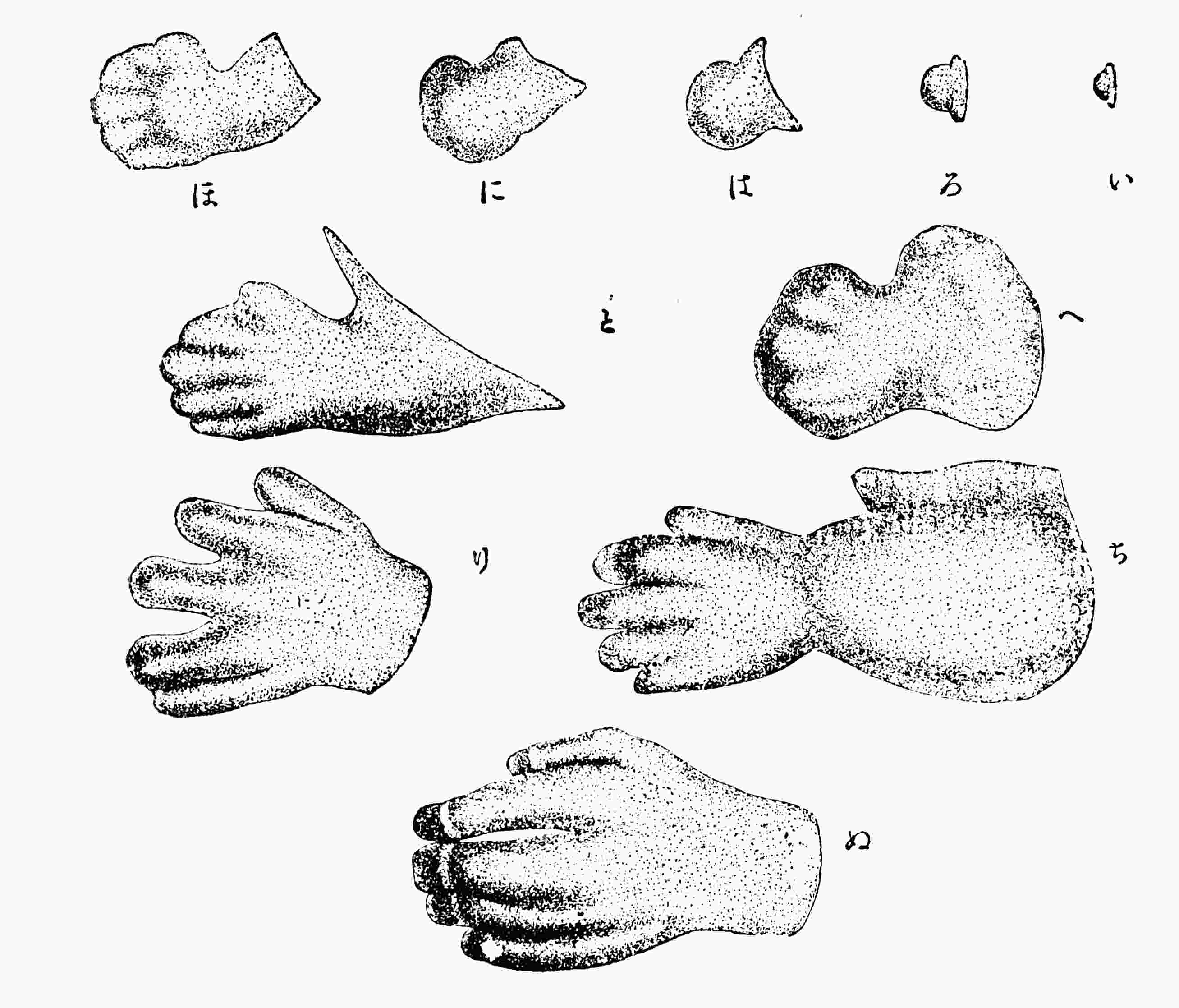 手の発育
手の発育
「い」図は手が始めて
胴の上部の
側面に
現われたところで、いまだ
単に
低い
疣のごとき形のものにすぎぬ。「ろ」図ではこれが少しく大きくかつ高くなり、「は」図ではさらに大きくなり、根元に少しくくびれたところが生ずる。しかしこのころまではいまだ部分の間の
区別はなにもない。ただ
末端の
周辺に少しく
扁平になった
縁が見えるだけである。さらに進んで「に」図になると、この
扁平な
縁がいちじるしくなり、「ほ」図においてはこの部に
厚いところと
薄いところとが
互い
違いにできる。
厚いところはすなわち後に指となるべき部で、その数は
初めから五つある。「へ」、「と」の両図では指がだんだん明らかになるが、いまだ一本一本に
離れず、
蹼のごとき
膜でみな
相連なっている。「ち」図では指は
先端のほうから
次第に
相分かれ
腕もいちじるしく長くなり、
肘の曲がりかども明らかに見える。「り」図、「ぬ」図はともにただ
手頸から先だけを
示したものであるが、「り」では指はいまだ太く短く、「ぬ」にいたって
初めて、指の
端に
爪ができ、指の形が
完全になる。これから後は、ただ全体が大きく
成長するだけであって、
特に言うべきほどの
変化はない。
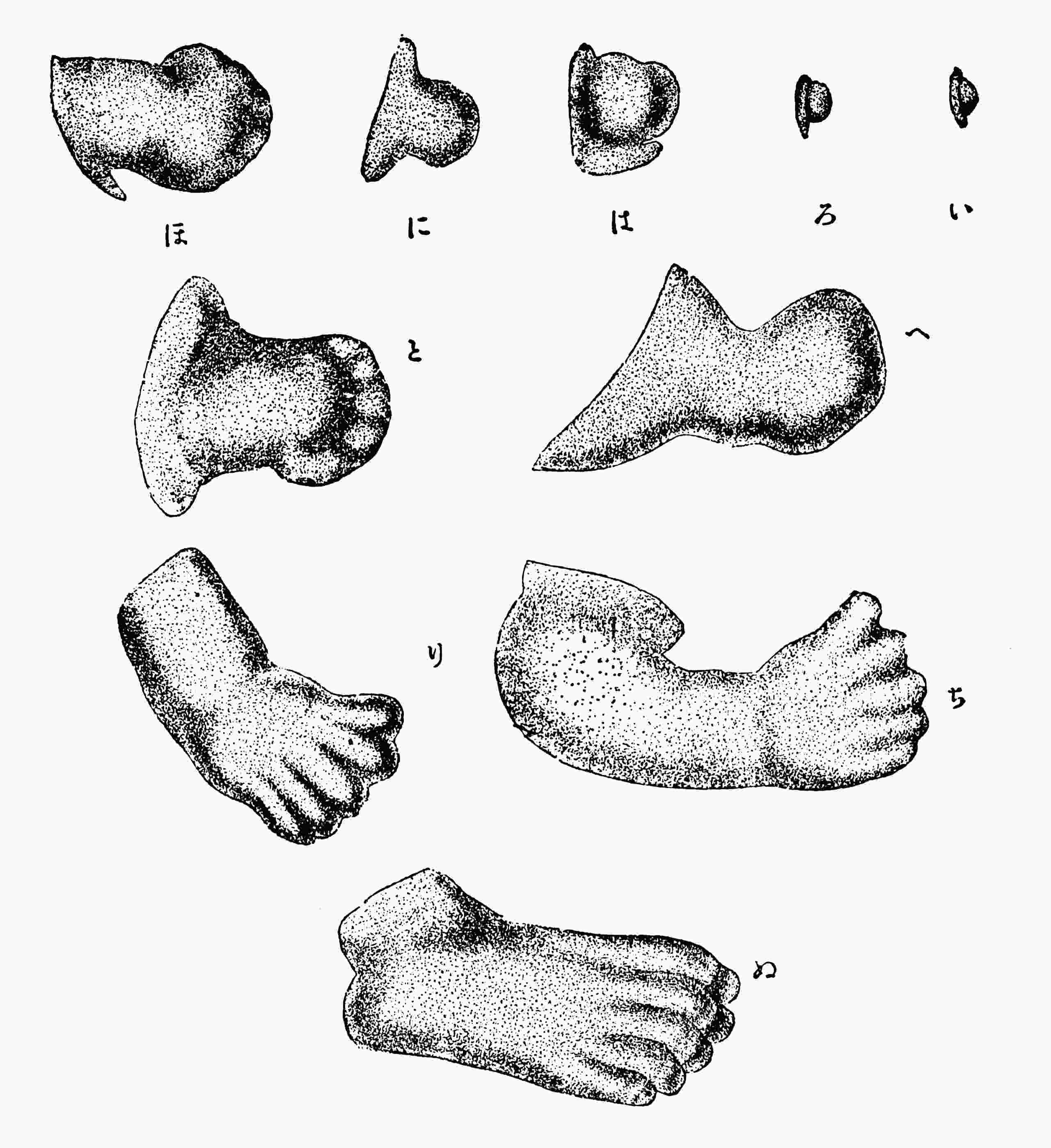 足の発育
足の発育
足のできる具合いはほとんど手と同じであるゆえ、前の図について
述べたことは全部上の図にもあてはまる。ただ手の指の代わりに足の
趾、
肘の代わりに
膝という字を用いさえすれば他にはなにも
変更する
必要はない。
特にでき始まりのころには、手も足も全く同じ形で、とうていこれを
識別することはできぬ。ただ一は
胴の上部に生じ、一は
胴の下部に生ずるゆえ、
位置の
相違によって手であるか足であるかを知り
得るのである。発生の進むに
従い手足の
形状の
相違も少しずつ
現われてくるが、それは
極めて
些細なことで、明らかに手と形が
違うようになるのは、ようやく「ち」図に
示すころからである。このころの足を手にくらべて見ると、
趾がやや短いこと、
拇趾が他の
趾よりも小さくないことに目がつくが、「り」図、「ぬ」図ではこの事がさらに明らかになり、しまいに足に
固有な
形状を
呈するにいたる。
胎内においては一体に足のほうが手よりも発育が
遅れる気味で、手の指が
現われるころには足の
趾はいまだなにも見えず、足の
趾のでき始まるころには手の指はすでにやや長くなっている。
従って生まれ出た赤子も
脚はよほど短いが、出生後はその反対に足のほうが
盛んにのびるので、
成人では
脚のほうが
腕に
比してはるかに大きくなる。されば
腕と
脚との長さの
割合からいうと、
胎児は
猿類と同様であって、人間の人間らしい
脚の長い形は、出生後の
成長によって
初めて
完成するのである。足の
裏は
初め内を向いているが、これも出生後おいおい下を向くようになる。
人間の身体中でもっとも人の
好奇心を
呼ぶものは、なんというても
陰部である。多くの動物におけるごとく、人にも男女の
別があってそれぞれ
陰部の
形状を
異にし、かつつねにこれを
隠蔽する
習慣があるために、
公然これを
熟視する
機会が
与えられぬゆえ、これに対する
好奇心は
勢い
極めて強からざるを
得ない。
解剖図譜のもっとも
手摺れているところは
必ず
陰部の絵のあるところで、
共同便所の
壁のらくがきも多くは
陰部の一筆画であることからおしても、
如何に
陰部が人の
意識を
支配しているかがわかる。
生殖器の一部として考えれば、
外陰部はただ出入口に
過ぎぬから、けっして
肝要な部分ではない。これを
睾丸、
卵巣、
子宮等にくらべれば、あたかも主人と
玄関番とのごとき
関係で、その役目もむしろ
低いものである。しかし
主要な
器官が体内にひそんでいるに反し、この部だけは
直接に外面に
現われているゆえ、その
調査には
困難が少ない。
胎児の発生においても、男女の内部
生殖器を
比較研究するとよほど面白いことがあるが、これは
解剖学、発生学の
特殊の
知識を
要するゆえ、ここには全く
省いて、ただ
外陰部の発育
変化のみについて
述べる。
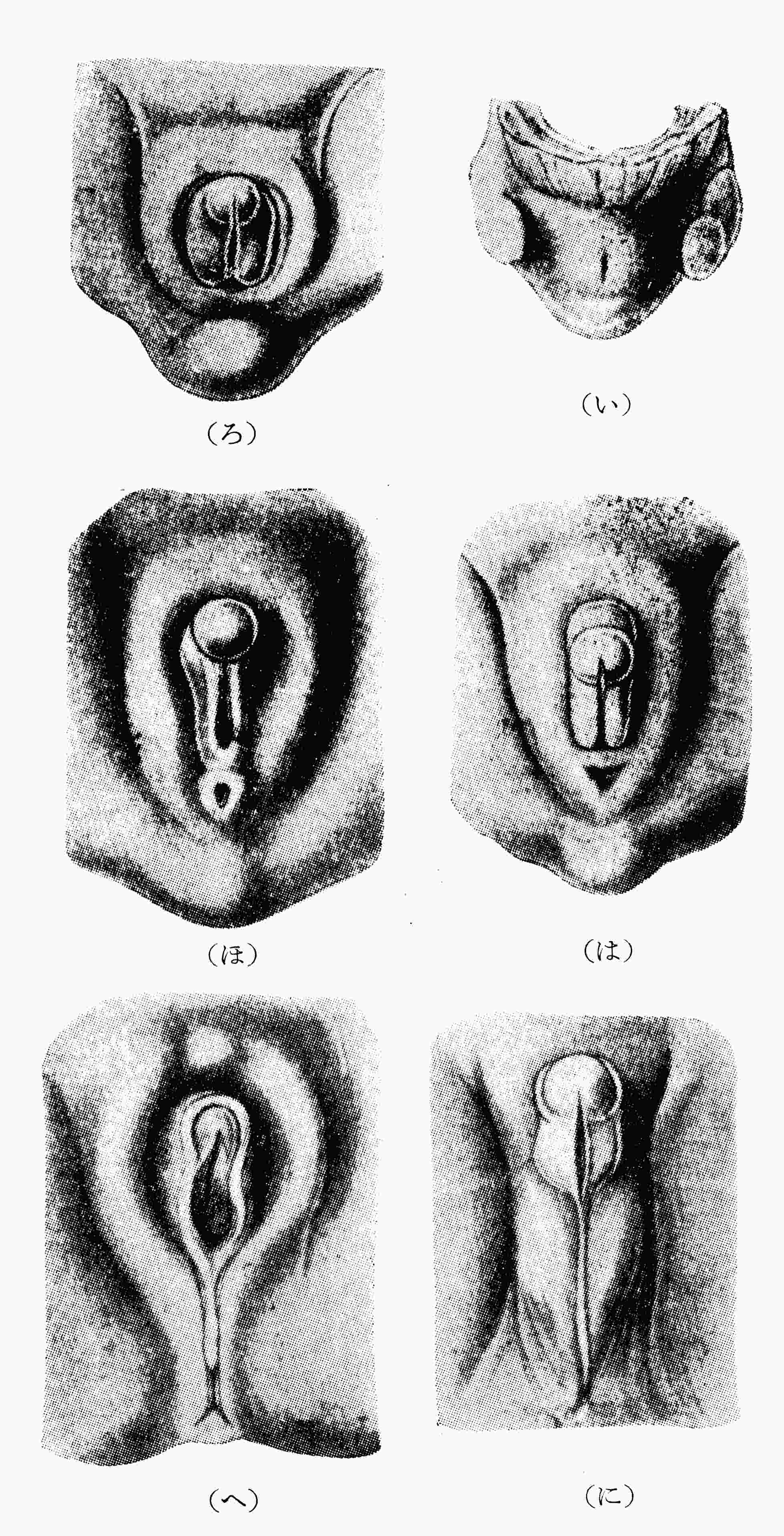 外陰部の発生
次頁
外陰部の発生
次頁に
示したのはすべて人間の
胎児の
外陰部の
郭大した写真である。「い」は第六週の
胎児、「ろ」は第八週の
胎児であるが、このころにはいまだ男女の
別はない。第六週のころには、体の後部の
腹面にあたり、左右両足の間に小さな
縦の
裂目が一つあるだけで、これが
肛門と
生殖器の出口とを
兼ねている。すなわちこの点においては、
鳥類もしくは
獣類中の「かものはし」などと同様である。第八週になると、この
裂目の
前端に小さな丸い
突起ができ、
裂目の
両側には
厚い
縁が生じ、全部を
囲んで土手のごとくに
皮膚の高まったところが
現われる。「は」、「に」はこれより男の
外陰部ができる
順序を
示した図で、「は」は
二箇月半、「に」は
三箇月の
胎児であるが、この二図をくらべれば、一々の部分を
説明せずとも、おいおいに形の整うてゆくありさまが大体わかるであろう。
初め
一個であって
裂目は後には前後の二つに分かれるが、後のは
肛門となり前のは
尿道の出口となる。
三箇月くらいの
胎児では、
外陰部の形もほぼでき上がって、その男なることは明らかに知れるが、
尿道の口はいまだ
陰茎の
末端に開かずしてその下面に開いている。もしこのままに
成長すると、
尿道下裂と
称する
奇形になる。また、
裂目がやや大きいとちょっと男か女かわからぬような、いわゆる
半陰陽のものができる。「ほ」、「へ」の両図は「い」、「ろ」のごとき
状態から、女の
外陰部ができる
順序を
示したものであるが、この場合でも、前と同じく
初め一つの
裂目は前後の二つに分かれ、後のは
肛門となり前のは
陰部の開口となる。「ろ」図で
裂目の
上端に見える円い
突起は、男のほうではだんだん大きくなって
陰茎の
亀頭となるが、女ではそれほど大きくならずに豆のような
陰核となる。また「ろ」図に見える土手のごとき
皮膚の高まりは、男のほうでは
睾丸を
収めるための
陰嚢となるが、女ではそのまま大きくなって
大陰唇となる。
以上述べたとおり、でき上がった男女の外
陰部を
比較すると、一は
突出し一はくぼんで、その間にいちじるしい
相違があるが、発生の始めにはいずれも全く同形で、
二箇月の終わりまでは、男になるか女になるかは少しもわからぬ。それからようやく男女の
相違が少しずつ
現われ発生の進むに
従い、一歩一歩に
相遠ざかって、ついに男女の
区別が
極めて
明瞭になり終わるのである。それゆえ男女の
外陰部は
形状がいちじるしく
違いながら、その
各部分を
互いに
比較して見ると、男のどの部が女のどの部にあたるというように、一々あてはめてくらべることができる。また発育が
不完全であるか、
或る部が
過度に大きくなるかすれば、その
結果として、男か女かわからぬような
曖昧な
外陰部が生ずるわけで、
実際かような
畸形もときどきある。男の子が生まれるか女の子が生まれるかは、あるいはすでに
受精の時に
確定しているかも知れず、また
卵細胞や
精虫に男の子になるべきものと女の子になるべきものとの
二種の
別があるかも知れぬが、これは形に
現われぬから全く知ることができぬ。外形に
現われたところをいうと、人間の
胎児は
二箇月まではいまだ男女の
別がなく、
三箇月目にその
区別が生じ、しかも
徐々に
相遠ざかって、その月の終わりには
胎児の
性が
判然とわかるようになるのである。男と女とは身体上のみならず、
精神的方面にもいちじるしい
相違があって、
互いに
了解することのできぬところも少なくないが、
胎児発生の
模様から
推して考えると、これもけっして根本からの
相違ではなく、同じ
根底から出発しながら、
異なった方向に
発達したために、
互いに
相隔たるにいたったものと思われる。
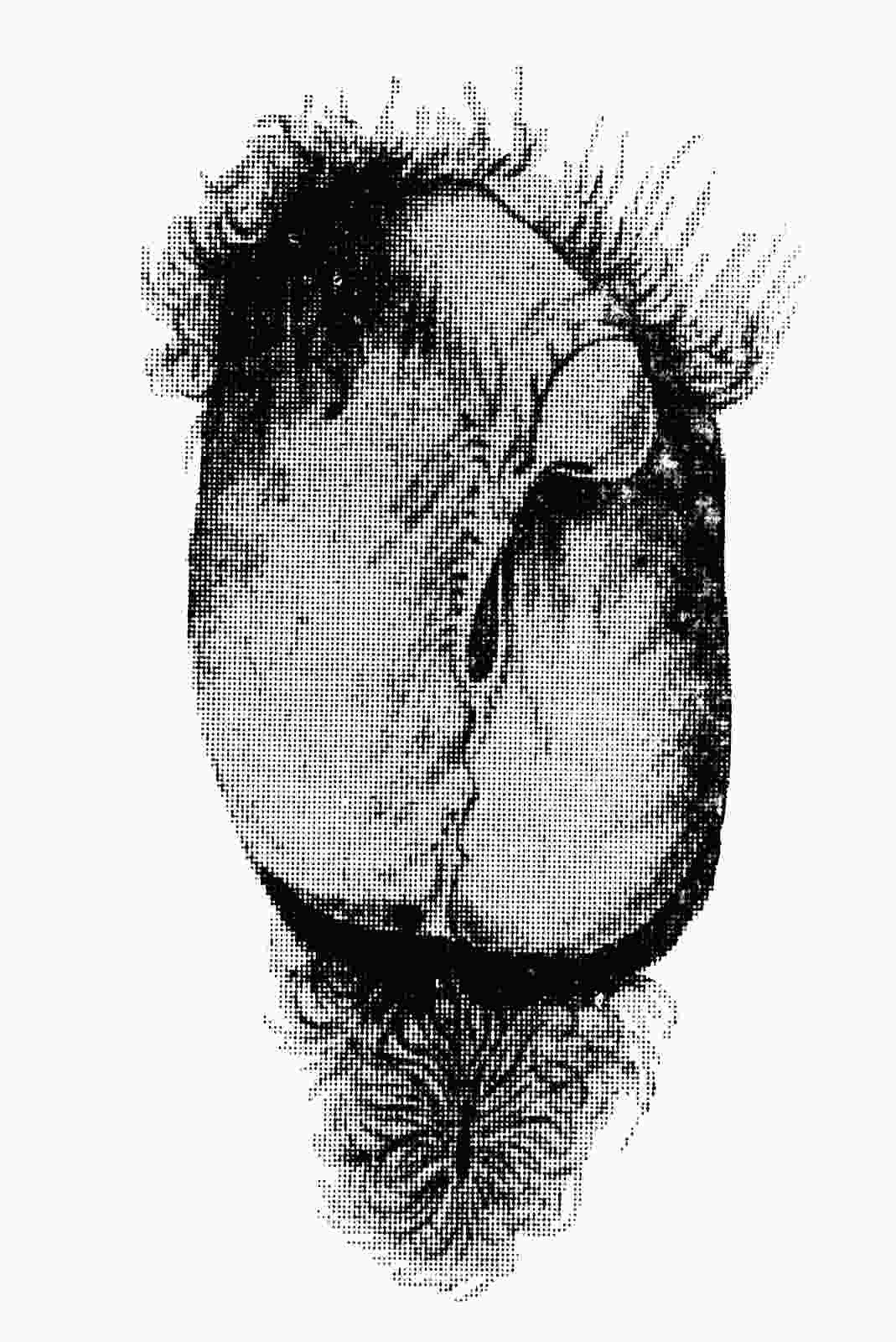 半陰陽
半陰陽
前章と本章とで
説いたところは、人間の
胎児発生中の
若干の点について
極めて
簡単に
述べたのであるが、かような
変化はけっして人間に
限るわけでなく、
如何なる動物でも
卵細胞から、
成長した形までに発育する
途中には、
必ず多少これに
類する
変遷を
通過する。
獣類ならばほとんど終わりまで人間に
似た発生を
経過するが、
鳥類は
途中からいくぶんか
違い、
魚類はさらに早くから
違うというように、人間に
似た動物ほど人間と同様の発生をする時期が長い。これらのことを
詳細に調べるとすこぶる面白い事実もたくさんにあるが、あまり長くなるゆえここにはすべてこれをはぶき、ただ動物発生の
一例として人間自身の
胎児について
述べるにとどめておく。しかし
単に人間の
胎児の発生だけでも、これを知ると知らぬとでは、人々の
知情意の
働きによほど
異なったところが生ずるであろう。たとえば
仏教ではあきらめることの一
方法として、美人を見ても
皮一重剥げばその下は
汚らわしい肉や
腸であると考えさせるとのことであるが、同じ
筆法で
論ずれば、
胎内第五週ころに鼻の
孔と口とが
連なって、顔が「あかえい」に
似ていたことや、
肛門と
生殖器の出口との
別がなく、
単に短い
縦裂であったありさまなどを目の前に考え
浮かべたならば、さらに
有効に思い切ることができるやも知れぬ。
親から
産まれたばかりの
幼児や
卵から
孵ったばかりの
幼児が、親にくらべて小さかるべきは言うまでもないが、ただ大きさの
相違のみならず
形状までがいちじるしく
違うような
種類もずいぶんある。
例えば人間の赤子や
鶏の
雛は大体において体形が親と同じであるが、
蝶の
卵から
孵った毛虫は親の
蝶にくらべると、体形も
習性もまるで
違うてほとんど
似たところはない。生まれた時すでに親に
似ているものは、
成長するにはただ大きくなりさえすればよろしいが、
初め親と形の
違う
種類では、
成長する間に体形がいちじるしく
変わらねばならぬ。親と
異なった形をして
独立生活を始め、
成長するにしたがい体形が
変じて、ついに親と同じ
姿に
達することを
変態と名づける。
変態をする動物では、同一
種類に
属する
個体にも
長幼によってはなはだしい
相違があり、
素性を知らぬ者にはとうてい同一
種のものと思われぬものが多い。
前にも
述べたとおり、たいがいの動物は発生の
初めに
単細胞の時代があり、次に
桑の実のごとき時代があり、次に
胃嚢のごとき時代があり、それより
複雑な
変化をへて
成長した形までに
達するのであるゆえ、発生の始めまでさかのぼれば、
如何なる動物でも
大変化をへぬものはない。されば
変態をする動物とか
変態をせぬ動物とかいうのは、ただいちじるしい体形の
変化を生まれる前にすませるか、または生まれてから後に
変化するかという
相違にすぎぬ。人間でも
胎内の発生までを見れば、毛虫が
蛹になり
蛹が
蝶になるよりもはなはだしい
変化を
経過しているのである。
獣類や
鳥類に
変態するものの
一種もないのは、一は長く
胎内にとどまって親から
滋養分の
供給を受け、一は
卵内に
含まれた
多量の
滋養物を
費して親と同じ形に
達するまでの
変化を、生まれ出る前にすませ
得るゆえであろう。
動物の
変態でもっともよく人に知られた
例は、おそらく
蛙と
昆虫類とであろう。
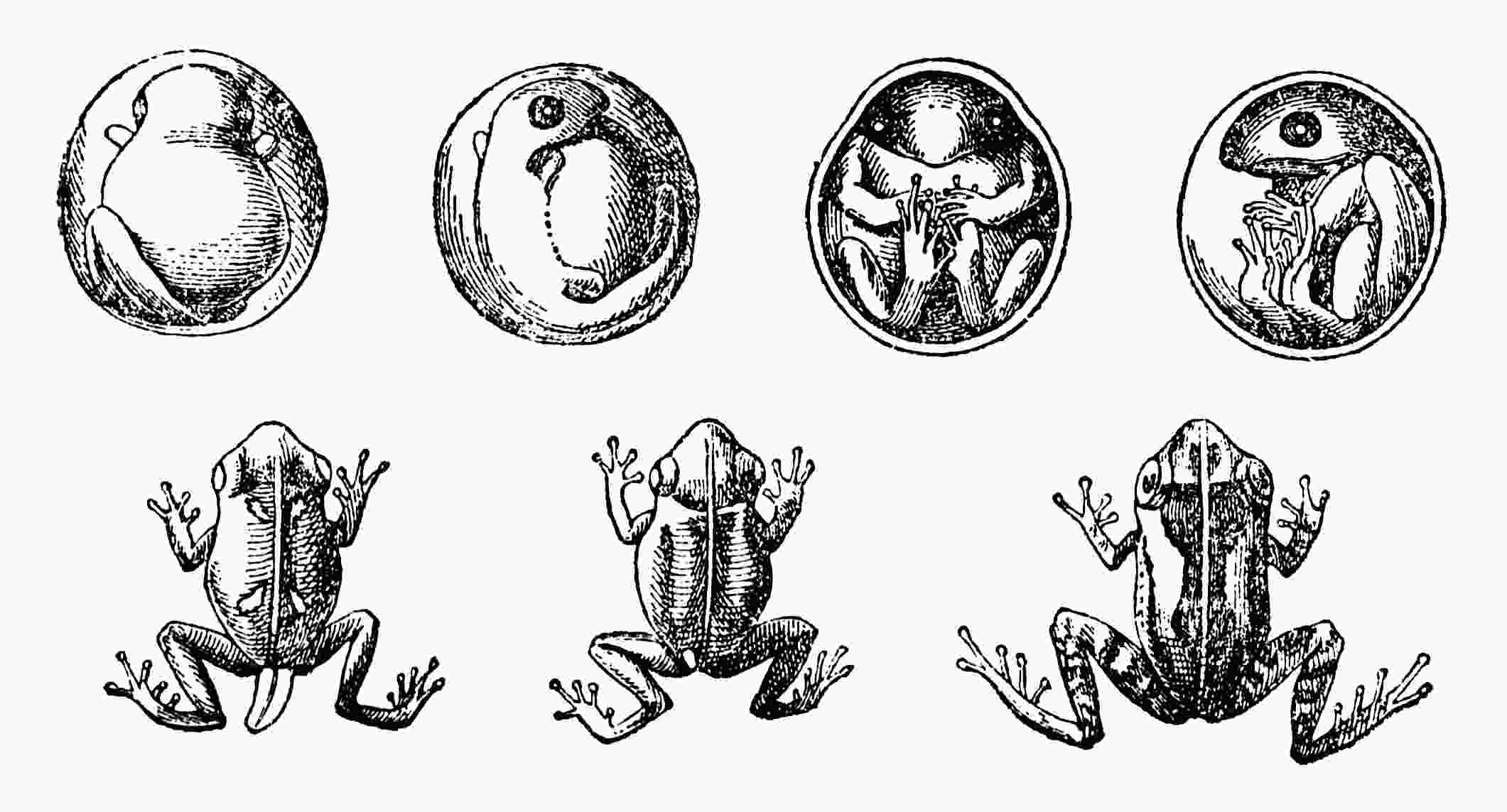 アメリカ熱帯地方産のマルチニック蛙の発生
蛙
アメリカ熱帯地方産のマルチニック蛙の発生
蛙の
変態は全く今
述べたごとき
性質のもので、もしも
卵が大きくあったならば、
孵化する前にすませ
得べきはずの
変化を
卵が小さくて
滋養分がたらぬために、止むを
得ず
孵化した後にするように見える。その
証拠には外国
産の
蛙で大きな
卵を
産む
種類では、
変態は全くなくて、
孵り立てから、すでに
四肢を
備えた親と同じ形の小さな
蛙ができる。わが国の
普通の
蛙は、春先に池や
沼におのおの千何百というたくさんの黒い
卵を
産み
卵からはまず「おたまじゃくし」が
孵って出て水中を
游ぎまわり、
水垢などを食うて、よほど大きくなってから
初めて
陸上にはい上がる。「おたまじゃくし」は
最初は前足も後足もなく
尾を
振って泳ぎ、
鰓で水を
呼吸して少しも
魚類と
違わぬが、
成長が進むとまず後足が生じ、次に前足が
現われる。しかし水中にいる間は、足は小さくて運動には何の役にも立たぬ。しかるにいったん
陸上へ出ると、足はたちまち大きくなり、
尾は
次第に
縮み、かくて小さな
蛙の形ができ上がる。五六月ごろに道行く人に
踏み
潰されるほど、たくさんに池の
近辺の路上に
飛び歩いている
蛙の子は、みなこれだけの
変態を
経過したものである。たいがいの
蛙はこのとおりの
変態をするが、アメリカ
熱帯地方の島に広く
産する
一種の
雨蛙では、
卵の中で
蛙の形まで発育し、
陸上で
孵化して直ちに
陸上を
躍ねまわる。もっとも
卵からでた時には、体の
後端に短い
尾の
徴がついているが、これは半日もたたぬうちに取れて落ちる。かようにこの
蛙は
普通の
蛙と
違うて
変態をせぬが、その代わり
卵は
非常に大きくて、その生まれる数もはなはだ少ない。すなわち親は
普通の
雨蛙ぐらいの大きさでありながら、
卵は
直径が
一分五厘(注:4.5mm)
以上もあり、数はわずかに十五か二十より
産まれぬ。
変態をせぬ
蛙はこのほかにもなお
幾種類もあるが、いずれも大きな
卵を数少なく
産むものばかりである。
昆虫類には
変態をするものとせぬものとがあるが、これは
必ずしも
卵の大きなものならば、
卵の内で
経過すべき
変化を、
卵の小さいものでは
止むを
得ず
孵化後に行なうというわけではない。
蝶、
蛾や
蜂、
蠅などに見るいちじるしい
変態は、むしろ
一生涯の仕事を前後の二期に分かち、おのおのその期の
働きに
適する体形を有するために、
次第生じたもののごとくに思われる。前にも
述べたとおり、動物の
生涯の仕事は食うて
産むにあるが、
昆虫類の
或る者では
一生涯を前後の二期に分かち、前期にはもっばら食うことばかりを
努め、後期には主として
産むことに力をつくし、これがすめば生活の役目を終わったものとして死んでしまう。
例えば
蝶、
蛾の
類でいえば
芋虫、毛虫などの
幼虫時代には体形
構造ともにもっぱら食うことに
適し、
翅が生えて空中を
飛びまわる、
成虫時代には体形
構造ともに全く
産むことに
適している。これはおそらく、
一生涯を通じて、同一の体形を有し、同一の
構造をもって食うこと
産むことを
兼ね行なうよりははるかに
有利であるために、一歩一歩
幼虫と
成虫との
相違の
程度が進み来たった
結果であろう。されば
昆虫類では「ばった」、「いなご」のごとくに、
卵から
孵化したときすでに親に
似た形を
呈し、いちじるしい
変態なしに
成長し終わるものは、進化の
程度のもっとも
低いものであって、
蝶、
蛾の
類や
蜂、
蠅のごとき
幼虫と
成虫との
相違のすこぶるいちじるしいものは、もと
変態をせぬ
先祖から起こり、一歩一歩進化して今日の
状態に
達したものと考えねばならぬ。しこうして
幼虫と
成虫との体形や
構造があまりいちじるしく
相違する
類では、
昨日まで
幼虫であったものが、今日は皮を
脱いで直ちに
成虫になるというわけにゆかぬゆえ、その間に
構造変更のために
若干の時期を
要する。
通常蛹と
称するのはすなわちこの期間のものである。多くは
静止して動かぬゆえ、外から見てはもっとも活動の少ない時のごとくに思われるが、体内の
組織を調べると実に
一生涯中の
最大変動の時期で、
幼虫時代の
諸器官はほとんど全部
消滅し、そのわずかに
残っている部から新たに
成虫の
諸器官が生じ、しばらくの間にほとんど
別物かと思われるほどの
成虫の体ができ上がるのである。
かくのごとく、
変態という中には、
卵が小さく
滋養分がたらぬため、親と同じ形までに
達せぬうちに生まれ出るより起こる場合と、
一生涯に行なうべき仕事を、前後に分けて
努めるために起こる場合とがある。
蛙の
変態は前の場合の
例であって、このほうの
変態は
卵が大きくなるか、または
胎生にでもなれば、せずにすむべきものである。
現にアメリカ
熱帯の
雨蛙の
一種では、「おたまじゃくし」時代を
卵の中で
経過する。しかも生まれ出た
蛙は、かつ食いかつ
産み
得る
構造を
備えているゆえ、
個体の
生存にも
種族の
維持にも何らの
差支えが生ぜぬ。これに反して、
蝶や
蛾の
変態は後の場合の
例であって、このほうは
如何に体を大きくしても、
幼虫時代をその中で過ごさせ、直ちに
成虫の
姿で生まれいでしめることはできぬ。
何故というに、
幼虫と
成虫とは、
一生涯の仕事なる食うことと
産むことをそれぞれ
専門として
分担しているゆえ、いずれの一方を
欠いても、
種族の
生存をつづけることができぬからである。
実際にはこの両方の中間に
位するような場合もたくさんにあるが、いずれにしても、
幼者は
幼者として
特別の
任務があって、
単に
成長するための
階梯とのみ見なすことのできぬものが多い。人間のごときは
特に
変態ということはないが、やはり
幼者にはまた
幼年のときでなければできぬような
自然の
務めがあって、けっして
成人の小さなものとして取り
扱うべきものでなかろう。
同じく
変態をする動物の中でも、
卵の小さい
種類は
卵の大きな
種類にくらべると子が早く
孵るために、
変態をよけいに
経過しなければならぬことは、さまざまの動物について明らかに見られる。
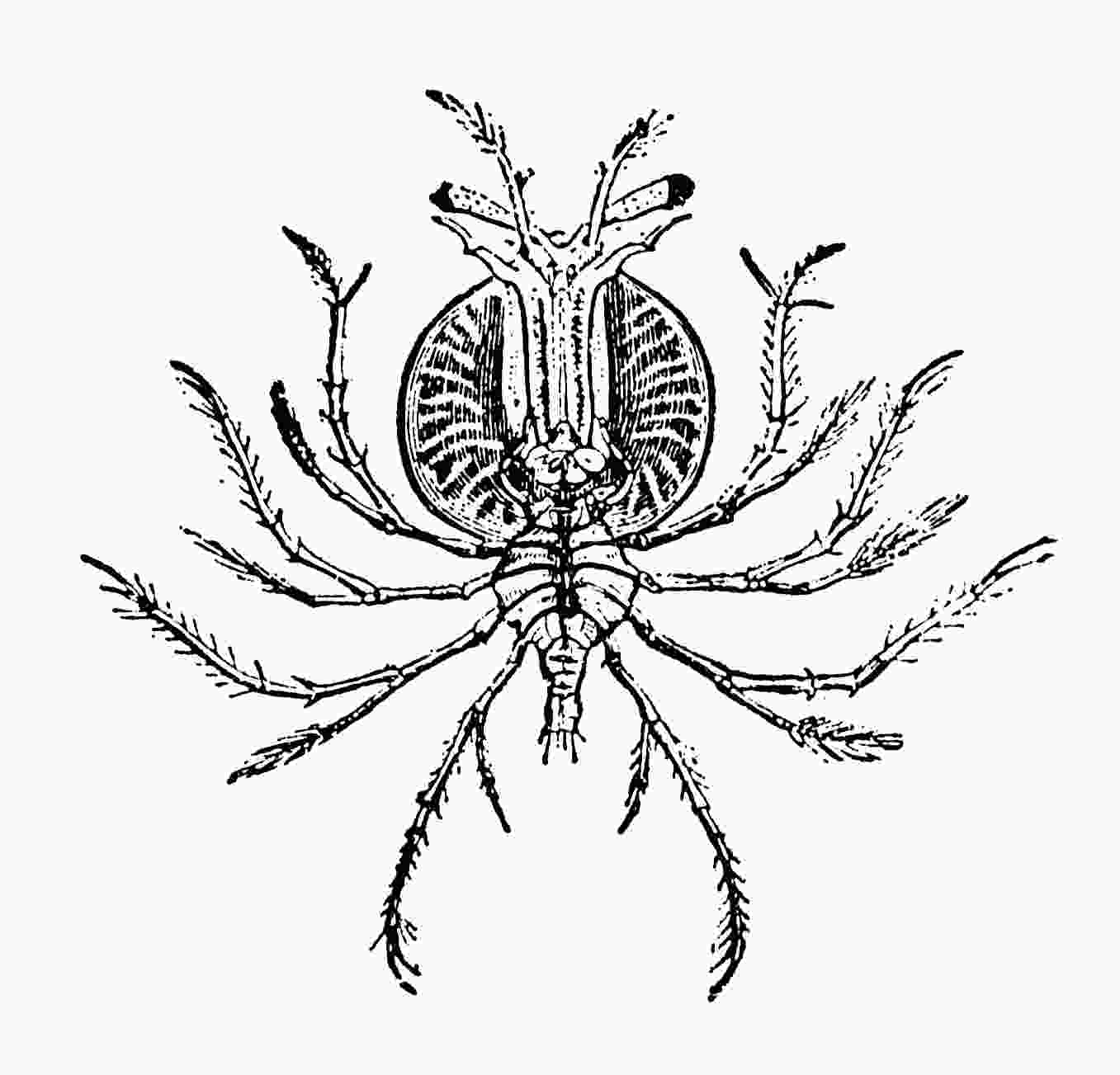 伊勢えびの幼虫
伊勢えびの幼虫
「えび」
類のごときもその
一例で、大きな
卵を
産む「えび」の
種類では小さな
卵を
産む
種類にくらべると、一つ次の
段から
変態を始める。いったい
甲殻類はずいぶん
変態のいちじるしいもので、何度も体形が
変わって
後に、
初めて
成長した形に
達するゆえ、親はよく知られながら、子の全く知られていない場合もいくらもある。「
伊勢えび」のごときも親の形はだれも見知っているが、その
幼時ガラス
細工のごとくに
透明で、海の表面に
浮かんでいるころの美しい
姿を知っている人はまれであろう。また
甲殻類には「えび」、
蟹のほかに「船虫」、「わらじ虫」、「みじんこ」、「ふじつぼ」など実にさまざまの形のものがあって、これがことごとく
変態をするが、その出発点と見なすべき形は
不思議によく
一致している。
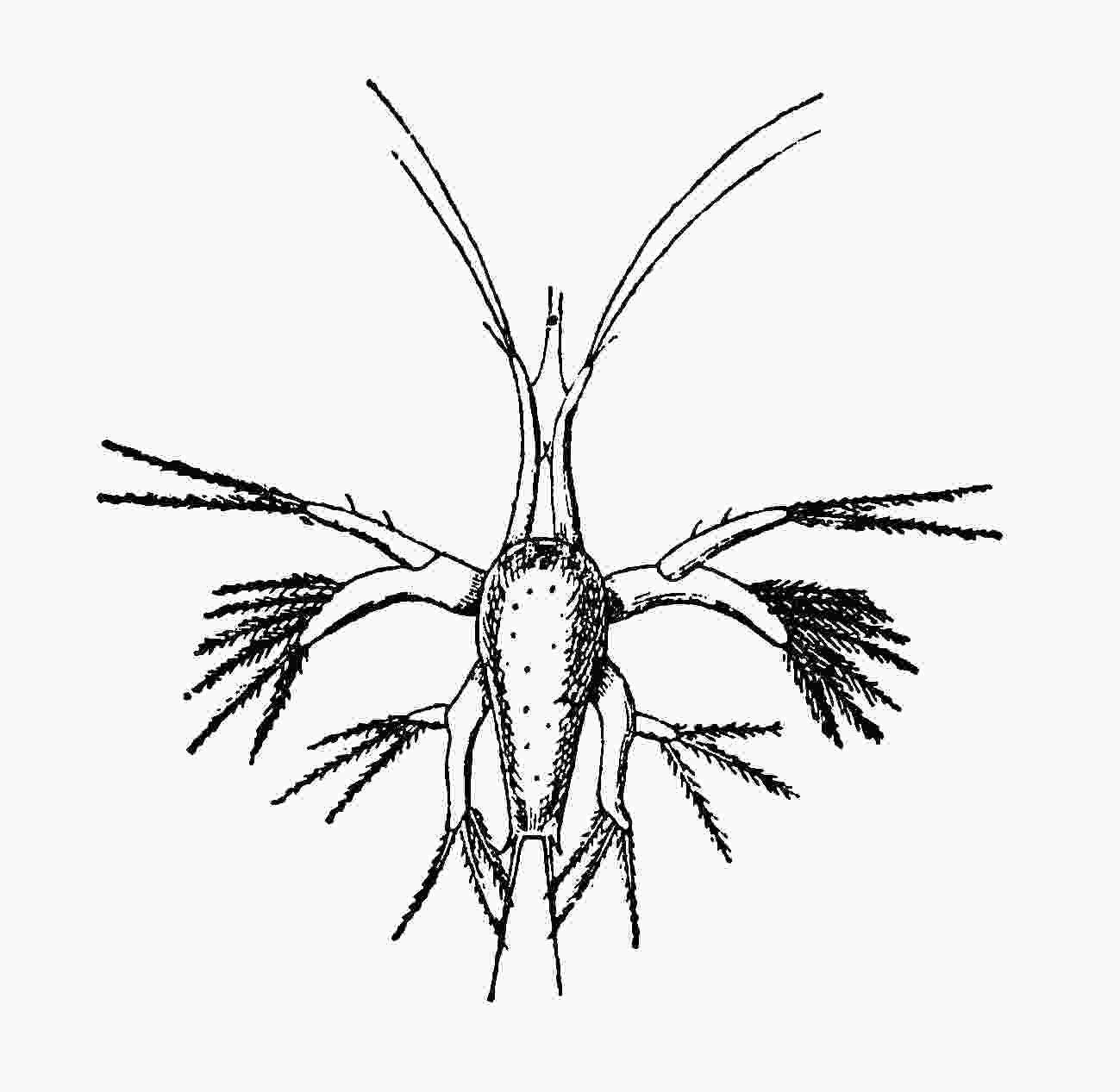 ナウプリウス
ナウプリウス
すなわち、「みじんこ」でも「ふじつぼ」でも、
卵から
孵ったばかりの
幼虫は、体は
楕円形で、
腹面に
必ず三対の足を
備え、これを用いて活発に水中を
游ぎまわっているが、他の
甲殻類もすべてそのとおりで、発生の
途中に一度は
必ず三対の足を
備えた、いわゆる「ナウプリウス」時代を
経過する。「えび」
類の子もむろんこの時代を
通過するが、
卵の大きな
種類ではこれを
卵の中ですませ、
卵の小さな
種類では
孵化した後
暫時この形で
独立生活をする。
例えば青森、
北海道などに
産する「ざりがに」と
称する
鋏の大きな「えび」は、
粒の大きな
卵を
産むが、これより
孵化する
子供は、「ナウプリウス」時代を
卵の内ですでにすませ、その次の
段の形となっている。しかるに「
芝えび」などでは
卵がはるかに小さいゆえ、その内ではようやく「ナウプリウス」の形までにより発育することができず、
孵化して後もしばらくはその形で生活している。すなわち
卵の大きな
種類では、
個体の発生中に起こるべき体形の
変化の大部分を
卵の内ですますゆえ、
孵化して後の
変態はそれだけ少なくなり、
卵の小さな
種類では、
滋養分が早く
尽きて子は早く生まれ出るゆえ、
孵化して後にそれだけ多くの
変態をせねばならぬ
理屈になる。これを人間の生活にくらべて言えば、
卵の内の
滋養分はあたかも
子供の
学資のごときもので、大きな
卵を
産む動物は十分な
学資を
遺す親、また小さな
卵を
産む動物はろくに
学資を
遺さぬ親に
似ている。
学資を十分にもろうた
子供は大学を
卒業するまで遊んでいられるが、
学資のたらぬものは止むを
得ず、新聞を売ったり、
牛乳を配ったりして自活しながら勉強せねばならぬ。この点からいうと、
甲殻類の「ナウプリウス」のごときは
一種の苦学生とも言える。
卵の大小についてはすでに前にも
述べたが、
種族維持の
目的から見ると、いずれも
一得一失があり、
各種動物の生活の
事情が
異なるにしたがい、大きな
卵を
産むほうが
利益になる場合もあれば、またその反対の場合もあろう。
卵が大きければ、
勢い数は少なからざるを
得ぬゆえ、それより生じた大きな
完全な子が
一匹死んでも、
種族に取って軽からぬ
損失となるが、小さな
卵ならば
無数に
産めるゆえ、それより生じた子が
百匹や
二百匹死んでも、
種族としては少しも
痛痒を感ぜぬ。
各種の動物は、
卵を大きくしてその数を
減らすか、
卵を小さくしてその数を
増すかの
二途のうち、一方を
採るのほかはないが、小さな
卵を数多く
産むならば、
必ずいくらかの
変態をせぬわけにはゆかず、
変態をすれば、
長幼の間にいちじるしい
相違が生ずる。
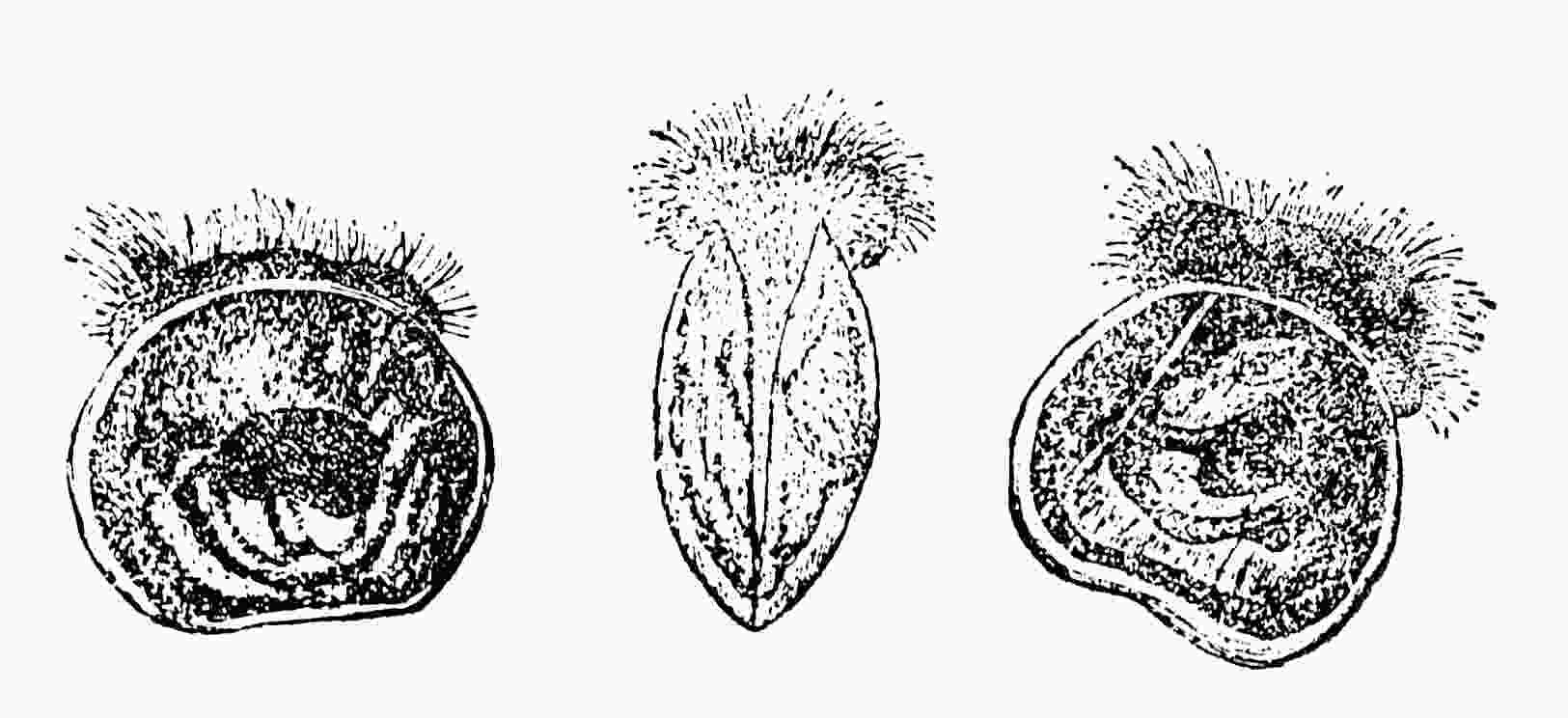 かきの幼児
かきの幼児
なお一つ
例をあげて見るに、
貝類は
蛤、「あさり」のごとき
二枚貝でも、「さざえ」、「あかにし」などのごとき
巻貝でも、たいていは目に見えぬほどの小さな
卵を数多く
産むものゆえ、その
初めて
孵化した
幼児は親とは全く
形状が
違い、
繊毛を
振り動かして
水面を
游ぎまわり、自活しながら
幾度か体形を
変じた後、ついに
海底に
沈んで、親と同じような形のものとなる。しかるに同じ
軟体動物でも、「たこ」、「いか」の
類は
葡萄の
粒くらいの大きな
卵を
産み、それより
孵化した
幼児は
初めから全く親と同じ形をしている。前の
譬にあてて言えば、「たこ」、「いか」の子はまず
相応の学校を
卒業してから社会へ出るようなもので、これを他の
貝類の子が
幼少の時から、自活のために
種々の
危険を
冒しているのにくらべると、よほど安全であるが、その代わり生まれる数においては、他の
貝類の子の
無数なるにくらべると、とうてい足もとにもよれぬ。
魚類も小さな
卵を
産む
種類が多いゆえ、
幼魚と親との
形状の
違うことは
極めて
普通である。もっとも
卵から出たときからすでに
脊椎動物としての形を
備えているゆえ、
変態というても、多くは
単に身体
諸部の
割合が
変わったりするだけで、
昆虫類に見るようなはげしい
変態はない。しかしながら多くの中には
幼魚の形が全く親と
違うので、親も知られ子も知られながら、それが
互いに親子であることが長く知られずにいたような
例もいくつかある。
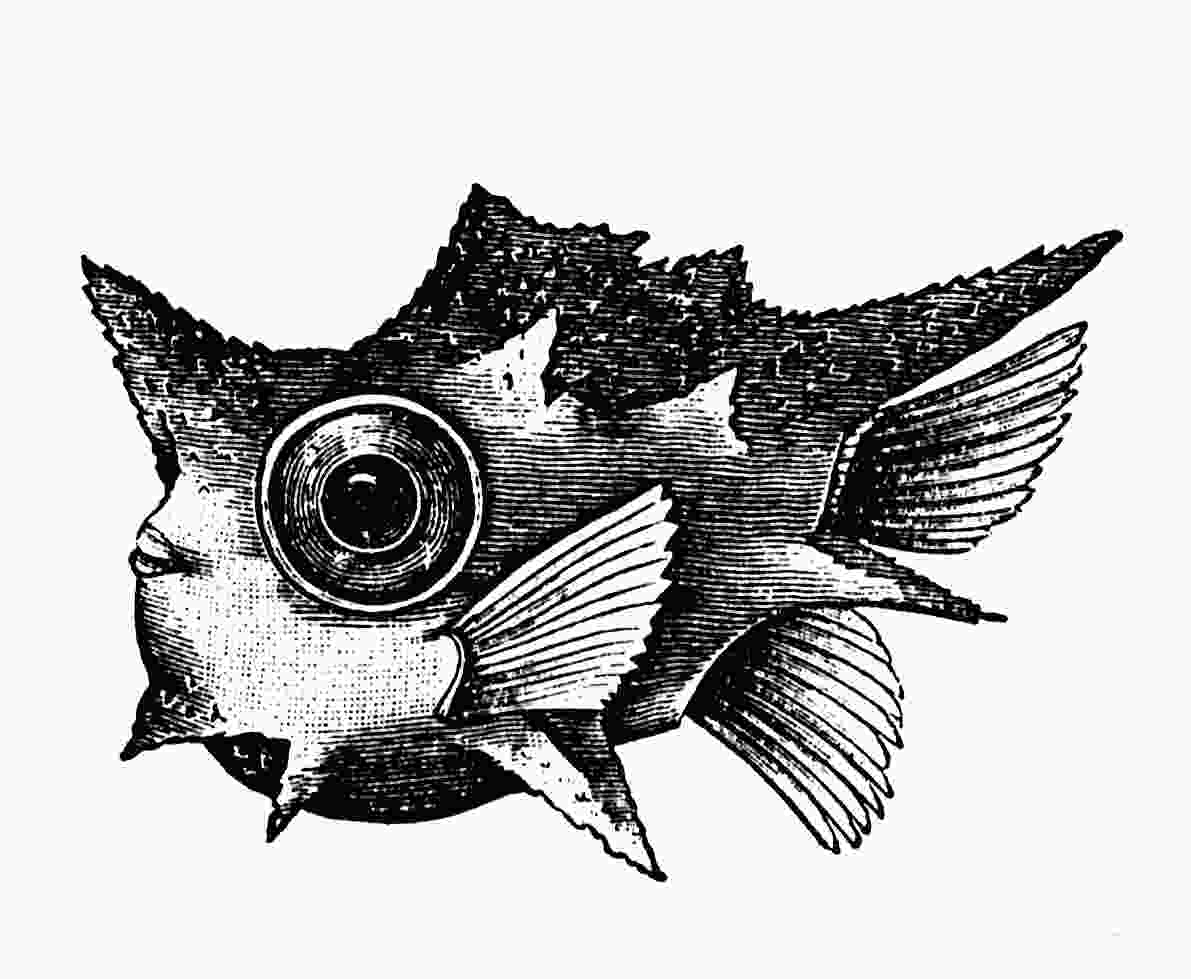 まんぼうのもっとも若き幼児
まんぼうのもっとも若き幼児
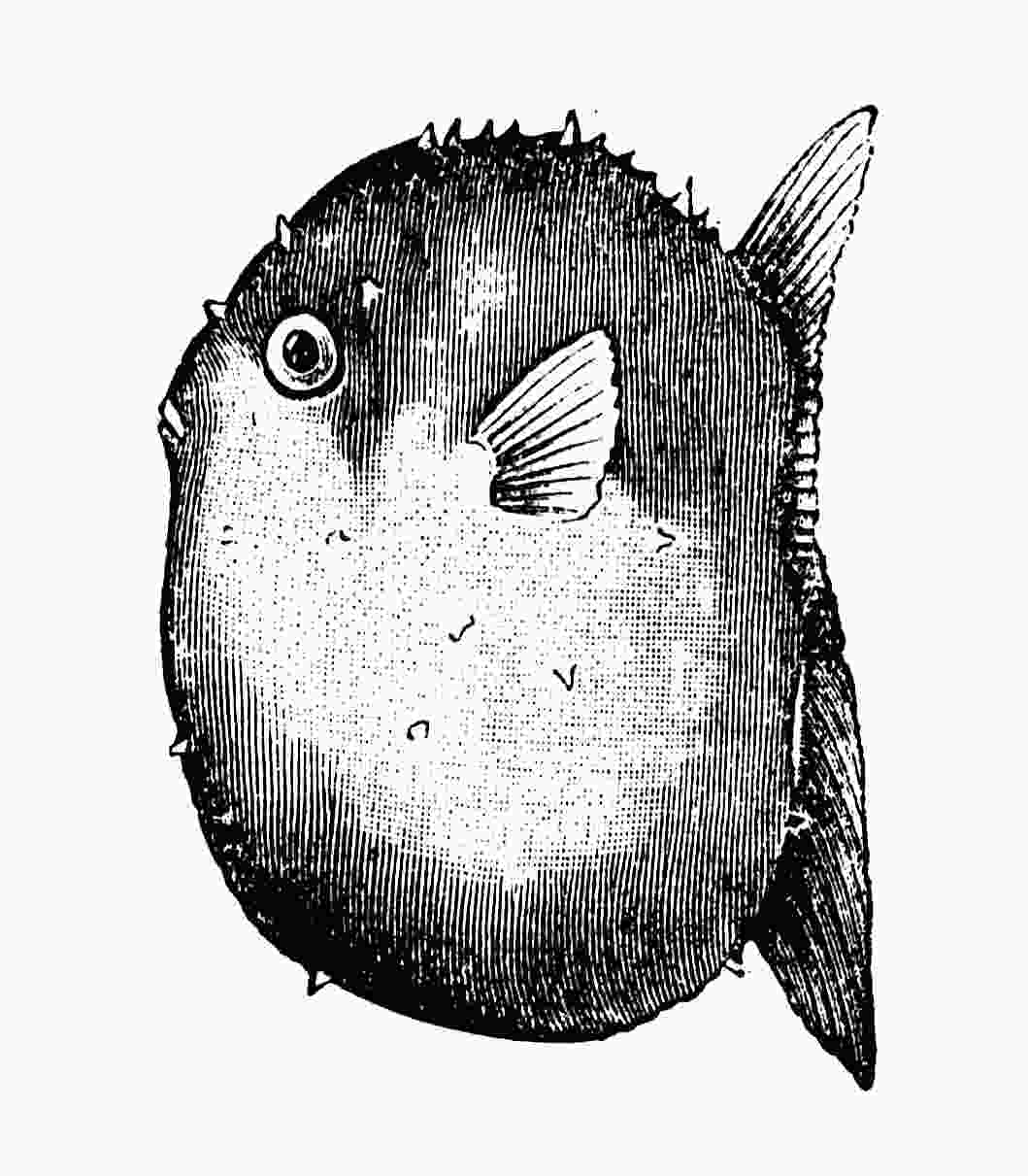 まんぼうの幼児
まんぼうの幼児
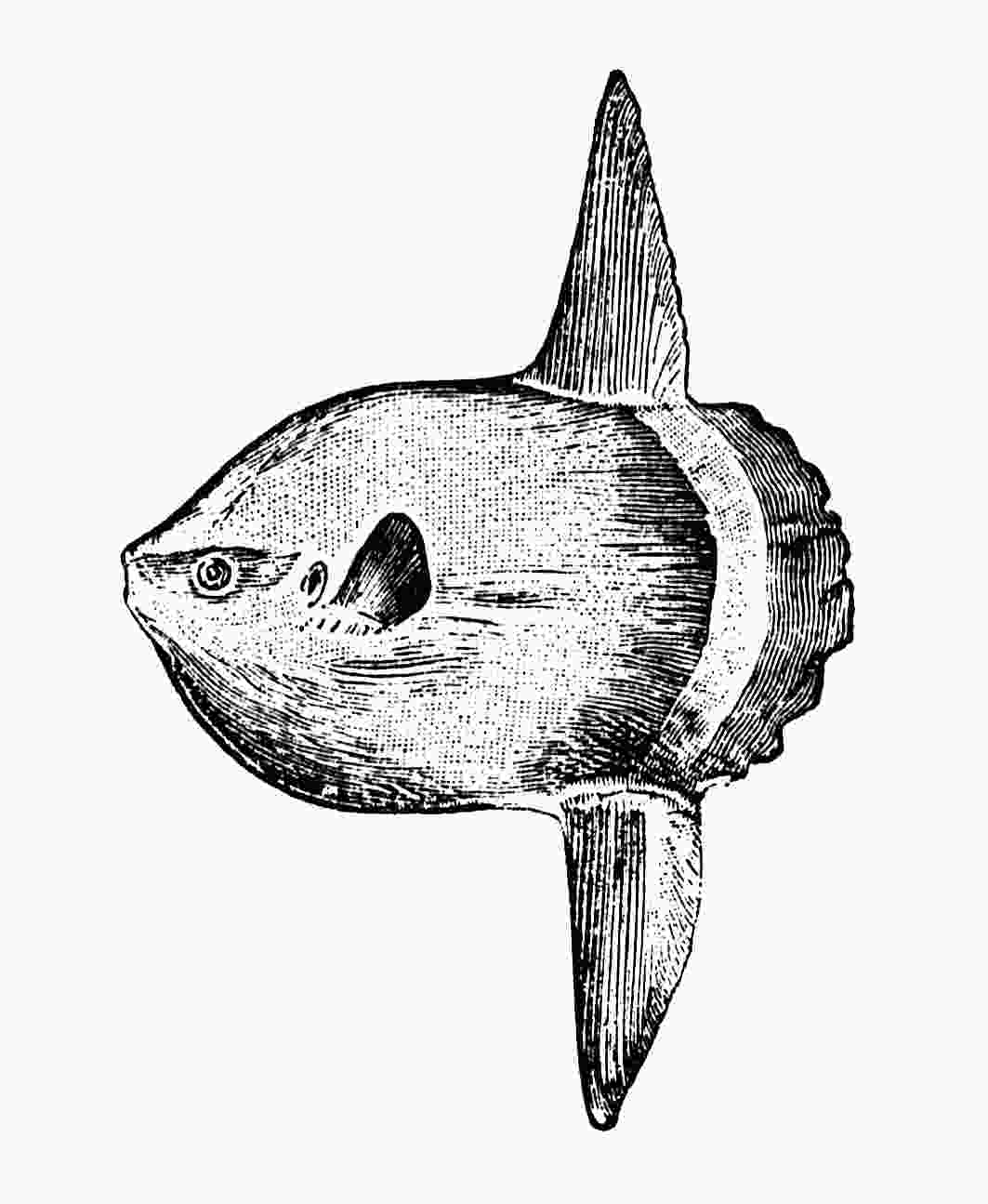 まんぼうの親
例
まんぼうの親
例えばここに図を
示した「まんぼう」のごときも、その
幼魚を
初めて見たものは、けっしてこれを親と同
種類の魚であるとは心づかぬに
違いない。
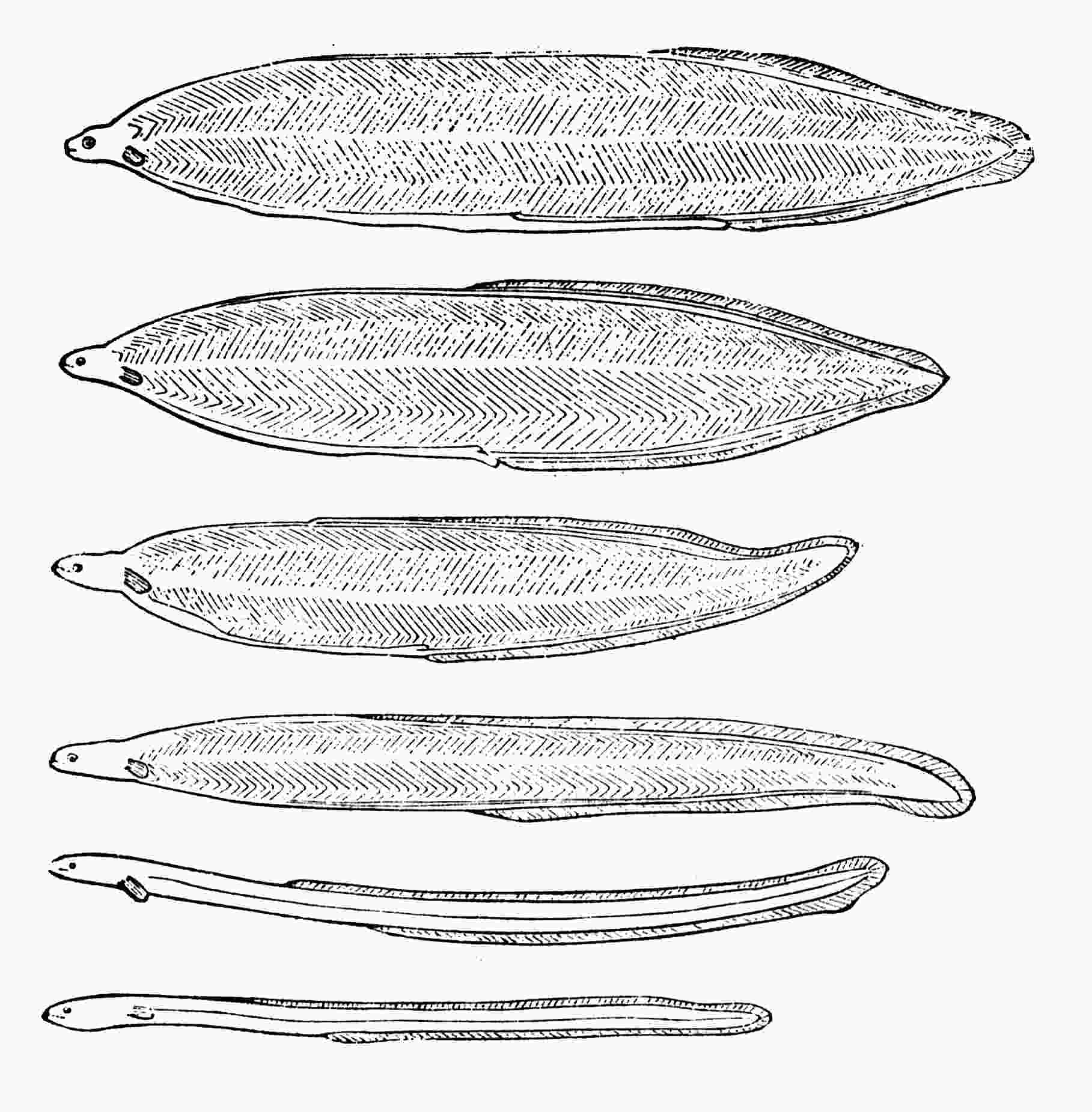 うなぎの発生
うなぎの発生
「
鰻」なども
幼魚が
確かに
鰻の
子供として知られるにいたったのは、今よりわずかに十数年前のことにすぎぬ。
鰻はわが国ではどこの池にも
沼にも
普通にいるもので、肉は
蒲焼にでもすると、すこぶる
美味であるゆえ、昔からだれにも知られているが、
鰻がいつどこで
卵を
産むやら、またその
卵から
如何なる形の子が
孵って出るやら少しも知られなかった。
何匹捕えて
腹を
割いて見ても
卵の見つけられることはほとんどなく、またあっても
卵の
粒が
極めて小さいゆえ、
普通の人には
卵とは気がつかぬくらいである。それゆえ
鰻の
繁殖に
関してはさまざまの
俗説が行なわれ、
鰻は
胎生すると
唱えている地方もたくさんある。
鰻の
胎児というものは
幾度も見せられたことがあるが、いずれもみな
鰻の
腹の中に
寄生する
一種の
蛔虫であった。
胎生説はおそらくこの
間違いから起こったものであろう。かくのごとく
鰻の
繁殖法は長い間全くわからずにあったが、その後だんだん調べた
結果、
鰻は
産卵するには
河を下って海に出て、やや深いところの
底まで行って
産むもので、その
卵から
孵った
幼児は、一時親の
鰻とは少しも
似たところのない、
透明なひらたい
奇妙な魚になることが
確かに知れるにいたった。しかもこの
幼魚は、すでに前から
漁師などの知っていたもので、日本ではこの
類を「びいどろうお」と名づけていた。「びいどろうお」は
底を引く
網にはいくらもかかってくるが、その
透明なることは
実際ガラスのとおりで、水中では全く見えぬくらいである。体は
柳の葉のごとき形で長さ
五六寸(注:15~18cm)にもなるが、これがさらに
成長すると、
不思議なことにはここに図に
示すごとくに、体がだんだん
縮小し、
幅は
狭くなり、長さも
減じ、その間に黒い
色素が生じて、しまいに小さな
鰻の形ができ上がる。この
程度まで
達すると、
鰻の
幼魚は
河をさかのぼり、小川や
溝を
伝うて池や
堀まで
達し、そこにとどまって大きくなるのである。
幼魚が
河を上るときは実に
盛んなもので、何百万か何千万かわからぬほどの
大群が、ただ流れに
逆うて上へ上へと進んで行くゆえ、
手拭ですくうても
百匹くらいは直ちに取れる。
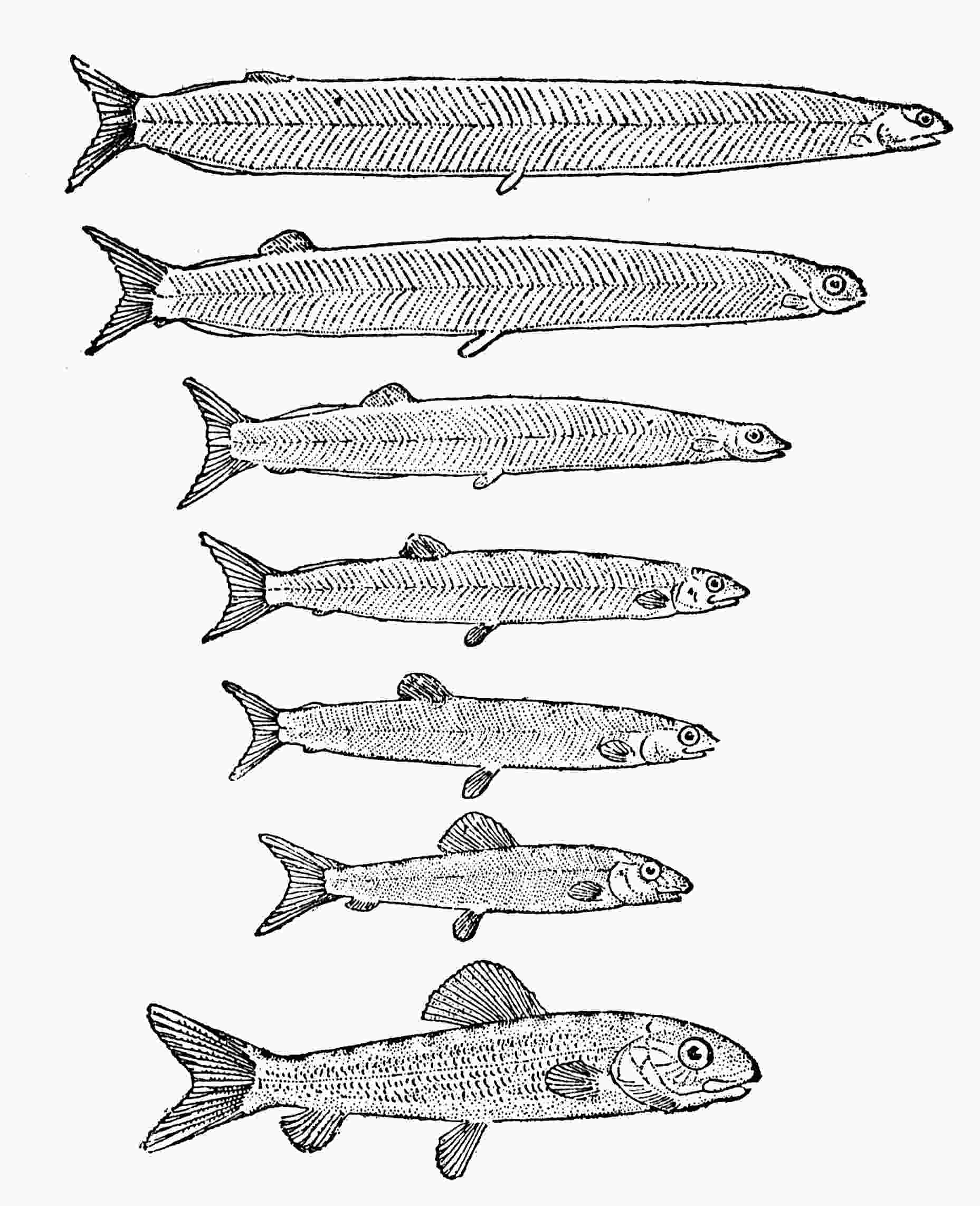 アメリカ魚の発生
成長
アメリカ魚の発生
成長するにしたがうて体が小さくなることはちょっと
奇態に考えられるが、かような
例はなおいくらもある。ここに図をかかげたのはアメリカ、カリフォルニア
産の魚であるが、これも
幼魚の時代には白魚によく
似た形で、体が
柔らかく
透明で
成長するにしたがい体長は
約二分の一に
減じながら、
次第に親の形に近づいてくる。
 不思議蛙とその子
不思議蛙とその子
また「おたまじゃくし」は
蛙の子であるから、
蛙よりも小さいのはつねであるが、
種類によっては親よりもはるかに大きいものもある。南アメリカに
産する「
不思議蛙」という
種類では、親の体は長さ
一寸五分(注:4.5cm)くらいにすぎぬが、その
産んだ
卵からできた「おたまじゃくし」は、もっとも大きいときは長さ
八寸(注:24cm)あまりにもなる。そのときは
胴だけでも
二寸五分(注:7.5cm)くらいもあり、
尾の幅も
三寸(注:9cm)
以上に
達するゆえ、親の
蛙にくらべると実に
何層倍も大きく、ほとんど
象と人間とをならべたごとくである。しかしそれより
成長が進むと、「おたまじゃくし」の体はだんだん
締って、一度は親よりも小さくなり、さらに
成長してついに親と同じものになる。
鰻の
幼魚でも、今
述べた
蛙の「おたまじゃくし」でも、一度大きかったものが、
成長とともに
縮むのは
何故かというに、これはけっして身体の生きた
物質が
減少するわけではなく、
単に水分が
減るだけである。
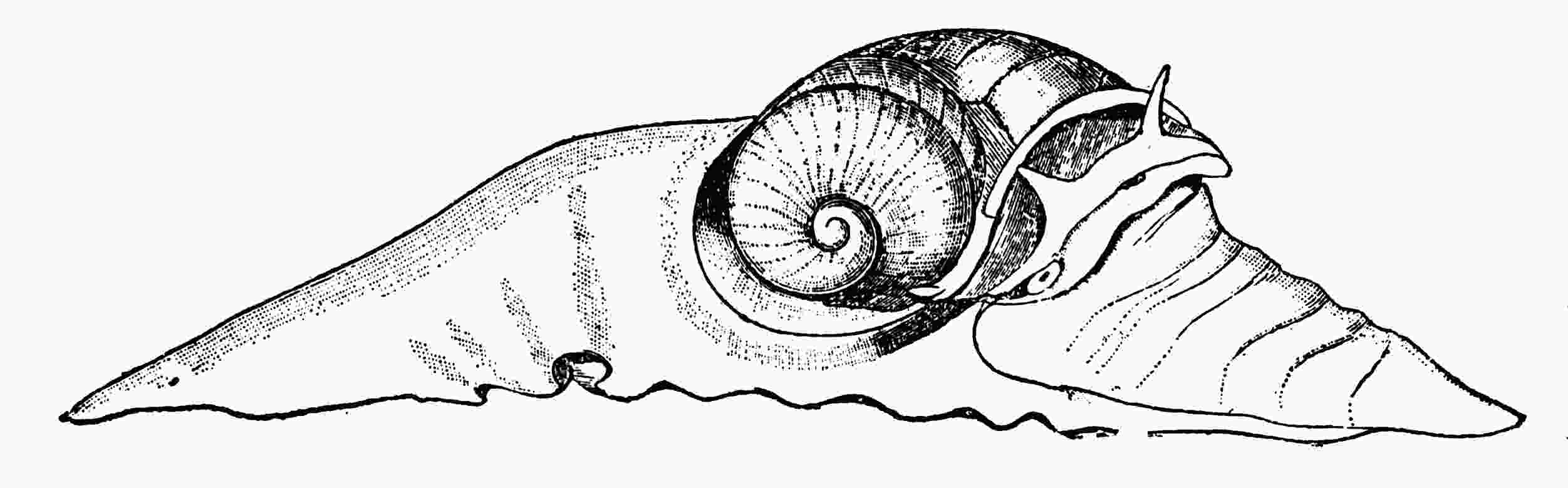 つめた貝
成長
つめた貝
成長とは
関係のないことではあるが、動物の体が水を
吸うて大きくなり、水を
吐いて小さくなることはつねに見るところで、
浅い
海底の
砂の中にいる「つめた貝」なども、体を
延ばしているところを見るとすこぶる大きくて、これが
如何にして小さな
貝殻の中へ引き
込み
得るかと、実に
不思議にたえられぬ。しかるにこれを手に取ると、貝の
柔らかい身体からはあたかも
濡手拭でも
絞る時のごとくに、
盛んに水が
滴り落ち、水が出ただけ体が小さくなって、ついには始めの何分の一かに
縮み、
容易に
貝殻の内に
収まってしまう。
鰻や
不思議蛙が
初め
成長とともに小さくなるのは、けっしてかく
急激に水を
失うのではないが、
漸々水分を
減じさえすれば、真の生活する
物質は
殖えながら、外見上の体の大きさを
縮めることはできる。しこうして、
幼児に
特に
多量の水分を
含むのはなんのためかというに、これはおそらく、体を大きくするか、または体を
透明にするためであって、いずれにしても
種族の
生存上、
特に
幼児にその
必要があるゆえであろう。
幼児と親との生活
状態が
違えば、食うべき
餌も
防ぐべき
敵も、それぞれ
違うであろうから、
幼虫にはこれに対する
特殊の
装置がなければならぬ。
海産の「びいどろうお」には
親鰻の知らぬ
敵があって、その
攻撃をまぬがれるために
特に体の
透明なるべき
必要があり、
不思議蛙の「おたまじゃくし」には、
陸上の親とは
違うた
餌を食うためか
敵を
防ぐためかに、
特に体の大なる
必要があるのであろう。小学校の一年生の身体が大人の二倍もあり、五年生のころになって
普通の
子供の大きさに
戻ると
想像すると、実に
奇妙に考えられるが、これまた食うため
産むための
便法として、その動物に取っては
都合のよろしいことに
違いない。
通常動物の
長幼を
区別するには
生殖作用の始まる時期を
境とし、これに
達すれば、すでに
完全に
成長を
遂げたものと見なし、いまだこれに
達せぬものは、なお
成長の
途中にあると見なしている。この
標準は大体においてはまず
間違いはないが、
詳しく調べるとずいぶん多くの
例外を見出し、しかもその
例外の中には、またさまざまに
相異なったものがある。たとえば
普通の
魚類、
蛇類、
亀類などは、子を
産み始めてから後もなお引きつづいて大きくなるが、これはすでに身体の
構造が一とおり
完成した後のことであるゆえ、子を
産み始めるころを
幼時とは名づけられぬ。これに反して、身体の
構造がいまだ親とは
異なって、
確かに
幼時と名づくべきころに子を
産めば、これを
特に
幼時生殖と名づける。次にその
例を二つ三つあげて見よう。
 アホロートル(上)子
アホロートル(上)子
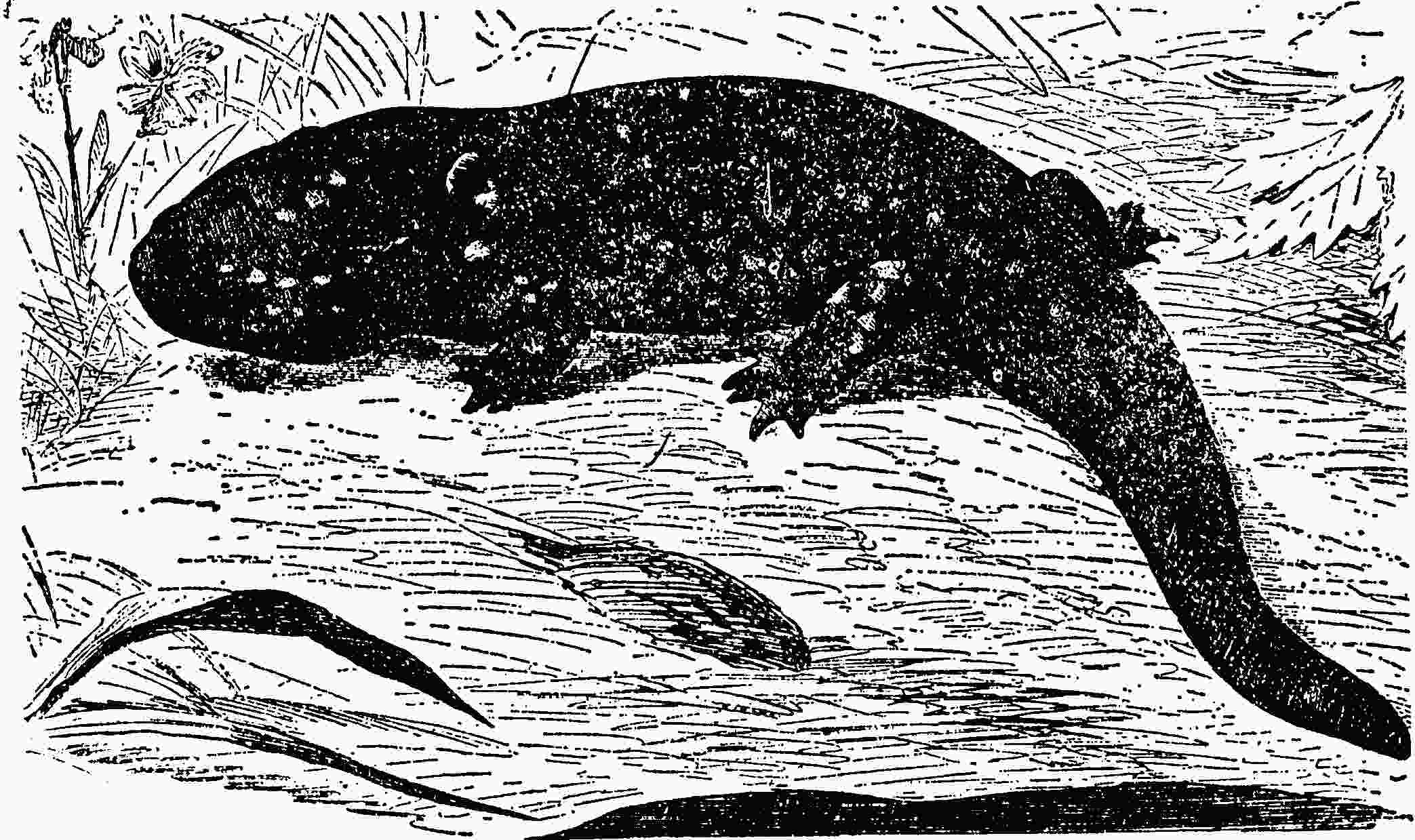 アホロートル(下)親
アホロートル(下)親
メキシコに
産する
山椒魚の
類で、そこの土人が「アホロートル」と
呼ぶものがある。これは形は「いもり」のごとくで、大きさは「いもり」の二倍
以上もあるが、つねに水中に
棲み、
頸の
両側には
鰓が
総状をなして、あたかもハイカラの
襟巻のごとくに見えている。また
尾の
幅の広いのは水を
漕いで
游泳するに
便利なためである。かように水中の生活に
適した
姿のままで、この動物は代々
卵を
産み、
卵からはまたこのとおりの子が
孵って、一度も水より外へ出ずにいるゆえ、昔はこれを
成長し終わった
一種の動物と見なして、
特別の学名がつけてあった。ところが今より五十年ばかりも前に、パリの動物園に
飼うてあったものが、
突然池の中央の島にはい上がり体形が
一変して、
陸上生活に
適するものとなった。すなわち体の表面に
現われていた
総状の
鰓はしなびてなくなり、
幅の広かった
尾は
狭くなって
鼠の
尾のごとくき形を
呈し、
従来別の
種類と思われていた
一種の
陸棲山椒魚となり終わった。いったい
山椒魚には
陸上に出るものと、水中にのみ生活するものとの二組があって、
生涯水より出ぬ
類では、
生涯総状の
鰓が外面に
現われ、
陸上へ出る
類では、ただ
幼時だけかような
鰓があり、
成長し終わると
鰓はなくなる。されば「アホロートル」は、
当然水より出ぬ組の
一種であると考えられていたのが、右の
経験によって実は
陸上へ出る
種類の
幼時であることが知れた。
陸上へ出て体形が
変わってからの
姿がすなわち
成長の終わったもので、かようになればまた
卵を
産むが、水中にいる
幼虫の時代にもつねに
卵を
産み、
幼虫の
姿で何代でも
生殖しっづけることができる。これを
蛙にくらべればちょうど「おたまじゃくし」のままで、代々
卵を
産み
繁殖することにあたるが、
成長して後も
生殖し、
幼時にも
生殖し
得る
性質を
備えていれば、なにかの
事情で
陸上へ出られぬところに
棲む場合にも自由に
繁殖ができて、
種族維持の上にはもっとも
好都合である。
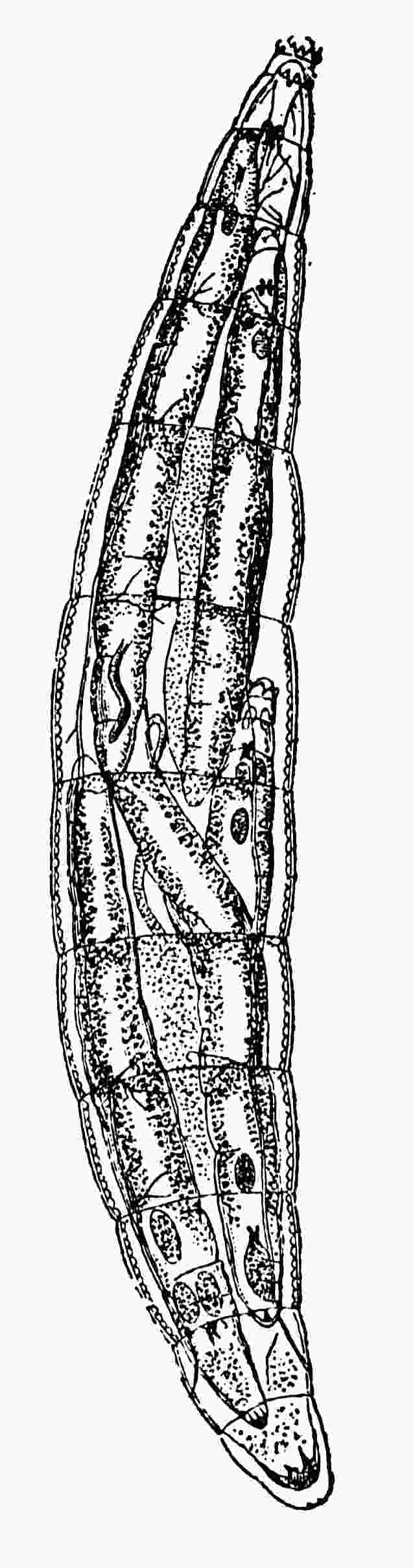 寄生蜂の幼虫
昆虫
寄生蜂の幼虫
昆虫が植物の
若芽などに
卵を
産みつけると、そこに「
虫'エイ」と名づける
団子のようなかたまりができることがある。
五倍子と
称して
染料やインキ
製造の
材料となるものは、その有名な
例であるが、かように植物にたまりを
造らせる
昆虫は、それぞれ
種類が定まっており、植物が
違えば
卵を
産みつける
昆虫の
種類も、それからできるかたまりの
形状性質もおのおの
違う。その中に
一種極めて小さな
蠅の
類があるが、これがまた
幼時生殖を行なう。しかも前の「アホロートル」とは
違うて、
生殖とともに
幼児は死んでしまう。この
蠅は「ありまき」などと同じく、一年中に何度も代を重ねるものであるが、夏の間は
卵から
孵った
蛆が少しく
成長すると、その体内に数多くの
蛆が生じ、親なる
蛆の体を食い
破ってはい出して、少しく
成長するとまたその体内に
蛆が生ずる。かくて
幾代かを
過ぎると、次に
蛆が
蛹となり
蛹が
脱皮して
蠅の形をした
成虫が
飛び出すのである。
昆虫類では
成虫と
幼虫との形の
相違が、
蛙や「いもり」と「おたまじゃくし」との
相違よりもなおいちじるしいゆえ、
幼時生殖を行なう場合には、
初めから一点の
疑いも起こらぬ。
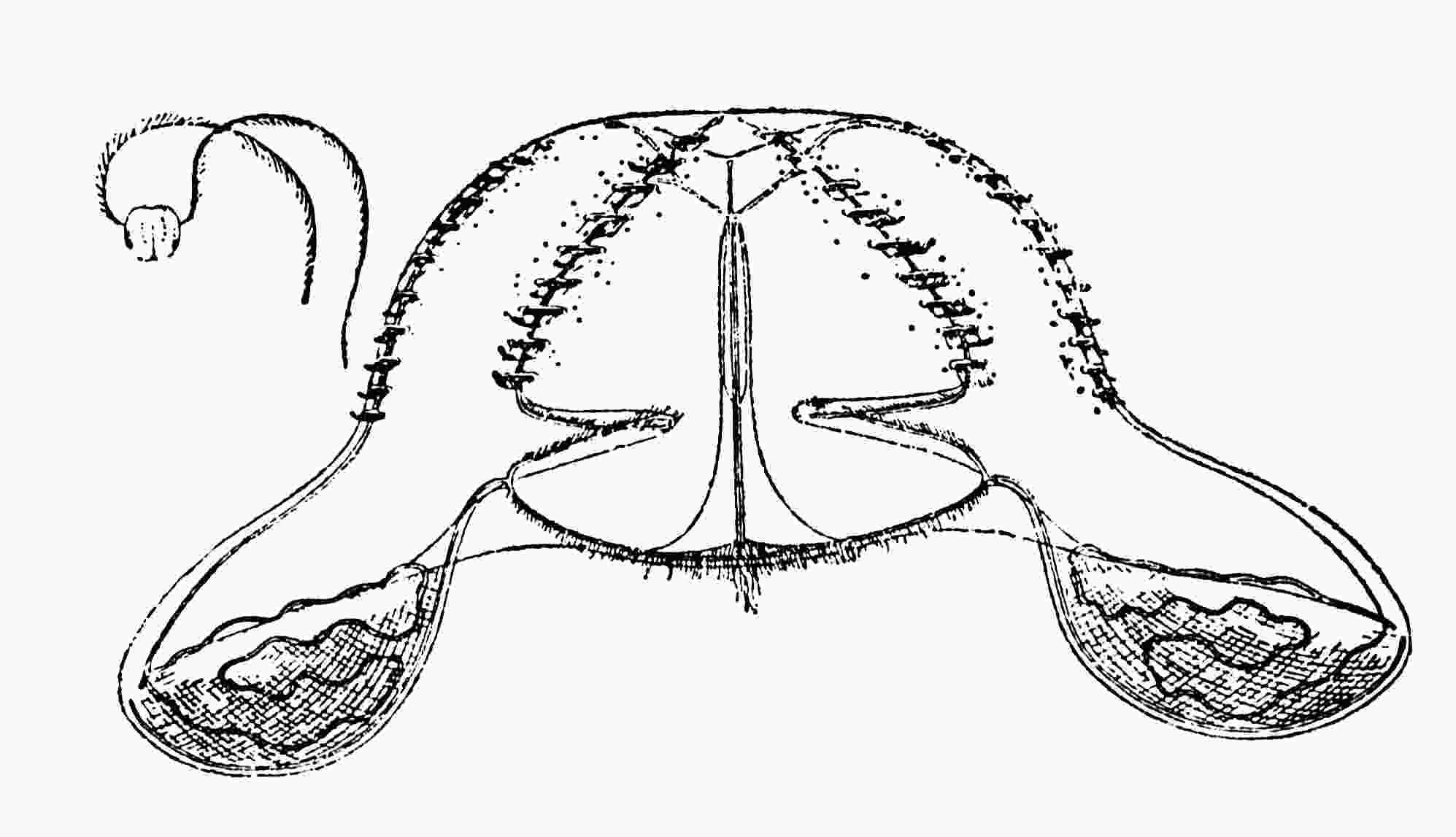
櫛くらげ
左の上に示したるはその幼児
なお一つ
幼時生殖の
例をあげて見るに、海の表面に
浮かんでいる
透明な「くらげ」の中に「
櫛くらげ」と名づけるものがある。
普通の「くらげ」が
椀や
傘のごとき形をしているのと
違い、この
類は多くは「なす」のごとき形でその
柄にあたるところに口があり、体の表面には多数の小さな
櫛状の板が
子午線に相当する方向に八本の
縦列をなしてならんでいる。しこうしてこの
櫛状の板が
絶えずそろうて動き水を
漕ぐので、かしこここへと
目的もなく転がって行く。「
櫛くらげ」
類の中には「
帯くらげ」というて、長さ
一二尺(注:30~60cm)にも
達する
幅の広い
帯状のものがあるが、これは「なす
状」の体を左右に引き
延ばしたようなもので、外形は大いに
違うが、内部の
構造は全く同一である。いったい「
櫛くらげ」はみなガラスのように
無色透明である上に、
櫛の列のところは
虹のごときさまざまの色を
反射してすこぶる美しいものであるが、
特に「
帯くらげ」が長い体を
徐々と
蜿らせながら、海面に
浮かび赤、青、緑、
紫などの
薄い光を放つごとく見えるありさまは、実になんとも言われぬほど
美麗である。西洋でこの「くらげ」を「
愛の女神ヴィーナスの
帯」と名づけるのもけっしてほめすぎではない。
残念なことには、
標本として
保存することがほとんど
不可能であるゆえ、自身で海へ出かけなければその美しい
姿を見ることができぬ。さてこの「
帯くらげ」でもこれに
類する他の「
櫛くらげ」でも
卵から
孵ったばかりの
極めて小さい時に、一度
成熟した
卵細胞と
精虫とを生じて
生殖作用を行ない、後直ちに
生殖力を
失うてただ大きくなり、
成長が終わると
再び
生殖を始める。人間にたとえて言えば、生まれたばかりの赤子が直ちに結婚して子を
産み、それより
普通の
子供に返って
成長し、
成年に
達してさらに
改めて
結婚し子を
産むことにあたる。かようなことのない人間から見ると、
如何にも
不思議な何となく
不条理なことのごとくに考えられるが、「
櫛くらげ」にとっては、これがやはり
種族維持のために
必ず
有利なことであろう。
生殖の
目的は
種族を
継続させるにあたるゆえ、
如何なる形の
生殖法でもこの
目的にかないさえすればよろしいわけで、
実際自然界には、さまざまな
生殖法の行なわれていることは、この
一例によっても
確かに知れる。
生殖法の中にはずいぶん
複雑なものがあって、
幼虫が
成長して
成虫になり終わるまでに、
幾度か代を重ね、
個体の数が
殖えながら進むものがある。
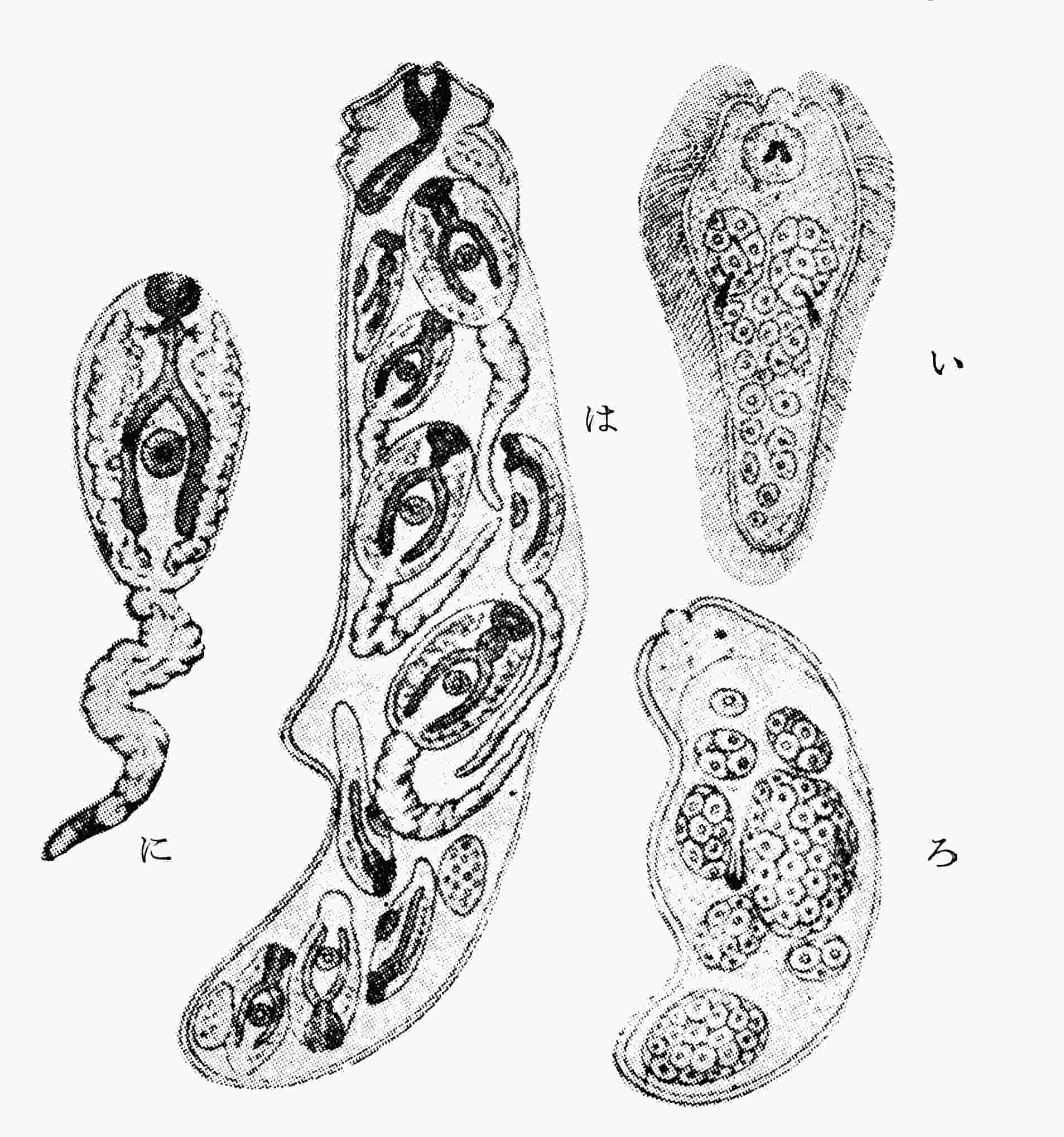
ジストマの発生
(い)幼虫 (ろ)幼虫より成長したる嚢状体 (は)(ろ)の体内に生じ次代の幼虫 (に)(は)の体内に生じた三代目の幼虫
たとえば人間の
肺臓や
肝臓に
寄生する「ジストマ」のごときものでは、
一匹の
幼虫がそのまま
成長して、
一匹の「ジストマ」となるのではなく、
途中に何回も
生殖して、
成虫となるころにはすでに
無数に
殖えている。
蚕の
幼虫は
成長して
一個の
蛹となり、
蛹が皮を
脱げば
一匹の
蛾がでるゆえ、
幼虫も
蛹も
蛾も、一
個体の
生涯の中の
異なった時期にすぎぬが、「ジストマ」では、
幼虫と
成虫とは
別の
個体で、
幼虫からいうと、
成虫は
曾孫か、
玄孫かにあたる。かく世代を重ねながら
変化するものでは、子は親に
似ず
孫は子に
似ず、それぞれ形を
異にし、同一の
形状を有する
個体は代をへだててのみ
現われることになるが、この
顕象を世代の
交番と名づける。
一例として「
肝臓ジストマ」の
生殖法を
簡単に
記述して見るに、
微細な
卵から
孵化した小さな
幼虫はしばらく
繊毛をもって水中を泳いでいるが、そのうちに
一種の
淡水産の
貝類に泳ぎついて、その
柔らかい体内にもぐり
込み皮を
脱ぎ
捨て、形を
変じて
長楕円形の
嚢のごときものとなる。ここまでが発生の第一代である。次にこの
嚢のごとき体の内に、前のとは形の
異なった
幼虫が多数にできる。この
幼虫は体は円柱形で、
一端に口があり、口よりは短い行き止まりの
腸がつづいている。また体の
後端に近いところには、太く短い足のごとき
突起が二つある。これはすなわち発生の第二代にあたるもので、少しく
成長すると親なる
嚢状の体からは出るが、いまだ貝の肉の内にとどまっている。次にこのものの体内に、さらに第三代のものがたくさんに生ずる。このものは体は円形で、その
後端から細長い
尾が生えて、多少
蛙の「おたまじゃくし」の形に
似ているが、発生がこの
程度まで進むと、「ジストマ」の子は貝の身体から水の中へ泳ぎでて、
淡水産の
魚類の体内にはいり、
筋肉の間にはさまって人に食われるのをまっている。かような魚をよく
煮たり
焼いたりせずに食うと、その人の体内で「ジストマ」が
成長し、たちまちの間に
生殖器が
成熟して日々
無数の
卵を
産むようになる。しこうして
卵は
大便とともに体外に出て、水に流されなどして
溝や
小河に
達すれば、
卵から
孵った
幼虫はまた
貝類の体内にもぐりこみ
得るわけであるゆえ、これより
再び同じ発生の
歴史を
繰り返すことになる。
実際にはなお少しく
込み入ったところもあるが、大体においてはまずここに
述べたとおりであろう。
条虫類にも世代
交番の行なわれるものがある。犬の
腸に
寄生する、長さわずかに一分
五厘(注:4.5mm)ばかりの
極めて小さな
条虫があるが、人がもし
誤ってその
卵をのみ下すと、
卵からは
微細な
幼虫が出て
肝臓、
肺臓などにはいりこみ、そこで
非常に大きな
嚢になる。これは医者のほうでは「
胞虫嚢腫」と名づけるもので、中に水のごとき
液を
含み、
直径が
数寸(注:十数cm)にも
達するゆえ、そのあるところの
器官の
働きに大きな
故障を生じ、ずいぶん
危険な
病いを起こす。
普通の
条虫はいくら大きくても
腸の内にいることゆえ、
下剤をかけ
絶食して
腸を
掃除し、
駆虫薬を用いればこれを
駆除することができるが、この
幼虫の
嚢は
駆虫薬の
直接届かぬところにあるゆえ、とうてい薬で
駆除するわけにゆかぬ。
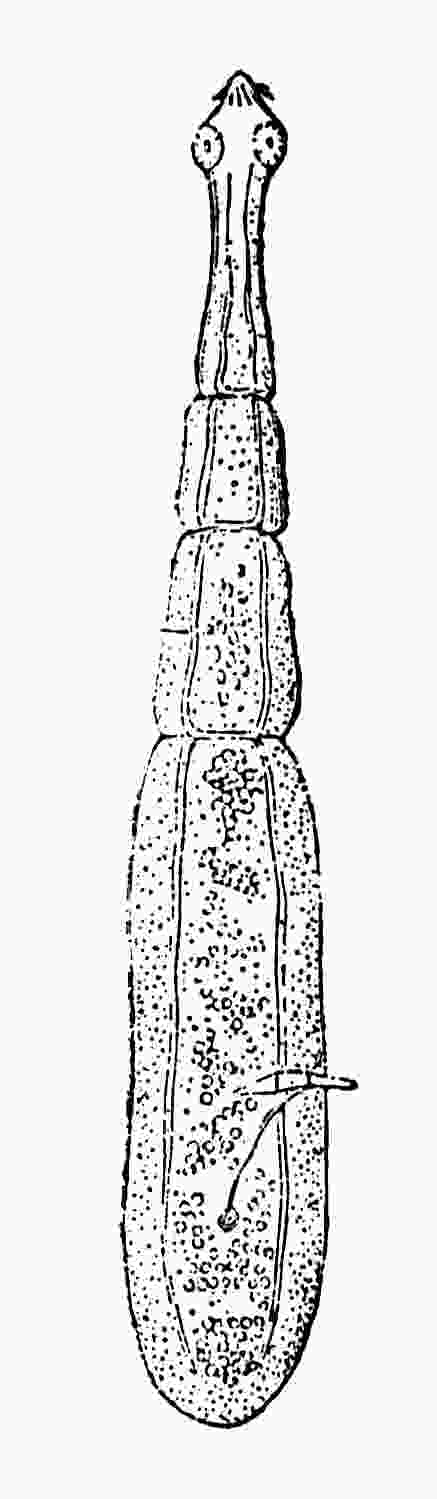 犬の条虫
犬の条虫
すなわち
条虫の中で一番
恐ろしい
種類であるゆえ、つねづね犬に
接近する人々はよく注意しなければならぬ。さて右の
幼虫の
嚢を切り開いて見ると、その
裏面には
無数の
条虫の頭がついているが、これがみな
嚢から
芽生によって生じたもので、もしその一部が犬の
腸にはいると、そこで
一匹ずつ
成熟した
条虫となるのである。

水くらげの発生
1は卵より孵った幼虫。それより数字の順序のとおりに発生し,7,8にいたって分裂し,各節が離れてついに目に見るごとき小さなくらげとなる。
以上はいずれも
寄生虫であるが、
独立生活を
営むものにも世代
交番の
例はいくらもある。近海の水面に
無数に
浮かんでいる「水くらげ」、一名「四つ目くらげ」というものもその一で、
卵から生じた
幼児はけっしてそのまま
成長して
一匹のくらげとはならず、
途中に
繁殖して
非常に数が
殖える。「水くらげ」の
卵から
孵った
幼虫は
卵形の小さなもので、全表面に
繊毛をそなえ、しばらくは水中を
游ぎまわるが、そのうちに
適当なところを
選んで
固着し、
縦にのびて
筍を
倒立させたような形のものとなり、
成長するに
従い
節々の切目が深く入りこんで、ついにはあたかも重ねた皿を
一枚ずつ取り出すごとくに、
一節ずつが、小さな「くらげ」となって水中で
浮き出すのである。これも前の
条虫の場合と同じく、
卵から生じた
幼虫が
成長し終わるまでの間に、一回
芽生または
分裂によって
生殖し、次の代にいたって
初めて
成熟した動物となるが、このような
種類では一方を「
幼虫の世代」、一方を「
成虫の世代」として、明らかに
長幼を
区別することができる。
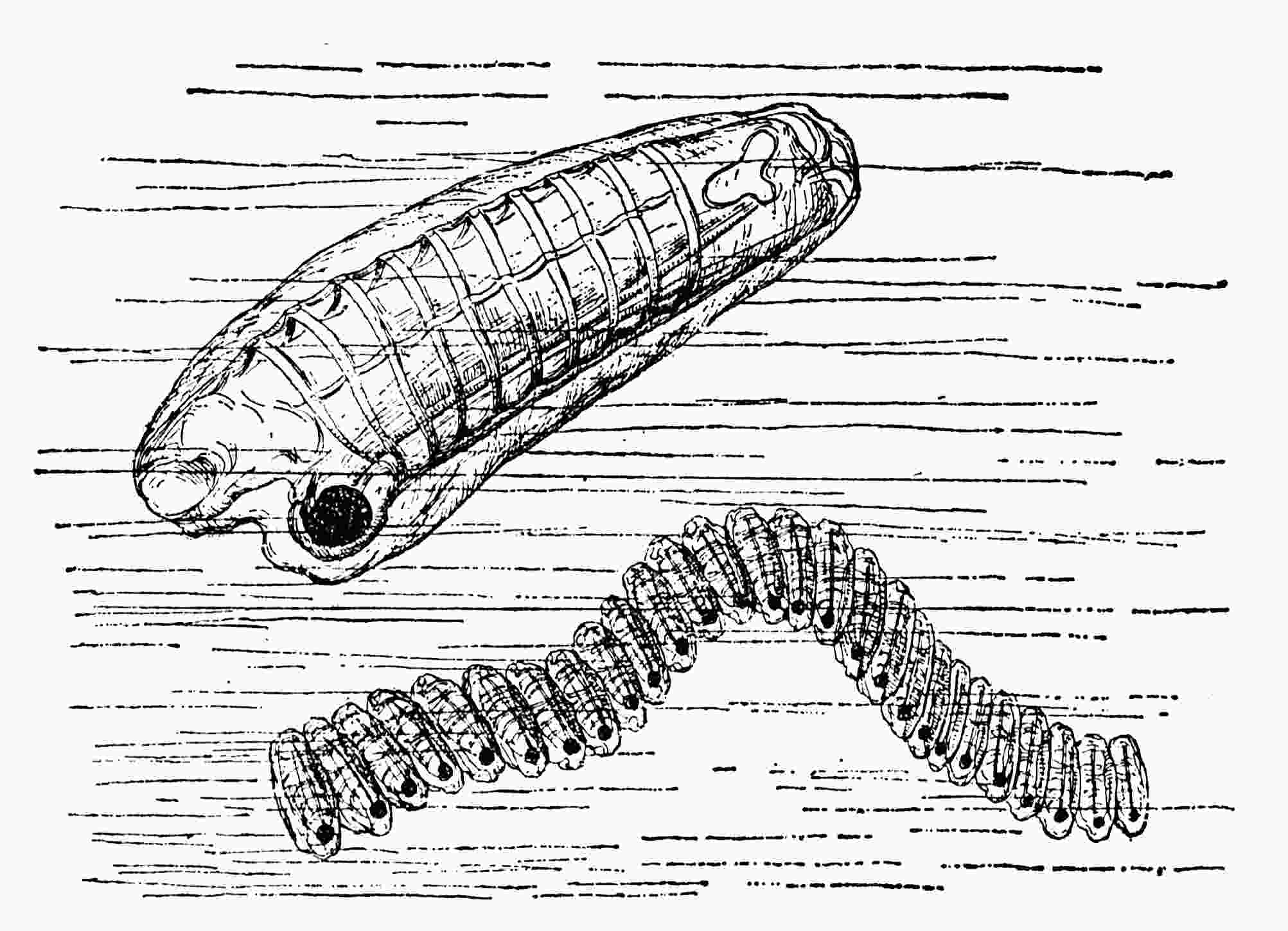 サルパ
サルパ
前になにかのついでに「サルパ」という動物の名をあげたが、この
類では世代の
交番が
特にいちじるしい。「くらげ」ならば人の知っているのは
水面に
浮かんでいる
有性時代のみであって、
海底に
固着している
無性時代はあまり人が知らぬゆえ、くらげの世代
交番はよく調べて見ないとわからぬが、「サルパ」ではかわるがわる
現われる二世代の
個体が、大きさもほぼ同じく数もほぼ同じく
相雑りて、海の表面に
浮かんでいるゆえ、両方ともに同じ
程度に知られている。一方は子を
産み一方は
芽を生じて、
生殖の
方法は
異なるが、生活の
状態が全く同じであるゆえ、いずれを
幼いずれを長と定めがたい。一体ならば
有性生殖をするほうを、
成長し終わった形と見るのが
当然であるが、「サルパ」では
芽生するものも、
卵を生ずるものにくらべて外形が少しく
違うだけで、
構造は同じ
程度にあるゆえ、これを
幼児の形と見なすことはできぬ。世代
交番のあることの知られなかった時代には、「サルパ」の
相交互する二世代の
個体をそれぞれ
別種の動物と考えて、
各種に
別々の学名をつけた。今日は、これが両方とも
一種の動物の
交互する二世代であることがわかったが、いずれか一方の名だけを用い、他の
名称を全く
廃しては
非常に
不便であるゆえ、他の動物には
例のないことであるが、「サルパ」だけは
特別として
各種の学名には
種名が二つずつならべてある。
以上種々の方面から
論じたとおり、動物の
長幼はただ身体の大小、
生殖力の
有無によってのみ
区別せられるものではなく、
種類が
違い生活
状態が
違えば、それにしたごうて
長幼の
区別の
程度にも
種々の
相違があり、
長幼のすこぶる
相似たものもあれば、また全く
相似たところのないようなものもある。
特に世代
交番の行なわれる
種類では、
成長の
途中に
生殖が行なわれ、
幼より長に
達する間に代が重なるから、
普通の場合とは
長幼の
関係がはなはだしく
違う。人間では
子供と大人とは身体の形にもいちじるしい
相違がなく、生活の
状態もほぼ同様であり、一人の
子供が
成長していつとはなくそのまま一人の大人となり終わるゆえ、他の動物もみなそのとおりであろうと思うている人が多いようであるが、
普通に人の知らぬ下等動物になると、生まれて直ちに
生殖するものもあれば、
成長の
途中に
分裂するものもあって、なかなか
複雑な
経過を
示すものも少なくない。されば親族
法を
専門とする
法学者が、
避暑のおりなどに人間にも世代
交番が行なわれ、
子供が大人になる間に
分裂によって数が
殖えるものと
想像して、なぐさみに
現今の
法理をあてはめて見たならば、あるはさらに深い
理屈を見いだすにいたるやも知れぬ。
種々の
異なった動物について、親と子との
関係をくらべて見ると、これにもずいぶんいちじるしい
相違がある。しかもいずれの場合にも
目的とするところはつねに一つで、ただそれを
達するための
手段が
相異なるというにすぎぬ。一つの
目的とはいうまでもなく
種族の
維持であって、
如何なる場合でもこの
目的に
撞著するようなことはない。子を
産み放すだけで、さらにかまいつけぬものと、子を助けるためには自分の命をも
捨てるものをならべて見ると、その行ないは
互いに
相反するごとくに思われるが、よく調べて見ると
結局同じことで、子を
産み放して少しも世話をせぬ動物は、それでも
種族の
維持がたしかにできるだけの
事情が
必ず
存する。また子のためには命を
捨てる動物は、もし親にかかる
性質が
備わっていなかったならば、
必ず
種族が
断絶すべきおそれのあるものに
限ってある。人間を
標準として考えると、子が
敵に
殺されるのを見ながら知らぬ顔をしている親は
如何にも
無慈悲に見え、自ら進んで命を
捨て子の
危難を
救うものは
如何にも
熱情が
溢れるように見えるが、
自然を
標準として考えると、いずれにもかくあるべき理由があってかくするのであるから、一方を
優れりとか一方を
劣れりとかいうことはできぬ。この事は
習性の
違うた動物をなるべく多く集めて、
互いに
比較して見るとすこぶる
明僚に知れる。
子を
産み放したままで、少しも世話をせぬ動物の
種類は
極めて多い。いわゆる下等動物はたいがい子を
産み放しにするものばかりで、いくぶんかでも子の世話をする
種類はただ
例外として、わずかにその中に
含まれているにすぎぬ。しかし
産んでから全く
捨てて
顧みぬものでも、
産むときに
適当な場所を
選むということだけは
必ずする。
何故というに、もしも
不適当なところに
産んで
卵が直ちに死んでしまえば、その
種族の
維持継続はむろんできぬからである。
「うに」、「なまこ」の
類では、
卵細胞と
精虫とが親の体を出てから勝手に
出遇うのであるゆえ、子は生まれぬ前から親との
縁が切れて、少しもその世話を受けぬ。体外
受精をする「ごかい」の
類や、
蛤、「あさり」のごとき
二枚貝類も全くこれと同様である。また
魚類もたいていは
卵を
産み放しにする。魚の
卵には
水面に
浮かぶものと、
水底に
付着するものとがあるが、
若干の
例外を
除けば、いずれも
独りで小さな
幼魚までに発育して、少しも親の世話になることはない。すべてこれらの動物は、
極めて小さく弱いときから、
独力で生活を
営まねばならず、したがって
餓えて死ぬことも、
敵に食われて死ぬこともすこぶる多かるべきはもちろんであるゆえ、これらの
損失を
最初から
見越して、実に
驚くべく多数の
卵がつねに生まれる。
「
海亀」はつねに海中に住んでいるが、
卵を
産むときだけは
陸へ上がってくる。東海道の
砂浜では、いくらも
亀の
卵を
鶏卵のごとくに売り歩いているのを見かけるが、
亀が
卵を
産むのは
必ず夜であって、人の見ぬ
静かな時をうかがい、後足をもって
砂のところに
壺形の深い
穴を
掘り、その中へたくさんの
卵を
産みこみ、ていねいに
砂をかぶせてもとのごとくにし、後足で自身の
足跡を
掃き消しながら海のほうへ帰ってゆく。それゆえ
亀の
卵のある場所を表面から知ることはなかなかできぬ。
海亀は
卵を
産むときにはかくのごとく実に用意
周到であるが、いったん
産み終わった後は他へ去って少しもかまわず、
卵はただ日光に温められて発育し、
再び
孵化するころになると、
幼児は夜明け前にことごとくそろうて
殻を
破り
砂上に出で、一直線に海のほうへはうてゆくが、数百千の
幼い
亀が急いで
砂のうえを
匍うゆえ、雨の
降っているような音が聞える。南洋
諸島に
棲む「マッカン
蟹」はちょうどこれと反対で、親はつねに
陸上のみに
棲み、
椰子の
樹に登り
椰子の実を食いなどしているが、
卵を
産むときだけは海へでかける。
蛙の
類は多くは水中へ
卵を
産んで、その後は少しもかまわずにおくが、
卵はそのまま水の中で「おたまじゃくし」になるからなんの
差支えもない。ただし「
青蛙」などは
例外で、水田の
傍の土に
孔を
穿ちその中で
産卵する。
卵は
粘液を
掻きまわした
泡に
包まれてかたまりとなっているが、おいおい発育が進んで「おたまじゃくし」の形になりかかるころには、
泡は
溶けて
卵とともに水中へ流れ落ちるから、その先の
成長は
差支えなくできる。これなども
産み放しではあるが
産む時にすでに子の
成長に
差支えが生ぜぬだけの注意が
払われている。
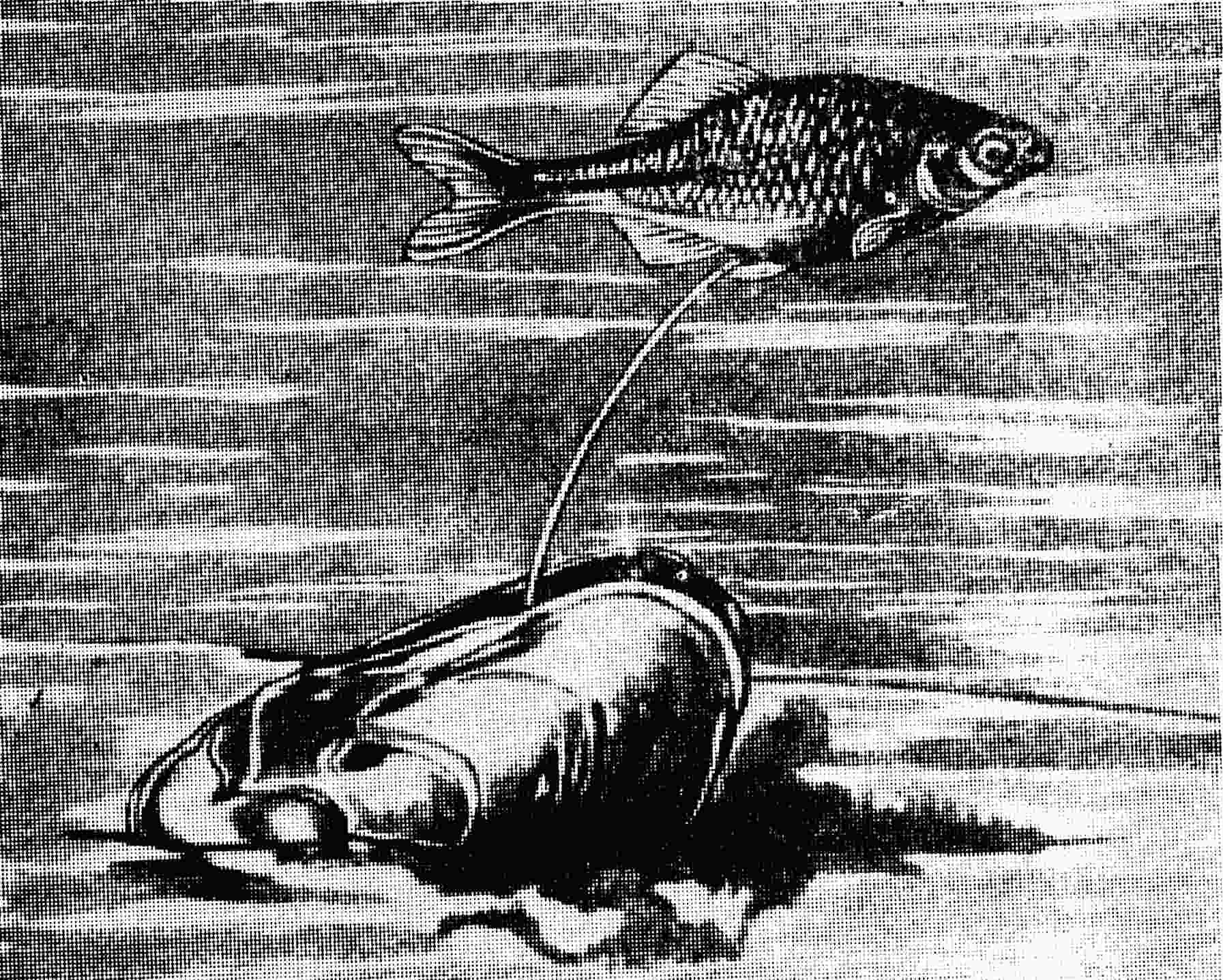 たなごの産卵
淡水
たなごの産卵
淡水に
産する「たなご」は、長い
産卵管を用いて生きた「からす貝」の
貝殻の中へ
卵を
産み
込むが、
産んだ後は少しもかまわぬ。
卵は貝の
鰓の間で発育し、小さな魚の形までに
成長してから水中へ
游ぎ出るのである。
昆虫類も多くは
卵を
産み放しにする。
変態の行なわれるために、
幼虫と
成虫とでは、住所も食物も
敵も
違うのがつねであるが、
成虫が
卵を
産むときには
成虫の
習性にはかまわず、
必ず
幼虫の発育に
都合のよい場所を
選ぶ。
例えば「とんぼ」の
成虫は空中を
飛んで、
昆虫を
捕え食うが、
卵は
必ず水の中へ
産む。これは「とんぼ」の
幼虫は水の中で発育するゆえである。また
蝶の
成虫は花の
蜜を
吸うだけであるが、
卵は
必ず草木の葉に
産みつける。これは
蝶の
幼虫は毛虫または
芋虫であって、草木の葉を食い
成長するからである。
蚊が
汚水に
卵を
産み落とし、
蠅が
腐肉に
卵を
産みつけるのも同じ
理屈で、
単に
産み放してさえおけば、
幼虫は食物の
欠乏なしに
必ずよく育つからである。
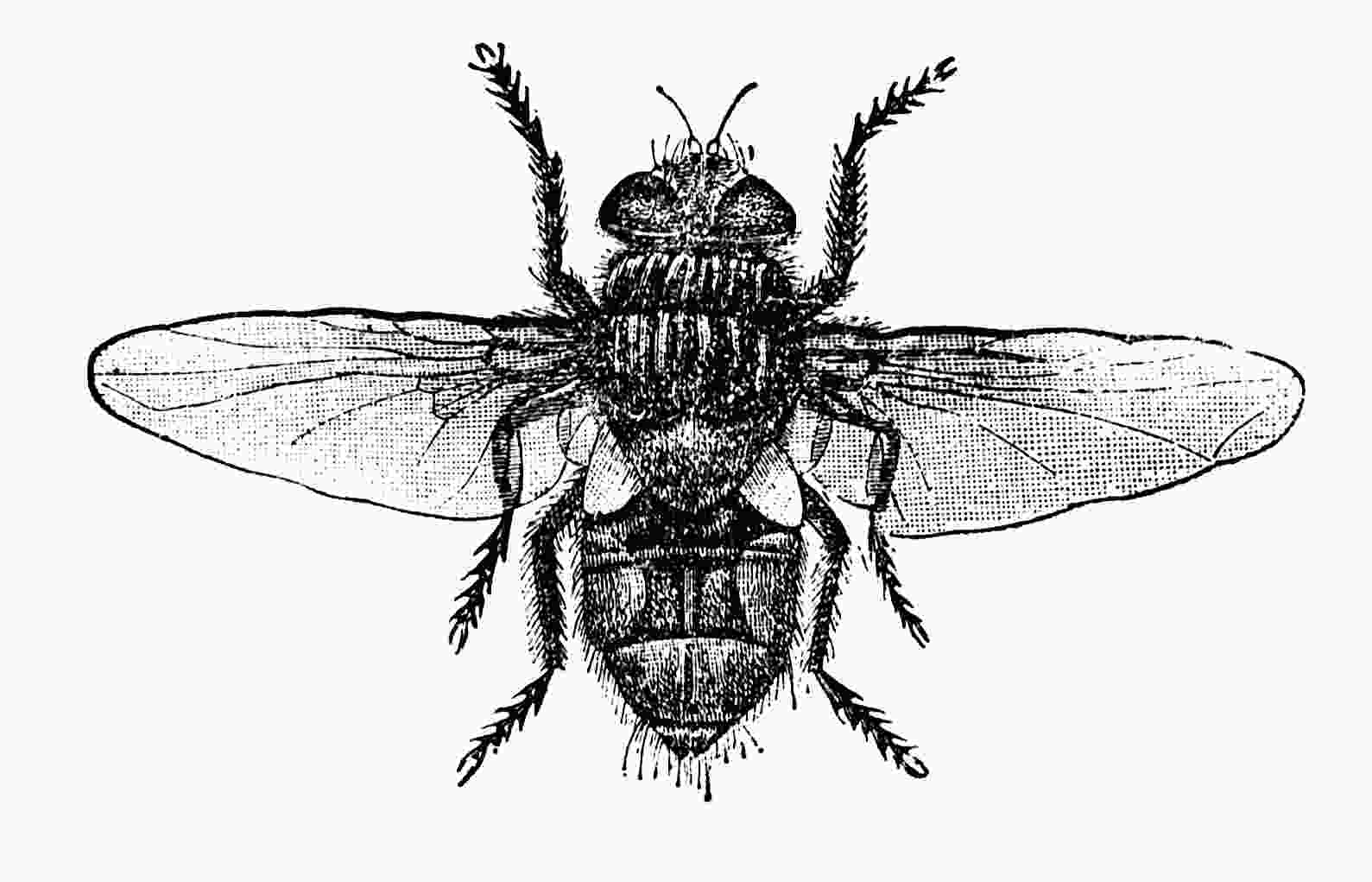 蚕の蛆蠅
寄生
蚕の蛆蠅
寄生生活をする
昆虫の
卵の
産みようはさらに面白い。
蚕に
寄生する
蛆の親は
一種の
蠅であるが、
卵を
必ず
桑の葉の
裏に
産みつける。かくしておけば、後は全く
捨ておいても、
自然に
蚕に食われ、その体内で発育して大きな
蛆となり、
蚕の体からはい出し、地中へもぐり
込んで
蛹となり、
翌年蠅となって
飛び出す。
蝶、
蛾の
幼虫に
寄生する小さな
蜂の
類はずいぶん数多くあり、そのため年々知らぬ間に農作物の
害虫がよほどまで
防がれているわけであるが、これらの
小蜂は
卵を
必ず
蝶、
蛾の
幼虫の体に
産みつける。また「
卵蜂」というて、
蝶、
蛾の
卵に自分の
微細な
卵を
産み
込んで歩く小さな
蜂もある。これらはいずれも
翅の生えた
成虫の生活
状態は
幼虫とは全く
違うて、
蝶、
蛾の
幼虫や
卵とは何の
関係もないにかかわらず、
産卵するには
必ずそれから出る
幼虫の育つような宿主動物を
選んで、これに
産みつける
本能を持っている。
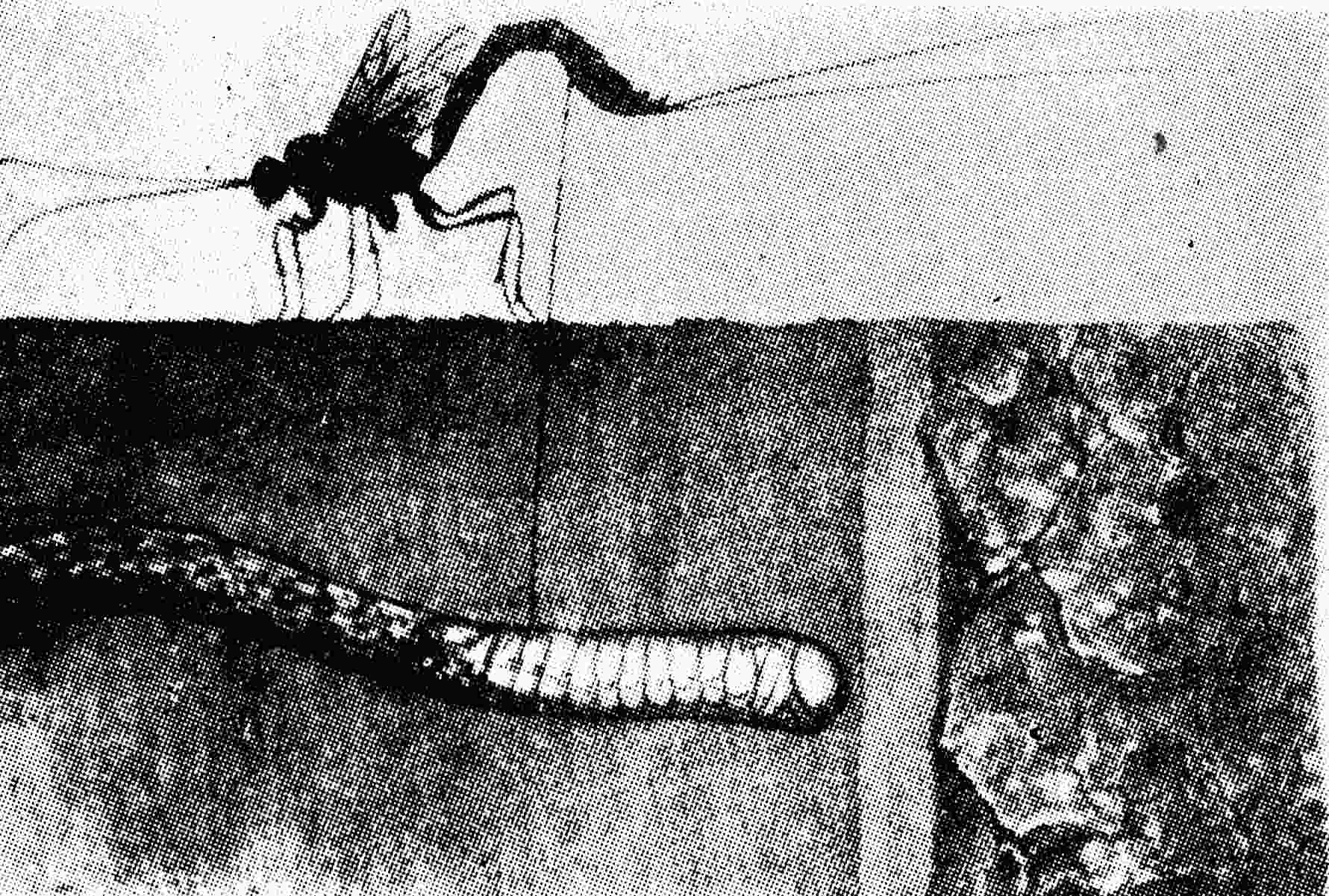 尾長蜂の産卵
尾長蜂の産卵
この点でなお
不思議に感ぜられるのは「
尾長蜂」
類の
産卵である。この
類の
幼虫は
樹木の
幹の内部に
棲む他の
昆虫の
幼虫に
寄生するが、
成虫が
卵を
産むにあたって何らかの
感覚によって、
幹の内の
幼虫のいる場所を知り、長い
産卵管で外から
幹に
孔を
穿ち、内にいる
幼虫の体、もしくはその
付近に
卵を
産み入れる。
尾長蜂の
産卵管が体に
比して数倍も長いのはそのためである。
卵から
孵って出た小さな
蛆は、宿主なる
幼虫の体内で
成長し、ついにこれを
斃し、のち
蛹の時代をへて皮を
脱ぎ、親と同じ
成虫となって
飛び出すのである。
以上いくつかの
例で
示したとおり、動物には
卵を
産み放したままで、その後少しも世話をせぬものが
非常に多いが、かかる場合には
必ず
非常に多くの
卵を
産むか、または子がよく育つべき場所を
選んで
産みつけるかして、
特に親がこれを
保護せずとも
種族の
維持継続が
確かにできるだけの道は
備わってある。
卵なり子なりを
産んでから後、しばらくの間親がこれを
保護する動物も
相応に多い。
獣類や
鳥類はことごとくこの
仲間に
属するが、それ
以外の動物にもたくさんの
例がある。
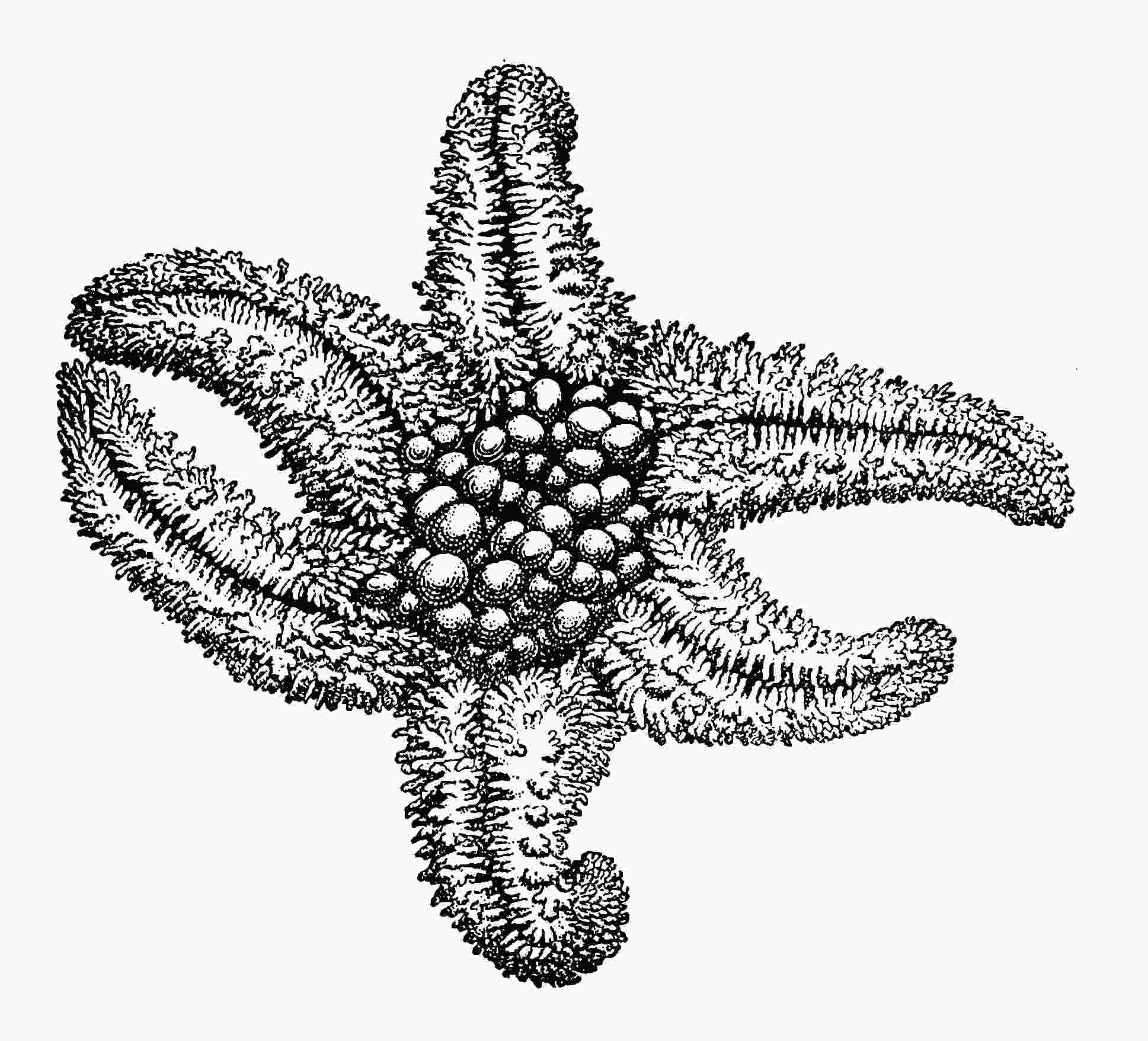 子を保護するひとで
概
子を保護するひとで
概していうと、子を
保護するものはやや高等の動物に多く、下等の動物はほとんどことごとく、
卵を
産み放すだけであるが、「うに」、「ひとで」のごとき
類でさえ、
例外として子を
保護するものがある。ここに図をかかげたのは
卵を体で
覆い
保護する「ひとで」の
一種であるが、かかる
種類では、
普通の「ひとで」に
比して、
卵が
直径十倍ないし二十倍も大きい。
直径が十倍ないし二十倍も大きければ、これを
体積としてかぞえると、一千倍ないし八千倍も大きいことにあたるゆえ、同じ大きさの
卵巣内に生じたとすれば、
卵の数は一千分の一ないし八千分の一よりできぬはずである。
如何なる動物でも
種族の
維持のためには、小さい子を
無数に
産んで、運を天にまかせるか、大きな子をわずか
産んで、これを大事に
保護するかの
二途のうち、いずれかを
選まねばならぬことが、この場合にも明らかに知れる。
昆虫類は多くは
卵を
産み放しにするが、中にはこれを
保護する
種類もある。
例えば池の中に
普通にいる「子負い虫」などは、
卵を
雄の
背の表面いっぱいに
並べ
付着せしめ、
雄はいつも子を負うたまま水中を泳いでいるが、
敵にあえば
逃げ去るゆえ、子は
無事に助かる。
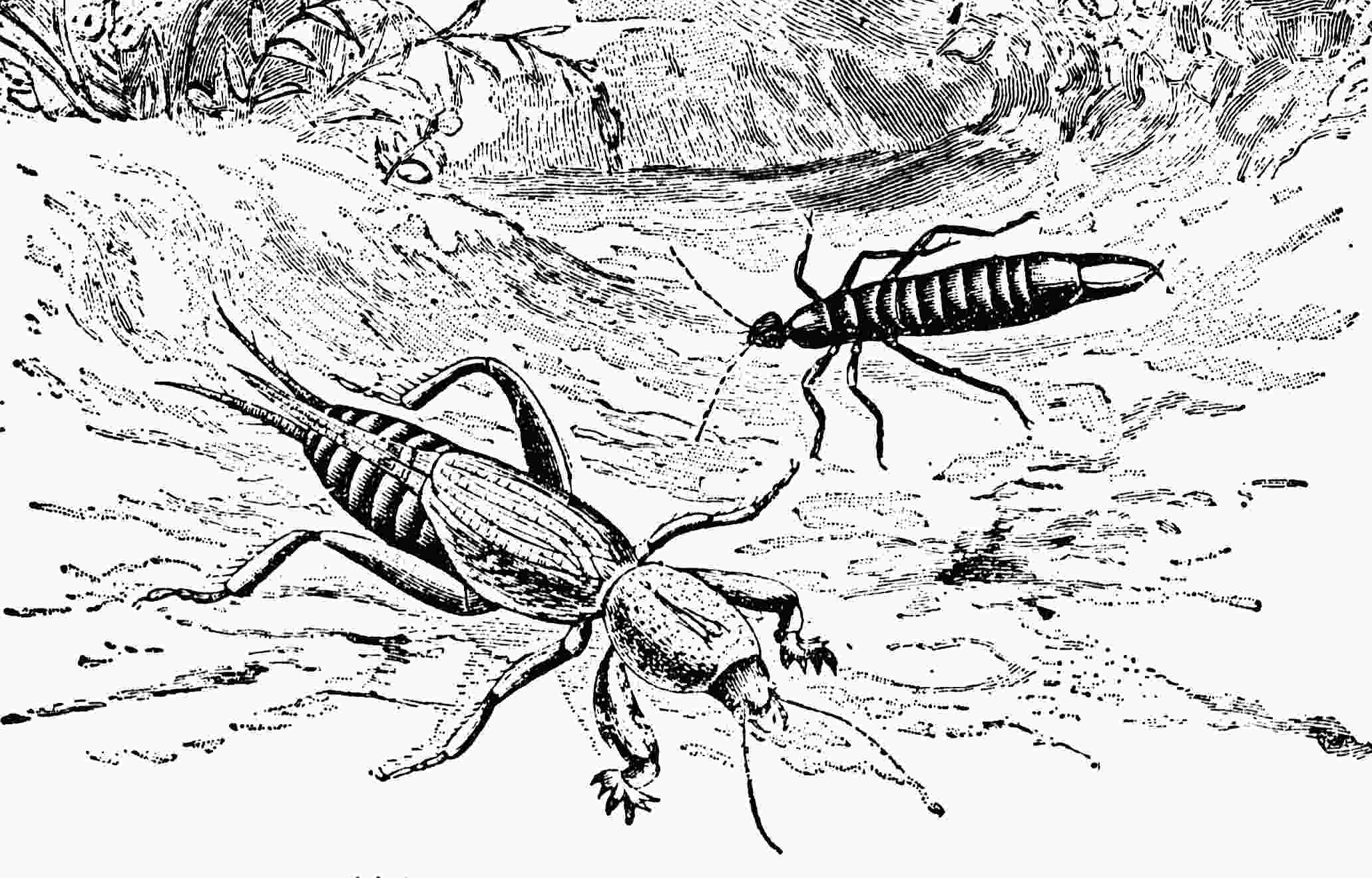 (左)けら (右)はさみ虫
(左)けら (右)はさみ虫
また「けら」のごときは、
卵を
産んでから
雌がその
側にいて
護っている。
蟻や
蜂の
類が
卵、
幼虫などをよく
保護し、
養育することはだれも知っているであろうから、ここには
述べぬ。その他「はさみむし」という
尻の先に
鋏のついた虫は、西洋
諸国では
眠っている人の耳にはいるという
伝説のためにおそれられているが、この虫は
卵を
保護するのみならず、それから
孵って出た
幼虫をも
愛して世話するということである。
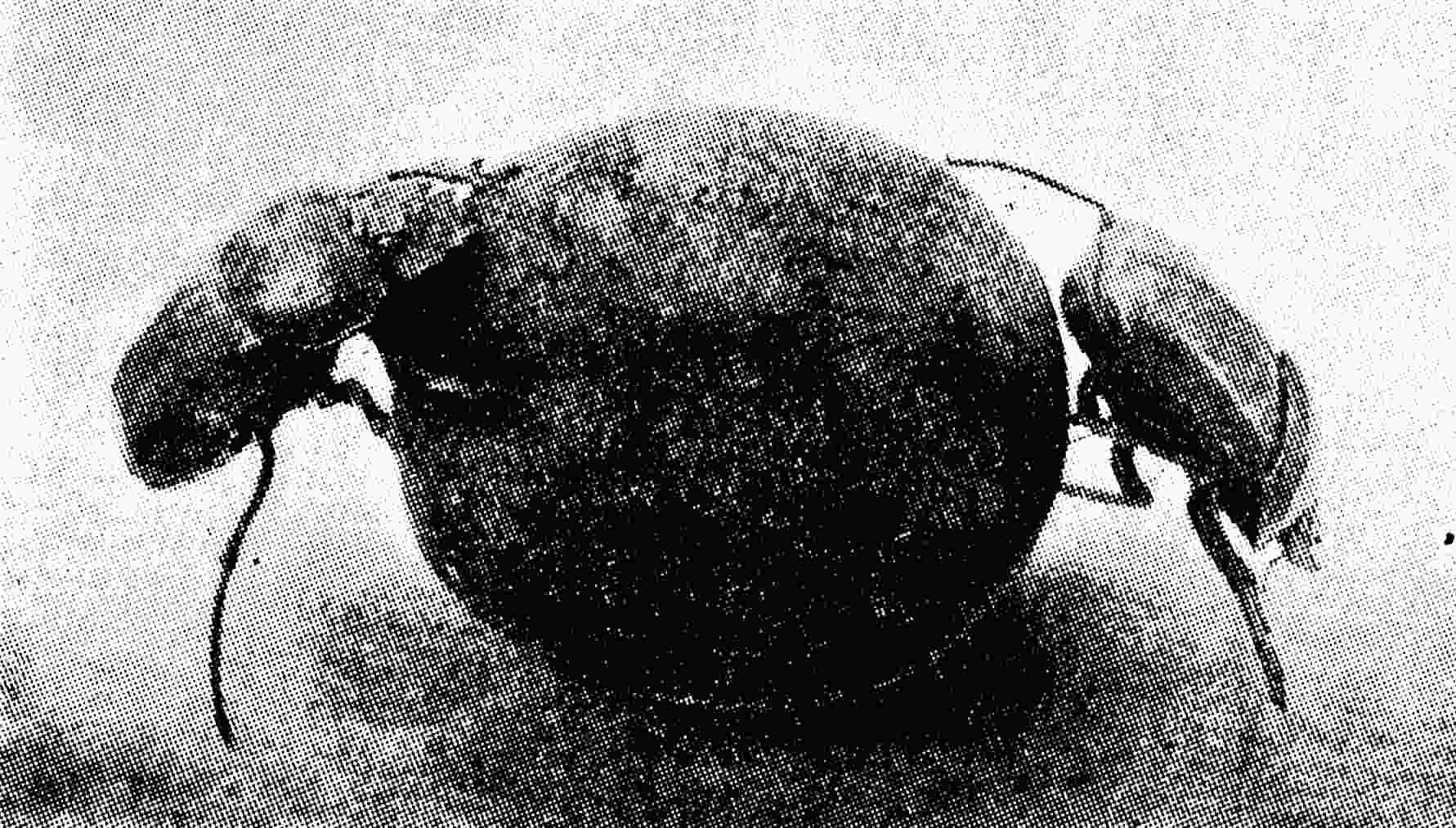 黄金虫
黄金虫
また「
黄金虫」の
類の中には
卵を
一粒産むごとに、馬や羊の
糞でこれを
包み、
次第々々に大きく丸めて、ついに親の身体よりははるかに大きな
堅い球とするものがある。丸めたものを
雌雄が力をあわせてころがして歩く。かくしていくつかの
卵を
産み、いくつかの大きな球をつくり終われば、親は力が
尽きて死んでしまうが、そのありさまはあたかも羊の
糞を丸めるために、世の中に生まれてきたように見える。
卵から
孵った
幼虫は、球の内部の
柔らかい羊の
糞を食うて
成長し、ついに球からはい出す。「くも」の
類は
昆虫類にくらべると
卵を
保護するものが
割合に多い。
特に「走りぐも」と
称して、
網を
張らずに草の間を走りまわっている
種類は、
卵を
産むとこれを
球状のかたまりとし、
一刻も
肌身を
離さずしじゅう足で
抱えている。
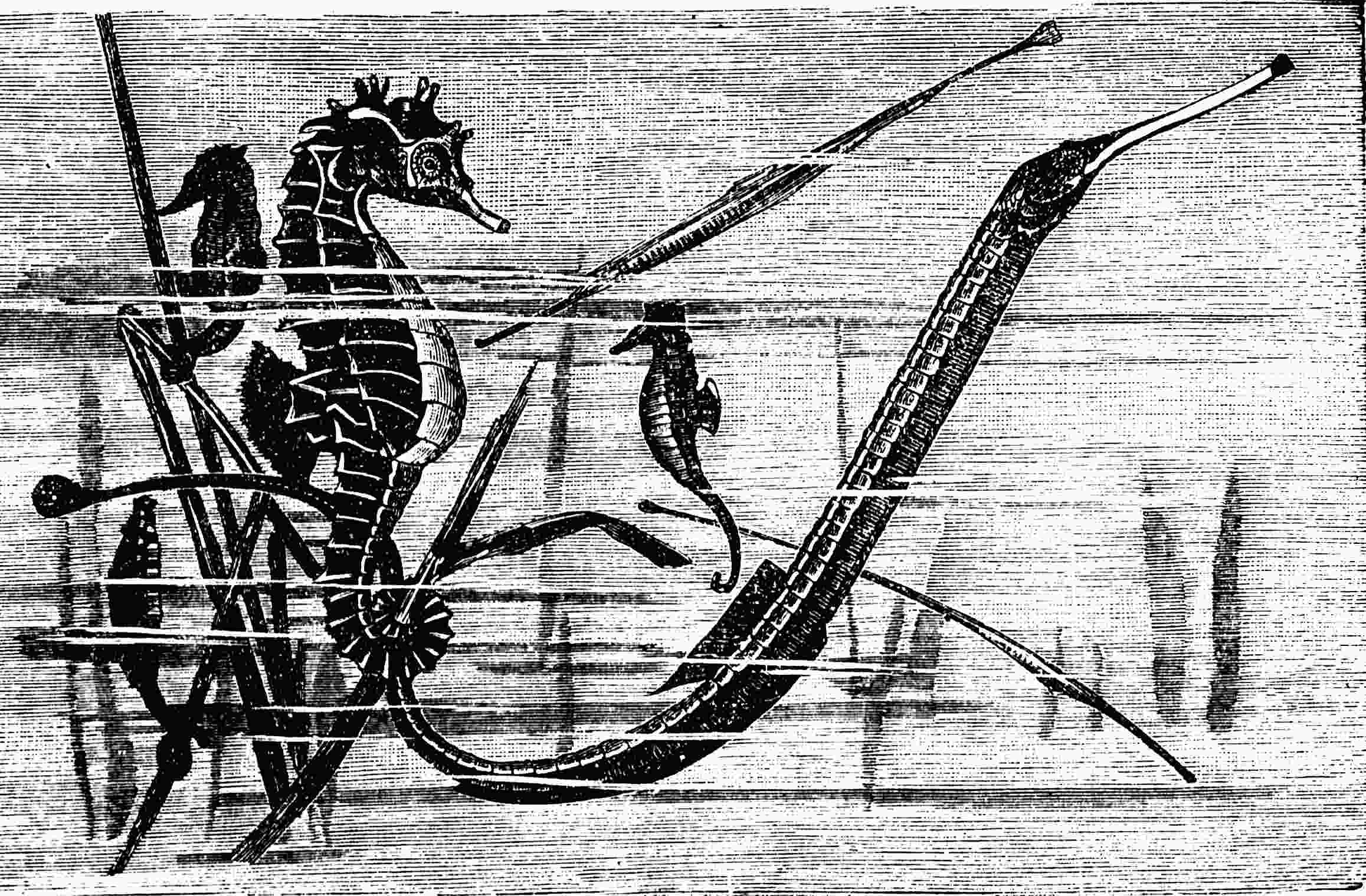 (左)たつのおとしご (右)ようじうお
魚類
(左)たつのおとしご (右)ようじうお
魚類もほとんどことごとく
卵を
産み放すだけで、親が子を
保護するような
種類は
滅多にない。しかしよく調べて見ると、全くないこともなく、しかも意外な
方法で子を
保護するものがある。
例えば「たつのおとしご」や「ようじうお」の
雄は、
雌の
産んだ
卵を自分の
腹の外面にある
薄い皮の
嚢に受け入れ、
幼魚が
孵化して出るまでこれを
保護する。両方ともに
浅い
海底の
藻の間に住む
魚類で、
別に
珍しいものでもないが、ちょっと
変わった形をしているゆえ、
見慣れぬ人には
珍しく見える。「たつのおとしご」の
雄の
腹の
嚢を開いて見ると、中に赤い
卵が四五十
粒もあるが、
普通の
魚類が一度に
幾十万の
卵を
産むのにくらべると、すこぶる少ないといわねばならぬ。「ようじうお」のはいくらか多いが、それでもなお少ない。
海藻の間にいる魚には
雌の
腹鰭が左右
寄って
嚢のごとき形となり、その中に
卵を入れて
保護する
種類もある。
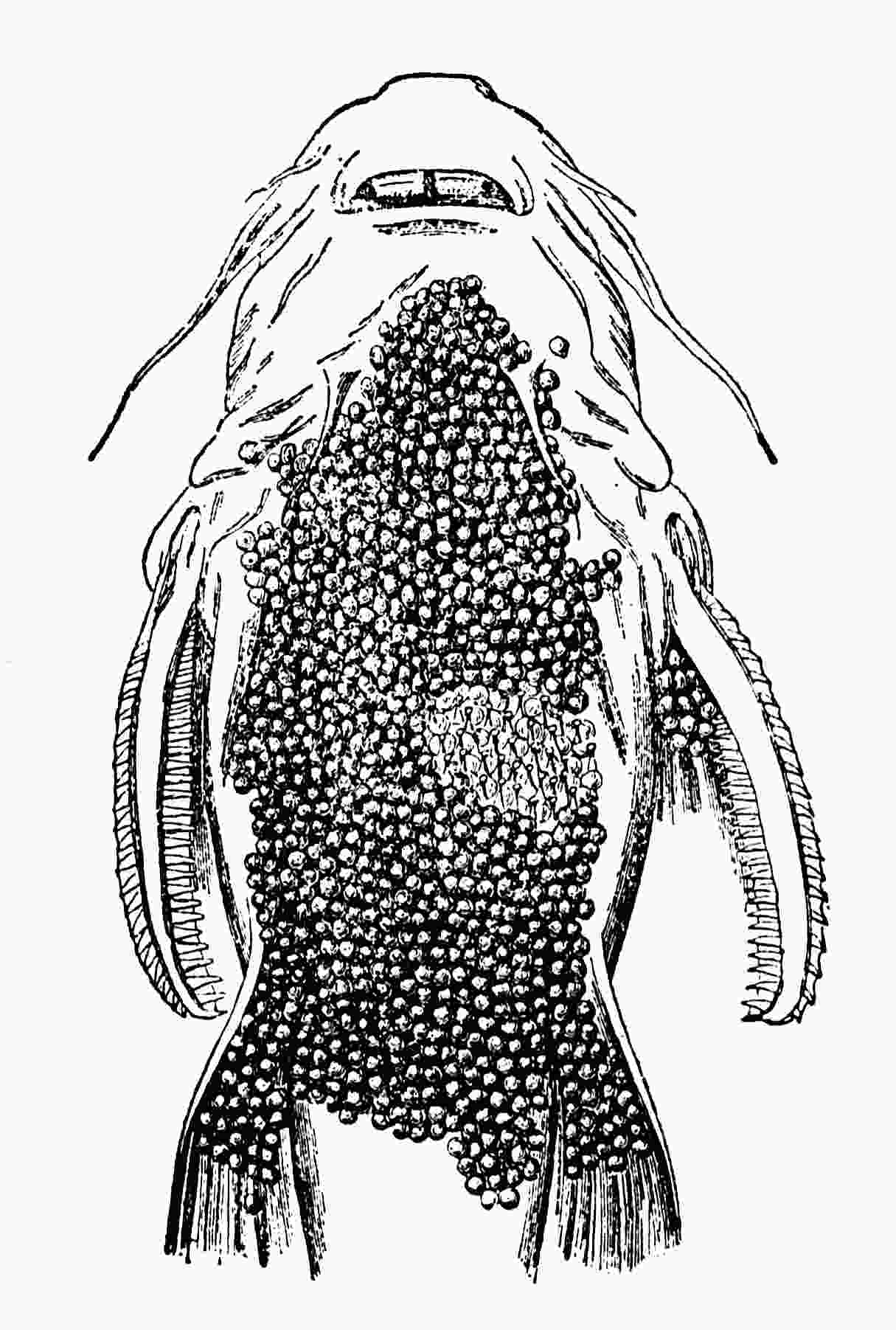 腹に卵をつけた魚
腹に卵をつけた魚
また「はぜ」に
似た魚で、
卵を体の
腹面に
付着せしめて
保護するものもあり、外国
産の魚には
雌の
産んだ
卵を
雄が口中にくわえて
保護するものさえある。
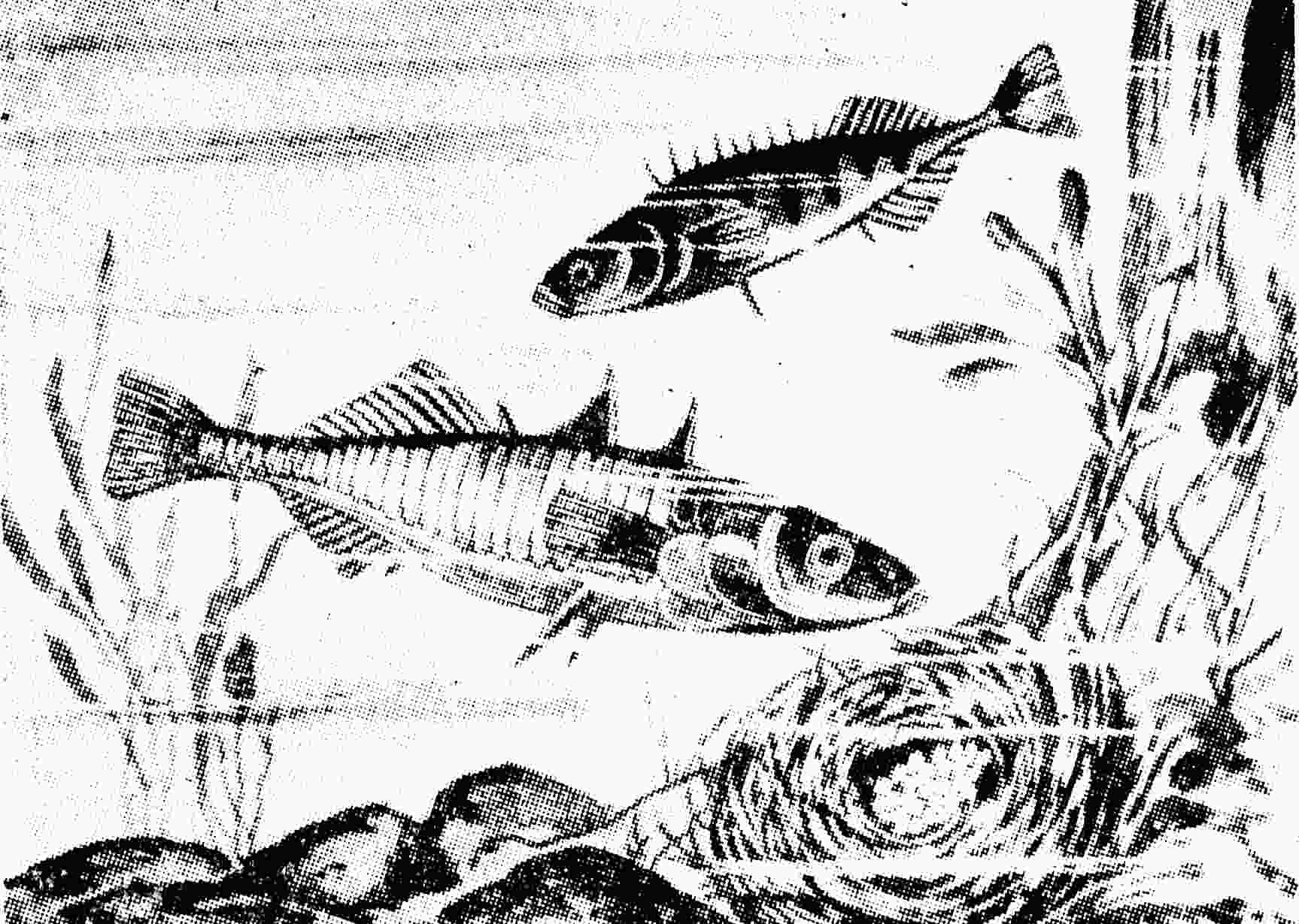 とげうお
巣
とげうお
巣をつくってその中で
卵をつくるものは
魚類にははなはだまれであるが、その中では
淡水産の「とげうお」
類がもっとも名高い。この
類はあたかも
鰹を小さくしたごとき形の魚で、ところどころの水の
綺麗な池や川にいるが、
産卵期になると
雄は
腎臓から出る
粘液を用いて、水草の
茎などを
寄せ集めて
円い
巣をつくり、
雌を
呼び来たってその中へ
卵を
産ませ直ちにこれを
受精して、その後は
絶えず
近辺にとどまって番をしている。なかなか
勇気のある魚で、指で
巣に
触れでもすると、直ちに
脊の
棘を立てて
攻めてくる。親魚の大きさにくらべると
割合に大きな
卵で、数はわずかに百か百五十くらいより生まれぬ。
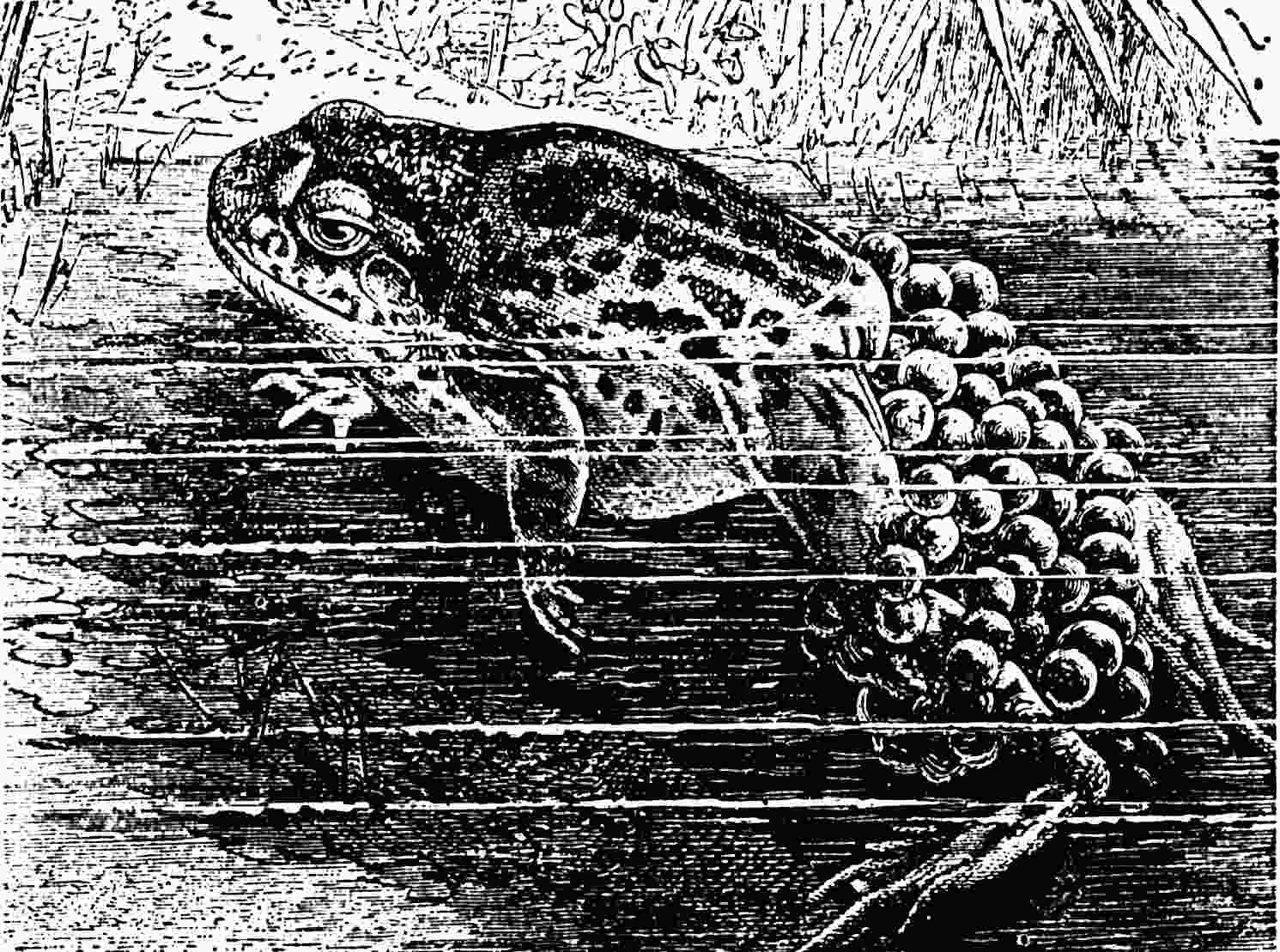 産婆蛙
蛙
産婆蛙
蛙の
類にはよほど
変わった
方法で
卵を
保護するものがある。ドイツ、フランスの南部に
普通にいる「
産婆蛙」は、大きさは
赤蛙くらいで、
姿は「ひき
蛙」に
似ているが、
産卵する時には、
雄は
雌をうえより
抱き、生まれ出る
卵を自分の足に
巻きつける。
蛙の
卵はいつも
粘液に
混じて生まれ出るもので、「ひき
蛙」や「
殿様蛙」では
粘液は直ちに水を
吸うて
量が
増し、
柔らかく
透明な
寒天ようのものとなるが、
産婆蛙は
陸上で
産卵するゆえ、
卵は
濃い
粘液につながれて
珠数のごとき形をなし、
雄がこれを足に
巻きつければ、
粘液のためにそこに
粘着する。かくして、
雄は
卵を
膝や
腿の
辺に
巻きつけたまま石の下などに
隠れ、
卵が発育して「おたまじゃくし」になるころになると、
近辺の池まで行き、水の中へ泳ぎ出させる。
普通の
蛙にくらべると、
卵は大きくて数がよほど少ない。
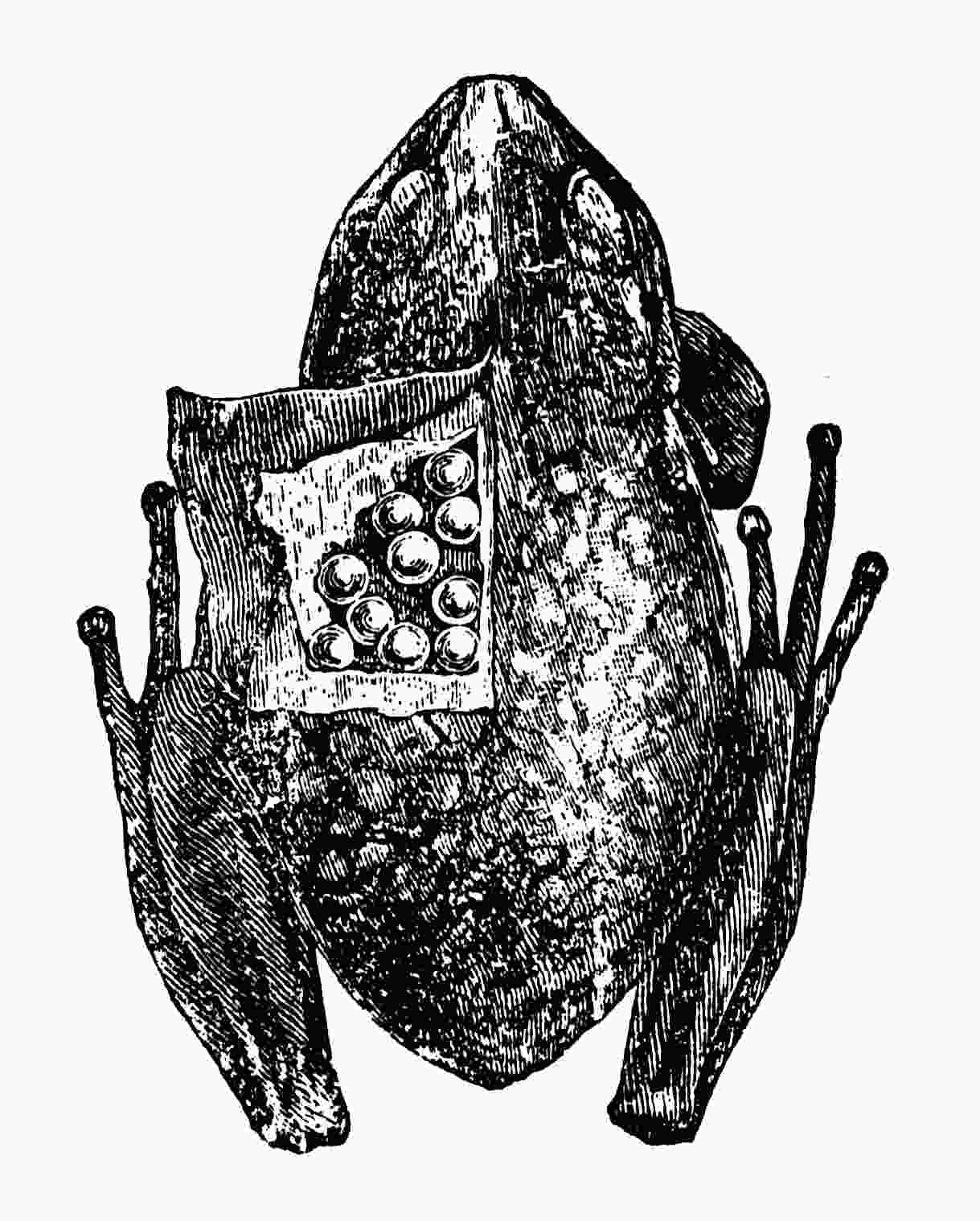 袋蛙
袋蛙
また南アメリカに
産する
雨蛙の
一種では、
雌の
背に一つの
嚢があり、その口は
背の
後端に近いところで
肛門の少しく前に開いているが、
卵は生まれると直ちにこの
嚢に入れられ、発生がよほど進むまでその中で
保護せられる。
卵はむろん
粒が大きくて数が少ない。
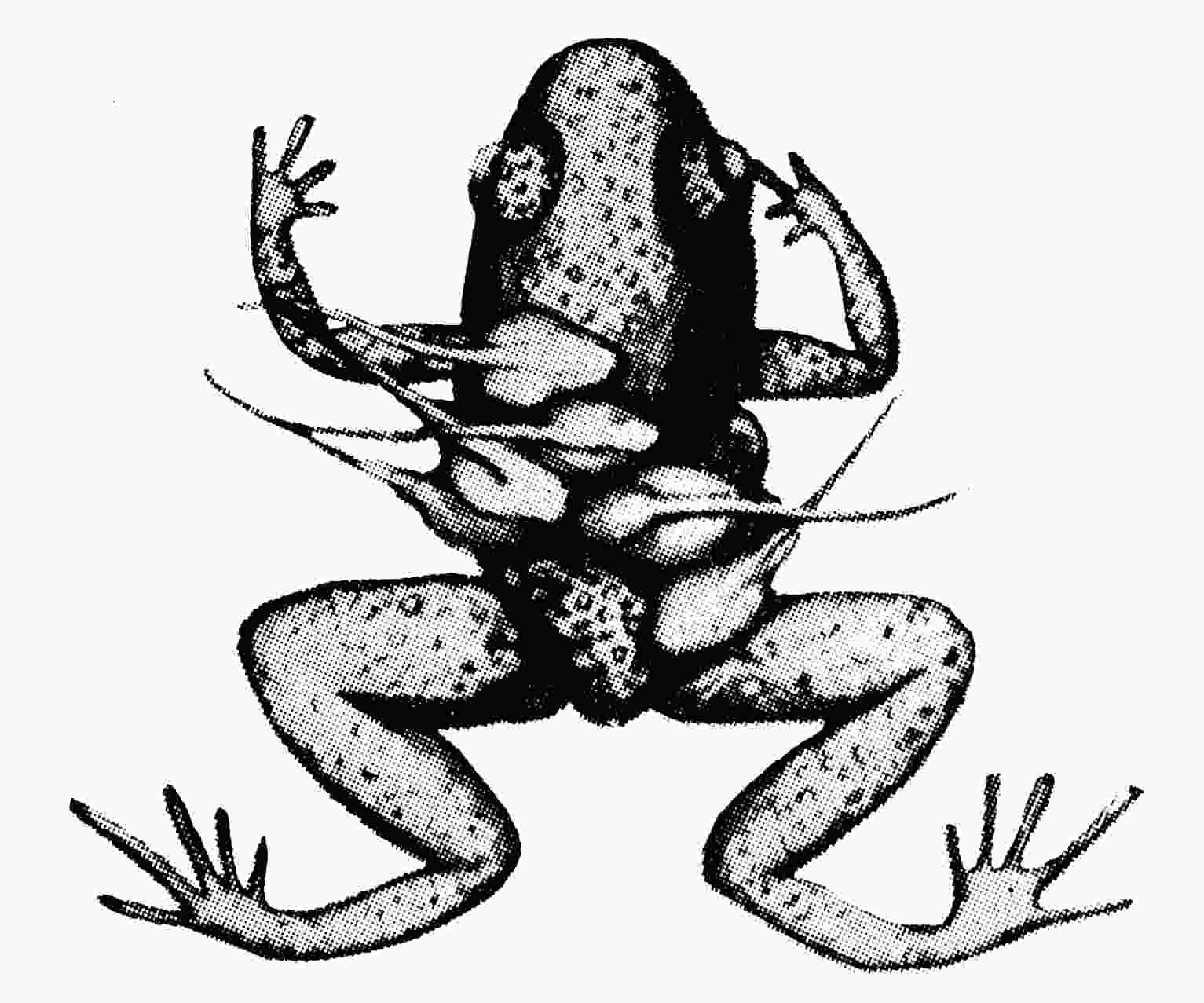 背負蛙
背負蛙
また同じく南アメリカに
産する
雨蛙で、
十数個の
大卵を
単に
背面に
粘着せしめて、
背負うて歩く
種類もある。インド洋の南にあるセイシェル島の
蛙は、「おたまじゃくし」を親が
背にのせて歩く。
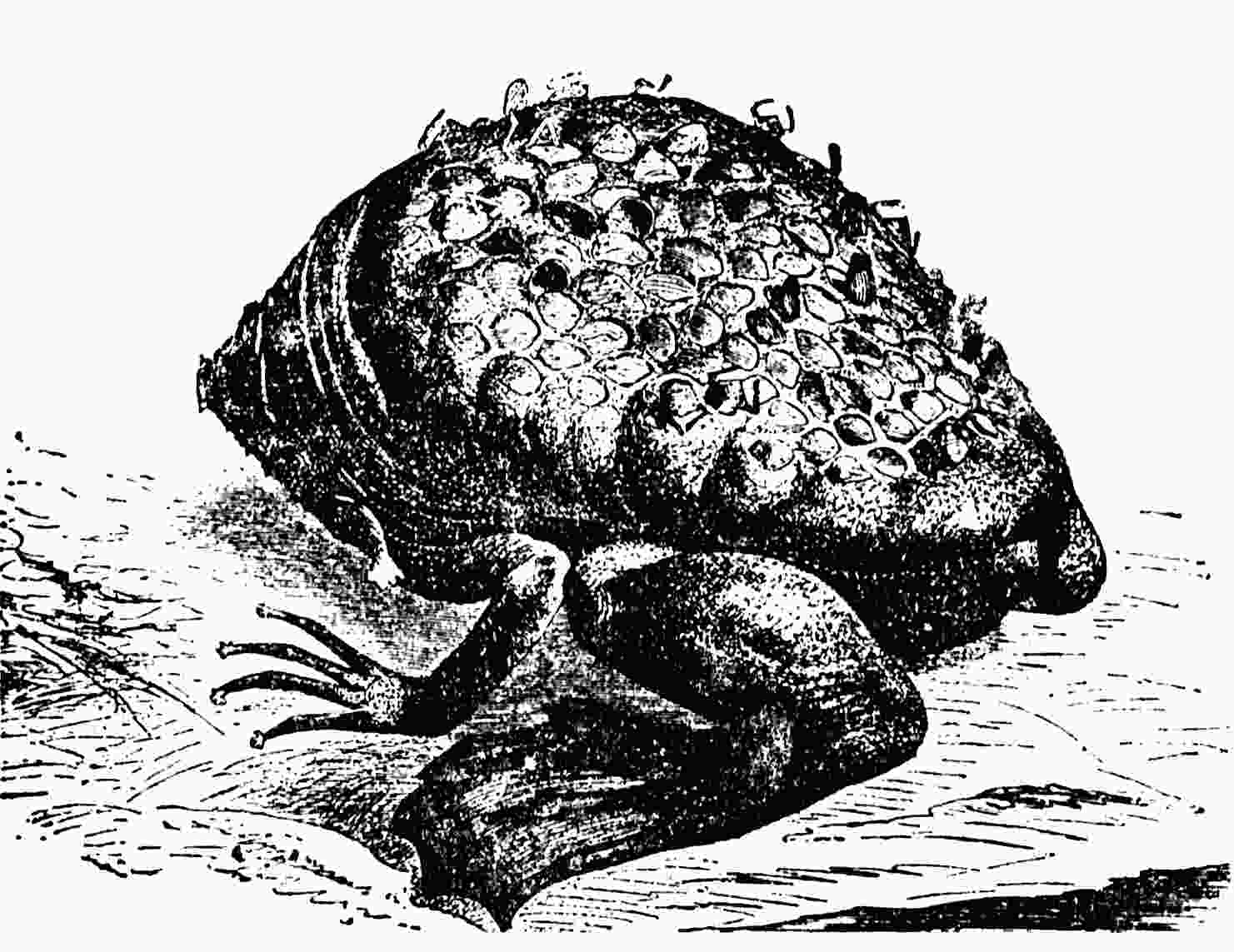 背孔蛙
背孔蛙
南アメリカの北部の
熱帯地方に
産する「
背孔蛙」と
称する
一種は他に
類のない
方法で
卵を
保護する。「ひきがえる」ほどの大きさの
妙な
蛙であるが、
雌が
粘液に
混じて
数十個の
卵を
産み出すと、
雄はこれを
雌の
背のうえに
塗りつけてやる。日数がへると
雌の
背中の
皮膚が
柔らかく
厚くなり、
卵は
一粒ずつその中の
孔にはまり
包まれ、かくして
保護せられるのみならず、「おたまじゃくし」時代をもとおり
越して、四本の足を
備えた小さな
蛙の形まで発育する。
幼児は
初めは親の
背中の
皮膚の
孔から顔だけを出しているが、後にはあたかも「カンガルー」の
幼児などのごとくに、自由にはい出したりまたもとの
孔にはいったりする。しかしこれは
極めて短い間であって、四足が自由に動くようになれば、親から
離れて
独立の生活を始める。
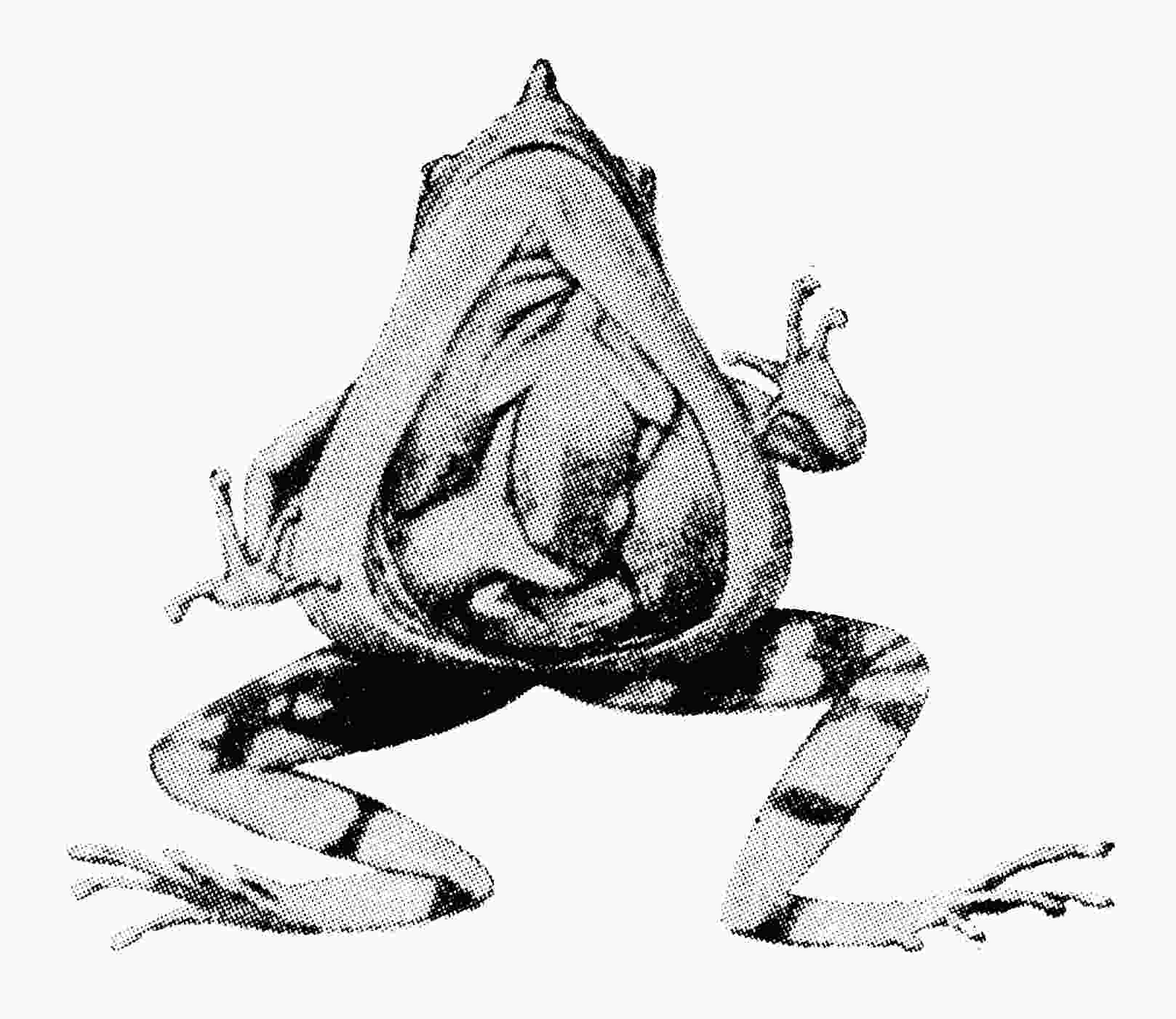 卵を呑む蛙
卵を呑む蛙
子が母親の
背中の表面から
産まれるというのも
珍しいが、同じ南アメリカのチリ
辺に
産する
一種の小さな
雨蛙は、さらに意外な
方法で
卵を
保護する。この
蛙は、
雌が大きな
卵を
一粒ずつ
産むと、
雄は直ちに
嚥み
込んでしまう。ただし
卵はむろん食道を
通過し、
胃にはいって消化せられるのではなく、
咽喉から
別の道をとおって
別の
嚢にはいり、その中で小さな
蛙の形まで発育し、ついに父親の口から
産み出される。それゆえ一時はこの
蛙は
胎生と思われていたが、
腹に子を持っているものを
解剖して見ると、いずれも
睾丸を
備えた
雄ばかりであるゆえ、なおよくよく調べて見たら、
子供のはいっている
嚢は、
普通の
雨蛙が鳴くとき声を
響かせるためにふくらせる
咽喉の
嚢に相当することが明らかに知れた。
普通の
雨蛙の鳴くところを横から見ると、声を発するごとに
咽喉の皮が大きくふくれるが、チリの小さな
雨蛙では、この
嚢がさらに大きくなり、
内臓のある場所と
皮膚との間に
割り
込んで、
腹のほうまで
達しているのである。
以上述べたのはいずれも親が何らかの
方法で
卵を
保護するだけの
例であるが、だれも知るとおり動物の中には、親が
幼児に食物を
与えて
養うものがいくらもある。しかしこれはほとんど
獣類、
鳥類のごとき
神経系の
発達した高等の動物に
限ることであって、
昆虫類には多少その
例があるが、それより
以下の動物ではこれに
類することは一つも行なわれぬ。親が子を
養うという
以上は、親の
生存時期と子の
生存時期とが一部重なりあい、その間親と子とが
相接触して
共同に生活していることは言うを待たぬが、子がいささかなりとも親を
慕う
形跡の見えるのは、全動物界中かような
類のみに
限られ、しかも子が親に
養われる期間のみに
限られている。その他のものにいたっては子はけっして親を知らず、全く
無関係のごとくに生活して代を重ねてゆく。前に
卵を
保護する
種類は
卵を
産み放しにするものにくらべると、はるかに少数の
卵を
産むことを
述べたが、親が子を
養う
種類では、子の生まれる数はなおいっそう少ない。しかもこの少数の子を大事に
保護し
養育するのも、小さな
卵を
無数に
産み
放すのも、
種族の
維持継続を
目的とすることにいたっては全く同じであって、その
効力にもけっして
甲乙はない。ただ
各種動物の
構造習性等に
適した
方法を
採っているというにすぎぬ。
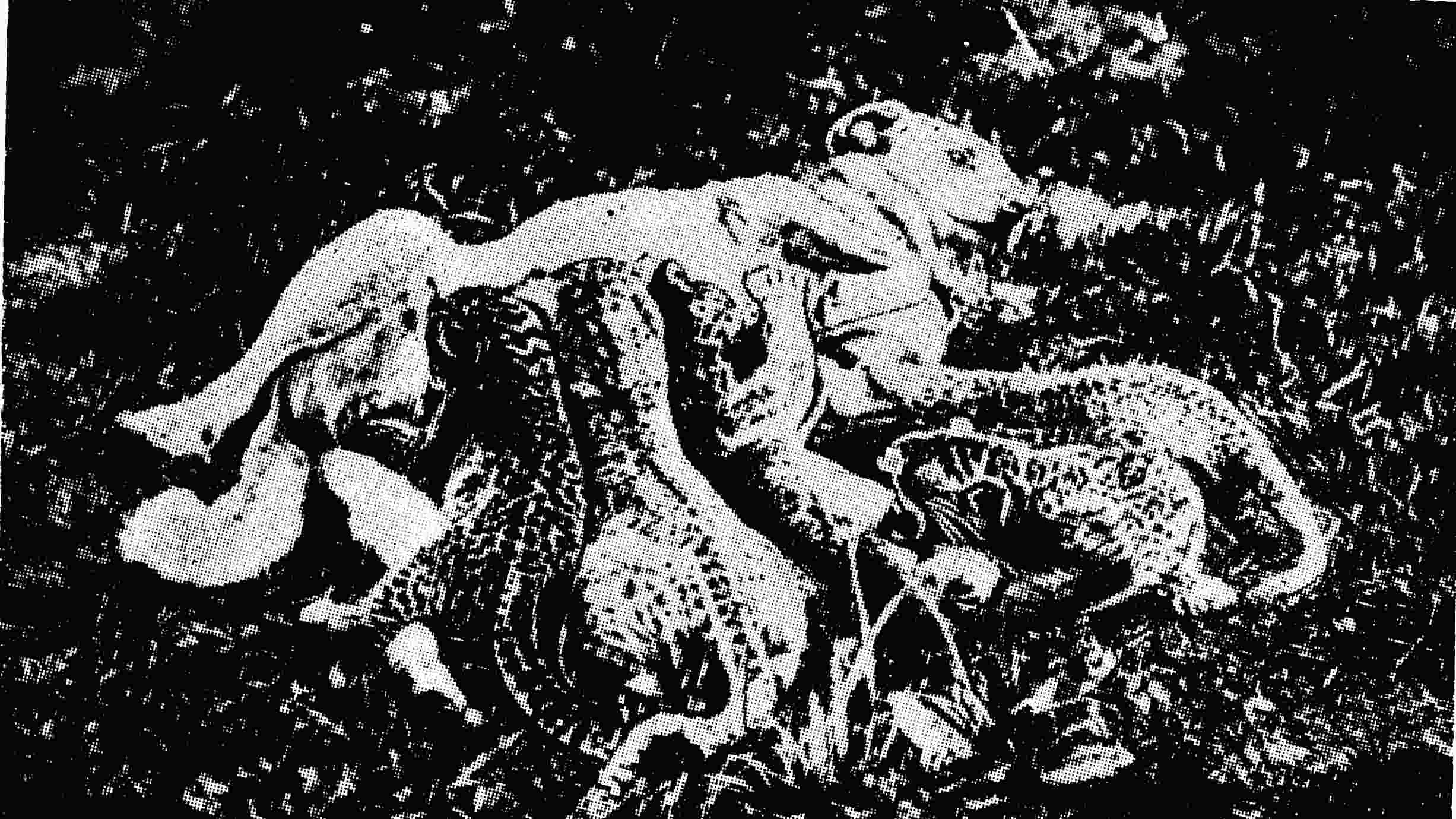 豹の子に乳を呑ませる犬
獣類
豹の子に乳を呑ませる犬
獣類の
幼児はすべて母の
乳汁で
養われるが、
乳汁は動物の
種類によってそれぞれ
成分がいくらずつか
違うて、あるいは
脂肪が多いとか
糖分が少ないとかいうことがある。それゆえ、
幼児を
養うのにもっとも
適するのはむろんその
児を
産んだ母か、またはこれと同じくらいの
同種の
雌が
分泌した
乳であって、人間の
幼児を育てるのに、人の
乳よりも牛の
乳とか
山羊の
乳とかのほうがさらによろしいというような
理屈はけっしてない。しかし
乳汁なるものは
一種の食物にすぎず、
児の
腸胃にはいってから消化せられ
吸収せられるのであるゆえ、一定の
滋養成分を
含んでいる
以上は、
甲の動物の
乳汁をもって
乙の動物の
幼児を育てることももとよりできる。外国の動物園では
獅子や
虎の
幼児に、
牝犬の
乳を
呑ませて
健全に育てた
例もある。
現に
駒場の農科大学では
牝犬が
狸の子に
乳を
呑ませている。
幼児が
乳汁のみで育てられる時期の長さは
種類によって大いに
違い、
概して大形の
獣は
成長も
遅く
乳を
呑む間も長い。しかし人間ほどに長い間
乳を
呑むものは他になかろう。
幼児が
乳を
呑むことを止める前から、すでに何か食物を食い始めるが、これはたいてい母親が多少かみ
砕いて、
児のたやすく食えるようにしてやる。
猫や犬が子を育てるのを見ても、その
例はたくさんに見られる。
鳥類の
雛が
卵から
孵って出た時のありさまは
種類によってはなはだ
違い、
鶏のごとく直ちに走るもの
家鴨のごとく直ちに
游ぐものもあるが、
巧みに
飛ぶ
種類の鳥では
雛は実に
憐れなもので、親に
養われなければ一日も生きてはいられぬ。
鳥類にはずいぶん
精巧な
巣をつくるものがあるが、これはみな
卵を
温めかつ
卵から
孵った
雛を安全に育て
得るためである。

機織鳥
草の繊維を織り合わせて樹の枝より垂れ下がりたる嚢状の巣をつくる。巣の入口は下に向きたる短き筒の先に開けるをもって飛ぶ動物にあらざれば巣の内に入るを得ず,図に示したるは印度産の一種なり。
今もっとも
精巧なものとして有名な
例を一二あげて見るに、アフリカの
諸地方に
産する「
機織鳥」と
称するものは、「つぐみ」か「ひよどり」ぐらいの大きさの鳥であるが、草の
軸の細い
繊維などを
巧みに
布のごとく
編み合わせて、
樹の
枝から
垂れた
嚢のような形の
巣をつくる。
 仕立屋鳥
仕立屋鳥
また東
印度の島に住む「仕立屋鳥」という小鳥は、大きな木の葉を
二枚寄せてその
縁を植物の
繊維で
巧みに
縫い合わせ、その間に
巣をつくる。
 食用燕巣
食用燕巣
その他にも鳥の
巣には
精巧なものが
種々あるが、中には他の
材料を用いず、自分の口から出す
唾液だけで
巣をつくるものがある。
支那人が
最上等の
料理として
珍重する有名な
燕の
巣はそれで、今では西洋人にもこれをたしなむものがなかなか多くなった。
普通の
燕は口に
泥をくわえてきて、
泥と
唾とを
混ぜて黒い
堅い
巣をつくるが、この
燕はただ
唾液だけでつくるゆえ、
巣は真白であたかも
乾いた
寒天のごとくである。
産地は東
印度の島々であるが、海岸の
絶壁のところにつくられるゆえ、たくさんあるにかかわらずこれを
採集することはなかなか
容易でない。
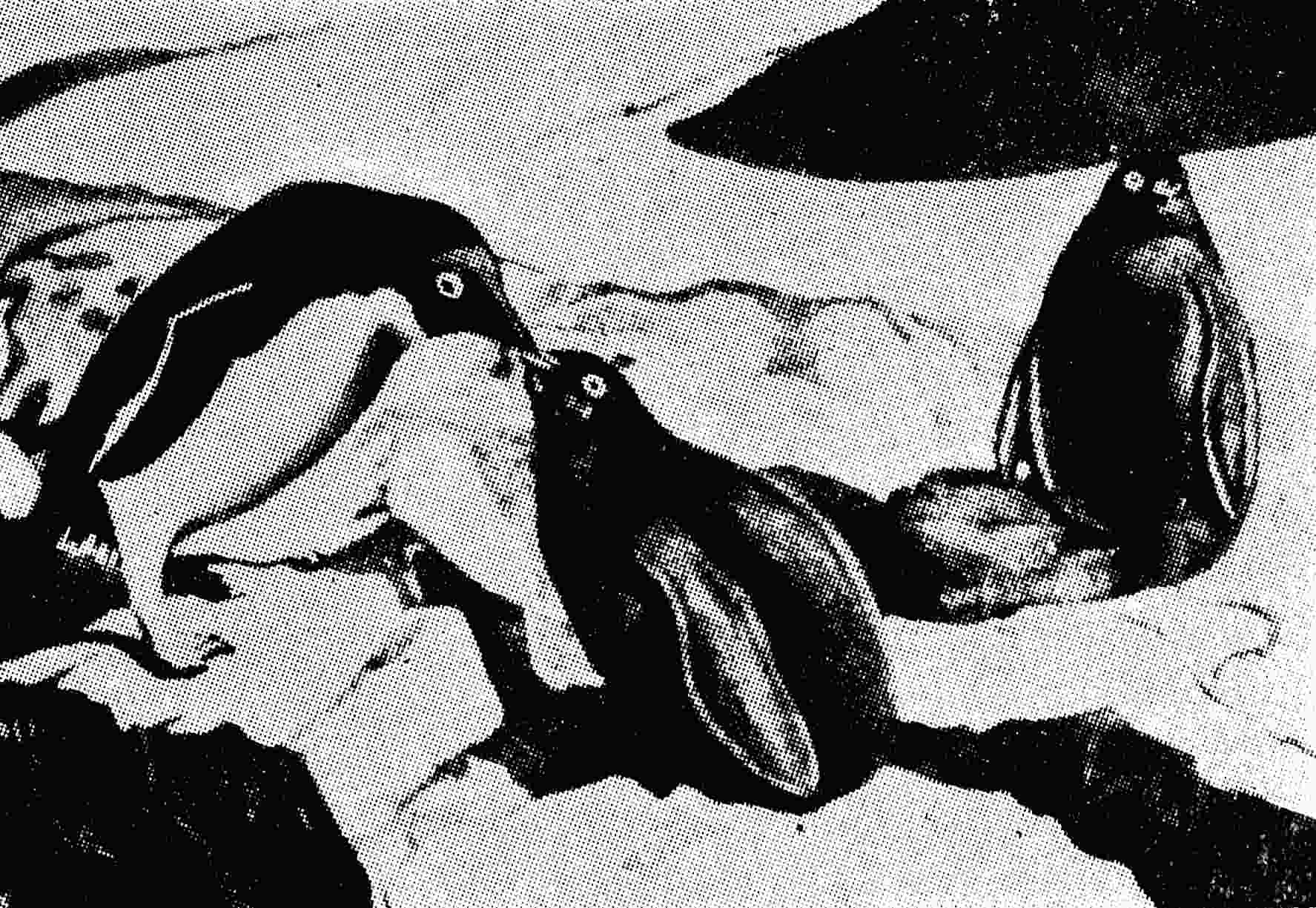 子に餌を与えるペンギン鳥
子に餌を与えるペンギン鳥
親鳥が
雛を
養う仕方も、
種類によって
種々に
違う。
燕などは
捕えてきた
昆虫をそのまま
雛の口に
移してやるが、
雀や
烏もこれと同様で、そこで
啄んだ食物をそのまま子に
与えるのをしばしば見かける。
鷲や
鷹の
類は
捕え
殺した
餌を、さらに小さく
裂いて
雛に食いやすいようにしてやる。動物園の
鶴なども子にやる時には、
鰌をまず小さくかみ切り、水で
洗うて
与える。また「ペリカン」のごとき鳥は、一度のみ
込んだ
餌を口まで
吐き出して子についばませる。
鳩類では
雛が
孵化するころには、
雌雄ともに
'ソ嚢の
壁が
厚くなり、
特に
一種の
濃い
滋養液を
分泌し、これを口から
吐き出して子の口に
移してやる。昔から「
鴉に
反哺の
孝がある。」と言い
伝えたのはおそらく、
鳥類の親が
雛の口の中へ
餌を
移し入れてやるところを遠方から見て、子が親を
養うのかと思い
誤ったためであろう。
鳥類にかぎらず
如何なる動物にも、子が
成長し終わった後に、
老耄して生き
残っている親に
餌を
与えて
養うものは、けっして
一種たりともない。その理由は、かかることをしても
種族の
維持のためには何の役にも立たぬのみか、
餌が少なくて生活の
困難な場合には、かえって
種族のために明らかに
不利益になるからであろう。
 餌を運ぶ蜂
昆虫類
餌を運ぶ蜂
昆虫類の中でも
蜂の
類には、子を
養うために親虫が
盛んに
餌を集めて
貯蔵するものがある。
蟻や
蜜蜂のことは
省くとして他の
種類について言うて見るに、地中に
孔を
穿ってその中に
卵を
産んでおくいわゆる「
地蜂」の
類は、昼の間は
絶えず
飛びまわって「くも」や
昆虫類などを
捕え、
尻の先の
毒針をもってその虫を
刺して
麻痺せしめ、動けぬようにしておいてこれを
孔の中へ運び入れ、自分の
幼虫に食わせる。
昔の人はこの
類が毎日「くも」を地に
埋めるのを見、またその同じ
孔から
蜂の子が出てくるのを見て、「くも」が
蜂に
変化するのであろうと早合点して、この
蜂の名前に「
似我蜂」という字を当て、この
蜂は実子を
産まず、「くも」を
連れてきて
養子とし「
我に
似よ。」「
我に
似よ。」というて
埋めておくと、やがてその「くも」が
蜂になるなどという
牽強付会な
説をつくった。かような
例はなお他にもいくつもあって、
卵を
産むときに一度だけ
餌を
添えておくものや、
卵が
孵って
幼虫になってからもしばしば
餌を持ってきて
与えるものなど、多少
相異なった
方法で子を
養うている。
生殖の
目的は
種族の
維持にあるゆえ、子の
生存し
得べき
見込みがついた上は、親の身体はもはや
無用となって死ぬべきはずである。親と子とが
相知らぬような
種類の動物では、
卵が生まれてしまえば、親はいつ死んでも
差支えはない。
特に父親のほうは
受精をすませばもはや用はないゆえ、なるべく早く死んだほうがかえって
種族の
生存のためには
経済にあたる。
蜜蜂の
雄が女王の体とつながったままで
気絶して死ぬのも、「かまきり」の
雄が
交尾したままで頭のほうから
雌に食われるのも、この
理屈にすぎぬ。子を
産めば直ちに死ぬ動物はずいぶん多いが、
或る
種類の
条虫のごとくに子を
産み出すべき
孔がなく、子は親の体が
破れて外に出るような動物では、親の
個体を
標準として
論ずれず、
妊娠はすなわち
自殺の
覚悟にあたる。これらは、子ができると同時に親の近々死なねばならぬことが定まるのであるが、いったん子ができてから後に、親が子のために命を
捨てるものも、けっして
珍しくはない。
獣類や
鳥類のごとくに、親が子を大事に
養育するものでは、
不意に
敵に
攻められた場合に、親が身をもって
子供を
護り、そのため一命を落とすことのあるは、
猟師などからしばしば聞くところであるが、かくまで
熱心に子を
保護する
性質が親に
備わってあることは、
種族維持のためにすこぶる
有利であるゆえ、
本能として、今日の
程度までに進み来たったのであろう。
鳥獣などのごとき
神経系の
発達した動物が、命をも
捨ててわが子を
護る
働きは、人間自身にくらべて、よく
了解することができるが、小さい
虫類になると、人間では思いがけぬような
方法で、子を
保護するものがある。
蛾の中で「まいまい
蛾」と
称する
普通の
種類は、
卵を
一塊産みつけると、その表面に自分の身体に生えていた毛を
被わせて
蔽い
包み、まるで黄色の
綿の
塊のごとくに見せておく。これは親が
即座に命を
捨てるわけではないが、まず自分の毛を全く
失うことゆえ、人間の女にたとえて言えばあたかも緑の
黒髪を根元から切って
子供の夜具につくり、しかる後に
自害するようなものであろう。また植物に
大害を
与える「
貝殻虫」の
類には、死んでもその場所にとどまり、自分の
干からびた
死骸をもって
卵の
塊をおおい
保護するものがある。「
貝殻虫」は
初めは「ありまき」のごとくに六本の足をもってはい歩くが、
一箇所に止まり、
吻を植物の
組織の中へ
差込んで動かぬようになると、体があたかも皿か
貝殻かのごとき形に
変じ、一見しては
昆虫とは思われぬようなものになる。しこうして
成熟して
産卵するころにいたると、虫の
柔らかい身体は
背面の
貝殻のごとき部とは
離れ、
貝殻に
被われたままでその中で
卵を
産むが、
卵を
一粒産むたびに親の身体はそれだけ
容積が
減じ、ことごとく
卵を
産み終われば
貝殻の内部は全く
卵のみで
満たされ、親の体はあたかも空の
紙袋のごとくになって
貝殻の
一隅に
縮んでしまう。これに
類する死に方をするものはなおいくつもあるが、ここには
略して、次に一つ全く
別の方面に、親が子のために一身を
犠牲に
供するものの
例をあげて見よう。
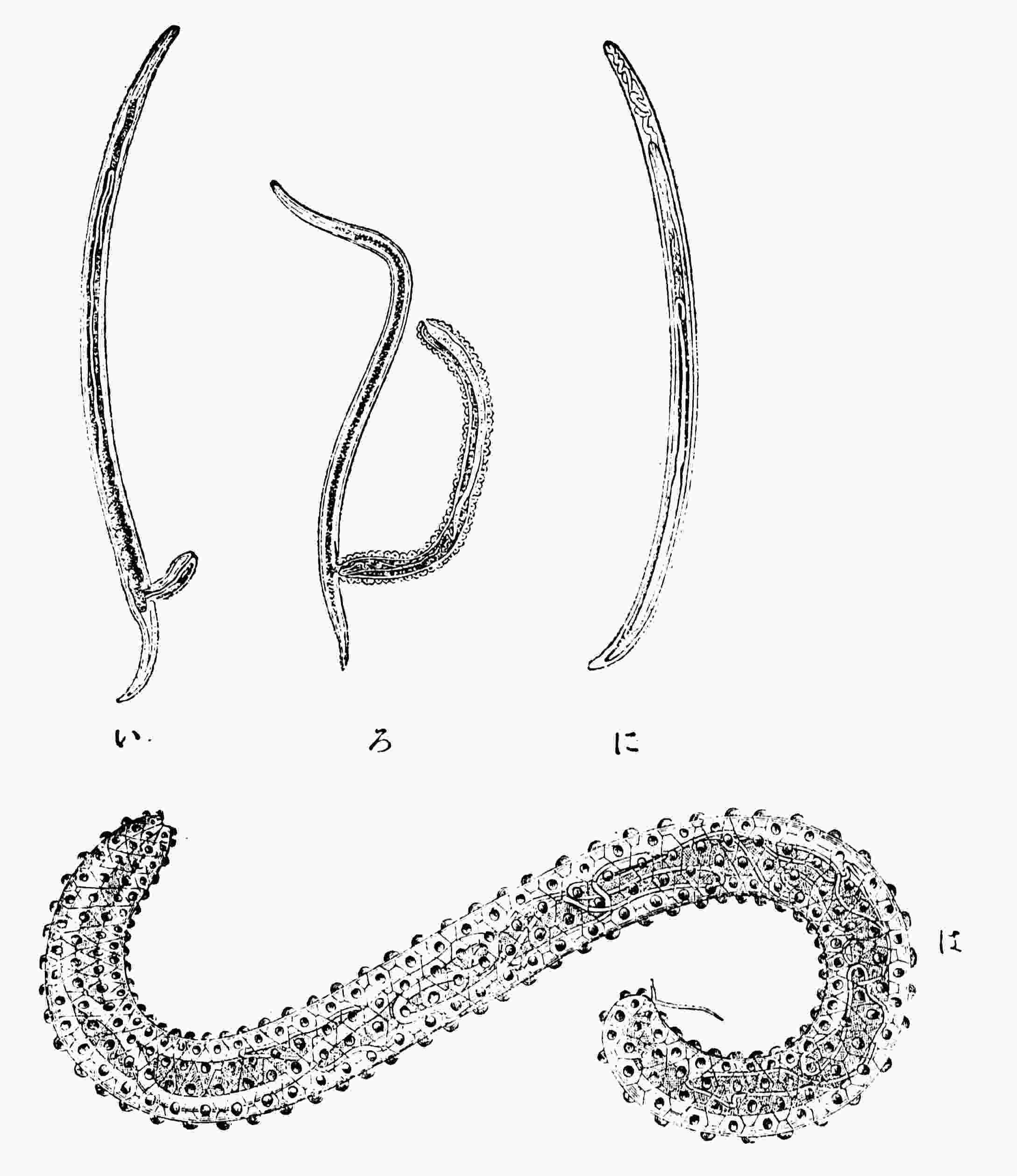
蜂の寄生虫
(い)膣の半ば裏返りて出たる雌(長さ約三厘(注:0.9mm))
(ろ)膣が全く裏返りて大きくなりたる雌
(は)成長し終わりたる膣の嚢(長さ約五分(注:1.5cm))その一端に付着するは雌の体
(に)雄
夏日花のあるところにたくさん
飛んでくる、「はなばち」、「まるばち」などという
蜂の
類は体が丸くて、黒色や黄色の「びろうど」のごとき毛で
被われているが、この
蜂の
雌が、冬
成虫のままで
隠れているのをとって
解剖して見ると、その体内に
奇妙な
寄生虫のいることが
往々ある。長さ五分(注:1.5cm)ばかりにも
達する小さな「なまこ」
状の
嚢で、その内には小さな
蛔虫に
似た虫がたくさんいるが、さてこの
嚢の形が内なる
子供といちじるしく
違うゆえ、たしかに親であるとも見えず。一体
如何にしてできたものか、そのままではとうてい知れがたい。しかし内なる
子供が
成長して、ついに次の代の子を
産むにいたるまでの発育の
順序をつまびらかに調べると、この
嚢の
素性が明らかに知れる。
子供は
嚢の中で
或る
程度まで
成長すると、
嚢を
破って出で、次いで
蜂の体よりも出で地中で
独立に生活し、長さ一分の三分の一(注:1cm)くらいになると、
生殖の
器官も十分に
成熟する。かくて
交尾の後、
雄は直ちに死んでしまうが、
雌は「はなばち」の体内にもぐり
込み、その中で母の体内の
子供がだんだん発育するのである。しこうしてその
際、母の体に意外な
変化が生ずる。すなわち図のとおり、
生殖器の開き口に直ちに
接する
膣と
称する部が、あたかも
巾着を
裏返しにしたごとくに
裏返しとなって、
生殖器の
孔から体の外面に
現われ出る。
膣の内面は外面となって、直ちに宿主動物の
組織にふれてこれより
滋養分を
吸収し、
膣のつづきなる
子宮は、中に子をいれたまま
膣が
裏返しになったためにできた
嚢の内に入り来たり、中の子の
成長するとともに
次第に大きくなる。これに引き
換え、
膣と
子宮とが体外へ
脱出した後の母の体はそのまま少しも
成長せぬゆえ、
膣の
裏返しになってできた
嚢が長さ五分(注:1.5cm)にもなったころには、ただ
極めて小さな
付属物として、その
一端に
付着しているにすぎぬ。
膣が
裏返しになって体外へ
現われ出ることは、「
膣外翻」と
称して人間の女にも
往々見るところであるが、ここに
述べた虫では、このことが
規則となり、
妊娠すれば
必ず
膣外翻が起こり、しかも新たに外向きになった
膣の内面は、宿主動物から
滋養分を
吸収して、
胎児に
供給すべき
器官としてさらに大いに
発達するのである。その代わり、
残りの母の体はもはや
不用物として、ついには宿主動物の
組織に
吸収せられてしまうのほかはない。子を宿主動物の体内でよく発育せしめるために、母体にかような
変化の生ずる虫は、今
述べたもののほかになお
甲虫類に
寄生するもの、
蠅類に
寄生するものなどが
幾程もある。
前に
幼時生殖のことを
述べるにあたって、植物に
五倍子をつくる
一種の
微細な
蠅のことを
例にあげたが、この
蠅の
幼虫が
卵を
産むときには、
卵は親なる
幼虫の体内で発育し、親と同じ形の
幼虫となり、
初めは
子宮の内にいるが、少しく大きくなるとみな
子宮を食い
破って、母の身体の
組織を
片っ
端から食い
盛んに
成長する。それゆえ母の体は、ついにはただ表面を
包む
薄皮が
一重残るだけで、あたかも
氷嚢のごときものとなってしまう。人間は母親のことをときどき「お
袋」と
呼ぶが、この虫では母親は真に
袋だけとなり、肉はことごとく
胎児に食われてその肉に化するのである。
胎児は
成長が進むと、ついに母の
遺骸なる
薄皮の
嚢を
破って出るが、かような場合にこれを「生まれ出る。」と名づくべきか
否か、すこぶる
曖昧で、実はなんと名づけてよろしいかわからぬ。「生まれる。」という文字はがんらい母の体はそのままに
存して、ただ子の体が母の体から出で
離れる
普通の場合にあたってつくられたものゆえ、
普通と
異なった場合によくあてはまらぬは
当然である。この虫などでは、子が生まれるときはすでに母親はいないが、いない親から子が生まれるというのは
如何にも
理屈に合わぬ。またそれならば、母親は死んだかというと、後に
死骸が
残らぬゆえ、
普通の意味の死んだとも言いがたい。すなわち生きている親の身体
組織が、生きたままで子に食われるから、これが親の
死骸であると言うて指し
示すことのできるものは全く生ぜぬ。前に
薄皮の
嚢を母の
遺骸と言うたが、これは
単に
便宜上言うたことで、体の表面を
包む
薄皮のごときは、人体にたとえて言えば毛か
爪か、
厚皮の表面のごとき
神経もなく、切っても
痛くない部分ゆえ、これのみではむろん真の
遺骸とは名づけられぬ。ただ
死骸の発見せられぬ人の
葬式に、
頭髪をもってこれに代用するのと同じ意味で、
遺骸と言うたにすぎぬ。
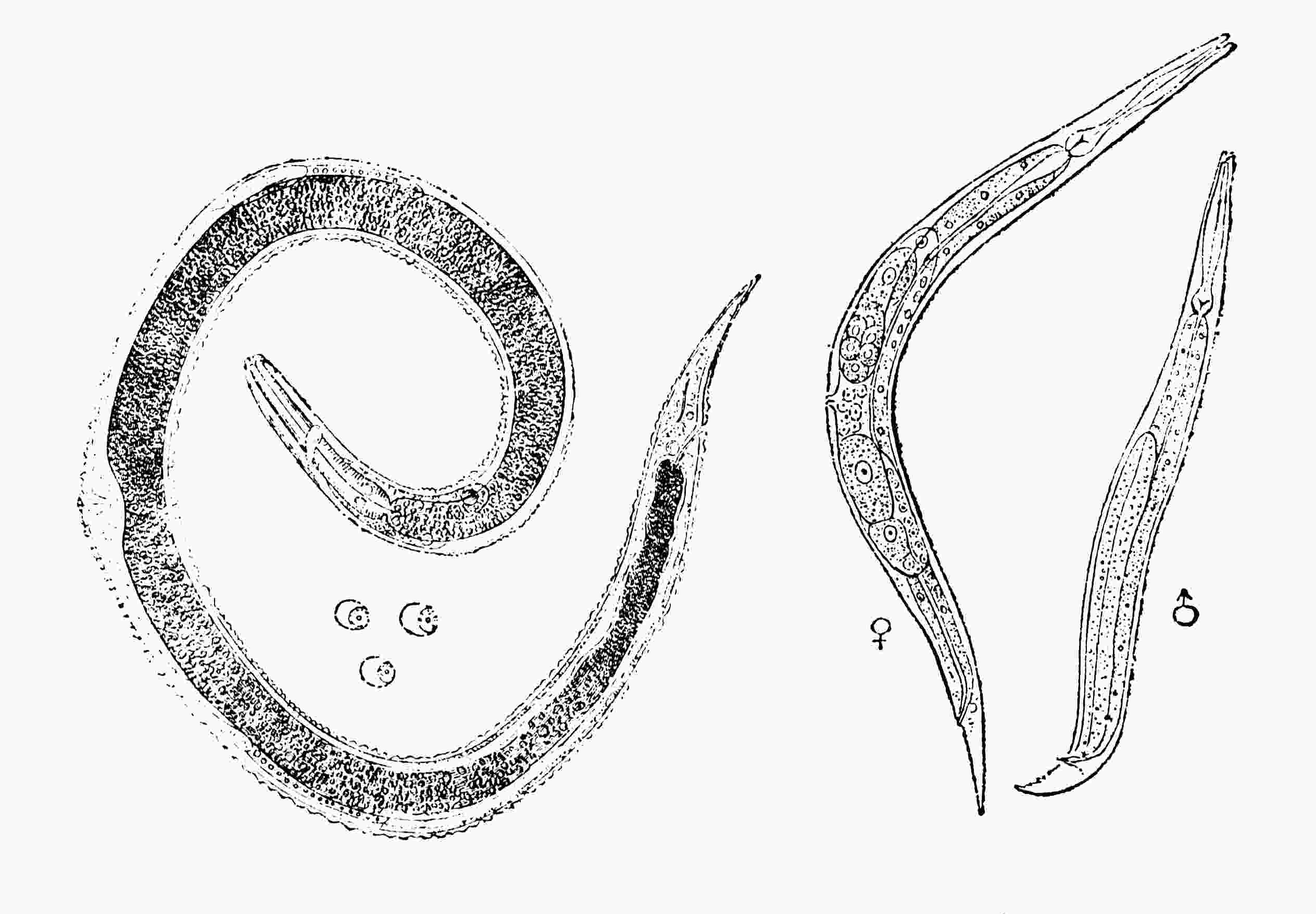
蛙の寄生虫
右の二匹は泥中に自由に生活するもの(長さ約五厘(注:1.5mm))
左の一匹は蛙の肺の内に寄生するもの(長さ約五厘(注:1.5mm))
これと同様の
例をなお一つあげて見るに、
蛙類の
肺臓の内に
往々一種の小さな糸のごとき
寄生虫がいる。
蛔虫、
十二指腸虫などと同じ
仲間に
属するものであるが、他のものがみな
雌雄異体であるに反し、これは
一匹ごとに
雌雄を
兼ね、その
産んだ
卵は
蛙の
肺より食道
胃腸に
移り、
蛙の
糞とともに体外に出で、水の中で発育する。かくして生じた子は親とは形が
違い同じく
糸状ではあるが、親にくらべるとやや太くて短く、かつ
雌雄の
別があって形も
互いに
違う。
泥の中で自由に生活し、
成熟すると
交尾して、
雌の体内に少数の子ができる。これらの
子供は始めは親の
子宮の内で発生し、少しく
成長すると
子宮を食い
破ってその外に出で、母親の肉を
順々に食い進み、ついにはただ表面の
薄皮のみを
残して、内部を全く
空虚にしてしまう。この点は、前の
例におけると少しも
違わぬ。次に
薄皮をも
破って
裸で
泥の中に生活し、
蛙に食われてその体内にはいると、直ちに
肺臓内に
匍い
移り、少時で
雌雄同体の
生殖器官が
成熟して
卵を
産むようになる。前の
蠅は
幼虫が子を
産むゆえ、
幼時生殖の
例であったが、この
寄生虫はかくのごとく
雌雄同体で
卵生する代と、
雌雄異体で
胎生する代とがかわるがわる
現われるゆえ、世代
交番の
例ともなる。
動物界における親と子の
関係を
見渡すと、本章にかかげた
例だけによっても知れるとおり、全く
無関係なものから、親が子を
保護するもの、親が子を
養育するもの、子が親の身体を食うて
成長するものまで、実にさまざまの
階段がある。しかもよく調べて見ると、けっして
偶然に
不規則にさまざまのものがならび
存するのではなく、一々かくあるべき理由が
存し、
如何なる場合には
種族の
維持継続を
目的として、そのためおのおの
異なった
手段を
採っているにすぎぬことが明らかに知れる。たとえば
最後にあげた
例のごときも、
種族継続の
目的からいうと、母親の身体が生きながら子の
餌食となることがもっとも
有利であろう。
最後の子を
産み終わった後の母の身体は、
種族を
標準としていうと、もはや
廃物であるが、これが
自然に死んで
腐ってしまうか、または
敵に食われ
敵の肉となって
敵の
勢を
増すことにくらべれば、わが子の身体をつくるために
利用せられ、
直接に自分の
種族の
繁栄に力を
添え
得るほうが、全体としてはるかに
得の
勘定となる。しからばなぜすべての動物で子が母親を食うて
成長せぬかというに、これは
各種類の生活
状態がみな
相異なって、
甲に対して
有利なことも、
乙に対しては
必ずしも
有利と
限らぬからである。何事にも
一得あれば
一失あるをまぬがれぬもので、子が母親の体の内部から食うて
成長するとすれば、母はたちまち運動の力を
失い、子は
一塊に集まって動かずにいることになるゆえ、
敵に
攻められた場合には全部食い
尽くされて
種が
残らぬおそれがある。
仮に
魚類が
胎生して、
胎児が
腹の内から母の肉を食うて
成長すると
想像するに、「さめ」にでも食われてしまえば
子孫全滅をまぬがれぬから、
種族保存の上から言えば
極めて
不利益であって、これにくらべれば
無数の小さな
卵を
蒔き
散らし、
残った母の体を
廃物として、
捨て去ったほうが
如何ほど
有効であるかわからぬ。かような
次第で、
各種動物の
習性に
応じて、それぞれもっとも
有効な
種族保存の
方法が
自然に
講ぜられているゆえ、親子の間にさまざまな
関係の
違うたものが生ずるのである。
たいがいの動物では
無数の
卵を
産み放しにするか、または子を
保護し
養育しさえすれば、
子孫のいくぶんかが
必ず
生存し
得べき
見込みは立つが、
獣類、
鳥類などのごとき
神経系のいちじるしく
発達した動物になると、さらに子を
或る
程度まで教育しておかぬと、安心して
生存競争場裡へ手放すことができぬ。
敵を
防ぐにあたっても
餌を取るにあたっても、
敏活な運動ができねば
競争に
敗けるおそれがあるが、
敏活な運動には数多くの
神経と
筋肉との
相調和した
働きが
必要で、それが
即座に行なわれ
得るまでには、多くの練習を
要する。しこうして練習するにあたって子が
独力で一々実地について練習しては
危険が多くて、大部分はその間に命を落とすをまぬがれぬ。
例えば
敵から
逃げることの練習をするのに、子が一々
実際の
敵に
遭遇して
逃げるとすれば、これは
真剣の勝負であるゆえ、練習中に
殺されるものがいくらあるか知れぬ。もしこれに反して、親が
仮想の
敵となって子を追いかけ子は
一生懸命に
逃げるとすれば、
危険は少しもなくて同じく練習となり、練習が
積もって
完全に
逃げ
得るようになってから、これを世間に出せば、子の死ぬ
割合はよほど
減ずるゆえ、親は子を
遺す数が少なくても、ほぼ
種族継続の
見込みがついたものと見なして安心して死ねる。されば生活に
必要な
働きの練習を、子が
若いときに
独力でするような動物は、よほど多くの子を
産まねばならず、また親が
手伝うて子に練習させるような動物ならば、それだけ子を少なく
産んでも
差支えはない。さらにこれを
裏からいえば、子を多く
産む
種類は、練習を子の自由にまかせておいてもよろしいが、子を少なく
産む
種類では、親がよほど
熱心に子の練習を助けてやらねば、
種族維持の
見込みが立たぬということになる。
もっとも動物の
種類によっては、少しも練習を
要せずしてずいぶん
精巧な仕事をなすものがある。
蜜蜂が六角の
規則正しい部屋をつくり、
蚕が
俵状の美しい
繭を
結ぶなどするのはその
例であるが、これはいわゆる
本能によることで、その理由は、おそらく
神経系が生まれながらにしてこれらの仕事をなし
得る
状態にあるゆえであろう。すなわち始めから他の動物が練習によって
達し
得る
状態と同じ
状態にあるのであろう。しこうしてまたその
源をたずぬれば、
先祖代々の
経験の
伝わったものと見なすのほかはないゆえ、やはり今日までの
種族発生の
歴史中に練習を重ね来たった
結果ということもできよう。人間でも生まれて直ちに
乳の
吸い方を
心得ていたり、
巧みに
吸呼運動をしたり、
咄嗟の間に
瞼を
閉じて
眼球を
保護したりするのは、みな
本能の
働きで、少しも練習を
要せぬ。
かように数え上げて見ると、動物のなす
働きの中には、
本能によって先天
的にその力の
備わってあるものと、練習によって後天
的に
完成するものとがあり、また練習するにあたっては、子が
独りで
自然に練習を
積む場合と、親が子を助けて安全に練習せしめる場合とがある。教育とはすべて終わりのごとき場合にあてはめて用うべき言葉であろう。
たいていの教科書を開いて見ると、ただ人間の教育のみについて書いてあるゆえ、その
目的のごときも、人間だけを
標準としていたって
狭く
論じてある。しかもその書き方がすこぶる
抽象的でつかまえどころを見出すに苦しむようなものも少なくない。今日では
比較心理学などの流行し来たった
結果、やむを
得ず
鳥獣にも子を教育するものがあると書いた
論文をも
往々見かけるが、少しく古い書物には「教育は人間のみにかぎる。
何故と言うに、
精神を有するのは人間のみである。」などと
臆面もなく書いてあったくらいで、他の生物に行なわれる教育までも、研究の
範囲内に入れ、全体を
見渡して、
論を立てるごときことは
夢にもなかった。そのありさまは、あたかもむかし天動
説の行なわれていたころに、地球をもって
一種特別のものと考え、その金星、火星、木星、土星などと
同格の一遊星なることを知らずにいたのと同じであるが、かように根本から考えが
間違うていては、
如何に
巧みに
議論しても、とうてい正しい
知識に
到着すべき
見込みがない。教育の
目的を
論ずるにあたっては、まずかかる
迷いを
捨て、人間も他の動物も一列にならべて、
虚心平気に考えねばならぬ。
動物の
種類をことごとくならべて
通覧すると、子を
産み放しにして少しも世話せぬ
種類が一番多く、子をいささかでも
保護する
種類はこれにくらべるとはるかに少ない。また子を
単に
保護するだけのものにくらべると、親が子に食物を
与えて
養育するものははるかに少なく、子を
養うものにくらべると、子を教育するものはさらにはるかに少ない。かくのごとく、子を教育する
種類は、全動物界中の
極めて小部分にすぎぬが、
如何なる動物が子を教育するかといえば、これはほとんどことごとく
獣類、
鳥類であって、その他にはおそらく
一種もなかろう。しこうしてこれらは
解剖学上から見れば、
現在生存する動物中、
脳のもっとも大きく
発達しているもの、また
地質学上から見れば、
諸動物中
最後に地球上に
現われたもの、
習性学上から見れば、他の動物に
比して子を
産む数のもっとも少ないものである。
獣類も
鳥類もともに
本能によって生まれながらなし
得ることよりは、練習によって
完成しなければならぬ仕事のほうがはるかに多いゆえ、教育の多少は直ちにその
種族の
存亡に
影響し、したがって教育に力を入れる
種類が、代々
競争に打ち勝ってついに今日のありさままでに
達したのであろう。これらの動物が、
如何にその子を教育するかは次の
節で
述べるが、いずれにしても
単細胞時代、
嚢状時代、もしくは水中を泳いでいた魚形時代の、昔の
先祖のころからすでに子を教育したわけではなく、おそらく
初めは
無数の子を
産み放した時代があり、次には子の数が
漸々減じて親がこれを
保護した時代があり、
次第に進んでこれを
養うようになり、
最後にこれを教えるようになったものと思われる。
動物の親子の
関係に
種々程度の
異なったもののあるを見、かつ一歩一歩その
関係の
親密になりゆく
状態を考えると、教育の
目的は
生殖作用の
補助として、
種族の
維持を
確かならしめるにあることは
極めて明らかである。教育の書物には何と書いてあろうが、生物学上から見れば、教育は
種族の
維持継続を
目的とする
生殖作用の一部であるゆえ、その
目的も全く
生殖作用の
目的と
一致して、やはり
種族の
維持にあることは
疑いない。これだけはすべての動物を
比較しての
結論であるゆえ、いずれの動物にもあてはまることで、その中の
一例なる人間にももとよりそのままにあてはまることと思う。ただし人間の教育については、さらに後の
節で
述べるから、ここには
省いておく。
前にも
述べたとおり、
鳥類の
卵から
孵って出る
雛は、
種類の
異なるにしたごうて、それぞれ発育の
程度が
違うゆえ、これを
養い教育する親の
骨折りにも
種々難易の
相違がある。がいして言えば、
雉子、
鶏などのごとき平生あまり
飛ばぬ鳥は
比較的大きな
卵を
産み、それより出る
雛は直ちに走り
得るくらいまでに発育している。これに反して、
燕や
鳩のような
巧みに
飛ぶ鳥は小さな
卵を
産み、それより出る
雛はすこぶる小さくて弱いゆえ、
特に親に
保護せられ
養われねば一日も生きてはいられぬ。また
雛がやや
成長してからも、地上を走る鳥ならば、ただ親の
呼声を
覚えしめ、地上から小さな物を速かに
啄むことを練習せしめなどすれば、それでよろしいが、つねに
飛ぶ鳥では
雛を教えて、
飛翔の
術を練習せしめねばならず、なお
飛びながら
餌を取る
法や、
敵からのがれる
法を
会得せしめねばならず、これにはなかなか
容易ならぬ
努力を
要する。
卵から
孵ったばかりの
鶏の
雛は、食物が地上にたくさん落ちてあっても、これを
啄むことを知らずにいることがある。しかるにもし
鉛筆かペン
軸で地面をたたいて音を立てると、直ちに
啄み始める。これは
一種の
反射作用であって、
雛に生まれながらこの
性質が
備わってあるために、親鳥が地面をたたくと、
雛がその音を聞いて直ちに物を
啄む練習を始めるのである。しこうして、はじめの間は
砂粒でも何でも
啄んで口に入れ、食えぬものは
再びこれを
吐き出すが、後にはだんだん
識別の力が進んで、食えるものだけを
選んで
啄むようになる。また
牝鶏が
雛を集め、
米粒などをわざわざ高くから地面に落として、そのはね
散るのを拾わせているところをしばしば見るが、これは
迅速にかつ
精確に小さな物を
啄むことを練習させているのであって、
雛にとってはすこぶる
有益な教育である。
鳥類の多数は
飛翔によって生活しているが、
飛翔はすべての運動中もっとも
困難なものゆえ、
巧みになるまでには大いに練習を
要する。
巣の内で育てられた
雛がやや大きくなると、親鳥はこれに
飛ぶことを練習させるが、
最初は
雛はあぶながって、
容易に
巣からはなれようとはせぬ。これを
巣から出して
飛ばせるためには、
或る
種類では親鳥が
雛のもっとも
好む
餌をくわえて、まず
巣より出で、あたかも人間が歩き始めの
幼児に「
甘酒進上」と言うて、歩行の練習を
奨励するごとくに、
餌を見せて
雛を
誘い出す、すなわち
興味をもって
導こうとする。また他の
種類では、いわゆる
硬教育の
流儀で、親鳥が
雛を
巣から
無理に
押し出して、止むを
得ず
翼を用いさせる。むろん
初めは
極めて短
距離のところを
飛ばせ、
次第に
距離を
増してしまいに自由
自在に
飛べるようになれば、全く親の手からはなすのである。
 鷲の親と子
鷲の親と子
南アメリカの「コンドル
鷲」のごとき大鳥になると、
雛が
飛翔の練習を
卒業して
独立の生活に
移るまでには
約三年を
要する。
餌を
巧みに
捕えるにもよほどの練習を
要する。
雀などでも
雛が
飛び
得るようになった後も、なおしばらくは親がつねに
連れ歩いて
餌を食わせているが、この間に
雛は親に見習うて、
次第に自分で
餌を拾い
得るようになり、もはや親の
補助なくとも十分に生活ができるようになれば、その時親とはなれてしまう。
鷲、
鷹のごときやや大きな生きた
餌を
捕えて食う
猛禽類では、教育がさらに
順序正しく行なわれ、まず
初めには両親が
雛を
猟に
連れてゆくが、ただ見学させるだけで、
実際餌を
捕える仕事には
加わらしめず、つぎには親が
餌を
傷つけ弱らせおいて
雛にこれを
捕え
殺させ、次には親と
雛と
協力して
猟をなし、
雛の
腕前がやや
熟達してくると、ついには
雛のみで
餌を
捕えさせ、親はただこれを
監督し、万一
餌が
逃げ去りそうな場合にこれを
防ぐだけを
務める。すなわち「
易より入って
難に進む」という
教授法の
原則が、
巧みに実行せられているのである。
水鳥が
雛に
游泳の練習をさせたり、魚を
捕える練習をさせたりする
方法も、
以上とほぼ同様で、
初めはただ
簡単な
游泳の練習のみをさせ、
餌は親が
直接に食わせてやり、次には親がつついて少しく弱らせた魚を、
雛より
一尺(注:30cm)ぐらいのところに放してこれを
捕えさせ、これができれば、次は
二尺(注:60cm)ぐらいのところ、次には
三尺(注:90cm)ぐらいのところというように、
順々に
距離を
増して、
速かに泳ぐことと
巧みに
捕えることとを
兼ねて練習せしめる。かくして
雛の
技術が進めば親は少しく助けながら、
自然のままの
勢いのよい魚を
捕えしめ、これが十分にできるようになればやがて
卒業する。
家鴨だけは長らく人に
飼われた
結果として、体は
肥り
翼は短くなり
卵は大きく、これから出た
雛は直ちに水面を
游ぎ
得るほどに発育しているゆえ、少しも教育らしいことをせぬが、これはもとより
例外であって、野生の水鳥はたいていみな
雛を教える。
雛がいまだ泳げぬ間は、これを足の間にはさんで
保護したり、あたかも人間が子を負うごとくに自分の
背にのせて泳ぐ
種類などもあるが、いずれにしても、親が手放す前には
必ず
独力で生活のできる
程度までに、泳ぐことと魚を
捕えることとの練習が進んでいる。
以上は食うための教育であるが、
鳥類にはなお
結婚して子を
遺し
得るための教育も行なわれる。すなわち歌や
踊もけっして
雛が生まれながらに
巧みにできるものではなく、聞いてはまねし見てはまねして、一歩一歩練習
上達して、ついに他と
競争し
得る
程度までに
達するのである。もっとも歌の大体の形だけは
遺伝で
伝わり、他の歌うのを聞かずとも、
本能によって
各種類に
固有な歌を
謡い始めるが、それだけでは
極めて
拙であってとうてい他と
競争することはできぬ。
鶯などもよく鳴かせるためには歌の
巧みな
鶯の
側へ持って行って、向うの歌を聞かせ習わせる
必要のあることは、
鶯を
飼う人のだれも知っていることであるが、かくのごとく聞けば
覚えてだんだん上手になるのは、がんらい教育せられ
得べき
素質を
備えているからであって、人に
飼われず、野生しているときにもむろんこの点に
変わりはなく、
雛のときに
拙く鳴き始め、
老成者の
熟練した歌をまねて
次第に
巧みになる。
薮の中ばかりにいてはとうてい
座敷の
鶯のごとくに、人間の注文に
応じたような歌い方はせぬであろうが、
鶯仲間での
競争に
加わり
得べき
程度までに
上達するのは、やはり教育の
結果である。
知力を
標準として
論ずると、
獣類の中には
非常に
程度の
異なったものがあって、
或るものははるかに
鳥類に
優っているが他のものはとうてい
鳥類におよばぬ。したがって教育の行なわれる
程度にもいちじるしい
相違があり、「かものはし」やカンガルーなどが、
如何ほどまで子を教育するかはすこぶる
疑わしいが、食肉
類、
猿類のごとき高等の
獣類になると、子の教育に力をそそぐことはけっして
鳥類に
劣ってはいない。
獣類の
普通の運動
法なる歩行は、
鳥類の
飛翔にくらべるとはるかに
容易で、親が
特に世話を
焼かずとも、子の発育の進むにしたごうて
自然にできるようになるから、わざわざ教育する
必要のある
事項が鳥よりは一つ少ないことになる。その代わり
或る
獣類では
大脳の
発達が
非常に進んでいるために、いわゆる
知的方面の練習を
要することは
鳥類よりはいっそう多くなる
傾きが見える。 子持ちの
牝猫が
鼠を
捕えた場合に、
如何なることをするかを注意して見るに、けっして直ちに
殺して食うてしまうごときことをせず、まず
鼠を軽く
傷つけてこれを放し、その
逃げてゆくところを
小猫に
捕えさせる。これはすなわち
鼠を
捕える下
稽古で、たびたびかようなことをしている間に
鼠を見れば
必ずこれを追いかけずにはいられぬようになり、また追いかければたいがいこれを
捕え
得るまでに
熟達する。
飼猫でもつねにかような
方法で子を教えるが、野生の
食肉獣になると、さらにこれよりも
念を入れてわが子に
渡世の
途を
仕込む。
狐などは
幼児が生まれて二十日
過ぎになると、すでに
鳥類を
殺す
稽古を始めさせ、少しく大きくなると、夜出歩くときにいっしょに
連れまわり、
餌を取ることを
手伝わせ、
次第次第に自分の
餌だけは
独力で取れるように
仕込み、しかる後に手放してやる。
獅子などはかくして教育し終わるのに
約一年半もかかる。その間に
初めは親は子に見物させ、次に子を助けて実習させ、後にはただ
監督するだけで全く子にまかせ、少しずつ
骨の
折れる仕事に
慣れさす具合いは、前に
鳥類について
述べたところとほぼ同様である。
虎の食い
残した牛の
骨などを見るに急所には
親虎の大きな
牙の
跡があり、間のところには
子虎の小さい
牙の
跡がたくさんにあるのは、
虎も
猫と同じく子に肉を引き
裂いて食う
稽古をさせるからであろう。
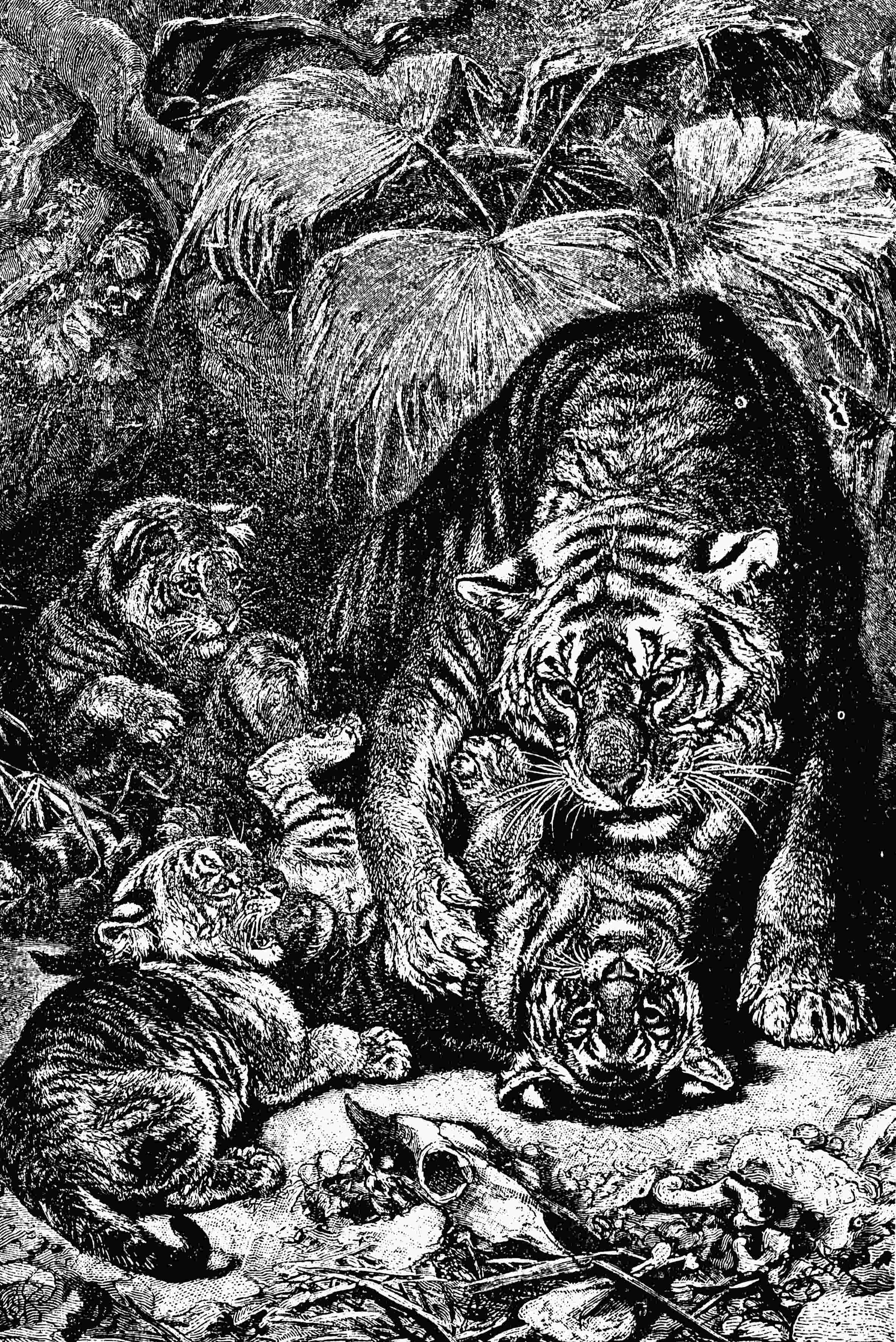
虎の教育
虎は猫と同じく幼児を長く養いこれに餌を捕え殺す法を教え,子が十分に自活し得るまでに進みたるころ初めてこれを放ち去らしむ。
猿の
類も多くは子を教育する。昔から
猿の人まねというて
猿ほど何でもよくまねをするものはないが、
児猿にこの
性質があれば教育は
自然にできる。動物園などで見ても、
母猿はほとんど世話を
焼きすぎると思われるほどに
絶えず
熱心に
児猿に注意し、
危険をおそれて
瞬時も
側より
離さず、もし
児猿が
客気にまかせて遠方へでも走りゆけば、直ちに追いついて
捕え帰り
打擲してこらしめる。
 猿作物を盗む
猿作物を盗む
かく
絶えず親のそばにおかれるゆえ
児猿は何でも親のすることを見てこれをまねする。親が
果物の皮をむいて食わせてくれれば、自分で食うときにも
必ず皮をむき、親が箱のふたをあけて
人参を
盗めば、子も同じく箱のふたをあけて
人参を
盗む。また
団体をつくって生活する
種類ならば
種々の
相図をおぼえ、一々これを聞き分けて
同僚の仕事と
衝突せぬように注意する。かくして
猿の生活に
必要な仕事をすべてまねしおぼえ、
熟練してついに
一匹前の
猿となるがこれがみな教育の
結果である。
獣類の
幼児は、犬や
猫の
例でも知れるとおり、すこぶる活発に
戯れまわるものであるが、
遊戯も教育の一部である。
獣類の
児は
如何なることをして遊ぶかというにむろん
種類によって
違い、
猿ならば木に登って遊び、「おっとせい」ならば水に泳いで遊ぶが、広く集めて
分類して見ると、主として追うこと、
逃げること、
捕えること、
防ぐことなどであって、いずれも
成長の後には
真剣に行なわれねばならぬことのみである。なかには
戯れに
交尾のまねまでするが、これも
成長の後には
真剣に行なわねばならぬ。されば
遊戯なるものは
単に元気のあり
余るままに身体を活動させて、時間を
浪費しているのではなく、
成長の後に
必要な
働きをあらかじめ練習しているのである。しこうして父親がこれに
加わることはけっしてなく、母親はときどき
仲間にはいってともに
戯れることもあれば、また
側に
静止して横着な
'保姆のごとくに横目で
監督していることもある。とにかく親が
保護しながら、かかる
有益な予習をさせるのであるから、これは
立派に教育と名づくべきものであろう。
以上述べたとおり、
鳥類にも
獣類にも子を教育するものはいくらもあり、その
方法のごときも一定の
規則にしたごうているが、人間の教育にくらべてはもとより
簡単極まるものである。しからば人間においてのみ、教育が他に
飛び
離れて
複雑になったのは
何故なるかと
尋ねると、その
原因は言うまでもなく言語と文字との
発達にある。音によって
互いに
通信することは動物界にけっして
珍しくはないが、人間のごとくに音を組み合わせて一々
特殊の意味を
現わすような言葉を用いるものは他にはないゆえ、「人は言語を有する動物なり」と、言い放ってもあえて
誤りではなかろう。しかも言語のみがあっていまだ文字がなかったならば、子を教育するにあたっても、ただ
先祖からの言い
伝えを親が
記憶しておいて子に
伝えるということが、他の動物に
異なるだけで、それ
以外に多くの
相違はない。
現に文字を知らぬ
野蛮人が、子を教育する
程度は
猫や
虎にくらべていちじるしくは
違わぬ。しかるにいったん文字なるものが発明せられると、その後は子の受くべき教育の
分量はただ
増す一方で、ほとんどその止まるところを知らず、ついには
一生涯の大部分をもそのために
費さざるを
得ぬようになって、人間の教育と他の動物の教育との間に、はなはだしい
懸隔を生ずるのである。
そもそも文字は
脳髄の
記憶力を助けるための
補助器官である。はじめは
縄に
結び玉をつくり、
捧に切れ目をつけたりしただけであったのが、だんだん進歩して今日見るごとき
便利なものまでになったが、かく
便利な文字ができた
以上は、これを用いて
無限に物を
記憶することができる。
脳髄ばかりで
記憶していたころは、あたかも
猿が食物を'
頬の
嚢に
貯えるごとくで、身体の
一隅にため
込むだけであるゆえ、その
量にももとより
狭い
際限があったが、文字を用いて、
脳髄以外に
記憶し
得るようになると、ちょうど
畑鼠が米や麦の
穂を自分の
巣の内に
貯蔵すると同じ
理屈で、
孔さえ広く
掘ればいくらでも
限りなくためることができる。かような
次第で、人間は文字の発明
以来、日々の
経験によって
獲た新たな
知識を文字に
収めて
貯え来たったが、人間の
生存競争においては
知識がもっとも
有効な
武器であるゆえ、
敵に負けぬためには子を
戦場に立たせる前に、これに十分の
知識を
授けておかねばならぬ。
敵にくらべて知育がいちじるしく
劣っていては、その
民族は平時にも
戦時にも
競争に勝つ
見込みが立たぬゆえ、つねづね
子弟に十分な
知識を
与えておかぬと親は安心して死なれぬ。されば、今日の文明国における教育の
状態を見ると、
伝来の
迷信のためにずいぶん
無駄なことをしている部分もあるが、大体は
敵に負けぬだけの
知識を
授けることを
務めている。しこうしてその
知識は文字によって
脳髄以外に
貯蔵せられ、
蓄積せられ
得べきものである。人間の教育が他の動物の教育と
異なるところは、主としてかかる
種類の
知識を子弟に
授ける点に
存する。
世間には
単に
理論の上から教育を三分して、知育、
徳育、体育とし、いずれにも
偏せぬように平等に力を
尽くすがよろしいと
説く人もあるが、
以上述べたところから考えると、この
三種の教育はけっして対等の
性質のものではなく、かつ
如何に平等に
取扱うても、その
効果はすこぶる
不平等なるをまぬがれぬであろう。人間の教育について
詳しく
述べることは、本書の
趣意でもなく、また門外漢なる
著者のよくするところでもないゆえ、他はすべて
略して、ここには
以上の三育の
効果の
相異ならざるべからざる理由を一言するだけにとどめる。
知育は
特に人間にとって大切な教育であって、かつその
効果もすこぶるいちじるしく
現われる。学校の
課程を見ても、その大部分は知育に
属するもので、
生徒の
知識が
如何に一年ごとに進みゆくかは
誰の目にも明らかに知れる。
試みに学校を
踏んできた
子供と、学校へ行ったことのない
子供とをくらべたら、その
知識の
相違は
非常なもので、今日の社会では「いろは」も読めぬような者はほとんど用いる
途がない。すなわち知育は行なえば行なうただけ
効果のあがるもので、
異民族が
互いに
競争する場合には、相手に負けぬためにできるだけ
程度を高めることが
必要であり、また高めれば
必ずそれだけの
効能がある。されば今後はそれぞれ
民族は
競うて知育の
程度を高めるであろうが、
程度を高めればそれだけ教育の
年限が長くなるをまぬがれぬ。新たな
知識は年とともに
積もるばかりであるが、古い
知識がそのため
不用になるわけでもないゆえ、
授くべき
教材は年々多くならざるを
得ない。エッキス光線、
無線電信、
飛行機、
潜航艇のことを
追加して教えるからというて、その代わりに物理学教科書の
最初の
数頁を
破り
捨てるわけにはいかぬから、いずれの学科においても、やはり「いろは」から始めて
最新の発見まで
授けることとなり、これを
満足に教えるには
次第次第に教育の年数を
増さねばならぬ。
如何に
教授法が
巧みになっても、
教材が
無限に
殖えては、時間を
延長するよりほかに
途はない。しかし教育の
年限をどこまでも
延ばすことは、むろんできぬことであって、人間わずか五十年のうち、
二十歳で
丁年に
達しながら四十
歳まで学校へ通うようでは、とうてい教育
費と
生産力とのつりあいがとれぬ。それゆえ、もし
各民族がどこまでも
競うて知育を高めたならば、今日
大砲や
軍艦の大きさ、
飛行機や
潜航艇の数を
競争して
互いに
困っているごとくに、知育の
競争に行き
詰まって、お
互いに
閉口する
時節が
早晩くるであろう。
徳育は知育と
違うて、
骨を
折る
割合に
効果があがるか
否かすこぶる
疑わしい。
団体生活を
営む動物が
互いに
競争するにあたってもっとも大切なことは
協力一致、
義勇奉公の
精神であるが、この
精神は
如何にして
養成せられるかというに、数多の小
団体が
絶えず
激烈に
競争して勝った
団体のみが生き
残り、
敗けた
団体が
亡び
失せるによるのほかはない。かくすれば、一代ごとに
必ず少しずつ、
義勇奉公というごとき
団体的競争に勝つべき
性質が進歩して、ついに今日の
蜜蜂や
蟻に見るごとき
程度までに
発達する。しかるに近世の人間は、
民族間に
絶えず
紛議があるにかかわらず、
敗けた
団体が全部
亡びるというごときことはけっしてなく、生まれながら
義勇奉公の
念のやや強い者もやや弱い者もひとしく
生存の
機会を
得るゆえ、この
精神の進歩すべき
望みがなくなった。その上、
団体内における
個人間の
競争では、
義勇奉公の
念の
薄い者のほうが勝つような
事情も生じて、この
精神はむしろ
漸々滅びゆくもののごとくに見える。教育者は
往々、教育の力によって
如何なる
性質の人間をも、注文に
応じて
随意につくり
得るかのごとくに言うが、
実際はけっして
人形師が人形をつくるようにはゆかず、
各個人の
性質は
先祖および父母からの
遺伝によって、生まれたときすでに大体は定まり、教育者はわずかばかりこれを
変更し
得るにすぎぬ。教育の力によって、手の指を一本
殖やすことも
減らすこともできぬと同じく、
脳髄の
細胞をならべ直して、
義勇奉公の
念を
自然に強くすることはとうていできぬであろう。かような
次第であるゆえ、
徳育は今後
如何に力を
尽くしても、けっして知育におけるごとき
目覚しい
効果のあがらぬのみならず、知育が進めば悪事もますます
巧みにするようになるから、これに
対抗するだけでもなかなか
容易ではなかろうと思われる。
しからば体育は
如何というに、これまた十分に
効果のあがらぬ
事情がある。一体ならば
子供を学校などへやらずに、自由
自在に「
鬼ごと」、「木登り」、「水泳ぎ」、「角力取り」などさせておくのが、体育のためにはもっともよいのであるが、
種属生存の
必要上、知育を
盛んにせねばならず、そのためには、動きたがる
子供らをしいて
静かにすわらせ、勉強させるのであるから、体育のほうから言うと知育はむろん
有害である。しかるに知育はこれを
減ずることができぬのみならず、今後は他
民族との
競争上ますます
増進する
必要があり、なるべく短い時間になるべく多くの
知識を
授けようとすれば、
勢い体育のほうはそれだけ
迫害せられるをまぬがれぬ。小学校の一年から六年まで、中学校の一年から五年までと級が進むにしたがって、一年
増しに毎日すわらせられうつ向かせられる時間が長くなって、身体の
自然の発育は
次第に
妨げられるが、これも
種族の
維持継続の上に
必要であるとすれば、止むを
得ぬこととして
忍ぶのほかはない。なおその他にも今日の人間の身体を少しずつ弱くする
原因がたくさんにある。されば体育は今後
如何に力を
尽くしても、知育を
暫時廃止せぬ
以上は、ただ知育のために受ける身体上の
損害をいくぶんか取り消し
得るのが
関の山で、とうてい進んで身体を昔の
野蛮時代
以上に
健康にすることはできぬであろう。
以上述べ来たったとおり、人間は
種族維持のためにもっとも有力の
武器なる
知識を
競うて進めねばならず、その
結果として、他の動物にはとうていその
比を見ぬほどの長年月を教育に
費すが、かくしては
各個体が
団体競争にあずかる一員として
完成する時期が
非常におくれる。
無数の子を
産むものは、そのまま
捨ておいて少しも世話をせず、
一生懸命に子の世話をするようなものは子の
産み方がすこぶる少ないことは、全動物界に通ずる
規則であるが、人間のごとくに子の教育に手間のかかる動物では
勢い子の数はもっとも少なからざるを
得ない。
現に人間の子を
産む
割合は女一人につき
平均四人か四人半により当たらぬが、このくらい少なく子を
産む
種類はけっして他にはない。しこうしてこの少数の子を一人一人
戦闘員として役に立つまでに育て上げるために、親もしくは親の代理者が
費やす時間と
労力とは、他の動物が子を教育する手間にくらべて
何層倍にあたるかわからぬほどである。
さて
恋愛に始まり教育に終わる
生殖事業の
目的は、言うまでもなく
自己の
種族の
維持継続にあるが、この点から見ると、
個体の命の
価値は
生殖法の
異なるにしたごうて、
非常に
相違があるように思われる。
各個体の命は、それを有する
個体自身から見ればむろん何よりも大切なもので、自身
一個を
標準として考えれば、命を
失うことは、全
宇宙の
滅亡したのと同じことにあたるが、
種族の生命を
標準として考えると、
個体の命なるものは全くその意味が
変わってくる。まず
無数の子を
産み放して、少しも世話をせぬような
種類について
論ずるに、おおよそ
種族維持のためには一対の親から
産まれた子の中から、
平均二匹だけが生き
残ればよろしく、また
実際そのくらいより生き
残らぬから、生まれた子が
五十匹や
百匹踏み
潰されても食い
殺されても、
種族としては少しも
痛痒を感ぜぬ。しかも後から後からと
盛んに子を
産むゆえ、かような動物の命はあたかも
掘抜き
井戸の水のようなもので、
絶えず
盛んにあふれて
無駄になっている。この場合には
個体の命の
価はほとんど
零にひとしい。かような虫を
殺すことを
躊躇するのは、あたかも
掘抜き
井戸の水を
柄杓で
酌むことを
遠慮しているようなものである。 これに反して、やや少数の子を
産む
種類では、それがさらに
減じては親の
跡を
継ぐだけの子が生き
残り
得るや
否やすこぶる
疑わしくなるゆえ、
種族維持の上から言うと、
一匹でもはなはだ大切である。それゆえ
実際かような動物では親が何らかの
方法で子を
保護し、また進んでは
養育もする。しこうして
夫婦で
五十匹の子を
産む
種類ならば、そのうち四十八
匹死んでもよろしいが、
十匹より
産まぬ
種類では、そのうち
八匹以上死なれては
後継者がなくなるゆえ、
種族維持の上からは前者に
比して後者のほうが数倍も
個体の命が
尊い。しこうして
尊いだけに
実際かような
種類では、
必ず親が
一生懸命になって長くこれを
保護し
養育している。おおよそ物の
価は何でも
需要が多くて
供給の少ないものが高く、また
製産に
費用の多くかかったものが高いのが
当然で、命の
価もこの
規則にしたごうて高いのと安いのとがあり、
概して言うと
個体の命の
尊さは、
個体を
完成するまでに
要する
保護教育の
量に
比例する。他の動物とは
飛び
離れて多くの教育を
要する人間
仲間で、
個人の命が他の動物とは
比較にならぬ高い
程度に
尊ばれるのは、やはりこの
理屈によることであろう。
無数に子を
産む動物では、全局を通算して
種族維持の
見込みがつけばよろしいのであって、
各個体の一々の生死のごときはほとんど問題にならぬが、人間などはその正反対で、
実際些細な事がらでも、事かりそめにも人命に
関すると切り出されると、止むを
得ずこれを重大
事件と見なさねばならぬこともある。かくのごとく人間はつねに命を
非常に
尊いものとして取り
扱う
癖がついているゆえ、これより
類推して、他の生物の命もすべて
尊いもののごとくに思い、虫
一匹の命を助けることをも
非常に
善い事のごとくに
誉め立てるが、
実際を調べて見ると、ここに
述べたとおり、
種類によっては命の
価のほとんど
零に近いものがいくらもある。
自然界には命の
浪費せられることがずいぶん
盛んで、命を
尊いものと考える人から見れば、
如何にももったいなくてたまらぬように感ぜられることがつねに行なわれている。
 水が涸れて死ぬ魚
大陸
水が涸れて死ぬ魚
大陸の
河が
旱魃のために
涸れる時には、
最後まで水のあるところへ魚がことごとく集まり来たり、そこまでが
涸れれば何万
何億という魚がみな一時に死んでしまう。少しく風が強く
吹けば、海岸一面に
種々の動物が
数限りもなく打ち上げられているのを見るが、
沿岸何里も
続くところではどのくらいの命が
捨てられるか
想像もできぬ。しかしこれらの
損失はときどきあるべきこととして、
各種族維持の予算には前もって組み
込んであり、
生殖によって直ちに
埋め合わす予定になっているゆえ、
初めから
別に
惜しまれるべき命ではない。
無益の
殺生はけっして
誉むべきことではないが、
印度の
宗教のごとくに生物の命をいっさい取らぬことを
善の一部と見なして、
蚊でも
蚤でも
殺すことを
躊躇するのは、生物の命をすべて
尊きもののごとくに
誤解した
結果で、実は何にもならぬ
遠慮である。
「生あるものは死あり」と昔から
承知していながら、やはり死にたくないのが
人情と見えて、少しでも物の
理屈を考える
余裕ができると、まず第一に死のことから注意し始め、
想像を
逞しうして、
不老不死の薬とか、
無限寿の
仙人とかの話をつくり出す。それより知力が進めば進むだけ、死に
関する
想像も
複雑精巧になり、
想像と
実際との
区別がわからぬためにさまざまの
迷信が生じて、今日にいたっても、死については実に
種々雑多の
説が行なわれている。生を
論ずるにあたっても、
材料を人間のみに取っては一部に
偏するために、とうてい公平な
結論に
達すべき
望みがないのと同じく、死を研究するにも、まず広く全生物界を
見渡して、
種々の
異なった死にようを
比較する
必要がある。しこうして広く
各種の動物について、その死にようを調べて見ると、あるいは外面だけが死んで内部が生き
残るもの、前半身が死んで後半身が生き
残るもの、死んでいるか生きているかわからぬもの、死んでも
死骸の
残らぬものなど、実に意外な死に方をするものがたくさんあって、人間の死のごときはただその中のもっとも
平凡なる
一例にすぎぬことが明らかに知れる。
そもそも死とは何ぞやとたずねると、これに対して
正確に答えることはとうていできぬ。ちょっと考えると、死とは生の反対で死ぬとは生の
止むことであるから、
至極明瞭でその間に何の
疑いも起こりそうにないが、すでに本書の
初めに短く
述べておいたとおり、生なるものの
定義が
容易に定められぬ。それゆえ生を知らず
奚んぞ死を知らんやというようなわけで、死についてもすべての場合にあてはまり、かつ一の
除外例をも
許さぬ
正確な
定義はなかなか見いだされぬ。しかしながら
正確な
定義の定められぬことは、ただ生と死とに
限るわけではなく、
自然界の事物にはむしろこれが
通則である。
例えば
獣類は
胎生するといえば、「かものはし」のごとき
卵生する
例外があり、
獣類の体は毛にて
蔽はるといえば、
象や
鯨のごとき毛のない
例外がある。しかもこれらを
含むような
定義をつくれば、
獣類は
胎生もしくは
卵生、体は毛にて
被われまたは
被われずと言わねばならず、かくては
定義として何の役にも立たぬ。それよりは
獣類は
胎生で体は毛で
被われるとしておいて、「かものはし」や
鯨は
例外としてやはりその中へ入れるほうがはるかに
便利である。かような考えから本書においては生の
定義などにはかまわずに、ただ生物は食うて
産んで死ぬものというだけにとどめておいたが、死についてもこれと同様に、まず動物には
如何なる死にようをするものがあるかを
述べて、死とはおおよそ
如何なるものかを
概論するにとどめる。
まず人間などについて見ても、死と生との
区別の
判然せぬ場合があり、死んだと思うて
棺に入れ、今から
葬式を始めようという時にその人が
蘇生したので、みなみな大いに
驚いたというような記事を新聞紙上に見ることが
往々ある。人間は死ねば
吸呼が止まり
脈が
絶え、温かかった身体が
冷たくなるが、これだけを見て直ちに死んだものときめてしまうと右のような
間違いも起こる。
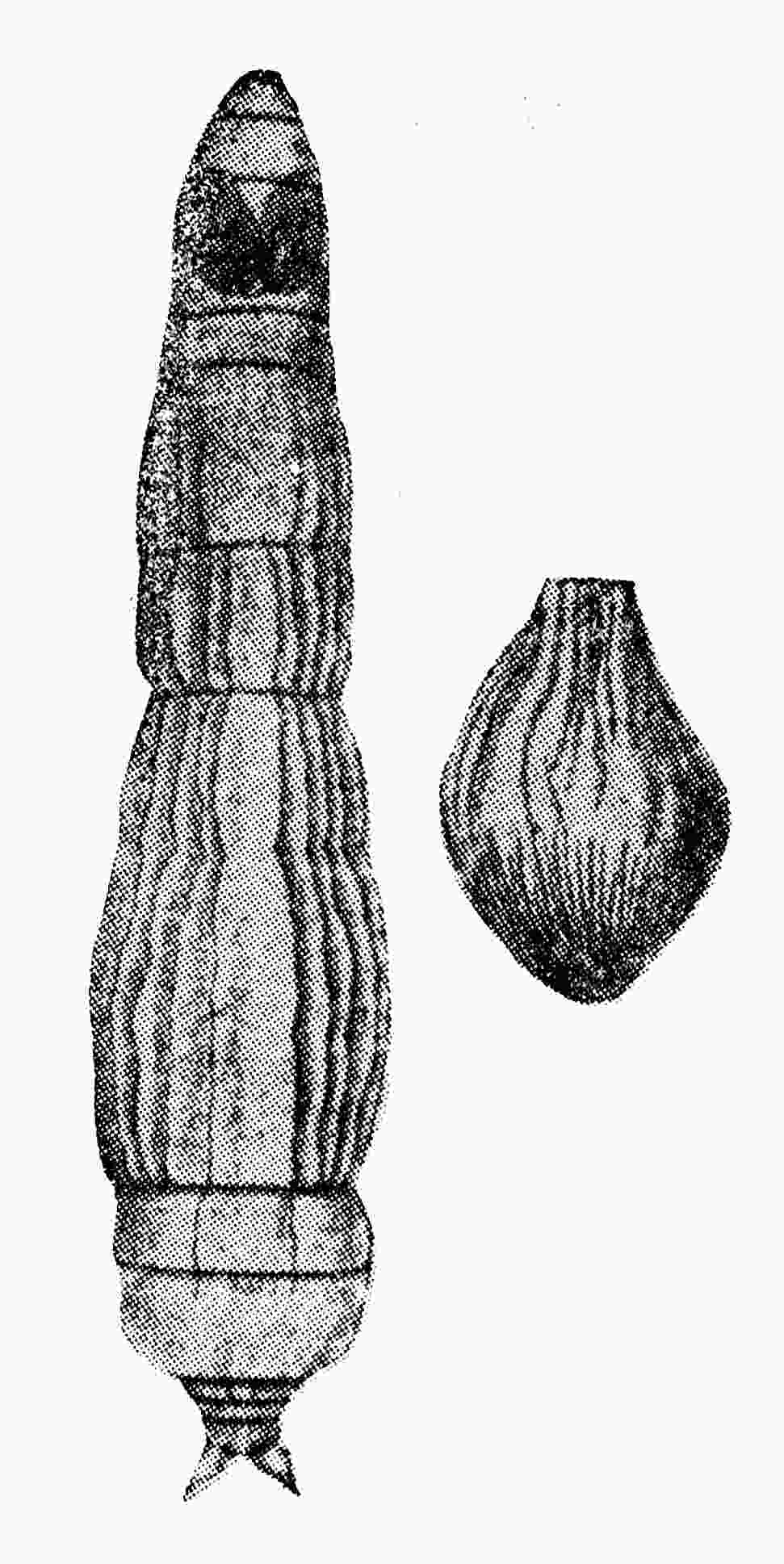
わむし
(左)生きて動くもの (右)乾きたるもの
淡水に
産する「わむし」や「
熊虫」などは、
干せば体が
収縮して全く
乾物となり、少しも生きているようすは見えず、そのまま何年も
貯蔵しておけるが、これに水を
加えるとたちまち水を
吸収してふくれ、もとの大きさにもどって平気で活発にはい出す。すなわち死んだように見えても
必ずしも真に死んだとはかぎらず、いつまでおいても生き返らぬことがたしかになって
初めて真に死んだと言えるのである。また全身としては
確かに死んでも、その
組織の生きていることはつねである。
例えば
頸を切られた
罪人はもはや生き返る気づかいはないゆえ、
確かに死んだに
違いないが、その
神経を
刺激すれば
盛んに
筋肉が
収縮する。
心臓のごときは
別に
刺激を
与えずとも、しばらくは生きているとおりに
搏動をつづける。
蛙などで
実験して見るに、取り出した
心臓の
血管の
根本をくくって
薄い
塩水の中に入れておくと、十日
以上も
絶えず
伸縮している。これに反して全身は
健全に生きていても、一部分ずつの
組織は
絶えず死んで
捨てられている。
血液中の赤血球や
粘膜の表面の
細胞のごときは、
特に
寿命が短くて
新陳代謝が始終行なわれている。かくのごとく、一部分ずつの
組織や
細胞が死んでも
通常これを死と名づけず、
組織や
細胞がなお生きていても、全体として
蘇生の
望みがなければこれを死と名づけるのであるから、世人の
通常死と
呼ぶのは
一般に生きた
個体としての
存在の止むことである。
獣類、
鳥類など人のつねに見なれている高等動物は人間と同じような死に方をするが、やや下等の動物にはさまざまに
変わった死にようのものがある。
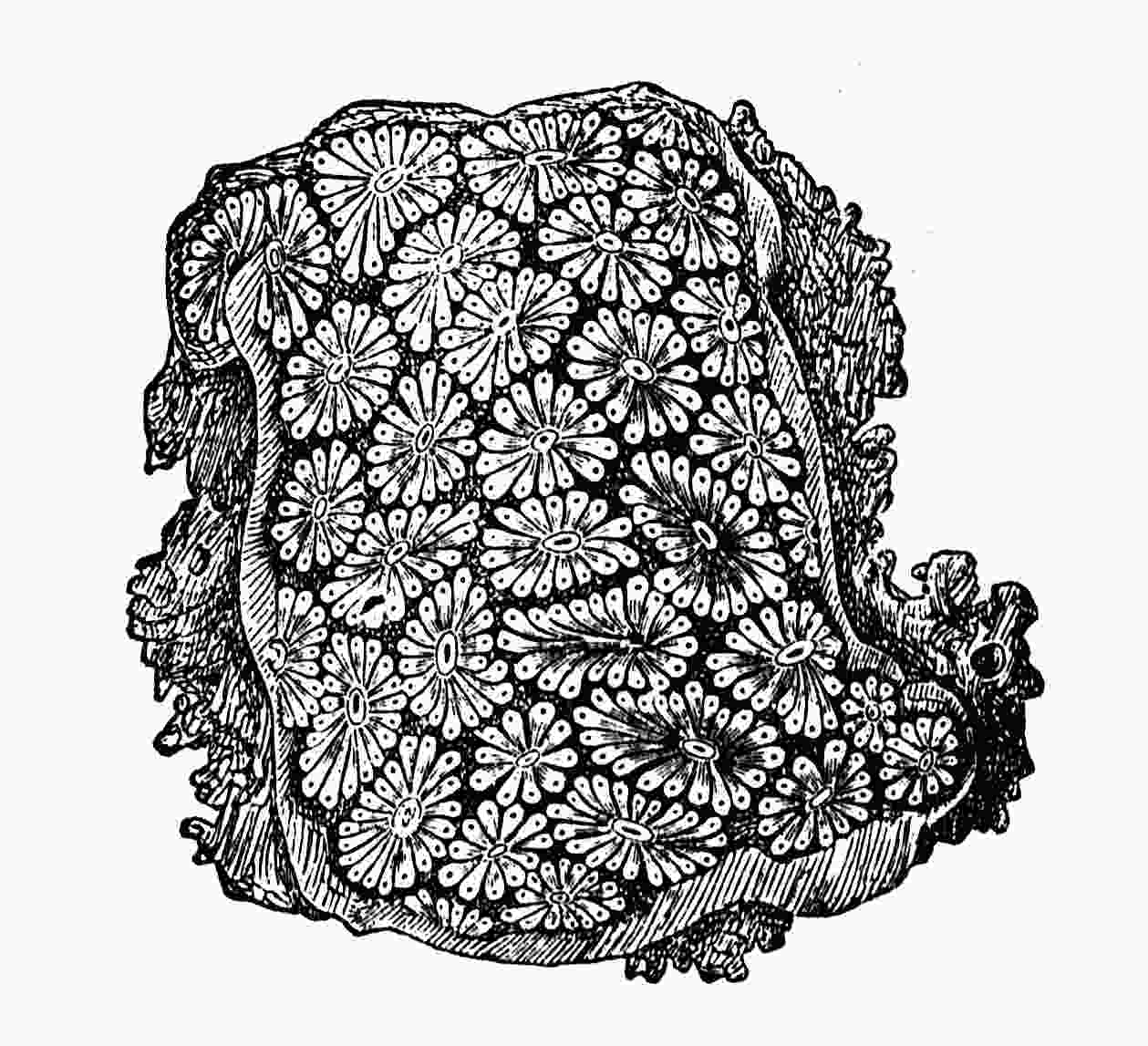 ほやの群体
例
ほやの群体
例えば「ほや」の
或る
種類ではときどき身体の上半だけが死んで
頽れ去り、下半はそのまま
残り、
芽生によって新たに上半身ができると、それが古い下半身と
連絡して
一匹の
完全な身体ができ上る。また
海産の「こけむし」
類では、
各個体が
老いて
勢いが弱くなるとついに死んで
組織が
変質し、茶色の丸い
脂肪の球となってしまうが、わずかに生き
残った
組織が
基となって後に新たな
個体が生ずる。しこうしてそのさい前の
脂肪の球は
芽の内に
包み
込まれ、
滋養分として
利用せられる具合いは、死んだ親の肉を
'缶詰にしておいて子がこれを食うて
成長するのに
比較することができよう。
群棲する「ほや」
類の中には、ときどき
群体内の
個体がみな死に
絶えて
一匹もなくなり、ただいずれの
個体にも
属せぬ
共同の部分だけ
残るものがあるが、しばらく
経るとこの部の表面から新たに
一揃いの
個体が生ずる。これなどは
各個体は毎回死ぬが、その
個体より
成る
群体は始終生きつづけている。また前に
述べた植物に
寄生する
小蝿や
蛙の
肺に
寄生する
蛔虫の
類では、子が生まれる前に母親の身体を内から食い
尽くすゆえ、母親は死んでも
'蝉の
抜殻よりもはるかに
薄い皮の
嚢が
残るだけで、真の
死骸というべきものは何もない。これに反して「うに」、「ひとで」などの発生中には、死なずして
死骸ができる。これはちょっと聞くと全く
不可能のことのようであるが、「うに」や「ひとで」の
類では
卵が発育しても直ちに親と同じ形になるのではなく、
最初しばらくは親と全く形の
異なった
幼虫となって海面を
浮游し、その
幼虫の身体の一小部分から「うに」や「ひとで」の形ができて、
残り全体はしなびて
捨てられるか
吸収せらるるかするゆえ、
個体としては
生存しっづけながら、大きな
死骸が一時そこに生ずることになる。
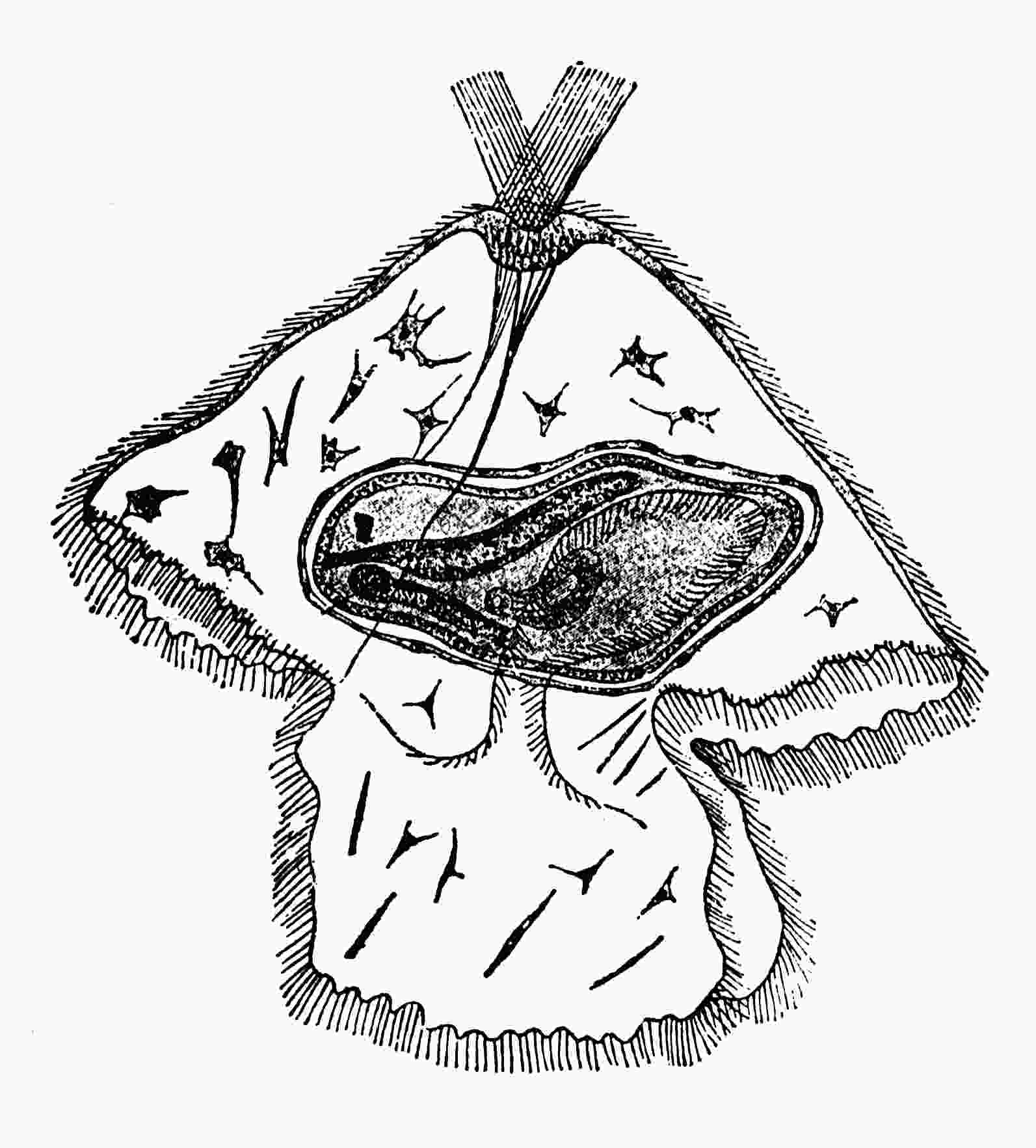 ひもむしの幼虫
浅
ひもむしの幼虫
浅い海の
底にすむ「ひもむし」という細長い
柔らかい虫の発生中にもこれと同様なことがある。すなわち海の表面に
浮いている
幼虫の体の一部に小さな
成虫の形ができ始まり、これが
幼虫の体からはなれて
成虫となるが、そのさい
幼虫の
残りの身体は
不用となって
捨てられる。「おたまじゃくし」が
蛙となる時には全身の形が
変わるが、「うに」、「ひとで」、「ひもむし」などの
変態する時には
幼虫の体の一小部分だけが
生存して
成虫となり、
残りは
死骸となるのであるゆえ、考えようによっては、
幼虫が
芽生によって
成虫を生ずると見なせぬこともなかろう。さればこれらの動物は
変態と世代
交番との中間に
位する
例ということができる。
死の
有無について
特に
議論のあるのは「アメーバ」、「ぞうりむし」などのごとき
単細胞虫類である。
甲なる
一匹が
分裂して
乙、
丙の
二匹になった場合に、
甲は死んだか死なぬかと言うて、今でも
議論をしているが、実はこれは
単に言葉の
争いにすぎぬ。
死骸が
残らねば、死んだと見なさぬ人は
甲は死なぬと言い、
個体としての
存在の止んだことを死と名づける人は
甲は死んだと言うが、いずれとしても事実は事実のままである。もしも死なぬものと見なせば、かかる
虫類は死ぬこともない代わりに生まれることもないと言わねばならず、またもし死ぬものと見なせば、これは死んでも
死骸を
残さぬ
一種特別の死にようである。がんらい生死という文字は、人間、
鳥獣などのごとき
雌雄生殖をする動物だけを
標準としてつくられたものゆえ、
無性生殖の場合によく当てはまらぬのは
当然のことで、「アメーバ」、「ぞうりむし」にかぎらず、「いそぎんちゃく」や「糸みみず」などが
分裂によって
繁殖する場合にも、子が生まれたとか親が死んだとかいう言葉は、
普通の意味ではとうてい用いることはできぬ。
非業の死という文字は新聞紙などでしばしば見かけるが、これは何か
不意の出来事のために命を取られることで、人間の社会ではむしろ数の少ない
例外のごとくに見なされている。すなわち人間は
慢性の病気にでもかかって死ぬのが
自然の死にようで、
強盗に
殺されるとか、汽車に
轢かれるとかいうのは、もしその事がなかったならば、なお
生存しつづけ
得たはずのところを
自然に反して
無理に命を
奪われたのであるゆえ、これを
非業と名づけるのであろう。もっとも
非業という中にも
種々の
程度があって、死にようが
激烈でない場合は、事実
非業であっても
通常これを
非業とは名づけぬ。
例えば何か事業に
失敗して
心痛のあまり病気となり、入院して死んだとすれば、これまた
非業の死と言うべきはずであるが、このくらいでは世人は
非業の死とは見なしてくれぬ。もしかような場合までを
非業のほうへかぞえこめば、人間の
非業の死の数はよほど
殖えるが、それでもまだけっして大多数とはならぬ。しかし他の動物では
如何と見ると、これはまるで
趣が
違う。
前に
幾度も
述べたとおり、多くの動物は
無数の
卵を
産み放すが、これより
孵った
児はほとんどことごとく
非業の死を
遂げる。
魚類は数十万の
卵を
産み、「うに」、「なまこ」、「ごかい」、
蛤などは数百万の
卵を
産むが、たいがいは発生の
途中に命を
失うて
成長し終わるまで
生存し
得るものは
極めて少数にすぎぬ。動物の
産む子は多くても、これを
常食とする
敵動物が待ちかまえているゆえ、多数はその
餌となってしまう。その他風雨のために
吹かれ流されて死ぬものもあり、
怒濤のために岩に打ちつけられ
浜へ打ち上げられて死ぬものもあり、
旱魃のために
干からびて死ぬものもあれば、
洪水のために
溺れて死ぬものもあろう。また
同僚との
競争に
敗けて
餌を
求め
得ずして
餓えて死ぬものや、
仲間同志の
共食いで食い
殺されるものもあろう。とにかく何らかの
方法で発生の
中途に命を
失うものが
非常に多数を
占め、
成長し終わるまで生き
残るのは
平均十万
匹中の
二匹、百万
匹中の
二匹にすぎぬ。すなわち十万
匹の中の九万九千九百九十八
匹、百万
匹の中の九十九万九千九百九十八
匹はことごとく
非業の死を
遂げるのである。
子を
産み放しにする動物では、かくのごとく
非業の死を
遂げるものの数が
極めて多いが、子を世話する
種類では
保護養育の
程度の進むとともに、
非業の死を
遂げる
子供の
割合が
次第に
減ずる。同じ
魚類でも
巣をつくって
卵を
保護する「とげうお」や、
雄の
腹の
嚢に
卵を入れる「たつのおとしご」では、
非業の死を
遂げるものの数はよほど少なくなり、
蛙の中でも
背に子を負う
種類、
背の
嚢に
卵を入れる
種類では、
非業の死を
遂げるものはさらに少ない。これらの動物はみな子を
産む数が少ないゆえ、もしも
普通の
魚類や「ごかい」、
蛤などにおけると同じ
割合に、多数の子が死んだならばたちまち
種族が
断絶するおそれがある。人間はもっとも少なく子を
産み、もっとも長くこれを
保護養育するものゆえ、
発達の
途中に命を
失うものの数は他の動物に
比するとはるかに少なく、かつそのうち
特に
悲惨な死にようをしたものでなければ
非業と名づけぬゆえ、それで
非業の死がまれな
例外のごとくに見えるのである。
動物に
非業の死の多いことは何を見ても直ちに知れる。魚市場や
肴屋、
料理屋の店にある
魚類はことごとく
非業の死を
遂げたもので、これらの
魚類の
胃を切り開いて見ると、また
非業の死を
遂げた小さな魚や虫や
貝類などが
充満している。しこうしてこの小さな魚や虫の
腹の中には、さらに小さな
幼虫や
卵などがいっぱいにあるが、これまた
非業の死を
遂げたものである。おおよそ肉食する動物がある
以上は、その
餌となる動物は日々
非業の死を
遂げるをまぬがれることはできぬ。また
田圃で
害虫を
駆除すれば数千万の虫が
非業の死を
遂げ、
養蚕を終われば何百万の
蛹が
非業の死を
遂げる。その他
自然界における
非業の死の
例をかぞえあげたら
際限はない。されば、
非業の死なるものは、人間社会においてこそややまれな場合であるごとき感じがあるが、広く
自然界を
見渡せば
非業の死はほとんどつねの
規則であって、そのうち
極めて少数のものがなかば
僥倖によって
成長を終わり子を
残し
得るのである。
非業の死をまぬがれたものはいつまで生きるかというに、その
期限は一
種類ごとにそれぞれほぼ定まっている。これを
寿命と名づける。すなわち
各種生物の生まれてから食うて
産んで死ぬまでの年数を指すのであるが、身体の大きなものは
成長に手間がかかるゆえ、身体の小さなものよりも
自然寿命が長い。
例えば
象や
鯨は
鼠、「モルモット」にくらべるとはるかに
長命である。しかし
寿命は
必ずしも身体の大きさと
比例するものではない。犬は二十年で
老衰するが、犬よりも小さな
烏は百年
以上も生きる。馬は三四十年で死ぬが、ひき
蛙は五十年あまりも生きている。しからば
寿命なるものは何によって定まるかというに、
如何なる動物でも、
子孫を
遺す
見込みの立たぬ前に死んではその
種族がたちまち
断絶するは知れたことゆえ、
必ず
若干の子を
産むに足るだけの
寿命がなければならず、しこうして
極めて多数の子を
産めば、そのまま親が死んでも
種族の
継続する
見込みが
確かに立つが、やや少数の子を
産むものはこれを
保護し
養育して
競争場裡に安心して手放せるように仕上げてからでなければ親は死なれぬ。
実際動物
各種の
寿命を調べて見ると、みなこの
辺に定まっている。
生物の
寿命については昔から
種々の
説が
唱えられ、その中にはずいぶん広く
俗間に知られているものがある。
一例をあげると、
如何なる動物でもその
寿命は
成長に
要する年月の五倍に定まっているという
説があるが、これには少しもよりどころはない。身体の大きくなることが止まり、
生殖の
器官が十分に
成熟した時を
通常成長の終わった時と見なすが、二三のもっとも
普通な動物についてその
寿命とこの
期限とを
比較して見たら、直ちにかかる
説の取るにたらぬことが知れる。
例えば
蚕は発育を始めてから
約一箇月で
成長し終わって
卵を
産むが、その後
四箇月生きるかというとわずかに四日も生きてはいない。「かげろう」の
幼虫は二年もかかって水中で
成長するが、
翅が生えて
飛び出せばわずかに数時間のうちにことごとく死んでしまうて、けっして十年の
寿命は
保たぬ。アメリカの有名な「十七年
'蝉」のごときは、
幼虫は十七年もかかって地中で
成長し、
成虫となって
卵を
産めば数日で死ぬが、これなどは五倍
説にしたがえば八十五
歳まで生きねばならぬはずである。また他の
類から
例を取って見るに、
鶴は二年で
成長し終わるが、その
寿命は十年と
限らず、よく百年
以上も生きる。
烏のごときも
雛は
数箇月で
成長し終わるが、
寿命はやはり百年に
達する。
総じて
鳥類ははなはだ命の長いもので、
成長期限の何十倍にもあたるのがつねである。また
魚類のごときは
卵を
産むようになってから後も引きつづいて身体が大きくなるゆえ、
成長の終わりをいつと定めることができぬ。かような
次第で
種々の動物から
実際の
例をあげてくらべて見ると、
成長に
要する年数と
寿命の年数との
割合は
種類によってそれぞれ
違うものでけっして一定の
率をもって言い
現わし
得べき
性質のものでないことが明らかである。ただいずれの場合にも
種族継続の
見込みのほぼ
確かについたころに親の命が終わることだけは
例外のない
規則のように見える。前の
例について見ても、
蚕はそれぞれの
雌蛾が数百
粒の
卵を
産んでおきさえすれば、後は
捨てておいても
蚕の
種族の
絶えるおそれはないと
見込んだごとくに、ほとんど
産卵がすむと同時に
寿命がつきる。これに反して
鳥類は
概して運動が
敏活であり、したがって
滋養分を
多量に
要するが、毎日食うた食物の中から自身を
養うべき
滋養分を引き去った、
残りの
滋養分だけがたまって
卵をつくる
材料となるのであるから、よほど食物が
潤沢になければ
卵を多く
産むことはできぬ。しかも
鳥類の
卵はすべての動物の中でもっとも
多量の
滋養分を
含んだもっとも大きな
卵であるゆえ、これを数多く
産むことはとうてい
望まれぬ。
鶏のごとく人に
飼われてつねに
豊富に
餌を食うものは、一年に百
以上も
卵を
産むが、野生の
鳥類は食物の十分にある時もあれば、食物のはなはだしく
欠乏する時もあり、かつ
競争者もあることゆえ、
平均してはけっして
豊富とは言われぬ。それゆえ
鳥類が一年に
産む
卵の数は
極めて少ないのがつねであって、
十個も
産めばすこぶる
多産のほうである。大きな鳥はたいてい一年に
一個もしくは
二個の
卵より
産まぬ。そのうえ
鳥類の
卵はすこぶる
壊れやすいもので、
雛が
孵化する前に何かの
怪我で
破損する場合もけっして少なくはなかろう。されば
鳥類はよほどの長命でなければ
種族維持の
見込みが立たぬ。一年に
卵を一つより
産まねば、百年かかってもわずかに
百個産むにすぎず、これを
如何に大事に
保護養育しても
非業の死を
遂げるものが
相応にあるゆえ、命は長くてもけっして
必要以上に長いわけではない。他の動物に
比して
鳥類の
寿命が
特に長いのはおそらくかような
事情が
存するゆえであろう。
要するに動物の
寿命は
種族継続の
見込みのほぼ立ったころを
限りとしたもので、そのためには
若干数の子を
産み終わるまで生きねばならぬことは言うまでもない。しこうして子の
総数を一度に
産んでしまう
種類もあれば、何度にも分けて
産む
種類もあり、分けて
産むものでは
最後の子を
産むまで
寿命はつづかねばならぬ。また子を
産み放しにする動物では、
最後の子を
産み終わると同時に親の
寿命が終わっても
差支えはないが、子を
保護し
養育する
種類では、
最後の子を
産んだ後になおこれを
保護養育する間
寿命が
延びる
必要がある。すなわち
最後の子を
産んだ後の親の
寿命は、ちょうど子が親の
保護養育を受ける
必要のある長さと
相ひとしかるべきはずである。
以上述べたところはむろん大体についての
理屈で、
一個一個の場合にはこのとおりになっていないこともあろうが、多数を
平均して考えるといずれの
種類にもよく当てはまってけっして
例外はない。人間のごときも「人生七十古来
稀なり」と言うて、まず七十
歳ないし七十五
歳くらいが
寿命の
際限であるが、これは二十五年かかって
成長し、五十
歳まで
生殖しつづけるものとすると、
最後の子が
徴兵検査を受けるか大学を
卒業するころに親の
寿命がつきる
勘定で、ここに
述べたところと全く
一致する。人間の
寿命も他の動物の
寿命と同じく、一定の
理法にしたごうて、何千万年の昔から今日までの間に
種族維持にもっとも
有利な
辺に定まったものと考えると、
特殊の薬品や
健康法を
工夫してこれを
延長せんと
努力することは、
賢い
業か
否か大いに
疑わざるを
得ない。
食うのは
産まんがためで、
産むのはさらに多く食わんがためであるとはかつていずれかの章で
述べたが、生物の動作を見ると、
無意識ながら
徹頭徹尾自己の
種族を
維持し
発展させんがために
働いている。食うのは他
種族の
物質を
自己の体内に取り入れ、これを同化して
自己の
物質とすることゆえ、
直接に
自己の
種族をそれだけ
膨張せしめたことに当たる。また
産めば
自己の
種族の
個体の数が
殖え、これが打ちそろうて食えばますます他
種族の
物質を取って
自己の
種族に
併合することができる。すなわち
食欲も
色欲もその
根底は
無意識の
種族発展欲にあるが、数多くの
種族が
相並んでそれぞれ
膨張しようと
努めるめえ、
互いに
圧しあい
攻めあうことをまぬがれず、少しでも力の強いほうはふくれて他を
圧迫し、少しでも弱いほうは他に
圧迫せられて
縮小せざるを
得ぬ。しこうしてそのさい
寿命の長さも
種族の消長に
関係し、もっとも
適当な長さの
寿命を有する
種族でなければたちまち
滅び
失せねばならぬ運命に
陥ることは、ほぼ次のごとき理由による。 そもそも動物
個体をなす
細胞は発生の進むにしたがいてその間に分業が行なわれ、
各種特別の
任務を
分担して
専門の仕事にのみ
適するようになると、始め持っていた
再生の力が
次第に
減ずるもので、ついには新たな
細胞を生ずる力が全くなくなる。
例えば
神経細胞とか赤血球とかいうものになってしまえば、その
分担の仕事は十分に
務めるが、さらに
分裂して新たな
細胞となることはできぬ。言を
換えれば、
細胞にも
年齢があり
老若の
別があって、
専門の仕事を
務めた
細胞はすでに
老細胞と見なさねばならぬ。
個体は
細胞の集まりであるゆえ、古くなるにしたがって
老細胞の数の
割合が
自然多くなり、
各部の
働きも
鈍くなり、
再生力も
減ずるをまぬがれぬ。身体内で
絶えず新たな
細胞ができてはいるが、その
割合は
老若によって
非常に
違い、
胎児の発生中のごときは実に
盛んに新
細胞ができるに反し、
老年になると古い
細胞が長くとどまって
働いている。それゆえ
若いときには
傷口などもすみやかに
癒えるが、
老年になるとなかなか手間がかかる。また物を
覚えるのでも
若い時にはたやすくできるが、年を取った後はとうていむずかしい。自転車の
稽古でも大人には八回も教えぬと
覚えぬところを
八歳の
子供ならばわずかに三回ですむ。「八十の手習」という
諺はあるが、その半分の四十をすぎては外国語の学習のごときはほとんど
絶望である。かような
次第で、
老いたる
個体は
壮年時代の
個体にくらべて生活上
種々劣ったところが生じ、
老の
積もるにしたがいますますいちじるしく
劣るようになるゆえ、
一種族の中に
老いたる
個体の多くあることは他
種族と
対抗するにあたっては
確かに
不得策である。
仮に
敵と味方との
個体の員数が
相ひとしいとすれば、
老いたる
個体を多く有する組のほうが
敗ける心配が多い。
寿命が短かすぎて
種族維持の
見込みの立たぬうちに親が死ぬようでは、その
種族はもちろん
生存ができぬが、また
寿命が長きにすぎて
種族維持の
見込みが
確かについた後に、
老者が長く
生存して
若い者の
占むべき
座席をふさぐようでも、他の
種族との
競争に勝てぬゆえ、昔から長い間の
種族間の
競争の
結果、ちょうど
適当の長さの
寿命を有するもののみが生き
残り、各
種類に
種族の
生存上もっとも
有利な長さの
寿命が
自然に定まったのであろう。
非業の死をまぬがれた
個体も
適当な時期に
達すれば
必ず死ぬことが、その
種族の
維持継続のために
必要であるが、今まで
健康なものが
即刻死ぬということは
困難であるゆえ、死ぬにはまずもって身体に少しずつ
変化が起こり、
変化が
積もってついに死に終わるのがつねである。もっともこの
変化が起こり始めてから死ぬまでの時の長さは、動物の
種類によって
非常に
違い、短いものはわずかに数秒にすぎず、長いものは二十年もかかる。
例えば
蜜蜂の
雄が死ぬのは
交尾のまさに終わらんとする
瞬間で、
雌に
交接器の根元を食い切られ、
雌の体から
離れて地上に落ちるころにはすでに死んでいる。これに反して人間のごときは四十
歳から四十五
歳以上になると、わずかずつ
変化が始まり、
次第に
変化がいちじるしく進んで七十
歳くらいになって死んでしまう。かくゆるゆると
変化の進む動物についてその
変化の
模様を
詳細に調べて見ると、身体の
諸部に
種々の
異なった
変化の起こることが知れるが、これに
基づいて死の
原因に
関するさまざまの
学説が
唱えられた。
老衰は身体に一定の
変化が起こってついに死の
転帰を取るものゆえ、昔はこれをもって
一種の病気と見なしたこともあるが、
一種の病気と見なす
以上は何らかの
手段によってこれを
治療することができるはずと考え、
不老不死の
方法の研究に苦心する人もあった。また
老衰をもって
一種の
慢性中毒と見なし、もしその
毒を消すことができたならば
老衰は
避けられると
論じた人もある。一時世間に
評判の高かったメッチニコフの新
養生法のごときはその
一例であるが、その
要点を
摘んで言うと、人間の
大腸の中にはたくさんの
黴菌がいて、その生ずる
毒のために
動脈の
壁が
硬くなり
弾力を
失いなどして
老衰の
現象が起こり、それが
積もってついに死ぬのである。それゆえ何らかの
方法で
腸内の
黴菌の
繁殖を
防ぎさえすれば
老衰は
避けられる。
黴菌の発生を
防ぐには
乳酸を用いるのがもっともよろしいが、食物としては
牛乳をブルガリア
菌で
乳酸化させた、ヨーグルトが一番その
目的にかのうている。ヨーグルトさえ食うていれば
老衰する気づかいはないとの
説で、
議論としては実に
簡単明瞭なものである。その他
老衰は身体内に
石灰がたまりすぎるために起こるとか、
血管壁の
硬化のために起こるとか、または
内分泌の
状態の
変化のために起こるとか、さまざまの
説があっていずれも有名な医学者によって
熱心に
唱えられているが、
著者の考えによると、これらはみな
原因と
結果とを
転倒しているのであって、
動脈の
硬くなるのも、
組織が
弾力を
失うのも、
石灰分がたまるのも、けっして
老衰を起こす
原因ではなく、むしろ
老衰のために生ずる
結果と見なさねばならぬ。前にも
述べたとおり、
各種動物の
寿命はその
種族維持のために長すぎず短かすぎずちょうどもっとも
有利なところに定まっているが、これは古代から今日までの長い間の
種族間
競争の
結果として生じたことで、その
根底は
各個体を
形成する
細胞の
原形質の深いところに
潜んでいるゆえ、
原形質までをつくりなおすことができぬ間は、
寿命の長さを
随意に
延長したり
短縮したりすることはむずかしかろう。
蚕の
蛾が
産卵後一両日で死ぬのも、人間が
末の
子供の
成長し終わるころに
寿命のつきるのも、
蚕の体の長さが
約二寸五分(注:7.5cm)をこえず、人間の身長が
平均五尺三寸(注:159cm)くらいにとどまるのと同じく、何千万年かの間に
自然に定まった
性質である。しこうして
寿命の
尽きたときに急に死ぬ
種類では、あたかも
急性の
心臓麻痺か
卒中で死ぬごとくに
特に
老衰と
称すべき時期がないが、
生殖後死ぬまでに手間の取れる動物ではその間に
漸々体質が
変化し、一歩一歩死に近づいてゆくゆえ、
老衰の
状態がいちじるしくあらわれる。すなわち
組織の
再生力が
次第に
減じ、古い
細胞が多くなれば、
各組織の
働きも
鈍くなって、あるいは
弾力がなくなるとか
硬く
脆くなるとか、
石灰がたまるとか、
分泌が十分でなくなるとか、その他なおさまざまの
変化が明らかに見える。広く生物界を
見渡して
諸種の
異なった生物を
比較することを
忘れ、ただ人間のみを
材料として
老衰期に起こる身体上の
変化を調べると、とかく
或る
一種の
変化をもって
老衰の
唯一の
原因と見なし、それさえ
防げば
老衰は
避けられるもののごとくに思い
誤る
傾きがある。
著者は
或る時
五歳ばかりの
幼児をつれて、
散歩の
途中に
半鐘を指して、「あれは何をするものか」と
尋ねたところが、「あれを
敲くと火事が始まるのでしょう」と答えたので大いに
笑うたことがあるが、
動脈の
硬化をもって
老衰の
原因と見なすことはいくぶんかこの
幼児の答えに
似ているように思われる。前に
述べたメッチニコフの
長寿論のごときも、一部ずつに
離せばおそらくみな正しかろう。すなわち
大腸の中に多くの
黴菌がいることも、
乳酸によって
黴菌の発生を止め
得ることも、年を取れば
動脈壁の
硬化することも、みなけっして
間違いではなかろうが、これをつなぎ合わせてヨーグルトさえ食うておれば
老衰が
避けられるごとくに
論ずるのは、もっとも大事なところで
原因と
結果とを
転倒しているゆえ、
半鐘さえ
敲かねば火事は起こらぬごとくに考えるのと同様な
誤りに
陥っているのである。
各種生物の
寿命はほぼその
種族の
維持継続にもっとも
有利な長さに定まってあるとすれば、これをさらに
延ばすことに
努力する
必要はない。したがって
寿命を
延ばし
得るとの
学説を聞いてこれを
歓迎することは大きな
間違いである。いまだ
寿命の終わらぬ
年齢の者が
非業の死を
遂げることはできるだけ
避ける
工夫をめぐらさねばならぬが、すでに
寿命を全うした者がその後なお長く生きていることは
種族のために
損はあっても
益はないゆえ、けっして
願わしいことでない。
種族発展のうえから言えば、今日
必要なことは、すでに
老いたる
老人の命をさらに長く
延ばすことではなく、他
種族との
競争場裡にたって勝つ
見込みのある
有望な
後継者をつくるにある。六十
歳ですでに
老耄する人もあれば八十
歳になっても
矍鑠たる人もあるゆえ、いちがいには
論ぜられぬが、
自然の
寿命を
超えれば身体も
精神もいちじるしく
衰えるのがつねであって、とうてい一人前の
働きはできぬ。書画などにも
年齢の書いてあるのは
子供か
老人に
限り、
八歳童とか七十八
翁とかは記してあるが、三十
歳四十
歳の人に
年齢を書く者はけっしてない。すなわち
老人は
子供と同じく年に
似合わぬところを
誇るつもりであろうが、これがすでに
老耄している
証拠である。人間はすこぶる大きな
団体をつくって生活するゆえ、その中に
老耄者が多少
混じていても、そのために
不利益をこうむることが明らかに見えぬが、他の動物では
種族の
生存上かかることはけっして
許されぬ。されば
一般に通じて言えば
種族の
維持発展のうえには、それぞれ
個体がその死すべき
適当の時期に
必ず死ぬことがもっとも
必要である。
身体は死んでも
魂だけは後に
残るとは昔から広く
信ぜられていることであるが、これなどもただ人間のみについて考えるのと、生物をことごとく
並べ、人間もその中に
加えて考えるのとでは、
結論も大いに
違うであろうと思われるから、死の話のついでにここに一言書きそえておく。すべての生物
種類を
並べた中へ、人間をも
加えて全部を
見渡すと、人間は
脊椎動物中の
獣類の中の
猿類中の
猩々類と同じ
仲間に
属するものなることは明らかであるゆえ、身体を
離れた
魂なるものが人間にあるとすれば、
猿にもあると考えねばならず、
猿に
魂があるとすれば、犬にもあると見なさねばならず、かくして先から先へとくらべゆくと、
何類までに
魂があって
何類以下には
魂がないか、とうていその
境を定めることができぬ。
仮に下等の動物まで
魂があるとすれば、これらの動物が人間とはまるで
違うた
方法で子を
産んだり死んだりするときに、
魂はいつ身体に入り来たりいつ身体から出で去るかと考えて見るとずいぶん面白い。「いそぎんちゃく」が
分裂して
二匹になる場合には
魂も
分裂して
二個となって両方へ
伝わるか、それとも今まで
宇宙に
浮かんでいた
宿無しの
魂が新たに一方に入り来たるか、もしさようならば、もとからいた
魂と新たに来た
魂とは
如何にして受持の体を定めるかなどといくつでも
謎が出てくる。また人間だけについて考えても、
卵細胞の
受精から
桑実期、
胃状期をへて、身体
各部が
次第々々に発育し終わった
成人になるまでを一目に
見渡したつもりになって、いつ
初めて
魂が
現われたかと
尋ねると、やはり答えに
当惑する。身体からはなれた
個体の
魂が
永久に
不滅であるとすれば、今日までに死んだ者の
魂がみなどこかに
存するわけで、その数はどのくらいあるか知れぬが、それらはいつ生じたものであるか。終わりを
不滅と
想像するならば、始めも
無限と
想像してよろしかろうが、
仮に始めもなく終わりもなく
永久に
存在するものとすれば、それが身体に乗り
移らぬ前には何をしていたか。世間で言う
魂はいつまでもその一時
関係していた肉体の死んだ時の
年齢で止まるようで、
五歳で死んだ
孩児の
魂はいつまでも
五歳の
幼い
状態にあり、九十で死んだ
老爺の
魂はいつまでも九十の
老耄した
状態にあるように思われているが、これらの
魂は肉体に宿る前には
如何なる
状態にあったかなどと
尋ねると、まるで雲のごとくでつかまえどころがない。かくのごとく身体とははなれて
独立に
存在し
得る
個体の
魂なるものがあるとの考えは、生物界のどこへ持っていっても
辻棲の合わぬことだらけであるゆえ、
虚心平気に考えるといわゆる
魂なるものがあるとは
容易に
信ぜられぬ。
神経系の
霊妙な
働きの一部を
魂の
働きと名づけるならば、これは
別であるが、身体が死んでも後に
魂が
残るというごときは、
実験と
観察とによって生物界を
科学的に研究するにあたっては全く問題にも上らぬことである。
しかるに肉体が死んでも
魂だけは生き
残るという
信仰が
極めて広く行なわれているのはなぜかというに、これには
種々の
原因があるが、一部分は
確かに
感情に
基づいている。その
感情とは、自分が死んだ場合に肉体も
精神もなくなって
全然消滅してしまうことを、何となく
残り
惜しく物足らぬように思う感じであるが、これも
熟考して見たならば
魂などが
残ってくれぬほうをありがたく思う人も多かろう。死んで
魂が
残るのは自分と自分の
愛する人とだけにかぎるならば実に
結構であるが、
嫌いな人も
憎い人も
債権者も
執達吏も死ねば、やはり
魂の
仲間入りをしてくることを考えると、むしろ
魂などを
残さずに
綺麗に消えてなくなったほうが
苦患が短くすむことに心づかねばならぬ。
魂という字は学者に言わせれば
種々深い
理屈もあろうが、
通俗に言い
伝え来たった
魂なるものは、
単に
個人の
性質が身体なしに
残ったごときもので、いたって
幼稚な
想像にすぎず、男ならば死んでも男、女ならば死んでも女、酒のみは死んだ後にも
酒好きで、
吃りは死んだ後にも
吃り、
実際草葉の
蔭か
位牌の後に
隠れていて、
供え物の
香をかぎ
御経の声を聞き
得るもののごとくに考えているのであるが、かような
種類の死後の命はこれをあると
信ずべき理由は少しもない。生物学上から言えば、
子孫を
遺すことがすなわち死後に命を
伝えることであって、
子孫が生き
残る
見込みのついた後に自分が死ねば、自分の命はすでに
子孫が
保証して受けついでくれたことゆえ、自分は全く消え
果てても少しも
惜しくはないはずである。されば、
子孫の生き
残ることを死後の命と考え、死後も
自己の
種族のますます
発展することを
願うて、もっぱら
種族のために
有効に
働き
得るような
優れた
子孫を
遺すことをつねづね心がけたならば、これが何よりも
功徳の多いことであろうと思われる。
生物の
各個体にはそれぞれ一定の
寿命があって、
非業の死はまぬがれ
得ても
寿命の
尽きた死はけっしてまぬがれることができず、早いかおそいか一度は
必ず死なねばならぬ運命を持っているが、さて
種族として
論ずるときは
如何であろうか。同様の
個体の集まりなる
種族にも、やはり
個体と同じように生死があり
寿命があって、一定の
期限の後には
絶滅すべきものであろうか。これらのことを
論ずるには、まず生物の
各種族は
如何にして生じ、
如何なる
歴史をへて今日の
姿までに
達したものかを
承知しておかねばならぬ。
動植物の
種族の数は今日学者が名をつけたものだけでも百万
以上もあって、その中には
極めて
相似たものやまるで
相異なったものがあるが、これらは
初め
如何にして生じたものであるかとの
疑問は、いやしくも物の
理屈を考え
得る
程度までに
脳髄の
発達した人間にはぜひとも起こるべきもので、
哲学をもって名高い昔のギリシア人の間にもこれに
関してはすでに
種々の
議論が
闘わされた。しかし近代にいたって
実証的にこれを
解決しようと
試みたのは、だれも知るとおりイギリスのダーウィンで、『
種の起原』と題する
著書のうちに次の
二箇条を明らかにした。すなわち第一には生物の
各種は長い間には少しずつ
変化すること、第二には
初め
一種の生物も代を多く重ねる間には
次第に
数種に分かれることであるが、
絶えず少しずつ
変化すれば、
先祖と
子孫とはいつか全く
別種のごとくに
相違するにいたるはずで、太古から今日までの間には
境は
判然せぬが
幾度も形の
異なった時代を
経過し来たったものと見なさねばならず、また
初め
一種の
先祖から起こった
子孫も後には
数種に分かれるとすれば、さらに後にいたれば
数種の
子孫のおのおのがまた
数種に分かれるわけゆえ、すべてが
生存するとしたならば、
種族の数は
次第に
増すばかりで、ついには
非常な多数とならねばならぬ。この
二箇条を
結び合わせて
論ずると、およそ地球上の生物は
初め
単一なる
先祖から起こり、
次第に
変化しながら
絶えず
種族の数が
殖えて今日のありさままでに
達したのである。すなわち生物
各種の間の
関係は、一本の
幹から何回となく
分岐して
無数の
梢に終わっている
樹枝状の
系図表をもって
示し
得べきもので、
各種族は一つの
末梢にあたり、
相似たる
種族は
相接近した
梢、
相異なる
種族ははるかに
相遠ざかれる
梢に当たって、いずれも
互いに
血縁の
連絡はあるが、その遠いと近いとにはもとより
種々程度の
相違がある。これだけは生物
進化論の
説くところであるが、これは
単に
議論ではなく、化石学をはじめとし
比較解剖学、
比較発生学、
分類学、
分布学など、生物学の
各方面にわたつて
無数の
証拠があるゆえ、今日のところではもはや
疑う
余地のない事実と見なさねばならぬ。
かくのごとく生物の
各種族はいずれも長い
歴史をへて今日の
姿までに
達したものであるが、その間には何度も形の
変じた
種族もあれば、また
割合に
変化することの少なかった
種族もあろう。しかしながらいずれにしても
変化は
徐々であるゆえ、いつから今日見るごとき形のものになったかは時期を定めて言うことはできぬ。化石を調べて見ると、少しずつ
次第々々に
変化して
先祖と
子孫とがまるで
別種になってしまうた
例はいくらもあるが、これらは
血筋は
直接に引きつづいていながらその
途中でいつとはなしに
甲種の形から
乙種の形に
移りゆくゆえ、
乙なる
種族はいつ生じたかというのは、あたかも
虹の
幅の中で黄色はどこから始まるかと問うのと同じである。人間などは化石の発見せられた数がいまだはなはだ少ないゆえ、この場合の
例には
不適当であるが、もしも時代の
相つづいた
地層から多数の化石が発見せられたならば、やはりいずれから後を人間と名づけてよいかわからず、したがっていつ
初めて生じたと言うことはできぬであろう。
生物
種族の
初めて
現われる具合いは、今
述べたとおり
漸々の
変化によるのがつねであるが、かくして生じた
種族は
如何になりゆくかというに、むろん
継続するか
断絶するかのほかはなく、
継続すればさらに少しずつ
変化するゆえ、長い間にはついに
別の
種族となってしまう。
地層の中から
掘り出された化石が時代の
異なるごとに
種族も
違うて、一として数代に
連続して生きていた
種族のないのは、昔もそのとおりであった
証拠であるが、今後とてもおそらく同じことであろう。まれには
変化の
極めて
遅いものがあって、いつまでも
変化せぬように見えるが、これはむしろ
例外に
属する。「しゃみせんがい」や「あかがい」などの
種族はずいぶん古い
地層から今日まで
継続しているゆえ、その間だけを見るとほとんど
永久不変のものであるかのごとき感じが起こるが、「しゃみせんがい」
属、「あかがい」
属の形になる前のことを考えると、むろん
変化したものに
違いない。また
或る
地層まではたくさんの化石が出て、その次の
地層からはもはやその化石が出ぬような
種族は、その間の時期に
断絶して
子孫を
残さなかったものと見なさねばならぬが、かような
種族の数はすこぶる多い。
獣類でも
魚類でも
貝類でも
途中で
断絶した
種族の数は、
現今生きている
種族の数に
比して
何層倍も多かろう。しこうしてこれらの
種族は
何故かく
絶滅したかというと、他
種族との
競争に
敗れて
亡びたものが多いであろうが、また
自然に弱って自ら
滅亡したものもあったであろう。
いつの世の中でも
種族間の
生存競争は
絶えぬであろうから、相手よりもはるかに
劣った
種族はとうてい長く
生存することを
許されぬ。同一の食物を食うとか、同一の
隠れ家を
求めるとか、その他何でも
生存上同一の
需用品を
要する
種族が、二つ
以上同じ場所に
相接して生活する
以上は
競争の起こるは
当然で、その間に少しでも
優劣があれば、
劣れるほうの
種族はしだいに
勢力を
失い、
個体の数もだんだん
減じてついには
一匹も
残らず死に
絶えるであろう。また
甲の
種族が
乙の
種族を食うというごとき場合に、もし食われる
種族の
繁殖力が食う
種族の
食害力に追いつかぬときは、
乙はたちまち
断絶するをまぬがれぬであろう。かくのごとく他
種族からの
迫害をこうむって一の
種族が
子孫を
残さず
全滅する場合はつねにいくらもある。しかして昔から同じところに
棲んでいた
種族の間では、勝負が急につかず勝っても負けても
変化が
徐々であるが、他地方から新たな
種族が
移り来たった時などは
各種族の
勢力に
急激な
変動が起こり、
劣った
種族は短日月の間に
全滅することもある。ヨーロッパへ、アジアの「あぶらむし」が入りこんだために、もとからいた「あぶらむし」は
圧倒されてほとんどいなくなったこともその
例であるが、かかることのもっともいちじるしく目立つのは、
大陸より遠く
離れた島国へ他から新たに動物が
移り入った場合であろう。ニュージーランドのごときは
従来他の島との交通が全くなくて、他には
異なった
固有の動物ばかりがいたが、ヨーロッパ
産の
蜜蜂を
輸入してから、がんらい土着の
蜜蜂の
種族はたちまち
減少して今日ではほとんどなくなった。
鼠もこの島に
固有の
種類があったが、
普通の
鼠が入り
込んでからはいつの間にか
一匹も
残らず
絶えてしまうた。
蝿にもこれと同様なことがある。
近代になって
絶滅した
種族もなかなか数多いが、その大部分は人間が
亡ぼしたのである。
鼠とか
雀とか
蝿とか
虱とかいうごときつねに人間に
伴うて
分布する動物を
除けば、その他の
種族はたいてい人間の
勢力範囲の
拡張するにしたごうてはなはだしく
圧迫せられ、
特に大形の
獣類、
鳥類のごときは
最近数十年の間にいちじるしく
減少した。
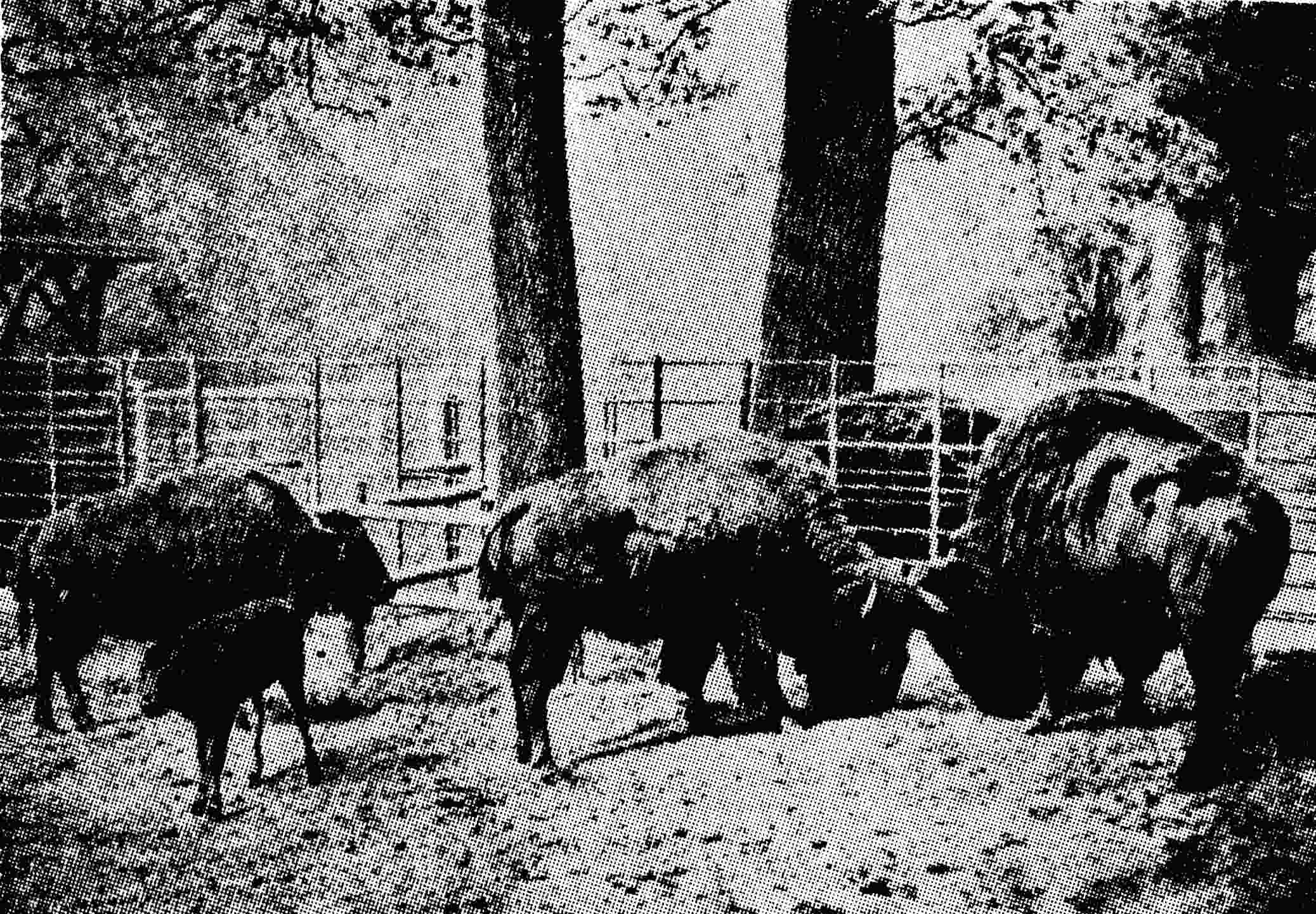 アメリカの野牛
アメリカの野牛
近ごろまでアメリカ
大陸に
無数に
群居して
往々汽車の進行を止めたといわれる野牛のごときは、今はわずかに少数のものが
特別の
保護を受けて
生存しているにすぎぬ。ヨーロッパの
海狸も昔は
各所の
河に多数に住んでいたのが、今はほとんど
絶滅に近いまでに
減少した。
獅子、
虎のごとき
猛獣はアフリカや
印度が全部
開拓せられた
暁には、動物園のほかには
一匹もいなくなるであろう。
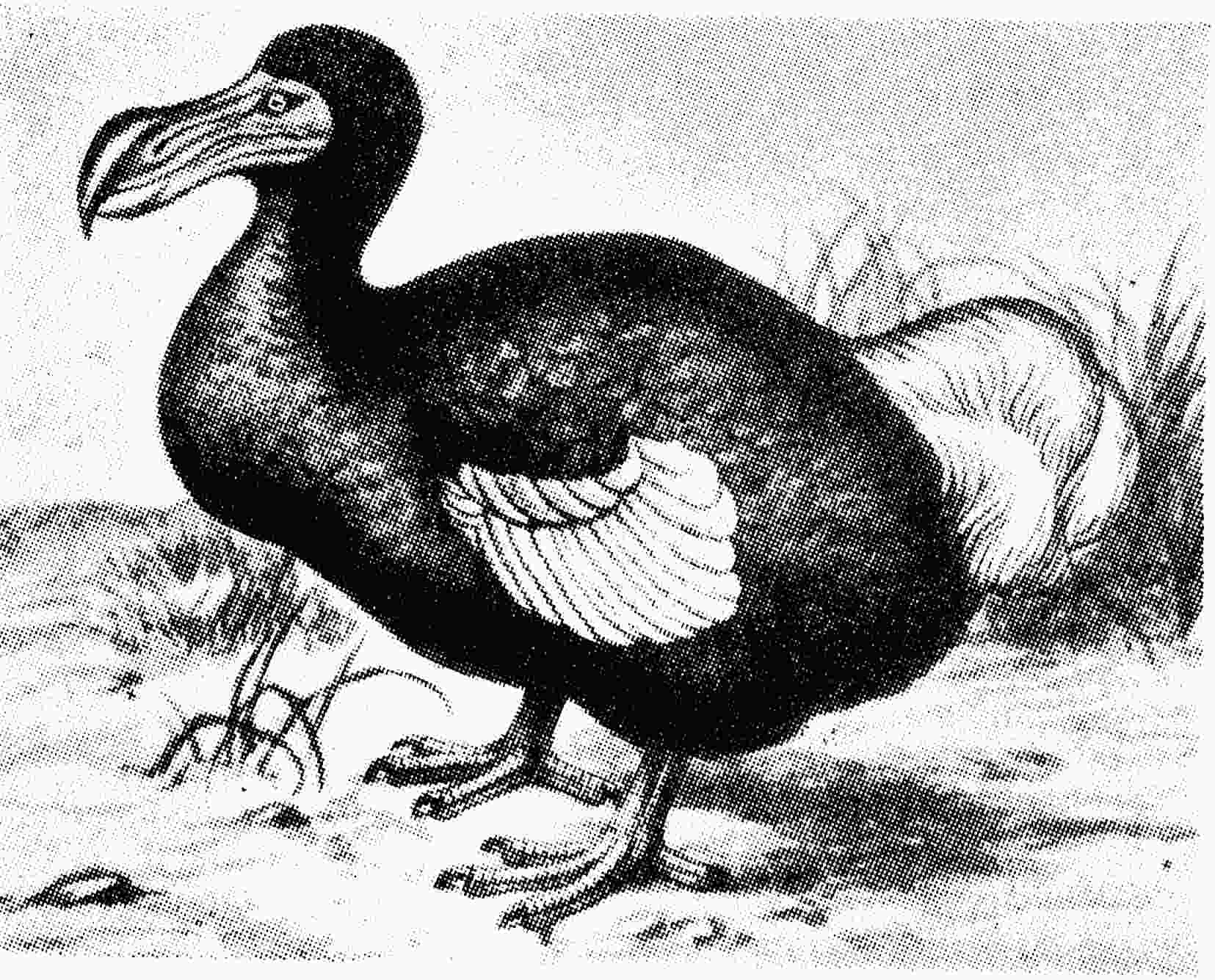 モーリシアス島にいた奇態な鳩
モーリシアス島にいた奇態な鳩
人間の力によってすでに
絶滅した
種族の
例をあげて見るに、マダガスカル島の東にあるモーリシアス島にいた
奇態な
鳩の
一種は今より二百年ばかり前に全く
絶えてしまうた。またこの島よりもさらに東に当たるロドリゲス島にはこれに
似た他の
一種の鳥が住んでいたが、このほうは今より百年ほど前に
捕りつくされた。これらは高さ二
尺五
寸(注:75cm)
以上目方が
三貫五百匁(注:115kg)もある大きな鳥で、力も
相応に強かったのであるが、長い間海中の
離れ島に住み、
恐ろしい
敵がいないために一度も
飛ぶ
必要がなく、したがって
翼は
退化して
飛ぶ力がなくなった。かかるところへ西洋人の
航海者がこの
辺まできてしばしばこの島に
立寄るようになったので、
水夫はそのたびごとに面白がってこの鳥を打ち
殺し、たちまちのうちに全部を
殺しっくして、今ではどこの
博物館にも
完全な
標本がないほどに
絶対に
絶えてしまうた。シベリア、カムチャツカ等の海岸には百四五十年前までは
鯨と「おっとせい」との間の形をした長さ四間(注:7.2m)もある
一種の大きな
海獣がいたが、
脂肪や肉を取るために
盛んに
捕えたので、しばらくで
種切れになった。前の
鳥類でもこの
海獣でも
敵に対して身を
護る力が十分でなかったゆえ、
生存競争に
劣者として
敗れ
亡びたのであるが、もし人間がゆかなかったならばむろんなお長く
生存しつづけ
得たに
違いない。
劣れる
種族が急に
滅亡するのはたいがい強い
敵が
不意に
現われた場合にかぎるようである。
人間の
各種族についても
理屈は全く同様で、遠くはなれて
相触れずに生活している間は、たとい
優劣はあっても
勝敗はないが、一朝
相接蝕するとたちまち
競争の
結果があらわれ、
劣れる
種族はしばらくのうちに
減少してついには
滅亡するをまぬがれぬ。
歴史あって
以来まされる
種族から
圧迫を受けてついに
絶滅した人間の
種族は今日までにすでにたくさんある。オーストラリアの南にあるタスマニア島の土人のごときは、昔は全島に
拡がって
相応に人数も多かったが、西洋の文明
人種が入り
込んで
攻めたてた
以来、たちまち
減少して今より数十年前にその
最後の一人も死んでしまうた。昔メキシコの全部に住んで
一種の文明を有していたアステカ人のごときも、エスパニア人が
移住し来たって何千人何万人と
盛んに
虐殺したので、今ではほとんど
遺物が
残っているのみとなった。古い西洋人のアフリカ
紀行を読んで見ると、
瓢を持って
泉へ水を
汲みにくる土人を、
樹の
陰から
鉄砲で打って
無聊を
慰めたことなどが書いてあるが、
鉄砲のない
野蛮人と
鉄砲のある文明人とが
相触れては、
野蛮人のほうがたちまち
殺し
尽くされるは
当然である。今日文明
人種の
圧迫をこうむってまさに
絶滅せんとしている
劣等人種の数はすこぶる多い。セイロン島のヴェッダ人でも、フィリピン島のネグリト人でも、ボルネオのダヤック人でも、ニューギニアのパプア人でも、今後急に
発展して先進の文明人と対立して
生存しつづけ
得べき
望みはもとよりない。文明
諸国の人口が
殖えて海外の
殖民地へあふれ出せば、他
人種の住むべき場所はそれだけ
狭められるゆえ、ついには文明人とその
奴隷とを
除いた他の人間
種族は地球上に身をおくべきところがなくなって、ことごとく
絶滅するのほかなきことは明らかである。
人種間の
競争においては、いくぶんかでも文明の
劣ったほうは
次第に
敵の
圧迫を受けて苦しい
境遇に
陥るをまぬがれぬゆえ、
自己の
種族の
維持継続をはかるには相手に
劣らぬだけに知力を高め文明を進めることが何よりも
肝要であろう。
劣れる
種族が
生存競争に
敗れて
滅亡することは理の
当然であるが、しからばまされる
種族は
永久に
生存し
得るかというに、これについては大いに
攻究を
要する点がある。まされる
種族は
敵と
競争するにあたってはむろん勝つであろうが、ことごとく
敵に打ち勝ってもはや天下におそるべきものがないというありさまに
達した後は
如何になりゆくであろうか。
敵がなくなった
以上は、なおいつまでも
全盛を
極めて
勢よく
生存しつづけ
得るであろうか。または
敵がなくなったためにかえって
種族の
退化を引き起こすごとき新たな
事情を生ずることはないであろうか。今日化石となって知られている古代の動物を調べて見るに、一時
全盛を
極めていたと思われる
種族はことごとく次の時代には
絶滅したが、これは
如何なる理由によることであるか。向かうところ
敵なきほどに
全盛を
極めていた
種族が、
何故今までおのれよりも
劣っていた
或る
種族との
競争にもろくも
敗北してたちまち
断絶するにいたったか。これらの点に
関してはいまだ学者間にも何らの
定説もないようで、古生物学の書物を見ても
満足な
説明を
与えたものは一つもない。されば今より
述べんとするところは全く
著者一人だけの考えであるゆえ、そのつもりで読んでもらわねばならぬ。
およそ
生存競争において
敵に勝つ動物には勝つだけの
性質が
備わってあるべきは言うまでもないが、その
性質というのは
種族によってさまざまに
違う。第一、
敵とする動物が
各種ごとに
違うゆえ、これに勝つ
性質も相手の
異なるにしたがい
異ならねばならぬ。今日学者が名前をつけた動物だけでも数十万
種あるが、
如何なる動物でもこれをことごとく
敵とするわけではなく、
日常競争する相手はその中の
極めて
僅少なる部分にすぎぬ。
例えば
産地が
相隔たれば
喧嘩はできず、同じ地方に
産するものでも森林に住む
種族と海中に住む
種族とでは
直接に
相敵対する
機会はない。されば勝つ
性質というのは、同じ場所に住み、ほぼ対等の
競争のできるような相手に対してまさることであって、
樹の上の運動では
巧みに
攀じるものが勝ち、水の中の運動では速く
游ぐものが勝つ。しこうして水中を速く
游ぐには足は
鰭の形でなければならぬゆえ、木に登るには
適せず、
巧みに木に登るには
腕は細くなければならぬゆえ、水を
游ぐには
適せぬ。それゆえ、水を
游ぐことにおいて
敵にまさるものは、
樹に登るには
敵よりもいっそう
不適当であり、木に登ることにおいて
敵にまさるものは、水を
游ぐには
敵よりもいっそう
不適当であるをまぬがれぬ。同一の足をもって、
樹上では
猿よりも
巧みに
攀じ、平原では
鹿よりも
迅く走り、水中では「おっとせい」よりも
速かに
游ぐというごときことはとうてい
無理な注文である。
鴨のごとく
飛ぶことも歩るくことも
游ぐこともできるものは、
飛ぶことにおいては遠く
燕におよばず、走ることにおいては遠く
駝鳥におよばず、
游ぐことにおいては遠くペンギンにおよばず、いずれの方面にも相手にまさる
望みはない。
魚類の中には
肺魚類というて
肺と
鰓とを兼ね
備え、空気でも水でも勝手に
呼吸のできる
至極重宝な
種類があるが、水中では水のみを
呼吸する
普通の
魚類に勝てず、
陸上では空気のみを
呼吸する
蛙の
類に勝てず、今ではわずかに
特殊の
条件のもとに
熱帯地方の
大河に
生存するものが二三
種あるにすぎぬ。
亀の
甲の
厚いことも、「とかげ」の運動の速いことも、それぞれその動物の
生存には
必要であるが、
甲が重くては速かに走ることがとうていできず、速かに走るには重い
甲は何よりも
邪魔になるから、「とかげ」よりも速力でまさろうとすれば、
甲の
厚さでは
亀に
劣ることを
覚悟しなければならず、
甲の
厚さで
亀よりもさまろうとすれば、速力では「とかげ」に
劣ることを
覚悟しなければならぬ。
かくのごとく、まされる
種族というのはみなそれぞれその
得意とするところで相手にまさるのであるから、
競争の
結果ますます
専門の方向に進むのほかなく、
専門の方向に進めば進むだけ
専門以外の方面には
適せぬようになる。鳥の
翼は
飛翔の
器官としては実に理想
的のものであるが、その代わり
飛翔以外には全く何の役にもたたぬ。犬ならば
餌を
押さえるにも顔を
拭うにも地を
掘るにも前足を用いるが、鳥は
翼を用いることができぬゆえ止むを
得ず後足または
嘴をもって間に合わせている。されば
如何なる
種族でもおのれが
得意とする点で相手にまさり
得たならば、たちまち相手に打ち勝ってその地方に
跋扈することができる。すなわち水中ならばもっともよく
游ぐ
種族が
跋扈し、
樹上ではもっともよく
攀じる
種族が
跋扈し、平原ならばもっともよく走る
種族が
跋扈することになるが、今日までに地球上に
跋扈した
種族を見ると、
実際みな
必ず
或る
専門の方面において
敵にまさったものばかりである。
対等の
敵と
競争するにあたっては一歩でも先へ
専門の方向に進んだもののほうが勝つ
見込みの多いことは、人間社会でも多くその
例を見るところであるが、同じ仕事をするものの間では、一歩でも分業の進んだもののほうが勝つ
見込みがある。身体
各部の間に分業が行なわれ、同じく食物を消化するにも、
唾液を出す
腺、
膵液を出す
腺、
硬い物を
咀嚼する
器官、液体を飲み
込む
器官、
澱粉を消化するところ、
蛋白質を消化するところ、
脂肪を
吸収するところ、
滓をためるところなどが、一々
区別せられるようになれば、身体の
構造がそれだけ
複雑になるは
当然であるゆえ、
数種の
異なった動物が同じ仕事で
競争する場合には、体の
構造の
複雑なもののほうが分業の進んだものとして
一般に勝ちを
占める。古い
地質時代に
跋扈していたさまざまの動物を見るに、いずれも
相応に身体の
構造の
複雑なものばかりであるのはこの理由によることであろう。相手よりも一歩先へ
専門の方向に進めば相手に打ち勝って一時世に
跋扈することはできるが、それだけ他の方面には
不適当となって
融通が
利かなくなるゆえ、万一何らかの
原因によって外界の
事情に
変化が起こった場合には、これに
適応してゆくことが
困難になるをまぬがれぬ。また相手よりもいっそう身体の
構造が
複雑であれば、
無事の時には
敵に勝つ
望みが多いが、
複雑であるだけ
破損のおそれが
増し、いったん
破損すればその
修繕が
容易でないゆえ、急の間に合わずして
失敗する場合も生ぜぬとはかぎらぬ。あたかも人力車と自動車とでは
平常はとても
競走はできぬが、自動車は少しでも
破損すると全く動かなくなって、とうてい
簡単で
破損の
憂いのない人力車におよばぬのと同じことである。かつて地球上に
全盛を
極めた
諸種の動物は、
各その相手に
比して
専門の生活に
適することと分業の進んだこととでまさっていたために、世界に
跋扈することを
得たのであるが、それと同時にここに
述べたごとき弱点を
備えていたものであることを
忘れてはならぬ。
地殻を
成せる岩石には
火成岩と
水成岩との
区別があるが、
水成岩のほうは長い間に水の
底へ
泥や
砂がたまり、それが
次第に
固まって岩となったものゆえ、
必ず
層をなして
相重なり、
各層の中にはその
地層のできたころに
生存していた生物の
遺骸が化石となって
含まれてある。
地質学者は
水成岩の
層をその生じた時代の
新旧にしたがい、始原代、古生代、中生代、新生代の四組に
大別し、さらに
各代のものを
若干の期に
細別するが、これらの
各時代に
属する
水成岩の
層を調べて見ると、その中にある化石にはすこぶるまれな
珍しい
種類もあれば、また
非常にたくさんの化石が出て、おそらくそのころ地球上のいたるところに多数に
棲息していたろうと思われる
種類もある。
個体の数や身体の大きさや
構造の進んだ点などから
推して、そのころ
全盛を
極めていたに
相違ないと思われる
種族がいずれの時代にも
必ずあるが、かかる
種族の中からもっともいちじるしいもの
若干を
選び出して、次に
簡単に
述べて見よう。
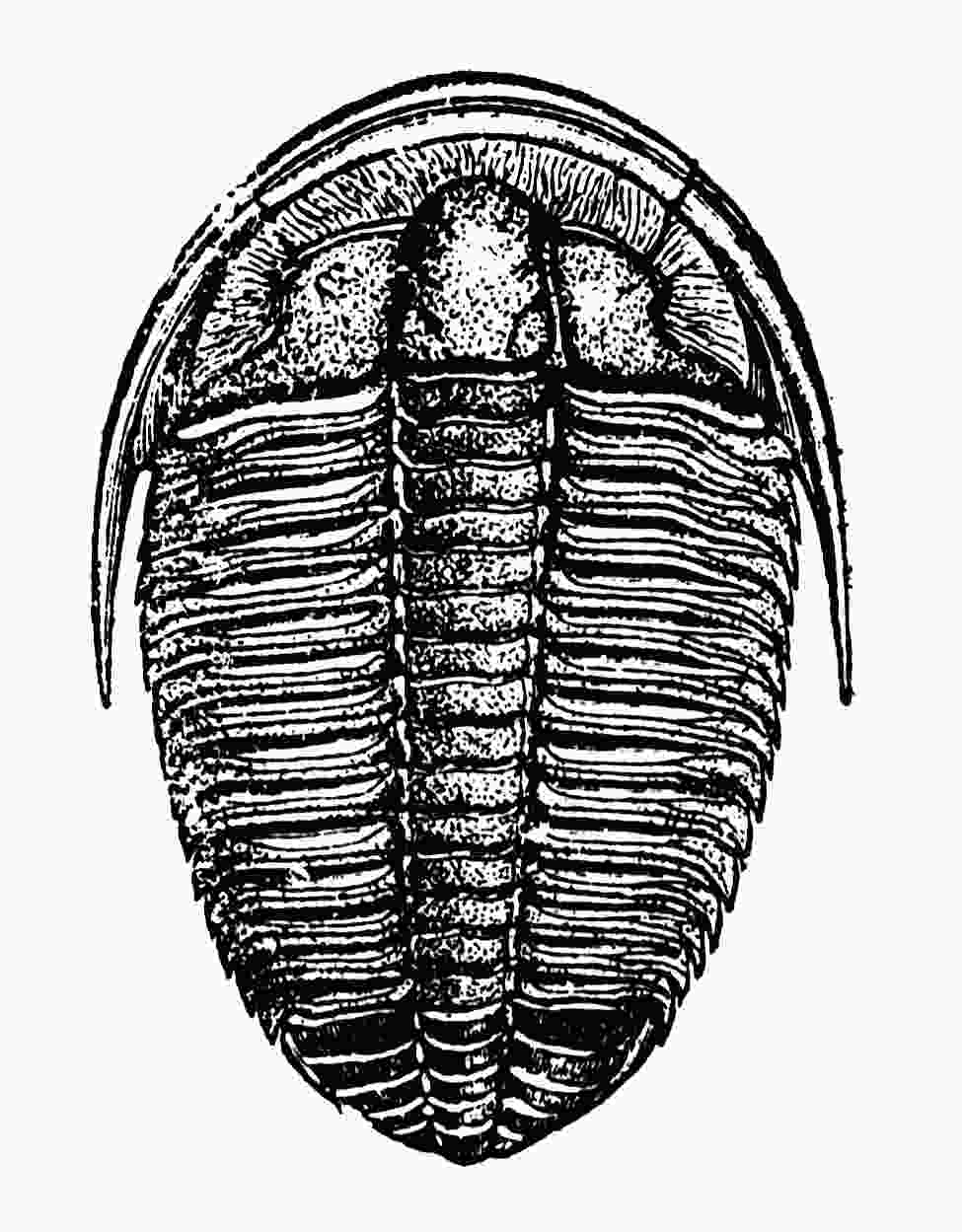 三葉虫
三葉虫
古生代(注:約5億4200万~約2億5100万年前)の岩石から
掘り出される「三葉虫」の
類も、そのころには実に
全盛を
極めていたものと見えて、世界
諸地方からおびただしく発見せられる。わが国では
極めてまれであるが、
支那の
山東省辺からは
非常にたくさん出て、板の形に
割った岩石の表面が全部三葉虫の化石でいっぱいになっていることが
珍しくない。三葉虫にもたくさん、
種や
属があって、小さいのは長さ一分(注:3mm)にもおよばず、大きいのは
一尺(注:30cm)
以上にも
達するが、いずれも
兜蟹と船虫との中間のごとき形で、
裏から見ると「わらじ虫」に
似て足が多数に生えている。この
類は古生代にはどこでもすこぶる
盛んに
繁殖したようであるが、
不思議にもその後たちまち
全滅したものと見えて、次なる中生代の
地層からは化石が一つも発見せられぬ。それゆえもし
或る岩石の中に三葉虫の化石があったならば、その岩石は古生代に
属するものと見なして
間違いはない。かくのごとく
或る化石さえ見れば直ちにその岩石の生じた時代を正しく
鑑定し
得る場合には、かような化石をその時代の「
標準化石」と名づける。
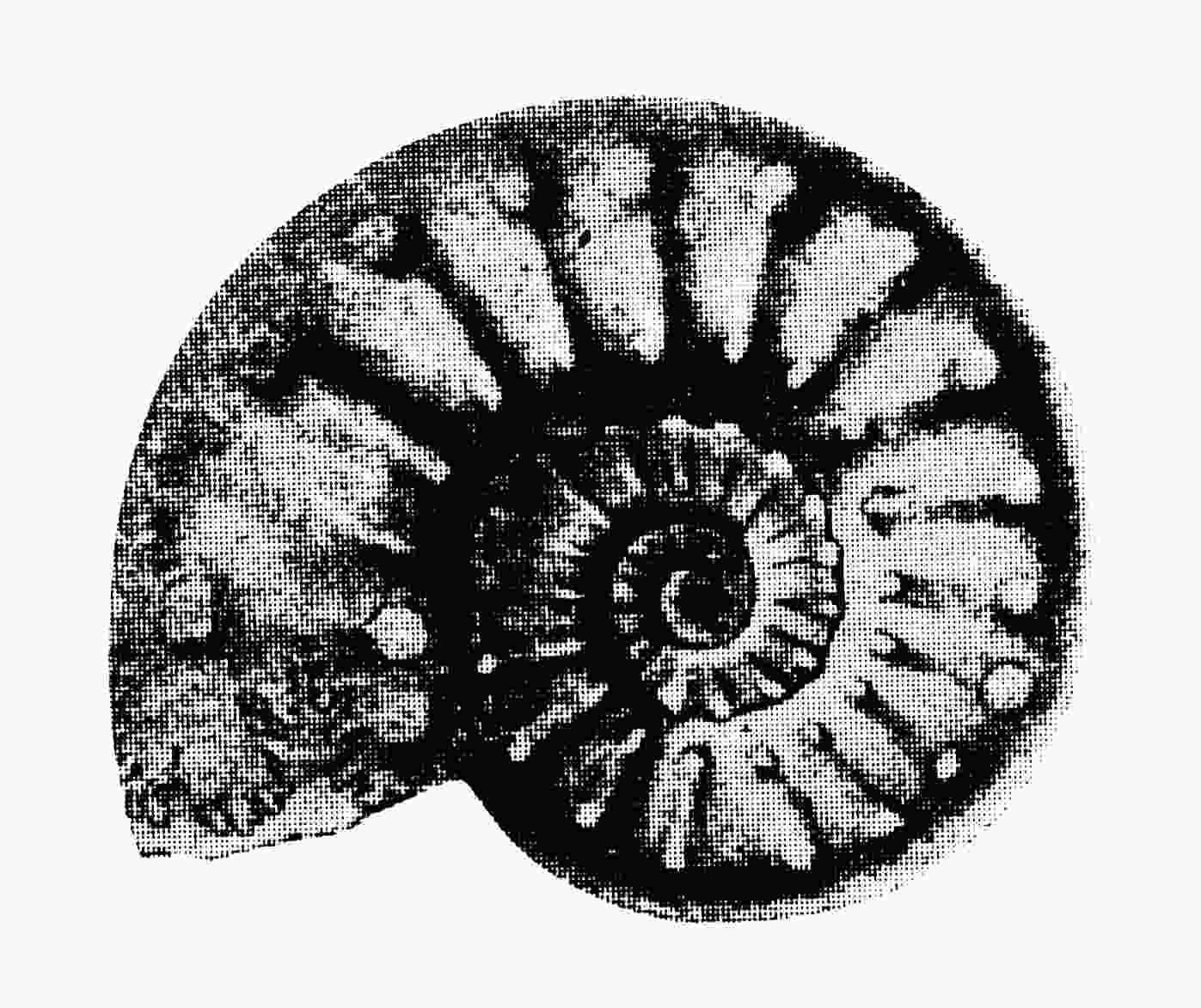 アンモン石
アンモン石
中生代(注:約2億5,217万年前~約6,600万年前)の
地層から
掘り出される「アンモン石」という化石は、「たこ」、「いか」などに
類する
海産軟体動物の
貝殻で、形があたかも
南瓜のごとくであるゆえ、
俗に「
南瓜石」と
呼ぶ地方もある。これもその時代には
全盛を
極めたものと見えて、
種の数も
属の数もすこぶる多く、
懐中時計ほどの小さなものから人力車の
車輪くらいの大きなものまで、世界の
各地方から多数に発見せられる。わが国のごときはそのもっとも有名な
産地である。今日生きている動物でややこれに
似た
貝殻を有するものはわずかに「おうむ貝」の
類のみであるが、「さざえ」や「たにし」の
貝殻とは
違い、
扁平に
巻いた
殻の内部にはたくさんの
隔壁があって多くの室に分かれている。しこうして、「アンモン石」では
隔壁と外面の
壁とのつなぎ目の線が実に
複雑に
屈曲して美しい
唐草模様を
呈し、その点においては
如何にも
発達の
極に
達したごとくに見える。この
類も中生代の終わりまでは
全盛を
極めていたが、その後たちまち
全滅したと見えて、次なる新生代(注:約6,500万年前~現代まで)の岩石からは一つもその化石が出ぬゆえ、
地層の新古を
識別するための
標準化石としてもっとも
重要なものである。
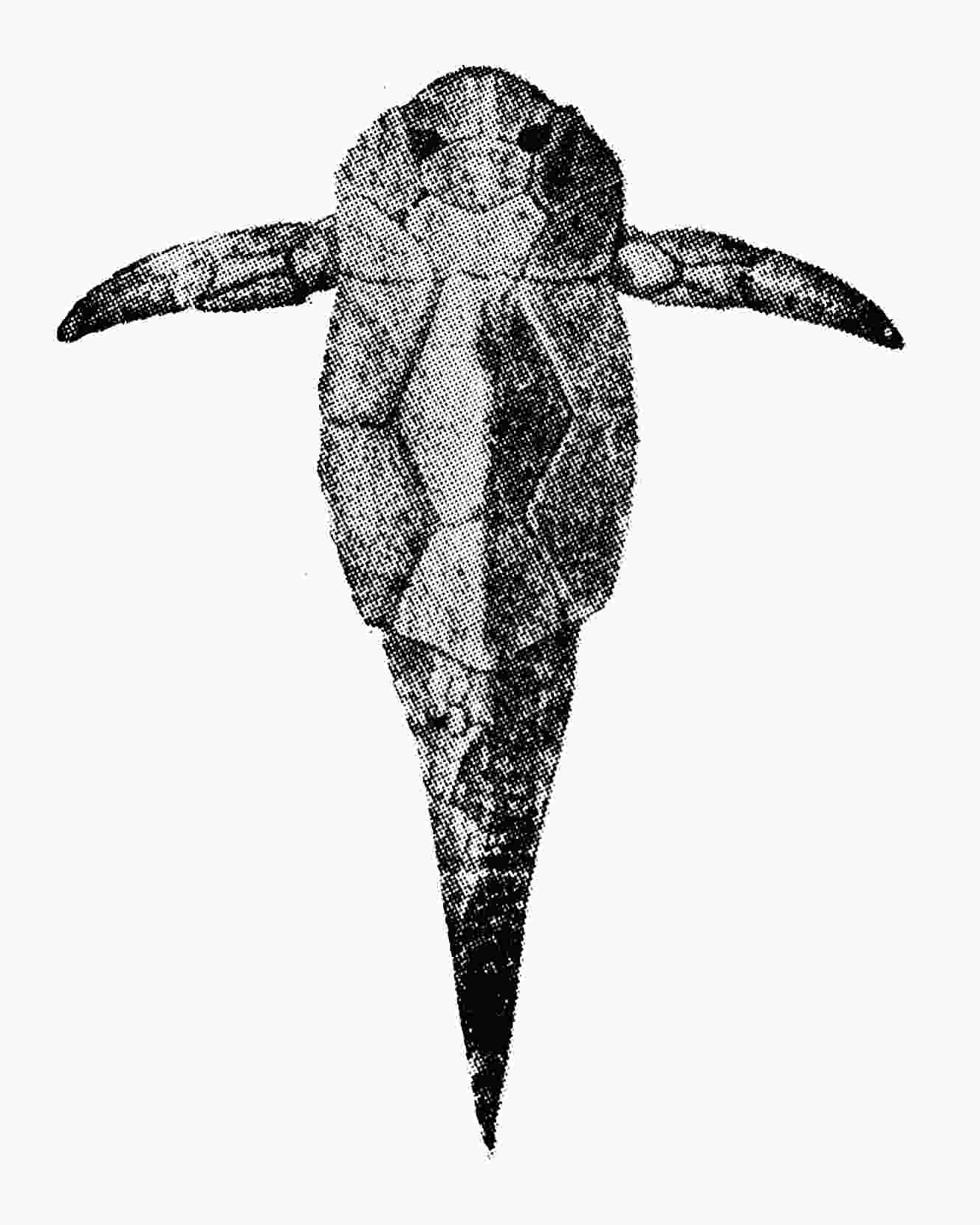 かぶと魚
以上
かぶと魚
以上は両方ともに
無脊椎動物の
例であるが、次に
脊椎動物について見ると、古生代の
魚類、中世代の
爬虫類、新生代の
獣類などには、それぞれその時代に
全盛を
極めていた
種族がたくさんにある。まず古生代の
魚類を見るに、今日の
普通の
魚類とは大いに
違うて
光沢のある
厚い
骨のような
鱗を
被った
種類が多く、スコットランドの赤色
砂岩から出た化石のごときは、「かに」か「えび」かのごとくに全身
厚い
甲冑をつけてほとんど
魚類とは見えぬ。もちろん
陸上へは
昇り
得なかったが、
魚類以上の
水棲動物がいまだいなかった時代ゆえ、かかる
異形の
魚類はいたるところの海中に
無数に
棲息して実に
全盛を
極めていた。
通俗の
地質学書に古生代のことを「魚の時代」と名づけてあるのももっともな
次第である。しかしその後にいたってみなたちまち
絶滅して、今日これらの
魚類にいささかでも
似ているのは、わずかに「ちょうざめ」などのごとき
硬鱗魚類が
数種あるにすぎぬ。
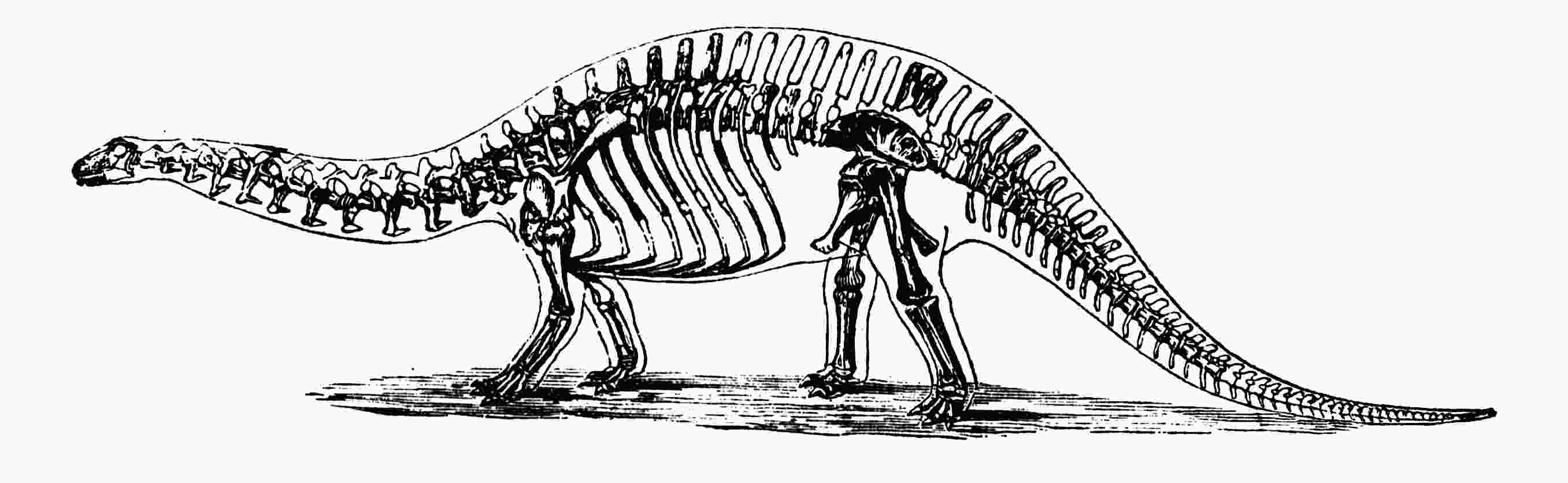 中生代の大蜥蜴
中生代の大蜥蜴
中生代における
爬虫類の
全盛のありさまはさらにめざましいもので、
陸にも海にも
驚くべき大形の
種類が
勢いをほしいままにしていた。今日では
爬虫類というと、
亀、
蛇、
蜥蜴などの
類にすぎず、
熱帯地方にはいくらか大きなものもいるが、
普通に見かけるものは小さな
種類ばかりであるゆえ、
全盛時代における
爬虫類の生活
状態はとうてい
想像もできぬ。ヨーロッパやアメリカの中生代の
地層から
掘り出された
爬虫類の化石を見ると、
陸上を四足ではい歩いた
種類には、長さ十数間(注:1間は1.8m)におよび
脛の
骨一本だけでもほとんど人間ほどあるもの、また「カンガルー」のごとく後足だけで立った
種類には、高さが三間(注:4.8m)
以上に
達するもの、また
蝙蝠のごとく前足が
翼の形となって空中を
翔けまわった
種類には、
両翼を
拡げると
優に三間(注:4.8m)を
超えるものがあり、その他形の
奇なるもの
姿のおそろしいものなど実に
千変万化極まりなきありさまであった。しかもそれがみなすこぶる数多く
掘り出され、ベルギーのベルニッサールというところからは長さ五間(注:9m)もある大
蜥蜴の化石が二十五
匹も一所に
発掘せられた。
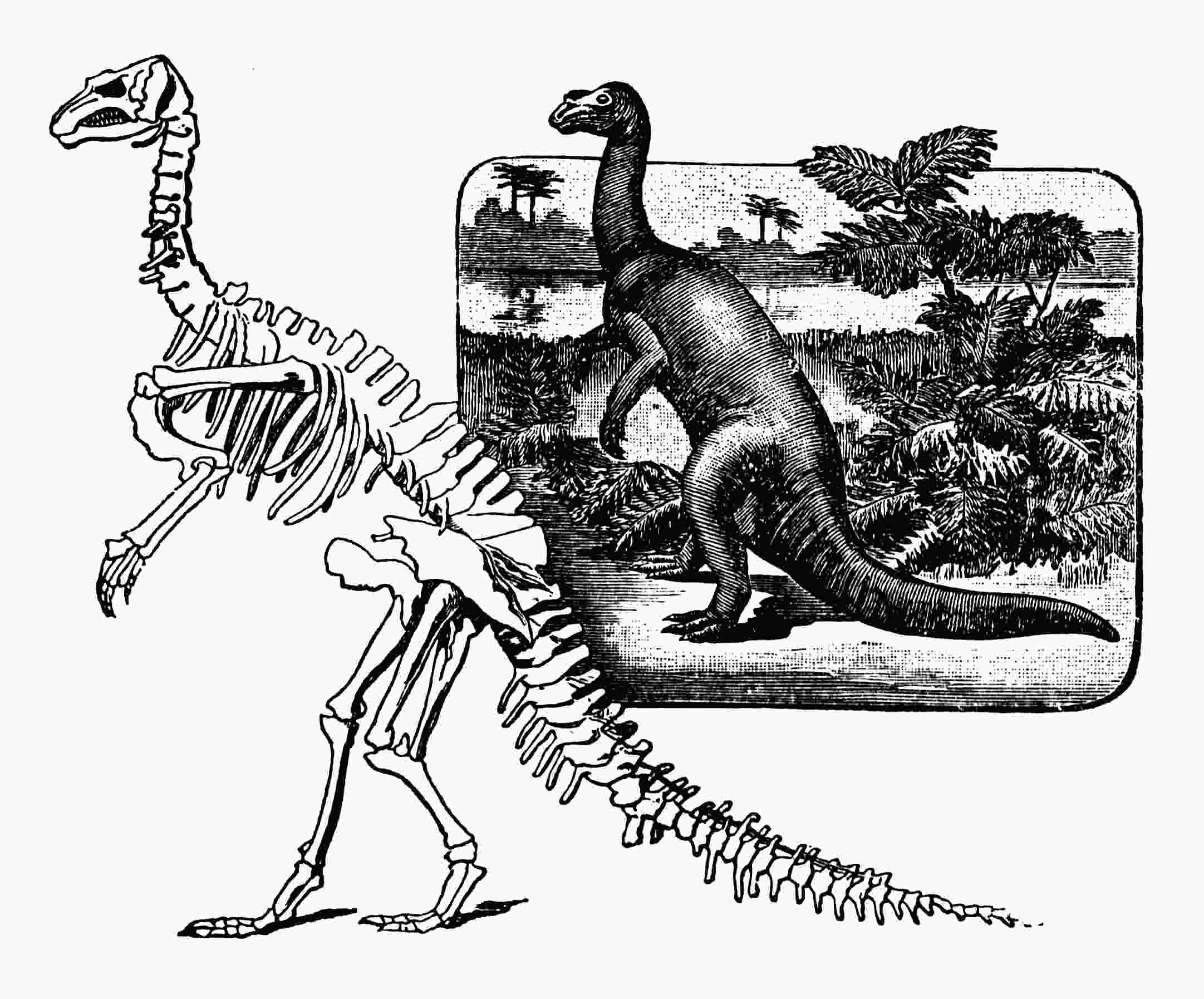 中生代の大蜥蜴
中生代の大蜥蜴
ブリュッセル
博物館の
特別館内に
陳列してあるのはこれである。中生代にはいまだ
獣類も
鳥類もでき始まりのすこぶる
幼稚な形のもののみであったゆえ、
陸上でこれらの
恐ろしい
爬虫類の相手になって
競争し
得る動物は
一種もなかったに
相違ない。さらに海中では
如何というに、ここにも
爬虫類が
全盛を
極めて魚のごとき形のもの、
海蛇のごとき形のものなどさまざまの
種類があり、大きなものは身長が四間(注:6.2m)ないし七間(注:12.6m)にも
達していて、あたかも今日の
鯨のごとくにしかも今日の
鯨よりははるかに多数にいたるところの海に
游泳していた。
通俗の書物に中生代のことを「
爬虫類の時代」と名づけてあるのもけっして
無理ではない。かように中世代には
非常に大きな
爬虫類が水中、
陸上ともに
全盛を
極め、ほとんど
爬虫類にあらざれば動物にあらずと思われるまでに
勢いを
得ていたが、その後にいたりいずれもついに
滅び
失せて、次なる新生代まで生き
残ったものは
一種としてない。
特に
不思議に感ぜられるのは
海産蜥蜴類の
絶滅したことで、
陸産のほうならばあるいは新たに
現われた
獣類などに
攻め
亡ぼされたかも知れぬという
疑いがあるが、海中に
鯨類の生じたのは新生代の中ごろであって、
海産蜥蜴類の
断絶してよりはるかに後のことゆえ、これらはけっして新たな
強敵に
出遇うて
敗けて
亡びたのではない。それゆえなぜ自ら
滅び
失せたかは今までただ
不可解というばかりであった。
次に新生代における
獣類を見るに、これまた一時は
全盛を
極めていた。今日では
陸上のもっとも大きな
獣というとまず
印度産とアフリカ
産との
象くらいであるが、人間の
現われる前の時代には今の
象よりもさらに大きな
象の
種類がたくさんにあり、その
分布区域も
熱帯から
寒帯まで
拡がっていた。
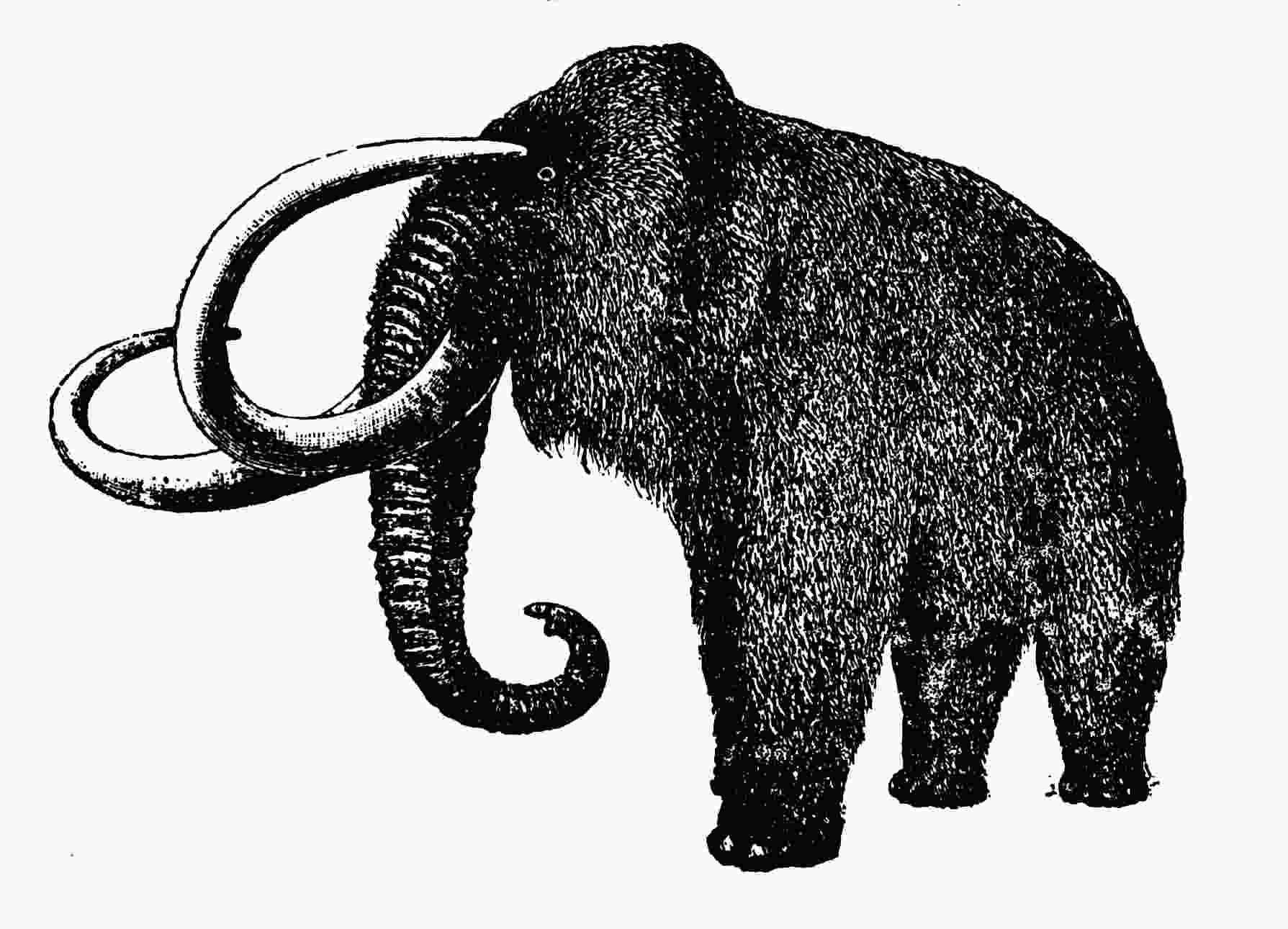 マンモス
マンモス
シベリアの氷原からはときどき「マンモス」と名づける
大象の
遺骸が
発掘せられることがあるが、氷の中に
埋もれていたことゆえ、あたかも
冷蔵庫の中に
貯蔵してあったのと同じ
理屈で、何十万年も
経たにかかわらず、肉も皮も毛も生きていた時のままに
残っている。ペトログラードの
博物館にある
完全な
剥製の
標本はかような
材料から
製作したものである。わが国でもこれまでところどころから「マンモス」その他の
象の化石、
犀の化石、
素性のわからぬ
大獣の
頭骨などが
掘り出されたことを考えると、太古には今日と
違うて
恐ろしい大きな
獣類が多数に
棲息していたに
違いない。また食肉
類には今日の
獅子や
虎よりもさらに大きく、
牙や
爪のさらに
鋭い
猛獣がたくさんにいた。ブラジルの
或る地方から
掘り出された
一種の
虎の化石では
上顎の
牙の長さが
一尺(注:30cm)ほどもある。
鹿などの
類にもずいぶん大きな
種類があって、左右の角の
両端の
距離が二間(注:3.6m)
以上に
達するものもあった。その他この時代にはなおさまざまの
怪獣がいたるところに
跋扈して世は
獣類の世であったが、その後人間が
現われてからはたいがいの
種族はたちまち
滅亡して、今日ではもはやかようなものは
一種も見ることができぬようになった。
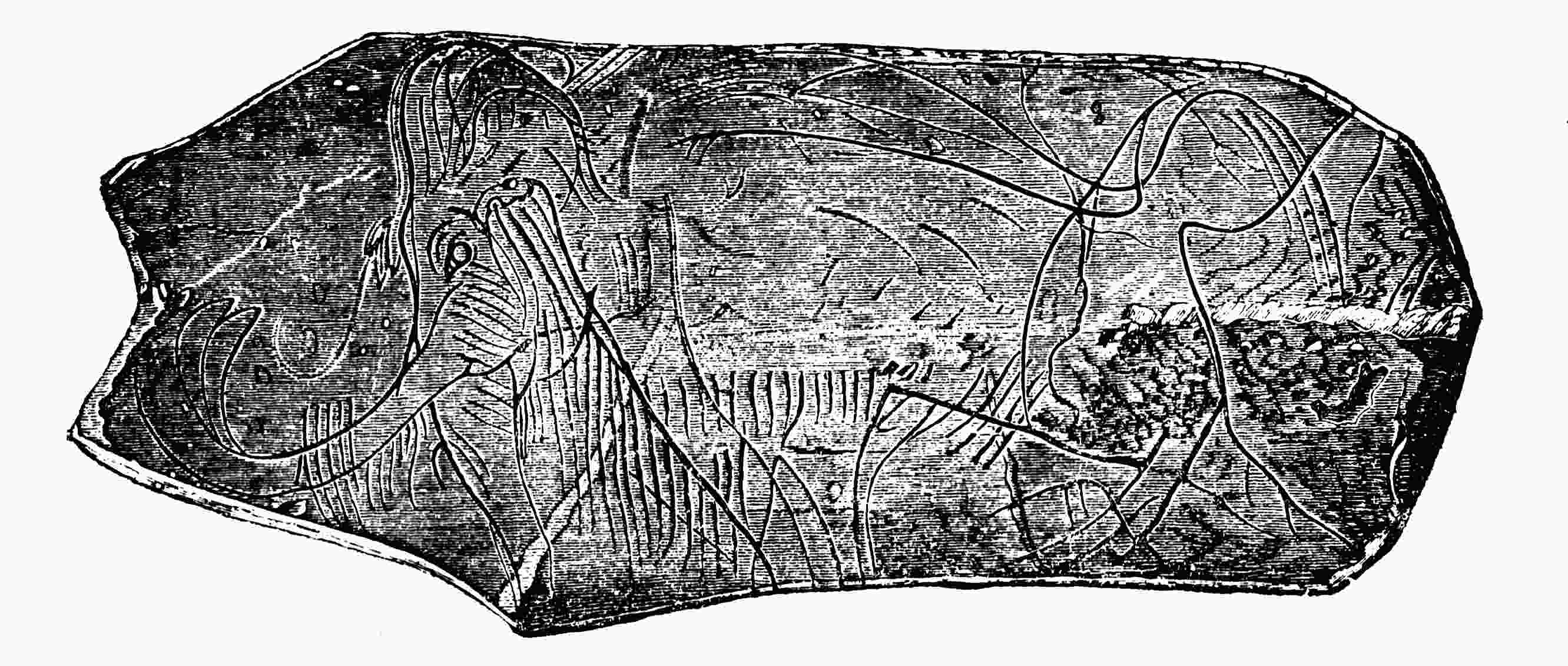 石器時代のマンモスの絵
石器時代のマンモスの絵
「マンモス」などがしばらく人間と同時代に生活していたことは、
石器時代の原人が
遺した
彫刻にその絵のあるのを見ても
確かに知られる。
以上若干の
例で
示したとおり、
地質時代に一時
全盛を
極めた動物
種族は、その後
必ず速かに
滅亡して次の時代には全く
影を止めぬにいたったが、これは一体
如何なる理由によるか。一度すべての
敵に打ち勝ち
得た
種族はなぜそのままに次の時代まで
優勢を
保ちつづけ
得ぬのであろうか。この問いに対しては、前にも
述べたごとくいまだ何らの
定説が発表せられたことを聞かぬ。少なくとも何びとをも
満足せしめ
得るような
明瞭な
解決を
試みた人はいまだないように見受ける。どの
種族も
全盛時代の
末期には
必ず何らかの
性質が
過度に
発達して、そのため
生存上かえって
不都合が生じ、ついに
滅亡したかのごとくに見えるところから考えて、
或る人は生物には一度進歩しかかった
性質はどこまでもその方向に一直線に進みゆく
性が
備わってあると
説き、これを直進
性と名づけ、一度
盛んに
発展した動物の
種族が進みすぎてついに
滅亡したのは、全く直進
性の
結果であると
唱えたが、これは
単に
不可解のことに
名称をつけただけで、わからぬことは
依然としてわからぬ。次に
説くところは
著者一人の考えである。
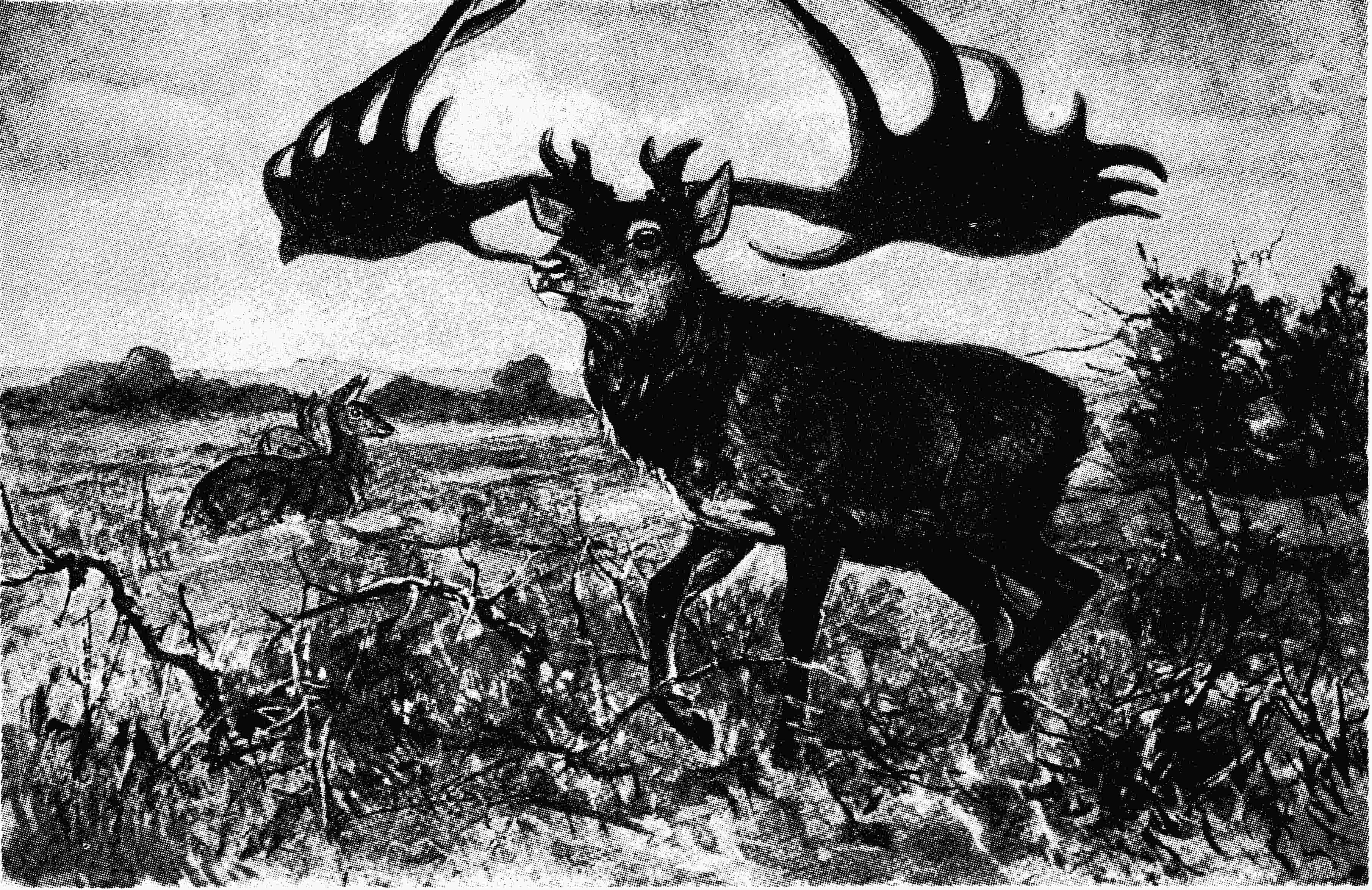
古代の大角鹿
アイルランドの新生代後期の地層より掘り出せる化石に基づきてその生きる姿を想像する図なり。左右の角の先端の距離約2間半(注:4.5m)。角と頭骨だけにても重さ30貫(注:112.5kg)以上。
およそ
生存競争に勝って
優勢を
占める動物
種族ならば、
敵にまさった
有効な
武器を
備えていることは、言うまでもないが、その
武器は
種族の
異なるにしたごうてそれぞれ
違う。あるいは
筋力の強さでまさるものもあろう。または
牙と
爪との
鋭さでまさるものもあろう。あるいは
感覚の
鋭敏なこと、走ることの速かなこと、
皮膚の
堅いこと、
毒の
激しいこと、
繁殖力の
旺盛なこと、その他何らかの点で
敵にまさったゆえ、
競争に勝つを
得たのであろうから、
全盛を
極める
種族にはおのおの
必ずその
得意とするところの
武器がある。さて生物
各種の
個体の数が
平常いちじるしく
殖えぬのは他
種族との
競争があるためで、もし
敵がなかったならばたちまちの間に
非常に
増加すべきはずであるゆえ、すべての
敵に勝ち終わった
種族は
盛んに
繁殖して
個体の数が
限りなく
殖えるであろう。しこうして
個体の数が多くなれば生活が
困難になるのをまぬがれず、したがって
同種族内の
個体間もしくは
団体間の
競争が
激烈にならざるを
得ないが、そのさい
各個体は
如何なる
武器をもって
相闘うであろうかというに、やはりその
種族がかつて他
種族を
征服するときに用いたのと同じものを用いるに
違いない。すなわち
筋力で他
種族に打ち勝った
種族ならば、その
個体が
相戦うにも同じく
筋肉によるであろう。また
爪と
牙とで他
種族を
亡ぼした
種族ならば、その
個体間においてもやはり
爪と
牙とによる
戦いが行なわれるであろう。
個体間に
激しい
競争が行なわれる
結果として、これらの
武器はますます強くなり大きくなるであろうが、いずれの
器官でも体部でも
過度に発育するとかえって
種族生存のためには
不利益なことになる。
例えば
筋力の強いことによって
敵をことごとく
征服した
種族が、
敵のなくなった後にさらに
個体間で
筋力の
競争をつづけてますます
筋力が
増進したと
想像するに、
筋力が強くなるには
筋肉の
量が
増さねばならぬが、
筋肉が太くなればその起点、着点となる
骨も大きくなりしたがって全身が大きくならねばならぬ。角力取りが
普通の人間より大きいのも、力まかせに
敵を
締め
殺す
大蛇が
毒蛇類よりもはるかに大きいのも、主として
筋肉発育の
結果である。かような
種族内の
競争では身体の少しでも大きいもののほうが力が強くて勝つ
見込みがあろうが、身体が大きくなればそれに
伴うてまた
種々の
不便不利益なことが生ずる。すなわち日々の生活に
多量の食物を
求めねばならず、
成長には
非常に手間がかかり、したがって
繁殖力は
極めて
低くなる。そのうえ「大男
総身に
知恵がまわりかね」というとおり、体が重いために
敏活な運動ができず、
特に曲り角のところで身の軽い小動物のごとくに急に方向を
変えることは
惰性のためにとうてい
不可能となるゆえ、小さな
敵に
攻められた場合にはあたかも
牛若丸に対する
弁慶のごとくにたちまち
敗けるおそれがある。されば身体の大きいことも度を
超えると明らかに
種族生存のために
不利益になるが、他
種族の
敵がなく
同種族内の
個体同志のみで
筋力の
競争をなしつづければ、この
程度を
超してなお止まらずに進むことを
避けられぬ。直進
性とはかかる
結果を
不可思議に思うて
付けた空名にすぎぬ。また
牙が大きくて
鋭いためにすべて他の
種族を
圧倒し
得た
種族が、
敵のなくなった後にさらに
個体間で
牙による
競争をつづけたならば、
牙はますます大きく
鋭くなるであろうが、これまた一定の度を
超えるとかえって
種族の
生存上には
不利益になる。
何故というに、およそ
如何なる
器官でも他の体部と
関係なしに、それのみ
独立に
発達し
得るものはけっしてない。
牙のごときももし大きくなるとすれば、その生じている
上顎、
下顎の
骨からして太くならねばならず、
顎を動かすための
筋肉も、その
付着する
頭骨も大きくならねばならぬが、頭が大きく重くなれば、これを
支えるための
頸の
骨や
頸の
筋肉まで大きくならねばならず、したがってこれを
維持するために動物の
負担がよほど重くなるをまぬがれぬ。すなわち他に
敵のない
種族の
個体が
牙の強さで
互いに
競争しつづければ、
牙と
牙に
関係する体部とはどこまでも大きくなり、ついには
畸形と見なすべき
程度に
達し、さらにこの
程度をも通り
越して進むのほかはない。そのありさまは
欧米の
諸強国が
大砲の大きさを
競争して
妙な形の
軍艦をつくっているのと同じである。何事でも一方に
偏すれば他方には
必ず
劣るところの生ずるは
自然の理であるゆえ、
牙の大きくなることも度を
超えて
極端まで進むとかえって
種族の
生存には
不利益となり、他日
意外の
敵に
遭遇した場合にもろくも
敗北するにいたるであろう。
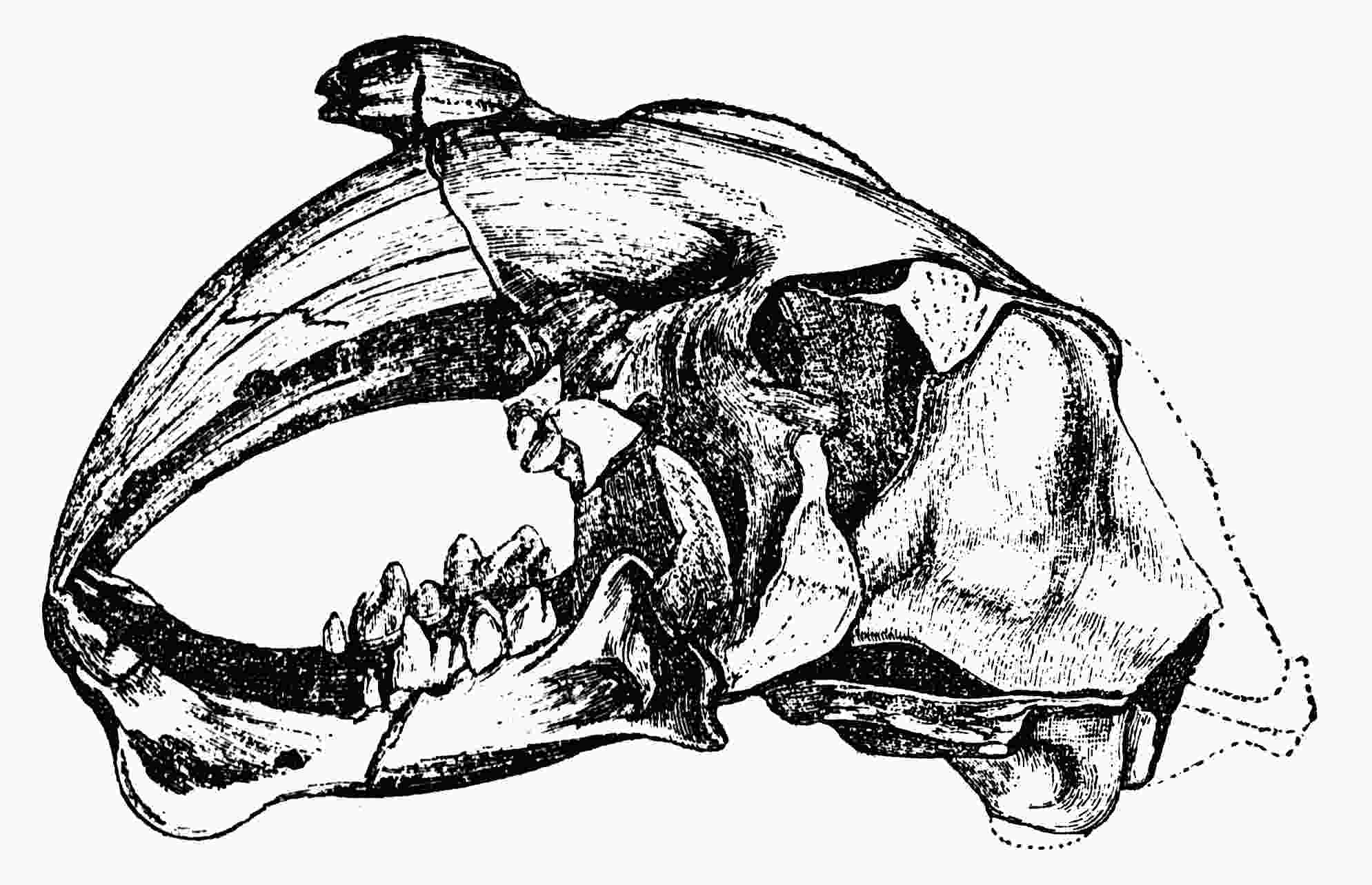 牙の大きすぎる虎の頭骨
以上
牙の大きすぎる虎の頭骨
以上は
単に一二の場合を
想像して
理屈だけを
極めて
簡単に
述べたのであるが、
実際地質時代に一時
全盛を
極め
後急に
絶滅したような動物
種族を見ると、その
末路におよべば
必ず身体のどこかに
過度に
発達したらしい部分がある。あるいは身体が大きすぎるとか、
牙が長すぎるとか、角が重すぎるとか、
甲が
厚すぎるとか、とかく
生存に
必要と思われるより
以上に発育してほとんど
畸形に近い
姿を
呈し、おそらくそのためにかえって
生存が
困難になったのではなかろうかと考えられるものがすこぶる多い。
従来はかようなことに対し直進
性という名をつけたりしていたが、
著者の考えによれば一方のみに
偏した
過度の発育は全く他
種族の
圧迫をこうむらずに
自己の
種族のみで
個体間または
団体間に
激しい
競争の行なわれた
結果である。他
種族と
競争している間は
種族の
生存に
不利益な
性質が
発達するはずはないが、すべて他の
種族を
征服して対等の
敵がなくなると、その後は
種族内で
競争をつづける
結果として、かつて他
種族に打ち勝つときに
有効であった
武器が
過度に進歩し、ほとんど
畸形に
類する発育をとげるであろう。
個体間の
競争で勝負の
標準となる
性質が、
競争の
結果過度に進むをまぬがれぬことは、
日常の生活にもしばしば見かける。
例えば女の顔のごときも色が白くて
唇の赤いのが美しいが、男の
愛を
獲んと
競争する
結果、白いほうはますます白く
塗って美しい白の
程度を通り
越し、赤いほうはますます赤く
染めて美しい赤の
程度を通り
越し、
白壁のごとくに
白粉を
塗り、玉虫のごとくに
紅を
付けて
得意になっている。
当人と、
痘痕も
靨に見える
情人とはこれを美しいと思うているであろうが、
無関係の第三者からはまるで
怪物のごとくに見える。新生代の
地層から
掘り出された
牙の大きすぎる
虎や、
角の重すぎる
鹿などもおそらくこれと同じように
同僚間の
競争の
結果過度の
発達をとげたものであろう。
一方に
過度の発育をとげれば、これに
伴うて他方には
過度の弱点の生ずるをまぬがれぬであろうから、これが
或る
程度まで進むと、今まではるかに
劣っているごとくに見えた
敵と
競争するにあたって、自分の
不得意とする方面から
攻められるともろく
敗北するおそれが生ずる。前にも
述べたとおり、まされる
種族とはいずれも自分の
得意とする方面だけで
敵にまさるものゆえ、
得意とせぬ方面にはなはだしい
欠陥が生じたならば、
種族の
生存はそのためすこぶる
危険となるに
違いない。一時
全盛を
極めた動物
種族がその
末路におよんではるかに
劣った
敵にも勝ち
得ぬにいたったのは、右のごとき
状態に
陥ったためであろう。そのうえ一時多くの
敵に勝つような
種族は
必ず
専門的に
発達し、身体
各部の分業も進んだものであるゆえ、もし外界に何らかの
変動が起こり、温度が
降るとか、
湿気が
増すとか、新たな
敵が
現われたとか、
従来の食物がなくなるとかいう場合には、これに
適応してゆくことがよほど
困難で、そのため
種族の
全滅するごときこともむろんしばしばあったであろう。
要するに
著者の考えによれば、生物
各種族の運命は次の三とおりのほかに出ない。
競争の相手よりもはるかに
劣った
種族はむろん
競争に
敗れて
絶滅するのほかはない。また
競争の相手よりもはるかにまさった
種族はすべての
競争者に打ち勝ち、天下に
敵なきありさまに
達して一時は
全盛を
極めるが、その後は
必ず
自己の
種族内の
個体間の
競争の
結果、始め他の
種族を
征服するときに
有効であった
武器や
性質が
過度に
発達し、他の方面にはこれに
伴う
欠陥が生じてかえって
種族の
生存に
有害となり、ついには今まではるかに
劣れるごとくに見えた
敵との
競争にも
堪え
得ずして自ら
滅亡するをまぬがれぬ。ただ
敵から急に
亡ぼされもせず、また
敵を
亡ぼし
尽くしもせず、つねに
敵を目の前にひかえ、これと
対抗しながら
生存している
種族は長く
子孫を
遺すであろうが、その
子孫は長い年月の間には
自然淘汰の
結果絶えず少しずつ
変化して、いつとはなしに全く
別種と見なすべきものとなり終わるであろう。ニイチェの書いたものの中に「
危く
生存する」という
句があったように
記憶するが、長く
種族を
継続せしめるには
危き
生存をつづけるのほかに
途はない。「
敵国外患なければ国はたちまち
亡びる」というとおり、
敵を
亡ぼし
尽くして
全盛の時代にふみ
込むときは、すなわちその
種族の
滅亡の第一歩である。
盛者必
[#「必」は底本では「心」]滅、
有為転変は実に古今に通じた生物界の
規則であって、これにもれたものは
一種としてあった
例はない。
以上述べたところは、これを一々の生物
種族に当てはめて
論じて見ると、なお
詳細に研究しなければならぬ点や、いまだ
説明の十分でないとところがたくさんにあるべきことはもとより
承知しているが、大体において事実と
矛盾するごときことはけっしてないと
信ずる。
今日地球上に
全盛を
極めている動物
種族は言うまでもなく人間である。かつて
地質時代に
全盛を
極めた
各種族はいずれも一時代
限りで
絶滅し、次の時代には全く
影を
隠したが、
現今全盛を
極めている人間
種族は
将来如何になりゆくであろうか。
著者の見るところによれば、かような
種族はみな
初め他
種族に打ち勝つときに
有効であった
武器が、その後
過度に
発達して、そのためついに
滅亡したのであるが、人間はけっしてこれに
類することは起こらぬであろうか。
未来を
論ずることは本書の
目的でもなく、また
著者のよくするところでないが、人間社会の
現在の
状態を見ると、一度
全盛を
極めた動物
種族の
末路に
似たところが明らかにあるように思われるゆえ、次にいささかそれらの点を
列挙して読者の
参考に
供する。
人間がことごとく他の動物
種族に打ち勝って向かうところ
敵なきにいたったのは
如何なる
武器を用いたによるかというに、これは
誰も知るとおり、物の
理屈を考え
得る
脳と、道具をつくって使用し
得る手とである。もしも人間の
脳が小さくて物を
工夫する力がなかったならば、とうてい今日のごとき
勢いを
獲ることは
不可能であったに
違いない。またもしも人間の手が馬の足のごとくに大きな
蹄で
包まれて、物を
握ることができなかったならば、けっして他の
種族に打ち勝ち
得なかったことは明らかである。されば
脳と手とは人間のもっとも大切な
武器であるが、手の
働きと
脳の
働きとは実は
相関連したもので、
脳で
工夫した道具を手でつくり、手で道具を使うて
脳に
経験をため、両方が
相助けて両方の
働きが進歩する。
如何に
脳で考えてもこれを実行する手がなければ何の役にも立たず、
如何に手を
働かそうとしても、あらかじめ
設計する
脳がなかったならば何を始めることもできぬ。矢を放ち、
槍で
突き、
網を
張り、落とし
穴を
掘りなどするのは、みな
脳と手との
連合した
働きであるが、かかることをなし
得る動物が地球上に
現われた
以上は、他の動物
種族はとうていこれに勝てる
見込みがなく、力は何倍も強く
牙は何倍も
鋭くともついにことごとく人間に
征服せられて、人間に
対抗し
得る
敵は
一種もなくなった。かくて人間はますます
勢いを
増し
全盛を
極めるにいたったが、その後はただ
種族内に
激しい
競争が行なわれ、
脳と手との
働きのまさった者は
絶えず
脳と手との
働きの
劣ったものを
圧迫して
攻め
亡ぼし、その
結果としてこれらの
働きは日を追うて
上達し、研究はどこまでも深く、道具はどこまでも
精巧にならねばやまぬありさまとなった。人はこれを文明開化ととなえて
現代を
謳歌しているが、
誰も知らぬ間に人間の身体や社会
的生活
状態に、次に
述べるごとき
種族の
生存上すこぶる面白からぬ
変化が生じた。
まず身体に
関する方面から始めるに、
脳と手との
働きが進歩してさまざまのものを
工夫し
製作することができるようになれば、寒いときには
獣の皮を
剥ぎ草の
繊維を
編みなどして
衣服を
纒い始めるであろうが、
皮膚は
保護せられるとそれだけ
柔弱になり、わずかの
寒気にもたえ
得ぬようになればさらに
衣服を重ね、頭のうえから足の先まで
完全に
被い
包むゆえ、ついにはちょっと
帽子をとっても
靴下を
脱いでも風を引くほどに身体が弱くなってしまう。また人間が自由に火を用い始めたことは、すべての他の動物に打ち勝ち
得たおもな
原因であるが、食物を
煮て食うようになってからは歯と
腸胃とがいちじるしく弱くなった。野生の
獅子や
虎にはけっしてない
齲歯がだんだんでき始め、生活が文明
的に進むにしたごうてその数が
殖えた。どこの国でも
下層の
人民にくらべると、
貴族や金持には
齲歯の数が
何層倍も多い。
嗜好はとかく
極端に走りやすいもので、冬は
沸きたつような
汁を
吹きながら
吸い、夏は口の
痛むような
氷菓子を
我慢して食う。
塩や
砂糖を
純粋に
製し
得てからは、あるいは
鹹すぎるほどに
塩を入れ、あるいは
甘すぎるほどに
砂糖を
加える。これらのことや運動の
不足やなおその他の
種々の
事情で
胃腸の
働きは
次第に
衰え、
虫様垂炎などもすこぶる
頻繁に起こり、
胃が悪いと言わねばほとんど大金持らしく聞えぬようになった。
住宅も
衣服と同じくますます
完全になって、夏は電気
扇で
冷風を送り、冬は
暖房管で室内を温めるようになると、つねにこれに
慣れて寒暑に対する
抵抗力が
次第に
減じ、少しでも
荒い風に
触れるとたちまち
健康を
害するような弱い身体となり終わるが、これらはすべて
脳と手との
働きが進んだ
結果である。
知力が進めば、病いをなおし
健康を
保つことにもさまざまの
工夫をこらし、病原
黴菌に対する
抵抗力の弱い者には人工
的に
抗毒血清を
注射してこれを助け、
消化液分泌の
不足する者には
人造のジアスターゼやペプシネを飲ませてこれを
補うが、
自然に
任せておけば死ぬべきはずの弱い者を人工で助け生かせるとすれば、人間
生来の
健康の
平均が少しずつ
降るはもちろんである。医学が進歩すれば一人一人の
患者の生命を何日か
延ばし
得る場合は多少
増すであろうが、それだけ
種族全体の
健康状態がいつとはなく悪くなるをまぬがれぬ。文明人の身体が少しずつ
退化するのはもとより他に多くの
原因があって、けっして
医術の進歩のみによるのではないが、知力を用いてできるだけ身体を
鄭重に
保護し助けることは
確かにその一
原因であろう。身体が弱くなれば病いにかかる者も
殖え、
統計をとって見ると、何病の
患者でも年々いちじるしく数が
増してゆくことがわかる。
他
種族を
圧倒して自分らだけの世の中となれば、安全に
子孫を育てることができるために、人口が
盛んに
殖えてたちまち
激しい生活
難が生ずる。
狭い土地に多数の人が
押し合うて住めば、
油断しては直ちに
落伍者となるおそれがあるゆえ、相手に負けぬように
絶えず新しい
工夫をこらし、新しい道具をつくって
働かねばならず、そのため
脳と手とはほとんど休まる時がない。そのうえ知力が進めば
如何なる仕事をするにも
大仕掛けの
器械を用いるゆえ、その運転する
響きと
振動とが日夜
神経を
悩ませる。かくて
神経系は
過度の
刺激のために
次第に
衰弱して
病的に
鋭敏となり、ささいなことにもたちまち
興奮して、軽々しく
自殺したり他を
殺したりする者が
続々と生ずる。
神経衰弱症は
野蛮時代にはけっしてなかったもので、全く文明の進んだために起こった
特殊の病気に
相違ないから、これを「文明病」と名づけるのは真に
理にかなうた
呼びかたである。
競争の
労苦を
慰めるための
娯楽も、
脳の
働きが進むと
単純なものでは
満足ができぬようになり、
種種工夫をこらして
濃厚な
激烈なものをつくるが、これがまた強く
神経を
刺激する。
芝居や活動写真などはそのいちじるしい
例であるが、真実の
生存競争の
労苦の
余暇をもって、
仮想人物の
生存競争の
労苦をわが身に引き受けて感ずるのであるから、むろん
神経系を
安息せしむべき道ではない。また人間は
労苦を
忘れるために酒、
煙草、
阿片などのごときものをつくって用いるが、これは
種族生存のためにはもとより
有害である。およそ
娯楽にはすべて
忘れるということが
要素の一つであって、
芝居でも活動写真でもこれを見て
喜んでいる間は自分の住する
現実の世界を
暫時忘れているのであるが、酒や
煙草の
類は
実際の
労苦を
忘れることを
唯一の
目的とし、
煙草には「
忘れ草」という名前さえつけてある。しこうしてかく
忘れさせる
働きを有するものはいずれも
劇毒であるゆえ、つねにこれを用いつづければ
当人にも
子孫にも身体
精神ともに
害を受けるをまぬがれぬ。
阿片のごときは少時これを用いただけでも
中毒の
症状がすこぶるいちじるしく
現われる。酒の
有害であることはだれが考えても明らかであるゆえ、
各国ともに
禁酒の運動が
盛んに行なわれるが、しばらくなりとも
現実の世界からのがれして
夢幻の世界に遊ぶことが何よりの楽しみである今日の社会においては、
飯を
減らし、着物を
脱いでも、酒や
煙草がやめられぬ人間が、いつまでもたくさんにあって、その
害も長く
絶えぬであろう。しこうしてこれらは他の動物
種族ではけっして見られぬ
現象である。
なお生活
難が
増すにしたがい、
結婚して家庭をつくるだけの
資力が
容易には
得られぬゆえ、
自然晩婚のふうが生じ、一生
独身で
暮らす男女もできるが、かくては
風儀も
乱れ、
売笑婦の数が年々
増加し、これらが日々多数の客に
接すれば
淋病や
梅毒はたちまち世間一体に
蔓延して、その一代の人間の
健康をそこなうのみならず、
子供は生まれたときから、すでに病いにかかったものがたくさんになる。その他、知力によって
工夫した
避妊の
方法が
下層の
人民にまであまねく知れ
渡れば、
性欲を
満足せしめながら子の生まれぬことを
望む場合には
盛んにこれを実行するであろうから、教育が進めば
自然子の生まれる数が
減ずるが、
繁殖力の
減退することは
種族の
生存からいうともっとも
由々しき大事である。子の生まれる数が
減れば生活
難が
減じて、かえって
結構であると考えるかも知れぬが、なかなかさようにはならぬ。
何故というに「さんご」や「こけ虫」の
群体ならば
百匹の虫に対して
百匹分の食物さえあればいずれも
満腹するが、人間は千人に対して千五百人分の食物があっても、その多数は
餓を
忍ばねばならぬような
特殊の
事情が
存するゆえ、人数は
殖えずとも
競争は
相変わらず
激しく、
体質は
以上述べたごとくに
次第に悪くなりゆくであろう。 次に
道徳の方面について考えるに、これまた
脳と手との
働きの進むにしたがいだんだん
退歩すべき理由がある。知力のいまだ進まぬ
野蛮時代には
通信や
運輸の
方法が
極めて
幼稚であるゆえ、
戦争するにあたって
一群となる
団体はすこぶる小さからざるを
得なかった。
隊長の
号令の聞こえるところ、
相図の
旗の見えるところより外へ出ては
仲間との
一致の行動が取れぬゆえ、そのくらいの広さのところに集まり
得るだけの人数が
一団をつくって、それぞれ
競争の
単位となったが、かかる
小団体の中では、
各人がその
団体におよぼす
結果はだれにも
明瞭に知れわたり、
団体の
生存に
有利な
行為は
必ず
善として
賞せられ、
団体の
生存に
有害な
行為は
必ず悪として
罰せられ、
善の
隠れて
賞せられず、悪のあらわれずして
罰をまぬがるるごときはけっしてなく、
善のなすべきゆえんが
極めて
確かに
了解せられる。かつかかる
小団体が数多く
相対立して
激しく
競争すれば、悪の行なわれることの多い
団体は
必ず
戦いに
敗けて、その中の
個体は
殺されるか食われるかして全部
滅亡し、
善の行なわれることの多い
団体のみが勝って生き
残り、それに
属する
個体のみが
子孫を
遺すゆえ、もしもそのままに進んだならば、
自然淘汰の
結果としてついには
蟻や
蜂のごとき
完全な社会
的生活を
営む動物となったかも知れぬ。しかるに
脳の
働きと手の
働きとが進歩したために、
通信や
運輸の
方法がすみやかに
発達し、これに
伴うて
競争の
単位となる
団体は
次第に大きくなり、電話や
電信で
命令を
伝え、汽車や自動車で
兵糧を
運搬するようになれば、
幾百万の
兵隊をも一人の
指揮官で動かすことができるために、いつの間にか
相争う
団体の数が
減じて
各団体は
非常に大きなものとなった。ところで
団体が
非常に大きくなり、その中の人数が
非常に多数になると、一人ずつの行動が
全団体におよぼす
結果はほとんどわからぬほどの
微弱なものとなり、一人が
善を行なうてもそのため急に
団体の
勢いがよくなるわけでもなく、一人が悪を行なうてもそのためにわかに
団体が
衰えるわけでもなく、したがって
善が
隠れて
賞せられぬこともしばしばあれば、悪がまぬがれて
罰せられぬこともしばしばあり、時としては悪を行なうた者が
善の
仮面を
被って
賞に
与ることもある。かような
状態にたちいたれば、
善は
何故になさねばならぬか、悪は
何故になすべからざるかという
理屈がすこぶる
曖昧になってくる。小さな
団体の内では悪は
必ず
現われて
厳しく
罰せられるゆえ、ひそかに悪を行なうたものは日夜
激しく
良心の
苛責を受けるが、
団体が大きくなって悪の
必ずしも
罰せられぬ
実例がたくさん目の前にならぶと、
勢い
良心の
刃は
鈍くならざるを
得ない。また
団体が大きくなるにしたがい、
団体間の
競争における勝負の決するのにはなはだしく手間が取れ、
競争は
絶えず行なわれながら、一方が
全滅して
跡をとどめぬまでにはいたらぬ。すなわち
敗けてもただ
兵士の一部が死ぬだけで、他は
依然として
生存するゆえ、
団体を
単位とした
自然淘汰は行なわれず、その
結果として
団体生活に
適する
性質は
次第に
退化する。大きな
団体の内では、
各個人の
直接に感ずるのは
各自一個の
生存の
要求であって、国運の消長のごときは
衣食足って後でなければ考えている
余裕がない。しこうして
個人を
単位とする
生存競争が激しくなれば、
自然淘汰の
結果としてますます
単独生活に
適する
性質が
発達し、自分さえよろしければ
同僚は
如何に
成りゆいてもかまわぬというようになり、かかる者の間に立っては
良心などを持ち合わさぬ者のほうがかえって
成功する
割合が多くなる。
各個人がかくのごとく
利己的になっては、
如何に
立派な
制度を
設け、
如何に
結構な
規約を
結んでも、とうてい
完全な
団体生活が行なわれるべき
望みはない。
団体的生活を
営む動物でありながら、おいおい
団体的生活に
適せぬ方向に進みゆくことは、
種族の
生存にとっては
極めて
不利益なことであるが、その
原因は全く
団体をして
過度に大ならざるを
得ざらしめた
脳と手との
働きにある。
さらに
財産に
関する方面を見るに、手をもって道具を用いる
以上は何事をなすにも道具と人とがそろわねばならず、人だけがあっても道具がなくてはほとんど何もできぬ。
獺ならば自分の足で水中を
游ぎ、自分の口で魚を
捕えるが、人間は船に乗り
櫓を
漕ぎ、
網ですくい、
籠に入れるのであるゆえ、この中の一品が
欠けても
漁にはでられぬ。わずかに
櫓にかける一本の短い
綱が見つからなくても岸をはなれることができぬ。かかる場合には、取れた魚の一部を
与える
約定で、
隣の人からあいている
櫓や
綱を
借りるであろうが、これが
私有財産を
貸して
利子を取る
制度の始まりである。しこうしていったん物を
貸して
利子を取る
制度が開かれると、道具をつくってこれを
貸すことを
専門とする者と、これを
借りて
働くことを
専門とするものとが生ずるが、
脳と手との
働きが進んで
次第に
精巧な
器械をつくるようになるとともに、
器械の
価はますます高く
労働の
価はますます安く、
器械を所有する者は
法外の
収入を
得るに反し、
器械を
借りる者は牛馬のごとくに
働かねばならぬようになる。
共同の生活を
営む社会の中に、一方には何もせずに
贅沢に
暮らす者があり、他方には終日
汗を流しても食えぬ者があるというのは、けっして
団体生活の
健全な
状態とは考えられぬ。
蒸気機関でも
機織り
器械でも
発電機でも化学工業でも、いちじるしい発明のあるごとに
富者はますます
富み
貧者はますます
貧しくなったところから見れば、今後もおそらく文明の進むにしたがい
最少数の
極富者と大多数の
極貧者とに分かれゆく
傾きが止まぬであろうが、それが社会生活の
各方面に
絶えず
影響をおよぼし、身体にも
精神にもいちじるしい
変化を引き起こす。しかもそれがいずれも
種族生存のうえに
不利益なことばかりである。
前に
健康や
道徳に
関して今日の人間が
如何なる方面に進みつつあるかを
述べたが、
貧富の
懸隔がはなはだしくなればすべてこれらの方面にも
直接に
影響する。
極富者と
極貧者とが
相隣して生活すれば、男女間の
風儀なども直ちに
乱れるのは
当然で、
餓えに
迫った女が
富家に
媚びて
淫を売るのを
防ぐことはできず、
貧者はもっとも
安価に
性欲の
満足を
求めようとするゆえ、それに
応ずる
職業の女も
殖え、世間
一般に品行が
乱脈になれば
花柳病が
盛んに
蔓延してついにはほとんど一人も
残らずその
害毒を
被るであろう。その他
富者は
飽いて病いを
得、
貧者は
餓えて
健康を
保ち
得ず、いずれも
体質が
次第に下落する。
現に文明
諸国の
貧民には
栄養不良のために
抵抗力が弱くなって、ささいな病いにも
堪え
得ぬものがおびただしくある。また
富者は金を
与えて
如何なることをもあえてし、
貧者は金を
得んがために
如何なることをも
忍ばざるを
得ぬゆえ、その
事柄の
善か悪かを問う
暇はなく、
道徳の
観念は
漸々薄らいで、たいがいの悪事は
日常のこととして人が注意せぬようになってしまうが、これではとうてい
協力一致を
旨とする
団体生活には
適せぬ。 国内の
人民が少数の
富者と多数の
貧者とに分かれ、
富者は金の力によって自分らのみに
都合のよいことを行なえば、
貧者はこれを見てけっして
黙ってはいず、
富者を
敵として
憎み、あらゆる
方法を
講じてこれを
倒そうと
試み、
貧者と
富者との間に
妥協の
余地のない
激しい
争闘が始まる。教育が進めば
貧者といえども知力においてはけっして
富者に
劣らぬゆえ、自分の
境遇と
富者の
境遇とを
比較して、
何故かくまで
相違するかと考えては
不満の
念にたえず、
現今の社会の
制度をことごとく
富者のみに
有利な
不都合千万なものと思いこみ、全部これをくつがえそうと
企てる者も
大勢出てくる。今日社会問題と名づけるものにはさまざまの
種類があるが、その根本はいずれも
経済の問題であるゆえ、
貧富の
懸隔がますますはなはだしくなる
傾きのある間はとうてい
満足に
解決せられる
見込みはなかろう。かくのごとく、一
団体の内がさらにいくつもの組に分かれて
互いに
相憎み
相闘うことは、
団体生活を
営む
種族の
生存にとってはすこぶる
有害であるが、その
根源を
質せばみな
初め手をもって道具を用いたのに
基づくことである。
要するに、今日の人間は
最初他の動物
種族を
征服するときに
有効であった
武器なる
脳と手との
働きが、その後
種族内の
競争のためにどこまでも進歩し、そのため身体は弱くなり、
道徳は
衰え、
共同生活が
困難になり、
貧富の
懸隔がはなはだしくなって、
不平をいだき
同僚を
呪う者が数多く生じ、日々
団体的動物の
健全なる生活
状態より遠ざかりゆくように見うける。これらのことの
実例をあげるのはわずらわしいゆえ
省くが、毎日の新聞紙上にいくらでも
掲げてあるゆえ、この点においては世界中の新聞紙を本章の
付録と見なしても
差支えはない。今日地球上の人間はいくつかの
民族に分かれ、
民族の間にも
個人の間にも
脳と手とによるはげしい
競争が行なわれているゆえ、今後もなお知力はますます進み
器械はますます
精巧になろうが、この
競争に一歩でも負けた
民族はたちまち相手の
民族から
激しい
圧迫をこうむり
極めて苦しい
位置に立たねばならぬから、
自己の
民族の
維持継続をはかるにはぜひとも
脳と手とを
働かせ、発明と
勤勉とによって
敵なる
民族にまさることを
努めねばならぬ。かく
互いに
相励めばいわゆる文明はなお
一層進むであろうが、その
結果は
如何というに、ただ
民族と
民族、
個人と
個人とが
競争するに用いる
武器が
精鋭になるだけで、前に
述べたごとき人間
種族全体に
現われる
欠陥を
救うためには何の役にもたたぬであろう。人間の身体や
精神が
漸々退化する
傾きのあることに気のついた学者はすでに
大勢あって、
人種改善とか
種族の
衛生とかいうことが、今日では
盛んに
唱えられているが、
以上述べたごとき
欠陥はいずれも
脳と手との
働きが進んだために
当然生じたものゆえ、同じ
脳と手との
働きによっていまさらこれを
救おうとするのは、あたかも火をもって火事を消し、水をもって
洪水を
防ごうとするのと同じようで、
結局はとうていその
目的を
達し
得ぬであろう。「知っていることは何の役にも立たず、役に立つようなことは何も知らぬ。」と言うたファウストの
歎息はそのまま
人種改良学者等の
最後の
歎息となるであろうと
想像する。ただし、
幾多の
民族が
相睨み合うている
現代においては少しでも相手の
民族よりも速く
退化するようなことがあっては、たちまち
敵の
迫害のために
極めて苦しい
地位に
陥らざるを
得ぬゆえ、一方
脳と手との力によって相手と
競争しながら、他方にはまた
脳の
働き、手の
働きの
結果として
当然生ずべき
欠陥をできるだけ
防ぐように
努めることが目下の
急務である。いずれの
民族も
結局は、
脳の
過度に
発達したためにますます
生存に
不適当な
状態に
赴くことを
避けられぬであろうが、いま
敵よりも先に
退化しては、直ちに
敵のために
攻められ苦しめられるべきは明らかであるゆえ、その苦しみをまぬがれんとするにはぜひとも、さらに
脳と手とを
働かせ、
工夫をこらし力を
尽くして、身体
精神ともになるべく長く
健全ならしめることを図らねばならぬ。人間全体がついには
如何になりゆくかというような遠い
将来の問題よりも、
如何にしてわが
民族を
維持すべきかという問題のほうが目前に
迫っているゆえ、
応急の
手段としては、やはり
人種改善や
種族衛生を学術
的に深く研究して、できるかぎりの
良法を実地に
試みるのほかはない。かくして、一方においては知力によって、
軍事、
殖産等の方面を進歩せしめ、他方においては同じく知力によって生活
状態の
退化を
防ぐことを
努めたならば、にわかに他の
民族のために
亡ぼされるごとき運命にはおそらく
遇わぬであろう。
以上のごとく考えて後にさらに
現今の人間を
眺めると、その身体には明らかに
過度に
発達した部分のあることに気づかざるを
得ない。前に
鹿の
或る
種類ではその
滅亡する前に角が大きくなりすぎ、
虎の
或る
種類では同じく
牙が大きくなりすぎたことを
述べたが、人間の身体では
脳が
確かに大きくなりすぎている。人間はいつも自分を
標準として物を
判断し、人体の美を
論ずるにあたっても
断金法などと
称する勝手な
法則を定め、これにかのうたものを
円満な
体格と見なすが、
虚心平気に考えて見ると、重さ十二三
貫(注:45~49kg)、長さ
五尺二三
寸(注:156~159cm)の身体に重さ三百六十
匁(注:1.35kg)、
直径五寸五分(注:16.5cm)もあるような大きな
脳が
備わり、これを
包むために、顔面部よりもはるかに大きな
頭蓋骨の
発達しているありさまは、前に
述べた
鹿の角や
虎の
牙と
相似たもので、いずれもほぼ
極端に
達している。もしもかの
鹿が、角の大きすぎるために
滅亡し、かの
虎が
牙の長すぎるために
滅亡したものとすれば、人間は今後あるいは
脳が大きくなりすぎたために
滅亡するのではなかろうかとの感じが
自然に
浮ぶが、これはあながちに
根拠のない
杞憂でもなかろう。すでに
現今でも
胎児の頭の大きいために
難産の場合がたくさんにあり、
出産の
際に命を
失う者さえ
相応にあるくらいゆえ、万一このうえに人間の
脳が
発達して
胎児の頭が大きくなったならば、それだけでも
出産に
伴う
苦痛と
危険とが
非常に
増し、
自然の
難産と
人工的の
避妊とのために
生殖の
率がいちじるしく
減ずるに
違いない。母が子を
産むのは生理
的に
当然のことで、本来は何の
故障もなしに行なわるべきはずのものであるに、人間だけは、
例外として
非常な
危険がこれに
伴うのは、
確かに人間が
種族の
生存上
不利益な方向に進み来たった
証拠と考えねばならぬ。本書の始めにも言うたとおり、およそ物は見ようによって
種々に
異なって見えるもので、同一の物に対しても
観察する人の立つ場所を
換えると全く
別の感じが起こる。人間
種族の
将来に
関してもそのとおりで、人間のみを見るのと、古今の
諸動物に
比較して見るのとでは大いに
趣きが
違い、また同じく生物学
的に
論じても一人一人に考え方はいちじるしく
異なるであろう。しこうして他の人々が
如何に考えるかは知らぬが、
著者一人の見るところはまず
以上略述したごとくである。
(注:Shift JIS で表現できない漢字
'さきつ'=※
[#「虫」+「鎖」のつくりの上が「く」113ページ-12行]
'蝉=

'藐=

'缶=

'鴎=

'蝦=

'蛄=

'保=※
[#「女+保」、U+5AAC、453ページ-5行]
'顛=

'テイ=

'エイ=

'ソ=

)